hellog〜英語史ブログ / 2021-10
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021-10-31 Sun
■ #4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている [hel_education][elt][world_englishes][standardisation]
英語教育や英語史の界隈ではある程度知られていることだが,平成30年(2018年)に告示された「高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 外国語編 英語編 平成30年7月」では,英語史の重要性が正当に評価されている.高校における英語科のいわゆる新指導要領において,英語史の役割がしっかり認められているということだ. *
「第3章第1節 指導計画作成上の配慮事項」の第7項 (214--15) に次のような文言が見える.
(7)言語能力の向上を図る観点から,言語活動などにおいて国語科と連携を図り,指導の効果を高めるとともに,日本語と英語の語彙や表現,論理の展開などの違いや共通点に気付かせ,その背景にある歴史や文化,習慣などに対する理解が深められるよう工夫をすること.
日本語や英語の背景にある「歴史や文化,習慣」への理解を促すためには,日本語史や英語史の知見が求められるということである.この後に,次のような説明書きも続く (215) .
この配慮事項は,言語能力の向上が,学校における学びの質や,教育課程全体における資質・能力の育成に関わる重要な課題であるという平成28年度12月の中央教育審議会答申に基づき,国語科の指導内容とのつながりについて述べたものである.
国語教育と英語教育は,学習の対象となる言語は異なるが,共に言語能力の向上を目指すものであるため,共通する指導内容や指導方法を扱う場面がある.各学校において指導内容や指導方法等を適切に連携させることによって,英語教育を通して日本語の特徴に気付いたり,国語教育を通して英語の特徴に気付いたりするなど,日本語と英語の言語としての共通性や固有の特徴への気付きを促すことにより,言語能力の効果的な育成につなげていくことが重要である.
「日本語と英語の言語としての共通性や固有の特徴への気付き」を促すことは,まさに日本において英語学や英語史が従来担ってきた役割でもある.
次に「第3章第2節 内容の取扱いに当たっての配慮事項」の第4項に注目したい (217) .
(4)現代の標準的な英語によること.ただし,様々な英語が国際的に広くコミュニケーションの手段として使われている実態にも配慮すること.
標準英語とともに,世界英語 (world_englishes) の存在にも注意を払うべきことが明記されている.様々な英語が存在し,尊重されるべきであることは,英語史を通じて最も効果的に理解することができる.昨今の英語史研究において,世界英語への関心が著しく高まってきていることは「#4558. 英語史と世界英語」 ([2021-10-19-1]) などでも触れてきた通りである.
「第3章第3節 教材についての配慮事項」の第2項には,より直接的に英語史に関わる文言が確認される (219) .
(2)英語を使用している人々を中心とする世界の人々や日本人の日常生活,風俗習慣,物語,地理,歴史,伝統文化,自然科学などに関するものの中から,生徒の発達の段階や興味・関心に即して適切な題材を効果的に取り上げるものとし,次の観点に配慮すること.〔後略〕
このように英語史は,新学習指導要領において正当に評価されており,重要な役割が認められていることを強調しておきたい.
2021-10-30 Sat
■ #4569. because が表わす3種の理由 [pragmatics][semantics][speech_act][cognitive_linguistics][performative_hypothesis][conjunction][conceptual_metaphor]
because は理由を表わすもっとも普通の接続詞だが,具体的な用例を観察してみると,そこに表わされている理由の種類にも様々なものがあることが分かる.ここで因果関係の哲学に入り込むつもりはないが,語用論や認知言語学の観点に絞って考察してみるだけでも,3種類は区別できそうだ.Sweetser (77) からの例文を挙げよう.
(1) John came back because he loved her.
(2) John loved her, because he came back.
(3) What are you doing tonight, because there's a good movie on.
3文における because が表わす理由の種類は明らかに異なる.(1) はもっとも普通で,現実世界の因果関係が表わされている.ジョンは彼女のことを愛していた,だからジョンは戻ってきたのだ.これを仮に「現実世界の読み」と呼んでおこう.
しかし,(2) の because の役割は,現実世界の因果関係を表わしているわけではない.ジョンが戻ってきた,そのことが理由でジョンが彼女を愛するようになったという読みは成り立たない.この文の言わんとするところは,ジョンが戻ってきた,そのことを根拠としてジョンが彼女を愛していたのだと話者が悟った,ということだ.because 節は,話者がジョンの愛を結論づける根拠となっている.この趣旨でもとの文を拡張すれば,"I conclude that John loved her, because he came back." ほどとなろうか.これを仮に「認識世界の読み」と呼んでおこう.
(3) は,主節が命題を表わす平叙文ですらなく疑問文なので,because が何らかの命題に対する理由であると解釈することは不可能だ.そうではなく,「今晩何してる?」と私が尋ねている理由は,いい映画が上映されているからであり,映画に誘おうと思っているからだ.もとの文を拡張すれば,"I am asking you what you are doing tonight, because there's a good movie on." ほどとなる.主節が表わす発話行為 (speech_act) を行なっている理由が because 以下で示されているわけだ.これを仮に「発話行為世界の読み」と呼んでおこう.
3文において because 節が何らかの理由を表わしているとはいっても,その理由が属する世界に応じて「現実世界の読み」「認識世界の読み」「発話行為世界の読み」と各々異なるのである.3つのパラレルワールドがあると考えてよいだろう.because は3つの世界を股にかけて活躍している接続詞であり,この語を混乱せずに使いこなしている話者もまた3つの世界を股にかけて言語生活を営んでいるのである.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-29 Fri
■ #4568. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」を終えました --- これにてシリーズ終了 [asacul][notice][history][link][slide]
去る10月23日(土)15:30?18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・12 「市民革命と新世界」」を,対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開講しました.2年ほど前に開始した「英語の歴史と語源」シリーズの最終回ということですが,何とか走りきることができました.参加者や朝カルのスタッフの皆さんのおかげです,ありがとうございました.
今回は,革命で大荒れだったスチュアート朝の時代,ほぼまるまる17世紀に焦点を当てました.ルネサンスの熱気が冷め,革命で荒れた時代ながらも,抑制と理知に特徴づけられた英語の散文が発展してきました.この時代の散文は,私たちにとってそれなりに現代的に見えます.とりわけ王政復古後の散文の文体は,私たちにとって身近で知っている英語の文章という感じがします.
そして,英語そのものもぐんと現代に近づいきています.この時代までに綴字の標準化はかなりの程度進んでいましたし,文法的にいえば例えば疑問文・否定文における do の使用など,現代的な統語的規則が確立しました.
17世紀半ばから18世紀初頭にかけて,英語を統制するアカデミー設立への関心が高まりましたが,1712年にその試みが頓挫すると,以後,関心は薄まりました.現在に至るまで英語アカデミーなるものが存在しないのは,このときの頓挫に負っています.英語が世界化した21世紀,アカデミーの不在は良いことなのか悪いことなのか.この現代的問題を論じる上でも,17世紀の英語を巡る状況を理解しておくことは重要です.
今回の講座で用いたスライドをこちらに公開しますので,ご覧ください.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.復習などにどうぞ.
1. 英語の歴史と語源・12「市民革命と新世界」
2. 第12回 市民革命と新世界
3. 目次
4. 関連年表
5. 1. スチュアート朝と市民革命 --- 清教徒革命と名誉革命
6. 2. ルネサンスの熱狂から革命・王政復古期の抑制と理知へ
7. 3. 英語の市民化とアカデミー設立の試み
8. 4. 17世紀の英語の注目すべき事項
9. 5. 英語の世界展開が本格的に開始
10. まとめ
11. 参考文献
12. 補遺1:フランシス・ベーコン『随筆集』 (Essays, 1597) より「怒りについて」
13. 補遺2:サミュエル・ピープス『日記』 (Diary, 1825) より「1665年のペストに関する記録」
「英語の歴史と語源」シリーズはこれにて終了ですが,次期も別の話題で講座を開く予定です.
2021-10-28 Thu
■ #4567. 法助動詞の根源的意味と認識的意味が同居している理由 [auxiliary_verb][modality][cognitive_linguistics][semantic_change][conceptual_metaphor][metaphor]
「#4564. 法助動詞の根源的意味と認識的意味」 ([2021-10-25-1]) に引き続き,法助動詞の2つの用法について.may を例に取ると,「?してもよい」という許可を表わす根源的意味と,「?かもしれない」という可能性を表わす認識的意味がある.この2つの意味はなぜ同居しているのだろうか.
この問題については英語学でも様々な分析や提案がなされてきたが,Sweetser の認知意味論に基づく解説が注目される.それによると,may の根源的意味は「社会物理世界において潜在的な障害がない」ということである.例えば John may go. 「ジョンはいってもよい」は,根源的に「ジョンが行くことを阻む潜在的な障害がない」を意味する.状況が異なれば障害が生じてくるかもしれないが,現状ではそのような障害がない,ということだ.
一方,may の認識的意味は「認識世界において潜在的な障害がない」ということである.例えば,John may be there. 「ジョンはそこにいるかもしれない」は,認識的な観点から「ジョンがそこにいるという推論を阻む潜在的な障害がない」を意味する.現在の手持ちの前提知識に基づけば,そのように推論することができる,ということだ.
つまり,社会物理世界における「潜在的な障害がない」が,認識世界の推論における「潜在的な障害がない」にマッピングされているというのだ.両者は,以下のような同一のイメージ・スキーマに基づいて解釈することができる.今のところ潜在的な障害がなく左から右に通り抜けられるというイメージだ.
┌───┐
│■■■│
│■■■│
├───┤
│///│
│///│
●─→………………………→
│///│
└───┘
Sweetser (60) はこのイメージ・スキーマの構造について,次のように説明する.
1. In both the sociophysical and the epistemic worlds, nothing prevents the occurrence of whatever is modally marked with may; the chain of events is not obstructed.
2. In both the sociophysical and the epistemic worlds, there is some background understanding that if things were different, something could obstruct the chain of events. For example, permission or other sociophysical conditions could change; and added premises might make the reasoner reach a different conclusion.
この分析は must や can など,根源的意味と認識的意味をもつ他の法助動詞にも適用できる.must についての Sweetser (64) の解説により,理解を補完されたい.
. . . I propose that the root-modal meanings can be extended metaphorically from the "real" (sociophysical) world to the epistemic world. In the real world, the must in a sentence such as "John must go to all the department parties" is taken as indicating a real-world force imposed by the speaker (and/or by some other agent) which compels the subject of the sentence (or someone else) to do the action (or bring about its doing) expressed in the sentence. In the epistemic world the same sentence could be read as meaning "I must conclude that it is John's habit to go to the department parties (because I see his name on the sign-up sheet every time, and he's always out on those nights)." Here must is taken as indicating an epistemic force applied by some body of premises (the only thing that can apply epistemic force), which compels the speaker (or people in general) to reach the conclusion embodied in the sentence. This epistemic force is the counterpart, in the epistemic domain, of a forceful obligation in the sociophysical domain. The polysemy between root and epistemic senses is thus seen (as suggested above) as the conventionalization, for this group of lexical items, of a a metaphorical mapping between domains.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-27 Wed
■ #4566. heldio で古英語期と古英語を手短かに紹介しています(10分×2回) [notice][hel_education][oe][heldio][link][masanyan]
昨日と今日の2日間,私の Voicy の番組 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で古英語(期)の超入門をお届けしています.10分×2回の短いものです.現代の英語は知っているけれども古い英語はまったく初めて,という多くの方々に向けて,古英語期とはどんな時代なのか,古英語とはどんな言語なのかについて,おしゃべりしています.
1本目の「古英語期ってどんな時代?」では,英語の始まりから説き起こして,英語の歴史の時代区分,そして古英語期といわれる5?12世紀のイングランドについて,駆け足で独りごちました.
2本目の「対談 『毎日古英語』のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」では,日本初の古英語系 YouTuber であるまさにゃんとインフォーマルな対談を通じて,古英語という言語の特徴を紹介しました.
ちなみに,最近まさにゃんは「まさにゃんチャンネル」にて,シリーズ「毎日古英語」を精力的に展開しています.今回の heldio 対談は古英語の超入門のみで終わっていますので,関心をもった方はぜひ「毎日古英語」で具体的な古英語にテキストに触れてみてください.なお,本ブログでも1年半ほど前に「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1]) で紹介しています.
2021-10-26 Tue
■ #4565. 高校世界史教科書(英語版)で読む「文明」と「文化」の違い [history][literacy]
日本の高校世界史教科書の英訳版が出版されている.講談社と山川出版社のものをもっているが,とてもおもしろい.世界史の教養を復習できることはもちろん,日本語としては知っているのに英語だと浮かんでこない用語がたくさんあり,たいへん勉強になる.高校生や大学生のみならず,誰にとっても1冊で2科目を学べるスーパー教材といってよい.英文としては平易である.
本村凌二(翻訳監修)の『英語で読む高校世界史』(講談社,2017年)の冒頭の1節は「文明と文化」について.この英語版高校世界史の解説は分かりやすい.
Civilizations and Cultures
In ancient times, people of the West Asia started to live together in cities surrounded by walls with sundried bricks or stones, because of a dry climate and barren land. In the cities, people processed various natural materials and made their lives more comfortable. They also invented irrigated agriculture, metal ware and vehicles. In addition to this, philosophies and religions were created, and massive architectural buildings were constructed. Thus, the oldest civilization was established.
From the beginning, civilisations were created being independent of or in conflict with, the natural environment.
Therefore, they could spread beyond the difference of environments. On the other hand, cultures were the lifestyles made by the relations between humans and natural environments. In other words, each area has its own culture suitable for its environment. Relationships between humans and nature have made unique landscapes. It is difficult for a culture to spread beyond its own environment. Thus, the cultures were thought to be inferior to the civilizations. Since the end of the 20th century, however, the meaning of natural environments began to be reconsidered.
文明と文化の定義や相違については文化人類学でも様々な立場があり,上記は1つの見解であることに注意.例えば『ブリタニカ国際大百科事典小項目版2015』によれば「文明」とは次の通り.
文化と同義に用いられることが多いが,アメリカ,イギリスの人類学では,特にいわゆる「未開社会」との対比において,より複雑な社会の文化をさして差別的に用いられてきた.すなわち国家や法律が存在し,階層秩序,文字,芸術などが比較的発達している社会を文明社会とする.しかし今日では,都市化と文字の所有を文明の基本要素として区別し,無文字 (前文字) 社会には文化の語を用いる学者も多い.この立場では文明は文化の一形態,下位概念とされる.またドイツ民族学や文化社会学では,精神的なものと自然的なものを区別し,自然を支配するための技術による物質的・実際的部門にかかわるものを文明,自然それ自体の価値を実現する精神的,感情的な部門にかかわるものを文化とする傾向がある.
文字の所有の有無,あるいは literacy の有無が重要な要因となるという見解だが,これに対して「#3118. (無)文字社会と歴史叙述」 ([2017-11-09-1]) でみた議論があることにも注意しておきたい
・ 本村 凌二(翻訳監修) 『英語で読む高校世界史 Japanese high school textbook of the WORLD HISTORY』 講談社,2017年.
・ 橋場 弦・岸本 美緒・小松 久男・水島 司(監修) 『WORLD HISTORY for High School 英文詳説世界史』 山川出版社,2019年.
2021-10-25 Mon
■ #4564. 法助動詞の根源的意味と認識的意味 [auxiliary_verb][modality][cognitive_linguistics][semantic_change][unidirectionality][conceptual_metaphor][metaphor]
must, may, can などの法助動詞 (auxiliary_verb) には,根源的意味 (root sense) と認識的意味 (epistemic sense) があるといわれる.通時的にも認知的にも前者から後者が派生されるのが常であることから,前者が根源的 (root) と称されるが,機能に注目すれば義務的意味 (deontic sense) を担っているといってよい.
must を例に取れば,例文 (1) の「?しなければならない」が根源的(あるいは義務的)意味であり,例文 (2) の「?にちがいない」が認識的意味ということになる (Sweetser 49) .
(1) John must be home by ten; Mother won't let him stay out any later.
(2) John must be home already; I see his coat.
一般的にいえば,根源的意味は現実世界の義務,許可,能力を表わし,認識的意味は推論における必然性,蓋然性,可能性を表わす.Sweetser (51) の別の用語でいえば,それぞれ "sociophysical domain" と "epistemic domain" に関係する.一見して関係しているとは思えない2つの領域・世界への言及が,同一の法助動詞によってなされているのは興味深い.
実際,英語に限らず多くの言語において,根源的意味と認識的意味の両方をもつ語が観察される.印欧語族はもちろん,セム,フィリピン,ドラヴィダ,マヤ,フィン・ウゴールの諸語でも似た現象が確認される.しかも,歴史的に前者から後者が派生されるという一方向性 (unidirectionality) の強い傾向がみられる(cf. 「#1980. 主観化」 ([2014-09-28-1])) .
とすると,これは偶然ではなく,何らかの動機づけがあるということになろう.認知言語学では,"sociophysical domain" と "epistemic domain" の間のメタファーとして説明しようとする.現実世界の因果関係を認識世界の因果関係にマッピングした結果,根源的意味から認識的意味が派生するのだ,という説明である.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-24 Sun
■ #4563. OALD10 活用ガイド [dictionary][lexicography][notice][elt]
昨年出版された英英辞書 Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English の第10版 (= OALD10) について,以下の記事を書いてきた.
・ 「#4518. OALD10 の世界英語のレーベル15種」 ([2021-09-09-1])
・ 「#4520. Oxford 3000, Oxford 5000, OPAL の語彙」 ([2021-09-11-1])
・ 「#4533. OALD10 が注意を促している同音異綴語の一覧」 ([2021-09-24-1])
入手してからなるべく多くの機会に冊子体なりオンライン版なりを使うようにしているが,いやはや,辞書として本当に進化しているなという印象である.とりわけオンライン版では,辞書の基本機能はもちろん,コロケーションなどの応用機能も利用できる.文法学習のコーナーも充実しているし,先の記事で紹介した Oxford 3000 などのワードリストも入手できる.英文テキストを投げ込むと,各単語が頻度やレベルに応じて色づけされて返ってくる Text Checker というサービスもある.その他,スピーキングやライティングの学習にも役立つリソースが用意されている.サイトを探検しているだけで英語の学習になるほどだ.
旺文社の特設ページより OALD10 の活用ガイドを入手できる.「OALD10活用ガイド 辞書編」と「OALD10活用ガイド アプリ/Web編」の2種類のPDFがあり,とりわけ前者は辞書学の研究者である山田茂氏による,同辞書の使い方の丁寧な解説となっており,たいへん有用.
OALD10 の辞書学の観点からの本格的な分析(100頁以上にわたる!)は Takahashi et al. を参照されたい.
・ Takahashi, Rumi, Yukiyoshi Asada, Marina Arashiro, Kazuo Dohi, Miyako Ryu, and Makoto Kozaki. "An Analysis of Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English, Tenth Edition." Lexicon 51 (2021): 1--106.
2021-10-23 Sat
■ #4562. 通時態は共時態に歴史的与件を提供する [saussure][diachrony][language_change][sociolinguistics][link]
ソシュール以来,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の関係を巡る論争は絶えたためしがない.本ブログでも,この話題について様々に議論してきた.
・ 「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1])
・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])
・ 「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1])
・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])
・ 「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1])
・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])
・ 「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1])
・ 「#3264. Saussurian Paradox」 ([2018-04-04-1])
・ 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])
言語にアプローチする2つの態に関して私の考えるところによれば,通時態は共時態に歴史的与件を提供するものではないか.歴史的与件とは,その時点で過去から受け継いだ言語的資産目録というほどの意味である.両態は確かに直行する軸であり性質がまるで異なっているのだが,現在という時点において唯一の接触点をもつ.この接触点に両態のエネルギーが凝縮しているとみている.時間軸上のある1点における断面図である言語の共時態は,通時態からエネルギーを提供されて,そのような断面図になっているのだ.
Sweetser (9--10) が著書の序章において,ソシュールのチェスの比喩をあえて引用しつつ,似たような見解を示しているので引用したい.
. . . [W]e cannot rigidly separate synchronic from diachronic analysis: all of modern sociolinguistics has confirmed the importance of reuniting the two. As with the language and cognition question, the synchrony/diachrony interrelationship has to be seen in a more sophisticated framework. The structuralist tradition spent considerable effort on eliminating confusion between synchronic regularities and diachronic changes: speakers do not necessarily have rules or representations which reflect the language's past history. But neither Saussure nor any of his colleagues would have denied that synchronic structure inevitably reflects its history in important ways: the whole chess metaphor is a perfect example of Saussure's deep awareness of this fact. Saussure, of course, uses chess because for future play the past history of the board is totally irrelevant: you can analyze a chess problem without any information about past moves. But he could hardly have picked --- as he must have known --- an example of a domain where past events more inevitably, regularly, and evidently (if not uniquely) determine the present resulting state. No phonologist today would reconstruct a proto-language's sound system without attention both to recognized universals of synchronic sound-systems and to attested (and phonetically motivated) paths of phonological change; it is assumed that the same perceptual, muscular, acoustic, and cognitive constraints are responsible for both universals of structure and universals of structural change. And, for a historical phonologist or semanticist trying to avoid imposing past analyses on present usage, it is an empirical question which aspects of diachrony are preserved in a given synchronic phonological structure or meaning structure.
詰め将棋は本番のための訓練としてはよいが,本番そのものではない.言語研究も,本番の真剣勝負こそを観察対象とするものであってほしい.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-22 Fri
■ #4561. 語順問題は統語論と情報構造の交差点 [word_order][syntax][information_structure]
英語の歴史においては,いかにして語順 (word_order) が変化してきたかという問いが,1つの重要な研究課題となっている.古英語ではそもそも SVO などの固定語順ではなく比較的自由だったわけだが,なぜ,どのようにして現代風の固定語順が発達してきたのか,というのが大きな論題となる.
また,古英語では主語自体が必須ではなく,主語を欠いた文があり得たという点も重要である.では,なぜ後の歴史において主語が必須となったのか,その点が議論の的となるわけだ.
このように,英語史研究の歴史において語順の変化は統語論 (syntax) における第一級の関心事であり続けてきた.しかし,語順といえば統語論の話題である,という一見すると当たり前のとらえ方も慎重に再検討する必要がある.語順は確かに統語論上の問題ではあるが,同時にすぐれて情報構造 (information_structure) に関わる問題でもあるからだ.Fischer et al. (211) は,語順の歴史的変化を扱った章の最後で,次のように結んでいる.
Word order sits at the cross-roads between syntax and information structure. On the one hand, syntax provides the basic templates that speakers can draw on to manage the information flow in and between clauses. On the other hand, the repertoire of syntactic structures available to speakers is attuned to the demands of information management. Unsurprisingly, then, it is by taking into account information structure that most recent progress in understanding word order and word-order change has been made.
情報構造の側からみると,古英語のように語順が比較的柔軟であれば,その柔軟さゆえに表現の自由度や選択肢が広がる.一方,語順が固定化すると,情報構造の操作に制約が課され,その制約による不自由を補うために,別の言語的工夫が必要となってくる.
英語学習者である私たちは英語の語順の歴史的変化や共時的変異の話題を,単に習得しやすい/しにくいという観点からとらえてしまいがちだが,言語にとって語順とは,確かに半分は統語的・形式的な問題ではあるが,もう半分は情報構造・談話に関する問題であることを認識しておきたい.
・ Fischer, Olga, Hendrik De Smet, and Wim van der Wurff. A Brief History of English Syntax. Cambridge: CUP, 2017.
2021-10-21 Thu
■ #4560. ゼミ合宿でのコンテンツ展覧会のベスト作品 [hel_education][khelf][notice]
去る9月21日,22日の両日,昨年に引き続きオンライン開催となりましたが,学部・大学院のゼミ合宿を実施しました.本ブログでも「#4530. 今年度のオンラインゼミ合宿の1日目」 ([2021-09-21-1]) と「#4531. 「World Englishes 入門」スライド --- オンラインゼミ合宿の2日目の講義より」 ([2021-09-22-1]) で簡単に報告した通りですが,2日間にわたるゼミ合宿では様々なイベントを催行しました.
そのなかの目玉の1つが,4大学合同で開催したオンラインの「英語史コンテンツ展覧会」でした(具体的には学習院大学,専修大学,明治学院大学,慶應義塾大学).学生が事前に英語史に関して調べたコンテンツ(雑談以上でレポート以下,ただし学術のルールに則って参考文献などはしっかり付すこと,という仕様)を匿名で公表し,決められた時間内にお互いに読み合って,ツイート風にコメントするというライヴ企画です.
展覧会の後には出展者である学生同士で投票を行ない,おもしろかったコンテンツを選出するという仕掛けも設けました.そのベスト10コンテンツ(実際には順位タイも含めて12件)が決まりましたので,一般にも公開したいと思います.khelf (= Keio History of the English Language Forum) のサイトに展覧会用特設ページを設けました.
ぜひ学生たちの柔軟な好奇心と鋭い問題意識,英語史の幅広さと奥深さ,遊び心からスタートする学びの素晴らしさをご堪能ください.以下にもラインアップを示しておきます.軽めで読みやすいものから調査を尽くした力作まで,硬軟のコンテンツが揃っています.なにせ出展者は学部2年生から博士課程シニアの学生までと幅広く,本当に感心するほど多岐にわたっておもしろいです!
・ "dog" に対する「人間」のイメージ
・ I think, I think うっせえわ
・ 主語と時制を無視するスラング 'ain't'
・ 「はい,チーズ!」 じゃなきゃダメなんですか?
・ フリーランスと騎士
・ 自分の名前を紹介するときどちらを使うか?
・ 語源から考える人間像
・ どっちそっち「チラ見」?
・ ちゃんと「カンパイ」出来ていますか?
・ アナ雪『Let It Go』はなぜ“ありのまま”と訳される?
・ 5文型の先の世界
・ ニューヨークの地名から見る英語史
英語史教育・学習の一環として行なった企画です.趣旨を理解していただき,ぜひ楽しんでお読みいただければ幸いです.
2021-10-20 Wed
■ #4559. 中英語の flouren cakes は(多分あまり甘くない)小麦パン [suffix][adjective][semantic_change][me_text]
今期の大学院の授業では Bennett and Smithers 版の The Land of Cokaygne を読んでいる.14世紀の写本に残る中英語テキストで,パラダイスの情景を描くパロディ作品である.パラダイスなので,いろいろとおもしろい描写があるのだが,建物が食べ物でできているというくだりがある.現代では童話などにもお菓子の家というモチーフがあり,いかにも甘そうなのだが,少なくとも中世イングランドでは甘いお菓子というわけではなさそうで,描写を眺める限り,肉や魚のパイだとか腸詰めだとか,どちらかというと塩気のある食べ物からなる建物の描写が目立つ.好みはあるだろうが,酒飲みには,こちらのほうがツマミとしておいしそうに読める.
その57行目に Fluren cakes beþ þe schingles alle と見える.「屋根板はすべて小麦粉の cakes である」という文だが,ここで2点指摘したい(以下,大学院生の講読担当者の解釈にも負っている).まず,ここでは cakes とあるが現代的な甘い「ケーキ」というよりは,それほど甘くもないかもしれない普通の「パン」を意味するように思われる.MED の cāke n. によると,第1語義は "A flat cake or loaf; also, an unbaked cake or loaf" とある.甘くないとも明記されてはいないが,現代人が期待する甘さではないだろうというのが私の見立てである.
次に Fluren に注目するが,これは小麦粉を意味する flour の形容詞形である.現代英語では *flouren は廃語となっており,普通は floury や floured が用いられる.英語史を通じても,名詞に対して -en 語尾を取るこの形容詞は稀のようで,MED でも OED でも,このテキストのこの箇所が唯一例となっている.MED の flouren adj. より,以下の通り.
?c1335(a1300) Cokaygne (Hrl 913)57 : Fluren cakes beþ þe scingles alle.
この -en 語尾とはいったい何か.これは「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]) で解説したように,素材や材質を表わす形容詞を作る接尾辞 (suffix) -en である.印欧語族の接尾辞のなかでも相当に古いものようで,ラテン語 -īnus,ギリシア語 -inos,サンスクリット語 -īna などにも同根辞を探り当てることができる.英語でも中英語期まではそこそこ生産的な接尾辞だったようだが,近代英語期以降は名詞がそのまま形容詞的に用いられるようになるという革新があり,-en による形容詞の語形成は衰退した.現在でも使われるものとして earthen, golden, wheaten, wooden, woolen などが挙げられるが,今回の *flouren は上記の例が唯一例のようで,しかも現代まで生き残っていない.
小麦粉のパンの屋根板であれば十分においしそうではあるが,甘さはさほど期待しないほうがよいのかなと思いつつ,当該の行を十分に賞味した.
・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.
2021-10-19 Tue
■ #4558. 英語史と世界英語 [hel_education][world_englishes][model_of_englishes][variety][link][heldio]
昨日の記事「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) で,明治学院大学で英語史の授業を担当している泉類尚貴氏による推薦書を紹介させていただきました.その中で7番目の書籍である鳥飼玖美子(著)『国際共通語としての英語』(講談社現代新書,2011年)が意外性をもって受け取られるかもしれません.タイトルからは確かに英語を巡る重要な問題であることは分かるのですが,英語史とどのように関わるのかという疑問が浮かぶのではないでしょうか.この点を確認すべく,昨日に引き続き「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて同氏と対談しました.「対談 英語史×国際英語」というお題です.以下よりどうぞ.
英語史の領域では近年,世界英語 (world_englishes) への関心が急上昇しています.私自身も食らいついていかなければと思い,にわか勉強を始めているわけですが,急激なオンライン・リソースの拡大も相まって,すでに分野を一望するのも難しい水準にまで膨張しています.関心はあってもどこから始めたらよいかと迷うのも無理もありません.
私のお勧め図書としては,唐澤一友(著)『世界の英語ができるまで』(亜紀書房,2016年)を挙げておきます.本ブログでも world_englishes や model_of_englishes にて関連する記事を多く書いてきましたが,比較的最近書いた記事をピックアップすると,次のようなラインアップになります.
・ 「#4531. 「World Englishes 入門」スライド --- オンラインゼミ合宿の2日目の講義より」 ([2021-09-22-1])
・ 「#4466. World Englishes への6つのアプローチ」 ([2021-07-19-1])
・ 「#4506. World Englishes の全体的傾向3点」 ([2021-08-28-1])
・ 「#4507. World Englishes の類型論への2つのアプローチ」 ([2021-08-29-1])
・ 「#4508. World Englishes のコーパス研究の未来」 ([2021-08-30-1])
・ 「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1])
・ 「#4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ」 ([2021-08-14-1])
・ 「#4493. 世界の英語変種の整理法 --- Mesthrie and Bhatt の12タイプ」 ([2021-08-15-1])
・ 「#4501. 世界の英語変種の整理法 --- McArthur の "Hub-and-Spokes" モデル」 ([2021-08-23-1])
・ 「#4502. 世界の英語変種の整理法 --- Görlach の "Hub-and-Spokes" モデル」 ([2021-08-24-1])
世界英語を扱うオンライン・コーパスとしては,上にも触れた GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) を入り口としてお勧めします.このコーパスについては,専修大学文学部英語英米語学科の菊地翔太先生のHPより,こちらのページに関連情報があります.ちなみに菊地翔太先生のHPを探検し紹介するコンテンツ「菊地先生のホームページを訪れてみよう 」を大学院生が作ってくれましたので,こちらもお勧めしておきます.
2021-10-18 Mon
■ #4557. 「英語史への招待:入門書10選」 [hel_education][bibliography][khelf][link][heldio][masanyan][voicy]
昨日,青山英語史研究会(青山学院大学・寺澤盾先生主催)がオンラインで開催されました.「研究会」とはいうものの,今回は英語史を学ぶ大学生を主たるオーディエンスとして想定し,英語史の学びをエンカレッジする様々な企画が組まれました.私も参加させていただきましたが,たいへん実りの多い会となりました.ありがとうございます.
プログラムの1つとして,明治学院大学で英語史の授業を担当している泉類尚貴氏による「英語史への招待:入門書10選」が紹介されました.氏の許可を得て,そのリスト(実際にはオマケ付きで11冊)を以下に掲載します.氏によると,この順序で手に取ってみることをお勧めするとのことです.
ちなみに泉類氏とは,本日の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて同じ話題で対談していますので,こちらも是非お聴きください.推薦書リストというものは,選者による簡単な解説があるだけでも説得力が増しますね.
・ 寺澤 盾 『英語の歴史:過去から未来への物語』 中公新書,2008年.
・ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.
・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』 研究社,2016年.
・ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.
・ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.
・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.
・ 鳥飼 玖美子 『国際共通語としての英語』 講談社現代新書,2011年.
・ 西村 秀夫 編 『コーパスと英語史』 ひつじ書房,2019年.
・ 高田 博行・渋谷 勝巳・家入 葉子(編著) 『歴史社会言語学入門』 大修館書店,2015年.
・ Baugh, A. C. and T. Cable. A History of the English Language. 6th ed. Routledge, 2013.
・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.
番外編として,参考になるウェブサイトということで以下の4点も紹介されました.
・ TED Ed
・ YouTube 「まさにゃんチャンネル」
・ 「hellog?英語史ブログ」
・ khelf (= Keio History of the English Language Forum)
以上,英語史の学びのエンカレッジでした.昨日の記事「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1]) も合わせてどうぞ.
2021-10-17 Sun
■ #4556. 英語史の世界にようこそ [hel_education][notice][heldio][hellog-radio][sobokunagimon][link]
学期の始めなので,標題のような「英語史の学びのエンカレッジ系」の記事が多くなります.最近では「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]) も書いており,本ブログの記事などに関連するリンクを多々張っていますので,詳しくは是非そちらもご覧ください.今回は先の記事から重要な6点のみピックアップし,改めて英語史への入り口を案内します.
(1) 私(堀田隆一)の考える「英語史の魅力」はズバリこれ.
1. 英語の見方が180度変わる!
2. 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
3. 素朴な疑問こそがおもしろい!
4. 英語が本当によく分かるようになる!
(2) 上記の「素朴な疑問こそがおもしろい!」は本当です.「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) に挙げたような疑問が,英語史によりスルスルと解けていきます.それでも足りない方は「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) でどうでしょう!
(3) 本ブログ「hellog?英語史ブログ」は「英語史に関する話題を広く長く提供し続けるブログ」として2009年5月1日に立ち上げたものです.大学の英語史概説の講義に対する補助的な読み物を提供する趣旨で始めました.日々の記事の種類は多岐にわたり,英語を学び始めたばかりの中学生などを読者と想定した話題もあれば,大学院博士課程の学生を念頭においた学術的な話題もあります.書き手以外何を言っているか分からないという話題も少なくないと思います,失礼! それでも,ぜひ毎日タイトルだけでも目を通していれば,英語史のカバーする範囲の広さが分かってくると思います.毎日タイトルをお届けするツイッターアカウントもあります.
(4) 本ブログの姉妹版・音声版として「hellog ラジオ版 (hellog-radio)」(2020年6月23日?2021年2月7日に不定期で),および続編である「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(2021年6月2日より現在まで毎日定期的に)を配信しています.hellog に比べ,話題は「英語に関する素朴な疑問」におよそ特化しています.各放送は10分以内の短い英語史ネタです.ぜひこれを聞くことを日課にどうぞ! ちなみに本日の放送では,上記 (1) を熱く語っています.
(5) 明後日10月19日は「TOEIC の日」.つい先日 TOEIC 事業などを手がける IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビューを受けました.テーマは「英語はいかにして世界の共通語になったのか」という,英語(史)に関する究極の疑問の1つです.英語史超入門ともなっているこちらのインタビュー記事をどうぞ(cf. 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1])).
(6) 最後に私の選んだ「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) をご覧ください.英語史を学び始めるには,なんといっても本を読むのが一番です.
2021-10-16 Sat
■ #4555. 対立する形式意味論と認知意味論 [semantics][cognitive_linguistics][history_of_linguistics]
意味論 (semantics) と一口にいっても,様々なとらえ方がある.そして,学界にも派閥がある.学問名 semantics の複数形の -sは,その点でふさわしいともいえる.
大きく2つの派閥に分けるならば,伝統的な形式意味論(構造主義意味論を含む)か,1970年代後半に興った新しい認知意味論かとなる.これは,一般言語学でいうところの構造主義・生成文法と認知言語学の対立になぞらえることもできるだろう.
Sweetser (12) が意味論の2つの派閥の対立について,分かりやすく記述している.
Recent work in linguistics has tended to view semantics in one of two divergent ways: either meaning is a potentially mathematiziable or formalizable domain (if only we could find the right primes or premises for the mathematical analysis), or meaning is a morass of culturally and historically idiosyncratic facts from which one can salvage occasional linguistic regularities. Those who do the former kind of semantics have frequently been eager to separate linguistic meaning from general human cognition and experience, and to keep linguistic "levels" 'syntax vs semantics vs pragmatics) distinct from one another; formalization is presumed to be easier if the domain can be successfully delimited. Semanticists of the latter sort, on the other hand, are often quite ready to accept the direct influence of experience or cognition on meaning-structures, but find it hard to see how such meaning-structures could be formalized: how can airtight generalizations be made about experience-shaped semantics, when experience itself is so varied and so far from currently being described by any complete formal analysis?
確かに対立の構図とはなっているが,伝統的意味論と新興の意味論の各々には長所もあれば短所もある.相互補完的にみておくのがよさそうだ.関連して「#1686. 言語学的意味論の略史」 ([2013-12-08-1]) も参照.
・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-15 Fri
■ #4554. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第8回「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][link][gvs]
NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」の11月号のテキストが発売となりました.連載している「英語のソボクな疑問」は第8回となっています.今回は英語の母音字の読みに関する,きわめて素朴な疑問「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」を取り上げています.
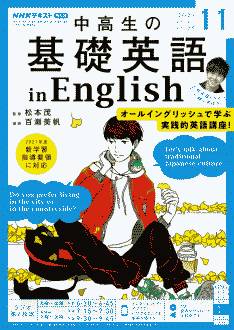
本ブログの読者の多くの方々は,この疑問が英語史でいうところの「大母音推移」 (gvs) に関わるものであることがお分かりかと思います.しかし,連載は中高生を対象読者とするものですので,この用語を持ち出すことは控えたいと考えました.そして,もちろん音声学の用語や概念なども前提とすることはできません.ということで,真正面から大母音推移の伝統的な説明を施すことはせず,なるべく易しく噛み砕いて伝えようと努めました.結果として,前舌母音のみの説明にとどめて後舌母音については触れないでおくなど,理解しにくくなりそうな部分を思い切って割愛しました.このような次第で,今回は私にとって1つの挑戦となりました(どのくらい成功しているかは分かりませんねえ).
大母音推移の教科書的な説明としては本ブログの「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) をどうぞ.もう少し詳しくは,拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の1.3節と2.5節をご参照ください.専門的には gvs の各記事で扱っています.
・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.
2021-10-14 Thu
■ #4553. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (4) [contact][language_change][causation][how_and_why][multiple_causation]
標題の話題について,本ブログでもたびたび議論してきた.例えば次の通り.
・ 「#443. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か?」 ([2010-07-14-1])
・ 「#1232. 言語変化は雨漏りである」 ([2012-09-10-1])
・ 「#1233. 言語変化は風に倒される木である」 ([2012-09-11-1])
・ 「#1582. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (2)」 ([2013-08-26-1])
・ 「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1])
・ 「#1977. 言語変化における言語接触の重要性 (1)」 ([2014-09-25-1])
・ 「#1978. 言語変化における言語接触の重要性 (2)」 ([2014-09-26-1])
・ 「#1986. 言語変化の multiple causation あるいは "synergy"」 ([2014-10-04-1])
・ 「#3152. 言語変化の "multiple causation"」 ([2017-12-13-1])
・ 「#3271. 言語変化の multiple causation 再考」 ([2018-04-11-1])
・ 「#3355. 言語変化の言語内的な要因,言語外的な要因,"multiple causation"」 ([2018-07-04-1])
・ 「#3377. 音韻変化の原因2種と結果3種」 ([2018-07-26-1])
・ 「#3842. 言語変化の原因の複雑性と多様性」 ([2019-11-03-1])
・ 「#3971. 言語変化の multiple causation 再再考」 ([2020-03-11-1])
今回は,もう1つ Hickey (487--88) より議論を追加したい.この問題を巡る近年の様々な立場が,要領よくまとめられている.
2.1 Language-internal versus contact factors
In the current context language-internal change is understood as that which occurs within a speech community, among monolingual speakers, and contact-induced change as that which is induced by interfacing with speakers of a different language.
Opinions are divided on when to assume contact as the source of change. Some authors insist on the primacy of internal factors . . . and so favor these when the scales of probability are not biased in either direction for any instance of change. Other scholars view contact explanations more favorably . . . while still others would like to see a less dichotomous view of internal versus and external factors in change . . . .
The fate of explanations based on language contact has varied in recent linguistic literature. During the 1980s many linguists reacted negatively to apparently superficial contact explanations . . . . Others . . . have been consistently skeptical of contact explanations, stressing the coherent internal structure of languages and assuming by default that this is the locus of new features. This position has also been theoretically contested . . . , as it is unproven that language-internal factors take automatic precedence over contact in language change.
Another point needs to be highlighted: at best contact accounts for a phenomenon but does not explain why this should have arisen in the first place. Contact treatments tend to push sources back a step, but not to explain ultimate origins. Rather contact seeks to account for how features come about. "Account" is a more muted term and does not raise expectations of high degrees of adequacy implied by "explanation" . . . .
It would be blind to neglect the possible language-internal arguments for various features suspected of having a contact source. If internal arguments are considered and then deemed insufficient on their own, this actually strengthens the contact case, as contact is then seen as a necessary contributory factor to account fully for the appearance of features. Ultimately, contact accounts depend for acceptance on whether scholars are convinced by what they know about contact scenarios in general, specific contact in the case being discussed, possible alternative accounts and the crucial balance of internal and external factors.
Given that both language-internal and contact sources are available to speakers, it might be fair to postulate that no matter what the likelihood of transfer though contact, language internal factors can always play a role. It is the nature and rate of change which can be influenced by contact, a factor which can vary in intensity.
私自身は,この問題について様々な意見を読み考えてきたが,言語変化一般についていえば言語内的・外的要因の両方が等しく重要であるという立場から動いたことはない.ただし,個別の言語変化についていえば,いずれかの要因がより強く作用しているということはあり得ると考える.
・ Hickey, Raymond. "Assessing the Role of Contact in the History of English." Chapter 37 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 485--96.
2021-10-13 Wed
■ #4552. borrowing, transfer, convergence [terminology][contact][borrowing][language_shift]
言語接触 (contact) に関わる標題の3つの重要な用語を解説する.このような用語を用いる際に注意すべき点は,論者によって何を指すかが異なり得ることだ.ここでは当該分野の専門家である Hickey (486--87) の定義を引用したい.
(1) Borrowing. Items/structures are copied from language X to language Y, but without speakers of Y shifting to X. In this simple form, borrowing is characteristic of "cultural" contact (e.g. Latin and English in the history of the latter, or English and other European languages today). Such borrowings are almost exclusively confined to words and phrases.
(2) Transfer. During language shift, when speakers of language X are switching to language Y, they transfer features of their original native language X to Y. Where these features are not present in Y they represent an innovation. For grammatical structures one can distinguish (i) categories and (ii) their realizations, either or both of which can be transferred.
(3) Convergence. A feature in language X has an internal source (i.e. there is a systemic motivation for the feature within language X), and the feature is present in a further language Y with which X is in contact. Both internal and external sources "converge" to produce the same result as with the progressive form in English. . . .
この3つの区分は,接触に起因する過程の agentivity が X, Y のいずれの言語話者側にあるのか,あるいは両側にあるのかに対応するといってよい.この agentivity の観点については「#3968. 言語接触の2タイプ,imitation と adaptation」 ([2020-03-08-1]),「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1]) も参照.
・ Hickey, Raymond. "Assessing the Role of Contact in the History of English." Chapter 37 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 485--96.
2021-10-12 Tue
■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]
「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.
Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.
As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.
端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).
16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.
The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2021-10-11 Mon
■ #4550. 歴史的辞書は言語の中立的な情報源ではない [lexicography][dictionary][cawdrey][johnson][philology]
言語研究上,辞書はなくてはならない情報源である.本ブログの中心的な話題である英語史研究においても,各時代の辞書や通時的な辞書はなくてはならないツールだ.しかし,辞書とて人の作ったものである.辞書編纂者の生きた時代の言語態度が反映されているものだし,辞書編纂者個人のバイアスもかかっているのが常である.言語研究のためには,この辺りを意識して歴史辞書(および現代の辞書)を用いる必要があるのだが,このようなすぐれてフィロロジカルな観点は意識の外に置かれることが多い.例えば,威信ある OED の情報であれば間違いがあるはずがない,などと絶対的な信頼を寄せてしまうことはよくある.
近代英語期に目を向けると,例えば英語史上初の英語辞書といわれる 1604年の Robert Cawdrey の A Table Alphabeticall と,時代も下って規範主義が成熟した1755年の Samuel Johnson の A Dictionary of the English Language とでは,編纂された時代背景も異なれば言語態度も異なるので,同じ見出し語の定義などを比べたとしても,そこには確かに通時的な変化が反映されている可能性はあるものの,そもそもの編纂意図が異なるという点を考慮しておかないと痛い目に合うかもしれない.Coleman (99--100) が,この点を指摘している.
For example, the title of Cawdrey's Table Alphabetical (1604) explains that the dictionary was compiled "for the benefit and help of ladies, gentlewomen, or any other unskillful persons. Whereby they may the more easily and better understand many hard English words, which they shall hear or read in scriptures, sermons, or elsewhere, and also be made able to use the same aptly themselves" (spelling modernized). Similarly often quoted is the preface to Johnson's Dictionary of the English Language (1755):
When I took the first survey of my undertaking, I found our speech copious without order, and energetic without rules: wherever I turned my view, there was perplexity to be disentangled, and confusion to be regulated; choice was to be made out of boundless variety, without any established principle of selection. (Johnson 1755: Preface)
These quotations illustrate changing ideas about the status of English and the purpose of a dictionary. Cawdrey acknowledged that the vocabulary of English was varied and challenging, but apparently did not consider this to be a problem. His purpose was to help uneducated people struggling to understand loans from classical and modern languages: the deficit was in English speakers, not the language. Johnson, on the other hand, considered the exuberance of English to be problematic in itself, and for him the priorities were regulation and control of the language.
17世紀初めの Cawdrey は問題は英語話者にあると考えていたが,18世紀半ばの Johnson は問題は英語そのものにあると考えていた.辞書編纂のポリシーが互いに異なっていたのも無理からぬことである.
標題にも掲げた通り「歴史的辞書は言語の中立的な情報源ではない」可能性が高いのだ.一方,この点を逆手に取れば,歴史的辞書を通じて,通時的な言語変化の証拠は得られなくとも,各時代の言語態度をこそ復元できるということなのかもしれない.歴史的辞書は使いようである.
・ Coleman, Julie. "Using Dictionaries and Thesauruses as Evidence." Chapter 7 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 98--110.
2021-10-10 Sun
■ #4549. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」のご案内 [asacul][notice][history][link][emode]
朝日カルチャーセンター新宿教室にて全12回の企画で2年ほど前に始めた「英語の歴史と語源」シリーズが,いよいよ最終回となります.2週間後に迫った第12回(最終回)のお知らせです.「市民革命と新世界」と題して2021年10月23日(土)15:30--18:45に開講予定です.対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式を予定しています.関心のある方はこちらよりご予約ください.今回の趣旨は以下の通りです.
17世紀イングランドは「清教徒革命」と「名誉革命」という2つの大変革を経験しました.一般に国内の混乱の世紀ととらえられていますが,英語史の観点からは,後に英語が国外に展開してゆく足場を築いた時期として重要な意義をもちます.実際,同世紀中にイングランドは北米に植民地を築き,インドへの影響力をもち始めました.英語の世界的展開が本格的に始まろうとしていた時代に焦点を当てつつ,英語の現在と未来についても考察します.
今回は,イングランドの革命の時代,17世紀に焦点を当てます.この時期は,イングランド国内の状況こそ混乱を極めましたが,国外への展開は順調であり,20--21世紀にかけて大国へと成長していくことになる北米やインドに橋頭堡を築いた時代として,歴史的にたいへん重要な意義をもちます.お祭り騒ぎというべきルネサンスの熱は冷めてしまったものの,英語がいよいよ自信と安定感を獲得し,国内外において規範を確立させようと引き締めに入った時期でもあります.現代に直接通じる言語特徴や言語意識が生まれたこの時代に注目しつつ,21世紀の英語も占いながら本シリーズを締めくくりたいと思います.皆様のご参加をお待ちしています.
2021-10-09 Sat
■ #4548. 比喩と意味借用の関係 [metaphor][semantic_borrowing][semiotics][semantic_change][semantics][polysemy]
語の意味変化に関して Williams を読んでいて,なるほどと思ったことがある.これまであまり結びつけてきたこともなかった2つの概念の関係について考えさせられたのである.比喩 (metaphor) と意味借用 (semantic_borrowing) が,ある点において反対ではあるが,ある点において共通しているというおもしろい関係にあるということだ.
比喩というのは,既存の語の意味を,何らかの意味的な接点を足がかりにして,別の領域 (domain) に持ち込んで応用する過程である.一方,意味借用というのは,既存の語の形式に注目し,他言語でそれと類似した形式の語がある場合に,その他言語での語の意味を取り込む過程である.
だいぶん異なる過程のように思われるが,共通点がある.記号論的にいえば,いずれも既存の記号の能記 (signifiant) はそのままに,所記 (signifié) を応用的に拡張する作用といえるのである.結果として,旧義と新義が落ち着いて共存することもあれば,新義が旧義を追い出すこともあるが,およその傾向はありそうだ.比喩の場合にはたいてい旧義も保持されて多義 (polysemy) に帰結するだろう.一方,意味借用の場合にはたいてい旧義はいずれ破棄されて,結果として語義置換 (semantic replacement) が生じたことになるだろう.
動機づけについていえば,比喩は主にオリジナリティあふれる意味上の関連づけに依存しているが,意味借用はたまたま他言語で似た形式だったことによる関連づけであり,オリジナリティの点では劣る.
上記のインスピレーションを得ることになった Williams (193) の文章を引用しておきたい.
Semantic Replacement
In our linguistic history, there have been cases in which the reverse of metaphor occurred. Instead of borrowing a foreign word for a new semantic space, late OE speakers transferred certain Danish meanings to English words which phonologically resembled the Danish words and shared some semantic space with them. The native English word dream, meaning to make a joyful noise, for example, was probably close enough to the Scandinavian word draumr, or sleep vision, to take on the Danish meaning, driving out the English meaning. The same may have happened with the words bread (originally meaning fragment); and dwell (OE meaning: to hinder or lead astray).
引用中で話題となっている意味借用の伝統的な例としての dream, bread, dwell については「#2149. 意味借用」 ([2015-03-16-1]) を参照.とりわけ bread については「#2692. 古ノルド語借用語に関する Gersum Project」 ([2016-09-09-1]) を参照されたい.
・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975.
2021-10-08 Fri
■ #4547. clang association [semantic_change][synonym][psycholinguistics][terminology][etymology][semiotics][pun][clang_association]
英語史の古典的著書といってよい Algeo and Pyles を読んでいて,語の意味変化 (semantic_change) の話題と関連して clang association という用語を知った.もともとは心理学の用語のようだが「類音連想(連合),音連合」と訳され,例えば cling と ring のように押韻するなど発音が似ている語どうしに作用する意味的な連想のことをいうようだ.いくつかの英語学用語辞典を引いても載っていなかったので,これを取り上げている Algeo and Pyles (233--34) より引用するほかない.
Sound Associations
Similarity or identity of sound may likewise influence meaning. Fay, from the Old French fae 'fairy' has influenced fey, from Old English fǣge 'fated, doomed to die' to such an extent that fey is practically always used nowadays in the sense 'spritely, fairylike.' The two words are pronounced alike, and there is an association of meaning at one small point: fairies are mysterious; so is being fated to die, even though we all are so fated. There are many other instances of such confusion through clang association (that is, association by sound rather than meaning). For example, in conservative use fulsome means 'offensively insincere' as in "fulsome praise," but it is often used in the sense 'extensive' because of the clang with full. Similarly, fruition is from Latin frui 'to enjoy' by way of Old French, and the term originally meant 'enjoyment' but now usually means 'state of bearing fruit, completion'; and fortuitous earlier meant 'occurring by chance' but now is generally used as a synonym for fortunate because of its similarity to that word.
発音が近い単語どうしが,意味の点でも影響し合うというのは,記号論的にはもっともなことだろう.当然視しており深く考えることもなかったが,記号間の連携というのは,高度に記号を操ることのできるヒトならでは芸当である.ダジャレや,それに立脚するオヤジギャグを侮ることなかれ.立派な clang association なのだから.
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005.
2021-10-07 Thu
■ #4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方 [hel_education][sobokunagimon][link]
今年度も後期が始まる時期となりました.年度初めの4月に,本ブログでは英語史の学びのモチベーションを高めるキャンペーンを張ったのですが,この学期初めの10月にも,改めて英語史の学びを促すべく広報したいと思います.
まず,私が新年度あるいは新学期の初回の授業で必ず述べることにしている「英語史」の魅力4点を明記します.
--- 英語史の魅力 ---
(1) 英語の見方が180度変わる!
(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!
(4) 現代英語に戻ってくる英語史
以下に,上記4点とも密接に関わる,英語史の学びに役立つ本ブログからの記事をいくつか紹介します.
・ 「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) --- 入門書から専門書までの厳選書誌
・ 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]) --- この hellog の効果的な使い方の tips
・ 「#4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました」 ([2021-06-04-1]) --- hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) を Voicy にて毎日配信中.1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.
・ 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1]) --- 皆が関心をもつ英単語の語源の話題.自らどんどん調べてみてください.
・ 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) --- 上記の魅力 (2) に通じる話です
・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) --- 上記の魅力 (3) に通じる話です
・ 「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) --- おびただしい疑問の一覧は直接こちらからどうぞ
・ 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1]) --- 英語史に関する究極の疑問かもしれません.インタビューに基づいたわかりやすい解説になっています.直接こちらからどうぞ.
・ 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット --- 様々な角度から検討してみました.「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています.
・ 「#4417. 「英語史導入企画2021」が終了しました」 ([2021-05-31-1]) --- 今年度初めに企画した英語史の学びを応援するイベント.すでに終了していますが「英語史コンテンツ」とは何かがよく分かります.
皆さん,今学期も実り多い学びを!
2021-10-06 Wed
■ #4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー [notice][hel_education][sobokunagimon][link][future_of_english][linguistic_imperialism]
先日,TOEIC 事業などを手がける IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)の Newsletter 44号のために,標題についてのインタビューを受けました.10月19日が「TOEIC の日」に制定されたそうで,その特別企画としての取材でした.(関係者の皆様,夏の暑い時期でしたが,私の研究室までお運びいただきありがとうございました.)
冊子体でも発行されているのですが,ウェブでも公表されています.こちらよりご一読ください.英語史超入門ともなっています.(ゲルマン語系統図や英語史略年表も,とてもきれいに作っていただきました.あ,それから写真も.)
標題の素朴な疑問への答えはインタビュー記事を読んでいただければ分かるわけですが,かいつまんでいえば英米両国の覇権という社会的な要因がほぼすべてです.英語の語彙が豊かだからとか,文法が簡単だからとか,その他の英語の言語的特質に起因するものでは決してありません.この点は拙著や本ブログでも繰り返し主張してきました.以下は関連する記事群です.
・ 「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1])
・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1])
・ 「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1])
・ 「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1])
・ 「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1])
・ 「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1])
・ 「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1])
・ 「#2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」」 ([2017-05-10-1])
・ 「#3470. 言語戦争の勝敗は何にかかっているか?」 ([2018-10-27-1])
・ 「#4279. なぜ英語は世界語となっているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-13-1])
インタビューの後半では,むしろ今後英語がどうなっていくのかという問題も熱く論じました.これについては future_of_english の記事群をどうぞ.
2021-10-05 Tue
■ #4544. 英単語の意味変化と意味論を研究しようと思った際の取っ掛かり書誌(改訂版) [semantic_change][semantics][bibliography][lexicology][htoed]
今年の初めに「#4289. 英単語の意味変化と意味論を研究しようと思った際の取っ掛かり書誌」 ([2021-01-23-1]) という記事をポストしました.今週から本格的に動き出した今年度後期は,英語史関連のいくつかの授業で「英単語の意味変化」を主たるテーマとして掲げることにしています.そこで取っ掛かり書誌の改訂版を作成しました.いくつかの文献を新たに加え,一言コメントも付しました.種別ごとに,お勧め順で並べてみました.本ブログから semantic_change や semantics もどうぞ.今後も随時この書誌に追加していきたいと思っています.
[ 通時的な関心のために --- 英単語の意味変化についてのお薦め書誌 ]
・ 寺澤 盾 「第7章 意味の変化」『英語の意味』 池上 嘉彦(編),大修館,1996年.113--34頁.(まずはこちらから,という手始めの1章です)
・ 寺澤 盾 『英単語の世界 --- 多義語と意味変化から見る』 中央公論新社〈中公新書〉,2016年.(まずはこちらから,という手始めの1冊です)
・ 堀田 隆一 「第8章 意味変化・語用論の変化」『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 服部 義弘・児馬 修(編),朝倉書店,2018年.151--69頁.(cf. 「#3283. 『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]が出版されました」 ([2018-04-23-1]))
・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.(pp. 98--107 にコンパクトが意味変化概論があります)
・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.(英語学事典より pp. 765--80 が意味変化の概論となっています)
・ Williams, Joseph M. Origins of the English Language: A Social and Linguistic History. New York: Free P, 1975. (pp. 153--93 が意味変化論として非常によく書けています)
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. "Words and Meanings." Chapter 10 of The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Boston: Thomson Wadsworth, 2005. 227--44.(よく読まれている英語史概説書の1章より,よく書けた意味変化の概論です)
・ Bloomfield, Leonard. "Semantic Change." Chapter 24 of Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984. 425--43.(言語学の古典的名著の1章で,読み応えがあります)
・ Waldron, R. A. Sense and Sense Development. New York: OUP, 1967.(意味変化の本格的な研究書でよくまとまっています)
・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.(意味変化の古典的研究書で,高度に専門的です)
・ Ullmann, Stephen. The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow: Jackson, 1957.(同じく意味(変化)論の古典的名著で,専門的です)
・ Meillet, Antoine. "Comment les mots changent de sens." Année sociologique 9 (1906). 1921 ed. Rpt. Dodo P, 2009.(フランスの著名な言語学者による語の意味変化の古典的論考です)
・ Room, Adrian, ed. NTC's Dictionary of Changes in Meanings. Lincolnwood: NTC, 1991.(これを手元においておくと便利です.cf. 「#4243. 英単語の意味変化の辞典 --- NTC's Dictionary of Changes in Meanings」 ([2020-12-08-1]))
・ Cruse, Alan. A Glossary of Semantics and Pragmatics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2006.(意味論・語用論のハンディな用語辞典です)
・ Kastovsky, Dieter. "Semantics and Vocabulary." The Beginnings to 1066. Vol. 1 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 290--408.(これと下の2件は,権威ある英語史シリーズの各時代における語彙と意味変化の専門的な議論です)
・ Burnley, David. "Lexis and Semantics." 1066--1476. Vol. 2 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 409--99.
・ Nevalainen, Terttu. "Early Modern English Lexis and Semantics." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 332--458.(とりわけ pp. 433--54 は意味変化の概論ともなっています)
・ Kay, Christian and Kathryn Allan. English Historical Semantics. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.(英語の史的意味論の一冊本としては今のところ唯一のもの.HTOED への導入書でもあります.cf. 「#3159. HTOED」 ([2017-12-20-1]))
・ Hughes, G. A History of English Words. Oxford: Blackwell, 2000.(意味変化というよりも語彙変化がメインですが,随所に関連する話題があります.読み物としてもおもしろいです.)
・ Hughes, G. Words in Time. Oxford: Blackwell, 1988.(上と同じ著者による史的語彙論です)
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.(史的語彙論,とりわけ借用語の史的語彙論ですが,意味変化の隣接分野でもあります)
・ 山中 桂一,原口 庄輔,今西 典子 (編) 『意味論』 研究社英語学文献解題 第7巻.研究社.2005年.(意味変化も含めた専門的な解題書誌です)
・ Coleman, Julie. "Using Dictionaries and Thesauruses as Evidence." Chapter 7 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. (歴史辞書を用いた言語変化・意味変化の研究についてのメタな方法論が論じられています.斜めからの視点ですが,かなり貴重です.)
[ 共時的な関心のために --- 意味とは何かを学ぶためのお薦め書誌 ]
・ 中野 弘三(編)『意味論』 朝倉書店,2012年.(意味論入門としては,この本から)
・ ピエール・ギロー 著,佐藤 信夫 訳 『意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,1990年.(文体論を専門とする著者による意味論概説です)
・ イレーヌ・タンバ 著,大島 弘子 訳 『[新版]意味論』 白水社〈文庫クセジュ〉,2013年.(かなり歯ごたえのある本です)
・ Hofmann, Th. R. Realms of Meaning. Harlow: Longman, 1993.(英語の読みやすい意味論入門書としてお勧めです)
・ Ogden, C. K. and I. A. Richards. The Meaning of Meaning. 1923. San Diego, New York, and London: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.(意味論の古典的名著です)
・ Saeed, John I. Semantics. 3rd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009.(比較的新しい意味論の概説書です)
2021-10-04 Mon
■ #4543. subreption [semantic_change][semantics][terminology]
語の意味変化の典型的なパターンとして,ある語の意味が技術や文化の発展に伴って変化するというもの例がある.例えば,英語 ship は古英語からある古株の単語だが,当時のへっぽこな船と,中世の帆船と,近代の蒸気船と,現代のコンピュータ搭載の最新鋭の船とでは,指示対象の姿形や性能が大きく異なるにもかかわらず,「水に浮かぶ移動手段」という基本機能の点で同一であるために,同じ ship という名で呼ばれている.ship の意味が変化したといえるのかどうかは微妙だが,指示対象が相当に変化してきたということは認めざるを得ないだろう.この手のタイプは,語の意味変化の議論において,しばしば最初に挙げられるタイプの事例である (cf. 「#1873. Stern による意味変化の7分類」 ([2014-06-13-1]),「#1953. Stern による意味変化の7分類 (2)」 ([2014-09-01-1])).
Stern はこの種の意味変化を "substitution" と呼んでいる.一方,今回調べるなかで初めて知ったのだが,Pearce (183--84) によると,"subreption" という術語も用意されているようだ.
Subreption A process of semantic change in which objects, entities, social roles, concepts, institutions and so on change over time, but the words for them remain the same. Take, for example, the phrase 'the driver of the car looked at the dashboard'. The emphasized words have their English origins at a time when all wheeled vehicles were powered by horses: the original meaning of drive (a meaning which it still retains) was 'to force to move before one' (which is what a 'driver' did with horses); car is derived from an earlier word meaning 'chariot', and dashboard originally referred to the wooden board located at the fron of a horse-drawn carriage to prevent objects kicked up by the horses' hooves from hitting the driver.
subreption は通常は「虚偽申請」を意味する法律用語である.普通の辞書では詳しく載っていないほどの専門用語である.OED を引いてみると,言語学用語としては掲載されていないようだ.第1語義は "Misrepresentation or suppression of the truth or facts; an act or instance of this." にとどまる.
語の意味変化に関して何がどう「虚偽申請」なのかと考えたのだが,こういうことだろうか.例えば,上の引用にもある dashboard は,本来は「馬車馬によって跳ね飛ばされた泥をよける板」ほどの意味だが,それを基準とすると,現在の普通の意味「自動車・飛行機などの計器盤」は,虚偽とはいわずとも原義が隠蔽されてしまっていることは確かだ.現在の意味は dash + board から常識的に推測される意味から遠く離れてしまっている.そのような意味での「虚偽申請」(大げさな呼び方ではあるが)ということだろうか.
現代日本語では,下駄ではなく靴を入れているのに,いまだに「下駄箱」ということがある.これも厳密にいえば確かに「虚偽申請」ではある(=突っ込みどころがある)から,subreption の例になるのだろう.
・ Stern, Gustaf. Meaning and Change of Meaning. Bloomington: Indiana UP, 1931.
・ Pearce, Michael. The Routledge Dictionary of English Language Studies. Abingdon: Routledge, 2007.
2021-10-03 Sun
■ #4542. 中英語の人名のトレンド [onomastics][personal_name][me][norman_conquest]
「#4539. アングロサクソン人名の構成要素」 ([2021-09-30-1]) で古英語の人名の傾向をみたので,続いて中英語の人名のトレンドも覗いてみたい (Coates 320--21) .すでに以下の記事などで述べてきたとおりだが,基本的にはノルマン征服を境に,古英語の人名の大多数が受け継がれずに消え,新たにフランス語かぶれの人名が流入し人気を博したといってよい.
・ 「#813. 英語の人名の歴史」 ([2011-07-19-1])
・ 「#590. last name はいつから義務的になったか」 ([2010-12-08-1])
・ 「#2364. ノルマン征服後の英語人名のフランス語かぶれ」 ([2015-10-17-1])
・ 「#2365. ノルマン征服後の英語人名の姓の採用」 ([2015-10-18-1])
・ 「#3902. 純アングロサクソン名の Edward, Edgar, Edmond, Edwin」 ([2020-01-02-1])
フランス語かぶれの人名という言い方をしたが,厳密にいえばフランス語を経由して入ってきた人名ということであり,起源を探ればフランス語ではなく別の言語に起源をもつ名前がほとんどである.おおまかに2種類に分けられる.
1つは,もともとは英語自身が属している西ゲルマン語に由来する人名で,それがフランス語を経由して再び英語に戻ってきたとでもいうべき人名である.William, Robert, Richard, Gilbert, Alice, Eleanor, Rose/Rohais, Maud などが挙げられる.いずれもフランス語ぽい香りがするが,実はもとはゲルマン系の人名である.
もう1つは聖書に現われる人物や,人気のある聖人にちなむ名前で,Adam, Matthew, Bartholomew, James, Thomas, Andrew, Stephen, Nicholas, Peter/Piers, John; Joan, Anne, Margaret/Margery などが挙げられる.12世紀後半からは Mary が,14世紀からは Christopher なども入ってきている.
その他,アーサー王伝説の有名な登場人物の名前として Arthur, Guenevere, Launcelot や,ブルトン語からの Alan などもあったが,さほど目立たない.
現代でも世代によって人気のある名付けというのは異なるものだが,中英語期も同じで,はやりすたりがあったようである.
・ Coates, Richard. "Names." Chapter 6 of A History of the English Language. Ed. Richard Hogg and David Denison. Cambridge: CUP, 2006. 312--51.
2021-10-02 Sat
■ #4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript]
1731年10月23日,ウェストミンスターのアシュバーナム・ハウスが火事に見舞われた.そこに収納されていたコットン卿蔵書 (Cottonian Library) も焼けたが,辛くも焼失を免れた古写本のなかに古英語の叙事詩 Beowulf のテキストを収めた写本があった.これについて Watts (29) が次のように述べている.
The loss of Beowulf would have meant the loss of the greatest literary work and one of the most puzzling and enigmatic texts produced during the Anglo-Saxon period.
仮定法の文だが,裏を返せば英文学を代表する最も偉大な作品が奇跡的にも火事から救われたという趣旨の文である.英文学者や英語史学者ならずとも,ほとんどの人々が,この写本が消失を免れて本当によかったと思うだろう.
しかし,「言語の神話」の解体をもくろむ Watts の考えは異なる.焼失したほうがよかったと主張するわけでは決してないが,驚くことに次のように文章を続けるのだ.
But it would also have made one of the most powerful linguistic myths focusing on the English language, the myth of the longevity of English, immeasurably more difficult to construct. This is not because other Anglo-Saxon texts have not come down to us; it is, rather, because of the perceived literary and linguistic value of Beowulf. To construct the longevity myth one needs to locate such texts, and the further back in time they can be located, the "older" the language becomes and the greater is the "cultural" significance that can be associated with that language.
Watts の主張は,焼失を免れた Beowulf 写本は,英語に関する最も強力な神話,すなわち「英語長寿神話」を創出し,確立させるのに利用されてきたということだ.Beowulf 写本が生き残ったことにより「英語は歴史のある偉大な言語である」と言いやすくなったというわけだ.
現に Beowulf 写本が生き残ったのは偶然である.別の棚に保存されていたら焼失していたかもしれない.そして,もし焼けてしまっていたならば,英文学や英語はさほど歴史がないことになり,さほど偉大でもなくなるだろう.英文学や英語は別の「売り」を探さなければならなかったに違いない.
この見方は,英文学や英語が偉大かそうでないかは火事の及んだ範囲という偶然に依存しており,必然的に,あるいは本質的に偉大なわけではないという洞察につながる.これが,Watts が神話の解体によって行なおうとしていることなのだろう.
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2021-10-01 Fri
■ #4540. 概念メタファー「言語は人間である」 [conceptual_metaphor][language_myth][link]
「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1]) で見たとおり,「言語は○○である」の○○には様々なものが入る.言語を生き物に喩えるのは日常茶飯だが,生き物のなかでもとりわけ人間に喩えるという発想,つまり「言語は人間である」という概念メタファー (conceptual_metaphor) は意外と見過ごされてきたかもしれない.Watts (13--14) より "A LANGUAGE IS A HUMAN BEING" を体現する表現をいくつか拾ってみよう.
- <A language is born>
- <A language dies>
- <A language grows old>
- <A language is mature>
- <A language at time point x is the same language as at time point y>
- <A language has a character>
- <A language is a potential actor> (i.e. has the ability to initiate and carry out actions)
- <A language is corrupt>
- <A language is noble>
- <A language is perfect>
- <A language is homogeneous>
- <A language is polite>
- <A language is hesitant>
- <A language is bold>
- <A language is great>
- <A language is healthy>
- <A language is sick/ill>
- <A language is fit>
- <A language is ailing>
- <A language is dying>
- <A language is weak>
- <A language recovering/reviving>
この一覧には,character (性格)に関する表現がいくつか含まれている.言語を一般的に生き物に喩えるのではなく,とりわけ人間に喩えるポイントは「性格づけ」にありそうだ.人間一人ひとりに性格があるのと同様に,各言語にも特有の性格があるという点に引っかけた比喩ということだ.
様々な概念メタファーを通じて言語の性質,あるいは言語のとらえ方のパターンを見いだしていくのは,なかなかおもしろそうである.関連する過去の記事として,以下を挙げておきたい.
・ 「#1578. 言語は何に喩えられてきたか」 ([2013-08-22-1])
・ 「#1579. 「言語は植物である」の比喩」 ([2013-08-23-1])
・ 「#1722. Pisani 曰く「言語は大河である」」 ([2014-01-13-1])
・ 「#2631. Curzan 曰く「言語は川であり,規範主義は堤防である」」 ([2016-07-10-1])
・ 「#2743. 貨幣と言語」 ([2016-10-30-1])
・ 「#3771. Wittgenstein の「言語ゲーム」 (1)」 ([2019-08-24-1])
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2026 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
最終更新時間: 2026-02-27 09:32
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow