2025-05-07 Wed
■ #5854. 「hellog-radio」全62回の YouTube 版シリーズ再配信が完結しました [hellog-radio][radio_broadcast][sobokunagimon][youtube][notice][link]

コロナ禍の始まった2020年の6月から翌2021年の2月にかけて不定期に,英語史の話題,とりわけ一級の「英語に関する素朴な疑問」を取り上げる音声配信シリーズ「hellog-radio」をお届けしていました.全62回のシリーズです.当時は大学のオンライン授業の補足資料というつもりで,こちらの音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)の下部のリンク集のとおり,HPに音声ファイル (MP3) を置いておくだけの内輪向けシリーズでした.
その後,hellog-radio シリーズがきっかけとなり,Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を始めたという経緯があり,後から振り返ると hellog-radio はいわば heldio の前身という位置づけのような存在になりました.このまま hellog-radio を眠らせておくのはもったいないと思い,「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) や「#5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介」 ([2025-04-16-1]) でも触れたとおり,今年の3月6日より YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」で再配信を始めました.
1日1回を公開していき,昨日をもって全62回の再配信が完結しました.2ヶ月余,日々お付き合いいただいた方々に感謝を申し上げます.hellog-radio の YouTube版再配信の再生リストは「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」として公開していますので,折に触れて本シリーズを聴き直していただければと思います.以下,全62回のタイトル一覧とリンクも示しておきます.
1. なぜ大文字と小文字があるのですか?
2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?
3. なぜ q の後には必ず u がくるのですか?
4. なぜ現在完了形は過去を表わす副詞と共起できないのですか?
5. なぜ put は put--put--put と無変化活用なのですか?
6. なぜ go の過去形は went になるのですか?
7. なぜ英語は左から右に書くのですか?
8. 現存する最古の英文は何か?
9. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのですか?
10. なぜ hour の h は発音されないのですか?
11. なぜ careless の反対は *caremore ではなく careful なのですか?
12. なぜ「the 比較級,the 比較級」で「?すればするほど?」の意味になるのですか?
13. once や twice の -ce とは何ですか?
14. なぜ she の所有格と目的格は her で同じ形になるのですか?
15. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか?
16. なぜ英語では「兄」も「弟」も brother と同じ語になるのですか?
17. なぜ定冠詞 the は母音の前では the apple のように「ズィ」と発音するのですか?
18. なぜ数詞 one は「ワン」と発音するのですか?
19. なぜ数詞 two は「トゥー」と発音するのですか?
20. guest と host は,なんと同語源
21. なぜ often は「オフトゥン」と発音されることがあるのですか?
22. なぜ will の否定形は won't になるのですか?
23. なぜ w の文字は v が2つなのに "double-u" なのですか?
24. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか?
25. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか?
26. なぜ know の綴字には発音されない k があるのですか?
27. なぜ英語では l と r が区別されるのですか?
28. なぜ英語では v と b が区別されるのですか?
29. なぜ you は「あなた」でもあり「あなたがた」でもあるのですか?
30. なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?
31. なぜ child の複数形は children なのですか?
32. なぜ number の省略表記は no. となるのですか?
33. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか?
34. 形容詞 able と接尾辞 -able は別語源だった!
35. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか?
36. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか?
37. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?
38. なぜ as にはあんなに多くの用法があるのですか?
39. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか?
40. なぜ input は *imput と綴らないのですか?
41. なぜ形容詞 friendly には副詞語尾のはずの -ly が付いているのですか?
42. <x> の不思議あれこれ
43. なぜ同じ <oo> の綴字なのに book と food では母音が異なるのですか?
44. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか?
45. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか?
46. なぜ比較級には -er をつけるものと more をつけるものとがあるのですか?
47. なぜ3単現なのに *He cans swim. とはならず He can swim. となるのですか?
48. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか?
49. タコの「足」は英語で何といいますか?
50. なぜ three と thirteen では r の位置が異なるのですか?
51. 英語の人名 Johnson, Jackson, Dickson などに現われる -son とは何ですか?
52. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?
53. harassment の強勢はどこに置きますか?
54. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか?
55. なぜアメリカでは英語が主たる言語として話されているのですか?
56. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか?
57. 世界に言語はいくつあるのですか?
58. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか?
59. なぜ英語は世界語となっているのですか?
60. many years ago などの過去の時間表現に用いられる ago とは何ですか?
61. なぜ island の綴字には s が入っているのですか?
62. なぜ foot の複数形は feet なのですか?
また,本再配信シリーズには YouTube 版のほか Spotify (Video) Podcast 版や stand.fm 版もありますので,お好きなプラットフォームでお聴きください.
hellog-radio の再配信シリーズはこれにて完結ですが,別途 hellog の再配信シリーズは日々継続中です.その再生リストは「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」となります.引き続きご聴取ください.
2025-04-16 Wed
■ #5833. YouTube で「英語史をお茶の間に」 --- 3つの再生リストをご紹介 [youtube][heltube][inohota][helkatsu][voicy][heldio][hellog-radio][heltalk][sobokunagimon][notice]
新年度,英語史の学びを始める/続ける方も多いと思います.私は「英語史をお茶の間に」をモットーに様々な媒体で,英語史の情報をお伝えしています.英語史の学びを促す活動を「hel活」 (helkatsu) と呼んでいますが,最近もっとも伸びているhel活の媒体が YouTube です.
2つの YouTube チャンネルを運営しており,各々の内部でいくつかの再生リストが用意されています.煩雑にならないよう,ここでは3つの厳選お薦め再生リストを示したいと思います.
1. 「【再配信】 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の再生リスト
毎朝6時頃に配信.4年弱続いている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を,YouTube で再放送しているものです.3年ほど遅れて,初回から1つずつ配信を重ねています.ここ数ヶ月ほど,視聴回数がぐんぐん伸びています.ちなみに今朝の配信回は「#270. cheap の語源」です.
2. 「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」の再生リスト
同じく毎朝6時頃に配信.上記 Voicy heldio の前身として2020年度に不定期で音声配信してきた hellog-radio の全62回を,目下毎日1回ずつ再放送しています.ちなみに,今朝の配信回は「#42. <x> の不思議あれこれ」です.参考までに「#5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています」 ([2025-03-20-1]) もお読みください.
3. 「いのほた言語学チャンネル」・堀田回の再生リスト
同僚の英語学研究者,井上逸兵先生と毎週水・日の午後6時に配信している「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)より,堀田がメインで英語史について語っている回を集めた再生リストです.ちなみに,最新の配信回は「#325. English ということばをここまで掘り下げました」です(5000回以上視聴されています).
いずれのチャンネルも視聴回数が伸びています.ぜひチャンネル登録の上,定期的にご覧になり,英語史の学びに活かしていただければ.
2025-03-20 Thu
■ #5806. heldio の前身「hellog-radio」で一軍級の素朴な疑問を取り上げています [sobokunagimon][helkatsu][hellog-radio][heldio][heltalk][heltube]
本ブログの姉妹版・音声版として,毎朝6時に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を配信しています.heldio は2021年6月2日に開始したチャンネルですが,実はその前身として「hellog-radio」という個人的な音声シリーズを前年の2020年6月23日より不定期で公開していました.その一覧はこちらのページの下部からご覧になれます.ただし,当時は特別な音声配信プラットフォームを利用しておらず,HP上に音声ファイルを直置きしていただけなので,聴かれる機会は多くありませんでした.
「hellog-radio」は62件の英語史小ネタからなる音声配信のシリーズで,選りすぐりの一軍級の「英語に関する素朴な疑問」が集まっています.そのまま寝かせておいてはもったいないと思い,2週間前の3月6日から毎朝6時前後に1つずつ,再放送の体で公開し始めています.いくつかのプラットフォームよりアクセス可能ですので,お好きなところからどうぞ.
・ YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」の再生リスト「【再配信】 hellog-radio --- 英語史小ネタ」
・ stand.fm 「英語史つぶやきチャンネル (heltalk)」内で配信回タイトルに「hellog-radio」がついているもの
・ 上記の Spotify (Video) Podcast 版
「hellog-radio」再放送については,heldio の一昨日の回「#1388. heldio の前身「hellog-radio」なるものを YouTube で再放送しています」でもお話ししているので,ぜひお聴きください.この配信回のインフォグラフィックも掲載しておきます.

2022-04-07 Thu
■ #4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります [hel_education][hellog][hellog-radio][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]
慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.本日,今年度の同講義が開始となります.1年間をかけて英語の歴史を紐解いていく予定です.
本日の初回は,重要なイントロの回になりますが,本ブログの記事を組み合わせることで講義を展開していく予定です.情報量が多いので,講義で完全消化できなかった場合であっても,履修生の皆さんはいつでもこの記事に戻ってくることができます.また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,部分的・擬似的に初回授業を体験できるかと思います.目下,新年度ということで「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) として,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しているので,あえてこのような形態を取る次第です.
1. イントロ
1.1. 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]): 不定冠詞 a と an について.heldio の 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」もどうぞ.
1.2. 「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2]): 担当者の紹介
2. 英語史の世界へようこそ
2.1. 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]): 英語史の魅力4点
(1) 英語の見方が180度変わる!
(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!
(4) 現代英語に戻ってくる英語史
2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます
2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. 「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています)
3. 英語に関する素朴な疑問
3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます
3.2. 2685件の素朴な疑問
3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集
3.4. 知識共有サービス「Mond」で,英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています
4. 英語史を日常の話題に
4.1. 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]): 毎日欠かさず更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.
4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .毎日欠かさず1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.年度初めは英語史研究者との対談ものが多いです.
4.3. 「英語史スタートアップ」企画: 新年度開始に合わせて4月1日より始まっています
4.4. 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]): 世界初の英語史に関する新聞の第1号です
4.5. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]): ほぼ毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます
4.6. 「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]): 上記だけでは足りない,という方はこちらからどうぞ
4.7. 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1]): khelf ホームページと公式ツイッターアカウント @khelf_keio も開設されています
4.8. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 同専攻の井上逸兵先生と一緒に週2回(水・日)で放送しています
5. 英語史の読書案内
5.1. 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]): 今年度版を昨日公表しました
5.2. 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),および heldio での「対談 英語史の入門書」
6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答えるコーナー(時間があれば)
2022-03-28 Mon
■ #4718. 仮定法と直説法の were についてまとめ [be][preterite][subjunctive][hellog_entry_set][hellog-radio][heldio]
昨日,井上逸兵さんとの YouTube の第9弾が公開されました.I wish I were a bird. の were はあの were とは別もの!?--わーー笑【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル #9 】です.連動して,この hellog や heldio でも,わーわーしていますので,うるさいかもしれません(笑).
今回の YouTube (の後半)では,同じ were でも2つはちょっと違う,という話題を取り上げました.I wish I were a bird. や If I were you . . . という場合の「仮定法過去」の were と,普通の we were young のような場合の「直説法過去」の場合の were との違いについてです.この話題については,本ブログでもこちらの記事セットで取り上げてきましたし,音声メディアでも以下の2件で扱ってきました.
・ 「was と were --- 過去形を2つもつ唯一の動詞」(heldio: 2021年7月7日放送)
・ 「なぜ仮定法では If I WERE a bird のように WERE を使うのですか?」(hellog-radio: 2020年10月4日放送)
およそ,これで説明は尽きているといえば尽きているのですが,今回の YouTube の内容に合わせて,新たに Voicy としても「was と were の関係について整理しておきましょう」と題して話しました.
仮定法過去の were についてこのように英語史的に理解しておくと,むしろ昨今の口語で聞かれる I wish I was a bird. の was こそがおもしろくなってきます.英語学習者の99%の方々が was のほうが「レギュラー」ではないかと思うかもしれませんが,英語史研究者としては,おお,ついに were ではなく was になってきたのか,という面白い問題に見えます.仮定法は千年以上をかけて衰退してきたのですが,その衰退の過程がいよいよ最も大事な were/was にも及んできた,と見えるわけです.千年レベルの話しとして興奮しますネ.
2022-03-15 Tue
■ #4705. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第13回「なぜ one, two はこの綴字でこの発音なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][numeral][spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][hellog-radio]
この新年度も,1年間続いてきたNHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」での連載「英語のソボクな疑問」が継続されることになりました.読者の方々に毎月ご愛読いただいたおかげと感謝しております.ありがとうございました.ソボクな疑問を歴史的な観点からなるべくわかりやすく解説するというのが連載の趣旨です.引き続きご愛読のほど,よろしくお願いいたします.
昨日発売された4月号テキストに,連載の第13回が掲載されました.新年度に向けての一発目は「なぜ one, two はこの綴字でこの発音なの?」という綴字と発音の乖離に関する話題です.皆さん,すでに見慣れ,読み慣れている単語ですので不思議など感じないかと思いますが,普通であれば one で「ワン」,two で「トゥー」などとはひっくり返っても読めないはずです.なぜ素直に「オネ」や「トゥウォー」などとならないのでしょうか.そこには,あっと驚く歴史的な理由があったのです.
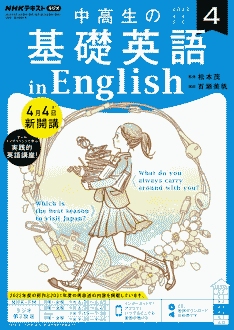
one, two に限らず,英語には発音と綴字がかみ合っていない単語がごまんとあります.実のところ基本的な単語であればあるほどチグハグなケースが多いので,初学者にとっては特にキツいのです.規則から入るのではなく,いきなり不規則から入るに等しいわけですから.
連載記事ではできる限り丁寧な説明を心がけました.同じ問題について本ブログや音声メディアでも取り上げたことがありますので,そちらも合わせて参照し,理解を深めていただければと思います.関連する記事セットよりどうぞ.音声メディアについては,以下より直接お聴きください.
2022-03-13 Sun
■ #4703. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) を整理しました [link][sobokunagimon][notice][hel_education][heldio][hellog-radio][heldio][youtube]
この1年9ヶ月ほどの間,本ブログの趣旨である「英語史に関する話題を広く長く提供し続ける」を音声メディアに載せる試みを続けてきました.
まず,2020年6月23日から2021年2月7日までは,不定期ではありましたが「hellog ラジオ版 (hellog-radio)」と題して,1つ10分程度の音声コンテンツを計62本,本サイトのなかで独自にアップロードしてきました.ちなみに初回は「#4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-06-23-1]) という話題でした(その他,hellog-radio の記事も参照).
その後,2021年6月2日より,音声コンテンツ配信用のプラットフォームとして Voicy に活動の場を移し,「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」と題するチャンネルにてコンテンツ配信を続けてきました.以後,本日に至るまで毎日10分程度の英語史の話題を配信してきました(計286本).
一貫して英語に関する素朴な疑問を中心とした内容にこだわってきましたが,上記のように途中からプラットフォームを変更したこともあり,音声コンテンツの在処が2カ所に分かれてしまっていました.これでは概観や検索に不便なので,このたび両プラットフォームからのコンテンツを一覧できるページを作りました.ブログ最上部のメニューにもありますが「音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)」をクリックしてみてください.最新のものから順にコンテンツが整理されています.
この一覧ページは今後もなるべく頻繁に更新していきたいと思っていますが,再生回数などは常に変化しており,毎日更新というわけにもいきませんので,最新コンテンツについては「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でご確認ください.
さて,年明けの1月2日に「#4633. 2021年によく聴かれた「英語の語源が身につくラジオ」の放送」 ([2022-01-02-1]) で再生回数のランキングを覗いてみましたが,それから3ヶ月ほど経っていますし,今回一覧を整理するに当たって新しいランキングが得られましたので,よく聴かれている上位50コンテンツを挙げたいと思います.時間のあるときにでも気軽にお聴きください.
ちなみにトップは昨年9月17日の同僚の井上逸兵さんとの対談でした.実はこの収録のときに,音声コンテンツの対談もよいですが,いずれ YouTube 動画も一緒にどうでしょうかね,などというやりとりがあり,先日2月26日に YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設してしまったという次第です.
- 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(1,004回再生,第108回,2021/09/17 放送)
- 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」(993回再生,第1回,2021/06/02 放送)
- 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」(820回再生,第2回,2021/06/03 放送)
- 「なぜ否定語が文頭に来ると VS 語順になるの?」(719回再生,第88回,2021/08/28 放送)
- 「「塵も積もれば山となる」に対応する英語の諺」(629回再生,第3回,2021/06/04 放送)
- 「なぜ used to do が「〜したものだった」なの?」(502回再生,第169回,2021/11/16 放送)
- 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(495回再生,第144回,2021/10/22 放送)
- 「なぜ月曜日 Monday はムーンデイではなくマンデイなの?」(480回再生,第6回,2021/06/07 放送)
- 「harassment のアクセントはどこに置けばいいの?」(470回再生,第4回,2021/06/05 放送)
- 「なぜ one と書いてオネではなくてワンなの?」(427回再生,第7回,2021/06/08 放送)
- 「対談 英語史の入門書」(418回再生,第140回,2021/10/18 放送)
- 「meat のかつての意味は「食物」一般だった!」(386回再生,第5回,2021/06/06 放送)
- 「one, only, any は同語源って知ってました?」(386回再生,第8回,2021/06/09 放送)
- 「forget, forgive の for- とは何?」(384回再生,第87回,2021/08/27 放送)
- 「対談 英語史 X 国際英語」(368回再生,第141回,2021/10/19 放送)
- 「first の -st は最上級だった!」(365回再生,第9回,2021/06/10 放送)
- 「現在完了は過去を表わす表現と共起したらNG?」(350回再生,第83回,2021/08/23 放送)
- 「Japanese の -ese って何?」(346回再生,第165回,2021/11/12 放送)
- 「this,that,theなどのthは何を意味するの?」(343回再生,第233回,2022/01/19 放送)
- 「立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」(324回再生,第173回,2021/11/20 放送)
- 「英語語彙の1/3はフランス語!」(322回再生,第26回,2021/06/27 放送)
- 「前置詞ならぬ後置詞の存在」(318回再生,第133回,2021/10/11 放送)
- 「時・条件の副詞節では未来でも現在形を用いる?」(316回再生,第33回,2021/07/04 放送)
- 「read - read - read のナゾ」(315回再生,第199回,2021/12/16 放送)
- 「third は three + th の変形なので準規則的」(310回再生,第10回,2021/06/11 放送)
- 「なぜアメリカ英語では R の発音があ〜るの?」(309回再生,第14回,2021/06/15 放送)
- 「なぜ名詞は REcord なのに動詞は reCORD なの?」(302回再生,第15回,2021/06/16 放送)
- 「スーパーマーケットとハイパーマーケット」(302回再生,第43回,2021/07/14 放送)
- 「It's kind of you to come. の of」(302回再生,第91回,2021/08/31 放送)
- 「sheep と deer の単複同形のナゾ」(301回再生,第12回,2021/06/13 放送)
- 「対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(300回再生,第149回,2021/10/27 放送)
- 「shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(300回再生,第218回,2022/01/04 放送)
- 「英語とギリシア語の関係って?」(299回再生,第137回,2021/10/15 放送)
- 「i, j の上の点は何?」(297回再生,第128回,2021/10/07 放送)
- 「-ly が付かない単純形副詞の用法と歴史」(292回再生,第127回,2021/10/05 放送)
- 「地球46億年の歴史における世界語としての英語」(292回再生,第134回,2021/10/12 放送)
- 「そもそも English という単語はナゾだらけ!」(290回再生,第16回,2021/06/17 放送)
- 「ウクライナ(語)について」(289回再生,第271回,2022/02/26 放送)
- 「a lot of の lot とは?」(287回再生,第100回,2021/09/09 放送)
- 「-ment, -ance など近代英語の名詞語尾の乱立」(286回再生,第170回,2021/11/17 放送)
- 「なぜ文頭や固有名詞は大文字で始めるの?」(285回再生,第50回,2021/07/21 放送)
- 「古英語期ってどんな時代?」(285回再生,第148回,2021/10/26 放送)
- 「なぜ will must のように助動詞を並べてはダメなの?」(284回再生,第152回,2021/10/30 放送)
- 「基本英単語100語の起源はほぼアングロサクソン」(282回再生,第106回,2021/09/15 放送)
- 「アメリカ英語の歴史と時代区分」(282回再生,第164回,2021/11/11 放送)
- 「星の star と星座の constellation」(281回再生,第168回,2021/11/15 放送)
- 「「対面授業」はレトロニムでした」(280回再生,第51回,2021/07/22 放送)
- 「なぜか second 「2番目の」は借用語!」(279回再生,第11回,2021/06/12 放送)
- 「重要な文法的単語には強音と弱音の2つの発音がある」(279回再生,第162回,2021/11/09 放送)
- 「接頭辞 dis- は否定なの,強調なの?」(278回再生,第225回,2022/01/11 放送)
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2021-10-17 Sun
■ #4556. 英語史の世界にようこそ [hel_education][notice][heldio][hellog-radio][sobokunagimon][link]
学期の始めなので,標題のような「英語史の学びのエンカレッジ系」の記事が多くなります.最近では「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]) も書いており,本ブログの記事などに関連するリンクを多々張っていますので,詳しくは是非そちらもご覧ください.今回は先の記事から重要な6点のみピックアップし,改めて英語史への入り口を案内します.
(1) 私(堀田隆一)の考える「英語史の魅力」はズバリこれ.
1. 英語の見方が180度変わる!
2. 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
3. 素朴な疑問こそがおもしろい!
4. 英語が本当によく分かるようになる!
(2) 上記の「素朴な疑問こそがおもしろい!」は本当です.「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) に挙げたような疑問が,英語史によりスルスルと解けていきます.それでも足りない方は「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) でどうでしょう!
(3) 本ブログ「hellog?英語史ブログ」は「英語史に関する話題を広く長く提供し続けるブログ」として2009年5月1日に立ち上げたものです.大学の英語史概説の講義に対する補助的な読み物を提供する趣旨で始めました.日々の記事の種類は多岐にわたり,英語を学び始めたばかりの中学生などを読者と想定した話題もあれば,大学院博士課程の学生を念頭においた学術的な話題もあります.書き手以外何を言っているか分からないという話題も少なくないと思います,失礼! それでも,ぜひ毎日タイトルだけでも目を通していれば,英語史のカバーする範囲の広さが分かってくると思います.毎日タイトルをお届けするツイッターアカウントもあります.
(4) 本ブログの姉妹版・音声版として「hellog ラジオ版 (hellog-radio)」(2020年6月23日?2021年2月7日に不定期で),および続編である「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(2021年6月2日より現在まで毎日定期的に)を配信しています.hellog に比べ,話題は「英語に関する素朴な疑問」におよそ特化しています.各放送は10分以内の短い英語史ネタです.ぜひこれを聞くことを日課にどうぞ! ちなみに本日の放送では,上記 (1) を熱く語っています.
(5) 明後日10月19日は「TOEIC の日」.つい先日 TOEIC 事業などを手がける IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビューを受けました.テーマは「英語はいかにして世界の共通語になったのか」という,英語(史)に関する究極の疑問の1つです.英語史超入門ともなっているこちらのインタビュー記事をどうぞ(cf. 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1])).
(6) 最後に私の選んだ「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) をご覧ください.英語史を学び始めるには,なんといっても本を読むのが一番です.
2021-06-04 Fri
■ #4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました [heldio][hellog-radio][sobokunagimon][notice][hel_education][voicy]
一昨日,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしました.本ブログとも部分的に連携しつつ,英語史に関するコンテンツを広くお届けする試みとして始めました.一昨日,昨日と,10分弱の音声コンテンツを2本配信していますので,そちらをご案内します.
1. 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」
2. 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」
チャンネル設立の趣旨は,Voicy 公式ページに掲載していますが,以下の通りです.
英語の歴史を研究しています,慶應義塾大学の堀田隆一(ほったりゅういち)です.このチャンネルでは,英語に関する素朴な疑問を入口として,リスナーの皆さんを広く深い英語史の世界に招待します.とりわけ語源の話題が満載です.
英語史と聞くと難しそう!と思うかもしれませんが,心配いりません.実は皆さんが英語に対して日常的に抱いているナゼに易しく答えてくれる頼もしい味方なのです.
なぜアルファベットは26文字なの? なぜ man の複数形は men なの? なぜ3単現の s なんてあるの? なぜ go の過去形は went なの? なぜ英語はこんなに世界中で使われているの?
英語の先生もネイティブスピーカーも辞書も教えてくれなかった数々の謎が,スルスルと解決していく快感を味わってください.ついでに,英語の豆知識を得るにとどまらず,言葉の新しい見方にも気づくことになると思います.
本チャンネルと同じような趣旨で,毎日「hellog?英語史ブログ」を更新しています.合わせてご覧ください.なおハッシュタグの #heldio は,"The History of the English Language Radio" にちなみます.
基本的には,これまで私が本ブログ,著書,雑誌記事,大学教育,公開講座などで一貫して行なってきた「英語史の魅力を伝える」という活動の延長です.メディア,オーディエンス,スタイルは変わるかもしれませんが,この方針は変わりません.
チャンネル設立の背景について,もう少し述べておきたいと思います.昨年度,大学などでオンライン初年度となったことと関連して,通常の文章によるブログ記事の配信に加えて,音声版記事を「hellog ラジオ版」として配信する試みを始めました.主として英語に関する素朴な疑問に答えるという趣旨で,学期中は定期的に,学期外はやや不定期ですが継続してきました.結果として,数分から10分程度の長さの音声コンテンツが62本蓄積されました.
学生などから様々なフィードバックをもらって分かったことは,発音に関するトピックは音声コンテンツのほうが伝わりやすいということです.当たり前といえば当たり前の話しですが,私はナルホドと深くうなずきました.私自身は英語の綴字と発音の関係に大きな関心を寄せており,音声の話題はよく取り上げるのですが,文章ブログでは発音を発音記号で表現しなければならず,実際に口で発音すればすぐに伝わるものが容易に伝わらないもどかしさを,どこかで感じていました.そのような折に,試しに音声コンテンツを作ってみたら,発音の話題と相性が良いという当たり前のことに改めて気づいた次第です.逆に音声メディアでは綴字については語りにくいという側面もあり,一長一短ではあるのですが,従来の文章ベースの本ブログと平行して,音声ベースのブログがあるとよいと考えました.
昨年度は手弁当で「hellog ラジオ版」を作ってきましたが,昨今ウェブ上で音声配信プラットフォームが充実してきているという流れを受け,収録・配信の便を念頭に Voicy を通じて配信することに致しました.
本「hellog?英語史ブログ」では,高度に専門的な話題から中学生も読める話題まで,日々気の向くままに様々なレベルで書いているのですが,音声コンテンツとなると「素朴な疑問」系の話題や単語の語源に関する話題が多くなるかと思います.今後具体的にどのような感じになっていくのかは私も分からないのですが,基本方針としては「英語史に関する話題を広く長く提供し続ける」趣旨で,本ブログの姉妹版のような位置づけとなっていけばよいなと思っています.通称/ハッシュタグを「#heldio」 (= "The History of the English Language Radio") としたのも,本ブログとの連携を念頭に置いた上での命名です.
今後とも,本「hellog?英語史ブログ」と合わせて,「英語の語源が身につくラジオ」のほうもよろしくお願い申し上げます.
2021-02-07 Sun
■ #4304. なぜ foot の複数形は feet なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][plural][number][i-mutation]
名詞の複数形は通常は -(e)s をつければよいだけですが,なかには不規則複数形といわれるものがあります.不規則複数形にも実は多種類あるのですが,1つのタイプとして foot --feet, goose -- geese, louse -- lice, man -- men, mouse -- mice, tooth -- teeth, woman -- women が挙げられます.語幹の母音が変異するタイプですね.英語史的にいえば,これらの複数形は同一の原理によるものとして説明できます.foot -- feet を例に,音変化の機微をご覧に入れましょう.音声解説をお聴きください.
/i/ という母音は,音声学的にいえば極端でどぎつい音です.周囲の音を自分自身の近くに引きつけ,しばしば自他ともに変質させてしまう強力なマグネットとして作用します.例えば,この効果による /ai/ → /eː/ はよくある音変化で,「やばい」 /yabai/ も口語ではしばしば「やべー」 /yabeː/ となりますね.英語でも,day はもともとは綴字が示す通りに /dai/ に近い発音でしたが,近代までに /deː/ へと変化しました.
これと似たようなことが,英語成立に先立つゲルマン語の時代に foot の当時の発音である /foːt/ に起こったのです.複数語尾である -iz が付加された /foːtiz/ は,どぎつい /i/ の音声的影響のもとに,やがて /feːtiz/ となりました.その後,強勢のおかれない語尾に位置する /z/ や,変化を引き起こした元凶である /i/ 自体が弱まって消失していき,最終的に /feːt/ に帰着したのです.この複数形態こそが,古英語の fēt であり,現代英語の feet なのです.
この話題については##157,2017の記事セットで本格的に扱っていますので,関心のある方は是非そちらもご覧ください.
2021-01-24 Sun
■ #4290. なぜ island の綴字には s が入っているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][etymological_respelling][etymology][spelling_pronunciation_gap][reanalysis][silent_letter][renaissance]
英語には,文字としては書かれるのに発音されない黙字 (silent_letter) の例が多数みられます.doubt の <b> や receipt の <p> など,枚挙にいとまがありません.そのなかには初級英語で現われる非常に重要な単語も入っています.例えば island です.<s> の文字が見えますが,発音としては実現されませんね.これは多くの英語学習者にとって不思議中の不思議なのではないでしょうか.
しかし,これも英語史の観点からみると,きれいに解決します.驚くべき事情があったのです.音声解説をどうぞ.
「島」を意味する古英語の単語は,もともと複合語 īegland でした.「水の(上の)陸地」ほどの意味です.中英語では,この複合語の第1要素の母音が少々変化して iland などとなりました.
一方,同じ中英語期に古フランス語で「島」を意味する ile が借用されてきました(cf. 現代フランス語 île).これは,ラテン語の insula を語源とする語です.古フランス語の ile と中英語 iland は形は似ていますが,まったくの別語源であることに注意してください.
しかし,確かに似ているので混同が生じました.中英語 iland が,古フランス語 ile に land を継ぎ足したものとして解釈されてしまったのです.
さて,16世紀の英国ルネサンス期になると,知識人の間にラテン語綴字への憧れが生じます.フランス語 ile を生み出したラテン語形は insula と s を含んでいましたので,英語の iland にもラテン語風味を加味するために s を挿入しようという動きが起こったのです.
現代の英語学習者にとっては迷惑なことに,当時の s を挿入しようという動きが勢力を得て,結局 island という綴字として定着してしまったのです.ルネサンス期の知識人も余計なことをしてくれました.しかし,それまで数百年の間,英語では s なしで実現されてきた発音の習慣自体は,変わるまでに至りませんでした.ということで,発音は古英語以来のオリジナルである s なしの発音で,今の今まで継続しているのですね.
このようなルネサンス期の知識人による余計な文字の挿入は,非常に多くの英単語に確認されます.語源的綴字 (etymological_respelling) と呼ばれる現象ですが,これについては##580,579,116,192,1187の記事セットもお読みください.
2021-01-17 Sun
■ #4283. many years ago などの過去の時間表現に用いられる ago とは何ですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][adjective][adverb][participle][reanalysis][be][perfect]
標題は皆さんの考えたこともない疑問かもしれません.ago とは「?前に」を表わす過去の時間表現に用いる副詞として当たり前のようにマスターしていると思いますが,いったいなぜその意味が出るのかと訊かれても,なかなか答えられないのではないでしょうか.そもそも ago の語源は何なのでしょうか.音声解説をお聴きください.
いかがでしたでしょうか.ago は,動詞 go に意味の薄い接頭辞 a- が付いただけの,きわめて簡単な単語なのです.歴史的には "XXX is/are agone." 「XXXの期間が過ぎ去った」が原型でした.be 動詞+過去分詞形 agone の形で現在完了を表わしていたのですね.やがて agone は語末子音を失い ago の形態に縮小していきます.その後,文の一部として副詞的に機能させるめに,be 動詞部分が省略されました.XXX (being) ago のような分詞構文として理解してもけっこうです.
この成り立ちを考えると,I began to learn English many years ago. は,言ってみれば I began to learn English --- many years (being) gone (by now). といった表現の仕方だということです.この話題について,もう少し詳しく知りたい方は「#3643. many years ago の ago とは何か?」 ([2019-04-18-1]) の記事をどうぞ.
2021-01-13 Wed
■ #4279. なぜ英語は世界語となっているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][linguistic_imperialism]
これは英語を外国語として学んでいるすべての学習者にとって本質的な疑問です.あまりに基本的すぎて話題にする機会がほとんどなく,何となく宙ぶらりんになっている問いだと思います.しかし,とても重要です.効果的な英語学習のためにも,英語教育を論じるためにも,すべてこの問いから始めなければなりません.
そもそも私たちはなぜ英語を学ぶことになっているのでしょうか.それは英語が世界語として有用だからですね.それでは,なぜ英語が世界語となっているのでしょうか.これは英語史を参照しなければ決して解決しない問いです.小中高の英語科でも社会科でも触れられない話題なのです.
とはいえ,答えは単純明快です.拍子抜けするほど簡単です.音声解説をお聴きください.
英語が他言語よりも優れた言語であるから,ではありません.そのようなことは決してありません.英語に内在する言語的な特徴(文法,語彙,発音など)によって,その言語が有力となるということは,人類言語史上,一度もありませんでした.古代地中海世界の古典ギリシア語,西洋中世のラテン語,中世イスラム世界のアラビア語,東アジア世界の中国語なども,その時代その地域の「世界語」といってよい影響力のある言語でしたが,いずれも言語的特徴によってではなく,その母語話者たち --- 古代ギリシア人,古代ローマ人,イスラム教徒,中国人たち --- が圧倒的な社会的権力をもっていたからにすぎません.
英語も同じです.英語が世界語となっているのは,近現代の世界史において,英語の話し手たち(具体的には18世紀以降のイギリス帝国の盟主たるイギリス人たちと,20世紀の覇権国家となったアメリカ合衆国のアメリカ人たち)が,圧倒的な政治力,経済力,軍事力,文化力,技術力をもって世界に甚大な影響を与えてきたからにすぎません.彼らの言語であるからこそ,英語は威信を獲得し,世界で広く学ばれる機会を得たのです.英語自体は優れた言語でも何でもないのです(もちろん,断じて劣った言語でもありません).
関連する話題と議論について,##1072,1082,1083,2487,2673,2935,3470の記事セットもお読みください.
2021-01-10 Sun
■ #4276. なぜ say の過去形,3単現形は「セイド」「セイズ」ではなく「セッド」「セズ」と発音されるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hellog_entry_set][diphthong][monophthong][vowel][phonetics][spelling][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][sound_change][assimilation]
動詞 say /seɪ/ は超高頻度の語で,初学者もすぐに覚えることになる基本語です.この動詞の過去形 said もきわめて高頻度なわけですが,綴字として不規則であるばかりか,実は発音においても不規則です.予想される2重母音をもつ /seɪd/ とはならず,短母音の /sɛd/ となるのです.同じような不規則性は3単現の -s を付けた形についてもいえます.綴字こそ says と規則的に見えますが,発音はやはり2重母音をもつ /seɪz/ とはならず,短母音の /sɛz/ となってしまいます.なぜ said, says はこのような発音なのでしょうか.これには歴史的な経緯があります.音声解説をどうぞ.
実は,英語母語話者の発音を調査してみますと,先にダメ出しはしたものの,予想される通りの2重母音をもつ発音 /seɪd/, /seɪz/ も行なわれているのです.ただ,あくまで非標準的でマイナーな発音としてですので,私たちとしては不規則ながらもやはり短母音をもつ /sɛd/, /sɛz/ を確実に習得しておくのが無難でしょう.
歴史的な音変化の経緯を要約すれば次のようになります.もともと動詞 say は,近代英語期の入り口までは,綴字が示す通り /saɪ/ でした.それに従って,過去形は /saɪ(ə)d/,3単現形は /saɪ(ə)z/ と規則的な発音を示していました.ところが,17世紀までに2重母音 /aɪ/ は長母音 /ɛː/ へと変化したのです.ちょうど日本語の「ヤバイ」が,ぞんざいな素早い発音で「ヤベー」となるのに似た,どの言語にもよく見られる音変化です.別の変化が起こらず,およそこの段階にとどまったまま現代に至っていたのであれば,めでたく規則的に say /seɪ/, said /seɪd/, says /seɪz/ となっていたでしょう(実のところ,後者2つもマイナーな発音としてあり得ることは上述しました).
ところが,過去形と3単現形については,その後もう1つ別の音変化が生じました.長母音 /ɛː/ が短化して短母音 /ɛ/ となったのです.こうして say /seɪ/ に対して不規則にみえる /sɛd/, /sɛz/ が生じてしまったのです.同じ音変化に巻き込まれた別の単語として,again や against を挙げておきましょう.短母音をもつ /əˈgɛn(st)/ が優勢ですが,2重母音をもつ /əˈgeɪn(st)/ も並行して聞かれるという状況になっています.
なぜ過去形と3単現形でのみ母音が短化したのかというのは,必ずしも解明されていない謎です.said ˈhe, says ˈshe のような用いられ方が多く,主語代名詞に対して相対的に動詞が弱く発音されるので短化したという説明が提案されていますが,これも1つの仮説にすぎません.
関連する話題と議論について,##541,543,2130の記事セットもお読みください.
2021-01-06 Wed
■ #4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][world_languages][statistics][demography][language_death][hellog_entry_set]
英語も1つの言語,日本語も1つの言語なので,合わせて2言語ですね.ほかにフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,中国語,韓国語など知っている言語名を挙げ,足し合わせていくと,はたして現代世界にはいくつの言語があることになるでしょうか.100個くらい? あるいは1,000個? もしかして10,000個? このような疑問は抱いたこともなく,見当がつかないという方も多いかもしれません.
実は専門の言語学においても,様々な理由により,正確な数を出すことはできません.論者によって相当な揺れがみられるのです.この辺りの事情も含めて,音声で解説していきましょう.以下をお聴きください.
言語学者が時間とお金をかけて世界中を調査し,頑張って言語を数えていけば,いずれは正確な数が出るのではないかと疑問に思うかもしれませんが,その答えは No です.いくら言語学者が頑張っても,正確な言語数を得ることは不可能です.というのは,これは言語の問題ではないからです.政治の問題なのです.世界の言語を数えるということは,いったいどのような行為なのか.この問いこそが重要なように思われます.
それでも数が知りたいというのが人情です.試しに Ethnologue (第23版,2020年)を参照してみますと,世界の言語の数は7,117とカウントされています.ただし,これとて1つの参考値にすぎませんのでご注意を.今回の素朴な疑問に対しては,私としては「数千個程度」と答えて逃げておきたいと思います.
言語を数えるという問題,およびそれに関連する話題として,##3009,270,1060,274,401,1949の記事セットも合わせてお読みください.
2021-01-03 Sun
■ #4269. なぜ digital transformation を略すと DX となるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][abbreviation][grammatology][prefix][word_game][x][information_theory][preposition][latin]
本年も引き続き,大学や企業など多くの組織で多かれ少なかれ「オンライン」が推奨されることになるかと思います.コロナ禍に1年ほど先立つ2018年12月に,すでに経済産業省が「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」 (PDF) を発表しており,この DX 路線が昨今の状況によりますます押し進められていくものと予想されます.
ですが,digital transformation の略が,なぜ *DT ではなく DX なのか,疑問に思いませんか? DX のほうが明らかに近未来的で格好よい見映えですが,この X はいったいどこから来ているのでしょうか.
実は,これは一種の言葉遊びであり文字遊びなのです.音声解説をお聴きください
trans- というのはラテン語の接頭辞で,英語における through や across に相当します.across に翻訳できるというところがポイントです.trans- → across → cross → 十字架 → X という,語源と字形に引っかけた一種の言葉遊びにより,接頭辞 trans- が X で表記されるようになったのです.実は DX = digital transformation というのはまだ生やさしいほうで,XMIT, X-ing, XREF, Xmas, Xian, XTAL などの略記もあります.それぞれ何の略記か分かるでしょうか.
このような X に関する言葉遊び,文字遊びの話題に関心をもった方は,ぜひ##4219,4189,4220の記事セットをご参照ください.X は実におもしろい文字です.
2020-12-30 Wed
■ #4265. なぜアメリカでは英語が主たる言語として話されているのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][sociolinguistics][history][ame][official_language][history][koine][dialect_levelling][sociolinguistics]
標題は,問うまでもないと思われるような疑問かもしれませんが,当たり前の事実こそ,その背景を探ることに意味がある,というケースは少なくありません.現在では,英語といえば英国よりも先に米国のことを思い浮かべる人が多いと思いますが,歴史的には米国は後発の英語国です.17世紀初頭にイギリスの植民地としてスタートした,英語を用いる地域としては歴史の浅い国です.
米国が著しい移民の国であることはよく知られています.アイルランドを含むイギリス諸島からの移民にとどまらず,17世紀後半からはドイツなどヨーロッパ諸国からの移民も多くやってきましたし,19世紀後半からはアジアやアフリカ,そして20世紀には世界中から人々が押し寄せました.世界中の異なる言語を話す人々が,アメリカンドリームを抱いて米国を目指したのです.
とすると,英語を筆頭としつつも複数の異なる言語が並び立ち,名実ともに多言語国家となる可能性もあったはずです.事実,米国では多言語使用は認められていますし行なわれてもいますが,現実的にいえば,英語が圧倒的に有力な唯一の言語であるといえるでしょう.これはなぜなのでしょうか.歴史的に考えてみましょう.
様々な言語の話者が次々と米国に移民としてやってきたことは確かですが,最初期に移民文化の下敷きを作ったのは,何といってもイングランド,スコットランド,アイルランドなどイギリス諸島出身の人々,つまり英語話者でした.最初に敷かれた英語インフラが,後々まで影響を及ぼしたということです.まず第一に,この事実が効いています.
もう1つ,西部開拓に代表されるパイオニア精神に裏付けられた移民たちの移動性・可動性 (mobility) も効いています.社会のなかで広く動く人々というのは,言語を含む文化を平準化する人々でもあります.そのような社会では,各々の土地に固有の言語や方言が発達しにくく,むしろ全体として平板化していきます.もともと多くのシェアをもっていた英語はそのような平板化のマグネットとして機能し,対する他の諸言語は拡散する機会を得られなかったのです.
さらにいえば,他の諸言語の存在感が薄められつつ英語一辺倒の社会へ収斂していく過程において,英語内部の方言差すら平板化していきました (dialect_levelling) .イギリス英語に比べてアメリカ英語に地域による方言差が少ないのも,移民社会という事情が関与しています.
この辺りは,歴史社会言語学的にたいへんおもしろい話題です.関心をもった方は,##2784,158,591の記事セットをご覧ください.
2020-12-27 Sun
■ #4262. なぜ have, has, had はこのような発音と綴字なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][gvs][sound_change][vowel][spelling_pronunciation_gap][pronunciation][spelling][have][conjugation][3sp][verb][consonant][phonetics]
動詞としても助動詞としても超高頻度語である have .超高頻度語であれば不規則なことが起こりやすいということは,皆さんもよく知っていることと思います.ですが,have の周辺にはあまりに不規則なことが多いですね.
まず,<have> と綴って /hæv/ と読むことからして妙です.gave /geɪv/, save /seɪv/, cave /keɪv/ と似たような綴字ですから */heɪv/ となりそうなものですが,そうはなりません.have の仲間で接頭辞 be- をつけただけの behave が予想通り /biˈheɪv/ となることを考えると,ますます不思議です.
次に,3単現形が *haves ではなく has となるのも妙です.さらに,過去(分詞)形が *haved ではなく had となるのも,同様に理解できません.なぜ普通に *haves や *haved となってくれないのでしょうか.では,この3つの疑問について,英語史の立場から答えてみましょう.音声解説をどうぞ.
そうです,実は中英語期には /hɑːvə/ など長い母音をもつ have の発音も普通にあったのです.これが続いていれば,大母音推移 (gvs) を経由して現代までに */heɪv/ となっていたはずです.しかし,あまりに頻度が高い語であるために,途中で短母音化してしまったというわけです.
同様に,3単現形や過去(分詞)形としても,中英語期には今ではダメな haves や haved も用いられていました.しかし,13世紀以降に語中の /v/ は消失する傾向を示し,とりわけ超高頻度語ということもあってこの傾向が顕著に表われ,結果として has や had になってしまったのです./v/ の消失は,head, lord, lady, lark, poor 等の語形にも関わっています(逆にいえば,これらの語には本来 /v/ が含まれていたわけです).
一見不規則にみえる形の背景には,高頻度語であること,そして音変化という過程が存在したのです.ちゃんと歴史的な理由があるわけですね.この問題に関心をもった方は,##4065,2200,1348の記事セットにて詳しい解説をお読みください.
2020-12-23 Wed
■ #4258. harassment の強勢はどこに置きますか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][stress][pronunciation][ame_bre]
今回の hellog ラジオ版は,いきなり皆さんに質問です.英単語 harass(ment) のアクセントはどこに置きますか? 第1音節の hárass(ment) でしょうか,あるいは第2音節の haráss(ment) でしょうか.答えは,音声解説をどうぞ.実はここに英語史の魅力が隠されています.
さあ,いかがでしたでしょうか.いずれの音節に強勢を置くかというのは,英米差という空間的な問題のようにも見え,それはそれで間違っていないのですが,一方で時間的な問題でもあるという興味深い側面があるのです.アメリカ英語では haráss(ment) が優勢で,イギリス英語では hárass(ment) が優勢であるという大きな傾向は確かに見られます.しかし,それよりもおもしろいのは,いずれの英語でも若年層で haráss(ment) の発音が顕著であることです.このことが示唆するのは,現世代から次世代にかけて,ますます haráss(ment) が増えていくのではないかということです.私たちは1つの言語変化をリアルタイムで目の当たりにしているのです.
英語史といっても,常に古英語から現代英語にかけての1500年というスケールで起こっている言語変化を話題にしているわけではありません.ここ数十年という短期間の変化も,立派な英語史の話題です.今回のような単語の強勢位置の揺れなど,いま観察できる variation というものは,まさに言語変化が起こっていることを示唆しているのです.こう考えると,英語史が生きた分野であるということが分かるかと思います.古い歴史を扱うだけが英語史ではないのです!
今回の話題を通じて単語の強勢位置の揺れに関心をもった方は,ぜひ##342,321,366,488の記事セットをご覧ください.
2020-12-20 Sun
■ #4255. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか? [hellog-radio][sobokunagimon][number][plural][3sp]
これは私も初学者のときに疑問に思っていたような気がします.中高生に英語を教えている関係者にきいてみますと,よく出される「あるある」疑問だということで,今回の話題に取り上げようと思った次第です.s は名詞だと複数マーカーなのに,動詞だとむしろ単数マーカー.これは一体どうなっているのか,という質問は無理もありません.答えとしては,通時的に英語をみる英語史の立場からいえば完全なる偶然です.音声解説をお聴きください.
古英語にさかのぼると,名詞の複数形の s の起源として -as という語尾があったことが分かります.確かに s と複数性は結びついていたようにも見えますが,あくまで名詞全体の1/3程度の「男性強変化名詞」に限定しての結びつきです.その他の2/3の名詞は,実は複数形で s など取らなかったのです.つまり「s = 名詞複数」の発想は,現代英語ほど強くはありませんでした.しかし,中英語以降に,この2/3を占めていた非 s 複数名詞が,次々に s 複数へと乗り換えていったのです.結果として,現在では99%の名詞が s 複数を作るに至り,「s = 名詞複数」の関係が定着しました.この s 複数の歴史的拡大にはいろいろな原因があり本格的に論じたいのもやまやまですが(←私の博士論文のテーマなのです!),半分くらいは歴史的偶然であるということで議論を止めておきたいと思います.
一方,動詞の3単現の s についてですが,古英語や中英語ではそもそも s という語尾は一般的でなく,むしろ似て非なる子音 th をもつ -eth などが普通でした.この th が近代英語期にかけて s に置き換えられていきました.両音が音声的に近いからマージしたということでは決してなく,あくまで「置き換え」です.この変化の原因についても諸説ありますが,いずれにせよ,もともと th だったものが歴史の過程で半ば偶然に s に置換されたのです.それが現在の3単現の s となります.
ということで,名詞の複数形語尾の s も,動詞の3単現在語尾の s も,たまたま現代では一致しているだけで,歴史的にみれば起源が異なりますし,各々の事情で変化してきた結果にすぎません.顔は似ているけれども実は血縁関係にはない,という「あるある」なのです.
しかし,まったくの偶然ではないかもしれないという別の見方もあり得ます.「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]) の記事をどうぞ.これはこれで,なかなか鋭い視点です.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow