2017-12-26 Tue
■ #3165. 英製羅語としての conspicuous と external [waseieigo][latin][borrowing][loan_word][derivation][etymology][suffix][adjective][emode][neologism][lexicology][word_formation][shakespeare]
標題と関連する話題は,「#1493. 和製英語ならぬ英製羅語」 ([2013-05-29-1]),「#1927. 英製仏語」 ([2014-08-06-1]),「#2979. Chibanian はラテン語?」 ([2017-06-23-1]) や,waseieigo の各記事で取り上げてきた.
Baugh and Cable (222) で,初期近代期に英語がラテン単語を取り込む際に施した適応 (adaptation) が論じられているが,次のような1文があった.
. . . the Latin ending -us in adjectives was changed to -ous (conspicu-us > conspicuous) or was replaced by -al as in external (L. externus).
これらの英単語は,ある意味では借用された語ともいえるが,ある意味では英語が自ら形成した語ともいえる.「英製羅語」と呼ぶのがふさわしい例ではないだろうか.
OED によれば,conspicuous は,ラテン語 conspicuus に基づき,英語側でやはりラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -ous を付すことによって新たに形成した語である.16世紀半ばに初出している.
1545 T. Raynald tr. E. Roesslin Byrth of Mankynde Hh vij These vaynes doo appeare more conspicuous and notable to the eyes.
実はこの接尾辞を基体(主としてラテン語由来だが,その他の言語の場合もある)に付加して自由に新たな形容詞を作るパターンはロマンス諸語に広く見られたもので,フランス語で -eus を付したものが,14--15世紀を中心として英語にも -ous の形で大量に入ってきた.つまり,まずもって仏製羅語というべきものが作られ,それが英語にも流れ込んできたというわけだ.例として,dangerous, orgulous, adventurous, courageous, grievous, hideous, joyous, riotous, melodious, pompous, rageous, advantageous, gelatinous などが挙げられる(OED の -ous, suffix より).
また,英語でもフランス語に習う形でこのパターンを積極的に利用し,自前で conspicuous のような英製羅語を作るようになってきた.同種の例として,guilous, noyous, beauteous, slumberous, timeous, tyrannous, blusterous, burdenous, murderous, poisonous, thunderous, adiaphorous, leguminous, delirious, felicitous, complicitous, glamorous, pulchritudinous, serendipitous などがある(OED の -ous, suffix より).
標題のもう1つの単語 external も conspicuous とよく似たパターンを示す.この単語は,ラテン語 externus に基づき,英語側でラテン語由来の形容詞を作る接尾辞 -al を付すことによって形成した英製羅語である.初出は Shakespeare.
a1616 Shakespeare Henry VI, Pt. 1 (1623) v. vii. 3 Her vertues graced with externall gifts.
a1616 Shakespeare Antony & Cleopatra (1623) v. ii. 340 If they had swallow'd poyson, 'twould appeare By externall swelling.
反意語の internal も同様の事情かと思いきや,こちらは一応のところ post-classical Latin として internalis が確認されるという.しかし,この語のラテン語としての使用も "14th cent. in a British source" ということなので,やはり英製の匂いはぷんぷんする.英語での初例は,15世紀の Polychronicon.
?a1475 (?a1425) tr. R. Higden Polychron. (Harl. 2261) (1865) I. 53 The begynnenge of the grete see is..at the pyllers of Hercules..; after that hit is diffusede in to sees internalle [a1387 J. Trevisa tr. þe ynnere sees; L. maria interna].
「○製△語」は決して珍しくない.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2017-05-27 Sat
■ #2952. Shakespeare も使った超強調の副詞 too too [reduplication][intensifier][adverb][preposition][iconicity][shakespeare]
「あまりに」を意味する強調の副詞 too を重複 (reduplication) させ,強調の度合いをさらに強めた too too なる副詞がある.too 自身が前置詞・副詞 to の音韻形態的・意味的な強形というべき語であり,それを重ねた too too においては,強調まさに極まれり,といったところだろうか.Shakespeare でも O that this too too sallied flesh would melt. (Hamlet 1. 2. 129) として用いられており,現在でも口語で She is too-too kind. などと用いられる.
OED によると,かつては1語で toto, totoo, tootoo などと綴られたこともあったというが,形容詞や副詞の程度を強める副詞としての初出はそれほど古くなく,初期近代の1542年からの例が挙げられている(ただし,動詞を強める副詞としては a1529 に初出あり).
1542 N. Udall tr. Erasmus Apophthegmes f. 271, It was toto ferre oddes yt a Syrian born should in Roome ouer come a Romain.
この表現の発生の動機づけは,長々と説明する必要もないだろう.重複とは繰り返しであり,繰り返しは意味的強調に通じる.重複と強調は,iconicity (図像性)の点で,きわめて自然で密接な関係を示す.とりわけ感情のこもりやすい口語においては,言語現象として日常茶飯事といえる(関連して「#65. 英語における reduplication」 ([2009-07-02-1]) を参照).
なお,上にも述べたように強調の副詞 too 自体が,前置詞・副詞 tō の強形である.古英語では to は単独で「その上,さらに」の意の副詞として用いることもでき,形容詞などと共起すると「あまりに?」の副詞の意味を表わすことができた.主として,母音部を弱く短く発音すれば前置詞に,強く長く発音すれば強調の副詞として機能したのである.役割の分化にもかかわらず,綴字上は同じ to で綴られ続けたが,16世紀頃から強調の副詞のほうは too と綴られるようになり,独立した.
起源を一にする語の強形と弱形が独立して別の語と認識されるようになる過程は,英語史でも少なからず生じている.「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]),「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]),「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1]) を参照.
2017-05-22 Mon
■ #2947. A's X is better than B という構造 [genitive][syntax][shakespeare][variation]
A's X という表現の後で,B's X を意味するものとして,X が省略された B's という表現を用いるケースは近現代にも見られる.例えば,A's X and B's や A's X is better than B's のような構造だ.しかし,このような場合に,2つ目の要素 B に所有格の 's すらつけず,単に B とだけ述べる表現も,近代までは普通に見られた.例えば,A's X and B や A's X is better than B のような構造だ.これでは論理的に X と B を比べていることになり,おかしな構造といえばそうなのだが,現実には中英語から近代英語まで広く行なわれていた.
Jespersen (302) は中英語からの例として以下を挙げている.
・ His top was dokked lyk a preest biforn (like that of a p.) [Ch., A., 589]
・ Hys necke he made lyke no man. [Guy of Warw., 8054]
この構造は近代にも続くが,特に Shakespeare で多用されているという報告がある.Jespersen (302--03) が多くの例とともにこの見解を紹介しているので,引用しよう.
Al. Schmidt has collected a good many examples of this phenomenon from Shakespeare. He considers it, however, as a rhetorical figure rather than a point of grammar; thus he writes (Sh. Lex., p. 1423): "Shakespeare very frequently uses the name of a person or thing itself for a single particular quality or point of view to be considered, in a manner which has seduced great part of his editors into needless conjectures and emendations". I pick out some of his quotations, and add a few more from my own collections:---
・ Her lays were tuned like the lark (like the lays of the lark) [Pilgr., 198]
・ He makes a July's day short as December (as a December's day) [W. T., i., 2, 169]
・ Iniquity's throat cut like a calf [2 H. VI., iv., 2, 29]
・ Mine hair be fixed on end as one distract [2 H. VI., iii., 2, 318]
・ I know the sound of Marcius' tongue from every meaner man [Cor., i., 6, 27]
・ My throat of war be turned into a pipe small as an eunuch [ibid., iii., 2, 114]
歴史的には,上記の A's X is better than B の構造と並んで,現代風の A's X is better than B's もありえたので,両構造は統語的変異形だったことになる.問題は,上の引用でも触れられている通り,この変異が Shakespeare などにおいて自由変異だったのか,あるいは修辞的な差異を伴っていたのかである.もし 's という小さな形態素の有無が文法と文体の接触点となりうるのであれば,文献学上のエキサイティングな話題となるだろう.
・ Jespersen, Otto. Progress in Language with Special Reference to English. 1894. London and New York: Routledge, 2007.
2016-08-14 Sun
■ #2666. 初期近代英語の不安定な句読法 [punctuation][emode][printing][manuscript][shakespeare][writing][orthography][standardisation][apostrophe][hyphen]
15世紀後半に印刷術 (printing) がもたらされた後,続く16世紀の間に標準的な正書法への模索が始まったが,その際の懸案事項は綴字にとどまらず句読法 (punctuation) にも及ぶことになった.
先立つ中世の手書き写本の時代には,各種の句読記号が,統語意味的な目的というよりは音読のためのガイドとして様々に用いられていた.多くは印刷の時代以降に消えてしまったが,その数は30種類を超えた.現在使われているのと同形の句読記号もあったが,中世の写本ではその機能は必ずしも現代のものと同じではなかった.この中世の奔放な状況が,印刷時代の到来を経て徐々に整理へと向かい出したが,その過程は緩慢としており,初期近代英語期中にもいまだ安定を示さなかった.
初期の印刷業者は基本的には写本にあった句読記号を再現しようとしたが,対応する活字がないものもあり,選択を迫られることも多かった.一般的には,</> (virgule) や <.> (point) は広く認められた(</> の機能は現在の <,> (comma) に相当し,1520年代から現在のような <,> に置き換えられるようになったが,印刷業者によっては両者ともに用いるものもあった).
初期の印刷では,ほかに <:> (colon), <¶> (paragraph mark), <//> (double virgule) なども用いられ,新しい句読記号としては <( )> (parentheses), <;> (semicolon), <?> (question mark) なども導入されたが,定着には時間を要した.例えば,<;> などは,Coverdales による1538年の新約聖書の献題に現われこそするが,イングランドで用いられるようになるのは1570年代以降といってよい.
17世紀に入っても,いまだ句読法の不安定は続いた.例えば,Shakespeare の First Folio (1623) でも,疑問符と感嘆符,コロンとセミコロンの使い分けは一貫していなかったし,アポストロフィ (apostrophe) やハイフン (hyphen) も予期しないところに現われた (ex. advan'st (= advanced), cast-him (= cast him)) .この不安定さは現代の Shakespeare の校訂にも反映しており,異なる版が異なる句読点を採用するという事態になっている.
アポストロフィについて一言加えておこう.この句読記号は近代の新機軸であり,省略を示すために用いられ出したのは1559年からである.なお,現在のアポストロフィの用法として所有格を表わす <'s> での使用があるが,この発達はずっと遅れて18世紀のことである.
このように,現代では正書法の一環として用法が定まっている種々の句読記号も,初期近代英語ではいまだ定着していなかった.このことは,印刷術導入の衝撃がいかに革命的だったか,印刷業者が新時代に適応するのにいかに試行錯誤したのかを示す1つの指標とみなすことができるのではないか.以上,Crystal (261) を参照して執筆した.
関連して,「#574. punctuation の4つの機能」 ([2010-11-22-1]),「#575. 現代的な punctuation の歴史は500年ほど」 ([2010-11-23-1]),「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) も参照されたい.
・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.
2016-01-01 Fri
■ #2440. flower と flour (2) [doublet][spelling][shakespeare][johnson][orthography][standardisation]
年が明けました.2016年も hellog を続けます.新年の一発目は,以前にも「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]) で取り上げた話題でお届けします.
この2つの単語は,先の記事で説明したように,もともと1つの語のなかの2つの異なる語義だった.しかし,おそらく語義が離れすぎてしまったために,多義語としてではなく同音異義語として認識されるようになり,少なくとも綴字上は区別するのがふさわしいと感じられるようになったのだろう,近代英語期には綴り分ける傾向が生じていた.
さて,この語が「花」の意味でフランス語から借用されたのは13世紀初頭のことである.MED の flour (n.(1)) によれば,"c1230(?a1200) *Ancr. (Corp-C 402) 92a: & te treou .. bringeð forð misliche flures .. uertuz beoð .. swote i godes nease, smeallinde flures." が初例である.一方,関連する「小麦粉(=粉のなかの最も上等の「華」)」の意味でも13世紀半ばには英語で初例が現われている.MED の flour (n.(2)) によれば," a1325(c1250) Gen. & Ex. (Corp-C 444) 1013: Kalues fleis and flures bred..hem ðo sondes bed." が初例となっている.見出し語の綴字や例文の綴字を見ればわかるように,当初はいずれの語義においても <flour> や <flur> が普通だった.
その後,近代英語では両語義の関係が不明瞭となり,「花」が「小麦粉」から分化して,中英語以来のマイナーな異綴字であった <flower> を採用するようになった.綴字上の棲み分けは意外と遅く18世紀頃のことだったが,その後も19世紀までは「小麦粉」が <flower> と綴られるなどの混用がみられた.綴り分けるか否かは,個人によっても異なっていたようで,Shakespeare や Cruden の Concordance to the Bible (1738) では現在のような区別が付けられていたが,Johnson の辞書では,いまだ flower という1つの見出しのもとに両語義が収められている.OED の flour, n. の語源欄でも "Johnson 1755 does not separate the words, nor does he recognize the spelling flour." と述べられているが,Horobin (150) が指摘しているように Johnson の辞書の biscotin の定義のなかでは "A confection made of flour, sugar, marmalade, eggs. Etc." のように <flour> が使用されている.綴り分けが定着するには,ある程度の時間がかかったということだろう.標準綴字の定着,正書法の確立は,かくも心許なく緩慢な過程である.
・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.
2015-10-16 Fri
■ #2363. hapax legomenon [hapax_legomenon][terminology][lexicology][lexicography][word_formation][productivity][bible][zipfs_law][frequency][corpus][shakespeare][chaucer]
昨日の記事「#2362. haplology」 ([2015-10-15-1]) でギリシア語の haplo- (one, single) に触れたが,この語根に関連してもう1つ文献学や辞書学の用語としてしばしば出会う hapax (legomenon) を取り上げよう.ある資料のなかで(タイプ数えではなくトークン数えで)1度しか用いられていない語(句)を指す.ギリシア語の hapax (once) + legomenon (something said) からなる複合語だ.複数形は hapax legomena という.
"nonce word" を hapax legomenon と同義としている辞書もあるが,前者は「臨時語」と訳され「その時限りに用いる語」を指す.nonce-word は新語の臨時的な生産性を念頭に用いられることが多いのに対し,hapax legomenon は文献に現われる回数が1度であることに焦点が当てられているという違いが感じられる.nonce (その場限りの)という語の語源については,「#1306. for the nonce」 ([2012-11-23-1]) を参照.
hapax legomenon は,聖書の注釈との関連で,しばしば言及されてきた歴史がある.OED によると英語における初例は1692年のことで,"J. Dunton Young-students-libr. 242/1 There are many words but once used in Scripture, especially in such a sence, and are called the Apax legomena." とある.
文献学や語源学において,hapax legomenon はしばしば問題となる.その語の語源はおろか,意味すら不明であることが少なくない.語彙論や辞書学では,それを一人前の「語」として認めてよいのか,何かの間違いではないか,辞書に掲載すべきか否か,という頭の痛い問題がある (see 「#912. 語の定義がなぜ難しいか (3)」 ([2011-10-26-1])) .一方で,語形成やその生産性という観点からは,hapax legomenon は重要な考察対象となる.というのは,1度だけ臨時的に出現するためには,話者の生産的な語形成機構が前提とされなければならないからである (see 「#938. 語形成の生産性 (4)」 ([2011-11-21-1])) .
だが,実際のところ halax legomenon は決して少なくない.このことは,ジップの法則に照らせば驚くべきことではないだろう (see 「#1101. Zipf's law」 ([2012-05-02-1]), 「#1103. GSL による Zipf's law の検証」 ([2012-05-04-1])) .英語の例としては,Chaucer の用いたnortelrye (education) や Shakespeare の honorificabilitudinitatibus, また Dickens の sassigassity (audacity?) などが挙げられる.
2015-07-28 Tue
■ #2283. Shakespeare のラテン語借用語彙の残存率 [shakespeare][inkhorn_term][loan_word][lexicology][emode][renaissance][latin][greek]
初期近代英語期のラテン語やギリシア語からの語彙借用は,現代から振り返ってみると,ある種の実験だった.「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1]) で見た通り,16世紀に限っても13000語ほどが借用され,その半分以上の約7000語がラテン語からである.この時期の語彙借用については,以下の記事やインク壺語 (inkhorn_term) に関連するその他の記事でも再三取り上げてきた.
・ 「#478. 初期近代英語期に湯水のように借りられては捨てられたラテン語」 ([2010-08-18-1])
・ 「#1409. 生き残ったインク壺語,消えたインク壺語」 ([2013-03-06-1])
・ 「#114. 初期近代英語の借用語の起源と割合」 ([2009-08-19-1])
・ 「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1])
16世紀後半を代表する劇作家といえば Shakespeare だが,Shakespeare の語彙借用は,上記の初期近代英語期の語彙借用の全体的な事情に照らしてどのように位置づけられるだろうか.Crystal (63) は,Shakespeare において初出する語彙について,次のように述べている.
LEXICAL FIRSTS
・ There are many words first recorded in Shakespeare which have survived into Modern English. Some examples:
accommodation, assassination, barefaced, countless, courtship, dislocate, dwindle, eventful, fancy-free, lack-lustre, laughable, premeditated, submerged
・ There are also many words first recorded in Shakespeare which have not survived. About a third of all his Latinate neologisms fall into this category. Some examples:
abruption, appertainments, cadent, exsufflicate, persistive, protractive, questrist, soilure, tortive, ungenitured, unplausive, vastidity
特に上の引用の第2項が注目に値する.Shakespeare の初出ラテン借用語彙に関して,その3分の1が現代英語へ受け継がれなかったという事実が指摘されている.[2010-08-18-1]の記事で触れたように,この時期のラテン借用語彙の半分ほどしか後世に伝わらなかったということが一方で言われているので,対応する Shakespeare のラテン語借用語彙が3分の2の確率で残存したということであれば,Shakespeare は時代の平均値よりも高く現代語彙に貢献していることになる.
しかし,この Shakespeare に関する残存率の相対的な高さは,いったい何を意味するのだろうか.それは,Shakespeare の語彙選択眼について何かを示唆するものなのか.あるいは,時代の平均値との差は,誤差の範囲内なのだろうか.ここには語彙の数え方という方法論上の問題も関わってくるだろうし,作家別,作品別の統計値などと比較する必要もあるだろう.このような統計値は興味深いが,それが何を意味するか慎重に評価しなければならない.
・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 2nd ed. Cambridge: CUP, 2003.
2015-05-09 Sat
■ #2203. twentieth の綴字と発音 [suffix][numeral][shakespeare]
序数詞を作る接尾辞に -th がある.最初の3つの序数詞 first, second, third は「#67. 序数詞における補充法」 ([2009-07-04-1]) でみたように語尾が特殊であり,fifth, twelfth も「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) でみたように基数詞の語幹末子音が無声化している点で例外的にみえるが,その他は基本的には基数詞に -th をつければよい.fourth, tenth, hundredth, millionth のごとく規則的である.
しかし,規則のなかの不規則と呼びうるものに,twentieth から ninetieth までの8つの -ieth 語尾がある.twentieth でいえば,発音は */ˈtwentiθ/ ならぬ /ˈtwentiəθ/ であり,序数詞語尾の e が発音されるために,全体として3音節となることに注意したい.なぜ素直に twenty + th の綴字および発音にならないのだろうか.
古英語では,20, 30, 40 . . . の基数詞は twēntiġ, þrītiġ, fēowertiġ のように,半子音 ġ で終わっていた.これらの基数詞を序数詞にするには,つなぎ母音を頭にもつ接尾辞の異形態 -oða, -oðe を付加し,twēntiġoða, þrītiġoða, fēowertiġoða のようにした.基数詞においては,後にこの半子音は先行する母音 /i/ に吸収されて消失したが,序数詞においては,この半子音と接尾辞のつなぎ母音の連鎖が曖昧母音 /ə/ として生き残ったものと考えられる.つまり,twentieth のやや不規則な綴字と発音は,歴史的には,10の倍数を表わす基数詞が,語尾にある種の子音的な ġ を保持していたことに部分的に起因するといえる.
しかし,実際の歴史的発展は,古英語から現代英語にかけて上の説明にあるように直線的だったわけではないようだ.というのは,古英語でもつなぎ母音のない twentigþa のような綴字はあったし,中英語では twentiþe, twentythe などの素直な綴字も普通にみられたからだ (cf. MED twentīeth (num.)) .むしろ,現在の形態は,16世紀になってから顕著になってきた.例えば,Shakespeare では,Quarto 版では twentith,1st Folio 版では twentieth (MV 4.1.329, Ham 3.4.97) と綴られており,通時的変化を示唆している.おそらくは,時代によって,方言によって,つなぎ母音の有無はしばしば交替したと思われ,初期近代英語期における語形の標準化の流れのなかで,つなぎ母音のある形態が選択されたということなのではないか.
以下,参考までに OED による序数詞接尾辞 -th, suffix2 の解説を貼りつけておく.
Forming ordinal numbers; in modern literary English used with all simple numbers from fourth onward; representing Old English -þa, -þe, or -oða, -oðe, used with all ordinals except fífta, sixta, ellefta, twelfta, which had the ending -ta, -te; in Sc., north. English, and many midland dialects the latter, in form -t, is used with all simple numerals after third (fourt, fift, sixt, sevent, tent, hundert, etc.). In Kentish and Old Northumbrian those from seventh to tenth had formerly the ending -da, -de. All these variations, -th, -t, -d, represent an original Indo-European -tos (cf. Greek πέμπ-τος, Latin quin-tus), understood to be identical with one of the suffixes of the superlative degree. In Old English fífta, sixta, the original t was retained, being protected by the preceding consonant; the -þa and -da were due to the position of the stress accent, according to Verner's Law. The ordinals from twentieth to ninetieth have -eth, Old English -oða, -oðe. In compound numerals -th is added only to the last, as 1/1345, the one thousand three hundred and forty-fifth part; in his one-and-twentieth year.[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2015-03-08 Sun
■ #2141. 3単現の -th → -s の変化の概要 [verb][conjugation][emode][language_change][suffix][inflection][3sp][bible][shakespeare][schedule_of_language_change]
「#1857. 3単現の -th → -s の変化の原動力」 ([2014-05-28-1]) でみたように,17世紀中に3単現の屈折語尾が -th から -s へと置き換わっていった.今回は,その前の時代から進行していた置換の経緯を少し紹介しよう.
古英語後期より北部方言で行なわれていた3単現の -s を別にすれば,中英語の南部で -s が初めて現われたのは14世紀のロンドンのテキストにおいてである.しかし,当時はまだ稀だった.15世紀中に徐々に頻度を増したが,爆発的に増えたのは16--17世紀にかけてである.とりわけ口語を反映しているようなテキストにおいて,生起頻度が高まっていったようだ.-s は,およそ1600年までに標準となっていたと思われるが,16世紀のテキストには相当の揺れがみられるのも事実である.古い -th は母音を伴って -eth として音節を構成したが,-s は音節を構成しなかったため,両者は韻律上の目的で使い分けられた形跡がある (ex. that hateth thee and hates us all) .例えば,Shakespeare では散文ではほとんど -s が用いられているが,韻文では -th も生起する.とはいえ,両形の相対頻度は,韻律的要因や文体的要因以上に個人または作品の性格に依存することも多く,一概に論じることはできない.ただし,doth や hath など頻度の非常に高い語について,古形がしばらく優勢であり続け,-s 化が大幅に遅れたということは,全体的な特徴の1つとして銘記したい.
Lass (162--65) は,置換のスケジュールについて次のように要約している.
In the earlier sixteenth century {-s} was probably informal, and {-th} neutral and/or elevated; by the 1580s {-s} was most likely the spoken norm, with {-eth} a metrical variant.
宇賀治 (217--18) により作家や作品別に見てみると,The Authorised Version (1611) や Bacon の The New Atlantis (1627) には -s が見当たらないが,反対に Milton (1608--74) では doth と hath を別にすれば -th が見当たらない.Shakespeare では,Julius Caesar (1599) の分布に限ってみると,-s の生起比率が do と have ではそれぞれ 11.76%, 8.11% だが,それ以外の一般の動詞では 95.65% と圧倒している.
とりわけ16--17世紀の証拠に基づいた議論において注意すべきは,「#1856. 動詞の直説法現在形語尾 -eth は17世紀前半には -s と発音されていた」 ([2014-05-27-1]) で見たように,表記上 -th とあったとしても,それがすでに [s] と発音されていた可能性があるということである.
置換のスケジュールについては,「#1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s」 ([2014-05-26-1]) も参照されたい.
・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 3. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.
・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.
2014-11-09 Sun
■ #2022. 言語変化における個人の影響 [neolinguistics][geolinguistics][dialectology][idiolect][chaucer][shakespeare][bible][literature][neolinguistics][language_change][causation]
「#1069. フォスラー学派,新言語学派,柳田 --- 話者個人の心理を重んじる言語観」 ([2012-03-31-1]),「#2013. イタリア新言語学 (1)」 ([2014-10-31-1]),「#2014. イタリア新言語学 (2)」 ([2014-11-01-1]),「#2020. 新言語学派曰く,言語変化の源泉は "expressivity" である」 ([2014-11-07-1]) の記事で,連日イタリア新言語学を取り上げてきた.新言語学では,言語変化における個人の役割が前面に押し出される.新言語学派は各種の方言形とその分布に強い関心をもった一派でもあるが,ときに村単位で異なる方言形が用いられるという方言量の豊かさに驚嘆し,方言細分化の論理的な帰結である個人語 (idiolect) への関心に行き着いたものと思われる.言語変化の源泉を個人の表現力のなかに見いだそうとしたのは,彼らにとって必然であった.
しかし,英語史のように個別言語の歴史を大きくとらえる立場からは,言語変化における話者個人の影響力はそれほど大きくないということがいわれる.例えば,「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]) や「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]) の記事でみたように,従来 Chaucer の英語史上の役割が過大評価されてきたきらいがあることが指摘されている.文学史上の役割と言語史上の役割は,確かに別個に考えるべきだろう.
それでも,「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1]) や「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]) などの記事でみたように,ある特定の個人が,言語のある部門(ほとんどの場合は語彙)において限定的ながらも目に見える貢献をしたという事実は残る.多くの句や諺を残した Shakespeare をはじめ,文学史に残るような文人は英語に何らかの影響を残しているものである.
英語史の名著を書いた Bradley は,言語変化における個人の影響という点について,新言語学派的といえる態度をとっている.
It is a truth often overlooked, but not unimportant, that every addition to the resources of a language must in the first instance have been due to an act (though not necessarily a voluntary or conscious act) of some one person. A complete history of the Making of English would therefore include the names of the Makers, and would tell us what particular circumstances suggested the introduction of each new word or grammatical form, and of each new sense or construction of a word. (150)
Now there are two ways in which an author may contribute to the enrichment of the language in which he writes. He may do so directly by the introduction of new words or new applications of words, or indirectly by the effect of his popularity in giving to existing forms of expression a wider currency and a new value. (151)
Bradley は,このあと Wyclif, Chaucer, Spenser, Shakespeare, Milton などの名前を連ねて,具体例を挙げてゆく.
しかし,である.全体としてみれば,これらの個人の役割は限定的といわざるを得ないのではないかと,私は考えている.圧倒的に多くの場合,個人の役割はせいぜい上の引用でいうところの "indirectly" なものにとどまり,それとて英語という言語の歴史全体のなかで占める割合は大海の一滴にすぎない.ただし,特定の個人が一滴を占めるというのは実は驚くべきことであるから,その限りにおいてその個人の影響力を評価することは妥当だろう.言語変化における個人の影響は,マクロな視点からは過大評価しないように注意し,ミクロな視点からは過小評価しないように注意するというのが穏当な立場だろうか.
・ Bradley, Henry. The Making of English. New York: Dover, 2006. New York: Macmillan, 1904.
2014-08-22 Fri
■ #1943. Holofernes --- 語源的綴字の礼賛者 [shakespeare][etymological_respelling][mulcaster][spelling_pronunciation][silent_letter][orthography][popular_passage]
16世紀は,ラテン語に基づく語源的綴字 (etymological_respelling) が流行した時代である.その衒学的な風潮を皮肉って,Shakespeare は Love's Labour's Lost (1594--95) のなかで Holofernes なる学者を登場させている.Holofernes は,語源的綴字の礼賛者であり,綴字をラテン語風に改めるばかりか,その通りに発音すべしとすら吹聴する綴字発音 (spelling_pronunciation) の礼賛者でもある.Holofernes は助手 Nathanial との会話において,Don Armado の無学を非難しながら次のように述べる.
He draweth out the thred of his verbositie, finer then the staple of his argument. I abhore such phanaticall phantasims, such insociable and poynt deuise companions, such rackers of ortagriphie, as to speake dout sine b, when he should say doubt; det, when he shold pronounce debt; d e b t, not d e t: he clepeth a Calfe, Caufe: halfe, haufe: neighbour vocatur nebour; neigh abreuiated ne: this is abhominable, which he would call abbominable, it insinuateth me of infamie: ne intelligis domine, to make frantick lunatick? (Love's Labour's Lost, V.i.17--23 qtd. in Horobin, p. 113--14)
Shakespeare は当時の衒学者を皮肉るために Holofernes を登場させたが,実際に Holofernes の綴字発音擁護論は歴史的な皮肉ともなった.というのは,ここで触れられている doubt, debt, calf, half, neighbour, neigh, abhominable (PDE abbominable) のいずれにおいても,現代英語では問題の子音は発音されないからだ.しかし,これらの子音字は綴字としてはその後定着したのであり,Holofernes の望みの半分はかなえられた結果になる.
さて,Holofernes は綴字に合わせて発音を変える「綴字発音」を唱えたが,むしろ発音に合わせて綴字を変える「発音綴字」の方向もなかったわけではない.例えば,フランス語から借用した中英語の <delite> は,すでに綴字の定着していた <light>, <night> と同じ母音をもつために,類推により <delight> と綴りなおされた.これは,発音を重視し,語源を無視した綴字へ変えるという Holofernes の精神とは正反対の事例である.
冒頭で16世紀は語源的綴字の流行した時代と述べたが,実際には16世紀の綴字論者には,語源重視の Holofernes のような者もあれば,発音重視の者もあった.「#1940. 16世紀の綴字論者の系譜」 ([2014-08-19-1]) でみたように,当時の綴字論には様々な系譜がより合わさっていた.Shakespeare もこの問題に対する自らの立場を作品のなかで示唆しようとしたのではないか.
なお,Holofernes は当時の教育界の重鎮 Richard Mulcaster (1530?--1611) に擬せられるとする解釈があるが,Mulcaster 自身は語源的綴字の礼賛者ではなかったことを付け加えておく.
・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.
2014-05-30 Fri
■ #1859. 初期近代英語の3複現の -s (5) [verb][conjugation][emode][paradigm][analogy][3pp][shakespeare][nptr][causation]
今回は,これまでにも 3pp の各記事で何度か扱ってきた話題の続き.すでに論じてきたように,動詞の直説法における3複現の -s の起源については,言語外的な北部方言影響説と,言語内的な3単現の -s からの類推説とが対立している.言語内的な類推説を唱えた初期の論者として,Smith がいる.Smith は Shakespeare の First Folio を対象として,3複現の -s の例を約100個みつけた.Smith は,その分布を示しながら北部からの影響説を強く否定し,内的な要因のみで十分に説明できると論断した.その趣旨は論文の結論部よくまとまっている (375--76) .
I. That, as an historical explanation of the construction discussed, the recourse to the theory of Northumbrian borrowing is both insufficient and unnecessary.
II. That these s-predicates are nothing more than the ordinary third singulars of the present indicative, which, by preponderance of usage, have caused a partial displacement of the distinctively plural forms, the same operation of analogy finding abundant illustrations in the popular speech of to-day.
III. That, in Shakespeare's time, the number and corresponding influence of the third singulars were far greater than now, inasmuch as compound subjects could be followed by singular predicates.
IV. That other apparent anomalies of concord to be found in Shakespeare's syntax,---anomalies that elude the reach of any theory that postulates borrowing,---may also be adequately explained on the principle of the DOMINANT THIRD SINGULAR.
要するに,Smith は,当時にも現在にも見られる3単現の -s の共時的な偏在性・優位性に訴えかけ,それが3複現の領域へ侵入したことは自然であると説いている.
しかし,Smith の議論には問題が多い.第1に,Shakespeare のみをもって初期近代英語を代表させることはできないということ.第2に,北部影響説において NPTR (Northern Present Tense Rule; 「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) を参照) がもっている重要性に十分な注意を払わずに,同説を排除していること(ただし,NPTR に関連する言及自体は p. 366 の脚注にあり).第3に,Smith に限らないが,北部影響説と類推説とを完全に対立させており,両者をともに有効とする見解の可能性を排除していること.
第1と第2の問題点については,Smith が100年以上前の古い研究であることも関係している.このような問題点を指摘できるのは,その後研究が進んできた証拠ともいえる.しかし,第3の点については,今なお顧慮されていない.北部影響説と類推説にはそれぞれの強みと弱みがあるが,両者が融和できないという理由はないように思われる.
「#1852. 中英語の方言における直説法現在形動詞の語尾と NPTR」 ([2014-05-23-1]) の記事でみたように McIntosh の研究は NPTR の地理的波及を示唆するし,一方で Smith の指摘する共時的で言語内的な要因もそれとして説得力がある.いずれの要因がより強く作用しているかという効き目の強さの問題はあるだろうが,いずれかの説明のみが正しいと前提することはできないのではないか.私の立場としては,「#1584. 言語内的な要因と言語外的な要因はどちらが重要か? (3)」 ([2013-08-28-1]) で論じたように,3複現の -s の問題についても言語変化の "multiple causation" を前提としたい.
・ Smith, C. Alphonso. "Shakespeare's Present Indicative S-Endings with Plural Subjects: A Study in the Grammar of the First Folio." Publications of the Modern Language Association 11 (1896): 363--76.
・ McIntosh, Angus. "Present Indicative Plural Forms in the Later Middle English of the North Midlands." Middle English Studies Presented to Norman Davis. Ed. Douglas Gray and E. G. Stanley. Oxford: OUP, 1983. 235--44.
2014-05-26 Mon
■ #1855. アメリカ英語で先に進んでいた3単現の -th → -s [colonial_lag][ame_bre][verb][conjugation][bible][shakespeare][suffix][inflection][3sp][schedule_of_language_change][lexical_diffusion][speed_of_change]
動詞の3複現語尾について「#1413. 初期近代英語の3複現の -s」 ([2013-03-10-1]),「#1423. 初期近代英語の3複現の -s (2)」 ([2013-03-20-1]),「#1576. 初期近代英語の3複現の -s (3)」 ([2013-08-20-1]),「#1687. 初期近代英語の3複現の -s (4)」 ([2013-12-09-1]),「#1850. AAVE における動詞現在形の -s」 ([2014-05-21-1]) で扱ってきたが,3単現語尾の歴史についてはあまり取り上げてこなかった.予想されるように,3単現語尾のほうが研究も進んでおり,とりわけイングランドの北部を除く方言で古英語以来 -th を示したものが,初期近代英語期に -s を取るようになった経緯については,数多くの論著が出されている.
初期近代英語の状況を説明するのにしばしば引き合いに出されるのは,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV])では伝統的な -th が完璧に保たれているが,同時代の Shakespeare では -th と -s が混在しているということだ.このことは,17世紀までに口語ではすでに -th → -s への変化が相当程度進んでいたが,保守的な聖書の書き言葉にはそれが一切反映されなかったものと解釈されている.
さて,ちょうど同じ時代に英語が新大陸へ移植され始めていた.では,その時すでに始まっていた -th → -s の変化のその後のスケジュールは,イギリス英語とアメリカ英語とで異なった点はあったのだろうか.Kytö は,16--17世紀のイギリス英語コーパスと,17世紀のアメリカ英語コーパスを用いて,この問いへの答えを求めた.様々な言語学的・社会言語学的なパラメータを設定して比較しているが,全体的には1つの傾向が確認された.17世紀中の状況をみる限り,-s への変化はアメリカ英語のほうがイギリス英語よりも迅速に進んでいたのである.Kytö (120) による頻度表を示そう.
| British English | American English | ||||||
| -S | -TH | Total | -S | -TH | Total | ||
| 1500--1570 | 15 (3%) | 446 | 461 | - | |||
| 1570--1640 | 101 (18%) | 459 | 560 | 1620--1670 | 339 (51%) | 322 | 661 |
| 1640--1710 | 445 (76%) | 140 | 585 | 1670--1720 | 642 (82%) | 138 | 780 |
この結果を受けて,Kytö (132) は,3単現の -th → -s の変化に関する限り,アメリカ英語に colonial_lag はみられないと結論づけている.
Contrary to what has usually been attributed to the phenomenon of colonial lag, the subsequent rate of change was more rapid in the colonies. By and large, the colonists' writings seem to reflect the spoken language of the period more faithfully than do the writings of their contemporaries in Britain. In this respect, speaker innovation, rather than conservative tendencies, guided the development.
過去に書いた colonial_lag の各記事でも論じたように,言語項目によってアメリカ英語がイギリス英語よりも進んでいることもあれば遅れていることもある.いずれの変種もある意味では保守的であり,ある意味では革新的である.その点で Kytö の結論は驚くべきものではないが,イギリス本国において口語上すでに始まっていた言語変化が,アメリカへ渡った後にどのように進行したかを示唆する1つの事例として意義がある.
・ Kytö, Merja. "Third-Person Present Singular Verb Inflection in Early British and American English." Language Variation and Change 5 (1993): 113--39.
2014-02-23 Sun
■ #1763. Shakespeare の作品と言語に関する雑多な情報 [shakespeare][statistics][link][timeline]
Shakespeare とその作品については,周知の通り,膨大な研究の蓄積がある.年表や統計の類いも多々あるが,Crystal and Crystal から適当に抜粋したものをいくつか載せておきたい.なお,Crystal and Crystal の種々の統計の元になっているデータベースは,Shakespeare's Words よりアクセスできる.その他の Shakespeare 関連のリンクについては,「#195. Shakespeare に関する Web resources」 ([2009-11-08-1]) を参照.
(1) Chronology of works (Crystal and Crystal 6)
| 1590--91 | The Two Gentlemen of Verona; The Taming of the Shrew |
| 1591 | Henry VI Part II; Henry VI Part III |
| 1592 | Henry VI Part I (perhaps with Thomas Nashe); Titus Andronicus (perhaps with George Peele) |
| 1592--3 | Richard III; Venus and Adonis |
| 1593--4 | The Rape of Lucrece |
| 1594 | The Comedy of Errors |
| 1594--5 | Love's Labour's Lost |
| by 1595 | King Edward III |
| 1595 | Richard II; Romeo and Juliet; A Midsummer Night's Dream |
| 1596 | King John |
| 1596--7 | The merchant of Venice; Henry IV Part I |
| 1597--8 | The Merry Wives of Windsor; Henry IV Part II |
| 1598 | Much Ado About Nothing |
| 1598--9 | Henry V |
| 1599 | Julius Caesar |
| 1599--1600 | As You Like It |
| 1600--1601 | Hamlet; Twelfth Night |
| by 1601 | The Phoenix and Turtle |
| 1602 | Troilus and Cressida |
| 1593--1603 | The Sonnets |
| 1603--4 | A Lover's Complaint; Sir Thomas More; Othello |
| 1603 | Measure for Measure |
| 1604--5 | All's Well that Ends Well |
| 1605 | Timon of Athens (with Thomas Middleton) |
| 1605--6 | King Lear |
| 1606 | Macbeth (revised by Middleton); Antony and Cleopatra |
| 1607 | Pericles (with George Wilkins) |
| 1608 | Coriolanus |
| 1609 | The Winter's Tale |
| 1610 | Cymbeline |
| 1611 | The Tempest |
| 1613 | Henry VIII (with John Fletcher); Cardenio (with John Fletcher) |
| 1613--14 | The Two Noble Kinsmen (with John Fletcher) |
(2) Top ten content words (Crystal and Crystal 153)
| good | 3995 |
| lord | 3164 |
| man | 3091 |
| love | 3047 |
| sir | 2548 |
| know | 2252 |
| give | 2114 |
| think/thought | 1911 |
| king | 1680 |
| speak | 1626 |
(3) Poetry or prose (Crystal and Crystal 165)
| Poetry (%) | No. of lines | Prose (%) | No. of lines | Play |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 2752 | 0 | 0 | Richard II |
| 100 | 2569 | 0 | 0 | King John |
| 100 | 2493 | 0 | 0 | King Edward III |
| 99.7 | 2892 | 0.3 | 8 | Henry VI Part III |
| 99.5 | 2664 | 0.5 | 14 | Henry VI Part I |
| 98.6 | 2479 | 1.4 | 35 | Titus Andronicus |
| 97.6 | 3517 | 2.4 | 85 | Richard III |
| 97.4 | 2735 | 2.6 | 74 | Henry VIII |
| 94.5 | 2641 | 5.5 | 154 | The Two Noble Kinsmen |
| 93.5 | 1948 | 6.5 | 135 | Macbeth |
| 90.1 | 2208 | 9.9 | 244 | Julius Caesar |
| 89.8 | 2718 | 10.2 | 308 | Antony and Cleopatra |
| 86.9 | 2610 | 13.1 | 393 | Romeo and Juliet |
| 86.6 | 1543 | 13.4 | 239 | The Comedy of Errors |
| 85.2 | 2808 | 14.5 | 487 | Cymbeline |
| 83.7 | 2580 | 16.3 | 503 | Henry VI Part II |
| 81.2 | 1903 | 18.8 | 441 | Pericles |
| 80.6 | 2076 | 19.4 | 498 | The Taming of the Shrew |
| 80.6 | 1713 | 19.4 | 413 | A Midsummer Night's Dream |
| 80.4 | 2599 | 19.6 | 633 | Othello |
| 78.6 | 2025 | 21.4 | 551 | The Merchant of Venice |
| 77.2 | 2571 | 22.8 | 760 | Coriolanus |
| 76.5 | 1569 | 23.5 | 481 | The Tempest |
| 73.2 | 2181 | 26.8 | 800 | The Winter's Tale |
| 73.1 | 2345 | 26.9 | 865 | King Lear |
| 73.1 | 1707 | 26.9 | 627 | Timon of Athens |
| 73.1 | 1613 | 26.9 | 595 | The Two Gentlemen of Verona |
| 71.5 | 2742 | 28.5 | 1092 | Hamlet |
| 66.4 | 2250 | 33.6 | 1137 | Troilus and Cressida |
| 64.2 | 1716 | 35.8 | 955 | Love's Labour's Lost |
| 60.6 | 1634 | 39.4 | 1062 | Measure for Measure |
| 60.5 | 1943 | 39.5 | 1269 | Henry V |
| 55.6 | 1666 | 44.4 | 1332 | Henry IV Part I |
| 51.6 | 1447 | 48.4 | 1356 | All's Well that Ends Well |
| 47.6 | 1547 | 52.4 | 1700 | Henry IV Part II |
| 47.4 | 1276 | 52.6 | 1415 | As You Like It |
| 38.2 | 949 | 61.8 | 1532 | Twelfth Night |
| 28.3 | 739 | 71.7 | 1871 | Much Ado About Nothing |
| 12.5 | 338 | 87.5 | 2370 | The Merry Wives of Windsor |
(4) How long are the plays? (Crystal and Crystal 139)
| Total lines | Total words | Play | First Folio | Riverside |
|---|---|---|---|---|
| 3834 | 29,844 | Hamlet | 3906 | 4042 |
| 3602 | 28,439 | Richard III | 3887 | 3667 |
| 3387 | 25,730 | Troilus and Cressida | 3592 | 3531 |
| 3331 | 26,479 | Coriolanus | 3838 | 3752 |
| 3295 | 26,876 | Cymbeline | 3819 | 3707 |
| 3247 | 25,737 | Henry IV Part II | 3350 | 3326 |
| 3232 | 26,003 | Othello | 3685 | 3551 |
| 3212 | 25,623 | Henry V | 3381 | 3297 |
| 3210 | 25,341 | King Lear | 3302 | 3487 |
| 3083 | 24,490 | Henry VI Part II | 3355 | 3130 |
| 3026 | 23,726 | Antony and Cleopatra | 3636 | 3522 |
| 3003 | 24,023 | Romeo and Juliet | 3185 | 3099 |
| 2998 | 24,126 | Henry IV Part I | 3180 | 3081 |
| 2981 | 24,597 | The Winter's Tale | 3369 | 3348 |
| 2900 | 23,318 | Henry VI Part III | 3217 | 2915 |
| 2809 | 23,333 | Henry VIII | 3463 | 3221 |
| 2803 | 22,537 | All's Well that Ends Well | 3078 | 3013 |
| 2795 | 23,388 | The Two Noble Kinsmen | not in | 3261 |
| 2752 | 21,884 | Richard II | 2849 | 2796 |
| 2708 | 21,290 | The Merry Wives of Windsor | 2729 | 2891 |
| 2696 | 21,269 | Measure for Measure | 2938 | 2891 |
| 2691 | 21,477 | As You Like It | 2796 | 2810 |
| 2678 | 20,541 | Henry VI Part I | 2931 | 2695 |
| 2671 | 20,881 | Love's Labour's Lost | 2900 | 2829 |
| 2610 | 20,767 | Much Ado About Nothing | 2684 | 2787 |
| 2576 | 20,911 | The Merchant of Venice | 2737 | 2701 |
| 2574 | 20,552 | The Taming of the Shrew | 2750 | 2676 |
| 2569 | 20,472 | King John | 2729 | 2638 |
| 2514 | 19,888 | Titus Andronicus | 2708 | 2538 |
| 2493 | 19,406 | King Edward III | not in | not in |
| 2481 | 19,592 | Twelfth Night | 2579 | 2591 |
| 2452 | 19,149 | Julius Caesar | 2730 | 2591 |
| 2344 | 17,728 | Pericles | not in | 2459 |
| 2334 | 17,796 | Timon of Athens | 2607 | 2488 |
| 2208 | 16,936 | The Two Gentlemen of Verona | 2298 | 2288 |
| 2126 | 16,305 | A Midsummer Night's Dream | 2222 | 2192 |
| 2083 | 16,372 | Macbeth | 2529 | 2349 |
| 2050 | 16,047 | The Tempest | 2341 | 2283 |
| 1782 | 14,415 | The Comedy of Errors | 1918 | 1787 |
(5) Using you and thou (Crystal and Crystal 126)
| You-forms | Thou-forms | ||
| you | 14,244 | thou | 5,942 |
| ye | 352 | thee | 3,444 |
| your | 6,912 | thy | 4,429 |
| yours | 260 | thine | 510 |
| yourself | 289 | thyself | 251 |
| yourselves | 74 | ||
| Total | 22,131 | 14,576 | |
|---|---|---|---|
・ Crystal, David and Ben Crystal. The Shakespeare Miscellany. Woodstock & New York: Overlook, 2005.
2014-01-23 Thu
■ #1732. Shakespeare の綴り方 (2) [shakespeare][spelling][alphabet][graphemics]
「#1720. Shakespeare の綴り方」 ([2014-01-11-1]) で,劇作家の現存する自著としては,現在の標準的な綴字 Shakespeare は見当たらないと述べた.自著の綴字は5種類あったが,いずれも <k> と <s> のあいだに母音字 <e> がなかったのである.ただし,当時,この姓を表わす綴字として <e> をもつ Shakespeare か Shake-speare が多く行われていたことも確かである.では,この <e> の有無はどのように説明されるのだろうか.
Crystal and Crystal (72) によると,Shakespeare の綴字が最初に印刷物に現れたのは,1593年の Venus and Adonis の出版に伴う献呈の辞においてである.以降,印刷業者はこの綴字を続けることになった.<e> を挿入したのは,おそらく <k> と <s> の活字を隣り合わせにするのを避けるためだった.というのは,隣り合わせにすると,<k> の右下の脚の湾曲が long <s> の左下の脚の湾曲とぶつかってしまうおそれがあるからだ.この間に <e> を(そしてさらに続けてハイフンを)挿入すると,この活字上の問題は解決する(下図参照).つまり,私たちの見慣れているあの綴字は,エリザベス朝の活版印刷に特有の事情により生じた,印刷業者の作り出した綴字だったということになる.
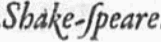
long <s> については,「#584. long <s> と graphemics」 ([2010-12-02-1]) を参照.
・ Crystal, David and Ben Crystal. The Shakespeare Miscellany. Woodstock & New York: The Overlook Press, 2005.
2014-01-11 Sat
■ #1720. Shakespeare の綴り方 [shakespeare][spelling]
英語の綴字の歴史は本ブログでも様々に扱ってきたが,歴史的にはすべての単語に異綴りが確認されるといっても過言ではない.Shakespeare という姓も,例外ではない.現在では,英語の読み手や書き手は,この姓とこの綴字に慣れ親しんでいるが,英語史上確認される異綴りは70以上もある.
姓の構成は単純で,shake + spear すなわち「槍持ち」ほどの意味である.13世紀に遡ることのできる比較的凡庸な名前であり,その70以上の歴史的異綴りのなかには,1248年に文証される Shakespere のほか,Shaksper, Chacsper, Schakespere, Scakespeire, Saksper などが含まれる.
David Kathman という研究者が収集したところによると,劇作家 William Shakespeare (1564--1616) の姓としては,生存中のものとして,25種類の異綴りが確認されたという.全収集例342個のうち,6割以上は Shakespeare か Shake-speare だったというから,現在の綴字は歴史的にも正当 (?) といってよいかもしれない.
Crystal and Crystal (108) に挙げられている,その25種類の綴字を以下に列挙しよう.
Schaksp, Shackespeare, Shackespere, Shackspeare, Shackspere, Shagspere, Shakespe, Shakespear, Shakespeare, Shake-speare, Shakespere, Shakespheare, Shakp, Shakspe?, Shakspear, Shakspeare, Shak-speare, Shaksper, Shakspere, Shaxberd, Shaxpeare, Shaxper, Shaxpere, Shaxspere, Shexpere
なお,真正とされる Shakespeare による自著は6点残っているが,そのなかに次の5種類の綴字が現れる (Crystal 131) .Shakp (1612年,Belott-Mountjoy Deposition), Shakspe(r) (1613年,Gatehouse Conveyance), Shaksper (1613年,Gatehouse Mortgage), Shakspere (1616年,first and second sheet of will), Shakspeare (1616年,third sheet of will) .おもしろいことに,このなかに現在の標準的な綴字はない.
Shakespeare の時代には,綴字の標準化は着々と進行中だったが,定着したといえるまでにはもう数十年が必要だった.17世紀半ばにはおよそ定着したが,より強固な基盤ができあがるまでには18世紀半ばの Johnson の辞書を待たねばならなかった.とりわけ印刷ではなく手書きでは,綴字の揺れはいまだ激しかったろう.
現在の Shakespeare の綴字は,現代人にとっても十分に変則的な綴字に見えるが,多少間違えたところで恥ずかしく感じる必要はない.Shakespeare 自身も使っていなかった可能性はあるし,かつてはこんな綴字もあったのだと軽く受け流せばよい(かもしれない)ので.
・ Crystal, David and Ben Crystal. The Shakespeare Miscellany. Woodstock & New York: The Overlook Press, 2005.
2013-12-30 Mon
■ #1708. *wer- の語根ネットワークと weird の語源 [etymology][indo-european][literature][shakespeare][word_family]
昨日の記事「#1707. Woe worth the day!」 ([2013-12-29-1]) で,印欧語根 *wer- (to turn, bend) に由来する動詞 worth について取り上げた.この語根に由来する英単語は数多く,語彙の学習に役立つと思われるので,『英語語源辞典』 (1643) に従って語根ネットワークを示そう.
・ Old English: inward, stalworth, -ward, warp, weird, worm, sorry, worth, wrench, wrest, wrestle, wring, wrinkle, wrist, wry
・ Middle English: (wrap)
・ Old Norse: wrong
・ Other Germanic: gaiter, garrote, ribald, (wrangle), wrath, wreath, wriggle, writhe, wroth
・ Latin: avert, controversy, converge, converse, convert, dextrorse, diverge, divert, extrovert, introvert, inverse, obvert pervert, prose, reverberate, revert, (ridicule), subvert, transverse, universe, verge, vermeil, vermi-, vermicelli, vermicular, vermin, versatile, verse, version, versus, vertebra
・ Greek: rhabd(o)-, rhabdomancy, rhapsody, (rhomb, rhombus)
・ Slavic: verst
・ Sanskrit: bat (speech)
一見すると形態的には簡単に結びつけられない語もあるが,意味的には「曲がりくねった」でつながるものも多い.くねくね動く虫 (worm) のイメージと結びつけられるものが多いように思われる.
この中で,特に weird (不思議な,気味の悪い)を取り上げよう.この語の語源を古英語まで遡ると,(ge)wyrd (運命)にたどりつく.古英語文学においてとりわけ重要な単語であり概念である."to happen" を意味する weorþan の名詞形であり,"what is to happen" (起こるべきこと)を意味した.現代標準英語では「運命」の語義は古風だが,スコットランド方言などではこの語義が生きている.
さて,この語は古英語以来,名詞として用いられていたが,1400年くらいから「運命を司る」を意味する形容詞としての用法が発達した.形容詞用法としては,Shakespeare が Macbeth において weird sisters (魔女;運命の3女神)を用いたことが後世に影響を与え,Shelley, Keats などのロマン派詩人もそれにならった.しかし,Shelley らは意味を「運命を司る」から「不可思議な,超自然的な」へと拡大し,さらに「奇妙な,風変わりな」の語義も発展させた.ロマン派詩人ならではの意味の発展のさせ方といえよう.この語は,古英語と後期近代英語の文学を象徴するキーワードといってもよいのではないか.
現在の語形 weird は,中英語の北部方言形 wērd, weird に由来するとされる.Shakespeare 1st Folio では,the weyward sisters という綴字が見られ,語源的に区別すべき wayward (強情な;気まぐれな)との混同がうかがえる.
・ 寺澤 芳雄 (編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2013-03-15 Fri
■ #1418. 17世紀中の its の受容 [personal_pronoun][genitive][emode][bible][shakespeare][speed_of_change]
古英語の人称代名詞体系において,中性単数属格形は男性単数属格形と同じ his であり,これが中英語でも継承されたが,16世紀末にits が現われ,17世紀中に his を置換していった.この歴史について,「#198. its の起源」 ([2009-11-11-1]) で概説した.
Baugh and Cable (243--44) によれば,後期中英語から初期近代英語にかけて,中性単数属格形の his の代用品として,its 以外にも様々なものが提案されてきた.聖書にみられる two cubits and a half was the length of it や nine cubits was the length thereof のような迂言的表現 (「#1276. hereby, hereof, thereto, therewith, etc.」の記事[2012-10-24-1]を参照),Shakespeare にみられる It lifted up it head (Hamlet) や The hedge-sparrow fed the cuckoo so long, / That it had it head bit off by it young (Lear) のような主格と同じ it をそのまま用いる方法,Holland の Pliny (1601) にみられる growing of the own accord のような定冠詞 the で代用する方法などである.
しかし,名詞の属格として定着していた 's の強力な吸引力は,人称代名詞ですら避けがたかったのだろう.おそらく口語から始まった its あるいは it's (apostrophe s のついたものは1800年頃まで行なわれる)の使用は,16世紀末に初例が現われてから数十年間は,正用とはみなされていなかったようだが,17世紀の終わりにかけて急速に受け入れられていった.例えば,17世紀前半では,欽定訳聖書 (The King James Bible) での使用は皆無であり,Shakespeare の First Folio (1623) では10例を数えるにすぎなかったし,John Milton (1608--74) でもいささか躊躇があったようだ.しかし,John Dryden (1631--1700) ではすでに his が古風と感じられていた.
Görlach (86) も,17世紀に入ってからの its の急速な受容について,次のように述べている.
The possessive its . . . is the only EModE innovation; his, common for neuter reference until after 1600 . . ., did not reflect the distinction 'human':'nonhuman' found elsewhere in the pronominal system. This is likely to be the reason for the possessive form it . . ., which is found from the fourteenth century, and the less equivocal forms of it or thereof, which are common in the sixteenth and seventeenth centuries . . . . But its . . . obviously fitted the system ideally, as can be deduced from its rapid spread in the first half of the seventeenth century.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.
・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.
2013-03-11 Mon
■ #1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか? [conversion][shakespeare][word_formation][causation][synthesis_to_analysis]
品詞転換 (conversion) あるいはゼロ派生 (zero-derivation) については,「#190. 品詞転換」 ([2009-11-03-1]) をはじめ conversion の各記事で関連する話題を取り上げてきた.品詞転換が生産的な語形成として登場するのは初期近代英語,特に Shakespeare においてであり,ルネサンス期の活力,若々しさ,挑戦心などと結びつけられることがある.後に続く規範主義の時代と対比して,確かにのびのびとした雰囲気に満ちた時代である.Baugh and Cable (250) も,ルネサンス期の英語の特徴の1つとして,品詞転換を以下のように評している.
English in the Renaissance, at least as we see it in books, was much more plastic than now. People felt freer to mold it to their wills. Words had not always distributed themselves into rigid grammatical categories. Adjectives appear as adverbs or nouns or verbs, nouns appear as verbs---in fact, any part of speech as almost any other part. When Shakespeare wrote stranger'd with an oath he was fitting the language to his thought, rather than forcing his thought into the mold of conventional grammar. This was in keeping with the spirit of his age. It was in language, as in many other respects, an age with the characteristics of youth---vigor, a willingness to venture, and a disposition to attempt the untried. The spirit that animated Hawkins and Drake and Raleigh was not foreign to the language of their time.
当時の社会の風潮と品詞転換という語形成とを結びつけて考えるのは,確かに魅力的ではある.しかし「#1015. 社会の変化と言語の変化の因果関係は追究できるか?」 ([2012-02-06-1]) で取り上げた Martinet の主張に従い,まずは品詞転換の発展という問題を,あくまで言語内的に論じる必要があるのではないだろうか.
「屈折の衰退=語根の焦点化」 ([2011-02-11-1]) で述べたように,英語はこの時代までにほぼすべての品詞において屈折を著しく衰退させ,語根主義とでも呼ぶべき分析的な言語へと発展してきた.同時に,語順も厳しく固定化し,主として統語的な位置により各語の品詞や用法が同定される言語となってきた.このような統語的,形態的な特徴をもつに至った初期近代英語においては,本来語や中英語までに入った借用語の多くは,すでに品詞転換の自由を与えられていたといえる.そこへラテン語を中心としたおびただしい借用語が新たに加わり(この大量借用がルネサンス期の時代の産物であるとみなすことには異論はないだろう),それらも品詞転換という便法に付されることとなった,ということではないだろうか.
社会の風潮と品詞転換のあいだの関係は否定すべきだと言っているのではない.ただ,その関係が直接的というよりはワンクッション挟んだ間接的なものであると考え,あくまで言語内的,機能主義的な因果関係を探るのが先ではないかということである.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.
2013-03-09 Sat
■ #1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas [emode][renaissance][lexicology][loan_word][shakespeare][bible]
英語史では,特定の作家や作品がその後の英語の発展において大きな役割を果たしたと明言できる例は多くないということが言われる.そのなかで,初期近代英語を代表する Shakespeare や The King James Bible は例外だと言われることもある.そこに現われる多くの語彙や表現が,現代英語に伝わっており,広く用いられているからだ.確かに,質においても量においても,この両者の影響は他の作家や作品を圧倒している.
ここから連想されるのは,後期中英語の Chaucer の英語史上,特に英語語彙史上の意義を巡る議論である.「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]), 「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1]), 「#524. Chaucer の用いた英語本来語 --- stevene」 ([2010-10-03-1]) で見たとおり,最近の議論では,中英語におけるフランス語借用の重要な部分を Chaucer に帰する従来の見解に対する慎重論が出されている.借用語を英語文献に初出させるのはほぼ常に個人だが,そうだからといってその個人が英語語彙史上の栄光を独り占めにしてよいということにはならない.借用熱に浮かされた時代に生まれ,書く機会とある程度の文才があれば,ある借用語を初出させること自体は可能である.多くの場合,語彙の初出に関わる個人の貢献は,その個人そのものに帰せられるべきというよりは,そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられるべきだろう.特に,そのような個人が複数現われる時代には,なおさらである.
Utopia (1516) を著わした Sir Thomas More (1478--1535) や The Boke named the Governour (1531) を著わした Sir Thomas Elyot (c1490--1546) がその例として挙げるにふさわしいかもしれない.Baugh and Cable (229) によれば,More は次のような借用語(あるいはその特定の語義)を初出させた.
absurdity, acceptance, anticipate, combustible, compatible, comprehensible, concomitance, congratulatory, contradictory, damnability, denunciation, detector, dissipate, endurable, eruditely, exact, exaggerate, exasperate, explain, extenuate, fact, frivolous, impenitent, implacable, incorporeal, indifference, insinuate, inveigh, inviolable, irrefragable, monopoly, monosyllable, necessitate, obstruction, paradox, pretext
一方,Elyot は以下の語彙を導入した.
accommodate, adumbrate, adumbration, analogy, animate, applicate, beneficence, encyclopedia, exerp (excerpt), excogitate, excogitation, excrement, exhaust, exordium, experience (v.), exterminate, frugality, implacability, infrequent, inimitable, irritate, modesty, placability
赤字で示したものは,「#708. Frequency Sorter CGI」([2011-04-05-1]) にかけて,頻度にして800回以上現われる上位6318位までに入る語である.当時難語と言われた可能性があるというのが信じられないほどに,現在では普通の語だ.
Baugh and Cable (230) は,この2人の人文主義者の語彙的貢献を,上に述べた私の見解とは異なり,ともすると全面的に個人に帰しているように読める.
So far as we now know, these words had not been used in English previously. In addition both writers employ many words that are recorded from only a few years before. And so they either introduced or helped to establish many new words in the language. What More and Elyot were doing was being done by numerous others, and it is necessary to recognize the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century.
しかし,最後の "the importance of individuals as "makers of English" in the sixteenth and early seventeenth century" が意味しているのはある特定の時代に属する複数の個人の力のことであり,私の述べた「そのような個人を輩出させた時代の潮流に帰せられる」という見解とも矛盾しないようにも読める.
この問題は,時代が個人を作るのか,個人が時代を作るのかという問題なのだろうか.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow