2025-09-28 Sun
■ #5998. 英語史旅,hel旅,あるいは helgrimage [helgrim][helkatsu][notice][chaucer][canterbury_tales][cockney][london][johnson][blend][100_places]
「英語語源辞典通読ノート」でおなじみの lacolaco さんが,9月23日付けで興味深い note 記事を公開された.「2025年ロンドン」 と題するその記事は,単なるロンドン旅行記ではない.「英語史」というレンズを通してロンドンとカンタベリーをめぐるという,体を張った知的なhel活 (helkatsu) の記録である.
同記事によれば,lacolaco さんは今月半ばのロンドン滞在の折に,A History of the English Language in 100 Places をガイドブックとして,英語史にゆかりのある数々の場所を訪ね歩いたという.この本については hellog でも以下の記事などで取り上げてきた.
- 「#5956. 100の場所で英語史を学ぶ本 --- A History of the English Language in 100 Places」 ([2025-08-17-1])
- 「#5968. 「あなたが選ぶ英語史ゆかりの場所100選」はおもしろい企画になりそう --- HEL in 100 Places の序文より」 ([2025-08-29-1])
今回の lacolaco さんの旅は,まさにこの本を実践に移した旅といえる.Geoffrey Chaucer (1340?--1400) が The Canterbury Tales の構想を練ったとされる Aldgate, Cockney (cockney) の語源となった鐘の音で知られる St Mary-le-Bow,そして Samuel Johnson が英語史上初の本格的な辞書を編纂した Dr Johnson's House など,訪問地はいずれも英語史を学ぶ者にとって胸が熱くなる場所ばかりだ.極めつけは,巡礼の最終目的地である Canterbury への日帰り旅.Chaucer の像や,大聖堂に鎮座する St. Augustine's Chair --- すなわちカンタベリー大聖堂の cathedra (司教座) そのもの --- を目の当たりにした感動が伝わってくる.
この記事でとりわけ私の心を捉えたのは,lacolaco さんが自らを helgrim (英語史聖地巡礼者)と称していることだ.これは HEL (= History of the English Language) と pilgrim (巡礼者)を掛け合わせた混成語 (blend)である.このネーミングセンスには脱帽する.
この素晴らしいアイデアに乗っかり,英語史の巡礼行為そのものを helgrimage (英語史旅,あるいはhel旅)と呼びたい.英語史を学び,その歴史が刻まれた土地を訪ね歩く.これは,書物と向き合うだけでは得られない,身体的な学びの形である.言語が実際に使用され,変容を遂げてきた現場の空気を吸うことで,英語史年表の各項目が,単なる知識ではなく,生きた実感として立ち上がってくるはずだ.
英語史研究は,基本的には文献学であり,書斎にこもって写本や刊本を読んだり,PCの前で電子コーパスを分析するのが一般的だ.しかし,本来,言語は常に特定の場所と結びついている.歴史言語学が,地理学,社会学,人類学などの分野と密接に関わるのはそのためだ.helgrimage は,英語史という学問にフィールドワークの側面を与え,その魅力をさらに深めてくれる可能性を秘めている.
これまで本ブログでは様々なhel活を提案してきたが,この helgrimage はきわめて能動的な活動といえるだろう.ロンドンやカンタベリーに限らず,ヴァイキングが足跡を残したイングランド北部,古英語の写本が眠る図書館,さらには英語が世界に展開していく拠点となった要衝など,helgrimage の目的地は世界中に存在する.
lacolaco さんの今回の実践は,英語史の楽しみ方に新たな地平を切り開くものである.多くの helgrims がこれに続くことを願ってやまない.私も helgrimage に出かけることにしよう.
・ Lucas, Bill and Christopher Mulvey. A History of the English Language in 100 Places. London: Robert Hale, 2013.
2023-04-25 Tue
■ #5111. チョーサーによるブルトン・レ「地方地主の話の序」を読む [chaucer][canterbury_tales][franklins_tale][breton_lai][me_text][celtic][breton][voicy][heldio][me_text][literature][brittany_exhibition]
今回は Geoffrey Chaucer (1340?--1400) の傑作 The Canterbury Tales より The Franklin's Tale 「地方地主の話の序」を読んでみたい.
この作品は,ブルターニュ地方が舞台となっている.ブルターニュといえば,ブリテン島のケルト人の一派が,5--6世紀にアングロサクソン人による侵攻から逃れ,イギリス海峡を南に越えてたどり着いたフランス側の土地である.その地には現在もブルトン人が住んでおり,ブルトン語 (Breton) を話している.
ブルトン人たちは Breton lai (ブルトン・レ)と呼ばれる短い物語詩のジャンルを生み出し,そのジャンルは海峡の両側に伝わっている.フランス側では Marie de France (c. 1160--1215) がフランス語で書いた作品が有名だが,ブリテン島側でも翻案作品が著わされた.今回のチョーサーによる「地方地主の話」は,その1つである.
「地方地主の話の序」の中英語原文を The Riverside Chaucer より,日本語訳を『カンタベリ物語 共同新訳版』より引用する.
THE FRANKLIN'S PROLOGUE
Prologe of the Frankeleyns Tale.
l. 709 Thise olde gentil Britouns in hir dayes 710 Of diverse aventures maden layes, 711 Rymeyed in hir firste Briton tonge, 712 Whiche layes with hir instrumentz they songe 713 Or elles redden hem for hir plesaunce; 714 And oon of hem have I in remembraunce, 715 Which I shal seyn with good wyl as I kan. 716 But, sires, by cause I am a burel man, 717 At my bigynnyng first I yow biseche, 718 Have me excused of my rude speche. 719 I lerned nevere rethorik, certeyn; 720 Thyng that I speke, it moot be bare and pleyn. 721 I sleep nevere on the Mount of Pernaso, 722 Ne lerned Marcus Tullius Scithero. 723 Colours ne knowe I none, withouten drede, 724 But swiche colours as growen in the mede, 725 Or elles swiche as men dye or peynte. 726 Colours of rethoryk been to me queynte; 727 My spirit feeleth noght of swich mateere. 728 But if yow list, my tale shul ye heere.
地方地主の話の序
今は昔,雅びなブルターニュの人たちは,さまざまなできごとを歌に詠み,いにしえのケルトの言葉で技をこらし,楽器に合わせて歌ったり,読み語りを楽しんだりしておりました.そのような話をひとつ覚えていますので,微力を尽くしてお話ししたいと思っております.
けれども,何しろ学がないもので,乱暴な言葉遣いをお許しいただくよう,まずは皆さんにお願いします.まったく,修辞学なんぞ習ったこともなく,あからさまな話し方しかできんのです.パルナッソス山で眠ったこともなければ,マルクス・トゥリウス・キケロを学んだこともない.言葉のあやなどさっぱりで,目もあやな野の花や,染めたり織ったりのあやしか知らんのです.語りのあやは解らんし,その類のセンスも持ちあわせておらん.でも,よろしければ話をお聞き下さい.
なお,上記の中英語原文を今朝の Voicy heldio で読み上げている.中英語に関心がある方,読解に挑戦してみたいと思う方は,ぜひ「#694. チョーサーによるブルトン・レ「地方地主の話の序」を原文で味わってみませんか?」をお聴きください.
・ Benson, Larry D., ed. The Riverside Chaucer. 3rd ed. Oxford: OUP, 1987.
・ ジェフリー・チョーサー(著),池上 忠弘(監訳) 『カンタベリ物語 共同新訳版』 悠書館,2021年.
・ 池上 昌・堀田 隆一・狩野 晃一 「チョーサーの英語」 『チョーサー巡礼 古典の遺産と中世の新しい息吹に導かれて』(池上 忠弘(企画),狩野 晃一(編)) 悠書館,2022年.93--124頁.
2022-12-24 Sat
■ #4989. 近代英語の Merry Christmas! と中英語の Nowell! [interjection][chaucer][christmas][greetings][anglo-norman][shakespeare][chaucer][sggk]
2022年のクリスマス・イヴです.この時期の英語での「時候の挨拶」は,いわずとしれた Merry Christmas! ですね.オリジナルの形は (I wish you a) merry Christmas! ほどで,挨拶 (greetings) のために先行する部分が省略された事例です.イギリス英語ではしばしば Happy Christmas! ともいわれ,宗教色を控えてHappy Holidays! なども用いられます.関連して「#4284. 決り文句はほとんど無冠詞」 ([2021-01-18-1]),「#4259. クリスマスの小ネタ5本」 ([2020-12-24-1]) もご一読ください.
Merry Christmas について OED を調べてみると,この挨拶の初出は初期近代英語期の1534年のことです.1534年といえば,ヘンリー8世がローマ教会と決別して英国国教会 (Church of England) を成立させた年ですね.16世紀からの最初期の3例文を挙げましょう.
1534 J. Fisher Let. 22 Dec. in T. Fuller Church Hist. Eng. (1837) v. iii. 47 And thus our Lord send yow a mery Christenmas, and a comfortable, to yowr heart desyer.
1565 J. Scudamore Let. 17 Dec. in Hereford Munic. MSS (transcript) (O.E.D. Archive) I. ii. 209 And thus I comytt you to god, who send you a mery Christmas & many.
1600 W. Shakespeare Henry IV, Pt. 2 v. iii. 36 Welcome mery shrouetide.
最初期は,共起する動詞は wish よりも send が普通だったのでしょうか.Lord 「主」から贈られる言葉だったようですね.
中英語期までは,代わりにアングロノルマン語由来の Nowell が「クリスマス」の意味および挨拶のために用いられていました (cf. フランス語 (Je souhaite un) joyeux No&etrema;l!) .OED の Nowell, int. and n. の第1語義と初例を覗いてみましょう.初例はジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) の『カンタベリ物語』 (The Canterbury Tales) からです.
A. int.
A word shouted or sung: expressing joy, originally to commemorate the birth of Christ. Now only as retained in Christmas carols (cf. NOEL n.).
c1395 G. Chaucer Franklin's Tale 1255 Biforn hym stant brawen of tosked swyn, And Nowel crieth euery lusty man.
ちなみに,Nowell は「クリスマスの饗宴」の語義もあり,これは『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の冒頭に近いアーサー王の宮廷の場面での使用が初例となっています.
c1400 (?c1390) Sir Gawain & Green Knight (1940) 65 (MED) Loude crye watz þer kest of clerkez & o綻er, Nowel nayted o-newe, neuened ful ofte.
クリスマス関連の語彙については,OED ブログより A Christmassy Lexicon の記事をお勧めします.
ということで,今日は中世風に Nowell!
2022-12-24 Sat
■ #4989. 近代英語の Merry Christmas! と中英語の Nowell! [interjection][chaucer][christmas][greetings][anglo-norman][shakespeare][chaucer][sggk]
2022年のクリスマス・イヴです.この時期の英語での「時候の挨拶」は,いわずとしれた Merry Christmas! ですね.オリジナルの形は (I wish you a) merry Christmas! ほどで,挨拶 (greetings) のために先行する部分が省略された事例です.イギリス英語ではしばしば Happy Christmas! ともいわれ,宗教色を控えてHappy Holidays! なども用いられます.関連して「#4284. 決り文句はほとんど無冠詞」 ([2021-01-18-1]),「#4259. クリスマスの小ネタ5本」 ([2020-12-24-1]) もご一読ください.
Merry Christmas について OED を調べてみると,この挨拶の初出は初期近代英語期の1534年のことです.1534年といえば,ヘンリー8世がローマ教会と決別して英国国教会 (Church of England) を成立させた年ですね.16世紀からの最初期の3例文を挙げましょう.
1534 J. Fisher Let. 22 Dec. in T. Fuller Church Hist. Eng. (1837) v. iii. 47 And thus our Lord send yow a mery Christenmas, and a comfortable, to yowr heart desyer.
1565 J. Scudamore Let. 17 Dec. in Hereford Munic. MSS (transcript) (O.E.D. Archive) I. ii. 209 And thus I comytt you to god, who send you a mery Christmas & many.
1600 W. Shakespeare Henry IV, Pt. 2 v. iii. 36 Welcome mery shrouetide.
最初期は,共起する動詞は wish よりも send が普通だったのでしょうか.Lord 「主」から贈られる言葉だったようですね.
中英語期までは,代わりにアングロノルマン語由来の Nowell が「クリスマス」の意味および挨拶のために用いられていました (cf. フランス語 (Je souhaite un) joyeux No&etrema;l!) .OED の Nowell, int. and n. の第1語義と初例を覗いてみましょう.初例はジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) の『カンタベリ物語』 (The Canterbury Tales) からです.
A. int.
A word shouted or sung: expressing joy, originally to commemorate the birth of Christ. Now only as retained in Christmas carols (cf. NOEL n.).
c1395 G. Chaucer Franklin's Tale 1255 Biforn hym stant brawen of tosked swyn, And Nowel crieth euery lusty man.
ちなみに,Nowell は「クリスマスの饗宴」の語義もあり,これは『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の冒頭に近いアーサー王の宮廷の場面での使用が初例となっています.
c1400 (?c1390) Sir Gawain & Green Knight (1940) 65 (MED) Loude crye watz þer kest of clerkez & o綻er, Nowel nayted o-newe, neuened ful ofte.
クリスマス関連の語彙については,OED ブログより A Christmassy Lexicon の記事をお勧めします.
ということで,今日は中世風に Nowell!
2022-12-16 Fri
■ #4981. Reginald Pecock --- 史上最強の "infinitive-splitter" [split_infinitive][infinitive][syntax][word_order][pecock][chaucer][wycliffe][shakespeare]
「#4976. 「分離不定詞」事始め」 ([2022-12-11-1]),「#4977. 分離不定詞は14世紀からあるも増加したのは19世紀半ば」 ([2022-12-12-1]),「#4979. 不定詞の否定として to not do も歴史的にはあった」 ([2022-12-14-1]) の流れを受け,分離不定詞 (split_infinitive) について英語史上のおもしろい事実を1つ挙げたい.
分離不定詞を使用する罪深い人間は infinitive-splitter という呼称で指さされることを,先の記事 ([2022-12-11-1]) で確認した.OED が1927年にこの呼称の初出を記録している.infinitive-splitter という呼称が初めて現われるよりずっと前,5世紀も遡った時代に,英語史上の真の "infinitive-splitter" が存在した.ウェールズの神学者 Reginald Pecock (1395?--1460) である.
分離不定詞の事例は14世紀(あるいは13世紀?)より見出されるといわれるが,後にも先にも Pecock ほどの筋金入りの infinitive-splitter はいない.彼に先立つ Chaucer はほとんど使わなかったし,Layamon や Wyclif はもう少し多く使ったものの頻用したわけではない.後の Shakespeare や Kyd も不使用だったし,18世紀末にかけてようやく頻度が高まってきたという流れだ.中英語期から初期近代英語期にかけての時代に,Pecock は infinitive-splitter として燦然と輝いているのだ.しかし,なぜ彼が分離不定詞を多用したのかは分からない.Visser (II, § 977; p. 1036) も,次のように戸惑っている.
Quite apart, however, stands Reginald Pecock, who in his Reule (c 1443), Donet (c 1445), Repressor (c. 1449), Folewer (c 1454) and Book of Faith (c 1456) not only makes such an overwhelmingly frequent use of it that he surpasses in this respect all other authors writing after him, but also outdoes them in the boldness of his 'splitting'. For apart from such patterns as 'to ech dai make him ready', 'for to in some tyme, take', 'for to the better serve thee', which are extremely common in his prose, he repeatedly inserts between to and the infinitive adverbial adjuncts and even adverbial clauses of extraordinary length, e.g. Donet 31, 17, 'What is it for to lyue þankingly to god ...? Sone, it is forto at sum whiles, whanne oþire profitabler seruycis of god schulen not þerbi be lettid, and whanne a man in his semyng haþ nede to quyke him silf in þe seid lovis to god and to him silf and nameliche to moral desires (whiche y clepe here 'loves' or 'willingnis') vpon goodis to come and to be had, seie and be aknowe to god ... þat he haþ receyued benefte or benefetis of god.') . . .
It is not ascertainable what it was that brought Pecock, to this consistent deliberate and profuse use of the split infinitive, which in his predecessors and contemporaries only occurred occasionally, and more or less haphazardly. Neither can the fact be accounted for that he had no followers in this respect, although his works were widely read and studied.
上に挙げられている例文では,不定詞マーカーの forto と動詞原形 seie and be の間になんと57語が挟まれている.Pecock に史上最強の infinitive-splitter との称号を与えたい.
・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.
2022-11-30 Wed
■ #4965. チョーサーは頭韻がお嫌い? 'rum, ram, ruff' [alliteration][rhyme][chaucer][sggk][literature]
映画『グリーン・ナイト』が公開中です.その原作『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) は14世紀末の中英語ロマンスですが,ほぼ同時代に書かれたジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) の『カンタベリ物語』 (The Canterbury Tales) とは,あらゆる面で異なっています.前者はコテコテのイングランド北西部の英語方言で頭韻 (alliteration) によって書かれており,後者は後に標準英語へと発展していくロンドン英語で脚韻 (rhyme) によって書かれています.
チョーサーはもっぱら大陸由来の脚韻で詩作し,ゲルマン語としての英語に伝統的に受け継がれてきた頭韻には関心がなかったようです.現代の日本の歌謡界になぞらえていえば「私はポップス歌手だけれど民謡や演歌はやりませんよ」といった雰囲気です.このことは,チョーサー自身が本気では頭韻を利用していないこと,また『カンタベリ物語』の「教区主任司祭の話の序」 (ll. 42--47) にて,次のように述べていることからも間接的に知られます (The Riverside Chaucer より).
But trusteth wel, I am a Southren man;
I kan nat geeste 'rum, ram, ruf,' by lettre,
Ne, God woot, rym holde I but litel bettre;
And therfore, if yow list --- I wol nat glose ---
I wol yow telle a myrie tale in prose
To knytte up al this feeste and make an ende.
これを日本語に訳すと次のようになります.
ですが,ぜひともご理解いただきたいのですが,私は南の出身です.ですから "rum","ram","ruf" という具合に言葉の頭で韻を踏むことなどできません.また,神もご存知ですが,私は脚韻も踏むこともまずできません.ですから,よろしければ --- 注釈する気はさらさらないのですが --- 皆様に散文で楽しい話をいたしましょう.それでこのお楽しみの会で編まれるべきものをすべて編み上げて締めくくりましょう
チョーサーは,教区主任司祭という登場人物にやや軽んじた口調で 'rum, ram, ruff' と発言させています.文字通りには頭韻も脚韻もやりませんと読めますが,頭韻を脚韻より劣るものと見なしていると読むことも可能かもしれません.いかがでしょうか.ここでは,池上 (144) の読みを紹介しておきたいと思います.引用で「彼」とは詩人チョーサーのことです.
彼はどうもアーサー王物語の頭韻詩があまり好きでないらしい.時どき頭韻調を使ってみたり,『教区司祭の話 前口上』では,「私は南部の人間なので,ルム・ラム・ルフ (rum, ram, ruf) なんて頭韻を踏む吟唱などは出来ません」(X 四二ー四三)という有名な台詞がある.当時から見ても古くさい,異質の,田舎くさい,違ったジャンルの詩物語と見ているらしいのである.
このような時代と状況下で,なぜガウェイン詩人は主に頭韻を用いて詩作したのか.この辺りがおもしろい問題です.
・ Benson, Larry D., ed. The Riverside Chaucer. 3rd ed. Oxford: OUP, 1987.
・ ジェフリー・チョーサー(著),池上 忠弘(監訳) 『カンタベリ物語 共同新訳版』 悠書館,2021年.
・ 池上 忠弘(訳) 『「ガウェイン」詩人 サー・ガウェインと緑の騎士』 専修大学出版局,2009年.
2022-09-04 Sun
■ #4878. 『チョーサー巡礼』が刊行されました [chaucer][notice]
8月30日に悠書館より『チョーサー巡礼 古典の遺産と中世の新しい息吹きに導かれて』が刊行されました.
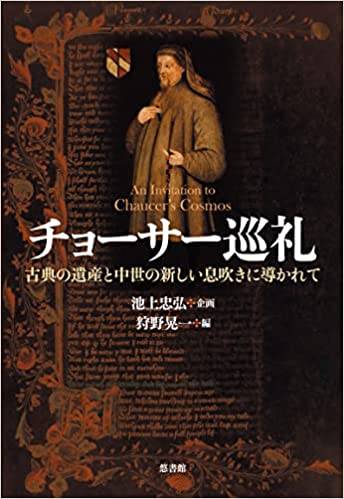
故池上忠弘氏が企画し,狩野晃一氏が編集した,チョーサーの作品と時代背景に関する本格的なコンパニオンです.こちらの目次をご覧いただくと分かるように,チョーサーの生涯,写本,言語はもとより,中世ヨーロッパ文学の背景から,当時の政治,美術,音楽に至るまでの広い範囲をカバーしていますので,中世英語英文学とその周辺分野への導入書としても役立つと思います.
私自身は,池上昌氏,狩野晃一氏とともに第3章「チョーサーの英語」を執筆しました.チョーサーの英語は中英語 (Middle English) と呼ばれており,中英語期(1100--1500年頃)の後半に相当する時代の英語です.現代英語の知識があれば,多少の手ほどきと注を頼りに何とか読み進めることができます.とは言っても,6世紀以上の隔たりがありますので,たやすく読めるわけではありません.現代英語と比較して異なっている点,そして異なっていない点を先に押さえておけば,チョーサーの原文にも馴染みやすいはずです.第3章ではチョーサーの英語の特徴について,語彙,文法,発音,スペリング,韻律の観点から30頁ほどで易しく解説しています.
今回の『チョーサー巡礼』刊行より1年ほど先立って,悠書館より『カンタベリ物語 共同新訳版』(池上忠弘(監訳))も刊行されています.当初は1冊で同時刊行という話もあったのですが,あまりに分量が嵩んだこともあり,2冊を順次刊行するということになりました.
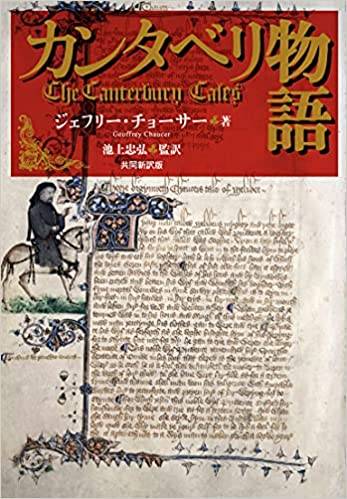
2冊の編集に尽力された狩野晃一氏が,ヒロ・ヒライ氏による YouTube 「BH チャンネル」にて対談されていますので,ぜひ以下よりご視聴ください.
・ 「【対談】チョーサー『カンタベリ物語』共同新訳版!!」
・ 「【生配信】待望の『チョーサー巡礼』ついに登場!中世英文学!」
・ 池上 忠弘(企画),狩野 晃一(編) 『チョーサー巡礼 古典の遺産と中世の新しい息吹きに導かれて』 悠書館,2022年.
・ ジェフリー・チョーサー(著),池上 忠弘(監訳) 『カンタベリ物語 共同新訳版』 悠書館,2021年.
・ 池上 昌・堀田 隆一・狩野 晃一 「チョーサーの英語」 『カンタベリ物語 共同新訳版』(池上 忠弘(企画),狩野 晃一(編)) 悠書館,2022年.93--124頁.
2022-05-27 Fri
■ #4778. 変わりゆく言葉に嘆いた詩人 Edmund Waller の "Of English Verse" [chaucer][language_change][hel_contents_50_2022][emode][literature]
khelf(慶應英語史フォーラム)による「英語史コンテンツ50」が終盤を迎えている.今回の hellog 記事は,先日5月20日にアップされた院生によるコンテンツ「どこでも通ずる英語…?」にあやかり,そこで引用されていたイングランドの詩人 Edmund Waller による詩 "Of English Verse" を紹介したい.
Waller (1606--87年)は17世紀イングランドを代表する詩人で,文学史的にはルネサンスの終わりと新古典主義時代の始まりの時期をつなぐ役割を果たした.Waller は32行の短い詩 "Of English Verse" のなかで,変わりゆく言葉(英語)の頼りなさやはかなさを嘆き,永遠に固定化されたラテン語やギリシア語への憧れを示している.一方,Chaucer を先輩詩人として引き合いに出しながら,詩人の言葉ははかなくとも,詩人の心は末代まで残るのだ,いや残って欲しいのだ,と痛切な願いを表現している.
Waller は,まさか1世紀ほど後にイングランドがフランスとの植民地争いを制して世界の覇権を握る糸口をつかみ,その1世紀後にはイギリス帝国が絶頂期を迎え,さらに1世紀後には英語が世界語として揺るぎない地位を築くなどとは想像もしていなかった.Waller はそこまでは予想できなかったわけだが,それだけにかえって現代の私たちがこの詩を読むと,言語(の地位)の変わりやすさ,頼りなさ,はかなさがひしひしと感じられてくる.
OF ENGLISH VERSE.
1 Poets may boast, as safely vain,
2 Their works shall with the world remain;
3 Both, bound together, live or die,
4 The verses and the prophecy.
5 But who can hope his lines should long
6 Last in a daily changing tongue?
7 While they are new, envy prevails;
8 And as that dies, our language fails.
9 When architects have done their part,
10 The matter may betray their art;
11 Time, if we use ill-chosen stone,
12 Soon brings a well-built palace down.
13 Poets that lasting marble seek,
14 Must carve in Latin, or in Greek;
15 We write in sand, our language grows,
16 And, like the tide, our work o'erflows.
17 Chaucer his sense can only boast;
18 The glory of his numbers lost!
19 Years have defaced his matchless strain;
20 And yet he did not sing in vain.
21 The beauties which adorned that age,
22 The shining subjects of his rage,
23 Hoping they should immortal prove,
24 Rewarded with success his love.
25 This was the generous poet's scope;
26 And all an English pen can hope,
27 To make the fair approve his flame,
28 That can so far extend their fame.
29 Verse, thus designed, has no ill fate,
30 If it arrive but at the date
31 Of fading beauty; if it prove
32 But as long-lived as present love.
・ Waller, Edmond. "Of English Verse". The Poems Of Edmund Waller. London: 1893. 197--98. Accessed through ProQuest on May 27, 2022.
2021-03-17 Wed
■ #4342. Chaucer にみられる4体液説 [chaucer][humours][literature][me_text][four_cardinal_humours]
昨日の記事「#4341. Shakespeare にみられる4体液説」 ([2021-03-17-1]) に続き,西洋古代中世を通じて広く信じられていた4体液説 (the four humours) について.英文学において中世といえば,まず Chaucer の名前が挙がるが,Chaucer 文学においても4体液説は現役である.現役どころか,随所にそのパワーの炸裂をみることができる.
4種の体液のうち,現代まで最も強く当時の余韻と意味を保持しているのは黒胆汁 (melancholy) だろう.現代英語の melancholy という単語の語源は,ギリシア語 melas/melan- (black) + kholē (bile) に遡り,文字通り「黒胆汁」となる.この体液が過剰だと,人間はふさぎ込み「憂鬱」になるとされた.
Chaucer における melancholy の最たる事例の1つとして,The Canterbury Tales の Knight's Tale より,恋の病に陥った Arcite が「憂鬱」に犯されているシーンをみてみよう (I(A), 1361--76) .
His slep, his mete, his drynke, is hym biraft,
That lene he wex and drye as is a shaft;
His eyen holwe and grisly to biholde,
His hewe falow and pale as asshen colde,
And solitarie he was and evere allone,
And waillynge al the nyght, makynge his mone;
And if he herde song or instrument,
Thanne wolde he wepe, he myghte nat be stent.
So feble eek were his spiritz, and so lowe,
And chaunged so, that no man koude knowe
His speche nor his voys, though men it herde.
And in his geere for al the world he ferede
Nat oonly lik the loveris maladye
Of Hereos, but rather lyk manye,
Engendred of humour malencolik
Biforen, in his celle fantastic.
最後から2行目の humour malencolic が問題の箇所である.恋の病に陥った Arcite は,黒胆汁に犯されて狂人のようになっていたという.哀れな騎士の外見と心理を描写するのに,humour が一役買っている事例である.以上,Rogers (186--89) の Chaucer 百科事典より "Four Humours" の項を参照した.
・ Rogers, Shannon L. All Things Chaucer: Ann Encyclopedia of Chaucer's World. 2 vols. Westport, Connecticut and London: Greenwood, 2007.
2021-01-19 Tue
■ #4285. Shakespeare の英語史上の意義? [shakespeare][conversion][chaucer][bible]
Shakespeare の英文学史上の意義については言うまでもない(「英」を取り除いて,文学史上の意義といっても変わらないだろう).また,英国文化史上の意義も同じように甚大だろう.あまりに自明すぎて議論にもならない,という反応が多いにちがいない.
しかし,Shakespeare の英語史上の意義についてはどうだろうか.Shakespeare が英語という言語に与えたインパクト,と問い直してもよい.私は,上に述べた英文学史上,英国文化史上の意義と比べて,英語史上の意義はそれほど大きくないだろうと考えている.しかし,大学生の意見などを聞いていると,一般的に「英文学=英国文化=英語」という等式が成り立っているようで,Shakespeare の英語史上の意義もまた大きいという結論になることが圧倒的に多い.
誤解を招きそうなので先に断わっておく.Shakespeare が後世に残した表現(台詞,成句,諺,単語,語法など)の種類の豊富さについては,疑う余地はない.現代に至るまでの被引用頻度ということでいえば,聖書か Shakespeare かと言われるほどの絶対王者である.それほどの有名人であるから,英語史記述でも何かと登場する機会が多い.私自身も英語史概説の授業で初期近代英語を解説するに当たって,Shakespeare に触れずに済ますことはできない(cf. 「#1412. 16世紀前半に語彙的貢献をした2人の Thomas」 ([2013-03-09-1])).触れずに済ますにはもったいない存在である.
ただ,今回の議論のポイントは,Shakespeare の英語史上の意義である.Shakespeare が英語という言語にどれほど多種多様なインパクトを与えたか,である.上に述べたように,名句や語彙などの「表現」を英語において導入したり,広めたり,定着させたりしたことに関しては,その分だけ英語に影響を与えたと評価できる.しかし,英語という言語は,そのような「表現」のみから成り立っているわけではない.Shakespeare は,はたして当時および後の英語の発音に何らかのインパクトを与えただろうか.綴字についてはどうだろうか.また,文法についてはどうか.はたまた,語用についてはいかに.「表現」を除けば,Shakespeare が英語に直接的なインパクトを与えた部門はあまりないのではないかと疑っている.
直接的ではなく間接的なインパクトはどうだろうか.例えば,当時すでに慣習的に行なわれていた発音,綴字,文法,語用などが Shakespeare に採用され,Shakespeare という影響力のある媒体によって広められ,さらに広く行なわれるようになった,というようなことがあっただろうか.繰り返すが,「表現」に関しては,直接にも間接にもインパクトを与えたことはあったろう.しかし,英語を構成するそれ以外の言語部門へのインパクトというのは,どれだけあったのだろうか.例えば,言葉遊びの天才である Shakespeare は品詞転換 (conversion) を多用したが,だからといって彼が品詞転換という統語形態的な過程を英語にもたらした最初の人などではない.では,せめて同過程を英語に広めたり,定着させたりするのに一役買ったほどの働きはしたのだろうか.私には,Shakespeare その人ではなく,彼をその一員とする当時の英語共同体が,全体として同過程の流行に貢献したというように思われるのである(cf. 「#1414. 品詞転換はルネサンス期の精力と冒険心の現われか?」 ([2013-03-11-1])).
そもそも言語上の新機軸において個人が果たす役割とは,大きい役割であり得るのだろうか.「#2022. 言語変化における個人の影響」 ([2014-11-09-1]) で論じたように,フォスラー学派やイタリア新言語学では,個人の役割が重視されるものの,私としては,あったとしても限定的な役割にとどまるだろうと考えている.ただ,この本質的な言語論については,広く議論してみたいと思っている.
たとえ Shakespeare が「表現」という言語の表面的な部門にしか影響を与えていなかったとしても,それでも一個人がそこまでの影響を与えたというのは凄いことではないか,というコメントがあるとすれば,それには私も完全に賛同する.しかし,その点を強調して,Shakespeare が英語という言語(全体)に甚大なインパクトを与えたと表現するのは言い過ぎではないだろうか.Shakespeare が英語の何にどのくらい影響を与えたのか,それを過不足なく吟味するほうが,かえって Shakespeare の英語史上の意義を本当に評価することになるだろうと思っている.これは,英語史における聖書の意義や Chaucer の意義という問題とも共通している(cf. 「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1]),「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1]),「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2)」 ([2010-02-19-1])).
なお,1ヶ月ほど前に書いた「#4250. Shakespeare の言語の研究に関する3つの側面と4つの目的」 ([2020-12-15-1]) では,「Shakespeare の英語史上の意義を明らかにする」に対応する側面や目的には触れられていなかった.
2020-07-11 Sat
■ #4093. 標準英語の始まりはルネサンス期 [standardisation][renaissance][emode][sociolinguistics][chaucer][chancery_standard][spenser][ethnic_group]
英語史において,現代の標準英語 (Standard English) の直接の起源はどこにあるか.「どこにあるか」というよりも,むしろ論者が「どこに置くのか」という問題であるから,いろいろな見解があり得る.書き言葉の標準化の兆しが Chaucer の14世紀末に芽生え,"Chancery Standard" が15世紀前半に発達したこと等に言及して,その辺りの時期を近代の標準化の嚆矢とする見解が,伝統的にはある.しかし,現代の標準英語に直接連なるのは「どこ」で「いつ」なのかという問題は,標準化 (standardisation) とは何なのかという本質的な問題と結びつき,なかなか厄介だ.
Crowley (303--04) は,標準英語の形成に関する論考の序説として "Renaissance Origins" と題する一節を書いている.標準化のタイミングに関する1つの見方として,洞察に富む議論を提供しているので,まるまる引用したい.Thomas Wilson, George Puttenham, Edmund Spenser という16世紀の著名人の言葉を借りて,説得力のある標準英語起源論を展開している.
The emergence of the English vernacular as a culturally valorized and legitimate form took place in the Renaissance period. It is possible to trace in the comments of three major writers of the time the origins of a persistent set of problems which later became attached to the term "standard English." Following the introduction of Thomas Wilson's phrase "the king's English" in 1553, the principal statement of the idea of a centralized form of the language in the Renaissance was George Puttenham's determination in 1589 of the "natural, pure and most usual" type of English to be used by poets: "that usual speech of the court, and that of London and the shires lying about London, within lx miles and not much above" (Puttenham 1936: 144--5). In the following decade the poet and colonial servant Edmund Spenser composed A View of the State of Ireland (1596) during the height of the decisive Nine Years War between the English colonists in Ireland and the natives. In the course of his wide-ranging analysis of the difficulties facing English rule, Spenser offers a diagnosis of one of the most serious causes of English "degeneration" (a term often used in Tudor debates on Ireland to refer to the Gaelicization of the colonists): "first, I have to finde fault with the abuse of language, that is, for the speaking of Irish among the English, which, as it is unnaturall that any people should love anothers language more than their owne, so it is very inconvenient, and the cause of many other evils" (Spenser 1633: 47). Given Spenser's belief that language and identity were linked ("the speech being Irish, the heart must needes bee Irish), his answer was the Anglicization of Ireland. He therefore recommended the adoption of Roman imperial practice, since "it hath ever been the use of the Conquerour, to despise the language of the conquered, and to force him by all means to use his" (Spencer 1633: 47).
There are several notable features to be drawn from these Renaissance observations on English, a language which, it should be recalled, was being studied seriously and codified in its own right for the first time in this period. The first point is the social and geographic basis of Wilson and Puttenham's accounts. Wilson's phrase "the king's English" was formed by analogy with "the king's peace" and "the king's highway," both of which had an original sense of being restricted to the legal and geographic areas which were guaranteed by the crown; only with the successful centralization of power in the figure of the monarch did such phrases come to have general rather than specific reference. Puttenham's version of the "best English" is likewise demarcated in terms of space and class: his account reduces it to the speech of the court and the area in and around London up to a boundary of 60 miles. A second point to note is that Puttenham's definition conflates speech and writing: its model of the written language, to be used by poets, is the speech of courtiers. And the final detail is the implicit link between the English language and English ethnicity which is evoked by Spenser's comments on the degeneration of the colonist in Ireland. These characteristics of Renaissance thinking on English (its delimitation with regard to class and region, the failure to distinguish between speech and writing, and the connection between language and ethnicity) were characteristics which would be closely associated with the language throughout its modern history.
英国ルネサンスの16世紀に,(1) 階級的,地理的に限定された威信ある変種として,(2) 「話し言葉=書き言葉」の前提と,(3) 「言語=民族」の前提のもとで生み出された英語.これが現代まで連なる "Standard English" の直接の起源であることを,迷いのない文章で描き出している.授業で精読教材として使いたいほど,読み応えのある文章だ.同時代のコメントを駆使したプレゼンテーションと議論運びが上手で,内容もすっと受け入れてしまうような一節.このような文章を書けるようになりたいものだ.
上記の Puttenham の有名な一節については,「#2030. イギリスの方言差別と方言コンプレックスの歴史」 ([2014-11-17-1]) で原文を挙げているので,そちらも参照.
・ Crowley, Tony. "Class, Ethnicity, and the Formation of 'Standard English'." Chapter 30 of A Companion to the History of the English Language. Ed. Haruko Momma and Michael Matto. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2008. 303--12.
2020-05-28 Thu
■ #4049. 科学誌 Nature に掲載された The Canterbury Tales の系統学 [chaucer][reconstruction][manuscript][textual_transmission][family_tree][linguistics][philology]
言語学や文献学には,生物の系統図を思わせる樹 (tree) が様々なところに生えている.統語論の句構造樹,比較言語学の系統樹,写本の系統樹などである.3つめに挙げた写本の系統樹 (stemma) は,現存する写本間の世代,伝達,改変などに関する詳細な分析に基づいて,それらの関係を視覚化したものである(cf. 「#730. 写本文化の textual transmission」 ([2011-04-27-1]) ).主として特定のテキストの源泉を突き止めることを目的に stemma を作り上げていく写本系統学 (stemmatology) は,かつての英語文献学研究の花形だったといってよい.
写本系統学は現在ではさほど盛んではないが,新しい科学技術に支えられた革新的な取り組みもないわけではない.新しいといっても1998年の論文だが,科学誌 Nature に,進化生物学に用いられる技術を用いた,Chaucer のThe Canterbury Tales の写本に関する研究が掲載された.中世英語の記念碑的作品といってよい The Canterbury Tales は約80ほどの写本で現存している.そのうちの15世紀に書かれた58写本について,"The Wife of Bath's Prologue" のテキスト(850行)のデータをもとに計算処理を行ない,写本の系統関係を明らかにしようという試みだ.作業の過程で,複数の写本からのコピーである可能性があるなどの判断で14写本が外され,最終的には44写本に関する系統図の作成が試みられた.コンピュータによりはじき出された系統図に基づき,次のような結論が導き出されたという.
From this analysis and other evidence, we deduce that the ancestor of the whole tradition, Chaucer's own copy, was not a finished or fair copy, but a working draft containing (for example) Chaucer's own notes of passages to be deleted or added, and alternative drafts of sections. In time, this may lead editors to produce a radically different text of The Canterbury Tales. (Barbrook et. al 839)
まさか Chaucer も自分の作品(の批評)が科学誌に掲載されるとは夢にも思わなかったろう,と想像すると愉快である.
・ Barbrook, Adrian C., Chirstopher J. Howe, Norman Blake, and Peter Robinson. "The Phylogeny of The Canterbury Tales." Nature 394 (1998): 839.
2019-04-20 Sat
■ #3645. Chaucer を評価していなかった Dryden [popular_passage][dryden][chaucer][inflection][final_e]
17世紀後半の英文学の巨匠 John Dryden (1631--1700) が,3世紀ほど前の Chaucer の韻律を理解できていなかったことは,よく知られている.後期中英語から初期近代英語にかけてのこの時期には,"final e" に代表される屈折語尾に現われる無強勢母音が完全に消失し,「屈折の水平化」と呼ばれる英語史上の一大変化が完遂された.この変化の後の時代を生きていた Dryden は,変化が起こる前(正確にいえば,起こりかけていた)時代の Chaucer の音韻や韻律を想像することができなかったのである.Dryden は,Chaucer の詩行末に現われる final e を,17世紀の英語さながらに存在しないものと理解していた.結果として,Chaucer の韻律は Dryden の琴線に触れることはなかった.
上記のことは,Dryden 自身の Chaucer 評からわかる.Cable (25) 経由で,Dryden (Essays II: 258--59) の批評を引用しよう.
The verse of Chaucer, I confess, is not harmonious to us . . . there is the rude sweetness of a Scotch tune in it, which is natural and pleasing, though not perfect. It is true, I cannot go so far as he who published the last edition of him; for he would make us believe the fault is in our ears, and that there were really ten syllables in a verse where we find but nine. But this opinion is not worth confuting; it is so gross and obvious an errour, that common sense (which is rare in everything but matters of faith and revelation) must convince the reader, that equality of numbers in every verse which we call heroic, was either not known, or not always practiced in Chaucer's age.
Dryden の抱いていたような誤解は,その後2世紀ほどかけて文献学の進展により取り除かれることになったものの,final -e という形式的には小さな要素が,英語史においても英文学史においても,いかに大きな存在であったかが知られる好例だろう.
・ Cable, Thomas. "Restoring Rhythm." Chapter 3 of Approaches to Teaching the History of the English Language: Pedagogy in Practice. Introduction. Ed. Mary Heyes and Allison Burkette. Oxford: OUP, 2017. 21--28.
・ Dryden, John. Essays. Ed. W. P. Ker. Oxford: Clarendon, 1926.
2019-02-17 Sun
■ #3583. "halff chongyd Latyne" としての aureate terms [lydgate][chaucer][style][latin][aureate_diction][literature][terminology][rhetoric]
標題は "aureate diction" とも称される,主に15世紀に Lydgate などが発展させたラテン語の単語や語法を多用した「金ぴかな」文体である.この語法と John Lydgate (1370?--1450?) の貢献については「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]),「#2657. 英語史上の Lydgate の役割」 ([2016-08-05-1]) で取り上げたことがあった.今回は "aureate terms" の定義と,それに対する同時代の反応について見てみたい.
J. C. Mendenhall は,Areate Terms: A Study in the Literary Diction of the Fifteenth Century (Thesis, U of Pennsylvania, 1919) のなかで,"those new words, chiefly Romance or Latinical in origin, continually sought under authority of criticism and the best writers, for a rich and expressive style in English, from about 1350 to about 1530" (12) と定義している.Mendenhall は,Chaucer をこの新語法の走りとみなしているが,15世紀の Chaucer の追随者,とりわけスコットランドの Robert Henryson や William Dunbar がそれを受け継いで発展させたとしている.
しかし,後に Nichols が明らかにしたように,aureate terms を大成させた最大の功労者は Lydgate といってよい.そもそも aureat(e) という形容詞を英語に導入した人物が Lydgate であるし,この形容詞自体が1つの aureate term なのである.さらに,MED の aurēāt (adj.) を引くと,驚くことに,挙げられている20例すべてが Lydgate の諸作品から取られている.
この語法が Lydgate と強く結びつけられていたことは,同時代の詩人 John Metham の批評からもわかる.Metham は,1448--49年の Romance of Amoryus and Cleopes のエピローグのなかで,詩人としての Chaucer と Lydgate を次のように評価している(以下,Nichols 520 より再引用).
(314)
And yff I the trwthe schuld here wryght,
As gret a style I schuld make in euery degre
As Chauncerys off qwene Eleyne, or Cresseyd, doth endyght;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(316)
For thei that greyheryd be, affter folkys estymacion,
Nedys must be more cunne, be kendly nature,
Than he that late begynnyth, as be demonstration,
My mastyr Chauncerys, I mene, that long dyd endure
In practyk off rymyng;---qwerffore proffoundely
With many prouerbys hys bokys rymyd naturally.
(317)
Eke Ion Lydgate, sumtyme monke off Byry,
Hys bokys endyted with termys off retoryk
And halff chongyd Latyne, with conseytys fantastyk,
But eke hys qwyght her schewyd, and hys late werk,
How that hys contynwaunz made hym both a poyet and a clerk.
端的にいえば,Metham は Chaucer は脚韻の詩人だが,Lydgate は aureate terms の詩人だと評しているのである.そして,引用の終わりにかけての箇所に "termys off retoryk / And halff chongyd Latyne, with conseytys fantastyk" とあるが,これはまさに areate terms の同時代的な定義といってよい.それにしても "halff chongyd Latyne" とは言い得て妙である.「#3071. Pig Latin」 ([2017-09-23-1]) を想起せずにいられない.
・ Nichols, Pierrepont H. "Lydgate's Influence on the Aureate Terms of the Scottish Chaucerians." PMLA 47 (1932): 516--22.
2019-01-14 Mon
■ #3549. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」 [asacul][chaucer][proverb][hel_education][slide][link]
「#3531. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」のお知らせ」 ([2018-12-27-1]) で告知したように,1月12日(土)に同タイトルで講座を開きました.参加された方におかれましては,600年も前のチョーサーの英語が,現代英語の知識で意外と読めることが分かったのではないでしょうか.むしろ,チョーサーの英語と比較しながら,現代英語の理解が深まることにも気づいたのではないかと思います.次のようなメニューで話しました.
1. まずは General Prologue の冒頭を音読
2. チョーサーと『カンタベリ物語』
3. 中英語期の言語事情
4. 『カンタベリ物語』の言語
5. General Prologue の冒頭を精読
6. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問
講座で使用したスライド資料をこちらにアップしておきます.また,スライドのページごとのリンクも以下に張っておきます.スライド中からも本ブログの関連記事へリンクを豊富に張りつけていますので,ご参照ください.
1. シリーズ「英語の歴史」第1回 中世の英語チョーサー『カンタベリ物語』
2. 本講座のねらい
3. Ellesmere MS, fol. 1r
4. General Prologue の冒頭18行 (Benson)
5. 現代英語訳 (市河・松浪,p. 191)
6. 西脇(訳)「ぷろろぐ」より (pp. 7--8)
7. チョーサーと『カンタベリ物語』
8. 中英語期の言語事情
9. ノルマン征服から英語の復権までの略史 (#131)
10. 『カンタベリ物語』の言語
11. General Prologue の冒頭を精読
12. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問
13. 異なる写本を覗いてみる(第7行目に注目)
14. まとめ
15. 参考文献
2018-12-27 Thu
■ #3531. 講座「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」のお知らせ [notice][chaucer][asacul][link]
1月12日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,「英語の歴史」と題するシリーズ講座の第1弾として「中世の英語 チョーサー『カンタベリ物語』」を開講します.以下,お知らせの文章です.
英詩の父と称されるジェフリー・チョーサーによる中世英文学の傑作『カンタベリ物語』の総序の冒頭を,英語史の知識を補いながら中英語の原文で味わいます.冒頭箇所は英文学史上に名高い文章とされ,その格調高さや小気味よい韻律を最大限に堪能するためには,原文に触れることが欠かせません.チョーサーの英文は,少々のコツさえつかめば,現代英語の知識を頼りに読み進めることが十分に可能です.本講座で,中世イングランドの風景を覗いてみましょう.
1. ジェフリー・チョーサーの時代のイングランド
2. 『カンタベリ物語』の構造
3. 『カンタベリ物語』の韻律
4. 有名な冒頭部分を音読する
5. 冒頭部分を英語史的に読む
6. 中英語から解きほぐす現代英語の疑問
冒頭のみではありますが,『カンタベリ物語』を原文で読みたい方,中英語というものに触れてみたい方,具体的な文学作品を通じて英語史を堪能したい方,現代英語の謎に英語史の観点から迫りたい方など,英語・英文学に関心がありさえすれば,きっと楽しめます.ふるってご参加ください.
Chaucer に関しては本ブログでも chaucer の諸記事で直接・間接に多く取り上げてきましたが,とりわけ以下の話題が本講座と関係が深いので,ご参照ください.
・ 「#290. Chaucer に関する Web resources」 ([2010-02-11-1])
・ 「#257. Chaucer が英語史上に果たした役割とは?」 ([2010-01-09-1])
・ 「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2) 」 ([2010-02-19-1])
・ 「#534. The General Prologue の冒頭の現在形と完了形」 ([2010-10-13-1])
・ 「#791. iambic pentameter のスキャン」 ([2011-06-27-1])
・ 「#2275. 後期中英語の音素体系と The General Prologue」 ([2015-07-20-1])
・ 「#2667. Chaucer の用いた語彙の10--15%がフランス借用語」 ([2016-08-15-1])
・ 「#2788. General Prologue の第7行目の写本間比較」 ([2016-12-14-1])
・ 「#3449. Chaucer 関連年表」 ([2018-10-06-1])
2018-10-06 Sat
■ #3449. Chaucer 関連年表 [chaucer][timeline]
Fisher and Allen の見返しにある "A Chaucer Chronology" を再現する.Chaucer が公職で最も忙しかった時期に,創作活動が活発化しているということがわかる.1380年代?1390年代が,The Canterbury Tales の執筆を含む,最も脂ののった時期である.
| 1327 | Edward III crowned, age 14. | ||
| 1328 | Edward marries Philippa of Hainault; Sir Paon de Roet in her entourage. | ||
| 1330 | Birth of Edward, the Black Prince. | ||
| 1331 | England at war with Scotland; France intervenes on behalf of Scotland. | ||
| 1338 | Unsuccessful invasion of northern France (beginning of Hundred Years' War); John Chaucer (Geoffrey's father) in the King's company. | ||
| 1340 | (?)Birth of Geoffrey Chaucer. Birth of John of Gaunt. Edward III takes title "King of France" | ||
| 1346 | Battle of Crécy | ||
| 1348 | Black Death | ||
| 1356 | Battle of Poitiers; high point of England's success in the wars with France. | ||
| 1357 | First record of Chaucer: in household of Countess of Ulster, wife of Prince Lionel. Philippa Pan' also in household. | ||
| 1359 | May: (?) Chaucer at wedding of John of Gaunt and Blanche of Lancaster. Gaunt becomes Duke of Lancaster. After November 3: Chaucer in French war in Prince Lionel's company. | ||
| 1360 | Chaucer captured and ransomed by the King. | ||
| 1361 | Black Prince marries Joan of Kent. (?) Chaucer at Inns of Chancery. | Prier a Nostre Dame; Romaunt of the Rose; early Complaints (--1367) | |
| 1363 | Death of Countess of Ulster. (?) Philippa Pan' enters service of Queen Philippa. (?) Chaucer at Inns of Court. | ||
| 1366 | February 22--May 24: safe conduct for Chaucer to travel in Spain. Philippa Chaucer (so designated) granted royal annuity of 10 marks. | ||
| 1367 | Geoffrey Chaucer granted royal annuity of of 20 marks. Chaucer enters the King's service. | ||
| 1368 | Death of Blanche, Duchess of Lancaster. French war active. Chaucer on mission in France. | Book of the Duchess (--1369) | |
| 1369 | Chaucer with Gaunt in raid on Picardy. Death of Queen Philippa. (?) Philippa Chaucer enters Gaunt's household. | ||
| 1370 | June 20--September 29: Chaucer on mission in France, (?) with Gaunt in Aquitaine. | ||
| 1371 | Gaunt marries Princess Costanza of Castile. | ||
| 1372 | Katherine Swynford, sister of Philippa Chaucer, bears first son by Gaunt. August 30: Gaunt grants Philippa Chaucer annuity of ?10. December 1: Chaucer leaves for Genoa, visits Florence. (Boccaccio in Florence; Petrarch in Padua.) | Parliament of Fowls; St. Cecilia; Monk's tragedies; Anelida (--1377) | |
| 1373 | May 23: Chaucer returns to London. (?) Birth of Thomas Chaucer. July 13: Gaunt goes to French wars. | ||
| 1374 | April 10: Gaunt returns from French wars. April 23: Chaucer receives a royal grant of a pitcher of wine daily. May 10: Chaucer leases Aldgate house and sets up housekeeping. June 8: Chaucer made controller of customs. June 13: Geoffrey and Philippa receive ?10 annuity from Gaunt. | ||
| 1376 | Death of Black Prince. Chaucer on mission to Calais. | ||
| 1377 | February 17, April 30: Chaucer on missions in France concerning peace treaty and marriage of Richard. June 22: death of Edward III and accession of his grandson, Richard II, age 10. Government controlled by Gaunt. | ||
| 1378 | January 16--March 9: Chaucer in France concerning marriage of Richard to French king's daughter Marie. April 18: daily pitcher of wine replaced by annuity of 20 marks. May 28--September 19: Chaucer in Lombardy to treat with Barnado Visconti (Gower given Chaucer's power of attorney). | House of Fame; Boece; Boethian balades; Palamon and Arcite (--1381) | |
| 1380 | May 1: Chaucer released from suit for "raptus" of Cecily Champain. (?) Birth of Lewis Chaucer. | ||
| 1381 | Peasants' Revolt. June 19: deed of Geoffrey Chaucer, son of John Chaucer, vintner of London, quitclaiming his father's house. | ||
| 1382 | Richard II marries Anne of Bohemia. | Troylus and Criseyde; Legend of Good Women (--1386) | |
| 1383 | Chaucer obtains first loan against his annuity. | ||
| 1385 | October 12: Chaucer appointed justice of the peace in Kent. Political struggle between Gaunt and his brother, Thomas of Woodstock. September: death of Joan of Kent. | ||
| 1386 | Justice of peace reaffirmed. February 19: Philippa admitted to fraternity of Lincoln Cathedral. August: Chaucer elected member of parliament from Kent. October 5: Aldgate house rented to Richard Forester. October 15: Scrope-Grosvenor trial. December 4: Adam Yardley appointed controller of customs. | Canterbury Prologue; early Tales (Knight, Part VII) (--1387) | |
| 1387 | June 18: last payment of annuity of Philippa Chaucer. | ||
| 1388 | May 1: Chaucer surrenders his royal annuities to John Scalby of Lincolnshire. | Fabliaux (Miller, Reeve) (--1389) | |
| 1389 | King Richard assumes power. Chaucer appointed clerk of the King's works (more than ?30 a year). | ||
| 1390 | Commissions to repair St. George's Chapel, Windsor; to oversee repairs on the lower Thames sewers and conduits; to build bleachers for jousts at Smithfield, etc. The three robberies. Chaucer appointed subforester of North Petherton, Somerset. | Marriage group (Wife of Bath, Friar, Summoner, Merchant, Clerk, Franklin); Astrolabe; Equatorie (--1394) | |
| 1391 | June 17: another clerk of the works appointed. | ||
| 1393 | Chaucer granted a gift of ?10 from Richard for services rendered "in this year now present." | ||
| 1394 | Death of Queen Anne. Chaucer granted a new annuity of ?20. | ||
| 1395 | Richard marries Isabella of France. Thomas Chaucer marries heiress Maud Burghersh. | ||
| 1396 | John of Gaunt marries Katherine Swynford. | Balades to Scogan, Bukton (--1399) | |
| 1398 | Chaucer borrows against his annuity; action for debt against Chaucer; letters of protection from the King. | ||
| 1399 | Deposition of Richard II. Election of Henry IV. Death of John of Gaunt. October 13: on his coronation day, Henry doubles Chaucer's annuity. December 24: Chaucer signs 53-year lease for tenement in the garden of the Lady Chapel, Westminster Abbey. | ||
| 1400 | September 29: last record of Chaucer: quittance given by him for a tun of wine received. October 25: date of Chaucer's death on tombstone in Westminster Abbey (erected in 1556) |
・ Fisher, John H. and Mark Allen, eds. The Complete Canterbury Tales of Geoffrey Chaucer. Boston: Thomson Wadsworth, 2006.
2018-03-13 Tue
■ #3242. ランカスター朝の英語国語化のもくろみと Chancery Standard (2) [standardisation][politics][monarch][chancery_standard][lancastrian][chaucer][lydgate][hoccleve][language_planning]
[2018-02-24-1]の記事に引き続いての話題.昨日の記事「#3241. 1422年,ロンドン醸造組合の英語化」 ([2018-03-12-1]) で引用した Fisher は,ランカスター朝が15世紀初めに政策として英語の国語化と Chancery Standard の確立・普及に関与した可能性について,積極的な議論を展開している.確かにランカスター朝の王がそれを政策として明言した証拠はなく,Hoccleve や Lydgate にもその旨の直接的な言及はない.しかし,十分な説得力をもつ情況証拠はあると Fisher は論じる.その情況証拠とは,およそ Chancery Standard が成長してきたタイミングに関するものである.
Hoccleve, no more than Lydgate, ever articulated for the Lancastrian rulers a policy of encouraging the development of English as a national language or of citing Chaucer as the exemplar for such a policy. But we have the documentary and literary evidence of what happened. The linkage of praise for Prince Henry as a model ruler concerned about the use of English and for master Chaucer as the "firste fyndere of our faire langage"; the sudden appearance of manuscripts of The Canterbury Tales, Troylus and Criseyde, and other English writings composed earlier but never before published; the conversion to English of the Signet clerks of Henry V, the Chancery clerks, and eventually the guild clerks; and the burgeoning of composition in English and the patronage of literature in English by the Lancastrian court circle are all concurrent historical events. The only question is whether their concurrence was coincidental or deliberate. (34)
特に Chaucer の諸作品の写本が現われてくるのが14世紀中ではなく,15世紀に入ってからという点が興味深い.Chaucer は1400年に没したが,その後にようやく写本が現われてきたというのは偶然なのだろうか.あるいは,「初めて英語で偉大な作品を書いた作家」を持ち上げることによって,対外的にイングランドを誇示しようとした政治的なもくろみの結果としての出版ではなかったか.(関連して,Hoccleve による Chaucer の評価 ("firste fyndere of our faire langage") について「#298. Chaucer が英語史上に果たした役割とは? (2)」 ([2010-02-19-1]) を参照.)
Fisher は,このような言語政策は古今東西ありふれていることを述べつつ自説を補強している.
All linguistic changes of this sort for which we have documentation---in Norway, India, Canada, Finland, Israel, or elsewhere---have been the result of planning and official policy. There is no reason to suppose that the situation was different in England.
・ Fisher, John H. "A Language Policy for Lancastrian England." Chapter 2 of The Emergence of Standard English. John H. Fisher. Lexington: UP of Kentucky, 1996. 16--35.
2018-02-17 Sat
■ #3218. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」 [slide][spelling][spelling_pronunciation_gap][norman_conquest][chaucer][manuscript][reestablishment_of_english][timeline][me_dialect][minim][orthography][standardisation][digraph][hel_education][link][asacul]
朝日カルチャーセンター新宿教室で開講している講座「スペリングでたどる英語の歴史」も,全5回中の3回を終えました.2月10日(土)に開かれた第3回「515通りの through --- 中英語のスペリング」で用いたスライド資料を,こちらにアップしておきました.
今回は,中英語の乱立する方言スペリングの話題を中心に据え,なぜそのような乱立状態が生じ,どのようにそれが後の時代にかけて解消されていくことになったかを議論しました.ポイントとして以下の3点を指摘しました.
・ ノルマン征服による標準綴字の崩壊 → 方言スペリングの繁栄
・ 主として実用性に基づくスペリングの様々な改変
・ 中英語後期,スペリング再標準化の兆しが
全体として,標準的スペリングや正書法という発想が,きわめて近現代的なものであることが確認できるのではないかと思います.以下,スライドのページごとにリンクを張っておきました.その先からのジャンプも含めて,リンク集としてどうぞ.
1. 講座『スペリングでたどる英語の歴史』第3回 515通りの through--- 中英語のスペリング
2. 要点
3. (1) ノルマン征服と方言スペリング
4. ノルマン征服から英語の復権までの略史
5. 515通りの through (#53, #54), 134通りの such
6. 6単語でみる中英語の方言スペリング
7. busy, bury, merry
8. Chaucer, The Canterbury Tales の冒頭より
9. 第7行目の写本間比較 (#2788)
10. (2) スペリングの様々な改変
11. (3) スペリングの再標準化の兆し
12. まとめ
13. 参考文献
2018-01-26 Fri
■ #3196. 中英語期の主要な出来事の年表 [timeline][me][history][chronology][norman_conquest][reestablishment_of_english][monarch][hundred_years_war][black_death][wycliffe][chaucer][caxton]
「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]) に引き続き,中英語期の主要な出来事の年表を,Algeo and Pyles (123--24) に拠って示したい,
| 1066 | The Normans conquered England, replacing the native English nobility with Anglo-Normans and introducing Norman French as the language of government in England. |
| 1204 | King John lost Normandy to the French, beginning the loosening of ties between England and the Continent. |
| 1258 | King Henry III was forced by his barons to accept the Provisions of Oxford, which established a Privy Council to oversee the administration of the government, beginning the growth of the English constitution and parliament. |
| 1337 | The Hundred Years' War with France began and lasted until 1453, promoting English nationalism |
| 1348--50 | The Black Death killed an estimated one-third of England's population, and continued to plague the country for much of the rest of the century |
| 1362 | The Statute of Pleadings was enacted, requiring all court proceedings to be conducted in English. |
| 1381 | The Peasants' Revolt led by Wat Tyler was the first rebellion of working-class people against their exploitation; although it failed in most of its immediate aims, it marks the beginning of popular protest. |
| 1384 | John Wycliffe died, having promoted the first complete translation of scripture into the English language (the Wycliffite Bible). |
| 1400 | Geoffrey Chaucer died, having produced a highly influential body of English poetry. |
| 1476 | William Caxton, the first English printer, established his press at Westminster, thus beginning the widespread dissemination of English literature and the stabilization of the written standard. |
| 1485 | Henry Tudor became king of England, ending thirty years of civil strife and initiating the Tudor dynasty. |
中英語の外面史は,まさに英語の社会的地位の没落とその後の復権に特徴づけられていることがよくわかる.
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow