2024-09-25 Wed
■ #5630. 語源学とは何か? --- 『英語語源辞典』 (p. 1647) より [hellive2024][khelf][kdee][etymology][terminology][archaeology][history][philology][methodology][lexicology][historical_linguistics][comparative_linguistics]
一昨日の Voicy heldio にて「#1212. 『英語語源辞典』の「語源学解説」精読 --- 「英語史ライヴ2024」より」を配信しました.これは,9月8日に heldio を媒体として開催された「英語史ライヴ2024」の午前9時過ぎから生配信された精読会のアーカイヴ版です.研究社より出版されている『英語語源辞典』の巻末の専門的な解説文を,皆で精読しながら解読していこうという趣旨の読書会です.当日は多くのリスナーの方々に生配信でお聴きいただきました.ありがとうございました.
khelf の藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生)が MC を務め,そこに「英語語源辞典通読ノート」で知られる lacolaco さん,およびまさにゃんこと森田真登さんが加わり,45分間の集中精読会が成立しました.ニッチな企画ですが,非常に濃い議論となっています.『英語語源辞典』のファンならずとも楽しめる配信回だと思います.ぜひお聴きください.以下は,精読対象となった文章の最初の2段落です (p. 1647) .
1. 語源学とは何か
語源学の目的は,特定言語の単語の音形(発音・綴り字)と意味の変化の過程を可能なかぎり遡ることによって,文献上または文献以前の最古の音形と意味を同定または推定し,その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある.したがって,語源学はフィロロジーの一分科あるいは語彙論に属するが,その方法論と実践とにおいて,歴史・比較言語学と密接に関連し,また歴史的考証や考古学の成果をも援用する.
英語の場合であれば,現代英語から中期英語 (Middle English: 略 ME),古期英語 (Old English: 略 OE) の段階にまで遡る語史的語源的研究と,さらに英語の成立以前に遡ってゲルマン基語 (proto-Germanic: 略 Gmc),印欧基語 (Proto-Indo-European: 略 IE) の段階を扱う遡源的語源研究とが考えられる.ある単語の語源を特定するためには,この両面を通じて,形態の連続性と同時に意味の連続性が確認されなければならない.そして,英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう.
上記配信回を受けて,私の感想です.この2段落は,実はかなり難解だと思います.2点を指摘します.1つめに「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」をすんなりと理解できる読者は少ないのではないでしょうか.私自身もこの文の字面の「意味」は理解したとしても,それがどのような「意義」をもつのかを理解するには少々の時間を要しましたし,その理解が当たっているのかどうかも心許ないところです.
2つめは,最後の部分「英語という言語が成立した後の語史的考察が英語成立以前の遡源的考察に先行すべきこと,すわなち英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべきことはいうまでもないであろう」です.この箇所については,本当にいうまでもないほど自明なのだろうか,という疑問が生じます.というのは,時間的にみる限り,語史的考察は遡源的考察に先行しないからです.それなのに「英語史的研究が比較言語学的研究に先行すべき」というのは,むしろ矛盾しているように聞こえないでしょうか.この2点目については,この後の段落を読めば,確かに真意がわかってきます.いずれにせよ,なかなかの水準の高い最初の2段落ではないでしょうか.
1点目について私は考えるところがあるのですが,皆さんも改めて「語源学の目的は〔中略〕その言語の語彙組織におけるその語の位置を通時的に決定することにある」の解釈を考えていただければと思います.
語源学とは何か? という問いについては,hellog より以下の記事を参照.
・ 「#466. 語源学は技芸か科学か」 ([2010-08-06-1])
・ 「#727. 語源学の自律性」 ([2011-04-24-1])
・ 「#1791. 語源学は技芸が科学か (2)」 ([2014-03-23-1])
・ 「#598. 英語語源学の略史 (1)」 ([2010-12-16-1])
・ 「#599. 英語語源学の略史 (2)」 ([2010-12-17-1])
ここまでのところで『英語語源辞典』に関心をもった方は,ぜひ入手していただければ.

・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.
2024-07-05 Fri
■ #5548. 音変化と類推の峻別を改めて考える [sound_change][analogy][neogrammarian][phonetics][phonology][morphology][language_change][history_of_linguistics][comparative_linguistics][lexical_diffusion][terminology]
比較言語学 (comparative_linguistics) の金字塔というべき,青年文法学派 (neogrammarian) による「音韻変化に例外なし」の原則 (Ausnahmslose Lautgesetze) は,音変化 (sound_change) と類推 (analogy) を峻別したところに成立した.以来,この言語変化の2つの原理は,相容れないもの,交わらないものとして解釈されてきた.この2種類を一緒にしたり,ごっちゃにしたら伝統的な言語変化論の根幹が崩れてしまう,というほどの厳しい区別である.
しかし,この伝統的なテーゼに対する反論も,断続的に提出されてきた.例外なしとされる音変化も,視点を変えれば一律に適用された類推として解釈できるのではないか,という意見だ.実のところ,私自身も語彙拡散 (lexical_diffusion) をめぐる議論のなかで,この2種類の言語変化の原理は,互いに接近し得るのではないかと考えたことがあった.
この重要な問題について,Fertig (99--100) が議論を展開している.Fertig は2種類を峻別すべきだという伝統的な見解に立ってはいるが,その議論はエキサイティングだ.今回は,Fertig がそのような立場に立つ根拠を述べている1節を引用する (95) .単語の発音には強形や弱形など数々の異形 (variants) があるという事例紹介の後にくる段落である.
The restriction of the term 'analogical' to processes based on morpho(phono)logical and syntactic patterns has long since outlived its original rationale, but the distinction between changes motivated by grammatical relations among different wordforms and those motivated by phonetic relations among different realizations of the same wordform remains a valid and important one. The essence of the Neogrammarian 'regularity' hypothesis is that these two systems are separate and that they interface only through the mental representation of a single, citation pronunciation of each wordform. The representations of non-citation realizations are invisible to the morphological and morphophonological systems, and relations among different wordforms are invisible to the phonetic system. If we keep in mind that this is really what we are talking about when we distinguish analogical change from sound change, these traditional terms can continue to serve us well.
言語変化を論じる際には,一度じっくりこの問題に向き合う必要があると考えている.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-07-02 Tue
■ #5545. 古英語の定冠詞・疑問詞の具格 [oe][article][determiner][interrogative_pronoun][case][instrumental][inflection][etymology][comparative_linguistics][germanic]
昨日の記事「#5544. 古英語の具格の機能,3種」 ([2024-07-01-1]) に引き続き,具格 (instrumental) について.古英語の定冠詞(あるいは決定詞) (definite article or determiner) の屈折表を「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1]) で示した.それによると,þȳ, þon といった独自の形態をとる具格形があったことがわかる.同様に疑問(代名)詞 (interrogative_pronoun) についても,その屈折表を「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]) に示した.そこには hwȳ という具格形が見られる.
Lass (144) によると,これらの具格形は比較言語学的にも,直系でより古い形に遡るのが難しいという.純粋な語源形が突きとめにくいようだ.この辺りの事情を,直接 Lass に語ってもらおう.
There are remains of what is usually called an 'instrumental' in the masculine and neuter sg; this term as Campbell remarks 'is traditional, but reflects neither their origin nor their prevailing use' (1959: §708n). The two forms are þon, þȳ, neither of which is historically transparent. In use they are most frequent in comparatives, e.g. þȳ mā 'the more' (cf. ModE the more, the merrier), and as alternatives to the dative in expressions like þȳ gēare '(in) this year'. There is probably some relation to the 'instrumental' interrogative hwȳ 'why?', which in sense is a real one (= 'through/by what?'), but the /y:/ is a problem; hwȳ has an alternative form hwī, which is 'legitimate' in that it can be traced back to the interrogative base */kw-/ + deictic */ei/.
比較言語学の手に掛かっても,すべての語源を追いかけて明らかにすることは至難の業のようだ.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
・ Campbell, A. Old English Grammar. Oxford: OUP, 1959.
2024-07-01 Mon
■ #5544. 古英語の具格の機能,3種 [oe][noun][pronoun][adjective][article][demonstrative][determiner][case][inflection][instrumental][dative][comparative_linguistics]
古英語には名詞,代名詞,形容詞などの実詞 (substantive) の格 (case) として具格 (instrumental) がかろうじて残っていた.中英語までにほぼ完全に消失してしまうが,古英語ではまだ使用が散見される.
具格の基本的な機能は3つある.(1) 手段や方法を表わす用法,(2) その他,副詞としての用法,(3) 時間を表わす用法,である.Sweet's Anglo-Saxon Primer (47) より,簡易説明を引用しよう.
Instrumental
88. The instrumental denotes means or manner: Gāius se cāsere, ōþre naman Iūlius 'the emperor Gaius, (called) Julius by another name'. It is used to form adverbs, as micle 'much, by far', þȳ 'therefore'.
It often expresses time when: ǣlċe ȝēare 'every year'; þȳ ilcan dæȝe 'on the same day'.
具格はすでに古英語期までに衰退してきていたために,古英語でも出現頻度は高くない.形式的には与格 (dative) の屈折形に置き換えられることが多く,残っている例も副詞としてなかば語彙化したものが少なくないように思われる.比較言語学的な観点からの具格の振る舞いについては「#3994. 古英語の与格形の起源」 ([2020-04-03-1]) を参照されたい.ほかに具格の話題としては「#811. the + 比較級 + for/because」 ([2011-07-17-1]) と「#812. The sooner the better」 ([2011-07-18-1]) も参照.
・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.
2024-02-21 Wed
■ #5413. ゲルマン祖語と古英語の1人称単数代名詞 [comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][reconstruction][paradigm][oe][indo-european][rhotacism][analogy][sound_change]
Hogg and Fulk (202--203) を参照して,ゲルマン祖語 (Proto-Germanic) と古英語 (Old English) の1人称単数代名詞の格屈折を並べて示す.
| PGmc | OE | |
|---|---|---|
| Nom. | *ik | iċ |
| Acc. | *mek | mē |
| Gen. | *mīnō | mīn |
| Dat. | *miz | mē |
表の左側の PGmc の各屈折が,いかにして右側の OE の形態へ変化したか.ここにはきわめて複雑な類推 (analogy や音変化 (sound_change) やその他の過程が働いているという.Hogg and Fulk (203) の解説をそのまま引用しよう.
nom.sg.: *ik must have been the unstressed form, with analogical introduction of its vowel into the stressed form, with only ON ek showing retention of the original stressed vowel amongst the Gmc languages (cf. Lat egō/ǒ).
acc.sg.: *mek is the stressed form; all the other Gmc languages show generalization of unstressed *mik. The root is *me-, with the addition of *-k borrowed from the nom. The form mē could be due to loss of *-k when *mek was extended to unstressed positions, with lengthening of the final vowel when it was re-stressed . . . . More likely it represents replacement of the acc. by the dat. . . . as happened widely in Gmc and IE . . . .
gen.sg.: To the root *me- was added the adj. suffix *-īn- (cf. stǣnen 'made of stone' < *stain-īn-a-z . . .), presumably producing *mein- > *mīn- . . . . To this was added an adj. ending, perhaps nom.acc.pl. neut. *-ō, as assumed here.
dat.sg.: Unstressed *miz developed in the same way as *hiz . . . .
最後のところの PGmc *miz が,いかにして OE mē になったのかについて,Hogg and Fulk (198) を参照して補足しておこう.これはちょうど3人称男性単数主格の PGmc *hiz が OE *hē へ発達したのと平行的な発達だという.*hiz の z による下げの効果で *hez となり,次に語末子音が rhotacism を経て *her となった後に消失して *he となり,最後に強形として長母音化した hē に至ったとされる.
人称代名詞は高頻度の機能語として強形と弱形の交替が激しいともいわれるし,次々に新しい強形と弱形が生まれ続けるともされる.上記の解説を事情を概観するだけでも,比較言語学の難しさが分かる.関連して,以下の記事も参照.
・ 「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1])
・ 「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])
・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])
・ 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])
・ 「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])
・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2024-02-16 Fri
■ #5408. 3人称代名詞はゲルマン祖語の共通基語に遡れない [indo-european][comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][german][reconstruction]
英語の3人称代名詞 he, she, it, they (各々は主格の形)の屈折体系は現代でも複雑なほうだが,歴史的にも相当にかき混ぜられてきた経緯がある.対応する古英語の主格形を挙げれば,それぞれ hē, hēo, hit, hīe となるが,見た目だけでも現代との差が大きいことが分かる (cf. 「#155. 古英語の人称代名詞の屈折」 ([2009-09-29-1])).
ゲルマン諸語の人称代名詞体系を比べると,全体として類似しているとはいえ,とりわけ3人称の個々の格形については,必ずしも同一の語源に遡るわけではない.ましてや印欧祖語まで遡らせることもできない.つまり,1つの共通基語を再建することができないということになる.3人称代名詞は,この点で1,2人称代名詞や,指示詞,疑問詞などとは事情が異なる.Lass (139) より関連する説明を引用しよう.
Proto-Germanic did not inherit a fully coherent pronoun or determiner system; nothing quite like this reconstructs even for Proto-IE. Rather the collections labelled 'pronouns' or 'articles' or 'demonstratives' in the handbooks represent dialect-specific selections out of a mass of inherited forms and systems. There are clear IE first-, second-person pronoun systems: we can easily identify a first-person nom sg root */H1egh-/ (l eg-o, Go ik, OE ic 'I') and a second-person root in */t-/ (L tu, OCS ty, OE þū). There is also an interrogative in */kw-/ (L qu-is, OE hw-ā 'who?') and a deictic in */to-/ (Go to 'def art, masc nom sg', OE þæ-s 'def art m/n gen sg'). There is no reconstructable third-person pronoun, however. The personal pronouns may be heterogeneous even across Germanic: Go is, OE hē 'he' are not cognate. But overall the main systems are related, at least in outline.
これは何を意味するのだろうか? 3人称代名詞が他よりも後発であることを示唆するのだろうか? 冒頭に述べたように,英語史では歴史時代に限っても同語類は大きくかき混ぜられてきたという経緯がある.ということは,言語間・方言間の借用や体系内組み替えが頻繁な語類であるということなのだろうか?
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2024-01-30 Tue
■ #5391. 「いのほたチャンネル」リニューアル初回は「グリムの法則」 [grimms_law][inohota][notice][comparative_linguistics][indo-european][germanic][sound_change]
「#5388. YouTube 「いのほたチャンネル」で200回記念として初めてのライヴ配信を行ないました」 ([2024-01-27-1]) で紹介したように,記念すべき200回をライヴ配信でお届けしました.その後,300回に向けての新たな一歩として,一昨日の18時に第201回を配信しました.オープニングやエンディングを含め,いろいろとリニューアルしています(←すべて井上逸兵さんにお任せ)ので,ぜひご覧ください.
言語学の古典・基本シリーズのつもりで,堀田がグリムの法則 (grimms_law) で有名なドイツの比較言語学者 Jacob Grimm (1785--1863) を紹介しています.「リニューアルしました!言語学者グリム兄弟の偉業とは?ーなぜ童話を収集?」です(14分ほどの動画).
「グリムの法則」の入門というよりもグリム(兄弟)の入門という内容でしたが,今後は法則自体にも注目していきたいと思います.この hellog でも,すでに grimms_law の各記事で取り上げていますので,予習や復習に役立てていただければ.
グリムの法則は,比較言語学的にも謎の多い音変化です.現代の比較言語学者 Ringe (93--94) の評を挙げておきましょう.
It remains unclear whether Grimm's Law was, in any sense, a unitary natural sound change, or a series of changes that need not have occurred together. It is true that no sound change can be shown to have occurred between any of the components of Grimm's Law; but since Grimm's Law was among the earliest Germanic sound changes, and since the other early changes that involved single non-laryngeal obstruents affected only the place of articulation and rounding of dorsals, that could be an accident. In any case, Grimm's Law is most naturally presented as a sequence of changes that counterfed each other.
・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.
2024-01-29 Mon
■ #5390. 印欧語における word, root, stem, theme, ending [morphology][indo-european][germanic][comparative_linguistics][reconstruction][terminology][inflection][oe]
どの学問分野でもよくあることだが,印欧語比較言語学においても専門家にしか通じない類いの術語は多い.標題に掲げた形態論上の用語がその典型だろう.関連する話題は「#700. 語,形態素,接辞,語根,語幹,複合語,基体」 ([2011-03-28-1]) で取り上げたが,そこで挙げたもの以上に特化した学術用語という感がある.
それぞれ word 「語」, root 「語根」, stem 「語幹」, theme 「語幹形成素」, ending 「語尾」と訳せるが,訳が与えられただけで理解が深まるわけでもない.これらは印欧祖語における以下の形態論的分析が前提となっている.
┌─ ROOT
┌─ STEM ─┤
│ └─ THEME
WORD ─┤
│
└─────── ENDING
ROOT は語彙的意味を担う部分である.THEME はもとは何らかの文法的機能を担っていた可能性があるが,すでに印欧祖語の段階において,意味を担わない純粋な語幹形成要素として機能していた.直後の屈折語尾を形成する ENDING への「つなぎ」と考えておけばよい.ROOT + THEME が STEM となり,それに ENDING が付加されて,具体的な WORD の語形となる.
例えば「馬」を意味するラテン語の単数主格形 equus は equ (ROOT) + u (THEME) + s (ENDING) と分析され,同じくギリシア語の hippos は hipp (ROOT) + o (THEME) + s (ENDING) と分析される.
古英語以降の比較的新しい段階にあっては,印欧祖語における上記の形態的区分はすでに透明性を欠き,ROOT, THEME, ENDING が互いに融合してしまっていることも多い.したがって,上記の前提は厳密にいえば共時的な分析には不向きだ.しかし,通時的・歴史的には有意味であるし,比較言語学の分野における慣習的な前提となっているために,古英語文法の文脈でも(ほとんど説明がなされないままに)前提とされていることが多い.
なお,THEME には母音幹と子音幹があり,ゲルマン祖語や古英語の名詞論において,前者は「強変化名詞」,後者は「弱変化名詞」と通称される.THEME を欠く "athematic" なる語類も存在するので注意を要する.
以上,Lass (123--26) を参照して執筆した.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2024-01-16 Tue
■ #5377. YouTube で「近代言語学の祖」と称される Sir William Jones を紹介しました [youtube][notice][jones][indo-european][history_of_linguistics][link][comparative_linguistics][biography]
昨年大晦日に井上・堀田の YouTube (いのほたチャンネル)で公開した「#193. インド・ヨーロッパ祖語という着想のどこがすごいのか?! --- 近代言語学の祖と言われる Sir William Jones はどのような人物?」がよく視聴されています.本ブログでもご紹介しましょう.
Jones は,「比較言語学」 (comparative_linguistics) という近代的で科学的な言語学の扉を開いた人物として言語学史上に名を残しています.しかし,動画の中でも述べている通り,私が考える Jones の最大の功績は,共通の祖語(後の比較言語学で「印欧祖語」と呼ばれることになる言語)が今や失われているだろうと看破し喝破した点にあります.ヘブライ語やギリシア語など,ユダヤ・キリスト教と関わりの深い宗教的威信のある既存の言語のいずれでもなく,もう失われてしまった言語なのだろうと予言した慧眼に敬服します.
この事情については,上記 YouTube のほか hellog や Voicy heldio でも取り上げてきましたので,合わせて参照していただければ
・ hellog 「#282. Sir William Jones,三点の鋭い指摘」 ([2010-02-03-1])
・ hellog 「#658. William Jones 以前の語族観」 ([2011-02-14-1])
・ hellog 「#1272. William Jones 以前の語族観 (2)」 ([2012-10-20-1])
・ hellog 「#3705. Sir William Jones」 ([2019-06-19-1])
・ heldio 「#352. Sir William Jones --- 語学の天才にして近代言語学・比較言語学の祖」(2022年5月18日配信)
2023-11-24 Fri
■ #5324. Voicy 対談「モンゴル語周辺について学ぶ回 --- 梅谷博之先生との対談」 [mongolian][voicy][heldio][altaic][comparative_linguistics]
一昨日 Voicy heldio にて「#905. モンゴル語周辺について学ぶ回 --- 梅谷博之先生との対談」を配信しました.馴染みのない方も多いと思われるモンゴル語に関する話題です.対談のお相手は,本ブログでも先日「#5320. 「モンゴルの英語」 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第12章」 ([2023-11-20-1]) でご紹介した梅谷博之先生(明海大学)です.30分ほどの肩の凝らない対談となっていますので,ぜひ時間のあるときにお気軽にお聴きください.
対談は,モンゴル語族の話題に始まり,モンゴル語の文字事情を経由し,モンゴル語の言語学的なトピックへと移り変わっていきます.梅谷先生がいかにしてモンゴル語を専攻するに至ったかのお話しもうかがいました.もっとお話しを続けていたいほど楽しい対談でした.
とりわけ興味深く思ったのは,私が学生時代に言語学の教科書等でよく目にした「アルタイ語族」という大きな括りが,(異なる意見はあるにせよ)目下は前提とされていないことです.今回の対談で紹介された「モンゴル語族」は,アルタイ大語族説の下では「モンゴル語派」と呼ばれていましたが,最近では独立した語族としてみなされるようになっているようです(cf. 「#1548. アルタイ語族」 ([2013-07-23-1])).比較言語学の難しさとおもしろさ,手堅さと危うさを感じさせる話題ですね.
梅谷先生,貴重なお話をありがとうございました!
2023-06-25 Sun
■ #5172. なぜ印欧祖語には母音交替があったのか? [gradation][vowel][indo-european][reconstruction][comparative_linguistics][yurugengogakuradio][sound_symbolism][sobokunagimon]
1ヶ月半ほど前の5月6日(土)に,YouTube チャンネル「ゆる言語学ラジオ」に初めて出演させていただきました.「歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】#227」というお題で,水野さんと私が日英語の語源の話題で盛り上がるという回でした(cf. 「#5122. 本日公開の「ゆる言語学ラジオ」に初ゲスト出演しています」 ([2023-05-06-1])).
日英語に限らず言語には一般に母音交替がよくある,という話をしていたところ,動画の19分40秒付近で,堀元さんが,なぜそもそも母音を替えるというパターンがあるものなのか,という素朴な疑問を投げかけてきました.あまりに本質的で鋭い問いなので,水野さんも私もしばらく固まってしまいました.私もしどろもどろになりつつ,背後にある原理の1つとして音象徴 (sound_symbolism) がありそうだ,というところまでは述べたのですが,まったく納得できる回答にはなっていなかったと思います.
先日,Comrie による論文を読んでいて,この究極の問いに関連する言及を見つけました.ゲルマン語派に生じたウムラウト (i-mutation or umlaut) の再建について論じた後で,印欧祖語の母音交替 (gradation or ablaut) の起源と再建を考察している箇所です (252) .
. . . if we go back to an earlier stage of the Indo-European ablaut --- for instance, some instances of the so-called zero grade, with complete loss of the vowel, can plausibly be attributed to shift of the accent away from that vowel --- there is no general explanation, so that ablaut remains a morphophonemic alternation for which we cannot reconstruct a plausible origin.
なぜ印欧祖語(そして後代の印欧諸語の多く)に母音交替があるのかについて,やはり一般的な説明はないということです.この問いは「母音を替えることによって機能を替えるという言語上の工夫ががいかにして芽生えたか」と換言することができますが,これは確かに究極の問いのように思われます.調音・聴覚・音響音声学の観点からも,母音の変異が人類言語において利用しやすいデバイスだからなのではないかと想像していますが,はたしてどうなのでしょうか.
・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.
2023-06-02 Fri
■ #5149. 再建された印欧祖語で作文された羊と馬の小咄 [indo-european][reconstruction][comparative_linguistics]
19世紀のドイツの比較言語学者 August Schleicher (1821--68) は,再建された印欧祖語で羊と馬の小咄を作文している.実際の印欧祖語は文字に付されていなかったので,あくまで理論的再建に基づく近代の言語学者による創作である.半ば本気で半ばお遊びの作品を,Ringe (45) 経由で引用する(後に現代英語訳が続く).
Schleicher's Tale
Avis, jasmin varnā na ā ast, dadarka akvams, tam, vāgham garum vaghantam, tam, bhāram magham, tam, manum āku bharantam. Avis akvabhjams ā vavakat: kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam.
Akvāsam ā vavakant: krudhi avai, kard aghnutai vividvant-svas: manus patis varnām avisāms karnauti svabhjam gharmam vastram avibhjams ka varnā na asti.
Tat kukruvants avis agram ā bhugat.
A sheep that had no wool saw horses---one pulling a heavy wagon, another one a great load, and another swiftly carrying a man. The sheep said to the horses: 'it pains my heart seeing a man driving horses.'
The horses said to the sheep: 'listen sheep! it pains our hearts seeing man, the master, making a warm garment for himself from the wool of a sheep when the sheep has no wool for itself.'
On hearing this the sheep fled into the plain.
この Schleicher の印欧祖語小咄には19世紀の印欧語比較言語学の成果が反映されているわけだが,その後の同分野の研究の発展により,この小咄の言語自体も更新されてきた経緯がある.つまり,現代の印欧語比較言語学者は,上記の Schleicher による印欧祖語をそのままの形では受け入れていないということだ.
夢とロマンのある分野だが,一方でいつダメだしされるか分からない緊張感がある.
・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.
2023-06-01 Thu
■ #5148. ゲルマン祖語の強変化動詞の命令法の屈折 [germanic][imperative][inflection][paradigm][verb][person][number][subjunctive][mood][reconstruction][comparative_linguistics]
現代英語の動詞の命令法の形態は,原形に一致する.一方,古英語に遡ると,命令法では原形(不定詞)とは異なる形態を取り,さらに2人称単数と複数とで原則として異なる屈折語尾を取った.
しかし,さらに歴史を巻き戻してゲルマン祖語にまで遡ると,再建形ではあるにせよ,数・人称に応じて,より多くの異なる屈折語尾を取っていたとされる.以下に,ゲルマン祖語の大多数の強変化動詞について再建されている屈折語尾を示す (Ringe 237) .
| indicative | subjunctive | imperative | ||
| active | infinitive -a-ną | |||
| sg. | 1 -ō | -a-ų | --- | participle -a-nd- |
| 2 -i-zi | -ai-z | ø | ||
| 3 -i-di | -ai-ø | -a-dau | ||
| du. | 1 -ōz(?) | -ai-w | --- | |
| 2 -a-diz(?) | -a-diz(?) | -a-diz(?) | ||
| pl. | 1 -a-maz | -ai-m | --- | |
| 2 -i-d | -ai-d | -i-d | ||
| 3 a-ndi | -ai-n | -a-ndau |
とりわけ imperative (命令法)の列に注目していただきたい.単数・両数・複数の3つの数カテゴリーについて,2・3人称に具体的な屈折語尾がみえる.数・人称に応じて異なる屈折が行なわれていたことが理論的に再建されているのだ.
英語史も含め,その後のゲルマン語史は,命令法の形態の区別が徐々に弱まり,失われていく歴史といってよい.英語史内部での命令法の形態や,それと関連する話題については,以下の記事を参照.
・ 「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1])
・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])
・ 「#2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件」 ([2016-02-06-1])
・ 「#2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2)」 ([2016-02-10-1])
・ 「#2881. 中英語期の複数2人称命令形語尾の消失」 ([2017-03-17-1])
・ 「#3620. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (1)」 ([2019-03-26-1])
・ 「#3621. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (2)」 ([2019-03-27-1])
・ 「#4935. 接続法と命令法の近似」 ([2022-10-31-1])
・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2023-01-08 Sun
■ #5004. 聖書で英語とフリジア語を比較 --- まさにゃんの note 記事の紹介 [notice][frisian][bible][link][masanyan][khelf][contrastive_linguistics][comparative_linguistics][contrastive_language_history][germanic][voicy][heldio]
昨日の記事「#5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内」 ([2023-01-07-1]) で,聖書が英語の通時的な比較に適したテキストであることを述べました.内容が原則として古今東西同一だからです.ということは,聖書は通言語的な比較にも適しているということになります.ギリシア語,ラテン語,英語,フランス語,ドイツ語,中国語,日本語などの間で手軽に言語比較できてしまいます.つまり,聖書は対照言語学 (contrastive_linguistics),比較言語学 (comparative_linguistics),そして対照言語史 (contrastive_language_history) の観点からも有用なテキストとなります.
年末に,khelf(慶應英語史フォーラム)の会長のまさにゃんが,自身の note にて「ゼロから始めるフリジア語(シリーズ企画)」を開始しました.フリジア語は年末から始めたにわか趣味とのことです(笑).1日目,2日目,3日目,4日目と,4日分の記事が掲載されています.「創世記」より英語訳 In the beginning God created the heaven and the earth. とフリジア語訳 Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. を主に比べながら,軽妙な口調でフリジア語超入門を展開しています.
フリジア語 (Frisian) は,比較言語学的に英語と最も近親の言語とされています.この言語について hellog でも以下の記事で触れてきましたので,ぜひご覧ください.
・ 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])
・ 「#2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化」 ([2017-05-25-1])
・ 「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1])
・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])
・ 「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1])
Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも「#40. 英語に最も近い言語は「フリジア語」」にて解説しています.ぜひお聴きください.
2022-12-15 Thu
■ #4980. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第22回「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][indo-european][comparative_linguistics][reconstruction][germanic][italic][french][latin][german][dutch][spanish][italian][heldio]
『中高生の基礎英語 in English』の1月号が発売されました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第22回として「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」に答えています.
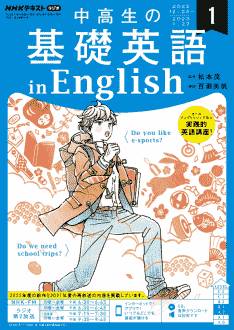
この素朴な疑問は,大雑把でナイーヴな問いに響くかもしれません.ヨーロッパ人がみな英語が上手なわけではありませんし,アジアやアフリカを含めた世界の各地に英語が上手な人はたくさんいます.このことは承知の上で,今回の記事をなるべく多くの中高生に届けたいという思いから,あえてこのような表題を掲げた次第です.
中高生に英語学習の早い段階でぜひとも知ってもらいたい重要なことがあります.それは,英語とヨーロッパの主要言語との関係です.将来大学などに進学して英語以外の言語を学ぶことになったとき,あるいは独学で他言語に挑んでみようと思い立ったとき,もしヨーロッパの諸言語を念頭においているのであれば,ぜひ英語,ドイツ語,オランダ語,フランス語,スペイン語,イタリア語などの相互関係について言語学・言語史的な観点から理解しておいてください.学習言語を選択する上で,とても大事な知識だからです.
大学教員である私は日常的に大学生と付き合っていますが,彼らのなかには,英語史の授業などで英語とヨーロッパの諸言語との関係を初めて知ると,第2外国語として○○語ではなくフランス語/ドイツ語を選択しておけばよかった,などと口にする学生がいます.もう1年か2年早く諸言語間の関係を知っていたら△△語を選んでいたのに,と後悔しているようなのです.
中高生の皆さんは,いずれ英語以外の言語を学ぶ可能性があるのであれば,英語と他の言語との関係について知っていたほうが得です.主体的に学習言語を選択できることになるからです.最終的にどの言語を選ぶにせよ,事前に多くの情報をもっておくに越したことはありません.
英語やヨーロッパの主要言語は,いずれもインドヨーロッパ語族と呼ばれる言語家族の一員です.おおまかにいえば言語が互いに似ているのです.しかし,英語と比較してどの点でどのくらい似ているのか,あるいは似ていないのかは,言語ごとに異なります.
ドイツ語とオランダ語は,英語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもゲルマン語派という派閥に属しており,文法や発音において互いに似ているところがあります.しかし,実際にドイツ語やオランダ語に触れてみると,英語と同じ派閥に属しているわりには,それほど似ていないという印象を受けるかもしれません.似ているけれども似ていない,似ていないけれども似ている,といった妙な距離感です.
一方,フランス語,スペイン語,イタリア語などは,長らくヨーロッパの共通語だったラテン語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもイタリック語派という派閥に属しています.英語とは大きく異なる派閥なのですが,英語は歴史を通じてフランス語やラテン語から多くの単語を借りてきた経緯があるため,語彙に関しては実は共通しているものが非常に多いのです.したがって,これらの言語を学んでみると,表面的には英語とよく似ているという印象を受けます.
英語は,ゲルマン語派にルーツをもつけれどもイタリック語派の影響を大きく受けながら発展してきた言語なのです.単純化していえば,英語はヨーロッパのいくつかの言語を混ぜ合わせたような混合言語といってよいでしょう.皆さんが英語の次に学ぶ言語を選択する際には,ぜひこのことを参考にしてみてください.
今回の話題と関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回としては「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」がお勧めです.ぜひお聴きください.
2022-02-24 Thu
■ #4686. 比較言語学では音の類似性ではなく対応こそが大事 [comparative_linguistics][reconstruction][methodology][phonetics][sound_change][etymology]
比較言語学 (comparative_linguistics) では,系統関係にあるかもしれないと疑われる2つの言語をピックアップし,対応するとおぼしき語どうしの音形を比較する.その際に,両語の音形が何らかの点で「似ている」ことに注目するのが自然で直感的ではあるが,比較言語学の「比較」の要諦は類似性 (similarity) ではなく対応 (correspondence) である.これは意外と盲点かもしれない.音形としてまったく似ても似つかないけれども同一語源に遡る例もあれば,逆に見栄えはそっくりだけれども系統的に無関係な例もあるからだ.
それぞれの例として「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1]),「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]),「#4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合」 ([2022-02-21-1]),「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) などを参照されたい.
この比較言語学の要諦について,Campbell (266--67) は次のように雄弁に指摘している.
. . . it is important to keep in mind that it is correspondences which are crucial, not mere similarities, and that such correspondences do not necessarily involve very similar sounds. It is surprising how the matched sounds in proposals of remote relationship are typically so similar, often identical, while among the daughter languages of well-established, non-controversial, older language families such identities are not as frequent. While some sounds may stay relatively unchanged, many undergo changes which leave phonetically non-identical correspondences. One wonders why correspondences that are not so similar are not more common in such proposals. The sound changes that lead to such non-identical correspondences often change cognate words so much that their cognancy is not apparent. These true but non-obvious cognates are missed by methods such as multilateral comparison which seek inspectional resemblances.
音声は時とともに予想よりもずっと激しく変わり得る.これが比較言語学の教訓である.関連して「#411. 再建の罠---同根語か借用語か」 ([2010-06-12-1]) も参照.
・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.
2022-02-23 Wed
■ #4685. Campbell による glottochronology 批判 [glottochronology][history_of_linguistics][comparative_linguistics][methodology]
アメリカの言語学者 Swadesh により提唱された glottochronology (言語年代学)については,「#1128. glottochronology」 ([2012-05-29-1]),「#1729. glottochronology 再訪」 ([2014-01-20-1]),「#2659. glottochronology と lexicostatistics」 ([2016-08-07-1]),「#2660. glottochronology と基本語彙」 ([2016-08-08-1]),「#2661. Swadesh (1952) の選んだ言語年代学用の200語」 ([2016-08-09-1]) をはじめとして glottochronology の各記事で取り上げてきた.
個別言語の基本語彙はゆっくりではあるが一定の速度で置き換えられていくという仮説に基づく歴史言語研究の方法論だが,言語学の主流派からは手厳しい非難を浴びており,すでに過去の仮説とみなされることも多い.様々な批判があるが,今回は短いながらも的確な Campbell の議論 (264) に耳を傾けてみよう.実に手厳しい.
Glottochronology, which depends on basic, relatively culture-free vocabulary, has been rejected by most linguists, since all its basic assumptions have been challenged . . . . Therefore, it warrants little discussion here; suffice it to say that it does not find or test relationships, but rather it assumes that the languages compared are related and proceeds to attach a date based on the number of core-vocabulary words that are similar between the languages compared. This, then, is no method for determining whether languages are related or not.
A question about lexical evidence in long-range relationships has to do with the loss or replacement of vocabulary over time. It is commonly believed that "comparable lexemes must inevitably diminish to near the vanishing point the deeper one goes in comparing remotely related languages" . . . , and this does not depend on glottochronology's assumption of a constant rate of basic vocabulary loss through time and across languages. In principle, related languages long separated may undergo so much vocabulary replacement that insufficient shared original vocabulary will remain for an ancient shared kinship to be detected. This constitutes a serious problem for those who believe in deep relationships supported solely by lexical evidence.
・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.
2022-02-21 Mon
■ #4683. 異なる言語の間で「偶然」類似した語がある場合 [comparative_linguistics][statistics][lexicology][sound_change][arbitrariness][methodology]
「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) の (1) で「偶然の一致」という可能性に言及した.2つの言語の系統的な関係を同定することを目指す比較言語学 (comparative_linguistics) にとって,2言語からそれぞれ取り出された1対の語が,言語の恣意性 (arbitrariness) に基づき,たまたま似ているにすぎないのではないか,という疑念は常に脅威的である.類似性の偶然と必然をどう見分けるのか,これは比較言語学の方法論においても,あるいはそれを論駁しようとする陣営にとっても,等しく困難な問題である.
この問題について,Campbell (275--76) が "Chance Similarities" と題する1節で Doerfer の先行研究に言及しながら論じている.偶然性には2種類あるという趣旨だ.
Doerfer (1973: 69--72) discusses two kinds of accidental similarity. "Statistical chance" has to do with what sorts of words and how many might be expected to be similar by chance; for example, the 79 names of Latin American Indian languages which begin na- (e.g., Nahuatl, Naolan, Nambicuara, etc.) are similar by sheer happenstance, statistical chance. "Dynamic chance" has to do with forms becoming more similar through convergence, that is, lexical parallels (known originally to have been different) which come about due to sounds converging through sound change. Cases of non-cognate similar forms are well known in historical linguistic handbooks, for example, French feu 'fire' and German Feuer 'fire' . . . (French feu from Latin focus 'hearth, fireplace' [-k- > -g- > -ø; o > ö]; German Feuer from Proto-Indo-European *pūr] [< *puHr-, cf. Greek pür] 'fire,' via Proto-Germanic *fūr-i [cf. Old English fy:r]).
共時的・通言語的な偶然の一致が "statistical chance" であり,通時的な音変化の結果,形態が似てしまったという偶然が "dynamic chance" である.比較言語学で2言語からそれぞれ取り出された1対の語を比べる際に,だまされてはいけない2つの注意すべき点として銘記しておきたい.
"dynamic chance" の1例として「#4072. 英語 have とラテン語 habere, フランス語 avoir は別語源」 ([2020-06-20-1]) を参照.
・ Campbell, Lyle. "How to Show Languages are Related: Methods for Distant Genetic Relationship." Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Oxford: Blackwell, 262--82.
・ Doerfer, Gerhard. Lautgesetz und Zufall: Betrachtungen zum Omnikomparatismus. Innsbruck: Institut für vergleichende Sprachwissenschaft der Universität Innsbruck, 1973.
2021-11-06 Sat
■ #4576. The Anglo-Saxon Chronicle か The Anglo-Saxon Chronicles か [anglo-saxon_chronicle][pchron][manuscript][textual_transmission][englishes][comparative_linguistics][family_tree]
日本語で『アングロサクソン年代記』と訳されている古英語テキストの英題は The Anglo-Saxon Chronicle である.しかし,同テキストには様々なヴァージョンがあり,複数形で The Anglo-Saxon Chronicles と称すべきではないかという議論がある.『アングロサクソン年代記』を巡る単複問題である.これはテキストの系統図 (stemma) をどのように解釈するのかという問題でもある.
「#4573. Peterborough Chronicle のテキストの後半における文体や言語の変容」 ([2021-11-03-1]) で参照した Watts (59--60) は,明らかに複数形論者だ.
The Anglo-Saxon Chronicles are a unique set of manuscripts from scriptoria in different parts of the country, written in Anglo-Saxon, documenting events from the birth of Christ (or from Julius Caesar's abortive attempt to conquer Britain) to the time at which the scribe is entering his annal, which is generally not the immediate present of making the entry. Paleographical evidence indicates that scribes may not always have made the entries immediately after the year that they were recording, but may have chosen to write up entries for a set of years. . . .
There is some dispute over whether it is more appropriate to refer to the ASC in the singular or to use the plural form. Those in favour of just one chronicle base their argument on the fact that successive copies were made from one master copy, and . . . there is undoubtedly more than a grain of truth in this argument. However, some scholars have found it safer and, in view of the complexity of the existing manuscript situation, more expedient to consider the manuscripts that have survived as being, at least in part, independent versions. Many of the chronicles make use of sources other than the original Alfredian Chronicle . . . , and there are clear cases of changes having been made to chronicle entries at later dates in history, often for propaganda purposes.
これは複数のヴァージョンを互いに "independent" とみなすべきかどうかという微妙な判断の問題である.客観的な事実が提供されていたとしても,ある程度は主観的な判断に依存せざるを得ない問題でもある.
この議論を(比較)言語学の領域に引きつければ,"English" なのか "Englishes" なのかも,ほぼ平行的な問題と考えてよいだろう.
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2021-05-25 Tue
■ #4411. German と Germanic の違い --- ややこしすぎる言語名の問題 [onomastics][khelf_hel_intro_2021][sobokunagimon][german][germanic][comparative_linguistics][terminology][language_myth]
英語にはややこしい民族名,国民名,言語名が多々あります.民族も国民も言語もたいてい複雑な固有の歴史を背負ってきているので,それを表わす語もややこしくなってしまうのは致し方のないことかもしれません.しかし,標題の2語はそれにしても誤解を招きやすい点では最右翼に位置づけられるペアといってよいでしょう.「#4380. 英語のルーツはラテン語でもドイツ語でもない」 ([2021-04-24-1]) で触れたような誤解が生まれるのも無理からぬことです.
言語の呼称としての German は「ドイツ語」を指します.一方,Germanic は比較言語学的に再建された「ゲルマン(祖)語」 (= Proto-Germanic) を指します.形容詞としては,後者は「ゲルマン(祖)語の」あるいは,このゲルマン(祖)語から派生した一群の言語を指して「ゲルマン語派の」ほどを意味します.
「英語史導入企画2021」より今日紹介するコンテンツは,まさにこの2語のややこしさに焦点を当てた,院生による「A Succinct Account of German and Germanic」です.英語による音声コンテンツとなっています.
英和辞典によると German は「ドイツ人,ドイツ語;ドイツの」ほど,Germanic は「ゲルマン(祖)語;ゲルマン系の,ドイツ的な」ほどとなりますが,すでにこの時点で分かりにくいですね.学習者用英英辞典 OALD8 によると,各々およそ次の通りでした.
German
adjective:
from or connected with Germany
noun:
1 [countable] a person from Germany
2 [uncountable] the language of Germany, Austria and parts of Switzerland
Germanic
adjective:
1 connected with or considered typical of Germany or its people
2 connected with the language family that includes German, English, Dutch and Swedish among others
形容詞としては,"connected with Germany" が共通項となっていますし,やはり分かったような分からないような区別です.
両語の区別を理解する上で参考になるのは各語の初出年です.German の初出は,名詞としては1387年より前,形容詞としては1536年で,そこそこ古いといえますが,Germanic はまず形容詞として1539年に初出し,「ゲルマン(祖)語」を意味する名詞としてはさらに遅く1718年のことです.つまり「ゲルマン(祖)語」の語義は,言語学用語としての後付けの語義だと分かります.
後付けであればこそ,後発の強みを活かして誤解を招かない別の用語を選んでもらいたかったところです.いや,実のところ,比較言語学では「ゲルマン祖語」を指すのに Teutonic (cf. 英語 Dutch, ドイツ語 Deutsch) という別の用語を用いる慣習も古くはあったのです.それだけに,紛らわしい Germanic が結局のところ勝利し定着してしまったことは皮肉と言わざるを得ません.
関連して「#3744. German の指示対象の歴史的変化と語源」 ([2019-07-28-1]) と「#864. 再建された言語の名前の問題」 ([2011-09-08-1]) もご一読ください.
(後記 2021/05/26(Wed):今回紹介した音声コンテンツの文章版が「'German' と 'Germanic' についての覚書」として後日公表されましたので,こちらも案内しておきます.)
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow