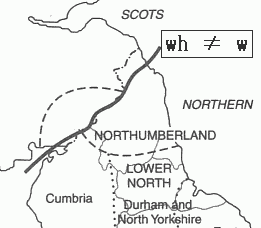2015-06-05 Fri
■ #2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][consonant][phoneme][grapheme][degemination][x][phonemicisation]
5月16日付の「素朴な疑問」に,<s> と <x> の綴字がときに無声子音 /s, ks/ で,ときに有声子音 /z, gz/ で発音される件について質問が寄せられた.語頭の <s> は必ず /s/ に対応する,強勢のある母音に先行されない <x> は /gz/ に対応する傾向があるなど,実用的に参考となる規則もあるにはあるが,最終的には単語ごとに決まっているケースも多く,絶対的なルールは設けられないのが現状である.このような問題には,歴史的に迫るよりほかない.
英語史的には,/(k)s, (g)z/ にとどまらず,摩擦音系列がいかに綴られてきたかを比較検討する必要がある.というのは,伝統的に,古英語では摩擦音の声の対立はなかったと考えられているからである.古英語には摩擦音系列として /s/, /θ/, /f/ ほかの音素があったが,対応する有声摩擦音 [z], [ð], [v] は有声音に挟まれた環境における異音として現われたにすぎず,音素として独立していなかった (cf. 「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]),「#17. 注意すべき古英語の綴りと発音」 ([2009-05-15-1])).文字は音素単位で対応するのが通常であるから,相補分布をなす摩擦音の有声・無声の各ペアに対して1つの文字素が対応していれば十分であり,<s>, <þ> (or <ð>), <f> がある以上,<z> や <v> などの文字は不要だった.
しかし,これらの有声摩擦音は,中英語にかけて音素化 (phonemicisation) した.その原因については諸説が提案されているが,主要なものを挙げると,声という弁別素性のより一般的な応用,脱重子音化 (degemination),南部方言における語頭摩擦音の有声化 (cf. 「#2219. vane, vat, vixen」 ([2015-05-25-1]),「#2226. 中英語の南部方言で語頭摩擦音有声化が起こった理由」 ([2015-06-01-1])),有声摩擦音をもつフランス語彙の借用などである(この問題に関する最新の論文として,Hickey を参照されたい).以下ではとりわけフランス語彙の借用という要因を念頭において議論を進める.
有声摩擦音が音素の地位を獲得すると,対応する独立した文字素があれば都合がよい./v/ については,それを持ち込んだ一員とも考えられるフランス語が <v> の文字をもっていたために,英語へ <v> を導入することもたやすかった.しかも,フランス語では /f/ = <f>, /v/ = <v> (実際には <<v>> と並んで <<u>> も用いられたが)の関係が安定していたため,同じ安定感が英語にも移植され,早い段階で定着し,現在に至る.現代英語で /f/ = <f>, /v/ = <v> の例外がきわめて少ない理由である (cf. of) .
/z/ については事情が異なっていた.古英語でも古フランス語でも <z> の文字はあったが,/s, z/ のいずれの音に対しても <s> が用いられるのが普通だった.フランス語ですら /s/ = <s>, /z/ = <z> の安定した関係は築かれていなかったのであり,中英語で /z/ が音素化した後でも,/z/ = <z> の関係を作りあげる動機づけは /v/ = <v> の場合よりも弱かったと思われる.結果として,<s> で有声音と無声音のいずれをも表わすという古英語からの習慣は中英語期にも改められず,その「不備」が現在にまで続いている.
/ð/ については,さらに事情が異なる.古英語より <þ> と <ð> は交換可能で,いずれも音素 /θ/ の異音 [θ] と [ð] を表わすことができたが,中英語期に入り,有声音と無声音がそれぞれ独立した音素になってからも,それぞれに独立した文字素を与えようという機運は生じなかった.その理由の一部は,消極的ではあるが,フランス語にいずれの音も存在しなかったことがあるだろう.
/v/, /z/, /θ/ が独立した文字素を与えられたかどうかという点で異なる振る舞いを示したのは,フランス語に対応する音素と文字素の関係があったかどうかよるところが大きいと論じてきたが,ほかには各々の音素化が互いに異なるタイミングで,異なる要因により引き起こされたらしいことも関与しているだろう.音素化の早さと,新音素と新文字素との関係の安定性とは連動しているようにも見える.現代英語における摩擦音系列の発音と綴字の関係を論じるにあたっては,歴史的に考察することが肝要だろう.
・ Hickey, Raymond. "Middle English Voiced Fricatives and the Argument from Borrowing." Approaches to Middle English: Variation, Contact and Change. Ed. Juan Camilo Conde-Silvestre and Javier Calle-Martín. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 83--96.
2015-05-17 Sun
■ #2211. 古英語 engel における g の子音 [oe][phonetics][consonant][pronunciation][g][j]
現代英語 angel は,古英語 engel に遡り,これ自体は後期ラテン語 angelus の借用語である.さらに,angelus はギリシア語 ággelos (one that announces) からの借用である.現代英語での発音は [eɪnʤəl] であり,<g> に相当する第2音節の最初の子音は破擦音となるが,古英語ではどのように発音されたのだろうか.古英語入門書のあるものでは,<g> が与えられており,他のものでは <ġ> が与えられている.前者では破裂音 [g] であり,後者ではそれが口蓋化した何らかの子音(しばしば接近音 [j] )であると想定される.また,Hogg (37) によれば,<n> に後続する <g> が,現代英語と同じように破擦音 [ʤ] として実現された例 (ex. OE singe (> PDE singe [sɪnʤ])) がいくつか挙げられているので,現代の発音に引かれて [ʤ] と調音したくもなる.この破擦音も,少なくとも口蓋化音とされるものの1候補ではあるだろう.
具体的な典拠に当たってみよう.『英語語源辞典』によれば,「OE 音 /-g-/ は13Cまで残るが,ME 初期から OF angele, angel (F ange) (▭ LL) の影響を受けて /ʤ/ となった」とある.また,古英語音韻論の専門書 Lass and Anderson (136) によれば,古英語 ġimm (gem; < L. gemma) と対比して古英語 engel を与えているところから,[g] を想定していることがわかる.
もう1つの古英語音韻論の専門書 Hogg (223) は,enġel と表記しており,口蓋化音を想定している.その実現が接近音 [j] なのか,破裂音 [ɟ] なのか,はたまた破擦音 [ʤ] なのかは判然としない.
一方,小野・中野の『英語史 I』 (100) によれば,古英語では en- や yn- の後位置で破裂音 [ɟ] が生じ,これが古英語期中に破擦音 [ʤ] へ変化したという.この例として,まさに enġel (angel) が,lenġr (longer), hynġran (be hungry) とともに挙げられている.
一般に古英語の音声的実現については様々な議論があり,わからないことも多いのだが,今回の件については,上にも触れた Lass and Anderson (136) が歯切れがよいので引用しておこう.古英語 <g> の音価について現代英語のそれとも関連づけながら解説している箇所で,古英語 engel の問題の子音が破擦音 [ʤ] だったはずはないことを示唆している(赤字の部分を参照).
. . . the 'normal' developments:
(a) [j] before original front vowels: ġeolu 'yellow', ġieldan 'yield'.
(b) [g] before original back vowels: gōs 'goose', gāst 'ghost'.
(c) [g] before umlauted back vowels: gēs 'geese', gyrdels 'girdle'.
Some of the major anomalies are these:
(a) [g] before original front vowels: give, get, gate, gallows, OE ġ(i)efan, ġ(i)etan, ġeat, ġealga. The simplest answer here is the traditional one of 'Scandinavian influence'---however that may have operated. The most likely way would seem to be by direct borrowing of forms, i.e. ON gefa, geta, gata, galgi. Since Old Norse did not at that time have a palatal softening rule, these foms, if they were borrowed as is, would be 'synchronically foreign' in OE dialects that had palatal softening: an OE form beginning with the 'impermissible' sequence [ge] would then be the equivalent of a form like Dvořak, or Vladimir in Modern English. That the OE forms did indeed have [j] is borne out by survivals like yett in place names from OE ġeat, and by the Middle English spelling distributions: basically non-northern forms like yeve, yive, as against northern ones like gyve, give, gyff.
(b) [ʤ] before original front vowels: gem, OE ġimm < L. gemma. The answer here, as in angel (OE engel) is undoubtedly reborrowing from French after the Conquest.
(c) [j] before original back vowels. We know of only one clear case of this type, which is yawn. The vowel suggests OE gānian 'gape, yawn', rather than the apparently synonomous (sic) verb ginian (gynian, gionian). The consonantism, however, suggests the latter. The OED (s.v. yawn) proposes, perhaps correctly, a sort of 'conflation': [j]-forms 'influenced by' (whatever that means) the vowel of now obsolete [g]-forms.
このようにいくつかの典拠に当たってはみたが,結局のところ,諸説紛々としており,いかなる子音だったかを確定することは難しい.
関連して,「#1651. j と g」 ([2013-11-03-1]),「#1914. <g> の仲間たち」 ([2014-07-24-1]),「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) も参照.
・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
・ Lass, Roger and John M. Anderson. Old English Phonology. Cambridge: CUP, 1975.
・ 小野 茂,中尾 俊夫 『英語史 I』 英語学大系第8巻,大修館書店,1980年.
2015-05-07 Thu
■ #2201. 誕生おめでとう! Princess Charlotte [onomastics][french][loan_word][pronunciation][consonant][personal_name][title][palatalisation][fricativisation]
先週末から英国王室のロイヤルベビー Princess Charlotte 誕生の話題が,英国や日本で沸いている.Prince William と Kate Middleton 夫妻の選んだファーストネームは Charlotte.ミドルネームは,よく考え抜かれ,世間にも好評の Elizabeth Diana である.一般には,称号を付して Her Royal Highness Princess Charlotte of Cambridge と呼ばれることになる (cf. 「#440. 現代に残る敬称の you」 ([2010-07-11-1]), 「#1952. 「陛下」と Your Majesty にみられる敬意」 ([2014-08-31-1])) .

Charlotte は,Charles の語根に女性接辞かつ指小辞 (diminutive) を付した形態に由来し,「小さくてかわいい Charles お嬢ちゃん」ほどが原義である.この語根は究極的にはゲルマン祖語 *karlaz (man) に由来し,これがラテン語に Carolus として借用され,後に古フランス語へ発展する過程で語頭子音が [k] → [ʧ] と口蓋化 (palatalisation) した.この口蓋化子音をもった古フランス語の音形が英語へ借用され,現在の [ʧɑːlz] に連なっている.
フランス語に話を戻そう.フランス語では13世紀中に破擦音 [ʧ] が [ʃ] へと摩擦音化 (fricativisation) し,元来は男性主格語尾だった s も発音を失い,現在,同名前は [ʃaʁl] と発音されている.同様に,Charlotte も現代フランス語での発音は摩擦音で始まる [ʃaʁlɔt] である.今回の英語のロイヤルベビー名も,摩擦音で始まる [ʃɑːlət] だから,現代フランス語的な発音ということになる.上記をまとめると,現代英語の男性名 Charles は破擦音をもって古フランス語的な響きを伝え,女性名 Charlotte は摩擦音をもって現代フランス語的な響きを伝えるものといえる.
現代英語におけるフランス借用語で <ch> と綴られるものが,破擦音 [ʧ] を示すか摩擦音 [ʃ] を示すかという基準は,しばしば借用時期を見極めるのに用いられる.例えば chance, charge, chief, check, chair, charm, chase, cheer, chant はいずれも中英語期に借用されたものであり,champagne, chef, chic, chute, chaise, chicanery, charade, chasseur, chassis はいずれも近代英語期に入ったものである.しかし,時期を違えての再借用が関与するなど,必ずしもこの規則にあてはまらない例もあるので,目安にとどめておきたい.Charles と Charlotte の子音の差異については歴史的に詳しく調べたわけではないが,時代の違いというよりは,固有名詞に随伴しやすい流行や嗜好の反映ではないかと疑っている.
なお,ゲルマン祖語 *karlas (man) からは,直接あるいは間接に現代英語の churl と carl が生まれている.いずれも意味が本来の「男」から「身分の低い男」へと下落しているのがおもしろい.逆に,人名 Charles と Charlotte は,英国王室の人気により,むしろ価値が高まっているといえる(?).
フランス借用語の年代に関しては,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]),「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1291. フランス借用語の借用時期の差」 ([2012-11-08-1]),「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]), 「#2184. 英単語とフランス単語の相違 (2)」 ([2015-04-20-1]) を参照されたい.
2015-02-03 Tue
■ #2108. <oa> の綴りの起源 (2) [spelling][orthography][pronunciation][diphthong][gvs]
「#435. <oa> の綴りの起源」 ([2010-07-06-1]) で述べたのとは異なる <oa> の綴字の起源説を紹介する.boat, foam, goal などに現われる2重母音に対応する綴字 <oa> の習慣は,出現したのも定着したのも歴史的には比較的遅く,初期近代英語のことである.近代英語期以降の綴字標準化の歴史は,ほとんどの場合非難の対象にこそなれ,賞賛されることは滅多にないものだが,この <oa> に関しては少し褒めてもよい事情がある.
現代英語において,例えば boot と boat は母音部の発音が異なり,したがって対応する綴字も異なるというのは当たり前のように思われるが,この当たり前が実現されたのは,初期近代英語期に後者の単語を綴るのに <oa> が採用されたそのときだった.というのは,それより前の中英語では,両単語の母音は同様に異なっていたものの,その差異は綴字上反映されていなかったからだ.具体的にいえば,boot, boat に対応する中英語の形態では,発音はそれぞれ [boːt], [bɔːt] であり,長母音が異なっていた.2つの長母音は音韻レベルでも異なっていたので,綴り分けられることがあってもよさそうなものだが,実際にはいずれも <bote> などと綴られるのが普通であり,綴字上の区別は特に一貫していなかった.この語に限らず,中英語の [oː], [ɔː] の2つの長母音は,いずれも <o>, <oo>, <o .. e> などと表記することができ,いわば異音同綴となっていた.
中英語の間は,それでも大きな問題は生じなかった.だが,中英語末期から初期近代英語期にかけて大母音推移 (gvs) が始まると,[oː], [ɔː] の差異は [uː], [oː] (> [oʊ]) の差異へとシフトした.大母音推移の後では音質の差が広がったといってよく,綴字上の区別もつけられるのが望ましいという意識が芽生えたのだろう,狭いほうの母音には <oo> をあてがい,広いほうの母音には <oa> (あるいは <o .. e>)をあてがうという慣習が生まれ,定着した.異なる語であり異なる発音なのだから異なる綴字で表記するという当たり前の状況が,ここでようやく生まれたことになる.
ブルシェ (74) によれば,「<oa> という結合は恐らく <ea> にならって作られ,12?13世紀に出現した」が,「その後 <oa> は消滅し」た.それが,上記のように大母音推移が始まる15世紀に復活し,その後定着することになった.現われては消え,そして再び現われるという <oa> の奇妙な振る舞いは,対応する前舌母音を表記する <ea> の歴史とも,確かに無関係ではないのかもしれない.<ea> については「#436. <ea> の綴りの起源」 ([2010-07-07-1]) も参照.
・ ジョルジュ・ブルシェ(著),米倉 綽・内田 茂・高岡 優希(訳) 『英語の正書法――その歴史と現状』 荒竹出版,1999年.
2015-01-25 Sun
■ #2099. fault の l [etymological_respelling][spelling][pronunciation][dialect][johnson]
「#192. etymological respelling (2)」 ([2009-11-05-1]) のリストにあるとおり,現代英語の fault の綴字に l が含まれているのは語源的綴字によるものである.語源的綴字は典型的には初期近代英語期のラテン語熱の高まった時代の所産といわれるが,実はもっと早い例も少なくない.fault も14世紀末の Gower ((a1393) Gower CA (Frf 3) 6.286) に "As I am drunke of that I drinke, So am I ek for falte of drinke." として初出する.実在のラテン単語で直接の起源とされる語はないが,仮説形 *fallitum が立てられている.フランス語でも15--17世紀に faute や faulte の形で現われている.英語で l を含む綴字が標準となったのは17世紀以降だが,発音における /l/ の挙動はその前後で安定しなかった.
OED によると,17--18世紀の Pope や Swift において fault が thought や wrought と脚韻を踏んでいたというし,1855年の Johnson の辞書にも "The l is sometimes sounded, and sometimes mute. In conversation it is generally suppressed." と注意書きがある.fault と似たような環境にある l は,近代の正音学者にとっても問題の種だったようで,その様子を Dobson (Vol. 2, §425. fn. 5) がよく伝えている.
Balm, calm, palm, almond, falcon, salmon, &c. should by etymology have no [l], being from OF baume, &c., and normally are recorded without [l]. But some of them had 'learned' OF forms, adopted directly from Latin, which retained [l] . . ., and others came to be spelt with l partly on etymological grounds and partly on the model of psalm, &c., spelt with but pronounced without l; and from the OF 'learned' variants, and perhaps partly from the spelling in combination with the variation in pronunciation in psalm, &c., there arose pronunciations with ME aul, recorded by Salesbury in calm, Bullokar in almond, balm, and calm, Gil in balm (as a 'learned' variant), and Daines in calm (as a variant). . . .
Variation between pronunciations with and without l in such native words as malt and salt has clearly aided the establishment of the spelling-pronunciations with [l] in fault and vault, in which the orthoepists regularly show the l to be silent, with the following exceptions. Hart once retains l in faults, probably by error; Gil says that most omit the l, but some -pronounce it, and twice gives transcriptions with l elsewhere (in Luick's copy of the 1619 edition a transcription faut is corrected by hand to falt); Tonkis fails to say that the l is silent, and the anonymous reviser (1684) of T. Shelton's Tachygraphy does not omit it (in contrast to this treatment of, for example, balm); and Hodges relegates to his 'near alike' list the paring of fault and fought. Bullokar twice transcribes vault without l, but once retains it.
fault について近代方言に目を移すと,English Dialect Dictionary には,"FAULT, sb. and v. Var. dial. uses in Sc. Irel. Eng. and Amer. Also in forms faut Sc. Ir. n.Yks.2 e.Yks. n.Lin.1 War. Shr.1 2 Som. w.Som.1; faute Sc.; fowt Suf. [folt, fat, f$t, fout.]" と記載されてあり,数多くの方言に l なしの形態が分布していることがわかる.
現代標準英語の発音は /fɔːlt/ で安定しており,通常は何の問題意識も生じないだろうが,標準から目をそらせば,そこには別の物語が広がっている.fault を巡る語源的綴字現象の余波は,始まってから数世紀たった今も,確かに続いているのである.
・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. Vol. 2. Oxford: OUP, 1968.
2015-01-19 Mon
■ #2093. <gauge> vs <gage> [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap][eebo][clmet][emode][lmode][coha][ame_bre][spelling_pronunciation]
「#2088. gauge の綴字と発音」 ([2015-01-14-1]) を受けて,<gauge> vs <gage> の異綴字の分布について歴史的に調べてみる.まずは,初期近代英語の揺れの状況を,EEBO (Early English Books Online) に基づいたテキスト・データベースにより見てみよう
| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |
|---|---|---|
| 1451--1500 (244,602 words) | 0 wpm (0 times) | 0 wpm (0 times) |
| 1501--1550 (328,7691 words) | 3.35 (11) | 0.00 (0) |
| 1551--1600 (13,166,673 words) | 6.84 (90) | 0.076 (1) |
| 1601--1650 (48,784,537 words) | 3.01 (147) | 0.35 (17) |
| 1651--1700 (83,777,910 words) | 0.060 (5) | 0.19 (5) |
| 1701--1750 (90,945 words) | 0.00 (0) | 0.00 (0) |
17世紀に <gauge> 系が少々生起するくらいで,初期近代英語の基本綴字は <gage> とみてよいだろう.次に,18世紀以後の後期近代英語に関しては,CLMET3.0 を利用して検索した.
| Period (subcorpus size) | <gage> etc. | <gauge> etc. |
|---|---|---|
| 1710--1780 (10,480,431 words) | 5 | 1 |
| 1780--1850 (11,285,587) | 19 | 20 |
| 1850--1920 (12,620,207) | 2 | 49 |
おそらく1800年くらいを境に,それまで非主流派だった <gauge> が <gage> に肉薄し始め,19世紀中には追い抜いていったという流れが想定される.現代英語では BNCweb で調べる限り <gauge> が圧倒しているから,20世紀中もこの流れが推し進められたものと考えられそうだ.
一方,<gage> の使用も多いといわれるアメリカ英語について COHA で調べてみると,実際のところ現代的には <gauge> のほうが圧倒的に優勢であるし,歴史的にも <gauge> が20世紀を通じて堅調に割合を伸ばしてきたことがわかる.あくまで,現代アメリカ英語では <gage> 「も」使われることがあるというのが実態のようだ.この事実は,「#1739. AmE-BrE Diachronic Frequency Comparer」 ([2014-01-30-1]) により "(?-i)\bgau?g(e|es|ed|ings?)\b" として検索をかけて得られる以下の表からも示唆される.いずれの変種でも <gauge> 系は見られるものの,<gage> 系についてはイギリス英語ではゼロ,アメリカ英語では部分的に使用されるという違いがある.
| ID | WORD | 1961 | 1991--92 | ca 2006 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown (AmE) | LOB (BrE) | Frown (AmE) | FLOB (BrE) | AmE06 (AmE) | BE06 (BrE) | ||
| 1 | gage | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | gages | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | gaging | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | gauge | 16 | 15 | 10 | 6 | 16 | 21 |
| 5 | gauged | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | gauges | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | gauging | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |