2025-11-09 Sun
■ #6040. 今朝の朝日新聞朝刊に「英語帝国主義」をめぐるインタビュー記事が掲載されています [notice][sociolinguistics][helkatsu][linguistic_imperialism][world_englishes][elf][elt][hel_education][demography][voicy][heldio]
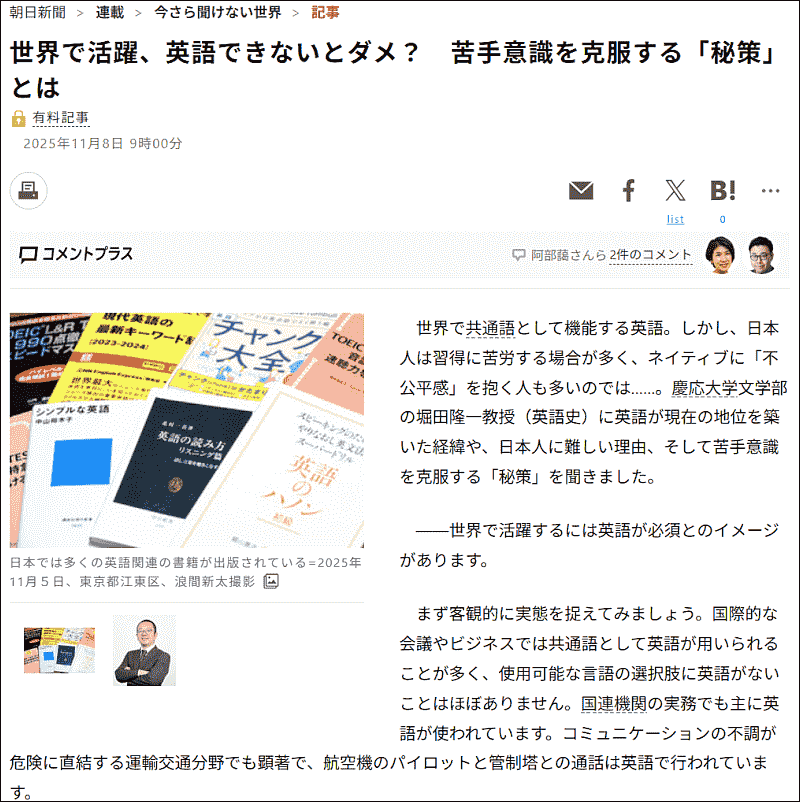
昨日11月8日(土),朝日新聞デジタル版にインタビュー記事「世界で活躍,英語できないとダメ? 苦手意識を克服する「秘策」とは」が公開されました.この記事は,同紙の連載企画「今さら聞けない世界」の一環として,各分野の専門家へのインタビューを基にして,編集されたものです.
先日,連載の担当者の方より,「英語帝国主義」を念頭に,世界における英語の位置づけと,その英語に対して私たちはどのように臨めばよいかについて伺いたいとのご連絡をいただき,このインタビューを実施した次第です.貴重な機会をいただき,朝日新聞の関係者の方々に感謝申し上げます.
昨日公開されたデジタル版は有料記事となっておりますが,フルバージョンでお読みいただけます.また,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に,同記事の短縮版が掲載される予定です.
さて,インタビュー(記事)の内容ですが,英語史研究者の立場から,英語が歴史を通じて築き上げてきた世界的な地位,日本語母語話者が英語学習で難しさを感じる構造的な要因,そして,苦手意識を乗り越えて自信をもって英語を使うための「秘策」についてお話ししました.
まず,国際的な舞台で英語が共通語 (lingua_franca) として機能しているという客観的事実をを確認しました.その上で,英語が世界的な地位を得た背景には,過去のギリシア語やラテン語など,かつての有力言語がたどった道筋と質的には同じ構造があることを指摘しています.特定の国家の政治的・経済的な力が,その言語の拡散を支えてきたという歴史的事実は,言語の力学を理解する上で重要です.この議論は,英語史における大きな論点の1つである「英語帝国主義批判」とも関わってきます.
次に,日本人にとって英語習得が難しいとされる構造的な理由についても触れました.日本語と英語は,発音や文法体系,語彙などの点で共通点が非常に少なく,言語の距離が遠いという事実があります.(数千年レベルで見れば)互いに方言といってよい関係にあるヨーロッパ諸語の母語話者と比べると,日本人が英語の習得に長い時間を要するのは,むしろ自然なことです.
さらに,単なる言語知識の問題を超えて,英米人と日本人の間には,コミュニケーションの土台となる宗教,歴史,文化,習慣の面での共通項も少なく,英語での会話における「作法」を知らないことが,習得のもう1つの大きな壁になっていることも指摘しました.欧州諸国の人々が英語での会話にあまり抵抗感がないのと比べると,日本人はいざ話そうとしたときに「そもそもどのように会話を始めたらよいのか」という戸惑いを感じやすいようです.
そして,記事のなかで最も注目していただきたいのが,苦手意識を克服し自信をもって話すための「秘策」です.具体的な内容はここでは伏せておきますが,英語史や社会言語学の知見に基づき,現在の世界の英語使用の実態に鑑みた,実践的なアドバイスとなっていると思います.鍵となるのは,世界の英語話者20億人のうち,英米人などの母語話者はマイノリティであるという事実です.
「英語帝国主義」については,本ブログでも linguistic_imperialism のタグの着いた記事をはじめとして,様々に議論してきました.ここでは Voicy heldio の関連回をご案内しておきたいと思います.ぜひお聴きいただければ.
・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」
・ 「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」
改めて,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に短縮版が掲載される予定ですので,そちらからもご一読いただければ幸いです.
2024-05-13 Mon
■ #5495. インド憲法第343条に記載されている連邦の公用語 [hindi][india][statistics][official_language][demography]
1950年に定められたインド憲法(英語版)の第343条の第1項によれば,連邦の公用語 (official_language) はデーヴァナーガリー文字 (Devanagari) で書かれたヒンディー語 (hindi) とされている.しかし,向こう15年間は英語の暫定的使用も認める,という但し書き条項が加えられていた.さらに,その15年の後にも,英語を引き続き公的に使用することができる選択肢は開かれていた.インドの公用語をめぐる問題は,すでに憲法制定時より,このように奥歯に物が挟まったような言い方で始まっていたということだ.英語版より343条を引用しよう.
343. Official language of the Union.---(1) The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.
The form of numerals to be used for the official purposes of the Union shall be the international form of Indian numerals.
(2) Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commencement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement:
Provided that the President may, during the said period, by order authorise the use of the Hindi language in addition to the English language and of the Devanagari form of numerals in addition to the international form of Indian numerals for any of the official purposes of the Union.
(3) Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of---
(a) the English language, or
(b) the Devanagari form of numerals,
for such purposes as may be specified in the law.
憲法上の記載の順序でいえば,ヒンディー語が筆頭の公用語である.実際,インド国内ではヒンディー語は話者が最も多く,2020年の時点で約6億人以上を数えるという(大石(編),p. 70).さらにいえば,ヒンディー語は,世界の中でも3番目に話者の多い超大言語である.2020年のこちらのニュース記事によると,Ethnologue による統計に基づき,次のような解説がなされている.
Hindi is the 3rd most spoken language of the world in 2019 with 615 million speakers. The 22nd edition of the world language database Ethnologue stated English at the top of the list with 1,132 million speakers. Chines Mandarin is at the second position with 1,117 million speakers.
今後もインドの人口増加と連動してヒンディー語の話者人口は増えていくものと思われる.インドのダイナミックな言語事情からは目を離せない.
関連して Ethnologue の言語話者人口について「#3009. 母語話者数による世界トップ25言語(2017年版)」 ([2017-07-23-1]) を,多言語国家の公用語の話題として「#3291. 11の公用語をもつ南アフリカ共和国」 ([2018-05-01-1]) を参照.
・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.
2023-10-04 Wed
■ #5273. 英語に関する最新統計 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の序章より [world_englishes][notice][hel_education][hel][statistics][demography][review][we_nyumon]
先日の記事「#5268. 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)」 ([2023-09-29-1]) で紹介したこちらの本,一般発売が開始となったようです.
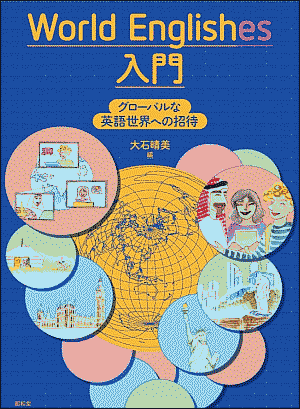
これまで本ブログでもWorld Englishes (世界英語')については多く取り上げてきました (cf. (world_englishes)) .21世紀に入ってから英語学・英語史でも驚くほど注目されるようになった今をときめく話題です.この15年ほどを振り返ってみても,英語学・英語史を専攻する大学生の研究テーマとして大人気のトピックといってよいでしょう.この World Englishes の人気の高まりには,間違いなく社会的な背景があると考えています.この問題についていろいろな機会に書いたり話したりしてきましたが,今後も注目していく予定です.
そんな折りに,この『World Englishes 入門』が出版されました.これから,本書を参照しつつ本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,関連する話題を取り上げていくつもりですので,ぜひ伴走していただければ.
大石晴美・梅谷博之氏による「序章 World Englishes---世界諸英語」では,世界の言語や英語に関する最新の事実や統計が示されています.いくつか引用します.
・ 現在,世界には196か国が存在し,7000以上の言語が使われている.(p. 6)
・ 2022年11月,世界の総人口は80億人を超えた(世界人口推計 2022).そのうち英語を使用する人口(母語,第二言語,外国語としての英語使用者)は約14億5000万人,そのうち母語話者が約3億7000万,第二言語,外国語としての使用者は約10億8000万人である (Ethnologue 2022) .このことから非母語話者の数が母語話者の数をはるかに上回っていることがわかる.(p. 9--10)
・ 世界で,英語を公用語もしくは準公用語と定めている国は54か国である.4か国のうち1か国が英語を公用語や準公用語にしていることになる.(p. 10)
・ 世界のインターネット総人口は,約41億6000万人(全人口の69%)である (Internet World Stats 2023) .そのうち,26%が英語仕様人口であり,インターネット普及率が英語の広がりにつながっている.(p. 10)
・ 世界で上映されている映画のうち英語が用いられているのは8割以上である. (p. 10)
本書はコラムも充実しています.例えば,序章のなかの2つめのコラムにおいて「世界の英語を映画で学ぶ研究会」(京都府立大学)が紹介されています.すべての映画が観たくなってしまい,たいへん困っています.
・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.
2022-08-03 Wed
■ #4846. 遺伝と言語の関係 [anthropology][evolution][demography][genetics][language_family]
篠田謙一氏による近刊書『人類の起源』(中公新書)を読んでいる.人類学 (anthropology) は言語学の隣接分野の1つでもあり関心を寄せているが,アフリカなどで化石人骨が発見されるたびに人類史が書き換わる様を目の当たりにして,なんとスピード感のある分野なのだろうと思っている.
篠田 (174) では,アジア人の起源を探る章で,「言語とゲノム」の関係について議論が展開されている.その一部を引用する.
二〇〇九年には,東南アジアから北東アジアにかけての現代人集団のゲノムデータが解析され,アジアの集団の遺伝的な分化は基本的に言語集団に対応していることが示されています.〔中略〕同じ言語集団に属する人びとは似たような遺伝的な構成をしているということを表しています.婚姻は基本的には同じ言語グループの中で行われますから,当然の結果でしょう.分化のもっとも重要な要素は言語であり,それが集団の遺伝的な構成を規定しているのです.
この引用にあるように,遺伝と言語に基づく集団の分布が一致しているという指摘は,おそらく多くの読者にとって直観と常識に見合うために,すんなりと受け入れられるものだろう.しかし,私にとって,このストレートな指摘は,なかなかショッキングだった.遺伝,人種,言語の関係について,単純に結びつけることに懐疑的であり抵抗があるからだ.
社会言語学では,言語とその他の種々のパラメーターは,相関関係にあることは多いものの,絶対的な結びつきはないということが説かれ,しばしば強調される.社会言語学は,ある意味では,言語と他のパラメーターの関係は直観・常識とは完全にイコールではないので,盲目的にイコールで結びつける言説とは距離を置け,と主張する分野でもあると私は考えている.このような立場からすると,上記の結論はあまりにストレートで,オッと身構えてしまうわけだ.
ただし,あいにく「遺伝」について門外漢である私が何か言えることがあるかと問われれば,残念ながらない.ここでは,関連する以下の記事を指摘するにとどめたい.
・ 「#2838. 新人の登場と出アフリカ」 ([2017-02-02-1])
・ 「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1])
・ 「#2844. 人類の起源と言語の起源の関係 (2)」 ([2017-02-08-1])
・ 「#2872. 舌打ち音とホモ・サピエンス」 ([2017-03-08-1])
・ 「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1])
・ 「#3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか?」 ([2019-02-27-1])
・ 「#1871. 言語と人種」 ([2014-06-11-1])
・ 「#3599. 言語と人種 (2)」 ([2019-03-05-1])
・ 「#3810. 社会的な構築物としての「人種」」 ([2019-10-02-1])
現時点での私のまとまらない考えを言語化すると次のようになる.遺伝と言語の相関関係は,直観・常識のみならず科学的にも濃密のようである,しかし絶対的なイコール関係ではない.
・ 篠田 謙一 『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』 中公新書,2022年.
2021-01-06 Wed
■ #4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][world_languages][statistics][demography][language_death][hellog_entry_set]
英語も1つの言語,日本語も1つの言語なので,合わせて2言語ですね.ほかにフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,中国語,韓国語など知っている言語名を挙げ,足し合わせていくと,はたして現代世界にはいくつの言語があることになるでしょうか.100個くらい? あるいは1,000個? もしかして10,000個? このような疑問は抱いたこともなく,見当がつかないという方も多いかもしれません.
実は専門の言語学においても,様々な理由により,正確な数を出すことはできません.論者によって相当な揺れがみられるのです.この辺りの事情も含めて,音声で解説していきましょう.以下をお聴きください.
言語学者が時間とお金をかけて世界中を調査し,頑張って言語を数えていけば,いずれは正確な数が出るのではないかと疑問に思うかもしれませんが,その答えは No です.いくら言語学者が頑張っても,正確な言語数を得ることは不可能です.というのは,これは言語の問題ではないからです.政治の問題なのです.世界の言語を数えるということは,いったいどのような行為なのか.この問いこそが重要なように思われます.
それでも数が知りたいというのが人情です.試しに Ethnologue (第23版,2020年)を参照してみますと,世界の言語の数は7,117とカウントされています.ただし,これとて1つの参考値にすぎませんのでご注意を.今回の素朴な疑問に対しては,私としては「数千個程度」と答えて逃げておきたいと思います.
言語を数えるという問題,およびそれに関連する話題として,##3009,270,1060,274,401,1949の記事セットも合わせてお読みください.
2019-09-27 Fri
■ #3805. The Cambridge Encyclopedia of the English Language 第3版の Part I 「英語史」の目次 [toc][review][demography]
Crystal による英語百科事典 The Cambridge Encyclopedia of the English Language が16年振りに改版された.新しい第3版の序文で,この15年の間に英語に関して多くのことが起こったと述べられているとおり,百科事典として,質も量も膨らんでいる.特に本文の2章から7章を構成する Part I は,120ページ近くに及ぶ英語史の話題の宝庫となっている.その部分の目次を眺めるだけでも楽しめる.以下に掲載しよう.
PART I The History of English
2 The Origins of English
3 Old English
Early Borrowings
Runes
The Old English Corpus
Literary Texts
The Anglo-Saxon Chronicle
Spelling
Sounds
Grammar
Vocabulary
Late Borrowings
Dialects
4 Middle English
French and English
The Transition From Old English
The Middle English Corpus
Literary Texts
Chaucer
Spelling
Sounds
Grammar
Vocabulary
Latin borrowings
Dialects
Middle Scots
The Origins of Standard English
5 Early Modern English
Caxton
Transitional Texts
Renaissance English
The Inkhorn Controversy
Shakespeare
The King James Bible
Spelling and Regularization
Punctuation
Sounds
Original Pronunciation
Grammar
Vocabulary
The Academy Issue
Johnson
6 Modern English
Transition
Grammatical Trends
Prescriptivism
American English
Breaking the Rules
Variety Awareness
Scientific Language
Literary Voices
Dickens
Recent Trends
Current Trends
Linguistic Memes
7 World English
The New World
American Dialects
Canada
Black English Vernacular
Australia
New Zealand
South Africa
West Africa
East Africa
South-East Asia and the South Pacific
A World Language
Numbers of Speakers
Standard English
The Future of English
English Threatened and as Threat
Euro-Englishes
現代を扱う第7章の "World English" が充実している.たとえば英語話者の人口統計がアップデートされており,現時点での総計は23億人を少し超えているという (115) .ちなみに第2版での数字は20億だった.
・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. Cambridge: CUP, 2019.
2019-09-02 Mon
■ #3780. Foley による「標準英語の発展」の記述 [standardisation][hel_education][demography][me_dialect][black_death][printing][caxton]
私たちが普段学び,用いている標準英語 (Standard English) が,歴史上いかに発展してきたかという話題は,英語史の最重要テーマの1つであり,本ブログでも standardisation の記事を中心に様々に取り上げてきた(とりわけ「#3231. 標準語に軸足をおいた Blake の英語史時代区分」 ([2018-03-02-1]),「#3234. 「言語と人間」研究会 (HLC) の春期セミナーで標準英語の発達について話しました」 ([2018-03-05-1]) を参照).
英語の標準化の歴史は,どの英語史の概説書でも必ず取り上げられる話題だが,人類言語学の概説書を著わした Foley の書いている "The Development of Standard English" という1節が,すこぶるよい文章である.要点を押さえながら,教科書的な標準英語の発展を非常に上手にまとめている.3ページ弱にわたるので,引用するのにも決して短くはないが,授業の講読の題材としても使えそうなので,PDFでこちらに用意しておく.
この記述がすぐれている点の1つは,標準英語のベースとなるロンドン英語が諸方言の混合物であることについて,歴史的経緯を分かりやすく説明してくれていることだ.もともと南部方言的な要素を多分に含んでいたロンドンの英語が,14--15世紀のあいだに,経済的に繁栄していた中東部からの人口流入を受けて中部方言的な要素を獲得した.ここには,14世紀後半からの黒死病に起因する人口流動性の高まりも相俟っていたろう.さらに,15世紀中には,羊毛製品で経済的に潤った北部方言の話者も,多くロンドンの上流層へ流れ込み,結果として,諸方言の混合としてのロンドン英語が成立した.そして,これが後の標準英語の母体となっていったのである.
もう1つ注目すべきは,英語史に限定されない一般的な立場から,言語の標準化の3つの条件を提示して議論を締めくくっている点である.1つは,経済的・政治的に有力な地域の言語・方言が標準語の土台となるということ.もう1つは,その言語・方言がエリート集団のものであること.最後に,文学伝統をもった言語・方言が標準語の土台となりやすいことだ.この下りだけでも,以下に直接引用しておきたい.
To summarize, the rise of Standard English . . . exhibits a number of important general points about the how and whys of language standardization: first, if economic and political power is centralized in a particular area, the language of that area has a strong likelihood of being the basis of the standard, as the center imposes its hold upon the periphery (Standard French based on the Parisian dialect is another example of this); second, the standard is likely to be based on the speech of economically and politically powerful social groups, the elite, as their speech becomes imposed upon or diffused to lower status groups; ability to speak this dialect now becomes emblematic of higher social standing and thus a desirable skill, a kind of symbolic resource further empowering the elite, who may control access to the dialect through the education system, as is clearly the case in most modern nation-states; and third, a language or dialect which is the basis of literate forms and other cultural activities is a strong candidate for an imposed standard (Standard Italian based on the Tuscany dialect of Dante exemplifies this). (Foley 403)
・ Foley, William A. Anthropological Linguistics: An Introduction. Malden, MA: Blackwell, 1997.
2019-02-27 Wed
■ #3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか? [history][celtic][anglo-saxon][celtic][historiography][demography][genetics]
昨日の記事「#3592. 文化の拡散を巡る migrationism と diffusionism」 ([2019-02-26-1]) の終わりで述べたように,アングロサクソンの文化や言語の定着は,伝統的にいわれるようにアングロサクソンによる移住・征服によるものだったのか (migrationism) ,あるいは大きな人口の置き換えを伴わない平和的な伝播によるものだったのか (diffusionism) という論争を取り上げよう.
伝統的な migrationism の仮説に対して,主として遺伝学の立場から異論を唱え,diffusionism を掲げた論客として Oppenheimer を紹介しよう.Oppenheimer は,5世紀のアングロサクソンの渡来によって先住のケルト人が一掃されたとする "wipe-out theory" を支持する遺伝学的な証拠はないという.むしろ,驚くべきことに,おそらく新石器時代から現代までの数千年間,ブリテン島の人口構成は,遺伝学的にみる限り,大きく変動していないという.
具体的にいえば,イングランド人の2/3は,最初に農業がもたらされるよりもずっと昔の段階で渡来した南西ヨーロッパ人の遺伝子を引き継いでいるという.一方,残りの1/3の大多数は,紀元前3000--1000年ほどの間に主にスカンディナヴィアからやってきた北西ヨーロッパ人に由来する.そして,おそらく前者がケルト系,後者がゲルマン系の文化と言語をもった人々に対応するだろうという.そして,この比率は,5世紀のアングロサクソン,8世紀のヴァイキング,11世紀のノルマンの渡来によって特に大きく変動することはなく,現代に連なっている(アングロサクソンの征服がイングランド人口にもたらした遺伝上の貢献は5%程度).
このことが意味するのは,アングロサクソンが渡来してきた5世紀はもとより,ローマ人が遠征してきた紀元前後よりも前に,場合にってはそこから3千年以上も遡った時代に,すでに「ケルトの素」と「ゲルマンの素」となる人々が,それぞれ大陸の南西部と北西部からブリテン(諸)島に入ってきていたのではないかということだ.そして,後者の話していた言語は,後の英語に発展するゲルマン系(とりわけ北ゲルマン系)の言語だったのではないかと.
この仮説を信じるならば,この島におけるケルトとゲルマンの共存の歴史は,5世紀のアングロサクソンの渡来に始まるのではなく,もっと古いということになる.5世紀のアングロサクソンの渡来は,すでに両者が共存生活に慣れていたところへ,新世代のアングロサクソンが加わった程度の出来事であり,そこに「征服」というような社会的な大変動があったわけではないということになる.
この仮説は,当然ながら英語史に関しても根本的な再考を促すことになろう.そもそも紀元前よりブリテン島の先住の言語の1つだったということになるからだ.
関連して「#2353. なぜアングロサクソン人はイングランドをかくも素早く征服し得たのか」 ([2015-10-06-1]),「#3094. 449年以前にもゲルマン人はイングランドに存在した」 ([2017-10-16-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) などの記事も参照.
・ Oppenheimer, Stephen. The Origins of the British. 2006. London: Robinson, 2007.
2018-10-27 Sat
■ #3470. 言語戦争の勝敗は何にかかっているか? [japanese][world_languages][lingua_franca][elf][demography][sociolinguistics]
徳川 (245--46) は,日本語史における東西方言(江戸方言と上方方言)の優位をめぐる争いを「言語戦争」の例としながら,一般に言語戦争の勝敗が何によって左右されるのか,されないのかについて論じている.
まず第一に,言語戦争の勝敗は,単純な言語の使用人口などによってきまるものではない,ということである.ひとにぎりの権力者の言語が,多数の庶民の上に君臨するといった場合がある.
また,言語戦争の帰趨は,一般的に,なにも言語それ自体の構造によってきまるものでもない.
たとえば,母音の数が多いから戦に負けるとか,名詞に性と数の別があるから勝つ,といったものではない.ただし,その言語が,言語機能に関して,新しい社会に適応できる性質を具備しているかどうか,といった問題はある.現代にひきつけていえば,複雑な社会機構に対応できるかといった,たとえば表現文体の種類の問題や,原子物理学がその言語で処理できるか,といった内容の問題などがある.さらに,言語コミュニケーションが,他のコミュニケーションチャンネルと,どれほど切り離されているか,といった問題などもあるかもしれない.このことは,おそらく,書きことばの文体の確立と,不離の関係にある.
さきに単なる使用人口の差は言語戦争の勝敗の鍵にならないとしたが,もし多数者の使用言語が,その社会の複雑さと対応して,すでに述べた言語機能を高め,今後さらに多くの人びとをのみ込んでいく包容力といったものを備えているということと結びつくようになれば,それは,ある程度利いてくる条件と言えるであろう.これに対して,土俗的な小言語は,こうした言語機能の面で,将来性について劣る場合が多そうに思われる.また,言語の使用人口の多さが,その言語社会の経済的・政治的・文化的な優位に結びついて,言語の威信といったものの背景になることはありうる.“東西のことば争い”の歴史を考えるにあたっても,こうしたことへの配慮が必要となってくる.
ここで徳川は慎重な議論を展開している.話者人口や言語構造そのものが直接に言語戦争の勝利に貢献するということはないが,それらが当該言語の社会的な機能を高める方向に作用したり,利用されたりすれば,その限りにおいて間接的に貢献することはありうるという見方である.結局のところ,社会的な要素が介在して初めて勝敗への貢献について論じられるということなので,話者人口や言語構造の「直接的な」貢献度はほぼゼロと考えてよいのだろう.英語の世界的拡大や「世界語化」を考える上で,とても重要な論点である.
英語の世界語化の原因を巡っては,関連する話題として「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1]),「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1]),「#2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」」 ([2017-05-10-1]) を参照.
・ 徳川 宗賢 「東西のことば争い」 阪倉 篤義(編)『日本語の歴史』 大修館書店,1977年.243--86頁.
2018-08-02 Thu
■ #3384. 現代世界の代表者としての印欧語族 [indo-european][demography][language_family]
「#1949. 語族ごとの言語数と話者数」 ([2014-08-28-1]) や「#398. 印欧語族は世界人口の半分近くを占める」 ([2010-05-30-1]) で紹介したように,印欧語族 (indo-european) の現代世界における影響力は他の追随を許さない.
現存する最古の文献は Hittite 語のそれであり,4000年ほども遡る.2000年ほど前からは古代ギリシア語,ラテン語,サンスクリット語の文献も多く伝わり,それ以降になると,さらに多くの言語で記された文献が入手可能となる.つまり,世界で最もよく記録に残っている語族なのである.
母語話者人口の観点からみると,2003年の統計ではあるが,印欧語族の言語を母語とする話者は約25億人いるという.標準変種をもち,100万人以上の母語話者を擁する印欧諸語は,70以上ある.400年ほど前までは,およそ旧大陸の西半分にしかその母語話者は分布していなかったが,現代では世界中にその分布を拡げている.まさに近現代を代表する一大語族といってよい.
以上は,Clackson による印欧語言語学入門書のイントロにある,印欧語族の記述をまとめたものである.Clackson (2) の原文を引用しておこう.
The IE language family is extensive in time and space. The earliest attested IE language, Hittite, is attested nearly 4,000 years ago, written on clay tablets in cuneiform script in central Anatolia from the early second millennium BC. We have extensive textual remains, including native-speaker accounts of three more IE languages from 2,000 years ago: Ancient Greek, Latin and Sanskrit. Also from the beginning of the Christian Era we have much more limited corpora of many more IE languages. The stock of recorded IE languages further increases as we move forward in time. In 2003, over 2.5 billion people spoke an IE language as their first language, and there were at least seventy codified varieties, each spoken by a million or more native speakers. Four hundred years ago nearly all speakers of IE lived in Europe, Iran, Turkey, Western Asia and the Indian subcontinent, but migrations have now spread speakers to every part of the world. The wealth of historical material makes IE the best-documented language family in the world.
・ Clackson, James. Indo-European Linguistics. Cambridge: CUP, 2007.
2017-12-02 Sat
■ #3141. 16世紀イングランドの識字率 [literacy][demography][spelling][standardisation]
「#3101. 初期近代英語期の識字率」 ([2017-10-23-1]),「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) に引き続いての話題.16世紀ヨーロッパでは教育制度がおおいに拡充され,文字を読み書きできる人々が多くなってきたことは確かだが,識字率として具体的な数字を与えることは難しい.都市と地方の差,階級差,男女差などが大きく,一般化することが困難であるばかりでなく,そもそも多くの統計や研究が誤った前提に立っているという事情がある.その前提とは,法的書類に署名できる人は文字を読むこともできたとするものだ.近年の脳科学の知見によれば,書くことと読むことはまったく別の行為であり,両者が常に連動するものと考えることはできない.
そこで,ペティグリー (317--19) は,様々な地域からの識字能力に関する断片的な情報を寄せ集めて,識字率を総合的に求めるという手法に訴えかけた.その結果として,以下の見解を導き出している.まず,都市と地方の識字率の差異については,言われるほど大きくなかったのではないかと述べている.人々は年と地方の間を頻繁に移動したし,彼らの集まる市場や酒場ではどこでも印刷物が貼り出されていたからだ.地方出身者であっても,文字を見慣れてはいただろう.
識字率の男女差については,差があっただろうとは想像できても,それが具体的に確かめられるような資料は乏しい.女性は高い識字能力が要求される仕事につくことはなかったために,記録としても残りにくいのである.それでも本を読み,楽しむ女性は多くいたようではある.
よく記録の残っている都市部の男性に限定すれば,高い識字率を誇る都市は印刷以前より存在した.16紀末のヴェネツィアでは33%ほどあったし,1530年のヨークでは20--25%ほどあった.このヨークの男性識字率は,同世紀末までには41%にまで跳ね上がっている.
16世紀,そして続く17世紀にイングランドの識字率が大幅に上昇したことは間違いない.教育の拡充,印刷の普及,その他の社会的要因がこの上昇に貢献しているが,これらの諸要因はまた英語の綴字の標準化にも間接的に寄与しているのである.いよいよ大衆が本格的に文字に接し始めたときに,標準的な綴字が求められるようになったのだろう.
・ ペティグリー,アンドルー(著),桑木 幸司(訳) 『印刷という革命 ルネサンスの本と日常生活』 白水社,2015年.
2017-10-23 Mon
■ #3101. 初期近代英語期の識字率 [literacy][demography][emode][standardisation]
「#3043. 後期近代英語期の識字率」 ([2017-08-26-1]),「#3066. 宗教改革と識字率」 ([2017-09-18-1]) で,英語社会の識字率について話題にしたが,今回は水井 (116--17) より,テューダー朝期を中心とする16--17世紀のイングランドの識字率をみてみよう.
ジェントリの子どもたちにとっては高等教育が社会的に必要であったし,聖職者や法律家になるにはこの方法しかなかった.また,都市の商人の子どもたちにとっては読み書きと計算が将来のために必要であった.しかし,教育費は高額で,富裕層の家庭でも子どもに高等教育を受けさせるためには,家計の中でも相当の割合を占めるような出費を覚悟せねばならなかったのである.より貧しい層では子どもの労働力を家計の足しにする必要があったので,子どもが読み書きを習うために村や町の初等学校に行ったとしても,仕事に就くために通学が短期間で終わることが多かった.読み書きは生きていくために不可欠というわけではなく,農業や手工業の経験的な技術・知識の取得のほうが重要だと考えられることも多かった.
この時期のイングランドではジェントリ層,商人,富裕な農民層を中心に識字率が向上した.一七世紀中にジェントルマン層の識字率はほぼ一〇〇%に近付いていき,商人層,浮遊農民層でも過半数を上回るようになる.しかし,職人層や貧しい農民,女性の識字率は低く一七世紀末でも一〇%から二〇%に達する程度であったと推定されている.
あくまで推計であるし,階層によって数値が異なるという事情も当然あったわけなので,当時の識字率の全体像をつかむことは容易ではない.しかし,この時期の印刷術の普及,出版物の大量の発行,宗教改革に後押しされた読書習慣,教育の向上などにより,着実に人々の識字率が向上していたという趨勢は間違いないだろう.標準綴字の模索と定着も,まさにこの時期の出来事だったことを合わせて確認しておきたい.
・ 水井 万里子 『図説 テューダー朝の歴史』 河出書房,2011年.
2017-09-14 Thu
■ #3062. 1665年のペストに関する Samuel Pepys の記録 [black_death][pepys][literature][history][demography][statistics]
17世紀のイングランドの海軍大臣 Samuel Pepys (1633--1703) は,1660--69年ロンドンでの出来事を記録した日記 The Diary of Samuel Pepys で知られる.1665--66年にロンドンを襲った腺ペスト (The Great Plague) についても,不安をもって記録している.関連する箇所をいくつか抜き出そう.
Sunday 30 April 1665 . . . . Great fears of the sickenesse here in the City, it being said that two or three houses are already shut up. God preserve as all!
Sunday 7 June 1665 . . . . This day, much against my will, I did in Drury Lane see two or three houses marked with a red cross upon the doors, and "Lord have mercy upon us" writ there; which was a sad sight to me, being the first of the kind that, to my remembrance, I ever saw. It put me into an ill conception of myself and my smell, so that I was forced to buy some roll-tobacco to smell to and chaw, which took away the apprehension.
Sunday 10 June 1665 . . . . In the evening home to supper; and there, to my great trouble, hear that the plague is come into the City (though it hath these three or four weeks since its beginning been wholly out of the City) . . . .
Saturday 16 September 1665 . . . . At noon to dinner to my Lord Bruncker, where Sir W. Batten and his Lady come, by invitation, and very merry we were, only that the discourse of the likelihood of the increase of the plague this weeke makes us a little sad, but then again the thoughts of the late prizes make us glad.
上の3つめの引用にあるとおり,ペストがシティに入ってきたのは6月10日頃である.6月下旬には,ロンドン市長と市参事会の連名でペスト条例が公布されている.当時のロンドンの人口は25万人ほどという説があるが,その1/5ほどがわずか1年のあいだに腺ペストに倒れたというから,その勢いは凄まじい(蔵持,pp. 219--226).ペストは翌1666年には下火になっていたものの,くすぶってはいた.ペストが完全に制圧されたのは,皮肉にも9月2日のロンドン大火によってだった.その日の Pepys の日記 (Sunday 2 September 1666) も参照されたい.
・ 蔵持 不三也 『ペストの文化誌 ヨーロッパの民衆文化と疫病』 朝日新聞社〈朝日選書〉,1995年.
2017-09-08 Fri
■ #3056. 黒死病による人口減少と技術革新 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics][printing]
英語史における黒死病 (black_death) の意義は,黒死病→人口減少→英語母語話者の社会的台頭→英語の復権といった因果関係の連鎖に典型的にみることができる.しかし,もっと広い視野から歴史の因果関係を考察すると,黒死病→人口減少→賃金上昇→技術革新という連鎖も認められ,この技術革新が間接的に英語の復権をサポートしたという側面もありそうだ.
ケリーが『黒死病 ペストの中世史』のなかの「必要が新しい技術を生む」という節で,次のように述べている (376--77) .
人口減少は技術革新にも大きな影響を及ぼした.労働力が急激に減少したことから,人手を省くための装置の開発が各分野で進み,書籍作りにもその動きが見られた.十三世紀と十四世紀には,商人や大学教育を受けた専門職や職人などの階級が成長したことから,書籍への需要が着実に伸びた.しかし,中世の造本はきわめて労働集約的な作業だった.まず,数人の写字生が手分けして一冊の本を一折りずつ書き写す.労働賃金が安かった黒死病以前の時代には,この方法でも儲けが出たが,黒死病以後の高賃金の時代になると,そうはいかなかった.そこでドイツのマインツに生まれた野心家の若者ヨハネス・グーテンベルクの登場である.大量死の時代からおよそ百年後の一四五三年,グーテンベルクは世界初の印刷機を世に送り出した.
以上より,1世紀ほどの時間幅があるとはいえ,黒死病→人口減少→賃金上昇→技術革新→印刷術の発明,という連鎖が得られた.印刷術の発明の後に続く連鎖については,「#2927. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上」 ([2017-05-02-1]) と「#2937. 宗教改革,印刷術,英語の地位の向上 (2)」 ([2017-05-12-1]) を参照されたい.黒死病が,最終的には英語の社会的地位の向上につながる.
ケリー (377--79) は,黒死病に起因する技術革新や制度変化が,造本のほか,鉱業,漁業,戦争形態,医療,公衆衛生,高等教育など多くの分野で生じたことを示しており,すでに近代的な科学の方法論を取り入れる素地ができあがりつつあったとも述べている.例えば,高等教育の変化について「ペスト流行後の学問の衰退と聖職者兼教育者の不足」に言及している(ケリー,p. 379).当時の大学の置かれていた状況については「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1]) および「#3055. 黒死病による聖職者の大量死」 ([2017-09-07-1]) を参照.
・ ジョン・ケリー(著),野中 邦子(訳) 『黒死病 ペストの中世史』 中央公論新社,2008年.
2017-09-07 Thu
■ #3055. 黒死病による聖職者の大量死 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics]
連日,黒死病 (black_death) の話題を取りあげている.昨日の記事「#3054. 黒死病による社会の流動化と諸方言の水平化」 ([2017-09-06-1]) では Gooden の英語史読本を参照したが,黒死病を手厚く扱っているもう1つのポピュラーな英語史読本として,Bragg (60--61) を挙げよう.黒死病の英語史における意義に関して特に目新しことを述べているわけではないが,さすがに読ませる書き方ではある.
In 1348 Rattus rattus, the Latin-named black rodent, was the devil in the bestiary. These black rats deserted a ship from the continent which had docked near Weymouth. They carried a deadly cargo, a term that modern science calls Pasteurella pestis, that the fourteenth century named the Great Pestilence and that we know as the Black Death.
The worst plague arrived in these islands, and much, including the language, would be changed radically.
The infected rats scaled out east and then north. They sought out human habitations, building nests in the floors, climbing the wattle and daub walls, shedding the infected fleas that fed on their blood and transmitted bubonic plague. It has been estimated that up to one-third of England's population of four million died. Many others were debilitated for life. In some places entire communities were wiped out. In Ashwell in Hertfordshire, for instance, in the bell tower of the church, some despairing soul, perhaps the parish priest, scratched a short poignant chronicle on the wall in poor Latin. "The first pestilence was in 1350 minus one . . . 1350 was pitiless, wild, violent, only the dregs of the people live to tell the tale."
The dregs are where our story of English moves on. These dregs were the English peasantry who had survived. Though the Black Death was a catastrophe, it set in train a series of social upheavals which would speed the English language along the road to full restoration as the recognised language of the natives. The dregs carried English through the openings made by the Black Death.
The Black Death killed a disproportionate number of the clergy, thus reducing the grip of Latin all over the land. Where people lived communally as the clergy did in monasteries and other religious orders, the incidence of infection and death could be devastatingly high. At a local level, a number of parish priests caught the plague from tending their parishioners; a number ran away. As a result the Latin-speaking clergy was much reduced, in some parts of the country by almost a half. Many of their replacements were laymen, sometimes barely literate, whose only language was English.
More importantly, the Black Death changed society at its roots --- the very place where English was most tenacious, where it was still evolving, where it roosted.
In many parts of the country there was hardly anyone left to work the land or tend the livestock. The acute shortage of labour meant that for the first time those who did the basic work had a lever, had some power to break from their feudal past and demand better conditions and higher wages. The administration put out lengthy and severe notices forbidding labourers to try for wage increases, attempting to force them to keep to pre-plague wages and demands, determined to stifle these uneasy, unruly rumblings. They failed. Wages rose. The price of property fell. Many peasants, artisans, or what might be called working-class people discovered plague-emptied farms and superior houses, which they occupied.
引用中に,聖職者が特にペストの餌食となったことにより,イングランド社会におけるラテン語の影響力が減じたとある.含意として,相対的に大多数の人々の母語である英語が影響力を増したと読める.しかし,聖職者がとりわけ被害を受けたというのが本当なのかどうかについては論争があり,真実は必ずしも明らかにされていない.とはいえ,「聖職者というのは,埋葬に立ち会い,終油の秘蹟をさずけ,あるいは救助活動に身を捧げたりで,患者や死者との接触度が一般人よりもはるかに大きく,それだけ危険度も高かった」(村上,p. 131)というのは,理に適っているように思われる.なお,聖職者は教育者でもあったことも付け加えておこう (cf. 「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1])) .
・ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.
・ 村上 陽一郎 『ペスト大流行 --- ヨーロッパ中世の崩壊 ---』 岩波書店〈岩波新書〉,1983年.
2017-09-06 Wed
■ #3054. 黒死病による社会の流動化と諸方言の水平化 [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][me_dialect][sociolinguistics][dialect_levelling]
英語史では中世における英語の復権と関連して,たいてい黒死病のことが触れられる.しかし,簡単に言及されるにとどまり,突っ込んだ説明のないものも多い.そのなかで,一般向けの英語史読本を著わした Gooden (67--68) は,黒死病に対して1節を割くほどの関心を示している.読み物としておもしろいので引用しておこう.なお,引用の第2段落の1部は,Black Death の語源と関連して「#2990. Black Death」 ([2017-07-04-1]) でも取りあげた.
The Black Death had a devastating effect on the British Isles, as on the rest of Europe. The population of England was cut by anything between a third and a half. Probably originating in Asia, the plague arrived in a Dorset port in the West country in 1348, rapidly spreading to Bristol and then to Gloucester, Oxford and London. If a rate of progress were to be allotted to the plague, it was advancing at about one-and-a-half miles a day. The major population centres, linked by trading routes, were the most obviously vulnerable but the epidemic had reached even the remotest areas of western Ireland by the end of the next decade. Symptoms such as swellings (the lumps or buboes that characterize bubonic plague), fever and delirium were almost invariably followed within a few days by death. Ignorance of its cause heightened panic and public fatalism, as well as hampering effectual preventive measures. Although the epidemic petered out in the short term, the disease did not go away, recurring in localized attacks and then major outbreaks during the 17th century which particularly affected London. One of them disrupted the preparations for the coronation of James I in 1603; the last major epidemic killed 70,000 Londoners in 1665.
The term 'Black Death' came into use after the Middle Ages. It was so called either because of the black lumps or because in the Latin phrase atra mors, which means 'terrible death', atra can also carry the sense of 'black'. To the unfortunate victims, it was the plague, or, more often, the pestilence. So Geoffrey Chaucer calls it in The Pardoner's Tale, where he makes it synonymous with death. The words survive in modern English even if with a much diminished force in colloquial use: 'He's a pest.' 'Stop plaguing us!' Curiously, although pest in the sense of 'nuisance' has its roots in pestilence, the word pester comes from a quite different source, the Old French empêtrer ('entangle', 'get in the way of').
The impact of the pestilence on English society was profound. Quite apart from the psychological effects, there were practical consequences. Labour shortages meant a rise in wages and more fluid social structure in which the old feudal bonds began to break down. Geographical mobility would also have helped in dissolving regional distinctions and dialect differences.
黒死病による人口減少により,生き残った労働者の賃金が上がり,彼らの社会的地位が上昇するとともに彼らの母語である英語の社会的地位も上昇した,というのが黒死病の英語史上のインパクトと言われる.しかし,引用の最後にあるように,人々が社会的にも地理的にも流動化したという点にも注目すべきである.これにより,人々がますます混交し,とりわけロンドンのような都会では諸方言が水平化してゆく契機となった (cf. dialect levelling) .黒死病は,確かに英語の行く末に間接的な影響を与えたといえるだろう.
・ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.
2017-09-05 Tue
■ #3053. 黒死病により農奴制から自由農民制へ [black_death][reestablishment_of_english][history][demography][sociolinguistics]
1348年に起こった黒死病 (black_death) について,本ブログでも何度か取りあげてきた(cf. 「#119. 英語を世界語にしたのはクマネズミか!?」 ([2009-08-24-1]),「#138. 黒死病と英語復権の関係について再考」 ([2009-09-12-1]),「#1206. 中世イングランドにおける英語による教育の始まり」 ([2012-08-15-1])).今回は,英語史における黒死病の意義を考えるにあたって,特に農業経済の変化に焦点を当てつつ,広い視野から当時の歴史的背景を紹介したい.
黒死病に関する McDowall (46--47) からの文章を引こう.
Probably more than one-third of the entire population of Britain died, and fewer than one person in ten who caught the plague managed to survive it. Whole villages disappeared, and some towns were almost completely deserted until the plague itself died out.
The Black Death was neither the first natural disaster of the fourteenth century, nor the last. Plagues had killed sheep and other animals earlier in the century. An agricultural crisis resulted from the growth in population and the need to produce more food. Land was no longer allowed to rest one year in three, which meant that it was over-used, resulting in years of famine when the harvest failed. This process had already begun to slow down population growth by 1300.
After the Black Death there were other plagues during the rest of the century which killed mostly the young and healthy. In 1300 the population of Britain had probably been over four million. By the end of the century it was probably hardly half that figure, and it only began to grow again in the second half of the fifteenth century. Even so, it took until the seventeenth century before the population reached four million again.
The dramatic fall in population, however, was not entirely a bad thing. At the end of the thirteenth century the sharp rise in prices had led an increasing number of landlords to stop paying workers for their labour, and to go back to serf labour in order to avoid losses. In return villagers were given land to farm, but this tenanted land was often the poorest land of the manorial estate. After the Black Death there were so few people to work on the land that the remaining workers could ask for more money for their labour. We know they did this because the king and Parliament tried again and again to control wage increases. We also know from these repeated efforts that they cannot have been successful. The poor found that they could demand more money and did so. This finally led to the end of serfdom.
Because of the shortage and expense of labour, landlords returned to the twelfth-century practice of letting out their land to energetic freeman farmers who bit by bit added to their own land. In the twelfth century, however, the practice of letting out farms had been a way of increasing the landlord's profits. Now it became a way of avoiding losses. Many "firma" agreements were for a whole life span, and some for several life spans. By the mid-fifteenth century few landlords had home farms at all. These smaller farmers who rented the manorial lands slowly became a new class, known as the "yeomen". They became an important part of the agricultural economy, and have always remained so.
Overall, agricultural land production shrank, but those who survived the disasters of the fourteenth century enjoyed a greater share of the agricultural economy. Even for peasants life became more comfortable. For the first time they had enough money to build more solid houses, in stone where it was available, in place of huts made of wood, mud and thatch.
黒死病の勃発する1358年より前にも,疫病,人口増加,農地不足はすでに大きな問題となっており,農業経済は行き詰まっていた.農奴制 (serfdom) も持ちこたえられなくなっており,賃金労働者たる自由農民 (yeoman) という新しい身分が出現し始めていた.そこへ黒死病が到来し,生産者人口が激減するに及んで,生き残った生産者の社会的地位が高まった.このようにして,とりわけ自由農民の層が15世紀にかけて存在感と発言力を増していった.そして,彼らの話す言葉こそが,英語だったのである.
McIntyre (15) が述べている通り,"the greater the influence a particular group has within society, the more likely it is that the language spoken by that group will be seen as prestigious."である.英語は,中世イングランドの農業経済の変化(農奴制から自由農民制へ)とともに復権を果たしたといえる.
ただし,黒死病が必ずしも農業経済に直接の影響を及ぼしたわけではない,それは旧来の学説だとする見方も,近年影響力を高めてきているようではあるマクニール(下巻,p. 58 を参照).
・ McDowall, David. An Illustrated History of Britain. Harlow: Longman 1989.
・ McIntyre, Dan. History of English: A Resource Book for Students. Abingdon: Routledge. 2009.
・ ウィリアム・H・マクニール(著),佐々木 昭夫(訳) 『疫病と世界史 上・下』 中央公論新社〈中公文庫〉,2007年.
2017-08-26 Sat
■ #3043. 後期近代英語期の識字率 [literacy][demography][spelling][lexicology]
過去の社会の識字率を得ることは一般に難しいが,後期近代英語期の英語社会について,ある程度分かっていることがある.以下にメモしておこう.
まず,Fairman (265) は,19世紀初期の状況として次の事実を指摘している.
1) In some parts of England 70% of the population could not write . . . . For them English was only sound, and not also marks on paper.
2) Of the one-third to 40% who could write, less than 5% could produce texts near enough to schooled English --- that is, to the type of English taught formally --- to have a chance of being printed.
Simon (160) は,19世紀中の識字率の激増,特に女性の値の増加について触れている.
The nineteenth century witnessed a huge increase in literacy, especially in the second half of the century. In 1850 30 per cent of men and 45 per cent of women were unable to sign their own names; by 1900 that figure had shrunk to just 1 per cent for both sexes.
上のような識字率と関連させて,Tieken-Boon van Ostade (45--46) がこの時代の綴字教育について論じている.貧しさゆえに就学期間が短く,中途半端な綴字教育しか受けられなかった子供たちは,せいぜい単音節語を綴れるにすぎなかっただろう.このことは,本来語はおよそ綴れるが,ほぼ多音節語からなるラテン語やフランス語からの借用語は綴れないことを意味する.文体レベルの高い借用語を自由に扱えないようでは社会的には無教養とみなされるのだから,彼らは書き言葉における「制限コード」 (restricted code) に甘んじざるをえなかったと表現してもよいだろう.
識字率,綴字教育,音節数,本来語と借用語,制限コード.これらは言語と社会の接点を示すキーワードである.
・ Fairman, Tony. "Letters of the English Labouring Classes and the English Language, 1800--34." Insights into Late Modern English. 2nd ed. Ed. Marina Dossena and Charles Jones. Bern: Peter Lang, 2007. 265--82.
・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.
・ Tieken-Boon van Ostade, Ingrid. An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2009.
2017-07-23 Sun
■ #3009. 母語話者数による世界トップ25言語(2017年版) [statistics][world_languages][demography][japanese]
「#397. 母語話者数による世界トップ25言語」 ([2010-05-29-1]) を書いてから7年の年月が経った.Ethnologue (20th ed) の最新版が出たので,Summary by language size の表3により,母語話者数による世界トップ23言語の最新ランキングを示したい.
| Rank | Language | Primary Country | Countries | Speakers (20th ed, 2017) | Speakers (16th ed, 2009) | (13th ed, 1996) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chinese | China | 37 | 1,284 million | 1,213 | 1,123 |
| 2 | Spanish | Spain | 31 | 437 | 329 | 266 |
| 3 | English | United Kingdom | 106 | 372 | 328 | 322 |
| 4 | Arabic | Saudi Arabia | 57 | 295 | 221 | 202 |
| 5 | Hindi | India | 5 | 260 | 182 (242.6 with Urdu) | (236 with Urdu) |
| 6 | Bengali | Bangladesh | 4 | 242 | 181 | 189 |
| 7 | Portuguese | Portugal | 13 | 219 | 178 | 170 |
| 8 | Russian | Russian Federation | 19 | 154 | 144 | 288 |
| 9 | Japanese | Japan | 2 | 128 | 122 | 125 |
| 10 | Lahnda | Pakistan | 6 | 119 | 78.3 | |
| 11 | Javanese | Indonesia | 3 | 84.4 | 84.6 | |
| 12 | Korean | Korea | 7 | 77.2 | 66.3 | |
| 13 | German | Germany | 27 | 76.8 | 90.3 | 98 |
| 14 | French | France | 53 | 76.1 | 67.8 | 72 |
| 15 | Telugu | India | 2 | 74.2 | 69.8 | |
| 16 | Marathi | India | 1 | 71.8 | 68.1 | |
| 17 | Turkish | Turkey | 8 | 71.1 | 50.8 | |
| 18 | Urdu | Pakistan | 6 | 69.1 | 60.6 | |
| 19 | Vietnamese | Viet Nam | 3 | 68.1 | 68.6 | |
| 20 | Tamil | India | 7 | 68.0 | 65.7 | |
| 21 | Italian | Italy | 13 | 63.4 | 61.7 | 63 |
| 22 | Persian | Iran | 30 | 61.9 | ||
| 23 | Malay | Malaysia | 16 | 60.8 | 39.1 | 47 |
2009年の16版の統計では2位スペイン語と3位英語の差はごくわずかで事実上のタイだったが,今回のデータによれば,2位のスペイン語が英語を勢いで引き離しにかかっていることがわかる.3位の英語は,むしろ今後は4位のアラビア語に詰め寄られることになりそうだ.
続くランキングで,9位につけている日本語までは,ここ数年で順位が変わっていないものの,10位だったドイツ語が13位まで順位を落としているのが印象的である.フランス語は,むしろ16位から14位へ若干順位を上げている.
近い将来,9位につけている日本語が徐々にランキングを下げていくことは必至である.日本以外に母語として使用される国がないこと,また日本の人口減の傾向が主たる要因である.ジャワ語やベトナム語などに肉薄されるのも時間の問題だろう.
「#274. 言語数と話者数」 ([2010-01-26-1]) で示したように,少数のトップ言語が世界人口の多くを担っているという事態は変わっていないどころか,傾向が加速化している.例えば,上の表の15位までの言語の母語話者の合計は約40億人となり,これは世界人口の6割近くに当たる.うち6言語は国連の公用語であり,これだけで148国をカバーする.言語の寡頭支配ぶりは明らかだろう.
2016-12-29 Thu
■ #2803. アイルランド語の話者人口と使用地域 [irish][ireland][demography][celtic][map]
アイルランドにおけるアイルランド語から英語への言語交替 (language_shift) について「#2798. 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.」 ([2016-12-24-1]),「#1715. Ireland における英語の歴史」 ([2014-01-06-1]) で取り上げた.言語交替は現在も進行中だが,アイルランド語 (irish) はいまだ確かに使用されている.アイルランド語使用の実態について,嶋田 (20--20) の記述を箇条書きにまとめてみよう.
・ 現代アイルランドでは日々のコミュニケーションの主流は英語である
・ アイルランド語のみを話す話者は存在しない
・ 日常的にアイルランド語を用いるのは,人口の2%程度である
・ 2011年の国勢調査によるとアイルランド語話者(=「アイルランド語が話せる話者」)は約177万人で,これは3歳以上の人口の40.6%に相当する
・ アイルランド共和国憲法第8条にはアイルランド語が国語 (national language) であり第1公用語であることが記されている(英語は第2公用語)
・ アイルランド語は,多くのアイルランド人にとって学校で学ぶ言語である
・ 民族語であるアイルランド語を習得することは公共機関の仕事に就くために必須であり,高く評価される
・ アイルランドは,2010年から2030年までの「20年戦略」でアイルランド語と英語のバイリンガルをできる限り増やす計画を立てている
・ 現地ではアイルランド語は「ゲール語」 (Gaelic) と称され,ゲール語使用地域は「ゲールタハト」 (Gaeltacht) と呼ばれる
最後に触れたゲールタハトは,アイルランド島の西部を中心に小区画として点在している(ただし,広義にはスコットランドのゲール語使用地域も含む).Údarás na Gaeltachta のホームページによると,"The Gaeltacht covers extensive parts of counties Donegal, Mayo, Galway and Kerry --- all along the western seaboard --- and also parts of counties Cork, Meath and Waterford." と説明書きがある.以下に簡単な地図を再現しておこう(「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]) の地図も参照).

アイルランド語の歴史の概略については,Background on the Irish Language の記事も有用.関連して,アイルランドの歴史について「#762. エリザベス女王の歴史的なアイルランド訪問」 ([2011-05-29-1]),「#2361. アイルランド歴史年表」 ([2015-10-14-1]) も参照されたい.
・ 嶋田 珠巳 『英語という選択 アイルランドの今』 岩波書店,2016年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow