2024-06-30 Sun
■ #5543. syntagmatic contamination と paradigmatic contamination [language_change][analogy][folk_etymology][contamination][assimilation][numeral][collocation][semantics][antonymy]
言語変化 (language_change) の基本的な原動力の1つである類推作用 (analogy) に関する本格的な研究書,Fertig の Analogy and Morphological Change についてはこちらの記事群で取り上げてきた.
今回は Fertig を参照し,contamination (混成)と呼ばれるタイプの類推作用について考えてみたい.「混成」とその周辺の現象が明確に分けられるかどうかについては議論があり,「#5419. blending と contamination」 ([2024-02-27-1]) でも関連する話題を取り上げたが,ひとまず contamination を区別できるものと理解し,そのなかに2つのタイプがあるという議論を導入したい.syntagmatic contamination と paradigmatic contamination である.具体例とともに Fertig からの関連箇所を引用する (64) .
Paul's initial conception of contamination (1886) involved influence attributable exclusively to paradigmatic (semantic) relations between forms, but he later (1920) recognized that lexical contamination often involves items that are not only semantically related but also frequently occur in close proximity in utterances. The importance of these syntagmatic relationships is emphasized in almost all modern accounts of contamination (Campbell 2004: 118--20 being the only exception that I am aware of). The most frequently cited examples involve adjacent numerals, which often influence each other's phonetic make-up: English eleven < Proto-Gmc. *ainlif under the influence of ten; Latin novem 'nine' instead of expected *noven under the influence of decem 'ten'; Greek dialectal hoktō 'eight' under the influence of hepta 'seven' (Osthoff 1878b; Trask 1996: 111--12; Hock and Joseph 2009: 163). Similar effects are attested in a number of languages among days of the week and months of the year, e.g. post-classical Latin Octember < Octōber under the influence of November and December.
Such contamination attributable to syntagmatic proximity of the affecting and affected items is often characterized as distant assimilation. Some scholars characterize contamination as a kind of assimilation even when it is purely paradigmatically motivated. Anttila calls it 'assimilation . . . toward another word in the semantic field' (1989: 76). Andersen (1980: 16--17) explicitly distinguishes such 'paradigmatic assimilation' from the more familiar 'syntagmatic assimilation'. As an unambiguous example of the latter, he mentions the influence of one word on another within a formulaic expression, such as French au fur et à mesure 'as, in due course' < Old French au feur et mesure (Wackernagel 1926: 49--50). Contamination involving antonyms, such as Late Latin sinexter < sinister 'left' under the influence of dexter 'right' or Vulgar Latin grevis < gravis 'heavy' under the influence of levis 'light', could be both paradigmatically and syntagmatically motivated since antonyms frequently co-occur in close proximity within an utterance, especially in questions: Is that thing heavy or light? Should I turn right or left? Wundt's view of paradigm leveling as a type of assimilation should also be mentioned in this context (Paul 1920: 116n 1).
syntagmatic contamination と paradigmatic contamination の2種類を区別しておくことは,理論的には重要だろう.しかし,実際的には両者は互いに乗り入れており,分別は難しいのではないかと思われる.paradigmatic な関係にある2者は syntagmatic には and などの等位接続詞で結ばれることも多いし,逆に syntagmatic に共起しやすい2者は paradigmatic にも意味論的に強固に結びつけられているのが普通だろう.
個々の事例が,いずれかのタイプの contamination であると明言することができるのかどうか,あるいはできるとしても,そう判断してよい条件は何か,という問題が残っているように思われる.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-03-11 Mon
■ #5432. 複数形の -(r)en はもともと派生接尾辞で屈折接尾辞ではなかった [exaptation][language_change][plural][morphology][derivation][inflection][indo-european][suffix][rhotacism][sound_change][germanic][german][reanalysis]
長らく名詞複数形の歴史を研究してきた身だが,古英語で見られる「不規則」な複数形を作る屈折接尾辞 -ru や -n がそれぞれ印欧祖語の段階では派生接尾辞だったとは知らなかった.前者は ċildru "children" などにみられるが,動作名詞を作る派生接尾辞だったという.後者は ēagan "eyes" などにみられるが,個別化の意味を担う派生接尾辞だったようだ.
この点について,Fertig (38) がゲルマン諸語の複数接辞の略史を交えながら興味深く語っている.
There are a couple of cases in Germanic where an originally derivational suffix acquired a new inflectional function after regular phonetic attrition at the ends of words resulted in a situation where the suffix only remained in certain forms in the paradigm. The derivational suffix *-es-/-os- was used in proto-Indo-European to form action nouns . . . . In West Germanic languages, this suffix was regularly lost in some forms of the inflectional paradigm, and where it survived it eventually took on the form -er (s > r is a regular conditioned sound change known as rhotacism). The only relic of this suffix in Modern English can be seen in the doubly-marked plural form children. It played a more important role in noun inflection in Old English, as it still does in modern German, where it functions as the plural ending for a fairly large class of nouns, e.g. Kind--Kinder 'child(ren)'; Rind--Rinder 'cattle'; Mann--Männer 'man--men'; Lamm--Lämmer 'labm(s)', etc. The evolution of this morpheme from a derivational suffix to a plural marker involved a complex interaction of sound change, reanalysis (exaptation) and overt analogical changes (partial paradigm leveling and extension to new lexical items). A similar story can be told about the -en suffix, which survives in modern standard English only in oxen and children, but is one of the most important plural endings in modern German and Dutch and also marks a case distinction (nominative vs. non-nominative) in one class of German nouns. It was originally a derivational suffix with an individualizing function . . . .
child(ren), eye(s), ox(en) に関する話題は,これまでも様々に取り上げてきた.以下のコンテンツ等を参照.
・ hellog 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])
・ hellog 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])
・ hellog 「#145. child と children の母音の長さ」 ([2009-09-19-1])
・ hellog 「#218. 二重複数」 ([2009-12-01-1])
・ hellog 「#219. eyes を表す172通りの綴字」 ([2009-12-02-1])
・ hellog 「#2284. eye の発音の歴史」 ([2015-07-29-1])
・ hellog-radio (← heldio の前身) 「#31. なぜ child の複数形は children なのですか?」
・ heldio 「#202. child と children の母音の長さ」
・ heldio 「#291. 雄牛 ox の複数形は oxen」
・ heldio 「#396. なぜ I と eye が同じ発音になるの?」
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-03-10 Sun
■ #5431. 指示詞 that は定冠詞 the から独立して生まれた [exaptation][language_change][article][demonstrative][determiner][oe][pronoun][voicy][heldio][reanalysis]
英語史では,指示詞 that が定冠詞 the から分岐して独立した語であることが知られている.古英語の定冠詞(起源的には指示詞であり,まだ現代の定冠詞としての用法が強固に確立してはいなかったが,便宜上このように呼んでおく)の se は性・数・格に応じて屈折し,様々な形態を取った.そのなかで中性,単数,主格・対格の形態が þæt だった.これが現代英語の指示詞 that の形態上の祖先である.この古英語の事情に鑑みると,that は the の1形態にすぎないということになる.
では,なぜその後 that は the の仲間グループから抜け出し,独立した指示詞として発達したのだろうか.古英語から中英語にかけて,定冠詞の様々な屈折形態は the という同一形態へと水平化していいった.この流れが続けば,the の1屈折形にすぎない that もやがて消えゆく運命ではあった.ところが,that は指示詞という別の機能を獲得し,消えゆく運命から脱することができたのである.正確にいえば,もとの the 自身にも指示詞の機能はあったところに,その指示詞の機能を the から奪うようにして that が独立した,ということだ.つまり,指示詞 that の機能上の祖先は the に内在していたことになる.その後,既存の「近称」の指示詞 this との棲み分けが順調に進み,that は「遠称」の指示詞として確立するに至った.
Fertig (37--38) は,この一連の言語変化を外適応 (exaptation) の事例として紹介している.
A simple example can be seen in the modern survival of two singular forms from the Old English demonstrative paradigm: the and that. The contrast between these two forms originally reflected a gender distinction; that (OE þæt) was an exclusively neuter form, while the predecessors of the were non-neuter. One would expect one of these forms to have been lost with the collapse of grammatical gender. They survived by being redeployed for the distinction between definite article (the) and demonstrative (that).
指示詞 that の発達と関連して,以下の heldio と hellog のコンテンツを参照.
・ heldio 「#493. 指示詞 this, that, these, those の語源」
・ hellog 「#154. 古英語の決定詞 se の屈折」 ([2009-09-28-1])
・ hellog 「#156. 古英語の se の品詞は何か」 ([2009-09-30-1])
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-02-20 Tue
■ #5412. 原初の言語は複雑だったのか,単純だったのか? [origin_of_language][language_change][evolution][history_of_linguistics][language_myth][sobokunagimon][simplification][homo_sapiens]
言語学史のハンドブックを読んでいる.Mufwene の言語の起源・進化に関する章では,これまでに提案されてきた様々な言語起源・進化論が紹介されており,一読の価値がある.
私もよく問われる素朴な疑問の1つに,原初の言語は複雑だったのか,あるいは単純だったのか,という言語の起源に関するものがある.一方,言語進化の観点からは,原初の段階から現代まで言語は単純化してきたのか,複雑化してきたのか,という関連する疑問が生じてくる.
真の答えは分からない.いずれの立場についても論者がいる.例えば,前者を採る Jespersen と,後者の論客 Bickerton は好対照をなす.Mufwene (31) の解説を引用しよう.
His [= Jespersen's] conclusion is that the initial language must have had forms that were more complex and non-analytic; modern languages reflect evolution toward perfection which must presumably be found in languages without inflections and tones. It is not clear what Jespersen's position on derivational morphology is. In any case, his views are at odds with Bickerton's . . . hypothesis that the protolanguage, which allegedly emerged by the late Homo erectus, was much simpler and had minimal syntax, if any. While Bickerton sees in pidgins fossils of that protolanguage and in creoles the earliest forms of complex grammar that could putatively evolve from them, Jespersen would perhaps see in them the ultimate stage of the evolution of language to date. Many of us today find it difficult to side with one or the other position.
両陣営ともに独自の前提に基づいており,その前提がそもそも正しいのかどうかを確認する手段がないので,議論は平行線をたどらざるを得ない.また,言語の複雑性と単純性とは何かという別の難題も立ちはだかる.最後の問題については「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#4165. 言語の複雑さについて再考」 ([2020-09-21-1]) などを参照.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2024-02-19 Mon
■ #5411. heldio で「文法化」を導入するシリーズをお届けしました [voicy][heldio][grammaticalisation][notice][hel_education][language_change][link]
毎朝6時に,本ブログの姉妹版ともいえる音声ブログ Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」を配信しています.2024年の heldio のテーマは言語変化 (language_change) です.大きなテーマなので取り上げていく話題も多岐にわたりますが,避けて通れないものの1つに文法化 (grammaticalisation) があります.本ブログでも「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) を始めとして,多くの記事で注目してきました.
先週,heldio にて5日連続で文法化の超入門となる話題をお届けしました.結果的に文法化の導入シリーズとなりました.こちらにリンクをまとめておきます.
・ 「#988. ぎゅうぎゅうの単語とすかすかの単語 --- 内容語と機能語」
・ 「#989. 内容語と機能語のそれぞれの特徴を比較する」
・ 「#990. 文法化とは何か?」
・ 「#991. while の文法化」
・ 「#992. while の文法化(続き)」
(以下,後記)
・ 「#1001. 英語の文法化について知りたいなら --- 保坂道雄(著)『文法化する英語』(開拓社,2014年)」
・ 「#1003. There is an apple on the table. --- 主語はどれ?」
(後記,ここまで)
5回の話しはスムーズにつながっているので,順に聴いていただくとよいと思います.手っ取り早く聴きたいという方は,中心回となる「#990. 文法化とは何か?」だけでもシリーズの大枠はつかめると思います.
もっと本格的に文法化を学びたいという方は,本ブログの grammaticalisation の各記事をご覧ください.特に重要な記事をいくつか挙げておきます.
・ 「#1972. Meillet の文法化」 ([2014-09-20-1])
・ 「#1974. 文法化研究の発展と拡大 (1)」 ([2014-09-22-1])
・ 「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1])
・ 「#2575. 言語変化の一方向性」 ([2016-05-15-1])
・ 「#2576. 脱文法化と語彙化」 ([2016-05-16-1])
・ 「#3273. Lehman による文法化の尺度,6点」 ([2018-04-13-1])
・ 「#3272. 文法化の2つのメカニズム」 ([2018-04-12-1])
・ 「#3281. Hopper and Traugott による文法化の定義と本質」 ([2018-04-21-1])
・ 「#5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要」 ([2023-05-08-1])
2024-01-21 Sun
■ #5382. 文法化のもう1つの道筋 [grammaticalisation][language_change][unidirectionality][bleaching][subjectification]
昨日の記事「#5381. 文法化の道筋と文法化の程度を図るパラメータ」 ([2024-01-20-1]) で,Wischer を参照して文法化の道筋と,それと関連するパラメータを紹介した.もともと文法化 (grammaticalisation) という場合には,昨日示した統語的単位から形態的単位への変化過程がその基本的なパターンとして認識されてきた.つまり,あくまで命題内部での文法的変化としてとらえられてきたのである.
しかし,命題よりスコープの広いテキスト (text) や談話 (discourse) というレベルに関わる,もう1つのタイプの文法化があることがわかってきた.Wischer (356) は Traugott を参照して一方向性 (unidirectionality) を含意する次の経路を示している.
proposition → text → discourse
この談話化ともいうべきタイプの文法化は,昨日示したタイプの文法化とは多くの点で異なっている.実際,昨日挙げたパラメータは,今回のタイプにはあまり当てはまらない.(1) attrition については,確かに音形の縮小や意味の漂白化(とりわけ主観化)が生じやすいとはいえる.しかし,(2) paradigmaticization はまったくあてはまらない.(3) obligatorification については,文法化された項の頻度は高まるものの,文法規則のような義務化は起こらない.(4) condensation に関してはスコープは狭まるのではなく,むしろ拡がるし,(5) coalescence も生じない.(6) fixation については,生起する統語的位置には傾向が見られるが,必ずしも厳密に固定されるわけではない.
文法化の議論では,このように2つのタイプが論じられてきたものの,それぞれが独自の特徴をもっているため,区別して理解しておくべきだろう.
・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.
・ Traugott, E. C. "From Propositional to Textual and Expressive Meanings: Some Semantic-Pragmatic Aspects of Grammaticalization." Perspectives on Historical Linguistics. Ed. W. P. Lehmann and Y. Malkiel. Amsterdam: Benjamins, 1982. 245--71.
2024-01-20 Sat
■ #5381. 文法化の道筋と文法化の程度を図るパラメータ [grammaticalisation][language_change][syntax][morphology][phonology][unidirectionality]
言語変化のメカニズムとして研究が深まってきている文法化 (grammaticalisation) については「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) をはじめ多くの記事で取り上げてきた.今回は,多くの先行研究を参照した Wischer 論文の冒頭部分を参考に,文法化の典型的な道筋と文法化の程度を図るパラメータを紹介する.
まず Wischer (356) は Givón (1979: 209) を参照しつつ,文法化の1つの典型的な経路として以下のパターンを導入する.
discourse → syntax → morphology → morphophonemics → zero
文法化の理論では,ここの矢印に示される言語変化の一方向性 (unidirectionality) がしばしば問題となる.
続けて Wischer (356) は,Lehmann (1985: 307--08) を参照しつつ,文法化の程度を図るパラメータを示す.
1. "attrition": the gradual loss of semantic and phonological substance;
2. "paradigmaticization": the increasing integration of a syntactic element into a morphological paradigm;
3. "obligatorification": the choice of the linguistic item becomes rule-governed;
4. "condensation": the shrinking of scope;
5. "coalescence": once a syntactic unit has become morphological, it gains in bondedness and may even fuse with the constituent it governs;
6. "fixation": the item loses its syntagmatic variability and becomes a slot filler.
要約していえば,文法化とは,拘束されない統語的単位が高度に制限された文法的形態素へ変容していく過程ととらえることができる.
・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.
・ Givón, Talmy. On Understanding Grammar. New York: Academic P, 1979.
・ Lehmann, Chr. "Grammaticalisation: Synchronic Variation and Diachronic Change." Lingua e stile 20 (1985): 303--18.
2024-01-19 Fri
■ #5380. 類推は言語が変化しないことをも説明できる [analogy][language_change][plural][voicy][heldio]
Fertig (76) は "Analogical non-change" と題する節のなかで,英語の規則的な複数形を作る -s を題材にして,類推作用 (analogy) の役割について独特な視点から論じている.
. . . stasis over time can be just as interesting a historical phenomenon as change (Janda and Joseph 2003: 83, 86). Although accounts of analogy rarely call attention to the fact, there are a number of examples in the literature where the mechanisms of morphological change are invoked to account for an absence of overt change, i.e. for the survival of an element, construction or distinction. Saussure (1995 [1916]: 236--7) reminds us that analogy2 is just as much responsible for the lack of change in the inflection of most forms that have always belonged to dominant, regular classes as it is for change in other, primarily irregular items. English speakers, for example, form the plural of dozens of nouns such as stone, eel, oath, comb, stool, etc. essentially the same way they were formed in Old English, not because each of these plurals has been transmitted perfectly across all the generations, but rather primarily because analogy2 yields exactly the same results as if the forms had been transmitted perfectly. These nouns all belong to the dominant class that formed their plurals with -as in Old English so even if English speakers never memorize any of them and always rely on analogy2 to recreate them, they continue to come up with the same forms that were used in the past.
Fertig は,言語の変化のみならず言語の無変化の背景にも関心を寄せる論者である.「#4228. 歴史言語学は「なぜ変化したか」だけでなく「なぜ変化しなかったか」をも問う」 ([2020-11-23-1]) でも,Fertig からの重要な指摘を引用している.言語の無変化にも意義があるという議論については「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1]) も参照されたい.
今年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の主題は言語変化 (language) だが,同様に言語無変化も取り上げていきたい.新年の2回の配信回もぜひお聴きください.
・ 「#945. なぜ言語は変化するのか?」 (2024/01/01)
・ 「#947. なぜ言語は変化しないのか?」 (2024/01/03)
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-01-13 Sat
■ #5374. 類推および関連する過程を例示する英文 --- Fertig の冒頭より [analogy][backformation][folk_etymology][morphology][language_change][voicy][heldio]
一昨日の heldio で「#955. 妙な英文で味わうアナロジー(および関連する過程)」を配信した.本ブログでも同じ話題をカバーしておきたい.
「#4229. Fertig による analogy の定義」 ([2020-11-24-1]) や「#5336. Fertig による analogy の本格的研究書の目次」 ([2023-12-06-1]) で紹介した Fertig の analogy に関する研究書の冒頭は,次のような英文の例示で飾られる.
A book about analogy and morphological change? That is so not what I was expecting. I never imaginated there'd ever be such a book. I guess I had another thing coming. Who'd of thunk it?
この英文には類推 (analogy) およびそれと関連する言語革新の過程を示す事例が4つ(あるいは5つ)含まれている.すべてが類推の事例,あるいは類推に似ている事例である.それぞれを解説する1節も引用しておきたい.
The short paragraph above contains at least four recognizable examples of some of the different kinds of innovations that we will be exploring in this book. That is so not . . . is an example of analogical change in syntax. Until recently, the intensifier so could only be used directly before an adjective or adverb. Now some speakers regularly use it in other syntactic contexts, such as before the negative particle not. This change can be attributed to the analogy of other intensifiers such as really . . . . The next sentence contains the verb imaginate, which sounds very odd to many English speakers today but has been around since 1541. It means the same thing as the much more common and older verb imagine and may have been created by backformation from the noun imagination, on the analogical model of pairs like speculation--speculate, dedication--dedicate, etc. The fourth sentence contains an altered version of the familiar expression to have another think coming, meaning 'to be seriously mistaken about something'. For at least a century, English speakers/learners have sometimes mistaken the word think in this expression for thing. This kind of change is called folk etymology. It occurs when speakers identify one element in an expression with a different, often historically unrelated element. The word of (for 've) in the final sentence of the paragraph could also be considered folk etymology. Finally, thunk is obviously an innovative past-participle form corresponding to standard thought. It is based on analogical models such as sink--sank--sunk or stick--stuck.
ここから太字表記のものも含めいくつかキーワードと拾うと,innovations, analogical change, backformation, analogical model, folk_etymology などが挙がってくる.Fertig の本では,これらの用語や概念が丁寧に議論されていく.言語における類推(作用)の研究の必読書である.

・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-01-12 Fri
■ #5373. Voicy heldio を通じて「hel活」仲間が増えてきました [voicy][heldio][helwa][hel_education][khelf][language_change][link][helkatsu]
毎朝6時にお届けしている Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の2024年の大テーマは「言語変化」 (language_change) です.この「hellog~英語史ブログ」でも長きにわたって注目してきたトピックですが,音声メディア heldio も用いて,より広く「なぜコトバは変化するのか」という魅力的な話題をお届けしていきたいと思います.よろしくお願いいたします.
heldio チャンネルは2021年6月2日に開設し,2年7ヶ月ほどの間,毎朝英語史に関するお話しをお届けしてきました.heldio 開設2周年に当たる2023年6月2日には,有料版となるプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」もオープンしました(こちらは毎週火木土の午後6時に配信しています).
私はブログや Voicy 等のメディアを通じて「英語史をお茶の間に」広げていくことをモットーとしていますが,「hel活」(英語史活動)を推進してゆく「助っ人」にも囲まれるようになりました.感謝に堪えません.そのhel活助っ人のごく一部にすぎませんが,以下にご紹介します.
・ khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー:「hel活」の最大の応援団体です.『英語史新聞』を季刊で刊行しています.HP での広報のほか,X(旧ツイッター)アカウント @khelf_keio からも日々元気にhel活中.
・ heldio/helwa のリスナーの皆さん:日々の配信回へのコメント,SNS を通じての広報,企画回や生放送への参加,その他のhel活でお世話になっています.とりわけ最近注目すべきSNS上での活動としては:
- リスナーの umisio さんによる「2024年「英語史の輪#77」英語語源辞典を読む.ノート完成.」,および「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む(34)のノートを取ったどー」等
- リスナーの kitako さんによる「heldio瓦版2024年1号」
- 同じく kitako さんによるインスタグラムでの日々の heldio 配信回の紹介
が目を見張ります
・ heldio/helwa 対談出演者の研究者や学生の皆さんにもお世話になっています.特に出演回数の多い方々の一覧は,いずれ整理したいと思っています.当面は以下のお二方が独自にまとめられているものをどうぞ.
- 菊地翔太先生(専修大学)の HP
- 矢冨弘先生(熊本学園大学)の HP
・ そしてもちろん本ブログを毎日お読みいただいている皆さんにも感謝いたします.私の公式 X アカウント @chariderryu からも情報を発信していますので,ぜひフォローをお願い致します.
皆さんのhel活支援に感謝いたします.引き続き「英語史をお茶の間に」の応援をよろしくお願いします.今回と同趣旨の記事として「#5256. heldio/hel活応援リンク集」 ([2023-09-17-1]) もご覧いただければ.
2023-09-27 Wed
■ #5266. 今井・秋田版「言語の大原則」7箇条 [linguistics][language_change][function_of_language]
昨日の記事「#5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年)」 ([2023-09-26-1]) で紹介した,爆発的に話題を集めている新刊書『言語の本質』より.
本書のメインの議論が味読に値することは間違いないが,何よりも驚いたのは本書の最後で野心的な今井・秋田版「言語の大原則」が挙げられていることだ.「ホケットの向こうを張って,筆者たちの考える「言語の大原則」を述べて,本書を締めくくりたい」 (257) と述べられている.
各項目の各箇条書きについて検討していくとおもしろそうだし,これをたたき台として複数人で議論していくのもエキサイティングだろう.そのために,今回は7箇条をそのまま引用しておこう (257--61) .
言語の本質的特徴
(1) 意味を伝えること
・ 言語は意味を表現する
・ 言語の形式は意味に,意味は形式に結びついていて,両者は双方向の関係にある
・ 言語はイマ・ココを超越した情報伝達を可能にする
・ 言語は意図を持って発話され,発話は受け取り手によって解釈される
・ 意味は推論によって作り出され,推論によって解釈される
・ よって話し手の発話意図と聞き手の解釈が一致するとは限らない
(2) 変化すること
・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである
・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる
・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する
・ 変化は不可避である
(3) 選択的であること
・ 言語は情報を選択して,デジタル的に記号化する
・ 記号化のための選択はコミュニティの文化に依存する.つまり,言語の意味は文化に依存する
・ 文化は多様であるので,言語は必然的に多用途なり,恣意性が強くなっていく
(4) システムであること
・ 言語の要素(単語や接辞など)は,単独では意味を持たない
・ 言語は要素が対比され,差異化されることで意味を持つシステムである
・ 単語の意味の範囲は,システムの中の当該の概念分野における他の単語群との関係性によって決まる.つまり,単語の意味は当該概念分野がどのように切り分けられ,構造化されていて,その単語がその中でどの位置を占めるかによって決まる.とくに,意味が隣接する単語との差異によってその単語の意味が決まる
・ したがって,「アカ」や「アルク」のようにもっとも知覚的で具体的な概念を指し示す単語でさえ,その意味は抽象的である
(5) 拡張的であること
・ 言語は生産的である.塊から要素を取り出し,要素を自在に組み合わせることで拡張する
・ 語句の意味は換喩・隠喩によって広がる
・ システムの中での意味の隙間があれば,新しい単語が作られる
・ 言語は知識を拡張し,観察を超えた因果メカニズムの説明を可能にする
・ 言語は自己生成的に成長・拡張し,進化していく
(6) 身体的であること
・ 言語は複数の感覚モダリティにおいて身体に接地している
・ その意味では言語はマルチモーダルな存在である
・ 言語はつねにその使い手である人間の情報処理の制約に沿い,情報処理がしやすいように自らの形を整える
・ 言語はマルチモーダルに身体に接地したあと,推論によって拡張され,体系化される
・ その過程によってヒトはことばに身体とのつながりを感じ,自然だと感じる.本来的に似ていないもの同士にも類似性を感じるようになり,もともとの知覚的類似性と区別がつかなくなる(二次的類似性の創発とアイコン性の輪)
・ 文化に根ざした二次的類似性は,言語の多様性と恣意性を生む.しかし,それらは身体的なつながりに発し,そこから拡張されて実現されている.このことにより,言語は,人間が情報処理できないような拡張の仕方はしない.また,言語習得可能性も担保されている
(7) 均衡の上に立っていること
・ 言語は身体的であるが,同時に恣意的であり,抽象的である
・ 慣習に制約されながらつねに変化する(慣習を守ろうとする力と新たに創造しようとする力の均衡)
・ 多様でありながら,同時に普遍的側面を包含する
・ 言語は,特定のコミュニティにおいて,共時的←→通時的,慣習の保守←→習慣からの逸脱,アイコン性←→恣意性,多様性←→普遍性,身体性←→抽象性など,複数の次元における二つの相反する方向に向かうベクトルの均衡点に立つ
・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.
2023-09-26 Tue
■ #5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年) [review][linguistics][language_change][yurugengogakuradio][youtube][onomatopoeia][abduction][language_acquisition][evolution][dynamic_equilibrium]

中公新書の新刊書『言語の本質』.言語学界隈ではすでに多くのメディアで取り上げられ,話題となっている.中央公論新社のサイトでは特設サイトが設けられており,盛り上がりの様子がわかる.
私が同僚の井上逸兵氏とともに運営している YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも「#141. ベストセラー本,今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』を語ってみました.」を2ヶ月ほど前に紹介している.また,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」でも,本書の著者の1人である今井むつみ氏の出演回を含め多くの関連回が配信されている.
本書では,(1) 従来の言語学研究では周辺的な扱いを受けてきたオノマトペ (onomatopoeia) が,言語進化・言語習得の初期段階においてきわめて大きな役割を演じており,(2) その基盤の上に,仮説形成推論 (abduction) というヒト固有の推論に駆動される形で,言語能力が雪だるま式に発展・向上していく(=ブートストラッピング)モデルが提案されている.仮説モデルではあるものの,豊富な先行研究に基づきつつ発達心理学の実証実験に裏打ちされた議論には,強い知的興奮を感じる.
本書は,言語変化や言語変異を考える上でも示唆的な指摘に富む.終章では7点の「言語の大原則」が提案されているが,その2点目に「変化すること」が掲げられている.そちらを引用する (258) .
・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである
・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる
・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する
・ 変化は不可避である
言語は,維持しようとする力と変化しようとする力の拮抗と均衡により,結局は変化していくとはいえ体系としては維持されていくという,まさに動的平衡 (dynamic_equilibrium) を体現する不思議な存在であることが,ここでは謳われている.
『言語の本質』,ぜひご一読を.
・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.
2023-09-23 Sat
■ #5262. 秋元実治先生との「他動性」談義 [transitivity][voicy][heldio][prototype][terminology][subjectification][language_change]
昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,「#844. 他動性とは何か? --- 秋元実治先生との対談」を配信しました.30分ほどの濃密な transitivity 談義です.秋元先生のご著書「#5184. 秋元実治『イギリス哲学者の英語』(開拓社,2023年)」 ([2023-07-07-1]) の議論に基づいた談義となっていますので,そちらもご覧いただければと思います.
対談でも論じている通り,他動性とは絶対的な指標というよりは,相対的で連続的でプロトタイプ的な指標です.他動性を決定するパラメータは様々ありますし,言語によっ具現化の仕方は異なります.それくらい抽象度の高い概念ではありますが,だからこそ広く一般的な言語の諸現象に関わってくるのであり,理論的にも興味深い視点となるわけです.主体性 (agentivity) や主観化 (subjectification) という概念とも複雑に関連してくるようで,合わせて言語変化の潮流を記述する有望な道具立てとなりそうです.
他動性については,本ブログでも次の記事を書いてきました.参考まで.
・ 「#5202. 他動性 (transitivity) とは何か?」 ([2023-07-25-1])
・ 「#5204. 他動性 (transitivity) とは何か? (2)」 ([2023-07-27-1])
・ 「#5209. 他動性 (transitivity) とは何か? (3)」 ([2023-08-01-1])
2023-09-08 Fri
■ #5247. 名前変化と多名性 [hydronymy][onomastics][toponymy][name_project][polynymy][language_change][terminology][sign][semiotics]
連日,固有名詞に関する話題をお届けしている.
地名や水域名によくみられるが,同一指示対象でありながら,時代によって異なる名前で呼ばれるケースがある.通時的な名前変化 (name change) の例である.一方,同じ時代に,同一指示対象に対して複数の名前が与えられているケースがある.共時的な多名性 (polynymy) の例である.固有名ではなく普通名でいえば,それぞれ「語の置き換え」 (onomasiological change) と「同義性・類義性」 (synonymy) に対応するだろうか.
昨日の記事「#5246. hydronymy --- 水域名を研究する分野」 ([2023-09-07-1]) で参照・引用した Strandberg (111) では,水域名の name change と polynymy について,実例とともに導入がなされている.
Name change is a common phenomenon in the history of hydronyms. In England, Blyth was replaced by Ryton, Granta by Cam, Hail by Kym, Writtle by Wid, etc. During a transitional stage of polynymy, there must often have existed both an older name and a new one. Trent (< Terente) is an alternative name for the river Piddle in Dorset. In Denmark, an older Guden and a younger Storå(en) were for a long time used in parallel for the same river.
Polynymy may also involve the simultaneous existence of different names for different parts of a (long) river. There are, for example, cases where the upper and lower reaches of a river have different names. The upper part of the Wylye in Wiltshire, England is called the Deverill, and the source of the French river Marne has the name Marnotte. A present-day name for a long river may have replaced several old ones denoting different stretches of it. The Nyköpingsån is a long and large river in Sweden; its name is formally secondary, containing the town name Nyköping. Two lost partial names of the Nyköpingsån (Blakka, Sølnoa) are recorded in medieval sources, while others, like *Sledh and *Vrena, may be or probably are preserved in names denoting settlements on the river; the current partial name Morjanån most likely goes back to an OSwed. *Morgha.
人名でいえば,同一人物が人生の節目に改名したり (name change),ニックネームやあだ名が複数ある (polynymy) ことに相当するだろう.固有名の最大の意義は,指示対象の同一性が固定名により恒久的に確保される点にあるはずと考えていたが,名前変化と多名性は,むしろその逆を行くものである.興味をそそられる現象だ.
・ Strandberg, Svante. "River Names." Chapter 7 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 104--14.
2023-05-08 Mon
■ #5124. Oxford Bibliographies による文法化研究の概要 [bibliography][syntax][grammaticalisation][language_change][oxford_bibliographies]
文法化 (grammaticalisation) は,いまや言語学の主要な領域を占めている.本来は言語史,歴史言語学,言語変化研究の文脈から現われてきた概念だが,現在では認知言語学やコーパス言語学とも結びつき,広く文法を扱う研究において一大潮流を形成している.文法化の具体的事例は,形態論,統語論,意味論でカバーされるものが多いものの,しばしば音韻論,語用論,語法研究など各種方面へはみ出していくので,ある意味では1つの言語学とみなしてもよいほどである.
Oxford Bibliographies は,各分野の専門家が整理した書誌を定期的にアップデートしつつ紹介してくれる重要なリソースだが,そこに "Grammaticalization" の項目も立てられている.D. Gary Miller と Elly van Gelderen による選書で,最終更新は2016年,最終レビューは2022年となっている.書誌の全文にアクセスするにはサブスクライブが必要である.ここでは,A4で印刷すると13ページほどにわたる書誌の冒頭部分 "Introduction" のみを引用しておく. *
The essence of grammaticalization is the evolution of a lexical category to a grammatical one or of a hybrid/functional category to another grammatical category. The first involves changes such as that of the verb have from "possess" to the marker of the perfect tense. The second involves changes such as that of to from a preposition (a hybrid category in English) to an infinitive marker or such as that of a demonstrative (e.g., the Latin ille 'that') to a definite article (the Italian il, the Spanish el, and so on). These changes have attracted attention for hundreds of years and are very well known. More recently, additional conditions and stipulations have been placed on this leading idea, but the essence remains the same.
Oxford Bibliographies の紹介シリーズの hellog 記事として,以下も参照.
・ 「#4631. Oxford Bibliographies による意味・語用変化研究の概要」 ([2021-12-31-1])
・ 「#4634. Oxford Bibliographies による英語史研究の歴史」 ([2022-01-03-1]) も参照.
・ 「#4742. Oxford Bibliographies による統語変化研究の概要」 ([2022-04-21-1])
2023-01-22 Sun
■ #5018. khelf メンバーと4人でジェンダーとコロナ禍周りのキーワードで『ジーニアス英和辞典』の版比較 in Voicy [dictionary][genius6][gender][covid][voicy][heldio][language_change][sociolinguistics][lexicography][methodology]
昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 では,khelf(慶應英語史フォーラム)の大学院生メンバー3名とともに「#600. 『ジーニアス英和辞典』の版比較 --- 英語とジェンダーの現代史」をお届けしました.ジェンダーとコロナ禍に関するキーワードについて『ジーニアス英和辞典』の初版から最新の第6版までを引き比べ,英語史を専攻する4人があれやこれやとおしゃべりしています.意外な発見が相次いで,盛り上がる回となりました.30分ほどの長さです.ぜい時間のあるときにお聴きいただければと思います.Voicy のコメント機能により,ご感想などもお寄せいただけますと嬉しいです.
今回比較した『ジーニアス英和辞典』の6つの版の出版年をまとめておきます.5--8年刻みで,おおよそ定期的に出版されており,1つのシリーズ辞典で英語の記述を通時的に追いかけることが可能となっています.
| 版 | 出版年 |
|---|---|
| G1 | 1987年 |
| G2 | 1993年 |
| G3 | 2001年 |
| G4 | 2006年 |
| G5 | 2014年 |
| G6 | 2022年 |
昨年11月に発売開始となった最新版の『ジーニアス英和辞典』第6版については,hellog および heldio で何度か取り上げてきました.以下をご参照ください.
・ hellog 「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1])
・ hellog 「#4950. 最近の英語の変化のうねり --- 『ジーニアス英和辞典』第6版のまえがきより」 ([2022-11-15-1])
・ hellog 「#4975. 2重目的語を取る動詞,取りそうで取らない動詞」 ([2022-12-10-1])
・ heldio 「#532. 『ジーニアス英和辞典』第6版の出版記念に「英語史Q&A」コラムより spring の話しをします」
・ heldio 「#557. まさにゃん対談:supply A with B の with って要りますか? --- 『ジーニアス英和辞典』新旧版の比較」
2022-11-21 Mon
■ #4956. 言語変化には「上から」と「下から」がある [language_change][sociolinguistics][terminology][prestige][stigma][style]
「#4952. 言語における威信 (prestige) とは?」 ([2022-11-17-1]) と「#4953. 言語における傷痕 (stigma) とは?」 ([2022-11-18-1]) で,言語における正と負の威信 (prestige) の話題を導入した.いずれも言語変化の入り口になり得るものであり,英語史を考える上でも鍵となる概念・用語である.
話者(集団)は,ある言語項目に付与されている正負の威信を感じ取り,意識的あるいは無意識的に,自らの言語行動を選択している.つまり,正の威信に近づこうとしたり,負の威信から距離を置こうとすることで,自らの社会における立ち位置を有利にしようと行動しているのである.その結果として言語変化が生じるケースがある.このようにして生じる言語変化は,話者が意識的に言語行動を選択している場合には change from above と呼ばれ,無意識の場合には change from below と呼ばれる.意識の「上から」の変化なのか,「下から」の変化なのか,ということである.
「上から」の変化は社会階層の上の集団と結びつけられる言語特徴を志向することがあり,反対に「下から」の変化は社会階層の下の集団の言語特徴を志向することがある.つまり,意識の「上下」と社会階層の「上下」は連動することも多い.しかし,Labov によって導入されたオリジナルの "change from above" と "change from below" は,あくまで話者の意識の上か下かという点に注目した概念・用語であることを強調しておきたい.
Trudgill の用語辞典より,それぞれを引用する.
change from above In terminology introduced by William Labov, linguistic changes which take place in a community above the level of conscious awareness, that is, when speakers have some awareness that they are making these changes. Very often, changes from above are made as a result of the influence of prestigious dialects with which the community is in contact, and the consequent stigmatisation of local dialect features. Changes from above therefore typically occur in the first instance in more closely monitored styles, and thus lead to style stratification. It is important to realise, however, that 'above' in this context does not refer to social class or status. It is not necessarily the case that such changes take place 'from above' socially. Change from above as a process is opposed by Labov to change from below.
change from below In terminology introduced by William Labov, linguistic changes which take place in a community below the level of conscious awareness, that is, when speakers are not consciously aware, unlike with changes from above, that such changes are taking place. Changes from below usually begin in one particular social class group, and thus lead to class stratification. While this particular social class group is very often not the highest class group in a society, it should be noted that change from below does not means change 'from below' in any social sense.
・ Trudgill, Peter. A Glossary of Sociolinguistics. Oxford: Oxford University Press, 2003.
2022-11-15 Tue
■ #4950. 最近の英語の変化のうねり --- 『ジーニアス英和辞典』第6版のまえがきより [notice][language_change][neologism][word_formation][shortening][gvs][singular_they][net_speak][genius6]
「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1]) でお知らせしましたが,8年ぶりの改訂版となる『ジーニアス英和辞典』第6版が,11月8日に発売となりました.36の単語のもとでコラム「英語史Q&A」を寄稿させていただいています.よろしくお願いいたします.
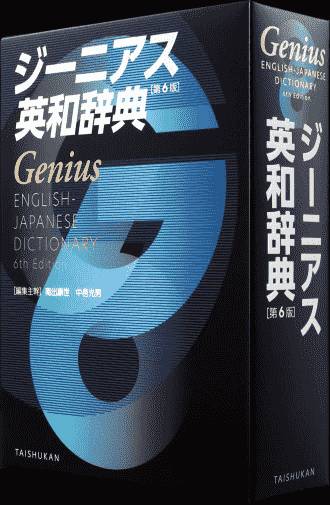
第6版まえがきの冒頭に,この8年間ほどの英語を取り巻く状況に「変化のうねり」があったことが触れられています.
『ジーニアス英和辞典』第5版が発行された2014年以降,デジタル化の拡大,インターネットの浸透,長引くコロナ禍,ジェンダーに関わる社会状況の変化などを反映して,英語の語彙・文法・文体等の面で変化のうねりが絶えなかった.語彙の面では上記の社会事象を反映する新語(特に SDGs, LGBTQ などの略語)が激増した.変化の波は文法面にも押し寄せた.顕著な例は,「総称の he」の衰退,「単数の they」の台頭である.これは中期英語(1400年代初頭)から,近代英語期(1600年代前半)にかけて起こった「大母音推移」 (The Great Vowel Shift) になぞらえて時に「The Great Pronoun Shift (大代名詞推移)」とも呼ばれ,将来代名詞の枠組みが書き換えられるかもしれないほどの大変化である.文体(スピーチレベル)に関していうと,これまでは書きことば=((正式)),話しことば=((略式)) という既成概念があったが,インターネットの SNS やブログなどでは「話すように書く」というのが主流で,この「話すように書く」スタイルがインターネット以外の書きことばにも拡大して,全体としてみれば,書きことばのインフォーマル化が進んでいる.
ここには,近年の英語の変化のうねりが要領よくまとめられている.確かに新語形成,大代名詞推移,書きことばのインフォーマル化のいずれの指摘も,歴史社会言語学や歴史語用論の立場から論じられるタイムリーな話題である,また,このような傾向が,以前からくすぶっていたとはいえ,このわずか数年ほどの間に著しく顕在化してきたことには改めて驚きを禁じ得ない.それほど言語変化の世界もスピードが速いのだ.
『ジーニアス英和辞典』の新版は,上記のような英語(および英語学習)を取り巻く最近の変化に鑑み,大きく8つの側面において改訂を加えたという.要約すると (1) 収録語彙の見直し,(2) コーパスを用いた語のランクの見直し,(3) 発音表記の見直し,(4) 語・語義に関する全体的な見直し,(5) 語法欄の充実とアップデート,(6) 「つなぎ語(句)」という新範疇の導入,(7) コラム「英語史Q&A」と「語のしくみ」の新設,(8) 紙面デザインの一新,の8点である.
私が執筆させていただいたコラム「英語史Q&A」の新設は,最近の英語の変化のうねりとの観点からみれば,辞典改訂における周辺的なポイントにみえるかもしれない.しかし,上記のように昨今英語はきわめて短期間の間にいくつもの大変化を遂げており,今後もこの流れは続いていくことが予想される.つまり,英語学習者はこのような言語変化の波に必死でくらいついていくことを余儀なくされるのである.現代の言語変化の速度,種類,規模の著しさに気づき,対応するためには,参照点として現代に先立つ時代の英語に生じてきた言語変化の速度,種類,規模を理解しておくことが役に立つ.
現代の英語を巡る変化は確かに著しい.しかし,それは過去の英語で生じてきた変化の延長線上にあることも確かである.英語史に親しむことは,現代を相対化することに貢献し,また歴史を現代的に捉えることをも可能にしてくれるだろう.
小さなコラムではありますが,「英語史Q&A」をそのような観点からも味わっていただければ幸いです.
・ 南出 康世・中邑 光男(編集主幹) 『ジーニアス英和辞典』第6版,大修館書店,2023年.
2022-06-16 Thu
■ #4798. ENL での言語変化は「革新」で,ESL/EFL では「間違い」? [language_change][world_englishes]
世界英語では,言語変化を通じて数々の非標準的な表現が数々生み出されてきている.不変の付加疑問 isn't it,several staffs のような名詞複数形,discuss about のような動詞語法などが例に挙げられる.
3つのサークル (the Inner, Outer, and Expanding Circles) を念頭に世界英語を論じている Jenkins は,このような言語変化の事例が「革新」 (innovation) なのか,あるいは単なる「間違い」 (error) なのかという解釈の問題に言及している.母語話者 (NS) によるものであれば「革新」であり,非母語話者 (NNS) によるものであれば「間違い」である,という短絡的な発想に陥っていないだろうかと.母語話者による言語変化と非母語話者による言語変化は何が同じで何が異なるのだろうか.Jenkins (32--33) の議論を聞いてみよう.
In fact it is not implausible that the only difference between English language change across the three circles is the time factor, with NNSs in both Outer and Expanding Circles speeding up the natural processes of regularization . . . that occur more slowly in the Inner Circle --- where currently it is perfectly acceptable to talk of 'teas' and 'coffees' instead of 'cups of tea' and 'cups of coffee' but not (yet) of 'advices' or 'furnitures'.
Another difference, though, is attitude towards such change. Linguists surveying language change in NS English tend to regard it as a sign of creativity and innovation. . . . On the other hand, linguists' tendency with NNS-led change, particularly in the Expanding Circle, is to label it wholesale as error regardless of how widespread its use or the degree to which it is mutually intelligible among speakers of English as a Lingua Franca (ELF).
1点目の,母語話者による言語変化と非母語話者による言語変化は速度が異なるだけであるという見方は,慎重に検討する必要はあるものの,言語変化の記述という観点からは,興味深い仮説である.
一方,2点目の,言語変化への態度の違いがあるのではないかという指摘は,社会言語学的な観点から,おもしろい(そして心がざわつく).同じ言語変化でも,どこの誰によって引き起こされたかによって,ポジティヴな「革新」かネガティヴな「間違い」かが決まってしまうということになるからだ.世界英語が広く論じられるようになった時代にあって,このような判断基準はどこまで妥当なのだろうか.
・ Jenkins, Jennifer. "Global Intelligibility and Local Diversity: Possibility or Paradox?" English in the World: Global Rules, Global Roles. Ed. Rani Rubdy and Mario Saraceni. London: Continuum, 2006. 32--39.
2022-05-27 Fri
■ #4778. 変わりゆく言葉に嘆いた詩人 Edmund Waller の "Of English Verse" [chaucer][language_change][hel_contents_50_2022][emode][literature]
khelf(慶應英語史フォーラム)による「英語史コンテンツ50」が終盤を迎えている.今回の hellog 記事は,先日5月20日にアップされた院生によるコンテンツ「どこでも通ずる英語…?」にあやかり,そこで引用されていたイングランドの詩人 Edmund Waller による詩 "Of English Verse" を紹介したい.
Waller (1606--87年)は17世紀イングランドを代表する詩人で,文学史的にはルネサンスの終わりと新古典主義時代の始まりの時期をつなぐ役割を果たした.Waller は32行の短い詩 "Of English Verse" のなかで,変わりゆく言葉(英語)の頼りなさやはかなさを嘆き,永遠に固定化されたラテン語やギリシア語への憧れを示している.一方,Chaucer を先輩詩人として引き合いに出しながら,詩人の言葉ははかなくとも,詩人の心は末代まで残るのだ,いや残って欲しいのだ,と痛切な願いを表現している.
Waller は,まさか1世紀ほど後にイングランドがフランスとの植民地争いを制して世界の覇権を握る糸口をつかみ,その1世紀後にはイギリス帝国が絶頂期を迎え,さらに1世紀後には英語が世界語として揺るぎない地位を築くなどとは想像もしていなかった.Waller はそこまでは予想できなかったわけだが,それだけにかえって現代の私たちがこの詩を読むと,言語(の地位)の変わりやすさ,頼りなさ,はかなさがひしひしと感じられてくる.
OF ENGLISH VERSE.
1 Poets may boast, as safely vain,
2 Their works shall with the world remain;
3 Both, bound together, live or die,
4 The verses and the prophecy.
5 But who can hope his lines should long
6 Last in a daily changing tongue?
7 While they are new, envy prevails;
8 And as that dies, our language fails.
9 When architects have done their part,
10 The matter may betray their art;
11 Time, if we use ill-chosen stone,
12 Soon brings a well-built palace down.
13 Poets that lasting marble seek,
14 Must carve in Latin, or in Greek;
15 We write in sand, our language grows,
16 And, like the tide, our work o'erflows.
17 Chaucer his sense can only boast;
18 The glory of his numbers lost!
19 Years have defaced his matchless strain;
20 And yet he did not sing in vain.
21 The beauties which adorned that age,
22 The shining subjects of his rage,
23 Hoping they should immortal prove,
24 Rewarded with success his love.
25 This was the generous poet's scope;
26 And all an English pen can hope,
27 To make the fair approve his flame,
28 That can so far extend their fame.
29 Verse, thus designed, has no ill fate,
30 If it arrive but at the date
31 Of fading beauty; if it prove
32 But as long-lived as present love.
・ Waller, Edmond. "Of English Verse". The Poems Of Edmund Waller. London: 1893. 197--98. Accessed through ProQuest on May 27, 2022.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow