2025-01-22 Wed
■ #5749. 言語ミーム [meme][internet][netspeak][biology][speed_of_change][evolution][variation]
言語学と「ミーム」 (meme) について,マクロの観点から「#3188. ミームとしての言語 (1)」 ([2018-01-18-1]) や「#3189. ミームとしての言語 (2)」 ([2018-01-19-1]) で話題にしてきた.
昨今はネット上で,ミクロな意味での言語上の「ミーム」が流行っているようだ.主にネットメディアで繰り返し用いられ,パロディ化しながらウイルスのように蔓延していく画像,動画,短文テキストである.言語学的にはこの短文テキストとしてのミームが話題となる.
もともと meme という英単語は,上記の過去記事で紹介しているようにイギリスの進化生物学者 Richard Dawkins の造語である.OED によると1976年に初出している.生物学用語としての meme が文化的な派生義を経て,第2語義として,すなわち "An image, video, piece of text, etc., typically humorous in nature, that is copied and spread rapidly by internet users, often with slight variations. Also with modifying word, as internet meme, etc." として用いられた初例は1998年の次の文である.
1998 The next thing you know, his friends have forwarded it [sc. an animation of a dancing baby] on and it's become a net meme. (Sci. & Technol. Week (transcript of CNN TV programme) (Nexis) 24 January)
現代では,日々ネット上で数々のミームが蔓延しては死滅していっている.Crystal (97) より,linguistic memes の解説を読んでみよう.
LINGUISTIC MEMES
The word meme was introduced in 1976 by evolutionary biologist Richard Dawkins in Chapter 11 of The Selfish Gene as a shortened form of mimeme, from a Greek word meaning 'that which is imitated'. As Dawkins put it: 'I want a monosyllable that sounds a bit like "gene". I hope my classicist friends will forgive me if I abbreviate mimeme to meme.' The word echoes the -eme suffix used in linguistics (phoneme, morpheme, etc), but lacks its notion of minimal contrastivity. A meme is a unit of cultural transmission which spreads throughout a population and which can persist for a considerable time. Dawkins illustrated from tunes, ideas, fashions in clothing, ways of making pots or of building arches, and --- of relevance to this book --- catch phrases.
The notion has achieved great prominence as a result of the Internet, which promotes the rapid spread of images and text, while at the same time allowing a potentially infinite number of variations. Most are photos with superimposed captions (similar to speech bubbles) that have humorous or satirical intent, though many convey messages of political or social seriousness, and some try to express notions of philosophy.
For a meme to work, it has to be unique, distinctive, and consistent --- something that is easily achievable using language. The chief linguistic feature is the use of nonstandard forms --- in earlier developments such as text messaging, chiefly deviant spelling; in more recent varieties, deviant grammar. Among the best-known inventions are Leetspeak, LOLcats, Doge, and Doggolingo (pp. 458--9). But standard English can also be a fruitful memic source, as the examples below illustrate.
No language domain is sacrosanct, and political correctness is conspicuous by its absence. Y U NO uses upper-case textese (p. 455) to parody the simplified speech of foreign learners, using a sketch of a character from a Japanese manga series: its memic origin began with I TXT U / Y U NO TXT BAK!? Ermahgerd shows a young woman holding several books from the children's horror fiction series Goosebumps; the name is a version of 'Oh my God', as spoken by someone with a speech impediment; it is also known as Gersberms and Berks (books).
There are hundreds of meme wannabes on the Internet now, all hoping (but few achieving) a permanent place in language history. Some sites provide instruction in 'how to create your own meme'. We must expect a significant increase in the amount of linguistic idiosyncrasy both on and off the web now, srsly.
もちろん言語ミームの流行は英語に限らない.日本(語)でも,昨今,多くの「○○構文」が生み出されているが,これも言語上のミームの一種といってよいだろう.
・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.
2024-12-25 Wed
■ #5721. 音象徴は語の適者生存を助長する [evolution][sound_symbolism][phonaesthesia][phonetics][vowel]
昨日の記事「#5720. little の i は音象徴か?」 ([2024-12-24-1]) に引き続き,Jespersen による「[i] = 小さい」の音象徴 (sound_symbolism) に関する論考より.
Jespersen は同論文で当該の音象徴を体現する多くの例を挙げているが,冒頭に近い部分で,音象徴の議論にありがちな誤解2点について,注意深く解説している.
In giving lists of words in which the [i] sound has the indicated symbolic value, I must at once ask the reader to beware of two possible misconceptions: first, I do not mean to say that the vowel [i] always implies smallness, or that smallness is everywhere indicated by means of that vowel; no language is consistent in that way, and it suffices to mention the words big and small, or the fact that thick and thin have the same vowel, to show how absurd such an idea would be.
Next, I am not speaking of the origin or etymology of the words enumerated: I do not say that they have from the very first taken their origin from a desire to express small things symbolically. It is true that I believe that some of the words mentioned have arisen in that way,---many of our i-words are astonishingly recent---but for many others it is well-known that the vowel i is only a recent development, the words having had some other vowel in former times. What I maintain, then, is simply that there is some association between sound and sense in these cases, however it may have taken its origin, and however late this connexion may be (exactly as I think that we must recognize secondary echoisms). But I am firmly convinced that the fact that a word meaning little or little thing contains the sound [i], has in many, or in most, cases been strongly influential in gaining popular favour for it; the sound has been an inducement to choose and to prefer that particular word, and to drop out of use other words for the same notion, which were not so favoured. In other words, sound-symbolism makes some words more fit to survive and gives them a considerable strength in their struggle for existence. If you want to use some name of an animal for a small child, you will preferably take one with sound symbolism, like kid or chick . . . , rather than bat or pug or slug, though these may in themselves be smaller than the animal chosen. (285--86)
1つめは「[i] = 小さい」の音象徴は絶対的・必然的なものではなく,あくまで蓋然的なものにすぎない点の確認である.2つめは,当該の音象徴を体現している語について,その音形と意味の関係が語源の当初からあったのか,後に形成されたのかは問わないということだ.合わせて,共時的にも通時的にも,音象徴の示す関係は緩い傾向にとどまり,何かを決定する強い力をもっているわけではない点が重要である.
それでも Jespersen は,引用の最後でその用語を使わずに力説している通り,音象徴には語の「適者生存」 (survival of the fittest) を助長する効果があると確信している.音象徴は,言語において微弱ながらも常に作用している力とみなすことができるだろうと.
・ Jespersen, O. "Symbolic Value of the Vowel I." Philologica 1 (1922). Reprinted in Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933. 283--303.
2024-02-20 Tue
■ #5412. 原初の言語は複雑だったのか,単純だったのか? [origin_of_language][language_change][evolution][history_of_linguistics][language_myth][sobokunagimon][simplification][homo_sapiens]
言語学史のハンドブックを読んでいる.Mufwene の言語の起源・進化に関する章では,これまでに提案されてきた様々な言語起源・進化論が紹介されており,一読の価値がある.
私もよく問われる素朴な疑問の1つに,原初の言語は複雑だったのか,あるいは単純だったのか,という言語の起源に関するものがある.一方,言語進化の観点からは,原初の段階から現代まで言語は単純化してきたのか,複雑化してきたのか,という関連する疑問が生じてくる.
真の答えは分からない.いずれの立場についても論者がいる.例えば,前者を採る Jespersen と,後者の論客 Bickerton は好対照をなす.Mufwene (31) の解説を引用しよう.
His [= Jespersen's] conclusion is that the initial language must have had forms that were more complex and non-analytic; modern languages reflect evolution toward perfection which must presumably be found in languages without inflections and tones. It is not clear what Jespersen's position on derivational morphology is. In any case, his views are at odds with Bickerton's . . . hypothesis that the protolanguage, which allegedly emerged by the late Homo erectus, was much simpler and had minimal syntax, if any. While Bickerton sees in pidgins fossils of that protolanguage and in creoles the earliest forms of complex grammar that could putatively evolve from them, Jespersen would perhaps see in them the ultimate stage of the evolution of language to date. Many of us today find it difficult to side with one or the other position.
両陣営ともに独自の前提に基づいており,その前提がそもそも正しいのかどうかを確認する手段がないので,議論は平行線をたどらざるを得ない.また,言語の複雑性と単純性とは何かという別の難題も立ちはだかる.最後の問題については「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#4165. 言語の複雑さについて再考」 ([2020-09-21-1]) などを参照.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2024-02-14 Wed
■ #5406. ダーウィンによる人類の進化,言語の進化,精神の進化 [homo_sapiens][origin_of_language][evolution][history_of_linguistics][darwin][ai]
Charles Darwin (1809--82) は,言語の進化は人類の進化そのものと平行的なところがあると考えており,また精神の進化とも関係しているとも述べている.特に後者に関して進化を考える上で言語と精神とを結びつけてみた論者は,Darwin が最初に近かったようだ.Mufwene (23) より解説を引用する.
Charles Darwin commented in The Descent of Man (1871) that the evolution of language was in several ways reminiscent of that of mankind itself. He hypotheisized that it had emerged gradually, had not been given by God or invented by design by humans, and could also be explained by natural selection. He was among the first to correlate the evolution of language with that of the human mind . . . , thus accounting for why parrots cannot produce original spoken messages intentionally, although they can imitate human speech fairly accurately. Showing what an important driver role the human mind has played in the evolution of language, he argued that it was for the same reason that other primates do not use their buccopharyngeal structure to speak.
これは生成AIが産出する言語が真の言語なのかという点にも関わってくる点で,古くて新しい論点かもしれない.
さらに,上の解説に続けて Mufwene (23) は,言語能力の発現と諸言語の発生は独立しているか否かという,もう1つの重要な論点を指摘している.
We now know that Charles Darwin was only partly right. The other primates' buccopharyngeal structure is not shaped in exactly the same way as that of humans, although, based on the parrot's phonetic accomplishments, we must wonder how critical this particular structure was for the emergence of language (not speech!) in the first place. After all, humans who cannot speak produce signed language, which is just as adequate for communication. This argument may be claimed to support the position that the emergence of the capacity for language must be distinguished from the emergence of languages. However, one must also wonder whether the two questions can be considered independently of each other . . . .
この論点も現代の視点からみると余計におもしろい.生成AIは,人間が発した多くの既存の言語データをエネルギーとして,言語能力らしきもの(正確にいえば言語産出の手法)を獲得したからである.
この時代に,Darwin を読んでみるのも有意義かもしれない.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2024-02-13 Tue
■ #5405. 言語多起源説を唱えた Maupertuis [homo_sapiens][origin_of_language][evolution][history_of_linguistics][language_myth][tower_of_babel]
連日 Mufwene を参照しつつ言語の起源をめぐる学説史を振り返っている.今回は,言語多起源説を唱えたフランスの哲学者・数学者の Pierre Louis Moreau de Maupertuis (1698--1759) を取り上げたい.Maupertuis は言語の多様性を説明するのに「バベルの塔」 (tower_of_babel) という神の力に頼ることをせず,そもそも言語発生の原初から多様な言語があったと,つまり言語の起源は複数あったと論じた.言語単一起源説 (monogenesis) に対する言語多起源説 (polygenesis) の提唱である.Mufwene (22--23) より関連する解説部分を引用する.
Another important philosopher of the eighteenth century was Pierre Louis Moreau de Maupertuis, author of Réflexions sur l'origine des langues et la vie des mots (1748). Among other things, he sought to answer the question of whether modern languages can ultimately be traced back to one single common ancestor or whether current diversity reflects polygenesis, with different populations developing their own languages. Associating monogenesis with the Tower of Babel myth, which needs a deus ex machina, God, to account for the diversification of languages, he rejected it in favour of polygenesis. Note, however, that his position needs Cartesianism, which assumes that all humans are endowed with the same mental capacity and suggests that our hominin ancestors could have invented similar communicative technologies at the same or similar stages of our phylogenetic evolution. This position makes it natural to project the existence of language as the common essence of languages beyond their differences.
人類の言語能力それ自体は世界のどこででもほぼ同時期に開花したが,そこから生み出されてきた個々の言語は互いに異なっており,全体として言語の多様性が現出した.これが Maupertuis の捉え方だろう.
単一起源説と多起源説については「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1]) の記事も参照.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2024-02-12 Mon
■ #5404. 言語は名詞から始まったのか,動詞から始まったのか? [homo_sapiens][origin_of_language][evolution][history_of_linguistics][grammaticalisation][noun][verb][category][name_project][onomastics][naming]
標題は解決しようのない疑問ではあるが,言語学史 (history_of_linguistics) においては言語の起源 (origin_of_language) をめぐる議論のなかで時々言及されてきた問いである.
Mufwene (22) を参照して,2人の論者とその見解を紹介したい.ドイツの哲学者 Johann Gottfried von Herder (1744--1803) とアメリカの言語学者 William Dwight Whitney (1827--94) である.
Herder also speculated that language started with the practice of naming. He claimed that predicates, which denote activities and conditions, were the first names; nouns were derived from them . . . . He thus partly anticipated Heine and Kuteva (2007), who argue that grammar emerged gradually, through the grammaticization of nouns and verbs into grammatical markers, including complementizers, which make it possible to form complex sentences. An issue arising from Herder's position is whether nouns and verbs could not have emerged concurrently. . . .
On the other hand, as hypothesized by William Dwight Whitney . . . , the original naming practice need not have entailed the distinction between nouns and verbs and the capacity to predicate. At the same time, naming may have amounted to pointing with (pre-)linguistic signs; predication may have started only after hominins were capable of describing states of affairs compositionally, combining word-size units in this case, rather than holophrastically.
Herder は言語は名付け (naming) の実践から始まったと考えた.ところが,その名付けの結果としての「名前」が最初は名詞ではなく述語動詞だったという.この辺りは意外な発想で興味深い.Herder は,名詞は後に動詞から派生したものであると考えた.これは現代の文法化 (grammaticalisation) の理論でいうところの文法範疇の創発という考え方に近いかもしれない.
一方,Whitney は,言語は動詞と名詞の区別のない段階で一語表現 (holophrasis) に発したのであり,あくまで後になってからそれらの文法範疇が発達したと考えた.
言語起源論と文法化理論はこのような論点において関係づけられるのかと感心した次第.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2024-02-11 Sun
■ #5403. 感情的叫びから理性的単調へ --- ルソーの言語起源・発達論 [roussseau][anthropology][homo_sapiens][origin_of_language][evolution][language_myth][history_of_linguistics]
フランスの思想家ルソー (Jean Jacques Rousseau [1712--78]) は,人類言語の起源は感情的叫びにあると考えた.その後,言語は人類の精神,社会,環境の変化とともに,より理性的なものへと発展してきたという.これは言語の起源と発達に関する古典的かつ代表的な仮説の1つといってよいだろう.
ルソーは言語起源・発達について,上記の基本的な考え方に基づき,より具体的な一風変わった諸点にも言及している.Mufwene (19--20) によるルソー解説を引用したい.
. . . Rousseau interpreted evolution as progress towards a more explicit architecture meant to express reason more than emotion. According to him,
Anyone who studies the history and progress of tongues will see that the more words become monotonous, the more consonants multiply; that, as accents fall into disuse and quantities are neutralized, they are replaced by grammatical combinations and new articulations. [...] To the degree that needs multiply [...] language changes its character. It becomes more regular and less passionate. It substitutes ideas for feelings. It no longer speaks to the heart but to reason. (Moran and Gode 1966: 16)
Thus, Rousseau interpreted the evolution of language as gradual, reflecting changes in the Homo genus's mental, social, and environmental structures. He also suggests that consonants emerged after vowels (at least some of them), out of necessity to keep 'words' less 'monotonous.' Consonants would putatively have made it easier to identify transitions from one syllable to another. He speaks of 'break[ing] down the speaking voice into a given number of elementary parts, either vocal or articulate [i.e. consonantal?], with which one can form all the words and syllables imaginable' . . . .
言語が,人間の理性の発達とともに "monotonous" となってきて,"consonants" が増えてきたという発想が興味深い.この発想の背景には,声調を利用する「感情的な」諸言語が非西洋地域で話されていることをルソーが知っていたという事実がある.ルソーも時代の偏見から自由ではなかったことがわかる.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2023-09-26 Tue
■ #5265. 今井むつみ・秋田喜美著『言語の本質』(中公新書,2023年) [review][linguistics][language_change][yurugengogakuradio][youtube][onomatopoeia][abduction][language_acquisition][evolution][dynamic_equilibrium]
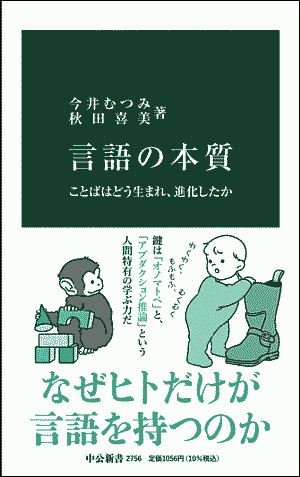
中公新書の新刊書『言語の本質』.言語学界隈ではすでに多くのメディアで取り上げられ,話題となっている.中央公論新社のサイトでは特設サイトが設けられており,盛り上がりの様子がわかる.
私が同僚の井上逸兵氏とともに運営している YouTube の「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」でも「#141. ベストセラー本,今井むつみ・秋田喜美『言語の本質』を語ってみました.」を2ヶ月ほど前に紹介している.また,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」でも,本書の著者の1人である今井むつみ氏の出演回を含め多くの関連回が配信されている.
本書では,(1) 従来の言語学研究では周辺的な扱いを受けてきたオノマトペ (onomatopoeia) が,言語進化・言語習得の初期段階においてきわめて大きな役割を演じており,(2) その基盤の上に,仮説形成推論 (abduction) というヒト固有の推論に駆動される形で,言語能力が雪だるま式に発展・向上していく(=ブートストラッピング)モデルが提案されている.仮説モデルではあるものの,豊富な先行研究に基づきつつ発達心理学の実証実験に裏打ちされた議論には,強い知的興奮を感じる.
本書は,言語変化や言語変異を考える上でも示唆的な指摘に富む.終章では7点の「言語の大原則」が提案されているが,その2点目に「変化すること」が掲げられている.そちらを引用する (258) .
・ 慣習を守る力と,新たな形式と意味を創造して慣習から逸脱しようとする力の間の戦いである
・ 典型的な形式・意味からの一般化としては完全に合っていても,慣習に従わなければ「誤り」あるいは「不自然」と見なされる
・ ただし,言語コミュニティの大半が新たな形式や意味,使い方を好めば,それが既存の形式,意味,使い方を凌駕する
・ 変化は不可避である
言語は,維持しようとする力と変化しようとする力の拮抗と均衡により,結局は変化していくとはいえ体系としては維持されていくという,まさに動的平衡 (dynamic_equilibrium) を体現する不思議な存在であることが,ここでは謳われている.
『言語の本質』,ぜひご一読を.
・ 今井 むつみ・秋田 喜美 『言語の本質 --- ことばはどう生まれ,進化したか』 中公新書,2023年.
2023-06-22 Thu
■ #5169. 人類言語は最初から複雑だったか? [sobokunagimon][evolution][origin_of_language]
言語類型論で知られる Comrie (248) が,言語の起源と発展をめぐる考察において,人類言語は最初から複雑だったか否かという問題について議論している.ちなみに,ここでいう複雑さとは,主に形態(音韻)論的な複雑さを指している.
One question that then arises is how some languages come to have such complexities as complex morphologies and morphophonemics.
One possible answer is that they have always had these complexities, i.e. that some languages, from the beginnings of human language, just started out being complex. After all, if languages with complex morphologies, like, say, the Eskimo languages, can be acquired with relatively little difficulty by children, then they are clearly within whatever limits exist on the acquisition and use of language by human beings in general, and as soon as humans attained the level necessary for dealing with such complexity they would have been able to deal with such a language. But although such a scenario cannot be excluded a priori, the nagging question keeps coming back of where such complexity could have come from, almost as if it were improbable to accept the complexity as always having been there and at least more tempting to try to explain its origin.
引用の最後に示唆されているように,Comrie 自身は,人類言語が最初から複雑だったという説には否定的のようだ.当初は単純だったものが徐々に複雑化してきた,という正反対の説を声高に表明しているわけでもないが,何らかの複雑化説を念頭に置いていると考えられる.
そもそも言語における複雑さという問題は難しい.上記では形態(音韻)論における複雑さのみが考慮されているにすぎないが,その他の部門の複雑さも含めて総合的に評価する必要があるからだ.そして,その評価の基準について研究者間での合意はない.この問題と関連して,以下の記事を参照.
・ 「#293. 言語の難易度は測れるか」 ([2010-02-14-1])
・ 「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1])
・ 「#2820. 言語の難しさについて」 ([2017-01-15-1])
・ 「#4165. 言語の複雑さについて再考」 ([2020-09-21-1])
・ Comrie, Barnard. "Reconstruction, Typology and Reality." Motives for Language Change. Ed. Raymond Hickey. Cambridge: CUP, 2003. 243--57.
2022-08-07 Sun
■ #4850. アフリカの語族と遺伝子 [africa][language_family][anthropology][origin_of_language][genetics][evolution][speed_of_change][world_languages][map]
アフリカの4つの語族について「#3811. アフリカの語族と諸言語の概要」 ([2019-10-03-1]) で紹介した.先日「#4846. 遺伝と言語の関係」 ([2022-08-03-1]) で参照した篠田に,言語と遺伝子の関係に触れつつアフリカの語族について論じられている節があった.そちらから引用する (87--88) .
突然変異は世代を経るごとに蓄積しますから,同じ地域に長く暮らすほど個体間の遺伝的な違いは大きくなります.ホモ・サピエンスは他のどの地域よりも長くアフリカ大陸で生活していますから,アフリカ人同士は,他の大陸の人びとよりも大きな遺伝的変異を持っています.実際,人類の持つ遺伝的な多様性のうち,実に八五パーセントまではアフリカ人が持っていると推定されています.一方,言語もDNA同様,時間とともに変化していきます.そのスピードはDNAの変化よりもはるかに早く,一万年もさかのぼると言語間の系統関係を追えないほど変化するといわれていますが,同じような変化をすることから,言語の分布と集団の歴史のあいだには密接な関係があることが予想されます.
アフリカには,世界中に存在する言語の三分の一に当たる,およそ二〇〇〇の言語が存在します.それは,アフリカ大陸に長期にわたって人びとが暮らしていることの証拠でもあります.アフリカで話されている言語は大きく四つのグループに分かれており,北から,アフロ・アジア言語,ナイル・サハラ言語,ニジェール・コンゴ言語,コイ・サン言語が分布します.ただし,コイ・サン言語はさらに五つのグループに分かれており,互いの共通性はほとんどないといわれています.遠い昔に分岐した一群の言語族の総称と捉えるべきものです.ともあれ,言語グループの分布の様子と集団の遺伝的な構成には密接な関係があることがわかっています〔後略〕.
また,アフリカの人々の語族,遺伝子,地理的分布が互いに関係することに加え,彼らの生業も相関関係に組み込まれていくるという.アフロ・アジア語族は牧畜民や牧畜農耕民と関連づけられ,ナイル・サハラ語族は牧畜民と,ニジェール・コンゴ語族は農耕民と,コイ・サン語族は狩猟採集民とそれぞれ関連づけられる. *
篠田 (89) は「言語や生業,地理的分布の違いは,過去における集団の移動や融合の結果と考えられるので,化石やDNA,さらには考古学的な証拠や言語の系統を調べることで,現代のアフリカ集団の成立のシナリオを多角的に描くことができます」と同節を締めくくっている.
関連して「#3807. アフリカにおける言語の多様性 (1)」 ([2019-09-29-1]),「#3808. アフリカにおける言語の多様性 (2)」 ([2019-09-30-1]),「#3814. アフリカの様々な超民族語」 ([2019-10-06-1]) ほか africa の各記事を参照.
・ 篠田 謙一 『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』 中公新書,2022年.
2022-08-03 Wed
■ #4846. 遺伝と言語の関係 [anthropology][evolution][demography][genetics][language_family]
篠田謙一氏による近刊書『人類の起源』(中公新書)を読んでいる.人類学 (anthropology) は言語学の隣接分野の1つでもあり関心を寄せているが,アフリカなどで化石人骨が発見されるたびに人類史が書き換わる様を目の当たりにして,なんとスピード感のある分野なのだろうと思っている.
篠田 (174) では,アジア人の起源を探る章で,「言語とゲノム」の関係について議論が展開されている.その一部を引用する.
二〇〇九年には,東南アジアから北東アジアにかけての現代人集団のゲノムデータが解析され,アジアの集団の遺伝的な分化は基本的に言語集団に対応していることが示されています.〔中略〕同じ言語集団に属する人びとは似たような遺伝的な構成をしているということを表しています.婚姻は基本的には同じ言語グループの中で行われますから,当然の結果でしょう.分化のもっとも重要な要素は言語であり,それが集団の遺伝的な構成を規定しているのです.
この引用にあるように,遺伝と言語に基づく集団の分布が一致しているという指摘は,おそらく多くの読者にとって直観と常識に見合うために,すんなりと受け入れられるものだろう.しかし,私にとって,このストレートな指摘は,なかなかショッキングだった.遺伝,人種,言語の関係について,単純に結びつけることに懐疑的であり抵抗があるからだ.
社会言語学では,言語とその他の種々のパラメーターは,相関関係にあることは多いものの,絶対的な結びつきはないということが説かれ,しばしば強調される.社会言語学は,ある意味では,言語と他のパラメーターの関係は直観・常識とは完全にイコールではないので,盲目的にイコールで結びつける言説とは距離を置け,と主張する分野でもあると私は考えている.このような立場からすると,上記の結論はあまりにストレートで,オッと身構えてしまうわけだ.
ただし,あいにく「遺伝」について門外漢である私が何か言えることがあるかと問われれば,残念ながらない.ここでは,関連する以下の記事を指摘するにとどめたい.
・ 「#2838. 新人の登場と出アフリカ」 ([2017-02-02-1])
・ 「#2841. 人類の起源と言語の起源の関係」 ([2017-02-05-1])
・ 「#2844. 人類の起源と言語の起源の関係 (2)」 ([2017-02-08-1])
・ 「#2872. 舌打ち音とホモ・サピエンス」 ([2017-03-08-1])
・ 「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1])
・ 「#3593. アングロサクソンは本当にケルトを一掃したのか?」 ([2019-02-27-1])
・ 「#1871. 言語と人種」 ([2014-06-11-1])
・ 「#3599. 言語と人種 (2)」 ([2019-03-05-1])
・ 「#3810. 社会的な構築物としての「人種」」 ([2019-10-02-1])
現時点での私のまとまらない考えを言語化すると次のようになる.遺伝と言語の相関関係は,直観・常識のみならず科学的にも濃密のようである,しかし絶対的なイコール関係ではない.
・ 篠田 謙一 『人類の起源 古代DNAが語るホモ・サピエンスの「大いなる旅」』 中公新書,2022年.
2021-12-26 Sun
■ #4626. 現代の手話研究の成果 [sign_language][evolution][history_of_linguistics][linguistics][history_of_linguistics]
手話 (sign_language) がれっきとした言語の1形態であることについて「#1662. 手話は言語である (1)」 ([2013-11-14-1]),「#1663. 手話は言語である (2)」 ([2013-11-15-1]) などで取り上げてきた.
Woll (96) によれば,手話の研究史は17世紀にさかのぼるが,現代の本格的な手話研究が始まったのは,つい最近ともいえる1950--60年代のことである.Tervoort (1953) と Stokoe (1960) の研究が画期的とされている.その後1970年代以降は,主流派言語学も手話研究から刺激を受け,この領域への関心を強めてきた.言語進化論の分野へのインパクトも大きかったようだ.Woll (104) 曰く,
. . . sign languages are the creation of humans with 'language-ready' brains. Thus it is inappropriate to view sign languages as comparable to the communication of pre-linguistic humans. Perhaps the most important contribution of sign linguistics to language evolution theory is the recognition that human communication is essentially multi-channel.
現代の手話言語学は70年ほどの歴史をもつことになるが,この経験を通じて手話の3つの特徴が浮き彫りになってきたと Woll (92) は述べている.
・ Sign languages are complex natural human languages.
・ Sign languages are not related to the spoken languages of the surrounding hearing communities.
・ Sign languages can be compared and contrasted in terms of typology and modality with spoken language.
手話言語は音声言語からの派生物ではなく,れっきとした言語の1形態であり,音声言語と比較できる側面とそうでない側面をもつ,ということだ.
ちなみに世界に手話言語はいくつあるのか.Ethnologue (2009年版)では170の手話言語が挙げられているそうだが,別のデータベースによると数千ものエントリーが確認できるという (Woll 93) .幾多の理由で,音声言語と同様に,否それ以上に,正確に数え上げるのは困難なようだ.
・ Woll, Bencie. "The History of Sign Language Linguistics." Chapter 4 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 91--104.
・ Tervoort, Bernard T. Structurele analyse van visueel taalgebruik binnen een groep dove kinderen. Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij, 1953.
・ Stokoe, William C. "Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication Systems of the American deaf." Studies in Linguistics Occasional Papers 8 (1060): 1--78. University of Buffalo.
2021-12-14 Tue
■ #4614. 言語の起源と発達を巡る諸説の昔と今 [evolution][origin_of_language][history_of_linguistics][anthropology][biology][philosophy_of_language]
「#4612. 言語の起源と発達を巡る諸問題」 ([2021-12-12-1]) で引用した Mufwene (51) は,言語の起源と発達を巡る諸説について,最近何か新しい提案が出てきているという事実はないと述べている.「諸説」は18世紀の哲学者の手により,すでに出そろっているという認識だ.
For instance, the claim that language is what distinguishes mankind the most clearly from the animal kingdom is already evident in Condillac. It is also hard to sharply distinguish eighteenth-century arguments for the emergence of human language out of instinctive cries and gestures from Bickerton's position that the predecessor of his 'protolanguage' consisted of holistic vocalizations and gestures. The idea of gradualism in the evolution of language is not new either; and Rousseau had already articulated the significance of social interactions as a prerequisite to the emergence of language. And one can keep on identifying a number of current hypotheses which are hardly different from earlier speculations on the subject.
では,だからといってこの領域における研究が進んでいないかといえば,そういうわけでもない,と Mufwene (51--52) は議論を続ける.18世紀の哲学者や19世紀の言語学者と,現代の我々との間には重要な違いがいくつかあるという.
1つ目は,我々が10--20万年前の化石人類と我々とが解剖学的にも生態学的にも異なった存在であることを認識していることだ.言語の起源と発達を論じる上で,この認識は重要である.
2つ目は,我々が言語の起源と発達を巡る諸説が "speculative" な議論であるということを認識していることだ.別の言い方をすれば,我々のほうがこの話題を取り上げるに当たって科学的知識の限界に自覚的なのである.
3つ目は,我々は言語の発達について概ねダーウィニズムを受け入れているということだ.言語が神によって付与された能力であるという立場を取る論者も,少数派であるとはいえ今も存在する.しかし,主流の見方では,言語能力は変異によって生じてきたものだとされている.
4つ目は,我々は言語の構造がモジュール化されたものである (modular) と考えている.かつてのように言語の構成要素がすべてあるとき同時に発現したと考える必要はないということだ.現在は,言語が徐々に発達してきたことを前提としてよい空気がある.
このように,現代になって何か新しい説が現われてきたわけではないものの,18--19世紀には前提とされていなかったことが今では前提とされているようになったということは,それこそが進歩なのだろう.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2021-12-12 Sun
■ #4612. 言語の起源と発達を巡る諸問題 [evolution][origin_of_language][history_of_linguistics][anthropology][sign_language][biology][philosophy_of_language]
言語の起源と発達について,本ブログでは origin_of_language や evolution の記事で取り上げてきた.古代から現代に至るまで問い続けられてきた古くて新しい問題だが,とりわけ昨今は学際的なアプローチが不可欠である.あまりに深く広く領域であり,研究の歴史と成果を一望するのも難しいほどだが,Mufwene (14--15) が "The Origins and the Evolution of Language" と題する論考で,関連する諸問題の一端をリストで示しているので,そちらを引用する.
1. Was language given to humans by God or did it emerge by Darwinian evolution?
2. From a phylogenetic perspective, did language emerge abruptly or gradually? If the emergence of language was protracted, what plausible intermediate stages can be posited and what would count as evidence for positing them? Assuming that the structure of modern languages is modular, would gradual evolution apply to any of the modules, only to some of them, or only to the overall architecture? What is the probable time of the emergence of the first real ancestor of modern language?
3. Does possessing Language, the non-individuated construct associated exclusively with humans, presuppose monogenesis or does it allow for polygenesis? How consistent is either position with paleontological evidence about the evolution of the Homo genus? How did linguistic diversity start? Assuming Darwinian (variational rather than transformational) evolution, can monogenesis account for typological variation as plausibly as polygenesis?
4. What is the chronological relationship between communication and language? What light does this distinction shed on the relation between sign(ed) and spoken language? Did some of our hominin ancestors communicated by means of ape-like vocalizations and gestures? If so, how can we account for the transition from them to phonetic and signed languages? And how can we account for the fact that modern humans have favoured speaking over signing? Assuming that language is a communication technology, to what extent are some of the structural properties of language consequences of the linearity imposed by the phonic and signing devices used in their architecture.
5. Is the evolution of language more biological than cultural? Or is it the other way around, or equally both? Are languages as cultural artifacts deliberate inventions or emergent phenomena? Who are the agents in the emergence of language: individuals or populations, or both?
6. What is the relationship between language and thought? Did these entities co-evolve or did one cause the other?
7. Is there such a thing as 'language organ' or 'biological endowment for language'? How can it be characterized relative to modern humans' anatomical and/or mental makeups? What are the anatomical, mental, and social factors that facilitated the emergence of language?
8. Can we learn something about the evolution of language from historical language change, especially from the emergence of creoles and pidgins? Can we learn something from child language and/or from home sign language? And what can be learned from 'linguistic apes'? Does it make sense to characterize these particular communicative 'systems' as fossils of the human protolanguage . . . ? In the same vein, what can modelling contribute to understanding the evolution of language. This is definitely the kind of thing that scholars could not do before the twentieth century; it is important to assess its heuristic significance.
一覧を眺めるだけで膨大な問いだということがよく分かる.私の研究している英語史や言語変化 (language_change) は,この茫洋たる分野からみれば本当に微々たる存在にすぎず,しかもこの分野に直接的に資するかも分からない細事である.
・ Mufwene, Salikoko S. "The Origins and the Evolution of Language." Chapter 1 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 13--52.
2021-06-01 Tue
■ #4418. 併合,Subassembly Strategy,自己家畜化 --- 進化言語学による統語的併合の起源説 [syntax][biology][evolution][exaptation]
日本歴史言語学会の2019年のシンポジウム「進化言語学への招待」での基調講演に基づいた論文が,『歴史言語学』の最新号に掲載されている.進化言語学という分野について私自身は門外漢だが,藤田論文「階層的シンタクスと(自己)家畜化」を読み,このような議論がなされているのかと興味を覚えた.同論文の狙いは,冒頭 (p. 69) で次のように述べられている.
特に,人間言語の大きな特徴となっている回帰的・階層的シンタクスについて,これが物体の組み合わせ操作からの外適応的進化によるとする「運動制御起源仮説」 (Fujita 2009, 2017, 藤田 2012 他)を振り返り,そこで残されていた問題を「(自己)家畜化) ((self-)-domestication)」の観点から解決する可能性について考察してみたい.
進化言語学や生成文法において,併合 (merger) は「2つの統語体(語彙項目および語彙項目からなる集合)を組み合わせて1つの無順序集合 (unordered set) を形成する回帰的演算操作」(藤田,p. 71)を指す.定式化すると,Merge(α, β) → {α, β} ということだ.2つの統語体であれば組み合わせ方は単純に1種類しかない(これは "Pairing Strategy" と呼ばれる).しかし,3つの統語体となると「戦略」はもっと複雑になる.
A (小), B (中), C (大)の3つのカップを想定しよう.3つのカップをすっぽりはめるやり方は2通りある.B を C にはめ,最後に最小の A を合わせてはめるというやり方が1つ ("Pot Strategy") .もう1つは,先に A を B にはめておき,その一体化したものを最大の C にはめるというやり方だ ("Subassembly Strategy") .
藤田の仮説によれば,戦略の進化は,"Pairing Strategy" → "Pot Strategy" → "Subassembly Strategy" の順で起こってきたのではないかという.このような「行動文法」の進化と連動する形で,言語上の統語体の併合も進化してきたのではないかと.そして,この仮説のことを「運動制御起源仮説」と呼んでいる.
"Subassembly Strategy" の最大の特徴は「先に形成した集合を記憶に蓄えておき,それ全体を部分部品として再利用する点」(藤田,p. 76)にある.反応を遅延させる能力,将来に備えた準備,平たくいえば今したいことを我慢する力ととらえてもよいかもしれない.これは人間が自らを制御する能力に関わるので,「自己家畜化」という見方が出てくるという理屈だ.
門外漢として狐につままれた感があるが,進化言語学の議論の雰囲気を知ることができた.
・ 藤田 耕司 「階層的シンタクスと(自己)家畜化」『歴史言語学』第9号(日本歴史言語学会編),2020年.69--85頁.
2020-01-09 Thu
■ #3909. 相同 (homology) と相似 (analogy) [biology][evolution][terminology][onomatopoeia][arbitrariness][borrowing]
「#3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1)」 ([2020-01-05-1]) と「#3906. 系統学の歴史言語学への適用について (2)」 ([2020-01-06-1]) で,生物学と言語学の連携可能性に触れた.以前から生物進化の分野で気になっている用語・概念に,相同 (homology) と相似 (analogy) がある.2つのものが互いに「似ている」とき,似ている理由には2種類があるという洞察だ.中尾 (11) による解説が簡潔で要を得ている.
祖先種 A が形質 α を持っていたという理由で子孫種 B と C も形質 α を保持しているのであれば,この形質 α は相同であるといわれる.他方,祖先種 A が形質 α を持っておらず,子孫種 B と C がそれぞれ別個に類似した環境に適応して形質 α を獲得していた場合,この形質は相似であるといわれる.
Encyclopaedia Britannica からの解説も挙げておこう.
Homologous structures develop from similar embryonic substances and thus have similar basic structural and developmental patterns, reflecting common genetic endowments and evolutionary relationships. In marked contrast, analogous structures are superficially similar and serve similar functions but have quite different structural and developmental patterns. The arm of a man, the wing of a bird, and the pectoral fins of a whale are homologous structures in that all have similar patterns of bones, muscles, nerves, blood vessels, and similar embryonic origins; each, however, has a different function. The wings of birds and those of butterflies, in contrast, are analogous structures---i.e., both allow flight but have no developmental processes in common.
この2種類の「似ている」を言語に当てはめるとどうなるだろうか.2つの言語において形式・機能ともに似ている言語項(たとえば単語)がみられる場合,やはり相同と相似の2種類が区別される.同一語源にさかのぼるがゆえに似ている場合,たとえば英語の one とフランス語の un は,相同である.一方,英語の bow-wow とフランス語の ouah-ouah は犬の鳴き声 (cf. onomatopoeia) を独立して模した結果,似ているケースと考えられるので,相似といえる.
しかし,生物にはほとんどみられず,言語には普通にみられる第3の「似ている」がある.借用 (borrowing) だ(ただし,生物にも「交雑」の事例はあるにはある).英語の people とフランス語の peuple は似ているが,これは前者が後者を借用したからである.借用を言語における「遺伝」の1パターンととらえるのであれば一種の相同関係ともいえなくはないが,これには異論もあるだろう.借用は相似ではないし,相同ともいいにくい.言語の世界に特有の「似ている」だ.
関連して「#1136. 異なる言語の間で類似した語がある場合」 ([2012-06-06-1]) も参照.
・ 中尾 央 「文化の過去を復元すること 文化進化のパターンとプロセス」『文化系統学への招待』中尾 央・三中 信宏(編),勁草書房,2012年.1--16頁.
2020-01-06 Mon
■ #3906. 系統学の歴史言語学への適用について (2) [evolution][methodology][biology][archaeology][historical_linguistics][comparative_linguistics][phylogenetics]
昨日の記事 ([2020-01-05-1]) に引き続き,系統学の方法論を歴史言語学に応用する問題について.
昨日も引用した三中は,「考古学は進化学から何を学んだか?」と題した別の論考で,生物の系統学を他の分野に適用しようとする際にあげられる批判に対して反論を展開しつつ,オブジェクトに応じた因果プロセスを探求することの重要性を説いている (207--08) .ここで念頭に置いているのは,考古学的な遺物の系統推定である.
文化的構築物としての考古学的遺物の「系統関係」とは何かを考察することは大きな意味がある.系統学的な考古学研究に対する頑強な反対意見の一つとして,生物学的な現象を前提とする系統発生の概念と系統推定法をこれらの遺物にそのまま適用することはそもそもまちがいではないかという反論である.
たしかに,生物が生物を生殖によって生み出すという意味で,遺物が遺物を生むわけではない.考古学的な遺物には必ずそれを工作した原始人がいる.その工作者の知能や心象あるいは文化的伝承を通じて,遺物は遺物を生み出すといえる.〔中略〕
しかし,研究対象であるオブジェクトがどのような因果的背景のもとに祖先から子孫への伝承で生じてきたかは,系統発生のパターンの問題ではなく,むしろそれぞれのオブジェクト固有の由来に関するプロセス仮定であると解釈すればいいのではないだろうか.古写本の伝承仮定はある一つの祖本を手本とする書写という因果プロセスが前提となる.一方,有性生殖をする生物集団ではそれぞれの個体だけでは遺伝は生じない.雌雄が存在する個体群を前提としてはじめて系統発生の素過程が進行しうる.また言語ならば複数の話者からなる集団(部族)を仮定してはじめて言語や方言の進化を論じることができるだろう.
オブジェクトを問わず,系統推定はマーカー(標識)となる情報源にしたがってベストの系統仮説を選び出す.生物の場合であっても,たとえば形態形質にてらした系統推定の場合,表現型である個々の形質(たとえばカエルの前肢とかクワガタの角)にもとづく系統推定は「足が足を生む」とか「角が角を生む」というような仮定を置いているわけではけっしてない.足や角の形状は系統推定のためのマーカーにすぎないからである.
それとまったく同様に,系統推定の情報源としての遺物を考古学的マーカーとみなすならば,最初に挙げたような反論は退けることができるだろう.
では,言語というオブジェクトを想定した系統学において,その分岐の因果プロセスやマーカーは何になるだろうか.19世紀に興隆した比較言語学の場合でいえば,因果プロセスの仮定は,音変化の規則性 ("Ausnahmslose Lautgesetze") と,それを共有する/しない話者集団の離合集散ということになろう.また,マーカーは語の音韻形式ということになる.このような因果プロセスやマーカーの設定が必ずしもベストとはいえない云々は議論できるかもしれないが,系統学を応用した比較言語学のアーキテクチャそのものは十分に有効とみてよいだろう.
・ 三中 信宏 「考古学は進化学から何を学んだか?」『文化進化の考古学』中尾 央・松木 武彦・三中 信宏(編),勁草書房,2017年.125--65.
2020-01-05 Sun
■ #3905. 系統学の歴史言語学への適用について (1) [evolution][methodology][family_tree][biology][comparative_linguistics][manuscript][abduction][phylogenetics][historical_linguistics]
生物進化や生物分類の研究で発展してきた系統学 (phylogenetics) の方法論が言語変化や写本伝達などの文化進化にも適用することができるのではないか,という気付き自体はさほど新しいものではないが,その重要性が注目されるようになったのは最近のことである.系統学の諸分野への一般的な適用に関して精力的に啓蒙活動を行なっている論者の1人に,三中がいる.本ブログでも,歴史言語学の観点から「#3162. 古因学」 ([2017-12-23-1]),「#3172. シュライヒャーの系統図的発想はダーウィンからではなく比較文献学から」 ([2018-01-02-1]),「#3175. group thinking と tree thinking」 ([2018-01-05-1]) の記事で紹介してきた.
今回読んだのは,三中による「考古学は進化学から何を学んだか?」と題する論考である.生物系統学と歴史言語学の関連を述べた箇所 (129--30) をみつけたので,引用しよう(引証文献への言及は中略する).
「一般化オブジェクト系統学」は,この分野の歴史を振り返るならば,異なる諸分野で繰り返し“再発見”されてきたロジックである.たとえば,写本系図学や歴史言語学において最節約法(分岐学)に基づく系統推定法が,生物系統学と並行して独立に“再発見”されてきた事例をまず挙げるべきだろう.写本の転写過誤や言語の音韻変化が伝承される過程でさらなる変異を遂げるという因果プロセスが仮定できるとき,現存する子孫写本や子孫言語の情報に基づいて祖本や祖語を推定することが原理的に可能である.そして,それらの形質状態変化の総数を最小化するという最節約基準を置けば,生物のみならず言語や写本の系統関係を共通の最節約法によって推定できる.私が想定している一般化オブジェクト系統学は,この「アブダクション」による推論様式を一般的な歴史復元のロジックとみなしている.
なかでも,生物系統学との関わりを近年強めてきた歴史言語学では,生物分子系統学のさまざまな統計モデルを言語系統推定に利用しつつある.当然予想されるように,生物と言語ではその時空的変化を担う因果過程に違いがあるのだから,共通の系統推定法をそのまま適用するのはまちがっているのではないかという批判も実際に提起されている.しかし,共通のロジックを適用することと個別の条件設定を調整することは別の問題である.たとえ同じ生物であっても,有性生殖をするかしないかどうか,交雑が起こりやすいかどうか,共生進化があるかどうかは場合によって大きく異なり,それに応じて系統推定を実行するときの前提条件やモデル設定は大きく変わる可能性がある.それを考えるならば,オブジェクト間の違いは歴史の推定や探求にとっては実は深刻ではないと結論しても問題ないだろう.むしろ,オブジェクトのもつ性質の違いを考慮した系統樹の推定や進化の考察を適切に行っているかどうかのほうがはるかに重要である.考古学や先史学においても,まったく同様に,遺物など文化構築物の系統や変遷を研究する際には,共通の総論としてのロジックと個別の各論としてのオブジェクト特性とは分けて議論する必要があるだろう.
生物学で発展してきた方法論をそのまま言語変化の研究に当てはめるという姿勢には,批判もあるだろう.生物と言語はまったく異なるオブジェクト(進化子)であり,その変化や変異のあり方も大いに異なっているにもかかわらず,同じ方法論を並行的に適用するのは危険であると.しかし,三中は系統学の手法を「そのまま」適用するなどとは一言も述べていない.むしろ,オブジェクトが異なるという点には,最大限の注意を払うべきだと主張している.オブジェクトに応じて細かいチューニングは必要だが,機械(ロジック)そのものは共通して使える,と力説しているのだ.
日常的にも学術的にも,生物と言語はしばしば互いに喩えられてきた.しかし,2つはあくまで異なるオブジェクトであり,短絡的な比較は慎まなければならない.私も,これまでこの点には注意してきたつもりである(cf. 「#807. 言語系統図と生物系統図の類似点と相違点」 ([2011-07-13-1]),「#2529. evolution の evolution (3)」 ([2016-03-30-1]),「#3146. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (1)」 ([2017-12-07-1]),「#3147. 言語における「遺伝的関係」とは何か? (2)」 ([2017-12-08-1]),「#3148. 言語における「遺伝的関係」の基本単位は個体か種か?」 ([2017-12-09-1]),「#3149. なぜ言語を遺伝的に分類するのか?」 ([2017-12-10-1])).しかし,短絡的でない熟慮された比較ならば,多くの場合,有益なはずにちがいない.系統学の歴史言語学への適用について,もう少し真剣に考えてもよさそうだ.
・ 三中 信宏 「考古学は進化学から何を学んだか?」『文化進化の考古学』中尾 央・松木 武彦・三中 信宏(編),勁草書房,2017年.125--65.
2019-02-25 Mon
■ #3591. ネアンデルタール人は言葉を話したか? [anthropology][homo_sapiens][origin_of_language][evolution]
標題と関連する話題を「#2980. 30万年前の最古のホモサピエンス」 ([2017-06-24-1]),「#1544. 言語の起源と進化の年表」 ([2013-07-19-1]) で取り上げてきた.ホモ・サピエンスに最も近い兄弟であるネアンデルタール人は,はたして言語をもっていたのかどうか.
言語を使いこなすためには,(1) 言語を処理できる脳内機構をもっていること,(2) 言語音を発するための運動機構をもっていること,の2つの条件が満たされなければならない.この2点に関して,人骨化石や考古学的な証拠をもとに様々な検討が加えられているが,なかなか推測の域を出ないようだ.[2013-07-19-1]では次のように述べたが,これとて1つの見解にすぎない.
ネアンデルタール人は喉頭がいまだ高い位置にとどまっており,舌の動きが制限されていたため,発することのできる音域が限られていたと考えられている.しかし,老人や虚弱者の世話,死者の埋葬などの複雑な社会行動を示す考古学的な証拠があることから,そのような社会を成立させる必須要素として初歩的な言語形式が存在したことが示唆される.
更科 (204--05) も,上記とある点で類似した結論に達しているが,言語の進化についても新たな示唆を加えている.ホモ・サピエンスとネアンデルタール人の両方の母体となったホモ・ハイデルベルゲンシス,及びその母体だった可能性のあるさらに古いホモ・エレクトゥスと比較しながら,ネアンデルタール人の言語能力についてコメントしている.
ホモ・エレクトゥスでは脳の形から,ブローカ野が識別できるようになった.ホモ・ハイデルベルゲンシスでは舌骨が,声を出せる形になった.ネアンデルタール人では脊椎骨の穴が広がり,FOXP2 遺伝子も言語に適したタイプになった.言葉はいきなり現われたのではなく,段階的に少しずつ発展してきたのだろう.
したがって,ネアンデルタール人がまったく話せなかったとは考えにくい.石器と枝を組み合わせて槍を作ったり,仲間と協力して狩りをしたりするためには,ある程度は言葉を話せることが必要だ.これはホモ・ハイデルベルゲンシスにも言えることだが,舌骨の形から,かなり自由に声は出せたと考えられる.
しかし,どの程度の文法を使った言葉を話していたのかは,わからない.おそらく目の前で起きている現在のことについては話せただろうが,過去のことについてはどうだったのだろうか.仮定法を使って,現実には起きていないことまで話せたのだろうか.さらに,言語は象徴化行動の最たるものである.ヒトとネアンデルタール人のあいだで象徴化行動に大きな差があったとすれば,言葉についても同様に,大きな差があったと考えるのが自然である.抽象的なこと,たとえば「平和」を,言葉を使わずに考えることはかなり難しい.ネアンデルタール人の辞書には,「私」や「肉」はあっても,「平和」はなかったのではないだろうか.
・ 更科 功 『絶滅の人類史』 NHK出版〈NHK出版新書〉,2018年.
2019-01-30 Wed
■ #3565. 韻律論と分節音韻論の独立性について [gvs][vowel][prosody][phonology][ot][acquisition][evolution]
英語には,歴史的な大母音推移 (Great Vowel Shift; gvs) とは別に,現代英語の共時的な現象としての "Modern English Vowel Shift Rule (alterations)" というものがある.後者は,現代英語の派生語ペアにみられる音韻形態論的な変異に関する共時的な規則である.Chomsky and Halle に端を発し,その後の語彙形態論でも扱われてきたトピックだ.たとえば,次のようなペアの母音に関して交替がみられる.various ? variety, comedy ? comedian, study ? studious, harmony ? harmonious; divine ? divinity, serene ? serenity, sane ? sanity, reduce ? reduction, fool ? folly, profound ? profundity (McMahon 342) .
McMahon は,この共時的な規則を最適性理論 (Optimality Theory; ot) で分析した先行研究の不備を指摘しながら,同理論は韻律論 (prosody) の問題を扱うのには長けているが,母音交替のような分節音に関する問題には適用しにくいのではないかと論じている.両部門は,一般には同じ「音韻論」にくくられるとはいえ,実際には独立性が高いのではないかという.McMahon (357) は,独立性の根拠をあげながら次のように論じている.
. . . we must recognise prosodic and melodic phonology as two different systems, and in fact there are many different strands of evidence pointing in that direction. For instance, prosodic phonology shows clearer connections with emotion, with gesture, and with aspects of call systems in other primates. Prosodic and segmental phonology behave very differently in cases of language disorder and breakdown, with some children who are seriously language-impaired finding considerable compensatory strength in prosody, for instance. Prosodic phonology is also acquired early, and there is evidence that the brain lateralisation of prosody and melody is different too, with more involvement of the right hemisphere in prosody, and strong left hemisphere localisation for segmentals. If prosody phonology and segmental phonology are actually two very different systems, which have evolved differently, are processed differently, are acquired differently, and interact with different systems (as with the paralinguistic uses of prosody, for instance), then there is no need for us to expect a single theory to deal with both.
この見解は,OT の理論的な扱いに関するにとどまらず,言語学における音韻論の位置づけについても再考を促すものとなるだろう.
・ Chomsky, Noam and Morris Halle. The Sound Pattern of English. New York: Harper & Row, 1968.
・ McMahon, April. "Who's Afraid of the Vowel Shift Rule?" Language Sciences (Issues in English Phonology) 29 (2007): 341--59.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow