2025-12-05 Fri
■ #6066.take の多義性 [johnson][oed][loan_word][old_norse][polysemy][collocation][idiom][phrasal_verb][asacul]
動詞 take の多義性 (polysemy) について考えている.語義をどこで区分するのは意味論の古典的な難問とはいえ,どのような切り方をしても,take のような基本語は,多義語と言わざるを得ない.
手元の英和辞書でみてみると,『新英和大辞典』第6版では,他動詞項目だけで38の語義が立てられている.各語義には下位区分もある.分け方次第では,もっと細かくもなれば粗くもなるだろう.英英語辞書での扱いはといえば,OALD8 で42語義ある.歴史的な辞書をを見てみると,Johnson の辞書(1755年)で113語義ほど.OED 第2版で引くと,動詞 take の項は第17巻の pp. 557--72 にわたり,47コラムほどの分量がある.語義数でいえば94を数え,ページをめくっていくだけで壮観である.辞書には,そのほか take を用いた句動詞やイディオムなど,コロケーションの記載も豊富だ.
いちいちの動詞についてきちんと裏取りしたわけではないが,OED でみる限り,take は英語の一般動詞のなかでも群を抜いて記述が多く,その限りにおいて,ひとまず多義的といっておいて間違いない.対応する日本語の「とる」を考えても,これは十分に納得できるだろう.
現行の OED Online の take に比べ,冊子体の OED 第2版の記述がすぐれていると思うのは,同項目の冒頭に近いところで,膨大な多義性を整理し,12の大分類として簡潔に示してくれているところだ.OED Online も,ディスプレイ上で語義をある程度アウトライン化してくれるので,同様の情報は得られるのだが,積極的に取りに行かなければならない.
ここでは利便性を活かして第2版より,take の語義の大分類を示そう.
General arrangement of senses: I. To touch. II. To seize, grip, catch. III. Ordinary current sense, i. with material obj.; ii. with non-material obj. IV. To choose, take for a purpose, into use. V. To derive, obtain from a source. VI. To receive, accept, admit, contain. VII. To apprehend mentally, comprehend. VIII. To undertake, perform, make. IX. To convey, conduct, deliver, apply or betake oneself, go. X. Idiomatic uses with special obj. XI. Intransitive uses with preposition. XII. Adverbial combinations = compound verbs. XIII. Idiomatic phrases, and Phrase-key.
これらの多義をきっちり使いこなすのは非常に難しいことだ.
2025-11-28 Fri
■ #6059. take --- 古ノルド語由来の big word の起源と発達 [etymology][loan_word][lexicology][grammaticalisation][phrasal_verb][asacul][polysemy][collocation][particle][idiom][old_norse][french][contact][borrowing]
明日29日(土)の朝日カルチャーセンター新宿教室での講座では,take という英単語に注目し,その驚くべき起源と発達をたどる予定でいる.この単語は,英語語彙のなかでも最も多義的な単語のひとつである.その意味の広がりと,しかも古ノルド語からの借用語であるという事実に,改めて驚かざるを得ない.
OED 第2版(冊子体)で調べると,動詞 take の項目だけで第17巻の pp. 557--72 を占める.あの OED の小さな文字まで,47コラムほどの分量である.日本語では一般に「取る」と訳されることが多いが,この「取る」という動作概念があまりにも一般的で抽象的であるがゆえに,そこから無数の意味的な発展や共起表現が派生してきた.まさに,英語語彙のなかでも有数の "big word"と言って差し支えないだろう.
この多義的な動詞の歴史をたどると,まず根源にあるのは積極的な行動としての「取る」という意味だ.場所や土地を目的語として「占拠する」といった軍事的な含みをもつ語義だ.ここから派生して,モノを「取る」ことは,それを「自分のものにする」こと,すなわち「所有権を得る」という意味が展開してくる.さらに,モノや人を目的語にとって,何かを「もっていく」,誰かを「連れて行く」へも発展する.
この「積極的に取りにいく」という性質が希薄化していくと,むしろ意味は反対の方向へと向かう.すなわち,「受け取る」「引き受ける」といった,比較的消極的な意味が生まれてくるのだ.
さらに興味深いのは,意味がより希薄化し,いわば文法化 (grammaticalisation) へと進むケースである.例えば,take a walk や take a bath のように,単に特定の動作を行うことを示す,あたかも do に近い補助動詞的な役割を帯び始めるのだ.ここでは「取る」や「受け取る」といった具体的な意味はもはや感じられず,文法的な機能を果たす道具として用いられているにすぎない.この現象は,動詞の語彙的意味が薄れていく過程を示している.
また,take の語彙的価値を高めているのは,句動詞 (phrasal_verb) を生み出す母体としての役割である.take away, take in, take off, take out など,後ろに小辞 (particle) を伴うことで,数限りない表現が生み出されている.これらは1つひとつが独立した意味を持つため,英語学習者にとっては厄介な暗記項目となるが,その豊かさが,英語という言語の表現力を支えている.
加えて,take effect, take place, take part in のように特定の名詞と結びついてイディオム (idiom) を形成する用法も,現代英語では多数存在する.この背景には,中英語期にフランス語の対応する動詞 prendre という単語がどのような目的語をとるのか,という文法的・語彙的な情報を,英語が積極的に参照し,取り入れてきた歴史が関わっていると考えられている.
しかし,この多義的で,これほどまでに英語の語彙体系に深く食い込み,核をなしている動詞 take が,実は英語本来語ではない,という点こそが最も驚くべき事実だ.古英語の本来の「取る」を意味する動詞は niman として存在したにもかかわらず,古英語後期以降に take が古ノルド語から借用されてきたのである.なぜ,古ノルド語からの借用語が,土着の日常的な動詞を駆逐し,英語のなかで最も多義的で強力な "big word" の地位を獲得するに至ったのか.
この現象は,単に語彙の取捨選択の問題にとどまらず,言語接触のメカニズムの複雑さと不思議さを私たちに教えてくれる.この謎について,明日の朝カル講座で考察していきたい.
2025-02-18 Tue
■ #5776. 続,passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][french][syntax][noun][suffix]
昨日の記事「#5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形」 ([2025-02-17-1]) に続き,複数形の -s が語中に紛れ込んでいる例について.今日も Poutsma を参照する (142--43) .
フランス語の慣用句に由来する複合名詞(句)の多くは,英語に入ってからもフランス語の統語論を反映して「名詞要素+形容詞要素」の順にとどまる.英語としては,これらの語句の複数形を作るにあたって,名詞要素に -s をつけるのが一般的である.attorneys general, cousins-german, book-prices current, battlesroyal, Governors-General, damsels-errant, heirs-apparent, knights-errant のようにだ(ただし,attorney generals, letters-patents 等もあり得る).
今回の話題の発端である passer(s)-by のタイプ,すなわち名詞要素の後ろに前置詞句・副詞が付く複合語も,名詞要素に -s を付して複数形を作るのが一般的だ.commanders-in-chef, fathers-in-law, heirs-at-law, quarters-of-an-hour, bills of fare; blowings-up, callings-over, hangers-n, knockers-up, lookers-on, lyings-in, standars-by, whippers-in, goers-in, comers-out, breakings-up, droppings asleep, fallings forward など (cf. men-at-arms) .
ただし,表記上ハイフンの有無などについてしばしば揺れが見られる通り,各々の表現について歴史や慣用があるものと思われ,一般化した規則を設けることは難しそうだ.形態論と統語論の交差点にある問題といえる.
・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.
2025-02-17 Mon
■ #5775. passers-by のような中途半端な位置に -s がつく妙な複数形 [plural][compound][morphology][inflection][phrasal_verb][conversion][noun][suffix]
複数要素からなる複合語名詞について,その複数形は語末に,つまり最終要素に -s を付加すればよい,というのが一般的な規則である.brother-officers, penny-a-liners, forget-me-nots, go-between, ne'er-do-wells, three-year-olds, merry-go-rounds のようにである.
ところが,標記の passers-by のように,一部の句動詞 (phrasal_verb) にに由来し,それが品詞転換した類いの名詞に関しては,事情が異なるケースがある.最終要素となる小辞(前置詞や副詞と同形の語)が語末に来ることになって,そこに直接 -s を付けるのがためらわれるからだろうか,*passer-bys ではなく passers-by として複数形を作るのだ.
「#5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧」 ([2023-08-07-1]) を参考にすると,passers-by 型の複数形をとるものとして crossings-out, lookers-on, tellings-off, tickings-off, turn-ups を挙げることができる.
しかし,一筋縄では行かない.同じタイプに見えても,大規則に従って語末に -s を付ける turn-ups, hand-me-downs, lace-ups, left-overs, makeshifts, onlookers の例が出てくる.
関連して,接尾辞 -ful(l) を最後要素としてもつ複合語は,この点で揺れが見られる.現代英語ではなく後期近代英語の事情であることを断わりつつ,原則として handfuls (of marbles), bucketfulls (of fragrant milk) などと最後要素に -s を付して複数形を作るが,ときに (two) table-spoonsfull (of rum), (two) donkeysful (of children), bucketsfull (of tea) のように第1要素に -s をつける異形もみられた.
以上,Poutsma (141--43) を参照して執筆した.単語によって揺れがあるということは,意味的な考慮や通時的な側面の関与も疑われる.興味深い問題だ.
・ Poutsma, H. A Grammar of Late Modern English. Part II, The Parts of Speech, 1A. Groningen: P. Noordhoff, 1914.
2024-07-14 Sun
■ #5557. 秋元実治(著)『増補 文法化とイディオム化』(ひつじ書房,2014年) [toc][grammaticalisation][idiomatisation][idiom][composite_predicate][syntax][lexicology][frequency][lexicalisation][preposition][phrasal_verb][voicy][heldio]

先日,秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)と標記の書籍を参照しつつ対談しました.そして,その様子を一昨日 Voicy heldio で「#1139. イディオムとイディオム化 --- 秋元実治先生との対談 with 小河舜さん」として配信しました.中身の濃い,本編で22分ほどの対談回なっております.ぜひお時間のあるときにお聴きください.
秋元実治(著)『増補 文法化とイディオム化』(ひつじ書房,2014年)については,これまでもいくつかの記事で取り上げてきており,とりわけ「#1975. 文法化研究の発展と拡大 (2)」 ([2014-09-23-1]) で第1章の目次を挙げましたが,今回は今後の参照のためにも本書全体の目次を掲げておきます.近日中に対談の続編を配信する予定です.
改訂版はしがき
はしがき
理論編
第1章 文法化
1.1 序
1.2 文法化とそのメカニズム
1.2.1 語用論的推論 (Pragmatic inferencing)
1.2.2 漂白化 (Bleaching)
1.3 一方向性 (Unidirectionality)
1.3.1 一般化 (Generalization)
1.3.2 脱範疇化 (Decategorialization)
1.3.3 重層化 (Layering)
1.3.4 保持化 (Persistence)
1.3.5 分岐化 (Divergence)
1.3.6 特殊化 (Specialization)
1.3.7 再新化 (Renewal)
1.4 主観化 (Subjectification)
1.5 再分析 (Reanalysis)
1.6 クラインと文法化連鎖 (Grammaticalization chains)
1.7 文法化とアイコン性 (Iconicity)
1.8 文法化と外適応 (Exaptation)
1.9 文法化と「見えざる手」 (Invisible hand) 理論
1.10 文法化と「偏流」 (Drift) 論
第2章 イディオム化
2.1 序
2.2 イディオムとは
2.3 イディオム化
2.4 イディオム化の要因
2.4.1 具体的から抽象的
2.4.2 脱範疇化 (Decategorialization)
2.4.3 再分析 (Reanalysis)
2.4.4 頻度性 (Frequency of occurrence)
2.5 イディオム化,文法化及び語彙化
分析例
第1章 初期近代英語における複合動詞の発達
1.1 序
1.2 先行研究
1.3 データ
1.4 複合動詞のイディオム的特徴
1.4.1 Give
1.4.2 Take
1.5 ジャンル間の比較: The Cely Letters と The Paston Letters
1.6 結論
第2章 後期近代英語における複合動詞
2.1 序
2.2 先行研究
2.3 データ
2.4 構造の特徴
2.5 関係代名詞化
2.6 各動詞の特徴
2.6.1 Do
2.6.2 Give
2.6.3 Have
2.6.4 Make
2.6.5 Take
2.7 複合動詞と文法化
2.8 結論
第3章 Give イディオムの形成
3.1 序
3.2 先行研究
3.3 データ及び give パタンの記述
3.4 本論
3.4.1 文法化とイディオム形成
3.4.2 再分析と意味の漂白化
3.4.3 イディオム化
3.4.4 名詞性
3.4.5 構文と頻度性
3.4 本論
3.4.1 文法化とイディオム形成
3.4.2 再分析と意味の漂白化
3.4.3 イディオム化
3.4.4 名詞性
3.4.5 構文と頻度性
3.5 結論
第4章 2つのタイプの受動構文
4.1 序
4.2 先行研究
4.3 データ
4.4 イディオム化
4.5 結論
第5章 再帰動詞と関連構文
5.1 序
5.2 先行研究
5.3 データ
5.3.1 Content oneself with
5.3.2 Avail oneself of
5.3.3 Devote oneself to
5.3.4 Apply oneself to
5.3.5 Attach oneself to
5.3.6 Address oneself to
5.3.7 Confine oneself to
5.3.8 Concern oneself with/about/in
5.3.9 Take (it) upon oneself to V
5.4 再帰動詞と文法化及びイディオム化
5.5 再起動し,受動化及び複合動詞
5.5.1 Prepare
5.5.2 Interest
5.6 結論
第6章 Far from の文法化,イディオム化
6.1 序
6.2 先行研究
6.3 データ
6.4 文法化とイディオム化
6.4.1 文法化
6.4.2 意味変化と統語変化の関係:イディオム化
6.5 結論
第7章 複合前置詞
7.1 序
7.2 先行研究
7.3 データ
7.4 複合前置詞の発達
7.4.1 Instead of
7.4.2 On account of
7.5 競合関係 (Rivalry)
7.5.1 In comparison of/in comparison with/in comparison to
7.5.2 By virtue of/in virtue of
7.5.3 In spite of/in despite of
7.6 談話機能の発達
7.7 文法化,語彙化,イディオム化
7.8 結論
第8章 動詞派生前置詞
8.1 序
8.2 先行研究
8.3 データ及び分析
8.3.1 Concerning
8.3.2 Considering
8.3.3 Regarding
8.3.4 Relating to
8.3.5 Touching
8.4 動詞派生前置詞と文法化
8.5 結論
第9章 動詞 pray の文法化
9.1 序
9.2 先行研究
9.3 データ
9.4 15世紀
9.5 16世紀
9.6 17世紀
9.7 18世紀
9.8 19世紀
9.9 文法化
9.9.1 挿入詞と文法化
9.9.2 丁寧標識と文法化
9.10 結論
第10章 'I'm afraid' の挿入詞的発達
10.1 序
10.2 先行研究
10.3 データ及びその文法
10.4 文法化---Hopper (1991) を中心に
10.5 結論
第11章 'I dare say' の挿入詞的発達
11.1 序
11.2 先行研究
11.3 データの分析
11.4 文法化と文体
11.5 結論
第12章 句動詞における after と forth の衰退
12.1 序
12.2 For による after の交替
12.2.1 先行研究
12.2.2 動詞句の選択と頻度
12.2.3 After と for の意味・機能の変化
12.3 Forth の衰退
12.3.1 先行研究
12.3.2 Forth と共起する動詞の種類
12.3.3 Out による forth の交替
12.4 結論
第13章 Wanting タイプの動詞間に見られる競合 --- desire, hope, want 及び wish を中心に ---
13.1 序
13.2 先行研究
13.3 昨日変化
13.3.1 Desire
13.3.2 Hope
13.3.3 Want
13.3.4 Wish
13.4 4つの動詞の統語的・意味的特徴
13.4.1 従属節内における法及び時制
13.4.1.1 Desire + that/Ø
13.4.1.2 Hope + that/Ø
13.4.1.3 Wish + that/Ø
13.4.2 Desire, hope, want 及び wish と to 不定詞構造
13.4.3 That の省略
13.5 新しいシステムに至る変化及び再配置
13.6 結論
結論
補章
参考文献
索引
人名索引
事項索引
・ 秋元 実治 『増補 文法化とイディオム化』 ひつじ書房,2014年.
2023-09-03 Sun
■ #5242. 川端朋広先生と20世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][pde][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][preposition]
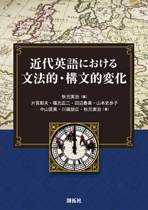
こちらの本は6月に開拓社より出版された『近代英語における文法的・構文的変化』です.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆されています.
本書については本ブログや Voicy heldio で何度かご紹介してきましたが,今回は,第6章「20世紀の文法的・構文的変化」を執筆された川端朋広先生(愛知大学)との heldio 対談をご案内します.「#824. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 川端朋広先生との対談 (1)」と題し,40分超でじっくりお話しをうかがっています.
2023年の現在,20世紀の英語は正確にいえば「過去の英語」となりますが,事実上は私たちが日常的に触れている英語と同じものと考えられます.しかし,100年余の時間を考えれば,当然ながら細かな言語変化はたくさん起こってきたはずです.1901年と2023年の英語とでは,お互いに通じないことはないにせよ,やはり微妙なズレはあるはずです.現代英語の文法にも確かに変化が生じてきたのです.
英語史ときくと,古英語や中英語のような古文を研究する分野という印象があるかもしれませんが,直近数十年に生じた英語の変化を追うのも立派な英語史研究の一部です.今回の川端先生のお話しからも,言語変化のダイナミックさと複雑さが伝わるのではないでしょうか.
本書についてご関心をもった方は,ぜひ以下のコンテンツも訪問していただければと思います.
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])
・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])
・ hellog 「#5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-16-1])
・ hellog 「#5235. 片見彰夫先生と15世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-27-1])
・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」
・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」
・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」
・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」
・ heldio 「#817. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 片見彰夫先生との対談」
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-08-27 Sun
■ #5235. 片見彰夫先生と15世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][lme][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][caxton][malory][negative][impersonal_verb][preposition][periodisation]
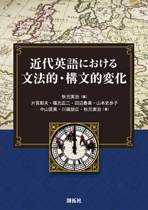
6月に開拓社より出版された『近代英語における文法的・構文的変化』について,すでに何度かご紹介してきました.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆するというユニークな構成の本です.
本書の第1章「15世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された片見彰夫先生(青山学院大学)と,Voicy heldio での対談が実現しました.えっ,15世紀というのは伝統的な英語史の時代区分では中英語期の最後の世紀に当たるのでは,と思った方は鋭いです.確かにその通りなのですが,対談を聴いていただければ,15世紀を近代英語の枠組みで捉えることが必ずしも無理なことではないと分かるはずです.まずは「#817. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 片見彰夫先生との対談」をお聴きください(40分超の音声配信です).
私自身も,片見先生と対談するまでは,15世紀の英語はあくまで Chaucer に代表される14世紀の英語の続きにすぎないという程度の認識でいたところがあったのですが,思い違いだったようです.近代英語期への入り口として,英語史上,ユニークで重要な時期であることが分かってきました.皆さんも15世紀の英語に関心を寄せてみませんか.最初に手に取るべきは,対談の最後にもあったように,Thomas Malory による Le Morte Darthur 『アーサー王の死』ですね(Arthur 王伝説の集大成).
時代区分の話題については,本ブログでも periodisation のタグのついた多くの記事で取り上げていますので,ぜひお読み下さい.
さて,今回ご案内した『近代英語における文法的・構文的変化』については,これまで YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきました.以下よりご参照ください.
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])
・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])
・ hellog 「#5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-16-1])
・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」
・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」
・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」
・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」
・ heldio 「#817. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 片見彰夫先生との対談」
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-08-16 Wed
■ #5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][lmode][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation]
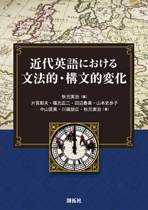
6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた『近代英語における文法的・構文的変化』が出版されました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)による編著です.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆しています.
このたび,本書の第5章「19世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された中山匡美先生(神奈川大学ほか)と,Voicy heldio での対談が実現しました.19世紀は,英語史全体からみると現代に非常に近い時期ですので,それほど大きな違いはないと思われがちです.確かに現代英語を読めるのであれば19世紀の英語もおおよそ読めてしまうというのは事実です.しかし,それだからこそ,小さな違いを見過ごしてしまい,大きな誤解に陥ってしまう危険性があるのです.似ているだけに,落とし穴にはまらないよう,注意深く意識的な観察が必要ということにもなります.この辺りの事情を,19世紀の英語の専門家にお聴きしました.「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」です.どうぞご聴取ください(27分ほどの音声配信です).
中山先生とは,これまでも2回の heldio 対談を行ない,配信しています.
・ 「#803. 中山匡美先生にとって英語とは何ですか? --- 「英語は○○です」企画の関連対談回」(2023/08/12 配信)
・ 「#323. 中山匡美先生との対談 singular "they" は19世紀でも普通に使われていた!」 (2022/04/19 配信)
今回ご案内した『近代英語における文法的・構文的変化』については,すでに YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきましたので,以下よりご参照いただければ幸いです.
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])
・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])
・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」
・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」
・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」
・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-08-07 Mon
■ #5215. 句動詞から品詞転換した(ようにみえる)名詞・形容詞の一覧 [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][punctuation][hyphen][gerund][voicy][heldio]
「#5213. 句動詞の品詞転換と ODPV」 ([2023-08-05-1]),「#5214. 句動詞の品詞転換と ODPV (2)」 ([2023-08-06-1]) を受けて,Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) の巻末 (514--17) に挙げられている表記の語の一覧を再現する.数えてみると372件あった.ただし,これも氷山の一角なのだろうと思う.
関連して今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,この話題と間接的に関わる「#798. outbreak か breakout か --- 動詞と不変化詞の位置をめぐる問題」を配信したので,お聴きいただければ.
以下の一覧に挙がっているほぼすべての語が「動詞+不変化詞」の語形成となっているが,uplift と upturn のみが「不変化詞+動詞」となっている.この2語は各々 a1845, 1868 が初出となっており,歴史的にいえば「不変化詞+動詞」の語形成として遅めの造語ということになる.
back-up
balls-up
bawling-out
beating-up
blackout/black-out
blast-off
blowout
blowout (main entry)
blowing-up
blow-up
botch-up
(a) breakaway (group)
(a) break-away (state)
break-back
breakdown
break-in
break-out
breakthrough
break-up
brew-up
brush(-)down
brush-off
build-up
bust-up
bust-up (main entry)
call(ing)-up
carry-on
carryings-on
carve-up
castaway
cast-off
cave-in
change-down
change-over
change-up
check-in
check-out
check-over
check-through
check-up
clamp-down
clawback
clean-out
clean-up
clear-up
climb-down
clip-on (ear-rings)
clock-in (time)
clock-off (time)
clock-on (time)
clock-out (time)
close-down
cock-up
come-back
come-back (main entry)
come-down (main entry)
come-hither (look) (main entry)
come-on
cop-out
count-down
cover-up
crack-down
crack-up
crossing(s)-out
cut-away
cut-back
cut-off
cut-out
die-back
dig-in
doss-down
downpour
drawback (main entry)
dressing-down
drive-in (main entry)
drop-out
drying-up
fade-out
falling-off
fall-out (main entry)
feedback
fight-back
fill-up
fit-up
flare-up
flashback (main entry)
flick(-)through
flip(-)through
flyover (main entry)
flypast
follow-on
follow-through
follow-up
foul-up
frame-up
freak-out
freeze-off
freeze-up
freshen-up
fuck-up
gadabout
getaway (main entry)
get-together
get-up
give-away
glance-over/through
(the) go-ahead (to do sth)
(a) go-ahead (organization)
go-between (main entry)
go-by (main entry)
goings-on (main entry)
going-over (main entry)
hand-me-down(s)
hand-off
hand-out
hand-over
hang-out
hangover/hung over (main entry)
hang-up/hung up (main entry)
hideaway
hold-up, holdup
hook-up/hooked up (main entry)
hose down
hush-up
jump-off
kick-back
kick-off
kip-down
knockabout (main entry)
knock-down, knockdown (price)
knock-down, knockdown (furniture)
knock-on
knock-on effect (main entry)
knock-out
knock-up
lace-up(s)
layabout (main entry)
laybay (main entry)
lay-off
lay-out
lead-in
lead-off
leaf-through
leaseback
left-over(s)
let-down
let-out
let-up
lie-down
lie-in
lift-off
lift-up
limber-up
line-out (main entry)
line-up
listen-in
(a) live-in (maid)
(a) living-out (allowance)
lock-out
lock-up (main entry)
(a) look about/around/round
look-in (main entry)
looker(s)-on
look-out
(be sb's) look-out (main entry)
look-over
(a) look round
look-through
make-up
makeshift(s)
march-past
mark-down
mark-up
marry-up
meltdown (main entry)
mess-up
mix-up
mock-up (main entry)
(a) mop-up (operation)
muck-up
(a) nose(-)about/around/round
offprint
onlooker(s)
outbreak
outcast
outlay
output
overspill
passer(s)-by
paste-up
pay-off, payoff
peel-off
phone-in
pick-me-up
pick-up
pick-up (truck) (main entry)
pile-up
pile-up (main entry)
pin-up (main entry)
play-back
play-off
(a) poke(-)about/around
(a) pop-up (book)
(a) potter(-)about/around
print-off
print-out
pull-in
(a) pull-out (section)
pull-up
punch-up
push-off
pushover (main entry)
put-down
(a) put-down (point)
(a) put-up (bed)
quickening-up
(a) rake(-)about/around/round
rake-off
rake(-)round
rave-up
read-through
read-through (main entry)
riffle(-)through
rig-out
rinse-out
rip-off
roll-on/roll-off (main entry)
roll-up (main entry)
round-up
rub-down
rub-up
runabout (main entry)
run-around (main entry)
runaway (children)
runaway (main entry)
(a) runaway (marriage)
(a) runaway (victory)
run-down
run-down (main entry)
run-in (with) (main entry)
run-off
run-through
run-up
(a) scout-about/around
(a) see-through (blouse etc)
seize-up
sell-off
sell-out
sell-out/sold-out (main entry)
send-off (main entry)
send-up
setback
set-to
set-up
setback
set-to
set-up
set-up (main entry)
shake-down
shake-out
shake-up
share-out
shoot-out
(a) shop around
show-down (main entry)
show-off
shut-down
sit-down
sit-down (demonstration/strike) (main entry)
sit-in
skim-through
sleep-in
(a) sleep-in (nanny)
slip-up
smash-up
snarl-up
snoop(-)about/around/round
speed-up
spin-off (main entry)
splash-down
(a) spring-back (binder)
stack-up
stake-out
standby
stand-in
stand-off (main entry)
stand-to
stand-up comedian/comic (main entry)
start-up (capital)
step-up
(a) stick-on (label)
stick-up
stitch-up
stop-over
stowaway
strip-down
summing-up
sun-up
swab(-)out
sweep-out
sweep-up
swill-out
swing-round
switch-over
tailback
take-away
take-home (pay)
take-off
take-out
take-up
talk-in (main entry)
talk-through
teach-in (main entry)
tearaway (main entry)
tee off (main entry)
telling(s)-off
(a) through-away (can)
(a) throw-away (remark)
throw-back
throw-back (main entry)
throw-in
throw-out
(a) thumb(-)through
ticking(s)-off
tick-over
tidy-up
tie-up/tied up (main entry)
tip-off
(a) tip-up (seat)
top-up
toss-up
touch-down
trade-in
trade-off
try-on
try-out
turnabout
turn-around
turndown
turn-off
turn-on
turn-out
turn-over
turn-over (main entry)
turn-round
turn-up(s) (main entry)
turn-up for the books (main entry)
upturn
uplift
(a) wake-up (call)
walkabout (main entry)
walk on (main entry)
(a) walk-on (part)
walk-out
walk-over
walk-through
warm-up
wash-down
wash-out
wash-out (main entry)
watch-out
weigh-in
whip-round (main entry)
wind-up
wipe-down
wipe-over
work-in (main entry)
work-out (main entry)
write-in (main entry)
write-off
write-up
(a) zip-up (jacket)
・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.
2023-08-06 Sun
■ #5214. 句動詞の品詞転換と ODPV (2) [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][punctuation][hyphen][gerund]
昨日の記事 ([2023-08-05-1]) に引き続き,句動詞辞典 Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) を参照しつつ句動詞 (phrasal_verb) の品詞転換 (conversion) について.
ODPV の巻末 (514) に,名詞化した句動詞について概説と凡例が掲載されている.この部分を読むだけで,句動詞の品詞転換をめぐる問題や様々な側面がみえてくる.例えば,2要素の間にハイフンが挟まれるのかどうかを含めた句読法の問題,句動詞のゼロ派生ではなく動詞に -ing を付して動名詞化する別法の存在,一見句動詞の品詞転換のようでいて実はもとの対応する句動詞が欠けているケース,形容詞への品詞転換の事例など.
This index covers all the nominalized forms (ie nouns derived from verbs + particles/prepositions) recorded in the main part of the dictionary (usually but not always the base form of the verb + particle/preposition, with or without a hyphen). For a full treatment of these forms, see The Student's Guide to the Dictionary.
Nominalized forms sometimes consist of the -ing form of the verb + particle/preposition (eg (a) dressing-down, (a) summing-up, (a) telling-off). The more common examples are recorded here.
Each nominal form is listed alphabetically and is followed by the headphrase(s) of the entry (or entries) in which it appears in the main text:
change-over change over (from)(to); change round/over
output put out 7
When the nominalized form is the headphrase itself, the fact is noted as follows:
fall-out (main entry)
(There is no finite verb + particle expression in regular use from which fall-out derives: a sentence such as *The nuclear tests fell out over a large area is unacceptable.)
When a nominalized form is generally used attributively, a noun with which it commonly occurs is given in parentheses after it:
(a) see-through (blouse) see through 1
start-up (capital) start up 2
Whether a nominalized form appears as one word, as one word with a hyphen, or as two words, is often a matter of printing convention or individual usage. The entries in the dictionary and in this index generally show the most accepted form in British usage, but variations are recorded where appropriate, eg. a) poke(-)about/around.
ちなみに第1段落で参照されている The Student's Guide to the Dictionary の該当箇所 (xiii) には,次のようにある.
1 what is a nominalized form?
A nominalized form ('nom form' for short) is a noun formed from a phrasal verb: make-up, for instance, is formed from make up (ie 'apply cosmetics to one's face') and take-off is formed from take off (ie 'leave the ground in an aircraft'). Sometimes nom forms have a spelling which includes the letters -ing: tell off (ie 'reproach, reprimand') has the nom form telling-off.
ただでさえ使いこなすのが難しい句動詞だが,そこからの発展形というべき品詞転換した名詞・形容詞についても相当に複雑な事情があるようだ.
・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.
2023-08-05 Sat
■ #5213. 句動詞の品詞転換と ODPV [dictionary][lexicography][phrasal_verb][conversion][voicy][heldio]
句動詞 (phrasal_verb) の品詞転換 (conversion) について,今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で取り上げました.「#796. get-together, giveaway --- 句動詞の品詞転換」をお聴き下さい.
配信のなかで触れた Oxford Dictionary of Phrasal Verbs (= ODPV) について紹介します.新版も出ているようですが,配信のために私が参照したのは1993年版のこちらでした.
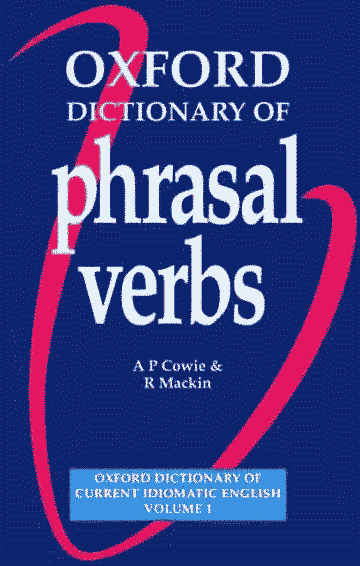
この辞書の巻末 (514--17) に句動詞が品詞転換してできた多くの名詞(ときに形容詞)が一覧されています.400個近くあるのではないでしょうか.出版から20年経っていますが,現在までに品詞転換した句動詞も少なくないものと想像されます.
句動詞の品詞転換については,本ブログでも以下の記事で触れていますのでご参照下さい.
・ 「#420. 20世紀後半にはやった二つの語形成」 ([2010-06-21-1])
・ 「#1695. 句動詞の品詞転換」 ([2013-12-17-1])
また,句動詞に限らず一般の品詞転換の話題については,本ブログの記事としては conversion を,heldio の配信回としてはこの辺りをお訪ねいただければ.
・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.
2023-07-31 Mon
■ #5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][emode][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation]
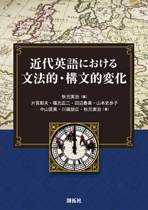
6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた『近代英語における文法的・構文的変化』が出版されました.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)による編著です.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆しています.
このたび,本書の第3章「17世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された田辺春美先生(成蹊大学)と,Voicy heldio での対談が実現しました.17世紀は英語史上やや地味な時代ではありますが,着実に変化が進行していた重要な世紀です.ことさらに取り上げられることが少ない世紀ですので,今回の対談はむしろ貴重です.「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」をお聴き下さい(21分ほどの音声配信です).
田辺先生の最後の台詞「17世紀も忘れないでね~」が印象的でしたね.
本書については,すでに YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきましたので,そちらもご参照いただければ幸いです.
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])
・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」
・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」
・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-07-09 Sun
■ #5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました [voicy][heldio][review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation]
6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた書籍が出版されました.『近代英語における文法的・構文的変化』です.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)が編者を務められ,他に6名の研究者が執筆に加わっています.本書については,すでにこのブログや YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で紹介する機会がありました.
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
このたび,本書をめぐって編者の秋元実治先生とじきじきに対談する機会に恵まれました.対談の様子は,今朝の Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」として配信しています.対談本体は27分ほどとなっています.お時間のあるときにゆっくりお聴きいただければ.
エンディングチャプター(第5チャプター)では,秋元先生から対談収録後にうかがった,本書の表紙下部のビッグベンの写真についての貴重な裏話を紹介しています.
皆さん,ぜひ近代英語の文法変化について関心を寄せていただければ!
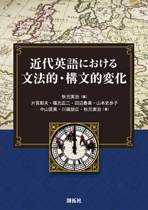
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-06-19 Mon
■ #5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年) [review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation][youtube]
近代英語の文法変化についてコーパスを用いて実証的に研究した論考集が開拓社より出版されました.英語史分野の一線で活躍されている著者7名(片見彰夫氏,福元広二氏,田辺春美氏,山本史歩子氏,中山匡美氏,川端朋広氏,秋元実治氏)による書籍です.著者の方々よりご献本いただきました由,ここに感謝致します.
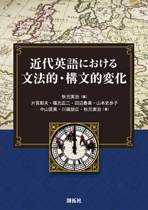
この本の最大の特徴は,各章が15--20世紀の各世紀を考察範囲としていることです.注目する話題は半ば固定されており,その点で定点観測となっているのですが,全体として整理された通時的な統語論の研究となっています.「はしがき」の冒頭に次のようにあります (v) .
本書は近代英語(1500--Present)における文法的・構文的変化についてコーパス等の使用による実証的研究である.
これまで英語史の記述において世紀別に述べることはあまりなかったように思われる.ひとつにはほとんどの言語変化は世紀を横断するため,各世紀の記述が難しいことがある.しかしながら,文学史などでは世紀別はきわめて普通であり(例えば,Oxford History of English Literature 12 volumes),このこともあってか英語史においても最近 Kytö et al. (2006), Mair (2006) などが出版され,それぞれ19世紀,20世紀の英語における変化・特徴に焦点をあてている.
本書では近代英語における上記のような変化の連続性と各世紀の特徴を捉えるために,以下の点を執筆者の間で共有した.
1. 全ての執筆者は共通項目,句動詞,仮定法,補文について述べる.
2. それ以外の項目で,その世紀の特徴と考えられる文法的・構文的変化について述べる.
3. 電子コーパス,テキスト等を使って,実証的に記述する.
英語史の時代区分 (periodisation) については,最近では「#5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り」 ([2023-05-24-1]) で取り上げるなどし,私自身も長らく考えてきました.「古英語」や「近代英語」などとラベルを貼るのではなく,きっぱりと世紀単位で切る,あるいは言及するというのは確かに一般的ではありませんでしたが,Curzan (33) が述べるように,ラベルを避けたい立場の論者は世紀単位を好むようです.一見すると無機質な時代区分のようでいて,むしろ読み手に世紀をまたいだ言語の連続性と断絶性を意識させるという効果があるのではないでしょうか.
本書ではコーパスを用いた具体的で実証的な研究が紹介されており,この分野を研究する学生や研究者には,手法も含めて直接参考になります.また,文法変化・構文変化といっても扱うべき話題は多岐にわたるものですが,各章では各世紀の英語を考察する上でとりわけ重要な項目が選ばれており,たいへん有用です.
最終章は全体のまとめとなっており,いったん各章のために世紀別に分けられたものが建て直され,読み手の視界がすっきりします.参考文献も充実しており,中英語末期から現代に至るまでの文法変化に関心のある方には,ぜひ手に取ってもらいたい一冊です.私も学生に薦めたいと思います.
著者の一人,山本史歩子さん(青山学院大学)におかれましては,本書の出版を見る前にご逝去されたとの報に接しました.悲しみでいっぱいです.ご冥福をお祈りいたします.
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.
2023-02-22 Wed
■ #5049. 句動詞の多様な型 [phrasal_verb][syntax][word_order][verb][adverb][preposition][particle][idiom]
英語には,動詞 (verb) と小辞 (particle) の組み合わせからなる句動詞 (phrasal_verb) が数多く存在している.とりわけ口語で頻出し,慣習的・比喩的な意味をもつものも多い.さらに統語構造上も多様な型を取り得るため,しばしば英語学習の障壁となる.
例えば run と up を組み合わせた表現を考えてみよう.統語的には4つのパターンに区分される.
(1) A girl ran up. 「ある少女が駆け寄ってきた」
ran up が全体として1つの自動詞に相当する.
(2) The spider ran up the wall. 「そのクモは壁を登っていった」
自動詞 ran と前置詞句 up the wall の組み合わせである.
(3) The soldier ran up a flag. 「その兵士は旗を掲げた」
ran up の組み合わせにより1つの他動詞に相当し,目的語を取る.この場合,小辞 up と名詞句の目的語 a flag の位置はリバーシブルで,The soldier ran a flag up. の語順も可能.ただし,目的語が it のような代名詞の場合には,むしろ The soldier ran it up. の語順のみが許容される.
(4) Would you mind running me up the road? 「道路の先まで車に乗せていっていただけませんか」
他動詞 run と前置詞句 up the road の組み合わせである.
run と up の組み合わせのみに限定しても,このように4つの型が認められる.他の動詞と他の小辞の組み合わせの全体を考慮すれば,型としては8つの型があり,きわめて複雑となる.
・ Cowie, A. P. and R Mackin, comps. Oxford Dictionary of Phrasal Verbs. Oxford: OUP, 1993.
2021-05-19 Wed
■ #4405. ポップな話題としての「句動詞の品詞転換」 [phrasal_verb][conversion][word_formation][khelf_hel_intro_2021]
本日紹介する「英語史導入企画2021」のためのコンテンツは,学部生による「POP-UP STORE って何だろう?」です.比較的新しい語で「ポンと上がる型の,飛び出し式の;〈本・カードなどが〉開くと絵の飛び出す」ほどを意味する形容詞として用いられることが多い.pop-up birthday card, pop-up toaster, pop-up window など,わりと身近なものも多い.今回のコンテンツで扱われているのは,最近イギリスや日本でも流行ってきているという pop-up store である.
pop-up (n. and adj.) という比較的新しい語を OED により紹介してくれたコンテンツだが,実は英語史的にはおおいに注目すべき話題なのである.これは,句動詞 pop up (ポンと飛び出す)が全体として形容詞あるいは名詞として機能する「句動詞の品詞転換」というべき事例の1つである.そして,この句動詞の品詞転換は,20世紀以降に発達してきた現代的で革新的な語形成の1つなのである.実際,数年前にはこのテーマで修士論文を書いた学生がいたし,現在もこのテーマに関心を寄せる大学院生がいる.なかなかポップなトピックだ.
この話題については,すでに「#420. 20世紀後半にはやった二つの語形成」 ([2010-06-21-1]),「#1695. 句動詞の品詞転換」 ([2013-12-17-1]),「#2300. 句動詞の品詞転換と名前動後」 ([2015-08-14-1]) 等の記事で取り上げているので,そちらをご覧いただきたい.
句動詞の品詞転換は確かに現代英語的な現象として注目に値するのだが,英語史の長期的スパンの観点からすると,その歴史的前提として (1) 中英語期に句動詞 (phrasal_verb) そのものが発達したこと,そして (2) 近代英語期にかけて品詞転換 (conversion) という形態過程が確立したことが重要である.当たり前のことではあるが,この2つの歴史的な所与の条件がなければ,現代英語における句動詞の品詞転換の流行などあり得なかったはずだ.その意味で,この歴史的所与の2点を,句動詞の品詞転換に連なる地下水脈と呼んでおきたい.
2020-03-27 Fri
■ #3987. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 (2) [old_norse][contact][syntax][word_order][phrasal_verb][plural][link]
「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1]) で挙げたリストに,Dance (1735) を参照し,いくつか項目を追加しておきたい.いずれも実証が待たれる仮説というレベルである.
(1) the marked increase in productivity of the derivational verbal affixes -n- (as in harden, deepen) and -l- (e.g. crackle, sparkle)
(2) the rise of the "phrasal verb" (verb plus adverb/preposition) at the expense of the verbal prefix, most persuasively the development of up in an aspectual (completive) function
(3) certain aspects of v2 syntax (including the development of 'CP-v2' syntax in northern Middle English)
(4) the general shift to VO order
上記 (1) については,「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1]) で関連する話題に触れているので,そちらも参照.
(2) については,関連して「#2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論」 ([2015-11-18-1]) を参照.
(3), (4) は統語現象だが,とりわけ (4) は大きな仮説である.これについては拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)の第5章第4節でも論じている.さらに以下の記事やリンク先の話題も合わせてどうぞ.
・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])
・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])
最後にリストに加えるのを忘れていたもう1つの項目があった.
(5) the spread of the s-plural
これは,私自身が詳細に論じている説である.詳しくは Hotta をご覧ください.
・ Dance, Richard. "English in Contact: Norse." Chapter 110 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1724--37.
・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.
・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.
2019-07-23 Tue
■ #3739. 素朴な疑問を何点か [sobokunagimon][link][y][do-periphrasis][verb][lexicology][phrasal_verb]
今期の理論言語学講座「史的言語学」(すでに終了)の講座を受講されていた方より,素朴な疑問をいくつかいただいていました.既存のブログ記事へ差し向ける回答が多いのですが,せっかくですのでその回答をこちらにオープンにしておきます.
[ 1.英語の Y/N 疑問文はどうして作り方が違うのですか? (be 動詞があると be 動詞が先頭に来て,ないと do や does が先頭にくる) ]
[ 2. 上記の do はどうしてこのように使うようになったのですか?(do はどこからやってきたのですか?) ]
この2つの素朴な疑問については,来月8月14日に発売予定の大修館『英語教育』9月号に,ズバリこの話題で記事を寄稿していますので,ご期待ください(連載については「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」を参照).hellog 記事としては,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#491. Stuart 朝に衰退した肯定平叙文における迂言的 do」 ([2010-08-31-1]) をご覧ください.
[ 3. アルファベットの Y は何故ワイと読むのですか? ]
いくつか説があるようですが,とりあえず「#1830. Y の名称」 ([2014-05-01-1]) を参照ください.
[ 4. 不規則動詞はどうして不規則のままで今使われているのですか? ]
[ 5. どうして動詞には規則変化動詞と不規則変化動詞があるのですか? ]
この2つの素朴な疑問については,「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]) の記事で紹介したリンク先の記事や,『英語教育』の雑誌記事(拙著)をご参照ください.
[ 6. 同じような意味で複数の単語があるのはどうしてですか?(require と need とか) ]
英語語彙には「階層」があります.典型的に3層構造をなしますが,これについては「#2977. 連載第6回「なぜ英語語彙に3層構造があるのか? --- ルネサンス期のラテン語かぶれとインク壺語論争」」 ([2017-06-21-1]) を始めとして,そこにリンクを張っている記事をご参照ください.require はフランス語からの借用語,need は本来の英単語となります.
[ 7. 動詞と前置詞の組み合わせで表す表現はどうして使われ始めたのですか? 動詞1語で使う単語と2語以上に組み合わせた単語はどちらが先に出てきたのですか? ]
いわゆる「句動詞」 (phrasal_verb) の存在についての質問かと思います.「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) で紹介したように,中英語期にフランス語の句動詞を翻訳借用 (loan_translation) したということもありますが,「#3606. 講座「北欧ヴァイキングと英語」」 ([2019-03-12-1]) の 14. 句動詞への影響 でみたように,ヴァイキングの母語(古ノルド語)の影響によるところも大きいと考えられます.もっと調べる必要がありそうです.
[ 8. 第3文型と第4文型は薑き換えが可能ですが,どうして2つのパターンが生じたのですか? ]
これは本ブログでも取り上げたことのない問いです.難しい(とても良い)問いですね・・・.今後,考えていきたいと思います.
ということで,不十分ながらも回答してみました.素朴な疑問,改めてありがとうございました.
2016-03-12 Sat
■ #2511. 動詞の目的語として不定詞を取るか,動名詞を取るか (1) [gerund][infinitive][verb][phrasal_verb]
現代英語では,他動詞の目的語として取りうる準動詞の選択肢として,不定詞と動名詞がある.しかし,他動詞によっては,どちらかしか受け付けないものもあれば,両方受け付けるもの,また両方受け付けるが意味が相互に異なるものなど,まちまちである.この問題について3月3日付けで掲示板に質問が寄せられた.現代英語学では動詞の補文の型の問題や文型の問題として様々に研究されているようだが,歴史的にはどうなのだろうか.あまり関連する論文などを読んだことがないので,正直なところ状況があまり分からない.当面,以下のような回答しかできなかった.
動詞の目的語として不定詞をとるか動名詞をとるかという問題ですね.現代英語では,不定詞は未来志向で動名詞は過去志向と言われることがありますが,必ずしもきれいには説明できないようです.歴史的にも説明はたやすくなく,研究すべき重要な問題だと思います.中英語でもすでに,個々の動詞によっていずれを目的語にとるかの傾向があり,全体としては不定詞のほうが多かったようですが,詳しくは未調査です.歴史的には,目的語のタイプについて相互乗り入れしたり,一方から他方へ乗り換えたりという過程を経た動詞もあったのではないかと思われますし,現在もそのような変化の最中というケースがあるかもしれません.統語的な観点から動詞を分類し,その分類の上に立って歴史的変遷を追っていく必要がありそうです.ご質問に明確な答えを出すことができませんが,おいおい調べたいと思います.
この問題について調べてゆく手始めとして,現代英語の状況をまとめておきたい.まずは,Quirk et al. (§16.38--40) を参照して,目的語として不定詞を取ることのできる動詞を,意味範疇ごとに区分しながら一覧する.頭に * 記号の付されている動詞は,動名詞を取ることもできるものである.また,各行でセミコロンの後にある動詞は,名詞目的語を取る場合に前置詞を要するものである.
[ 不定詞を取る動詞 ]
(i) *dread, *hate, *like, *loathe, *love, *prefer; long [for], ache [for], aim [for], aspire [to], burn [for], burst [for], (not) care [for], clamour [for], itch [for], yearn [for]
(ii) *begin, *cease, *commence, *continue, *start;
(iii) *forget, *remember, *regret; *bother [about], condescend [to], *delight [in], *hesitate [about]
(iv) *choose, hope, *intend, *mean, *need, *plan, *propose, *want, wish;
(v) deign, *disdain, *help, *scorn, *venture
(vi) ask, beg, decline, demand, offer, promise, refuse, swear, undertake, vow; agree [to/on/about], consent [to]
(vii) affect, claim, *profess; pretend [to]
(viii) *afford, *attempt, contrive, endeavour, fail, learn, manage, neglect, omit, *try; strive [for], seek [for]
(ix) *arrange [for], *decide [on], *resolve [on], *prepare [for], *serve [for]
次に,動名詞を取る動詞を一覧する.頭に * 記号の付されている動詞は,不定詞を取ることもできるものである.(vi) は前置詞を伴う動詞,(v) は句動詞,(vi) は前置詞を伴う句動詞である.
[ 動名詞を取る動詞 」
(i) (can't) bear, begrudge, detest, dislike, *dread, *enjoy, (not) fancy, *hate, *like, *loathe, *love, (not) mind, miss, *regret, relish, resent, (can't) stand
(ii) *cease, *commence, *continue, quit, resume, *start, stop
(iii) admit, avoid, confess, consider, deny, deserve, discourage, envisage, escape, *forget, (can't) help, imagine, involve, justify, *need, permit, *propose, recall, recommend, *remember, repent, require, risk, save, *try, *want
(iv) bank on, count on, decide on, delight in, play at, resort to, see about, shrink from
(v) break off, give up, leave off, put off, take up
(vi) do away with, get around to, go in for, look forward to
今回は列挙のみに終わったが,明日は不定詞と動名詞のいずれも取り得る動詞について,その意味的な差違について触れたい.
・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.
2015-11-18 Wed
■ #2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論 [french][loan_translation][borrowing][contact][phraseology][ormulum][old_norse][phrasal_verb]
「#2351. フランス語からの句動詞の借用」 ([2015-10-04-1]) と昨日の記事「#2395. フランス語からの句の借用」 ([2015-11-17-1]) で話題にしたように,英語は中英語期にフランス語の単語のみならず句や表現を借用してきたと主張されてきた.一方,この主張に対して慎重な立場を取る論者もいる.その1人が Sypherd である.Sypherd はフランス語法借用説を主張する Sykes による論文 French Elements in Middle English (1899) を厳しく批判し,慎重論を展開した.
Sypherd の論の進め方は明解である.Sykes がフランス語の影響があると指摘している英語の句や表現の多くが,Sykes の取り上げている諸文献よりも早い時期に書かれた Ormulum に現われていることを,実証的に示したのである.Ormulum は,East Midland 方言で1200年頃に書かれたとされる長大な宗教詩で,方言的にも時代的にもフランス語の影響が少ないとされるテキストである.このテキストは,むしろ古ノルド語の言語的影響を強く示すものとして知られている.そこで,Sypherd (6--7) は,Sykes のいう「フランス語法」とは,むしろ古ノルド語法とすら考えられるのではないかと,逆手を取る.
Now, if in the Ormulum, a poem free from French influence, these phrases which Mr. Sykes ascribes to the Old French occur with considerable frequency, we are surely justified in denying the overwhelming French phrasal influence on Middle English. Furthermore, the justification of this denial is strengthened when we find that in Old-Norse literature anterior to or contemporary with Orm there exist in comparative abundance many of the identical phrases found in the Ormulum and in other Middle-English literature. And finally, though I do not urge it, the probability of considerable Old-Norse phrasal influence on Orm demands consideration, especially if we bear in mind the following facts: (1) the marked Old-Norse influence in general on Orm; (2) the Old-Norse literature in which these phrases occur in homiletic, sermonic; (3) much of the literature antedates the Ormulum.
もちろん,Sypherd はこの後論文のなかで,古ノルド語の文献から問題の英語の語法におよそ対応する表現を取り出して,提示してゆく.対象となったのは "bear witness", "take baptism", "take flesh, humanity", "take death", "take example", "take heed, take keep, take ȝeme", "take end", "take wife", "take rest", "take cross" に相当する句動詞であり,種類は必ずしも多くないが,議論と例示は全体として盤石で説得力がある.
昨日の記事の末尾でも述べたように,句の借用を実証することは案外難しい.Sypherd も,論文の読後感としては,フランス語からの借用とする説そのものを鋭く批判しているように聞こえるが,おそらく主張したいのは,そのような説には慎重に向き合うべきであり,別の可能性も考慮すべきである,ということだろう.
・ Sypherd, W. Owen. "Old French Influence on Middle English Phraseology." Modern Philology 5 (1907): 85--96.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow