2025-11-04 Tue
■ #6035. 英語史年表を作るのは難しい --- 「いのほたなぜ」の「超ざっくり英語史年表」制作裏話 [inohota][inohotanaze][inoueippei][timeline][historiography][notice][youtube][periodisation]
11月2日(日),井上逸兵さんと共著で上梓した『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を記念し,ホームグラウンドである YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて本書を紹介する回を配信しました.「#384. いのほた本は,世に問いたい言語学のひとつのかたち --- 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」です(16分半ほどの動画).ぜひご覧ください.
本書は,2人が3年半にわたり YouTube 上で対談してきた内容が凝縮されており,お陰様で発売早々から大きな反響をいただいています.本書の特設HPも開設していますので,こちらよりぜひご訪問ください.また,SNS などで,ハッシュタグ #いのほたなぜ を添えて,本書に関するご意見やご感想などをお寄せいただけますと幸いです.
さて,「いのほた」の最新回では,本書の構成について言及しつつ,私が担当した「超ざっくり英語史年表」 (pp. 6--9) の制作舞台裏を披露しました.これまでも英語史の略年表は様々な形で作ってきましたが,年表制作という作業には常に悩みがつきまといます.単なる年号の羅列以上の,厄介な問題を含んでいるのです.この点について掘り下げてみます.
年表を作るにあたり,まず歴史的な出来事には「線」を引きやすいものと,そうでないものとがあります.政治史や軍事史における事件,例えば1066年のノルマン征服 (norman_conquest) のようなものは,年号(そして日付まで)が明確に記録されており,年表に掲載する際に悩みはありません.「1066年,ノルマン征服」とズバッと書き込めばよいだけです.
ところが,言語変化を多く扱う英語史年表では,そうは単純にいかないことが多いのです.例として,英語史の最たる音変化の1つ,大母音推移 (gvs) を考えてみましょう.一般にこの変化は1400年頃から1700年頃にかけて,じっくり,ゆっくり起こったと説明されることが多いです.ここでの問題は,この変化の始まりと終わりが,特定の何年とは決められないことです.実際は1400年の元旦に始まったわけでも,1700年の大晦日に終わったわけでもありません.年表という2次元のレイアウトの制約の中で,どこに始まりと終わりを置くのか,あるいはどれくらいの時間幅で矢印を引くかというのは,その都度,苦渋の選択を迫られる作業となります.レイアウト上は,書き込む文字やイラストとの兼ね合いもあり,さらに問題は複雑化します.
年表制作における恣意性のもっと顕著な例として,英語史の開始年をどこに置くかという大きな問題があります.この問題の根深さは,hellog の periodisation のタグのついた各記事で見てきたとおりですが,年表に反映させるとなると,明示的に年号を示すことが要求されているようで,プレッシャーが大きいのです.伝統的に英語史の始まりは449年とされてきました.これは,アングロサクソン人と呼ばれる西ゲルマン人の一派が,ブリテン島へ本格的に来襲した年とされているからです.これをもって,アングロサクソン王国の始まり,ひいてはイギリスの始まり,そして英語の始まりと了解されてきたわけです.
しかし,言語プロパーの歴史を論じる立場からすると,この449年開始説はきわめて眉唾ものです.なぜならば,アングロサクソン人がまだ大陸にいたとされる448年と,ブリテン島に上陸したとされる449年とで,彼らの話していた言語自体は何ら変わっていないはずだからです.
言語は,社会的な事件によって急にその姿を変えるものではなく,あくまでゆっくりと変容していく連続体として存在しています.極論をいえば,英語の歴史は,印欧祖語まで(少なくともある程度は)地続きで繋がっていると理解できますし,さらに突き詰めれば,人類の言語の始まりにも繋がっている可能性があります.つまり,「○○語史の始まり」という区切りは,純粋な言語学的な考慮ではなく,その言語を話す集団の社会的な歴史,すなわち国史や政治史とシェアさせてもらう形で,便宜的に設定されているにすぎないのです.
ただ,とりわけ入門的な書籍に掲載する年表で「449年」などと明記しないと,「では,英語史はいつ始まったのですか?」という素朴な疑問にサラッと答えられなくなるため,伝統的な区切りをひとまず採用しているにすぎない,ということなのです.年表に書かれている年号は,学習の便宜という実用的な要請に応えるための妥協の産物といってよいものです.文章であれば「~年頃」などといった表現で逃げることができるのですが,年表という形式では,どうしても数直線の上にピンポイントで明示的に配置するといったデジタルな感覚が強く,それゆえに悩ましいのです.言語の歴史は,革命のような劇的な断絶ではなく,ゆっくりと変化していくファジーな世界です.そのことを理解した上で,本書の「超ざっくり英語史年表」に目を通していただけると,より深く英語史というものに思いを馳せることができるかと思います.
新刊書「いのほたなぜ」に関する話題は,引き続き「いのほた言語学チャンネル」や hellog その他の媒体で繰り広げていくつもりです.関連情報はすべて特設HPにまとまっていますので,日々そちらをご覧ください.よろしくお願い致します.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2023-10-06 Fri
■ #5275. 19世紀のイングランド英語という時代区分とさらなる下位区分 [periodisation][lmode][prescriptivism][prescriptive_grammar][sociolinguistics][timeline][history]
昨日の記事「#5274. 19世紀のイングランド英語を研究する意義」 ([2023-10-05-1]) で取り上げた,英語史の大家 Görlach による19世紀イングランド英語の入門書の冒頭には,19世紀という英語史上の区切りには,特に社会的・言語的な根拠があるわけではないと述べられている.別の論者 (DeKeyser) によれば,規範主義の1つのピークである1795年の Murray による文法書と,もう1つのピークである1906年の Fowler による King's English に挟まれた時代として理屈づけられてはいるようだが牽強付会の気味はある (Görlach 5) .
とはいえ,Görlach 自身も,19世紀のイングランド英語を研究する際に念頭においておくべき下位区分を提示しているし,関連する社会文化的な出来事も指摘している.下位区分として「長い19世紀」を4期に分けている (6) .
1776--1800 William Pitt's coalitions; the beginnings of the Industrial Revolution; the separation of the United States; the colonization of Australia and occupation of Ceylon and Malta; the start of the Romantic Movement; th end of Irish independence; 1800--1830 The final phase of the Hanoverian reign, predating the great reforms; Napoleonic wars and the Regency; Romantic poetry; 1830--1870 The great reforms; the Chartist movements; the heyday of capitalist industrialism; the expansion of literacy and printed matter; increased mobility as a consequence of railways; 1870--1914 Late Victorian imperialism and the last phase of global 'stability'; general education; modern communication.
上記の下位区分とは別に,19世紀中に起こった,社会言語学的な含意のある出来事も略年表の形で示されている (6) .こちらも参考までに挙げておこう.
1824 the repeal of the Combination Acts; 1828 the emancipation of the Nonconformists; 1832 the First Reform Bill, which can be seen as a triumph of the middle class; 1833 the first important Factory Act restricting child work; 1834 the abolition of slavery; 1834 the Poor Law Amendment Act; 1838--48 the Chartist movement; publication of the People's Charter; 1846 the repeal of the Corn Laws; 1855 the final repeal of the Stamp Act of 1712 (making cheap newspapers available); 1867 the Second Reform Bill (1 million new voters) and Factory Acts; 1870 the Elementary Education Act (establishing compulsory education in the 1870s); 1884--5 the Third Reform Bill (2 million new voters)
このように略年表を眺めると19世紀イングランドは自由化の世紀だということが改めてよく分かる.この時代は,英語という言語が世界的に拡大していく時期であるとともに,イングランド内でも大衆化が進展していった時期ととらえてよいだろう.
・ Görlach, Manfred. English in Nineteenth-Century England: An Introduction. Cambridge: CUP, 1999.
2023-08-27 Sun
■ #5235. 片見彰夫先生と15世紀の英文法について対談しました [voicy][heldio][review][corpus][lme][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][caxton][malory][negative][impersonal_verb][preposition][periodisation]
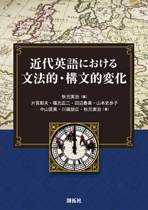
6月に開拓社より出版された『近代英語における文法的・構文的変化』について,すでに何度かご紹介してきました.6名の研究者の各々が,15--20世紀の各世紀の英文法およびその変化について執筆するというユニークな構成の本です.
本書の第1章「15世紀の文法的・構文的変化」の執筆を担当された片見彰夫先生(青山学院大学)と,Voicy heldio での対談が実現しました.えっ,15世紀というのは伝統的な英語史の時代区分では中英語期の最後の世紀に当たるのでは,と思った方は鋭いです.確かにその通りなのですが,対談を聴いていただければ,15世紀を近代英語の枠組みで捉えることが必ずしも無理なことではないと分かるはずです.まずは「#817. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 片見彰夫先生との対談」をお聴きください(40分超の音声配信です).
私自身も,片見先生と対談するまでは,15世紀の英語はあくまで Chaucer に代表される14世紀の英語の続きにすぎないという程度の認識でいたところがあったのですが,思い違いだったようです.近代英語期への入り口として,英語史上,ユニークで重要な時期であることが分かってきました.皆さんも15世紀の英語に関心を寄せてみませんか.最初に手に取るべきは,対談の最後にもあったように,Thomas Malory による Le Morte Darthur 『アーサー王の死』ですね(Arthur 王伝説の集大成).
時代区分の話題については,本ブログでも periodisation のタグのついた多くの記事で取り上げていますので,ぜひお読み下さい.
さて,今回ご案内した『近代英語における文法的・構文的変化』については,これまで YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」,hellog, heldio などの各メディアで紹介してきました.以下よりご参照ください.
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ hellog 「#5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました」 ([2023-07-09-1])
・ hellog 「#5208. 田辺春美先生と17世紀の英文法について対談しました」 ([2023-07-31-1])
・ hellog 「#5224. 中山匡美先生と19世紀の英文法について対談しました」 ([2023-08-16-1])
・ heldio 「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」
・ heldio 「#772. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 16世紀の英語をめぐる福元広二先生との対談」
・ heldio 「#790. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 田辺春美先生との対談」
・ heldio 「#806. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 中山匡美先生との対談」
・ heldio 「#817. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 片見彰夫先生との対談」
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-07-09 Sun
■ #5186. Voicy heldio に秋元実治先生が登場 --- 新刊『近代英語における文法的・構文的変化』についてお話しをうかがいました [voicy][heldio][review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation]
6月に開拓社より近代英語期の文法変化に焦点を当てた書籍が出版されました.『近代英語における文法的・構文的変化』です.秋元実治先生(青山学院大学名誉教授)が編者を務められ,他に6名の研究者が執筆に加わっています.本書については,すでにこのブログや YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で紹介する機会がありました.
・ hellog 「#5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年)」 ([2023-06-19-1])
・ hellog 「#5167. なぜ18世紀に規範文法が流行ったのですか?」 ([2023-06-20-1])
・ hellog 「#5182. 大補文推移の反対?」 ([2023-07-05-1])
・ YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」より「#137. 辞書も規範文法も18世紀の産業革命富豪が背景に---故山本史歩子さん(英語・英語史研究者)に捧ぐ---」
このたび,本書をめぐって編者の秋元実治先生とじきじきに対談する機会に恵まれました.対談の様子は,今朝の Voicy チャンネル「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#769. 『近代英語における文法的・構文的変化』 --- 秋元実治先生との対談」として配信しています.対談本体は27分ほどとなっています.お時間のあるときにゆっくりお聴きいただければ.
エンディングチャプター(第5チャプター)では,秋元先生から対談収録後にうかがった,本書の表紙下部のビッグベンの写真についての貴重な裏話を紹介しています.
皆さん,ぜひ近代英語の文法変化について関心を寄せていただければ!
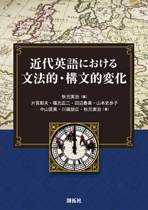
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
2023-06-19 Mon
■ #5166. 秋元実治(編)『近代英語における文法的・構文的変化』(開拓社,2023年) [review][mode][corpus][syntax][phrasal_verb][subjunctive][complementation][periodisation][youtube]
近代英語の文法変化についてコーパスを用いて実証的に研究した論考集が開拓社より出版されました.英語史分野の一線で活躍されている著者7名(片見彰夫氏,福元広二氏,田辺春美氏,山本史歩子氏,中山匡美氏,川端朋広氏,秋元実治氏)による書籍です.著者の方々よりご献本いただきました由,ここに感謝致します.
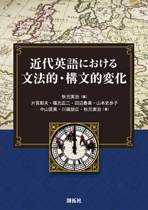
この本の最大の特徴は,各章が15--20世紀の各世紀を考察範囲としていることです.注目する話題は半ば固定されており,その点で定点観測となっているのですが,全体として整理された通時的な統語論の研究となっています.「はしがき」の冒頭に次のようにあります (v) .
本書は近代英語(1500--Present)における文法的・構文的変化についてコーパス等の使用による実証的研究である.
これまで英語史の記述において世紀別に述べることはあまりなかったように思われる.ひとつにはほとんどの言語変化は世紀を横断するため,各世紀の記述が難しいことがある.しかしながら,文学史などでは世紀別はきわめて普通であり(例えば,Oxford History of English Literature 12 volumes),このこともあってか英語史においても最近 Kytö et al. (2006), Mair (2006) などが出版され,それぞれ19世紀,20世紀の英語における変化・特徴に焦点をあてている.
本書では近代英語における上記のような変化の連続性と各世紀の特徴を捉えるために,以下の点を執筆者の間で共有した.
1. 全ての執筆者は共通項目,句動詞,仮定法,補文について述べる.
2. それ以外の項目で,その世紀の特徴と考えられる文法的・構文的変化について述べる.
3. 電子コーパス,テキスト等を使って,実証的に記述する.
英語史の時代区分 (periodisation) については,最近では「#5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り」 ([2023-05-24-1]) で取り上げるなどし,私自身も長らく考えてきました.「古英語」や「近代英語」などとラベルを貼るのではなく,きっぱりと世紀単位で切る,あるいは言及するというのは確かに一般的ではありませんでしたが,Curzan (33) が述べるように,ラベルを避けたい立場の論者は世紀単位を好むようです.一見すると無機質な時代区分のようでいて,むしろ読み手に世紀をまたいだ言語の連続性と断絶性を意識させるという効果があるのではないでしょうか.
本書ではコーパスを用いた具体的で実証的な研究が紹介されており,この分野を研究する学生や研究者には,手法も含めて直接参考になります.また,文法変化・構文変化といっても扱うべき話題は多岐にわたるものですが,各章では各世紀の英語を考察する上でとりわけ重要な項目が選ばれており,たいへん有用です.
最終章は全体のまとめとなっており,いったん各章のために世紀別に分けられたものが建て直され,読み手の視界がすっきりします.参考文献も充実しており,中英語末期から現代に至るまでの文法変化に関心のある方には,ぜひ手に取ってもらいたい一冊です.私も学生に薦めたいと思います.
著者の一人,山本史歩子さん(青山学院大学)におかれましては,本書の出版を見る前にご逝去されたとの報に接しました.悲しみでいっぱいです.ご冥福をお祈りいたします.
・ 秋元 実治(編),片見 彰夫・福元 広二・田辺 春美・山本 史歩子・中山 匡美・川端 朋広・秋元 実治(著) 『近代英語における文法的・構文的変化』 開拓社,2023年.
・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.
2023-05-24 Wed
■ #5140. 「英語史の時代区分」月間の振り返り [periodisation][hel_contents_50_2023][khelf][hel_education][voicy][heldio]
khelf(慶應英語史フォーラム)では「英語史コンテンツ50」を開催中です.休日を除く毎日,khelf メンバーによる英語史コンテンツが1つずつウェブ公開されてきています.4月13日に開始し,後半戦に入ってきました.
この企画のなかで4月17日には khelf 会長の青木輝さんによるコンテンツ「#4. 「時代区分」を考える」が公開されました.英語史の時代区分に関する Curzan の論文をベースに据えつつ,異なる研究者(書)からの時代区分の事例を比較し,そもそも時代区分とは何かを問うたコンテンツでした.
英語史の時代区分の問題は,このブログでも periodisation の記事群で長きにわたって本格的に議論してきました.しかし,今回このコンテンツ公開を受け,さらに本格的に議論したいと思うに至り,khelf メンバーを含む学生たちや Voicy heldio リスナーの方々を巻き込む形で1ヶ月を過ごしてきました.
まず大学院の授業で Curzan 論文を徹底的に読み込みました.その上で,数時間をかけて,大学院生とともに英語史の時代区分について激論を交わしました.後日,この激論の様子をなるべく多くの方々に伝えたいと,Voicy heldio で収録し公開しました.「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)です.
リスナーの皆さんにも時代区分問題のおもしろさを共有いただき,コメントも寄せていただきました(ありがとうございます).
さらに後日,学部の「英語史」の授業にて,先の対談回を含めた以下の3つの heldio 放送回を,数十名の受講生に聴取してもらいました.
・ 「#618. 英語史の時代区分」(2023/02/08放送)
・ 「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」(2023/04/08放送)
・ 「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」(2023/05/11放送)
受講生には多くのリアクションを寄せてもらいました.以下,長くなるので折りたたんでおきます.
「英語史」受講生からのリアクション
ことばの歴史の区分は曖昧で,そもそも言葉というもの自体が使用の経過で徐々に変化するものなので,きっぱりここという風に定めるのは難しいが,研究をする上である程度の線引きが必要なので,決めている.〔中略〕これらの時代区分については,研究者によって相違があるという放送回は面白かった.研究者的には厳密に端数まで切り詰めて出したいという気持ちと,一般論として,普通の人にもわかりやすく理解を促すためには,端数を切り捨てて,きっぱりした数字で表示したいという気持ちもあるという葛藤があることが皆さんの討論から強く伝わってきた.特に現代英語 ModE を,さらに最近の数十年の英語を「グローバルイングリッシュ」と区切りたいという話はとても賛同できる発想だった.確かに明らかにスラングが増えたり,明らかに世界的な規模で英語の需要が高まったという意味では言語が基盤から変化したという主張(時代区分を区切る)は正しいと思う.
英語史の時代区分は明確なものが決まっていないので,専門家の方や詳しい方の中でも区分の仕方がそれぞれであった.実際にラジオの中でも堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さん,藤原さんそれぞれの時代区分は同じところもあれば違うところもあり,おもしろかった.堀田先生が微妙にこだわっている部分などもあり,時代区分は十人十色なのだと改めて感じた.また,時と場合に合わせて区分の仕方を変えているという話もあり,そんなにも柔軟に変えられるものであるのだと驚いた.
英語史の前史と言える部分をまずは学びました.紀元前4000年以前が原インド・ヨーロッパ語,紀元前4000年から紀元前500年が原ゲルマン語.紀元前500年から448年が原古英語.その後,英語史は449年〜1100年の古英語時代で幕開けし,1100年〜1500年の中英語が続きます.そして1500年〜1900年が近代英語,1900年〜現在までが現代英語だそうです.しかし,これはあくまで英語史の標準的,教科書的な分け方です.heldioでは,言語外的な動きもこうした言語史の時代区分に大きな影響を与えていることを学びました.449年にブリテン島へ西ゲルマンの一派の連中が渡ってきた,軍事史上重要な出来事は正にその格好の例だと思います.その連中にはアングル人,サクソン人,ジュート人などが含まれます.ただ,そうした動きがどのように時代区分に影響を与えるかは,各学者の考え方によって様々というのが興味深かったです.和田先生,khelfの青木さん,寺澤さん,藤原さんとの対談の中でそれが浮き彫りになっていたと思います.そもそも言語とは gradual に変化するものであるため,時代区分とは曖昧なもの,そもそもはっきりとは区分出来ないものという考えにみなさん,立っていました.その中でもしかし,便宜上区分が必要となった場合には,境目を「〜年頃」とするか「〜年」と刻むかで各々の学者の意図が見えて来る様です.「〜年頃」は『頃』というぼかしワードを使いつつも,実際はその境目が曖昧な実態を『正確』に表しているという,この矛盾点も面白かったです.一方で「〜年」と刻む場合,実際には言語変化が徐々に起こっているため明確な境目はない事を承知の上で,変化に一定以上の影響を与えたと思われる言語外的な動きに対し,より『象徴的』な役割を与えようとしていているとの分析がなされていました.
英語史の時代区分について,今回の授業とラジオの内容を踏まえて,英語史の時代区分は区切りのつけ方によって変わってくるのだとわかりました.院生や先生方一人一人とっても区分の主張が異なる所も興味深かったです.個人的には,Voicy に出演されていた青木さんのように,年をぼかすというよりは象徴的な出来事が起きた年を境目にして正確性を持たせる方がしっくりくるなと思いました.(何事も具体的な数値で出して欲しいという個人的なこだわりが強いのかもしれませんが…)
今日は今まで曖昧だった時代区分が解決しました.ただ,ひとつ疑問に思ったのは,高校生の時の世界史の教員は,ヨーロッパにおける中世世界は395年の西ローマ帝国の滅亡から,1453年の英仏百年戦争までと習ったのですが,この中世世界と Old English の年代が丸かぶりしていて,(Middle English)中世英語が大半が被っていると言う状況であり,不思議に思いました.近代史のスタートは薔薇戦争の終焉ということで,この点では,世界史の教員と同じ分かれ目でした.ラジオの中に対する意見としては,私は和田先生の意見に賛成で,言語はある都市を境目にキッパリと変わるわけではなく,年月をかけて徐々に変化していくので,「頃」と濁さざるをえないかなと思います.それから,僕の感覚としては何か出来事が起こった,だから,言葉もその変化に追随して(幾分かのタイムラグはあるとは思うが)変化していくという方式だと思うのですが,教授の場合は結構「00」で区切るところが多いと思うのですが,「00」が英語の時代区分に境目に登場しやすくなる理由が知りたいと思いました.特に,1900年だと私の知る限りイギリスにとっての特別な事件は特にないように思えます.むしろ,第一次世界大戦が行われた1914〜1918年が外国との交流や敵対関係,新語の登場などが多いように思える年な気がします.
今まで学校で習ってきた日本史や世界史の時代区分は年号で明確に区分されていたのに対して,英語の時代区分は研究者によって異なるという点が新鮮で興味深かったです.堀田先生のあえて分かりやすい年号で区切ることも,和田先生の〜年ごろ,と年号をぼかすことも,青木さんのどの時代区分も英語史上重要なできごと(ウィリアム・キャクストンの印刷術など)に合わせて時代区分をすることも,いずれもその方自身の英語史の捉え方や英語自体への価値観が表れており,もっとお話を拝聴したくなりました.英語の時代区分は研究する中での利便性のためのもの,でありながらも,こうも研究者の間で意見が分かれるところを見ると,大体何年ごろ,と区分を曖昧にする方が無難かとも思ったのですが,やはり英語の変化のきっかけとなった出来事で年号をはっきりと区分することも英語史の理解に役立つとも思えるので,英語の時代区分という問題は非常に難しく,興味深いと思いました.英文学史でたびたび英語の時代区分に基づいてその時代ごとの写本などが紹介されるのですが,時代区分自体人為的に決められているもの,とこれからは意識した上で学んでいきたいと思います.
確かに,言葉は社会や時代の変化に伴って微妙に少しずつ,そしてなによりも流動的に変化していくものなので,ある年代ではっきりと区分すること自体が本来はできないのだと言う考えは納得できた.その上で,研究する際や,一般人へ向けて解説する際に,便宜上区切りがついていた方が共通認識が作りやすいという点で,敢えてはっきりとしたラベリングをするというのも理解できる.しかし,区分する側の歴史解釈や信念(こだわり)によって,どこでどう区分するのかというのが微妙に(時には大きく)異なるというのはとても興味深いと思った.
私はまだ英語史を学び始めたばかりなので細かいことはわからないものの,個人的には #710 で青木さんが言っていた「使い分ける」という視点が大事になると感じた.初学者や,一般の人に向けて解説する際に具体的な年号(例えば449年や1066年,1795年など)を使うのは,わかりづらいだけでなく,その年を境にいきなり言語が大きく変わったなどという誤った印象を与えかねない.象徴としての具体的な年号を基準に分けるのももちろんいいが,あくまで言語の変化は少しずつ進むものだという大前提を頭に入れるためには,ざっくりとした区分を最初に覚えるのがいいと思った.その上で,実際にはさまざまな考え方・捉え方があることを学ぶと,より理解が深まるのではないかと感じた.
英語史の時代区分については,端数と概数の両方を使い分けるのが適切だと考える.「英語史」とは第1回授業で述べられたように英語「と」歴史を扱う学問である.英語史において,両者のうちの英語の面に着目する場合には端数を,歴史の面に着目する場合には概数を使うのがよいのではないか.〔中略〕次に歴史を学習する際は,概数で全体的な役割を担うことが学習を円滑に進めるうえで不可欠だ.Voicy中にもあったように概数は学習事項の目次のような役割を果たし,学問において今何を学んでいてこの先何を学ぶのかが常に明らかにしてくれるろう.また概数が逆に「正確性を期している」という堀田先生の考えには新しい気づきがあった.概数は未知のものに対して「年頃」といった表現で真理を曖昧にしているともいえる一方で,「未知である」といったメッセージを伝える役割も果たしておりその点では正確性を期していると私も考えた.
歴史には分ける区分はあるけど,決してその分けるは共通ではなく,それに数字があるわけでもなく,人によって一区分の長さも軸も違うことに驚きました.また,先生と対談先の方が全く違う脳みそで似たような区分をするあたり,歴史を感じてすごいなと思いました.でも,凄く似てるように見えて微妙なこだわりもあるというのが面白いなと思いました.また,洗脳されているとされる教科書も元はといえば誰かの脳内なのに,みんながそれにとらわれてるのが面白いなあと思います.教えてる側の方,つまり先生って研究し倒してるかたなので,聞いたことは正しいと思って聞いているけれど,先生どうしの話を聞くと認識の違いの存在や先生も1人の人間であることを感じて,その絶対的力という信頼が生徒だったら先生,人だったら教科書のようにあるのが面白いと思います.(別に間違ってると言いたいのではなく)
時代区分を定めたうえで信じすぎないという考え方が,斬新だが言われてみればそうだと思った.時代の境界がはっきり定まっておらず,ましてや言語は次第に変化していくものなので,時代区分は恣意的な象徴的なものなのだと思った.「700年に文字資料が登場するため700年を英語の始まりとする」という考え方は私は納得できなかった.地域や階級によっても使用する英語は異なっていたと思うので,端数まで時代区分をはっきり考えておき,その周辺の境界を曖昧にするのが一番納得いくかなと思った.でも,1476年の活版印刷術導入のように,言語に影響を与えるような象徴的な出来事を境界とするという考え方も一理あると思ったが,ただ,事件が起きたと同時に急速に言語が変化するわけではないので,きっちりした境界を定めることはできないと思う.
今回は英語史の時代区分について学びました.紀元前4000年以前の Indo-European (IE) や紀元前4000年から紀元前500年までの Germanic (Gmc) である英語前史の言語はどのようであったのかとても気になりました.また,Old English (OE) の始まりを「449年,ゲルマン人のブリテン島移動とする説」と「英語での文献が出された700年とする説」があることがとても興味深かったです.どちらも象徴的だと感じますが,やはりはっきりと「Old English」の始まりを区分することは難しいのではないかと感じました.講義では堀田先生の時代区分の考え方として,1100年から1500年までを Middle English (ME),1500年から1900年までを Modern English (ModE),1900年から現在までを Present-Day English (PDE) としてざっくり区切ることを学びました.私もやはりそのように区切る方が良いのではないかと考えます.ラジオで細かい英語史の時代区分の区切りをなさっていた大学院生の方々の意見はとても筋が通っていて,納得のできるものでした.でも,言語はその年,その瞬間から切り替わるものではないし,むしろグラデーションのようなものだと私は考えます.時代区分はある程度の目安として,時にはそれぞれの時代の特徴が混ざっていることも念頭に置いた上で,英語について考えていく必要があると感じました.これは私の「こだわり」かもしれません.
英語史の始まりをイギリスの国づくりの基礎が始まった年としていることは衝撃を受けた.さらに,英語史の始まりの年である449年より前の英語の基礎を英語としてはみなしていないということは意外だった.また,Old English と記述すればそれは英語史における古英語を指すというルールが,中英語を記述する際のルールにも当てはめられていることは意外だった.また,それ以降の英語史区分を,400年ごとに区切っているというキリの良さは,英語史のはじめを449年としていることとは,対照的だと感じた.また,和田教授との対談の中で,英語史学習において,英語史の区分は,その入り口であり目次的な存在であるにもかかわらず,研究者同士で異なり,議論が交わされるものと知り,奥の深さを感じた.また,区分年を明確にいうか,それともぼかすのか,そこのこだわりもなかなか面白いなとも感じた.アングロサクソンの伝説的な449年をどう捉えるかで,時代区分の始まりをどこにするかが決まるのは興味深かった.
今回の授業やラジオの内容を通して,英語の歴史とはまさにイギリスの歴史であり,切っても切り離せない関係にあるということが強く感じられました.学生さんとの激論からも分かるように,英語の年代を区分する年はそれぞれ端数的であったり,ざっくりであったりと違いはあっても,やはりそこには何かしらの歴史的事象があり,改めて歴史とは変化であるということも同時に実感しました.また,年代区分が端数であると,言語がその年にきっかりと変化したように感じられ,逆にざっくりであれば,ぼやっと,変わった部分もあればそうでない部分もあるように感じられるという議論は,どこか人の考え方の性質といったものも絡んだ議論のように感じられ,面白かったです.実際,どの言語にも言えることだと思いますが,言語の中には昔の年代からずっと変わらず残っているもの,時代を追っていくうちに変容したもの,そして,現代になってから今までとは全く違う形で追加されたものなどがあるわけで,一概に年代区分を分けるのはかなり難しいと思いました.
英語の始まりは449年とされており,そこから1100年までは古英語,1100年から1500年は中英語,1500年から1900年までは近代英語,そして現在に至るまでを現代英語と定義されている.英語史においては,このように時代ごとに英語が名前づけされて分類されているが,日本語にはこのように時代ごとに名称をつけては区別していない.この点に関して,英語と日本語では言語研究の進み具合による違いが見られると思った.細かく分類できるということはそれだけ自国語の研究が進んでいるからだと思う.また,ラジオ内で先生も言及していたように,この英語史の時代区分は,あくまでもわかりやすくするための暫定的なものであり,それぞれの時代区分内においても変化は起きているということを忘れてはならない.時代区分されてしまうと,その区分においては同じ語が使われていたというイメージを持ってしまうが,常に英語が変化していたということを踏まえた上で,様々な問題について考えていくべきだと考える.英語史の時代区分はわかりやすい一方で簡単に誤解をも招いてしまう可能性がある点に注意するべきだ.
「#618. 英語史の時代区分」,「#677. 英語史の時代区分を語る --- 和田先生との対談」「#710. 激論!時代区分 --- 青木くん,寺澤さん,藤原くんとの対談」を聴いて,英語史の時代区分は考える人でそれぞれ異なり,十人十色であるということが強く伝わってきた.英語の転換期を象徴的な出来事と重ねて,端数まで細かく区切って考えている人もいれば,言語の変化はある事件をきっかけに急に起こるものではなく徐々に時間をかけて起こるということで,具体的な年数は明言せずに,〇〇年ごろと考える人もいて,英語史の時代区分の奥の深さに驚かされた.また,時代区分の数も人それぞれ違っていて,面白いと思った.
今回の授業で堀田先生の考える英語史の時代区分について触れました.古英語が449〜1100年,中英語が1100〜1500年,近代英語が1500〜1900年,そして現代英語が1900年〜現在という区分を聞いたとき,初めは「区分ってこんなにざっくりかつシンプルできれいな数字でいいのか.」「古英語の始まりが449年というのはしっくりくるけど,他はあまりにも単純化しすぎではないか.」と素人ながら個人的には違和感を覚えていました.しかし,heldioを聞いて英語史の時代区分は人によって違うということ,またその時代区分を絶対視してはいけないということに気が付きました.和田先生は堀田先生とほとんど同じぐらいの数字で区分していましたが,それでも和田先生の方は○○年“頃”というように少し曖昧に区分していました.また青木さんは時代区分に端数を使っていて,その時代の象徴的な出来事を非常に意識していましたし,寺澤さんは端数を使うところとそうでないところがありました.堀田先生,和田先生,青木さん,寺澤さんのたった4人だけでも誰一人として同じ時代区分の人はいませんでした.本当に時代区分は十人十色なのだなと実感しました.先ほども書きましたが私は初め堀田先生の時代区分の仕方に違和感を覚えていました.449年のゲルマン民族の大移動によりブリテン島にアングロサクソン人が入ってくるという出来事を古英語の始まりとして設定するというように,中英語や近代英語などに関してもそのように象徴的な出来事と関連させて区切れば具体的で納得しやすいので端数を使った方がわかりやすいと思っていました.しかし,heldio の中で堀田先生が「あえてざっくり,シンプルな数字にすることで奇麗すぎてうさん臭さが出る.逆にそうしたほうが安易に区分を絶対視しにくくなる.端数だとその象徴的な出来事がちゃんと伝わればいいけど,そうでないとリアルすぎて信じてしまう.」とおっしゃっていました.これを聞いて自分にはなかった考え方を知ることができ,なるほどなと思いました.このように英語史の時代区分という一つのテーマだけでもいろんな人がいろんな考えをもっていました.堀田先生がいろんな人と議論しているのを聞いて,他者と議論し合うことはやはり面白いし自分にはなかった考えに出会うことができとても刺激になるのだなと思いました.私は時代区分を絶対視しやすいので時代区分は必ずしも絶対視するものではなくあくまで参照用として使うということを忘れないでおきたいです.私も英語史をもっと勉強して自分なりの時代区分というのを考え,それを他の人と話し合いってみたいと思いました.
今まで英語の歴史について英米文学専攻に進むまで考えたことがありませんでした.前回の授業で先生が時代区分にはっきりしたものはなく,大体で決めているのだということを聞いて少し驚きました.確かに考えてみると,歴史上の中世や近世などの区分もあくまで人が考えたものなので曖昧な部分があるのでそれは言語史にも通ずるのだと思いました.449年から英語史が始まるというのは,とても中途半端な時期だなと感じもっと区切りのいい時期にすればいいのにと感じたのですが,歴史的なブリテン島における国の出現を考えると納得がいきました.
「英語史の時代区分を一旦忘れてください.」と先生がおっしゃった時にはとても驚いたのですが,英語史をあくまでわかりやすく考えるための人為的なものであり,あまりに時代区分を絶対視してしまうと,それにとらわれすぎてしまい考えが固くなってしまうため,頭を柔らかくして考える必要があるという理由を聞いて,これから英語史を学ぶ上で自分も気をつけようと思いました.また,先生と和田先生の英語史の時代区分が意外と違わなかったので,研究者によって時代区分は異なるとはいえどある程度はやはり同じなのだなと感じました.
今回の授業と3つのラジオを聞かせていただいて分かった事は,「英語史の時代区分」に関しては,10人いれば10通りの解釈があると言うことです.しかも結論は同じでも,そこに至るまでのプロセスはまた人それぞれいろんな考え方をしていて非常に面白いと感じました.言葉がグラジュアルに発展する以上,正確な年号や日付を述べる事は不可能だと言う結論があるからこそ,逆に言えば自分の主観で決めてもいいと言う考え方もあります.堀田先生が言っていた,449年のアングロ・サクソン人がブリタニアに侵攻した年を古英語の年代とするなど非常に象徴的で面白いと思います.しかし一方でわからないこそ,はっきりと述べず,ぼんやりと表現すると言う考え方もあります.和田先生が450年頃と述べていたように,「〜頃」とすることで,断定できないものだからこそ,そのニュアンスをしっかりと表現すると言う考え方もとても納得できるところです.こういった1つの「英語史の時代区分」と言うことに関してからでも,研究者としてのスタンスやあるいは人としての性格のようなものが現れると言う部分は非常に面白いです.
和田先生との対談について語りについての感想を述べる.いきなり,449年と450年の区切りに関して対立が生じたのが面白かった.学者によって,考え方が異なることがあるということを改めて認識した.自分は,和田先生のように〜ごろと,アバウトにするのは大切だと思った.また,最後の「気が合いますね,カンパーイ」という言葉にとても笑いました.違いがあると言いながらも,似たものに帰着することもあるんですね!
まず,「英語史の時代区分」を聞いて,449年から英語の歴史が始まることを学んだ.そして,定義上紀元前500年から紀元後449年までは原古英語,紀元前4000年から紀元前500年までは原ゲルマン語,紀元前4000年以前は原印欧語と言われていることを知った.また,449年から1100年までは古英語 (Old English) が,1100年から1500年までは中英語 (Middle English),1500年から1900年までは近代英語 (Modern English),1900年から現在までは現代英語 (Present day English) ということも知った.次に,「和田先生との対談」を聞いて,英語史の時代区分は,人によって分け方の違う,曖昧なものであることがわかった.堀田先生は,英語史の始まりを,アングロサクソン人がブリテン島に侵入した年である449年に厳格にしていたのに対し,和田先生は450年ごろとしていた.これは,どちらかが正しくどちらかが間違っているというわけではなく,言葉はゆっくり変わるものであるため,本当は区切れないものであることを前提に考えた結果出された,考え方の違いであることを理解した.最後に,放送を聞いて私はアングロサクソン人がブリテン島に侵入した449年を古英語の始まり,ノルマン征服が起きた1066年を中英語の始まり,つまり歴史に残る象徴的な出来事が起きた年を英語史の時代区分と考えました.
このように,この1ヶ月ほどは「英語史の時代区分」月間となった次第ですが,振り返ってみると khelf 活動がフル回転してよい空気を生み出したなあと実感しています.
(1) 「英語史コンテンツ50」企画を通じて一般公開された,とあるコンテンツから議論が始まった
(2) それをもとに大学院の授業で関連論文を精読しつつ白熱した議論へと発展
(3) その議論を heldio 対談として収録し,一般リスナーの方々に向けて配信した
(4) そこでのコメントバックを受け,問題を再考した
(5) ここまでの流れを受けて,学部の「英語史」の授業で時代区分問題を紹介し,数十名の受講者に考察の上リアクションを寄せてもらった
(6) 本記事でそのリアクションを共有した
(7) 今後,さらなる議論へ
とても良い流れとなりました.関係した皆さん,ありがとうございました!
・ Curzan, Anne. "Periodization in the History of the English Language." Chapter 12 of The History of English. 1st vol. Historical Outlines from Sound to Text. Ed. Laurel J. Brinton and Alexander Bergs. Berlin: Mouton de Gruyter, 2017. 8--35.
2022-10-23 Sun
■ #4927. 言語学上の様々な区分は方法論上の区分にすぎない [methodology][saussure][linguistics][periodisation]
言語学には,方法論上の様々な区分や2項対立がある.ソシュール (Ferdinand de Saussure; 1857--1913) の導入したラング (langue) とパロール (parole) ,形式 (form) と実体 (substance) ,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) などは著名である(cf. 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])).
また,音声学 (phonetics),音韻論 (phonology),形態論 (morphology),統語論 (syntax),意味論 (semantics),語用論 (pragmatics) などの部門も,方法論上の重要な区分である(cf. 「#377. 英語史で話題となりうる分野」 ([2010-05-09-1]),「#378. 語用論は言語理論の基本構成部門か否か」 ([2010-05-10-1]),「#4865. 英語学入門の入門 --- 通信スクーリング「英語学」 Day 1」 ([2022-08-22-1])).
ほかには,個人と社会,話し手と聞き手,話し言葉と書き言葉など,対立項は挙げ始めればキリがないし,歴史言語学でいえば時代区分 (periodisation) も重要な区分である.
重要なのは,これらの区分は言語学の方法論・理論上,意図的に設けられたものにすぎないということだ.現実の言語実態はあまりに複雑なため,研究者はそのまま観察したり分析したりすることができない.そこで,便宜上小分けに区分し,区分された一画をじっくり観察・分析するという研究上の戦略を立てるわけである.そして,小分けにした各々の区画についておおよそ明らかになった暁には,それらをブロックのように組み合わせて最終的に言語というものの総体を理解したい.そのよう壮大な戦略に基づいて,あくまで作業上,様々に区分しているのだ.
この戦略的区分について,古典的英語史 A History of English を著わした Strang が序説に相当する "Synchronic variation and diachronic change" にて,次のように述べている (17) .
Language is human behaviour of immeasurable complexity. Because it is so complex we try to subdivide it for purposes of study; but every subdivision breaks down somewhere, because in practice, in actual usage, language is unified. The levels of phonology, lexis and grammar are interrelated, and so are structure and history. There remains a further dichotomy, implicit in much of our discussion, but not yet looked at in its own right. Language is both individual and social. Acquisition of language takes place in the individual, and we have stressed that he (sic) is an active, even a creative, participant in the process. Yet what he learns from is exposure to the social use of language, and although cases are rare there is reason to think that the individual does not master language if he develops through the relevant stages of infancy without such exposure. And if he does have normal experience of language as a baby the speaker's linguistic creativeness is held on a fairly tight rein by the control of social usage --- he cannot be too idiosyncratic if he is to be understood and accepted. The governing conditions come from society, though executive language acts (speaking, writing, etc.) are made by individuals. Here, too, then, we have not so much a dichotomy as an interplay of factors distinguishable for certain purposes.
なお,私は様々な言語理論も同様に戦略的区分にすぎないと考えている.言語理論Aは,ある言語現象を説明するのには力を発揮するが,すべての言語現象をきれいに説明することはできない.言語理論B,言語理論Cも然りである.後にそれぞれの得意領域を持ち寄り,言語の総体的な理解につなげたい --- それが言語学の戦略なのだろうと考えている.したがって,どの理論をとっても,それが絶対的に正しいとか,間違いということはないと思っている.
・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.
2022-07-29 Fri
■ #4841. 『言語の標準化を考える』の第7章へのコメントより [gengo_no_hyojunka][contrastive_language_history][periodisation]
この2日間の「#4839. 英語標準化の様相は1900年を境に変わった」 ([2022-07-27-1]) と「#4840. 「寺澤盾先生との対談 英語の標準化の歴史と未来を考える」in Voicy」 ([2022-07-28-1]) の記事で,『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年)の第7章「英語標準化の諸相―20世紀以降を中心に」(寺澤盾先生執筆)を紹介しました(昨日公開した寺澤先生との対談 Voicy はこちらです).
本書の最大の特徴の1つは,他の著者からのコメント(=ツッコミ)です.例えば英語史に関する章の文章に対して,異なる言語の歴史を専門とする方々が,その言語史の知見に基づいて,自由に注を入れていくという形式です.このようにすると,英語史研究者どうしの議論では決して現われてこない視点や発想が,次々と出てきます.同分野では前提とみなされてきた知見が,他分野では前提とされていない,などの気づきが得られます.まさに「対照言語史」 (contrastive_language_history) の真骨頂です.
例えば,第7章に対して寄せられたコメントの一部で,私がインスピレーションを受けたものをいくつか引用して紹介します.まず,英語史の時代区分 (periodisation) に対する,日本語史・田中牧郎氏からのコメントより.
時代の数と時期だけではなく,何に着眼して時代区分を行うかを観察して,英語史と日本語詞を対照して見ることは興味深い課題だろう.(p. 129)
同じく田中氏より,チョーサーが『カンタベリー物語』をフランス語やラテン語ではなく英語で書いたという事実に対するコメントも示唆的です.まさか『土佐日記』と比較し得るとは!
文芸作品を,自国語で書くか外国語・古典語で書くかの選択であるが,日本語では,和文で書くか漢文で書くか,という選択が問題になることがあった.著名な例として,10世紀はじめに,紀貫之が,『土佐日記』を書く際,その冒頭で「男もすなる日記といふものを女もしてみむとてするなり」と記し,通常は男性の手によって漢文で書かれる「日記」を,女性も書いてみようとするのだと行って,女性も書いてみようとするのだと言って,女性に仮託して口語体書きことばで書いたことが挙げられる.(p. 135)
ドイツ語史・高田博行氏は,18世紀の規範主義の時代を代表するジョンソン博士が言及されている箇所で次のようにコメントしています.
このあたりも,ドイツ語史と平行的である.18世紀中葉(1748年)にゴットシェートが有力な規範文法を出し,そのあとアーデルングが1770年代に辞書を,1780年代に文法書を出し,これらがオーストリアでも受け入れられることで,ドイツ語標準文章語が確立する.なお,アーデルングの辞書は,ジョンソンから強い影響を受けている.(p. 136)
同じく高田氏は,英語史における標準化のサイクルに対し,次のように反応しています.
このようなサイクルの繰り返しがドイツ語史には見当たらないところが,英独の本質的な違いのように思われる.(p. 137)
上記は,英語史を対照言語史の観点から眺める可能性に気づかせてくれたコメントのほんの一部です.ある物事の特徴は,他と比較して初めて浮き彫りになるということを改めて実感しました.ぜひ本書を手に取ってご覧ください.
2021-07-17 Sat
■ #4464. インド英語の歴史の時代区分 [indian_english][periodisation][esl][sociolinguistics][hindi]
近年,インドは国際的に存在感を高めているが,それに伴ってインドで用いられる英語,いわゆるインド英語 (Indian English) への注目も高まってきている.このインド英語には意外と長い歴史がある.少なくみても400年ほどはある.
Sharma (2077--85) は,インド英語の歴史を社会言語学的な観点から緩く4つの時代に区分している.簡単に説明を補いながら以下に示そう.
(1) The early presence of English in India (17th--18th century)
エリザベス1世の統治下の1600年,東インド会社が設立され,イギリスとインドの交易が本格的に始まった.この東インド会社は,1858年のイギリスによる直接統治まで拡大を続けることになる.当初は英語とインドの土着言語との接触は実用的なもので,互いの言語を不完全に習得する程度にとどまった.18世紀からはキリスト教学校が設立され,次第に英語使用がインドの人々の間に広がっていった.
(2) Colonial language ideologies (18th--19th century)
1757年,東インド会社軍がプラッシーの戦いでベンガル軍に勝利し,インドに対するイギリスの支配権が確立した.インドの不満は100年後の1857年にインド大反乱として爆発したが,鎮圧された後,翌1858年からはイギリスによる直接統治が始まった.イギリスには,植民地インドに対して2つの対立するイデオロギーがあった.インド土着の言語や文化を黙認する "Orientalist" と,イギリスの言語や文化によってインドを啓蒙しようとする "Anglicist" とである.Orientalist の立場としては,近代英語学の祖と呼ばれる William Jones などがいた.この立場は18世紀中には優勢だったが,19世紀に入ると Anglicist のイデオロギーが強まってきた.そのピークが1835年の Thomas Macaulay の "Minute on Indian Education" に結実しており,そこでは英語の優越性が明確に宣言された.インド人の知識人のなかにも Rammohun Roy のように Anglicist の立場をとるものがいた(cf. 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])).この結果,19世紀中,教育,出版,政治における英語使用が着実に増加した.
(3) English and the Independence movement (19th--20th century)
第1次大戦後,イギリス支配からの独立を目指す民族運動が起こった.英語ではなく土着言語の使用を訴えた Mahatma Gandhi の運動に象徴されるように,反英語のイデオロギーが台頭してきた.国民会議派の指導者で後にインドの初代首相となった Nehru も英語への抵抗を呼びかけた.しかし,1947年に独立が成し遂げられると,現実的な観点からは英語を保持せざるを得ないとの論調が復活してきた.以降,インドでの英語使用は継続してきたが,かつてのようなイギリス標準英語への憧憬をもつインド人は減ってきた.
(4) English in independent India: planning and use (20th century)
少なく見積もって415の言語が用いられているインドでは,複雑な多言語使用の様相がみられる.そのなかで22の言語が地域公用語として認められている.中央政府の言語としてはヒンディー語が公用語として,英語が準公用語として指定されている.独立直後には教育言語としてインドの土着言語が厚遇され,英語も当面は必要悪として保持するものの,いずれは使用されなくなっていくべきものと予期されていた.しかし,現実には土着言語間の政治的軋轢という問題があり,非土着言語として中立的な立場にある英語の使用が止まることはなかった.現在ではヒンディー語が優勢ではあるが,若い世代で英語のバイリンガルも普通となってきており,「インドの土着英語」というとらえ方が広がってきている.
・ Sharma, Devyani. "Second-Language Varieties: English in India." Chapter 132 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2077--91.
2021-01-12 Tue
■ #4278. クブラーの『時のかたち』からのインスピレーション [historiography][periodisation][speed_of_change][language_change][teleology]
ある言語の体系や正書法を「本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面」ととらえる見解について,美学者・考古学者のクブラー (George Kubler [1912--96]) を引用・参照しながら「#3911. 言語体系は,本来非同期的な複数の時のかたちが一瞬出会った断面である」 ([2020-01-11-1]) の記事で論じた.また,クブラー流の歴史観・時間観に触発されて,他にも「#3083. 「英語のスペリングは大聖堂のようである」」 ([2017-10-05-1]),「#3874. 「英語の正書法はパリのような大都会である」」 ([2019-12-05-1]),「#3912. (偽の)語源的綴字を肯定的に評価する (1)」 ([2020-01-12-1]),「#3913. (偽の)語源的綴字を肯定的に評価する (2)」 ([2020-01-13-1]) の記事を書いてきた.
今回,クブラーの『時のかたち』を読了し,言語がそのなかで変化していく「時間」について,改めて考えを巡らせた.言語変化の速度 (speed_of_change) や言語史における時代区分 (periodisation) に関してインスピレーションを得た部分が大きいので,関連する部分を備忘録的に引用しておきたい.
物質の空間の占め方がそうであるように,事物の時間の占め方は無限にあるわけではない.時間の占め方の種類を分類することが難しいのは,持続する期間に見合った記述方法を見つけ出すことが難しかったからである.持続を記述しようとしても,出来事を,あらかじめ定められた尺度で計測しているうちに,その記述は出来事の推移とともに変化してしまう.歴史学には定められた周期表もなく,型や種の分類もない.ただ太陽時と,出来事を区分けする旧来の方法が二,三あるのみで,時間の構造についての理論は一切なかったのである.
出来事はすべて独自なのだから分類は不可能だとするような非現実的な考え方をとらず,出来事にはその分類を可能とする原理があると考えれば,そこで分類された出来事は,疎密に変化する秩序を持った時間の一部として群生していることがわかる.この集合体のなかには,後続する個々の出来事によってその要件が変化していくような諸問題に対して,漸進的な解決として結びつく出来事が含まれている.その際,出来事が急速に連続すればそれは密な配列となり,多くの中断を伴う緩慢な連続であれば配列は疎となる.美術史ではときおり,一世代,ときには一個人が,ひとつのシークエンスにとどまらず,一連のシークエンス全体のなかで,多くの新しい地位を獲得することがある.その対極として,目前の課題が,解決されないまま数世代,ときには何世紀にもわたって存続することもある.(189--90)
時代とその長さ
こうして,あらゆる事物はそれぞれに異なった系統年代に起因する特徴を持つだけでなく,事物の置かれた時代がもたらす特徴や外観としてのまとまりをも持った複合体となる.それは生物組織も同様である.哺乳類の場合であれば,その血液と神経は生物史(絶対年代)的な見地での歴史が異なっているし,眼と皮膚というそれぞれの組織はその系統年代と異なっている.
事物の持続期間は絶対年代と系統年代というふたつの基準で計測が可能である.そのために歴史的時間は未来から現在を通過して過去へと続く単純な絶対年代の流れに加えて,系統年代という多数の包皮から構成されているとみなすことができる.この包皮は,いずれも,それが包んでいるその内容によって持続時間が決定されるために,その輪郭は多様なものとなるが,大小の異なった形状の系に容易に分類することができる.誰しも自身の生活のなかの同じ行為の初期のやり方と後期のやり方からなるこのようなパターンの存在を見出すことができるが,ここで,個人の時間における微細な形式にまで立ち入るつもりはない.それらは,ほんの数秒の持続から生涯にわたるものまで,個人のあらゆる経験に見出すことができる.しかし,私たちがここで注目したいのは,人の一生より長く,集合的に持続して複数の人数分の時間を生きている形や形式についてである.そのなかで最小の系は入念につくり上げられた毎年の服装の流行である.それは,現代の商業化された生活では服飾産業によるものであり,産業革命以前には宮廷の儀礼によるものであった.そこではこの流行を着こなすことが外見的に最も確かな上流階級の証しだったのである.一方,全宇宙のような大規模な形のまとめ方はごくわずかである.それらは人類の時間を巨視的にとらえた場合にかすかに思い浮かぶ程度のものである.すなわち,西洋文明,アジア文化,あるいは先史,未開,原始の社会などである.そして最大と最小の中間には,太陽暦や十進法にもとづく慣習的な時間がある.世紀という単位の本当の優位性は,おそらく自然現象にも,またそれが何であれ,人為的な出来事のリズムにも対応していないことになるのかもしれない.その例外は,西暦千年紀が近づいたときに終末論的な雰囲気が人々を襲ったことや,フランス革命中に恐怖政治が行われた一七九〇年代との単なる数値の類似が一八九〇年以降に世紀末の無気力感を引き起こしたことぐらいである.(193--95)
私たちは,〔中略〕時間の流れを繊維の束と想定することができる.それぞれの繊維は,活動のための特定の場として必要に応え,繊維の長さは必要とその問題に対する解決の持続に応じてさまざまである.したがって,文化の束は,出来事という繊維状のさまざまな長さの期間で構成される.その長さはたいてい長いのだが,短いものも多数ある.それらはほとんど偶然によって並べられ,意識的な将来への展望や緻密な計画によって並べられることはめったにないのである.(228)
最後の引用にある比喩を言語に当てはめれば,言語体系とは異なる長さからなる繊維の束の断面であるという見方になる.「言語体系」を,その部分集合である「正書法」「音韻体系」「語彙体系」などと置き換えてもよい.これと関連する最も理解しやすい卑近な例として,数語からなる短い1つの英文を考えてみるとよい.その構成要素である各語の語源(由来や初出年代)は互いに異なっており,体現される音形・綴字や,それらを結びつけている文法規則も,各々歴史的に発展してきたものである.この短文は,異なる長さの時間を歩んできた個々の部品から成り立っており,偶然にこの瞬間に組み合わされて,ある一定の意味を創出しているのである.
・ クブラー,ジョージ(著),中谷 礼仁・田中 伸幸(訳) 『時のかたち 事物の歴史をめぐって』 鹿島出版会,2018年.
2020-09-24 Thu
■ #4168. 言語の時代区分や方言区分はフィクションである [me_dialectology][periodisation][dialectology][variety]
英語史の概説書を読んでいると,「古英語」「中英語」「近代英語」などと特定の名前のついた時代区分が至るところに現われる.また「イングランド北部方言」「スコットランド方言」「ニューイングランド方言」などと名付けられた方言区分もよく出てくる.そのような区分名称があまりに自然に頻繁に用いられるために,英語に関して,時間や空間のなかで区切られた,そのような枠 --- 変種 (variety) --- が実際に存在すると思い込んでしまうことが多い.
しかし,言語の変種というものは常にフィクションである.○○英語もフィクションだし,英語それ自体もフィクションである.そして,日本語も然り.それと連動して,時代区分や方言区分もまたフィクションにすぎない.
これらの問題については,「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]),「#4123. 等語線と方言領域は方言学上の主観的な構築物である」 ([2020-08-10-1]) などで取り上げてきた.
言語に関するあらゆることがフィクションだと聞くと,狐につままれたようなような気がするかもしれない.しかし,ポイントは簡単だ.言語(変種)は時間的にも少しずつ変化するし,空間的にも少しずつ変異する連続体であり,名称をつけた区域のどこが始まりで,どこが終わりかを正確に指差しすることができないからだ.ここだと指差ししたところの1日手前,あるいは1ミリ手前の点を代わりにとって,そこを始まり/終わりとしてはなぜダメなのか,ということを客観的に示すことができないのである.
中英語の時代区分と方言区分について考察した Laing and Lass が,この問題について簡潔に解説している.まずは時代区分について.
The 'early'/'late' division is largely . . . a matter of convenience. The language of the 12th century and that of the 15th are different enough to justify separate identifying names. But language differences in time, like those in space, form continua: there are no sharp temporal boundaries. With respect to 'archaism' and 'modernness' Middle English before 1300 is certainly 'early' and that after 1350 'late'; the language written between is perhaps 'transitional', but this property exists only by virtue of the strong differences at both ends. (418--19)
次に方言区分について.
There are no such things as dialects. Or rather, 'a dialect' does not exist as a discrete entity. Attempts to delimit a dialect by topographical, political or administrative boundaries ignore the obvious fact that within any such boundaries there will be variation for some features, while other variants will cross the borders. (417)
「言語はフィクションである」というとき,必ずしも否定的な含みがあるわけではない.それは人間にとって便利なフィクションだし,おそらく不可欠なフィクションでもあるだろう.むしろそこには積極的な側面すらあり得る.「#2265. 言語変種とは言語変化の経路をも決定しうるフィクションである」 ([2015-07-10-1]) でみたように,言語のフィクション性そのものが言語の現実を変えてしまうこともあり得るのだから.
・ Laing, M. and R. Lass. "Early Middle English Dialectology: Problems and Prospects." Handbook of the History of English. Ed. A. van Kemenade and Los B. L. Oxford: Blackwell, 2006. 417--51.
2020-08-28 Fri
■ #4141. 1150年を越えて残らなかった古英語単語は OED から外されている [oed][oe][doe][periodisation][lexicography][lexicology][manuscript]
OED では古英語の単語はどのように扱われているか.この辺りの話題は,OED Online の提供する Old English in the OED を通じて知ることができる.
OED は,原則として1150年を超えて残らなかった古英語単語は取り扱わないと宣言している.歴史的原則を貫く OED としては,このように除外される単語もれっきとした英単語であるとは認識しているはずだ.しかし,同辞書編纂の長い歴史の当初からの方針であり,別途 The Dictionary of Old English (DOE) も編纂中であることから,現実的な選択肢としてそのような原則を立てているのだろう.それでも,1150年より前に文証され,この境の年を生き延びた7500語ほどの古英語単語が収録されているという事実は指摘しておきたい.
古英語期の内部の時期区分についても,新版 OED では3期に分けるという新しい方針を示している.'early OE' (600--950), 'OE' (950--1100), and 'late OE' (1100--1150) の3期である.主たる古英語写本約200点のうち,ほとんどが 'OE' (950--1100) に由来し,その点で証拠の偏りがあることは致し方がない(それ以前の 'early OE' (600--950) に属するものは20点未満).この3期区分は粗くはあるが,できるかぎり学術的正確性を期すための方法であり,写本年代や語の初出年代の記述にも有効に用いられている.
2020-04-20 Mon
■ #4011. 英語史の始まりはいつか? --- 700年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][inscription][manuscript][oe]
標題について,過去2日間の記事 ([2020-04-18-1], [2020-04-19-1]) で449年説と600年説を取り上げてきたが,今回は最後に700年説について考察したい.この年代は,英語の文献が本格的に現われ出すのが700年前後とされることによる.現代の英語史研究者がアクセスできる最古の文献の年代に基づいた説であるから,さらに古い文献が発見されれば英語史の始まりもその分さかのぼるという点で,相対的,可変的,もっと言ってしまえば研究者の都合を優先した説ということになる.Mengden (20) はこの説を次のように評価している.
. . . one could approach the question of the starting point of Old English from a modern perspective. . . . Our direct evidence of any characteristic of (Old) English begins with the oldest surviving written sources containing Old English. Apart from onomastic material in Latin texts and short inscriptions, the earliest documents written in Old English date from the early 8th century. A distinction between a reconstructed "pre-Old English" before 700 and an attested "Old English" after 700 . . . therefore does not seem implausible.
しかし,Mengden (20) は,700年前後という設定は必ずしも研究者の都合を優先しただけのものではないとも考えている.
. . . it is feasible that the shift from a heptarchy of more or less equally influential Anglo-Saxon kingdoms to the cultural dominance of Northumbria in the time after Christianization may be connected with the fact that texts are produced not exclusively in Latin, but also in the vernacular. In other words, we may speculate (but no more than that) that the emergence of the earliest Anglo-Saxon cultural and political centre in Northumbria in the 8th century may lead the Anglo-Saxons to view themselves as one people rather than as different Germanic tribes, and, accordingly to view their language as English (or, Anglo-Saxon) rather than as the Saxon, Anglian, Kentish, Jutish, etc. varieties of Germanic.
700年前後は,5世紀半ばにブリテン島に渡ってきた西ゲルマン集団が,アングロサクソン人としてのアイデンティティ,英語話者としてのアイデンティティを確立させ始めた時期であるという見方だ.これはこれで1つの洞察ではある.
さて,3日間で3つの説をみてきたわけだが,どれが最も妥当と考えられるだろうか.あるいは他にも説があり得るだろうか(私にはあると思われる).もっとも,この問いに正解があるわけではなく,視点の違いがあるにすぎない.だからこそ periodisation の問題はおもしろい.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2020-04-19 Sun
■ #4010. 英語史の始まりはいつか? --- 600年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][latin][borrowing][alphabet][oe]
昨日の記事「#4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説」 ([2020-04-18-1]) に引き続き,英語史の開始時期を巡る議論.今回は,実はあまり聞いたことのなかった(約)600年説について考えてみたい
597年に St. Augustine がキリスト教宣教のために教皇 Gregory I によってローマから Kent 王国へ派遣されたことは英国史上名高いが,この出来事がアングロサクソンの社会と文化を一変させたということは,象徴的な意味でよく分かる.社会と文化のみならず英語という言語にもその影響が及んだことは「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1]),「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) でたびたび注目してきた.確かに英語史上きわめて重大な事件が600年前後に起こったとはいえるだろう.Mengden の議論に耳を傾けてみよう.
. . . because the conversion is the first major change in the society and culture of the Anglo-Saxons that is not shared by the related tribes on the Continent, it is similarly significant for (the beginning of) an independent linguistic history of English as the settlement in Britain. Moreover, the immediate impact of the conversion on the language of the Anglo-Saxons is much more obvious than that of the migration: first, the Latin influence on English grows in intensity and, perhaps more crucially, enters new domains of social life; second, a new writing system, the Latin alphabet, is introduced, and third, a new medium of (linguistic) communication comes to be used --- the book.
600年説の要点は3つある.1つめは,主に語彙借用のことを述べているものと思われるが,ラテン語からキリスト教や学問を中心とした文明を体現する分野の借用語が流れ込んだこと.2つめはローマン・アルファベットの導入.3つめは本というメディアがもたらされたこと.
いずれも英語に直接・間接の影響を及ぼした重要なポイントであり,しかも各々の効果が非常に見えやすいというメリットもある.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2020-04-18 Sat
■ #4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][oe]
○○史の時代区分 (periodisation) というのは,その分野において最も根本的な問題である.英語史も例外ではなく,この問題について絶えず考察することなしには,そもそも研究が成り立たない.とりわけ英語史の始まりをどこに置くかという問題は,分野の存立に関わる大問題である.本ブログでも,periodisation とタグ付けした多数の記事で関連する話題を取り上げてきた.
最も伝統的かつポピュラーな説ということでいえば,アングロサクソン人がブリテン島に渡ってきたとされる449年をもって英語史の始まりとするのが一般的である.この年代自体が伝説的といえばそうなのだが,もう少し大雑把にみても5世紀前半から中葉にかけての時期であるという見解は広く受け入れられている.
一方,「歴史」とは厳密にいえば文字史料が確認されて初めて成立するという立場からみれば,英語の文字史料がまとまった形で現われるのは700年くらいであるから,その辺りをもって英語史の開始とする,という見解もあり得る.実際,こちらを採用する論者もいる.
上記の2つが英語史の始まりの時期に関する有力な説だが,Mengden (20) がもう1つの見方に言及している.600年頃のキリスト教化というタイミングだ.キリスト教化がアングロサクソン社会にもたらした文化的な影響は計り知れないが,そのインパクトこそが彼らの言語を初めて「英語」(他のゲルマン語派の姉妹言語と区別して)たらしめたという議論だ.かくして,古い方から並べて (1) (象徴的に)紀元449年,(2) およそ600年,(3) およそ700年,という英語史の開始時期に関する3つの候補が出たことになる.
各々のポイントについて考えて行こう.定説に近い (1) を重視する理由は,Mengden 曰く,次の通りである.
Although the differences between the varieties of the settlers and those on the continent cannot have been too great at the time of the migration it is the settlers' geographic and political independence as a consequence of the migration which constitutes the basis for the development of English as a variety distinct and independent from the continental varieties of the West Germanic speech community . . . . (20)
要するに,449年(付近)を英語史の始まりとみる最大のポイントは,言語学的視点というよりも社会(言語学)的視点を取っている点にある.もっといえば,空間的・物理的な視点である.大陸の西ゲルマン語の主要集団から分離して独自の集団となったのが「英語」社会だるという見方だ.実際 Mengden 自身も様々に議論した挙げ句,この説を最重要とみなしている.
I would therefore propose that, whatever happens to the language of the Anglo-Saxon settlers in Britain and for whatever reason it happens, any development after 450 should be taken as specifically English and before 450 should be taken as common (West) Germanic. That our knowledge of the underlying developments is necessarily based on a different method of access before and after around 700 is ultimately secondary to the relevant linguistic changes themselves and for any categorization of Old English. (21)
結局 Mengden も常識的な結論に舞い戻ったようにみえるが,一般的にいって,深く議論した後にぐるっと一周回って戻ってきた結論というものには価値がある.定説がなぜ定説なのかを理解することは,とても大事である.
他の2つの説については明日以降の記事で取り上げる.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2020-03-05 Thu
■ #3965. 古英語の方言区分が難しい理由 [oe_dialect][oe][dialectology][periodisation]
古英語の方言区分については「#1433. 10世紀以前の古英語テキストの分布」 ([2013-03-30-1]) で地図を掲げた.Northumbrian, Mercian, Kentish, West-Saxon ときれいに分かれているようにみえるが,古英語期特有の込み入った事情があり,実際には不明な点が多いことに注意しておく必要がある.Hogg (4) が3点挙げている.
. . . it is important to recognize that it is open to several major caveats and objections. Firstly, it is well known that these dialects refer only to actual linguistic material, and therefore there are large areas of the country, most obviously East Anglia, about whose dialect status we cannot know directly from OE evidence. Secondly, the nomenclature adopted is derived from political structures whereas most of the writing we have is to be more directly associated with ecclesiastical structures. Thirdly, the type of approach which leads to the above division is a product of the Stammbaum and its associated theories, whereas modern dialectology, either synchronic or diachronic ... demonstrates that such a rigidly demarcated division is ultimately untenable. It would be preferable to consider each text as an 'informant', ... which is more or less closely related to other texts on an individual basis, with the classification of texts into dialect groups being viewed as a process determined by the purposes of the linguistic analysis at hand, rather than as some a priori fact. . . .
まとめれば,古英語期からの証拠 (evidence) の分布が時期や地域によってバラバラであり量も少ないこと,地域方言の存在の背景にある当時の社会言語学的な事情が不詳であること,そして様々な程度の方言間接触があったはずであることの3点である.いずれも方言区分しようとする際に頭の痛い問題であることは容易に理解される.引用の最後に明言されているように,古英語の方言区分は,当面の言語分析のための仮説上の構築物ととらえておくのが妥当である.この点では,時代区分 (periodisation) の問題にも近いといえる.
・ Hogg, Richard M. A Grammar of Old English. Vol. 1. 1992. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2019-09-16 Mon
■ #3794. 英語史で用いる諸言語名の略形 [abbreviation][periodisation][etymology][terminology]
本ブログで英語史の話題を提供するのに,語源解説などでしばしば諸言語を参照する必要があるが,その際に用いる言語名の略形を一覧する.これまでの記事では必ずしも略形を統一させてこなかったが,今後はなるべくこちらに従いたい.ソースとしては『英語語源辞典』の「言語名の略形」 (xvi--xvii) に依拠する.主要な(歴史的)言語については,同辞典の xiv より年代区分も挙げておく.略形関係としては「#1044. 中英語作品,Chaucer,Shakespeare,聖書の略記一覧」 ([2012-03-06-1]) も参照.
| Aeol. | Aeolic | |
| AF | Anglo-French | 1100--1500 |
| Afr. | African | |
| Afrik. | Afrikaans | |
| Akkad. | Akkadian | |
| Alb. | Albanian | |
| Aleut. | Aleutian | |
| Am. | American | |
| Am.-Sp. | American Spanish | |
| Anglo-L | Anglo-Latin | |
| Arab. | Arabic | |
| Aram. | Aramaic | |
| Arm. | Armenian | |
| Assyr. | Assyrian | |
| Austral. | Australian | |
| Aves. | Avestan | |
| Braz. | Brazilian | |
| Bret. | Breton | |
| Brit. | Brittonic/Brythonic | |
| Bulg. | Bulgarian | |
| Canad. | Canadian | |
| Cant. | Cantonese | |
| Cat. | Catalan | |
| Celt. | Celtic | |
| Central-F | Central French | |
| Chin. | Chinese | |
| Corn. | Cornish | |
| Dan. | Danish | |
| Drav. | Dravidian | |
| Du. | Dutch | |
| E | English | |
| E-Afr. | East African | |
| Egypt. | Egyptian | |
| F | French | |
| Finn. | Finnish | |
| Flem. | Flemish | |
| Frank. | Frankish | |
| Fris. | Frisian | |
| G | German | |
| Gael. | (Scottish-)Gaelic | |
| Gaul. | Gaulish | |
| Gk | Greek | --200 |
| Gmc | Germanic | |
| Goth. | Gothic | |
| Heb. | Hebrew | |
| Hitt. | Hittite | |
| Hung. | Hungarian | |
| Icel. | Icelandic | |
| IE | Indo-European | |
| Ind. | Indian | |
| Ir. | Irish(-Gaelic) | |
| Iran. | Iranian | |
| It. | Italian | |
| Jamaic.-E | Jamaican English | |
| Jav. | Javanese | |
| Jpn. | Japanese | |
| L | Latin | 75 B.C.--200 |
| Latv. | Latvian | |
| Lett. | Lettish | |
| LG | Low German | |
| LGk | Late Greek | 200--600 |
| Lith. | Lithuanian | |
| LL | Late Latin | 200--600 |
| MDu. | Middle Dutch | 1100--1500 |
| ME | Middle English | 1100--1500 |
| Mex. | Mexican | |
| Mex.-Sp. | Mexican Spanish | |
| MGk | Medieval Greek | 600--1500 |
| MHeb. | Medieval Hebrew | |
| MHG | Middle High German | 1100--1500 |
| MIr. | Middle Irish | 950--1300 |
| Mish. Heb. | Mishnaic Hebrew | |
| ML | Medieval Latin | 600--1500 |
| MLG | Middle Low German | 1100--1500 |
| ModE | Modern English | |
| ModGk | Modern Greek | |
| ModHeb. | Modern Hebrew | |
| MPers. | Middle Persian | |
| MWelsh | Middle Welsh | 1150--1500 |
| N-Am.-Ind. | North American Indian | |
| NGk | Neo-Greek | |
| NHeb. | Neo-Hebrew | |
| NL | Neo-Latin | |
| Norw. | Norwegian | |
| ODu. | Old Dutch | |
| OE | Old English | 700--1100 |
| OF | Old French | 800--1550 |
| OFris. | Old Frisian | 1200--1550 |
| OHG | Old High German | 750--1100 |
| OIr. | Old Irish | 600--950 |
| OIt. | Old Italian | |
| OL | Old Latin | 500--75 B.C. |
| OLG | Old Low German | 800--1100 |
| OLith. | Old Lithuanian | |
| ON | Old Norse | 800--1300 |
| ONF | Old Norman French | |
| OPers. | Old Persian | |
| OProv. | Old Provençal | |
| OPruss. | Old Prussian | 1400--1600 |
| OS | Old Saxon | 800--1000 |
| Osc. | Oscan | |
| Osc.-Umbr. | Osco-Umbrian | |
| OSlav. | Old (Church) Slavonic | 900--1100 |
| OSp. | Old Spanish | |
| OWelsh | Old Welsh | 700--1150 |
| PE | Present-Day English | |
| Pers. | Persian | |
| Phoen. | Phoenician | |
| Pidgin-E | Pidgin English | |
| Pol. | Polish | |
| Port. | Portuguese | |
| Prov. | Provençal | |
| Rum. | Rumanian | |
| Russ. | Russian | |
| S-Afr. | South African | |
| S-Am.-Ind. | South American Indian | |
| Scand. | Scandinavian | |
| Sem. | Semitic | |
| Serb. | Serbian | |
| Serbo-Croat. | Serbo-Croatian | |
| Siam. | Siamese | |
| Skt | Sanskrit | |
| Slav. | Slavonic, Slavic | |
| Sp. | Spanish | |
| Sumer. | Sumerian | |
| Swed. | Swedish | |
| Swiss-F | Swiss French | |
| Syr. | Syriac | |
| Tibet. | Tibetan | |
| Toch. | Tocharian | |
| Turk. | Turkish | |
| Umbr. | Umbrian | |
| Ved. | Vedic | |
| VL | Vulgar Latin | |
| W-Afr. | West African | |
| W-Ind. | West Indies | |
| WS | West Saxon | |
| Yid. | Yiddish |
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2018-09-28 Fri
■ #3441. 日本語史の時代区分 (3) [periodisation][japanese]
「#1525. 日本語史の時代区分」 ([2013-06-30-1]),「#3137. 日本語史の時代区分 (2)」 ([2017-11-28-1]) に続き,日本語史研究者の数だけあるといっても過言ではない時代区分 (periodisation) の話題を追加する.清水 (7) は,他のいくつかの伝統的な時代区分も挙げながら,もう1つの独自の区分を掲げている.
┌── 前期:弥生時代(前3世紀頃?後3世紀中頃)
I 太古日本語 (Proto-Japanese) ────┤
└── 後期:古墳時代(3世紀中頃?7世紀頃)
┌── 前期:奈良時代前(7世紀頃)?奈良時代(8世紀後半頃)………………………………………………………〔上代〕
│
II 古代日本語 (Ancient Japanese) ───┼── 中期:平安時代(8世紀後半頃?11世紀後半頃) …………………………………………………………………〔中古〕
│
└── 後期:院政鎌倉時代(11世紀後半頃?14世紀前半頃)……………………………………………………………〔中世〕
┌── 前期:室町時代(14世紀前半頃)?江戸時代前期(寛永頃まで含む:17世紀中頃)…………………〔中世?近世〕
│
III 近代日本語 (Modern Japanese) ───┼── 中期:江戸時代中期(上方期・江戸期含む:17世紀中頃)?江戸時代後期(明治20年頃まで含む)………〔中古〕
│
└── 後期:明治時代(明治20年頃以降)?大正時代?昭和20年 ……………………………………………〔近代?現代〕
┌── 前期:昭和20年以降?昭和48年頃 …………………………………………………………………………………〔現代〕
│
IV 現代日本語 (Present-day Japanese) ─┼── 中期:昭和48年頃以降?平成3年頃 …………………………………………………………………………………〔現代〕
│
└── 後期:平成3年頃以降?現時点 ………………………………………………………………………………………〔現代〕
一般的な見地からは,やや細かすぎる区分にも思えるが,専門的には細かい方が便利なこともあり,この区分もそのような趣旨からだろう.細かいもの,粗いものを含めて様々な時代区分法があるのは,まず言及する上での便宜という側面がある.○○年頃や○○世紀という言及に比べれば,細かい時代区分でも適度に粗いことになり,ある程度のまとまった時間の広がりを簡便に指し示すことができるのだ.
また,注目している言語項がどの程度の時間的な広がりをもって分布しているかに応じて,適切な細かさ・粗さの時代区分も変わってくる.例えば,語彙史を論じる場合と文法史を論じる場合とでは異なるタイムスケールを利用した方が,変化の流れを整理しやすい,などということもあるだろう.
結局のところ,各研究者がある時代区分を採用する際には,採用に先だって,言語(史)のどの側面に注目したいのかという方針や理念が決定されているのだ.時代区分は,それ自体が研究者のスタンスを表明しているものと考えてよい.だからこそ,時代区分にヴァリエーションがあるというのが,おもしろい.
・ 清水 史 「第1章 日本語史概観」服部 義弘・児馬 修(編)『歴史言語学』朝倉日英対照言語学シリーズ[発展編]3 朝倉書店,2018年.1--21頁.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2018-08-07 Tue
■ #3389. 沖森卓也『日本語史大全』の目次 [toc][japanese][periodisation][historiography]
目次シリーズの一環として,昨年出版された包括的な日本語史概説書,沖森卓也(著)『日本語史大全』を取り上げたい.文庫でありながら教科書的という印象で,記述は淡々としている.時代別に章立てされているが,各章の内部では分野別の記述がなされており,各章の該当節を拾っていけば,分野ごとの縦の流れも押さえられるように構成されている.したがって,目次を追っていくだけで日本語史の全体像が理解できる仕組みとなっている.以下に目次を再現しよう.
ちなみに英語史概説書の目次は「#2089. Baugh and Cable の英語史概説書の目次」 ([2015-01-15-1]),「#2050. Knowles の英語史概説書の目次」 ([2014-12-07-1]),「#2038. Fennell の英語史概説書の目次」 ([2014-11-25-1]),「#2007. Gramley の英語史概説書の目次」 ([2014-10-25-1]) を参照.
はじめに
歴史を知る意義
日本語史の対象と方法
話しことばの歴史
日本語史の時代区分
分野別の記述
日本語史へのいざない
第一章 古代前期――奈良時代まで
1 総説――古代語が確立する
古代前期とその言語
「万葉仮名文書」に口語の一端を見る
2 文字表記――日本語が漢字で書かれる
漢字の伝来
稲荷山古墳鉄剣銘
万葉仮名
漢字の音
字音の構造
音仮名の用法
訓の成立
訓と和化漢文
仮名文の原形
3 音韻――区別される音節の数が多い
上代特殊仮名遣
母音と子音
母音調和
頭音法則
母音交替
イ段乙類音とエ段音
連濁
音節構造とアクセント
4 語彙――固有語が用いられる
和語とは固有語か
和語と音節数
代名詞の語彙
動詞の語構成
形容詞の語構成
漢語
待遇表現の語彙
雅俗・男女差
方言
忌詞
5 文法――古代語法が形成される
動詞の活用
活用タイプの所属語
動詞活用の起源
命令形の由来
未然形と連用形の機能
連用形の由来
未然形の由来
終止形の由来
連体形の由来
連体形と已然形の類似点
已然形の用法
已然形の由来
上一段活用の由来
形容詞の活用
形容詞の活用の由来
ク語法
ミ語法
態の助動詞
推量の助動詞
過去・完了・継続の助動詞
断定・否定の助動詞
尊敬の助動詞
格助詞
接続助詞
副助詞
係助詞
終助詞
間投助詞
第二章 古代後期――平安時代
1 総説――古代語が完成する
古代後期とその言語
漢文と仮名文
『源氏物語』に古典語を見る
階級と地域
2 文字表記――仮名が成立する
漢文の訓読
訓点の方法
片仮名の成立
草仮名
平仮名の成立
仮名の起源
句読点と濁点
3 音韻――音節が複雑に発達する
上代特殊仮名遣の崩壊
母音と子音
音韻の混同
「あめつち」と「たゐに」
いろは歌
五十音図
漢字音
声点とアクセント
名詞のアクセント
動詞のアクセント
形容詞その他のアクセント
4 語彙――漢語の使用が漸増する
代名詞の語彙
多彩な形容動詞語彙
和語と漢語
漢語の日本語化
混種語
和文語と漢文訓読語
待遇表現の語彙
丁寧語の発生
漢和字書の誕生
5 文法――古典文法が完成する
動詞の活用
形容詞・形容動詞の活用
音便
音便発生の理由
態の助動詞
推量の助動詞
その他の助動詞
格助詞
接続助詞
副助詞・係助詞
終助詞
間投助詞
第三章 中世前期――院政鎌倉時代
1 総説――古代語が瓦解する
中世前期とその言語
口語の変化に着目する
『徒然草』に当時の口語を垣間見る
2 文字表記――仮名の使用が促される
東鑑体
真名本が生まれる
漢字の字体と書風
仮名で和語を書く
仮名使用の広がり
片仮名の使用者層
片仮名の字体
促音・撥音の表記
定家仮名遣
3 音韻――音韻が整理されていく
イとヰ,エとヱ
直音と拗音
鼻濁音
連濁と連声
開合
促音と撥音
漢字音の日本語化
東国方言の音韻
4 語彙――漢語が一般化する
代名詞の語彙
和語と漢語
和漢の混淆
唐音とその漢語
武家詞
待遇表現の語彙
国語辞典の出現
5 文法――古代語法が衰退する
連体形の終止法
係り結びの消滅
二段活用の一段化
ラ変活用の消滅
形容詞活用の一本化
連体形活用語尾「る」の脱落
形容動詞の活用
接続詞
態の助動詞
「しむ」をめぐる混乱
推量の助動詞
過去・完了の助動詞
断定・否定の助動詞
願望・希望の助動詞
格助詞
接続助詞
副助詞
係助詞
終助詞・間投助詞
第四章 中世後期――室町時代
1 総説――近代語が胎動する
中世後期とその言語
外国語との交流
『天草本伊曽保物語』に口語の全容を見る
2 文字表記――文字の使用が広がる
キリシタン資料のローマ字つづり
印刷技術のもう一つの伝来
漢字
仮名
濁点・半濁点
3 音韻――現代語の発音に近づく
母音
子音
四つ仮名
連濁と連声
漢字音
4 語彙――外来語が登場する
代名詞の語彙
副詞の語彙
感動詞の語彙
現代語と異なる語形
漢語
ポルトガル語からの外来語
女房詞と武家詞
待遇表現の語彙
尊敬語
謙譲語
丁寧語
5 文法――近代語法が芽生える
二段活用の一段化の進行
動詞活用のヤ行化
動詞の命令形
可能動詞
テ形の発達
授受表現
形容詞
形容動詞
音便
形式名詞の「の」
態の助動詞
推量の助動詞
過去の助動詞とアスペクト
断定の助動詞
その他の助動詞
格助詞
接続助詞
副助詞・係助詞
終助詞・間投助詞
複合辞の増加
第五章 近世――江戸時代
1 総説――近代語が発達する
近世とその言語
上方語と江戸語
『浮世風呂』に江戸語の位相差を見る
2 文字表記――文字が庶民に普及する
文字の学習
近世の文体
漢字と仮名
契沖仮名遣
濁点・半濁点と句読点
3 音韻――現代語の音韻が確立する
母音
子音
合拗音の消滅
開合と四つの仮名の混同
江戸語の音韻的特色
4 語彙――漢語で訳語が造られる
代名詞の語彙
感動詞の語彙
階層によって異なる使用語彙
尊敬語
丁寧語
あそばせ詞
謙譲語ほか
女性語の発展
漢語の尊重
漢語による翻訳語
オランダ語からの外来語
5 文法――近代語法が整備される
動詞の活用
可能動詞
形容動詞
推量の助動詞
断定の助動詞
否定の助動詞
態の助動詞とアスペクト
格助詞
順接の接続助詞
逆接の接続助詞
その他の接続助詞
副助詞
終助詞
間投助詞
複合辞の発達
第六章 近代――明治時代
1 総説――共通語が普及する
近代とその言語
『あひゞき』に口語体の創出を見る
2 文字表記――文字施策が浸透する
漢字と訓
言文一致体
出版の大衆化
漢字の廃止論と制限論
国語施策と漢字制限
当用漢字と常用漢字
外来語の表記
ヘボン式と日本式のローマ字つづり
戦後のローマ字つづり
3 音韻――外来語が影響を与える
現代日本語の音韻
外来語の音韻
二拍名詞のアクセント
アクセントの型の対応
方言アクセントの系譜
三拍名詞のアクセント
東京アクセントの形成
4 語彙――漢語・外来語が急増する
新漢語の出現
『浮雲』の漢語
漢語の増加
『浮雲』の外来語
外来語の急増
現代語の語種
待遇表現の語彙
5 文法――現代語法が展開する
動詞の活用
形容詞・形容動詞
ラ抜きことば
助動詞
格助詞
接続助詞
副助詞
終助詞・間投助詞
東京語の文末表現
????????????
参考文献
索引
・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.
2018-05-12 Sat
■ #3302.「英語の帝国」のたどった3段階の「帝国」 [history][linguistic_imperialism][periodisation][anglo-saxon]
5世紀半ばにアングロサクソン人がブリテン島に来住し,その後に建てた国家の領土は,イングランドに始まり,ブリテン島,ブリテン諸島へと拡張し,最終的には北米,カリブ海,南アジア,太平洋,アフリカなど世界中に拡がった.この拡張の流れは,大きく3つの段階に分けて考えることができる.アングロサクソン人の来住以来の経緯を端的にまとめた平田 (10--11) の文章を引用する.
中世において,イングランドは,ブリテン島の隣人であるスコットランド,ウェールズ,海を越えたアイルランド島を侵略し支配した.イングランドが支配したこれらのブリテン諸島は「イングランド帝国」と呼ばれることがある.英語は中世の長期間をかけて,このイングランド帝国に普及した.
近代になり,とくに,イングランドとスコットランドが連合した一七〇七年の「グレート・ブリテン」成立以降に海外に獲得した植民地を含む大帝国を「ブリテン帝国」または「大英帝国」と呼ぶ.ブリテン帝国は,北米とカリブ海に領土を広げ,アメリカが独立するとインドを中心にして領土を築いた.近代においては,英語はブリテン諸島を越えてこのブリテン帝国にも広がっていった.
近代,とくに一九世紀以後,ブリテンは「公式帝国」と区別される「非公式帝国」にも支配を広げた.「非公式帝国」とは「公式帝国」が法律上の帝国なのに対して,経済的・文化的に支配された事実上の帝国を指し,一九世紀におけるブリテンの「非公式帝国」はラテンアメリカ,中東,極東などを含む.英語は「公式帝国」を超えてこの「非公式帝国」と呼ばれる地域にも広がった.日本もこの「非公式帝国」の一つとして論じられることがあり,本書は最後に日本にたどりつく.
時代とともに「イングランド帝国」,「公式ブリテン帝国」,「非公式ブリテン帝国」と名前こそ変えてきたものの,これらに通底する共通項である「英語」をくくりだして,すべてを俯瞰する名前を付ければ「英語帝国」となる,というのが著者の主張である.英語史と関連づけたイギリス史の帝国主義史観といえるだろう.
「イングランド帝国」,「公式ブリテン帝国」,「非公式ブリテン帝国」のそれぞれは,非常に緩くではあるが Kachru のいう Inner Circle, Outer Circle, Expanding Circle に対応すると考えられる(「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])を参照).
関連して,「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1]) も,似たような発想に基づいた英語史観として参照されたい.
・ 平田 雅博 『英語の帝国 ―ある島国の言語の1500年史―』 講談社,2016年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow