2020-11-10 Tue
■ #4215. 強意複数 (2) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability][poetry][latin][rhetoric]
昨日の記事 ([2020-11-09-1]) に引き続き強意複数 (intensive_plural) の話題について.この用語は Quirk et al. などには取り上げられておらず,どうやら日本の学校文法で格別に言及されるもののようで,たいていその典拠は Kruisinga 辺りのようだ.それを参照している荒木・安井(編)の辞典より,同項を引用する (739--40) .昨日の記事の趣旨を繰り返すことになるが,あしからず.
intensive plural (強意複数(形)) 意味を強調するために用いられる複数形のこと.質量語 (mass word) に見られる複数形で,複数形の個物という意味は含まず,散文よりも詩に多く見られる.抽象物を表す名詞の場合は程度の強いことを表し,具象物を表す名詞の場合は広がり・集積・連続などを表す: the sands of Sahara---[Kruisinga, Handbook] / the waters of the Nile---[Ibid.] / The moon was already in the heavens.---[Zandvoort, 19757] (月はすでに空で輝いていた) / I have my doubts.---[Ibid.] (私は疑念を抱いている) / I have fears that I may cease to be Before my pen has glean'd my teeming brain---J. Keats (私のペンがあふれんばかりの思いを拾い集めてしまう前に死んでしまうのではないかと恐れている) / pure and clear As are the frosty skies---A Tennyson (凍てついた空のように清澄な) / Mrs. Payson's face broke into smiles of pleasure.---M. Schorer (ペイソン夫人は急に喜色満面となった) / To think is to be full of sorrow And leaden-eyed despairs---J. Keats (考えることは悲しみと活気のない目をした絶望で満たされること) / His hopes to see his own And pace the sacred old familiar fields, Not yet had perished---A. Tennyson (家族に会い,なつかしい故郷の神聖な土地を踏もうという彼の望みはまだ消え去っていなかった) / All the air is blind With rosy foam and pelting blossom and mists of driving vermeil-rain.---G. M. Hopkins (一面の大気が,ばら色の泡と激しく舞い落ちる花と篠つく朱色の雨のもやで眼もくらむほどになる) / The cry that streams out into the indifferent spaces, And never stops or slackens---W. H. Auden (冷淡な空間に流れ出ていって,絶えもしないゆるみもしない泣き声).
同様に,石橋(編)の辞典より,Latinism の項から関連する部分 (477) を引用する.
(3) 抽象名詞を複数形で用いる表現法
いわゆる強意複数 (Intensive Plural) の一種であるが,とくにラテン語の表現法を模倣した16世紀後半の作家の文章に多く見られ,その影響で後代でも文語的ないし詩的用法として維持されている.たとえば,つぎの例に見られるような hopes, fears は,Virgil (70--19 B.C.) や Ovid (43 B.C.--A.D. 17?) に見られるラテン語の amōrēs [L amor love の複数形], metūs [L metus fear の複数形] にならったものとみなされる.Like a young Squire, in loues and lusty-hed His wanton dayes that ever loosely led, . . . (恋と戯れに浮き身をやつし放蕩に夜も日もない若い従者のような…)---E. Spenser, Faerie Qveene I. ii. 3 / I will go further then I meant, to plucke all feares out of you. (予定以上のことをして,あなたの心配をきれいにぬぐい去って上げよう)---Sh, Meas. for M. IV. ii. 206--7 / My hopes do shape him for the Governor. (どうやらその人はおん大将と見える)---Id, Oth. II. i. 55.
ほほう,ラテン語のレトリックとは! それがルネサンス・イングランドで流行し,その余韻が近現代英語に伝わるという流れ.急に呑み込めた気がする.
・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.
・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.
・ 荒木 一雄,安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.
・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.
2020-11-09 Mon
■ #4214. 強意複数 (1) [plural][intensive_plural][semantics][number][category][noun][terminology][countability]
英語(やその他の言語)における名詞の複数形 (plural) とは何か,さらに一般的に言語における数 (number) という文法カテゴリー (category) とは何か,というのが私の研究におけるライフワークの1つである.その観点から,不思議でおもしろいなと思っているのが標題の強意複数 (intensive_plural) という現象だ.以下,『徹底例解ロイヤル英文法』より.
まず,通常は -s 複数形をとらないはずの抽象概念を表わす名詞(=デフォルトで不可算名詞)が,強意を伴って強引に複数形を取るというケースがある.この場合,意味的には「程度」の強さを表わすといってよい.
・ It is a thousand pities that you don't know it.
・ She was rooted to the spot with terrors.
このような例は,本来の不可算名詞が臨時的に可算名詞化し,それを複数化して強意を示すという事態が,ある程度慣習化したものと考えられる.可算/不可算の区別や単複の区別をもたない日本語の言語観からは想像もできない,ある種の修辞的な「技」である.心理状態を表わす名詞の類例として despairs, doubts, ecstasies, fears, hopes, rages などがある.
一方,上記とは異なり,多かれ少なかれ具体的なモノを指示する名詞ではあるが,通常は不可算名詞として扱われるものが,「連続」「広がり」「集積」という広義における強意を示すために -s を取るというケースがある.
・ We had gray skies throughout our vacation.
・ They walked on across the burning sands of the desert.
・ Where are the snows of last year?
ほかにも,気象現象に関連するものが多く,clouds, fogs, heavens, mists, rains, waters などの例がみられる.
「強意複数」 (intensive plural) というもったいぶった名称がつけられているが,thanks (ありがとう),acknowledgements (謝辞),millions of people (何百万もの人々)など,身近な英語表現にもいくらでもありそうだ.英語における名詞の可算/不可算の区別というのも,絶対的なものではないと考えさせる事例である.
・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.
2020-10-14 Wed
■ #4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][oe][sound_change][analogy][high_vowel_deletion][analogy]
sheep, deer のような普通名詞の複数形は,どういうわけか無変化で sheep, deer のままです.英語には,このような「単複同形」と呼ばれる名詞が少ないながらもいくつか存在しますが,いったいどのような背景があるのでしょうか.ラジオの解説をお聴きください.
英語の歴史においては,もともとは sheep にせよ deer にせよ,単数形と複数形は形態的に区別されていました.古英語より前の時代には,単数形 scēap に対して *scēapu,同様に単数形 dēor に対して *dēoru のように,語尾によって単複が区別されていたのです.しかし,古英語期までに,専門的には「高母音削除」(high_vowel_deletion) と呼ばれる音変化が生じて語尾の -u が消失し,単複同形となってしまっていたのです.
さて,このタイプの単語に,動物や単位を表わす名詞が少なからず含まれていたことが,続く中英語期の展開においてポイントとなってきます.主として狩猟対象となる動物(群れ)や数の単位を表わす名詞は,単数よりも複数で用いられることが多いのは自然に理解できるでしょう.これらの名詞は,複数形で使われるのがデフォルトなのです.すると,あえて -s などをつけて複数形であることを明示する必要もなく,そのまま裸の形で実質的に複数を表わすという慣習が拡がりました.もともと古英語期には複数形に -s 語尾をとっていた fish ですら,この慣習に巻き込まれて単複同形となりました.結果として,狭い意味領域ではありますが,動物の群れや数の単位を表わすいくつかの名詞が,英語では特殊な「単複同形」を取ることになったのです.具体的には,sheep, deer, fish, carp や hundred, thousand, million, billion などの名詞です.
sheep や deer は,このような傾向のモデルとなった,古英語から続く老舗の名詞なのです.しかし,改めて強調しておきますが,sheep や deer とて,古英語より前の時代には,きちんと形態的に異なる複数形を示していたということです.音変化とその後の語彙・意味的な類推作用 (analogy) の結果,現代のような単複同形になっているのだということを銘記しておきたいと思います.
この問題と関連して,##12,1512,2232の記事セットを参照していただければと思います.
2020-10-07 Wed
■ #4181. なぜ child の複数形は children なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][double_plural][oe]
不規則な名詞複数形の「なぜ?」は素朴な疑問の定番といってよいでしょう.しかも,英語史による説明が威力を発揮する疑問の定番とも言えます.(私自身,ある意味ではこの疑問を追い続けて英語史のの研究者になったといっても過言ではありません.)
ほとんどの名詞が -(e)s をつけて複数形を作るわけですが,少数の名詞は feet, sheep, phenomena, oxen など,予想もできない(つまり暗記するよりほかにない)複数形を作ります.そのような不規則な名詞複数形の最たるものが children です.なぜ単数形 child に -ren をつけると複数形になるのか,わけが分かりません.厳密な類例もないのです(先の oxen とちょっと似た匂いは感じさせますが).
この不可解な名詞複数形の謎を解くべく,歴史をひもといてみましょう.音声解説をお聴きください.
古英語には,名詞複数形の作り方が数種類ありました.そのうちの1つに -ru という語尾がありました.これが無事に残っていれば child の複数形は childru を経由して childer ほどの形態になっていたはずです.しかし,大多数の名詞が,古英語期より優勢であった -(e)s 語尾を付加する方法(あるいは,それに次いで優勢だった -(e)n 語尾による方法)に靡いていき,高頻度語であるがゆえに大勢から取り残されてしまった当該語 child の複数形 childru/childer は,周囲から浮いてしまう結果となりました.-ru/-er 複数の仲間が周りにいなくなってしまい,その語尾だけでは複数形であることを明示するのに頼りないと感じられたのでしょうか,中英語期にもう1つの有力な語尾である -(e)n を付して,新たなる複数形 children を作り出すに至ったのです.その後 -(e)s 複数がますます伸張するにつれて -(e)n 複数は衰えていき,oxen に痕跡を残す程度になってしまいましたが,children もある意味ではその仲間といえます.本来は r のみで複数を表わせたのですが,さらに -en も加えたという意味で,語源的な観点からは2重複数 (double_plural) の事例といわれます.
-(e)s 複数形への一本化の潮流は,ざっと千年ほど続いてきました.この潮流を考えれば,遠くない未来に children も *childs に置き換えられる運命なのかもしれません.children は,古英語の伝統と中英語期の革新を合わせて示す,英語史上銘記すべき稀な複数形なのです.
この問題と関連して,##146,218,145,337,2826の記事セットをご覧ください.とりわけ「「ことばを通時的にみる」とは?」をお薦めします.
2020-08-12 Wed
■ #4125. なぜ women は「ウィミン」と発音するのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][spelling_pronunciation_gap][plural][etymology][disguised_compound][phonetics]
hellog ラジオ版の第15回は,スペリングと発音の不一致しない事例の1つを取り上げます.women = /ˈwɪmɪn/ は,どうひっくり返っても理解できないスペリングと発音の関係です.単数形は woman = /ˈwʊmən/ となり,まだ理解できるのですが,複数形の women = /ˈwɪmɪn/ は,いったい何なのかという疑問です.以下をお聴きください.
最後のところで英語史の教訓として述べたように,現在不規則にみえるものが歴史的には規則的であり,説明を要しないということは多々あります.むしろ,現在規則的にみえるもののほうが歴史的には問題となってくるパターンが多いのです.
また,今回の話題のように,英語史と音声学の知識はしばしば関わり合います.本格的に英語史を学んでみたいという方は,是非とも音声学もいっしょに学んでください.英語史のおもしろさのかなりの部分は発音の変化にあります.今回取り上げた問題とその周辺については,##223,224の記事セットをどうぞ.
2020-05-05 Tue
■ #4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3) [plural][number][adjective][etymology][suffix][metanalysis][sobokunagimon]
標記の素朴な疑問について2日間の記事 ([2020-05-03-1], [2020-05-04-1]) で論じてきました.今日もその続きです.
Japanese や Chinese は本来形容詞であるから名詞として用いる場合でも複数形の -s がつかないのだという説に対して,いや初期近代英語期には Japaneses や Chineses のような通常の -s を示す複数形が普通に使われていたのだから,そのような形容詞起源に帰する説は受け入れられない,というところまで議論をみてきました.ここで問うべきは,なぜ Japaneses や Chineses という複数形が現代までに廃用になってしまったのかです.
考えられる答えの1つは,これまでの論旨と矛盾するようではありますが,やはり起源的に形容詞であるという意識が根底にあり続け,最終的にはそれが効いた,という見方です.例えば Those students over there are Japanese. と聞いたとき,この Japanese は複数名詞として「日本人たち」とも解釈できますが,形容詞として「日本(人)の」とも解釈できます.つまり両義的です.起源的にも形容詞であり,使用頻度としても形容詞として用いられることが多いとすれば,たとえ話し手が名詞のつもりでこの文を発したとしても,聞き手は形容詞として理解するかもしれません.歴とした名詞として Japaneses が聞かれた時期もあったとはいえ,長い時間の末に,やはり本来の Japanese の形容詞性が勝利した,とみなすことは不可能ではありません.
もう1つの観点は,やはり上の議論と関わってきますが,the English, the French, the Scottish, the Welsh, など,接尾辞 -ish (やその異形)をもつ形容詞に由来する「?人」が -(e)s を取らず,集合的に用いられることとの平行性があるのではないかとも疑われます(cf. 「#165. 民族形容詞と i-mutation」 ([2009-10-09-1])).
さらにもう1つの観点を示すならば,発音に関する事情もあるかもしれません.Japaneses や Chineses では語末が歯摩擦音続きの /-zɪz/ となり,発音が不可能とはいわずとも困難になります.これを避けるために複数形語尾の -s を切り落としたという可能性があります.関連して所有格の -s の事情を参照してみますと,/s/ や /z/ で終わる固有名詞の所有格は Socrates' death, Moses' prophecy, Columbus's discovery などと綴りますが,発音としては所有格に相当する部分の /-ɪz/ は実現されないのが普通です.歯摩擦音が続いて発音しにくくなるためと考えられます.Japanese, Chineses にも同じような発音上の要因が作用したのかもしれません.
音韻的な要因をもう1つ加えるならば,Japanese や Chinese の語末音 /z/ 自体が複数形の語尾を体現するものとして勘違いされたケースが,歴史的に観察されたという点も指摘しておきましょう.OED では,勘違いの結果としての単数形としての Chinee や Portugee の事例が報告されています.もちろんこのような勘違い(専門的には「異分析」 (metanalysis) といいます)が一般化したという歴史的事実はありませんが,少なくとも Japaneses のような歯摩擦音の連続が不自然であるという上記の説に間接的に関わっていく可能性を匂わす事例ではあります.
以上,仮説レベルの議論であり解決には至っていませんが,英語史・英語学の観点から標題の素朴な疑問に迫ってみました.英語史のポテンシャルと魅力に気づいてもらえれば幸いです.
2020-05-04 Mon
■ #4025. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (2) [plural][number][adjective][etymology][suffix][sobokunagimon]
昨日の記事 ([2020-05-03-1]) に引き続き,英語史の授業で寄せられた標題の素朴な疑問について.
昨日の議論では,-ese 語は起源的に形容詞であり,だからこそ名詞という品詞に特有の「複数形」などはとらないのだという説明を見ました.しかし,英語には形容詞起源の名詞はごまんとあり,それらは通例しっかり複数形の -s をとっているのです (ex. Americans, blacks, females, gays, natives) .この説明だけでは満足がいきません.
さらにこの説明にとって都合の悪いことに,初期近代英語には,なんと Japaneses という名詞複数形が用いられていたのです.OED の Japanese, adj. and n. より,該当する語義の項目と例文を挙げてみましょう.
B. n
1. A native of Japan.
Formerly as true noun with plural in -es; now only as an adjective used absolute and unchanged for plural: a Japanese, two Japanese, the Japanese.
. . . .
1655 E. Terry Voy. E.-India 129 I have taken speciall notice of divers Chinesaas, and Japanesaas there.
1693 T. P. Blount Nat. Hist. 105 The Iapponeses prepare [tea]..quite otherwise than is done in Europe.
. . . .
スペリングこそまだ現代風ではありませんが Japanesaas や Iapponeses という語形がみえます.つまり,名詞としての複数形 Americans, blacks, females, gays, natives が当たり前に用いられるのと同じように,Japaneses も当たり前のように用いられていたのです.上の1655年の例文には Chinesaas も用いられており,17世紀にはこれが一般的だったのです.実際,ピューリタン詩人ミルトンも名作『失楽園』にて "1667 J. Milton Paradise Lost iii. 438 Sericana, where Chineses drive With Sails and Wind thir canie Waggons light." のように Chineses を用いています.問題は,なぜ名詞複数形の Japaneses, Chineses が後に廃用となり,単複同形となったのかです.
引き続き,明日の記事で考えていきたいと思います.
2020-05-03 Sun
■ #4024. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (1) [plural][number][adjective][etymology][suffix][latin][french][sobokunagimon]
英語史の授業で寄せられた素朴な疑問です.-ese の接尾辞 (suffix) をもつ「?人」を意味する国民名は,複数形でも -s を付けず,単複同形となります.There are one/three Japanese in the class. のように使います.なぜ複数形なのに -s を付けないのでしょうか.これは,なかなか難しいですが良問だと思います.
現代英語には sheep, hundred, fish など,少数ながらも単複同形の名詞があります.その多くは「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) でみたように古英語の屈折事情にさかのぼり,その古い慣習が現代英語まで化石的に残ったものとして歴史的には容易に説明できます.しかし,-ese は事情が異なります.この接尾辞はフランス語からの借用であり,早くとも中英語期,主として近代英語期以降に現われてくる新顔です.古英語の文法にさかのぼって単複同形を説明づけることはできないのです.
-ese の語源から考えていきましょう.-ese という接尾辞は,まずもって固有名からその形容詞を作る接尾辞です.ラテン語の形容詞を作る接尾辞 -ensis に由来し,その古フランス語における反映形 -eis が中英語に -ese として取り込まれました.つまり,起源的に Japanese, Chinese は第一義的に形容詞として「日本の」「中国の」を意味したのです.
一方,形容詞が名詞として用いられるようになるのは英語に限らず言語の日常茶飯です.Japanese が単独で「日本の言語」 "the Japanese language" や「日本の人(々)」 "(the) Japanese person/people" ほどを意味する名詞となるのも自然の成り行きでした.しかし,現在に至るまで,原点は名詞ではなく形容詞であるという意識が強いのがポイントです.複数名詞「日本人たち」として用いられるときですら原点としての形容詞の意識が強く残っており,形容詞には(単数形と区別される)複数形がないという事実も相俟って,Japanese という形態のままなのだと考えられます.要するに,Japanese が起源的には形容詞だから,名詞だけにみられる複数形の -s が付かないのだ,という説明です.
しかし,この説明には少々問題があります.起源的には形容詞でありながらも後に名詞化した単語は,英語にごまんとあります.そして,その多くは名詞化した以上,名詞としてのルールに従って複数形では -s をとるのが通例です.例えば American, black, female, gay, native は起源的には形容詞ですが,名詞としても頻用されており,その場合,複数形に -s をとります.だとすれば Japanese もこれらと同じ立ち位置にあるはずですが,なぜか -s を取らないのです.起源的な説明だけでは Japanese の単複同形の問題は満足に解決できません.
この問題については,明日の記事で続けて論じていきます.
2020-03-27 Fri
■ #3987. 古ノルド語の影響があり得る言語項目 (2) [old_norse][contact][syntax][word_order][phrasal_verb][plural][link]
「#1253. 古ノルド語の影響があり得る言語項目」 ([2012-10-01-1]) で挙げたリストに,Dance (1735) を参照し,いくつか項目を追加しておきたい.いずれも実証が待たれる仮説というレベルである.
(1) the marked increase in productivity of the derivational verbal affixes -n- (as in harden, deepen) and -l- (e.g. crackle, sparkle)
(2) the rise of the "phrasal verb" (verb plus adverb/preposition) at the expense of the verbal prefix, most persuasively the development of up in an aspectual (completive) function
(3) certain aspects of v2 syntax (including the development of 'CP-v2' syntax in northern Middle English)
(4) the general shift to VO order
上記 (1) については,「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1]) で関連する話題に触れているので,そちらも参照.
(2) については,関連して「#2396. フランス語からの句の借用に対する慎重論」 ([2015-11-18-1]) を参照.
(3), (4) は統語現象だが,とりわけ (4) は大きな仮説である.これについては拙著『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)の第5章第4節でも論じている.さらに以下の記事やリンク先の話題も合わせてどうぞ.
・ 「#1170. 古ノルド語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-10-1])
・ 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
・ 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])
最後にリストに加えるのを忘れていたもう1つの項目があった.
(5) the spread of the s-plural
これは,私自身が詳細に論じている説である.詳しくは Hotta をご覧ください.
・ Dance, Richard. "English in Contact: Norse." Chapter 110 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1724--37.
・ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.
・ Hotta, Ryuichi. The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English. Tokyo: Hituzi Syobo, 2009.
2019-07-21 Sun
■ #3737. 「今日の不規則は昨日の規則」 --- 歴史形態論の原則 [morphology][language_change][reconstruction][comparative_linguistics][indo-european][sobokunagimon][3ps][plural][conjugation]
標題は,英語の歴史形態論においても基本的な考え方である.現代英語で「不規則」と称される形態的な現象の多くは,かつては「規則」の1種だったということである.しばしば逆もまた真なりで,「今日の規則は昨日の不規則」ということも多い.規則 (regular) か不規則 (irregular) かという問題は,共時的には互いの分布により明らかに区別できることが多いので絶対的とはいえるが,歴史的にいえばポジションが入れ替わることも多いという点で相対的な区別である.
この原則を裏から述べているのが,次の Fortson (69--70) の引用である.比較言語学 (comparative_linguistics) の再建 (reconstruction) の手法との関連で,教訓的な謂いとなっている.
A guiding principle in historical morphology is that one should reconstruct morphology based on the irregular and exceptional forms, for these are most likely to be archaic and to preserve older patterns. Regular or predictable forms (like the Eng. 3rd singular present takes or the past tense thawed) are generated using the productive morphological rules of the language, and have no claim to being old; but irregular forms (like Eng. is, sang) must be memorized, generation after generation, and have a much greater chance of harking back to an earlier stage of a language's history. (The forms is and sang, in fact, directly continue forms in PIE itself.
英語において不規則な現象を認識したら「かつてはむしろ規則的だったのかもしれない」と問うてみるとよい.たいてい歴史的にはその通りである.逆に,普段は何の疑問も湧かない規則的な現象に思いを馳せてみてほしい.場合によっては,それはかつての不規則な現象が,どういうわけか歴史の過程で一般化し,広く受け入れられるようになっただけかもしれないと.ここに歴史言語学的発想の極意がある.もちろん,この原則は英語にも,日本語にも,他のどの言語にもよく当てはまる.
「今日の不規則は昨日の規則」の例は,枚挙にいとまがない.上でも触れた例について,英語の歴史から次の話題を参照.
・ 「不規則」な名詞の複数形 (ex. feet, geese, lice, men, mice, teeth, women) (cf. 「#3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」」 ([2019-04-13-1]))
・ 「不規則」な動詞の活用 (ex. sing -- sang -- sung) (cf. 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]))
・ 3単現の -s (cf. 英語史連載第2回「なぜ3単現に -s を付けるのか?」)
・ Fortson IV, Benjamin W. "An Approach to Semantic Change." Chapter 21 of The Handbook of Historical Linguistics. Ed. Brian D. Joseph and Richard D. Janda. Blackwell, 2003. 648--66.
2019-05-06 Mon
■ #3661. 複数所有格のアポストロフィの後に何かが省略されているかのように感じるのは自然 [apostrophe][genitive][plural][punctuation][haplology][folk_etymology][sobokunagimon]
先日「#3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか?」 ([2019-05-01-1]) と題する素朴な疑問を取り上げた.歴史的な観点からの回答として,端的に「何も省略されていない」と答えた.共時的に想像を膨らませれば,kings という複数形に,さらに所有格の 's を付したが,綴字上,末尾が s's とうるさくなりそうなので,簡略表記したのではないか,とみることもできそうだ (cf. haplology) .実際,そのような発想のもとで近代英語期に現行の句読法 (punctuation) が定まっていた可能性は高いのではないかと思われる.もしそうだったとしたら,歴史的な事実に基づくというよりは,共時的な想像に基づく正書法の確立だったということになる.これを非難するつもりもないし,先の記事で述べたように複数形 kings,単数所有格形 king's,複数所有格形 kings' の3つが,せめて表記上は区別されることになったわけだから,結果として便利になったと考えている.ただし,歴史的にはそういうわけではなかった,ということをここでは主張しておきたい.
この辺りの問題については,Jespersen (272) がまさに取り上げている.それを引用するのが手っ取り早いだろう.
16.86. These forms [genitive plurals with -es] (in which e was still pronounced) show that the origin of the ModE gen pl is the old gen pl in -a (which in ME became e) + the ending s from the gen sg, which was added analogically for the sake of greater distinctiveness. The s' in kings' thus is not to be considered a haplological pronunciation of -ses, though some of the early grammarians look upon it as an abbreviation: Bullokar Æsop 225 writes the gen pl ravenzz and crowzz with his two z-letters, which do not denote two different sounds, but are purely grammatical signs, one for the plural and the other for the genitive.---Wallis 1653 writes "the Lord's [sic] House, the House of Lords . . pro the Lords's House", with the remark "duo s in unum coincident." Lane, Key to the Art of Lettters 1700 p. 27: "Es Possessive is often omitted for easiness of pronunciation as . . . the Horses bridles, for the Horsesses bridles."
In dialects and in vg speech the ending -ses is found: Franklin 152 (vg) before gentle folkses doors | GE M 1.10 other folks's children; thus also 1.293, 1.325, 2.7 | id A 251 gentlefolks's servants; ib 403; all in dialect | London schoolboy, in Orig. English 25: I wish my head was same as other boyses. Cf Murray D 164 the bairns's cleose, the færmers's kye, the doags's lugs; Elworthy, Somers. 155 voaksez (not other words, cf GE)
このような解説を読んでいると,標準語の「正史」としては -s's がうるさいから -s' にしたという理屈は採用できないものの,非標準語の歴史という観点からみると,それもあながち間違っているとは言い切れないのかなと思い直したりする.
・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.
2019-05-01 Wed
■ #3656. kings' のような複数所有格のアポストロフィの後には何が省略されているのですか? [sobokunagimon][apostrophe][genitive][plural][punctuation]
令和時代の第1号の記事は,素朴な疑問シリーズより.鋭くも素朴な疑問です.
現代英語では表記上 kings (王たち), king's (王の),kings' (王たちの)と,意味に応じて3種類の書き方が区別されます.発音上はすべて /kɪŋz/ で同じなのですが,綴字・句読法上はしっかりと区別することになっているのです.この表記上の区別は何に由来するのでしょうか.
アポストロフィ (apostrophe) は,典型的に省略を表わすために用いられます.it's は it is の省略ですし,I'm は I am の省略,you're は you are の省略です.しかし,アポストロフィは省略のために用いられるとは限りません.「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]),「#1772. greengrocer's apostrophe」 ([2014-03-04-1]) でみたように,第一義的には省略を表わすために用いられますが,その他の目的にも使われます.標題の疑問も,この観点からみる必要がありそうです.kings, king's, kings' の各々の成り立ちを紹介していきましょう.
古英語で「王たち」を表わす「王」の複数形(主格・対格)は cyningas でした.これが後の複数形 kings になるわけですが,これは古英語 cyningas → 中英語 kinges → 近代英語 kings という音変化の過程を経た結果です.語尾に注目すると,-as や -es という古い複数語尾が母音を消失させ,-s となったわけです.このように通時的には複数語尾の曖昧母音 /ə/ が「消失」したととらえますが,共時的には母音が「省略」されたようにもみえます.複数形の綴字 kings は実はこのように「省略」が絡んでいるにもかかわらず,それを示唆するアポストロフィは用いずに済ませているというわけです.
次に,「王の」を表わす単数所有格形の綴字 king's について考えましょう.古英語では,単数属格(所有格のことを古英語ではこう呼びます)形は cyninges と綴られ,これが中英語にそのまま kinges として受け継がれました.近代英語期にかけて,先の複数形の場合とパラレルに語尾の曖昧母音が消えたため,同じく kings と綴られていました.そのままでもよさそうなものでしたが,後にせめて綴字上は区別しようということなのか,単数所有格形のほうは king's と表記することになりました.今回は曖昧母音 /ə/ が「省略」されているのだから,それを標示するために king's というアポストロフィ付きの書き方になったのだ,と理屈をつけることができます.
最後に「王たちの」を表わす複数属格形の kings' ですが,これにはやや詳しい歴史的な説明が必要です.古英語では複数属格形は cyninga のように -a 語尾をもっていました.しかし,中英語にかけてこの -a が脱落し,代わって単数属格語尾 -es (後に母音消失を経て -s)が複数属格語尾としても用いられるようになったのです.つまり,king(e)s という形態で「王の」と「王たちの」(と「王たち」)を同時に表わしうる状況が出現したのです.そして,近代以降,いずれにせよ発音上は区別できないのですが,せめて書き言葉においては区別しようと,単数所有格形は king's,複数所有格は kings' という書き分けが発達したのでした.
以上をまとめれば次のようになります.複数(主格)の kings は中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」されたとみることができますが,その省略を表わすのにアポストロフィを付けることをしませんでした.これは理に適っていないようにみえます.一方,単数所有格形の king's は,先の複数形と同じく中英語の kinges に由来し,屈折語尾の e が「省略」された結果の形態ですので,アポストロフィを付けた綴字は理に適っているといえそうです.最後に複数所有格形の kings' は,単数所有格形と合一した形態にすぎず,その意味では問題のアポストロフィの後に何かが省略されているわけではありません.
(1) 何かが省略されているのにアポストロフィが付いていない複数形 kings
(2) 何かが省略されているから(という理由で)アポストロフィが付いている(と解せる)単数所有格形 king's
(3) 何も省略されていないのにアポストロフィが付いている複数所有格形 kings'
何だかメチャクチャという感じなのですが,せめて表記上は3者を区別したいという方針だったのでしょう,その意図は理解できます.いずれにせよ,これが英語の正書法なのです.
2019-04-13 Sat
■ #3638.『英語教育』の連載第2回「なぜ不規則な複数形があるのか」 [notice][hel_education][elt][sobokunagimon][plural][number][rensai][link]
『英語教育』の英語史連載記事「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ」が,前回の4月号より始まっています.昨日発売された5月号では,第2回の記事として「なぜ不規則な複数形があるのか」という素朴な疑問を取りあげています.是非ご一読ください.
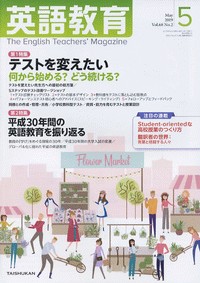
名詞複数形の歴史は,私のズバリの専門分野です(博士論文のタイトルは The Development of the Nominal Plural Forms in Early Middle English でした).そんなこともあり,本ブログでも複数形の話題は plural の記事で様々に取りあげてきました.今回の連載記事の内容ととりわけ関係するブログ記事へのリンクを以下に張っておきます.
・ 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])
・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1])
・ 「#157. foot の複数はなぜ feet か」 ([2009-10-01-1])
・ 「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1])
・ 「#337. egges or eyren」 ([2010-03-30-1])
・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1])
・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1])
・ 「#3586. 外来複数形」 ([2019-02-20-1])
英語の複数形の歴史というテーマについても,まだまだ研究すべきことが残っています.英語史は奥が深いです.
2017年に連載した「現代英語を英語史の視点から考える」の第1回「「ことばを通時的にみる 」とは?」でも複数形の歴史を扱いましたので,そちらも是非ご一読ください.
・ 堀田 隆一 「英語指導の引き出しを増やす 英語史のツボ 第2回 なぜ不規則な複数形があるのか」『英語教育』2019年5月号,大修館書店,2019年4月12日.62--63頁.
2019-02-22 Fri
■ #3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か? [plural][spelling][corpus]
-o で終わる加算名詞から規則的な複数形を作る場合に,綴字上 -s のみを付す pianos タイプと,-es とする potatoes タイプが区別される.
LGSWE (285) は,LGSWE Corpus によって両タイプの分布を調査した.両語尾の間で揺れを示すものもあるので,80%以上の生起率を基準にして,いずれかのタイプかに割り振ったリストである.別途『徹底例解ロイヤル英文法』から補った類例( * を付した)も含めつつ,以下に列挙しよう.
・ pianos タイプ: *autos, avocados, casinos, commandos, concertos, discos, *dynamos, embryos, Eskimos, *ghettos, jumbos, kilos, memos, pesos, photos, pianos, portfolios, radios, scenarios, shampoos, solos, stereos, studios, taboos, tacos, tattoos, *torsos, trios, twos, videos, weirdos, zeros, zoos
・ potatoes タイプ: buffaloes, cargoes, echoes, heroes, mangoes, mosquitoes, mottoes, negroes, potatoes, tomatoes, tornadoes, torpedoes, vetoes, volcanoes
一般論をいえば,-s のみを付す pianos タイプが原則である.特に,略語に由来する -o 語や最近の新語として加わった -o 語は -s で複数形を作るのがデフォルトである.また,語末が「母音字+ o」となる場合にも,綴字配列の都合と思われるが,-s のみを付けるのが規則である (e.g. bamboos, cameos, cuckoos, curios, folios, radios, studios, trios) .
一方,potatoes タイプはどちらかといえば「例外」の側になるわけだが,このタイプには英語化した度合いの比較的強い,日常語が含まれるので注意を要する.
また,-s と -es の間で揺れを示す名詞も少なくない.『徹底例解ロイヤル英文法』では,例として banjo(e)s, buffalo(e)s, cargo(e)s, fresco(e)s, ghetto(e)s, grotto(e)s, halo(e)s, mango(e)s, manifesto(e)s, mosquito(e)s, motto(e)s, tornado(e)s, volcano(e)s, zero(e)s が挙げられている.先に挙げたリストと重複する単語もあることから,-o 語の複数形をもっと細かく調査すれば,実際にはさらに広範な揺れが観察されるのかもしれない.
なお,この話題と関連して,単数形 potato の綴りを potatoe と誤って覚えていたアメリカ元副大統領 Dan Quayle のスキャンダル,通称「potato 事件」について,Horobin (2--3) あるいはその拙訳 (16--17) を参照.1文字のスペリング・ミス(だけではないが)で,政治生命が断たれることもあるという驚くべき事例である.pianos か potatoes かという問題は決して侮れない.
・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.
・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.
・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.
・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.
2019-02-20 Wed
■ #3586. 外来複数形 [plural][latin][greek][french][italian]
英語の不規則複数形をとる名詞には,外来複数形と呼ばれる一群がある.主として近代英語以降にラテン語,ギリシア語,フランス語,イタリア語などから借用された学術・専門語で,原語における複数形を保っているものだ.現代にかけて,英語の規則的な語尾 -(e)s を取るようになったものも少なくないが,それらも含めて代表的な単語を,『徹底例解ロイヤル英文法』に依拠して以下に示そう.
特にラテン系 -us 名詞に見られる20世紀中の規則複数化の流れについては,Hotta の拙論を参照(関連して,「#121. octopus の複数形」 ([2009-08-26-1]),「#161. rhinoceros の複数形」 ([2009-10-05-1]) も).
1. ラテン語系の名詞
1.1 -us で終わる語
a) -us [əs] → -i [aɪ]
alumnus (男子卒業生) → alumni
bacillus (バチルス菌) → bacilli
esophagus (食堂) → esophagi
locus (軌跡) → loci, loca
stimulus (刺激) → stimuli
b) 規則複数語尾 -es をつけるもの
apparatus (装置) → apparatuses
bonus (ボーナス) → bonuses
campus (校庭) → campuses
caucus (幹部会議) → caucuses
chorus (コーラス) → choruses
circus (サーカス) → circuses
impetus (起動力) → impetuses
minus (負の数,マイナス符号) → minuses
prospectus (学校などの案内) → prospectuses
sinus (洞) → sinuses
status (地位) → statuses
c) -us → -i の変化と -es の両様のもの
cactus (サボテン) → cacti, cactuses
cirrus (巻雲) → cirri, cirruses
cumulus (積雲) → cumuli, cumuluses
focus (焦点) → foci, focuses
fungus (きのこなどの菌類) → fungi, funguses
genius (守護神;天才) → genii (守護神),geniuses (天才)
nimbus (乱雲) → nimbi, nimbuses
nucleus (原子核) → nuclei, nucleuses
radius (半径) → radii, radiuses
stratus (層雲) → strati, stratuses
syllabus (教授細目) → syllabi, syllabuses
terminus (末端,終着駅) → termini, terminuses
d) その他
corpus (集大成,言語資料) → corpora, corpuses
genus (属) → genera, genuses
1.2 -a で終わる語
a) -a [ə] → -ae [iː]
alga (藻) → algae
alumna (女子卒業生) → alumnae
larva (幼虫) → larvae
b) 規則複数語尾 -s をつけるもの
area (地域) → areas
arena (闘技場) → arenas
dilemma (ジレンマ) → delemmas
diploma (学位免状) → diplomas [まれに diplomata もあり]
drama (ドラマ) → dramas
era (時代) → eras
c) -a → -ae と -s の両様のもの
antenna (触角;アンテナ) → antennae (触覚), antennas (アンテナ)
formula (公式) → formulae, formulas
nebula (星雲) → nebulae, nebulas
vertebra (脊椎) → vertebrae, vertebras
1.3 -um で終わる語
a) -um [əm] → -a [ə]
addendum (付録) → addenda
bacterium (バクテリア) → bacteria
corrigendum (ミスプリント) → corrigenda (正誤表)
datum (データ) → data
desideratum (切実な要求) → desiderata
erratum (誤植) → errata (正誤表)
ovum (卵子) → ova
b) 規則複数語尾 -s をつけるもの
album (アルバム) → albums
chrysanthemum (菊) → chrysanthemums
forum (討論会) → forums [まれに fora もあり]
museum (博物館) → museums
premium (割り増し金) → premiums
stadium (スタジアム) → stadiums [まれに stadia もあり]
c) -um → -a と -s の両様のもの
aquarium (水族館) → aquaria, aquariums
curriculum (教育課程) → curricula, curriculums
maximum (最大限) → maxima, maximums
medium (媒介物) → media, mediums [media が単数形,medias が複数形という用法もあり]
memorandum (メモ) → memoranda, memorandums
millennium (千年間) → millennia, millenniums
minimum (最小限) → minima, minimums
moratorium (支払い猶予期間) → moratoria, moratoriums
podium (指揮台,葉柄) → podia, podiums
referendum (国民投票) → referenda, referendums
spectrum (スペクトル) → spectra, spectrums
stratum (地層) → strata, stratums
symposium (シンポジウム) → symposia, symposiums
ultimatum (最後通告) → ultimata, ultimatums
1.4 -ex, -ix で終わる語
a) -ex [ɛks], -ix [ɪks] → -ices [ɪsiːz]
codex (古写本) → codices
b) -ex, -ix → -ices と -es の両様のもの
apex (頂点) → apices, apexes
appendix (付録,虫垂) → appendices, appendixes [「虫垂」の意味の複数形は appendixes]
index (指標) → indices, indexes [「索引」の意味の複数形は indexes]
matrix (母体,行列) → matrices, matrixes
vortex (渦) → vortices, vortexes
2. ギリシャ語系の名詞の複数形
2.1 -is [ɪs] で終わる語
a) 語尾は -es [iːz] になる.
analysis (分析) → analyses
axis (軸) → axes [ax(e) 「斧」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]
basis (理論的基礎) → bases [base 「基地」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]
crisis (危機) → crises
diagnosis (診断) → diagnoses
ellipsis (省略) → ellipses [ellipse 「長円」の複数 (発音は [ɪz])ともなることに注意]
hypothesis (仮説) → hypotheses
oasis (オアシス) → oases
paralysis (麻痺) → paralyses
parenthesis (丸かっこ) → parentheses
synopsis (概要) → synopses
synthesis (総合,合成) → syntheses
thesis (論文) → theses
b) 規則複数語尾 -es をつけるもの
metropolis (首都,大都会) → metropolises
2.2 -on で終わる語
a) -on [ən] → -a [ə]
criterion (判断の基準) → criteria
phenomenon (現象) → phenomena
b) 規則複数語尾 -s をつけるもの
electron (電子) → electrons
neutron (中性子) → neutrons
proton (陽子) → protons
c) -on → -a と -s の両様のもの
automaton (自動装置,ロボット) → automata, automatons
ganglion (神経節) → ganglia, ganglions
3. フランス語系の名詞の複数形
3.1 -eau, -eu → -eaux, -eux
adieu [əˈdjuː] (別れ) → adieux [əˈdjuːz] または adieus
bureau [ˈbjʊəroʊ] (事務局) → bureaux [ˈbjʊəroʊz] または bureaus
plateau [ˈplætou] (高原) → plateaux [ˈplætoʊz] または plateaus
tableau [ˈtæbloʊ] (絵) → tableaux [ˈtæbloʊz] または tableaus
3.2 単複同 (ただし複数のときのみ -s [z] を発音する)
corps (団) → corps
chassis [ˈʃæsi(ː)] (自動車の車台,シャシー) → chassis
faux pas [foʊ pɑː] (エチケットに反する失敗) → faux pas
rendezvous [ˈrɑːndəˌvuː] (約束による会合) → rendezvous
4. イタリア語系の名詞の複数形
4.1 -o → -i
libretto (脚本) → libretti [-iː] または librettos
tempo (テンポ) → tempi [-iː] または tempos
virtuoso (巨匠) → virtuosi [-iː] または virtuosos
4.2 規則複数語尾 -s をつけるもの
solo (独奏[唱]) → solos
soprano (ソプラノ) → sopranos
・ 綿貫 陽(改訂・著);宮川幸久, 須貝猛敏, 高松尚弘(共著) 『徹底例解ロイヤル英文法』 旺文社,2000年.
・ Hotta, Ryuichi. "Thesauri or Thesauruses? A Diachronic Distribution of Plural Forms for Latin-Derived Nouns Ending in -us." Journal of the Faculty of Letters: Language, Literature and Culture. 106 (2010): 117--36.
2018-07-01 Sun
■ #3352. scarves と hooves [plural][lmode][speed_of_change]
「#3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3)」 ([2018-05-10-1]) で,/f/ で終わる名詞をいくつか挙げ,その複数形が -f か -ves かのいずれを取るか,あるいは両者の示す揺れについて簡単にまとめた.
先日 Mondorf による後期近代英語期の形態論に関する文章を読んでいて,この時期の間に「不規則形」の scarves, hooves が拡張し,「規則形」の scarfs, hoofs が相対的に減少してきているという記述に出会った.特に scarves は,18世紀には20%ほどの生起率だったが,20世紀中に80%近くまで大きく躍進した.hooves は18世紀の0%から19世紀の1桁台の比率を経て,20世紀中には30%強まで数値を延ばしてきたようだ.
語幹を変形させずに単純に -s を付すことを「規則的」と見るのであれば,これらの名詞で起こっていることは「不規則化」となるが,語幹末の -f を -v とした上で -es というパターンは「小規則」として確かに存在するともいえる.つまり,この現象は見方によっては「不規則化」とも「小規則化」とも,場合によっては「規則化」とも解しうることになる.このような視点の問題は,分析者が共時・通時のいずれの観点をとるかによっても微妙な影響を受けるので,取り扱いが難しい.
しかし,言語変化はこのような過程の繰り返しではある.1つの大規則に収められる方向で進んでいるかと思いきや,気づけば複数の小規則が林立している.ところが,だからといって言語体系が著しく無秩序になるかといえばそうもならず,むしろ互いの分布がある程度整理され,別の秩序が生み出される,等々.大規則と小規則の関係については,「#1596. 分極の仮説」 ([2013-09-09-1]) を参照されたい.
・ Mondorf, Britta. "Late Modern English: Morphology." Chapter 53 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 843--69.
2018-05-11 Fri
■ #3301. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (4) [sobokunagimon][genitive][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection][paradigm][clitic]
3日間にわたり標題の話題を発展させてきた ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1], [2018-05-10-1]) .今回は第4弾(最終回)として,この問題にもう一ひねりを加えたい.
wolves (および間接的に wives)の背景には,古英語の男性強変化名詞の屈折パターンにおいて,複数主格(・対格)形として -as が付加されるという事情があった.これにより古英語 wulf が wulfas となり,f は有声音に挟まれるために有声化するのだと説明してきた.wīf についても,本来は中性強変化という別のグループに属しており,自然には wives へと発達しえないが,後に wulf/wulfas タイプに影響され,類推作用 (analogy) により wives へと帰着したと説明すれば,それなりに納得がいく.
このように,-ves の複数形については説得力のある歴史的な説明が可能だが,今回は視点を変えて単数属格形に注目してみたい.機能的には現代英語の所有格の -'s に連なる屈折である.以下,単数属格形を強調しながら,古英語 wulf と wīf の屈折表をあらためて掲げよう.
|
|
両屈折パターンは,複数主格・対格でこそ異なる語尾をとっていたが,単数属格では共通して -es 語尾をとっている.そして,この単数属格 -es を付加すると,語幹末の f は両サイドを有声音に挟まれるため,発音上は /v/ となったはずだ.そうだとするならば,現代英語でも単数所有格は,それぞれ *wolve's, *wive's となっていてもよかったはずではないか.ところが,実際には wolf's, wife's なのである.複数形と単数属格形は,古英語以来,ほぼ同じ音韻形態的条件のもとで発展してきたはずと考えられるにもかかわらず,なぜ結果として wolves に対して wolf's,wives に対して wife's という区別が生じてしまったのだろうか.(なお,現代英語では所有格形に ' (apostrophe) を付すが,これは近代になってからの慣習であり,見た目上の改変にすぎないので,今回の議論にはまったく関与しないと考えてよい(「#582. apostrophe」 ([2010-11-30-1]) を参照).)
1つには,属格標識は複数標識と比べて基体との関係が疎となっていったことがある.中英語から近代英語にかけて,属格標識の -es は屈折語尾というよりは接語 (clitic) として解釈されるようになってきた(cf. 「#1417. 群属格の発達」 ([2013-03-14-1])).換言すれば,-es は形態的な単位というよりは統語的な単位となり,基体と切り離してとらえられるようになってきたのである.それにより,基体末尾子音の有声・無声を交替させる動機づけが弱くなっていったのだろう.こうして属格表現において基体末尾子音は固定されることとなった.
それでも中英語から近代英語にかけて,いまだ -ves の形態も完全に失われてはおらず,しばしば類推による無声の変異形とともに並存していた.Jespersen (§16.51, pp. 264--65) によれば,Chaucer はもちろん Shakespeare に至っても wiues などが規則的だったし,それは18世紀終わりまで存続したのだ.calues も Shakespeare で普通にみられた.特に複合語の第1要素に属格が用いられている場合には -ves が比較的残りやすく,wive's-jointure, staves-end, knives-point, calves-head などは近代でも用いられた.
しかし,これらとて現代英語までは残らなかった.属格の -ves は,標準語ではついえてしまったのである.いまや複数形の wolves など少数の語形のみが,古英語の音韻規則の伝統を引く最後の生き残りとして持ちこたえている.
・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2018-05-10 Thu
■ #3300. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (3) [sobokunagimon][plural][consonant][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][inflection]
2日間の記事 ([2018-05-08-1], [2018-05-09-1]) で,標記の素朴な疑問を題材に,英語史の奥深さに迫ってきた.今回は第3弾.
古英語の wulf (nom.acc.sg.)/wulfas (nom.acc.pl) を原型とする wolf (sg.)/wolves (pl.) という単複ペアのモデルが,類推作用 (analogy) によって,歴史的には wulf と異なる屈折クラスに属する,語尾に -f をもつ他の名詞にも拡がったことを見た.leaf/leaves や life/lives はそれにより説明される.
しかし,現代英語の現実を眺めると,語尾に -f をもつ名詞のすべてが複数形において -ves を示すわけではない.例えば,roof/roofs, belief/beliefs などが思い浮かぶが,これらは完全に「規則的」な複数形を作っている.とりわけ roof などは,古英語では hrōf という形態で,まさに wulf と同じ男性強変化グループに属していたのであり,正統には古英語で実際に用いられていた hrōfas が継承され,現在は *rooves となっていて然るべきなのである.ところが,そうなっていない(しかし,rooves については以下の表も参照).
ここで起こったことは,先に挙げたのとは別種の類推作用である.wife などの場合には,類推のモデルとなったのは wolf/wolves のタイプだったのだが,今回の roof を巻き込んだ類推のモデルは,もっと一般的な,例えば stone/stones, king/kings といったタイプであり,語尾に -s をつければ済むというという至極単純なタイプだったのである.同様にフランス借用語の grief, proof なども,もともとのフランス語での複数形の形成法が単純な -s 付加だったこともあり,後者のモデルを後押し,かつ後押しされたことにより,現在その複数形は griefs, proofs となっていると理解できる.
語尾に -f をもつ名詞群が,類推モデルとして wolf/wolves タイプを採用したか,あるいは stone/stones タイプを採用したかを決める絶対的な基準はない.個々の名詞によって,振る舞いはまちまちである.歴史的に両タイプの間で揺れを示してきた名詞も少なくないし,現在でも -fs と -ves の両複数形がありうるという例もある.類推作用とは,それくらいに個々別々に作用するものであり,その意味でとらえどころのないものである.
一昨日の記事 ([2018-05-08-1]) では,wolf の複数形が wolves となる理由を聞いてスッキリしたかもしれないが,ここにきて,さほど単純な問題ではなさそうだという感覚が生じてきたのではないだろうか.現代英語の現象を英語史的に考えていくと,往々にして問題がこのように深まっていく.
以下,主として Jespersen (Modern, §§16.21--16.25 (pp. 258--621)) に基づき,語尾に -f を示すいくつかの語の,近現代における複数形を挙げ,必要に応じてコメントしよう(さらに多くの例,そしてより詳しくは,Jespersen (Linguistic, 374--75) を参照).明日は,懲りずに第4弾.
| 単数形 | 複数形 | コメント |
|---|---|---|
| beef | beefs/beeves | |
| belief | beliefs | 古くは believe (sg.)/believes (pl.) .この名詞は,OE ġelēafa と関連するが,語尾の母音が脱落して,f が無声化した.16世紀頃には believe (v.) と belief (n.) が形態上区別されるようになり,名詞 -f が確立したが,これは grieve (v.)/grief (n.), prove (v.)/proof (n.) などの類推もあったかもしれない. |
| bluff | bluffs | |
| brief | briefs | |
| calf | calves | |
| chief | chiefs | |
| cliff | cliffs | 古くは cleves (pl.) も. |
| cuff | cuffs | |
| delf | delves | 方言として delfs (pl.) も.また,標準英語で delve (sg.) も. |
| elf | elves | まれに elfs (pl.) や elve (sg.) も. |
| fief | fiefs | |
| fife | fifes | |
| gulf | gulfs | |
| half | halves | 「半期(学期)」の意味では halfs (pl.) も. |
| hoof | hoofs | 古くは hooves (pl.) . |
| knife | knives | |
| leaf | leaves | ただし,ash-leafs (pl.) "ash-leaf potatoes". |
| life | lives | 古くは lyffes (pl.) など. |
| loaf | loaves | |
| loof | looves/loofs | loove (sg.) も. |
| mastiff | mastiffs | 古くは mastives (pl.) も. |
| mischief | mischiefs | 古くは mischieves (pl.) も. |
| oaf | oaves/oafs | |
| rebuff | rebuffs | |
| reef | reefs | |
| roof | roofs | イングランドやアメリカで rooves (pl.) も. |
| safe | safes | |
| scarf | scarfs | 18世紀始めからは scarves (pl.) も. |
| self | selves | 哲学用語「自己」の意味では selfs (pl.) も. |
| sheaf | sheaves | |
| shelf | shelves | |
| sheriff | sheriffs | 古くは sherives (pl.) も. |
| staff | staves/staffs | 「棒きれ」の意味では staves (pl.) .「人々」の意味では staffs (pl.) .stave (sg.) も. |
| strife | strifes | |
| thief | thieves | |
| turf | turfs | 古くは turves (pl.) も. |
| waif | waifs | 古くは waives (pl.) も. |
| wharf | warfs | 古くは wharves (pl.) も |
| wife | wives | 古くは wyffes (pl.) など.housewife "hussy" でも housewifes (pl.) だが,Austen ではこの意味で huswifes も. |
| wolf | wolves |
・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part VI. Copenhagen: Ejnar Munksgaard, 1942.
・ Jespersen, Otto. Linguistica: Selected Papers in English, French and German. Copenhagen: Levin & Munksgaard, 1933.
2018-05-09 Wed
■ #3299. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (2) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][analogy][number][conjugation][inflection][paradigm]
昨日の記事 ([2018-05-08-1]) で,wolf (sg.) に対して wolves (pl.) となる理由を古英語の音韻規則に照らして説明した.これにより,関連する他の -f (sg.)/ -ves (pl.) の例,すなわち calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などもきれいに説明できると思うかもしれない.しかし,英語史はそれほどストレートで美しいものではない.言語という複雑なシステムがたどる歴史は,一癖も二癖もあるのが常である.
例えば,wife (sg.)/wives (pl.) の事例を取り上げよう.この名詞は,古英語では wīf という単数主格(見出し語)形を取っていた(当時の語義は「妻」というよりも「女性」だった).f は,左側に有声母音こそあれ右側には何もないので,「有声音に挟まれている」わけではなく,デフォルトの /f/ で発音される.そして,次に来る説明として予想されるのは,「ところが,複数主格(・対格)形では wīf に -as の屈折語尾が付くはずであり,f は有声音に挟まれることになるから,/v/ と有声音化するのだろう」ということだ.
しかし,そうは簡単にいかない.というのは,wulf の場合はたまたま男性強変化というグループに属しており,昨日の記事で掲げた屈折表に従うことになっているのだが,wīf は中性強変化というグループに属する名詞であり,古英語では異なる屈折パターンを示していたからだ.以下に,その屈折表を掲げよう.
| (中性強変化名詞) | 単数 | 複数 |
|---|---|---|
| 主格 | wīf | wīf |
| 対格 | wīf | wīf |
| 属格 | wīfes | wīfa |
| 与格 | wīfe | wīfum |
中性強変化の屈折パターンは上記の通りであり,このタイプの名詞では複数主格(・対格)形は単数主格(・対格)形と同一になるのである.現代英語に残る単複同形の名詞の一部 (ex. sheep) は,古英語でこのタイプの名詞だったことにより説明できる(「#12. How many carp!」 ([2009-05-11-1]) を参照).とすると,wīf において,単数形の /f/ が複数形で /v/ に変化する筋合いは,当然ながらないことになる./f/ か /v/ かという問題以前に,そもそも複数形で s など付かなかったのだから,現代英語の wives という形態は,上記の古英語形からの「直接の」発達として理解するわけにはいかなくなる.実は,これと同じことが leaf/leaves と life/lives にも当てはまる.それぞれの古英語形 lēaf と līf は,wīf と同様,中性強変化名詞であり,複数主格(・対格)形はいわゆる「無変化複数」だったのだ.
では,なぜこれらの名詞の複数形が,現在では wolves よろしく leaves, lives となっているのだろうか.それは,wīf, lēaf, līf が,あるときから wulf と同じ男性強変化名詞の屈折パターンに「乗り換えた」ことによる.wulf のパターンは確かに古英語において最も優勢なパターンであり,他の多くの名詞はそちらに靡く傾向があった.比較的マイナーな言語項が影響力のあるモデルにしたがって変化する作用を,言語学では類推作用 (analogy) と呼んでいるが,その典型例である(「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1]) を参照).この類推作用により,歴史的な複数形(厳密には複数主格・対格形)である wīf, lēaf, līf は,wīfas, lēafas, līfas のタイプへと「乗り換えた」のだった.その後の発展は,wulfas と同一である.
ポイントは,現代英語の複数形の wives, leaves, lives を歴史的に説明しようとする場合,wolves の場合ほど単純ではないということだ.もうワン・クッション,追加の説明が必要なのである.ここでは,古英語の「摩擦音の有声化」という音韻規則は,まったく無関係というわけではないものの,あくまで背景的な説明というレベルへと退行する.本音をいえば,昨日と今日の記事の標題には,使えるものならば wolf (sg.)/wolves よりも wife (sg.)/wives (pl.) を使いたいところではある.wife/wives のほうが頻度も高いし,両サイドの有声音が母音という分かりやすい構成なので,説明のための具体例としては映えるからだ.だが,上記の理由で,摩擦音の有声化の典型例として前面に出して使うわけにはいかないのである.英語史上,ちょっと「残念な事例」ということになる.
とはいえ,wives は,類推作用というもう1つのきわめて興味深い言語学的現象に注意を喚起してくれた.これで英語史の奥深さが1段深まったはずだ.明日は,関連する話題でさらなる深みへ.
2018-05-08 Tue
■ #3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1) [sobokunagimon][plural][consonant][oe][phonetics][fricative_voicing][number][v][conjugation][inflection][paradigm]
標題は,「#1365. 古英語における自鳴音にはさまれた無声摩擦音の有声化」 ([2013-01-21-1]) で取り上げ,「#1080. なぜ five の序数詞は fifth なのか?」 ([2012-04-11-1]) や「#2948. 連載第5回「alive の歴史言語学」」 ([2017-05-23-1]) でも具体的な例を挙げて説明した問題の,もう1つの応用例である.wolf の複数形が wolves となるなど,単数形 /-f/ が複数形 /-vz/ へと一見不規則に変化する例が,いくつかの名詞に見られる.例えば,calf/calves, elf/elves, half/halves, leaf/leaves, life/lives, loaf/loaves, knife/knives, self/selves, sheaf/sheaves, shelf/shelves, thief/thieves, wife/wives などである.これはどういった理由だろうか.
古英語では,無声摩擦音 /f, θ, s/ は,両側を有声音に挟まれると自らも有声化して [v, ð, z] となる音韻規則が確立していた.この規則は,適用される音環境の条件が変化することもあれば,方言によってもまちまちだが,中英語以降でもしばしばお目にかかるルールである.必ずしも一貫性を保って適用されてきたわけではないものの,ある意味で英語史を通じて現役活動を続けてきた根強い規則といえる.摩擦音の有声化 (fricative_voicing) などという名前も与えられている.
今回の標題に照らし,以下では /f/ の場合に説明を絞ろう.wolf (狼)は古英語では wulf という形態だった.この名詞は男性強変化というグループに属する名詞で,格と数に応じて以下のように屈折した.
| (男性強変化名詞) | 単数 | 複数 |
|---|---|---|
| 主格 | wulf | wulfas |
| 対格 | wulf | wulfas |
| 属格 | wulfes | wulfa |
| 与格 | wulfe | wulfum |
単数主格(・対格)の形態,いわゆる見出し語形では wulf には屈折語尾がつかず,f の立場からみると,確かに左側に有声音の l はあるものの右側には何もないので「有声音に挟まれている」環境ではない.したがって,この f はそのままデフォルトの /f/ で発音される.しかし,表のその他の6マスでは,いずれも母音で始まる何らかの屈折語尾が付加しており,問題の f は有声音に挟まれることになる.ここで摩擦音の有声化規則が発動し,f は発音上 /f/ から /v/ へと変化する.古英語では綴字上 <f> と <v> を使い分ける慣習はない(というよりも <v> の文字が存在しない)ので,文字上は無声であれ有声であれ <f> のままである(文字 <v> の発達については「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1]) を参照).この屈折表の複数主格(・対格)の wulfas が,その後も生き残って現代英語における「複数形」として伝わったわけだ.この複数形では,綴字こそ wolves と書き改められたが,発音上は古英語の /f/ ならぬ /v/ がしっかり残っている.
このように,古英語の音韻規則を念頭におけば,現代の wolf/wolves の関係はきれいに説明できる.現代英語としてみると確かに「不規則」と呼びたくなる関係だが,英語史を参照すれば,むしろ「規則的」なのである.このような気づきこそが,英語史を学ぶ魅力であり,英語史の奥深さといえる.
しかし,英語史の奥深さはここで止まらない.上の説明で納得して終わり,ではない.ここから発展してもっとおもしろく,不可思議に展開していくのが英語史である.新たな展開については明日以降の記事で.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow