2024-07-23 Tue
■ #5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][borrowing][norman_french][doublet][hybrid][lexicology]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.本日『ふらんす』8月号が刊行されました.連載としては第5回となります.
今回は前回の「フランス借用語の大流入」に引き続いての話題です.大流入の結果,英語語彙にどのような衝撃がもたらされたのか,に迫ります.以下の4つの小見出しのもとにエッセイを書いています.
1. 単語借用と語彙体系の変化
中英語期にフランス語からの大量の単語借用があり,英語の語彙体系に大きな影響を与えました.これにより,英語の語彙のあり方が大きく変化しました.
2. 死語となった本来の英単語
フランス語からの借用語により,既存の英単語が置き換えられ死語となるケースが多くありました.例えば「おじ」を意味する ēam が uncle に,「嫉妬」を意味する anda が envy に置き換えられるなどしました.
3. ノルマン・フランス語と中央フランス語
初期の借用語はノルマン方言から,後期はパリの中央フランス語から入りました.これにより,同じ語源を持つ単語が異なる形で英語に入り,2重語 (doublet) として共存するようになりました.
4. 英仏ハイブリッド語
フランス語の語形成に慣れた英語は,フランス語由来の接辞を英語本来の単語に付けて新しい単語を作り出しました.これらは英仏要素を含むハイブリッド語として英語に定着しました.
過去4回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりお読みください.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁.
2023-04-17 Mon
■ #5103. 支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない [linguistic_imperialism][linguistic_ideology][norman_conquest][norman_french][link][review]
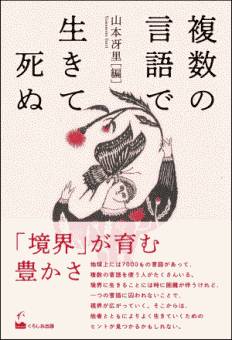
英語史において,1066年のノルマン征服はきわめて大きなインパクトをもつ.その意義について,本ブログでも norman_conquest の多くの記事で取り上げてきた.1066年の後,確かに英語はフランス語の支配下に置かれ,その社会的地位は失墜したものの,英語話者のほぼすべてが英語話者にとどまり,フランス語化したわけではなかった.征服者であるノルマン人自身はイングランド支配に際して自らの言語であるノルマン・フランス語を使い続けたが,それを被征服者であるイングランド人に(少なくともイングランド人一般に)押しつけようとした形跡はない.
支配者が自らの言語を被支配者に押しつけてきた例は,確かに古今東西みられる.実際,大日本帝国は植民地に日本語を押しつけてきた.しかし,支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない.
山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)に,次のようにある (pp. 9--10) .
しかし,植民地に暮らす人すべてに対して自らの言語を強制することは,支配者側にとっても利益ばかりにつながるわけではなく,多大なコストと相当のリスクを伴う行為でもあって,ゆえにそう頻繁には採用されない.コストとは教育や管理にかかる時間と費用だ.リスクは,言語を押しつけられた側からの反発や,支配者側の言語を身につけた被支配者側の者が,その言語を武器として,支配者に対して批判のできるような,より広い舞台に立つ可能性である.だからこそ,過去に列強と呼ばれる国々が行なった植民地政策においては,被支配者グループのすべてではなく,ただ上流階級,管理層のみを対象に支配者側の言語教育を行う場合もあったし(したがって,管理層に入りたければ支配者側の言語を習得することが必須となった),より広く言語教育を供給するにしても,庶民に対しては「読み書き」を軽視または実質的に禁じ,「話し聞く」ことばかりを推奨する土地もあった (Migge & Léglise 2007) .
本ブログでは言語帝国主義 (linguistic_imperialism) に関わる議論を多く取り上げてきたが,とりわけ今回の話題に関係するものを挙げておきたい.
・ 「#1461. William's writ」 ([2013-04-27-1])
・ 「#5041. 英語帝国主義の議論のために」 ([2023-02-14-1])
・ 「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])
・ 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])
・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.
2020-10-01 Thu
■ #4175. 「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事紹介 [french][history_of_french][norman_conquest][norman_french][sobokunagimon][hel_education][notice]
三省堂のことばのコラムのシリーズとして,「歴史で謎解き!フランス語文法(フランス語教育 歴史文法派)」が展開しています.今回は,英語史との関連でその第18回「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事をご紹介します.英語史の学徒として実に読みやすく,英仏海峡の向こうから英語史を記述してもらったようで,こそばゆいような,瑞々しいような気持ちになりました.英語とフランス語に関心のあるすべての方に一読をお薦めします.
英語史の専門家がフランス語史を学ぶことは重要ですし,フランス語史に通じている方より英語史に関心を示してもらえるのは,お互いにメリットのあることだと思っています.学界的にも,この辺りの相互交流が欠如しているのは残念なことだと思っています.中世ヨーロッパにおいては現代のような厳密な国境意識はなく,言語的にいえば multilingual な世界が常態だったわけですから.今回の記事で扱われている時期の「イギリス」でも,「国語」が英語だったのか,フランス語だったのか,はたまたラテン語だったのか,はっきりしません.西欧近代諸国の「標準語」とて,背後にあるイギリス,フランス,ドイツ等の主権国家の「主たる言語」が前面に出てきたにすぎないわけです.
21世紀の現在,英語が世界的な言語となったのは歴史の偶然にすぎません.英語という言語の本質的な力によるものではなく,主に18世紀から20世紀まで続いたイギリス,アメリカという二大国家の覇権のなせるわざです.
そのような覇権的な動きが始まる近代より前の時代に焦点を移せば,ヨーロッパには「主権国家」もなければ「国語」も,厳密な意味においてはありませんでした.英語もヨーロッパのありふれた言語の1つにすぎませんでした.英語が大陸のゲルマン語にルーツを持ちつつも,同じく大陸のラテン系のロマンス諸語と長らく接触してきた歴史を,この機会にあらためて顧みてはいかがでしょうか.
2020-09-09 Wed
■ #4153. なぜ w の文字は v が2つなのに double-u なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]
hellog ラジオ版の第23回は,しばしば寄せられる <w> の文字の呼称に関する疑問です.英語ではこの文字は "double-u "と呼ばれますが,フランス語などを学んだことがある方は,"double-v" と呼ばれているのを知っているかと思います.見た目は確かに v が2つですね.では,英語ではなぜ u が2つという呼び方をするのでしょうか.背景には,なかなか興味深い歴史があります.
英語がラテン語からローマ字一式を借りたときに,そのなかに <w> の文字がなかったのが,そもそもの出発点です./w/ 音を多用する英語は,相当する文字がなくては不便で仕方がないので,自ら文字を考案することにしました.ローマ字一式には <u> はあった(ただし <v> はなかった)ので,それを2つ合わせて <uu> とすることで,この難局を乗り切ろうとしました.一方,英語は以前より使っていたルーン文字から /w/ 音を表わす <ƿ> (wynn) を流用する慣習も発達させ,先に考案した <uu> はあまり使われなくなりました.
ところが,英語で不使用となった <uu> は,お隣のフランスに渡り,そこで「亡命」生活をして生き延びることとなりました.その後11世紀頃に,亡命していた <uu> は再び英語に舞い戻る機会を得て,<ƿ> を置き換えることになりました.こうして英語で "double-u" の <uu>,転じて <w> が定着することになりました.
ちなみに,亡命先のフランスでは <u> から派生した(<u> の先を尖らせた) <v> の文字も早くから使われており,例の文字を "double-v" の <vv> と解釈したのです.
この疑問のキモは,<u>, <v>, <w> (そして実は <f> も!)の文字が,歴史的にはすべて近親関係にあるという点です.関心のある方は,ぜひ##2411,373,374,3391,3927,1825の記事セットをじっくりお読みください.
2020-05-12 Tue
■ #4033. 3重字 <tch> の分布と歴史 [spelling][orthography][consonant][phonotactics][digraph][norman_french][digraph][trigraph][romaji]
中学1年生の英語教科書に,英語綴字の世界に徐々に誘うためにヘボン式ローマ字を経由するという試みがあるようだ.そこで「抹茶」は matcha と綴られるとの記述がある.案の定それ以上の詳しい説明はなく,ヘボン式ローマ字(そして含意として英語の正書法の一部)では,そのように綴られるのだとさらっと提示されているだけである.今回は,この無声後部歯茎破擦音 [ʧ] に対応する <tch> という3重字 (trigraph) が,英語の正書法において,そしてその歴史において,どのように位置づけられてきたかを考えてみたい.
現代英語の正書法では,[ʧ] の発音に対しては <ch> という2重字 (digraph) の対応が最も普通である (ex. chance, child, choose, crunchy, duchess, luncheon, bench, such, which) .しかし,主に語末において問題の <tch> への対応例も少なくない.例えば,「#49. /k/ の口蓋化で生じたペア」 ([2009-06-16-1]) でみたように古英語の口蓋化 (palatalisation) で生じた語形に由来する batch, ditch, match (相手), watch, wretch などがすぐに挙げられるし,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) でみたように catch といった Norman French 由来の借用語や,その他フランス語からの借用語の例として crotch, match (マッチ棒),butcher, hatchet, hutch などもある.
Upward and Davidson (159) によれば,<tch> の事例の7割ほどは,ゲルマン系の語の語末において起こっているという.語中に現われる例は,上にいくつか示したもののほか,重要な語として古英語から文証される kitchen を挙げておこう.
また,相対的に目立たないが,上述の通りフランス借用語の例も確かにある.それらの語は,中英語期の借用時にこそ boucher, hachet, huche などと <ch> で綴られたが,後に <tch> をもつ本来語に引きつけられたのか,butcher, hatchet, hutch という綴字へ鞍替えした.鞍替えといえば逆のパターンもあり,初期近代英語では atchieve, batcheler, dutchess, toutch などと綴られていた語が,後に <ch> で綴られるようになっている (Upward and Davidson 159) .
語の内部での位置についていえば,「#3882. 綴字と発音の「対応規則」とは別に存在する「正書法規則」」 ([2019-12-13-1]) で触れたように,<tch> が語頭に立つことは原則としてない.
音素配列論の観点からは,<tch> に先行する母音は原則として短母音であるという特徴がある.しかし,aitch (= H) だけは例外で2重母音が先行している.これは,オリジナルの ache の綴字が「痛み」を意味する語と同綴りになってしまうことを嫌った19世紀の刷新とされる (Upward and Davidson 159) .
改めて中英語にまで話しを戻すと,当時の綴字の多様性はよく知られている通りだが,問題の無声後部歯茎破擦音についても <cc>, <cch>, <chch>, <hch>, <tch> などの異綴りがあった.現代英語の <tch> をもつ語群が,その安定的な綴字を示すようになるのは1600年頃だという (Upward and Davidson 38) .
最後に世界の諸言語からの借用語にみられる,多少なりともエキゾチックな <tch> を挙げておこう.apparatchik, datcha, etch, ketchup, kvetch, litchi, patchouli, potlatch, sketch. そして興味深い固有名の例も.Aitchison, Batchelor, Bletchley, Cesarewitch, Craitchit, Dutch, Hitchin, Hutchinson, Kitchener, Mitchell, Redditch, Ritchie, Saskatchewan, Thatcher.
このような複雑な歴史を経てどうにかこうにか定着した英語正書法の <tch> が,ヘボン式ローマ字による matcha (抹茶)の綴字に引き継がれていることになる.
・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2019-04-01 Mon
■ #3626. 柳 朋宏(著)『英語の歴史をたどる旅』 [review][norman_french][doublet][pictish]
年度初めに,新刊の英語史入門書を1冊紹介します.私も多方面でお世話になっている中部大学の柳朋宏氏の書かれた『英語の歴史をたどる旅』が,この3月に出版されました(柳先生,ご献本いただきましてありがとうございます).中部大学ブックシリーズ Acta の30作目という位置づけです.
柳氏は英語の通時的な言語変化を理論的な観点から分析する研究者として活躍されていますが,今回はご専門の内面史的な要素をばっさり切り落とし,英語外面史(主に中世前期)を,簡略化も複雑化もしすぎずリーダブルに記述したのが最大の特徴かと思います.イギリスで著者自らが撮影した写真などが多く掲載され,図表やコラムも豊富でありながら,本体価格800円というのも驚きです.
取り上げられている話題としては,イギリス国旗,日本における英語接触の歴史,ルーン文字,羊皮紙といった文化的な要素が多く,気軽に読み進めていくことができます.ツボをつく細かなネタも満載です.たとえばノルマン・フランス語 (norman_french) と中央フランス語 (Central French) の2重語 (doublet) の話題について,本ブログでもいくつか取り上げてはきましたが,pinch (つまむ)と pincers (やっとこ)というペアもそうだったのかと教わりました(本書 p. 69; cf. 「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1])).イノシシやガチョウを描いたピクト人のシンボル (Pictish symbols) なども,写真とともに紹介されており,興味を引かれました(本書 p. 32--34).
本書で扱われている時代は古代・中世についての記述が大半ですが,新年度に各大学で開講される英語史概説の講義はおよそ古代・中世から始まるわけですので,学生にはタイムリーです.英語外面史への最初の一歩としてふさわしい図書です.
・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.
2018-08-28 Tue
■ #3410. 英語における「合拗音」 [labiovelar][pronunciation][phonetics][consonant][japanese][indo-european][comparative_linguistics][norman_french]
昨日の記事「#3409. 日本語における合拗音の消失」 ([2018-08-27-1]) で,合拗音「クヮ」「グヮ」音が直音化した経緯に注目した.合拗音の [kw], [gw] という「子音+半子音」の部分に着目すれば,話題としては,印欧語比較言語学でいうところの軟口蓋唇音 (labiovelar) ともつながってくる (cf. 「#1151. 多くの謎を解き明かす軟口蓋唇音」 ([2012-06-21-1])) .
英語では印欧祖語に遡るとされる [kw] や [gw] は比較的よく保存されており,この点では日本語の音韻傾向とは対照的である.綴字としては典型的に <qu>, <gu> で表わされ,queen, quick, liquid, language, sanguine などの如くである.さらにいえば,英語では [k], [g] が先行する音環境に限らず,一般に [w] はよく保存されている.
とはいうものの,そのような英語でも歴史的な [w] が失われているケースはある.「#383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」」 ([2010-05-15-1]) で見たように,フランス借用語のなかでも,Norman French から取り込まれたものは,その方言の音韻特徴を反映して /kw/ が保たれているが (e.g. conquest /ˈkɒŋkwɛst/) ,Central French からのものは,その方言の特徴を受け継いで /w/ が落ちている (e.g. conquer /ˈkɒŋkə/) .
また,「#51. 「5W1H」ならぬ「6H」」 ([2009-06-18-1]),「#184. two の /w/ が発音されないのはなぜか」 ([2009-10-28-1]) で見たたように,後舌母音が後続する場合の [w] は脱落しやすいという調音的な事情があり,それにより how, who, sword, two などの発音(と綴字とのギャップ)が生じている.
[w] は半子音と呼ばれるだけに中途半端な音声的特質をもっており,日本語でも英語でもその挙動(の歴史)は複雑である.
2017-02-25 Sat
■ #2861. Cursor Mundi の著者が英語で書いた理由 [popular_passage][norman_conquest][norman_french][reestablishment_of_english][language_shift][eme][me_text]
ノルマン征服 (norman_conquest) の後,イングランドに定住することになったノルマン人とその子孫たちは,しばらくの間,自分たちの母語である norman_french を話し続けた.イングランド社会の頂点に立つノルマン人の王侯貴族とその末裔たちは,特に公的な文脈において,フランス語使用をずっと長く続けていたことは事実である.この話題については,以下の記事を始めとして,いろいろと取り上げてきた.
・ 「#131. 英語の復権」 ([2009-09-05-1])
・ 「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1])
・ 「#1204. 12世紀のイングランド王たちの「英語力」」 ([2012-08-13-1])
・ 「#1461. William's writ」 ([2013-04-27-1])
・ 「#2567. 13世紀のイングランド人と英語の結びつき」 ([2016-05-07-1])
・ 「#2604. 13世紀のフランス語の文化的,国際的な地位」 ([2016-06-13-1])
特に,1300年頃に Robert of Gloucester の著わした Chronicle では,ノルマン人がフランス語を使用し続けている現状について,著者がぼやいている箇所があるほどだ(「#2148. 中英語期の diglossia 描写と bilingualism 擁護」 ([2015-03-15-1]) の引用を参照).
しかし,考えなければいけないことは,上に述べた状況は,およそノルマン人の王侯貴族にのみ当てはまったということだ.比較的身分の低いノルマン人たちは,周囲にいる大多数の英語母語話者たるイングランド人の圧力のもとで,早くにフランス語から離れ,英語へ乗り換えていた.
このような言語事情ゆえに,すでに1300年頃には,英語母語話者のなかには,英語でものを書こうという「個人的な」動機づけは十分にあったはずだ.ただ,英語で書くことは社会的慣習の外にあったので,「社会的に」ためらわれるという事情があっただけである.だが,その躊躇を振り切って,英語でものする書き手も現れ始めていた.1300年頃に北部方言で書かれた長詩 Cursor Mundi の著者も,その1人である.なぜ英語で書くのかという理由をあえて書き記している箇所 (Prologue, II, ll. 232--50) を,Gramley (72--73) 経由で引用しよう.
þis ilk bok es translate
Into Inglis tong to rede
For the loue of Inglis lede,
Inglish lede of Ingland,
For the commun at understand.
Frankis rimes here I redd,
Comunlik in ilk[a] sted;
Mast es it wroght for frankis man,
Quat is for him na Frankis can?
In Ingland the nacion,
Es Inglis man þar in commun;
þe speche þat man wit mast may spede;
Mast þarwit to speke war nede.
Selden was for ani chance
Praised Inglis tong in France;
Give we ilkan þare langage,
Me think we do þam non outrage.
To laud and Inglish man I spell
þat understandes þat I tell.
英語で書く理由をあえて書き記しているということから,逆にそれが社会的にはまだ普通の行いではなかったことが示唆される.
・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.
2017-01-23 Mon
■ #2828. carnage [etymology][norman_french]
先日のトランプ大統領の就任演説について,多くのメディアが酷評している.英語自体は相変わらずの「トランプ語法」で分かりやすいのは確かだが,語彙レベルは幼稚であるという(「#2825. 「トランプ話法」」 ([2017-01-20-1]) を参照).また,アメリカの歴代大統領の演説は一般に格調高く,理想に燃えた前向きの内容となるものだが,今回の演説には,過去の政権への批判をにじませた後ろ向きで否定的な要素が多いという.
そのような否定的な含意を最も直接的に感じさせたのが,American carnage という表現だ.演説の前半で,"This American carnage stops right here and stops right now." と述べている (see Inaugural address: Trump's full speech --- CNNPolitics.com) .
carnage とは「殺戮;(集合的に)大量の死体」を意味する文語的な語である.OALD7 の定義によると,"the violent killing of a large number of people" とある.また,OED の定義では " The slaughter of a great number, esp. of men; butchery, massacre." とある.いずれにせよ強烈な含意をもつ語である.現代英語から用例を挙げてみよう.
・ The scene of carnage was indescribable.
・ They hoped never to repeat the carnage of the First World War.
・ Years of violence and carnage have left the country in ruins.
carnage の語史をひもといてみよう.OED によると初出は1600年のことで,"1600 P. Holland tr. Livy Rom. Hist. ii. 16 The carnage and execution was no lesse after the conflict than during the fight." として初出する.Philemon Holland (1552--1637) が好んで用いたようだが,それ以降の使用は稀で,18世紀後半になってようやく一般的に用いられるようになった.
16世紀のフランス語に carnage という語が確認され,それが英語に入ったものと見られるが,そのフランス単語自体はイタリア語 carnaggio の借用である.そのとき,すでに「殺戮」の語義はあったようだ.このイタリア単語はさらに後期ラテン語 carnāticum からの借用であり,その段階での語義は "flesh-meat, also, the flesh-meat supplied by tenants to their feudal lords" だった.語根としては「肉」を意味するラテン語 carn-, carō に遡る.
古フランス語にも対応語として charnage という語が確認され,その北部方言形には英語形と同じ語頭子音をもつ carnage もあったが,英語版は後者からの直接の借用ではないようだ(当時の中央フランス語と北部(ノルマン)フランス語の子音対応 <ch> = /tʃ/ vs <c> = /k/ については,「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]) を参照).
いやはや,おぞましい語でアメリカ新政府が走り出したものだ.今後の成り行きを見守りたい.
2015-12-03 Thu
■ #2411. 英語の <w> = "double u" とフランス語の <w> = "double v" [w][grapheme][alphabet][norman_french][u][v]
英語のアルファベットの23文字目の <w> は,英語では double u と称するが,フランス語では double vé と称する (cf. Italian doppio vu, Spanish uve doble, Portuguese vê dobrado) .この呼び方の違いは,<u> と <v> が同一の文字素として認識されていた時代の混同に基づいている (cf. 「#373. <u> と <v> の分化 (1)」 ([2010-05-05-1]),「#374. <u> と <v> の分化 (2)」 ([2010-05-06-1])) .
もともとラテン語には <w> の文字はなく,/w/ 音は <v> あるいは <u> の文字で表記していた.古典期以降,7世紀までに /w/ 音自体がより子音的な /v/ へと発達し,音素としても文字素としても w は消えていった.その後の事情について,梅田 (73) に語ってもらおう.
ところが,ラテン語では消失した [w] は,ゲルマン系言語では特徴的に残っていた.特に,語頭においては [w] は顕著で,どうしても [w] を表す記号が必要となった.そこで7世紀ごろに一番近い音を表わす u を重ねて uu という表記法を発明したのである.w の名前 double-u はそのことをよく表わしている.フランス語では,double-v [dublve] と呼ばれる.
このようにして発明された uu はノルマンディーに広がり,ノルマン・フレンチのなかのゲルマン語に残る [w] を表現する文字として使われた.一方イングランドでは8世紀ごろに,uu はルーン文字から借用した ƿ (wen) にとって替わられて次第に使われなくなった.そして uu は11世紀にノルマン人によって w として逆輸入されるのである.
このようなことから,語頭に w をもつ言葉のほとんどが本来語,あるいは,ゲルマン語系の言葉である.例えば,way, wake, walk, week, west, wide, work, word, world は本来語であり,window, want, weak, wing などはデーン人がもたらした言葉であり,wait, war, ward, wage, wicket, wise, warranty などはノルマン人がもたらしたゲルマン語起源の言葉である.
OED の W, n. の語源欄より補足すると,古英語ではいくつかの Northumbrian のテキストで <uu> の使用が規則的だったが,8世紀にルーン文字からの <ƿ> (West-Saxon wynn, Kentish wenn) に置き換えられた.その後,<ƿ> は1300年くらいに消滅している.
さて,"double u" か "double v" かの問題に戻ろう.古英語には <v> が存在しなかったし,その後も近代英語に至るまで <v> は <u> の異文字体ととらえられていた.このような事情から,英語において <w> の呼称として "u" が採用され,"double u" として固定したのは不思議ではない.一方,ノルマン・フレンチにおいては子音字としての <v> がすでに存在しており,英語から導入されたこの新しい文字も,<v> と同様に子音を表わすのに用いられたため,<v> の重なった字形として迎え入れられ,"double v" と呼ばれるようになったのだろう.
<w> と関連して,「#1825. ローマ字 <F> の起源と発展」 ([2014-04-26-1]) の記事も参照されたい.
・ 梅田 修 『英語の語源事典』 大修館書店,1990年.
2015-10-13 Tue
■ #2360. 20世紀のフランス借用語 [french][loan_word][borrowing][statistics][norman_french][creole][oed]
英語のフランス語との付き合いは古英語最末期より途切れることなく続いている.フランス語彙借用のピークは「#2357. OED による,古典語およびロマンス諸語からの借用語彙の統計」 ([2015-10-10-1]) や「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たように1251--1375年だが,その後も,規模こそ縮小しながらも,借用は連綿と続いてきている.中英語以降の各時代のフランス語彙の借用については,「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]),「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]),「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]), 「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]) を参照されたい.
今回は,現代英語におけるフランス借用語の話題を取り上げたい.Schultz は,OED Online を利用して,1900年以降に英語に入ってきたフランス語彙を調査した.Schultz がフランス借用語として取り出し,認定したのは,1677語である.Schultz の論文では,それらを14個の意味分野(とさらなる下位区分)ごとに整理し,サンプル語を列挙しているが,ここでは12分野それぞれに属する語の数と割合のみを示そう (Shultz 4--6) .
(1) Anthropology (11 borrowings, i.e. 0.7%)
(2) Metapsychics and parapsychology (11 borrowings, i.e. 0.7%)
(3) Archaeology (30 borrowings, i.e. 1.8%)
(4) Miscellaneous (46 borrowings, i.e. 2.7%)
(5) Technology (62 borrowings, i.e. 3.7%)
(6) La Francophonie (63 borrowings, i.e. 3.8%)
(7) Fashion and lifestyle (77 borrowings, i.e. 4.6%)
(8) Entertainment and leisure activities (86 borrowings, i.e. 5.1%)
(9) Mathematics and the humanities (92 borrowings, i.e. 5.5%)
(10) People and everyday life (154 borrowings, i.e. 9.2%)
(11) Civilization and politics (156 borrowings, i.e. 9.3%)
(12) Gastronomy (179 borrowings, i.e. 10.7%)
(13) Fine arts and crafts (260 borrowings, i.e. 15.5%)
(14) The natural sciences (450 borrowings, i.e. 26.8%)
20世紀のフランス借用語の特徴は何だろうか.1つは,Schultz が "the vocabulary recently adopted from French is characterized by its great variety, ranging from words related to everyday matters to highly specific terms in technology and science" (8) とまとめているように,意味分野の幅広さが挙げられる.食,芸術,自然科学が相対的に強いが,全体としてはマルチジャンルといってよい.ただし,マルチジャンルであることは中英語期のフランス借用語の特徴にも当てはまることから,これは英語史におけるフランス語彙借用に汎時的にみられる特徴といってもよいかもしれない.
注目すべきは,借用語のソースとして,標準フランス語のみならず,フランス語の諸変種やクレオール語なども含まれていることだ.カリブ諸島,カナダ,ルイジアナ,アフリカなどのフランス語変種からの借用語が少なくない.中英語期にも,中央フランス語のみならず,とりわけ初期にノルマン・フランス語 (norman_french) からも語彙が流入していたが,近代以降「フランス語」の指す範囲が拡がるとともに,借用元変種も多様化してきたということだろう.
現代世界の借用元言語としての英語を考えてみても,従来はイギリス標準英語やアメリカ標準英語がほぼ唯一の借用元変種だったかもしれないが,現在ではピジン語やクレオール語も含めた各種の英語変種が借用元変種となっている事実がある.それと同じことが,フランス語についても言えるということなのではないか.
・ Schultz, Julia. "Twentieth-Century Borrowings from french into English --- An Overview." English Today 28.2 (2012): 3--9.
2015-08-01 Sat
■ #2287. chicken, kitten, maiden [suffix][norman_french][etymology][i-mutation][germanic]
表記の3語は,いずれも -en という指小辞 (diminutive) を示す.この指小辞は,ゲルマン祖語の中性接尾辞 *-īnam (neut.) に遡る.したがって,古英語の文証される cicen と mægden は中性名詞である.
chicken の音韻形態の発達は完全には明らかにされていないが,ゲルマン祖語 *kiukīno に遡るとされる.語幹の *kiuk- は,*kuk- が,接尾辞に生じる前舌高母音の影響下で i-mutation を経たもので,この語根からは cock も生じた.古英語では cicen などとして文証される (cf. Du. kuiken, G Küken, ON kjúklingr) .問題の接尾辞が脱落した chike (> PDE chick) は「ひよこ;ひな」の意味で,後期中英語に初出する.
kitten は,古フランス語 chitoun, cheton (cf. 現代フランス語 chaton) のアングロ・ノルマン形 *kitoun, *ketun を後期中英語期に借用したものとされる.本来的には -o(u)n という語尾を示し,今回話題にしている接尾辞とは無関係だったが,17世紀頃に形態的にも機能的にも指小辞 -en と同化した.
maiden (乙女)は,古英語で mægden などとして文証される.mægden が初期中英語までに語尾を脱落させて生じたのが mæide であり,これが現代の maid に連なる.つまり,古英語に先立つ時代において maid への接辞添加により maiden が生じたと考えられるが,実際に英語史上の文証される順序は,maiden が先であり,そこから語尾消失で maid が生じたということである.両形は現在に至るまで「少女,乙女」の意味をもって共存している.いずれもゲルマン祖語 *maȝaðiz (少女,乙女)に遡り,ここからは関連する古英語 magð (少女,女性)も生じている.さらに,「少女,乙女」を表わす現代英語 may (< OE mǣġ (kinswoman)) も同根と考えられ,関連語の形態と意味を巡る状況は複雑である.なお,maid は中英語では「未婚の男子」を表わすこともあった.
接尾辞 -en には他にも起源を異にする様々なタイプがある.「#1471. golden を生み出した音韻・形態変化」 ([2013-05-07-1]),「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1]),「#2221. vixen の女性語尾」 ([2015-05-27-1]) を参照.
2015-04-20 Mon
■ #2184. 英単語とフランス単語の相違 (2) [french][norman_french][loan_word][borrowing][lexicology][norman_conquest][false_friend]
昨日の記事「#2183. 英単語とフランス単語の相違 (1)」 ([2015-04-19-1]) に引き続いての話題.昨日は,英仏語の対応語の形や意味のズレの謎を解くべく,(1) 語彙の借用過程 (borrowing) に起こりがちな現象に注目した.今回は,(2) フランス語彙の借用の時期とその後の言語変化,(3) 借用の対象となったフランス語の方言という2つの視点を導入する.
まずは (2) について.英語とフランス語の対応語を比較するときに抱く違和感の最大の原因は,時間差である.私たちが比較しているのは,通常,現代英語と現代フランス語の対応語である.しかし,フランス単語が英語へ借用されたのは,大多数が中英語期においてである (cf. 「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1])) .つまり,6--8世紀ほど前のフランス語彙が6--8世紀ほど前の英語に流れ込んだ.昨日の記事でみたように,当時の借用過程においてすら model となるフランス単語と loan となる英単語のあいだに多少のギャップの生じるのが普通だったのであるから,ましてや当時より数世紀を経た現代において両言語の対応語どうしが形や意味においてピタッと一致しないのは驚くことではない.この6--8世紀のあいだに,その語の形や意味は,フランス語側でも英語側でも独自に変化している可能性が高い.
例えば,英語 doubt はフランス語 douter に対応するが,綴字は異なる.英単語の綴字に <b> が挿入されているのは英語における革新であり,この綴字習慣はフランス語では定着しなかった (cf. 「#1187. etymological respelling の具体例」 ([2012-07-27-1])) .またフランス語 journée は「1日」の意味だが,対応する英語の journey は「旅行」である.英語でも中英語期には「1日」の語義があったが,後に「1日の移動距離」を経て「旅行」の語義が発展し,もともとの語義は廃れた.数世紀の時間があれば,ちょっとしたズレが生じるのはもちろんのこと,初見ではいかに対応するのかと疑わざるを得ないほど,互いにかけ離れた語へと発展する可能性がある.
次に,(3) 借用の対象となったフランス語の方言,という視点も非常に重要である.数十年前ではなく数世紀前に入ったという時代のギャップもさることながら,フランス語借用の源が必ずしもフランス語の中央方言(標準フランス語)ではないという事実がある.私たちが学習する現代フランス語は中世のフランス語の中央方言に由来しているが,とりわけ初期中英語期に英語が借用したフランス語彙の多くは実はフランス北西部に行われていたノルマン・フレンチ (norman_french) である (cf. 「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1])) .要するに,当時の「訛った」フランス単語が英単語として借用されて現在に至っているのであり,それと現代標準フランス語とを比較したときに,ズレが感じられるのは当然である.現代のフランス語母語話者の視点から現代英語の対応語を眺めると,「なぜ英語は大昔の,しかも訛ったフランス単語を用いているのだろうか」と首をかしげたくなる状況がある.具体的な事例については,「#76. Norman French vs Central French」 ([2009-07-13-1]),「#95. まだある! Norman French と Central French の二重語」 ([2009-07-31-1]),「#388. もっとある! Norman French と Central French の二重語」 ([2010-05-20-1]) などを参照されたい.
以上,2回にわたって英単語とフランス単語の相違の原因について解説してきた.両者のギャップは,(1) 借用過程そのものに起因するものもあれば,(2) 借用の生じた時代が数世紀も前のことであり,その後の両言語の歴史的発展の結果としてとらえられる場合もあるし,(3) 借用当時の借用ソースがフランス語の非標準方言だったという事実によるものもある.現代英単語と現代フランス単語とを平面的に眺めているだけでは見えてこない立体的な奥行を,英語史を通じて感じてもらいたい.
2014-07-03 Thu
■ #1893. ヘボン式ローマ字の <sh>, <ch>, <j> はどのくらい英語風か [alphabet][japanese][writing][grammatology][orthography][romaji][j][norman_french][digraph]
昨日の記事 ([2014-07-02-1]) の最後に,ヘボン式ローマ字の綴字のなかで,とりわけ英語風と考えられるものとして <sh>, <ch>, <j> の3種を挙げた.現代英語の正書法を参照すれば,これらの綴字が,共時的な意味で「英語風」であることは確かである.しかし,この「英語風」との認識の問題を英語史という立体的な観点から眺めると,問題のとらえ方が変わってくるかもしれない.歴史的には,いずれの綴字も必ずしも英語に本来的とはいえないからである.
まず,<sh> = /ʃ/ が正書法として確立したのは15世紀中頃のことにすぎない.古英語では,この子音は <sc> という二重字 (digraph) で規則的に綴られていた.この二重字は中英語へも引き継がれたが,中英語では様々な異綴りが乱立し,そのなかで埋没していった.例えば,現代英語の <ship> に対応するものとして,中英語では <chip>, <scip>, <schip>, <ship>, <sip>, <ssip> などの綴字がみられる.このなかで,中英語期中最もよく用いられたのは <sch> だろう.現代的な <sh> は,13世紀初頭に Orm が初めてかつ規則的に用いたが,ある程度一般的になったのは14世紀のロンドンで Chaucer などが <sh> を常用するようになってからである.その後,<sh> は15世紀中頃に広く受け入れられるようになり,17世紀までに他の異綴りを廃用へ追い込んだ.このように,二重字 <sh> の慣習は,英語の土壌から発したことは確かだが,中英語期の異綴りとの長い競合の末にようやく定まった慣習であり,英語の規準となってからの歴史はそれほど長いものではない (Upward and Davidson 157) .
次に,<ch> = /ʧ/ の対応の起源は,疑いなく外来である.この子音は,古英語では典型的に前舌母音の前位置に現われ,規則的に <c> で綴られた.しかし,音韻変化の結果,<c> は同じ音韻環境で /k/ をも表わすようになり,二重の役割をもつに至った.この両義性が背景にあったことと,中英語期に Norman French の綴字慣習が広範な影響力をもったことにより,英語では自然と Norman French の <ch> = /ʧ/ が受け入れられる結果となった.12世紀には,早くも古英語的な <c> = /ʧ/ の対応はほとんど廃れ,古英語由来の単語も以降こぞって <ch> で綴り直されるようになった.二重字 <ch> の受容には,文字と音韻の明確な対応を目指す言語内的な要求と,Norman French の綴字習慣の進出という言語外的な要因とが関与しているのである (Upward and Davidson 100) .
<j> については,「#1828. j の文字と音価の対応について再訪」 ([2014-04-29-1]) と「#1650. 文字素としての j の独立」 ([2013-11-02-1]) で見たように,フランス借用語を大量に入れた中英語期に,やはりフランス語の綴字習慣をまねたものが,後に英語でも定着したにすぎない.実際,<j> で始まる英単語は原則として英語本来語ではない.
以上のように,今では「英語風」と認識されている <sh>, <ch>, <j> も,定着するまでは不安定な綴字だったのであり,当初から典型的に「英語風」だったわけではない.<ch> と <j> の2つに至っては,当時のファッショナブルな言語であるフランス語の綴字習慣の模倣であった.英語が当時はやりのフランス語風を受容したように,日本語が現在はやりの英語風を受容したとしても驚くには当たらないだろう.綴字習慣や正書法も,時代の潮流とともに変化することもあれば変異もするのである.そして,言語接触における影響の方向は,流行や威信などの社会言語学的な要因に依存するのが常である.ローマ字の○○式の評価も,歴史的な観点を含めて立体的になされる必要があると考える.
・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2014-06-24 Tue
■ #1884. フランス語は中英語の文法性消失に関与したか [personal_pronoun][gender][prescriptive_grammar][norman_french][norman_conquest][bilingualism][french][contact][inflection][singular_they]
昨日の記事「#1883. 言語における性,その問題点の概観」 ([2014-06-23-1]) に関連して,英語では generic 'he' の問題,そしてその解決策として市民権を得てきている「#1054. singular they」 ([2012-03-16-1]) の話題が思い出される.singular they について,最近ウェブ上で A Linguist On the Story of Gendered Pronouns という記事を見つけたので紹介したい.singular they の例が Chaucer など中英語期からみられること,generic 'he' の伝統は18世紀後半の規範文法家により作り出されたものであることなど,この問題に英語史的な観点から迫っており,一読の価値がある.
しかし,記事の後半にある一節で,フランス語が中英語期の文法性の消失に部分的に関与していると示唆している箇所について疑問が生じた.記事の筆者によれば,当時のイングランドにおける英語と Norman French との2言語使用状況が2つの異なる文法性体系を衝突させ,これが一因となって英語の文法性体系が崩壊することになったという.もっとも屈折語尾の崩壊が性の崩壊の主たる原因と考えているようではあるが,上のような議論は一般的に受け入れられているわけではない(ただし,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) や,中英語が古英語とフランス語の混成言語であるとするクレオール語仮説の議論 ##1223,1249,1250,1251 を参照されたい).
So what you really have is an extended period of several centuries in which many people were more-or-less proficient in both Norman French and Anglo Saxon, which in actual fact meant speaking the highly intermingled versions known as Anglo-Norman and Middle English. But words that belong to one gender in one language don't necessarily belong to the same gender in the other. To use a modern example, the word for "bridge" in French, pont, is masculine, but the word for "bridge" in German, ''Brücke, is feminine. If you couple this with the fact that people had begun to stop pronouncing altogether the endings that indicate a word窶冱 gender and case, you can see how these features became irrelevant for the language in general.
まず,当時のイングランドの多くの人が程度の差はあれ2言語話者だったということが,どの程度事実と合っているのかという疑問がある.貴族階級のフランス系イングランド人や知識階級の人々は多かれ少なかれバイリンガルだった可能性は高いが,大多数の庶民は英語のモノリンガルだった(「#338. Norman Conquest 後のイングランドのフランス語母語話者の割合」 ([2010-03-31-1]) および「#661. 12世紀後期イングランド人の話し言葉と書き言葉」 ([2011-02-17-1]) の記事を参照).英語の言語変化の潮流を決したのはこの大多数のモノリンガル英語話者だったに違いなく,社会的な権力はあるにせよ少数のバイリンガルがいかに彼らに言語的影響を及ぼしうるのか,はなはだ疑問である.
次に,「#1223. 中英語はクレオール語か?」 ([2012-09-01-1]) でみたように,一般にフランス語の英語への直接的な言語的影響は些細であるという説得力のある議論がある.語彙や綴字習慣を除けば,フランス語が英語に体系的に影響を与えた言語項目は数少ない.ただし,間接的な影響,社会言語学的な影響は甚大だったと評価している.それは,「#1171. フランス語との言語接触と屈折の衰退」 ([2012-07-11-1]) や「#1208. フランス語の英文法への影響を評価する」 ([2012-08-17-1]) で論じた通りである.
今回の性の消失という問題に対するには,フランス語によるこの間接的な効果,屈折語尾の消失を間接的に促したという効果を指摘するだけで十分ではないだろうか,
2012-09-18 Tue
■ #1240. ノルマン・コンクェスト後の法律用語の置換 [lexicology][norman_conquest][history][loan_word][french][norman_french][me][law_french]
[2012-09-03-1]の記事「#1225. フランス借用語の分布の特異性」で言及した Lutz の論文に,標題の語彙交替を示す表が挙げられていた.古英語で用いられていた本来語の法律用語が,中英語以降(現代英語へ続く)に対応するフランス借用語語により置きかえられたという例である.網羅的ではないが,一瞥するだけで置換の様子がよく分かる表である.以下に再現しよう (149) .
| OE | ModE | |
| dōm | -- | judgment |
| dōmærn †, dōmhūs | -- | court-house |
| dōmlic † | -- | judicial |
| dēma †, dēmere † | -- | judge |
| dēman | -- | to judge |
| fordēman | -- | to condemn |
| fordēmend | -- | accuser |
| betihtlian † | -- | to accuse, charge |
| gebodian †, gemeldian † | -- | to denounce, inform |
| andsacian †, onsecgan † | -- | to renounce, abjure |
| gefriþian † | -- | to afford sanctuary |
| mānswaru †, āþbryce † | -- | perjury |
| mānswara † | -- | perjurer |
| mānswerian † | -- | to perjure oneself |
| (ge)scyld †, scyldignes † | -- | guilt |
| scyldig † | -- | guilty, liable |
| scyldlēas | -- | guiltless |
| āþ | > | oath |
| þēof | > | thief |
| þeofþ | > | theft |
| morþ, morþor + OF murdre | > | murder |
doom や deem など,現代まで残っている本来語はあるが,法律用語としての語義は失っている.また,法律用語として残っている最後の4語についても,フランク語や古ノルド語の同根語がノルマン人の法律用語としてすでに定着していたゆえとも考えられる.
Lutz は,征服者の制度と強く結びついたこれらの語彙が英語へ借用された事実を挙げ,とかくフランス文化への憧れというような借用の原動力に関する議論がなされるが,征服者の「力」を想定せざるを得ないフランス語借用もあるということを主張する.フランス語のもつ宮廷文化,ロマンス,食事,学問といった華やかな連想の影に,生々しい政治的,軍事的な力が隠されてしまっているのではないか,と問題を提起しているかのようだ.
. . . the particularly large share of French in the basic vocabulary of Modern Standard English cannot be attributed to its cultural appeal alone but results from forced linguistic contact exerted by the speakers of the language of a conquering power on that of the conquered population. Ordinary borrowing, guided by the wish to acquire new things and concepts and, together with them, the appropriate foreign terms, could not have led to such an extreme effect on the basic vocabulary of the recipient language.
関連して,「#1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分」 ([2012-08-18-1]) や「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) を参照.また,法律におけるフランス語について,「#336. Law French」 ([2010-03-29-1]) と「#433. Law French と英国王の大紋章」 ([2010-07-04-1]) も参照.
・ Lutz, Angelika. "When did English Begin?" Sounds, Words, Texts and Change. Ed. Teresa Fanego, Belén Méndez-Naya, and Elena Seoane. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins, 2002. 145--71.
2012-08-18 Sat
■ #1209. 1250年を境とするフランス借用語の区分 [french][loan_word][me][norman_french][lexicology][statistics][bilingualism]
英語におけるフランス借用語の話題は,french loan_word などの多くの記事で扱ってきた.特に中英語期にフランス借用語が大量に借用された経緯とその借用の速度について,「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) 及び「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1]) で記述した.借用の速度でみると,13世紀の著しい伸びがフランス語借用史の1つの転換点となっているが,この前後ではフランス語借用について何がどう異なっているのだろうか.Baugh and Cable (168--69) により,それぞれの時代の特徴を概説しよう.
ノルマン・コンクェストから1250年までのフランス借用語は,(1) およそ900語と数が少なく,(2) Anglo-Norman の音韻特徴を示す傾向が強く,(3) 下流階級の人々が貴族階級との接触を通じて知るようになった語彙,とりわけ位階,文学,教会に関連する語彙が多い.例としては,baron, noble, dame, servant, messenger, feast, minstrel, juggler, largess; story, rime, lay, douzepers など.
一方,1250年以降のフランス借用語の特徴は次の通り.(1) 1250--1400年に爆発期を迎え,この1世紀半のあいだに英語史における全フランス借用語の4割が流入した.なお,中英語期に限れば1万語を超える語が英語に流れ込み,そのうちの75%が現在にまで残る (Baugh and Cable 178) .(2) フランス語に多少なりとも慣れ親しんだ上流階級が母語を英語へ切り替える (language shift) 際に持ち込んだとおぼしき種類の語彙が多い.彼らは,英語本来語の語彙では満足に表現できない概念に対してフランス語を用いたこともあったろうし,英語の習熟度が低いためにフランス語で代用するということもあったろうし,慣れ親しんだフランス語による用語を使い続けたということもあったろう.(3) 具体的には政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野の語彙が多いが,このような区分に馴染まないほどに一般的で卑近な語彙も多く借用されている.
要約すれば,1250年を境とする前後の時代は,誰がどのような動機でフランス語を借用したかという点において対照的であるということだ.Baugh and Cable (169) は,鮮やかに要約している.
In general we may say that in the earlier Middle English period the French words introduced into English were such as people speaking one language often learn from those speaking another; in the century and a half following 1250, when all classes were speaking or learning to speak English, they were also such words as people who had been accustomed to speak French would carry over with them into the language of their adoption. Only in this way can we understand the nature and extent of the French importations in this period.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 5th ed. London: Routledge, 2002.
2010-05-20 Thu
■ #388. もっとある! Norman French と Central French の二重語 [norman_french][doublet]
この話題は何度かにわたって取りあげてきた ([2010-05-15-1], [2009-07-31-1], [2009-07-30-1], [2009-07-13-1], [2009-07-12-1]) .英語における Norman French と Central French の対応語ペアで,Gachelin の論文で追加的に見つけたものを整理する.現代に残る代表的な語義と,その語義での初出年も合わせて記す.
| NF | CF |
|---|---|
| car 「馬車」 1301 | chariot 「花馬車」 1358 |
| pocket 「小袋」 1350 | pouch 「小袋」 a1325 |
| wage 「賃金」 ?a1300 | gage 「抵当物」 ?a1300 |
| wallop 「ギャロップで走る」 1375-1721 | gallop 「ギャロップで走る」 a1425 |
| wise 「方法,仕方」 OE | guise 「やりかた,流儀」 a1338 |
| convey 「運ぶ」 a1383 | convoy 「同行する」 1375 |
こうして探してみると,結構あるのだなと感心した.Gachelin はフランス語を母語とする英語学者で,フランス借用語の問題に詳しい.具体例が豊富で,読ませる論文だった."Is English a Romance Language?" という論題こそ挑戦的だが,英語がロマンス化したことは評価すべきだという肯定的な態度をとっている.
・ Gachelin, Jean-Marc. "Is English a Romance Language?" English Today 23 (July 1990): 8--14.
2010-05-15 Sat
■ #383. 「ノルマン・コンケスト」でなく「ノルマン・コンクェスト」 [norman_french][doublet]
英国史上の最大の出来事である1066年の Norman Conquest については,これまでも様々な形で触れてきた.この事件の名称を日本語でカタカナ表記するとき,「ノルマン・コンクエスト」「ノルマン・コンクェスト」「ノルマン・コンケスト」などの間に揺れがあるようだ.[2010-04-24-1]で紹介した JReK による検索では,「ノルマン・コンクエスト」が圧倒的に多い.しかし,私としては是非とも「ノルマン・コンクェスト」と表記し発音したいと思っている.その理由は,何も /ˈkɒŋkwɛst/ という英語の発音に忠実でありたいからではない.「ノルマン」ときたら「コンクェスト」しかない歴史的な理由がある.
conquest はフランス語からの借用語だが,特にそのノルマン方言 ( Norman French ) から借りてきた語である.このことは <quest> という綴字と /kwɛst/ という発音によって示されている.一方,中央のパリ方言 ( Central French ) での形は,現代フランス語の conquête 「獲得;征服」や conquêt 「取得財産」の綴字
それでは,動詞形の conquer /ˈkɒŋkə/ はどうだろうか.conquest と同様に <qu> という綴字を含むものの,現代英語での第二音節の最初の子音(群)は /kw/ でなく /k/ なので,こちらは Central French の形に由来すると考えてよいだろう.
Norman French と Central French の二重語 doublet に関する話題は[2009-07-13-1], [2009-07-30-1], [2009-07-31-1]を参照.
2010-03-29 Mon
■ #336. Law French [me][french][reestablishment_of_english][norman_french][loan_word][law_french]
[2010-03-17-1]の記事で触れたが,法律文書の英語化は非常に緩慢としたプロセスだった.1362年に口頭の訴訟手続きこそフランス語から英語に切り替わったが,法律関係の文書にはまだまだフランス語が使用されていた.実に1731年まで使われ続けたのである.このフランス語は Law French と呼ばれ,Norman Conquest 以来の Norman French がもととなって確立された法律文章語である.
現在でも英語の法律用語の大半がフランス語由来であるのは,上述の歴史に負っている.法律関係の役職名と犯罪名だけをとってみても,英語の法律の世界がいかに French かが分かるだろう.
・ 役職名: advocate 「代言者」, attorney 「代理人」, bailiff 「執行吏」, coroner 「検視官」, counsel 「弁護人」, defendant 「被告」, judge 「裁判官」, jury 「陪審」, plaintiff 「原告」
・ 犯罪名: arson 「放火」, assault 「暴行」, felony 「重罪」, fraud 「詐欺」, libel 「文書誹毀」, perjury 「偽証」, slander 「口頭誹毀」, trespass 「侵害」
また,フランス語の統語では「名詞+形容詞」という語順が普通なので,これを反映した法律関係の句がたくさん存在する.
・ attorney general 「司法長官;法務長官」, court martial 「軍法会議」, fee simple 「単純封土権」, heir apparent 「法定推定相続人」, letters patent 「開封勅許状」, malice aforethought 「予謀の犯意」
英語で法律を勉強するのはものすごく大変そう・・・.
・McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992. 591.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow