2024-11-28 Thu
■ #5694. ゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説について --- 池上俊一(著)『森と山と川でたどるドイツ史』より [purism][germanic][language_myth][linguistic_ideology]
3日前の記事「#5691. 池上俊一(著)『森と山と川でたどるドイツ史』(岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年)の目次」 ([2024-11-25-1]) で紹介した書籍より,ゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説について,著者の解説を引用したい.本書の最後の第7章の「政治と結びつく危険性」と題する1節 (206--07) より.
ドイツ人は二〇〇〇年近くにわたって,具体的な自然を活用して生活に役立てるだけでなく,より深い精神的・身体的な交流をもってきました.それが,彼らを政治的不安定・未確定の宙吊り状態の不安から救い,安心感,誇りと名誉の感覚さえ与えてきたのです.
パリやロンドンのような中心もなければ拠るべきギリシャ・ローマの伝統やキリスト教の伝統もない,しかもおびただしい領邦に分断されたドイツ人が,自己の定着地として認められるのは,曖昧だが根源的な自然や風景であって,生命とエロスが躍動しているーー個体としての人間とその魂がごく一部を構成するーー有機体世界=自然世界でした.
ですから一九世紀になって,ドイツにナショナリズムがわきおこってきたとき,根源とか自然とか,家郷とか祖国とか,血縁とか地縁などとの,情感あふれる結びつきに深く訴えながらのプロパガンダがくり広げられました.まさにウェットなナショナリズムなのですが,その大元には,ドイツ人にとっては「自然」こそが「家郷」であり,そこから引き離されてはドイツ人のドイツ人たる存在理由がなくなる,という思いがあったのです.
この独特な自然観を深く考察した当時の思想家たちによると,その「自然」には「言語」との密接な連関がありました.そして「ドイツ人の祖先はーー他のゲルマン民族とは異なりーー原民族の居住地にずっと止まり,かつもとの言語をそのまま維持した」「だからドイツ民族のみが根元とつながっており,そこに真に固有文化が育つのだ」と主張されました.
ここでは「言語」こそがひとつの「民族」の基礎をなすものであり,それがあたかも,植物や動物であるかのように分化し,成長していくととらえられています.「ドイツ人は言語も自然の根源性につながっているのに,他の諸民族は余所の言語を受け容れたり,故地から別の地域に移動して堕落し,文化も停滞してしまった」とされるのです.
このような考えに立てば「ドイツ語が話されているすべての地域がドイツとして統一されるべきだ」ということになり,このドイツ民族中心主義が,純血主義や世界主義と結びついていくとどんな恐ろしい結果がおきるかは,ナチ・ドイツが赤裸々に示したとおりです.
ドイツ語が「もとの言語をそのまま維持した」と考えられた際に,比較対照されたゲルマン諸語の筆頭はおそらく英語と考えてよいだろう.歴史的にみても,英語ほど純粋でないゲルマン語はないからだ.あまつさえ,英語は世界語の地位を得つつある著名な言語でもある.もちろん英語(の歴史)そのものに罪はないが,英語がゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説のために引き合いに出されたということは十分にありそうだ
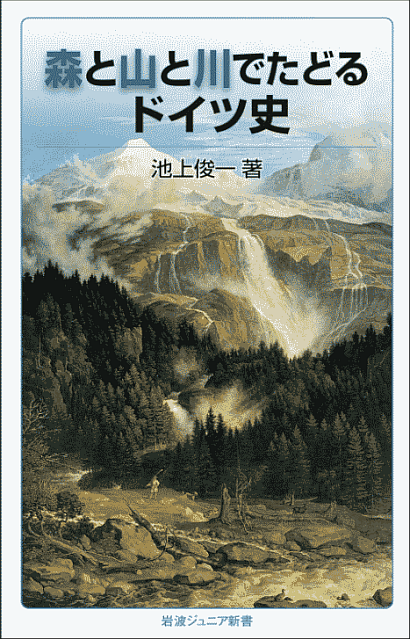
・ 池上 俊一 『森と山と川でたどるドイツ史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年.
2023-04-19 Wed
■ #5105. 英語の後光効果 [linguistic_imperialism][language_myth][linguistic_ideology][sociolinguistics]
一昨日の記事「#5103. 支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない」 ([2023-04-17-1]) で紹介した山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)に,有力な言語のもつ「後光のようなもの」について論じられている箇所がある (pp. 14--15) .
言語そのものというより,言語に冠された後光のようなもの.それがX語の持つ力である.過去,東アジア世界では漢文が,ローマ時代の地中海地域と中世のヨーロッパではラテン語が,一七世紀~一九世紀のヨーロッパ知識人の間ではフランス語が,そしてイスラム世界ではアラビア語が光を帯びていた.そしていま,多くの地域で,眩しい光を放っているのは英語だ.日本でも,圧倒的な教育資源が,英語に注ぎ込まれている.「英語ができる」ことで発生する(かもしれない)利益への期待をあおる広告表現の多くは,おくめんもなく,英語を,輝く未来を保障〔ママ〕してくれるような魔法の鍵として描き出している.英語ができれば,人生がよりよい方向に変わる.仕事が見つかり収入が上がる.そんなイメージを散りばめた表現を,街角の広告に見かけたことはないだろうか.いわく,「英語ができれば人生はもっと楽しくなる!」(NHK通信講座),「英語の力は,世界とつながる力」 (AEON),「英語を,習いはじめた.商談が,動きはじめた」 (AEON),「いまこの国が求めているのは,英語が話せるあなたです」 (CLUB CUE),「英語で夢をカタチに」 (AEON) .
イギリス政府が設立したブリティッシュ・カウンシル(主要事業は英語の普及)は,こうした事態に対してきわめて意識的である.ブリティッシュ・カウンシルは,イギリスが英語使用の規範として見なされる地位を誇り利用する.
これは英語の「後光効果」の警告的な指摘にほかならない.「後光効果」とは『ブリタニカ国際大百科事典 小項目版 2015』によると次の通り.
ハロー効果,光背効果ともいう.人がもっているある特徴を評価する場合に,その人についての一般的印象やその人のもつ他の特徴によって,その評価が影響を受けやすい傾向をさす.たとえば,ノーベル賞を受賞した自然科学者の専門外の分野における社会的発言が権威をもって受入れられること.
「英語には力がある」というときの「力」とは,英語に内在する力ではなく,あくまで人々が外側から英語に付与している力である.そこには人々の尊敬,憧れ,羨望,期待などがこめられている.英語自身が後光を発しているというよりは,人々がそこに後光を見ている,と表現するほうが適切だろう.人々は英語の後光効果 (halo effect) にかかっているのである.
・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.
2023-04-17 Mon
■ #5103. 支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない [linguistic_imperialism][linguistic_ideology][norman_conquest][norman_french][link][review]
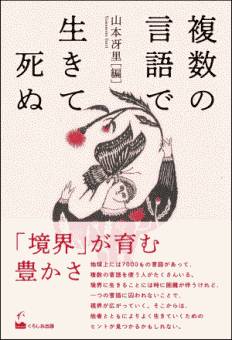
英語史において,1066年のノルマン征服はきわめて大きなインパクトをもつ.その意義について,本ブログでも norman_conquest の多くの記事で取り上げてきた.1066年の後,確かに英語はフランス語の支配下に置かれ,その社会的地位は失墜したものの,英語話者のほぼすべてが英語話者にとどまり,フランス語化したわけではなかった.征服者であるノルマン人自身はイングランド支配に際して自らの言語であるノルマン・フランス語を使い続けたが,それを被征服者であるイングランド人に(少なくともイングランド人一般に)押しつけようとした形跡はない.
支配者が自らの言語を被支配者に押しつけてきた例は,確かに古今東西みられる.実際,大日本帝国は植民地に日本語を押しつけてきた.しかし,支配者は必ずしも自らの言語を被支配者に押しつけるわけではない.
山本冴里(編)『複数の言語で生きて死ぬ』(くろしお出版,2022年)の第1章「夢を話せない --- 言語の数が減るということ」(山本冴里)に,次のようにある (pp. 9--10) .
しかし,植民地に暮らす人すべてに対して自らの言語を強制することは,支配者側にとっても利益ばかりにつながるわけではなく,多大なコストと相当のリスクを伴う行為でもあって,ゆえにそう頻繁には採用されない.コストとは教育や管理にかかる時間と費用だ.リスクは,言語を押しつけられた側からの反発や,支配者側の言語を身につけた被支配者側の者が,その言語を武器として,支配者に対して批判のできるような,より広い舞台に立つ可能性である.だからこそ,過去に列強と呼ばれる国々が行なった植民地政策においては,被支配者グループのすべてではなく,ただ上流階級,管理層のみを対象に支配者側の言語教育を行う場合もあったし(したがって,管理層に入りたければ支配者側の言語を習得することが必須となった),より広く言語教育を供給するにしても,庶民に対しては「読み書き」を軽視または実質的に禁じ,「話し聞く」ことばかりを推奨する土地もあった (Migge & Léglise 2007) .
本ブログでは言語帝国主義 (linguistic_imperialism) に関わる議論を多く取り上げてきたが,とりわけ今回の話題に関係するものを挙げておきたい.
・ 「#1461. William's writ」 ([2013-04-27-1])
・ 「#5041. 英語帝国主義の議論のために」 ([2023-02-14-1])
・ 「#1784. 沖縄の方言札」 ([2014-03-16-1])
・ 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])
・ 山本 冴里(編) 『複数の言語で生きて死ぬ』 くろしお出版,2022年.
2023-02-14 Tue
■ #5041. 英語帝国主義の議論のために [linguistic_imperialism][youtube][link][elf][language_myth][linguistic_ideology][voicy][heldio]
一昨日公開された YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新動画は「#101. 英語コンプレックスから解放される日はくるのか? --- 英語帝国主義と英語帝国主義批判を考える」です.英語帝国主義(批判)をめぐって2人で議論しています.よろしければご視聴ください.また,YouTube のコメント機能よりご意見などもお寄せいただければと思います.
hellog でも英語帝国主義(批判)や,より一般的に言語帝国主義 (linguistic_imperialism) の話題を多く取り上げてきました.英語帝国主義を議論するに当たっては,現在の英語の覇権的な地位をよく認識しておく必要があることはもちろん,なぜ英語がここまで覇権的な言語になってきたのかという歴史を押さえておくことが肝心だと考えています.英語帝国主義をめぐる議論は英語史の重要な論題であり,まさに英語史の知見こそが,関連する議論に大きく貢献できるものと信じています.
私自身,この議論に関してまだ明確な意見を固められているわけではありません.しかし,英語の帝国主義的な歴史や覇権的な側面を認めつつ,英語を完全に受容することも完全に拒絶することもできないもの,つまり全肯定も全否定もできない言語と考えています.今後も議論を続けていきたいと思います.
英語帝国主義や言語帝国主義に関する書籍は多く出されていますが,周辺領域は広く深いです.まずは hellog から関連する記事をピックアップしてみました.今後の議論のためにご参考まで.
・ 「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1])
・ 「#1073. 英語が他言語を侵略してきたパターン」 ([2012-04-04-1])
・ 「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1])
・ 「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1])
・ 「#1194. 中村敬の英語観と英語史」 ([2012-08-03-1])
・ 「#1606. 英語言語帝国主義,言語差別,英語覇権」 ([2013-09-19-1])
・ 「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1])
・ 「#1785. 言語権」 ([2014-03-17-1])
・ 「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1])
・ 「#1838. 文字帝国主義」 ([2014-05-09-1])
・ 「#1919. 英語の拡散に関わる4つの crossings」 ([2014-07-29-1])
・ 「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1])
・ 「#2306. 永井忠孝(著)『英語の害毒』と英語帝国主義批判」 ([2015-08-20-1])
・ 「#2429. アルファベットの卓越性という言説」 ([2015-12-21-1])
・ 「#2458. 施光恒(著)『英語化は愚民化』と土着語化のすゝめ」 ([2016-01-19-1])
・ 「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1])
・ 「#2549. 世界語としての英語の成功の負の側面」 ([2016-04-19-1])
・ 「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1])
・ 「#2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」」 ([2017-05-10-1])
・ 「#2986. 世界における英語使用のジレンマ」 ([2017-06-30-1])
・ 「#3004. 英語史は英語の成功物語か?」 ([2017-07-18-1])
・ 「#3010. 「言語の植民地化に日本ほど無自覚な国はない」」 ([2017-07-24-1])
・ 「#3011. 自国語ですべてを賄える国は稀である」 ([2017-07-25-1])
・ 「#3012. 英語はリンガ・フランカではなくスクリーニング言語?」 ([2017-07-26-1])
・ 「#3277. 「英語問題」のキーワード」 ([2018-04-17-1])
・ 「#3278. 社会史あるいは「進出・侵略」の観点からの英語史時代区分」 ([2018-04-18-1])
・ 「#3286. 津田幸男による英語支配を脱する試案,3点」 ([2018-04-26-1])
・ 「#3302.「英語の帝国」のたどった3段階の「帝国」」 ([2018-05-12-1])
・ 「#3315. 「ラモハン・ロイ症候群」」 ([2018-05-25-1])
・ 「#3470. 言語戦争の勝敗は何にかかっているか?」 ([2018-10-27-1])
・ 「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1])
・ 「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1])
・ 「#3851. 帝国主義,動物園,辞書」 ([2019-11-12-1])
・ 「#4279. なぜ英語は世界語となっているのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-13-1])
・ 「#4467. インド英語は「崩れた英語」か「土着化した英語」か?」 ([2021-07-20-1])
・ 「#4536. 言語イデオロギーの根底にある3つの記号論的過程」 ([2021-09-27-1])
・ 「#4537. 英語からの圧力による北欧諸語の "domain loss"」 ([2021-09-28-1])
・ 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1])
・ 「#4829. 19世紀イギリス「白人の責務」から「英語帝国主義」へ」 ([2022-07-17-1])
・ 「#4830. 19世紀イギリスの植物園・動物園趣味と帝国主義」 ([2022-07-18-1])
関連して Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」もお聴きください.
2022-06-29 Wed
■ #4811. なぜどうでもよいほど小さな語法が問題となるのか? [complaint_tradition][sociolinguistics][linguistic_ideology][prescriptive_grammar][prescriptivism][language_myth]
「英語に関する不平不満の伝統」 (complaint_tradition) は,英語のお家芸ともいえる.hellog でも「#3239. 英語に関する不平不満の伝統」 ([2018-03-10-1]),「#4596. 「英語に関する不平不満の伝統」の歴史的変化」 ([2021-11-26-1]) などでこの伝統について考えてきた.英米では語法の正用・誤用への関心が一般に高く,「#301. 誤用とされる英語の語法 Top 10」 ([2010-02-22-1]) のような議論がよく受ける.間違えたところでコミュニケーション上の障害にはならない,取るに足りない語法がほとんどなのだが,このような小さな点にこだわる「文化」が育まれてきたといってよい.
Horobin は著書の最終章 "Why Do We Care?" にて,この「文化」の背景を探っている.論点はいくつかあるが,大きく3点あるように読める.
(1) 英語話者は,自身が英語の不条理と長年付き合ってきた結果,英語を使いこなせるに至ったという経験をもつため,いまさら語法の正用・誤用について中立的な視点をもつことができない.Horobin (153) の言葉を引けば,次の通り.
. . . as users of English, it is impossible for us to take an external stance from which to observe current usage. As we have all had to acquire the English language, negotiating its grammatical niceties, its fiendishly tricky spellings, and its unusual pronunciations, it is impossible for us to adopt a neutral position from which to observe debates concerning correct usage.
単純化していってしまえば「私はこんなにヘンテコな語法ばかりの英語を頑張って習得してきた.だから,他の皆にも同じ苦労を味わってもらわなければ不公平だ」という気持ちに近い.
(2) 語法に関する本,「良い文法」に関する本は市場価値があり,よく売れる.現代はあらゆるものの変化が早く,言葉に関して頼りになる不変の支柱があれば,人々は安心するものである.Horobin (155) 曰く,
Much of the success of style guides may be credited to society's tacit acceptance that there are rights and wrongs in all aspects of usage, and a desire to be saved from embarrassment. Rather than question the grounds for the prescription, we turn to usage pundits as we once turned to our schoolteachers, in search of guidance and certitude. In a fast-changing and uncertain world, there is something reassuring about knowing that the values of our schooldays continue to be upheld, and that the correct placement of an apostrophe still matters.
(3) ラテン語文法への信奉.ラテン語は屈折の豊富な「立派な」言語であり,文法も綴字も約2千年のあいだ不変だった.それに対して,英語は屈折を失った「堕落した」言語であり,文法も綴字もカオスである.英語もラテン語のような不変で盤石の言語的基盤をもつべきである,という言語観.Horobin (162--63) の解説を引こう.
Since Latin had not been a living language (one with native speakers) for centuries, it existed in a fixed form; by contrast, English was unstable and in decline. This view of Latin as a unified and fixed entity perseveres today, encouraged by the way modern textbooks present a single variety (usually that of Cicero), suppressing the wide variation attested in original Latin writings. Since the eighteenth century, efforts to outlaw variation and to introduce greater fixity in English have been driven by a desire to emulate the model of this prestigious classical forebear.
3点目については,言語変化を「堕落」と捉える見方と関連する.これについては「#432. 言語変化に対する三つの考え方」 ([2010-07-03-1]),「#2543. 言語変化に対する三つの考え方 (2)」 ([2016-04-13-1]),「#2544. 言語変化に対する三つの考え方 (3)」 ([2016-04-14-1]) を参照.「英語に関する不平不満の伝統」を支える言語観は,18世紀の規範主義の時代から,ほとんど変わっていないようだ.
・ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.
2022-04-14 Thu
■ #4735. なぜ Webster は綴字改革をなし得たか? [webster][spelling_reform][sociolinguistics][linguistic_ideology][ame][spelling][orthography][american_revolution]
一般的にいって綴字改革 (spelling_reform) は成功しないものである.実際,英語の歴史で見る限り成功例はほとんどない.その理由については「#606. 英語の綴字改革が失敗する理由」 ([2010-12-24-1]),「#2087. 綴字改革への心理的抵抗」 ([2015-01-13-1]),「#634. 近年の綴字改革論争 (1)」 ([2011-01-21-1]),「#635. 近年の綴字改革論争 (2)」 ([2011-01-22-1]) などで触れてきた.
英語史において綴字改革がそれなりに成功したとみなすことのできるほぼ唯一の事例が,Noah Webster によるアメリカ英語における綴字改革である(改革の対象となった単語例は「#3087. Noah Webster」 ([2017-10-09-1]) を参照).
では,なぜ Webster の綴字改革は類い希なる成功を収め得たのか.この問題については「#468. アメリカ語を作ろうとした Webster」 ([2010-08-08-1]),「#3086. アメリカの独立とアメリカ英語への思い」 ([2017-10-08-1]) でも取り上げてきた.端的にいえば,ウェブスターの綴字改革は,反イギリス(綴字)という時代の勢いを得たということである.アメリカ独立革命とそれに伴うアメリカの人々の新生国家に対する愛国心に支えられて,通常では実現の難しい綴字改革が奏功したのである.もちろん,Webster 自身も強い愛国者だった.
Webster の愛国心の強さについては上記の過去の記事でも言及してきたが,それをさらに雄弁に語る解説を見つけたので紹介したい.昨日の記事でも触れた Coulmas (267) が,アメリカ英語の歴史を著わした Mencken を適宜引用しながら,愛国者 Webster の綴字イデオロギーについて印象的な記述を施している.
Webster was an ardent nationalist who had an intuitive understanding of the symbolic significance of the written language as a national emblem. Like many of his contemporaries in England and in the colonies, Webster promoted a reformed mode of spelling; however, what distinguished him from others is that he realised the political significance of claiming an independent standard for American English. Spelling to him was a way to write history. Webster's various publications on the English language were intended to further America's intellectual independence and to prove political nationalism with a manifest appearance for all to see and identify with. 'As an independent nation, our honor requires us to have a system of our own, language as well as government' (Webster 1789: 20).
Reducing the number of letters, weeding out silent letters, and making the spelling more regular were general principles of reform in line with the Enlightenment's call for more rationality. While Webster subscribed to these ideals, to him the 'greatest argument', as Mencken put it, 'was the patriotic one: "A capital advantage of his reform in these States would be that it would make a difference between the English orthography and the American"' (quoted from Mencken 1945 [1919]: 382). Regulating spelling conventions since the Renaissance had been intended to advance homogeneity, but Webster's new spelling was, on the contrary, designed to bring about a schism. Reversing the printers' plea for as wide a distribution of print products as possible, he argued that 'the English would never copy our orthography for their own use' and that the alteration would thus 'render it necessary that all books should be printed in America' (Mencken 1945 [1919]: 382). The assumed economic advantages of a simpler spelling system that would accrue from savings in the cost of teaching as well as publishing books at home rather than buying them from England were an important part of his reasoning.
Self-interest and nationalism thus prevailed over rationalism. Webster's new spelling could succeed because it was supported by a strong political ideology, because it was not so sweeping as to burn all the bridges and make literature in the conventional orthography unintelligible, and because the population concerned was favourably disposed to novelty and not strongly tied to a literary tradition, hailing to a large part from less-educated strata of society. If any generalisation can be drawn from this example, it would seem to be that in spelling reforms ideological motives are more important than correcting system-intrinsic flaws of the extant norm, although it is usually properties of this kind --- irregularity, redundancy, polyvalence --- that are first put forth by reform proponents.
私が興味を引かれたのは,第2段落後半に言及がある印刷と本作りに関するくだりである.アメリカ綴字で印刷された本はイギリスでは売れない.それは結構なことである.アメリカ国内で印刷産業が育つことになり,イギリスから本を輸入する必要もなくなるからだ.この綴字改革の政治経済的インパクトを予見していたとすれば,Webster,まさに恐るべしである.
・ Coulmas, Florian. "Sociolinguistics and the English Writing System." The Routledge Handbook of the English Writing System. Ed. Vivian Cook and Des Ryan. London: Routledge, 2016. 261--74.
・ Webster, Noah. Dissertation on the English language. Boston, MA: Isaiah Thomas and Co., 1789. Available online at https://archive.org/stream/dissertationsone00webs#page/20/mode/2up.
・ Mencken, H. L. The American Language: An Inquiry into the Development of English in the United States. 4th ed. New York: Alfred A. Knopf, 1945 [1919].
2022-01-17 Mon
■ #4648. 言語とジェンダーを巡る研究の3タイプ [gender][gender_difference][sociolinguistics][linguistic_ideology]
昨日の記事「#4647. 言語とジェンダーを巡る研究の動向」 ([2022-01-16-1]) に引き続き,昨今の言語とジェンダーを巡る研究について.『日本語学大辞典』より「ジェンダー」の項を執筆している,この分野の第一人者である中村桃子氏によれば,同分野の研究には3つのタイプがあるという.
ジェンダー 社会文化的性差.1960年代にフェミニズムによって提案された.一般には「女らしさ,男らしさ」と呼ばれる.セックス(生物学的性別)と別にジェンダーを設定することにより,「女/男らしさ」は社会によってつくられ,ゆえに,変えられることを示した.多くの近代社会のジェンダーには,(1) 両極に2分されている,(2) 補い合う対をなす,(3) 非対称的な権力関係である(男が「主体」で,女は「他者」),(4) 人種・民族・階級・宗教・年齢など他の権力関係と交差している,などの特徴が認められる.しかし,セックスは生物学的事実でジェンダーは文化的構築物だとして両者を区別する考え方は,1980年代のポスト構造主義によって否定された.スコット (Joan Scott) は,ジェンダーとは「身体的差異に意味を付与する知」だと述べ,バトラー (Judith Butler) も,ジェンダーはセックスをあたかもその起源であるかのように遡及的に構築すると主張している.さらに,異性愛を規範とみなすセクシュアリティもジェンダーの2分法によって構築されていることが指摘され,セックスもセクシュアリティもジェンダーによって規定されていることが明らかになった.現在ジェンダーは人文社会科学に不可欠な重要概念である.言語とジェンダーの研究は,大きく3つに分けられる.第1は,ジェンダーに関する常識や知識(ジェンダー・イデオロギー)はどのように構築されたのかを明らかにする言説分析である.これは,常識や知識は言説によって作られるというフーコー (Michel Foucault) 等の指摘に基づいている.性差別表現や言葉によるセクハラなど,性差別を構成する言語の是正が提案された.また,女性語や男性語も,女性や男性が実際に使ってきた言葉使いではなく,言語に関わるジェンダー・イデオロギーとして捉え直され,言説による歴史的構築が研究されている.第2は,会話分析,談話分析,語用論などにより,ジェンダー・アイデンティティの構築過程を明らかにする分野である.初期の研究においては,ジェンダーを話し手の属性とみなす本質主義に基づいて,男女の話し方の違いを明らかにする性差研究が行われていた.しかし,人は,あらかじめ持っているアイデンティティを表現するためにことばを使っているのではなく,さまざまな話し方を使い分けることで多様なアイデンティティを表現していることが明らかになった.そこで,アイデンティティを言語行為の原因ではなく結果とみなす構築主義が提案された.ジェンダーは,言語行為によって作り上げるアイデンティティ,「ジェンダーする」行為の結果である.構築主義によれば,女性語のように特定のアイデンティティと結びついた言語要素は,女性に限らずだれもがアイデンティティ構築に利用できる言語資源として捉え直される.いつ,どのような言語資源をアイデンティティ構築に利用するのか,話し手の主体性が強調される.第3は,この主体的な言語行為が既存のジェンダー秩序を変革する方策を明らかにすることである.聞き手に理解してもらうためには,社会で共有されている言語資源を使うしかない.しかし社会には,限られたアイデンティティと結びついた言語資源しか用意されていない.その結果,話し手は,さまざまな言語資源を組み合わせたりずらしたりしながら,多様なアイデンティティを表現することになる.このような「ずれた言語行為」には,ジェンダーの支配関係を変化させる可能性がある.
3つのタイプにラベルを貼りつければ,次のようになるだろうか.
(1) 社会のジェンダー・イデオロギーの構築に関する研究
(2) 個人のジェンダー・アイデンティティの構築に関する研究
(3) 既存のジェンダー秩序の変革に関する研究
なお,英語史研究においては,古い時代の文献を主に扱うからだろうか,いまだに言語使用の男女差という「古典的」というべき話題が多いように思われる.
・ 日本語学会(編) 『日本語学大辞典』 東京堂,2018年.
2021-12-09 Thu
■ #4609. 英語史における標準語信仰と古代純粋語信仰 [historiography][linguistic_ideology][language_myth]
英語史に関する神話については,最近も「#4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視」 ([2021-12-04-1]),「#4605. 規範英文法ならぬ規範英語史」 ([2021-12-05-1]) などで考えてきた.内容としてはそれらの繰り返しでもあるのだが,Milroy が指摘している2つの重要な神話,すなわち「標準語信仰」と「古代純粋語信仰」について改めて考えてみたい.
まず,Milroy (25) より「標準語信仰」について.
. . . the typical history has been influenced by, and sometimes driven by, certain ideological positions. The first of these implicitly suggests that the language is not the possession of all its native speakers, but only of the elite and the highly literate, and that much of the evidence of history can be argued away as error or corruption. The effect of this is to focus on what is alleged to be the standard language, but this is actually the language of those who have prestige in society, which may not always be a standard in the full sense. Of course, it may often be the same as the standard language, but this elitism can also mislead us into believing that speech communities are far less complex than they actually are and that the history of the language is very narrowly unilinear. We need a more realistic history than this.
次に,Milroy (25--26) より「古代純粋語信仰」について.
The second position can be briefly characterised as an ideology of nationhood and sometimes race. This ideology requires that the language should be ancient, that its development should have been continuous and uninterrupted, that important changes should have arisen internally within this language and not substantially through language contact, and that the language should therefore be a pure or unmixed language. I have tried to show that much of the history of English is traditionally presented within this broad framework of belief. The problem, I have suggested, is that, prima facie, English as a language does not seem to fit in well with these requirements. For that reason much ingenuity has been expended on proving that what does not seem to be so actually is so: Anglo-Saxon is English, the development of English has been uninterrupted and the language is not mixed. The most recent strong defence of this position --- by Thomason and Kaufman (1988) --- is merely the latest in a long line. It demonstrates that this system of belief is --- for better or worse --- still operative in the historical description of English.
2つの神話・信仰の内容はよくわかるし,傾聴に値する.
しかし,1点気になることがある.最初の引用で Milroy が,否定的な文脈ではあるものの,"the language is not the possession of all its native speakers" と述べ,言語が母語話者の所有物という点を前提としている点だ.確かにたいていの言語はその母語話者の生活に最も多く寄与するものであり,まずもって母語話者の所有物であるという見解は一見すると妥当のように思われる.しかし,現代の英語のようなリンガ・フランカについて語る文脈にあっては,母語話者だけの所有物であることを前提としてよいのだろうか.非母語話者を含めた英語話者全体の所有物であるという発想は浮かばなかったのだろうか.Milroy は伝統的な英語史がエリートや知識人だけの英語を扱ってきたことを非難しているが,Milroy の英語史観とて,母語話者だけの英語を扱うことを前提としているかのように聞こえ,違和感が残る.
・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.
・ Thomason, Sarah Grey and Terrence Kaufman. Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: U of California P, 1988.
2021-12-05 Sun
■ #4605. 規範英文法ならぬ規範英語史 [historiography][linguistic_ideology][language_myth]
昨日の記事「#4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視」 ([2021-12-04-1]) に引き続き,伝統的な英語史記述に対する Milroy の批判について考えてみたい.昨日 Milroy の論考の冒頭の1段落を引用したが,その次の段落も実にインパクトが強く,ガツンと頭を殴られたような気がした.
This conventional history, as it appears in written histories of English for the last century or more, can be viewed as a codification -- a codification of the diachrony of the standard language rather than its synchrony. It has the same relationship to this diachrony as handbooks of correctness have to the synchronic standard language. It embodies the received wisdom on what the language was like in the past and how it came to have the form that it has now, and it is regarded as, broadly, definitive.
共時的なレベルにおいて規範英文法が標準英語を成文化しているのと同じように,通時的なレベルにおいて伝統的な英語史記述が,すなわち「規範英語史」が標準英語の歴史を成文化しているのだという指摘には,虚を突かれた.この見方によると,伝統的な英語史記述を受け入れ,広めることは,すなわち標準英語(の歴史)を受け入れ,広めることにつながる.このこと自体の是非はともかくとして,それを十分に認識した上で伝統的な英語史記述を受けれたり,広めたりしてきただろうか,と自問自答してしまった.標準英語以外にも様々な英語があるのと同様に,伝統的な英語史記述以外にも様々な英語史の描き方があるはずである.
"the history of English" は存在しない."alternative histories of English" があるだけである.ただし,ひとときに描けるのは,せいぜい "a history of English" である.その時々で様々にあるものの中から,どの1つを選んで提示するのか.その選択の根拠や狙いは何か.このような問いに常に意識的でありたい.
・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.
2021-12-04 Sat
■ #4604. 伝統的な英語史記述の2つの前提 --- ゲルマン系由来と標準英語重視 [historiography][indo-european][linguistic_ideology][language_myth]
英語史という分野は,それ自体の歴史も長いので,伝統的な「英語史記述」というべきスタイルが確立している.英語史の著書は多くあるが,大多数の記述方針は一致している.英語が印欧語族のなかのゲルマン語派に属する言語であるところから始め,とりわけ近代以降に標準英語 (Standard English) という1変種にのみ注目して,現代までの歴史を描くというものだ.
この伝統的な英語史記述の基本方針は,私の大学の英語史概説の授業でも採用してきたし,これまで書いてきた英語史関連の書籍や記事でも前提としてきた.しかし,概説レベルから抜け出して学術的に英語史に向き合うならば,上記のような伝統的な英語史記述にのみ肩入れしているわけにはいかないことは重々承知している.慣習的な英語史記述を相対化する視点が必要だと常々思っている.
伝統的な英語史記述を批判的に評価するに当たって「#3897. Alternative Histories of English」 ([2019-12-28-1]) で紹介した同名の論考集より,第1章を執筆した Milroy (7) の冒頭の1段落を引用しておきたい.上にも触れたように,従来の主流派の英語史記述には,2つの前提があるという指摘だ.
The word 'history' is often understood simplistically to mean an accurate account of what happened in the past; yet, the writing of history can depend on differing underlying assumptions and can lead to differing interpretations. There can therefore be alternative histories of the same thing, including alternative histories of language. This chapter is about what may be called the conventional history of the English language, as it appears in many accounts, e.g. Jespersen (1962) and Brook (1958). This is seen as a particular version of history, which is one of a number of potential versions, and it is assumed that this version has reasonably clear and recurrent characteristics. The most prominent of these are: (1) strong emphasis on the early history of English and its descent from Germanic and Indo-European, and (2) from 1500 onward, an almost exclusive focus on standard English. Thus, the functions of this history are primarily to provide a lineage for English and a history for the standard language (in effect, the recent history of English is defined as the history of this one variety). Plainly, if we chose to focus on varieties other than the standard and if we did not accept the validity of the Stammbaum model of language descent, the version of history that we would produce would be substantially different.
この書き出しからして,社会言語学者 Milroy による伝統的な英語史記述への疑念が生々しく伝わってくる.多くの英語史学習者(そして研究者)が前提としている2点について,もし疑ってみたら,どんな英語史記述になるのだろうか.英語が世界語となっている現在,この思考実験はとても重要である.
・ Milroy, Jim. "The Legitimate Language: Giving a History to English." Chapter 1 of Alternative Histories of English. Ed. Richard Watts and Peter Trudgill. Abingdon: Routledge, 2002. 7--25.
2021-11-26 Fri
■ #4596. 「英語に関する不平不満の伝統」の歴史的変化 [complaint_tradition][sociolinguistics][linguistic_ideology]
英語の歴史を通じて観察されてきた "the complaint tradition" 「英語に関する不平不満の伝統」については「#3239. 英語に関する不平不満の伝統」 ([2018-03-10-1]) を始めとして complaint_tradition の各記事で取り上げてきた.中世から現代に至るまで,そしておそらくは未来にかけても,この伝統は続いていくだろう.
しかし,これを伝統とひとくくりにしてしまうと,かえって見えなくなることもある.というのは,英語に関する不平不満の内実や種類は時代とともに変化してきたからである.ある時代には不平不満の矛先は国家主義や方言変異に向けられていたが,別の時代には規範主義や政治的公正さ (pc) に向けられるなど,不平不満のあり方そのものが通時的に変化してきたのである.
上記の趣旨での Crowley (981) による "the complaint tradition" の概説を読み,たいへん刺激を受けた.そのイントロの文章を引用したい.
It is worth noting at the start of this account that the phrase "the complaint tradition" is slightly misleading. What it suggests is a continuing practice which, although it differs over time, is recognisably the same by dint of a common set of features. That is to say, a legacy which is more or less passed down over a prolonged period in which certain characteristics and themes recur. In one limited sense this is an accurate description of a practice which does indeed reach far back into the history of the English language; yet in another sense the conception of a "complaint tradition" is far too abstract and non-specific for analytical purposes. For while it is undoubtedly a matter of interest that people have consistently sought to complain about English since it became a language which was considered to be worthy of comment at all, what the general phrase "the complaint tradition" obscures is that fact that what precisely people were complaining about --- and why --- has varied historically. If the same complaints had been made about the English language throughout its history, it would perhaps be an interesting phenomenon but one which might be easily explained. As will be seen, however, complaints about English have been radically different at distinct points in the history of the language, and it is this which makes the "complaint tradition" both fascinating and complicated. The complaints themselves have ranged all the way from accusations that the English language was not "copious" enough for the purposes of various forms of written usage, to the charge that it is a vehicle of neo-imperialism in its acquired role as a global language; from the allegation that it was a debased and inconsistent language as a result of political corruption to the claim that it somehow caused moral decadence on the part of its users. What such variability tells us is that there has indeed been a long-standing practice of complaining about English, but that the criticism of the language has been historically specific and has often been intertwined with other arguments beyond the linguistic sphere. In other words, as has been noted elsewhere, language debates are very rarely simply debates about language; they are, more often than not, intertwined with questions of value.
各時代の人々の間に,言語に対する何らかの理想があるからこそ,そこに達していない現実への不平不満が募るのだろう.とすると,これは言語イデオロギー (linguistic_ideology) の問題といえる.英語(否,一般に言語)に関する不平不満の伝統そのものの歴史を明らかにしたいという気にさせる,素晴らしいイントロではないだろうか.
・ Crowley, Tony. "Standardization: The Complaint Tradition." Chapter 61 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 980--94.
2021-09-27 Mon
■ #4536. 言語イデオロギーの根底にある3つの記号論的過程 [linguistic_imperialism][linguistic_ideology][standardisation][world_englishes]
世界英語 (world_englishes) の話題は,言語イデオロギー (linguistic_ideology) の問題と結びつきやすい.英語帝国主義の議論 (cf. linguistic_imperialism) もその1つの反映である.このことは「#4466. World Englishes への6つのアプローチ」 ([2021-07-19-1]) でも触れられている.
そもそも言語イデオロギーをどのように解釈するか.「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1]) で1つの見方を示したが,今回は Bhatt (293) の見解を紹介する.まず定義に相当する部分を引用する.
Language ideologies, broadly construed, refer to beliefs, feelings, and conceptions of language structure and use that to serve political and economic interest of those in power . . . . Under this view, language---English, for our purposes---is used as a resource to promote and protect the econo-cultural and political interests of those in power; however, it must be noted that language ideologies are rarely brought up to the level of discursive consciousness.
平たくいえば,言語イデオロギーとは,特定の言語とその権力に関する信念体系であり,意識に上ることが少ない類いのもの,ということになる.Bhatt (293) は続けて,このイデオロギーの根底には3つの記号論的過程があるという.
The three semiotic processes underlying the ideological representation of language variation are: iconization---the process that fuses some quality of the linguistic feature and a supposedly parallel quality of the social group and understands one as the cause or the inherent, essential, explanation of the other . . . ; fractal recursivity---the projection of an opposition made at one level onto some other level so that the distinction is seen to recur across categories of varying generality; and erasure---selective disattention to, or non-acknowledgment of, unruly forms of linguistic variation, those that do not fit neatly into predetermined paradigms of linguistic descriptions.
記述的な言語研究は言語イデオロギーの解体に貢献し得るが,一方でそもそもそのような言語研究が特定の言語イデオロギーに立脚している可能性が常にあり,注意を要する.否,何らかの言語イデオロギーに立脚していない言語研究(や言語理論)はないといってよいだろう.
・ Bhatt, Rakesh M. "World Englishes and Language Ideologies." Chapter 15 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 291--311.
2021-08-29 Sun
■ #4507. World Englishes の類型論への2つのアプローチ [world_englishes][variety][typology][linguistic_ideology][ecolinguistics][methodology]
昨日の記事「#4506. World Englishes の全体的傾向3点」 ([2021-08-28-1]) で触れたように,世界英語 (world_englishes) の研究はコーパスなどを用いて急速に発展してきている.Fong (88) による概括を参照すると,研究の潮流としては,世界英語の普遍性と多様性を巡る類型論 (typology) には大きく2つの方向性があるようだ.
(1) 1つは様々な英語に共通する "angloversals" を探る方向性である.ENL と ESL の英語変種を比べても,一貫して受け継がれているかのように見える不変の特徴が確認される.ここから "angloversals" と称される英語諸変種の共通点を探る試みがなされてきた.「継承」という通時的な側面はあるが,その結果としての類似性を重視する共時的な視点といってよいだろう.
(2) もう1つは,どちらかというと英語の諸変種間で共通する側面や相違する側面があることを認め,なぜそのような共通点や相違点があるのかを,歴史社会的なコンテクストに基づいて説明づけようとする視点である.主唱者の Mufwene (2001) の見方を参照すれば,諸英語の歴史的発展は接触言語の特徴や社会経済的な環境,いわゆる「言語生態系」に敏感なものであるということになる.
Fong は,世界英語研究への対し方として,このような2つの系譜があることをサラっと紹介しているが,言語イデオロギー的には,この2つは相当に異なるベルクトルをもっているものと思われる.研究者も自らがどちらの視点に立つかを自覚しておく必要があるように思われる.
・ Fong, Vivienne. "World Englishes and Syntactic and Semantic Theory." Chapter 5 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 84--102.
・ Mufwene, S. S. The Ecology of Language Evolution. Cambridge: CUP, 2001.
2021-07-20 Tue
■ #4467. インド英語は「崩れた英語」か「土着化した英語」か? [variety][esl][indian_english][linguistic_ideology][sociolinguistics]
「#4463. 「印製英語」」 ([2021-07-16-1]) と「#4464. インド英語の歴史の時代区分」 ([2021-07-17-1]) でインド英語 (Indian English) の話題を取り上げた.インド英語に限らないのだが,ESL (English as a Second Language) や EFL (English as a Foreign Language) などの非母語変種を観察すると,当然ながら英米標準英語と異なる言語特徴が多く浮かび上がってくる.このような特徴をどうみるかに関して2つの対立する立場がある.
1つは,非母語話者がモデルとして想定していた英米標準英語を不完全にしか習得できなかったがゆえの言語的逸脱と見る立場である.「崩れた英語」観と呼んでおこう.もう1つは,その特徴を方言的革新ととらえ,それを含めて自立した英語変種であると見る立場だ.「土着化した英語」観と呼んでおきたい.1990--91年,「崩れた英語」観を唱えた Randolph Quirk と「土着化した英語」観を唱えた Braj Kachru の間で論争が起こった,世界英語の研究史における有名な論争である.
いずれの立場が真実を体現しているのだろうか.言語学的な観点からは,各々の言語特徴についてその起源と発達を調査したり,第2言語習得の知見を参照するなどして判断するという方法はあるだろう.しかし,それだけでは問題は解決しそうにない.というのは,これは純粋に言語学的な問題というよりは,言語変種に対する態度,もっといえば言語イデオロギーの問題だからだ.
インド英語研究に関していえば,先の記事で参照してきた Sharma (2089--90) によると,初期の研究はおよそ「崩れた英語」観に立つものが多かったが,最近では「土着化した英語」観に立つものが増えてきているという.英語規範を英米変種など外に仰ぐ "exo-normative" な見方から,規範を自身で内に築き上げる "endo-normative" な見方へ移行してきているようだ.ただし,Sharma (2090) が締めくくりの言葉として "Indian English . . . undergoing a shift from exonormative to endonormative stablization but not as fully nativezed and diversified as native varieties" と述べているように,現在のインド英語は,両極の中間,過渡期的な位置づけにあるというのが事実のように思われる.
・ Sharma, Devyani. "Second-Language Varieties: English in India." Chapter 132 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 2077--91.
2021-07-19 Mon
■ #4466. World Englishes への6つのアプローチ [world_englishes][variety][sociolinguistics][lingua_franca][contact][linguistic_ideology][linguistic_imperialism]
現代世界に展開する様々な英語変種,いわゆる "World Englishes" の研究は,この40年ほどの間,主に社会言語学の立場から注目されてきた.世紀をまたぐこの数十年間,リングア・フランカとしての英語は存在感を著しく増し,世界を席巻する社会現象というべきものになった.英語研究においても明らかにその衝撃が感じられ,例えば World Englishes に関する学術雑誌が続々と発刊されてきた.English World Wide (1979),English Today (1984) ,World Englishes (1985) などである.
World Englishes は(応用)言語学の様々な角度から迫ることができる.英語史も様々な角度の1つであり,本ブログでも種々に取り上げてきた次第である.Mesthrie and Bhatt の序説 (1) によると,World Englishes へのアプローチとして6点が挙げられている.
・ as a topic in Historical Linguistics, highlighting the history of one language within the Germanic family and its continual fission into regional and social dialects;
・ as a macro-sociolinguistic topic 'language spread' detailing the ways in which English and other languages associated with colonisation have changed the linguistic ecology of the world;
・ as a topic in the filed of Language Contact, examining the structural similarities and differences amongst the new varieties of English that are stabilising or have stabilised;
・ as a topic in political and ideological studies --- 'linguistic imperialism' --- that focuses on how relations of dominance are entrenched by, and in, language and how such dominance often comes to be viewed as part of the natural order;
・ as a topic in Applied Linguistics concerned with the role of English in modernisation, government and --- above all --- education; and
・ as a topic in cultural and literary studies concerned with the impact of English upon different cultures and literatures, and the constructions of new identities via bilingualism.
このような概説は,実に視野を広げてくれる.私など World Englishes を主として英語史の立場から見るにすぎなかったが,とたんに多次元の話題に見えてくるようになった.各分野の概説書の第1ページというものは,しばしば啓発的である.
・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.
2021-07-03 Sat
■ #4450. 中英語期は,英語とフランス語が共存・接触した時代 [french][contact][anglo-norman][bilingualism][reestablishment_of_english][historiography][language_myth][linguistic_ideology]
伝統的な英語史記述では,中英語期は英語が(アングロ)フランス語のくびきの下にあった時代として描かれる.1066年のノルマン征服の結果,英語はイングランド社会において自律性を失い,代わってフランス語が「公用語」となった.しかし,12世紀以降,英語の復権はゆっくりではあるが着実に進み,14世紀後半には自律性を回復するに至った.このように,中英語期に関しては,浮かんでいた英語がいったん沈み,再び浮かび上がる物語として叙述されるのが常である.
しかし,Trotter (1782) は,このような中英語期の描き方は神話に近いものだと考えている.当時の英語と(アングロ)フランス語の関係は,浮き沈みの関係,あるいは時間軸に沿って交替した関係ではなく,むしろ共存・接触の関係とみるべきだと主張する.この時代にフランス語が英語に与えた言語的影響を考察する上でも,共存・接触関係を前提とすることが肝要だと説く.
In much which is still being written on the history of medieval English, the specialist scholarship from the Anglo-French perspective has not been taken into account. Even in quite recent publications, Middle English scholarship continues to recycle a history of Anglo-French to which Anglo-French specialists would no longer subscribe. A particular example in the persistence of the traditional "serial monolingualism" model . . ., according to which Anglo-Saxon gives way to Anglo-French, pending the revival of Middle English, with each language succeeding the other. Born out of the 19th-century nationalist ideology which accompanied and prompted the emergence of philology in England and elsewhere . . ., this model ignores the reality of the long-term coexistence of languages, and of language contact . . . . Prominent amongst the areas in which language contact, going far beyond the limited "cultural borrowing" model, is evident, are (a) wholesale lexical transfer, (b) language mixing, (c) morphosyntactic hybridization, and (d) syntactic/idiomatic influences.
確かに中英語期にフランス語が英語に与えた言語的影響の話題を導入する場合,まずもって文化語の借用から話しを始めるのが定番だろう.典型的には「#1210. 中英語のフランス借用語の一覧」 ([2012-08-19-1]) や「#331. 動物とその肉を表す英単語」 ([2010-03-24-1]) などを提示するということだ.しかし,そこで止まってしまうと,両言語の接触に関して表面的な理解しか得られずに終わることになる.一歩進んで,引用の (a), (b), (c), (d) のような,より深い言語的影響があったことまで踏み込みたいし,さらに一歩進んで両言語の関係が長期にわたる共存・接触の関係だったことに言及したい.
・ Trotter, David. "English in Contact: Middle English Creolization." Chapter 114 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1781--93.
2018-04-20 Fri
■ #3280. アメリカにおける民族・言語的不寛容さの歴史的背景 [sociolinguistics][aave][ame_bre][ame][linguistic_ideology][ethnic_group]
英語を主たる言語としてもつ英米両国では,言語における標準 (standard) のあり方,捉え方が異なる.イギリスでは標準的な発音である RP が存在するが,アメリカでは RP に相当する威信をもった唯一の発音は存在しない.また,標準と非標準を区別する軸は,イギリスでは階級 (class) といえるが,アメリカでは民族 (ethnic group) にあるというべきだろう.この違いは両国の歴史と社会を反映している.以下,18世紀以降のアメリカの状況を Milroy and Milroy (157--58) に従って略述しよう.
アメリカが民族という観点から,例えば AAVE のような英語変種に対する寛容さを欠いているのには歴史的な背景がある.18世紀までは,アメリカにも言語的寛容さが相当に存在した.国家としても話者個人としても多言語使用は日常の事実だったのだ.まず第1に,18世紀のアメリカには,植民地支配の伝統を有する支配的な言語として,英語のほかにスペイン語やフランス語も存在していた.南西部やフロリダでは,むしろ英語よりもスペイン語を使用する伝統のほうが長かったし,フランス語の伝統を受け継ぐ地域もあった.第2に,初期の植民者たちはアメリカ先住民の諸言語に触れてきた経緯があり,ほかにドイツ人植民者のコミュニティなどもあった.アメリカにおける全体的な英語の優勢は疑い得なかったとしても,多言語使用は社会的に忌避される対象などではなかった.
ところが,19世紀が進むにつれ多言語使用に対する寛容さが失われ,英語偏重思想が表出してきた.これには,世紀半ばのゴールド・ラッシュが1つの契機となっている.中国人移民が金を求めて西部に大量に入ったことにより,強烈な排外思想が生まれた.1848年のアメリカによる南西部メキシコ領の併合も,スペイン語話者に対する英語話者の優勢思想を惹起し,民族・言語的不寛容を増長させるのに一役買った.そして,1878年にはカリフォルニアが初の「英語オンリー」の州となった.このような不寛容な社会風潮のなかで,先住民の諸言語も軽視されるようになった.最後に,奴隷貿易や南北戦争の歴史も,当然ながらこの民族・言語的不寛容の重要な背景をなしている.その後,この風潮は,20世紀,そして21世紀にも受け継がれている.
Milroy and Milroy (160) のまとめに耳を傾けよう.
In the US, bitter divisions created by slavery and the Civil War shaped a language ideology focused on racial discrimination rather than on the class distinctions characteristic of an older monarchical society like Britain which continue to shape language attitudes. Also salient in the US was perceived pressure from large numbers of non-English speakers, from both long-established communities (such as Spanish speakers in the South-West) and successive waves of immigrants. This gave rise in the nineteenth and twentieth centuries to policies and attitudes which promoted Anglo-conformity. To this day these are embodied in a version of the standard language ideology which has the effect of discriminating against speakers of languages other than English --- again an ideology quite different from that characteristic of Britain.
・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 4th ed. London and New York: Routledge, 2012.
2018-03-06 Tue
■ #3235. 標準語イデオロギー,標準化イデオロギー [linguistic_ideology][standardisation][language_myth][terminology]
標準語イデオロギー (standard language ideology) とは,Swann et al. の社会言語学辞典によると以下の通りである.
standard language ideology A concept introduced to sociolinguistics by James Milroy and Lesley Milroy (1999) in order to describe the prescriptive attitudes that accompany the emergence of standard languages. Standard Language Ideologies (SLIs) are characterised by a metalinguistically articulated and culturally dominant belief that there is only one correct way of speaking (i.e. the standard language). The SLI leads to a general intolerance towards linguistic variation, and non-standard varieties in particular are regarded as 'undesirable' and 'deviant'.
ここで参照されている Milroy and Milroy に,第4版(2012年)で当たってみると,p. 19 に関連する記述がある.
. . . it seems appropriate to speak more abstractly of standardisation as an ideology, and a standard language as an idea in the mind rather than a reality --- a set of abstract norms to which actual usage conform to a greater or lesser extent.
標準○○語というものが抽象物であることは,「#3232. 理想化された抽象的な変種としての標準○○語」 ([2018-03-03-1]) でも Milroy and Milroy を通じて確認した.そのような変種が存在すると信じることは,1つのイデオロギーであるということだ.これが「標準語イデオロギー」である.
さらに進めていえば,言語の標準化 (standardisation) という過程自体も実体としての過程というよりも,言語観察者の頭の中にあるイデオロギーにすぎないというべきだろう.こちらは「標準化イデオロギー」と呼んでよい.
「○○語史における標準化の形成と発展」というようなテーマを扱う場合には,そのテーマの立て方自体に1つの言語イデオロギーが宿っている点に注意すべきだろう.私もこれまで英語の標準化の歴史を素朴な疑問として追求してきたが,標準化を論じる際には,その前提にあるイデオロギー性に自覚的でなければならないと反省している.
・ Swann, Joan, Ana Deumert, Theresa Lillis, and Rajend Mesthrie, eds. A Dictionary of Sociolinguistics. Tuscaloosa: U of Alabama P, 2004.
・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 4th ed. London and New York: Routledge, 2012.
2018-03-03 Sat
■ #3232. 理想化された抽象的な変種としての標準○○語 [standardisation][linguistic_ideology][sociolinguistics]
標準英語の歴史に焦点を当てた論文集の巻頭で,Milroy (11) が非常にうまい言い方で標準○○語というものの抽象性について述べている.
It has been observed (Coulmas 1992: 175) that 'traditionally most languages have been studied and described as if they were standard languages'. This is largely true of historical descriptions of English, and I am concerned in this paper with the effects of the ideology of standardisation (Milroy and Milroy 1991: 22--3) on scholars who have worked on the history of English. It seems to me that these effects have been so powerful in the past that the picture of language history that has been handed down to us is a partly false picture --- one in which the history of the language as a whole is very largely the story of the development of modern Standard English and not of its manifold varieties. This tendency has been so strong that traditional histories of English can themselves be seen as constituting part of the standard ideology --- that part of the ideology that confers legitimacy and historical depth on a language, or --- more precisely --- on what is held at some particular time to be the most important variety of a language.
In the present account, the standard language will not be treated as a definable variety of a language on a par with other varieties. The standard is not seen as part of the speech community in precisely the same sense that vernaculars can be said to exist in communities. Following Haugen (1966), standardisation is viewed as a process that is in some sense always in progress.
標準○○語とは静的な存在物ではなく,動的で流体のようなものである.標準化という動的な過程を,静的なものへとマッピングした架空の抽象的な言語変種に近いということだ.もちろん,標準○○語に限らず,あらゆる言語変種がフィクションであるとはいえる(cf. 「#1373. variety とは何か」 ([2013-01-29-1]),「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]),「#2116. 「英語」の虚構性と曖昧性」 ([2015-02-11-1]),「#2265. 言語変種とは言語変化の経路をも決定しうるフィクションである」 ([2015-07-10-1])).しかし,標準○○語は,標準を神聖視するイデオロギーに支えられて,重層的なフィクション――フィクションのフィクション――になりやすい代物であるのかもしれない.「#1396. "Standard English" とは何か」 ([2013-02-21-1]) という問題に迫るにも,幾重もの表皮をはぎ取らなければならないのだろう.
・ Milroy, Jim. "Historical Description and the Ideology of the Standard Language." The Development of Standard English, 1300--1800. Ed. Laura Wright. Cambridge: CUP, 2000. 11--28.
・ Coulmas, F. Language and Economy. Oxford: Blackwell, 1992.
・ Milroy, Lesley and James Milroy. Authority in Language: Investigating Language Prescription and Standardisation. 2nd ed. London and New York: Routledge, 1991.
・ Haugen, Einar. "Dialect, Language, Nation." American Anthropologist. 68 (1966): 922--35.
2018-01-31 Wed
■ #3201. アメリカ英語の「保守性」について --- Algeo and Pyles の見解 [ame_bre][ame][colonial_lag][linguistic_ideology]
標題について,「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]),「#2926. アメリカとアメリカ英語の「保守性」」 ([2017-05-01-1]) をはじめ,colonial_lag や ame_bre の各記事で様々に論じてきた.私自身の書いたまとまった記述としては,本ブログ記事以外に,「#2916. 連載第4回「イギリス英語の autumn とアメリカ英語の fall --- 複線的思考のすすめ」」 ([2017-04-21-1]) でも同種の問題について論じている.
英語の英米差については,英語史研究者による様々なコメントがあるが,英語史の概説書の古典 Algeo and Pyles (205) の所見を紹介したい.英米差の評価として,事実に即しており,的確かつ妥当な見解だと思う.
On the whole . . . American English is essentially a conservative development of the seventeenth-century English that is also the ancestor of present-day British. Except in vocabulary, there are probably few significant characteristics of New World English that are not traceable to the British Isles. There are also some American English characteristics that were doubtless derived from British regional dialects in the seventeenth century, for there were certainly speakers of such dialects among the earliest settlers, though they would seem to have had little influence.
The majority of those English men and women to settle permanently in the New World were not illiterate bumpkins but ambitious and industrious members of the upper-lower and lower-middle classes, with a sprinkling of the well-educated---clergymen and lawyers---and even a few younger sons of the aristocracy. It is likely that there was a cultured nucleus in all of the early American communities. Such facts as these explain why American English resembles present standard British English more closely than it resembles any other British type of speech. The differences between the two national varieties are many but not of great importance.
この引用文では,イギリス(標準)英語とアメリカ英語のあいだに言語学的および歴史社会言語学的な連続性があることが明瞭に述べられている.アメリカ英語について,イギリス(標準)英語からの連続性を強調することは,その保守性を主張することにはなろう.このスタンス自体がある種の言語イデオロギー (linguistic_ideology) である可能性を認めつつ,私もこの立場を取りたい.
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow