2022-04-08 Fri
■ #4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版) [hel_education][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]
大学なども新年度が始まりつつあると思います.私の所属する慶應義塾大学も昨日から本格的に学期がスタートしました.昨日の記事「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1]) の通りです.
4月1日より khelf(慶應英語史フォーラム)の協力のもと「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) しています.英語史の学びを応援するいくつかのイベントがすでに始まっていますが,それらのベースキャンプとして捉えてもらいたいのが,この hellog~英語史ブログです.
hellog には日々英語史に関する話題を上げてきましたが,増え続けるバックナンバーを,キーワードなどを媒介としてリンクで結ぶことにより,一種のデータベースのようなものができあがってくることに気付きました.これは hellog を始めた当初は私も思いも寄らなかった効果なのですが,かなり強力なデータベースができあがっています.私自身,一日に何度も hellog を検索しています.
昨年度の「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]) を上書きする形で,2022年度版を以下に示します.
(1) hellog では,英語に関する素朴な疑問を重視してきました.そのなかから多くの読者の皆様に読まれている記事が浮上してきます.アクセス・ランキングのトップ500記事をご覧ください.
(2) 英語に関する素朴な疑問集もお薦めです.本ブログでは,英語学習者から数年にわたって収集した数々の「英語に関する素朴な疑問」に答えてきました.疑問集をまとめた英語に関する素朴な疑問の一覧(2020年度と2021年度の統合版)もご覧ください.あわせて,最近始めた知識共有サービス「Mond」への回答も,ぜひご一読を.
(3) hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) を日々運営しています.音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) をご覧ください.hellog 同様,主として英語に関する素朴な疑問を取り上げています.
(4) 講義・講座等で用いてきたスライド資料の多くを,ブログ記事として公開しています.cat:slide よりご覧ください.大きめのテーマを扱っていることが多く,スライドだけでは何のことか分からない部分もあると思いますが,ざっと眺めるだけでも概要は学べると思います.
(5) 毎回の hellog 記事では,雑多でランダムな話題を扱っていますが,多数の記事のあいだの関連性を確保する手段として「カテゴリー」と「記事セット」という概念を採用しています.「カテゴリー」はその名の通り,各記事に付けられているカテゴリー・タグに基づいて記事群をまとめたもので,トップページの右下のアルファベット順に並んでいるカテゴリーの一覧からアクセスできます.トップページ最上部の検索欄に "cat:○○" と入力してもらうこともできます.例えば,"cat:norman_conquest" や "cat:start_up_hel_2022" などと入れてみてください.
(6) もう1つの「記事セット」という概念は,記事番号を連ねることで,複数の任意の記事をまとめて閲覧できる仕様です.トップページ最上部の検索欄に,カンマ区切りの一連の記事番号を入力してみてください.その順序で,見やすい形式で記事が表示されます.
「記事セット」は簡易的なスライドともなるので,私自身も講義・講座に頻繁に利用しています.私がよく行なうのは,例えば「英語語彙の世界性」 (cosmopolitan_vocabulary) という話題について講義しようとする場合に,"##151,756,201,152,153,390,3308" という構成で記事(とそこに含まれる視覚資料)を順に示して解説していくというものです(先頭の "##" は任意).
この新年度には,「英語史スタートアップ」企画に関する記事セットをお薦めしておきましょう.
他にも様々な記事セットを提供してきましたので,具体例として cat:hellog_entry_set の各記事からジャンプしていただければと思います.
(7) 本ブログでは,図表や写真をはじめとする視覚資料をなるべく多く掲載するように努めてきました.とりわけ地図 (map),言語系統図 (family_tree),年表 (timeline) などは多く掲載していますので,お薦めです.漫然と眺めるだけでも学べると思います.画像集も,13年間の蓄積により,だいぶんたまってきました.
(8) トップページの右手に「ツール」という欄があります.CGIを用いた1世代前のスクリプトですでに動かないものもありますが,なかには便利なものもあります.例えば,Frequency Sorterは,単語群を頻度順にソートしてくれる便利ツールで,私もよく使っています.また,hel typist はASCIIのみを用いて発音記号(国際音標文字,IPA)を出力するためのツールで,日々の hellog 執筆に欠かせないツールとなっています.他にもおもしろいツールを探してみてください.cgi や web_service も参照.
(9) hellog の外ではありますが,英語史に関するオンライン(連載)記事を機会あるごとに書いてきました.とりわけ2017年1月から12月にかけて連載した12本のオンライン記事「現代英語を英語史の視点から考える」は,内容的にもまとまっており,お薦めです.もう1つ,昨秋の IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビュー「英語はいかにして世界の共通語になったのか」もどうぞ.
(10) 最後に,hellog は雑多な記事群ですので,本格的な学びのためにはまったく不十分です.体系的な英語史の学びのために,ぜひ概説書を読んでください.最新の推薦図書のリストは「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]) をどうぞ.さらに「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) と,その heldio 版「対談 英語史の入門書」も参考までに.
今後もオンライン学習・教育の機会は続き,増えていくと予想されます.上記を参考に hellog を有効利用していただければ幸いです.
2022-04-07 Thu
■ #4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります [hel_education][hellog][hellog-radio][heldio][hellog_entry_set][link][start_up_hel_2022]
慶應義塾大学文学部英米文学専攻では,必修科目の1つに「英語史」の講義があります.本日,今年度の同講義が開始となります.1年間をかけて英語の歴史を紐解いていく予定です.
本日の初回は,重要なイントロの回になりますが,本ブログの記事を組み合わせることで講義を展開していく予定です.情報量が多いので,講義で完全消化できなかった場合であっても,履修生の皆さんはいつでもこの記事に戻ってくることができます.また,一般の hellog 読者の方も,以下のリンクを通じて,部分的・擬似的に初回授業を体験できるかと思います.目下,新年度ということで「#4722. 新年度の「英語史スタートアップ」企画を開始!」 ([2022-04-01-1]) として,英語史に関心のあるすべての方々の学びを応援しているので,あえてこのような形態を取る次第です.
1. イントロ
1.1. 「#831. Why "an apple"?」 ([2011-08-06-1]): 不定冠詞 a と an について.heldio の 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」もどうぞ.
1.2. 「#2. 自己紹介」 ([2009-05-01-2]): 担当者の紹介
2. 英語史の世界へようこそ
2.1. 「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]): 英語史の魅力4点
(1) 英語の見方が180度変わる!
(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!
(4) 現代英語に戻ってくる英語史
2.2. 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]): 魅力 (2) に通じます
2.3. 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット: 様々な角度から「なぜ学ぶのか」を検討してみました(cf. 「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています)
3. 英語に関する素朴な疑問
3.1. 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]): 魅力 (3) に通じます
3.2. 2685件の素朴な疑問
3.3. これまで hellog で取り上げてきた素朴な疑問集
3.4. 知識共有サービス「Mond」で,英語・言語に関する素朴な疑問に回答しています
4. 英語史を日常の話題に
4.1. 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]): 毎日欠かさず更新している英語史のブログです.この hellog の効果的な使い方の tips をどうぞ.
4.2. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio): hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) .毎日欠かさず1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.年度初めは英語史研究者との対談ものが多いです.
4.3. 「英語史スタートアップ」企画: 新年度開始に合わせて4月1日より始まっています
4.4. 「#4723. 『英語史新聞』創刊号」 ([2022-04-02-1]): 世界初の英語史に関する新聞の第1号です
4.5. 「#4725. khelf イベント「英語史コンテンツ50」が始まっています」 ([2022-04-04-1]): ほぼ毎日,英語史を専攻するゼミ生・院生から手軽に読める「英語史コンテンツ」がウェブ上にアップされてきます
4.6. 「#4726. 昨年度のコンテンツ企画のベスト10」 ([2022-04-05-1]): 上記だけでは足りない,という方はこちらからどうぞ
4.7. 「#4724. 慶應英語史フォーラム (khelf) の活動」 ([2022-04-03-1]): khelf ホームページと公式ツイッターアカウント @khelf_keio も開設されています
4.8. 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」: 同専攻の井上逸兵先生と一緒に週2回(水・日)で放送しています
5. 英語史の読書案内
5.1. 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1]): 今年度版を昨日公表しました
5.2. 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]),および heldio での「対談 英語史の入門書」
6. ライヴで寄せられた英語の素朴な疑問に即興で答えるコーナー(時間があれば)
2022-04-06 Wed
■ #4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版) [bibliography][hel_education][link][start_up_hel_2022]
毎年度始めに,英語史の学習・研究に役立つ書誌の最新版を公表しています.英語史の学びに活用してもらえればと思います.
初学者にお薦めの図書に◎を,初学者を卒業した段階のお薦めの図書に○を付してあります.各図書の巻末などには,たいてい解題書誌や参考文献一覧が含まれていますので,さらに学習を続けたい方は芋づる式にたどっていくことができます.印刷用のPDFをこちらに用意しましたので,自由に配布していただいて結構です.関連して「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) もご参照ください.
[英語史(日本語)]
◎ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.
・ 宇賀治 正朋 『英語史』 開拓社,2000年.
◎ 唐澤 一友 『多民族の国イギリス --- 4つの切り口から英国史を知る』 春風社,2008年.
◎ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.
○ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.
・ 島村 宣男 『新しい英語史 --- シェイクスピアからの眺め ---』 関東学院大学出版会,2006年.
◎ 寺澤 盾 『英語の歴史』 中央公論新社〈中公新書〉,2008年.
・ 高橋 英光 『英語史を学び英語を学ぶ --- 英語の現在と過去の対話』 開拓社,2020年.
・ 中尾 俊夫,寺島 廸子 『図説英語史入門』 大修館書店,1988年.
・ 橋本 功 『英語史入門』 慶應義塾大学出版会,2005年.
◎ 堀田 隆一 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』 中央大学出版部,2011年.
○ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.
・ サイモン・ホロビン(著),堀田 隆一(訳) 『スペリングの英語史』 早川書房,2017年.
・ 松浪 有(編),小川 浩・小倉 美知子・児馬 修・浦田 和幸・本名 信行(著) 『英語の歴史』 大修館書店,1995年.
・ 柳 朋宏 『英語の歴史をたどる旅』 中部大学ブックシリーズ Acta 30,風媒社,2019年.
・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.
[英語史(英語)]
○ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.
◎ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
・ Blake, N. F. A History of the English Language. Basingstoke: Macmillan, 1996.
◎ Bradley, Henry. The Making of English. London: Macmillan, 1955.
○ Bragg, Melvyn. The Adventure of English. New York: Arcade, 2003.
○ Brinton, Laurel J. and Leslie K. Arnovick. The English Language: A Linguistic History. Oxford: OUP, 2006.
・ Bryson, Bill. Mother Tongue: The Story of the English Language. London: Penguin, 1990.
・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.
◎ Fennell, Barbara A. A History of English: A Sociolinguistic Approach. Malden, MA: Blackwell, 2001.
○ Gelderen, Elly van. A History of the English Language. Amsterdam, John Benjamins, 2006.
・ Görlach, Manfred. The Linguistic History of English. Basingstoke: Macmillan, 1997.
○ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.
・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.
・ Hogg, R. M. and D. Denison, eds. A History of the English Language. Cambridge: CUP, 2006.
・ Horobin, Simon. Does Spelling Matter? Oxford: OUP, 2013.
◎ Horobin, Simon. How English Became English: A Short History of a Global Language. Oxford: OUP, 2016.
・ Jespersen, Otto. Growth and Structure of the English Language. 10th ed. Chicago: U of Chicago, 1982.
○ Knowles, Gerry. A Cultural History of the English Language. London: Arnold, 1997.
・ McCrum, Robert, William Cran, and Robert MacNeil. The Story of English. 3rd rev. ed. London: Penguin, 2003.
・ Mugglestone, Lynda, ed. The Oxford History of English. Oxford: OUP, 2006.
・ Smith, Jeremy J. An Historical Study of English: Function, Form and Change. London: Routledge, 1996.
○ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.
○ Svartvik, Jan and Geoffrey Leech. English: One Tongue, Many Voices. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2006.
[英語史関連のウェブサイト]
・ 家入 葉子 「英語史全般(基本文献等)」 https://iyeiri.com/569 .(より抜かれた基本文献のリスト)
・ 堀田 隆一 「hellog~英語史ブログ」 2009年5月1日~,http://user.keio.ac.jp/~rhotta/hellog/ .
・ 堀田 隆一 「連載 現代英語を英語史の視点から考える」 2017年1月~12月,http://www.kenkyusha.co.jp/uploads/history_of_english/series.html .
・ 三浦 あゆみ 「A Gateway to Studying HEL」 https://sites.google.com/view/gatewaytohel/ .
[英語史・英語学の参考図書]
・ 荒木 一雄・安井 稔(編) 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.
・ 石橋 幸太郎(編) 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.
・ 大泉 昭夫(編) 『英語史・歴史英語学:文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.
・ 大塚 高信・中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.
・ 小野 茂(他) 『英語史』(太田 朗・加藤 泰彦(編) 『英語学大系』 8--11巻) 大修館書店,1972--85年.
・ 佐々木 達・木原 研三(編) 『英語学人名辞典』,研究社,1995年.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語史・歴史英語学 --- 文献解題書誌と文献目録書誌』 研究社,1997年.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.
・ 寺澤 芳雄・川崎 潔 (編) 『英語史総合年表 --- 英語史・英語学史・英米文学史・外面史 ---』 研究社,1993年.
・ 松浪 有・池上 嘉彦・今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.
・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012.
・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English. 5 vols. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.
・ Biber, Douglas, Stig Johansson, Geoffrey Leech, Susan Conrad, and Edward Finegan, eds. Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow: Pearson Education, 1999.
・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003.
・ Crystal, David. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: CUP, 1995. 2nd ed. 2003. 3rd ed. 2019.
・ Hogg, Richard M., ed. The Cambridge History of the English Language. 6 vols. Cambridge: CUP, 1992--2001.
・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum, eds. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.
・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.
・ van Kemenade, Ans and Bettelou Los, eds. The Handbook of the History of English. Malden, MA: Blackwell, 2006.
2022-03-26 Sat
■ #4716. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」を終えました --- これにて本当にシリーズ終了 [asacul][notice][history][link][slide][lexicology]
3月19日(土)15:30--18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて標題のお話しをさせていただきました.2年半ほど前より12回に渡る「英語の歴史と語源」シリーズを開講してきましたが,そのダイジェストとして番外編ではありますが第13回を開いた次第です.これで本当にシリーズ終了となります(シリーズ全体については「#4702. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」のご案内」 ([2022-03-12-1]) をご覧ください).第13回の番外編も前回に続き対面・オンラインのハイブリッド形式で行ないましたが,合わせて多くの方々にご参加いただきました.ありがとうございます.
ダイジェストとは言いながらも,実際には新しい話題も少なからず加えましたので,ある程度独立した内容となっていたかと思います.とりわけ英語と日本語の語彙史の比較などは,シリーズ中では簡単に触れることはあっても詳しくは取り上げてきませんでしたので,今回の機会を借りて注目することができました.
今回の講座で用いたスライドをこちらに公開します.以下はスライドの各ページへのリンクです.
1. 英語の歴史と語源・13「英語語彙の歴史 ? ダイジェスト英語の歴史と語源」
2. 「英語語彙の歴史 ? ダイジェスト英語の歴史と語源」
3. 目次
4. 1. はじめに ? 英語語彙史の概要
5. 過去12回の「英語の歴史と語源」シリーズ
6. 2. 英語語彙の規模と種類の豊富さ
7. 語源で世界一周
8. 3. 日英語彙史比較
9. 4. 印欧語族
10. 5. 英語語彙史の詳細
11. 6. 現代の英語語彙にみられる歴史の遺産
12. 7. 現代英語の新語形成
13. 8. 英語の人名の歴史
14. 9. 英語語彙史から考える語彙拡充の功罪
15. 「インク壺語」の大量借用
16. 大量借用への反応
17. インク壺語,チンプン漢語,カタカナ語の対照言語史
18. 10. おわりに
19. 参考文献
長きにわたってシリーズにご参加いただいた方々には感謝いたします.ありがとうございました.
今後は新シリーズとして4回にわたり「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」を開講する予定です.初回は少し先の6月11日(土)となりますが,案内はすでにこちらに出ていますので関心のある方はご参照ください.今後ともよろしくお願いいたします.
2022-03-25 Fri
■ #4715. 否定的な感情を表わす形容詞・副詞は強調語になりやすい [mond][sobokunagimon][intensifier][adjective][adverb][semantics][semantic_change][link]
今日はクロスポスト的な記事で新味がなくてすみません.それでも意味変化 (semantic_change) の観点から大事な話題なので,こちらでも取り上げる次第です.
この2ヶ月ほど「Mond」という質問サイトにて,英語史に関連のある質問に回答するということを行なってきました.最近の質問として,次の興味深い問いが寄せられてきました.
凄い(すごい)という言葉には
・ぞっとするほど恐ろしい
・並外れている.たいそうな.
という2つの意味がありますが,後者の意味で主に用いられている印象です.英語や他の言語にも失われつつある意味を持つ単語はあるのでしょうか?
これは,まさに古今東西の言語に普遍的な意味変化のパターンに関する質問です.強意語 (intensifier) は,使われすぎると強意がすり減って逓減していくものなので,新たに強意を表わす表現が常に求められるのです.新たな強意語のソースは,いろいろとあるのですが,その典型の1つが「否定的な感情語」です.怖い,おぞましい,痛い,苦しい,というホラー用語は,どうしても強調語になりやすいのですね.それは,なぜか? 10秒ほど考えれば分かると思います.あの負の感情が10秒続いたら,ちょっと参りますよね・・・
上記の質問を受けて,こんな感じで回答しました.
とても身近でおもしろい指摘,ありがとうございます.「すごい」に2つの意味があるというのは,それぞれの用例をみれば明らかですね.例えば「すごい目つき」といえば「恐ろしい」の意味だとわかりますし,「すごい美人」といえば「並外れた」の意味だとわかります.この2つの意味をざっくり区別するならば,「恐ろしい」は感情の種類・質に関する意味で,「並外れた」は物事の程度・量に関する意味ということになります.歴史的には前者から後者が派生しているので,質から量への意味変化と言っておいてよいかと思います.
この「質から量への意味変化」というのは,かなり普遍的なようです.とりわけ「恐ろしい」「痛い」「ひどい」といった否定的な感情・知覚を表わす形容詞・副詞は,しばしば感情の質そのものよりも,その感情の程度の甚だしさが注目され,結果として単なる強調表現になり下がるということが,よくあるパターンのようです.
日本語の「恐ろしく優しい」「痛く感心した」「ひどく喜んだ」のような例から分かる通り,文字通りの否定的な質の意味で解釈すると,むしろ矛盾するような表現もありますね.すでに量の意味になり下がっているということだと思います.
英語からも類例がいくらでも挙がります.terrible/terribly の語幹は terror 「恐怖」と同一ですが,本来の「恐ろしい/恐ろしく」の意味で使われることは少ないです (ex. a terrible weapon 「恐ろしい武器」) .むしろ,程度の激しいことを示すだけの強調語として in a terrible hurry 「非常に急いで」のように使うことのほうが多いです.質から量への意味変化が生じたもう1つの例ですね.
ほかには amazingly, awfully, desperately, dreadfully, horribly, marvellously, sorelyなど感情に起因する副詞は,強調語になり下がる例が多いようです.
おっしゃるとおり,これらの語では,本来の質的な意味は希薄になってしまい,ほとんどの場合,量的な意味で強調語として用いられるに至ったのだと思います.
いずれの言語でも,並行的な現象が見られるというのは,たいへん面白いですね.ありがとうございました.
関連して,英語に関する話題ではありますが,筆者によるこちらの記事をご覧ください.
鋭い質問は学びの基本だと思います.よく答えるよりもよく問うほうが圧倒的に難しいです.もう1週間で新年度が始まりますが,とりわけ新大学生は大学生活のなかで「問う方法」こそを習得してください!
強意語に関しては,以下の記事や intensifier もご参照ください.
・ 「#992. 強意語と「限界効用逓減の法則」」 ([2012-01-14-1])
・ 「#1220. 初期近代英語における強意副詞の拡大」 ([2012-08-29-1])
・ 「#1219. 強意語はなぜ種類が豊富か」 ([2012-08-28-1])
・ 「#2190. 原義の弱まった強意語」 ([2015-04-26-1])
・ 「#4236. intensifier の分類」 ([2020-12-01-1])
2022-03-13 Sun
■ #4703. 音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio) を整理しました [link][sobokunagimon][notice][hel_education][heldio][hellog-radio][heldio][youtube]
この1年9ヶ月ほどの間,本ブログの趣旨である「英語史に関する話題を広く長く提供し続ける」を音声メディアに載せる試みを続けてきました.
まず,2020年6月23日から2021年2月7日までは,不定期ではありましたが「hellog ラジオ版 (hellog-radio)」と題して,1つ10分程度の音声コンテンツを計62本,本サイトのなかで独自にアップロードしてきました.ちなみに初回は「#4075. なぜ大文字と小文字があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-06-23-1]) という話題でした(その他,hellog-radio の記事も参照).
その後,2021年6月2日より,音声コンテンツ配信用のプラットフォームとして Voicy に活動の場を移し,「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」と題するチャンネルにてコンテンツ配信を続けてきました.以後,本日に至るまで毎日10分程度の英語史の話題を配信してきました(計286本).
一貫して英語に関する素朴な疑問を中心とした内容にこだわってきましたが,上記のように途中からプラットフォームを変更したこともあり,音声コンテンツの在処が2カ所に分かれてしまっていました.これでは概観や検索に不便なので,このたび両プラットフォームからのコンテンツを一覧できるページを作りました.ブログ最上部のメニューにもありますが「音声コンテンツ一覧 (heldio & hellog-radio)」をクリックしてみてください.最新のものから順にコンテンツが整理されています.
この一覧ページは今後もなるべく頻繁に更新していきたいと思っていますが,再生回数などは常に変化しており,毎日更新というわけにもいきませんので,最新コンテンツについては「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でご確認ください.
さて,年明けの1月2日に「#4633. 2021年によく聴かれた「英語の語源が身につくラジオ」の放送」 ([2022-01-02-1]) で再生回数のランキングを覗いてみましたが,それから3ヶ月ほど経っていますし,今回一覧を整理するに当たって新しいランキングが得られましたので,よく聴かれている上位50コンテンツを挙げたいと思います.時間のあるときにでも気軽にお聴きください.
ちなみにトップは昨年9月17日の同僚の井上逸兵さんとの対談でした.実はこの収録のときに,音声コンテンツの対談もよいですが,いずれ YouTube 動画も一緒にどうでしょうかね,などというやりとりがあり,先日2月26日に YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設してしまったという次第です.
- 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(1,004回再生,第108回,2021/09/17 放送)
- 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」(993回再生,第1回,2021/06/02 放送)
- 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」(820回再生,第2回,2021/06/03 放送)
- 「なぜ否定語が文頭に来ると VS 語順になるの?」(719回再生,第88回,2021/08/28 放送)
- 「「塵も積もれば山となる」に対応する英語の諺」(629回再生,第3回,2021/06/04 放送)
- 「なぜ used to do が「〜したものだった」なの?」(502回再生,第169回,2021/11/16 放送)
- 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(495回再生,第144回,2021/10/22 放送)
- 「なぜ月曜日 Monday はムーンデイではなくマンデイなの?」(480回再生,第6回,2021/06/07 放送)
- 「harassment のアクセントはどこに置けばいいの?」(470回再生,第4回,2021/06/05 放送)
- 「なぜ one と書いてオネではなくてワンなの?」(427回再生,第7回,2021/06/08 放送)
- 「対談 英語史の入門書」(418回再生,第140回,2021/10/18 放送)
- 「meat のかつての意味は「食物」一般だった!」(386回再生,第5回,2021/06/06 放送)
- 「one, only, any は同語源って知ってました?」(386回再生,第8回,2021/06/09 放送)
- 「forget, forgive の for- とは何?」(384回再生,第87回,2021/08/27 放送)
- 「対談 英語史 X 国際英語」(368回再生,第141回,2021/10/19 放送)
- 「first の -st は最上級だった!」(365回再生,第9回,2021/06/10 放送)
- 「現在完了は過去を表わす表現と共起したらNG?」(350回再生,第83回,2021/08/23 放送)
- 「Japanese の -ese って何?」(346回再生,第165回,2021/11/12 放送)
- 「this,that,theなどのthは何を意味するの?」(343回再生,第233回,2022/01/19 放送)
- 「立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」(324回再生,第173回,2021/11/20 放送)
- 「英語語彙の1/3はフランス語!」(322回再生,第26回,2021/06/27 放送)
- 「前置詞ならぬ後置詞の存在」(318回再生,第133回,2021/10/11 放送)
- 「時・条件の副詞節では未来でも現在形を用いる?」(316回再生,第33回,2021/07/04 放送)
- 「read - read - read のナゾ」(315回再生,第199回,2021/12/16 放送)
- 「third は three + th の変形なので準規則的」(310回再生,第10回,2021/06/11 放送)
- 「なぜアメリカ英語では R の発音があ〜るの?」(309回再生,第14回,2021/06/15 放送)
- 「なぜ名詞は REcord なのに動詞は reCORD なの?」(302回再生,第15回,2021/06/16 放送)
- 「スーパーマーケットとハイパーマーケット」(302回再生,第43回,2021/07/14 放送)
- 「It's kind of you to come. の of」(302回再生,第91回,2021/08/31 放送)
- 「sheep と deer の単複同形のナゾ」(301回再生,第12回,2021/06/13 放送)
- 「対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(300回再生,第149回,2021/10/27 放送)
- 「shall とwill の使い分け規則はいつからあるの?」(300回再生,第218回,2022/01/04 放送)
- 「英語とギリシア語の関係って?」(299回再生,第137回,2021/10/15 放送)
- 「i, j の上の点は何?」(297回再生,第128回,2021/10/07 放送)
- 「-ly が付かない単純形副詞の用法と歴史」(292回再生,第127回,2021/10/05 放送)
- 「地球46億年の歴史における世界語としての英語」(292回再生,第134回,2021/10/12 放送)
- 「そもそも English という単語はナゾだらけ!」(290回再生,第16回,2021/06/17 放送)
- 「ウクライナ(語)について」(289回再生,第271回,2022/02/26 放送)
- 「a lot of の lot とは?」(287回再生,第100回,2021/09/09 放送)
- 「-ment, -ance など近代英語の名詞語尾の乱立」(286回再生,第170回,2021/11/17 放送)
- 「なぜ文頭や固有名詞は大文字で始めるの?」(285回再生,第50回,2021/07/21 放送)
- 「古英語期ってどんな時代?」(285回再生,第148回,2021/10/26 放送)
- 「なぜ will must のように助動詞を並べてはダメなの?」(284回再生,第152回,2021/10/30 放送)
- 「基本英単語100語の起源はほぼアングロサクソン」(282回再生,第106回,2021/09/15 放送)
- 「アメリカ英語の歴史と時代区分」(282回再生,第164回,2021/11/11 放送)
- 「星の star と星座の constellation」(281回再生,第168回,2021/11/15 放送)
- 「「対面授業」はレトロニムでした」(280回再生,第51回,2021/07/22 放送)
- 「なぜか second 「2番目の」は借用語!」(279回再生,第11回,2021/06/12 放送)
- 「重要な文法的単語には強音と弱音の2つの発音がある」(279回再生,第162回,2021/11/09 放送)
- 「接頭辞 dis- は否定なの,強調なの?」(278回再生,第225回,2022/01/11 放送)
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2022-03-12 Sat
■ #4702. 講座「英語の歴史と語源」のダイジェスト「英語語彙の歴史」のご案内 [asacul][notice][history][link]
2年半ほど前に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源」と題するシリーズ講座を開始しました.全12回の講座は,おかげさまをもちまして昨年10月23日(土)をもって終了いたしました.
さて,このたび上記シリーズのダイジェスト版となる単発講座「英語語彙の歴史」を開講することになりました.来週3月19日(土)15:30--18:45に開講予定です.新宿教室での対面のほか,オンラインも組み合わせた形式で開講しますので,空間に制限されずに参加いただけます.ご関心のある方はこちらよりご予約ください.ダイジェスト版とはいえ独立した1つの講座です.趣旨は以下の通りとなります.
英語の語彙は世界一の規模を誇りますが,語源の観点からみても種類が実に豊富です.英語の語彙が規模・種類において豊かであることは,英語がたどってきた歴史,とりわけ多くの言語と交流してきた歴史と密接に関係しています.本講座では,日本語の語彙史とも比較対照させながら,英語の語彙史を通覧します.2019年から2021年にかけて全12回にわたって開講してきたシリーズ「英語の歴史と語源」の総括としても是非どうぞ.
なお,過去12回のシリーズの各回については本ブログでも取り上げてきました.以下をご参照ください.
・ 「#3731. 講座「英語の歴史と語源」の第1回「インドヨーロッパ祖語の故郷」を終えました」 ([2019-07-15-1])
・ 「#3757. 講座「英語の歴史と語源」の第2回「ケルトの島」を終えました」 ([2019-08-10-1])
・ 「#3792. 講座「英語の歴史と語源」の第3回「ローマ帝国の植民地」を終えました」 ([2019-09-14-1])
・ 「#3832. 講座「英語の歴史と語源」の第4回「ゲルマン民族の大移動」を終えました」 ([2019-10-24-1])
・ 「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1])
・ 「#3988. 講座「英語の歴史と語源」の第6回「ヴァイキングの侵攻」を終えました」 ([2020-03-28-1])
・ 「#4180. 講座「英語の歴史と語源」の第7回「ノルマン征服とノルマン王朝」を終えました」 ([2020-10-06-1])
・ 「#4266. 講座「英語の歴史と語源」の第8回「ジョン失地王とマグナカルタ」を終えました」 ([2020-12-31-1])
・ 「#4347. 講座「英語の歴史と語源」の第9回「百年戦争と黒死病」を終えました」 ([2021-03-22-1])
・ 「#4423. 講座「英語の歴史と語源」の第10回「大航海時代と活版印刷術」を終えました」 ([2021-06-06-1])
・ 「#4485. 講座「英語の歴史と語源」の第11回「ルネサンスと宗教改革」を終えました」 ([2021-08-07-1])
・ 「#4568. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」を終えました --- これにてシリーズ終了」 ([2021-10-29-1])
どうぞよろしくお願いいたします.
2022-03-03 Thu
■ #4693. YouTube 第2弾,複数形→3単現→英方言→米方言→Ebonics [youtube][notice][plural][3sp][aave][sociolinguistics][dialect][ame_bre][link][hellog_entry_set]
2月27日に開設した「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の第2弾が公開されました.「標準英語」がイギリスの○○方言だったら,日本人,楽だったのにー!!・英語学への入り口(堀田編)です.
堀田が英語学・英語史に関心を持ったきっかけが「英語の複数形とは何ぞや?」であったことから始まり,同じ -s つながりで動詞の3単現の話しに移り,3単現でも -s のつかないイギリス方言があるぞという話題に及びました.さらに,今度はアメリカ方言にまで飛び火し,最後には黒人英語の話題,とりわけ Ebonics 論争に到達しました.10分間の英語学のお散歩を楽しんでいただければ.
今回の話題と関連する本ブログからの記事を以下に紹介しておきます.一括して読みたい方はこちらからどうぞ.
・ 「#946. 名詞複数形の歴史の概要」 ([2011-11-29-1])
・ 「#2112. なぜ3単現の -s がつくのか?」 ([2015-02-07-1])
・ 「#2310. 3単現のゼロ」 ([2015-08-24-1])
・ 「#2566. 「3単現の -s の問題とは何か」」 ([2016-05-06-1])
・ 「#4255. なぜ名詞の複数形も動詞の3単現も同じ s なのですか?」 ([2020-12-20-1])
・ 「#591. アメリカ英語が一様である理由」 ([2010-12-09-1])
・ 「#3653. Ebonics 論争」 ([2019-04-28-1])
・ 「#2672. イギリス英語は発音に,アメリカ英語は文法に社会言語学的な価値を置く?」 ([2016-08-20-1])
2022-01-02 Sun
■ #4633. 2021年によく聴かれた「英語の語源が身につくラジオ」の放送 [link][sobokunagimon][notice][hel_education]
昨年6月2日に音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしました.以後,毎日更新しています(cf. 「#4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました」 ([2021-06-04-1])).前身の「hellog ラジオ版」も合わせてどうぞ.
7ヶ月ほど続けてきましたが,最もよく聴かれている放送20件を以下に示します.たまに対談ものも織り交ぜています.本ブログの追補版として始めたのですが,収録となると毎日そこそこ気は張りますね.
ちなみに,本日の放送は,この本日のブログ記事と連動させた2021年の放送の振り返りです.以下,正月の余暇にお聴きください.
1. 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」,9月17日放送,917回再生
2. 「なぜ A pen なのに AN apple なの?」,6月2日放送,860回再生
3. 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」,6月3日放送,655回再生
4. 「なぜ否定語が文頭に来ると VS 語順になるの?」,8月28日放送,621回再生
5. 「塵も積もれば山となる」に対応する英語の諺」,6月4日放送,548回再生
6. 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」,10月22日放送,430回再生
7. 「なぜ月曜日 Monday はムーンデイではなくマンデイなの?」,6月7日放送,421回再生
8. 「harassment のアクセントはどこに置けばいいの?」,6月5日放送,407回再生
9. 「なぜ used to do が「?したものだった」なの?」,11月16日放送,397回再生
10. 「なぜ one と書いてオネではなくてワンなの?」,6月8日放送,369回再生
11. 「対談 英語史の入門書」,10月18日放送,353回再生
12. 「forget, forgive の for- とは何?」,8月27日放送,353回再生
13. 「one, only, any は同語源って知ってました?」,6月9日放送,334回再生
14. 「対談 英語史×国際英語」,10月19日放送,333回再生
15. 「meat のかつての意味は「食物」一般だった!」,6月6日放送,332回再生
16. 「現在完了は過去を表わす表現と共起したらNG?」,8月23日放送,316回再生
17. 「first の -st は最上級だった!」,6月10日放送,314回再生
18. 「Japanese の -ese って何?」,11月12日放送,285回再生
19. 「前置詞ならぬ後置詞の存在」,10月11日放送,284回再生
20. 「英語とギリシア語の関係って?」,10月15日放送,277回再生
2022-01-01 Sat
■ #4632. 2021年によく読まれた記事 [link][sobokunagimon][notice][hel_education]
謹賀新年.今年も英語史に関する話題を広く長く提供し続ける「hellog?英語史ブログ」を続けていきます.引き続きよろしくお願いいたします.
2021年に本ブログのどの記事が最もよく読まれたか,調べてみました.12月30日付のアクセス・ランキング (access ranking) のトップ500記事をご覧ください(昨年版と一昨年版については,それぞれ「#4267. 2020年によく読まれた記事」 ([2021-01-01-1]) と「#3901. 2019年によく読まれた記事」 ([2020-01-01-1]) をどうぞ).
「素朴な疑問」系の記事 (sobokunagimon) がよく読まれているようなので,その系列で上位に入っている50件ほどを以下に挙げておきます(各行末の数字は年間アクセス数).お正月の読み物(ラジオの場合は聴き物)としてどうぞ.
・ 「#4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-14-1]) (8159)
・ 「#4044. なぜ活字体とブロック体の小文字 <a> の字形は違うのですか?」 ([2020-05-23-1]) (7541)
・ 「#3717. 音声学と音韻論はどう違うのですか?」 ([2019-07-01-1]) (5679)
・ 「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]) (5164)
・ 「#1299. 英語で「みかん」のことを satsuma というのはなぜか?」 ([2012-11-16-1]) (4807)
・ 「#4017. なぜ前置詞の後では人称代名詞は目的格を取るのですか?」 ([2020-04-26-1]) (3126)
・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1]) (2937)
・ 「#3611. なぜ He is to blame. は He is to be blamed. とならないのか?」 ([2019-03-17-1]) (2756)
・ 「#4042. anti- は「アンティ」か「アンタイ」か --- 英語史掲示板での質問」 ([2020-05-21-1]) (2696)
・ 「#2784. なぜアメリカでは英語が唯一の主たる言語となったのか?」 ([2016-12-10-1]) (2511)
・ 「#3747. ケルト人とは何者か」 ([2019-07-31-1) (2304)
・ 「#3677. 英語に関する「素朴な疑問」を集めてみました」 ([2019-05-22-1]) (2226)
・ 「#4272. 世界に言語はいくつあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2021-01-06-1]) (2120)
・ 「#2924. 「カステラ」の語源」 ([2017-04-29-1]) (1882)
・ 「#4069. なぜ live の発音は動詞では「リヴ」,形容詞だと「ライヴ」なのですか?」 ([2020-06-17-1]) (1845)
・ 「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞 と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) (1801)
・ 「#4060. なぜ「精神」を意味する spirit が「蒸留酒」をも意味するのか?」 ([2020-06-08-1]) (1695)
・ 「#4196. なぜ英語でいびきは zzz なのですか?」 ([2020-10-22-1]) (1598)
・ 「#2618. 文字をもたない言語の数は? (2)」 ([2016-06-27-1]) (1591)
・ 「#2885. なぜ「前置詞+関係代名詞 that」がダメなのか (1)」 ([2017-03-21-1]) (1563)
・ 「#1205. 英語の復権期にフランス借用語が爆発したのはなぜか」 ([2012-08-14-1]) (1539)
・ 「#4233. なぜ quite a few が「かなりの,相当数の」の意味になるのか?」 ([2020-11-28-1]) (1529)
・ 「#4199. なぜ last には「最後の」と「継続する」の意味があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-25-1]) (1526)
・ 「#3648. なんで *He cans swim. のように助動詞には3単現の -s がつかないのですか?」 ([2019-04-23-1]) (1475)
・ 「#3017. industry の2つの語義,「産業」と「勤勉」 (1)」 ([2017-07-31-1]) (1447)
・ 「#3298. なぜ wolf の複数形が wolves なのか? (1)」 ([2018-05-08-1]) (1446)
・ 「#4304. なぜ foot の複数形は feet なのですか?」 ([2021-02-07-1]) (1404)
・ 「#11. 「虹」の比較語源学」 ([2009-05-10-1]) (1398)
・ 「#3941. なぜ hour, honour, honest, heir では h が発音されないのですか?」 ([2020-02-10-1]) (1395)
・ 「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) (1360)
・ 「#2105. 英語アルファベットの配列」 ([2015-01-31-1]) (1358)
・ 「#3852. なぜ「新橋」(しんばし)のローマ字表記 Shimbashi には n ではなく m が用いられるのですか? (1)」 ([2019-11-13-1]) (1350)
・ 「#3831. なぜ英語には冠詞があるのですか?」 ([2019-10-23-1]) (1337)
・ 「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) (1280)
・ 「#3588. -o で終わる名詞の複数形語尾 --- pianos か potatoes か?」 ([2019-02-22-1]) (1270)
・ 「#4195. なぜ船や国名は女性代名詞 she で受けられることがあるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-10-21-1]) (1262)
・ 「#417. 文法化とは?」 ([2010-06-18-1]) (1249)
・ 「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) (1224)
・ 「#423. アルファベットの歴史」 ([2010-06-24-1]) (1211)
・ 「#4186. なぜ Are you a student? に対して *Yes, I'm. ではダメなのですか?」 ([2020-10-12-1]) (1156)
・ 「#4026. なぜ Japanese や Chinese などは単複同形なのですか? (3)」 ([2020-05-05-1]) (1122)
・ 「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]) (1062)
・ 「#2891. フランス語 bleu に対して英語 blue なのはなぜか」 ([2017-03-27-1]) (1053)
・ 「#3983. 言語学でいう法 (mood) とは何ですか? (1)」 ([2020-03-23-1]) (1012)
・ 「#47. 所有格か目的格か:myself と himself」 ([2009-06-14-1]) (962)
・ 「#4219. なぜ DX が digital transformation の略記となるのか?」 ([2020-11-14-1]) (938)
・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1]) (936)
・ 「#580. island --- なぜこの綴字と発音か」 ([2010-11-28-1]) (925)
・ 「#2189. 時・条件の副詞節における will の不使用」 ([2015-04-25-1]) (920)
・ 「#146. child の複数形が children なわけ」 ([2009-09-20-1]) (890)
新年は学び始めにふさわしい時期でもあります.英語史に関心をもった方,さらに関心をもちたい方は,「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]) および「なぜ英語史を学ぶか」の記事セットをご覧ください.
また,本ブログとは別に,昨年の6月2日に音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしました.耳で学ぶ英語史として毎日配信していますので,こちらも是非お聴きください(cf. 「#4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました」 ([2021-06-04-1])).
2021-12-28 Tue
■ #4628. 16世紀後半から17世紀にかけての正音学者たち --- 英語史上初の本格的綴字改革者たち [orthography][orthoepy][spelling][standardisation][emode][mulcaster][hart][bullokar][spelling_reform][link]
英語史における最初の綴字改革 (spelling_reform) はいつだったか,という問いには答えにくい.「改革」と呼ぶからには意図的な営為でなければならないが,その点でいえば例えば「#2712. 初期中英語の個性的な綴り手たち」 ([2016-09-29-1]) でみたように,初期中英語期の Ormulum の綴字も綴字改革の産物ということになるだろう.
しかし,綴字改革とは,普通の理解によれば,個人による運動というよりは集団的な社会運動を指すのではないか.この理解に従えば,綴字改革の最初の契機は,16世紀後半から17世紀にかけての一連の正音学 (orthoepy) の論者たちの活動にあったといってよい.彼らこそが,英語史上初の本格的綴字改革者たちだったのだ.これについて Carney (467) が次のように正当に評価を加えている.
The first concerted movement for the reform of English spelling gathered pace in the second half of the sixteenth century and continued into the seventeenth as part of a great debate about how to cope with the flood of technical and scholarly terms coming into the language as loans from Latin, Greek and French. It was a succession of educationalists and early phoneticians, including William Mulcaster, John Hart, William Bullokar and Alexander Gil, that helped to bring about the consensus that took the form of our traditional orthography. They are generally known as 'orthoepists'; their work has been reviewed and interpreted by Dobson (1968). Standardization was only indirectly the work of printers.
この点について Carney は,基本的に Brengelman の1980年の重要な論文に依拠しているといってよい.Brengelman の論文については,以下の記事でも触れてきたので,合わせて読んでいただきたい.
・ 「#1383. ラテン単語を英語化する形態規則」 ([2013-02-08-1])
・ 「#1384. 綴字の標準化に貢献したのは17世紀の理論言語学者と教師」 ([2013-02-09-1])
・ 「#1385. Caxton が綴字標準化に貢献しなかったと考えられる根拠」 ([2013-02-10-1])
・ 「#1386. 近代英語以降に確立してきた標準綴字体系の特徴」 ([2013-02-11-1])
・ 「#1387. 語源的綴字の採用は17世紀」 ([2013-02-12-1])
・ 「#2377. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (1)」 ([2015-10-30-1])
・ 「#2378. 先行する長母音を表わす <e> の先駆け (2)」 ([2015-10-31-1])
・ 「#3564. 17世紀正音学者による綴字標準化への貢献」 ([2019-01-29-1])
・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.
・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.
・ Brengelman, F. H. "Orthoepists, Printers, and the Rationalization of English Spelling." JEGP 79 (1980): 332--54.
2021-10-29 Fri
■ #4568. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」を終えました --- これにてシリーズ終了 [asacul][notice][history][link][slide]
去る10月23日(土)15:30?18:45に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・12 「市民革命と新世界」」を,対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式で開講しました.2年ほど前に開始した「英語の歴史と語源」シリーズの最終回ということですが,何とか走りきることができました.参加者や朝カルのスタッフの皆さんのおかげです,ありがとうございました.
今回は,革命で大荒れだったスチュアート朝の時代,ほぼまるまる17世紀に焦点を当てました.ルネサンスの熱気が冷め,革命で荒れた時代ながらも,抑制と理知に特徴づけられた英語の散文が発展してきました.この時代の散文は,私たちにとってそれなりに現代的に見えます.とりわけ王政復古後の散文の文体は,私たちにとって身近で知っている英語の文章という感じがします.
そして,英語そのものもぐんと現代に近づいきています.この時代までに綴字の標準化はかなりの程度進んでいましたし,文法的にいえば例えば疑問文・否定文における do の使用など,現代的な統語的規則が確立しました.
17世紀半ばから18世紀初頭にかけて,英語を統制するアカデミー設立への関心が高まりましたが,1712年にその試みが頓挫すると,以後,関心は薄まりました.現在に至るまで英語アカデミーなるものが存在しないのは,このときの頓挫に負っています.英語が世界化した21世紀,アカデミーの不在は良いことなのか悪いことなのか.この現代的問題を論じる上でも,17世紀の英語を巡る状況を理解しておくことは重要です.
今回の講座で用いたスライドをこちらに公開しますので,ご覧ください.以下にスライドの各ページへのリンクも張っておきます.復習などにどうぞ.
1. 英語の歴史と語源・12「市民革命と新世界」
2. 第12回 市民革命と新世界
3. 目次
4. 関連年表
5. 1. スチュアート朝と市民革命 --- 清教徒革命と名誉革命
6. 2. ルネサンスの熱狂から革命・王政復古期の抑制と理知へ
7. 3. 英語の市民化とアカデミー設立の試み
8. 4. 17世紀の英語の注目すべき事項
9. 5. 英語の世界展開が本格的に開始
10. まとめ
11. 参考文献
12. 補遺1:フランシス・ベーコン『随筆集』 (Essays, 1597) より「怒りについて」
13. 補遺2:サミュエル・ピープス『日記』 (Diary, 1825) より「1665年のペストに関する記録」
「英語の歴史と語源」シリーズはこれにて終了ですが,次期も別の話題で講座を開く予定です.
2021-10-27 Wed
■ #4566. heldio で古英語期と古英語を手短かに紹介しています(10分×2回) [notice][hel_education][oe][heldio][link][masanyan]
昨日と今日の2日間,私の Voicy の番組 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で古英語(期)の超入門をお届けしています.10分×2回の短いものです.現代の英語は知っているけれども古い英語はまったく初めて,という多くの方々に向けて,古英語期とはどんな時代なのか,古英語とはどんな言語なのかについて,おしゃべりしています.
1本目の「古英語期ってどんな時代?」では,英語の始まりから説き起こして,英語の歴史の時代区分,そして古英語期といわれる5?12世紀のイングランドについて,駆け足で独りごちました.
2本目の「対談 『毎日古英語』のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」では,日本初の古英語系 YouTuber であるまさにゃんとインフォーマルな対談を通じて,古英語という言語の特徴を紹介しました.
ちなみに,最近まさにゃんは「まさにゃんチャンネル」にて,シリーズ「毎日古英語」を精力的に展開しています.今回の heldio 対談は古英語の超入門のみで終わっていますので,関心をもった方はぜひ「毎日古英語」で具体的な古英語にテキストに触れてみてください.なお,本ブログでも1年半ほど前に「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1]) で紹介しています.
2021-10-23 Sat
■ #4562. 通時態は共時態に歴史的与件を提供する [saussure][diachrony][language_change][sociolinguistics][link]
ソシュール以来,共時態 (synchrony) と通時態 (diachrony) の関係を巡る論争は絶えたためしがない.本ブログでも,この話題について様々に議論してきた.
・ 「#866. 話者の意識に通時的な次元はあるか?」 ([2011-09-10-1])
・ 「#1025. 共時態と通時態の関係」 ([2012-02-16-1])
・ 「#1076. ソシュールが共時態を通時態に優先させた3つの理由」 ([2012-04-07-1])
・ 「#1260. 共時態と通時態の接点を巡る論争」 ([2012-10-08-1])
・ 「#2134. 言語変化は矛盾ではない」 ([2015-03-01-1])
・ 「#2197. ソシュールの共時態と通時態の認識論」 ([2015-05-03-1])
・ 「#2555. ソシュールによる言語の共時態と通時態」 ([2016-04-25-1])
・ 「#3264. Saussurian Paradox」 ([2018-04-04-1])
・ 「#3508. ソシュールの対立概念,3種」 ([2018-12-04-1])
言語にアプローチする2つの態に関して私の考えるところによれば,通時態は共時態に歴史的与件を提供するものではないか.歴史的与件とは,その時点で過去から受け継いだ言語的資産目録というほどの意味である.両態は確かに直行する軸であり性質がまるで異なっているのだが,現在という時点において唯一の接触点をもつ.この接触点に両態のエネルギーが凝縮しているとみている.時間軸上のある1点における断面図である言語の共時態は,通時態からエネルギーを提供されて,そのような断面図になっているのだ.
Sweetser (9--10) が著書の序章において,ソシュールのチェスの比喩をあえて引用しつつ,似たような見解を示しているので引用したい.
. . . [W]e cannot rigidly separate synchronic from diachronic analysis: all of modern sociolinguistics has confirmed the importance of reuniting the two. As with the language and cognition question, the synchrony/diachrony interrelationship has to be seen in a more sophisticated framework. The structuralist tradition spent considerable effort on eliminating confusion between synchronic regularities and diachronic changes: speakers do not necessarily have rules or representations which reflect the language's past history. But neither Saussure nor any of his colleagues would have denied that synchronic structure inevitably reflects its history in important ways: the whole chess metaphor is a perfect example of Saussure's deep awareness of this fact. Saussure, of course, uses chess because for future play the past history of the board is totally irrelevant: you can analyze a chess problem without any information about past moves. But he could hardly have picked --- as he must have known --- an example of a domain where past events more inevitably, regularly, and evidently (if not uniquely) determine the present resulting state. No phonologist today would reconstruct a proto-language's sound system without attention both to recognized universals of synchronic sound-systems and to attested (and phonetically motivated) paths of phonological change; it is assumed that the same perceptual, muscular, acoustic, and cognitive constraints are responsible for both universals of structure and universals of structural change. And, for a historical phonologist or semanticist trying to avoid imposing past analyses on present usage, it is an empirical question which aspects of diachrony are preserved in a given synchronic phonological structure or meaning structure.
詰め将棋は本番のための訓練としてはよいが,本番そのものではない.言語研究も,本番の真剣勝負こそを観察対象とするものであってほしい.
・ Sweetser, E. From Etymology to Pragmatics. Cambridge: CUP, 1990.
2021-10-19 Tue
■ #4558. 英語史と世界英語 [hel_education][world_englishes][model_of_englishes][variety][link][heldio]
昨日の記事「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1]) で,明治学院大学で英語史の授業を担当している泉類尚貴氏による推薦書を紹介させていただきました.その中で7番目の書籍である鳥飼玖美子(著)『国際共通語としての英語』(講談社現代新書,2011年)が意外性をもって受け取られるかもしれません.タイトルからは確かに英語を巡る重要な問題であることは分かるのですが,英語史とどのように関わるのかという疑問が浮かぶのではないでしょうか.この点を確認すべく,昨日に引き続き「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて同氏と対談しました.「対談 英語史×国際英語」というお題です.以下よりどうぞ.
英語史の領域では近年,世界英語 (world_englishes) への関心が急上昇しています.私自身も食らいついていかなければと思い,にわか勉強を始めているわけですが,急激なオンライン・リソースの拡大も相まって,すでに分野を一望するのも難しい水準にまで膨張しています.関心はあってもどこから始めたらよいかと迷うのも無理もありません.
私のお勧め図書としては,唐澤一友(著)『世界の英語ができるまで』(亜紀書房,2016年)を挙げておきます.本ブログでも world_englishes や model_of_englishes にて関連する記事を多く書いてきましたが,比較的最近書いた記事をピックアップすると,次のようなラインアップになります.
・ 「#4531. 「World Englishes 入門」スライド --- オンラインゼミ合宿の2日目の講義より」 ([2021-09-22-1])
・ 「#4466. World Englishes への6つのアプローチ」 ([2021-07-19-1])
・ 「#4506. World Englishes の全体的傾向3点」 ([2021-08-28-1])
・ 「#4507. World Englishes の類型論への2つのアプローチ」 ([2021-08-29-1])
・ 「#4508. World Englishes のコーパス研究の未来」 ([2021-08-30-1])
・ 「#4169. GloWbE --- Corpus of Global Web-Based English」 ([2020-09-25-1])
・ 「#4492. 世界の英語変種の整理法 --- Gupta の5タイプ」 ([2021-08-14-1])
・ 「#4493. 世界の英語変種の整理法 --- Mesthrie and Bhatt の12タイプ」 ([2021-08-15-1])
・ 「#4501. 世界の英語変種の整理法 --- McArthur の "Hub-and-Spokes" モデル」 ([2021-08-23-1])
・ 「#4502. 世界の英語変種の整理法 --- Görlach の "Hub-and-Spokes" モデル」 ([2021-08-24-1])
世界英語を扱うオンライン・コーパスとしては,上にも触れた GloWbE (= Corpus of Global Web-Based English) を入り口としてお勧めします.このコーパスについては,専修大学文学部英語英米語学科の菊地翔太先生のHPより,こちらのページに関連情報があります.ちなみに菊地翔太先生のHPを探検し紹介するコンテンツ「菊地先生のホームページを訪れてみよう 」を大学院生が作ってくれましたので,こちらもお勧めしておきます.
2021-10-18 Mon
■ #4557. 「英語史への招待:入門書10選」 [hel_education][bibliography][khelf][link][heldio][masanyan][voicy]
昨日,青山英語史研究会(青山学院大学・寺澤盾先生主催)がオンラインで開催されました.「研究会」とはいうものの,今回は英語史を学ぶ大学生を主たるオーディエンスとして想定し,英語史の学びをエンカレッジする様々な企画が組まれました.私も参加させていただきましたが,たいへん実りの多い会となりました.ありがとうございます.
プログラムの1つとして,明治学院大学で英語史の授業を担当している泉類尚貴氏による「英語史への招待:入門書10選」が紹介されました.氏の許可を得て,そのリスト(実際にはオマケ付きで11冊)を以下に掲載します.氏によると,この順序で手に取ってみることをお勧めするとのことです.
ちなみに泉類氏とは,本日の「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて同じ話題で対談していますので,こちらも是非お聴きください.推薦書リストというものは,選者による簡単な解説があるだけでも説得力が増しますね.
・ 寺澤 盾 『英語の歴史:過去から未来への物語』 中公新書,2008年.
・ 家入 葉子 『ベーシック英語史』 ひつじ書房,2007年.
・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』 研究社,2016年.
・ 唐澤 一友 『英語のルーツ』 春風社,2011年.
・ 唐澤 一友 『世界の英語ができるまで』 亜紀書房,2016年.
・ 寺澤 盾 『聖書でたどる英語の歴史』 大修館書店,2013年.
・ 鳥飼 玖美子 『国際共通語としての英語』 講談社現代新書,2011年.
・ 西村 秀夫 編 『コーパスと英語史』 ひつじ書房,2019年.
・ 高田 博行・渋谷 勝巳・家入 葉子(編著) 『歴史社会言語学入門』 大修館書店,2015年.
・ Baugh, A. C. and T. Cable. A History of the English Language. 6th ed. Routledge, 2013.
・ Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. 3rd ed. CUP, 2018.
番外編として,参考になるウェブサイトということで以下の4点も紹介されました.
・ TED Ed
・ YouTube 「まさにゃんチャンネル」
・ 「hellog?英語史ブログ」
・ khelf (= Keio History of the English Language Forum)
以上,英語史の学びのエンカレッジでした.昨日の記事「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1]) も合わせてどうぞ.
2021-10-17 Sun
■ #4556. 英語史の世界にようこそ [hel_education][notice][heldio][hellog-radio][sobokunagimon][link]
学期の始めなので,標題のような「英語史の学びのエンカレッジ系」の記事が多くなります.最近では「#4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方」 ([2021-10-07-1]) も書いており,本ブログの記事などに関連するリンクを多々張っていますので,詳しくは是非そちらもご覧ください.今回は先の記事から重要な6点のみピックアップし,改めて英語史への入り口を案内します.
(1) 私(堀田隆一)の考える「英語史の魅力」はズバリこれ.
1. 英語の見方が180度変わる!
2. 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
3. 素朴な疑問こそがおもしろい!
4. 英語が本当によく分かるようになる!
(2) 上記の「素朴な疑問こそがおもしろい!」は本当です.「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) に挙げたような疑問が,英語史によりスルスルと解けていきます.それでも足りない方は「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) でどうでしょう!
(3) 本ブログ「hellog?英語史ブログ」は「英語史に関する話題を広く長く提供し続けるブログ」として2009年5月1日に立ち上げたものです.大学の英語史概説の講義に対する補助的な読み物を提供する趣旨で始めました.日々の記事の種類は多岐にわたり,英語を学び始めたばかりの中学生などを読者と想定した話題もあれば,大学院博士課程の学生を念頭においた学術的な話題もあります.書き手以外何を言っているか分からないという話題も少なくないと思います,失礼! それでも,ぜひ毎日タイトルだけでも目を通していれば,英語史のカバーする範囲の広さが分かってくると思います.毎日タイトルをお届けするツイッターアカウントもあります.
(4) 本ブログの姉妹版・音声版として「hellog ラジオ版 (hellog-radio)」(2020年6月23日?2021年2月7日に不定期で),および続編である「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(2021年6月2日より現在まで毎日定期的に)を配信しています.hellog に比べ,話題は「英語に関する素朴な疑問」におよそ特化しています.各放送は10分以内の短い英語史ネタです.ぜひこれを聞くことを日課にどうぞ! ちなみに本日の放送では,上記 (1) を熱く語っています.
(5) 明後日10月19日は「TOEIC の日」.つい先日 TOEIC 事業などを手がける IIBC (一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会)のインタビューを受けました.テーマは「英語はいかにして世界の共通語になったのか」という,英語(史)に関する究極の疑問の1つです.英語史超入門ともなっているこちらのインタビュー記事をどうぞ(cf. 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1])).
(6) 最後に私の選んだ「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) をご覧ください.英語史を学び始めるには,なんといっても本を読むのが一番です.
2021-10-15 Fri
■ #4554. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第8回「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][link][gvs]
NHKラジオ講座「中高生の基礎英語 in English」の11月号のテキストが発売となりました.連載している「英語のソボクな疑問」は第8回となっています.今回は英語の母音字の読みに関する,きわめて素朴な疑問「なぜ A の読みは「アー」ではなく「エイ」なの?」を取り上げています.
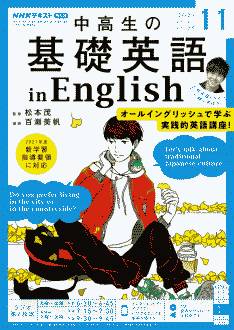
本ブログの読者の多くの方々は,この疑問が英語史でいうところの「大母音推移」 (gvs) に関わるものであることがお分かりかと思います.しかし,連載は中高生を対象読者とするものですので,この用語を持ち出すことは控えたいと考えました.そして,もちろん音声学の用語や概念なども前提とすることはできません.ということで,真正面から大母音推移の伝統的な説明を施すことはせず,なるべく易しく噛み砕いて伝えようと努めました.結果として,前舌母音のみの説明にとどめて後舌母音については触れないでおくなど,理解しにくくなりそうな部分を思い切って割愛しました.このような次第で,今回は私にとって1つの挑戦となりました(どのくらい成功しているかは分かりませんねえ).
大母音推移の教科書的な説明としては本ブログの「#205. 大母音推移」 ([2009-11-18-1]) をどうぞ.もう少し詳しくは,拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の1.3節と2.5節をご参照ください.専門的には gvs の各記事で扱っています.
・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.
2021-10-10 Sun
■ #4549. 講座「英語の歴史と語源」の第12回「市民革命と新世界」のご案内 [asacul][notice][history][link][emode]
朝日カルチャーセンター新宿教室にて全12回の企画で2年ほど前に始めた「英語の歴史と語源」シリーズが,いよいよ最終回となります.2週間後に迫った第12回(最終回)のお知らせです.「市民革命と新世界」と題して2021年10月23日(土)15:30--18:45に開講予定です.対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド形式を予定しています.関心のある方はこちらよりご予約ください.今回の趣旨は以下の通りです.
17世紀イングランドは「清教徒革命」と「名誉革命」という2つの大変革を経験しました.一般に国内の混乱の世紀ととらえられていますが,英語史の観点からは,後に英語が国外に展開してゆく足場を築いた時期として重要な意義をもちます.実際,同世紀中にイングランドは北米に植民地を築き,インドへの影響力をもち始めました.英語の世界的展開が本格的に始まろうとしていた時代に焦点を当てつつ,英語の現在と未来についても考察します.
今回は,イングランドの革命の時代,17世紀に焦点を当てます.この時期は,イングランド国内の状況こそ混乱を極めましたが,国外への展開は順調であり,20--21世紀にかけて大国へと成長していくことになる北米やインドに橋頭堡を築いた時代として,歴史的にたいへん重要な意義をもちます.お祭り騒ぎというべきルネサンスの熱は冷めてしまったものの,英語がいよいよ自信と安定感を獲得し,国内外において規範を確立させようと引き締めに入った時期でもあります.現代に直接通じる言語特徴や言語意識が生まれたこの時代に注目しつつ,21世紀の英語も占いながら本シリーズを締めくくりたいと思います.皆様のご参加をお待ちしています.
2021-10-07 Thu
■ #4546. 新学期の始まりに,英語史の学び方 [hel_education][sobokunagimon][link]
今年度も後期が始まる時期となりました.年度初めの4月に,本ブログでは英語史の学びのモチベーションを高めるキャンペーンを張ったのですが,この学期初めの10月にも,改めて英語史の学びを促すべく広報したいと思います.
まず,私が新年度あるいは新学期の初回の授業で必ず述べることにしている「英語史」の魅力4点を明記します.
--- 英語史の魅力 ---
(1) 英語の見方が180度変わる!
(2) 英語と歴史(社会科)がミックスした不思議な感覚の科目!
(3) 素朴な疑問こそがおもしろい!
(4) 現代英語に戻ってくる英語史
以下に,上記4点とも密接に関わる,英語史の学びに役立つ本ブログからの記事をいくつか紹介します.
・ 「#4358. 英語史概説書等の書誌(2021年度版)」 ([2021-04-02-1]) --- 入門書から専門書までの厳選書誌
・ 「#4359. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2021年度版)」 ([2021-04-03-1]) --- この hellog の効果的な使い方の tips
・ 「#4421. 「英語の語源が身につくラジオ」をオープンしました」 ([2021-06-04-1]) --- hellog の音声版というべき「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) を Voicy にて毎日配信中.1本10分未満で英語史の話題をお届けしています.
・ 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1]) --- 皆が関心をもつ英単語の語源の話題.自らどんどん調べてみてください.
・ 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1]) --- 上記の魅力 (2) に通じる話です
・ 「#1093. 英語に関する素朴な疑問を募集」 ([2012-04-24-1]) --- 上記の魅力 (3) に通じる話です
・ 「#4389. 英語に関する素朴な疑問を2685件集めました」 ([2021-05-03-1]) --- おびただしい疑問の一覧は直接こちらからどうぞ
・ 「#4545. 「英語はいかにして世界の共通語になったのか」 --- IIBC のインタビュー」 ([2021-10-06-1]) --- 英語史に関する究極の疑問かもしれません.インタビューに基づいたわかりやすい解説になっています.直接こちらからどうぞ.
・ 「なぜ英語史を学ぶのか」の記事セット --- 様々な角度から検討してみました.「英語史って何のため?」 (heldio) でもしゃべっています.
・ 「#4417. 「英語史導入企画2021」が終了しました」 ([2021-05-31-1]) --- 今年度初めに企画した英語史の学びを応援するイベント.すでに終了していますが「英語史コンテンツ」とは何かがよく分かります.
皆さん,今学期も実り多い学びを!
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow