2024-05-15 Wed
■ #5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
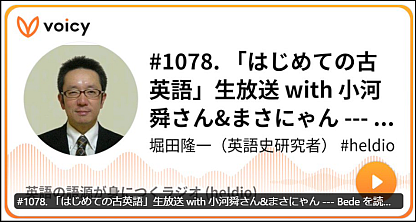
5月9日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.
精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますので,そちらをご覧になりながらお聴きください.
著者の Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.
今回は,古英語の動詞屈折の話題,とりわけ過去形や仮定法の話題に触れる機会が多くありました.また,定冠詞 the に相当する語の屈折についても議論しました.事後に出演者の1人「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)が,ご自身の note 上で復習となる記事「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#6 生放送3回目)」を公開されているので,そちらも合わせてご参照ください.
これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.
(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」
目下,次回 Part 7 に向けて3人とも鋭意準備中です.
2024-04-24 Wed
■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
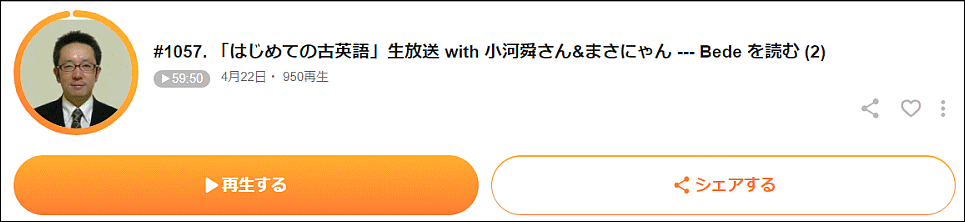
4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.
前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.
Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.
復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.
(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.
最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.
・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])
・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])
今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!
2024-03-23 Sat
■ #5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる [bchel][voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
731年,ビード (あるいはベーダ;Bede [673--735]) によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) は,古代イングランド史を記した貴重なテキストである.後にアルフレッド大王 (849--99) の指示のもとで古英語に翻訳されている.
597年,ローマの修道士で,後にカンタベリの初代大司教となる St. Augustine (?--604) が,イングランドに布教にやってきた.イングランド史上きわめて重大なこの年に起こった出来事について,Bede の古英語版より読んでみたい.以下,英語史の古典的名著 Baugh and Cable (pp. 58--60) に掲載されている古英語原文を再現する.
Ða wæs on þā tīd Æþelbeorht cyning hāten on Centrīce, and mihtig: hē hæfde rīce oð gemǣru Humbre strēames, sē tōscādeþ sūðfolc Angelþēode and norðfolc. Þonne is on ēasteweardre Cent micel ēaland, Tenet, þæt is siex hund hīda micel æfter Angelcynnes eahte. . . . On þyssum ēalande cōm ūp sē Godes þēow Augustinus and his gefēran; wæs hē fēowertiga sum. Nāmon hīe ēac swelce him wealhstodas of Franclande mid, swā him Sanctus Gregorius bebēad. And þā sende to Æþelbeorhte ǣrendwrecan and onbēad þæt hē of Rōme cōme and þæt betste ǣrende lǣdde; and sē þe him hīersum bēon wolde, būton twēon he gehēt ēcne gefēan on heofonum and tōweard rīce būton ende mid þone sōþan God and þone lifigendan. Ðā hē þā sē cyning þās word gehīerde, þa hēt hē hīe bīdan on þæm ēalande þe hīe ūp cōmon; and him þider hiera þearfe forgēaf, oð þæt hē gesāwe hwæt hē him dōn wolde. Swelce ēac ǣr þǣm becōm hlīsa tō him þǣre crīstenan ǣfæstnesse, forþon hē crīsten wīf hæfde, him gegiefen of Francena cyningcynne, Beorhte wæs hāten. Þæt wīf hē onfēng fram hiere ieldrum þǣre ārǣdnesse þæt hēo his lēafnesse hæfde þæt hēo þone þēaw þæs crīstenan gelēafan and hiere ǣfæstnesse ungewemmedne healdan mōste mid þȳ biscope, þone þe hīe hiere tō fultume þæs gelēafan sealdon, þæs nama wæs Lēodheard.
Ðā wæs æfter manigum dagum þæt sē cyning cōm tō þǣm ēalande, and hēt him ūte setl gewyrcean; and hēt Augustinum mid his gefērum þider tō his sprǣce cuman. Warnode hē him þȳ lǣs hīe on hwelc hūs tō him inēoden; brēac ealdre hēalsunga, gif hīe hwelcne drȳcræft hæfden þæt hīe hine oferswīðan and beswīcan sceolden. . . . Þā hēt sē cyning hīe sittan, and hīe swā dydon; and hīe sōna him līfes word ætgædere mid eallum his gefērum þe þǣr æt wǣron, bodedon and lǣrdon. Þā andswarode sē cyning and þus cwæð: "Fæger word þis sindon and gehāt þe gē brōhton and ūs secgað. Ac forðon hīe nīwe sindon and uncūðe, ne magon wē nū gēn þæt þafian þæt wē forlǣten þā wīsan þe wē langre tīde mid ealle Angelþēode hēoldon. Ac forðon þe gē hider feorran elþēodige cōmon and, þæs þe mē geþūht is and gesewen, þā þing, ðā ðe [gē] sōð and betst gelīefdon, þæt ēac swelce wilnodon ūs þā gemǣnsumian, nellað wē forðon ēow hefige bēon. Ac wē willað ēow ēac fremsumlīce on giestlīðnesse onfōn and ēow andleofne sellan and ēowre þearfe forgiefan. Ne wē ēow beweriað þæt gē ealle, ðā þe gē mægen, þurh ēowre lāre tō ēowres gelēafan ǣfæstnesse geðīeden and gecierren."
目下,Baugh and Cable の英語史書 A History of the English Language を1節ずつ丁寧に読んでいくオンライン読書会シリーズを Voicy heldio で展開中です(有料配信ですが第1チャプターは試聴可).上に引用した古英語原文が含まれているのは第47節で,これを扱った回は「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (47) The Language Illustrated」です.ただし,そこでは上記の古英語原文は,かなり長いために解説するのを割愛していました.
これを補うべく,明後日3月25日(月)の午後1時30分より heldio の生放送による解説を配信します.小河舜さん(フェリス女学院大学ほか)および「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)とともに,「はじめての古英語」シリーズの一環としての特別企画です.上記の古英語原文は,その予習用として掲げた次第です.お楽しみに!
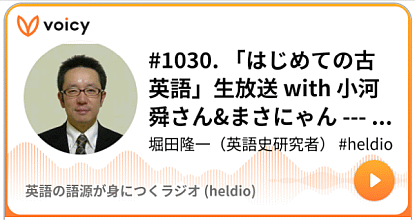
Bede の古英語訳の原文としては,ほかにも「#2900. 449年,アングロサクソン人によるブリテン島侵略」 ([2017-04-05-1]) を参照.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2023-09-04 Mon
■ #5243. 異教時代の古英語地名 [oe][toponymy][anglo-saxon][christianity][name_project][onomastics][history][chronology][heathenism]
地名の構成要素の意味をひもとくことによって,どの時代にその地名がつけられたのか,示唆を得られる事例がある.同じ場所が後に別の地名に置き換えられていたりするので,時系列に整理した上で慎重に解釈する必要があるが,地名研究が歴史学など他分野に貢献し得る点で興味深い.
Hough (98) によると,キリスト教化する以前のイングランドの古英語地名に,異教の神や寺院などの名前が用いられているものがあるという.このようなケースでは,それだけ古い土地であると解釈してよさそうだ.
Also indicative of early settlement are place-names referring to religious or other customs that were later superseded. Place-names referring to Anglo-Saxon paganism represent an early stratum which must pre-date the conversion to Christianity around 627. In England they fall into two main groups: those containing the names of pagan gods, and those containing a word for a heathen shrine or temple. Examples of the former are Tysoe (Tiw + OE hōh 'heel; hill-spur'), Wensley (Woden + OE lēah 'wood, clearing'), Thursley (Thunor + OE lēah 'wood, clearing', and Friden (Frig + denu 'valley'); examples of the latter are Harrow (OE hearg 'temple') and Weeford (OE wēoh 'shrine' + ford 'ford). The absence of either type from the corpus of Old English place-names in Scotland is usually taken to indicate that the Anglo-Saxons did not move north until after the conversion to Christianity, although this has been challenged on the grounds that pagan names are also absent from large areas of England . . . .
このような異教的地名がスコットランドには認められないという議論も意味深長である.
・ Hough, Carole. "Settlement Names." Chapter 6 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 87--103.
2023-07-30 Sun
■ #5207. 朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を終えました [asacul][writing][grammatology][alphabet][notice][spelling][oe][literature][beowulf][runic][christianity][latin][alliteration][distinctiones][punctuation][standardisation][voicy][heldio]
先日「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1]) でご案内した通り,昨日,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回となる「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」を開講しました.多くの方々に対面あるいはオンラインで参加いただきまして感謝申し上げます.ありがとうございました.
古英語期中に,いかにして英語話者たちがゲルマン民族に伝わっていたルーン文字を捨て,ローマ字を受容したのか.そして,いかにしてローマ字で英語を表記する方法について時間をかけて模索していったのかを議論しました.ローマ字導入の前史,ローマ字の手なずけ,ラテン借用語の綴字,後期古英語期の綴字の標準化 (standardisation) ,古英詩 Beowulf にみられる文字と綴字について,3時間お話ししました.
昨日の回をもって全4回シリーズの前半2回が終了したことになります.次回の第3回は少し先のことになりますが,10月7日(土)の 15:00~18:45 に「中英語の綴字 --- 標準なき繁栄」として開講する予定です.中英語期には,古英語期中に発達してきた綴字習慣が,1066年のノルマン征服によって崩壊するするという劇的な変化が生じました.この大打撃により,その後の英語の綴字はカオス化の道をたどることになります.
講座「文字と綴字の英語史」はシリーズとはいえ,各回は関連しつつも独立した内容となっています.次回以降の回も引き続きよろしくお願いいたします.日時の都合が付かない場合でも,参加申込いただけますと後日アーカイブ動画(1週間限定配信)にアクセスできるようになりますので,そちらの利用もご検討ください.
本シリーズと関連して,以下の hellog 記事をお読みください.
・ hellog 「#5088. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」 ([2023-04-02-1])
・ hellog 「#5194. 7月29日(土),朝カルのシリーズ講座「文字と綴字の英語史」の第2回「古英語の綴字 --- ローマ字の手なずけ」」 ([2023-07-17-1])
同様に,シリーズと関連づけた Voicy heldio 配信回もお聴きいただければと.
・ heldio 「#668. 朝カル講座の新シリーズ「文字と綴字の英語史」が4月29日より始まります」(2023年3月30日)
・ heldio 「#778. 古英語の文字 --- 7月29日(土)の朝カルのシリーズ講座第2回に向けて」(2023年7月18日)
2023-03-21 Tue
■ #5076. キリスト教の普及と巻子本から冊子本へ --- 高宮利行(著)『西洋書物史への扉』より [christianity][bible][manuscript][writing][history][medium][review]
この2月に髙宮利行(著)『西洋書物史への扉』が岩波新書より出版されています.西洋における本の歴史が,多くの写真やエピソードとともにコンパクトにまとめられています.参考文献も整理されており,次の一冊に進むのに有用です.
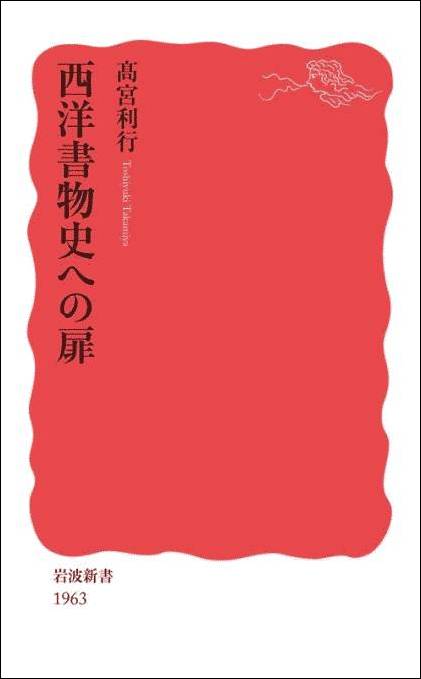
本の歴史には数々の論点がありますが,巻子本(かんすぼん;volume)から冊子本 (codex) へと本の形態がシフトした問題について「冊子本の登場」と題する章で紹介されています.
巻子本は冊子本に比べて検索しにくかったということがしばしば言われます.シフトの背景にはそのような実用的な要因もあったことは確かと思われますが,キリスト教の普及と関係する社会的な要因もあったと考えられています.
髙宮 (pp. 45--45) では,紀元1--5世紀に作られた現存するギリシア古典作品の本について,巻子本と冊子本の比率を比べた調査が紹介されています.それによると,1世紀には冊子本はほとんどなかったものの,2世紀には2%,3世紀には17%,4世紀には70%,5世紀初頭には90%と加速度的に増えていきました.一方,キリスト教関連の本について調査すると,ずっと早い段階から冊子本が広範囲で採用されており,2世紀までに100%に達していました.つまり,キリスト教関連本と冊子本は歴史的に密接な関係にあったということです.
これについて髙宮 (pp. 46--48) は次のように説明しています.
ここで論じられている写本が発見されているのはエジプトである.かねてより,冊子本という形態の出現とキリスト教伝播が並行して起こっていることは指摘されてきたが,冊子本は三世紀に増加,四世紀に支配的となり,同様にキリスト教も三世紀に急速に普及し,三一三年に公認されていく.
巻子本から冊子本への形態的な転換は,いずれが使用に便利かといった実用的・経済的判断だけから起こったのではないだろう.冊子写本は,巻子本を用いていたユダヤ教や周辺に存在していた異教に対して,原始キリスト教がユダヤ教から分派し,成立したことを示す象徴的な形態として,選ばれたのである.キリスト教の教えを説き普及させる聖書の形態として,キリスト教の写字生を異教徒の書記から区別するために,冊子本は採用されたのであった.ユダヤ教典が現在でもなお,羊皮紙巻子本の形態で作られている点に注目すれば,紀元後まもなくキリスト教関係者の中に,聖書およびその関連書の写本を冊子本の形態に転換すべく努力した重要な人物がいたであろうことが浮かび上がる.
宗教と本の形態が関与しているとは,まさに驚きです.
・ 髙宮 利行 『西洋書物史への扉』 岩波書店〈岩波新書〉,2023年.
2021-04-11 Sun
■ #4367. 「英語の人名」の記事セット [personal_name][onomastics][christianity][hellog_entry_set][khelf_hel_intro_2021]
英語の人名に関するテーマは幅広く関心をもたれる.英語史の授業などで自由レポート課題を出すと,必ず複数の学生が人名に関するトピックを選ぶ.身近で具体的な名前だし,たいてい何らかの歴史的・語源的背景が隠されているので調査する甲斐がある,ということだろう.
本ブログでも(英語の)人名について様々な記事で書いてきた.個別の具体的な名前に関する記事もあれば,もう少し抽象的に人名学や人名史の観点から書いた記事もある.以下の記事セットで少々整理してみた.
・ 「英語の人名」の記事セット
記事セットのなかに「#2557. 英語のキラキラネーム,あるいはキラキラスペリング」 ([2016-04-27-1]) という記事があるが,これと関連して,「英語史導入企画2021」の一環として昨日学部生よりアップされた「キラキラネームのパイオニア?」のコンテンツもぜひ読まれたい.
人名学 (anthroponymy) は地名学 (toponymy) とともに固有名詞学 (onomastics) を構成する分野である.人名について研究したいと思えば固有名詞そのものの特徴を理解する必要がある.一般名詞と比べて何が同じで何が異なるのか,という視点が重要だろう.本質的な差異の1つは,一般名詞は言語体系の内側にあるが,固有名詞はむしろ外側にある(あるいは外側を指向する)という点にあるといってよい.すると,固有名詞の特徴は,言語体系(内部)の特徴に照らして,浮き彫りにされるべき対象ということになる.つまり,人名学に深く分け入るに当たっては,同時に言語体系の何たるかをよく理解しておくこと(=まさに言語学の目標)が肝心である.
英語の人名というテーマは,一見楽しく研究できそうに思われるかもしれないが,本格的に分け入ろうとするとなかなかの難物である.
2020-04-20 Mon
■ #4011. 英語史の始まりはいつか? --- 700年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][inscription][manuscript][oe]
標題について,過去2日間の記事 ([2020-04-18-1], [2020-04-19-1]) で449年説と600年説を取り上げてきたが,今回は最後に700年説について考察したい.この年代は,英語の文献が本格的に現われ出すのが700年前後とされることによる.現代の英語史研究者がアクセスできる最古の文献の年代に基づいた説であるから,さらに古い文献が発見されれば英語史の始まりもその分さかのぼるという点で,相対的,可変的,もっと言ってしまえば研究者の都合を優先した説ということになる.Mengden (20) はこの説を次のように評価している.
. . . one could approach the question of the starting point of Old English from a modern perspective. . . . Our direct evidence of any characteristic of (Old) English begins with the oldest surviving written sources containing Old English. Apart from onomastic material in Latin texts and short inscriptions, the earliest documents written in Old English date from the early 8th century. A distinction between a reconstructed "pre-Old English" before 700 and an attested "Old English" after 700 . . . therefore does not seem implausible.
しかし,Mengden (20) は,700年前後という設定は必ずしも研究者の都合を優先しただけのものではないとも考えている.
. . . it is feasible that the shift from a heptarchy of more or less equally influential Anglo-Saxon kingdoms to the cultural dominance of Northumbria in the time after Christianization may be connected with the fact that texts are produced not exclusively in Latin, but also in the vernacular. In other words, we may speculate (but no more than that) that the emergence of the earliest Anglo-Saxon cultural and political centre in Northumbria in the 8th century may lead the Anglo-Saxons to view themselves as one people rather than as different Germanic tribes, and, accordingly to view their language as English (or, Anglo-Saxon) rather than as the Saxon, Anglian, Kentish, Jutish, etc. varieties of Germanic.
700年前後は,5世紀半ばにブリテン島に渡ってきた西ゲルマン集団が,アングロサクソン人としてのアイデンティティ,英語話者としてのアイデンティティを確立させ始めた時期であるという見方だ.これはこれで1つの洞察ではある.
さて,3日間で3つの説をみてきたわけだが,どれが最も妥当と考えられるだろうか.あるいは他にも説があり得るだろうか(私にはあると思われる).もっとも,この問いに正解があるわけではなく,視点の違いがあるにすぎない.だからこそ periodisation の問題はおもしろい.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2020-04-19 Sun
■ #4010. 英語史の始まりはいつか? --- 600年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][latin][borrowing][alphabet][oe]
昨日の記事「#4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説」 ([2020-04-18-1]) に引き続き,英語史の開始時期を巡る議論.今回は,実はあまり聞いたことのなかった(約)600年説について考えてみたい
597年に St. Augustine がキリスト教宣教のために教皇 Gregory I によってローマから Kent 王国へ派遣されたことは英国史上名高いが,この出来事がアングロサクソンの社会と文化を一変させたということは,象徴的な意味でよく分かる.社会と文化のみならず英語という言語にもその影響が及んだことは「#3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-24-1]),「#3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました」 ([2019-11-06-1]),「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1]) でたびたび注目してきた.確かに英語史上きわめて重大な事件が600年前後に起こったとはいえるだろう.Mengden の議論に耳を傾けてみよう.
. . . because the conversion is the first major change in the society and culture of the Anglo-Saxons that is not shared by the related tribes on the Continent, it is similarly significant for (the beginning of) an independent linguistic history of English as the settlement in Britain. Moreover, the immediate impact of the conversion on the language of the Anglo-Saxons is much more obvious than that of the migration: first, the Latin influence on English grows in intensity and, perhaps more crucially, enters new domains of social life; second, a new writing system, the Latin alphabet, is introduced, and third, a new medium of (linguistic) communication comes to be used --- the book.
600年説の要点は3つある.1つめは,主に語彙借用のことを述べているものと思われるが,ラテン語からキリスト教や学問を中心とした文明を体現する分野の借用語が流れ込んだこと.2つめはローマン・アルファベットの導入.3つめは本というメディアがもたらされたこと.
いずれも英語に直接・間接の影響を及ぼした重要なポイントであり,しかも各々の効果が非常に見えやすいというメリットもある.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2020-04-18 Sat
■ #4009. 英語史の始まりはいつか? --- 449年説 [periodisation][anglo-saxon][christianity][history][oe]
○○史の時代区分 (periodisation) というのは,その分野において最も根本的な問題である.英語史も例外ではなく,この問題について絶えず考察することなしには,そもそも研究が成り立たない.とりわけ英語史の始まりをどこに置くかという問題は,分野の存立に関わる大問題である.本ブログでも,periodisation とタグ付けした多数の記事で関連する話題を取り上げてきた.
最も伝統的かつポピュラーな説ということでいえば,アングロサクソン人がブリテン島に渡ってきたとされる449年をもって英語史の始まりとするのが一般的である.この年代自体が伝説的といえばそうなのだが,もう少し大雑把にみても5世紀前半から中葉にかけての時期であるという見解は広く受け入れられている.
一方,「歴史」とは厳密にいえば文字史料が確認されて初めて成立するという立場からみれば,英語の文字史料がまとまった形で現われるのは700年くらいであるから,その辺りをもって英語史の開始とする,という見解もあり得る.実際,こちらを採用する論者もいる.
上記の2つが英語史の始まりの時期に関する有力な説だが,Mengden (20) がもう1つの見方に言及している.600年頃のキリスト教化というタイミングだ.キリスト教化がアングロサクソン社会にもたらした文化的な影響は計り知れないが,そのインパクトこそが彼らの言語を初めて「英語」(他のゲルマン語派の姉妹言語と区別して)たらしめたという議論だ.かくして,古い方から並べて (1) (象徴的に)紀元449年,(2) およそ600年,(3) およそ700年,という英語史の開始時期に関する3つの候補が出たことになる.
各々のポイントについて考えて行こう.定説に近い (1) を重視する理由は,Mengden 曰く,次の通りである.
Although the differences between the varieties of the settlers and those on the continent cannot have been too great at the time of the migration it is the settlers' geographic and political independence as a consequence of the migration which constitutes the basis for the development of English as a variety distinct and independent from the continental varieties of the West Germanic speech community . . . . (20)
要するに,449年(付近)を英語史の始まりとみる最大のポイントは,言語学的視点というよりも社会(言語学)的視点を取っている点にある.もっといえば,空間的・物理的な視点である.大陸の西ゲルマン語の主要集団から分離して独自の集団となったのが「英語」社会だるという見方だ.実際 Mengden 自身も様々に議論した挙げ句,この説を最重要とみなしている.
I would therefore propose that, whatever happens to the language of the Anglo-Saxon settlers in Britain and for whatever reason it happens, any development after 450 should be taken as specifically English and before 450 should be taken as common (West) Germanic. That our knowledge of the underlying developments is necessarily based on a different method of access before and after around 700 is ultimately secondary to the relevant linguistic changes themselves and for any categorization of Old English. (21)
結局 Mengden も常識的な結論に舞い戻ったようにみえるが,一般的にいって,深く議論した後にぐるっと一周回って戻ってきた結論というものには価値がある.定説がなぜ定説なのかを理解することは,とても大事である.
他の2つの説については明日以降の記事で取り上げる.
・ Mengden, Ferdinand von. "Periods: Old English." Chapter 2 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 19--32.
2019-11-06 Wed
■ #3845. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」を終えました [asacul][notice][slide][link][christianity][alphabet][latin][loan_word][bible][religion]
「#3833. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」のご案内」 ([2019-10-25-1]) で案内した朝日カルチャーセンター新宿教室の講座を11月2日(土)に終えました.今回も大勢の方に参加していただき,白熱した質疑応答が繰り広げられました.多岐にわたるご指摘やコメントをいただき,たいへん充実した会となりました.
講座で用いたスライド資料をこちらに置いておきますので,復習等にご利用ください.スライドの各ページへのリンクも張っておきます.
1. 英語の歴史と語源・5 「キリスト教の伝来」
2. 第5回 キリスト教の伝来
3. 目次
4. 1. イングランドのキリスト教化
5. 古英語期まで(?1066年)のキリスト教に関する略年表
6. 2. ローマ字の採用
7. ルーン文字とは?
8. 現存する最古の英文はルーン文字で書かれていた
9. ルーン文字の遺産
10. 古英語のアルファベット
11. 古英語文学の開花
12. 3. ラテン語の借用
13. 古英語語彙におけるラテン借用語比率
14. キリスト教化以前と以後のラテン借用
15. 4. 聖書翻訳の伝統
16. 5. 宗教と言語
17. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響の比較
18. 日本語における宗教語彙
19. まとめ
20. 補遺:「主の祈り」の各時代のヴァージョン
21. 参考文献
次回の第6回は少し先の2020年3月21日(土)の15:15?18:30となります.「ヴァイキングの侵攻」と題して英語史上の最大の異変に迫る予定です.
2019-11-02 Sat
■ #3841. Whitby の宗教会議(664年)の英語史上の意義 [history][christianity][norman_conquest]
英語史関連の年表を眺めていると,たいてい標記の Whitby の宗教会議 (Synod of Whitby) が項目として挙げられている(以下の記事の年表を参照).
・ 「#1419. 橋本版,英語史略年表」 ([2013-03-16-1])
・ 「#2526. 古英語と中英語の文学史年表」 ([2016-03-27-1])
・ 「#2562. Mugglestone (編)の英語史年表」 ([2016-05-02-1])
・ 「#2871. 古英語期のスライド年表」 ([2017-03-07-1])
・ 「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1])
・ 「#3624. 安藤貞雄『英語史入門』の英語史年表」 ([2019-03-30-1])
この宗教会議は,どのような会議だったのか.『英米史辞典』 によると次の通りである.
Whitby, Synod of 〔英〕 ホイットビー教会会議 663/664年,ノーサンブリア (Northumbria) 王オズウィ (Oswy) により,領内のホイットビー(現在はノース・ヨークシャーの沿岸都市)で,宗教問題解決のために開かれた会議.ノーサンブリアではケルト教会 (Celtic Church) 系のキリスト教会が先に広まり,遅れてローマ教会系のキリスト教が伝わったが,それとともに,両者の軋轢が強まった.特に,復活祭 (Easter) の日取りそのほかをめぐって対立が目立つようになり,ノーサンブリア教会としてはどちらの教会のしきたりを採用するべきかを決定する必要に迫られた.その結果,この会議が招集され,ケルト教会側はリンディスファーン (Lindisfarne) 司教コールマン (Coleman),ローマ教会側はウィルフリッド (Wilfrid) が代表となって論戦を展開したが,結局,オズウィの支持により,ローマ教会方式の採用が決定した.これを機に,ケルト教会が有力であったアングロ・サクソン諸国もノーサンブリアの例にならい,8世紀中にはウェールズ・スコットランド・アイルランドの教会もローマ教会を受け入れた.この会議は,ブリテン島やアイルランドのキリスト教がローマ教会により統一され,ヨーロッパ大陸の教会と一体化する契機を作った.
Whitby の宗教会議の歴史的な意義は,引用の最後にも述べられているとおり,ブリテン諸島を大陸側へグイッと引きつけた点にある.これを契機に,北方の海・島の文化圏が南方の大陸の文化圏へ接近することになった.664年とは,ブリテン諸島がある意味で北から南へと旋回した象徴的な年なのである.それからほぼ400年後,1066年のノルマン征服により,その北から南への旋回はスピードを増すことになった.
英語史の観点から考えてみよう.ノルマン征服の英語史上の意義は,つとに知られている (cf. 「#2047. ノルマン征服の英語史上の意義」 ([2014-12-04-1]),「#3107. 「ノルマン征服と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-29-1])) .端的にいえば,フランス語(およびラテン語)からの影響が強まったということだ.これは言語学的な意味での「北から南への旋回」である.しかし,その旋回の下準備として4世紀前の Whitby の宗教会議があったと解釈すると,俄然この会議の存在が重くみえてくる.あくまで間接的な意義というべきものだが,英語史的にも象徴的な会議だったといえそうだ.
・ 松村 赳・富田 虎男 『英米史辞典』 研究社,2000年.
2019-10-25 Fri
■ #3833. 講座「英語の歴史と語源」の第5回「キリスト教の伝来」のご案内 [asacul][notice][christianity][anglo-saxon][link]
来週末の11月2日(土)の15:15?18:30に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源・5 キリスト教の伝来」と題する講演を行ないます.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.趣旨は以下の通りです.
6世紀以降,英語話者であるングロサクソン人はキリスト教を受け入れ,大陸文化の影響に大いにさらされることになりました.言語的な影響も著しく,英語はラテン語との接触を通じて2つの激震を経験しました.(1) ローマ字の採用と (2) キリスト教用語を中心とするラテン単語の借用です.これは,後のイングランドと英語の歴史を規定することになる大事件でした.今回は,このキリスト教伝来の英語史上の意義について,ほぼ同時代の日本における仏教伝来の日本語史的意義とも比較・対照しながら,多面的に議論していきます.
合わせて,英語史における聖書翻訳の伝統にも触れる予定です.
以下,予習のために,関連する話題を扱った記事をいくつか紹介しておきます.
・ 「#2485. 文字と宗教」 ([2016-02-15-1])
・ 「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1])
・ 「#3038. 古英語アルファベットは27文字」 ([2017-08-21-1])
・ 「#3199. 講座「スペリングでたどる英語の歴史」の第2回「英語初のアルファベット表記 --- 古英語のスペリング」」 ([2018-01-29-1])
・ 「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1])
・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])
・ 「#3787. 650年辺りを境とする,その前後のラテン借用語の特質」 ([2019-09-09-1])
・ 「#3790. 650年以前のラテン借用語の一覧」 ([2019-09-12-1])
・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1])
・ 「#1439. 聖書に由来する表現集」 ([2013-04-05-1])
・ 「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1])
・ 「#1869. 日本語における仏教語彙」 ([2014-06-09-1])
・ 「#3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー」 ([2018-07-31-1])
・ 「#1427. 主要な英訳聖書に関する年表」 ([2013-03-24-1])
・ 「#1709. 主要英訳聖書年表」 ([2013-12-31-1])
2019-01-10 Thu
■ #3545. 文化の受容の3条件と文字の受容 [writing][japanese][kanji][alphabet][runic][buddhism][christianity]
安藤達朗(著)『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 【教養編】』を読んでいる.様々な点で示唆に富む日本史だ.pp. 30--31 に「文化の受容」と題するコラムがあり,その鋭い洞察に目がとまった.
異質の文化が受容されるには,一般に3つの条件がある.第一に,それが先進的なものであるならば,それを受容しうる能力がなければならない.例えば,江戸幕末に欧米近代文明を受容できたのは,日本人の中にすでに合理的思考法の素地もあり,技術に対する理解もかなり進んでいたからである.第二に,それを受容することが必要とされなければならない.例えば,元寇の際に日本軍は元軍の「てつはう」に悩まされながらも,それを取り入れる関心を示さず,戦国時代には鉄砲が伝わると数年後に国産されるようになったのは,鎌倉時代には集団戦が一般化していなかったからである.第三に,受容するに際して,受容する側の主体的条件によって選択がなされ,変更が加えられる.例えば仏教が受容されるとき,その教義よりは呪術的な側面に関心が向けられ,一方では鎮護国家の仏教となり,一方では土俗信仰と密着していったことはそれを示す.
文化の受容には,(1) 受容能力,(2) 受容の必要性,(3) 選択と変更,の3点が要求されるということだ.
言語史に関連する文化の受容の最たるものは,文字の受容だろう.英語や日本語の文字の歴史を振り返ると,いずれも進んだ文字文化をもっていた大陸からの影響で文字を使い出した.アングロサクソン人も日本人も,ローマ字や漢字との接触こそ紀元前後からあったが,必ずしもその段階でそれを「受容」はしなかった.そこまで文化が開けておらず受容の「能力」も「必要性」も足りなかったからだろう.要は当時はまだ準備ができていなかったのである.アングロサクソンでも日本でも,先進的な文字は5--6世紀になってようやく,国家成立の機運や大陸の宗教の流入という契機と結びつく形で,本格的に受容されるに至った.文字受容の能力と必要性を磨くのに,最初の接触以来,数世紀の時間を要したのである.
また,「選択と変更」という観点から,両社会の文字の受容を再考してみるのもおもしろい.アングロサクソン人はローマ字を受容する以前にすでにルーン文字をもっていたのであり,その意味では2つの選択肢のなかから外来の文字セットをあえて「選択」したともいえる.あるいは,後に常用するようになったローマ字セットのなかにルーン文字に由来する <þ> や <ƿ> を導入したのも,一種の「選択」とも「変更」ともいえる.日本の漢字の受容についても,数世紀の時間は要したが,漢字セットの部分集合を利用し,大幅な形態や機能の「変更」を経て仮名を作り出したのだった.
日英の文字の受容史については,これまでもいろいろと書いてきたが,とりわけ以下の記事を参考として挙げておきたい.
・ 「#296. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響」 ([2010-02-17-1])
・ 「#850. 書き言葉の発生と論理的思考の関係」 ([2011-08-25-1])
・ 「#2386. 日本語の文字史(古代編)」 ([2015-11-08-1])
・ 「#2485. 文字と宗教」 ([2016-02-15-1])
・ 「#2505. 日本でも弥生時代に漢字が知られていた」 ([2016-03-06-1])
・ 「#2757. Ferguson による社会言語学的な「発展」の度合い」 ([2016-11-13-1])
・ 「#3138. 漢字の伝来と使用の年代」 ([2017-11-29-1])
・ 「#3486. 固有の文字を発明しなかったとしても……」 ([2018-11-12-1])
・ 安藤 達朗 『いっきに学び直す日本史 古代・中世・近世 【教養編】』 東洋経済新報社,2016年.
2018-10-29 Mon
■ #3472. 慶友会講演 (1) --- 「歴史上の大事件と英語」 [keiyukai][hel_education][slide][christianity][runic][latin][loan_word][bible][norman_conquest][french][ame_bre][spelling][webster][history]
一昨日,昨日と「#3464. 大阪慶友会で講演します --- 「歴史上の大事件と英語」と「英語のスペリングの不思議」」 ([2018-10-21-1]) で案内した大阪慶友会での講演が終了しました.参加者のみなさん,そして何よりも運営関係者の方々に御礼申し上げます.懇親会も含めて,とても楽しい会でした.
1つめの講演「歴史上の大事件と英語」では「キリスト教伝来と英語」「ノルマン征服と英語」「アメリカ独立戦争と英語」の3点に注目し「英語は,それを話す人々とその社会によって形作られてきた歴史的な産物である」ことを主張しました.休憩を挟んで180分にわたる長丁場でしたが,熱心に聞いていただきました.通時的な視点からみることで,英語が立体的に立ち上がり,今までとは異なった見え方になったのではないかと思います.
この講演で用いたスライドを,以下にページごとに挙げておきます.
1. 「歴史上の大事件と英語」
2. はじめに
3. 英語史の魅力
4. 取り上げる話題
5. I. キリスト教伝来と英語
6. 「キリスト教伝来と英語」の要点
7. ブリテン諸島へのキリスト教伝来
8. 1. ローマン・アルファベットの導入
9. ルーン文字とは?
10. ルーン文字の起源
11. 知られざる真実 現存する最古の英文はルーン文字で書かれていた!
12. 古英語アルファベットは27文字
13. 2. ラテン語の英語語彙への影響
14. ラテン語からの借用語の種類と謎
15. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響の比較
16. 3. 聖書翻訳の伝統の開始
17. 各時代の英語での「主の祈り」の冒頭
18. 聖書に由来する表現
19. 「キリスト教伝来と英語」のまとめ
20. II. ノルマン征服と英語
21. 「ノルマン征服と英語」の要点
22. 1. ノルマン征服とは?
23. ノルマン人の起源
24. ノルマン人の流入とイングランドの言語状況
25. 2. 英語への言語的影響は?
26. 語彙への影響
27. 英語語彙におけるフランス借用語の位置づけ
28. 語形成への影響
29. 綴字への影響
30. 3. 英語への社会的影響は?
31. 堀田,『英語史』 p. 74 より
32. 「ノルマン征服と英語」のまとめ
33. III. アメリカ独立戦争と英語
34. 「アメリカ独立戦争と英語」の要点
35. 1. アメリカ英語の特徴
36. 綴字発音 (spelling pronunciation)
37. アメリカ綴字
38. アメリカ英語の社会言語学的特徴
39. 2. アメリカ独立戦争(あるいは「アメリカ革命」 "American Revolution")
40. アメリカ英語の時代区分
41. 独立戦争とアメリカ英語
42. 3. ノア・ウェブスターの綴字改革
43. ウェブスター語録 (1)
44. ウェブスター語録 (2)
45. ウェブスターの綴字改革の本当の動機
46. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめ
47. おわりに
48. 参考文献
2018-07-31 Tue
■ #3382. 神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳したアンジロー [japanese][christianity][borrowing][semantic_borrowing][religion][age_of_discovery]
1549年に鹿児島に入ったフランシスコ・ザビエルは,3人の有能な日本人信者を獲得した.そのうち素性がよく分かっているのは「アンジロー」である.ザビエルはこのアンジローのつてで,薩摩の領主,島津貴久に拝謁することができた.ザビエルは,早速布教を開始したが,キリスト教について何も知られていない日本での布教が多難であったことは想像に難くない.ザビエルやアンジローは,布教に際していかにしてキリスト教の概念や用語を日本人に理解させるかという問題に頭を悩ませたことだろう.この点について,平川 (46--47) が次のように述べている.
それにしても,ザビエルのおぼつかない日本語やアンジローの通訳した説教を聞いて,日本人は本当にキリスト教を理解したのだろうか.実際のところアンジローは,聖母マリアのことを「観音」,天国(パライソ)のことは「極楽」と訳していた.神様の訳語は「大日」であった.大日如来の「大日」のことである.唯一神の観念が日本にはないのでアンジローは困ってしまって「大日」と訳したのだろう.のちに来日した宣教師ヴァリニャーノは,「全くひどい訳だ」と批判しているが,大日如来は仏教では無限宇宙にあまねく存在する超越者という位置づけであるから,最初の訳語としてはそれなりに筋が通っているといってもよい.つまりザビエルたちは日本人に「大日を拝みなさい」と呼びかけたわけであるから,日本人達はキリスト教を仏教の一派だと思って抵抗感なく受け入れたということだろう.
その後ザビエルは,さすがに「大日」ではまずいということに気づいて「天道」と言うようになった.「天道」は「天地をつかさどり,すべてを見通す超自然の存在」という意味をもっているので,日本語で超越的存在を示す用語としては不自然ではない.もう少しあとになると,こうした翻訳語ではキリスト教の正しい概念を伝えられないとして,神のことはそのまま「デウス」,「マリア」のことも「観音」ではなく原語通りに「マリア」と言うようになった.しかしこれまでの研究により,慶長年間(一六〇〇年初頭)まではイエズス会もデウスのことを「天道」と呼ぶことを容認していたとされている.
デウスとは「天道」のことであるという説教を聞けば,多くの日本人はあまり抵抗を感じなかったのではないか.だからこそキリスト教が伝来してわずか四〇年ほどで三〇万人もの信者を得ることができたのだろう.仏教において,僧侶らはともかく,一般レベルでは各宗派の教義にこだわることはあまりなかったし,家付きの宗派または縁故などによって所属の宗派が決まっていたようなものだった.寺院自体が宗派替えをすることもあったのだから,俗人の宗派替えもありえただろう.したがって新しく知ったキリスト教に帰依することは,それほど深奥な宗派替えでも不自然なことでもなかったと思われる.
つまり,アンジローは当初,伝統的な仏教用語にしたがって,キリスト教の神様を「大日」,マリアを「観音」,パライソを「極楽」と訳していたのだ.これは,日本語の語彙体系の観点からいえば既存の用語に新語義を導入したということであり,つまるところ,ここで起こっていることは意味借用 (semantic_borrowing) である.「デウス」「マリア」「パライソ」という,当時の日本人にとってあまりに異質で,それゆえにショッキングであろう語形を借用語として導入するよりも,聞き慣れている既存の日本語のなかにそっと(むっつりと)新たな語義(あるいは宗教的解釈)を滑り込ませるほうが,布教・改宗を進める上では好都合だっただったろうと思われる.
おもしろいことに,6世紀以降にアングロサクソン人の間にキリスト教を広めようとした宣教師も,最初,似たような方法を選んだ.ラテン語 deus (神)を直接英語に導入するのではなく,英語本来語の God を利用して,その語義だけをそっと(むっつりと)キリスト教的な単一神に置き換えたのである.これについては「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1]) と「#2663. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (1)」 ([2016-08-11-1]) を参照されたい.
・ 平川 新 『戦国日本と大航海時代』 中央公論新社〈中公新書〉,2018年.
2018-01-23 Tue
■ #3193. 古英語期の主要な出来事の年表 [timeline][oe][christianity][synod_of_whitby][history][chronology][monarch]
Algeo and Pyles (86--87) より,古英語期の主要な出来事の年表を示そう.
| 449 | Angles, Saxons, Jutes, and Frisians began to occupy Great Britain, thus changing its major population to English speakers and separating the early English language from its Continental relatives. |
| 597 | Saint Augustine of Canterbury arrived in England to begin the conversion of the English by baptizing King Ethelbert of Kent, thus introducing the influence of the Latin language. |
| 664 | The Synod of Whitby aligned the English with Roman rather than Celtic Christianity, thus linking English culture with mainstream Europe. |
| 730 | The Venerable Bede produced his Ecclesiastical History of the English People, recording the early history of the English people |
| 787 | The Scandinavian invasion began with raids along the Northeast seacoast. |
| 865 | The Scandinavians occupied northeastern Britain and began a campaign to conquer all of England. |
| 871 | Alfred became king of Wessex and reigned until his death in 899, rallying the English against the Scandinavians, retaking the city of London, establishing the Danelaw, and securing the position of king of all England for himself and his successors. |
| 991 | Olaf Tryggvason invaded England, and the English were defeated at the Battle of Maldon. |
| 1000 | The manuscript of the Old English epic Beowulf was written about this time. |
| 1016 | Canute became king of England, establishing a Danish dynasty in Britain. |
| 1042 | The Danish dynasty ended with the death of King Hardicanute, and Edward the Confessor became king of England. |
| 1066 | Edward the Confessor died and was succeeded by Harold, last of the Anglo-Saxon kings, who died at the Battle of Hastings fighting against the invading army of William, duke of Normandy, who was crowned king of England on December 25. |
年代と出来事に加えて,簡単な解説が添えられているのがよい.しかも,歴史的意義に関する的確なコメントが散見される.例えば,449年の出来事は,しばしばブリテン島における英語の開始という象徴的な意味合いをもって紹介されるが,ここでは英語が他のゲルマン諸語から袂を分かったことを主眼におくコメントが加えられている.ここには,社会(言語学)的というよりは言語学的な側面により強い関心をもつ Algeo and Pyles の英語史記述の方針が現われているように思われる.
664年のホイットビー会議の歴史的意義にも注目したい.先立つ597年にイングランド人がキリスト教化する種は蒔かれていたといえるかもしれないが,当時のイングランドでは,ローマのキリスト教とともにアイルランドから入ったケルト化したキリスト教が拡大する可能性があった.しかし,この会議によりイングランドにおいてローマのキリスト教が優勢となったことで,後のイングランド史も英語史も,ラテン語を始めとする大陸的なものに大きく影響されていくことになった.島国でありながらも大陸的な要素との接触を常に保ち続けたその後の歴史を考えると,この会議の歴史的意義がおのずと知られる.
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.
2017-10-24 Tue
■ #3102. 「キリスト教伝来と英語」のまとめスライド [slide][christianity][history][bible][runic][alphabet][latin][loan_word][link][hel_education][asacul]
英語史におけるキリスト教伝来の意義について,まとめスライド (HTML) を作ったので公開する.こちらからどうぞ.大きな話題ですが,キリスト教伝来は英語に (1) ローマン・アルファベットによる本格的な文字文化を導入し,(2) ラテン語からの借用語を多くもたらし,(3) 聖書翻訳の伝統を開始した,という3つの点において,英語史上に計り知れない意義をもつと結論づけました.
1. キリスト教伝来と英語
2. 要点
3. ブリテン諸島へのキリスト教伝来 (#2871)
4. 1. ローマン・アルファベットの導入
5. ルーン文字とは?
6. 現存する最古の英文はルーン文字で書かれていた
7. 古英語アルファベット
8. 古英語の文学 (#2526)
9. 2. ラテン語の英語語彙への影響
10. 外来宗教が英語と日本語に与えた言語的影響の比較 (#206)
11. 3. 聖書翻訳の伝統の開始
12. 多数の慣用表現
13. まとめ
14. 参考文献
15. 補遺1: Beowulf の冒頭の11行 (#2893)
16. 補遺2:「主の祈り」の各時代のヴァージョン (#1803)
他の「まとめスライド」として,「#3058. 「英語史における黒死病の意義」のまとめスライド」 ([2017-09-10-1]),「#3068. 「宗教改革と英語史」のまとめスライド」 ([2017-09-20-1]),「#3089. 「アメリカ独立戦争と英語」のまとめスライド」 ([2017-10-11-1]) もご覧ください.
2017-04-13 Thu
■ #2908. キリスト教主要9教派の名称の由来 [etymology][christianity][bible]
英語(史)や英文学(史)を学んでいると,キリスト教に関する様々な知識が必要である.キリスト教の歴史にせよ現状にせよ,きわめて込み入っているので,学ぶのもなかなか大変だ.
八木谷(著)によるキリスト教の入門書を読んでいたら,その補遺 (52) に,主要9教派の起源や名称の由来その他が掲載された便利な一覧表があったので,ここにメモとして残しておきたい.同じ補遺には,キリスト教の教派の系譜なども分かりやすく図示されており,有用.*
| 教派 | 英語名 | 起源 | 名称の由来 | 拠り所 |
|---|---|---|---|---|
| 東方正教会 | Eastern Orthodox Church (Orthodox Churches) | イエスの使徒たちによって各地に創設.1054年,西方教会と分裂 | ギリシャ語の Orthodox は,「正しく(オルソス)」「神を賛美する(ドクサ)」ことを追求する態度に由来.5世紀ころに現れた「異端」の教会に対し,「正統」派とする立場.「東方」は「西方」のローマに対応 | 聖伝と聖書.ニケヤ第1公会議 (325) からニケヤ第2公会議 (787) までの七回の公会議の信条 |
| ローマ・カトリック教会 | Roman Catholic Church | イエスとの使徒ペトロを初代教皇(ローマ司教)とする.1054年,東方教会と分裂 | カトリック (Catholic) とはギリシャ語の Katholikos に由来する形容詞で,普遍的,公同の,万人のためという意味.その普遍性の中心をローマの司教座(ローマの司教がすなわちローマ教皇)におくことから,ローマ・カトリックと呼ばれる. | 聖書と聖伝.公会議の信条.教皇が発する教義 |
| ルター派(ルーテル教会) | Lutheran Churches | ローマ・カトリックの修道司祭だったマルティン・ルターによる宗教改革(ドイツ,1517年以降) | ドイツの宗教改革者マルティン・ルター (Martin Luther) の名前に由来 | 聖書のみ |
| 聖公会(イングランド国教会) | Anglican/Episcopal Churches | イングランド国王ヘンリー八世が政治的動機でローマ・カトリック教会から分離した,国家レベルの宗教改革(イングランド,1534年) | イングランドの国教会 Church of England を母教会とする一連の教会を,Anglican Church (アングリカン=アングル族,すなわちイングランド系の教会)という.日本語の「聖公会」は,使徒信経及びニケヤ信経の一節 "holy catholic church" (聖なる公同の教会)に由来 | 聖書のみ |
| 改革派/長老派 | Reformed/Presbyterian Churches | 進学者ツヴィングリ,カルヴァンらによる宗教改革(スイス,16世紀後半) | 大陸系のカルヴァン主義の教会を指す「改革派」は,「神の言によって改革された」教会の意.英国系の教会に使われる「長老派」は,教会政治において,主教ではなく,教会員のなかから「長老」(ギリシャ語の Presbyteros)を選んで代用とする制度に由来 | 聖書のみ |
| 会衆派(組合派) | Congregational Churches | イングランド国教会からの分離派(イングランド,16世紀後半) | 教会員(会衆)全体の合意にもとづく教会政治に由来.日本では「組合派」ともいい,「組合」の名前が一時教団名として使われた | 聖書のみ |
| バプテスト | Baptist Churches | 宗教改革期のスイスやドイツのアナバプテスト,およびイングランド国教会からの分離派(オランダ,イングランド,17世紀前半) | 聖書に示された洗礼,すなわちバプテスマは,自覚的な信従者のみが,全身を浸す浸礼で行うべきだとし,幼児洗礼を否定した教義に由来.幼児洗礼を認める者から,アナバプテスト(再洗礼者)あるいはバプテストと呼ばれた | 聖書のみ |
| メソジスト | Methodist Churches | イングランド国教会司祭ジョン・ウェスリーによる国教会内部の信仰覚醒運動(イングランド,18世紀半ば) | 教派の創設者ジョン・ウェスリーらに与えられた Methodist (メソッドを重んじる人/几帳面すぎる生活態度の人)というあだ名に由来.ウィースリー本人は,この名称を「聖書に言われている方法〔メソッド〕に従って生きる人」と定義した | 聖書のみ |
| ペンテコステ派 | Pentecostal Churches | 主としてメソジスト系の教会を背景に,北米大陸においては,カンザス州の聖書学校で始まった霊的覚醒運動(アメリカ,1900年ころ) | 新約聖書・使徒言行録第2章に描かれた復活祭後50日目の「五旬祭」,すなわち精霊降臨の日 (Pentecost) に由来.この日,使徒たちに降ったのと同じ精霊の働きを強調する立場を示す | 聖書のみ |
・ 八木谷 涼子 『知って役立つキリスト教大研究』 新潮社,2001年.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2017-04-07 Fri
■ #2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ [oe][literature][popular_passage][christianity][oe_text][pun][kochushoho]
古英語末期を代表する散文作家 Ælfric (955--1010) は,標準的な West-Saxon 方言で多くの文章を残した.今回は,Catholic Homilies の第2集に収められた,Pope Gregory のイングランド伝道に対する熱い想いを綴った,有名なテキストを紹介しよう.市川・松浪のエディション (105--10) の POPE GREGORY より,古英語テキストと現代英語訳を示す.
Þā underȝeat se pāpa þe on ðām tīman þæt apostoliċe setl ȝesæt, hū sē ēadiga Grēgōrius on hālgum mæȝnum ðēonde wæs, and hē ðā hine of ðǣre munuclican drohtnunge ȝenam, and him tō ȝefylstan ȝesette, on diaconhāde ȝeendebyrdne. Ðā ȝelāmp hit æt sumum sǣle, swā swā ȝȳt foroft dēð, þæt englisce ċȳpmenn brōhton heora ware tō Rōmāna byriȝ, and Gregorius ēode be ðǣre strǣt tō ðām engliscum mannum heora ðing scēawiȝende. Þā ȝeseah hē betwux ðām warum, ċȳpecnihtas ȝesette, þā wǣron hwītes līchaman and fæȝeres andwlitan menn, and æðelīċe ȝefexode.
Grēgōrius ðā behēold þǣra cnapena wlite, and befrān of hwilċere þēode hī ȝebrohte wǣron. Þā sǣde him man þæt hī of engla lande wǣron, and þæt ðǣre ðēode mennisc swā wlitiȝ wǣre. Eft ðā Grēgōrius befrān, hwæðer þæs landes folc cristen wǣre ðe hǣðen. Him man sǣde þæt hī hǣðene wǣron. Grēgōrius ðā of innweardre heortan langsume siċċetunge tēah, and cwæð: “Wā lā wā, þæt swa fæȝeres hīwes menn sindon ðām sweartan dēofle underðēodde.” Eft hē āxode hū ðǣre ðēode nama wǣre, þe hī of comon. Him wæs ȝeandwyrd þæt hī Angle ȝenemnode wǣron. Þā cwæð hē: “rihtlīċe hī sind Angle ȝehātene, for ðan ðe hī engla wlite habbað, and swilcum ȝedafenað þæt hī on heofonum engla ȝefēran bēon.” Gȳt ðā Grēgōrius befrān, hū ðǣre scīre nama wǣre, þe ðā cnapan of ālǣdde wæron. Him man sǣde þæt ðā scīrmen wǣron Dēre ȝehātene. Grēgōrius andwyrde: “Wel hī sind Dēre ȝehātene. for ðan ðe hī sind fram graman ȝenerode, and tō cristes mildheortnysse ȝecȳȝede.” Gȳt ðā hē befrān: “Hū is ðǣre leode cyning ȝehāten?” Him wæs ȝeandswarod þæt se cyning Ælle ȝehāten wǣre. Hwæt, ðā Grēgōrius gamenode mid his wordum to ðām naman, and cwæð: “Hit ȝedafenað þæt alleluia sȳ ȝesungen on ðām lande. tō lofe þæs ælmihtigan scyppendes.”
Grēgōrius ðā sōna ēode tō ðām pāpan þæs apostolican setles, and hine bæd þæt hē Angelcynne sume lārēowas āsende, ðe hī to criste ȝebiȝdon, and cwæð þæt hē sylf ȝearo wǣre þæt weorc tō ȝefremmenne mid godes fultume, ȝif hit ðām pāpan swā ȝelīcode. Þā ne mihte sē pāpa þæt ȝeðafian, þeah ðe hē eall wolde, for ðan ðe ðā rōmāniscan ċeasterȝewaran noldon ȝeðafian þæt swā ȝetoȝen mann and swā ȝeðungen lārēow þā burh eallunge forlēte, and swā fyrlen wræcsīð ȝename.
Then perceived the pope who at that time sat on the apostolic seat, how the blessed Gregory was thriving in the holy troops, and he then picked him up from the monastic condition, and made him (his) helper, (being) ordained to deaconhood. Then it happened at one time (= one day), as it yet very often does, that English merchants brought their wares to the city of Rome, and Gregory went along the street to the English men, looking at their things. Then he saw, among the wares, slaves set. They were men of white body and fair face, and excellently haired.
Gregory then beheld the appearance of those boys, and asked from which country they were brought. Then he was told that they were from England, and that the people of that country were so beautiful. Then again Gregory asked whether the fold of the land was Christian or heathen. They told him that they were heathen. Gregory then drew a long sigh from the depth of (his) heart, and said, 'Alas! that men of so fair appearance are subject to the black devil.' Again he asked how the name of the nation was, where they came from. He was answered that they were named Angles. Then said he, 'rightly they are called Angles, because they have angels' appearance, and it befits such (people) that they should be angels' companions in heavens!' Still Gregory asked how the name of the shire was, from which they were led away. They told him that the shiremen were called Deirians. Gregory answered, 'They are well called Deirians, because they are delivered from ire, and invoked to Christ's mercy.' Still he asked 'How is the king of the people called?' He was answered that the king was called Ælle. What! then Gregory joked with his words to the name, and said, 'It is fitting that Halleluiah be sung in the land, in praise of the Almighty Creator.'
Then Gregory at once went to the pope of the apostolic seat, and entreated him that he should send some preachers to the English, whom they converted to Christ, and said that he himself was ready to perform the work with God's help, if it so pleased the pope. The pope could not permit it, even if he quite desired (it), because the Roman citizens would not consent that such an educated and competent scholar should leave the city completely and take such a distant journey of peril.
なお,この逸話の主人公は後の Gregory I だが,テキスト中で示されている pāpa は当時の Pelagius II を指している.この後,さすがに Gregory が自らイングランドに布教に出かけるというわけにはいかなかったので,後に Augustinus (St Augustine) を送り込んだというわけだ.
この逸話を受けて,渡部とミルワード (50--51) は,英国のキリスト教はダジャレで始まったようなものだと評している.
渡部 若いときにグレゴリーがローマで非常に肌の白い,金髪の奴隷を見ました.で,その奴隷に「おまえはどこから来たのか」ときいたら,「アングル (Angle)」人と答えた.そこでグレゴリーは「おまえはアングル人じゃなくてエンジェル (angel) のようだ」といったというような有名な話があります.
ミルワード そう,有名なシャレです.ですから,ある意味でイギリスのキリスト教史は言葉のシャレから始まると言うことができます.--- Non angli, sed angeli, --- Not Angles, but angels.
渡部 そして,「おまえの国は?」と聞いたら「デイラ (Deira) です」とその奴隷は答えた.すると「〔神の〕怒から (de ira) 救われて,キリストの慈悲に招かれるであろう」とグレゴリーは言ってやった.それから「おまえの王様の名は何か」と聞いたら「エルラ (Ælla) です」と奴隷は答えた.するとグレゴリーはそれをアレルヤとかけて「エルラの国でもアルレルリア (Allelulia) と,神をたたえる言葉が唱えられるようにしよう」と言った有名な話がありますね.本当にジョークで始まったんですね,イギリスの布教は.
(後記 2024/04/13(Sat):Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて,この1節の "Eft hē āxode . . . ȝefēran bēon." の部分について古英語音読していますのでご参照ください.「#1048. コアリスナーさんたちと古英語音読」です.)
(後記 2024/06/12(Wed):上記 Voicy で読み上げた部分の写本画像へのリンクです:Catholic Homilies, Second Series, "IX, St Gregory the Great" (MS Ii.1.33, fol. 140v) *
・ 市河 三喜,松浪 有 『古英語・中英語初歩』 研究社,1986年.
・ 渡部 昇一,ピーター・ミルワード 『物語英文学史――ベオウルフからバージニア・ウルフまで』 大修館,1981年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow