2023-07-13 Thu
■ #5190. 小河舜さんとの heldio 対談と YouTube 共演 [ogawashun][voicy][heldio][youtube][wulfstan][oe][old_norse][history][anglo-saxon][literature][toponymy][onomastics]
昨日「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」の最新回がアップされました.「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡 --- ゲスト・小河舜さん」です.小河舜さんを招いての全4回シリーズの第1弾となります.
小河さんの研究テーマは後期古英語期の説教師・政治家 Wulfstan とその言語です.立教大学の博士論文として "Wulfstan as an Evolving Stylist: A Chronological Study on His Vocabulary and Style." を提出し,学位授与されています.Wulfstan については本ブログより「#5176. 後期古英語の聖職者 Wulfstan とは何者か? --- 小河舜さんとの heldio 対談」 ([2023-06-29-1]) をご覧ください.また,小河さんは今回の YouTube の話題のように,イギリスの地名(特に古ノルド語要素を含む地名)にも関心をお持ちです.
小河さんとは,今回の YouTube 共演以前にも,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で複数回にわたり対談し,その様子を配信してきました.実際,今朝の heldio 最新回でも小河さんとの対談を配信しています.これまでの対談回を一覧にまとめましたので,ぜひお時間のあるときにお聴きいただければ.
・ 「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」(6月29日配信)
・ 「#761. Wulfstan の生きたヴァイキング時代のイングランド --- 小河舜さんとの対談【第2弾】」(7月1日配信)
・ 「#763. Wulfstan がもたらした超重要単語 "law" --- 小河舜さんとの対談【第3弾】」(7月3日配信)
・ 「#765. Wulfstan のキャリアとレトリックの変化 --- 小河舜さんとの対談【第4弾】」(7月5日配信)
・ 「#767. Wulfstan と小河さんのキャリアをご紹介 --- 小河舜さんとの対談【第5弾】」(7月7日配信)
・ 「#770. 大学での英語史講義を語る --- 小河舜さんとの対談【第6弾】」(7月10日配信)
・ 「#773. 小河舜さんとの新シリーズの立ち上げなるか!?」(本日7月13日配信)
小河さんの今後の英語史活動(hel活)にも期待しています!
(以下は,2023/08/02(Wed) 付で加えた後記です)
・ YouTube 小河舜さんシリーズ第1弾:「#144. イギリスの地名にヴァイキングの足跡 --- ゲスト・小河舜さん」です
・ YouTube 小河舜さんシリーズ第2弾:「#146. イングランド人説教師 Wulfstan のバイキングたちへの説教は歴史的異言語接触!」
・ YouTube 小河舜さんシリーズ第3弾:「#148. 天才説教師司教は詩的にヴァイキングに訴えかける!?」
・ YouTube 小河舜さんシリーズ第4弾:「#150. 宮崎県西米良村が生んだ英語学者(philologist)でピアニスト小河舜さん第4回」
2023-06-29 Thu
■ #5176. 後期古英語の聖職者 Wulfstan とは何者か? --- 小河舜さんとの heldio 対談 [ogawashun][voicy][heldio][wulfstan][oe][old_norse][history][anglo-saxon][literature]
今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,「#759. Wulfstan て誰? --- 小河舜さんとの対談【第1弾】」を配信しました.対談相手の小河舜さんは,この Wulfstan とその著作の言語(古英語)を研究し,博士号(立教大学)を取得されています.対談の第1弾と銘打っている通り,今後,第2弾以降も順次お届けしていく予定です.
Wulfstan は,996--1002年にロンドン司教,1002--1023年にヨーク大司教,そして1002--1016年にウースター司教を務めた聖職者で,Lupus (狼)の仮名で古英語の説教,論文,法典を多く著わしました.ベネディクト改革を受けて現われた,当時の宗教界・政治界の重要人物です.司教になる前の経歴は不明です.
Wulfstan の文体は独特なものとして知られており,作品の正典はおおよそ確立されています.1008年から Æthelred と Canute の2人の王の顧問を務め,法律を起草しました.Wulfstan は,Canute にキリスト教の王として統治するよう促し,アングロサクソン文化を破壊から救った人物としても評価されています.Wulfstan は政治や社会のあり方に関心をもち,Institutes of Polity を著わしています.そこでは,王を含むすべての階級の責任を記述し,教会と国家の関係について論じています.
Wulfstan は教会改革にも深く関わっており,教会法の文献を研究しました.また,Ælfric に2通の牧会書簡を書くように依頼し,自身も The Canons of Edgar として知られるテキストを書いています.
Wulfstan の最も有名な作品は,Æthelred がデンマークの Sweyn 王に追放された後に,同胞に改悛と改革を呼びかけた情熱的な Sermo Lupi ad Anglos (1014) です.
Wulfstan は,アングロサクソン人にとってきわめて多難な時代に,政治の舵取りを任された人物でした.彼にとって,レトリックはこの難局を克服するための重要な手段だったはずです.悩める Wulfstan の活躍した時代背景やそのレトリックについて,小河さんとの今後の対談にご期待ください.
2023-06-05 Mon
■ #5152. 古英語聖書より「種をまく人の寓話」 --- 毒麦の話 [oe][popular_passage][bible][literature][oe_text][hel_education][voicy][heldio]
古英語テキストを原文で読むシリーズ.新約聖書のマタイ伝より13章の「種をまく人の寓話」より24--30節の毒麦の話を,古英語版で味わってみよう.以下,Sweet's Anglo-Saxon Primer (9th ed.) の校訂版より引用する.あわせて,1611年の The Authorised Version (The King James Version [KJV]) の近代英語訳と日本語口語訳も添えておく.
[ 古英語 ]
Heofona rīċe is ġe·worden þǣm menn ġe·līċ þe sēow gōd sǣd on his æcere. Sōþlīċe, þā þā menn slēpon, þā cōm his fēonda sum, and ofer·sēow hit mid coccele on·middan þǣm hwǣte, and fērde þanon. Sōþlīċe, þā sēo wyrt wēox, and þone wæstm brōhte, þā æt·īewde se coccel hine. Þā ēodon þæs hlāfordes þēowas and cwǣdon: 'Hlāford, hū, ne sēowe þū gōd sǣd on þīnum æcere? Hwanon hæfde hē coccel?' Þā cwæþ hē; 'Þæt dyde unhold mann.' Þā cwǣdon þā þēowas 'Wilt þū, wē gāþ and gadriaþ hīe?' Þā cwæþ hē: 'Nese: þȳ·lǣs ġē þone hwǣte ā·wyrtwalien, þonne ġē þone coccel gadriaþ. Lǣtaþ ǣġþer weaxan oþ rīp-tīman; and on þǣm rīptīman iċ secge þǣm rīperum: "Gadriaþ ǣrest þone coccel, and bindaþ scēaf-mǣlum tō for·bærnenne; and gadriaþ þone hwǣte in-tō mīnum berne."'
[ 近代英語 ]
[24] . . . The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field: [25] But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. [26] But when the blade was sprung up, and brought forth fruit, then appeared the tares also. [27] So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in thy field? from whence then hath it tares? [28] He said unto them, An enemy hath done this. The servants said unto him, Wilt thou then that we go and gather them up? [29] But he said, Nay; lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. [30] Let both grow together until the harvest: and in the time of harvest I will say to the reapers, Gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them: but gather the wheat into my barn.
[ 日本語口語訳 ]
[24] ………「天国は,良い種を自分の畑にまいておいた人のようなものである.[25] 人々が眠っている間に敵がきて,麦の中に毒麦をまいて立ち去った.[26] 芽がはえ出て実を結ぶと,同時に毒麦もあらわれてきた.[27] 僕たちがきて,家の主人に言った,『ご主人様,畑におまきになったのは,良い種ではありませんでしたか.どうして毒麦がはえてきたのですか』.[28] 主人は言った,『それは敵のしわざだ』.すると僕たちが言った『では行って,それを抜き集めましょうか』.[29] 彼は言った,『いや,毒麦を集めようとして,麦も一緒に抜くかも知れない.[30] 収穫まで,両方とも育つままにしておけ.収穫の時になったら,刈る者に,まず毒麦を集めて束にして焼き,麦の方は集めて倉に入れてくれ,と言いつけよう』」.
今回は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」との連動企画として,上記の古英語テキストを「#735. 古英語音読 --- マタイ伝「種をまく人の寓話」より毒麦の話」で読み上げています.ぜひお聴きください.
加えて,マタイ伝の同章の少し前の箇所,3--8節のくだりについて,関連する「#2906. 古英語聖書より「種をまく人の寓話」」 ([2017-04-11-1]) も参照.ほかに古英語聖書のテキストとしては「#2895. 古英語聖書より「岩の上に家を建てる」」 ([2017-03-31-1]),「#1803. Lord's Prayer」 ([2014-04-04-1]),「#1870. 「創世記」2:18--25 を7ヴァージョンで読み比べ」 ([2014-06-10-1]) も参照されたい.
・ Davis, Norman. Sweet's Anglo-Saxon Primer. 9th ed. Oxford: Clarendon, 1953.
2023-04-25 Tue
■ #5111. チョーサーによるブルトン・レ「地方地主の話の序」を読む [chaucer][canterbury_tales][franklins_tale][breton_lai][me_text][celtic][breton][voicy][heldio][me_text][literature][brittany_exhibition]
今回は Geoffrey Chaucer (1340?--1400) の傑作 The Canterbury Tales より The Franklin's Tale 「地方地主の話の序」を読んでみたい.
この作品は,ブルターニュ地方が舞台となっている.ブルターニュといえば,ブリテン島のケルト人の一派が,5--6世紀にアングロサクソン人による侵攻から逃れ,イギリス海峡を南に越えてたどり着いたフランス側の土地である.その地には現在もブルトン人が住んでおり,ブルトン語 (Breton) を話している.
ブルトン人たちは Breton lai (ブルトン・レ)と呼ばれる短い物語詩のジャンルを生み出し,そのジャンルは海峡の両側に伝わっている.フランス側では Marie de France (c. 1160--1215) がフランス語で書いた作品が有名だが,ブリテン島側でも翻案作品が著わされた.今回のチョーサーによる「地方地主の話」は,その1つである.
「地方地主の話の序」の中英語原文を The Riverside Chaucer より,日本語訳を『カンタベリ物語 共同新訳版』より引用する.
THE FRANKLIN'S PROLOGUE
Prologe of the Frankeleyns Tale.
l. 709 Thise olde gentil Britouns in hir dayes 710 Of diverse aventures maden layes, 711 Rymeyed in hir firste Briton tonge, 712 Whiche layes with hir instrumentz they songe 713 Or elles redden hem for hir plesaunce; 714 And oon of hem have I in remembraunce, 715 Which I shal seyn with good wyl as I kan. 716 But, sires, by cause I am a burel man, 717 At my bigynnyng first I yow biseche, 718 Have me excused of my rude speche. 719 I lerned nevere rethorik, certeyn; 720 Thyng that I speke, it moot be bare and pleyn. 721 I sleep nevere on the Mount of Pernaso, 722 Ne lerned Marcus Tullius Scithero. 723 Colours ne knowe I none, withouten drede, 724 But swiche colours as growen in the mede, 725 Or elles swiche as men dye or peynte. 726 Colours of rethoryk been to me queynte; 727 My spirit feeleth noght of swich mateere. 728 But if yow list, my tale shul ye heere.
地方地主の話の序
今は昔,雅びなブルターニュの人たちは,さまざまなできごとを歌に詠み,いにしえのケルトの言葉で技をこらし,楽器に合わせて歌ったり,読み語りを楽しんだりしておりました.そのような話をひとつ覚えていますので,微力を尽くしてお話ししたいと思っております.
けれども,何しろ学がないもので,乱暴な言葉遣いをお許しいただくよう,まずは皆さんにお願いします.まったく,修辞学なんぞ習ったこともなく,あからさまな話し方しかできんのです.パルナッソス山で眠ったこともなければ,マルクス・トゥリウス・キケロを学んだこともない.言葉のあやなどさっぱりで,目もあやな野の花や,染めたり織ったりのあやしか知らんのです.語りのあやは解らんし,その類のセンスも持ちあわせておらん.でも,よろしければ話をお聞き下さい.
なお,上記の中英語原文を今朝の Voicy heldio で読み上げている.中英語に関心がある方,読解に挑戦してみたいと思う方は,ぜひ「#694. チョーサーによるブルトン・レ「地方地主の話の序」を原文で味わってみませんか?」をお聴きください.
・ Benson, Larry D., ed. The Riverside Chaucer. 3rd ed. Oxford: OUP, 1987.
・ ジェフリー・チョーサー(著),池上 忠弘(監訳) 『カンタベリ物語 共同新訳版』 悠書館,2021年.
・ 池上 昌・堀田 隆一・狩野 晃一 「チョーサーの英語」 『チョーサー巡礼 古典の遺産と中世の新しい息吹に導かれて』(池上 忠弘(企画),狩野 晃一(編)) 悠書館,2022年.93--124頁.
2023-04-24 Mon
■ #5110. 国立西洋美術館「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けての予習 [museum][seminar][khelf][celtic][breton][voicy][heldio][breton_lai][contact][literature][linguistic_imperialism][language_death][brittany_exhibition]
目下,東京・上野の国立西洋美術館にて「憧憬の地 ブルターニュ ー モネ,ゴーガン,黒田清輝らが見た異郷」展覧会が開催中です.開催期間は3月18日から6月11日までとなっています.

この開催の機会をとらえ,今学期の私のゼミでは「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」をテーマとして,事前に予習した上で,5月末辺りに課外活動としてゼミの皆で展覧会を訪れる予定です.今後,本ブログでも Voicy heldio でも,関係する話題がチラホラ出てくるかと思います.本記事をお読みの皆さんも,ぜひブルターニュ(展)に関心を寄せていただければと.
フランス北西部ブルターニュ地方では,ケルト語派のブルトン語 (Breton) が伝統的に話されています.ただし,地域の強大言語であるフランス語に押されているという事実があります.これはブリテン諸島の北や西のコーナーで,ケルト系諸語が英語に圧迫されているのと平行的な状況です.
ケルト諸語の分布や歴史については「#774. ケルト語の分布」 ([2011-06-10-1]),「#778. P-Celtic と Q-Celtic」 ([2011-06-14-1]),「#779. Cornish と Manx」 ([2011-06-15-1]),「#3113. アングロサクソン人は本当にイングランドを素早く征服したのか?」 ([2017-11-04-1]),「#3761. ブリテンとブルターニュ」 ([2019-08-14-1]),「#4491. 1300年かかったイングランドの完全英語化」 ([2021-08-13-1]) を含む celtic の記事を参照してください.また,昨日の Voicy heldio では,関連して「#692. ケルト語派を紹介します」を配信しています.
展覧会訪問までの「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」のための予習事項は,主として以下の3点です.
1. 歴史的にみる英語の拡大とケルト諸語の縮小
2. 中英語で書かれたブルトン・レ (Breton lai)
3. 英語とケルト語の言語接触
今朝の Voicy heldio では,本記事と同様の内容でおしゃべりしています.「#693. 英語史とケルト,英語史とブルターニュ --- 国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」訪問に向けて」です,ぜひお聴きください.
国立西洋美術館の「憧憬の地 ブルターニュ展」,およびこれから1ヶ月ほど追いかけていく「英語史とケルト,英語史とブルターニュ」というテーマについて,ぜひご注目ください.
2022-11-30 Wed
■ #4965. チョーサーは頭韻がお嫌い? 'rum, ram, ruff' [alliteration][rhyme][chaucer][sggk][literature]
映画『グリーン・ナイト』が公開中です.その原作『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) は14世紀末の中英語ロマンスですが,ほぼ同時代に書かれたジェフリー・チョーサー (Geoffrey Chaucer) の『カンタベリ物語』 (The Canterbury Tales) とは,あらゆる面で異なっています.前者はコテコテのイングランド北西部の英語方言で頭韻 (alliteration) によって書かれており,後者は後に標準英語へと発展していくロンドン英語で脚韻 (rhyme) によって書かれています.
チョーサーはもっぱら大陸由来の脚韻で詩作し,ゲルマン語としての英語に伝統的に受け継がれてきた頭韻には関心がなかったようです.現代の日本の歌謡界になぞらえていえば「私はポップス歌手だけれど民謡や演歌はやりませんよ」といった雰囲気です.このことは,チョーサー自身が本気では頭韻を利用していないこと,また『カンタベリ物語』の「教区主任司祭の話の序」 (ll. 42--47) にて,次のように述べていることからも間接的に知られます (The Riverside Chaucer より).
But trusteth wel, I am a Southren man;
I kan nat geeste 'rum, ram, ruf,' by lettre,
Ne, God woot, rym holde I but litel bettre;
And therfore, if yow list --- I wol nat glose ---
I wol yow telle a myrie tale in prose
To knytte up al this feeste and make an ende.
これを日本語に訳すと次のようになります.
ですが,ぜひともご理解いただきたいのですが,私は南の出身です.ですから "rum","ram","ruf" という具合に言葉の頭で韻を踏むことなどできません.また,神もご存知ですが,私は脚韻も踏むこともまずできません.ですから,よろしければ --- 注釈する気はさらさらないのですが --- 皆様に散文で楽しい話をいたしましょう.それでこのお楽しみの会で編まれるべきものをすべて編み上げて締めくくりましょう
チョーサーは,教区主任司祭という登場人物にやや軽んじた口調で 'rum, ram, ruff' と発言させています.文字通りには頭韻も脚韻もやりませんと読めますが,頭韻を脚韻より劣るものと見なしていると読むことも可能かもしれません.いかがでしょうか.ここでは,池上 (144) の読みを紹介しておきたいと思います.引用で「彼」とは詩人チョーサーのことです.
彼はどうもアーサー王物語の頭韻詩があまり好きでないらしい.時どき頭韻調を使ってみたり,『教区司祭の話 前口上』では,「私は南部の人間なので,ルム・ラム・ルフ (rum, ram, ruf) なんて頭韻を踏む吟唱などは出来ません」(X 四二ー四三)という有名な台詞がある.当時から見ても古くさい,異質の,田舎くさい,違ったジャンルの詩物語と見ているらしいのである.
このような時代と状況下で,なぜガウェイン詩人は主に頭韻を用いて詩作したのか.この辺りがおもしろい問題です.
・ Benson, Larry D., ed. The Riverside Chaucer. 3rd ed. Oxford: OUP, 1987.
・ ジェフリー・チョーサー(著),池上 忠弘(監訳) 『カンタベリ物語 共同新訳版』 悠書館,2021年.
・ 池上 忠弘(訳) 『「ガウェイン」詩人 サー・ガウェインと緑の騎士』 専修大学出版局,2009年.
2022-11-28 Mon
■ #4963. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が首切りゲームをふっかけるシーン [sggk][me_text][me_dialect][literature][popular_passage][voicy][heldio]
映画『グリーン・ナイト』が公開中なので,連日この映画およびその原作『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) についての話題をお届けしています.一昨日,映画の字幕監修を務められた岡本広毅先生(立命館大学)と,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の生放送にて対談を行ないました.まだお聴きでない方はアーカイヴより「#544. 岡本広毅先生と『グリーン・ナイト』とその原作の言語をめぐって対談しました」を聴取ください.映画鑑賞のよい予習になると思います.
今回は「#4890. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が登場するシーン」 ([2022-09-16-1]) と「#4931. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より冒頭の2スタンザ」 ([2022-10-27-1]) に引き続き,原作 Sir Gawain and the Green Knight より名シーンを読み上げつつ紹介します.緑の騎士が首切りゲームをふっかけるシーンです.
映画の紹介として「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」として YouTube 動画(3分15秒)が公開されています.動画の0分50秒辺りから,映画のこのシーンと中英語テキストが導入されます.今回はこの中英語テキストを含む1スタンザ (ll. 279--300) を取り上げます.
今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では「#545. 『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が首切りゲームをふっかけるシーンを中英語原文で読み上げます」として原文を音読していますので,ぜひお聴きください.
以下に中英語原文(Andrew and Waldron 版)と日本語訳(池上)を掲げます.
'Nay, frayst I no fyȝt, in fayth I þe telle;
Hit arn aboute on þis bench bot berdlez chylder.
If I were hasped in armes on a heȝe stede,
Here is no mon me to mach, for myȝtez so wayke.
Forþy I craue in þis court a Crystemas gomen,
For hit is Ȝol and Nwe Ȝer, and here are ȝep mony.
If any so hardy in þis hous holdez hymseluen,
Be so bolde in his blod, brayn in hys hede,
Þat dar stifly strike a strok for anoþer,
I schal gif hym of my gyft þys giserne ryche,
Þis ax, þat is heué innogh, to hondele as hym lykes,
And I schal bide þe fyrst bur as bare as I sitte.
If any freke be so felle to fonde þat I telle,
Lepe lyȝtly me to and lach þis weppen---
I quit-clayme hit for euer, kepe hit as his auen---
And I schal stonde hym a strok, stif on þis flet,
Ellez þou wyl diȝt me þe dom to dele hym anoþer
Barlay,
And ȝet gif hym respite
A twelmonyth and a day.
Now hyȝe, and let se tite
Dar any herinne oȝt say.'
「いや,正直に申して,戦いを望んでいるのではないのだ.この辺りの席には,ひげの生えていない子供(がき)しかおらぬようだな.わしが甲冑を身にまとい,大きな馬に打ち跨がるならば,力不足でわしに立ち向かえる相手は一人もおるまい.そういう具合だから,わしがこの宮廷で望むのはクリスマスの遊びごと,いまちょうどクリスマスと新年の時期で,ここには元気のよい面々が沢山おるからな.この館で我こそは胆力ありと思う者がいるなら,気性激しく心猛り,臆せず大胆不敵にも打撃を打ちかわす者がいるならば,褒美の品としてこの見事な戦斧をくれてやるぞ.この斧はずしりと重いやつで,思うように扱うのが難しいが,わしがここに坐って甲冑もつけず,最初の一撃を受けることにしよう.わしの言ったことを試してみようという肝のすわった奴がいるならば,すぐさま飛びだしてきてこの武器を手に取るならば,この斧を永久に譲渡し,そいつの物にしてやろう.この床に坐って怯まず,そいつの一撃を受けよう.ただし,わしがそいつに返しの一撃を加える権利をもつということで,
わしの番には,
だが猶予期間を与えよう,
一年と一日の.
さあ,急いだり,さあすぐに,
名乗り出る奴はここにはおらんのか.」
・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.
・ 池上 忠弘(訳) 『「ガウェイン」詩人 サー・ガウェインと緑の騎士』 専修大学出版局,2009年.
2022-11-22 Tue
■ #4957. heldio 生放送(岡本&堀田の対談)のお知らせ! 11月26日(土)午前10:00--11:00「ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』」 [voicy][heldio][notice][khelf][literature][romance][sggk][link]
今週末11月26日(土)の午前10:00--11:00に,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で標記の生放送を配信します.立命館大学の岡本広毅先生との対談という形式でお届けします.
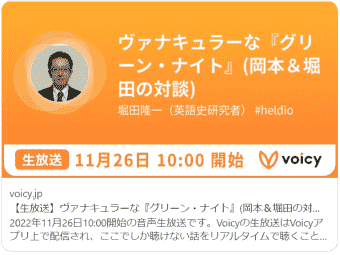
内容は,生放送の前日11月25日(金)に全国で封切りとなる映画『グリーン・ナイト』と,その原作である中英語ロマンス『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) について,その語りの媒体となっているヴァナキュラー,すなわち中英語イングランド北西方言に焦点を当てつつディープに雑談する予定です.映画公開直後ということですので,気を遣いつつも少々のネタバレはOK!?というノリで行きたいと思います(私もまだ観ていないままの対談なのです).緩く次のようなトピックで対談をお届けできればと思っています.
・ ヴァナキュラーな『グリーン・ナイト』について
・ 中英語原典『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) とその時代背景
・ 言語的特色(英語とローカリティ,方言)
・ 原典の紹介,読みどころ
・ 映画『グリーン・ナイト』に関して(ネタバレ注意)
26日(土)の生放送に向けて,事前に岡本先生に対するご質問やコメントなどがあれば,ぜひ上記の Voicy 配信案内を通じてお寄せください.また,生放送時の投げ込み質問にもなるべく対応したいと思っています.生放送に参加できない場合にも,翌朝の heldio レギュラー回で収録の様子をアーカイヴとして一般配信もしますので,そちらで聴取いただければ幸いです.
岡本先生より教えていただいた映画『グリーン・ナイト』の関連情報を,以下に貼り付けておきます.
・ 映画公式サイト
・ 本映画の映像制作・配給会社 Transformer
・ 本映画の特設ツイッター
・ 「A24が贈るダーク・ファンタジー『グリーン・ナイト』,大塚明夫がナレーションを務めた解説動画解禁」
・ 「山田南平が映画「グリーン・ナイト」のイラスト描き下ろし,奈須きのこらコメントも」
heldio では,これまでも岡本先生と3度ほど対談しています.今度の生放送に向けて,以下を聴取し復習・予習していただけると,理解度が倍増すると思います.実際,話す内容は過去回からの延長線上となる予定です.
・ heldio 「#173. 立命館大学,岡本広毅先生との対談:国際英語とは何か?」 (2021/11/20)
・ heldio 「#386. 岡本広毅先生との雑談:サイモン・ホロビンの英語史本について語る」 (2022/06/21)
・ heldio 「#478. 英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」 (2022/09/21)
さらに,今回の対談でも中心的な話題となるはずの vernacular についても,予習していただけると絶対におもしろくなると思います.以下に hellog の関連記事へのリンクを張っておきます.
・ 「#4804. vernacular とは何か?」 ([2022-06-22-1])
・ 「#4809. OED で vernacular の語義を確かめる」 ([2022-06-27-1])
・ 「#4812. vernacular が初出した1601年前後の時代背景」 ([2022-06-30-1])
・ 「#4814. vernacular をキーワードとして英語史を眺めなおすとおもしろそう!」 ([2022-07-02-1])
・ 「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1])
ぜひ肩の力を抜いて11月26日(土)の生放送をお聴きください!
2022-10-27 Thu
■ #4931. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より冒頭の2スタンザ [sggk][me_text][me_dialect][literature][popular_passage][voicy][heldio]
中英語ロマンスの傑作『ガウェイン卿と緑の騎士』 (Sir Gawain and the Green Knight) の翻案作品となる映画『グリーン・ナイト』が11月25日より公開されます.この機会を逃さず,大学(院)の授業などで SGGK の原文を読んでいます.
先日 hellog でも「#4890. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が登場するシーン」 ([2022-09-16-1]) を紹介しつつ Voicy と連携して読み上げてみました(こちらから聴いてみてください).今回は,同じ趣向ですが,作品冒頭の2スタンザ (ll. 1--36) を中英語原文(Andrew and Waldron 版)に基づいて Voicy 「#514. 『ガウェイン卿と緑の騎士』より冒頭の2スタンザを中英語原文で読み上げます」で読み上げました.以下の原文とともにお聴きください.
Siþen þe sege and þe assaut watz sesed at Troye,
Þe borȝ brittened and brent to brondez and askez,
Þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wroȝt
Watz tried for his tricherie, þe trewest on erthe.
Hit watz Ennias þe athel and his highe kynde,
Þat siþen depreced prouinces, and patrounes bicome
Welneȝe of al þe wele in þe west iles.
Fro riche Romulus to Rome ricchis hym swyþe,
With gret bobbaunce þat burȝe he biges vpon fyrst
And neuenes hit his aune nome, as hit now hat;
Ticius to Tuskan and teldes bigynnes,
Langoberde in Lumbardie lyftes vp homes,
And fer ouer þe French flod, Felix Brutus
On mony bonkkes ful brode Bretayn he settez
Wyth wynne,
Where werre and wrake and wonder
Bi syþez hatz wont þerinne
And oft boþe blysse and blunder
Ful skete hatz skyfted synne.
Ande quen þis Bretayn watz bigged bi þis burn rych
Bolde bredden þerinne, baret þat lofden,
In mony turned tyme tene þat wroȝten.
Mo ferlyes on þis folde han fallen here oft
Þen in any oþer þat I wot, syn þat ilk tyme.
Bot of alle þat here bult of Bretaygne kynges
Ay watz Arthur þe hendest, as I haf herde telle.
Forþi an aunter in erde I attle to schawe,
Þat a selly in siȝt summe men hit holden
And an outrage awenture of Arthurez wonderez.
If ȝe wyl lysten þis laye bot on littel quile,
I schal telle hit astit, as I in toun herde,
Wyth tongue.
As hit is stad and stoken
In stori stif and stronge,
With lel lettres loken,
In londe so hatz ben longe.
意味を確認するために Bantock の現代韻文訳および池上による日本語訳も挙げておきます.
When the assault on Troy and the siege had come to an end,
The ramparts smashed to a heap of smouldering ruins,
And that treacherous man Antenor brought to trial
For treason worse than has ever been known on earth,
Then noble Aeneas, with his clan of kindred knights,
Subdued the lands and at length became the lords
Of well nigh all of the wealth in the Western Isles.
Then swiftly, courageous Romulus swept into Rome,
His first concern to found, with fast-growing pride,
The noble city that now upholds his name.
Then Ticius with tents built interim towns in Tuscany,
And Langeberde laid out new homes in Lombardy.
Then the Channel was challenged from France by Felix Brutus,
Who boldly established Britain on her broad green slopes ---
In gladness long ago!
Though hatred, war and hell
Brought turmoil, tears and woe,
Their fortunes rose or fell
In endless ebb and flow.
The famous warrior founded Britain thus,
And bred a race of battle-loving men,
Who caused great torment in those troubled times.
More heart-enthralling things have happened there
Than anywhere else on earth since the ancient days.
But of the rulers reigning there, I have heard,
The noblest of all in honour was Arthur the king.
So now one great adventure will I make known,
Which many men will think a miracle ---
The most astounding tale of Arthur's time.
And if you'll listen to this legend a little while,
I'll tell it as I heard it told in town
In spoken song;
Inspired, I will expound
A story bold and strong,
With letters linked by sound,
As minstrels have made for long.
トロイの包囲攻撃が終わりをつげ,城都が崩壊し灰燼に帰してから,反逆を企てた騎士が裏切りの罪を問われて裁判にかけられたが,これは本当の話である.それは王子アエネーアスとその高貴な一族で,彼らはその後もろもろの大国を征服し,西方の諸島の財宝をほとんど手中にした支配者となった.偉大なロムルスはローマに逸速く侵入すると,まず手はじめに壮大にあの都市を建設し,自らの名前をとって命名したが,今でもその名で呼ばれている.ティシウスはトスカーナ地方に赴き住居を建て,ランゴバルドはロンバルディア地方に家屋をつくり,フェーリークス(幸福な)・ブルートゥスははるかフランス海峡を越えて多くの広大な丘陵にブリテンを創った,
喜び勇んで.
戦闘,災難,不思議なことが
おりおりそこで起り,
喜びと悲しみとがその後,たえず交互におとずれている.
この高貴な武将がブリテンを建国すると,剛胆な者どもが現われ,いくさを好み,幾度も紛争を引き起こした.この国ではその昔より,私が知っているどの国よりも世に驚くべきことがしばしば起っている.それはともかく,この国に居をかまえたすべてのブリテン王のうちで,アーサーこそ最も気高い王であったと聞いている.そこで奇妙な光景だと思うひともいるような世にも珍しい出来事,アーサーに関する話のうちでも途方もなく変った冒険談を語るつもりだ.みなさんがしばしの間,この物語詩に耳を傾けてくださるならば,いますぐに貴族の館で聞いたとおりに語りたいと思う,
言葉を使い.
それは勇壮な力強い物語に
書き留められて定着し,
正しい文字で結ばれて,
この国に長い間伝えられたもの.
・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.
・ Bantock, Gavin, trans. Sir Gawain & the Green Knight . Pearl: Two Middle-English Poems. Brimstone P, 2018.
・ 池上 忠弘(訳) 『「ガウェイン」詩人 サー・ガウェインと緑の騎士』 専修大学出版局,2009年.
2022-09-16 Fri
■ #4890. 中英語作品『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が登場するシーン [sggk][me_text][me_dialect][literature][popular_passage][voicy][heldio]
来たる11月25日に公開予定の映画『グリーン・ナイト』は,中英語テキスト Sir Gawain and the Green Knight (『ガウェイン卿と緑の騎士』;sggk)の本格的な翻案作品です.その字幕監修を,岡本広毅先生(立命館大学)が担当されています.その岡本先生と来週 Voicy 生放送で対談することになっていますので,ぜひお聴きください.詳しくは「#4885. 「英語ヴァナキュラー談義(岡本広毅&堀田隆一)」のお知らせ(9月20日(火)14:50--15:50 に Voicy 生放送)」 ([2022-09-11-1]) をご参照ください.
今回は生放送に先立って,SGGK の中英語原文を少し紹介しておきたいと思います.この作品は,Chaucer などと同時代の14世紀後半のものとされる写本 British Library MS Cotton Nero A.x にのみ現存する 2530行,101スタンザからなる作者不明の韻文テキストです.いわゆるアーサー王物というジャンルの作品です.同写本には,他に Pearl, Cleanness, Patience という作品が収められています.中英語の中西部方言で書かれています.各スタンザは,頭韻を踏む12--37の長詩行の後に,5行の "bob and wheel" と呼ばれる ababa 型の短い脚韻行が続くという形式になっています.
今回は,冒頭に近い ll. 130--50 より,緑の騎士が登場する印象的なシーンを覗いてみることにしましょう.Andrew and Waldron 版からの引用です.
Now wyl I of hor seruise say yow no more,
For vch wyȝe may wel wit no wont þat þer were.
Anoþer noyse ful newe neȝed biliue,
Þat þe lude myȝt haf leue liflode to cach;
For vneþe watz þe noyce not a whyle sesed,
And þe fyrst cource in þe court kyndely serued,
Þer hales in at þe halle dor an aghlich mayster,
On þe most on þe molde on mesure hyghe;
Fro þe swyre to þe swange so sware and so þik,
And his lyndes and hys lymes so longe and so grete,
Half-etayn in erde I hope þat he were,
Bot mon most I algate mynn hym to bene,
And þat þe myriest in his muckel þat myȝt ride;
For of bak and of brest al were his bodi sturne,
Both his wombe and his wast were worthily smale,
And alle his fetures folȝande in forme, þat he hade,
Ful clene.
For wonder of his hwe men hade,
Set in his semblaunt sene;
He ferde, as freke were fade,
And oueral enker grene.
Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の本日の放送「#473. 『ガウェイン卿と緑の騎士』より緑の騎士が登場するシーンを中英語原文で読み上げます」で,この中英語原文を読み上げていますので,合わせてお聴きください.
意味を確認するために Bantock の現代韻文訳より,同じ ll. 130--50 の箇所を引用します.
I've told you enough about the tables there
For you to guess how gorgeous that feast was.
But now another new uproar quickly approached,
That stirred Aurthur's spirit so strongly he started to eat.
For, just as the joyful music was fading away
And the first of the festive dishes was duly being served,
The doors crashed open wide with a terrible din
And a hideous giant charged boldly into the hall!
His body was strong and so broad from neck to waist,
And his legs and arms and thighs so long and thick,
He might have been half a giant and half a man,
But if a man, the biggest of all on this earth
That ever rode on horse; and most handsome too;
For though his breast and back were broad and stout,
His waist was slender and his belly lithe and slim,
And all of his features followed this twofold form ---
Both lust and lean!
By his colouring the court was amazed,
The most staggering sight they had seen,
For the body of that bold knight blazed
Head to foot with flaming bright green!
日本語訳としては,池上より (p. 9) 引用します.
さて食事のもてなしの様子をこれ以上語るのはもうやめておこう,何ひとつ欠けるものがなかったことは誰でもよく分ることだから.突然,また別の新たな音楽が聞こえてきたので,これでどうやら王も食事がとれるのではないかと思われた.そのトランペットの音が途絶え,最初の料理が宮廷内にきちんと出し終えたとたん,そこへ大広間の入り口から恐ろしい形相の騎士が勢いよく乗り込んできた.背丈がこの世で最も高い男であった.首から腰までひどく角張りずんぐりとし,腰部と手足は非常に長くてがっしりしており,この男は現世の半巨人ではないかと思ったが,しかしとにかく一番大柄な人間であり,馬に乗れる者の姿かっこうとしては最も端麗な人物だと言っておこう.彼の身体では背中と胸がものすごく逞しく,腹と腰はともに程よくほっそりして,身体の他の部分もすべて同じように姿かたちの均整がよくとれ,
格好がよかった.
彼の容貌にはっきり見えた
彼の色にみなびっくり仰天した.彼は大胆な(恐ろしい妖精の)戦士のように振舞い,
全身色あざやかな緑であった.
・ Andrew, Malcolm and Ronald Waldron, eds. The Poems of the Pearl Manuscript. 3rd ed. Exeter: U of Exeter P, 2002.
・ Bantock, Gavin, trans. Sir Gawain & the Green Knight . Pearl: Two Middle-English Poems. Brimstone P, 2018.
・ 池上 忠弘(訳) 『「ガウェイン」詩人 サー・ガウェインと緑の騎士』 専修大学出版局,2009年.
2022-05-27 Fri
■ #4778. 変わりゆく言葉に嘆いた詩人 Edmund Waller の "Of English Verse" [chaucer][language_change][hel_contents_50_2022][emode][literature]
khelf(慶應英語史フォーラム)による「英語史コンテンツ50」が終盤を迎えている.今回の hellog 記事は,先日5月20日にアップされた院生によるコンテンツ「どこでも通ずる英語…?」にあやかり,そこで引用されていたイングランドの詩人 Edmund Waller による詩 "Of English Verse" を紹介したい.
Waller (1606--87年)は17世紀イングランドを代表する詩人で,文学史的にはルネサンスの終わりと新古典主義時代の始まりの時期をつなぐ役割を果たした.Waller は32行の短い詩 "Of English Verse" のなかで,変わりゆく言葉(英語)の頼りなさやはかなさを嘆き,永遠に固定化されたラテン語やギリシア語への憧れを示している.一方,Chaucer を先輩詩人として引き合いに出しながら,詩人の言葉ははかなくとも,詩人の心は末代まで残るのだ,いや残って欲しいのだ,と痛切な願いを表現している.
Waller は,まさか1世紀ほど後にイングランドがフランスとの植民地争いを制して世界の覇権を握る糸口をつかみ,その1世紀後にはイギリス帝国が絶頂期を迎え,さらに1世紀後には英語が世界語として揺るぎない地位を築くなどとは想像もしていなかった.Waller はそこまでは予想できなかったわけだが,それだけにかえって現代の私たちがこの詩を読むと,言語(の地位)の変わりやすさ,頼りなさ,はかなさがひしひしと感じられてくる.
OF ENGLISH VERSE.
1 Poets may boast, as safely vain,
2 Their works shall with the world remain;
3 Both, bound together, live or die,
4 The verses and the prophecy.
5 But who can hope his lines should long
6 Last in a daily changing tongue?
7 While they are new, envy prevails;
8 And as that dies, our language fails.
9 When architects have done their part,
10 The matter may betray their art;
11 Time, if we use ill-chosen stone,
12 Soon brings a well-built palace down.
13 Poets that lasting marble seek,
14 Must carve in Latin, or in Greek;
15 We write in sand, our language grows,
16 And, like the tide, our work o'erflows.
17 Chaucer his sense can only boast;
18 The glory of his numbers lost!
19 Years have defaced his matchless strain;
20 And yet he did not sing in vain.
21 The beauties which adorned that age,
22 The shining subjects of his rage,
23 Hoping they should immortal prove,
24 Rewarded with success his love.
25 This was the generous poet's scope;
26 And all an English pen can hope,
27 To make the fair approve his flame,
28 That can so far extend their fame.
29 Verse, thus designed, has no ill fate,
30 If it arrive but at the date
31 Of fading beauty; if it prove
32 But as long-lived as present love.
・ Waller, Edmond. "Of English Verse". The Poems Of Edmund Waller. London: 1893. 197--98. Accessed through ProQuest on May 27, 2022.
2022-05-05 Thu
■ #4756. アングロサクソン時代の略年表 [timeline][anglo-saxon][oe][literature]
新学期の古英語の授業も少しずつ軌道に乗ってきた.時代背景を理解するために,この辺りでアングロサクソン時代の略年表を掲げたい.すでに「#2526. 古英語と中英語の文学史年表」 ([2016-03-27-1]),「#2871. 古英語期のスライド年表」 ([2017-03-07-1]),「#3193. 古英語期の主要な出来事の年表」 ([2018-01-23-1]) で類似の年表を掲げているが,バリエーションがあったほうがよいと考えているので今回は Godden and Lapidge (xii--xiii) からの略年表を再現する.
Chronological table of the Anglo-Saxon period
| from c. 400 | Germanic peoples settle in Britain |
| c. 540 | Gildas in De excidio Britanniae laments the effects of the Germanic settlements on the supine Britons |
| 597 | St Augustine arrives in Kent to convert the English |
| 616 | death of Æthelberht, king of Kent |
| c. 625 | ship-burial at Sutton Hoo (mound 1) |
| 633 | death of Edwin, king of Northumbria |
| 635 | Bishop Aidan established in Lindisfarne |
| 642 | death of Oswald, king of Northumbria |
| 664 | Synod of Whitby |
| 669 | Archbishop Theodore and Abbot Hadrian arrive in Canterbury |
| 674 | monastery of Monkwearmouth founded |
| 682 | monastery of Jarrow founded |
| 687 | death of St Cuthbert |
| 689 | death of Cædwalla, king of Wessex |
| 690 | death of Archbishop Theodore |
| c. 700 | 'Lindisfarne Gospels' written and decorated |
| 709 | deaths of Bishops Wilfrid and Aldhelm |
| 716--57 | Æthelbald king of Mercia |
| 731 | Bede completes his Ecclesiastical History |
| 735 | death of Bede |
| 754 | death of St Boniface, Anglo-Saxon missionary in Germany |
| 757--96 | Offa king of Mercia |
| 781 | Alcuin of York meets Charlemagne in Parma and thereafter leaves York for the Continent |
| 793 | Vikings attack Lindisfarne |
| 802--39 | Ecgberht king of Wessex |
| 804 | death of Alcuin |
| 839--56 | Æthelwulf king of Wessex |
| 869 | Vikings defeat and kill Edmund, king of East Anglia |
| 871--99 | Alfred the Great king of Wessex |
| 878 | Alfred defeats the Viking army at the battle of Edington, and the Vikings settle in East Anglia (879--80) |
| 899--924 | Edward the Elder king of Wessex |
| 924--39 | Athelstan king of Wessex and first king of All England |
| 937 | battle of Brunanburh: Athelstan defeats an alliance of Scots and Scandinavians |
| 957--75 | Edgar king of England |
| 859--88 | Dunstan archbishop at Canterbury |
| 963--84 | Æthelwold bishop at Winchester |
| 964 | secular clerics expelled from the Old Minster, Winchester, and replaced by monks |
| 971--92 | Oswald archbishop at York |
| 973 | King Edgar crowned at Bath |
| 978--1016 | Æthelred 'the Unready' king of England |
| 975--7 | Abbo of Fleury at Ramsey |
| 991 | battle of Maldon: the Vikings defeat an English army led by Byrhtnoth |
| c. 1010 | death of Ælfric, abbot of Eynsham |
| 1011 | Byrhtferth's Enchiridion |
| 1013 | the English submit to Swein, king of Denmark |
| 1016--35 | Cnut king of England |
| 1023 | death of Wulfstan, archbishop of York |
| 1042--66 | Edward the Confessor king of England |
| 1066 | battle of Hastings: the English army led by Harold is defeated by the Norman army led by William the Conqueror |
・ Godden, Malcolm and Michael Lapidge, eds. The Cambridge Companion to Old English Literature. Cambridge: CUP, 1986.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2021-12-08 Wed
■ #4608. 中英語の叙情詩の "I" [personal_pronoun][literature][me][genre]
昨日の記事「#4607. 中英語の叙情詩」 ([2021-12-07-1]) で,"Middle English lyric" というジャンルの特徴について見た.特徴の1つとして「"I" が "you" に語りかける」ことが挙げられていた.この点について,昨日も引用した Greentree (388--89) が次のように加えている.
The 'lyric I' who addresses the 'you' implied in Middle English lyrics is a general, typical figure, an 'I' without ego, who may make the reader a participant in the poem. Anonymity helps efface the poets of many medieval lyrics, removing distractions to focus attention on the poem itself. Aspects of style may suggest a particular poet, place or time of composition. Some political verses recount historical events, and some poets describe their situations, but a manuscript's time of compilation does not necessarily reveal the dates when its contents were written, and biographical details may be fictions. These factors can enhance or diminish the reader's appreciation of a work. Acrostics and other devices sometimes reveal a poet's name or the place of composition. However, the lack of details of a poet's life and state of mind spares the reader fruitless speculation, since it is both easier and more profitable to concentrate on the lyric 'I'.
中英語叙情詩の "I" は詩人本人を指示するというよりも,読み手・聞き手を取り込んで作品の中に同化させた1人称単数代名詞として機能している,という見方だ.これにより,詩人が誰かという問いは背景化し,詩の内容そのものに焦点が当てられることになる.作品への没入を誘う1人称単数代名詞の文体的用法とでも言おうか.
中英語叙情詩の特徴が少し分かり始めてきた.
・ Greentree, Rosemary. "Lyric." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 387--405.
2021-12-07 Tue
■ #4607. 中英語の叙情詩 [literature][me][genre]
目下,大学院の授業で Bennett and Smithers のアンソロジーより中英語の叙情詩 (Middle English lyrics) を読んでいる.最もよく知られているのは,輪唱の歌詞 Sumer is icumen in だろう(cf. 「#1438. Sumer is icumen in」 ([2013-04-04-1])).現代の歌い手による輪唱を生で聴いたことがあるが,調子と歌詞が明るくすがすがしい.輪唱だけに,頭の中でぐるぐる回ってしまい,口ずさまずにはいられない中毒性がある.
中英語の叙情詩といっても,話題としては世俗的なものもあれば宗教的なものまである.政治詩,恋愛詩,賛美歌を含めカバーする範囲は広い.Sumer is icumen in のように音楽に載せたものもあれば,そうでないものもある.形式も様々だ.基本的に短い詩が多いが,逆にいうと短い詩であれば "lyric" と呼んでしまえるのではないかという感がある.実際,このジャンルを定義づける要素は何かという問いに対して,端的に「短い詩である」という答えもあり得るようだ.Greentree (388) の "Characteristics of Lyrics" に関する説明を読んでみよう.
There are some constants in the genre. Ann S. Haskell notes a 'cluster of characteristics' including brevity, metrical pattern, rhyme scheme, theme and occasional hints of a plot. To John Burrow, the term 'usually means no more than a short poem', but he emphasizes 'the most characteristic axis of lyric poetry: the "I" addressing the "you", and distinguishes that 'I' from any other personal utterance, since the lyric 'I' 'speaks not for an individual but for a type' (Burrow 1982: 61). The voice of the lyric 'I' is always present, sounding many notes: laughing, weeping, expressing countless human feelings, praying, teaching or passing on scraps of knowledge.
このジャンルを定義づける試みがうまくいかないのは,そこでは相反するものが共存しているからである.むしろ,それこそが中英語の叙事詩の特徴なのかもしれない.このことを Greentree (387) が次のように表現している.
'Oh, to vex me, contraries meet in one'
Anyone who seeks the essence and boundaries of the medieval English lyric may find John Donne's line an apt expression of the task's pleasures and exasperations. The Middle English lyric attracts contraries of matter and manner, metre, diction and form. The slightest of structures may bear the weight of serious content with a paradox or exploration of holy mysteries in a form equally suited to celebration. Apparently artless forms may prove sophisticated and lavishly allusive. The disparate members of this genre vary from the glorious to the mundane . . . . Vexation comes from attempts to define the genre, to confine its members within a few descriptive sentences. Every statement can be questions, every adjective is ambiguous, every category has exceptions.
中英語の叙事詩は,そこに一定の傾向は見られるにせよ,かなり緩いジャンルととらえておいてよい.
・ Bennett, J. A. W. and G. V. Smithers, eds. Early Middle English Verse and Prose. 2nd ed. Oxford: OUP, 1968.
・ Greentree, Rosemary. "Lyric." A Companion to Medieval English Literature and Culture: c.1350--c.1500. Ed. Peter Brown. Malden, MA: Blackwell, 2007. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2009. 387--405.
・ Burrow, John. Medieval Writers and their Work: Middle English Literature and its Background 1100--1500. Oxford: OUP, 1982.
2021-10-12 Tue
■ #4551. 19世紀に Beowulf の価値が高騰した理由 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript][history][reformation][philology][linguistic_imperialism][oed]
「#4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」」 ([2021-10-02-1]) でみたように,Beowulf 写本とそのテキストは,"myth of the longevity of English" を創出し確立するのに貢献してきた.主に文献学的な根拠に基づいて,その制作時期を紀元700年頃と推定することにより,英語と英文学の歴史的時間幅がぐんと延びることになったからだ.しかも,文学的に格調の高い叙事詩とあっては,うってつけの宣伝となる.
Beowulf の価値が高騰し,この「神話」が醸成されたのは,19世紀だったことに注意が必要である.なぜこの時期だったのだろうか.なぜ,例えばアングロサクソン学が始まった16世紀などではなかったのだろうか.Watts (52) は,これが19世紀的な現象であることを次のように説明している.
As a whole the longevity of English myth, consisting of the ancient language myth and the unbroken tradition myth, was a nineteenth-century phenomenon that lasted almost till the end of the twentieth century. The need to establish a linguistic pedigree for English was an important discourse archive within the framework of the growth of the nation-state and the Age of Imperialism. In the face of competition from other European languages, particularly French, it was perhaps necessary to construct English as a Kultursprache, and one way to do this was to trace English to its earliest texts.
端的にいえば,イギリスは,イギリス帝国の威信を対外的に喧伝するために,その象徴である英語という言語が長い伝統を有することを,根拠をもって示す必要があった,ということだ.歴史的原則に立脚した OED の編纂も,この19世紀の文脈のなかでとらえる必要がある(cf. 「#3020. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (1)」 ([2017-08-03-1]),「#3021. 帝国主義の申し子としての比較言語学 (2)」 ([2017-08-04-1]),「#3376. 帝国主義の申し子としての英語文献学」 ([2018-07-25-1])).
16世紀には,さすがにまだそのような動機づけは存在していなかった.その代わりに16世紀のイングランドには別の関心事があった.それは,ヘンリー7世によって開かれたばかりのテューダー朝をいかに権威づけるか,そしてヘンリー8世によって設立された英国国教会をいかに正当化するか,ということだった.この目的のために,ノルマン朝より古いアングロサクソン時代に,キリスト教文典や法律が英語という土着語で書かれていたという歴史的事実が利用されることになった.テューダー朝はとりわけ宗教改革に揺さぶられていた時代であるから,宗教的なテキストの扱いには慎重だった.一方,Beowulf のような民族叙事詩のテキストには,相対的にいってさほどの関心が注がれなかったというわけだ.Watts (52) は次のように述べている.
The dominant discourse archive at this particular moment of conjunctural time [= the sixteenth century] was religious. It was the struggle to assert Protestantism after the break with the Church of Rome that determined the focus on religious, legal, constitutional and historical texts of the Anglo-Saxon era. The Counter-Reformation in the seventeenth century sustained this dominant discourse and relegated interest in the longevity of the language and the poetic value of texts like Beowulf till a much later period.
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2021-10-02 Sat
■ #4541. 焼失を免れた Beowulf 写本の「使い途」 [beowulf][oe][literature][language_myth][manuscript]
1731年10月23日,ウェストミンスターのアシュバーナム・ハウスが火事に見舞われた.そこに収納されていたコットン卿蔵書 (Cottonian Library) も焼けたが,辛くも焼失を免れた古写本のなかに古英語の叙事詩 Beowulf のテキストを収めた写本があった.これについて Watts (29) が次のように述べている.
The loss of Beowulf would have meant the loss of the greatest literary work and one of the most puzzling and enigmatic texts produced during the Anglo-Saxon period.
仮定法の文だが,裏を返せば英文学を代表する最も偉大な作品が奇跡的にも火事から救われたという趣旨の文である.英文学者や英語史学者ならずとも,ほとんどの人々が,この写本が消失を免れて本当によかったと思うだろう.
しかし,「言語の神話」の解体をもくろむ Watts の考えは異なる.焼失したほうがよかったと主張するわけでは決してないが,驚くことに次のように文章を続けるのだ.
But it would also have made one of the most powerful linguistic myths focusing on the English language, the myth of the longevity of English, immeasurably more difficult to construct. This is not because other Anglo-Saxon texts have not come down to us; it is, rather, because of the perceived literary and linguistic value of Beowulf. To construct the longevity myth one needs to locate such texts, and the further back in time they can be located, the "older" the language becomes and the greater is the "cultural" significance that can be associated with that language.
Watts の主張は,焼失を免れた Beowulf 写本は,英語に関する最も強力な神話,すなわち「英語長寿神話」を創出し,確立させるのに利用されてきたということだ.Beowulf 写本が生き残ったことにより「英語は歴史のある偉大な言語である」と言いやすくなったというわけだ.
現に Beowulf 写本が生き残ったのは偶然である.別の棚に保存されていたら焼失していたかもしれない.そして,もし焼けてしまっていたならば,英文学や英語はさほど歴史がないことになり,さほど偉大でもなくなるだろう.英文学や英語は別の「売り」を探さなければならなかったに違いない.
この見方は,英文学や英語が偉大かそうでないかは火事の及んだ範囲という偶然に依存しており,必然的に,あるいは本質的に偉大なわけではないという洞察につながる.これが,Watts が神話の解体によって行なおうとしていることなのだろう.
・ Watts, Richard J. Language Myths and the History of English. Oxford: OUP, 2011.
2021-05-04 Tue
■ #4390. 現存する古英詩の種類 --- なぞなぞも重要な1種 [oe][poetry][literature][manuscript][alliteration][anglo-saxon][oe_text][hel_education][khelf_hel_intro_2021]
古英語の詩 (Old English poetry) は,現存するテキストを合わせると3万行ほどのコーパスとなる古英語文学の重要な構成要素である.古英詩の「1行」は「半行+休止+半行」からなり,細かな韻律規則,とりわけゲルマン語的な頭韻 (alliteration) に特徴づけられる.
現存する古英詩の大半は以下の4つの写本に伝わっており,その他のものを含めた古英詩のほとんどが,校訂されて6巻からなる The Anglo-Saxon Poetic Records (=ASPR) に収められている.
・ The Bodleian manuscript Junius II (ASPR I): Genesis, Exodus, Daniel, Christ and Stan などを所収.
・ The Vercelli Book, capitolare CXVII (ASPR II): The Dream of the Room,Andreas と Elene の聖人伝などを所収.
・ The Exeter Book (ASPR III) (ASPR III): 宗教詩,Guthlac と Juliana の聖人伝,説教詩,The Wanderer, The Seafarer, The Ruin, The Wife's Lament, The Husband's Message, riddles (なぞなぞ)などを所収.
・ The British Library Cotton Vitellius A.xv (ASPR IV): Judith, Beowulf などを所収.
Mitchell (75) によれば,古英詩を主題で分類すると次の8種類が区別される.
1. Poems treating Heroic Subjects
Beowulf. Deor. The Battle of Finnsburgh. Waldere. Widsith.
2. Historic Poems
The Battle of Brunanburh. The Battle of Maldon.
3. Biblical Paraphrases and Reworkings of Biblical Subjects
The Metrical Psalms. The poems of the Junius MS; note especially Genesis B and Exodus. Christ. Judith.
4. Lives of the Saints
Andreas. Elene. Guthlac. Juliana.
5. Other Religious Poems
Note especially The Dream of the Rood and the allegorical poems --- The Phoenix, The Panther, and The Whale.
6. Short Elegies and Lyrics
The Wife's Lament. The Husband's Message. The Ruin. The Wanderer. The Seafarer. Wulf and Eadwacer. Deor might be included here as well as under 1 above.
7. Riddles and Gnomic Verse
8. Miscellaneous
Charms. The Runic Poem. The Riming Poem.
この中では目立たない位置づけながらも,7 に "Riddles" (なぞなぞ)ということば遊び (word_play) が含まれていることに注目したい.古今東西の言語文化において,なぞなぞは常に人気がある.古英語にもそのような言葉遊びがあった.古英語版のなぞなぞは内容としてはおよそラテン語のモデルに基づいているとされるが,古英語の独特のリズム感と,あえて勘違いさせるようなきわどい言葉使いの妙を一度味わうと,なかなか忘れられない.
10世紀後半の写本である The Exeter Book に収録されている "Anglo-Saxon Riddles" は,95のなぞなぞからなる.その1つを古英語原文で覗いてみたいと思うが,古英語に不慣れな多くの方々にとって原文そのものを示されても厳しいだろう.そこで,昨日「英語史導入企画2021」のために大学院生より公表されたコンテンツ「古英語解釈教室―なぞなぞで入門する古英語読解」をお薦めしたい.事実上,古英詩の入門講義というべき内容になっている.
・ Mitchell, Bruce. An Invitation to Old English and Anglo-Saxon England. Blackwell: Malden, MA, 1995.
2021-03-29 Mon
■ #4354. 擬人法の典型例 [personification][metaphor][rhetoric][stylistics][literature][toponymy]
昨日の記事「#4353. 擬人法」 ([2021-03-28-1]) に引き続き,擬人法 (personification) について.昨日からもう少し調べてみているが,擬人法の言語学的な扱いはやはり少ないようだ.あくまで修辞学や詩学の領域にとどまっている.今回は『大修館英語学事典』 (844) より,詩語の1特徴としての擬人法の解説を引用する.伝統的で典型的な例が挙げられているので,参照用に便利.
擬人法
擬人法 (personification) も好んで用いられた技法である.言うまでもなく人間でないものを人間(時に神)にたとえて表現するものである.
a) 自然現象を神話の神の名で表現する
Zephyr (西風),Phoebus (太陽),Cynthia (月),Diana (月),Apollo (太陽),Neptune (海),Boreas (北風),Hesper (宵の明星),など.
b) 抽象名詞の擬人化
たとえば 'ambitious people' という時 'Ambition' にように表現するもので,一種の寓意的表現である.
Gladness danc'd along the sky---Thompson, Epithalanium (喜びは空を踊りながら進んで行った) / Let not Ambition mock their useful toils---Gray, Elegy Written in a Country Church-Yard (野心をして彼らの有益な労役を侮らせるなかれ) / O stretch thy reign, fair Peace---Pope, Windsor Forest (うるわしの平和よ,汝の領土を広げよ).
c) 地名または一般の事物の擬人化
That Thame's glory to the stars shall rise!---Pope, Windsor Forest (テムズの栄光よ星まで届け) / Thy forest, Windsor!---Pope, ibid. (汝の森,ウインザーよ) / And weary waves, withdraw[n]ing from the Fight, die lull'd and panting on the silent Shore (疲れた波は戦いより退きて,物言わぬ岸の上でなだめられ,あえぎながらその身を横たえる).
・ 松浪 有,池上 嘉彦,今井 邦彦(編) 『大修館英語学事典』 大修館書店,1983年.
2021-03-28 Sun
■ #4353. 擬人法 [personification][metaphor][rhetoric][stylistics][terminology][literature][gender]
擬人法 (personification) は,文学的・修辞的な技法として知られているが,専門用語というよりは一般用語としても用いられるほどによく知られた用語・概念でもある.広く認知されているがゆえに,学術的に扱おうとするとなかなか難しい種類の話題かもしれない.
とりわけ言語学的に扱おうとする場合,どのようなアプローチが可能なのだろうか.この問題について本格的に考えたこともないので,まず取っ掛かりとして,種々の英語学辞典に当たってみた.最初は『英語学要語辞典』から.
personification 〔体〕(擬人化,擬人法) Fair science frowned not on his humble birth.---T. Gray, Elegy (美しき学問は彼の卑しい素性をいといはしなかった)のように,抽象概念や無生物に人間と同様の性質を与える修辞上の技巧.隠喩の一種で,英文学においては古英詩(特に謎詩)で用いられ始め,中世の道徳劇,寓意詩にもみられる.小説でもその用法は散見され,ゴシック小説では表現上の重要な特性とされている.なお,<+有生>など名詞の素性および選択規則という変形理論の適用により,擬人法を統一的に記述・説明することが可能である.
次に『新英語学辞典』より.
personification 〔修〕(擬人化,擬人法)
無生物や抽象概念を生物扱いしたり,感情など人間特有の性質を持つものとして表現する修辞技巧.擬人化は prosopropeia とも呼ばれ,隠喩 (METAPHOR) の一種で詩で古くから用いられた.Leech (1969) は 'an angry sky' や 'graves yawned' のように,無生物に生物の属性を付与するものを the animistic metaphor, 'this friendly river' や 'laughing valeys' のように,人間以外のものに人間特有の性質を付与するものを the humanizing [anthropomorphic] metaphor と名づけている.I. A. Richards (1929) が指摘しているように,人間以外の生物や無生物に対して抱く感情や思考は,人間相互の感情や思考と共通するもので,従って日常の言語ではもっぱら人間について用いる形容詞・動詞・代名詞を人間以外のものに適用するのはきわめて自然と言えよう.
擬人化は中世の寓意詩にまで遡ることができるが,その伝統を受けついだ Milton は "all things smil'd, With fragrance and with joy my heart oreflowd"---Paradise Lost 8: 265--66 のように,この修辞法を好んで用いた.擬古典主義の時代に入ると,Thomas Parnell, Richard Savage, Edward Young など,18世紀の詩人の言語の大きな特色となり,ますます装飾的な性格を帯びるようになった.しかし,やがてロマン派が台頭し,'the very language of men' を詩の言語たらしめることを標榜した Wordsworth は,慣習的な擬人化を 'a mechanical device of style' として斥けた (Preface to Lyrical Ballads, 1798).
このように,擬人化は詩の言語の伝統的手法であって,散文における比喩表現は直喩 (SIMILE) の形式をとるのがふつうであるが,詩的な散文では効果的に用いられることがある.例えば,Thomas Hardy が Egdon Heath を描写している次のパラグラフでは,観察者の存在を暗示する appeared, seemed, could be imagined 以外の動詞は,闇夜の荒野を擬人化して描き出している: The place became full of watchful intentness now; for when other things sank brooding to sleep the heath appeared slowly to awake and listen. Every night its Titanic form seemed to await something; but it had waited thus, unmoved, during so many centuries, through the crises of so many things, that it could only be imagined to await one last crisis---the final overthrow.---The Return of the Native. Bk. I, Ch. I.
英語における擬人法は,上記の通り,およそ修辞学的・文学史的な観点から話題にされてきたものであり,言語学的・意味論的なアプローチは稀薄だったように思われる.そもそも後者のアプローチとしては,どのようなものがあるのだろうか.探ってみる必要がありそうだ.関連して,「#2191. レトリックのまとめ」 ([2015-04-27-1]) の「擬人法」を参照.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語学要語辞典』 研究社,2002年.
・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.
2021-03-27 Sat
■ #4352. Skelton の口語的詩行 [literature][emode][rhyme][alliteration][onomatopoeia][3sp][skelton]
教会を揶揄する風刺詩を書いた John Skelton (1460?--1529) は,文学史上,押韻するが不規則な短行を用いた詩型 "Skeltonics" で知られる(ただし文学的に評価されるようになったのは20世紀になってからのこと).歯に衣着せぬ物言いながらも,Henry VIII の家庭教師となり宮廷でも地位を得た.主作品の1つに Colyn Cloute (1522) がある.当時の実力者 Thomas Wolsey 卿を軽口をたいて風刺するリズムが小気味よい.近代英語期最初期の生き生きとした口語的リズムを伝えるテキストとしても興味深い.
Bergs and Brinton (303) が,初期近代英語に関するハンドブックのなかで当時の「言葉遊び」 (language play) の1例として,Skelton のテキストを挙げている.
His hed is so fat
He wotteth neuer what
Nor wherof he speketh
He cryeth and he creketh
He pryethh and he peketh
He chydes and he chatters
He prates and he patters
He clytters and he clatters
He medles and he smatters
He gloses and he flatters
Or yf he speake playne
Than he lacketh brayn (1545 Skelton, Colyn Cloute A2v)
詩的技巧としては,脚韻 (rhyme) はもちろんのこと,頭韻 (alliteration) も目立つし,オノマトペ (onomatopoeia) に由来すると考えられる動詞も多用されている.3単現の語尾として従来の -eth と新興の -s が共存しているのも,当時の英語の変化と変異を念頭におくと興味深い.とりわけ調子が乗ってきた辺りで口語的な -s が連発するのも,味わい深い.詩である以上に言葉遊びであり,言葉遊びである以上に当時の生きた口語を映し出すものとして読むことができる.
・ Bergs, Alexander and Laurel J. Brinton, eds. The History of English: Early Modern English. Berlin/Boston: Gruyter, 2017.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow