2019-06-25 Tue
■ #3711. 印欧祖語とゲルマン祖語にさかのぼる基本英単語のサンプル [indo-european][germanic][lexicology][etymology]
『英語語源辞典』によると,印欧語比較言語学の成果により,1,000から2,000ほどの印欧語根が想定されている.そのおよそ半数が現代英語の語彙にも反映されているといわれるが,主に基本語彙として受け継がれているものを列挙しよう(寺澤,p. 1656;カッコは借用語を表わす).
| 身体 | arm, brow, ear, eye, foot, heart, knee, lip, nail, navel, tooth |
| 家族 | father, mother, brother, sister, son, daughter, nephew, widow |
| ?????? | beaver, cow, ewe, goat, goose, hare, hart, hound, mouse, sow, wolf; bee, wasp; louse, nit; crane, ern(e), raven, starling; fish, (lax) |
| 罎???? | alder, ash, asp(en), beech, birch, fir, hazel, tree, withy |
| 飲食物 | bean, mead, salt, water, (wine) |
| 天体・自然現象 | moon, star, sun; snow |
| 数詞 | one, two, ..., ten, hundred |
| 代名詞 | I, me, thou, ye, it, that, who, what |
| 動詞 | be, bear, come, do, eat, know, lie, murmur, ride, seek, sew, sing, stand, weave |
| 形容詞 | full, light, middle, naked, new, sweet, young |
| その他 | acre, ax(e), furrow, month, name, night, summer, wheel, word, work, year, yoke |
一方,ゲルマン祖語にさかのぼる,ゲルマン語に特有の基本英単語を挙げてみよう(寺澤,p. 1657).眺めてみると,印欧祖語の時代に比べ「社会生活の進歩,環境の変化がうかがわれ」「とくに,農耕・牧畜関係の語の充実とともに,航海・漁業関係の語が豊富であり,戦争・宗教関係の語も目立つ」(寺澤,p. 1657)ことが確認できる.
| 身体 | bone, hand, toe |
| 穀物・食物 | berry, broth, knead, loaf, wheat |
| 動物 | bear, lamb, sheep, †hengest (G Hangst), roe, seal, weasel |
| 鳥類 | dove, hawk, hen, rave, stork |
| 海洋 | cliff, east, west, north, south, ebb, sail, sea, ship, steer, keel, haven, sound, strand, swim, net, tackle, stem |
| 戦争 | bow, helm, shield, sword, weapon |
| 絎???? | god, ghost, heaven, hell, holy, soul, weird, werewolf |
| 住居 | bed, bench, hall |
| 社会 | atheling, earl, king, knight, lord, lady, knave, wife, borough |
| 経済 | buy, ware, worth |
| その他 | winter, rain, ground steel, tin |
「基本語彙」を巡る議論については,(基本語彙) の各記事を参照.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2019-06-12 Wed
■ #3698. 語源学習法のすゝめ [etymology][lexicology][academic_word_list][asacul][notice]
過去2日間の記事で,語源を活用した学習法を紹介してきた(「#3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」」 ([2019-06-10-1]) と「#3697. 印欧語根 *spek- に由来する英単語を探る」 ([2019-06-11-1]) ).中田氏による近著『英単語学習の科学』の第11章「語源で覚える英単語」でも「語源学習法」の効用が説かれている.
英単語は出現頻度によって,(1) 高頻度語,(2) 中頻度語,(3) 低頻度語の3つのグループに分類できます.中頻度語と低頻度語は,リーディングやリスニングにおける出現頻度があまり高くないため,文脈から自然に習得することは困難であり,意図的に学習することが欠かせません.中頻度語と低頻度語を覚えるには,その多く(約3分の2)がラテン語・ギリシア語起源であるため「語源学習法」が有効です.また,学術分野で頻度が高い英単語を集めた Academic Word List (Coxhead, 2000) の約90%もラテン語・ギリシア語起源なので,語源学習法が役に立ちます.(73)
特に中級以上の英語学習者にとって,語源学習法が有効である理由が説得力をもって示されている.中田は,章末において語源学習法のポイントを次のようにまとめている.
・ 英単語をパーツに分解し,パーツの意味を組み立ててその単語の意味を理解する学習法を「語源学習法」と呼ぶ.語源学習法は特に,中頻度語・低頻度語および学術的な英単語の学習に効果的である.
・ 語源学習法には,(1) 単語の長期的な記憶保持が可能になる,(2) 未知語の意味を推測するヒントになる,(3) 単語の体系的・効率的な学習が可能になる,といった利点がある.
・ 既知語やカタカナ語を手がかりにして,数多くの語のパーツを効率的に学習できる.特に,「最も役に立つ25の語のパーツ」は重要.
中田はさらに別の箇所で「無味乾燥になりがちな単語学習を,興味深い発見の連続に変えてくれる」 (75--76) とも述べている.
さらにもう2点ほど地味な利点を付け加えておきたい.1つは,語種の判別ができるようになることだ.主としてラテン語・ギリシア語からなる「パーツ」を多数学ぶことによって,初見の単語でも,ラテン語・ギリシア語のみならずフランス語,スペイン語,イタリア語などを含めたロマンス系諸語からの借用語であるのか,あるいはゲルマン系の本来語であるのか,ある程度判別できるようになる.借用語か本来語かという違いは,語感の形式・略式の差異ともおよそ連動するし,強勢位置に関する規則とも関係してくるので,語種を大雑把にでも判別できることには実用的な意味がある.
もう1つは,借用元の言語も当然ながら学びやすくなるということだ.とりわけ第2外国語としてフランス語なりスペイン語なりのロマンス系諸語を学んでいるのであれば,英語学習と合わせて一石二鳥の成果を得られる.
最近では,語源学習法に基づいた英単語集として,清水健二・すずきひろし(著)『英単語の語源図鑑』(かんき出版,2018年)が広く読まれているようだ.なお,私もこの7月より朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源」と題するシリーズ講座を開始する予定(cf. 「#3687. 講座「英語の歴史と語源」が始まります」 ([2019-06-01-1])).こちらはボキャビルそのものを主たる目標としているわけではないものの,その知識は当然ながらボキャビルのためにも役立つはずである.
なお,上の第1引用にある Academic Word List については,「#612. Academic Word List」 ([2010-12-30-1]) と「#613. Academic Word List に含まれる本来語の割合」 ([2010-12-31-1]) も参照.
・ 中田 達也 『英単語学習の科学』 研究社,2019年.
2019-06-11 Tue
■ #3697. 印欧語根 *spek- に由来する英単語を探る [etymology][indo-european][latin][greek][metathesis][word_family][lexicology]
昨日の記事「#3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」」 ([2019-06-10-1]) で取り上げたなかでも最上位に挙げられている spec(t) という連結形 (combining_form) について,今回はさらに詳しくみてみよう.
この連結形は印欧語根 *spek- にさかのぼる.『英語語源辞典』の巻末にある「印欧語根表」より,この項を引用しよう.
spek- to observe. 《Gmc》[その他] espionage, spy. 《L》 aspect, auspice, conspicuous, despicable, despise, especial, expect, frontispiece, haruspex, inspect, perspective, prospect, respect, respite, species, specimen, specious, spectacle, speculate, suspect. 《Gk》 bishop, episcopal, horoscope, sceptic, scope, -scope, -scopy, telescope.
また,語源の取り扱いの詳しい The American Heritage Dictionary of the English Language の巻末には,"Indo-European Roots" なる小辞典が付随している.この小辞典から spek- の項目を再現すると,次のようになる.
spek- To observe. Oldest form *spek̂-, becoming *spek- in centum languages.
▲ Derivatives include espionage, spectrum, despise, suspect, despicable, bishop, and telescope.
I. Basic form *spek-. 1a. ESPY, SPY, from Old French espier, to watch; b. ESPIONAGE, from Old Italian spione, spy, from Germanic derivative *speh-ōn-, watcher. Both a and b from Germanic *spehōn. 2. Suffixed form *spek-yo-, SPECIMEN, SPECTACLE, SPECTRUM, SPECULATE, SPECULUM, SPICE; ASPECT, CIRCUMSPECT, CONSPICUOUS, DESPISE, EXPECT, FRONTISPIECE, INSPECT, INTROSPECT, PERSPECTIVE, PERSPICACIOUS, PROSPECT, RESPECT, RESPITE, RETROSPECT, SPIEGELEISEN, SUSPECT, TRANSPICUOUS, from Latin specere, to look at. 3. SPECIES, SPECIOUS; ESPECIAL, from Latin speciēs, a seeing, sight, form. 4. Suffixed form *spek-s, "he who sees," in Latin compounds. a. Latin haruspex . . . ; b. Latin auspex . . . . 5. Suffixed form *spek-ā-. DESPICABLE, from Latin (denominative) dēspicārī, to despise, look down on (dē-), down . . .). 6. Suffixed metathetical form *skep-yo-. SKEPTIC, from Greek skeptesthai, to examine, consider.
II. Extended o-grade form *spoko-. SCOPE, -SCOPE, -SCOPY; BISHOP, EPISCOPAL, HOROSCOPE, TELESCOPE, from metathesized Greek skopos, on who watches, also object of attention, goal, and its denominative skopein (< *skop-eyo-), to see. . . .
2つの辞典を紹介したが,語源を活用した(超)上級者向け英語ボキャビルのためのレファレンスとしてどうぞ.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
・ The American Heritage Dictionary of the English Language. 4th ed. Boston: Houghton Mifflin, 2006.
2019-06-10 Mon
■ #3696. ボキャビルのための「最も役に立つ25の語のパーツ」 [elt][latin][greek][etymology][prefix][combining_form][lexicology]
中田(著)『英単語学習の科学』に,先行研究に基づいた「最も役に立つ25の語のパーツ」が提示されている (76--77) .これは,3000?1万語レベルの英単語を分析した結果,とりわけ多くの語に含まれるパーツを取り出したものである.パーツのほとんどが,ラテン語やギリシア語の接頭字 (prefix) や連結形 (combining_form) である.
| 語のパーツとその意味 | 具体例 |
| spec(t) = 見る | spectacle(見せ物),spectator(観客),inspect(検査する),perspective(視点),retrospect(回顧) |
| posit, pos = 置く | impose(負わせる,課す),opposite(反対の),dispose(配置する,処分する),compose(校正する,作る),expose(さらす) |
| vers, vert = 回す | versus(対),adverse(反対の,不利な),diverse(多様な),divert(転換する),extrovert(外交的な) |
| ven(t) = 来る | convention(大会,しきたり,慣習),prevent(妨げる,予防する),avenue(通り),revenue(歳入),venue(場所) |
| ceive/ceipt, cept = とる(こと) | accept(受け入れる,容認する),exception(例外),concept(概念),perceive(知覚する),receipt(レシート,受け取ること) |
| super- = 越えて | superb(すばらしい),supervise(感得する),superior(上級の),superintendent(監督者),supernatural(超自然の,神秘的な) |
| nam, nom, nym = 名前 | surname(苗字),nominate(指名する),denomination(命名,単位),anonymous(匿名の),synonym(同義語) |
| sens, sent = 感じる | sensible(分別のある),sensitive(敏感な),sensor(センサー),sensation(感覚),consent(同意,同意する) |
| sta(n), stat = 立つ | stable(安定した),status(地位),distant(離れた),circumstance(状況),obstacle(障害) |
| mis, mit = 送る | permit(許可する),transmit(送る),submit(提出する),emit(放射する),missile(ミサイル) |
| med(i), mid(i) = 真ん中 | intermediate(中級の),Mediterranean(地中海),mediocre(並みの),mediate(仲裁する),middle(中央,中間の) |
| pre, pris = つかむ | prison(刑務所),enterprise(事業),comprise(構成する),apprehend(捕らえる,理解する),predatory(捕食性の,食い物にする) |
| dictate, dict = 言う | dictate(書き取らせる,命じる),dedicate(捧げる),predict(予言する),contradict(否定する,矛盾する),verdict(評決) |
| ces(s) = 行く | access(アクセス,接近),excess(超過),recess(休憩),ancestor(先祖),predecessor(前任者) |
| form = 形 | formal(形式的な),transform(変形する),uniform(同形の,制服),format(形式),conform(一致する) |
| tract = 引く | extract(抜粋,抜粋する),distract(気をそらす),abstract(要約,抽象的な),subtract(引く),tractor(トラクター,牽引車) |
| graph = 書く | telegraph(電報),biography(伝記),autograph(サイン),graph(グラフ),geography(地理) |
| gen = 生む | genuine(本物の),gene(遺伝子),genius(天才),indigenous(土着の,固有の),ingenuity(工夫) |
| duce, duct = 導く | conduct(導く),produce(生み出す),reduce(減らす),induce(引き起こす,誘発する),seduce(誘惑する) |
| voca, vok = 声 | advocate(主張する,唱道者),vocabulary(語彙),vocal(声の,ボーカル),invoke(祈る),equivocal(あいまいな) |
| cis, cid = 切る | precise(正確な),excise(削除する),scissors(はさみ),suicide(自殺),pesticide(殺虫剤) |
| pla = 平らな | plain(明白な,平原),plane(平面,平らな),plate(皿),plateau(高原,高原状態) |
| sec, sequ = 後に続く | consequence(結果),sequence(連続),subsequent(その次の),consecutive(連続した),sequel(続編) |
| for(t) = 強い | fortress(要塞),effort(努力),enforce(実施する,強いる),reinforce(強化する),forte(長所) |
| vis = 見る | visible(目に見える),envisage(心に描く),revise(改訂する),visual(視覚の,映像),vision(視力,ビジョン) |
本ブログでも,必ずしもボキャビルを目的とした記事ではないが,接頭辞,接尾辞,連結形について多々取り上げてきた.prefix, suffix, combining_form などの記事をご覧ください.
・ 中田 達也 『英単語学習の科学』 研究社,2019年.
2019-06-01 Sat
■ #3687. 講座「英語の歴史と語源」が始まります [asacul][notice][etymology]
この夏,朝日カルチャーセンター新宿教室にて「英語の歴史と語源」と題するシリーズ講座が始まります.全12回ほどの予定となるシリーズで,1年ほどかけてゆっくりペースで進めていく企画です.完全なスケジュールは決まっていませんが,最初の3回分については確定しており,受付も開始しています.以下をご覧ください
・ 7月13日(土)15:15?18:30 「英語の歴史と語源・1 インドヨーロッパ祖語の故郷」
・ 7月27日(土)15:15?18:30 「英語の歴史と語源・2 ケルトの島」
・ 9月7日(土)15:15?18:30 「英語の歴史と語源・3 ローマ帝国の植民地」
まずは初回の7月13日の案内を,以下に掲載しておきます.
シリーズ「英語の歴史と語源」では,英語という言語がたどってきた波乱に富んだ紆余曲折の歴史を,世界史的な大事件と関連づけながら追っていきます.言語の歴史には文法や発音の歴史も含まれますが,本シリーズでとりわけ注目するのは語源,つまり単語の起源です.著名な事件と単語の起源とを結びつけながら,主にイギリスを舞台とする英語の歴史物語を,全12 回にわたり,つむいでいきます.
1 インドヨーロッパ祖語の故郷(7月13日)
シリーズの初回では,英語の究極の祖先というべきインドヨーロッパ祖語に焦点を当てます.英語はもとよりフランス語,スペイン語,ドイツ語,ロシア語,ヒンディー語などを含む巨大なインドヨーロッパ語族は,紀元前4千年頃の南ロシアのステップ地方に起源をもつとされます.実際,私たちの知る多くの英単語の語源が,この太古の時代にまでさかのぼります.6千年という時間を超えて受け継がれてきた数々の単語について,その由来をひもといて行きましょう.
これまでも英語史関連の講座をいくつか開いてきましたが,今回はとりわけ単語・語源に注目して,英語の歴史を辿っていく予定です.「シリーズ」とはいえ,単発での参加ももちろん可能ですので,ご関心のある方は是非どうぞ.シリーズの全体像につていは,こちらのチラシもご覧ください.
2019-05-02 Thu
■ #3657. mountain, mount, Mt. [etymology][latin][french][loan_word][abbreviation]
Mt. Fuji is the highest mountain in Japan. には,Mt. (= mount) と mountain という「山」を意味する2つの単語が現われる.固有名詞とともに現われる場合には mount (表記上はたいてい省略して Mt.)を用い,一般名詞としては mountain を用いる.
古英語で普通に「山」を意味する語は本来語の beorg (ドイツ語 Berg)だった.しかし,すでに古英語期から,ラテン語で「山」を意味する mōns, mont- が借用語 munt として入っており,用いられることはあった.さらに中英語期になると,同語源で古フランス語の語形 mont にも強められるかたちで通用されるようになった(MED の mount n.(1) を参照).現代英語では,一般名詞としては文語・古語としての響きを有し,上記のように Mt. として固有名詞の一部として用いられるのが普通である.
一方,mountain は13世紀後半に初出する.語源は先にもあげたラテン語 mōns, mont- の形容詞形ともいうべきもので,俗ラテン語の *montānea(m) (regiōnem) (= "mountainous region") から古フランス語形 montagne を経て,英語に mountain(e n. として入ってきたものである.現在までに最も普通の「山」を表わす一般名詞として発展してきた.(考えてみると,mountainous という形容詞は,語源的には形容詞の,そのまた形容詞ということになっておもしろい.)
実は Mt. という省略表記の使用の歴史について知りたいと思い,いくつかの歴史辞書でこれらの語を引いてみたのだが,ほとんど情報がない.別の資料にあたって調べてみる必要がありそうだ.ちなみに,関連するかもしれないと思って調べてみた Mr や Mrs などの表記については,およそ初期近代に遡るという(cf. 「#895. Miss は何の省略か?」 ([2011-10-09-1])).
2019-03-28 Thu
■ #3622. latter の形態を説明する古英語・中英語の "Pre-Cluster Shortening" [consonant][vowel][shortening][adjective][comparison][sound_change][etymology][shocc]
「#3616. 語幹母音短化タイプの比較級に由来する latter, last, utter」 ([2019-03-22-1]) で取り上げたように,中英語では,形容詞の比較級において原級では長い語幹母音が短化するケースがあった.これを詳しく理解するには,古英語および中英語で生じた "Pre-Cluster Shortening" なる音変化の理解が欠かせない.
"Pre-Cluster Shortening" とは,特定の子音群の前で,本来の長母音が短母音へと短化する過程である.音韻論的には,音節が「重く」なりすぎるのを避けるための一般的な方略と解釈される.原理としては,feed, keep, meet, sleep などの長い語幹母音をもつ動詞に歯音を含む過去(分詞)接辞を加えると fed, kept, met, slept と短母音化するのと同一である.あらためて形容詞についていえば,語幹に長母音をもつ原級に対して,子音で始まる古英語の比較級接尾辞 -ra (中英語では -er へ発展)を付した比較級の形態が,短母音を示すようになった例のことを話題にしている.Lass (102) によれば,
Originally long-stemmed adjectives with gemination in the comparative and superlative showing Pre-Cluster Shortening: great 'great'/gretter, similarly reed 'red', whit 'white', hoot 'hot', late. (The old short-vowel comparative of late has been lexicalised as a separate form, later, with new analogical later/latest.)
長母音に子音群が後続すると短母音化する "Pre-Cluster Shortening" は,ありふれた音変化の1種と考えられ,実際に英語音韻史では異なる時代に異なる環境で生じている.Lass (71) によれば,古英語で生じたものは以下の通り(gospel については「#2173. gospel から d が脱落した時期」 ([2015-04-09-1]) を参照).
About the seventh century . . . long vowels shortened before /CC/ if another consonant followed, either in the coda or the onset of the next syllable, as in bræ̆mblas 'branbles' < */bræːmblɑs/, gŏdspel 'gospel' < */goːdspel/. This removes one class of superheavy syllables.
この古英語の音変化は3子音連続の前位置で生じたものだが,初期中英語で生じたバージョンでは2子音連続の前位置で生じている.今回取り上げている形容詞語幹の長短の交替に関与するのは,この初期中英語期のものである (Lass 72--73) .
Long vowels shortened before sequences of only two consonants . . . , and --- variably--- certain ones like /st/ that were typically ambisyllabic . . . . So shortening in kĕpte 'kept' < cēpte (inf. cēpan), mĕtte met < mētte'' (inf. mētan), brēst 'breast' < breŏst 'breast' < brēost. Shortening failed in the same environment in priest < prēost; in words like this it may well be the reflex of an inflected form like prēostas (nom./acc.pl.) that has survived, i.e. one where the /st/ could be interpreted as onset of the second syllable; the same holds for beast, feast from French. This shortening accounts for the 'dissociation' between present and past vowels in a large class of weak verbs, like those mentioned earlier and dream/dreamt, leave/left, lose/lost, etc. (The modern forms are even more different from each other due to later changes in both long and short vowels that added qualitative dissociation to that in length: ME /keːpən/ ? /keptə/, now /kiːp/ ? /kɛpt/, etc.)
latter (および last) は,この初期中英語の音変化による出力が,しぶとく現代まで生き残った事例として銘記されるべきものである.
・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." The Cambridge History of the English Language. Vol. 2. Cambridge: CUP, 1992. 23--154.
2019-03-22 Fri
■ #3616. 語幹母音短化タイプの比較級に由来する latter, last, utter [etymology][comparison][vowel][adjective]
初期近代英語までは,形容詞の語幹母音を短くした上で接尾辞 -er を付すタイプの比較級形成法があった.たとえば great の比較級が gretter となったり,white が whitter となったりするような例だ.しかし,語幹母音が長く保たれる形態も併存していたので,大多数の形容詞においては,やがてそちらが優勢となり,語幹母音短化タイプの比較級形態は存在感を薄めていった.
ところが,それでも生き延びたものがいた.late の語幹母音短化タイプの比較級である latter と最上級の last だ.共時的には late の比較級・最上級とはみなされておらず,別の語彙項目と受け取られているが,歴史的には密接に関わっている.なお,母音を長く保った形態は各々 later, latest となり,現在の標準的な late の比較級・最上級となっている.
同様に,out の語幹母音短化タイプの比較級形態が現在の utter に連なっている.この場合も,utter は out と関連しているという共時的な感覚はなくなっており,独立した別の語となっている.だからこそ,utterly のように,さらなる派生接尾辞を付けることができる.一方,長い母音を保ったタイプは outer となったが,これはこれでやはり out の比較級形態としては意識されず,別の形容詞として受け取られているのがおもしろい.
latter と later,あるいは utter と outer のように,同機能を果たす変異形にすぎなかったものが,互いに役割を分化させ,独立した語へと発展していくという事例は少なくない.比較される例について「#55. through の語源」 ([2009-06-22-1]),「#86. one の発音」 ([2009-07-22-1]),「#693. as, so, also」 ([2011-03-21-1]) を参照.
以上,Lass (156) を参照して執筆した.
・ Lass, Roger. "Phonology and Morphology." 1476--1776. Vol. 3 of The Cambridge History of the English Language. Ed. Roger Lass. Cambridge: CUP, 1999. 56--186.
2019-02-16 Sat
■ #3582. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (2) [french][latin][loan_word][lexicology][etymology][borrowing]
昨日の記事 ([2019-02-15-1]) で,標題に関する Ellenberger の批評を紹介した.中英語の学問語 (= "mots savants") のソース言語に関する伝統的な見解は,不当にフランス語寄りではないかという問題提起である.では,Ellenberger 自身は,この問題についてどのような姿勢を取るのがふさわしいと考えているのだろうか.論文の終わりに,4箇条を掲げている (149--50) .
1. Words are borrowed not once and for all but many times and from many sources.
2. A Latin word borrowed into either of Anglo-French or English would be given an ending prescribed by Anglo-Norman scribal tradition.
3. Words could be borrowed from Latin or French depending on what spheres of society the borrowers moved in. Clerics would be more likely to borrow from Latin than would laics.
4. As the medieval libraries of England contained mainly Latin books and school curricula concentrated on Latin texts, learned words borrowed into French from written Latin sources would be more likely also to have entered English from those same sources than through French.
英語史では,中英語の借用語の話題といえばフランス語がさらっていく.しかし,学問語に関する限り,中英語期のラテン語からの借用は,一般に思われているよりもずっと豊富だったことに注意したい.関連して,「#120. 意外と多かった中英語期のラテン借用語」 ([2009-08-25-1]),「#1211. 中英語のラテン借用語の一覧」 ([2012-08-20-1]),「#2961. ルネサンスではなく中世こそがラテン語かぶれの時代?」 ([2017-06-05-1]),「#292. aureate diction」 ([2010-02-13-1]) を参照.
・ Ellenberger, Bengt. "On Middle English Mots Savants." Studia Neophilologica 46.1 (1974): 142--50.
2019-02-15 Fri
■ #3581. 中英語期のフランス借用語,ラテン借用語,"mots savants" (1) [french][latin][loan_word][lexicology][etymology][borrowing]
「#653. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別」 ([2011-02-09-1]),「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1]) で論じてきたように,とりわけ中英語期にラテン語・フランス語から入ってきた借用語は,いずれの言語をソースとするのか判然としないケースが多い.ラテン語なのか,ラテン語化したフランス語なのか,フランス語なのか,フランス語化したラテン語なのか,等々.
OED を中心とする,この問題に対する伝統的な対処法として,「フランス語形が文証されればフランス語を借用元言語とし,そうでない場合に限ってラテン語をソースとみなす」ことが一般的だった.もう少し強くいってしまえば,判然としない場合には,フランス語をソースとみなすのをデフォルトとしようというスタンスだ.Ellenberger (142) は,この立場を紹介しながら,それに対する批判的な見解を示している.
. . . the 'learned words' . . . could have been taken either from French or directly from Latin. The difficulty of determining the exact source has been recognized with varying hesitation. Foremost in Francophilia stands the Oxford English Dictionary, which regards as borrowed from Latin only those words that have not been recorded in French; in addition, French forms are often postulated. To the author's knowledge, no scholar before Marchand has openly criticized this procedure.
Ellenberger が引用中で同じ意見の仲間として引き合いに出している H. Marchand は,The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation (2nd ed. München, 1969) の p. 238 で次のように述べている (Ellenberger 142fn) .
It would . . . be an erroneous standpoint to be always looking for the Latin original or the French pattern of a word (which the OED often does). The existence of an actual pattern is irrelevant so long as, potentially, the coinage is Latin. . . . the principle of assuming an actual original is wrong.
借用元の形態が文証されるからフランス語であるとか,そうでないからラテン語であるとか,そのような議論はおそらく成り立たないだろうということだ.Ellenberger (148) 自身の言葉でいえば,次のような議論となる.
The clerks knew about adaptation and suffixation; they were used to latinizing English names, and sometimes words, and we may trust them to have been able to anglicize a Latin word in the same way as they or the French would have Frenchified it. To request a French intermediary for each and every word is to deny the knowledge of Latin in England. To regard an English word as a loan from French because a corresponding French loan is recorded a few years earlier in an ever so obscure source is to fall a victim to the perilous argument of post hoc, ergo propter hoc; as far as we know, no annual lists of new French words circulated among English clerks. Whether a learned word occurs first in French or English is simply a matter of chance, need, and literary activity.
中英語期の学問語 (= "mots savants") のソースがフランス語なのかラテン語なのかという問題を議論することよりも大事なことは,むしろそれが一般のフランス借用語とは異なるレベルに属することを再認識することだろう.Ellenberger (150) が,論文の最後で次のように述べている通りである.
A far more useful distinction than that between learned words that might have and those that could not have been mediated by French is that between Romance popular and learned words. Middle English mots savants are latinisms and should be treated as such.
なお,Ellenberger では,OED が上記のように槍玉に挙げられているが,現在編纂が進んでいるOED3 の編者の1人である Durkin は,この問題に柔軟な態度を示していることを付け加えておきたい.「#848. 中英語におけるフランス借用語とラテン借用語の区別 (2)」 ([2011-08-23-1]) を参照.
・ Ellenberger, Bengt. "On Middle English Mots Savants." Studia Neophilologica 46.1 (1974): 142--50.
2019-01-11 Fri
■ #3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識 [hel_education][etymology][toc][lexicology][historiography]
英語史や英語語源学が英語学習に貢献できる最大のものは,語源を利用した英単語の暗記である.ラテン系の接頭辞や接尾辞など,語源的な知識を用いて英語語彙を増やす方法は昔から試みられている.最近では『英単語の語源図鑑』が注目されているようだ.
この学習用の効果は私も疑わないが,この方向でさらにステップを目指すのであれば,ぜひ英語史概説の修得を視野に入れたい.そんなときに役立つのが,下宮ほか編の『スタンダード英語語源辞典』の付録である.語彙学習にカスタマイズされた簡易的な英語史の概説として,おおいに奨められる.pp. 611--41 という40頁ほどの(内容の割には)コンパクトな解説だが,よく書けており,これを読んでおくのとおかないのとではスタートラインが違うと思う.以下に,章節の見出しを再現し,雰囲気をつかんでもらおう.語彙の観点に立った英語史入門と理解して差支えない.
1. 英語の語源
1.1. 英語の語源を知るための予備知識
英語の歴史と同系の諸言語
1.2 歴史言語学 (historical linguistics) のキーワード
二重語
ウムラウトとアプラウト
1.3 単語の構造
派生語,複合語
混種語
1.4 音韻変化 (phonetic change)
同化
異化
音位転換
1.5 同源であるかどうかの見分け方
形が似ていて語源が異なる場合
形が異なっても同源の場合
1.6 印欧語根の例
1.7 英語・ドイツ語・フランス語の関係
ドイツ語とは文法・基本単語が共通
フランス語とは語彙が共通
2. 印欧祖語からゲルマン語へ
2.1 サンスクリットの発見と印欧祖語
比較言語学の成立
印欧語族の発見
2.2 印欧祖語と印欧語族
祖語の再建
印欧語族の系統
2.3 ゲルマン民族とゲルマン語
ゲルマン祖語
イギリス人の祖先
ゲルマン祖語の分化
2.4 印欧祖語からゲルマン語へ
グリムの法則
ヴェルナーの法則
ゲルマン語のアクセントの特徴
ゲルマン語の分化の進展
3. 英語の歴史 --- 古英語・中英語を中心にして ---
3.1 Stratford-upon-Avon について
英語の歴史の原点を見る
ブリテン島の原住民
ケルト語起源の語
ラテン語起源の語
本来の英語 --- ゲルマン起源の語 ---
3.2 英語の歴史の時代区分
3つの時代区分
古英語と中英語
古英語の時代
中英語の時代
3.3 外来語について
ラテン語からの借用
古ノルド語からの借用
フランス語からの借用
3.4 古英語ミニ解説
聖書の古英語訳
ドイツ語と似た文法上の性
名詞・形容詞・動詞の変化
屈折の実例
4. ラテン語・ギリシア語ミニマム
4.1 ヨーロッパの二大文明語
語彙の60%はギリシア・ラテン起源
4.2 ラテン語
名詞
動詞
文例
4.3 ギリシア語
豊富な変化形
名詞
動詞
用例
なお,筆者も別の観点から「語彙学習のための英語史」を試みたことがある(「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1]) を参照).
・ 下宮 忠雄・金子 貞雄・家村 睦夫(編) 『スタンダード英語語源辞典』 大修館,1989年.
2019-01-04 Fri
■ #3539. tip (心付け)の語源 [etymology][folk_etymology]
tip (心付け)の語源は不詳である.シップリー (628) は,次のように記述している.
tip [típ] 軽打,先端,チップ
この語には意味がいくつかあり,その語源も曖昧な点が多いが,「軽打」という意味では tap (軽くたたく),「先端」という意味では top (頂き)に関係があるものと思われる.
良いサービスに対して支払われるお金の「チップ」は,他の言語ではより特定的であり,例えばフランス語 pourboire (チップ)は飲物に対するものである.英語の tip は,ロンドンのコーヒーハウスでの18世紀初めの習慣からできたという説がある.その店には箱が置いてあって,急いでいる人はすぐさま注意を引くために,そこに少額硬貨を落とすようになっており,箱には to Insure Promptness (迅速さを確保するために)というラベルが貼られていた.そのイニシャルを取って T.I.P. となったという.
ユーカーズ (140) も,コーヒーハウスに引っかけた同趣旨の語源説を紹介している.
「チップ」という言葉とその習慣も,コーヒー・ハウスで始まったとされる.コーヒー・ハウスには,真鍮の箱が置かれ,ウェイターのためにコインを入れるようになっていた.その箱には「迅速さをお約束するために To Insure Promptness」と書かれていて,この頭文字をとり「TIP」という語ができたといわれる.
しかし,この語源説は怪しいようで,OED をはじめとした権威ある主要な語源記述では,この説は触れられてすらいない.語源の世界も,専門家向けと一般向けのレファレンスでは,そもそも交わっていないところがあり,語源学の難しさを感じさせる.
・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.
・ ウィリアム H. ユーカーズ 著,山内 秀文 訳 『ALL ABOUT COFFEE コーヒーのすべて』 KADOKAWA,2017年.
2018-11-02 Fri
■ #3476. 曜日名の語源 [etymology][greek][latin][mythology][calendar]
英語の月名の語源について,「#2910. 月名の由来」 ([2017-04-15-1]),あるいはより詳しく「#3229. 2月,February,如月」 ([2018-02-28-1]) とそのリンク先で取り上げてきた.一方,曜日名については「#2595. 英語の曜日名にみられるローマ名の「借用」の仕方」 ([2016-06-04-1]) や「#1261. Wednesday の発音,綴字,語源」 ([2012-10-09-1]) で取り上げてきたが,今回は参照に便利なようにシップリーの語源辞典 (674) より一覧を掲げたい.
Sunday (日曜日) ---the day of the sun (太陽の日)
Monday (月曜日) ---the day of the moon (月の日)
Tuesday (火曜日) ---the day of Tiw (ティウの日).Tiw はゲルマン人の戦争の神であり,ローマの Martis dies (マルスの日)の代わりとして使われるようになった.ちなみにフランス語では mardi である.Tiw はラテン語 deus (神)やギリシア語 Zeus と同族語である.
Wednesday (水曜日) ---Woden's day (ウォーディンの日).Woden は北欧の神々の王である.
Thursday (木曜日) ---Thor's day (トールの日).Thor は雷神 (thunderer) である.かつては同義語として Thunderday があった.
Friday (金曜日) ---the day of Friya or Frigga (フリヤもしくはフリッガの日).フリヤは北欧の愛の女神であり,フリッガはウォーディンの妻である.
Saturday (土曜日) ---the day of Saturn (サターンの日).サターンはローマの農業の神である.
week 自体は古英語 wicu, wucu (週)に遡り,これは wīce (奉仕,義務)から派生している.さらに遡れば,ゲルマン祖語の *wikōn "turning, succession" に由来する.時間を司る7曜の神々の「奉仕・義務の交替順序」ということらしい.OED によると,
It has been argued that the Germanic base underlying the attested words had an earlier sense referring to changes of duty, which was then applied to the sequence of deities governing the weekly cycle, and finally transferred to the week itself. Such an earlier sense may be reflected by Old Icelandic vika unit of distance travelled at sea (perhaps with reference to the periodical change of rowing teams, although this cannot be independently substantiated), Gothic wiko order in which something happens (in an isolated example in Luke 1:8 with reference to the allocation of religious duties, translating ancient Greek τάξις order, arrangement . . .), and also Old English wīce office, duty, function . . . .
「週」という単位や概念の起源は印欧語族にはなく東洋のものだが,ユダヤ人を介してギリシア人,ローマ人に伝わり,そこからキリスト教の伝播とともにヨーロッパに広がった.
・ ジョーゼフ T. シップリー 著,梅田 修・眞方 忠道・穴吹 章子 訳 『シップリー英語語源辞典』 大修館,2009年.
2018-10-26 Fri
■ #3469. cosmos, cosmopolitan, cosmetics [etymology][greek][indo-european][ormulum]
cosmos は,秩序整然とした体系としての「宇宙」を意味する語である.ギリシア語で秩序を表わす kósmos に由来し,これ自体は印欧祖語の語根 *kes- (秩序づける)に遡るのではないかとされる.「宇宙」の語義は,Pythagoras 派の哲学者が宇宙を完全な秩序体とみなしていたことによる.
英語では以下のように12世紀後半の Ormulum に最も早い単発の例がみられる.Orm の綴字から判断すると,cosmōs のように第2音節の母音は長母音だったと思われる.
?c1200 Orm.(Jun 1) 17559: Werelld iss nemmnedd Cossmos, Swa summ þe Grickess kiþenn.
?c1200 Orm.(Jun 1) 17592: Tohh is þeȝȝre baþre shrud þurrh Cossmos wel bitacnedd.
Ormulum 以降,この単語はしばらく用いられず,17世紀半ばになってようやく現われてくる.これは近代英語期の再借用とみなしてよいだろう.植物の「コスモス」の語義は,その秩序だった優美さから名付けられたもので,1813年に初出している.
関連語として,cosmopolitan, cosmopolite (世界主義者)がある.ギリシア語の cosmo- (宇宙,秩序)+ politēs (市民)に由来し,初出は17世紀前半,本格的な使用は19世紀半ばからである.語感については「#3308. Cosmopolitan Vocabulary という表現について」 ([2018-05-18-1]) で取り上げたので参照されたい.
そして,cosmetic (化粧,美容)も関連語である.ギリシア語の形容詞形 kosmēticós (秩序だった)がフランス語 cosmétique を経由して17世紀に英語に入ったものである.初例は1605年の Bacon からで「美容術」の語義で用いられた.「化粧」の語義としては1650年のものが最初である.
cosmetic は,現在の英単語としては「化粧の;美容の」に加え「うわべだけの」というネガティヴな含意で用いられることもあり「虚飾」感がつきまとう.しかし,原義を考えれば本来の化粧とは秩序だった端正な美しさを目指すものだったのだろう.化粧もやりすぎると,やはりギリシア起源の対義語である chaos (混沌,無秩序)(< Gk kháos "gulf, abyss, chaos") となってしまうので要注意です.
2018-10-18 Thu
■ #3461. 警官 bobby [prime_minister][etymology][personal_name][eponym][slang][history]
昨日の記事「#3460. 紅茶ブランド Earl Grey」 ([2018-10-17-1]) で,イギリス首相に由来する(といわれる)紅茶の名前について触れた.同じくイギリス首相に由来する,もう1つの表現を紹介しよう.イギリスで警官のことを俗語で bobby と呼ぶが,これは首都警察の編成に尽力した首相・内務大臣を歴任した Sir Robert Peel (1788--1850) の愛称,Bobby に由来するといわれる.

Peel は,19世紀前半,四半世紀にわたってイギリス政治を牽引した政界の重鎮である.初期の業績としては,Metropolitan Police Act を1828年に通過させ,翌1829年,首都警察を設置したことが挙げられる.その後,bobby が警官の意の俗語となっていった.いつ頃からの用法かは正確にはわからないが,OED の初例は1844年のものである.
1844 Sessions' Paper June 341 I heard her say..'a bobby'..it was a signal to let them know a policeman was coming.
首都警察の設置と同じ1829年には「カトリック教徒解放法案」も成立させており,著しい敏腕振りを発揮している.Peel は党利党略ではなく国家の利益を第一に考えた(この点では,昨日取り上げた Earl Grey も同じだった).Peel はもともと地主貴族階級の砦であった「穀物法」を切り崩すことを目論んでいたが,1845年のアイルランドのジャガイモ飢饉を機に,穀物法廃止に踏み切る決断を下した.そして,翌年に廃止を実現した.19世紀の大改革を次々と成し遂げた首相だった.
なお,同じく俗語の「警官」として実に peeler という単語もあるので付け加えておきたい.
2018-10-17 Wed
■ #3460. 紅茶ブランド Earl Grey [prime_minister][etymology][personal_name][eponym][history]
一般には Earl Grey といえば,紅茶の高級ブランドが想起されるかもしれない.Twinings にも同名の製品があるが,もともとは Jackson's 社製である.柑橘類の一種ベルガモット (bergamot) で香りづけをした癖のある風味で知られる.名前の由来は,しばしば 2nd Earl Grey こと Charles Grey (1764--1845) が,中国から帰任したときに持ち帰った中国茶のブレンド法にあるとされるが,この説の真偽のほどは定かではない.何しろ Earl Grey's mixture として現われる初例は,Grey が亡くなってから数十年も経った1884年のことなのだ.OED によるレポート Early Grey: The results of the OED Appeal on Earl Grey tea では,問題の紅茶ブランドの名前の由来について突っ込んだ記述があるので必読.
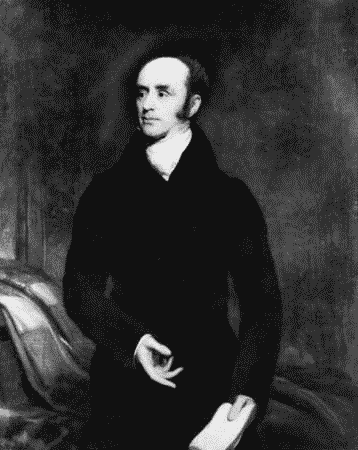
Earl Grey は,1830--34年に首相を務めたホイッグの政治家である.Eton と Cambridge で教育を受けた典型的な貴族で,22歳のときに国会議員となり,若いときから浮き名を流していた.しかし,Grey は George IV が王妃キャロラインを離縁させようと画策した際に王妃をかばい続けたことから,その後も王に嫌われ続け,おりしも自由トーリ主義の潮流にあって,政治的には長らく干されることになった.しかし,George IV が1830年に亡くなると,Grey に復活の機会が訪れた.新しく即位した William IV は Grey の古くからの親友だったからだ.ホイッグが政権を取り戻し,首相となった Grey (任期1830--34年)は,悲願だった選挙法改正を実現すべく邁進した.1831年,Grey の提示した改正法案は貴族院で否決されてしまったが,それを受けて民衆暴動が勃発.翌1832年,再び法案が議会にかけられ,紆余曲折を経ながらも結果として通過した.世にいう the First Reform Bill である.これによって年価値10ポンド以上の家屋・店舗・事務所などを所有する者や借家人にも選挙権が与えられることになり,有権者の数はイギリス全体で50万人から81万人にまで増えた.特にスコットランドでは4500人から5万5000人へと急増したという.
19世紀の大衆民主政治の立役者と香り豊かなミルクティーとの間に,実際のところどのような関係があるのか,真実を知りたいところである.
2018-09-19 Wed
■ #3432. イギリス議会の起源ともいうべきアングロ・サクソンの witenagemot [etymology][oe][anglo-saxon][parliament][history][monarch][compound]
ウェセックスのアルフレッド大王の孫に当たるアゼルスタン(Athelstan; 在位 924--40年)は,ウェセックス王にとどまらず,事実上の最初のイングランド王と呼ぶべき存在である.彼は937年のブルナンブルフの戦いで軍功をあげたほか,アルフレッド大王が作った州制を発展させ,法典を編纂し,銀ペニー貨の鋳造権を獲得し,諸外国と同盟するなどの業績を重ねた.君塚 (20--21) によれば,
しかしアゼルスタンにとって最大の功績は,のちの国王評議会や議会の起源ともいうべき機関を設置したことであろう.アゼルスタン以降の国王は「立法」に深く携わるようになり,そのために定期的に有力者たちとの会議を開くようになった.王が司教や伯(エアルダーマン)らに相談して立法を行う慣習は,ノーサンブリアのエドウィン王の時代(六二〇年代)やウェセックスのイネ王の時代(六九〇年代)にも見られたが,アゼルスタンはこれをさらに大規模なものとし,キリスト教の重要な行事であるキリスト降誕祭(一二月),復活祭(四月頃),聖霊降臨祭(五月頃)に定期的に開催するようになった.
これが「賢人会議」(ウィテナイェモート)と呼ばれるものである.イングランド各地から代表者を集めた会議で,カンタベリーとヨークの大司教,多くの司教や大修道院長たち,伯(エアルダーマン)らの有力貴族,豪族(セイン)らが出席するようになり,地方的な問題よりも,イングランド全体に関わる外交や防衛問題,さらには律法や司法に関わる問題を主に協議した.そしてこの会議に集まるようになった有力者たちにとって大切な役割となったのが,先王の死から次王の継承までの間に問題が生じないよう調整するという,まさに王位継承規範に関わる事柄であった.
賢人会議は,前期のキリスト教行事とは関わりのない時期にも召集されたが,復活祭の会議では春の軍事遠征に関わる相談も頻繁に行なわれた.また時代が下るとともに,出席者の席次(序列)も徐々に形成されるようになっていった.
アゼルスタンの設置した「賢人会議」は,古英語では witenagemōt と言い表した.これは witena + gemōt の2語からなる複合語であり,前者 witena は「賢人;評議員」を意味する名詞 wita の複数属格形である.この名詞は,現代英語の名詞 wit (cf. 古英語動詞 witan 「知る」)や形容詞 wise と語源的に関連している.
後者 gemōt は「会議」を意味する名詞だが,これ自体は接頭辞 ge- と名詞 mōt に分解される.ge- は集合を表わす接頭辞で,中英語以降に弱化し消失していったが,yclept, yclad, alike, among, enough, either, handicraft, handiwork などの母音に痕跡を残す.mōt は,語源的に meet (会う)と関係しており,現代では moot という語形で「議論の余地のある」を意味する形容詞として用いられている.
したがって,witenagemōt の意味はまさに「賢人たちが集合する会議」である.なお,現代英語での歴史用語としての発音は /ˈwɪtnəgəˌmoʊt/ となる.
ノルマン征服以降の議会 (parliament) については,「#2334. 英語の復権と議会の発展」 ([2015-09-17-1]) と「#2335. parliament」 ([2015-09-18-1]) を参照.また,アングロサクソン王朝の系図と年表について,「#2620. アングロサクソン王朝の系図」 ([2016-06-29-1]) と「#2547. 歴代イングランド君主と統治年代の一覧」 ([2016-04-17-1]) をどうぞ.
・ 君塚 直隆 『物語 イギリスの歴史(上下巻)』 中央公論新社〈中公新書〉,2015年.
2018-08-22 Wed
■ #3404. 講座「英語のエッセンスはことわざに学べ」のお知らせ [notice][etymology][proverb][hel_education][asacul][link][rhetoric]
9月8日(土)の15:00?18:15に,朝日カルチャーセンター新宿教室にて講座「英語のエッセンスはことわざに学べ」を開講します.知る人ぞ知る,ことわざは英語表現の醍醐味を味わうのにうってつけの素材なのです.以下の趣旨でお話しする予定です.
どの文化においても,ことわざは人生の機微を巧みに表現するものとして,古くから人々に言いならわされてきました.英語文化においても例外ではなく,古英語期よりことわざが尊ばれ,ことわざ集が編まれてきました.現代に伝わる英語のことわざを学ぶことにより,英語文化で培われてきた人生の知恵を味わえるばかりではなく,英語そのものの深い理解に達することができることは,あまり気づかれていません.ことわざの英語には,太古より存続してきた英語特有の韻律があり,古英語や中英語に起源をもつ英語らしい文法・語法が息づいています.
例えば,「塵も積もれば山となる」に対応する Many a little makes a mickle. は,古英語に典型的な頭韻という詩法と強弱音節の繰り返しという韻律が見事に調和した,言語的にも優れたことわざです.「地獄の沙汰も金次第」に相当する Money makes a mare to go. では,使役の make にもかかわらず to 不定詞が用いられており,現代の文法からは逸脱しているように思われますが,ここにも韻律上の効果を認めることができます.
本講座の前半では,千年以上にわたる英語のことわざの歴史を具体例とともにひもとき,後半では現代まで受け継がれてきた英語のことわざに用いられている様々な言語的な技法を読み解くことにより,現代に残る数々のことわざをこれまで以上に楽しむことを目指します.
英語史の概要はある程度知っているけれども,その知識の骨組みに具体的に肉付けしていこうとすれば,古英語や中英語の原文を読んでいく作業が避けられません.とはいうものの,多くの英語学習者にとって,外国語の古文を読み解くなどということは,あまりに敷居が高いと思われるのではないでしょうか.そこでよい材料となるのが,ことわざです.ことわざには,しばしば古い言葉遣いが残っています.そのようなことわざを題材に,古い音韻,形態,統語,語彙,意味,語法,方言などをつまみ食いつつ,英語史を学ぼうという趣旨です.英語の語彙増強や文法理解にも役立ちますし,英語史の枠をはみ出して,英語学,そして言語学一般の話題への導入にもなります.
もちろん,ことわざの内容自体もおおいに味わう予定です.どうぞお楽しみに.
本ブログでも,時々ことわざについて取り上げてきたので,以下の記事をご覧下さい.
・ 「#564. Many a little makes a mickle」 ([2010-11-12-1])
・ 「#780. ベジタリアンの meat」 ([2011-06-16-1])
・ 「#910. 語の定義がなぜ難しいか」 (1)」 ([2011-10-24-1])
・ 「#948. Be it never so humble, there's no place like home.」 (1)」 ([2011-12-01-1])
・ 「#955. 完璧な語呂合わせの2項イディオム」 ([2011-12-08-1])
・ 「#970. Money makes the mare to go」 ([2011-12-23-1])
・ 「#978. Money makes the mare to go」 (2)」 ([2011-12-31-1])
・ 「#2248. 不定人称代名詞としての you」 ([2015-06-23-1])
・ 「#2395. フランス語からの句の借用」 ([2015-11-17-1])
・ 「#2691. 英語の諺の受容の歴史」 ([2016-09-08-1])
・ 「#3319. Handsome is as handsome does」 ([2018-05-29-1])
・ 「#3320. 英語の諺の分類」 ([2018-05-30-1])
・ 「#3321. 英語の諺の起源,生成,新陳代謝」 ([2018-05-31-1])
・ 「#3322. Many a mickle makes a muckle」 ([2018-06-01-1])
・ 「#3336. 日本語の諺に用いられている語種」 ([2018-06-15-1])
2018-08-19 Sun
■ #3401. 英語語彙史の方法論上の問題 [methodology][dictionary][oed][htoed][philology][lexicography][lexicology][semantics][etymology]
昨日の記事「#3400. 英語の中核語彙に借用語がどれだけ入り込んでいるか?」 ([2018-08-18-1]) で取り上げた Durkin の論文では,英語語彙史の実証的調査は,OED と HTOED という2大ツールを使ってですら大きな困難を伴うとして,方法論上の問題が論じられている.結論部 (405--06) に,諸問題が要領よくまとまっているので引用する.
One of the most striking and well-known features of lexical data is its extreme variability: as the familiar dictum has it 'chaque mot a son histoire', and accounting for the varied histories of individual words demands classificatory frameworks that are flexible, nonetheless consistent in their approach to similar items. Awareness is perhaps less widespread that the data about word histories presented in historical dictionaries and other resources are rarely 'set in stone': sometimes certain details of a word's history, for instance the details of a coinage, may leave little or no room for doubt, but more typically what is reported in historical dictionaries is based on analysis of the evidence available at time of publication of the dictionary entry, and may well be subject to review if and when further evidence comes to light. First dates of attestation are particularly subject to change, as new evidence becomes available, and as the dating of existing evidence is reconsidered. In particular, the increased availability of electronic text databases in recent years has swollen the flow of new data to a torrent. The increased availability of data should also not blind us to the fact that the earliest attestation locatable in the surviving written texts may well be significantly later than the actual date of first use, and (especially for periods, varieties, or registers for which written evidence is more scarce) may actually lag behind the date at which a word or meaning had already become well established within particular communities of speakers. Additionally, considering the complexities of dating material from the Middle English period . . . highlights the extent to which there may often be genuine uncertainty about the best date to assign to the evidence that we do have, which dictionaries endeavour to convey to their readers by the citation styles adopted. Issues of this sort are grist to the mill of anyone specializing in the history of the lexicon: they mean that the task of drawing broad conclusions about lexical history involves wrestling with a great deal of messy data, but the messiness of the data in itself tells us important things both about the nature of the lexicon and about our limited ability to reconstruct earlier stages of lexical history.
語源情報は常に流動的であること,初出年は常に更新にさらされていること,初出年代は口語などにおける真の初使用年代よりも遅れている可能性があること,典拠となっている文献の成立年代も変わり得ること等々.ここに指摘されている証拠 (evidence) を巡る方法論上の諸問題は,英語語彙史ならずとも一般に文献学の研究を行なう際に常に意識しておくべきものばかりである.OED3 の編者の1人である Durkin が,辞書は(OED ですら!)研究上の万能なツールではあり得ないと説いていることの意義は大きい.
・ Durkin, Philip. "The OED and HTOED as Tools in Practical Research: A Test Case Examining the Impact of Loanwords in Areas of the Core Lexicon." The Cambridge Handbook of English Historical Linguistics. Ed. Merja Kytö and Päivi Pahta. Cambridge: CUP, 2016. 390--407.
2018-07-30 Mon
■ #3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」 [slide][etymology][hel_education][link][asacul][lexicology]
先日7月21日(土)に,朝日カルチャーセンター新宿教室の講座「歴史から学ぶ英単語の語源」を開きました.熱心にご参加いただき,ありがとうございました.講座で用いたスライド資料をこちらに置いておきます.
今回の狙いは以下の3点でした.
・ 英語の歴史をたどりながら英語語彙の発展を概説し
・ 単語における発音・綴字・意味の変化の一般的なパターンについて述べ
・ 語源辞典や英語辞典の語源欄を読み解く方法を示します.
語源と一口に言っても,何をどこから話し始めるべきか迷いました.結果として,英語語彙史を軸とする総花的な内容とはなりましたが,あまりに抽象的にならないよう単語の具体例は絶やさないように構成しました.
以下,スライドのページごとにリンクを張っておきます.各スライドは,ブログ記事へのリンク集にもなっています.
1. 講座『歴史から学ぶ英単語の語源』
2. Q. 次の英単語と起源の言語とを組み合わせてください.
3. 英語語彙の規模と種類の豊富さ
4. 本講座のねらい
5. 目次
6. 1.1 イントロダクション:語源(学)とは?
7. Every word has its own history.
8. 語源学の妖しさ・怪しさ
9. 民間(通俗)語源の役割
10. まとめ (1.1)
11. 1.2 英語語彙史の概略
12. 印欧語族 (The Indo-European Family)
13. 英語語彙史の概略 (##37,126,45)
14. 現代の英語語彙にみられる歴史の遺産
15. 現代の新語形成
16. 日英語彙史比較 (#1526)
17. 語源で世界一周 (#756)
18. まとめ (1.2)
19. 1.3 語の変化の一般的なパターン:発音
20. 語の変化の一般的なパターン:綴字
21. 語の変化の一般的なパターン:意味 (##473,1953,2252)
22. Q. 以下は意味変化を経たゆえに意味不明となっている英文です.下線を引いた単語のもとの意味を想像できますか? (#1954)
23. まとめ (1.3)
24. 2.1 語源辞典で語誌を読み解く
25. 2.2 語源辞典で発音と綴字の変化を読み解く
26. 2.3 語源辞典で意味の発展を読み解く
27. まとめ
28. 参考文献
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow