2025-11-25 Tue
■ #6056. 英語史研究と英語教育の接点を求めて --- 長崎県上五島にて [notice][hee][hel_education][lexicology][cosmopolitan_vocabulary][elt][lexical_stratification][vocabulary]
先日,長崎県の五島列島に位置する新上五島町の小・中・高の英語教員を対象とした研修会にて,お話しする機会をいただきました.私自身は目下海外滞在中ということで,Zoom でつないでのリモート研修会となりましたが,画面越しの交流を通じて,主催の先生をはじめとする参加された先生方お一人お一人の英語教育への熱意が伝わってきて,大変実り多い時間となりました.
研修会のテーマは「『英語語源ハンドブック』で学ぶ英語語彙史と授業への応用」でした.私の研究分野である英語史,とりわけ語彙史の知見を,小・中・高の英語授業でいかに活かせるか,という問題について,『英語語源ハンドブック』の記述を参照しつつ,具体的な単語に注目してアイディアを出してみました.研修会後半のディスカッションでは,参加された先生方からも具体的な発展案などのアイディアやコメントもいただきました.結果として,英語史研究と英語教育が交差する貴重な機会となったと感じています.
研修会では,特に英語語彙の世界性 (cosmopolitan_vocabulary) に注目しました.英語は語彙でみるかぎり決して "pure" な言語ではなく,歴史的に他言語から語彙を大量に借用してきた "hybrid" な言語です.その最たる例が,ノルマン征服 (norman_conquest) 以降にフランス語から大量に入ってきた語彙です.たとえば,calf (生きた子牛)と veal (子牛の肉),deer (生きた鹿)と venison (鹿の肉)のように,動物とその肉を表わす語が,英語本来語系列とフランス借用語系列に分裂している例は,英語史における鉄板ネタです.
このような言語の歴史的背景を学校の英語の授業で伝えることには,大きな意義があります.1つには,英語が純粋で「偉い」言語だという思い込みから,教員も生徒も解放されることです.現代世界において英語は「絶対的王者」の地位にあるとはいえ,歴史を紐解いてみれば,紆余曲折を経てきた言語であり,語彙的には "hybrid" な言語でもあり,「偉い」という形容詞とは相容れない性格を多々もっている言語なのです.歴史を知ると,英語とて実はさほど身構えるほどの相手ではない,と肩の力が抜けていくはずです.
また,上記の「動物と肉の単語」の例1つをとってみても,歴史・文化の学びにつながることはもちろん,さらには国語科の話題としての「語彙の3層構造」,すなわち日本語の和語・漢語・外来語の区分の問題にもシームレスに接続していきます.英語史は,英語科という1科目にとどまらず,歴史科や国語科とも連携していくハブとなり得るのです.
今回の研修会は,英語史研究が小中高の教育現場と結びつき,互いに学び合い,高め合うことができる「接点」が存在することを確信する機会となりました.この知的な刺激を糧に,今後も英語史の知見を様々な形で社会へ還元していく活動(=hel活)を続けていきたいと思っています.改めまして,主催者の先生,参加された先生方に心より感謝申し上げます.
2025-11-09 Sun
■ #6040. 今朝の朝日新聞朝刊に「英語帝国主義」をめぐるインタビュー記事が掲載されています [notice][sociolinguistics][helkatsu][linguistic_imperialism][world_englishes][elf][elt][hel_education][demography][voicy][heldio]
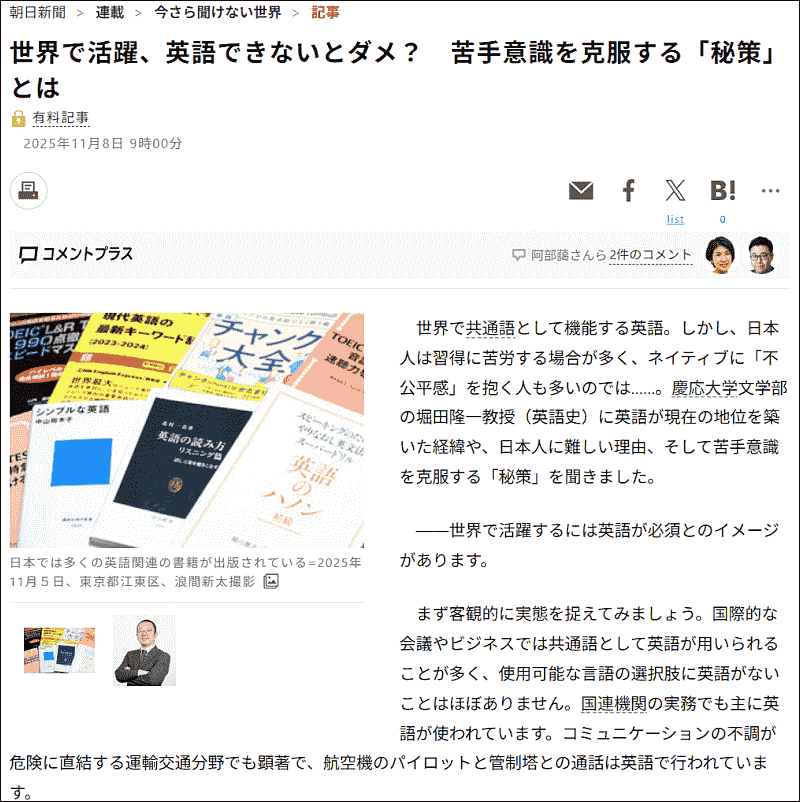
昨日11月8日(土),朝日新聞デジタル版にインタビュー記事「世界で活躍,英語できないとダメ? 苦手意識を克服する「秘策」とは」が公開されました.この記事は,同紙の連載企画「今さら聞けない世界」の一環として,各分野の専門家へのインタビューを基にして,編集されたものです.
先日,連載の担当者の方より,「英語帝国主義」を念頭に,世界における英語の位置づけと,その英語に対して私たちはどのように臨めばよいかについて伺いたいとのご連絡をいただき,このインタビューを実施した次第です.貴重な機会をいただき,朝日新聞の関係者の方々に感謝申し上げます.
昨日公開されたデジタル版は有料記事となっておりますが,フルバージョンでお読みいただけます.また,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に,同記事の短縮版が掲載される予定です.
さて,インタビュー(記事)の内容ですが,英語史研究者の立場から,英語が歴史を通じて築き上げてきた世界的な地位,日本語母語話者が英語学習で難しさを感じる構造的な要因,そして,苦手意識を乗り越えて自信をもって英語を使うための「秘策」についてお話ししました.
まず,国際的な舞台で英語が共通語 (lingua_franca) として機能しているという客観的事実をを確認しました.その上で,英語が世界的な地位を得た背景には,過去のギリシア語やラテン語など,かつての有力言語がたどった道筋と質的には同じ構造があることを指摘しています.特定の国家の政治的・経済的な力が,その言語の拡散を支えてきたという歴史的事実は,言語の力学を理解する上で重要です.この議論は,英語史における大きな論点の1つである「英語帝国主義批判」とも関わってきます.
次に,日本人にとって英語習得が難しいとされる構造的な理由についても触れました.日本語と英語は,発音や文法体系,語彙などの点で共通点が非常に少なく,言語の距離が遠いという事実があります.(数千年レベルで見れば)互いに方言といってよい関係にあるヨーロッパ諸語の母語話者と比べると,日本人が英語の習得に長い時間を要するのは,むしろ自然なことです.
さらに,単なる言語知識の問題を超えて,英米人と日本人の間には,コミュニケーションの土台となる宗教,歴史,文化,習慣の面での共通項も少なく,英語での会話における「作法」を知らないことが,習得のもう1つの大きな壁になっていることも指摘しました.欧州諸国の人々が英語での会話にあまり抵抗感がないのと比べると,日本人はいざ話そうとしたときに「そもそもどのように会話を始めたらよいのか」という戸惑いを感じやすいようです.
そして,記事のなかで最も注目していただきたいのが,苦手意識を克服し自信をもって話すための「秘策」です.具体的な内容はここでは伏せておきますが,英語史や社会言語学の知見に基づき,現在の世界の英語使用の実態に鑑みた,実践的なアドバイスとなっていると思います.鍵となるのは,世界の英語話者20億人のうち,英米人などの母語話者はマイノリティであるという事実です.
「英語帝国主義」については,本ブログでも linguistic_imperialism のタグの着いた記事をはじめとして,様々に議論してきました.ここでは Voicy heldio の関連回をご案内しておきたいと思います.ぜひお聴きいただければ.
・ 「#1607. 英語帝国主義から世界英語へ」
・ 「#145. 3段階で拡張してきた英語帝国」
改めて,紙面では本日11月9日(日)の朝刊に短縮版が掲載される予定ですので,そちらからもご一読いただければ幸いです.
2025-11-02 Sun
■ #6033. 「なぜ英語を学ばなければならないの?」を動画にしてみました by Google NotebookLM [hel_education][voicy][heldio][elt][notice][youtube][heltube][ai][helkatsu]
昨日の記事「#6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」 ([2025-11-01-1]) は,2023年5月30日の heldio 配信回「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」に基づいた文章である旨を述べました.話し言葉は書き言葉とは異なり,独特の勢いがありますので,ぜひ音声でもお聴きいただければ.
さらに,この同じコンテンツを動画化できないかと思案していたところ,Google NobebookLM で簡単にできることを知り,生成AIの力でアニメ+ナレーションの形に仕立て上げることにしました.細かいチューニングはできなかったので,出来上がりにはツッコミどころがいくつもありますが,初めての試みとして公開してみます.YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」に上げました.動画「なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて」(6分49秒)をご覧ください.
どんなものでしょうか? 今後も「hel活×生成AI」はいろいろと試していきたいと思っています.
2025-11-01 Sat
■ #6032. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中高生に向けて [hel_education][voicy][heldio][elt][notice]
中高生に向けて英語と英語史について話すセミナーがあり,何をどう語ろうかと考えていました.2年半ほど前の2023年5月30日に Voicy heldio で「#729. なぜ英語を学ばなければならないの? --- 中学生のための英語史」と題する回を配信し,反響が大きかったことを思い出したので,そのときの内容を,さらにかみ砕いて話したらどうだろうかと思いつきました.そのためにも一度その概要を(自分のために)文章化しておこうということで,以下の文章となりました.議論の順番を多少組み替えたり,2025年時点での生成AIの発展などを意識して議論に組み込んだりしてありますが,主張したいことは変わっていません.
小中高で英語を学んでいる生徒たちや,ビジネスの現場で奮闘する大人たちまで,多くの日本人が抱く共通の疑問があります.それは「なぜ英語を学ばなければならないの?」という純粋な問いです.
特に生成AIによる翻訳・通訳の技術が目覚ましい進化を遂げ,瞬時に,そしてかなり正確に言語の壁を取り払ってくれるようになった現代において,この問いはかつてないほど切実な重みを増しています.膨大な時間とエネルギーを投じる語学学習は,はたして「コスパが悪い」と言わざるを得ないのだろうか,と.
長らく英語史という分野を専攻してきた研究者の視点から,この疑問に対し,絶対的な「答え」ではなく,中高生の皆さんが自ら考えるための3つの「英語史・言語学的ヒント」を提供したいと思います.
1.英語の世界的な地位は「たまたま」である --- 400年前はわずか600万人の言語
まず,英語の世界語としての地位を相対化する必要があります.今でこそ,英語は世界最強の lingua_franca と見なされていますが,この地位は,英語が言語として本質的に優れていたから得られたものではありません.単に,歴史的な「たまたま」の結果です.驚くべきことに,今から400年ほど前の近代英語期,すなわちシェイクスピアが活躍していた頃の英語話者は,イングランドの人口とほぼ同じ,わずか600万人程度でした.これが,後のイギリス帝国による世界的な植民地拡大と,その後のアメリカ合衆国の台頭という,一連の出来事によって,今日の20億人規模へと爆発的に増加したのです.
この歴史的事実は,英語が絶対不変の覇権言語ではないことを示唆しています.将来,中国語やスペイン語,あるいは今ではまだ目立っていない言語が,この地位を脅かすことは十分にあり得ます.英語学習を考える際,まずはその地位が歴史上の偶然の産物であるという冷静な視点をもつことが大事です.
2.世界「4分の1」のリアル --- 万能ではないが,人類史上最大の言語
では,現在の英語の実力はどのくらいなのでしょうか.「英語ができれば世界中の人と話せる」という言説は,残念ながら過大な期待を含んでいます.現在の世界人口約80億人のうち,母語話者と非母語話者を含め英語でコミュニケーションが取れる人は,せいぜい約20億人.つまり,世界の4分の1ほどにすぎません.私自身,学生時代に世界を旅し,観光地から一歩離れると英語が全く通じないという現実には何度となく直面しました.今でも英語は決して万能ではありません.
しかし,この4分の1という割合は,人類史上,単一の言語が達成した最も高いシェアであることは間違いありません.ギリシア語,ラテン語,アラビア語,中国語など,歴史上「世界語」と呼ばれ得る立場にあった他の言語と比較しても,現代世界における英語の通用度は群を抜いています.
過大評価も過小評価もせず,この「80億分の20億」というリアルな実力を知ること.そして,1つの外国語を選ぶとすれば,史上最大のリーチを持つ英語こそが,最大限の実益を伴う選択肢であることもまた事実なのです.
3.英語(外国語)学習から得られる「発想の転換」
生成AIによる言語技術が発達した現代,労力に見合う英語学習の真の価値はどこにあるのでしょうか.それは,コミュニケーションの便にあるというよりも,むしろ私たちの思考生活を豊かにしてくれる点にあるのではないでしょうか.英語を学ぶことは,私たちが普段,無意識のうちに縛られている日本語の「思考の枠組み」から一時的に解放される機会を与えてくれます.
例えば,日本語では親族を「兄,弟,姉,妹」と年齢の上下関係で厳密に区別するのに対し,英語では brother, sister と性別でしか区別しません.また,日本語では「米,稲,ご飯」などと状況に応じて語彙を使い分けるものを,英語では基本的に rice 一語で表現します.こうした言葉の構造的な違いに触れるとき,「なぜ?」という驚きやショックが生じます.この驚きこそが,日本語という非常に強い束縛から抜け出し,もう1つの視点,つまり英語的な思考法を手に入れるということに他なりません.これは単なる翻訳知識では得られない,世界認識の転換です.
日本語と英語は構造的に非常に隔たりが大きい言語です.だからこそ,発想の転換の恩恵を最大限に受けることができるのです.日本語母語話者にとって,状況はむしろ「ラッキー」であると言えます.得られる知的な恩恵の大きさを考えれば,英語学習のコスパは決して悪くありません.
4. 答えは,あなた自身の中に
英語を学ぶべきか否か.その答えは,大人や先生や大人が与える単純なものではなく,学習者1人ひとりが自らの価値観と目標に基づき,主体的に見つけ出す必要があります.歴史的偶然性,リアルな通用度,そして思考を転換する力.これらの多角的な視点から英語と向き合い,中高生の皆さん自身が答えを見つけてください.最後に,この問いを投げかけたいと思います.生成AIが言葉の壁を取り払うかもしれない未来に向けて,あなたはなぜ,あるいは何を求めて英語(やその他の外国語)を学びますか?
関連して,中高生に向けた heldio 配信回として,以下もお聴きください.
・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)
・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)
・ 「#1577. helwa メンバー発信!中高生のあなたへ,私は今こうやって英語(外国語)とつきあっています --- 「英語史ライヴ2025」より」
2025-06-26 Thu
■ #5904. 旺文社『Argument』春夏号にエッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」を寄稿しました [voicy][heldio][elt][obunsha][notice]
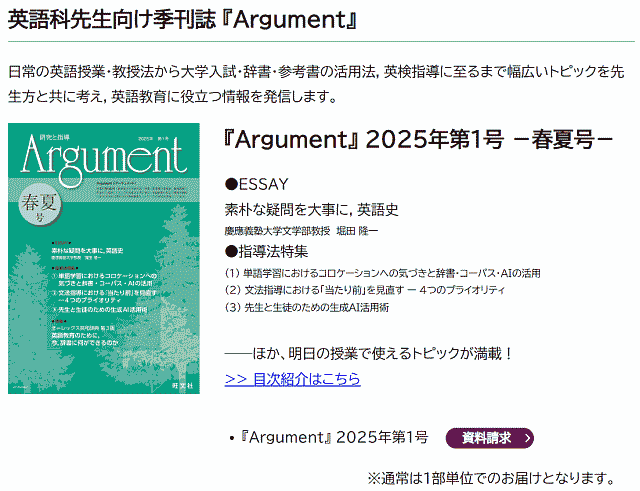
旺文社から発行されている英語の先生向け季刊誌『Argument --- 研究と指導』の2025年第1号(春夏号)に,巻頭エッセイを書かせていただきました.「素朴な疑問を大事に,英語史」と題する1ページの文章です.
『Argument』は高校英語科の教員に向けて限定配布されている情報誌で,その趣意としては次のようにあります.
日常の英語授業・教授法から大学入試・辞書・参考書の活用法,英検指導に至るまで幅広いトピックを先生方と共に考え,英語教育に役立つ情報を発信します.旺文社は先生方の「英語教育ネットワーク」の確立を目指しています.」
学校関係者であればこちらのHPよりより資料請求できますが,ご紹介の号については受付はすでに締め切られているとのことです.
一昨日,『Argument』に寄稿したエッセイと関連づける形で,Voicy heldio にて「#1486. 答えよりも問い,スッキリよりもモヤモヤが大事 --- 旺文社『Argument』春夏号の巻頭エッセイ「素朴な疑問を大事に,英語史」」を配信しました.
今日の hellog 記事では,上記の heldio 配信回の内容をベースに,文章としてまとめ直したものをお届けします.
巻頭エッセイでは,私自身が英語史研究の道に進んだきっかけや,日々の研究・教育活動で最も大切にしている姿勢について述べました.その核心は,「答え」よりも「問い」,そして「スッキリ」よりも「モヤモヤ」が物事の探求において重要である,という点です.
私たちは何か疑問に思うことがあると,すぐにその「答え」を知りたがる傾向があります.インターネットで検索すれば,大概の問いには何らかの答えが見つかる時代です.答えが与えられ,疑問が解消されると,一種の快感が得られます.いわゆる「スッキリ」した状態です.もちろん,この快感自体を否定するつもりはありません.しかし,学問上の探求においては,この「スッキリ」を性急に求めすぎることは,かえって深い理解を妨げることになりかねないのです.
なぜなら,真に価値があるのは,多くの場合「答え」そのものではなく,その答えを導き出すに至った「問い」の立て方にあるからです.陳腐な問いからは陳腐な答えしか生まれません.一方で,「良い問い」を立てることができたならば,その探求は半ば成功したようなものです.これは逆説的に聞こえるかもしれませんが,「良い問い」とは,それ自体がすでに答えへの道筋を,あるいは答えの本質的な部分を内包しているものなのです.問題を正しく設定し,焦点を明確に定める行為そのものが,きわめて創造的な知の営みといえます.
この「答えよりも問いが大事」という考え方は,「スッキリよりもモヤモヤが大事」という姿勢とパラレルです.「スッキリ」が「答え」によってもたらされる一時的な安堵であるとすれば,「モヤモヤ」は「問い」を抱え続け,思考を巡らせている持続的な状態です.この「モヤモヤ」こそが,知的探求のエンジンであり,新たな発見を生み出すための不可欠な基盤となります.すぐに答えの出る問いは,私たちをそれ以上遠くへ連れて行ってはくれません.むしろ,なかなか答えが見つからず,頭の中で様々な可能性が渦巻いている「モヤモヤ」した状態こそが,思考を深め,対象への解像度を高めてくれるのです.
これは,実際には,学問上の探求に限った話ではありません.日々の学習や仕事において,ふと心に浮かんだ「なぜ?」という素朴な疑問を大切に育てること,すぐに「答え」を求めて解消してしまうのではなく,しばらくの間「モヤモヤ」として抱え続け,自分なりに考えてみること,その知的な我慢こそが,私たちをより深い理解へと導いてくれるのではないでしょうか.皆さんの心の中にある「モヤモヤ」は,未来の豊かな実りにつながる貴重な種なのかもしれません.
以下の heldio 過去回でも同趣旨でお話ししていますので,ぜひお聴きいただければ.
・ 「#510. 中高生に向けて モヤり続けることが何よりも大事です」(2022年10月23日)
・ 「#633. 答えを出すより問いを立てよ」(2023年2月23日)
・ 堀田 隆一 「素朴な疑問を大事に,英語史」『Argument』2025年第1号(2025年春夏号),旺文社.2025年5月.1頁.
2025-06-04 Wed
■ #5882. 今週末(土),京都で『英語語源ハンドブック』の新刊紹介 --- 日本中世英語英文学会西支部例会にて [academic_conference][hee][notice][heldio][helwa][hel_education][elt][etymology]
今週末6月7日(土)の午後は,近刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)をめぐり京都が熱い!
立命館大学の衣笠キャンパスにて,日本中世英語英文学会の第41回西支部例会が開催されます.本日より2週間後の6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』の共著者3名による新刊紹介セッションが開かれることになっているのです.開催要領は以下の通りです.
IV 新刊紹介 (15:10~15:50) 学而館 GJ 401 教室
『英語語源ハンドブック』(研究社,2025 年)
唐澤一友(立教大学教授)
小塚良孝(愛知教育大学教授)
堀田隆一(慶應義塾大学教授)
司会 福田一貴(駒澤大学教授)
共著者である唐澤一友氏,小塚良孝氏,そして堀田隆一の3名が対面で集合し,公の場で本書について語るのは,本書出版の情報公開後,初めての機会となります.本書の狙いや魅力についてお話しする予定です.なお,司会の福田一貴氏には,小河舜氏(上智大学)とともに,本書の校閲に協力いただいています.
本書の位置づけは,単に英単語の語源を解説する語源辞典の簡略版ハンドブックというわけではありません.むしろ,英語史の知識をいかに英語の教育・学習に活かすか,その具体的な方法を提案することに主眼を置いています.英語教員が授業で披露すれば学生の知的好奇心をくすぐるであろう豆知識や,英語学習者が単語の奥深さに触れることで記憶に定着させやすくなるようなエピソードが豊富に盛り込まれています.語源のみならず,意味・発音・用法の歴史的変遷にも光を当て,巻頭の英語史概説や巻末の用語解説と合わせて読めば,自然と英語史の基礎知識も身につくように編まれています.
本書は日本語で書かれていますが,英語タイトルとして Handbook of English Etymology (= HEE) も設定されています.発売前ではありますが,hellog でもすでに hee のタグを付けて,いくつかの記事を公開してきましたので,そちらもお読みください.
ちなみに,今回の西支部例会には,新刊紹介の直後に目玉企画が用意されています.こちらも合わせてご案内します.
V 企画発表 (16:05~17:50) 学而館 GJ 401 教室
〈仄暗き中世〉の系譜と魅力 --- 中世暗黒化言説を巡って
司会・総論 岡本広毅(立命館大学准教授)
清川祥恵(佛教大学講師)
小澤実(立教大学教授)
大西巷一(漫画家)
こちらの西支部例会にご関心のある方は,公式HPをご訪問ください.
また,『英語語源ハンドブック』の共著者らが京都入りする金曜日以降,Voicy heldio 収録や生配信などもあり得ますので,ぜひ私の heldio および X アカウントをフォローして,続報をお待ちください.

・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.
2024-03-21 Thu
■ #5442. 『ライトハウス英和辞典 第7版』の付録「つづり字と発音解説」 [spelling][pronunciation][spelling_pronunciation_gap]lexicography][dictionary][lighthouse7][yod-dropping][vowel][diphthong][elt][phonetics]
「#5438. 紙の辞書の魅力 --- 昨秋出版の『ライトハウス英和辞典 第7版』より」 ([2024-03-17-1]) で紹介した,昨秋出版された老舗英和辞典の新版について再び取り上げます.
同辞書の巻末の付録が充実しています.付録コンテンツのトップを飾るのが「つづり字と発音解説」 (pp. 1666--77) です.英語の綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) の問題に関心のある向きは,ぜひ熟読してみると発見が多いと思います.
昨日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「#1025. blow - blew 「ブルー」 - blown」と題して,blew /bluː/ の綴字と発音の関係についてお話ししました.「ブリュー」の発音で覚えていた方もいるかもしれませんが,正しくは(yod-dropping が効いているので) blue と同じ「ブルー」の発音です.drew, flew, grew, slew, threw も同様で,/juː/ ではなく /uː/ の母音を示します.
では,『ライトハウス英和辞典 第7版』の「つづり字と発音解説」より,blew の発音問題にも関連する uː の項目 (p. 1668) を覗いてみましょう.
15 uː
日本語の「ウー」より唇を小さく丸めて前に突き出すようにして「ウー」と長めに発音する.
・規則的なつづり字
(ōō): boot /búːt/ 長靴,food /fúːd/ 食物
s, ch, j, l, r の後で
(ü): super /súːpɚ | -pə/ すばらしい,June /ʤúːn/ 6月,blue /blúː/ 青い,rule /rúːl/ 規則
ew (=ü): chew /ʧúː/ よくかむ,Jew /ʤúː/ ユダヤ人,blew /blúː/ blow の過去形,crew /krúː/ 乗組員
・注意すべきつづり字
(ui): suit /súːt/ (衣服の)ひとそろい,juice /ʤúːs/ 汁,fruit /frúːt/ 果物
ou (=ōō): group /grúːp/ 群れ,soup /súːp/ スープ
しっかり <ew> ≡ /uː/ の関係がカバーされているのが心強いですね.
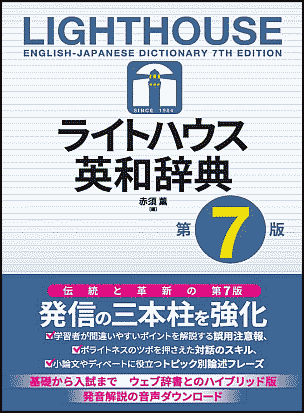
・ 赤須 薫(編) 『ライトハウス英和辞典 第7版』 研究社,2023年.
2023-12-29 Fri
■ #5359. 小林めぐみ先生との対談 --- 映画と World Englishes [voicy][heldio][notice][world_englishes][we_nyumon][indian_english][elt][efl]
Voicy heldio にて小林めぐみ先生(成蹊大学)との対談回を配信しています.「#936. 映画と World Englishes は相性がよい! --- 小林めぐみ先生との対談」と題して,映画を用いた World Englishes の英語教育・言語教育というテーマでお話しいただいています.本編は10分ほどです.ぜひお聴きください.
昨今は NetFlix や YouTube などで配信される映画やドラマを通じて,世界の様々な英語変種が身近に聞かれるようになってきました.このような資源は,英語学習・教育(特にリスニング)の教材としても役立ちますし,世界各地の言語事情や英語事情を理解する上でも貴重です.小林先生はこの点に注目し,大学の英語や(社会)言語学の授業で,積極的に映画と World Englishes を導入されているとのことでした.そして,本編の最後では,小林先生の推しが「○○英語(映画)」であることが明らかにされます.皆さんの推しの英語変種は何でしょうか?
今回の小林先生との対談は第2弾でして,前回の第1弾は先日12月12日に「#925. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 小林めぐみ先生との韓国の英語をめぐる対談」として配信しています.こちらも今回の内容と関連が深いので,ぜひお聴きいただければ.また,関連する hellog 記事「#5345. 「韓国の英語」 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第10章」 ([2023-12-15-1]) も合わせてどうぞ.
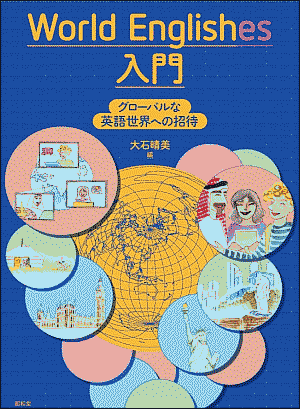
・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.
2023-12-15 Fri
■ #5345. 「韓国の英語」 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第10章 [voicy][heldio][review][notice][world_englishes][we_nyumon][korean][elt]
10月に昭和堂から出版された『World Englishes 入門』について,本ブログでも多く取り上げてきています.先日,本書の第12章「韓国の英語」を執筆された小林めぐみ先生(成蹊大学)と Voicy heldio にて対談しました.韓国は身近な国ですし,韓国が過酷な学歴社会であることや,関連する教育事情についての情報も入ってくることはあります.しかし,とりわけ英語教育事情については,知っているようでほとんど知らなかったことに,本書を読んで気づきました.今回の対談では執筆者の先生に直接お話しを伺い,たいへん勉強になりましたし,何よりもおしゃべりを楽しむことができました.小林先生,ご出演ありがとうございました.そして,今後ともどうぞよろしくお願いいたします.
本編で30分ほどの音声コンテンツとなっています.「#925. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 小林めぐみ先生との韓国の英語をめぐる対談」です.ぜひお聴き下さい.
今回話題となった本書の第10章「韓国の英語」 (pp. 163--75) は,以下の構成となっています.章末には「研究テーマ」コーナーと参考文献も付されています.
1 韓国の言語事情と英語教育
(1) 韓国の公用語(韓国語)
(2) 韓国における英語使用・教育の歴史
(3) 近年の英語教育と英語熱
コラム 韓国の住宅事情
2 韓国英語の特徴
(1) 発音
(2) 語彙
(3) 文法・表現
コラム 韓国人の姓とスペリング
コラム 韓国語の親族の呼び名
3 メディアに見る韓国英語
(1) 韓国ドラマ・映画の英語
(2) 韓国映画『英語完全征服』ほか
(3) K-pop の英語
韓国語の対外戦略,加熱する英語教育と英語留学事情,英語村のその後,韓製英語,K-pop の歌詞の「コードの曖昧化」など,おもしろい話題が盛りだくさんです.
『World Englishes 入門』関連の heldio 配信回を以下にまとめておきます.関連の hellog 記事については we_nyumon よりどうぞ.
・ 「#865. 世界英語のお薦め本の紹介 --- 大石晴美(編)『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)
・ 「#869. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 和田忍さんとの対談」
・ 「#883. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 今村洋美先生とのアメリカ・カナダ英語をめぐる対談」
・ 「#901. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 梅谷博之先生とのモンゴルの英語をめぐる対談」
・ 「#925. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 小林めぐみ先生との韓国の英語をめぐる対談」
今回の対談とは別に,小林先生とは別の対談回の配信も近日中に予定しています.英語教育と社会言語学と世界諸英語を掛け合わせた,おもしろいトークとなるはずですので,ぜひそちらにもご期待ください.
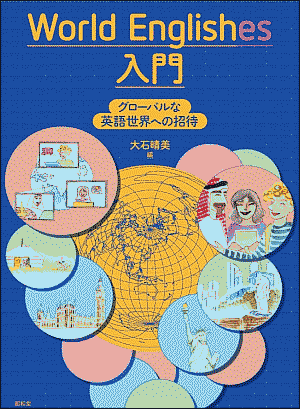
・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.
2023-09-19 Tue
■ #5258. 小学校英語ブームは鹿鳴館時代に一度あった [english_in_japan][elt]
「#5112. 江利川春雄(著)『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』(筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年)」 ([2023-04-26-1]) を読んでいる.現代の英語教育をめぐる問題の1つに「小学校英語」があるが,小学校への英語科の導入は,日本の英語教育史において今回が初めてではない.江利川 (34--35) より,関連する3段落を引こう.
文部科学省の学習指導要領によって,小学校では二〇二〇(令和二)年度から外国語(実質は英語)が正式教科となった.なので,小学校の英語教育は平成・令和に始まったと思う人が多いようだ.ところが実際には,明治期から小学校で英語が教えられていた.近代日本の学校制度を最初に定めた一八七二(明治五)年の「学制」には,すでに小学校で外国語を教えてもよいと書かれていた.しかし,当時は教師も教材も不足しており,外国語を教える小学校はほとんどなかった.
小学校で英語教育が本格的に始まったのは,鹿鳴館が開館した翌年の一八八四(明治一七)年一一月に「小学校教則綱領」が改正され,「英語の初歩を加えるときは読方,会話,習字,作文等を授くべき」と定められてからである.小学校への英語の導入は欧化政策の一環だったようだ.
二年後の一八八六年には高等小学校制度が発足した.これは四年制の尋常小学校(義務制)を修了した希望者が入学する二~四年制の学校で,現在の小学校五年から中学校二年(一〇~一三歳)に相当する.高等小学校の英語は加設科目(一種の選択科目)だったが,発足当初は週二~三時間ほど英語を教える学校がほとんどだった.たとえば一八八八年に,大阪府は「高等小学校は必ず英語科を置くこと」と定め,和歌山県でも英語を週三時間加設するよう通達している.
この歴史を知っていると知っていないとでは,目下の小学校英語をめぐる議論の前提が異なってくるだろう.もちろん上記の明治時代の教育政策は失敗した.鹿鳴館時代の英語ブームに乗っての政策だったわけだが,短期間のブームが終息すると,政策それ自身もしぼんでしまった.この歴史を押さえておくことは重要である.
・ 江利川 春雄 『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』 筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年.
2023-04-26 Wed
■ #5112. 江利川春雄(著)『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』(筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年) [review][elt]
見直しが進んでいる日本の英語受容史の話題,あるいは日本人がいかに英語と付き合ってきたかという話題について,もう1冊の本が出版されています.
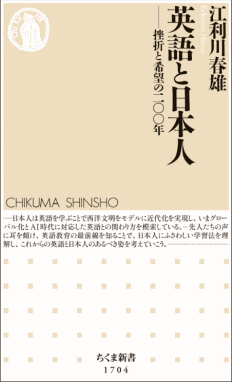
「はじめに」 (p. 12) には,私自身も何度も尋ねられ,うまく答えられないできた質問の数々が,以下のように列挙されています.いろいろな意味で耳の痛い質問の数々ですが,こういった問いにも自信をもって回答できるようになりたいとは思っています.
英語と日本人の関係は「なぜ」や「なぞ」に満ちている.
・ なぜ日本人は英語を学ぶのか.
・ 何年やっても英語が身につかないのはなぜなのか.
・ 小学校から英語を習えば,英語が話せるようになるのか.
・ 受験のために英単語の暗記や文法訳読をやる意味があるのか.
・ 英語が使える「グローバル人材」を学校で育成できるのか.
・ 英検や TOEIC でコミュニケーション能力が測れるのか.
・ コミュニケーション重視の英語教育改革は成果があったのか
・ AI(人工知能)自動翻訳・通訳が進んでも英語を学ぶ意味があるのか.
これらの「なぜ」や「など」に迫るには,著者も主張しているように,日本の英語受容史について真剣に学ぶ必要があると考えています.これは英語史の側からみると,英語の世界的拡大が日本社会においてはどのような展開を経たか,他の社会と何が似ていて,何が異なるのか,ということを探る試みになるだろうと思います.
関連書籍として「#4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より」 ([2022-10-13-1]) も参照.
・ 江利川 春雄 『英語と日本人 --- 挫折と希望の二〇〇年』 筑摩書房〈ちくま選書〉,2023年.
2023-04-18 Tue
■ #5104. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか? [voicy][heldio][hel_education][elt][khelf][masanyan][colloquia]
昨朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」で,同じ標題の放送回を配信しました.Voicy のコメント欄などを通じて反響をいただいています.ありがとうございます.「#686. 英語史の知識は,英語の先生が英語を教えるときに本当に役立つのか?」をお聴きください.
「英語史」という分野に多少なりとも興味をもって接しているすべての方々が意見を述べられる話題ではないかと思います.英語教員を始めとして英語史研究者から英語学習者まで,さらには英語のみならず他の外国語の教育・学習に関わる皆さんに,関心をもってもらいたいトピックです.上記放送回のコメント欄より,ご意見をお寄せいただければ幸いです.
議論の参考までに,いくつかの heldio 放送回,hellog 記事,コンテンツ,論文等にリンクを張っておきます.
・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」
・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])
・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])
・ hellog 「#5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版)」 ([2023-04-12-1])
・ hellog 「#4570. 英語史は高校英語の新学習指導要領において正当に評価されている」 ([2021-10-31-1])
・ hellog 「#4571. 英語史は中・高等学校教員養成課程のコアカリキュラムにおいて正当に評価されている」 ([2021-11-01-1])
・ 英語史コンテンツ「#59. 英語史は役に立たない,か」:khelf(慶應英語史フォーラム)顧問の N. S. 氏による,昨年度の「英語史コンテンツ50」の取りをとった論考.
・ 森田 真登 「高等学校英語教育における英語史の活用 --- OED Text Visualizer を用いて教科書本文の単語の理解を深める ---」 Colloquia 42 (2021): 125--41.
2023-04-12 Wed
■ #5098. 英語史を学び始めようと思っている方へ hellog と heldio のお薦め回一覧(2023年度版) [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french][start_up_hel_2023]
年度始めですので,英語史の学びを後押しする記事を書くことが多くなっています.昨年の夏に「#4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ」 ([2022-08-30-1]) の記事を書き,今回はそれと重なるところも多いのですが,改めて2023年度版ということで,英語史の学びに役立つ 「hellog~英語史ブログ」の記事や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回へのリンクをまとめてみました.
[ そもそも本ブログの執筆者(堀田隆一)は何者? ]
・ heldio 「#408. 自己紹介:英語史研究者の堀田隆一です」 (2022/07/13)
・ note 上のプロフィールもご覧ください
[ hellog と heldio の歩き方 ]
・ hellog 「#5097. hellog の読み方(2023年度版)」 ([2023-04-11-1])
・ hellog 「#5093. heldio の聴き方(2023年度版)」 ([2023-04-07-1])
[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから ]
・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)
・ heldio 「#650. 英語史の知恵が AI に負けない3つの理由」 (2023/03/12)
・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)
・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])
・ hellog 「#5096. 『英語史新聞』第5号が発行されました」 ([2023-04-10-1])
・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])
・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)
・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])
・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)
・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])
・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])
・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])
・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])
・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])
・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])
・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])
・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])
・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])
[ 英語史入門の文献案内 ]
・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)
・ hellog 「#5094. 英語史概説書等の書誌(2023年度版)」 ([2023-04-08-1])
・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])
・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])
・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)
・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])
・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)
・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])
[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]
・ heldio 「#607. 1年間の「英語史」の講義を終えて」 (2023/01/28)
・ hellog 「#5020. 2022年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2023-01-24-1])
・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])
・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])
・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])
・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])
[ とりわけ語源に関心がある方へ ]
・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])
・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])
・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])
・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])
・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])
[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]
・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)
・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])
・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])
[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]
・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)
・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)
・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)
・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])
・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)
・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)
・ heldio 「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」 (2022/09/29)
2022-10-13 Thu
■ #4917. 2500年に及ぶ「学習英文法」の水脈 --- 斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』より [prescriptive_grammar][lowth][history_of_linguistics][greek][latin][elt][review][english_in_japan]
今年5月に研究社より出版された斎藤浩一(著)『日本の「英文法」ができるまで』を読んだ.古代のギリシア語文法から始まり,ラテン語文法に受け継がれ,西洋諸言語に展開し,幕末・明治期に日本にやってきた,2500年に及ぶ(英)文法研究の流れを一望できる好著である.
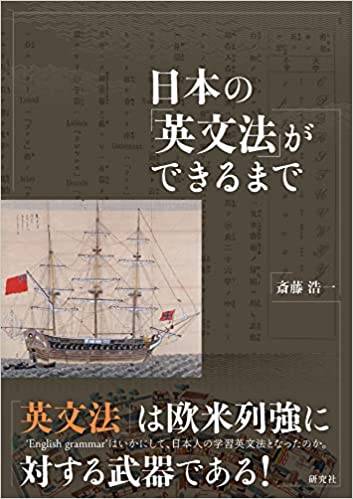
本書第1章の最初のページに「日本の「学習英文法」には,じつに2500年余りにも及ぶ長大な言語分析の伝統が盛り込まれている」 (p. 8) とあり,次のような見取り図が示されている.あまりに適切で,核心を突いており,分かりやすくて感動してしまった.
【古代】ギリシア語文法
≪ローマ帝国,カトリック教会の興隆≫
【(古代~)中世】ラテン語文法
≪宗教改革≫
【16~18世紀】英文法
≪19世紀イギリスのアジア進出≫
【19~20世紀】日本の「学習英文法」
≪ ≫に囲まれている語句は,時代を動かした「媒介項」を表わしているという.英文法史のエッセンスを,ここまで端的に(7行で!)大づかみにした図はみたことがない.見事な要約力.
古代ギリシア語文法からラテン語文法を経て,初期近代のヴァナキュラーとしての英文法を模索する時代に至るまでの歴史(日本における「学習英文法」に注目する本書の観点からみると「前史」)については,hellog でも様々に記事を書いてきた.とりわけ古典語との関連では,次のような話題を提供してきたので,関心のある方はぜひ以下をどうぞ.
・ 「#664. littera, figura, potestas」 ([2011-02-20-1])
・ 「#892. 文法の父 Dionysius Thrax の形態論」 ([2011-10-06-1])
・ 「#1256. 西洋の品詞分類の歴史」 ([2012-10-04-1])
・ 「#1257. なぜ「対格」が "accusative case" なのか」 ([2012-10-05-1])
・ 「#1258. なぜ「他動詞」が "transitive verb" なのか」 ([2012-10-06-1])
本書では,英語学史の奥深さを堪能することができる.昨今,近代英語期に関しては英語史と英語学史の研究の融合も起こってきているので,ぜひこのトレンドをつかみたいところ.
・ 斎藤 浩一 『日本の「英文法」ができるまで』 研究社,2022年.
2022-08-30 Tue
■ #4873. 英語史を学び始めようと思っている方へ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][elt][etymology][french]
この「hellog~英語史ブログ」では,定期的に読者の皆さんに英語史の学びを奨励してきました.この夏の間に英語(学)の学びを深め,そこから英語史にも関心が湧き始めたという方もいるかと思いますので,このタイミングで改めて英語史の学びをお薦めしたいと思います.ちなみに本ブログの執筆者(堀田隆一)が何者かについてはこちらのプロフィールをご覧ください.
これまで hellog や Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の両メディアを中心に,「英語史のすすめ」に関するコンテンツを蓄積してきました.以下にカテゴリー別にリンクを整理しておきます.各カテゴリー内部では,およそ重要な順にコンテンツを並べていますので,上から順に聴取・閲覧していくと効果的かと思います.
[ まずは英語史の学びのモチベーションアップから! ]
・ heldio 「#444. 英語史を学ぶとこんなに良いことがある!」 (2022/08/18)
・ hellog 「#4728. 2022年度「英語史」講義の初回 --- 慶應義塾大学文学部英米文学専攻の必修科目「英語史」が始まります」 ([2022-04-07-1])
・ hellog 「#4729. ぜひ英語史学習・教育のために hellog の活用を!(2022年度版)」 ([2022-04-08-1])
・ hellog 「#4556. 英語史の世界にようこそ」 ([2021-10-17-1])
・ heldio 「#139. 英語史の世界にようこそ」 (2021/10/17)
・ hellog 「#24. なぜ英語史を学ぶか」 ([2009-05-22-1])
・ heldio 「#112. 英語史って何のため?」 (2021/09/21)
・ hellog 「#4361. 英語史は「英語の歴史」というよりも「英語と歴史」」 ([2021-04-05-1])
・ hellog 「#1199. なぜ英語史を学ぶか (2)」 ([2012-08-08-1])
・ hellog 「#1200. なぜ英語史を学ぶか (3)」 ([2012-08-09-1])
・ hellog 「#1367. なぜ英語史を学ぶか (4)」 ([2013-01-23-1])
・ hellog 「#2984. なぜ英語史を学ぶか (5)」 ([2017-06-28-1])
・ hellog 「#4021. なぜ英語史を学ぶか --- 私的回答」 ([2020-04-30-1])
・ hellog 「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1])
・ hellog 「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1])
・ hellog 「#4073. 地獄の英語史からホテルの英語史へ」 ([2020-06-21-1])
[ 英語史入門の文献案内 ]
・ hellog 「#4727. 英語史概説書等の書誌(2022年度版)」 ([2022-04-06-1])
・ hellog 「#4557. 「英語史への招待:入門書10選」」 ([2021-10-18-1])
・ heldio 「#140. 対談 英語史の入門書」 (2021/10/18)
・ hellog 「#4731. 『英語史新聞』新年度号外! --- 英語で書かれた英語史概説書3冊を紹介」 ([2022-04-10-1])
・ heldio 「#313. 泉類尚貴先生との対談 手に取って欲しい原書の英語史概説書3冊」 (2022/04/09)
・ hellog 「#3636. 年度初めに拙著『英語の「なぜ?」に答える はじめての英語史』を紹介」 ([2019-04-11-1])
・ heldio 「#315. 和田忍先生との対談 Baugh and Cable の英語史概説書を語る」 (2022/04/10)
・ hellog 「#4133. OED による英語史概説」 ([2020-08-20-1])
[ かつて英語史に入門した「先輩」からのコメント ]
・ hellog 「#2470. 2015年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2016-01-31-1])
・ hellog 「#3566. 2018年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2019-01-31-1])
・ hellog 「#3922. 2019年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2020-01-22-1])
・ hellog 「#4661. 2021年度,英語史の授業を通じて何を学びましたか?」 ([2022-01-30-1])
[ とりわけ語源に関心がある方へ ]
・ hellog 「#3546. 英語史や語源から英単語を学びたいなら,これが基本知識」 ([2019-01-11-1])
・ hellog 「#3698. 語源学習法のすゝめ」 ([2019-06-12-1])
・ hellog 「#4360. 英単語の語源を調べたい/学びたいときには」 ([2021-04-04-1])
・ hellog 「#3381. 講座「歴史から学ぶ英単語の語源」」 ([2018-07-30-1])
・ hellog 「#600. 英語語源辞書の書誌」 ([2010-12-18-1])
[ とりわけ英語教育に関心がある方へ ]
・ heldio 「#310. 山本史歩子先生との対談 英語教員を目指す大学生への英語史のすすめ」 (2022/04/06)
・ hellog 「#4619. 「英語史教育」とは?」 ([2021-12-19-1])
・ hellog 「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1])
[ とりわけフランス語学習に関心がある方へ ]
・ heldio 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」 (2022/04/23)
・ heldio 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」 (2022/04/25)
・ heldio 「#368. 英語とフランス語で似ている単語がある場合の5つのパターン」 (2022/06/03)
・ hellog 「#4787. 英語とフランス語の間には似ている単語がたくさんあります」 ([2022-06-05-1])
・ heldio 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」 (2022/06/05)
・ heldio 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」 (2021/06/27)
2022-06-18 Sat
■ #4800. Lingua Franca Core への批判 [world_englishes][lingua_franca][elf][lfc][elt][standardisation][language_planning]
昨日の記事「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1]) で Lingua Franca Core (LFC) を導入した.LFC が提示された背景には,世界英語 (world_englishes) の時代にあって,世界の英語学習者,とりわけ EFL の学習者は,伝統的な英米標準変種やその他の世界各地で標準的とみなされている変種を習得するのではなく,ELF (= English as a Lingua Franca) や EIL (= English as an International Language) と称される変種を学習のターゲットとするのがよいのではないかという英語教育観が見え隠れする.世界の英語話者人口のおそらく半分以上は EFL 話者であり,その点では LFC を尊重する姿勢は EFL 学習者にとって「民主的」に見えるかもしれない.
しかし,LFC に対して批判的な意見もある.LFC も,伝統的な英米標準変種と同様に,単なる標準であるにとどまらず,規範となっていく恐れはないかと.規範の首を古いものから新しいものへとすげ替えるだけ,ということにならないだろうか.本当に民主的であろうとするならば,そもそも言語学者や教育者が人為的に「コア」として提示するということは矛盾をはらんだ営みではないか,等々.
Tomlinson (146) は,LFC のようなものを制定し「世界標準英語」の方向づけを行なおうとする行為は "arrogant" であると警鐘を鳴らしている.
But, are we not being rather arrogant in assuming that it is we as applied linguists, language planners, curriculum designers, teachers and materials developers who will determine the characteristics of a World Standard English? Is it not the users of English as a global language who will determine these characteristics as a result of negotiating interaction with each other? We can facilitate the process by making sure that our curricula, our methodology and our examinations do not impose unnecessary and unrealistic standards of correctness on our international learners, and by providing input and guiding output relevant to their needs and wants. But ultimately it is they and not us who will decide. To think otherwise is to be guilty of neo-colonist conceit and to ignore all that we know about how languages develop over time.
標準か規範かを巡るややこしい問題である.関連して「#1246. 英語の標準化と規範主義の関係」 ([2012-09-24-1]) を参照.
・ Tomlinson, Brian. "A Multi-dimensional Approach to Teaching English for the World" English in the World: Global Rules, Global Roles. Ed. Rani Rubdy and Mario Saraceni. London: Continuum, 2006. 130--50.
2022-06-13 Mon
■ #4795. 標準英語,世界英語,ELF の三すくみモデル [standardisation][world_englishes][elf][lingua_franca][elt][model_of_englishes]
昨日の記事「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1]) で取り上げたように Standard English か World Englishes かという対立の根は深い.とりわけ英語教育においては教育・学習のターゲットを何にするかという問題に直結するため,避けては通れない議論である.Rubdy and Saraceni は,この2つの対立に EIL/EFL という第3の要素を投入した三すくみモデルを考え,序章にて次のように指摘している (6) .
Towards simplifications: the teaching and learning of English
While an exhaustive description of the use of English is a futile pursuit, with regard to the teaching and learning of English in the classroom such complexities have necessarily to be reduced to manageable models. The language of the classroom tends to be rather static and disregardful of variation in style and register and, more conspicuously, of regional variation. One of the main issues in the pedagogy of English is indeed the choice of an appropriate model for the teaching of English as a foreign or second language. Here 'model' refers to regional variation, which is the main focus in the whole volume. In this sense, the choice is seen as lying between three principal 'rival' systems: Standard English (usually Standard British or Standard American English), World Englishes, and EIL/ELF (English as an International Language/English as a Lingua Franca).
ここでライバルとなるモデルとして言及されている Standard English, World Englishes, ELF は,それぞれ緩く ENL, ESL, EFL 志向の英語観に対応していると考えられる(cf. 「#173. ENL, ESL, EFL の話者人口」 ([2009-10-17-1])).
Standard English を中心に据える英語教育は,ENL 話者(とりわけ英米英語の話者)にとって概ね有利だろう.歴史的に威信が付されてきた変種でもあり「ブランド力」は抜群である,しかし,英語話者全体のなかで,これを母語・母方言とする話者は少数派であることに注意したい.
World Englishes は,主に世界各地の非英語母語話者,とりわけ ESL 話者が日常的に用いている変種を含めた英語変種の総体である.ESL 話者は英語話者人口に占める割合が大きく,今後の世界における英語使用のあり方にも重要な影響を及ぼすだろうと予想されている.昨今「World Englishes 現象」が注目されている理由も,ここにある.
ELF は,非英語母語話者,とりわけ EFL 話者の立場に配慮した英語観である.英語は国際コミュニケーションのための道具であるという,実用的,機能的な側面を重視した英語の捉え方だ.ビジネス等の領域で,非英語母語話者どうしが英語を用いてコミュニケーションを取る状況を念頭に置いている.理想的には,世界のどの地域とも直接的に結びついておらず,既存の個々の変種がもつ独自の言語項目からも免れているという中立的な変種である.EFL 話者は英語話者全体のなかに占める割合が最も大きく,この層に訴えかける変種として ELF が注目されているというわけだ.しかし,ELF は理念先行というきらいがあり,その実態は何なのか,人為的に策定すべきものなのかどうか等の問題がある.
日本の英語教育は,伝統的には明らかに Standard English 偏重だった.近年,様々な英語を許容するという World Englishes 的な見方も現われてきたとはいえ,目立っているとは言いがたい.一方,英語教育の目的としては ELF に肩入れするようになってきているとは言えるだろう.
今回の「三すくみ」モデルは,3つの英語観のいずれを採用するのかという三者択一の問題ではないように思われる.むしろ,3種類を各々どれくらいの割合でブレンドするかという問題なのではないか.
・ Rubdy, Rani and Mario Saraceni, eds. English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum, 2006.
2022-03-23 Wed
■ #4713. 言語教育エキスポ2020のシンポで「大母音推移」についてお話ししました [academic_conference][notice][slide][elt][gvs][heldio]
去る3月6日(日) 14:40--16:10 に,Zoom 開催の言語教育エキスポ2022のシンポジウム「英語史を英語教育に生かす」にてお話しさせていただきました.関係の先生方にはシンポジウムの準備から当日までたいへんお世話になりました.参加された皆様にも,たいへん貴重なご意見やご質問を賜わりました.ありがとうございます.
私がお話しした題目は「「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)」です.私自身が何か大母音推移 (gvs) についてオリジナルの新しい研究を試みたわけではまったくなく,あくまで学史を振り返っただけでした.予稿・概要はこちらからどうぞ.
何かの役に立つかもしれませんので,発表で用いたスライド資料を公開します.100年以上にわたって英語史研究者を魅了してきた「大母音推移」の行く末に思いをはせていただければと.以下はスライドの各ページへのリンクです.
1. 「大母音推移」の英語教育上の役割を再検討する(近年の研究動向を踏まえて)
2. 目次
3. 1. はじめに
4. GVS を母音四辺形で示すと
5. 2. GVS の研究史概観
6. 3. GVS の 5W1H
7. 具体的な単語例で
8. 4. GVS の「例外」
9. 4つの問題点
10. /ɛː/ > /eː/ > /iː/ の2段階の上げ
11. GVS 後に別途生じた音変化の結果
12. 近代以降のフランス借用語において
13. GVS は無強勢母音や短母音とは無縁
14. 派生語ペアにみる母音の長短
15. 派生語ペアにみる母音の長短の例外
16. 5. GVS の解体
17. GVS の貫徹度は方言によって異なる
18. 各々の母音変化は部分的には関連し合っているものの,独立した音変化である
19. GVS 進行表
20. 後期古英語期から後期近代英語期までの長期にわたる様々な母音変化の一部
21. 6. おわりに
22. 参考文献
23. 素朴な疑問 (1) 「nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」
24. 素朴な疑問 (2) 「なぜ friend はこの綴字でこの発音なのですか?」
ちなみに,先日の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 でも(散歩しながら)大母音推移についてしゃべったばかりなので紹介しておきたいと思います.大母音推移の威力と魅力を味わってみてください.
・ 「大母音推移(前編)」(2022年3月8日放送)
・ 「大母音推移(後編)」(2022年3月9日放送)
2022-01-31 Mon
■ #4662. 都立高入試の英語スピーキングテストを巡る問題 [elt][khelf][world_englishes][rp][walker][pronunciation]
昨年末,12月27日のことになりますが,朝日新聞 Edua に「どうなる中学・高校入試 都立高入試の英語スピーキングテスト 教員らが「導入反対」の記者会見」と題する記事が掲載されました.ゼミ生の1人がこの問題を紹介してくれまして,少々遅ればせながらもここ数日で内輪のフォーラム khelf で議論が活発化してきています.
いろいろと論点はあるのですが,とりわけ注目すべきは以下の点です(同記事より引用).
評価の信頼性については,どのような間違いがどれだけ減点されるか不透明だとし,特に都教委が示している採点基準にある「音声」の項目(3点満点)について疑問を呈した.この項目は,「母語の影響を非常に強く受けている」だと1点,「母語の影響を強く受けている」だと2点,「母語の影響を受けている場合があるが,概(おおむ)ね正しい」だと3点としている.法政大講師で新英語教育研究会長の池田真澄さんは「厳密な区別がつくとは思えない.日本語話者は日本語の影響は必ず受けており,気にしていたらまともに話なんてできない.世界には多様な英語があるのに,入試は別というのはおかしいのではないか」と話す.
ツッコミだしたらキリがないというのは,まさにこのことです.だからこそフォーラム内で盛り上がっているというわけで,ある意味でとてもよい論題となっています.(ただし,こちらのページより令和3年度のプレテスト採点基準では「母語の影響」に関する項目は削除されています.)
英語史研究者の立場から言えることは,発音を中心とする話し言葉に関する強い規範化は,いまだかつて例がないということです.18世紀の規範主義の時代の発音辞書についても,19世紀後半からの RP についても,あくまで目指すべき発音を示したものであり,今回の「公的な試験での点数化」という強さの規範化には遠く及びません(cf. 「#768. 変化しつつある RP の地位」 ([2011-06-04-1]),「#1456. John Walker の A Critical Pronouncing Dictionary (1791)」 ([2013-04-22-1]),「#3356. 標準発音の整備は18世紀後半から」 ([2018-07-05-1])).話し言葉について標準化・規範化し得る水準は,せいぜい "focused" にとどまり "fixed" を目指すことは現実には不可能です (cf. 「#3207. 標準英語と言語の標準化に関するいくつかの術語」 ([2018-02-06-1])) .そのような目標を,せめて試験では何とか実現したいということなのでしょうか.
また,現代世界の "World Englishes" では,多様な英語の発音が行なわれているという事実があります.教育上,参照すべき英語変種や発音を定めることは必要です.しかし,一方で他の変種や発音の存在を認めることも必要です.両方の必要性に目配りすべき状況において,上記の採点基準のような,一方にのみ振り切った方針を取るのは適切ではないと考えます.
本ブログの読者の皆さんも,この問題について考えてみてはいかがでしょうか.
2021-12-19 Sun
■ #4619. 「英語史教育」とは? [hel][hel_education][elt]
私は英語史を学習し,研究し,教える立場にある.教える立場から「英語史教育」という表現をしばしば用いるのだが,この表現は実際には多義的だと考えている.通常は「英語史を教えること」と解釈されるが,「英語史で(何か別のことを)教える」と解釈することもできる.後者の典型は「英語史の知見を活用して英語を教える」ことだろう.教わる立場からすれば「英語史を教わるのか」あるいは「英語史で教わるのか」という違いである.
この2つの区別を念頭に置きつつ,「誰が,何を通じて,何を,誰に,何のために,教えるのか」という文の各項に語句を流し込んでいくと,私が思いつく限り,議論に値するとおぼしき組み合わせが5種類あった.
(1) 英語史研究者が 英語史を 英語史専攻学生に 英語史研究のために 教える.
(2) 英語史研究者が 英語史を 英語教員に 英語教育のために 教える.
(3) 英語史研究者が 英語史を 英語学習者に 英語学習のために 教える.
(4) 英語史研究者が 英語史を 一般の人々に 教養のために 教える.
(5) 英語教員が 英語史を通じて 生徒・学生に 英語を 教える.
英語史研究者でもあり英語教員でもある私の私的な見解にすぎないので,他にも様々な組み合わせの可能性があるだろう(あれば教えてください).私自身としては5つのすべてについて多かれ少なかれ何らかの教育経験がある.本ブログや「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」も,ランダムではあるが,およそ5つのすべてに関わっている.とはいえ,普段の活動の基本は (1), (3), (4) 辺りに置いていると自己分析している.
(4) で「教養」という表現を敢えて用いたが,これが指す範囲はきわめて広い.言語,文学,歴史,文化,思考法,等々.英語史が専門科目であると同時に教養科目でもあることについては,「#3641. 英語史のすゝめ (1) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-16-1]),「#3642. 英語史のすゝめ (2) --- 英語史は教養的な学問領域」 ([2019-04-17-1]) を参照されたい.また「#4329. 「英語史の知見を活かした英語教育」について参考文献をいくつか」 ([2021-03-04-1]) もご覧ください.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow