2024-05-29 Wed
■ #5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][grimms_law][verners_law][consonant][stress][phonetics][loan_word][french][latin][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
これまでに第1回「語源辞典でたどる英語史」を4月27日(土)に,第2回「英語語彙の歴史を概観する」を5月8日(土)に開講しましたが,それぞれ驚くほど多くの方にご参加いただき盛会となりました.ご関心をお寄せいただき,たいへん嬉しく思います.
第3回「英単語と「グリムの法則」」は来週末,6月8日(土)の 17:30--1900 に開講されます.シリーズを通じて,対面・オンラインによるハイブリッド形式での開講となり,講義後の1週間の「見逃し配信」サービスもご利用可能です.シリーズ講座ではありますが,各回はおおむね独立していますし,「復習」が必要な部分は補いますので,シリーズ途中からの参加でも問題ありません.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.

2回かけてのイントロを終え,次回第3回は,いよいよ英語語彙史の各論に入っていきます.今回のキーワードはグリムの法則 (grimms_law) です.この著名な音規則 (sound law) を理解することで,英語語彙史のある魅力的な側面に気づく機会が増すでしょう.グリムの法則の英語語彙史上の意義は,思いのほか長大で深遠です.英語語彙学習に役立つことはもちろん,印欧語族の他言語の語彙への関心も湧いてくるだろうと思います.『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする語源辞典や,一般の英語辞典も含め,その使い方や読み方が確実に変わってくるはずです.
講座ではグリムの法則の関わる多くの語源辞典で引き,記述を読み解きながら,実践的に同法則の理解を深めていく予定です.どんな単語が取り上げられるかを予想しつつ講座に臨んでいただけますと,ますます楽しくなるはずです.『英語語源辞典』をお持ちの方は,巻末の「語源学解説」の 3.4.1. Grimm の法則,および 3.4.2. Verner の法則 を読んで予習しておくことをお薦めします.
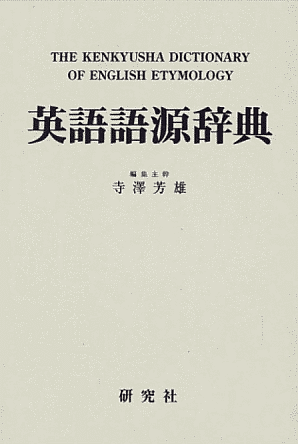
参考までに,本シリーズに関する hellog の過去記事へのリンクを以下に張っておきます.第3回講座も,多くの皆さんのご参加をお待ちしております.
・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])
・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])
・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])
(以下,後記:2024/05/30(Thu))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2024-05-27 Mon
■ #5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書かせていただいています.先日『ふらんす』6月号が刊行されました.今回で第3回となる記事のタイトルは「英語に借用された最初期の仏単語」です.以下の小見出しのもと,2頁ほどの読み物となっています.
・ フランス語との腐れ縁とその馴れ初め
・ 最初の仏借用語は古英語末期から
・ ノルマン征服後の2世紀は意外と地味
・ フランス語に置き換えられた法律用語
英語語彙にフランス語からの借用語が多く含まれていることはよく知られていますが,そもそも英仏語の言語接触 (contact) にはどのような背景があったのでしょうか.今回の記事では,両言語の出会いと,言語接触の最初期の状況を記述しました.最初期にはフランス語からの影響は意外と限定的だったことなどが,主たる話題となっています.
フランス語と英語史を掛け合わせた話題は豊富にあり,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも多く取り上げてきました.参考までに,関連する配信回をいくつか挙げておきます.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」
・ 「#1087. 英語の料理用語はフランス語とともにあり」
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第3回 英語に借用された最初期の仏単語」『ふらんす』2024年6月号,白水社,2024年5月23日.52--53頁.
2024-05-22 Wed
■ #5504. 接尾辞 -ive を OED で読む [etymology][suffix][french][oed][loan_word][oed][adjective][word_formation][noun][conversion][productivity]
「#2032. 形容詞語尾 -ive」 ([2014-11-19-1]) で取り上げた形容詞(およびさらに派生的に名詞)を作る接尾辞 (suffix) に再び注目したい.OED の -ive (SUFFIX) の "Meaning & use" をじっくり読んでみよう.
Forming adjectives (and nouns). Formerly also -if, -ife; < French -if, feminine -ive (= Italian, Spanish -ivo):--- Latin īv-us, a suffix added to the participial stem of verbs, as in act-īvus active, pass-īvus passive, nātīv-us of inborn kind; sometimes to the present stem, as cad-īvus falling, and to nouns as tempest-īvus seasonable. Few of these words came down in Old French, e.g. naïf, naïve:--- Latin nātīv-um; but the suffix is largely used in the modern Romanic languages, and in English, to adapt Latin words in -īvus, or form words on Latin analogies, with the sense 'having a tendency to, having the nature, character, or quality of, given to (some action)'. The meaning differs from that of participial adjectives in -ing, -ant, -ent, in implying a permanent or habitual quality or tendency: cf. acting adj., active adj., attracting adj., attractive adj., coherent adj., cohesive adj., consequent adj., consecutive adj. From their derivation, the great majority of these end in -sive and -tive, and of these about one half in -ative suffix, which tends consequently to become a living suffix, as in talk-ative, etc. A few are formed immediately on the verb stem, esp. where this ends in s (c) or t, thus easily passing muster among those formed on the participial stem; such are amusive, coercive, conducive, crescive, forcive, piercive, adaptive, adoptive, denotive, humective; a few are from nouns, as massive. In costive, the -ive is not a suffix.
Already in Latin many of these adjectives were used substantively; this precedent is freely followed in the modern languages and in English: e.g. adjective, captive, derivative, expletive, explosive, fugitive, indicative, incentive, invective, locomotive, missive, native, nominative, prerogative, sedative, subjunctive.
In some words the final consonant of Old French -if, from -īvus, was lost in Middle English, leaving in modern English -y suffix1: e.g. hasty, jolly, tardy.
Adverbs from adjectives in -ive are formed in -ively; abstract nouns in -iveness and -ivity suffix.
OED の解説を熟読しての発見としては:
(1) -ive が接続する基体は,ラテン語動詞の分詞幹であることが多いが,他の語幹や他の品詞もあり得る.
(2) ラテン語で作られた -ive 語で古フランス語に受け継がれたものは少ない.ロマンス諸語や英語における -ive 語の多くは,かつての -ivus ラテン単語群をモデルとした造語である可能性が高い.
(3) 分詞由来の形容詞接辞とは異なり,-ive は恒常的・習慣的な意味を表わす.
(4) -sive, -tive の形態となることが圧倒的に多く,後者に基づく -ative はそれ自体が接辞として生産性を獲得している.
(5) -ive は本来は形容詞接辞だが,すでにラテン語でも名詞への品詞転換の事例が多くあった.
(6) -ive 接尾辞末の子音が脱落し,本来語由来の形容詞接尾辞 -y と合流する単語例もあった.
上記の解説の後,-ive の複合語や派生語が951種類挙げられている.私の数えでこの数字なのだが,OED も網羅的に挙げているわけではないので氷山の一角とみるべきだろう.-ive 接尾辞研究をスタートするためには,まずは申し分ない情報量ではないか.
2024-05-04 Sat
■ #5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][loan_word][borrowing][word_formation][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
第1回「語源辞典でたどる英語史」は,4月27日(土)の 17:30--19:00 に開講され,おかげさまで盛況のうちに終了しました.こちらの回については,本ブログでも「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1]) および「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1]) で事前・事後に取り上げました.
第2回「英語語彙の歴史を概観する」は2週間後の5月18日(土)の 17:30--1900 に開講される予定です.対面・オンラインによるハイブリッド開講で,「見逃し配信」サービスもご利用可能です.第1回を逃した方も問題なくご参加いただけます.ご関心のある方は,ぜひこちらよりお申し込みください.

第2回は,シリーズ全体のイントロとして,1500年以上にわたる英語語彙史を俯瞰してみます.今後のシリーズ展開に向けて,英語の語彙の変遷について大きな見通しを得ることが目標です.英語語彙史を概観していく過程で,英語史の各時代からいくつかのキーワードをピックアップして『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする各種の英語語源辞典を参照します.同辞典をお持ちの方は,ぜひお手元にご用意しつつ,講座にご参加ください.どんな単語が取り上げられるかを予想しながら講座に臨んでいただければ.
(以下,後記:2024/05/14(Tue))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2024-04-25 Thu
■ #5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』に「英語史で眺めるフランス語」というシリーズタイトルで連載記事を寄稿しています.一昨日『ふらんす』5月号が刊行されました.シリーズ第2回の記事は「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」です.今回の記事は以下の小見出しで構成しています.
・ 単語が似ているのにはワケがある
・ 借用の方向に基づく3つのパターン
・ 言語学的な観点に基づく3つのパターン
・ 似ている単語を見つけたときには要注意
仏英語には似ている単語が多く見られます.背景には1066年のノルマン征服とその後の歴史があります.しかし,理由はこれに尽きません.歴史的および言語学的に検討すると,両言語に類似単語が存在する背景には6つのパターンがあるのでス.今回の記事では,具体例を交えつつ,この点を解説しています.
新年度に新しい外国語としてフランス語を学び始めている方も多いかと思います.そのなかには,すでに英語について知識のある方も少なくないはずです.英語とフランス語の学習は,連動させるのが吉です.その上で英語史の知見も連動させると,学び全体に何倍もの相乗効果が生み出されることを強調したいと思います.この観点から,以下の Voicy 配信回もお聴きいただければ.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
シリーズの初回記事については,hellog 記事「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1]) で取り上げていますので,そちらもご覧ください.
(以下,後記:2024/05/08(Wed))
5月8日に heldio で「#1073. 『ふらんす』5月号で「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」を書いています」を配信しました.
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第2回 なぜ仏英語には似ている単語があるの?」『ふらんす』2024年5月号,白水社,2024年4月23日.62--63頁.
2024-04-18 Thu
■ #5470. 中英語における職業を表わす by-name の取り扱い [onomastics][personal_name][name_project][methodology][eme][by-name][latin][french][med][evidence][loan_word][occupational_term]
「#5452. 英語人名史における by-name と family name の違い」 ([2024-03-31-1]) などで取り上げてきた,英語人名を構成する by-name の歴史研究について.初期中英語期に by-name を付ける慣習が徐々に発達していたとき,典型的な名付けのパターンの1つが職業名 (occupational terms) を利用するものだった.この方面の研究は,尽くされてはいないものの,それなりに知見の蓄積がある.Clark (294--95) は,カンタベリーにおける by-name を調査した論文のなかで,文証された by-name の解釈にまつわる難題に触れている.証拠をそのまま信じることは必ずしもできない理由が多々あるという.
The simplest of these Canterbury surnames offer supplementary records, mainly antedatings, of straightforward occupational terms. Yet all is not wholly straightforward. To begin with, we cannot be sure whether the occupational terms used in administrative documents were in fact all current as surnames, that is, in daily use among neighbours, or whether some were supplied by the scribes as formal specifiers, just as occupations and addresses are in legal documents of the present day. Nor can we be sure in what form neighbours would have used such terms as they did. With those examples that are latinized --- a proportion varying in the present material from three-quarters to nine-tenths --- scribal intervention is patent, although sometimes reconstruction of the vernacular base seems easy (such forms, and other speculative cases, are cited in square brackets). With those given in a French form matters are more complex. On the one hand, scribes had a general bias away from English and towards French, as though the latter were, as has been said, 'a sort of ignoble substitute for Latin'; therefore, use of a French occupational term guarantees neither its currency in the English speech of the time nor, alternatively, any currency of French outside the scriptorium: in so far as such terms appear neither in literary sources nor as modern surnames MED is justified in excluding them. On the other hand, many 'French' terms were adopted into English very early; use of these would by no means imply currency of French as such, either in the community at large or in the scriptorium itself.
証拠解釈が難題である背景は多様だが,とりわけラテン語やフランス語が関わってくる状況が厄介である.この時代の税金名簿などに記されている人名はラテン語化されているものが多く,英語名はその陰に隠されてしまっている.また,フランス語で書かれていることも多く,問題の職業名そのものがフランス語由来の場合,それがすでに英語に同化している単語なのか,それともフランス単語のままなのかの判断も難しい.
職業を表わす by-name は,そもそも文献学的に扱いにくい素材なのである.そして,これは職業を表わす by-name に限らず,中英語の固有名全般に関わる厄介な事情でもある.
・ Clark, Cecily. "Some Early Canterbury Surnames." English Studies 57.4 (1976): 204--309.
2024-04-15 Mon
■ #5467. OED の3月アップデートで日本語からの借用語が23語加わった! [oed][japanese][loan_word][notice][tufs][world_englishes]
OED Online は3ヶ月に一度のペースでアップデートがなされています.最新のアップデートは先月(2024年3月)のもので,Updates の一覧よりアクセスできます.
今回のアップデートを特徴づけるのは,なんと日本語からの借用語です.関連記事として "Words from the land of the rising sun: new Japanese borrowings in the OED" が公開されていますが,これは必読です.
今回 OED のアップデートで日本語からの借用語が注目されたのは,たまたまというわけではなく,とある背景があったようです.上記記事によると,OED 編纂チームが,昨年建学150周年を迎えた東京外国語大学(←私の出身大学です,おめでとう!)のパートナー研究者とコラボし,その研究成果に基づいて,これらの日本語単語を収録したということのようです.今回だけで23語の日本語単語が OED に新しく収録されるに至ったのですが,この数は1回のアップデートとしてはなかなかのものです.その23語とは,具体的には以下の通り.
donburi (n.), hibachi (n.), isekai (n.), kagome (n.), karaage (n.), katsu (n.), katsu curry (n.), kintsugi (n.), kirigami (n.), mangaka (n.), okonomiyaki (n.), omotenashi (n.), onigiri (n.), santoku (n.), shibori (n.), takoyaki (n.), tokusatsu (n.), tonkatsu (n.), tonkatsu sauce (n.), tonkotsu (n./1), tonkotsu (n./2), washi tape (n.), yakiniku (n.)
日本語母語話者としてはツッコミどころが満載で楽しいです.じっくり掘ってみてください.
・ tonkotsu という語はなんと2つの見出しが立っている.我々の知る「豚骨」(スープ,ラーメン)は tonkotsu2 だが,別に tonkotsu1 もあるという.皆さん,後者は何のことだか分かりますか?
・ donburi の語源解説で,日本語「どんぶり」は「ざぶんと」を意味した副詞用法と関係するのではないかとあり,日本語の語源まで学べてしまうスゴさが.
・ katsu 「カツ」は "boomerang word"
・ kintsugi 「金継ぎ」が,工芸技術の意にとどまらず美学的世界観へと昇華されていた!
・ isekai 「異世界」と tokusatsu 「特撮」は,さすが日本のサブカルというべき採録.
OED における日本語借用語の話題としては,OED 公式の以下の記事も参照.
・ Words of Japanese origin
・ From anime to zen: Japanese words in the OED
2024-03-28 Thu
■ #5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][voicy][heldio][false_friend]

*
「日本で唯一のフランス語・フランス文化専門の総合月刊誌」という謳い文句で白水社より刊行されている『ふらんす』.先日発行された『ふらんす』2024年4月号(新年度開始号)より,12ヶ月にわたり「英語史で眺めるフランス語」というシリーズタイトルで2ページの連載記事をお届けします.
初回となる今回は「英語にはフランス語風味がたくさん」と題して,次のような小見出しで構成しています.
・ なぜ英語の歴史?
・ 1066年の衝撃
・ 英語語彙のなかのフランス語単語
・ 語彙以外へのフランス語の影響
『ふらんす』の誌上で英語(史)とは何事か,とみる向きもあるかと思います.そもそも白水社の編集者の方より連載執筆のお声がけをいただいた際の私自身の感想が「なぜ?」でした.私は,本ブログでもその他の媒体でも英語とフランス語の密接な関わりについて,主に英語史の観点から様々に発信してきました.試しに本ブログの french タグをクリックしてみると,実に313の記事がヒットします.それくらい英仏語の歴史的関係を強調してきたわけですが,まさかフランス語(文化)を専門とする雑誌に英語史に関する文章を載せられる日が来るとは思いも寄りませんでした.お話しをいただいたときには,上記のようにやや狼狽しつつも「チャンス!」と叫びつつ,謹んでお引き受けした次第です.
ご関心のある方々には,ぜひ1年間お付き合いいただければと存じます.初回はとりわけ最初の小見出し「なぜ英語の歴史?」にご注目ください.
この連載を機に,私自身もフランス語とフランス語史をもっと勉強しなければと気を引き締めています.フランス語史といえば,「三省堂のことばのコラム」より「歴史で謎解き!フランス語文法(フランス語教育 歴史文法派)」がお薦めです.現時点で第46回まで続いている長寿シリーズです.そちらにも英語(史)とフランス語(史)の関係に注目したコラムがいくつかあります.例えば,第18回「なぜ英語とフランス語は似ているの?」は,今回の『ふらんす』に掲載した記事と見事にシンクロします(cf. 「#4175. 「なぜ英語とフランス語は似ているの?」の記事紹介」 ([2020-10-01-1])).
1年間続く連載「英語史で眺めるフランス語」では,英語史とフランス語はとにかく相性がよいということを力説し続けようと思っています.「英語(史)とフランス語はペアでとらえるのが吉」,このことを訴えていきます.
年度替わりの時期で,新年度からフランス語学習に挑戦しようという方も少なくないかと思います.そのような方には,上記連載のみならず,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」より以下の3本をお薦めしておきましょう.ぜひこちらもお聴きいただければ.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
(以下,後記:2024/04/02(Tue))
4月1日に heldio で「#1036. 月刊『ふらんす』で英語史の連載を始めています」を配信しました.
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第1回 英語にはフランス語風味がたくさん」『ふらんす』2024年4月号,白水社,2024年3月23日.62--63頁.
2024-03-12 Tue
■ #5433. フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce へ [etymological_respelling][french][latin][loan_word][waseieigo][borrowing][analogy]
seduce (誘惑する)の語源はラテン語の動詞 sēdūcere に遡る.接頭辞 sē- は "away; without" ほどを意味し,基体の dūcere は "to lead" の意味である.合わせて「外へ導く」となり,「悪の道に導く;罪に導く;そそのかす;誘惑する」などの語義を発達させた.
現代英語では「(性的に)誘惑する」の語義が基本だが,15世紀に初めて英語に入ってきたときには「自らの義務を放棄するように説得する」という道徳的な語義が基本だった.OED によると,初出は Caxton からの次の文である.
1477 Zethephius seduysed [French seduisoit] the peple ayenst him by tyrannye al euydente. (W. Caxton, translation of R. Le Fèvre, History of Jason (1913) 104)
この初出での語形は seduysed となっており,当時のフランス語の seduisoit に引きつけられた綴字となっている.
しかし,以下に挙げるもう1つの最初期の例文では,同じ Caxton からではあるが,語形は seduce となっている.
a1492 He [sc. the deuyll] procureth to a persone that he haue all the eases of his bodye, and may not begyle and seduce [Fr. seduire] hym by delectacyons and worldly pleasaunces. (W. Caxton, translation of Vitas Patrum (1495) ii. f. cclv/1
これ以降の例文ではすべて現代的な seduce が用いられている.つまり最初例のみフランス語形を取り,それ以後はすべてラテン語形をとっていることになる.
英語に借用されてきたのが,中英語期の最末期,あるいは初期近代英語期への入り口に当たる時期であることを考えると,英単語としての seduce の綴字は,ラテン語形を参照した語源的綴字 (etymological_respelling) の1例と見ることもできるかもしれない.当初はフランス語形を模していたものが,後からモデルをラテン語形に乗り換えた,という見方だ.あるいは,すでに英語に借用されていた adduce, conduce, deduce, educe, introduce, produce, reduce, subduce などの -duce 語からの類推作用が働いたのかもしれない.その場合には,英語内部で作り出された英製羅語の1例とみなせないこともない.
フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce への乗り換えはあくまで小さな変化にすぎないが,英語史的には深掘りすべき側面が多々ある.
2024-02-26 Mon
■ #5418. A Dictionary of Japanese Loanwords の前書きを読んでみよう [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][dictionary][inohota][notice][oed]
昨日,「いのほたチャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)の最新動画が公開されました.「最初の日本語由来の英語は?いまや hikikomori や enjo kosai も!---外来語の諸相-「ナイター」「柿」【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル 第209回】」です.英語に入った日本語単語の歴史を概説しています.馴染み深い日本語が多く出てくるので,入りやすい話題かと思いますが,れっきとした英語史の話題です.
動画内では典拠として OED のほか,A Dictionary of Japanese Loanwords というおもしろい辞書を用いており,紹介もしています.この辞書については,最近の hellog でも「#5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書」 ([2024-02-18-1]) にて取り上げていますので,そちらもご一読ください.

同辞書の冒頭の説明書きを読んでみましょう (ix--x) .
A Dictionary of Japanese Loanwords is a lexical index of terms borrowed from the Japanese language that are listed in standard English dictionaries and in publications that analyze new words. Therefore, this dictionary covers both the loanwords that have withstood the test of time and those whose test has just started.
American standard dictionaries keep records of borrowings from the Japanese language; most of them, however, do not furnish quotations. A Dictionary of Japanese Loanwords adds a special contribution by providing illustrative quotations from many entries. These quotations were collected from books, newspapers, magazines, advertisements, and databases, all of which were published or distributed in the United States between 1964 and 1995. They give details about the entry, demonstrate how it is used in a natural context, and indicate the degree of its assimilation into American English.
Recent studies report that Japanese is the second most productive source of new loanwords to English, which indicates that the English-speaking world is paying attention to Japan more closely than ever before. The entries and illustrative quotations present the aspects of Japan that Americans have been exposed to and have adopted. Karaoke, for example, first appeared in English in 1979, when English-speaking societies observed and read about a karaoke fever in Japan. Today, Americans find themselves enjoying karaoke. Karaoke showcase, a weekly television talent contest, appeared on 120 U.S. stations in June 1992. A phenomenon like this is shown in this book in the form of lexical entries.
The impact that Japan has made on America covers all aspects of life: aesthetics, architecture, arts and crafts, astronomy, biology, botany, business management, clothing, economics, education, electronics, fine art, food and food technology, medicine, oceanography, pathology, philosophy, physics, politics, religion, sports, technology, trade, weaponry, zoology, and so on. Some entries are not accompanied by a quotation; nevertheless, when dictionaries record words they indicate that these words are somehow linked to people's everyday lives. A Dictionary of Japanese Loanwords is also meant to be fun to read. I hope that it will provide the meaning for Japanese words the reader has come across on many occasions, and that it will be an occasion for happy browsing.
この辞書の魅力は,何よりも引用文が豊富なところ.まさに "happy browsing" に最適な「読める辞書」です.
・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.
2024-02-18 Sun
■ #5410. A Dictionary of Japanese Loanwords --- 英語に入った日本語単語の辞書 [review][loan_word][japanese][lexicography][lexicology][false_friend][semantic_change][oed][dictionary]

眺めているだけでおもしろい,決して飽きない辞書の紹介です.Toshie M. Evans 氏により編集された,英語に入った日本語単語を収録する辞書 A Dictionary of Japanese Loanwords です.1997年に出版されています.この hellog でも「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1]) で参照した通りですが,820語の日本語由来の「英単語」がエントリーされています.単に見出し語が列挙されているだけでなく,多くの語には,1964年から1995年の間にアメリカで出版された資料から取られた例文が付されており,たいへん貴重です.
雰囲気を知っていただくために「火鉢」こと hibachi のエントリーを覗いてみましょう.
hibachi [hibɑːtʃi] n. pl. -chi or s, 1. a brazier used indoors for burning charcoal as a source of heat.
In an old-style shop, the selling activity took place in a front room on a tatami (straw mat) platform about one foot above the ground level. Customers removed their shoes, warmed themselves by sitting on the floor next to a hibachi (earthen container with glowing embers) and were served tea and sweets. (Places, Summer 1992, p. 81)
2. a portable brazier with a grill, used for outdoor cooking.
Double stamped steel hibachi, lightweight & portable. Goes with you to the backyard or even the beach for tasty cookouts? (Los Angeles Times, Jul. 7, 1985, Part I, p. 13, advertisement)
[< hibachi < hi fire + bachi < hachi pot] 1874: hebachi 1863 (OED)
語義1は日本の「火鉢」そのものなのですが,語義2の「バーベキューコンロ」にはたまげてしまいますね.この語とその意味変化については「#4386. 「火鉢」と hibachi, 「先輩」と senpai」 ([2021-04-30-1]) でも扱っているので,ご参照ください.
日本語から英語に入った借用語に関心のある方は,ぜひ以下の記事もどうぞ.
・ 「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1])
・ 「#45. 英語語彙にまつわる数値」 ([2009-06-12-1])
・ 「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1])
・ 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])
・ 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])
・ 「#5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点)」 ([2023-02-28-1])
・ 「#5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題」 ([2023-05-31-1])
・ Toshie M. Evans, ed. A Dictionary of Japanese Loanwords. Westport, Conn.: Greenwood, 1997.
2024-02-04 Sun
■ #5396. フランス語とラテン語からの大量の語彙借用は英語の何をどう変えたか? [lexicology][french][latin][loan_word][word_formation][lexical_stratification][contact][semantic_change][derivation]
英語語彙史においてフランス語やラテン語の影響が甚大であることは,折に触れて紹介してきた.何といっても借用された単語の数が万単位に及び,大きい.しかし,数や量だけの影響にとどまらない.大規模借用の結果として,英語語彙の質も,主に中英語期以降に,著しく変化した.その質的変化について,Durkin (224) が重要な3点を指摘している.
・ The derivational morphology of English was (eventually) completely transformed by the accommodation of whole word families of related words from French and Latin, and by the analogous expansion of other word families within English exploiting the same French and Latin derivational affixes (especially suffixes).
・ Not only was a good deal of native vocabulary simply lost, but many other existing words showed meaning changes (especially narrowing) as semantic fields were reshaped following the adoption of new words from French and Latin.
・ The massive borrowing of less basic vocabulary, especially in a whole range of technical areas, led to extensive and enduring layering or stratification in the lexis of English, and also to a high degree of dissociation in many semantic fields (e.g. the usual adjective corresponding in meaning to hand is the etymologically unrelated manual)
1点目は,単語の家族 (word family) や語形成 (word_formation) そのものが,本来の英語的なものからフランス・ラテン語的なものに大幅に入れ替わったことに触れている.2点目は,本来語が死語になったり,意味変化 (semantic_change) を経たりしたものが多い事実を指摘している.3点目は,比較的程度の高い語彙の層が新しく付け加わり,語彙階層 (lexical_stratification) が生じたことに関係する.
単純化したキーワードで示せば,(1) 語形成の変質,(2) 意味変化,(3) 語彙階層の発生,といったところだろうか.これらがフランス語・ラテン語からの大量借用の英語語彙史上の質的意義である.
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.
2023-09-21 Thu
■ #5260. 喜びに満ちた delicious の同根類義語 [eebo][synonym][me][cognate][lexicology][borrowing][loan_word][latin][french][oed][thesaurus][htoed][voicy][heldio]
今週の月・火と連続して,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時に配信)にて delicious とその類義語の話題を配信しました.
・ 「#840. delicious, delectable, delightful」
・ 「#841. deleicious の歴史的類義語がたいへんなことになっていた」
かつて「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) と題する記事を書いたことがあり,これとも密接に関わる話題です.ラテン語動詞 dēlectāre (誘惑する,魅了する,喜ばせる)に基づく形容詞が様々に派生し,いろいろな形態が中英語期にフランス語を経由して借用されました(ほかに,それらを横目に英語側で形成された同根の形容詞もありました).いずれの形容詞も「喜びを与える,喜ばせる,愉快な,楽しい;おいしい,美味の,芳しい」などのポジティヴな意味を表わし,緩く類義語といってよい単語群を構成していました.
しかし,さすがに同根の類義語がたくさんあっても競合するだけで,個々の存在意義が薄くなります.なかには廃語になるもの,ほとんど用いられないものも出てくるのが道理です.
Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (= HTOED) で調べてみたところ,歴史的には13の「delicious 語」が浮上してきました.いずれも語源的に dēlectāre に遡りうる同根類義語です.以下に一覧します.
・ †delite (c1225--1500): Very pleasant or enjoyable; delightful.
・ delightable (c1300--): Very pleasing or appealing; delightful.
・ delicate (a1382--1911): That causes pleasure or delight; very pleasing to the senses, luxurious; pleasurable, esp. in a way which promotes calm or relaxation. Obsolete.
・ delightful (a1400--): Giving or providing delight; very pleasant, charming.
・ delicious (c1400?-): Very pleasant or enjoyable; very agreeable; delightful; wonderful.
・ delectable (c1415--): Delightful; extremely pleasant or appealing, (in later use) esp. to the senses; very attractive. Of food, drink, etc.: delicious, very appetizing.
・ delighting (?a1425--): That gives or causes delight; very pleasing, delightful.
・ †delitous (a1425): Very pleasant or enjoyable; delightful.
・ delightsome (c1484--): Giving or providing delight; = delightful, adj. 1.
・ †delectary (?c1500): Very pleasant; delightful.
・ delighted (1595--1677): That is a cause or source of delight; delightful. Obsolete.
・ dilly (1909--): Delightful; delicious.
・ delish (1915--): Extremely pleasing to the senses; (chiefly) very tasty or appetizing. Sometimes of a person: very attractive. Cf. delicious, adj. A.1.
廃語になった語もあるのは確かですが,意外と多くが(おおよそ低頻度語であるとはいえ)現役で生き残っているのが,むしろ驚きです.「喜びを与える,愉快な;おいしい」という基本義で普通に用いられるものは,実際的にいえば delicious, delectable, delightful くらいのものでしょう.
このような語彙の無駄遣い,あるいは類義語の余剰といった問題は,英語では決して稀ではありません.関連して,「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]),「#4969. splendid の同根類義語のタイムライン」 ([2022-12-04-1]),「#4974. †splendidious, †splendidous, †splendious の惨めな頻度 --- EEBO corpus より」 ([2022-12-09-1]) もご覧ください.
2023-05-31 Wed
■ #5147. 「ゆる言語学ラジオ」出演第3回 --- 『ジーニアス英和辞典』第6版を読む回で触れられた諸々の話題 [yurugengogakuradio][notice][youtube][genius6][suffix][prefix][heldio][voicy][hel_contents_50_2023][khelf][consonant][japanese][loan_word][spelling][terminology]
「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ
(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および
(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選
(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」
(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群
をご覧ください.
昨日5月30日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.ゲストとして出演させていただきまして第3回目となります(ぜひ第1回と第2回もご視聴ください).今回は「英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した#234」です.
昨秋出版された『ジーニアス英和辞典』第6版にて,新設コラム「英語史Q&A」を執筆させていただきました(同辞典に関連する hellog 記事は genius6 よりどうぞ).今回の出演はその関連でお招きいただいた次第です.水野さん,堀元さんとともに同辞典をペラペラめくっていき,何かおもしろい項目に気づいたら,各々がやおら発言し,そのままおしゃべりを展開するという「ゆる言語学ラジオ」らしい企画です.雑談的に触れた話題は多岐にわたりますが,hellog や heldio などで取り上げてきたトピックも多いので,関連リンクを張っておきます.
[ 接尾辞 -esque (e.g. Rubenesque, Kafkaesque) ]
・ hellog 「#216. 人名から形容詞を派生させる -esque の特徴」 ([2009-11-29-1])
・ hellog 「#935. 語形成の生産性 (1)」 ([2011-11-18-1])
・ hellog 「#3716. 強勢位置に影響を及ぼす接尾辞」 ([2019-06-30-1])
[ 否定の接頭辞 un- (un- ゾーンの語彙) ]
・ hellog 「#4227. なぜ否定を表わす語には n- で始まるものが多いのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-22-1])
・ 大学院生による英語史コンテンツ 「#36. 語源の向こう側へ ~ in- と un- と a- って何が違うの?~」(目下 khelf で展開中の「英語史コンテンツ50」より)
[ カ行子音を表わす3つの文字 <k, c, q> ]
・ hellog 「#1824. <C> と <G> の分化」 ([2014-04-25-1])
・ heldio 「#255. カ行子音は c, k, q のどれ?」 (2022/02/10)
[ 日本語からの借用語 (e.g. karaoke, karate, kamikaze) ]
・ hellog 「#4391. kamikaze と bikini --- 心がザワザワする語の意味変化」 ([2021-05-05-1])
・ hellog 「#142. 英語に借用された日本語の分布」 ([2009-09-16-1])
・ hellog 「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1])
・ hellog 「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1])
・ heldio 「#60. 英語に入った日本語たち」 (2021/07/31)
[ 動詞を作る en- と -en (e.g. enlighten, strengthen) ]
・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])
・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])
・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])
・ heldio 「#62. enlighten ー 頭にもお尻にも en がつく!」 (2021/08/02)
[ 文法用語の謎:tense, voice, gender ]
・ heldio 「#644. 「時制」の tense と「緊張した」の tense は同語源?」 (2023/03/06)
・ heldio 「#643. なぜ受動態・能動態の「態」が "voice" なの?」 (2023/03/05)
・ hellog 「#1520. なぜ受動態の「態」が voice なのか」 ([2013-06-25-1])
・ hellog 「#1449. 言語における「範疇」」 ([2013-04-15-1])
[ minister の語源 ]
・ 「#4209. なぜ minister は mini- なのに「大臣」なのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-04-1])
[ コラム「英語史Q&A」 ]
・ hellog 「#4892. 今秋出版予定の『ジーニアス英和辞典』第6版の新設コラム「英語史Q&A」の紹介」 ([2022-09-18-1])
・ heldio 「#532. 『ジーニアス英和辞典』第6版の出版記念に「英語史Q&A」コラムより spring の話しをします」 (2022/11/14)
・ hellog 「#4971. often の t は発音するのかしないのか」 ([2022-12-06-1])
2023-05-07 Sun
■ #5123. 「単語の語源を言い当てる」とは何か? --- 本日開幕した「語源バトル」のルールをめぐって [etymology][voicy][heldio][khelf][masanyan][fujiwarakun][folk_etymology][word_formation][loan_word][hellog_entry_set]
GW も最終日ですが,この連休中は Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて様々な対談企画を展開してきました.この余韻は GW 後も向こう1週間ほど続く予定ですので,どうぞお付き合い下さい.
今朝の heldio では,khelf(慶應英語史フォーラム)のメンバー2人とともに軽いノリで英単語の語源 (etymology) をめぐる遊びを披露しています.「#706. 爆笑・語源バトル with まさにゃん&藤原くん」です.30分超の放送回となりますので,お時間のあるときにどうぞ.
お聴きになれば分かる通り,今回の「語源バトル」は,ゲームそのものを実施したというよりは,ゲームのルール作りに着手したというのが正確なところです.単語の語源とはいったい何か? 「単語の語源を言い当てる」とは,結局何を答えればよいのか? ゲームのルール作りを念頭に考えてみると,問題が具体的に挙がってくるのが良いところです.放送中にもいくつかの問題点が持ち上がりました.
・ 何段階もの借用を経てきた単語について,直近の借用元言語を答えるべきか,その前段階の借用元言語を答えるべきか,あるいは究極の祖語(しばしば印欧祖語)を答えるべきか.
・ 借用語について,ラテン語からか,フランス語からか,という問いはしばしば解決が困難である.「ラテン系」などととして逃げることは,どこまで妥当か.(cf. こちらの記事セット)
・ taking のような語形については,語幹 take と屈折語尾 -ing の語源をそれぞれ答える必要があるのか.
・ 複合語や派生語の場合,構成する各形態素について語源を明らかにする必要があるのか.
・ UK のような省略語の語源とは,展開した United Kingdom が答えとなるのか.あるいは,Unite, -ed, King, -dom の各々の語源を答える必要があるのか.
その他,思いつくままに問題点を挙げてみると,ルール作りがなかなか厄介な仕事であることが分かってきます.
・ 本来語という答えは多くなりそうだが,本来語とは何か.
・ 語源説が揺れている単語(実際にかなり多いと思われる)の回答は何になるのか.
・ 固有名詞の語源とは何か.
・ 語源と語形成は何がどう異なるのか.
・ 民間語源 (folk_etymology) と学者語源は区別する必要があるのか.
これらは結局のところ「単語の語源とは何か」というメタな問いを発していることにほかなりません.この問いを議論するに当たって,まず「#3847. etymon」 ([2019-11-08-1]) を参照していただければと思います.
以下,「語源バトル」に出演した2人の HP へのリンクを張っておきます.
・ 「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学): https://note.com/masanyan_frisian/n/n01938cbedec6
・ 藤原郁弥さん(慶應義塾大学大学院生): https://sites.google.com/view/drevneanglijskij-jazyk/home
2023-03-11 Sat
■ #5066. 英語の前置詞としての sans [french][loan_word][preposition][shakespeare][connotation][idiom]
この1週間は hellog でも Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも前置詞 (preposition) に注目する機会がたまたま多く,途中から「前置詞ウィーク」と呼んで発信していました.前置詞にご関心のある方は,ぜひこの数日間の記事や放送回を振り返っていただければと思います..
今日も同じ流れで,意外性のある前置詞として sans を紹介します.without に相当するフランス語の前置詞でフランス語では sans /sɑ̃/ と発音されますが,英語としては綴字通りに /sænz/ と発音されます.フランス語からそのまま取り入れた慣用表現の前置詞句は,例えば sans doute 「疑いもなく」 /sɑ̃ duːt/ のように,フランス語風に発音されますが,そうでない場合には英語化した /sænz/ で発音されます.英語の文脈では,たいてい古風,あるいは冗談めかした connotation で用いられます.例文を挙げてみましょう.
・ Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. 「(老いぼれて)歯もなく,目もなく,味もなければ何もなし」(Shakespeare, As You Like It II. vii)
・ a wallet sans cash
・ There were no potatoes so we had fish and chips sans the chips.
・ He came to the door sans shirt.
・ She went to the party sans her husband.
・ She would not be happy with people seeing her sans makeup.
・ He was wearing running shoes, sans socks.
こうしてみると,なかなか使ってみたくなる前置詞ですね.
OED の sans, prep. によると,英語での初出は初期近代英語の Kyng Alisaunder です.
c1300 K. Alis. 134 Of gold he made a table Al ful of steorren, saun fable.
ただし,Shakespeare 以前の用法はいずれも目的語としてフランス単語を伴っており,いわばフランス語の慣用表現をそのまま英語に取り込んだもののようです (ex. sans delay, sans doubt, sans fable, sans pity, sans return).英語において生産的な前置詞として発達したのは,かの言葉遊びの天才がユーモアを交えて再導入したからといってよさそうです.
2023-03-02 Thu
■ #5057. because の語源と歴史的な用法 [conjunction][etymology][french][loan_word][phrase][hybrid][expletive][infinitive][syntax]
理由を表わす副詞節を導く because は英語学習の早い段階で学ぶ,きわめて日常的で高頻度の語である.しかし,身近すぎて特別な感情も湧いてこない表現にこそ,おもしろい歴史が隠れていることが少なくない.
because を分解すると by + cause となる.前者は古英語から続く古い前置詞であり,後者はフランス語からの借用語である.もともとは2語からなる前置詞句だったが,それが形式的にも機能的にも合一したのがこの単語である.その観点からすると,1種の混成語 (blend) とみてよい.
以下 OED を参照して,because の来歴を紹介しよう.この語の英語での初出は14世紀初めのことである.Bi cause whi (= "because why") のように用いられているのがおもしろい.
c1305 Deo Gratias 37 in Early Eng. Poems & Lives Saints (1862) 125 Þou hast herd al my deuyse, Bi cause whi, hit is clerkes wise.
ほかに because that のように that を接続詞マーカーとして余剰的に用いる例も,後期近代英語から初期近代英語にかけて数多くみられる(「#2314. 従属接続詞を作る虚辞としての that」 ([2015-08-28-1])).そもそも cause は名詞にすぎないので,節を導くためには同格の that の支えが必要なのである.because that の例を3つ挙げよう.
・ c1405 (c1395) G. Chaucer Franklin's Tale (Hengwrt) (2003) l. 253 By cause that he was hir neghebour.
・ 1611 Bible (King James) John vii. 39 The Holy Ghost was not yet giuen; because that Iesus was not yet glorified.
・ 1822 Ld. Byron Heaven & Earth i. iii, in Liberal 1 190 I abhor death, because that thou must die.
接続詞としての because は定義上後ろに節が続くが,現代にも残る because of として句を導く用法も早く14世紀半ばから文証される.初例は Wyclif からである.
1356 J. Wyclif Last Age Ch. (1840) 31 Þe synnes bi cause of whiche suche persecucioun schal be in Goddis Chirche.
もう1つ興味深いのは,because の後ろに to 不定詞が続く構造である.現代では残っていない構造だが,16世紀より2例が挙げられている.意味が「理由」ではなく「目的」だったというのもおもしろい.
・ 1523 Ld. Berners tr. J. Froissart Cronycles I. ccxxxix. 346 Bycause to gyue ensample to his subgettes..he caused the..erle of Auser to be putte in prison.
・ 1546 T. Langley tr. P. Vergil Abridgem. Notable Worke i. xv. 28 a Arithmetike was imagyned by the Phenicians, because to vtter theyr Merchaundyse.
because はさらに歴史的に深掘りしていけそうな単語である.これまでも以下の記事でこの単語に触れてきたので,ご参照を.
・ 「#1542. 接続詞としての for」 ([2013-07-17-1])
・ 「#1744. 2013年の英語流行語大賞」 ([2014-02-04-1])
・ 「#2314. 従属接続詞を作る虚辞的な that」 ([2015-08-28-1])
・ 「#3036. Lowth の禁じた語法・用法」 ([2017-08-19-1])
・ 「#4569. because が表わす3種の理由」 ([2021-10-30-1])
2023-02-28 Tue
■ #5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点) [contact][loan_word][borrowing][latin][celtic][old_norse][french][dutch][greek][japanese][link]
英語が歴史を通じて多くの言語と接触 (contact) してきたことは,英語史の基本的な知識である.各接触の痕跡は,歴史の途中で消えてしまったものもあるが,現在まで残っているものも多い.痕跡のなかで注目されやすいのは借用語彙だが,文法,発音,書記など語彙以外の部門でも言語接触のインパクトがあり得ることは念頭に置いておきたい.
英語の言語接触の歴史を短く要約するのは至難の業だが,Schneider (334) による厳選8点(時代順に並べられている)が参考になる.
・ continental contacts with Latin, even before the settlement of the British Isles (i.e., roughly between the second and fourth centuries AD);
・ contact with Celts who were the resident population when the Germanic tribes crossed the channel (in the fifth century and thereafter);
・ the impact of Latin through Christianization (beginning in the late sixth and seventh centuries);
・ contact with Scandinavian raiders and later settlers (between the seventh and tenth centuries);
・ the strong exposure to French as the language of political power after 1066;
・ the massive exposure to written Latin during the Renaissance;
・ influences from other European languages beginning in the Early Modern English period; and
・ the impact of colonial contacts and borrowings.
よく選ばれている8点だと思うが,私としてはここに3点ほど付け加えたい.1つは,伝統的な英語史では大きく取り上げられないものの,中英語期以降に長期にわたって継続したオランダ語との接触である.これについては「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) やその関連記事を参照されたい.
2つ目は,上記ではルネサンス期の言語接触としてラテン語(書き言葉)のみが挙げられているが,古典ギリシア語(書き言葉)も考慮したい.ラテン語ほど目立たないのは事実だが,ルネサンス期以降,ギリシア語の英語へのインパクトは大きい.「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) および「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.
最後に日本語母語話者としてのひいき目であることを認めつつも,主に19世紀後半以降,英語が日本語と意外と濃厚に接触してきた事実を考慮に入れたい.これについては「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]),「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1]) を参照.
Schneider の8点に,この3点を加え,私家版の厳選11点の完成!
・ Schneider, Edgar W. "Perspectives on Language Contact." Chapter 13 of English Historical Linguistics: Approaches and Perspectives. Ed. Laurel J. Brinton. Cambridge: CUP, 332--59.
2023-01-30 Mon
■ #5026. 接尾辞 -age [suffix][french][latin][word_formation][noun][borrowing][loan_word]
-age は名詞を作る接尾辞 (suffix) として一見目立たなそうだが,意外と基本的な単語にも用いられている.例えば percentage, marriage, usage, passage, storage, shortage, mileage, voltage, baggage, postage, luggage, breakage, bondage, anchorage, shrinkage, orphanage 等をみれば頷けるだろう.
語源としては,古典時代以降のラテン語 -agium に遡る場合もあれば,同じく古典時代以降のラテン語の別の語尾 -aticum(古典ラテン語の形容詞語尾 -āticus の中性形より)がフランス語に -age として伝わったものに由来する場合もある.いずれももとより名詞を作る接尾辞として機能していた.
この接尾辞をもつ単語は早くも初期中英語期にフランス語やラテン語から借用されていたが,後期中英語期になると peerage, mockage など英語内部で語形成されたものも現われ,この傾向は近代英語期になるととりわけ強くなった.現代英語においてもある程度の生産性を有する接辞で,1949年には signage などの語が作られている.
この接尾辞の主な意味を語例とともに挙げてみよう.
1. 集合: cellarage, leafage, luggage, surplusage, trackage, wordage
2. 動作・過程: coverage, haulage, stoppage
3. 結果: breakage, shrinkage, usage
4. 率・数量: acreage, dosage, leakage, mileage, outage, slippage
5. 家・場所: orphanage, parsonage, steerage
6. 状態: bondage, marriage, peonage
7. 料金: postage, towage, wharfage
このように -age は英語では原則として名詞を作る接尾辞だが,ラテン語の形容詞語尾 -āticus より機能を受け継ぎ,珍しく形容詞としてフランス語より入ってきた savage という語を挙げておこう.
2022-12-08 Thu
■ #4973. goblin mode --- 2022年の Oxford Word of the Year [woy][oed][french][loan_word][etymology]
goblin mode: a type of behaviour which is unapologetically self-indulgent, lazy, slovenly, or greedy, typically in a way that rejects social norms or expectations.
今年の Oxford Word of the Year に輝いたのは goblin mode なる語(複合名詞)だった.The Guardian の速報をご覧ください.今回からは一般投票も受け付けての選語だったようで,世界中の34万人を超える英語話者が投票し,次点を大きく突き放しての圧勝だったとのこと(次点は Metaverse, #IStandWith).
2022年,長いコロナ禍の生活における規範遵守に疲れ果てた人々が,SNSなどに理想の自分の姿をアップするのに飽き,むしろだらしない本当の自分をさらけ出す傾向が現われ,共感を呼んだ.ここにはウクライナ戦争も影を落としているかもしれない."goblin mode" に入った自堕落な人々の姿が人気を博す時代が来るとは!
この語は2009年にツイッター上に初出していたが,今年の2月に一気にバズワードとなった.Oxford University Press は,この語の流行の背景について次のようにコメントしており興味深い.時代を映す鏡というわけだ.
Seemingly, it captured the prevailing mood of individuals who rejected the idea of returning to 'normal life', or rebelled against the increasingly unattainable aesthetic standards and unsustainable lifestyles exhibited on social media.”
goblin は人間にいたずらを働く,醜い小人の妖精のことである.今回の流行語は「小人物である自らの堕落した醜い姿」を goblin に重ね合わせたという理解でよいだろうか.ただし,完全にゴブリンになってしまうわけではなく,ゴブリン風のモードに一時的に入っているだけ,という含みがあり,希望が見えなくもない.
goblin 自体の語源には諸説あるようだ.OED の語源解説を読んでみよう.
Apparently < Old French gobelin (late 12th cent. in an isolated attestation; subsequently in Middle French (a1506 as gobellin); French gobelin), apparently ultimately < ancient Greek κόβαλος rogue, knave, κόβαλοι (plural) mischievous sprites invoked by rogues, probably via an unattested post-classical Latin form; the suffix is probably either Old French -in or its etymon classical Latin -īnus -INE suffix1. Compare later (apparently < Greek) post-classical Latin cobalus, covalus, kind of demon (16th cent.).
Compare (apparently < French) post-classical Latin gobelinus (first half of the 12th cent. in a British source).
おそらく究極的にはギリシア語の「ごろつき」を意味する語に遡り,(ラテン語を経て)フランス語から英語に入ってきたものだろうという.英語での初出は1350年以前.
『英語語源辞典』によると,異説とともにおもしろい解説が与えられている.
1100年ごろフランスの町 Evreux に出没したという妖精は,中世ラテン語で gobelīnus と名付けられたが,これは (O)F gobelin による造語とも考えられる.ほかに,人名 Gobel (cobalt と同根か)に指小辞 -et のついたものとする説や,MHG kobolt (G Kobold) 'kobold' が OF を通じて借用されたとする説などがある.
まさか中世のゴブリンたちも現代の人間界でバズワードになるとは思っていなかっただろうなぁ.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow