2026-01-21 Wed
■ #6113. 朝カルで井上逸兵さんと「AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」 --- 「いのほたなぜ」出版記念 [inohota][inohotanaze][asacul][notice][inoueippei][ai]

ちょうど1ヶ月後のことになりますが,2月21日(土)の夜,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,井上逸兵さん(慶應義塾大学)と私のコンビによる特別講座が開講されます.タイトルは「いのほたチャンネル出版記念講座:AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは」です.
この講座は,昨年2025年10月にナツメ社より刊行された共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(略称「いのほたなぜ」)の出版を記念しての開講となります.本書は YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が元となっていますが,その2人が YouTube とも書籍とも異なる朝カルという場にて対談します.井上さんは教室で,堀田はオンラインで登場する予定です.
昨今,生成AIの進化は目覚ましく,言葉の壁が技術的に消えつつあるかのように見えます.そのような時代において,なぜ私たちはあえて言語学を学び,語学を続ける必要があるのでしょうか.本講座では,社会言語学と英語史,それぞれを専門とする2人が「人にとって言葉とは何なのか」という根源的な問いについて語り合います.
AI が生成するテキストが世界を埋め尽くすようになると,人間言語はどうなっていくのか.コーパス言語学の役割はどうなるのか.そして,語学や言語学を学ぶことの意味はどのように変容するのか.AI 時代だからこそ欠かせない言語への深い理解,すなわち「言語学的思考」の意義について,講座を通じて考えていきます.講座の最後には質疑応答の時間も設けます.
講座の概要は以下の通りです.
・ タイトル:いのほたチャンネル出版記念講座:AI時代にこそ必要な「言語学的思考」とは
・ 日時:2月21日(土)18:30--20:00
・ 受講方法:教室(新宿)あるいはオンライン (Zoom) の自由選択.2週間の見逃し配信のサービスもあります.
・ お申し込み:こちらのページよりどうぞ.
当日は,私たちの運営する「いのほた言語学チャンネル」がどこへ向かうのか,といった未来の話も飛び出すと思います.教室で,あるいはオンラインで,皆様とお会いできるのを楽しみにしています.見逃し配信もありますので,当日ご都合のつかない方もぜひ.
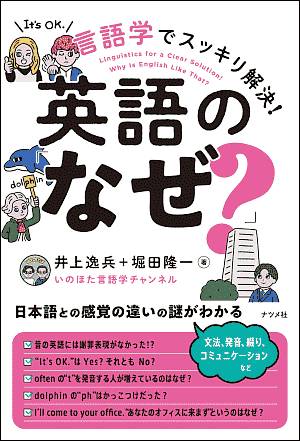
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-12-10 Wed
■ #6071. 「いのほた」で no に関する回が多く視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][negative][negation][etymology][article][sobokunagimon]
12月7日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の話題は「#391. おなじ no でも元々ちがうことば --- no money の no と No, I don't. の no」でした.3週間ほど前の「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が思いのほか人気回となった(1.45万回視聴)ので,冠詞 (article) の話題の続編というつもりで話しを始めたのですが,地続きのトピックとして no に言及したところ,井上さんがむしろそちらにスポットライトを当て,今回のタイトルとサムネになった次第です.結果として,今回も多くの方々に視聴していただき,良かったです.皆さん,ありがとうございます.
前回の冠詞回でも話したのですが,不定冠詞 a/an は,もともと数詞の one に由来しているので,その本質は存在標示にあるとみなせます.これに対して,否定語の no の本質は,まさに不在標示です.a/an と no は,ある意味で対極にあるものととらえられます.存在するのかしないのか,1か0か,という軸で,不定冠詞と no を眺めてみる視点です.
この観点から見ると,英文法で習う few と a few の意味の違いも理解できます.few は元来 many の対義語であり,「多くない」という否定的な意味合いが強い語です.しかし,これに存在標示の a をつけてみるとどうなるでしょうか.「ないわけではないが,多くはない」という few の否定に傾いた意味に,a が「少ないながらも存在はしている」という肯定的なニュアンスを付け加え,結果として「少しはある」へと意味が調整される,と解釈できるわけです.
さて,この a/an と no の対立構造も奥深いテーマなのですが,今回の動画で視聴者の皆さんが最も驚きをもって受け止めたのは,タイトルにもある通り,2つの no が別語源だった,という事実ではないでしょうか.現代英語では,形容詞として使われる no と,副詞として使われる no が,たまたま同じ綴字・発音になっていますが,実は歴史的なルーツは異なるものなのです.
普段何気なく使っている単語でも,そのルーツをたどると,驚くような歴史が隠されているものです.皆さんもこの不思議な no の歴史を,ぜひ YouTube の動画で確認してみてください.言語学的な知的好奇心を刺激されること請け合いです.また,冠詞や否定というテーマは,情報構造や会話分析にもつながる非常に大きな問題ですので,今後も多角的に掘り下げていきたいと考えています.
2025-11-27 Thu
■ #6058. 『いのほたなぜ』刊行記念 --- 大阪トークイベントと電子書籍化のお知らせ [notice][inohotanaze][inoueippei][inohota][youtube]
井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社,2025年)が10月15日に刊行されてから,早いもので1ヶ月以上が経過しました.おかげさまで多くの方にご好評をいただいており,心より感謝申し上げます.今回は,本書に関する直近のお知らせを3点,まとめてご報告します.
【 トークイベント 】
12月18日(木)19:00より,大阪梅田のライヴハウス梅田 Lateral にて新刊書「いのほたなぜ」の刊行記念トークイベントを開催します(後日アーカイヴ視聴も可).井上&堀田(堀田はリモート出演)が新刊書について語り尽くします.お題は「「いのほた言語学チャンネル」のスナック言語学 〜呑める!言語学の話〜」です.
当日は,井上さんと私・堀田隆一(私は海外よりリモート参加)の2人が登壇し,新刊書について大いに語り尽くします.本イベントは,そもそも2人の YouTube チャンネル「いのほた言語学チャンネル」から派生した書籍の刊行を記念してのトークです.書籍のタイトルが示す通り,「英語のなぜ」を言語学の視点からスッキリ解決し,その知的好奇心を「肴」に,文字通り「呑める」ようなざっくばらんなトークを展開しよう,という趣向です.
井上さんは現地会場にてサイン会も実施される(!)とのことですので,関西方面にお住まいの皆様,ぜひともこの機にお運びください.書籍をいまだお読みでない方はもちろん,既にお読みいただいた方にとっても,本書をより深く楽しむための裏話が聞ける貴重な機会となるはずです.
詳細とお申し込みは,以下の梅田 Lateralのサイトをご参照ください.3週間後,皆さんとお目に掛かるのを楽しみにしています!
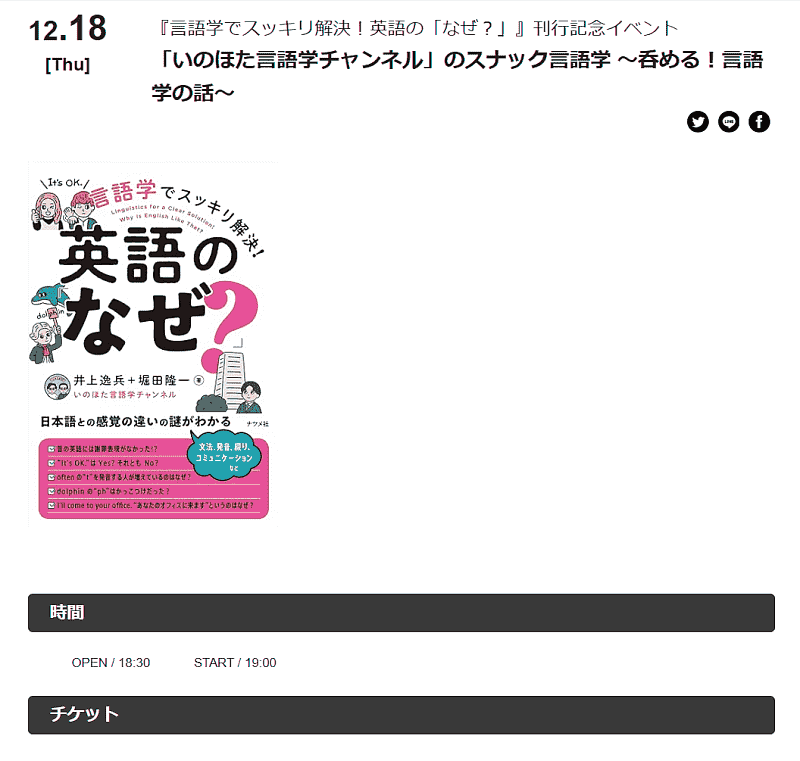
【 電子書籍が出ました 】
一昨日の11月25日,本書の電子書籍が出ました! 10月15日の刊行以来ご好評につき,電子書籍化されることになり,11月25日より電子版でもお読みいただけるようになった次第です.Amazon より,あるいはナツメ社の本書紹介ページ経由でご入手いただけます.
【 本書に関する熱いコメントや書評 】
本書に関する好意的なコメントや書評も多く寄せられてきています.ここでは,heldio/helwa のコアリスナーお2方によるの note 上の熱い書評をご紹介します.
・ heldio/helwa リスナーの Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)が,ご自身の note にて「いのほたなぜ」へのレビュー記事「『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を読んで、英語の世界を散歩しよう」を公開されています.特に高校生から大学の新入生くらいに届いてほしい,という熱いメッセージをいただきました.その通り,その通りと頷きつつ拝読しました.
・Grace さん さんも,ご自身の note にて「いのほたなぜ」へのレビュー記事「いのほたなぜ~言語学の世界へようこそ~」を公開されています.皆でコトバの問題を「深掘り」ましょう,という本書のメッセージをスマートに読み解いていただきました.
以上,「いのほたなぜ」が盛り上がってきています! 「いのほたなぜ」の紹介ページには,本書とオリジナル YouTube 配信回を紐付けたリンク集などもありますので,ぜひそちらも訪れていただければ.引き続き「いのほたなぜ」をよろしくお願いいたします.
2025-11-21 Fri
■ #6052. 「いのほた」で冠詞に関する回がよく視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][article][grammaticalisation][sobokunagimon][demonstrative][information_structure]
11月16日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が公開されました.テーマが「冠詞」 (article) という大物だったからでしょうか,おかげさまでよく視聴されています.今朝の時点で視聴回数が1万回を超えており,コメント欄も活発です.
冠詞 (the, a/an) は英語学習者にとって永遠の課題です.冠詞というものがない日本語を母語とする者にとって,とりわけ習得の難しい項目です.私も,なぜ英語にはこのような厄介なものがあるのだろうか,とずっと思っていました.今思うに,これは根源的な問いなのでした.
なぜ冠詞があるのか.この問いは,英語史の観点から紐解いてみると,まず驚くべき事実から始まります.定冠詞 the に相当する要素は,英語を含む多くのヨーロッパ語において,必ずしも最初から存在していたわけではないのです.歴史の途中で,それも比較的後になってから用いられるようになった「新参者」なのです.
古英語の時代にも,the に相当する形式は確かに存在しました.ただし,それは現代的な確立した用法・品詞として使われていたわけではなく,その前駆体というべき存在にとどまっていました.もともと「あれ」「それ」といった意味を表わす指示詞 (demonstrative) だったものが,徐々にその指示力を失い,単に既知のものであることを標示する文法的な要素へと変化していった結果として生まれたものです.このような,もともとの意味が薄まり,文法的な機能をもつようになる変化を「文法化」 (grammaticalisation) と呼んでいます.これは英語の歴史において非常に重要なテーマであり,本ブログでも度々取り上げてきました.
この歴史的な経緯を知ると,最初の素朴な疑問「なぜ冠詞があるのか」は,「なぜ英語は,わざわざ指示詞を冠詞に文法化させる必要があったのか」という,より深い問いへと昇華します.なぜなら,冠詞のない日本語話者は,冠詞のない世界が不便だとは感じていないからです.
この問いに対する1つの鍵となるのが,日本語の助詞「が」と「は」です.動画では,この「が」「は」の使い分けが,英語の冠詞の役割と似ている側面があることを指摘し,情報構造 (information_structure) の観点から議論を展開しました.
冠詞の最も基本的な役割は,話し手と聞き手の間ですでに共有されている情報(=旧情報)か,そうでない新しい情報(新情報)かを区別することにあります.この機能は,日本語の「が」「は」が担う役割と見事にパラレルなのです.日本の昔話を例にとってみましょう.
昔々あるところに,おじいさん(=新情報)とおばあさん(=新情報)がいました.おじいさん(旧情報)は山へ芝刈りに,おばあさん(=旧情報)は川へ洗濯に行きました.
英語にすると,第1文では不定冠詞が,第2文では定冠詞が用いられるはずです.それぞれ日本語の助詞「が」「は」に対応します.
この日本語の「が」「は」の使い分けにみられる新旧情報の区別をしたいというニーズは,言語共同体にとって普遍的なものです.しかし,そのニーズを満たすための手段は,言語ごとに異なっている可能性が常にあります.日本語はすでに発達していた助詞というリソースを選び,英語はたまたま手近にあった指示詞の文法化という道を選んだ,というわけです.
この事実は,英語の冠詞の習得に苦労する私たちに,ある洞察を与えてくれます.英語の冠詞の使い分けを理解するには,その背景にある情報の流れ,すなわち情報構造を理解する必要がある,ということです.英語の冠詞の感覚は,日本語母語話者が無意識のうちに「が」「は」を使い分けている,あの感覚と繋がっているのです.
言語は,その話者たちのコミュニケーションのニーズと,その時代に利用可能な言語資源が複雑に絡み合って形作られていきます.ある意味では実に人間くさい代物なのです.ぜひこの議論を動画でもおさらいください.
2025-11-05 Wed
■ #6036. 1分でわかる「英語のなぜ?」 --- 「いのほたなぜ」からの話題で YouTube ショートのシリーズを展開中 [inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helshort][etymological_respelling][deixis][helkatsu]
10月15日に刊行された,井上逸兵さんとの初めての共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)(通称「いのほたなぜ」)について,本ブログでも何度かご紹介してきました.
出版社のナツメ社の編集者の方と著者2人で,ちょっとした試みを始めています.YouTube ショート動画のシリーズ「1分でわかる「英語のなぜ?」」です.本書で取り上げているトピックを厳選し,短尺動画で解説しています.実際には,編集者の方が生成AIを利用してほぼすべて作成し,最後に著者である井上&堀田が確認した上で,「いのほた言語学チャンネル」より公開しているという次第です.通常の YouTube 動画だけでなく,ショート動画という別形態でも情報発信していくことで,より広い層にリーチできるのではないかと期待しています.もちろん最終的には本書を手に取ってもらい,それ通じて言語学・英語学・英語史のおもしろさを1人でも多くの方に知ってもらいたい,というのが狙いです.ある意味では,新しいスタイルのhel活の試みです.
これまでに,上に掲げた2本のショート動画を公開しています.1つ目は「doubt の b はかっこつけだった?」です.「いのほたなぜ」では「dolphin の ph はかっこつけだった?」 (pp. 78--79) にて取り上げられている話題について,別の具体例を1つ挙げながらの紹介です.いわゆる語源的綴字 (etymological_respelling) の問題です.綴られているのに発音しない黙字 (silent_letter) は,英語学習者泣かせですね.
2つ目は,本書の168--69頁で取り上げられている「なぜ英語では「あなたのオフィスに来ます」と言うのか」を題材としたショート動画です.英語の come と go の使い分けに関する直示性 (deixis) の問題です.日本語の「来る」「行く」とは使い方が異なり,やはり日本の英語学習者にとって混乱の種となりますね.
なお,「いのほた本」自体が「いのほた言語学チャンネル」に基づいているので,対応する(ショートではなく通常の)動画があります.関心をもった方は,ぜひ以下の2本をご覧ください.
・ 「#161. dolphin の ph は元は f,doubt の b は元はなかった!いったいなぜ???」
・ 「#253. come とか go とか this とか that とか単純そうに見えるけど,物理的空間と社会言語学と認知言語学の接点です」
本書で扱っているトピックは,このように単に豆知識にとどまらず,英語という言語の歴史的経緯やコミュニケーション上の社会的配慮を浮き彫りにするものです.新刊書は,井上さんの「言語の深層」と私の「英語の歴史」の2つの関心が融合しており,お互いの専門性がバランスよく反映された仕上がりになっていると自負しています.
ショート動画のシリーズは,今後も続いていきます.ぜひ,動画をご覧いただき,本書も手に取っていただければ幸いです.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-11-04 Tue
■ #6035. 英語史年表を作るのは難しい --- 「いのほたなぜ」の「超ざっくり英語史年表」制作裏話 [inohota][inohotanaze][inoueippei][timeline][historiography][notice][youtube][periodisation]
11月2日(日),井上逸兵さんと共著で上梓した『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)を記念し,ホームグラウンドである YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて本書を紹介する回を配信しました.「#384. いのほた本は,世に問いたい言語学のひとつのかたち --- 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」です(16分半ほどの動画).ぜひご覧ください.
本書は,2人が3年半にわたり YouTube 上で対談してきた内容が凝縮されており,お陰様で発売早々から大きな反響をいただいています.本書の特設HPも開設していますので,こちらよりぜひご訪問ください.また,SNS などで,ハッシュタグ #いのほたなぜ を添えて,本書に関するご意見やご感想などをお寄せいただけますと幸いです.
さて,「いのほた」の最新回では,本書の構成について言及しつつ,私が担当した「超ざっくり英語史年表」 (pp. 6--9) の制作舞台裏を披露しました.これまでも英語史の略年表は様々な形で作ってきましたが,年表制作という作業には常に悩みがつきまといます.単なる年号の羅列以上の,厄介な問題を含んでいるのです.この点について掘り下げてみます.
年表を作るにあたり,まず歴史的な出来事には「線」を引きやすいものと,そうでないものとがあります.政治史や軍事史における事件,例えば1066年のノルマン征服 (norman_conquest) のようなものは,年号(そして日付まで)が明確に記録されており,年表に掲載する際に悩みはありません.「1066年,ノルマン征服」とズバッと書き込めばよいだけです.
ところが,言語変化を多く扱う英語史年表では,そうは単純にいかないことが多いのです.例として,英語史の最たる音変化の1つ,大母音推移 (gvs) を考えてみましょう.一般にこの変化は1400年頃から1700年頃にかけて,じっくり,ゆっくり起こったと説明されることが多いです.ここでの問題は,この変化の始まりと終わりが,特定の何年とは決められないことです.実際は1400年の元旦に始まったわけでも,1700年の大晦日に終わったわけでもありません.年表という2次元のレイアウトの制約の中で,どこに始まりと終わりを置くのか,あるいはどれくらいの時間幅で矢印を引くかというのは,その都度,苦渋の選択を迫られる作業となります.レイアウト上は,書き込む文字やイラストとの兼ね合いもあり,さらに問題は複雑化します.
年表制作における恣意性のもっと顕著な例として,英語史の開始年をどこに置くかという大きな問題があります.この問題の根深さは,hellog の periodisation のタグのついた各記事で見てきたとおりですが,年表に反映させるとなると,明示的に年号を示すことが要求されているようで,プレッシャーが大きいのです.伝統的に英語史の始まりは449年とされてきました.これは,アングロサクソン人と呼ばれる西ゲルマン人の一派が,ブリテン島へ本格的に来襲した年とされているからです.これをもって,アングロサクソン王国の始まり,ひいてはイギリスの始まり,そして英語の始まりと了解されてきたわけです.
しかし,言語プロパーの歴史を論じる立場からすると,この449年開始説はきわめて眉唾ものです.なぜならば,アングロサクソン人がまだ大陸にいたとされる448年と,ブリテン島に上陸したとされる449年とで,彼らの話していた言語自体は何ら変わっていないはずだからです.
言語は,社会的な事件によって急にその姿を変えるものではなく,あくまでゆっくりと変容していく連続体として存在しています.極論をいえば,英語の歴史は,印欧祖語まで(少なくともある程度は)地続きで繋がっていると理解できますし,さらに突き詰めれば,人類の言語の始まりにも繋がっている可能性があります.つまり,「○○語史の始まり」という区切りは,純粋な言語学的な考慮ではなく,その言語を話す集団の社会的な歴史,すなわち国史や政治史とシェアさせてもらう形で,便宜的に設定されているにすぎないのです.
ただ,とりわけ入門的な書籍に掲載する年表で「449年」などと明記しないと,「では,英語史はいつ始まったのですか?」という素朴な疑問にサラッと答えられなくなるため,伝統的な区切りをひとまず採用しているにすぎない,ということなのです.年表に書かれている年号は,学習の便宜という実用的な要請に応えるための妥協の産物といってよいものです.文章であれば「~年頃」などといった表現で逃げることができるのですが,年表という形式では,どうしても数直線の上にピンポイントで明示的に配置するといったデジタルな感覚が強く,それゆえに悩ましいのです.言語の歴史は,革命のような劇的な断絶ではなく,ゆっくりと変化していくファジーな世界です.そのことを理解した上で,本書の「超ざっくり英語史年表」に目を通していただけると,より深く英語史というものに思いを馳せることができるかと思います.
新刊書「いのほたなぜ」に関する話題は,引き続き「いのほた言語学チャンネル」や hellog その他の媒体で繰り広げていくつもりです.関連情報はすべて特設HPにまとまっていますので,日々そちらをご覧ください.よろしくお願い致します.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-24 Fri
■ #6024. なぜ It is kind OF you to come. なのか? --- 「いのほた言語学チャンネル」最新回より [youtube][inohota][youtube][preposition][syntax][infinitive][construction][metanalysis][sobokunagimon]
井上逸兵さんと運営している YouTube チャンネル「いのほた言語学チャンネル」は,おかげさまで多くの方にご覧いただいています.先日公開した最新回「#381. It is important for you to . . . と It is kind of you to . . . って似た構文と思われがちですが,ルーツがまったくちがいます」は,視聴回数も4千回以上と好調です.多くの方々の知的好奇心を刺激することができたのではないかと嬉しく思っています.今回は,この動画の内容を hellog として要約しつつ,テーマとなった構文の謎に迫っていきます.
さて,問題の構文は It is kind of you to come. に代表される,人の行動を評価する形容詞を用いた文です.学校英文法では,不定詞の意味上の主語を伴う構文として,より一般的な It is important for you to go. の構文とセットで学習することが多いかと思います.そして,kind, foolish, wise のような人物評価の形容詞の場合には前置詞として of を,important や necessary のような場合には for を用いる,と整理して学習した方もいるのではないでしょうか(私自身がまさにそうでした).
しかし,なぜ人物評価の形容詞に限って of が用いられるのか,という理由まで踏み込んで教わることは少ないでしょう.動画でも指摘している通り,両者は表面的には前置詞が交替するだけの平行的な構文に見えますが,その歴史的なルーツはまったく異なるのです.
まず,important for you の構文について.こちらは,もともと it is important for you 「それはあなたにとって重要だ」と to go 「行くことが」という2つの要素が組み合わさってできたものです.つまり,for you は本来 important に副詞的にかかる前置詞句だったのです.「あなたにとって(重要だ)」ということですね.ところが,you が後続する不定詞 to go の意味上の主語でもあることから,時代を経るにつれて for you to go 全体が1つの大きな主語のように再解釈されるようになりました.これは統語論上の異分析 (metanalysis) と呼ばれる現象の典型例です.
一方,本題の kind of you の構文はどうでしょうか.こちらは異分析では説明がつきません.なぜなら,of you では「あなたにとって(親切だ)」の意味にはならないからです.親切なのは「あなた」自身なのであり,この意味関係を捉えるには別の解釈を探る必要があるのです.
この of の正体は,すでに本ブログの記事「#4116. It's very kind of you to come. の of の用法は?」 ([2020-08-03-1]) や「#4117. It's very kind of you to come. の of の用法は歴史的には「行為者」」 ([2020-08-04-1]) でも解説した通り,「行為者」を示す of と考えるのが最も説得的です.現代英語では受動態の行為者は by で示すのが普通ですが,中英語から初期近代英語にかけては of が優勢でした.つまり,of you は "(done) by you" (あなたによってなされた)に近い意味合いで理解されていたのです.
OED をひもとくと,この構文の原型は It was a kind thing of you to come. のような,形容詞が名詞 thing や act, part などを修飾する形だったことがわかります.この原型に「行為者の of」を適用すれば,a kind thing (done) by you 「あなたによってなされた親切なこと」とスムーズに解釈できます.この構文が使われるうちに,中間にある thing のような名詞が省略され,It was kind of you... という現代の形に化石化していった,というのが真相のようです.
このように,一見すると似通った2つの構文が,まったく異なる発生の経緯をもっているというのは,おもしろいことですね.学校英文法で出会う素朴な疑問の多くは,歴史を遡ることで,このように腑に落ちる説明が見つかることが多いです.これこそが英語史研究の醍醐味です.
今回の話題について,より詳しくは上記の YouTube 動画をご覧いただければ幸いです.また,音声メディア Voicy の heldio でも関連する放送回があるので,合わせてお聴きください.
・ heldio: 「#91. It's kind of you to come. の of」
・ heldio: 「#387. It is important to study. の構文について英語史してみます」
2025-10-20 Mon
■ #6020. 「いのほたなぜ」が第5位 --- Amazon 売れ筋ランキング英語部門 [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helkatsu][link]
連日,様々なメディアで新刊書『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)をご紹介しています.本書そのもののみならず,特設HPや関連のコンテンツも読んだり視たり聴いたりしていただけているようです.X(旧 Twitter)のハッシュタグ #いのほたなぜ でご意見やご感想などをお寄せいただけるよう呼びかけていますが,すでに読者の方々より,本書を手に取っている写真や書店・書棚の写真なども上げていただいています.Amazon レビューのほうにも,好意的なご感想の第1弾が届いています.温かく力強い応援,ありがとうございます.
Amazon ランキング(英語部門)のほうは,発売後,舞台が「新着ランキング」から「売れ筋ランキング」に移り,激しい争いとなっています.それでも,一昨日の第9位から,今朝の時点で第5位までジワジワと上がってきました.

目下,共著者の井上さんや,ライターさん,ナツメ社の編集者さんなどとも協力して,少しでも広く本書の存在を知っていただくべく広報に専念しています.英語学・英語史の魅力を最大限に引き出し,それを皆さんに伝えたいからです.実際,本書の元となった YouTube 「いのほた言語学チャンネル」も,同じ趣旨で3年半以上続けているのです.そして,この始めてから16年半になろうとしているご覧のブログもまた,同じです.
ここ数日間の本書に関連する各メディアでのコンテンツを以下に挙げておきます.
・ 井上&堀田による YouTube ショート動画:「いのほた本発売!--井上逸兵・堀田隆一『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』」
・ heldio: 「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売」
・ heldio: 「#1603. 「英語学」って何? --- 「いのほたなぜ」のプロローグより」
・ hellog: 「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1])
・ hellog: 「#6016. 「いのほたなぜ」の特設HPを公開しました」 ([2025-10-16-1])
・ hellog: 「#6017. SNS投稿のためにハッシュタグ「いのほたなぜ」をお使いください」 ([2025-10-17-1])
・ hellog: 「#6019. 「いのほた本」出版に合わせて YouTube ショート動画も公開しました」 ([2025-10-19-1])
また,すでにご紹介した特設HPでは,冒頭に日替わりの「本日の注目章」を掲載しています.今日10月20日の注目章は「20. 「家に連絡するの?」は英語で何と言う?」です.この章と紐付いた「いのほた言語学チャンネル」の動画へもリンクが張られています.また,章と動画を結びつける全リンクは,特設HPの末尾に一覧していますので,そちらもご利用ください.引き続き「いのほたなぜ」そして「いのほた言語学チャンネル」の応援のほど,よろしくお願い致します.
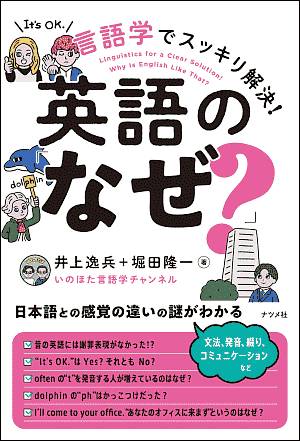
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-19 Sun
■ #6019. 「いのほたなぜ」出版に合わせて YouTube ショート動画も公開しました [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][youtube][helkatsu]
連日,本ブログでもお伝えしているように,同僚の井上逸兵さんと私の2人で3年半ほど続けてきた YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が,本になりました.『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)と題する本で,来たる10月15日に発売されました.略称およびハッシュタグ #いのほたなぜ として,英語史・英語学を広めるべく,皆さんにも応援いただけますと幸いです.
本書は,これまで週2回のペースで地道に配信してきた同 YouTube チャンネルのコンテンツから,選りすぐりのおもしろいネタを引き抜いて再構成したものです.チャンネルをご存じの方であれば,あの独特の雰囲気,すなわち大学教員2人が真剣勝負でカジュアルに,時に適当な(?)ことを喋っている空気感を思い出していただけるかと思います.あの雰囲気はそのままに,それでいて言語学のエッセンスが詰め込まれた1冊となっています.チャンネルをご覧になったことがない方にも,私たちの活動のエッセンスが詰まった入門書として,きっと楽しんでいただけることと思います.
そしてこの新刊書の発売を記念して,井上さんと私とで90秒ほどの短い YouTube ショート動画を作成しました.「いのほた本発売!--井上逸兵・堀田隆一『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』」です.以下よりご覧ください.
動画は,普段の私たちの掛け合いそのものです.お互いのコンテンツについてコメントし合うという,書籍にも盛り込まれた企画のおもしろささの一端を予想できるのではないでしょうか.動画内で井上さんが「適当なことをしゃべっているんですけど」と述べていますが,これはおそらく「高度なこと」の言い間違いでしょう(笑) 本書は入門編から上級編まで,実に幅広い話題を扱っており,レベルだけでなく濃度も高い内容となっています.
このショート動画をきっかけに,私たちの新刊書『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』に興味を持っていただければ望外の喜びです.そして,まだの方はぜひ「いのほた言語学チャンネル」のほうも覗いてみてください.本書と合わせてお楽しみいただければ,英語という言語の奥深さ,そして言語学という学問のおもしろさを,より一層感じていただけることと思います.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-17 Fri
■ #6017. SNS投稿のためにハッシュタグ「いのほたなぜ」をお使いください [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][helkatsu][instagram][twitter]
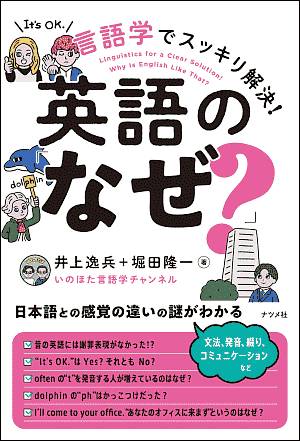
本日 Amazon 新着ランキングの英語部門で「いのほたなぜ」は第4位.日々ジワジワと上がってきています!
一昨日の記事「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1]) でもお伝えしましたが,このたび上梓された『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』の公式な略称は「いのほたなぜ」に決定しています.X(旧 Twitter)をはじめとする SNS のハッシュタグでは,平仮名6文字で #いのほたなぜ として展開していきますので,ご協力と応援のほどよろしくお願い致します.
著者としては,このハッシュタグが単なる宣伝文句にとどまらず,本書を介した読者の皆さんとの交流の場となることを願っています.本書をお読みになってのご意見やご感想,あるいは「この項目が特におもしろかった」「ここをもっと知りたい」といったフィードバックを,ぜひこのハッシュタグを付けてご投稿ください.
皆様から寄せられたご投稿は,一つひとつ拝見し,井上さんとも共有しつつ,今後の「いのほた言語学チャンネル」での新たな議論の種とさせていただきたいと考えています.皆さんのポストが,本書の続編ともいえるコンテンツを生み出すきっかけとなるのです.
1ヶ月ほど前,9月13日の「予約爆撃アワー企画」では,皆さんの熱量がいかに大きな力となるかを目の当たりにしました(cf. 「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1])).本書の出版はゴールではなく,皆様との新たな対話の始まりです.#いのほたなぜ のハッシュタグを通じて,著者と読者が一緒に本書を育てていく,そのような新しい関係性を築いていければ嬉しく思います.皆さんの積極的なご参加が,著者2人にとっての何よりの励みとなります.たくさんのご投稿を心待ちにしております.
昨日紹介した「いのほたなぜ」特設HPにも,「読者の声」セクションが設けられています.賑やかなセクションになっていくと楽しいですね.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-16 Thu
■ #6016. 「いのほたなぜ」の特設HPを公開しました [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][notice][helkatsu]
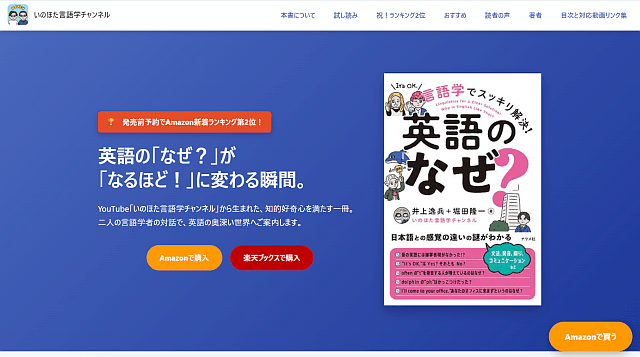
昨日の記事「#6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます」 ([2025-10-15-1]) でお知らせした通り,井上逸兵さんとの共著『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』が,昨日ついに世に出ました.すでにご予約注文いただいた皆様には,心より感謝申し上げます.お手元に届くまで今しばらくお待ちください.
本日10月16日の朝現在,Amazon 新着ランキングの英語部門で「いのほたなぜ」は第6位につけています! 昨日は第7位だったので,じわじわと上がってきています.
さて,本書の刊行に合わせて,「いのほたなぜ」特設HP を公開しましたので,本日はそのご案内です.ページの前半は「(日替わりの)本日の注目章」「本書について」「試し読み」「こんな方におすすめ」など本書の紹介が続きます.中程には「読者の声」のセクションを設けました.今後 Amazon レビューや SNS その他のプラットフォームに諸々のレビュー,ご意見,質問が寄せられてくることを期待していますが,なるべく多くのコメントをこちらのセクションに反映していければと思っています.
そして,特設HPのメインは後半に設置された「目次と対応動画リンク集」です.「いのほたなぜ」は YouTube チャンネル 「いのほた言語学チャンネル」 での対談を活字化したものですが,この特設HPでは,本書の各章とその種となった対応動画とを,紐付けて一覧にしています.各章には動画へのリンクに加えて QR コードも付しており,スマートフォンをかざすだけで,いつでもどこでも井上&堀田の生の対話に立ち返ることができます.書籍という静的な文字メディアと,YouTube という動的な映像メディアとを,この特設HPをハブとして自由に行き来きしていただければ.
動画から書籍へというメディアの移植は,著者としてもたいへん興味深い経験でした(cf. 「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1])).動画で話していたときには意識していなかった論点が,活字化の過程でくっきりと浮かび上がってくることもあれば,逆に,動画ならではの身振り手振りや声のトーンが含んでいたニュアンスが,文字だけでは伝えきれないというもどかしさを感じることもありました.
読者の皆さんには,ぜひこの特設HPにアクセスしつつ,両メディアの違いを味わっていただければと思います.「動画のこの部分が,本ではこう表現されているのか」「本で読んで疑問に思った点が,動画を見たら氷解した」といった発見がありましたら,それこそが本書の最もおもしろい楽しみ方といえます.また,本書とその魅力を SNS などで共有していただけると嬉しく思います.
今朝の heldio でも「#1600. 「いのほたなぜ」の特設HPをオープンしましたとして同じ話題でお話ししていますので,ぜひお聴きください.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-15 Wed
■ #6015. 本日「いのほたなぜ」が出ます [inohotanaze][inohota][inoueippei][notice][helkatsu]
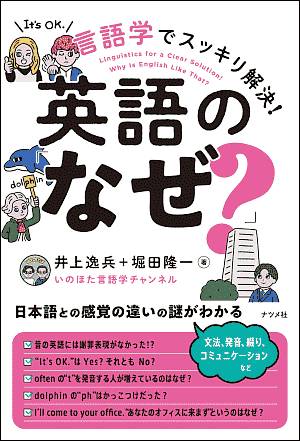
同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が本になりました! 本日10月15日が発行日となっております.ただし Amazon などの配本は,もう2,3日後のことになるようですので,予約注文された方は,もうしばらくお待ちください.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)
今回出版されるいのほた本の公式な略称は「いのほたなぜ」となっております.X(旧 Twitter)をはじめとする SNS のハッシュタグでは,平仮名6文字で #いのほたなぜ として展開していますので,ご協力のほどよろしくお願い致します.本書に関するご意見やご感想も,このハッシュタグを付して各種 SNS でご投稿ください.ご投稿のいくつかは,今後 hellog や heldio で取り上げて行く予定です.本書については,本ブログの「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) もお読み頂ければ.
さて,1ヶ月ほど前の9月13日のことですが,多くの方々に「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画にご参加いただき,盛り上げていただきました.その様子は,YouTube にて「いのほた本ライブ」としてご覧になれます.その折にたくさんの予約注文をいただきましたが,なんと同日の夜には Amazon 新着ランキングの英語部門で第2位を記録するに至りました.改めて皆さんの熱量に驚くとともに感謝申し上げます(cf. 「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1])).
今後は井上さんとともに「いのほたなぜ」の内容紹介などを様々な形で行なっていくつもりです.本ブログのみならず heldio や X アカウント などのメディアにも,ぜひご注目ください.今朝の heldio は「#1599. 「いのほたなぜ」本日発売です.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-10-09 Thu
■ #6009. 現在から過去へ遡る「遡及的英語史」の魅力 --- 「いのほた言語学チャンネル」より [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][hel][historiography][link]
10月5日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」より最新動画が配信されました.「#377. 角度を変えると,歴史は別物になる --- 遡及的英語史:理解は「今」から始まる」と題して,通常の通時的な歴史叙述とは異なる,現在から過去へと遡る「遡及的記述」という方法論について,井上さんと議論しました.今回注目した本は,英語史の古典的名著の1つ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970. です.この本を学生時代に読んだとき,目から鱗が落ちました.
歴史を語る方法として,多くの皆さんが思い浮かべるのは,最も古い時代から順に新しい時代へと進み,現代に至るという「年代順記述」でしょう.教科書も講義も,ほとんどはこのオーソドックスな方法を採用しています.しかし,Strang はその常識を覆し,出版当時の1970年代の「現在」から遡って,200年ずつのブロックで「過去」へと記述を進めるという斬新なアプローチをとりました.本格的な英語史書でこの手法を一貫して採用したのは,Strang が最初でしょう.
この遡及的記述には,いくつかのメリットがあります.まず第1に,現代に生きる私たちが抱く「なぜ今こうなっているのか?」という疑問からスタートできることです.現代の問題意識を起点に過去を遡ることで,歴史が単なる暗記科目ではなく,常に現代と関連づけられる生きた学問として捉えやすくなります.
第2に,情報は過去に遡るほど少なくなり,やがては靄に包まれていくという,知り得ることの限界に関する自然な現実に合致している点です.遡及的な記述は,明確なところから曖昧な部分へと自然に徐々に消えていく感があり,歴史の不思議とロマンへも誘ってくれます.
第3に,歴史に始まりも終わりもないという本質を表現できる点です.従来の記述では,便宜的に設定された始点と終点によって歴史が枠にはめられてしまいますが,実際には英語という言語に特定の「始まり」はなく,その物語は未来へと "to be continued" していくものであり「終わり」もないのです.
もちろん,遡及的記述には,言語変化の因果関係の説明が難しいというデメリットも存在します.原因は時間的に前にあり,結果は後に来るという「原因と結果の法則」は揺るぎありません.遡及的な順序では,「なぜこうなったのか?」という問いかけに対し,直感的に逆行する説明を強いられるため,ストレートな議論がしにくいという欠点があります.Strang 自身もこの点は認識しており,200年ごとのブロック内部では年代順に記述を進めることで因果関係を説明しようと試みています.
しかし,この一風変わった試みは,歴史の見方に新たな視点を与えてくれることは間違いありません.インドヨーロッパ祖語の系統樹を上下反転させてみるだけでも,見え方が大きく変わるように,歴史の「角度を変える」ことは,私たちの理解を深めるための重要な一歩となります.
この Strang の英語史書は,英語史の初めの1冊としてふさわしいかといえば,まったくふさわしくありません.順当な年代順記述から始めるのがよいでしょう.しかし,英語史にある程度慣れてきたところで読んでみると,その斬新さにきっと驚かれると思います.ぜひ今回の動画をご覧いただき,この遡及的な歴史記述の世界に触れてみてほしいと思います.
同じような議論は,これまでの hellog や heldio でも展開していますので,そちらも合わせてご参照ください.
・ hellog 「#253. 英語史記述の二つの方法」 ([2010-01-05-1])
・ hellog 「#2720. 歴史の遡及的記述の長所と短所」 ([2016-10-07-1])
・ heldio 「#656. 現在から過去にさかのぼる英語史」
「いのほた言語学チャンネル」と関連して,1つお知らせがあります.6日後の10月15日(水)に「いのほた本」が出ます! 詳細は,ぜひ「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) の記事をご覧ください.
・ Strang, Barbara M. H. A History of English. London: Methuen, 1970.
2025-09-25 Thu
■ #5995. khelf の藤平さんに「いのほたなぜ」のチラシを作成していただきました [notice][inohotanaze][inohota][inoueippei][khelf][helkatsu]

井上逸兵さんとともに毎週水・日にお届けてしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」が近々書籍化されることについては,「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) や「#5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位!」 ([2025-09-15-1]) の記事で触れてきました.発売は10月15日(水)となります.Amazon のこちらのページより予約受付中です.
上記のチラシは,khelf の藤平さんに制作していただきました.いつもご協力ありがとうございます! チラシの以下の文句にあるとおりの書籍です.
専門の知見をわかりやすく解説.「そう習ったから」では終わらない,一歩先の理解に繋がる一冊.
目下「いのほたなぜ」の編集者および著者2人で,本書を紹介する様々なコンテンツを作成中です.まず,特設ランディングページ (LP) を作っています.そこでは本書を紹介するのみならず,本書の各章と,元ネタとなっている「いのほた言語学チャンネル」の配信回とを結びつけたリンク集も掲載する予定です.
また,YouTube チャンネルから生まれた書籍だけに,動画でのお知らせにも力を入れていきます.9月13日(土)に井上&堀田で生配信した以下の「いのほた本ライブ」を皮切りに,今後に向けてショート動画も制作中です.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-09-23 Tue
■ #5993. 英語の未来と生成AIが拓く新たな局面 --- 言語における求心力と遠心力のダイナミズム [variety][sociolinguistics][function_of_language][future_of_english][world_englishes][model_of_englishes][notice][youtube][inohota][inoueippei][inohotanaze][ai]
一昨日 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新動画が配信されました.題して「#373. これからの英語はどうなる?AIと世界の英語・英語の未来を読む:多様化・AI・世界化」です.今回は,まさに今,私たちが目の当たりにしている言語とテクノロジーの劇的な交錯について,井上さんと議論を深めました.
この話題を選んだきっかけは,私が以前出演させていただいた「文藝春秋PLUS 公式チャンネル」で,関連する英語史トークを展開したことにあります.そのトークの最後のほうで,英語の多様性やその未来について触れたのですが,同じテーマを「いのほた言語学チャンネル」でもさらに掘り下げてみようと考えた次第です.今や生成AIによるリアルタイム通訳も実用的になりつつあり,英語の未来を考える上で,これは避けて通れない話題となっています.
いのほた動画では,英語(ひいては言語一般)のもつ「2つの相反する力」について議論しました.1つは,英語が世界の共通語,つまりコミュニケーションの道具としての役割を果たす「求心力」 (centripetal force) です.世界には約7000もの言語があると言われますが,その中で英語は最も広く通用する言語として,私たちの学習目標となってきました.異なる言語を話す人々を結びつける強力なツールとしての英語,という側面です.
しかし,同時に英語(ひいては言語一般)にはもう1つの側面があります.それは「遠心力」 (centrifugal force) です.20世紀後半以降,世界英語 (world_englishes) という現象が顕著になり,世界各地で標準英語から逸脱した多様な英語が生まれ,話されています.これは,各々の地域の話者が,独自の英語変種を通じて自身のアイデンティティを表現しようとする動きにほかなりません.言語が単なるコミュニケーションの道具にとどまらず,所属する集団や個人のアイデンティティを示す手段となるわけです.結果として,同じ英語を話していても,お互いにとって理解しにくい方向に枝分かれしていくという,一見矛盾した状況が生じています.
私は,この求心力と遠心力こそが,言語のダイナミズムを支える両輪であると考えています.結びつけようとする力と,分かち隔てようとする力.これらは常に拮抗し,揺れ動くことで言語変化の原動力となっているのです.社会がグローバル化すれば求心力が強まり,個々が多様性を志向すれば遠心力が強まる.まるで振り子のように揺れ動きながら,言語は機能し続けていると言えます.この2つの相反する力については,「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1]) や「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]) もご参照ください.
そして,人類史上長らく続いてきたこの言語のダイナミズムに,今,生成AIという前代未聞の技術が投入されてきています.これまでのコンピューター技術は標準的な英語のみを扱ってきたと言ってよいですが,AIは多様な英語をも処理できるようになりつつあります.これは,英語がインフラとしての基盤的役割を今後も担い続けるのかどうかという根本的な問いを突きつけているとも言えます.言語の求心力と遠心力のバランスは,AIの発展によってどのように変容していくのか,今後注視していくべき現象です.
2020年代は,人類言語史における大きな転換点として記憶されることになるかもしれません.私たちは今,その歴史の瞬間に立ち会っていると言えます.英語の未来,そして言語そのものの未来がどうなっていくのか,引き続き注目していきたいと考えています.ぜひ,今回の「いのほた言語学チャンネル」の配信をご覧いただき,皆さんも一緒に考えてみていただければ.
「いのほた言語学チャンネル」と言えば,10月15日に「いのほた本」が出ます! 詳細は,ぜひ「#5973. 「いのほた本」が出ます! --- 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』(ナツメ社)」 ([2025-09-03-1]) の記事をどうぞ.
2025-09-15 Mon
■ #5985. 一昨日「いのほたなぜ」予約爆撃アワー企画の効き目,英語部門で第2位! [inohotanaze][hellive2025][heldio][helkatsu][inohota][inoueippei][youtube][notice]
一昨日,「英語史ライヴ2025」を開催しました.「#5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」」 ([2025-09-13-1]) で予告した通り,当日の16:00より,Voicy heldio と YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両プラットフォームにて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信しました.
10月15日にナツメ社より出版予定の「いのほたなぜ」こと,井上・堀田の初めての共著となる『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』を,皆さんの力をお借りして,広めていただきたいという趣旨で企画したお祭りイベントです.会場参加された方々,およびライヴ視聴者の皆さんとともに,Amazon の本書のページより,一斉に(といっても文字通りにではありませんが)予約注文していただきました.当日は,ライヴのコメント欄などを通じても,熱い応援をいただき,たいへん心強く感じました.ありがとうございます.
当日のライヴの様子は,その後両プラットフォームでアーカイヴとしても出そろいましたので,ぜひ視聴・聴取していただければと思います.
・ Voicy heldio: 「#1569. 「いのほたなぜ」予約爆撃アワー --- 「英語史ライヴ2025」より」
・ YouTube: 「いのほた本ライブ」
さて,予約爆撃アワー企画の効き目はどうだったのでしょうか? 当日の夜に本書の順位を確認したところ,なんと Amazon 新着ランキングの英語部門で第2位にまで上がっていました! 短時間で皆さんにここまで押し上げていただきました.ありがとうございます.トップの座には手強いライバルが座っていますが,これからますます本書を広めて行きたいと思っています.引き続きご支援をお願いします!

2025-09-14 Sun
■ #5984. 昨日の「英語史ライヴ2025」おおいに盛り上がりました! [khelf][helwa][heldio][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube][helvillian][kenkyusha]

昨日9月13日(土),予定通り Voicy heldio にて「英語史ライヴ2025」が開催されました.khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の主催する音声配信イベントで,早朝から夕方まで断続的にではあれ,多くの英語史に関する音声セッションが配信されました.収録会場にはメンバー30名ほどが集まり,和やかな雰囲気のなかで収録したり,懇親したりしました.
まず,早朝6時からは,平常通りの heldio 配信.その後,helwa 配信も行ないました.7時からは Taku さんこと金田拓さん(帝京科学大学)との超精読セッション.続いて8時からは小河舜さん(上智大学)との「千本ノック」.土曜日の朝早くからの生配信でしたが,収録現場には複数名のギャラリーに立ち会っていただき,数十名のリスナーの方々にライヴでお聴きいただきました.大盛り上がりでした.
9時からは,皆で本格的に会場設営.10時頃からいくつかの収録室に分かれ,次々と音声セッションを収録しました.生配信でお届けすることもあれば,収録し終わったものを後からアーカイヴ配信することもありましたが,夕方までに heldio と helwa を合わせて10本近くの配信回をお届けすることになりました.
そして,最後に16時からは,heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 の両方にて,井上逸兵さんとともに「いのほた本の予約爆撃アワー」を生配信.来たる10月15日(水)に発売予定の井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.を,Amazon より皆に一斉に注文していただこうというお祭りイベントです.多くの皆さんにご参加いただきまして,ありがとうございました.
一日を通じて,会場には全国津々浦々からの参加者がお持ちになったお菓子で溢れていました.また,ラジオなので一般にお見せすることはできませんでしたが,多くの参加者が,今回のイベントのために有志で制作されたTシャツを着用していました.『英語語源ハンドブック』の表紙をモチーフとした Helvillian のTシャツです.さらに,午後からは研究社による英語史関連書のフェアが開かれ,賑わいました.多くの皆さんのご協力のもと,17時前には無事にイベントが終了しました.
夜はお楽しみの懇親会.1次会,2次会とはしごして夜が更けましたが,最後まで参加者の皆さんと英語史を語り続ける,思い出に残る1日となりました.
昨日中に公開されたセッションは十数本に限られますが,後日のアーカイヴ配信のために収録したセッションも数多くあり,ある意味では「英語史ライヴ2025」は終わっていません.むしろ始まったばかりです.ぜひ今後の heldio/helwa 配信にご期待ください.
以上,「英語史ライヴ2025」の盛会の旨,簡単に報告いたしました.リスナーの皆さん,関係者の方々,本当にありがとうございました!
2025-09-13 Sat
■ #5983. 本日の「英語史ライヴ2025」の締めは,16:00からの「いのほた本の予約爆撃アワー」 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

本日9月13日(土)は,昨日の記事 ([2025-09-12-1]) で予告した通り,年に一度の Voicy heldio による英語史のお祭り「英語史ライヴ2025」が開催されます.朝6時の通常配信を皮切りに,夕方5時頃まで,断続的に heldio/helwa で生配信やアーカイヴ配信をお届けします.主催は khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa の有志メンバーたちです.東京の収録会場に集まり,英語史に関する様々なセッションを収録・配信していきます.
hellog 読者の皆さん,heldio/helwa リスナーの皆さんにおかれましては,ぜひ英語史漬けの1日をお楽しみください.本イベントの特設HPをこちらに設けておりますので,ぜひご覧ください.
本日の hellog 記事としては,とりわけ16時より heldio および YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて同時生配信を予定している「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画についてお知らせします.
同僚の井上逸兵さんと毎週2回,水・日曜日に配信している同 YouTube チャンネルが本になりました! 来たる10月15日(水)に発売予定です.
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.(← Amazon へのリンク)
本日16時から heldio および YouTube にて生配信でお届けする予定の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は,井上・堀田がこの「いのほた本」をライヴで紹介しつつ,リスナーの有志の皆さんにその場で Amazon にて予約注文していただき,全体としてお祭りムードで盛り上がろうという遊び企画です.ぜひ時間になりましたら,いずれかのメディアにアクセスしていただき,こちらの Amazon リンクより予約注文していただければ幸いです.昨晩時点では,新着ランキングの英語部門にて,すでに第15位にランクインしています.「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」での皆さんのご協力により,ランクをさらに押し上げていただければと思います.この本を通じて,英語史・英語学・言語学のおもしろさを多くの方に伝えたいというのが,著者2人の願いです.
本書の内容や趣旨については,今後,本ブログでもご紹介していきますが,まずは本日16時の「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画にご参加いただければ幸いです.その時間は都合が悪いという方も,ぜひ夕方以降に予約注文をしていただければ.
どうぞよろしくお願いいたします.
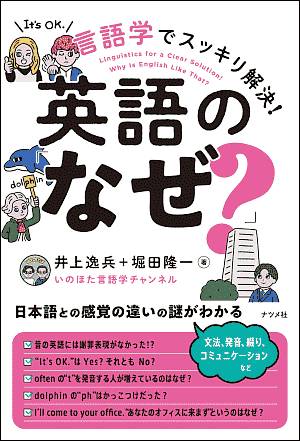
・ 井上 逸兵・堀田 隆一 『言語学でスッキリ解決!英語の「なぜ?」』 ナツメ社,2025年.
2025-09-12 Fri
■ #5982. 明日9月13日(土),早朝6時から「英語史ライヴ2025」開催 [khelf][helwa][hellive2025][notice][helkatsu][helmate][inohota][inoueippei][inohotanaze][youtube]

昨年に続き,今年も「英語史ライヴ」を開催します.明日9月13日(土)の早朝6時より開始です.Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」およびプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」にて,hel活 (helkatsu) の仲間たちとともに英語史に関する話題を1日中お届けします.
朝6時から夕方5時頃まで,断続的に生配信あるいはアーカイヴ配信を行ないますので,リスナーの皆さんにおかれましては,配信回の新着通知が届くよう,この機会に heldio のチャンネルのフォローをお願いいたします.また,同じくこの機会にプレミアム限定配信「英語史の輪 (helwa)」(月額800円のサブスクで,初月無料)にもお入りいただければ,追加的に helwa での新着配信もお聴きいただけます.
主催は,khelf(慶應英語史フォーラム)および helwa です.主として khelf の大学院生メンバーと helwa の有志メンバーに,事前の準備から明日のイベント当日の音声配信制作まで,直接,間接に携わっていただいています.会場参加される方々にとっては,hel活メンバー同士の交流の機会ともなりますので,おおいにお楽しみください.
ライヴの特設HPをこちらに準備しましたので,詳しくはそちらからどうぞ.配信スケジュールについては,最初と最後のほうに固定のセッションがいくつかありますが,日中の大部分の時間帯についてはフレキシブルとなりますのでご了承ください.
固定セッションのうち,とりわけ夕方4時からの「『いのほたなぜ』予約爆撃アワー」企画は必聴です.井上逸兵さんとともに,heldio のみならず YouTube 「いのほた言語学チャンネル」からも生配信します.10月15日に発売予定の「いのほた本」についてお話ししながら,皆で一緒に予約注文してしまいましょう,という盛り上げ企画となっています.
それでは,明日の「英語史ライヴ2025」をお楽しみに!
2025-09-05 Fri
■ #5975. 名著『英語語源辞典』の制作舞台裏 [kdee][notice][heldio][inohota][inoueippei][youtube][khelf][hel_herald]

『英語語源辞典』,あるいは KDEE (= The Kenkyusha Dictionary of English Etymology) は,世界最強の英語語源辞典として私が推し続けている書籍ですが,その制作舞台裏のストーリーも同じくらい強力です.同辞典は,辞書出版社である研究社の,最後の活版印刷による辞典なのです.日本の英語系出版史上の金字塔ともいってよいでしょう.
KDEE の制作舞台裏については,これまでも様々な媒体で取り上げてきました.近日中に改めて大々的に取り上げるべく新企画が進行中なのですが,この機会にこれまでの関連コンテンツをまとめておきたいと思います.
【 研究社 note (2023年8月1日) 】
KDEE の制作舞台裏に関する一連の話題の火付け役となったのは,研究社公式の「研究社note」に公開された「『英語語源辞典』と活版印刷裏話」と題する記事でした.2023年8月1日に,研究社の編集社さんがまとめられた文章です.何はともあれ,まずそちらをお読みください.
【 Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」 (2023年9月) 】
上記 note 記事を読み,あまりにおもしろいお話しだったので,同じ2023年の夏に,研究社にお声がけし,KDEE の編集・印刷に携わった方々にインタビューさせていただきました.そのインタビューは Voicy heldio にて3部作として公開されました.ぜひアーカイヴよりお聴きください.
・ 「#828. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (1)」
・ 「#834. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (2)」
・ 「#842. 『英語語源辞典』(研究社,1997年)ってスゴい --- 研究社会議室での対談 (3)」
【 YouTube 「いのほた言語学チャンネル」 (2024年7月7日) 】
同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でも KDEE 制作舞台裏に関する話題に触れました.2024年7月7日「#247. 堀田が1年間推してきた,日本語だが内容的には英語語源辞典の世界ベスト・寺澤芳雄編集主幹『英語語源辞典』(研究社)」です.
【 『英語史新聞』の号外(2024年9月8日発行) 】
khelf(慶應英語史フォーラム)が発行している『英語史新聞』の2024年9月8日の号外「英語史ラウンジ 第4回 寺澤盾先生 番外編」にて,KDEE の誕生秘話が紹介されています.khelf メンバーが,KDEE の制作にも関わられた寺澤盾先生(青山学院大学教授,東京大学名誉教授)の研究室に赴き,インタビューした内容が記事となったものです.寺澤盾先生の研究室に同辞典のゆかりの品があり,写真撮影も許可していただきました.関連記事・配信回も以下よりどうぞ.
・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])
・ 「#1216. 『英語史新聞』第10号と号外のお披露目 --- 「英語史ライヴ2024」より」
【 「hellog~英語史ブログ」 (2023年8月以降) 】
本ブログでも,上記のコンテンツへのリンクも含め, KDEE 制作舞台裏について,たびたび取り上げてきました.以下ではそのうち主立った記事のみ掲げます.ぜひ kdee のタグのついた他の記事もお読みいただければ.
・ 「#5210. 世界最強の英語語源辞典 --- 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)」 ([2023-08-02-1])
・ 「#5261. 研究社会議室での3回にわたる『英語語源辞典』をめぐるインタビューが完結」 ([2023-09-22-1])
・ 「#5436. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年3月15日版」 ([2024-03-15-1])
・ 「#5522. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2024年6月9日版」 ([2024-06-09-1])
・ 「#5553. 寺澤芳雄(編集主幹)『英語語源辞典』(研究社,1997年)の新装版 --- 「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました」 ([2024-07-10-1])
・ 「#5616. 『英語史新聞』号外が発行されました --- 『英語語源辞典』制作にかかわる貴重なエピソード」 ([2024-09-11-1])
・ 「#5856. 私の『英語語源辞典』推し活履歴 --- 2025年5月9日版」 ([2025-05-09-1])
2024年6月には新装版も刊行され,KDEE はますます勢いを得ています.ぜひ皆さんのお手元に1冊ご用意ください.KDEE 制作舞台裏に関する新企画もお楽しみに!
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow