2024-11-04 Mon
■ #5670. Grassmann's law --- 「グラスマンの法則」 [grassmanns_law][grimms_law][sound_change][sanskrit][greek][indo-european][dissimilation][verners_law][aspiration][phonetics][consonant]
著名なグリムの法則 (grimms_law) には,提案された当時より,様々な例外があることが気づかれていた.最も有名なのはヴェルネルの法則 (verners_law) に関する例外だが,もう1つグラスマンの法則 (grassmanns_law) というものがある.『新英語学辞典』 '(209--300) より,該当の解説を引く.
次に発見された例外は,通常グラスマンの法則 (Grassmann's law) と呼ばれるものである.ある系列の印欧語の対応は Grimm が設定した型に合致せず,説明が困難であったが,Herman Grassmann (1809--77) はギリシア語やサンスクリットのデータを調べ,これらの言語では例外的に不規則な対応を発達させたことを明らかにした.例えば
Goth. Skt -biudan 'offer' bódhāmi 'notice' dauhtar 'daughter' duhitā' gagg 'street' jánghā 'leg'
等の対応において,グリムの法則によればゲルマン語の b, d, g に対応するサンスクリットの語頭は帯気音 (bh, dh, gh) でなければならないのに非帯気音である.Grassmann は,これはギリシア語およびサンスクリットにおいて,二つの隣接する音節で帯気音が続いたとき,どちらか一つは異化 (DISSIMILATION) によって非帯気音になる現象のせいであることを発見した.ここにおいて言語学者は,単音の特徴や音声環境だけでなく,相接する音節との関係にも注意しなければならないことを知ったのである.
Bussmann の用語辞典からも引いておこう (198--99) .
Grassmann's law (also dissimilation of aspirates)
Discovered by Grassmann (1863), sound change occurring independently in Sanskrit and Greek which consistently results in a dissimilation of aspirated stops. If at least two aspirated stops occur in a single word, then only the last stop retains its aspiration, all preceding aspirates are deaspirated; cf. IE *bhebhoṷdhe > Skt bubodha 'had awakened,' IE *dhidhēhmi > Grk títhēmi 'I set, I put.' This law, which was discovered through internal reconstruction, turned a putative 'exception' to the Germanic sound shift (⇒ 'Grimm's law). . . into a law.
・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.
・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics''. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.
2024-07-04 Thu
■ #5547. father の語形について再び [phonetics][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][analogy][hybrid][contamination][sound_change][consonant][fricativisation]
father という単語は,比較言語学でよく引き合いにだされる語の代表格だ.ところがなのか,だからこそなのか,この語形を音韻論・形態論的に説明するとなるとかなり難しい.現在の語形は音変化の結果なのか,あるいは類推の結果なのか.おそらく両方が複雑に入り交じった,ハイブリッドの例なのか.基本語ほど,語源解説の難しいものはない.
ここでは Fertig (78) の contamination 説を引用しよう.ただし,これは1つの説にすぎない.
The d > ð change in English father (<OE fæder is a popular example of contamination). (The parallel case of mother is cited less often in this context, for reasons that are not entirely clear to me.) The claim is that, by regular sound change, this word should have -d- rather than -ð- both in Old English (as it apparently did) and in Modern English (as is clearly does not). The -ð- in Modern English is thus attributed to contaminating from the semantically related word brother, which has had -ð- throughout the history of English . . . .
father の第2子音を説明するというのは,英語史上最も難しい問題の1つといってよい.なぜ father が father なのか,その答えはまだ出ていない.以下,関連する記事を参照.
・ 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])
・ 「#481. father に起こった摩擦音化」 ([2010-08-21-1])
・ 「#698. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (1)」 ([2011-03-26-1])
・ 「#699. father, mother, brother, sister, daughter の歯音 (2)」 ([2011-03-27-1])
・ 「#703. 古英語の親族名詞の屈折表」 ([2011-03-31-1])
・ 「#2204. d と th の交替・変化」 ([2015-05-10-1])
・ 「#4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-11-25-1])
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-06-16 Sun
■ #5529. なぜ once の -ce が古英語属格の -es 由来であるなら,語末子音は /z/ にならず /s/ なの? [sobokunagimon][numeral][reanalysis][inflection][genitive][adverbial_genitive][adverb][verners_law]
今回は英語の先生より寄せられた疑問を紹介します.標題はもはや素朴な疑問 (sobokunagimon) の域を超えており,高度な英語史リテラシーを持っていて初めて生ずる疑問だろうと思います.
まず歴史的事実として,頻度・度数の副詞 once や twice の -ce は古英語の男性・中性の単数属格語尾 -es に遡ります.歴史的には副詞的属格の典型例となります.この件については「#84. once, twice, thrice」 ([2009-07-20-1]) と「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) で話題にしました.
once の語末子音が古英語の属格の -es(現代英語の所有格の 's に相当)に起源をもつのであれば,once の発音は現代の one's /wʌnz/ と同じになりそうなものですが,実際には語末子音は無声音で /wʌns/ となります.これはどうしたことか,という高度な疑問です.
今回の素朴な疑問については,先に挙げた2つめの hellog 記事「#4081. once や twice の -ce とは何か (2)」 ([2020-06-29-1]) の後半でも少し触れています.その部分を引用すると,問題のこの単語は
中英語では ones, twies, thrise などと s で綴られるのが普通であり,発音としても2音節だったが,14世紀初めまでに単音節化し,後に s の発音が有声化する契機を失った.それに伴って,その無声音を正確に表わそうとしたためか,16世紀以降は <s> に代わって <ce> の綴字で記されることが一般的になった.
ここで言わんとしていることは,副詞の once, twice, thrice は,その起源や語形成の観点からは属格と結びつけられるものの,おそらく中英語期にはすでにその発想が忘れ去られ,one + -es としては(少なくとも明確には)分析されないようになり,全体が1つの語幹であると意識されるに至ったのだろう,ということです.折しも中英語後期には -es の母音が弱化・消失し,単語全体が1音節となったことにより,1つの語幹としての意識がますます強くなったと思われます.だからこそ,続く近代英語期には,もはや屈折語尾を想起させる -<(e)s> と綴るのはふさわしくなく,同部分があくまで語幹の一部であるという解釈を促す -<ce> という綴字へと差し替えられたのではないでしょうか.
最後に語末子音の有声・無声の問題について触れます.古英語から中英語にかけて,屈折語尾として解釈された -(e)s は /(ə)s/ のように無声子音を示していました.ところが,近代英語期にかけて,この屈折語尾音節の /s/ が /z/ へと有声化します(これについては「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照).これにより,現代では(後の歴史的な事情により,有声音に先行される場合に限ってとなりますが)所有格語尾の -'s は /z/ で発音されることになっています.
しかし,副詞 once の類いは,この一般的な音変化の流れに,どうも乗らなかったようなのです.それは,先にも述べたように,早い段階から,問題の語尾が屈折語尾ではなく語幹の一部として認識されるようになっていたこと,また単語が1音節に縮まっていたことが関係していると思われます.
2024-05-29 Wed
■ #5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][grimms_law][verners_law][consonant][stress][phonetics][loan_word][french][latin][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
これまでに第1回「語源辞典でたどる英語史」を4月27日(土)に,第2回「英語語彙の歴史を概観する」を5月8日(土)に開講しましたが,それぞれ驚くほど多くの方にご参加いただき盛会となりました.ご関心をお寄せいただき,たいへん嬉しく思います.
第3回「英単語と「グリムの法則」」は来週末,6月8日(土)の 17:30--1900 に開講されます.シリーズを通じて,対面・オンラインによるハイブリッド形式での開講となり,講義後の1週間の「見逃し配信」サービスもご利用可能です.シリーズ講座ではありますが,各回はおおむね独立していますし,「復習」が必要な部分は補いますので,シリーズ途中からの参加でも問題ありません.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.

2回かけてのイントロを終え,次回第3回は,いよいよ英語語彙史の各論に入っていきます.今回のキーワードはグリムの法則 (grimms_law) です.この著名な音規則 (sound law) を理解することで,英語語彙史のある魅力的な側面に気づく機会が増すでしょう.グリムの法則の英語語彙史上の意義は,思いのほか長大で深遠です.英語語彙学習に役立つことはもちろん,印欧語族の他言語の語彙への関心も湧いてくるだろうと思います.『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする語源辞典や,一般の英語辞典も含め,その使い方や読み方が確実に変わってくるはずです.
講座ではグリムの法則の関わる多くの語源辞典で引き,記述を読み解きながら,実践的に同法則の理解を深めていく予定です.どんな単語が取り上げられるかを予想しつつ講座に臨んでいただけますと,ますます楽しくなるはずです.『英語語源辞典』をお持ちの方は,巻末の「語源学解説」の 3.4.1. Grimm の法則,および 3.4.2. Verner の法則 を読んで予習しておくことをお薦めします.
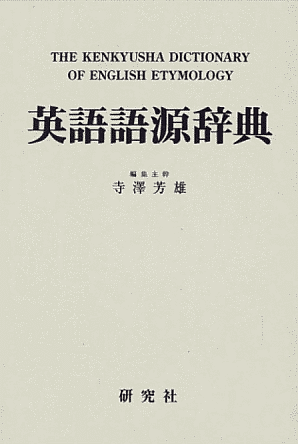
参考までに,本シリーズに関する hellog の過去記事へのリンクを以下に張っておきます.第3回講座も,多くの皆さんのご参加をお待ちしております.
・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])
・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])
・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])
(以下,後記:2024/05/30(Thu))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2023-06-06 Tue
■ #5153. knowledge, Greenwich, spinach の語末有声子音 [verners_law][consonant][stress][phonetics][spelling]
標題の3語の発音は各々次のようになる.語末子音に注目されたい.
・ knowledge [ˈnɑlɪʤ]
・ Greenwich [ˈgrɪnɪʤ, ˈgrɛnɪʤ, ˈgrɛnɪʧ]
・ spinach [ˈspɪnɪʧ, ˈspɪnɪʤ]
通常の綴字と発音の関係でいえば <dge> ≡ [ʤ],<ch> ≡ [ʧ] が普通である.knowledge は予想通りだが,Greenwich, spinach については <ch> ≡ [ʤ] の発音もあり得るという点でやや異質である.
これらの語における語末の有声破擦音 [ʤ] は,本来の無声破擦音が近代英語期に有声化したものである.英語史内での Verner's Law として知られる音変化だ (cf. 「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1])).「アクセントが子音の直前にないとき,その子音は有声化する」という規則を示す音変化で,例としてよく挙げられるのは ˈabsolute -- abˈsolve, ˈanxious -- anxˈiety, ˈexecute -- exˈecutive, exhiˈbition -- exˈhibit, ˈluxury -- luxˈurious, ˈoff -- of など摩擦音 [s, z, ks, gz, ʃ, ʒ, f, v] が関わるペアだが,標題の語のように破擦音 [[ʧ, ʤ]] が関わるものもある.
Prins (225) より,後者の例とその説明を引こう.
5. ʧ > ʤ
ME knowleche > MoE knowledge partriche > partridge spinach > spinach ['spinidʒ]
and in the suffix -wich in place-names: Norwich [noridʒ], Greenwich [grinidʒ], Woolwich [wulidʒ], Harwich [hæridʒ], Bromwich [brʌmidʒ]
Instead of the obsolete old pronunciation Ipswich [ipsidʒ] we find now [ipswitʃ].
The voicing is also found in MoE ajar < Scots and Nth dialect achar < on char-e (OE čerr, 'turn').
引用の最後にある通り,ajar が古英語 on cierre に遡るというのが興味深い.
・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.
2021-06-12 Sat
■ #4429. 序数詞 third の d と fourth の th の関係 [indo-european][germanic][numeral][grimms_law][verners_law][suffix][metathesis]
6月2日より,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしています.日々10分弱の英語史の話題を配信していますが,昨日は「third は three + the の変形なので準規則的」という話題を取り上げました(cf. 「#92. third の音位転換はいつ起こったか」 ([2009-07-28-1]),「#93. third の音位転換はいつ起こったか (2)」 ([2009-07-29-1]),「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])).この話題について専門的な補足を加えたいと思います.
third の末尾の -d は fourth など4以上の序数詞の末尾に現われる -th と起源的に同一物であり,それが変形したものであるという趣旨で話しました.大雑把にいえば上記の通りに理解しておいてよいのですが,厳密に議論すればそれなりに込み入った事情があります.
印欧語族の序数詞の語尾にはいくつかの種類があり,英語の -th に連なる語尾が唯一のものではありませんでした.3の序数詞についていえば,再建された形態としては,-th に連なる語尾を含む *tri-to- もあれば,別に *triy-o という形態もありましたし,さらにこれらの複雑な混成形と考えられる *t(e)r(e)tiyo- もありました.この最後のものが,現代英語の third (< OE þridda) を出力することになります.したがって,third の d は -th の起源である *-to- と直系の関係にはなく,あくまで「混成」を経由しての間接的な関係というのが正確なところです.典拠として,Mallory and Adams (311) を引用しておきます.
The number 'three', *tréyes (neuter: triha), is also marked by different forms for the different genders and was declined as an -i-stem plural (e.g. OIr trī, Lat trēs, NE three, Lith trỹs, OCS trije [m.], tri [f./nt.], Alb tre [m.], tri [f.], Grk treîs, Arm erek ̔, Hit tēri-, Av θrayō [m./f.], θri [nt.], Skr tráyas [m./f.], trī [nt.], Toch B trai [m.], tarya ([f.]). In some languages we have reflections of a very unusual feminine form, *t(r)is(o)res, i.e. OIr teōir, Av tišrō, Skt tisrás. The underlying derivation of *tréyes is generally sought in either *ter 'further', i.e. the number beyond 'two', or from a *ter- 'middle, top, protruding', i.e. the middle finger, assuming one counted on one's fingers in Proto-Indo-European. Again, the probability that either suggestion is correct is very low. The ordinal number is indicated by a variety of forms similar to *triy-o (e.g. Arm eri 'third', Hit teriyan 'third', tariyanalli- '賊 third officer'), or *tri-to- (e.g. Alb tretê, Grk trítos, Skt tritá-, Toch B trite), or finally *t(e)r(e)tiyo- (e.g. NWels tryddyd, Lat teritius, NE third, Lith trẽčias, Rus trétij, Av θritiya-, Skt tr̥tíya-) which is presumably a conflation of sorts, in various ways, of the previous two while *tris supplies the multiplicative (e.g. Lat ter, Grk trís, Av θriš, Skt tríṣ; despite its apparent phonetic similarity, NE thrice is of a different origin.
上記の通り,現代英語 third そして古英語 tridda の祖形は *t(e)r(e)tiyo- にあったと想定され,問題の語尾の子音は t だったことになります.この子音は順当に発達すればグリムの法則 (grimms_law) により θ に発達していたはずと想定されますが,強勢が後続していたために同発達がブロックされ,ヴェルネルの法則 (verners_law) に従って有声化して ð となり,これが後に脱摩擦音化して d となりました.この一連の流れは,古英語 fæder (> PDE father) に d が確認されるのとまったく同じ流れです(cf. 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])).この点については Lass (214) より引用しておきましょう.
3rd. Go þridja, OE þridda, OIc þriþe. This is not entirely suppletive, as it still obviously contains the root for '3'. But the formation is different from that of the other ordinals, involving a suffix */-tjo:-/ (cf. L ter-ti-us). The E, WGmc forms must go back to a variant with an accented suffix, hence the voiced dental from Verner's Law. ModE third is metathesized from þridda (cf. bird < OE bridd, dirt < Osc drit).
なお,印欧祖語レベルでは,英語の -th 語尾に連なる */-to-/ は4,5,6の序数詞のみに当てはまり,ゲルマン語において7以上の序数詞にも付されるようになったのは,後の類推 (analogy) によるものです (Lass 215) .現代英語では4以上の序数詞は -th できれいに揃っているように見えますが,もともとはそうではなかったことになります.
・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2021-03-20 Sat
■ #4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達 [oe][germanic][indo-european][etymology][suffix][participle][i-mutaton][grimms_law][verners_law][verb][sound_change]
昨日の記事「#4344. -in' は -ing の省略形ではない」 ([2021-03-19-1]) で現在分詞語尾の話題を取り上げた.そこで簡単に歴史を振り返ったが,あくまで古英語期より後の発達に触れた程度だった.今回は Lass (163) に依拠して,印欧祖語からゲルマン祖語を経て古英語に至るまでの形態音韻上の発達を紹介しよう.
The present participle is morphologically the same in both strong and weak verbs in OE: present stem (if different from the preterite) + -ende (ber-ende, luf-i-ende. etc.). All Gmc dialects have related forms: Go -and-s, OIc -andi, OHG -anti. The source is an IE o-stem verbal adjective, of the type seen in Gr phér-o-nt- 'bearing', with a following accented */-í/, probably an original feminine ending. This provides the environment for Verner's Law, hence the sequence */-o-nt-í/ > */-ɑ-nθ-í/ > */-ɑ-nð-í/, with accent shift and later hardening */-ɑ-nd-í/, then IU to /-æ-nd-i/, and finally /-e-nd-e/ with lowering. The /-i/ remains in the earliest OE forms, with are -ændi, -endi.
様々な音変化 (sound_change) を経て古英語の -ende にたどりついたことが分かる.現在分詞語尾は,このように音形としては目まぐるしく変化してきたようだが,基体への付加の仕方や機能に関していえば,むしろ安定していたようにみえる.この安定性と,同根語が印欧諸語に広くみられることも連動しているように思われる.
また,音形の変化にしても,確かに目まぐるしくはあるものの,おしなべて -nd- という子音連鎖を保持してきたことは注目に値する.これはもともと強勢をもつ */-í/ が後続したために,音声的摩耗を免れやすかったからではないかと睨んでいる.また,この語尾自体が語幹の音形に影響を与えることがなかった点にも注意したい.同じ分詞語尾でも,過去分詞語尾とはかなり事情が異なるのだ.
古英語以降も中英語期に至るまで,この -nd- の子音連鎖は原則として保持された.やがて現在分詞語尾が -ing に置換されるようになったが,この新しい -ing とて,もともとは /ɪŋɡ/ のように子音連鎖をもっていたことは興味深い.しかし,/ŋɡ/ の子音連鎖も,後期中英語以降は /ŋ/ へと徐々に単純化していき,今では印欧祖語の音形にみられた子音連鎖は(連鎖の組み合わせ方がいかようであれ)標準的には保持されていない(cf. 「#1508. 英語における軟口蓋鼻音の音素化」 ([2013-06-13-1]),「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1])).
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2020-11-25 Wed
■ #4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][phonetics][consonant][sound_change][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][fricativisation]
標題の親族名称 (relationship_noun) は,英語を学び始めて最初に学ぶ単語の代表格です.いったん暗記して習得してしまうと「そういうものだ」という捉え方になり,疑うことすらしません.しかし,英語を学び始めたばかりの生徒の視点は異なります.標記のようなドキッとする質問が寄せられるのです.father, mother, brother, sister という親族名詞の基本4単語を眺めると,問題の子音について確かに sister だけが浮いていますね.これはどういうわけでしょうか.音声の解説をお聴きください.
千年前の古英語期,上記の4単語は fæder, mōdor, brōþor, sweostor という形態でした(<þ> は <th> に相当する古英語の文字です).つまり,<th> に相当するものをもっていたのは,実は brother だけだったのです.第5の親族名称である daughter (OE dohtor) も合わせて考慮すると,2単語で d が用いられ,さらに別の2単語で t が用いられ,そして1単語でのみ th が用いられたということになります.つまり,当時は brōþor の þ (= th) こそが浮いていた,ということすら可能なのです.これは,現代人からみると驚くべき事実ですね.
ここで疑問となるのは,なぜ古英語で d をもっていた fæder と mōdor が,現代までに当該の子音を th に変化させたかということです.これは中英語後期以降の音変化なのですが,母音に挟まれた d はいくつかの単語で摩擦音化 (fricativisation) を経ました.類例として furder > further, gader > gather, hider > hither, togeder > together, weder > weather, wheder > whether, whider > whither を挙げておきましょう.
議論をまとめます.現代英語の観点からみると確かに sister が浮いているようにみえます.しかし,親族名称の形態の歴史をひもといていくと,実は brother こそが浮いていたと結論づけることができるのです.英語史ではしばしば出くわす「逆転の発想」の好例です.
上の音声解説と比べるとぐんと専門的になりますが,音変化の詳細に関心のある方は,ぜひ##698,699,480,481,703の記事セットの議論もお読みください.
2020-09-16 Wed
■ #4160. なぜ th には「ス」の「ズ」の2つの発音があるのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][pronunciation][consonant][voice][th][verners_law][stress][assimilation][phonetics]
前回の hellog ラジオ版では「#4156. なぜ英語には s と微妙に異なる th のような発音しにくい音があるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-09-12-1]) という素朴な疑問を取り上げました.今回も引き続き th-sound に関する話題です.th の綴字に対応する発音には,清んだ /θ/ と濁った /ð/ の2種類があり得ます(音声学では各々を無声音と有声音と呼んでいます).では,どのようなときに無声音となり,有声音となるのでしょうか.単語ごとに1つひとつ暗記しなければならないのでしょうか.
残念ながら,無声音と有声音の分布を完全に予測させる「規則」というものは存在しませんが,かなり有効な「傾向」は指摘できます.今回は歴史的な観点から2つの傾向を紹介したいと思います.では,以下の音声をどうぞ.
以上,2つの傾向を紹介しました.ある単語に現われる th が無声音か有声音かは,その意味,語形,綴字から,ある程度は推し量ることができるということが分かったでしょうか.そして,各々の傾向には数百年から千年以上の歴史があるということも重要なポイントです.昔の発音の「クセ」が現代の発音のなかに残っていると思うと不思議な感じがしますね.
今回の素朴な疑問とその周辺の話題について,ぜひ##842,858,3713,1365,702,3298,4069の記事セットをお読みください.
2020-04-17 Fri
■ #4008. <x> ≡ /z/ の対応について (3) [x][grapheme][verners_law][phonotactics][consonant][metathesis]
この2日間の記事 ([2020-04-15-1], [2020-04-16-1]) で標題について少し調べてきたが,いまだ解決していない.そこで,1つ仮説を立ててみた.
英語の音節の頭 (onset) に現われる子音連鎖には制約があり,原則として昔から今まで /ks/ も /gz/ も onset に立つことはできない.とはいえ借用語などでは例外的に可能な場合があり,まさに今回の一連の問題で扱ってきた xenon, Xerses などもすべて借用語であるため,/ks/ や /gz/ の発音はあり得るといえばあり得る.しかし,多くの場合,借用語が英語に同化する過程で,外来の不規則な発音も英語の音素配列規則に順応していくものだ.その際,どのように順応していくかにはいくつかのパターンがある.
1つは,子音連鎖を解消するために第1子音を落とす,語頭音消失 (apheresis) による解決法である.実際,すでに2日間の記事で見てきたように,<x> ≡ /z/ は <x> ≡ /gz/ から apheresis を経た結果として説明されてきた.「#3482. 語頭・語末の子音連鎖が単純化してきた歴史」 ([2018-11-08-1]),「#3938. 語頭における母音の前の h ばかりが問題視され,子音の前の h は問題にもされなかった」 ([2020-02-07-1]) でみたように,[kn-], [gn-], [wr-], [wl-], [hr-], [hl-], [hn-], [hw-] 等からの第1子音消失は英語史でもありふれた現象であり,[gz-] も同様に考えることができる.
もう1つは,子音連鎖の間に母音を挿入すること (anaptyxis) で子音連鎖を解消するという方法だ.Minkova (132--33) によれば,たとえば著名なアメリカ人スタントマン Evel Knievel の姓はドイツ語名として語頭の [k] も発音されるが,/kn-/ は現代英語の音素配列規則に反するので,[kəˈniːvəl] のように曖昧母音を間に挿入することで違反を回避している.同様に,中英語でも knight が <kinicht>, <cinth>,knife が <kinf>,kneeled が <keneleden> と綴られた anaptyxis を示唆する事例がある.xenon, Xerses などの [ks-], [gz-] に(曖昧)母音が挿入されて [kəs-], [gəz-] となった事例があったかどうかは確認できていないが,少なくとも理論上はあり得たと思われる.(ちなみに上記の knight を表わす <cinth> については,anaptyxis というよりは音位転換 (metathesis) の事例とみるべきかもしれない.音位転換も子音連鎖に対するもう1つの解決法である.)
3つめに,問題の子音連鎖の前に母音を挿入する (prosthesis) ことで,onset の制約を回避するという方法がある.「#739. glide, prosthesis, epenthesis, paragoge」 ([2011-05-06-1]) で取り上げたように,フランス借用語では子音連鎖の前に挿入された非語源的な語頭の e の例がよく見られる (ex. especial, escalade) .子音連鎖の例から離れるが,子音音素 /ŋ/ は原則として onset に立つことができないので,ザンビアの貨幣単位である ngwee は語頭に曖昧母音を挿入して [əŋ ˈwiː] と発音されるのが普通である.これによって /ŋ/ は音節頭ではなく音節末に立つことになり,音素配列論的に適格となる.
やや長い前置きとなったが,私の仮説は第3の解決法に基づくものである.<x> ≡ /ks/ をデフォルトとすると,借用語の語頭の <x> は直前に母音が挿入された [əks-] として実現される機会があったのではないか.これは ngwee の場合のように,綴字にはなかなか現われないと思われ,実証もしにくいだろうが,少なくとも発音の variant としてはあり得たと想定される.そうなると,子音連鎖に続く(新たな第2音節の)母音は相対的に強い強勢をもつことになるので,従来の「英語史における Verner's Law」にしたがって,件の子音連鎖は有声化し,[əgz-] となるだろう.この有声化した発音がもととなり,その上に第1の解決法である語頭音消失の効果も重なったのではないか.これについて非常に示唆的な指摘として,Minkova (139fn) の Xavier の発音に関するコメントを引用しておこう.
The initial <x> in Xavier [ˈzeɪvɪə(r)] is sometimes taken to represent [ks-] as in X-ray, triggering prosthetic [ɛ-/ə]: [ɛgˈzeɪvɪə(r)] . . . .
私の仮説は,端的にいえば [ks-] → [əks-] → [əgz-] → [gz-] → [z-] という過程である.実際にはこの過程は必ずしも時系列できれいに進んだわけではないだろうし,しばらくは異なる発音が variants として並存していたに違いない.また,語頭音添加 (prosthesis) と語頭音消失 (apheresis) という反対向きの解決法が同一過程に生じているという点についても,もっと説得力のある下支えが必要のように思われる.それでも,onset における特定の子音連鎖を回避するために,複数の解決法が同時に試みられ,その込み入った相互作用の結果,標準発音として /z-/ という1つの結論に終着した,ということは十分にありそうである.
・ Minkova, Donka. A Historical Phonology of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2014.
2020-04-16 Thu
■ #4007. <x> ≡ /z/ の対応について (2) [x][grapheme][latin][french][verners_law]
昨日の記事 ([2020-04-15-1]) に引き続き,xenon, xenophobia, Xerses, xylophone などに観察される借用語の語頭における <x> ≡ /z/ の対応について.この比較的稀な対応の前提に <x> ≡ /gz/ があったことは,論者の間でおよそ見解の一致をみているようだ.すると,<x> ≡ /gz/ となる条件を明らかにすることが重要となってくる.実はこれについては昨日も触れたし,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) や「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) でも言及してきた.要するに,後続する母音に強勢が落ちる環境で /ks/ が /gz/ へと有声化するという「英語史における Verner's Law」のことだ.
しかし,昨日も取り上げた Dobson は,Ekwall を参照しつつ,<x> ≡ /gz/ を説明するには「英語史における Verner's Law」だけでは不十分であり,もう少し込み入った事情があっただろうと考えている.Dobson (II §359) より該当箇所を引用する.
In many words of Latin origin the consonant x is pronounced [gz]; as this occurs chiefly when the stress follows, the explanation has been advanced . . . that [gz] develops from [ks] by voicing before the stress. But Ekwall, 則則150--1, rightly rejecting this view, has drawn attention to the parallel that exists between the English and French pronunciations of the words in question. It is apparent, especially from the Modern French pronunciation, that the medieval French (and English) pronunciation of Latin must have used [gz] for Latin x between vowels (as in ModFr exalter, exemple, examen, exécration &c.) and between a vowel and h (probably silent, as in ModFr exhalaison, exhaustif, exhiber, &c.), but [ks] for Latin x both before and after other consonants (as in ModFr expérience, &c. and anxiété). But at a later date (probably about 1500) the reform of the pronunciation of Latin led to the replacement of [gz] by [ks] for intervocalic x. By this change French pronunciation was little affected (but cf. [ks] in Alexandre), but English pronunciation was much altered, [ks] being introduced in many words. But the English tendency to use voiced consonants before the stress, which in the seventeenth century led to a voicing in this position of [s] to [z], influences the distribution of the old and new pronunciations: [gz] is retained in most words in which the stress follows (e.g. example, exert, exalt, exult, exhibit, Alexander, luxurious), but not in certain learned words (e.g. proximity, doxology, luxation), whereas [ks] has been substituted when the stress precedes (exodus, execute, exercise, &c.) except in derivatives which follow the simplex (exaltation, exultation); but there is some degree of variation, as usually when one pronunciation is replaced by another not phonetically developed from it.
実に込み入った説明なのでこのように長文なのだが,かいつまんで言えば次のようになる.フランス語と英語では,x をもつラテン借用語に関して,母音に挟まれた環境では [gz] として,子音が隣接する場合には [ks] として発音されていた.ところが,1500年くらいから,原則としてラテン語の x は [ks] と読むべしという慣習が発達し(何らかの規範意識の発生が関与か?),[gz] から [ks] への鞍替えが進行したが,その鞍替えの徹底度は英仏語間でも異なっていたし,英語内をみても音環境によって異なっており一貫していなかった.つまり,[gz] のまま残った単語も少なくなかったわけである.
そこで間接的に効いてくるのが,やはり「英語における Verner's Law」である.同法則は,通常の理解によれば特定の音環境において [ks] から [gz] への変化を説明する法則だが,Dobson の支持する説によると,むしろ [gz] から [ks] への変化を阻止する要因を説明する法則となる.Dobson 説でも「英語における Verner's Law」は結局のところ関与してくるのだが,通常とは異なる少し込み入った方法で,後世の <x> ≡ /gz/ の対応関係の確立に貢献したという解釈になる.
<x> ≡ /gz/ が中世イングランドにおけるラテン語発音の癖を引きずったものだとすれば,現在の <x> ≡ /z/ はその延長線上にあるともいえる.しかし,今回話題にしてきた xenon, Xerses 等は,そもそも「母音に挟まれた環境」ではない環境における x のケース(語頭の x)なので,本当にそのような延長線上にある問題と考えてよいのかよく分からない.
・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. Oxford: Clarendon, 1957. 2 vols.
・ Ekwall, E. Historische neuenglische Laut- und Formenlehre. 1922.
2020-04-15 Wed
■ #4006. <x> ≡ /z/ の対応について (1) [x][eme][grapheme][greek][latin][french][verners_law]
標題の対応は,稀ではあるがギリシア語等からの借用語の語頭においてみられる.例えば xenon, xenophobia, xerox, xylophone, Xanadu, Xanthippe, Xavier, Xenia, Xerxes は /z/ で始まる.以前の記事で「<x> ≡ /z/ の対応は,<x> ≡ /gz/ の第1子音の脱落によるものと考えられます」(「#3654. x で始まる英単語が少ないのはなぜですか?」 ([2019-04-29-1]))と述べた通り,デフォルトの対応 <x> ≡ /ks/ の有声版である <x> ≡ /gz/ という対応を想定すれば,このことは理解できる.語頭子音群 /gz/ から第1子音が落ちて /z/ となった,と考えればよい.
しかし,そもそもなぜこれらの稀なケースではデフォルトの <x> ≡ /ks/ ではなく,<x> ≡ /gz/ が想定されなければならないのだろうか(←先日,名古屋大学の大名力氏よりいただいいた疑問です.ありがとうございます).この問題について深く考えてみたことがなかったので,少し調べてみた.初期近代英語の発音を徹底的に研究した Dobson を参照すると,次のような言及が見つかった (II §359) .
PresE initial [z] in Xerxes, &c. is usually (and rightly) regarded as a reduction of [gz], but as French also has this pronunciation the reduction presumably occurred in the medieval pronunciation of Latin rather than in English itself. Cooper says that x in Xenophon is pronounced z, gz (for [gz]), or ks.
Dobson は意外なところに鍵を見出している.中世の英語話者やフランス語話者がこれらの語をラテン語として発音するときに,本来の無声の /ks/ ではなく,有声化した /gz/ として実現する傾向があったという.実際,現代フランス語でも Xerxès, xènon は /gzɛrsɛs/, /gzenɔ̃/ のように /gz/ が聞かれる.英語でも,17世紀の音声学者 Christopher Cooper が /z/, /gz/, /ks/ のいずれの発音にも言及している通り,揺れはあったものと思われるが,おそらく /ks/ よりも /gz/ が好まれ,さらに第1子音が脱落した /z/ が最終的に標準発音として落ち着くことになったと考えられる.
もちろん上記では標題の「なぜ」の疑問に真正面から答えられたわけではない.特殊な借用語の語頭という環境で /gz/ が選ばれた理由や,英語とフランス語の間に想定されている類似の振る舞いが何によるものかも分からない.
一般に英語で <x> ≡ /gz/ が成立する環境は,(1) x が母音に挟まれており,かつ (2) 先行する母音に強勢が落ちない(≒後続する母音に強勢が落ちる)場合である.これは「英語における Verner's Law」と言うべきもので,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]),「#2280. <x> の話」 ([2015-07-25-1]) で触れた通りである.もちろん今回のような x で始まる語は,厳密には (1) と (2) の両条件に当てはまるわけではないのだが,後続する母音に強勢が落ちる(換言すれば x で始まるその語頭音節が強勢をもつ)という条件 (2) には当てはまるものが多い.Dobson もこの緩めた条件を念頭に置いて上の見解を述べたということだろうか.よくは分からない.
今回の問題について調べるているうちに,英語の <x> ≡ /gz/ の対応の歴史的経緯について,Dobson が単純な「英語における Verner's Law」よりも込み入った説明を施していることにも気付いた.関連する話題なので明日の記事で取り上げたい.
・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 1st ed. 2 vols. Oxford: Clarendon, 1957.
2019-10-07 Mon
■ #3815. quoth の母音 [vowel][verb][preterite][verners_law][phonetics][sound_change][analogy][inflection][old_norse]
「#2130. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle."」 ([2015-02-25-1]),「#2158. "I wonder," said John, "whether I can borrow your bicycle." (2)」 ([2015-03-25-1]) で少し触れたが,quoth /kwoʊθ/ は「?と言った」を意味する古風な語である.1人称単数と3人称単数の直説法過去形のみで,原形などそれ以外の形態は存在しない妙な動詞である.古英語や中英語ではきわめて日常的かつ高頻度の動詞であり,古英語ウェストサクソン方言では強変化5類の動詞として,その4主要形は cweðan -- cwæþ -- cwǣdon -- cweden だった(「#3812. was と were の関係」 ([2019-10-04-1]) を参照).
ウェストサクソン方言の cweðan の語幹母音を基準とすると,その後の音変化により †queath などとなるはずであり,実際にこの形態は16世紀末まで用いられていたが,その後廃用となった(しかし,派生語の bequeath (遺言で譲る)を参照).したがって,現在の quoth の語幹母音は cweðan からの自然の音変化の結果とは考えられない.
OED の quoth, v. と †queath, v. を参照してみると,o の母音は,Northumbrian など非ウェストサクソン方言における後舌円唇母音を示す,同語の異形に由来するとのことだ.その背景には複雑な音変化や類推作用が働いていたようだ.OED は,quoth, v. の下で次の3点を紹介している.
(i) levelling of the rounded vowel resulting from combinative back mutation in Northumbrian Old English (see discussion at queath v.); (ii) rounding of Middle English short a (of the 1st and 3rd singular past indicative) after w; (iii) borrowing of the vowel (represented by Middle English long open ō) of the early Scandinavian plural past indicative forms (compare Old Icelandic kváðum (1st plural past indicative)); both short and long realizations are recorded by 17th-cent. orthoepists (see E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) II. 則則339, 421).
中英語における異形については MED の quēthen v. も参照.スペリングとして hwat など妙なもの(MED は "reverse spelling" としている)も見つかり,興味が尽きない.
2019-10-04 Fri
■ #3812. was と were の関係 [be][verb][preterite][subjunctive][inflection][verners_law][rhotacism][subjunctive][sobokunagimon]
現代英語において be 動詞が形態的にきわめて特殊な動詞であることについて,歴史的な観点から「#2600. 古英語の be 動詞の屈折」 ([2016-06-09-1]) で解説した.端的にいえば,4つの異なる語根からなる寄せ集め所帯ということだ.
be 動詞の屈折形のなかでも過去形に注目すると,w- で始まる形態が現われている.直説法においては人称・数によって was と were が区別され,接続法(現在の仮定法)においては不変の were となる.古英語では,過去形のみならず,現在形 wes, wesað,不定詞形 wesan,現在分詞形 wesende なども用いられたが,これらは後に衰退してしまった(命令形の化石としては「#3275. 乾杯! wassail」 ([2018-04-15-1]) を参照).
さて,was と were の2つの屈折形は,古英語から現代英語に至るまで,人称・数・法によって使い分けがなされてきたことになるが,なぜ s と r で子音が異なっているのだろうか.実は,これは英語史ではよく知られている Verner's Law (verners_law) と rhotacism のたまものである./s/ は,有声音に囲まれた環境では有声化して /z/ となり,さらに直前に強勢が落ちない環境では /r/ へと変化したのである(概要は「#36. rhotacism」 ([2009-06-03-1]) を参照).
was, were の素となる wesan (to live, remain) という動詞は,歴史的に強変化第5類の動詞として分類されるが,これは「言う」を意味する古英語の高頻度語 cweðan と同じ振る舞いをする.後者の4主要形が cweðan (不定詞形)-- cwæþ (第1過去形)-- cwǣdon (第2過去形) -- cweden (過去分詞形)となるように,前者は wesan (不定詞形)-- wæs (第1過去形)-- wǣron (第2過去形)となる(過去分詞形は欠損;Hogg and Fulk 246) .
ポイントは,古英語の直説法屈折においては人称・数によって wæs, wǣre, wǣron が使い分けられ,s と r が共存していたが,接続法屈折においては人称は不問であり,単数ならば wære,複数ならば wæren というように r しか現われなかった点である.この直説法と接続法の微妙な差異が,現在にまで響いており,なぜ *If I WAS a bird ではなく If I WERE a bird なのかという疑問を引き起こすことになる(「#2601. なぜ If I WERE a bird なのか?」 ([2016-06-10-1]) を参照).
この問題を裏からみれば,ほぼすべての動詞では形態的な区別が失われてしまった直説法と接続法がいまだに「公式に」区別されているのは,be 動詞にのみ残されている was と were の子音の違いゆえなのである.古英語以前に生じた Verner's Law と rhotacism という,ちょっとした音変化のいたずらのなせる技というわけだ.
なお,上記からもわかるとおり,be 動詞はかつての第1過去形と第2過去形の区別を残す唯一の動詞である.いや,sing の過去形として,フォーマルには sang と言いながらインフォーマルには sung と言う英語母語話者を知っているが,彼はある意味では第1過去形と第2過去形を(古英語とは別のやり方ではあるが)区別しているといえなくもない(「#2084. drink--drank--drunk と win--won--won」 ([2015-01-10-1]) を参照).
・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2018-06-14 Thu
■ #3335. 強変化動詞の過去分詞語尾の -n [participle][oe][inflection][reconstruction][indo-european][germanic][suffix][gradation][verb][verners_law]
現代英語の「不規則動詞」の過去分詞には,典型的に -(e)n 語尾が現われる.written, born, eaten, fallen の如くである.これらは,古英語で強変化動詞と呼ばれる動詞の過去分詞に由来するものであり,古英語でもそれぞれ writen, boren, eten, feallen のように,規則的に -en 語尾が現われた(「#2217. 古英語強変化動詞の類型のまとめ」 ([2015-05-23-1]) に示したパラダイムを参照).
古英語の強変化動詞の ablaut あるいは gradation と呼ばれる母音階梯では,現在,第1過去,第2過去,過去分詞の4階梯が区別され,合わせて動詞の「4主要形」 (four principal parts) と呼ばれる.その4つ目が今回話題の過去分詞の階梯なのだが,古英語からさらに遡れば,これはもともとは動詞そのものに属する階梯ではなかった.むしろ,動詞から派生した独立した形容詞に由来するらしい.ゲルマン祖語では *ROOT - α - nα- が再建されており,印欧祖語では * ROOT- o - nó- が再建されている.これらの祖形に含まれる鼻音 n こそが,現代英語にまで残る過去分詞語尾 -(e)n の起源と考えられている.
この語尾は,語幹の音韻形態にも少しく影響を与えている.特に注意すべきは,印欧祖語の祖形では強勢がこの n の後に続くことだ.これは,ゲルマン諸語では Verner's Law を経由して語幹の子音が変化するだろうことを予想させる.ちなみに,強変化 V, VI, VII 類について,過去分詞形の語幹母音の階梯が,類推により現在形と同じになっていることにも注意したい (ex. tredan (pres.)/treden (pp.), faran (pres.)/faren (pp.), healdan (pres.)/healden (pp.)) .
以上,Lass (161--62) を参照した.-en 語尾については,関連して「#1916. 限定用法と叙述用法で異なる形態をもつ形容詞」 ([2014-07-26-1]) も参照.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2018-04-01 Sun
■ #3261. ドイツ国歌の「父なる祖国」を巡るジェンダー問題 [gender][sociolinguistics][political_correctness][grimms_law][verners_law]
ドイツ国歌の歌詞にある Vaterland (父なる祖国)が男性バイアスの用語なので,Heimatland (故郷の国)に変更しようという political_correctness の提案がドイツ国内でなされている.ドイツ政府による男女共同参画の推進を担当する女性の政治活動家が提案したもので,目下,物議を醸している.ジェンダーについて中立な言葉遣いが時勢に合っているからという理由での提案だが,保守系の政治家は「やりすぎだ」「これを変えるなら『母語』という言葉も使えない」などと反発している.メルケル首相も変更は不要という立場のようだ.
ドイツ国歌は,オーストリアの作曲家ハイドンの曲に対して1841年に歌詞づけしたもので,国歌としては旧西ドイツから東西統一後のドイツへの引き継がれた.国歌の歌詞におけるジェンダーの問題は最近オーストリアやカナダでも起こっており,そこでは中立的な表現に置き換えられたという経緯がある.これらの先例を受けての,ドイツでの論争という次第である.
英語でも「祖国,故国」を表わす語として fatherland という言い方がある.motherland という言い方もあるが,PC の観点からはジェンダーについて中立な homeland, native country, home が用いられることが多くなっているという.しかし,借用語の patriot (愛国者),patriotism (愛国心)などでは語幹にラテン語で「父」を意味する pater が含まれており,発想としては fatherland と酷似するのだが,これについては特にジェンダー論争が起こっているという話しは聞かない.借用語では,語幹の「父」の意味が直接には感じ取られにくいからだろうか.
ラテン語 pater と英語 father は語源的には同根だが,その関係を詳しく理解しようと思えば「グリムの法則」 (grimms_law) や「ヴェルネルの法則」 (verners_law) の知識が必要となる.それには,「#2277. 「行く」の意味の repair」 ([2015-07-22-1]),「#102. hundred とグリムの法則」 ([2009-08-07-1]),「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1]),「#2297. 英語 flow とラテン語 fluere」 ([2015-08-11-1]) 辺りの記事をどうぞ.
2018-01-22 Mon
■ #3192. 西,北,東ゲルマン語群の間にみられる音韻・形態・統語上の主要な差違 [germanic][comparative_linguistics][verners_law][inflection][article][rhotacism][i-mutation][oe][gothic][old_norse]
ゲルマン祖語が紀元前3世紀頃に西,北,東のグループへ分裂していく際に,それぞれ独自の言語変化が生じた.結果として,起源を同じくする言語項の間に,ある種の対応関係が見いだされることになった.Algeo and Pyles (82--83) にしたがって,主要な変化と対応関係を6点挙げよう.
(1) ゲルマン祖語ではいくつかの名詞の主格単数形は *-az で終わっていた (ex. *wulfaz 「狼」) .この語尾は西ゲルマン語群では失われ (Old English wulf),北ゲルマン語群では -r となり (Old Icelandic ulfr),東ゲルマン語群では -s となった (Gothic wolfs) .
(2) ゲルマン祖語では動詞の2・3単現形がそれぞれ区別されていた.西・東ゲルマン語群では区別され続け,OE では bindest (you bind), bindeþ (he/she/it binds) となり,Go では bindis, bindiþ のごどくだったが,北ゲルマン語群では2単現形の -r が3単現形をも呑み込み,ともに bindr となった.
(3) 北ゲルマン語群では定冠詞が名詞に後続するようになった (ex. ulfrinn (the wolf)) が,西・東ゲルマン語ではそのような変化は起こらなかった.
(4) Verner's Law の出力としての *z は,西・北ゲルマン語群では r となった (= rhotacism) が,東ゲルマン語群では s となった.例として,OE ēare (ear), OIc eyra, Go auso.
(5) 西・北ゲルマン語群では i-mutation が生じて,例えば OE mann (man) に対してその複数形 menn (men) となったが,Go では単数形 mannan に対して複数形 mannans となり母音変化を反映していない.
(6) 西ゲルマン語群では Verner's Law の出力としての *ð は d となったが,北・東ゲルマン語群では摩擦音にとどまった.例として,OE fæder (father) に対して,OIc faðir, Go faðar (ただし綴字は fadar).
・ Algeo, John, and Thomas Pyles. The Origins and Development of the English Language. 5th ed. Thomson Wadsworth, 2005.
2017-09-25 Mon
■ #3073. 9譛茨シ郡eptember?シ碁聞譛? [calendar][month][latin][verners_law][etymology][numeral][analogy]
月名シリーズ (month) の「9月」をお届けする.「9月」を表わす語は,古英語では hærfest-mōnaþ "harvest month" (収穫の月)だった.しかし,古英語後期にはラテン語 September (mēnsis) が借用されている.中英語ではフランス語形 Septembre が普通だったが,近代英語になると再びラテン語形 September が採用された.ラテン語 septem は "seven" の意であるから,本来は「7番目の月」を表わしていた.現在の感覚からすると2月分ずれているように見えるが,これは古代ローマ暦では1月ではなく3月を年始としていたことに由来する.
「7」を表わす印欧祖語の再建形は *septm̥ であり,ラテン語形 septem から遠くない.なお,ギリシア語では印欧祖語の s は h に対応するため,「7」は heptá となる (cf. Heptarchy (七王国),s (七書);「#350. hypermarket と supermarket」 ([2010-04-12-1]) と「#352. ラテン語 /s/ とギリシャ語 /h/ の対応」 ([2010-04-14-1]) も参照) .印欧祖語形 *septm̥ の子音 *p は,ゲルマン祖語においては Verner's Law を経て有声摩擦唇音の *ƀ となる一方で,もう1つの子音 *t は,おそらく歯音接辞を付す序数詞形において4子音連続が生じてしまうために消失したことからの類推で落ちたものと考えられる (cf. Gmc *sebunða-) .結果として Gmc 古英語 *seƀun から,古英語 seofon,オランダ語 zeven,ドイツ語 sieben などが発達した.Verner's Law については,「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]),「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1]),「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) を参照されたい.
なお,October, November, December にもみられる -ber 語尾については,ラテン語 mēnsis に基づく形容詞形 *mēns-ris において,隣接する子音群の同化により -br- が現われたのではないかと推測されているが,詳細は不明である.
日本語で陰暦9月を表わす「長月」は,夜長月(ヨナガツキ)の略(あるいは稲刈月(イナカリツキ)の略)と言われるが,これは中古以来の民間語源説にすぎないという見解もある.折口信夫によれば,9月が長雨(ナガメ)の時季でもあることと関連して名付けられたのだろうとされる.
2017-08-22 Tue
■ #3039. 連載第8回「なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか」 [grimms_law][consonant][loan_word][sound_change][phonetics][french][latin][indo-european][etymology][cognate][germanic][romance][verners_law][sgcs][link][rensai]
昨日付けで,英語史連載企画「現代英語を英語史の視点から考える」の第8回の記事「なぜ「グリムの法則」が英語史上重要なのか」が公開されました.グリムの法則 (grimms_law) について,本ブログでも繰り返し取り上げてきましたが,今回の連載記事では初心者にもなるべくわかりやすくグリムの法則の音変化を説明し,その知識がいかに英語学習に役立つかを解説しました.
連載記事を読んだ後に,「#103. グリムの法則とは何か」 ([2009-08-08-1]) および「#102. hundred とグリムの法則」 ([2009-08-07-1]) を読んでいただくと,復習になると思います.
連載記事では,グリムの法則の「なぜ」については,専門性が高いため触れていませんが,関心がある方は音声学や歴史言語学の観点から論じた「#650. アルメニア語とグリムの法則」 ([2011-02-06-1]) ,「#794. グリムの法則と歯の隙間」 ([2011-06-30-1]),「#1121. Grimm's Law はなぜ生じたか?」 ([2012-05-22-1]) をご参照ください.
グリムの法則を補完するヴェルネルの法則 (verners_law) については,「#104. hundred とヴェルネルの法則」 ([2009-08-09-1]),「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1]),「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) をご覧ください.また,両法則を合わせて「第1次ゲルマン子音推移」 (First Germanic Consonant Shift) と呼ぶことは連載記事で触れましたが,では「第2次ゲルマン子音推移」があるのだろうかと気になる方は「#405. Second Germanic Consonant Shift」 ([2010-06-06-1]) と「#416. Second Germanic Consonant Shift はなぜ起こったか」 ([2010-06-17-1]) のをお読みください.英語とドイツ語の子音対応について洞察を得ることができます.
2015-07-25 Sat
■ #2280. <x> の話 [alphabet][grapheme][x][pronunciation][spelling][verners_law]
英語アルファベットの24文字目の <x> には,日陰者のイメージがつきまとう.まず,1文字なのに2つの子音結合 /ks/ に対応するというのが怪しい.頻度の点からも,「#308. 現代英語の最頻英単語リスト」 ([2010-03-01-1]) で示した通り,<z>, <q>, <j> に次いで稀な文字である.無ければ無いで済ませられそうな文字だ.
英語史における <x> の役割を簡単に振り返ってみよう.この文字素は,確かに /ks/ あるいは /hs/ に対応する文字として古英語から見られた.しかし,eax (axe), fleax (flax), fox, oxa (ox), siex (six), wæx (wax) などの一握りの単語に現われるのみで,当初から目立った文字ではなかった (Upward and Davidson 62) .これらの単語は,現代英語へも <x> を保ったまま伝わっている.その後,中英語期に入ると,方言によっては <x> を多用するものもあったが (cf. 「#663. 中英語方言学における綴字と発音の関係」 ([2011-02-19-1])) ,やはり概して頻度の高い文字ではなかった.
しかし,初期近代英語期になると,<x> はラテン語やギリシア語からの借用語に多く含まれていたために,これまでの時代に比べて出現頻度が増した.接頭辞 ex- をもつ多数の語に加え,語中で anxious, approximate, auxiliary, axis, maximum, nexus, noxious, toxic などに現われたし,語末でも apex, appendix, crux, index などが入った.ほかにも complexion, crucifixion, connexion, inflexion などの -xion 語尾や,近代フランス語からの faux pas, grand prix,さらにフランス語の複数形を表わす bureaux, chateaux, jeux など,<x> の生じる機会が目に見えて増した.
<x> はとりわけ専門的な借用語語彙に多く現われる.語頭,語中,語末それぞれの環境に現われる <x> の例をもう少し見てみよう (Upward and Davidson 213--14) .
[語頭]: xenophobia, Xerox, xylophone
[語中]: anorexia, apoplexy, asphyxia, axiom, axis, dyslexia, galaxy, lexical, hexagon, oxygen, paroxysm, taxonomy
[語末]: anthrax, calx, calyx, climax, coccyx, helix, larynx, onyx, paradox, phalanx, pharynx, phlox, phoenix, sphinx, syntax, thorax
このようにラテン語やギリシア語を中心とした借用語彙の貢献が大きいが,そのほかにも古英語から続く前述の語群が <x> を保持したばかりでなく,cox (< cockswain) や smallpox (< pl. of small pock) などの短縮によって作られた語に <x> が見られるようになったことが注目される.20世紀には,同様の短縮の過程を経て sox (< socks), fax (< facsimile), proxy (< proc'cy < procuracy) が生まれている.
The X of cox 'boatman' arose from cockswain, while pox (as in smallpox) was respelt from the plural of pock (as in pockmarked). These replacements of CC or CKS by X are first attested in EModE; other examples are 20th-century: sox for socks, fax from facsimile. Proxy < proc'cy < procuracy. (Upward and Davidson 168)
さて,現代英語における <x> の発音への対応を,Carney (377--78) に拠って見てみよう.語頭では,上記の第1群の語にみられる通り /z/ が基本である.ただし,例外として Xhosa /ˈkoʊsə/ や Xmas /ˈkrɪsməs, ˈɛksməs/ には注意 (<Xmas> は Christ の語頭子音に対応するギリシア語文字 <Χ> に由来).語頭以外では,続く母音に強勢があれば /gz/ がルールだ (ex. exact, exaggerate, exalt, examine, executive, exempt, exert, exhibit, exhort, exist, exonerate, exotic, exult) .それ以外は,/ks/ が基本である (ex. axe, boxing, extra, fox, mixture, orthodox, praxis, texture, vixen, wax) . 派生語間での /ks/ と /gs/ の交替については,「#858. Verner's Law と子音の有声化」 ([2011-09-02-1]) と「#2230. 英語の摩擦音の有声・無声と文字の問題」 ([2015-06-05-1]) を参照されたい.ほかには,<i> や <u> の前位置で,/kʃ/ となることがある (ex. anxious, connexion, flexure, luxury) .
<z> が歴史的に日陰者だったことは「#446. しぶとく生き残ってきた <z>」 ([2010-07-17-1]) でも確認したとおりだが,<x> も負けていない.未知の人物や数を表わすのに x をもってする慣習があるが,この由来は不詳である.もしかすると,原因なのか結果なのか,ここには <x> の日陰者としての歩みが関与しているのではないかとも疑われる・・・.
・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow