2024-11-16 Sat
■ #5682. Low Dutch という略称 [dutch][low_german][flemish][contact][lexicology][borrowing][loan_word][terminology][germanic][variety]
「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]) で,英語史におけるオランダ借用語をめぐって Durkin を参照した.そこで Dutch でも Low German でもなく,中間的な Low Dutch という用語が使われていた.これが何を指すのかといえば,Durkin 自身が丁寧に解説してくれていた.その1節 (354) を読んでみよう.
Loanwords into English from Dutch (including Flemish) and Low German are normally considered together, because it is so difficult to tell them apart. This is partly because word forms in both languages were, and to some extent still are, so similar, and partly because the social and cultural circumstances of borrowing into English are also often hard to tell apart. 'Low Dutch' is sometimes used as a collective cover term for borrowings from either or both languages into English, although it is important to note that Low Dutch is not itself a language name, but simply a terminological shorthand for referring to a complex situation.
Dutch と Low German は各々区別される言語変種ではあるが,単語の形態が互いによく似ており,借用元同定の文脈においては,実際上区別がつかないことも多いために,便宜上2変種を合わせた用語として Low Dutch を設定しておく,ということだ.ある意味で Low Dutch はフィクションということになる.フランス借用語かラテン借用語か判別がつきにくいときに,便宜上「フランス・ラテン系借用語」などと一括して呼ぶのに似ている.
しかし,こうした用語のフィクション性それ自体も程度の問題ともいえるかもしれない.というのは,上記の Dutch にしても Low German にしても,「区別される言語変種」と一応のところ述べはしたが,やはり何らかの程度においてフィクションでもあるからだ.この点については「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]) を参照.
便利に使えるのであれば Low Dutch というタームは悪くない.
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.
2024-11-12 Tue
■ #5678. 日本語に入ったオランダ語の単語 (2) [dutch][japanese][loan_word][lexicology][contrastive_language_history][contact]
「#5675. 日本語に入ったオランダ語の単語」 ([2024-11-09-1]) の続編.オランダ語から日本語へ借用された語はまだまだある.前回と重複する単語もあるが,以下,2つの文献より例を加えたい.まず,沖森 (548) より.
【医科学関係】アルコール,エキス,オブラート,ガス,カテーテル,カリ,カルキ,コレラ,チフス,ハトロン,メス,レトルト,レンズ
【物品名ほか】インキ,ガラス,コーヒー,コック,コップ,ゴム,スコップ,ブリキ,ビール,ピント,ペンキ,ホース,ポンプ,マドロス
続けて,佐藤 (179--80) からも追加する.
【医学・薬学関係】エーテル (ether)・オブラート (oblaat)・エキス (extract)・カルシウム (calcium)・カンフル (kamfer, kampher)・コレラ (cholera)・ペスト (pest)・メス (mes)・モルヒネ (morphine)
【化学・物理・天文】テレスコープ (telescoop)・レンズ (lens)・ピント (brandpunt)・コンパス (kompas)・アルカリ (alkali)・アルコール (alcohol)・ソーダ (soda)・エレキテル (eletriciteit)
【生活関係】コーヒ (kofij)・ビール (bier)・シロップ (siroop)・コップ (kop)・ギヤマン (diamant)・ゴム (gom)・ブリキ (blik)・ペン (pen)・ペンキ (pek)・ポンプ (pomp)・ランプ (lamp)・ズック (doek)・チョッキ (jak)・ホック (hoek)
【軍事関係】サーベル (sabel)・ピストル (pistool)・ランドセル (ransel)
主に明治時代以降に日本語に借用された英単語と事実上同形のものも散見されるが,以上のものはオランダ語からの借用であることに留意したい.
・ 沖森 卓也 『日本語全史』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2017年.
・ 佐藤 武義(編著) 『展望 現代の日本語』 白帝社,1996年.
2024-11-09 Sat
■ #5675. 日本語に入ったオランダ語の単語 [dutch][japanese][loan_word][lexicology][contrastive_language_history][contact]
近年の研究で,英語史におけるオランダ語 (dutch) の位置づけが少し変わってきていることについては,以下の記事で取り上げてきた.
・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])
・ 「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1])
・ 「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1])
・ 「#4446. 低地諸語が英語に及ぼした語彙以外の影響 --- 南部方言の TH-stopping と当中部方言の3単現のゼロ」 ([2021-06-29-1])
オランダ語との言語接触といえば,英語史のみならず日本語史でも重要なテーマである.日本語におけるオランダ借用語について,まず『日本語百科大事典』を開いてみた.その1027ページに「江戸時代の洋語」と題する1節があり,そこでオランダ語からの借用語が扱われている.そちらを読んでみよう.
江戸時代に入った洋語はほとんどすべてオランダ語である.長崎におけるオランダ人との貿易による,貿易に関連した用語および江戸後期に芽生え,幕末にいたってさかんになった蘭学に起因する科学技術の用語である.
貿易に関連した用語には,たとえば,
インデン(Indië,革製品)・ズック(doek)・ボートル(boter,バター)・ガラス(glas)・キルク(kurk)・コップ(kop)・ブリキ(blik)・ランプ(lamp)
などがある.蘭学関係の用語としては,
オブラート(oblaat)・メス(mes,外科用具)・カルキ(kalk)・キナ(kina,マラリアの薬)・サフラン(saffraan,薬草)・ヨジウム(jodium)・アルカリ(alkali)・アルコール(alcohol)・エレキテル(electriciteit)・タルモメートル(thermometer)・レンズ(lens)
などがある.
工業技術関係では,
ダライバン(draaibank,旋盤)・バイト(beitel,刃具)・ポンプ(pomp)・カラン(kraan,給水管のコック)
などがある.
これらのオランダ語系洋語の中には明治以後消失したものもあるが,かなり多くの語が現在まで続けて使われている.
日英語の対照言語史 (contrastive_language_history) という観点からも,オランダ語との言語接触はもっと注目されてよいトピックではないだろうか.
・ 『日本語百科大事典』 金田一 春彦ほか 編,大修館,1988年.
2024-09-27 Fri
■ #5632. フランス語は英語の音韻感覚を激変させた --- 月刊『ふらんす』の連載記事第7弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][phonology][phoneme][stress][prosody][rhyme][alliteration][me][rsr][gsr]

*
9月25日,白水社の月刊誌『ふらんす』10月号が刊行されました.この『ふらんす』にて,今年度,連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書かせていただいています.今回は連載の第7回です.「フランス語は英語の音韻感覚を激変させた」と題して記事を執筆しました.以下,小見出しごとに要約します.
1. 子音の発音への影響
フランス語からの借用語が英語の発音に与えた影響について導入しています.特に /v/ の確立や,/f/ と /v/ の音素対立の形成について解説します.
2. 母音の発音への影響
フランス語由来の母音や2重母音が英語の音韻体系に与えた影響を説明しています./ɔɪ/ の導入など,具体例を挙げながらの解説です.
3. アクセントへの影響
フランス語借用語によって英語の強勢パターンがどのように変化したかを論じています.異なる強勢パターンの共存など,英語史の観点から興味深い事例を提供します.
4. 英語らしさの形成
英語はフランス語の影響を受けつつも,独自の音韻体系を発達させてきました.その過程で形成されてきた発音の「英語らしさ」について批判的に考察します.
今回の記事では,フランス語が英語の(語彙ではなく)発音に与えた影響を,具体例を交えながら解説しています.フランス語の語彙的な影響については知っているという方も,発音への影響については意外と聞いたことがないのではないでしょうか.通常レベルより一歩上を行く英語史の話題となっています.
ぜひ『ふらんす』10月号を手に取っていただければと思います.過去6回の連載記事も hellog 記事で紹介してきましたので,どうぞご参照ください.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])
・ 「#5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾」 ([2024-07-23-1])
・ 「#5600. フランス語慣れしてきた英語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第6弾」 ([2024-08-26-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第7回 フランス語は英語の音韻感覚を激変させた」『ふらんす』2024年10月号,白水社,2024年9月25日.54--55頁.
2024-09-18 Wed
■ #5623. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]
一昨日の Voicy heldio にて「#1205. Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継 --- 「英語史ライヴ2024」より」をアーカイヴ配信しました.これは「#5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します」 ([2024-09-02-1]) で予告したとおり,9月8日(日)に開催された「英語史ライヴ2024」の早朝枠にて生配信された番組がもとになっています.
金田拓さん(帝京科学大学)がメインMCを務め,小河舜さん(上智大学)と私が加わる形での対談精読実況生中継でした.ヘルメイト(helwa リスナー)や khelf メンバーも数名がギャラリーとして収録現場に居合わせ,生配信でお聴きになったリスナーものべ81名に達しました.たいへんな盛況ぶりです.皆さん,日曜日の朝から盛り上げてくださり,ありがとうございました.
今回取り上げたセクションは,実はテクニカルです.古英語期のラテン借用語について,それぞれの単語が同時期内でもいつ借りられたのか,いわば借用の年代測定に関する方法論が話題となっています.取り上げられているラテン借用語の例はすこぶる具体的ではありますが,音変化の性質や比較言語学の手法に光を当てる専門的な内容となっています.
しかし,今回の対談精読会にそってに丁寧に英文を読み解いていえば,必ず理解できますし,歴史言語学研究のエキサイティングな側面を体験することもできるでしょう.本編48分ほどの長尺ですが,ぜひお時間のあるときにゆっくりお聴きください.
Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.
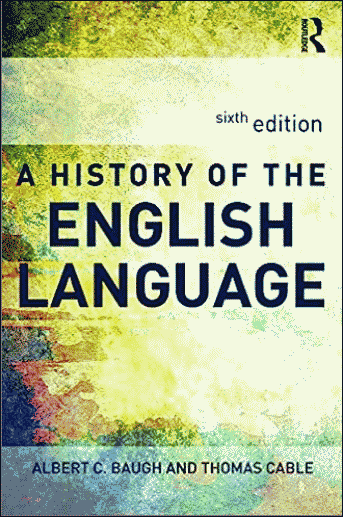
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2024-09-15 Sun
■ #5620. study の第1音節母音が短母音であることについて [senbonknock][sobokunagimon][phonetics][phonology][french][latin][loan_word][syllable][monophthong][hellive2024][heldio]
「#5618. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より」 ([2024-09-13-1]) で紹介した,Voicy heldio の「早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん」にて,本編の40分30秒くらいから「study と student で <u> の部分の発音の仕方が異なるのはなぜですか?」という問いが取り上げられています.「#3295. study の <u> が短母音のわけ」 ([2018-05-05-1]) の説明では不十分ではないか,という指摘がありました.
上記「千本ノック」では手元に詳しい情報がない状態での即興の回答だったのですが,その後,詳しく調べてみると,いろいろと込み入った事情があるようです.study の第1音節母音が短母音であるのは,この単語がもともとはラテン語由来でありながら,フランス語を経由してきたという経緯が関与していそうです.
これについては,英語音韻史を書いた中尾 (339) に手がかりがあった.
F [= French] 借入語の音量:OF [= Old French] の母音は CL [= Classical Latin] の音量ではなく,VL [= Vulgar Latin] の閉音節では短く,開音節では長いという原則を受け継いだ.ME [= Middle English] の音組織は F 借入語を通してこの新しい型の音量をしばしば反映する.
ここで短母音になる具体的な音環境が3点ほど挙げられているのだが,その1つに「3音節動詞,名詞,形容詞の第1音節」がある(中尾,p. 340).動詞 study の中英語形 studien が,この項目の多数の例の1つとして挙げられている(赤字で示した).
(3) 3音節動詞,名詞,形容詞の第1音節:banisshen (=banish)/ravisshen (=ravish)/vanisshen (=vanish)/perishen (=perish)/finishen (=finish)/florisshen (=flourish)/norishen (=nourish)/publisshen (=publish)/punisshen (=punish)/travailen (=travail)/honouren (=honour)/visiten (=visit)/governen (=govern)/studien (=study)/family/salary/memory/remedy/misery/chalaundre (=calendar)/chapitre (=chapter)/sepulcre/oracle/miracle/ministre (=minister)/vinegre (=vinegar)/covenant/rethorik (=rhetoric)/bacheler (=bachelor)/charitee (=charity)/vanite (=vanity)/jolitee (=jollity)/povertee (=poverty)/libertee (=liberty)/trinitee (=trinity)/facultee (=faculty)/vavasour/amorous/casuel (=casual)/natural/general/lecherous/seculer (=secular)/diligent
動詞 study は,中英語では stud・ī・en のように3音節語でした.この場合,現代の2音節語 stu・dent とは異なり,第1音節が閉音節となるために問題の母音が短く保たれる,といった理屈となります.
・ 中尾 俊夫 『音韻史』 英語学大系第11巻,大修館書店,1985年.
2024-09-02 Mon
■ #5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]
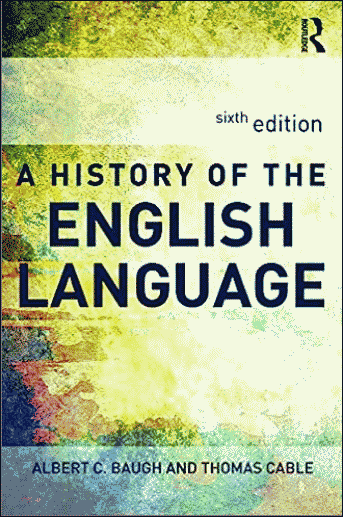
Baugh and Cable による英語史の古典的名著を Voicy heldio にて1節ずつ精読していくシリーズをゆっくりと進めています.昨年7月に開始した有料シリーズですが,たまの対談精読回などでは通常の heldio にて無料公開しています.
9月8日(日)に12時間 heldio 生配信の企画「英語史ライヴ2024」が開催されますが,当日の早朝 8:00-- 8:55 の55分枠で「Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継」を無料公開する予定です.金田拓さん(帝京科学大学)と小河舜さん(上智大学)をお招きし,日曜日の朝から3人で賑やかな精読回を繰り広げていきます.
テキストをお持ちでない方のために,当日精読することになっている第57節 "Chronological Criteria" (pp. 73--75) の英文を以下に掲載しておきます.古英語期のラテン借用語の年代測定に関するエキサイティングな箇所です.じっくりと予習しておいていただけますと,対談精読実況生中継を楽しく聴くことができると思います.
57. Chronological Criteria. In order to form an accurate idea of the share that each of these three periods had in extending the resources of the English vocabulary, it is first necessary to determine as closely as possible the date at which each of the borrowed words entered the language. This is naturally somewhat difficult to do, and in the case of some words it is impossible. But in a large number of cases it is possible to assign a word to a given period with a high degree of probability and often with certainty. It will be instructive to pause for a moment to inquire how this is done.
The evidence that can be employed is of various kinds and naturally of varying value. Most obvious is the appearance of the word in literature. If a given word occurs with fair frequency in texts such as Beowulf, or the poems of Cynewulf, such occurrence indicates that the word has had time to pass into current use and that it came into English not later than the early part of the period of Christian influence. But it does not tell us how much earlier it was known in the language, because the earliest written records in English do not go back beyond the year 700. Moreover, the late appearance of a word in literature is no proof of late adoption. The word may not be the kind of word that would naturally occur very often in literary texts, and so much of Old English literature has been lost that it would be very unsafe to argue about the existence of a word on the basis of existing remains. Some words that are not found recorded before the tenth century (e.g., pīpe 'pipe', cīese 'cheese') can be assigned confidently on other grounds to the period of continental borrowing.
The character of the word sometimes gives some clue to its date. Some words are obviously learned and point to a time when the church had become well established in the island. On the other hand, the early occurrence of a word in several of the Germanic dialects points to the general circulation of the word in the Germanic territory and its probable adoption by the ancestors of the English on the continent. Testimony of this kind must of course be used with discrimination. A number of words found in Old English and in Old High German, for example, can hardly have been borrowed by either language before the Anglo-Saxons migrated to England but are due to later independent adoption under conditions more or less parallel, brought about by the introduction of Christianity into the two areas. But it can hardly be doubted that a word like copper, which is rare in Old English, was nevertheless borrowed on the continent when we find it in no fewer than six Germanic languages.
The most conclusive evidence of the date at which a word was borrowed, however, is to be found in the phonetic form of the word. The changes that take place in the sounds of a language can often be dated with some definiteness, and the presence or absence of these changes in a borrowed word constitutes an important test of age. A full account of these changes would carry us far beyond the scope of this book, but one or two examples may serve to illustrate the principle. Thus there occurred in Old English, as in most of the Germanic languages, a change known as i-umlaut. (Umlaut is a German word meaning 'alteration of sound', which in English is sometimes called mutation.) This change affected certain accented vowels and diphthongs (æ, ā, ō, ū, ēa, ēo , and īo) when they were followed in the next syllable by an ī or j. Under such circumstances, æ and a became e, and ō became ē, ā became ǣ, and ū became ȳ. The diphthongs ēa, ēo, īo became īe, later ī, ȳ. Thus *baŋkiz > benc (bench), *mūsiz > mȳs, plural of mūs (mouse), and so forth. The change occurred in English in the course of the seventh century, and when we find it taking place ina word borrowed from Latin, it indicates that the Latin word had been taken into English by that time. Thus Latin monēta (which became *munit in Prehistoric OE) > mynet (a coin, Mod. E. mint) and is an early borrowing. Another change (even earlier) that helps us to date a borrowed word is that known as palatal diphthongization. By this sound change ǣ or ē in early Old English was changed to a diphthong (ēa and īe, respectively) when preceded by certain palatal consonants (ċ, ġ, sc). OE cīese (L. cāseus, chesse) mentioned earlier, shows both i-umlaut and palatal diphthongization (cāseus > *ċǣsi > *ċēasi > *ċīese). In many words, evidence for date is furnished by the sound changes of Vulgar Latin. Thus, for example, an intervocalic p (and p in the combination pr) in the Late Latin of northern Gaul (seventh century) was modified to a sound approximating a v, and the fact that L. cuprum, coprum (copper) appears in OE as copor with the p unchanged indicates a period of borrowing prior to this change (cf. F. cuivre). Again Latin ī changed to e before A.D. 400 so that words like OE biscop (L. episcopus), disc (L. discus), sigel 'brooch' (L. sigillum), and the like, which do not show this change, were borrowed by the English on the continent. But enough has been said to indicate the method and to show that the distribution of the Latin words in Old English among the various periods at which borrowing took place rests not upon guesses, however shrewd, but upon definite facts and upon fairly reliable phonetic inferences.
Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2024-08-26 Mon
■ #5600. フランス語慣れしてきた英語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第6弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][binomial][lexical_stratification][waseieigo][lexicology]

*
白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.先日23日に『ふらんす』9月号が刊行されました.連載の第6回が掲載されています.
今回の記事のタイトルは「フランス語慣れしてきた英語」です.過去数回の記事では,英語がフランス借用語を大量かつ広範に受け入れてきた経緯を紹介してきました.この衝撃を通じ,やがてフランス語慣れした英語は自らの語彙体系を大きく変容させるに至りました.今回は以下の4つの小見出しのもとに記事を執筆しています.
1. 英仏単語の「2項イディオム」
中英語期には,英語本来語とフランス借用語を並べる「2項イディオム」が多く見られました.これにはフランス語を英語に導入しやすくする役割がありましたし,表現を豊かにしリズム感を出す効果もありました.
2. 英語語彙の「2重構造」
英語本来語とフランス借用語が共存する場合,多くは微妙に異なる意味や用法を発達させています.一般に,英語本来語は純朴な響きを,フランス借用語は威厳ある響きを伴う傾向があります.
3. 「動物」と「肉」
英語では動物とその肉を表す単語が異なりますが,これはノルマン征服後の階級社会を反映しています.下層階級の英語話者が動物を育て,上層階級のフランス語話者がその肉を食べるという構図が,きれいに語彙に反映されているのです.
4. 「英製仏語」
英語がフランス語を取り入れる過程で,フランス語風の要素を使って独自に作り出した単語があります.「和製英語」ならぬ「英製仏語」です.
ぜひ『ふらんす』9月号を手に取って,数々の具体例をご確認ください.また,過去5回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりご参照ください.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])
・ 「#5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾」 ([2024-07-23-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第6回 フランス語慣れしてきた英語」『ふらんす』2024年9月号,白水社,2024年8月23日.52--53頁.
2024-08-21 Wed
■ #5595. poor と poverty [v][sound_change][adjective][inflection][noun][me][french][loan_word]
「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1]) で,形容詞 poor の語形についても触れた.この語は古フランス語 povre に由来し,本来は v をもっていたが,英語側で v が消失したということだった.しかし,対応する名詞形 poverty では v が消失していない.これはなぜかという質問が寄せられた.
後者には名詞語尾が付加されており,もとの v の現われる音環境が異なるために両語の振る舞いも異なるのだろうと,おぼろげに考えていた.しかし,具体的には調べてみないと分からない.
そこで,第一歩として Jespersen に当たってみた. v 削除 について,MEG1 より2つのセクションを見つけることができた.まず §2.532. を引用する.
§2.532. A /v/ has disappeared in a great many instances, chiefly through assimilation with a following consonant: had ME hadde OE hæfde, lady ME ladi, earlier lafdi OE hlæfdige . head from the inflected forms of OE hēafod; at one time the infection was heved, (heavdes) heddes . lammas OE hlafmæsse . woman ME also wimman OE wifman . leman OE leofman . gi'n, formerly colloquial, now vulgar for given . se'nnight [ˈsenit] common till the beginning of the 19th c. for sevennight. Devonshire was colloquially pronounced without the v, whence the verb denshire 'improve land by paving off turf and burning'. Daventry according to J1701 was pronounced "Dantry" or "Daintry", and the town is still called [deintri] by natives. Cavendish is pronounced [ˈkɚndiʃ] or [ˈkɚvndiʃ]. hath OE hæfþ. eavesdropper (Sh. R3 V. 3.221) for eaves-. The v-less form of devil, mentioned for instance by J1701 (/del/ and sometimes /dil/), is chiefly due to the inflected forms, but is also found in the uninflected; it is probably found in Shakespeare's Macb. I. 3.107; G1621 mentions /diˑl/ as northern, where it is still found. marle for marvel is frequent in BJo. poor seems to be from the inflected forms of the adjective, cf. Ch. Ros. 6489 pover, but 6490 alle pore folk; in poverty the v has been kept . ure† F œuvre, whence inure, enure . manure earlier manour F manouvrer (manœuvre is a later loan). curfew, -fu OF couvrefeu . kerchief OF couvrechef . ginger, oldest form gingivere . Liverpool without v is found in J1701 and elsewhere, see Ekwall's edition of Jones §184. Cf. further 7.76.
Jespersen は,形容詞における v 消失は,屈折形に由来するのではないかという.v の直後に別の子音が続けば v は脱落し,母音が続けば保持される,という考え方のようだ.いずれにせよ音環境によって v が落ちるか残るかが決まるという立場を取っていることになる.
参考までに,v 消失については,さらに §7.76. より,関係する最初の段落を引用しよう.
§7.76. /v/ and /f/ are often lost in twelvemonth (Bacon twellmonth, S1780, E1787, W1791), twelvepence (S1780, E1787), twelfth (E1787, cf. Thackeray, Van. F. 22). Cf. also the formerly universal fi'pence, fippence (J1701, E1765, etc.), still sometimes [fipəns]. Halfpenny, halfpence, . . .
この問題については,もう少し詳しく調べていく必要がありそうだ.以下,関連する hellog 記事を挙げておく.
・ 「#1348. 13世紀以降に生じた v 削除」 ([2013-01-04-1])
・ 「#2276. 13世紀以降に生じた v 削除 (2)」 ([2015-07-21-1])
・ 「#2200. なぜ *haves, *haved ではなく has, had なのか」 ([2015-05-06-1])
・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.
2024-07-23 Tue
■ #5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][borrowing][norman_french][doublet][hybrid][lexicology]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.本日『ふらんす』8月号が刊行されました.連載としては第5回となります.
今回は前回の「フランス借用語の大流入」に引き続いての話題です.大流入の結果,英語語彙にどのような衝撃がもたらされたのか,に迫ります.以下の4つの小見出しのもとにエッセイを書いています.
1. 単語借用と語彙体系の変化
中英語期にフランス語からの大量の単語借用があり,英語の語彙体系に大きな影響を与えました.これにより,英語の語彙のあり方が大きく変化しました.
2. 死語となった本来の英単語
フランス語からの借用語により,既存の英単語が置き換えられ死語となるケースが多くありました.例えば「おじ」を意味する ēam が uncle に,「嫉妬」を意味する anda が envy に置き換えられるなどしました.
3. ノルマン・フランス語と中央フランス語
初期の借用語はノルマン方言から,後期はパリの中央フランス語から入りました.これにより,同じ語源を持つ単語が異なる形で英語に入り,2重語 (doublet) として共存するようになりました.
4. 英仏ハイブリッド語
フランス語の語形成に慣れた英語は,フランス語由来の接辞を英語本来の単語に付けて新しい単語を作り出しました.これらは英仏要素を含むハイブリッド語として英語に定着しました.
過去4回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりお読みください.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁.
2024-07-21 Sun
■ #5564. 古英語のラテン語からの借用語はせいぜい数百語 [oe][loan_word][borrowing][latin][old_norse][celtic][latin][germanic][lexicology][link]
古英語の語彙は相当程度にピュアなゲルマン系の語彙といってよく,借用語は限られている.しかも,その限られた借用語の大部分がラテン語 (latin) からのものである.ほかには古ノルド語 (old_norse),ケルト語 (celtic),ゲルマン諸語 (germanic), フランス語 (french) からの借用語もないではないが,あくまで影は薄い.
これらの言語から古英語への借用語は,むしろ例外的だからこそ気になるのだろう.数が少ないので,古英語を読んでいるときに出くわすとやけに目立つのである.英語史研究でもかえってよく注目されている.Hogg は,古英語期の語彙と語彙借用について次のように評している.
. . . there are words of non-native origin in Old English, the vast majority of which are from Latin. It has been estimated only about 3 per cent of Old English vocabulary is taken from non-native sources and it is clear that the strong preference in Old English was to use its native resources in order to create new vocabulary. In this respect, therefore, and as elsewhere, Old English is typically Germanic. (102--03)
. . . there was in Old English only a very limited use of words taken from other language, i.e. borrowed or loan words, and those words were primarily from Latin. Apart from Latin, Old English borrowed words from the Scandinavian languages after the Viking invasions, from the celtic languages mostly at a very early date, and there was also a scattering of forms from the other Germanic languages. At the very end of the period we begin to see the first loan words from Norman French. (109)
古英語期の各言語からの語彙借用については,以下の記事を参照.
・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])
・ 「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1])
・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1])
・ 「#1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類」 ([2014-08-24-1])
・ 「#2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語」 ([2016-05-18-1])
・ 「#3787. 650年辺りを境とする,その前後のラテン借用語の特質」 ([2019-09-09-1])
・ 「#3788. 古英語期以前のラテン借用語の意外な日常性」 ([2019-09-10-1])
・ 「#3789. 古英語語彙におけるラテン借用語比率は1.75%」 ([2019-09-11-1])
・ 「#3790. 650年以前のラテン借用語の一覧」 ([2019-09-12-1])
・ 「#3829. 650年以後のラテン借用語の一覧」 ([2019-10-21-1])
・ 「#3830. 古英語のラテン借用語は現代まで地続きか否か」 ([2019-10-22-1])
・ 「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1])
・ 「#3821. Old Saxon からの借用語」 ([2019-10-13-1])
・ 「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1])
・ Hogg, Richard. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.
2024-07-13 Sat
■ #5556. kh の綴字をもつ単語とその外来性 [spelling][loan_word][digraph][h][digraph][silent_letter][orthography]
昨日の記事「#5555. kh の綴字」 ([2024-07-12-1]) に引き続き,2重字 (digraph) の <kh> について.Upward and Davidson (257) にまとまった記述があるので引用する.
KH
The KH spelling reflects an aspirated consonant (somewhat like [k] + [h]) or a fricative (like [x] as in Scottish loch) in the source or carrier languages, all from the Middle East or Indian subcontinent. In English, there is no difference in pronunciation between KH and K.
・ In initial position: khaki (< Hindi); khamsin 'hot wind' (< Arabic); khan (spelt caan when first borrowed in the 15th century; < a Turkic language)
- Khazi, a slang word for 'toilet' dating from the 19th century, is not, despite its spelling, of eastern origin, but probably derives from Italian or Spanish casa 'house'. It has various spellings in English (kazi, kharzie, karsey, etc.).
・ In medial position: astrakhan 'fabric' (< Russian place-name); bakhshish 'tip or bribe' (a spelling baksheesh --- see under 'K'); burkha (a spelling of burka/burqa --- see under 'K'); gymkhana (< Urdu gend-khana, altered by influence of gymnastics); kolkhoz 'collective farm in USSR' (< Russian).
・ In final position: ankh 'emblem of life' (< Egyptian 'nh); lakh '100,000' (also lac; < Hindi and Hindustani); rukh 'mythical bird' (another spelling of roc, which is the more common spelling in English; < Arabic rokh, rukhkh, Persian rukh); sheikh (< Arabic shaikh).
ほぼすべての単語が中東,インドア大陸,ロシアの諸言語に由来し,その原語の風味を保持するために,本来的には英語に馴染みのない <kh> という綴字が用いられているのだろう.書き言葉の綴字には,話し言葉の発音では標示し得ない,単語の由来を示唆する機能が部分的であれ備わっているという点が重要である.
・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2024-07-12 Fri
■ #5555. kh の綴字 [spelling][loan_word][digraph][h][khelf][acronym][digraph][silent_letter][orthography]

khelf(慶應英語史フォーラム)では『英語史新聞』を発行するなど,英語史を振興する「hel活」 (helkatsu) を様々に展開しています.
khelf という呼称は "Keio History of the English Language Forum" の頭字語 (acronym) で,私自身の造語なのですが,日本語発音では「ケルフ」,英語発音では /kɛlf/ となるのだろうと思います.khelf の <kh> の綴字連続が見慣れないという声が寄せられましたので,英語の綴字における 2重字 (digraph) について本記事で取り上げます.
<kh> は,英語においては決して頻度の高い文字の組み合わせではありませんが,khaki (カーキ色),khan (カーン,ハーン,汗),Khmer (クメール人),Khoisan (コイサン語族),Sikh (シク教徒)などに見られ,いずれの単語でも <kh> ≡ /k/ の対応関係を示します.ただし,すべて借用語や固有名であり,英語正書法に完全に同化しているかといえば怪しいところです.Carney (221) では,<kh> に言及しつつ astrakhan (アストラカン織), gymkhana (野外競技会), khaki, khan, khedive (エジプト副王)が挙げられています.
Carney (328) では,<h> を2文字目としてもつ,子音を表わす他の2重字とともに <kh> が扱われています.関連箇所を引用しましょう.
The clusters <ch>, <ph>, <sh>, <th>, <wh>, are treated as spelling units. So are the clusters <gh>, <kh>, <rh>, but there is a difference. In the first group, the <h> has the natural function of indicating the features 'voiceless and fricative' in representing [ʧ], [f], [ʃ], [ʍ]; <th> represents only 'fricative' for both voiceless [θ] and voiced [ð]. In the group <gh>, <kh>, <rh>, the <h> is empty and arbitrary; there is some marking, however: <rh> is §Greek, <kh> is exotic.
<kh> の <h> は音声的には動機づけのない黙字 (silent_letter) といってしかるべきだが,最後に触れられているとおり,その単語が "exotic" であることを標示する機能は有しているようだ.khelf もユニークで魅惑的という意味での "exotic" な活動を目指したい.
・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.
2024-06-25 Tue
■ #5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][reestablishment_of_english]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.昨日『ふらんす』7月号が刊行されました.今回は連載第4回となります.タイトルは「フランス借用語の大流入」です.以下の小見出しのもとに,2頁ほどの英語史エッセイを執筆しています.
・ フランス借用語の爆発期
・ 多分野にわたるフランス借用語
・ なぜ英語復権期にフランス借用語が多くもたらされたのか?
前回までの連載記事では,英語にフランス借用語は多いけれども,実はフランス語彙の流入は初期中英語期まではさほど著しくなかった,というところまで述べました.今回はいよいよ1250年以降の大流入について導入しています.
フランス語彙が数千語という規模で一気に入ってきた,その量にまず驚きますが,それ以上に興味深いのはカバーしている語彙分野の広さです.ノルマン征服以降,イングランドの社会や文化の多くの部分がフランス(語)の影響下に入りましたが,とりわけ政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野ではフランス語の存在感は圧倒的でした.連載記事では,そのような借用語彙のサンプルを挙げています.
ここで1つ大きな謎は,なぜノルマン征服から200年も経った後に,フランス語彙の大流入が生じたのか,です.普通に考えると,ちょっと遅すぎるように感じませんか.遅くてもせいぜい数十年,もっと我慢したとしても100年くらいが良いところではないか,と思われます.ところが,フランス語彙の流入が軌道に乗り調子が出てくるまでに,ノルマン征服後,200年もの長い時間が経過してしまっているのです.これはどのように考えればよいのでしょうか.今回の記事では,この謎に一つの答えを与えています.
連載は年度末まで続く予定ですが,これまでの3回分を購読された読者の方は,すでに仏英語の関係についておおいに関心を抱くようになったのではないでしょうか.
過去3回の連載記事についても hellog で取り上げてきましたので,以下よりお読みいただければ.関連するリンクも,そちらにたくさん張っています.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第4回 フランス借用語の大流入」『ふらんす』2024年7月号,白水社,2024年6月24日.52--53頁.
2024-06-23 Sun
■ #5536. 接頭辞 en- と in- の揺れについて OED の解説を読む [prefix][latin][french][spanigh][loan_word][word_formation][spelling][etymological_respelling][lexicography][analogy]
昨日の記事「#5535. 接頭辞 en- と in- の揺れを Chancery English でみる」 ([2024-06-22-1]) で取り上げた話題について,もっと調べてみたくなり OED の en- PREFIX1 を引いた.語源欄の Note 3 に,この揺れについて詳しい歴史的経緯が記されている.勉強になったので,その箇所をすべて引用しておく.
3. From 14th cent. onwards the prefix in- (im-) has been frequently substituted for en- (em-); and, conversely, en- (em-) has been substituted for the prefix in- (im-) of words of Latin or Italian origin, and for the native English in- prefix1. Nearly every word, of long standing in the language, which is formed with en- has at some period been written also with in-. Hence it is often impossible to determine whether in a particular word of English formation the prefix en- or in- is due to the analogy of words of French, Latin, or purely English origin; in many instances it must have been applied merely as a recognized English formative, without reference to the analogy of any individual word. In 17th cent. the form in- (im-) was generally preferred; the now prevailing tendency is to use en- (em-) in English formations, and where the prefix represents French en-; and in modern reprints of 17th cent. books, and in dictionaries, the in- (im-) of the original texts is often replaced by en- (em-). In some words, however, as em-, imbed, en-, inclose, the form with in- still occurs, but in most cases less frequently than the en- forms; in a few instances in- has entirely superseded en-, even where the latter is etymologically more correct, as in imbrue, impair, inquest. In a few words (e.g. ensure v., insure v.) the alternative forms have (in very modern times) been appropriated to express different senses. As a general rule the en- and in- forms are in this Dict. treated as belonging to one and the same word. A word still surviving in use is treated in the alphabetical place of its now more frequent form. In the case of obsolete words, where there is no decided preponderance in usage, the choice of the typical form has been determined by etymological considerations: thus the adapted words from French or Spanish with en-, and new formations apparently on the analogy of these, are by preference placed under E; while words apparently formed on Latin analogies, or probably originating as compounds of the English preposition in n.2, will appear under I.
The substitution of in- for en- has in part been due to notions of etymological fitness, the Romanic en- having been regarded as a corrupt and improper form of the Latin in-, while the English formations in en- were either referred to Latin analogies or treated as compounds of the native preposition. The phenomenon seems, however, to be partly of phonetic origin. Tendency to reduce and slightly raise the vowel in this prefix results in homophonic pronunciations of word pairs such as embed and imbed, enclose and inclose. Occurrence of spellings such as inbassed for embassade in the fourteenth century may suggest this phenomenon has existed from an early period.
揺れの要因についての議論が詳しいが,数々の要因が作用しているようで現実はきわめて複雑だ.語源がフランス語かラテン語かという要因はもちろん重要だ.しかし,個々の単語においては各々の語形が互いに乗り入れしており,緩い傾向があるような,ないようなという状況だ.さらに,英語内部での語形成の場合には,フランス語やラテン語は,類推のモデルとしてあくまで間接的に作用しているにすぎず,結局いずれの接頭辞かを決める主要因が何なのかが,しばしば分からない.これは似非的なヴァージョンを含む語源的綴字 (etymological_respelling) をめぐる議論にも近似してくる.
最初の段落の終わりにかけては,この揺れが辞書編纂者の視点からも悩ましい問題であることが示されている.OED では接頭辞 en- と in- を原則として同一物として扱うが,では,どちらの接頭辞で主見出しを立てるべきか,という実際的な悩みがここに吐露されているものと読める.
英語綴字の歴史的深み(闇?)をもう1つ知ってしまった.
2024-06-22 Sat
■ #5535. 接頭辞 en- と in- の揺れを Chancery English でみる [prefix][latin][french][loan_word][chancery_standard][etymology][spelling]
英語には ensure/insure,encase/incase, entitle/intitle, embed/imbed, enclose/inclose, enwrap/inwrap など,接頭辞が en- と in- で揺れるペアがある.意味や用法が異なる場合もあれば,形態上の英米差を示す場合もあるし,単なる異形・異綴字である場合もある.それもそのはず,この接頭辞の起源は一つなのだ.ラテン語 in- に由来するフランス語の形態が en- なのである.
この2つの異形態は,歴史的には,現代以上に揺れていたようだ.目下私が注目している15世紀の Chancery English では,相当の揺れがみられる.Fisher et al. (33) を引用する.
Since prefixes were unaccented, they were subject to the same kinds of irregularities and inconsistencies as the inflectional endings. Adding to the confusion was the lack of standardization of often competing Latin- and French-derived prefixes such as in, im, en, and em.
Many words with prefixes beginning in in/im in MnE were written with en/em prefixes in Chancery documents. One explanation for this is the continuing French influence; another is the drift towards e as the regular vowel in unaccented syllables, noted above. But the relative strength of each explanation is difficult to determine. In any case, en prefixes where MnE requires in are sometimes preferred in Chancery writing. There are, for example, 33 instances of entent(e) as opposed to one of intent, and that in an ecclesiastical petition (153.8) where the Latin in would be expected. Likewise we have endenture and its plurals 25 times and indenture/indentures only six times, five of them in non-Chancery items (238 and 239). Informed is found once (as a past participle, 146.9), while variants of the infinitive enforme are the clear preference, with 27 listings. Other cases where the en form is preferred include enheritaunce and endented. Prefixes beginning with im in MdE show the same kind of variation, with preferences for empechment and enprisoned.
Chancery English は現代標準綴字の萌芽を示すと評価されることが多いが,このようにいまだ揺れは相当に大きい.今回は en-/in- をもつ語彙に限ってみたが,他の一般の語彙についても事情はおおよそ同じだ.英語史における綴字標準化の道のりは長かったのである.今回取り上げた接頭辞と関連して,以下の記事も要参照.
・ 「#1877. 動詞を作る接頭辞 en- と接尾辞 -en」 ([2014-06-17-1])
・ 「#4241. なぜ語頭や語末に en をつけると動詞になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-12-06-1])
・ 「#3510. 接頭辞 en- をもつ動詞は品詞転換の仲間?」 ([2018-12-06-1])
・ Fisher, John H., Malcolm Richardson, and Jane L. Fisher, comps. An Anthology of Chancery English. Knoxville: U of Tennessee P, 1984. 392.
2024-05-29 Wed
■ #5511. 6月8日(土)の朝カル新シリーズ講座第3回「英単語と「グリムの法則」」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][grimms_law][verners_law][consonant][stress][phonetics][loan_word][french][latin][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
これまでに第1回「語源辞典でたどる英語史」を4月27日(土)に,第2回「英語語彙の歴史を概観する」を5月8日(土)に開講しましたが,それぞれ驚くほど多くの方にご参加いただき盛会となりました.ご関心をお寄せいただき,たいへん嬉しく思います.
第3回「英単語と「グリムの法則」」は来週末,6月8日(土)の 17:30--1900 に開講されます.シリーズを通じて,対面・オンラインによるハイブリッド形式での開講となり,講義後の1週間の「見逃し配信」サービスもご利用可能です.シリーズ講座ではありますが,各回はおおむね独立していますし,「復習」が必要な部分は補いますので,シリーズ途中からの参加でも問題ありません.ご関心のある方は,こちらよりお申し込みください.

2回かけてのイントロを終え,次回第3回は,いよいよ英語語彙史の各論に入っていきます.今回のキーワードはグリムの法則 (grimms_law) です.この著名な音規則 (sound law) を理解することで,英語語彙史のある魅力的な側面に気づく機会が増すでしょう.グリムの法則の英語語彙史上の意義は,思いのほか長大で深遠です.英語語彙学習に役立つことはもちろん,印欧語族の他言語の語彙への関心も湧いてくるだろうと思います.『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする語源辞典や,一般の英語辞典も含め,その使い方や読み方が確実に変わってくるはずです.
講座ではグリムの法則の関わる多くの語源辞典で引き,記述を読み解きながら,実践的に同法則の理解を深めていく予定です.どんな単語が取り上げられるかを予想しつつ講座に臨んでいただけますと,ますます楽しくなるはずです.『英語語源辞典』をお持ちの方は,巻末の「語源学解説」の 3.4.1. Grimm の法則,および 3.4.2. Verner の法則 を読んで予習しておくことをお薦めします.
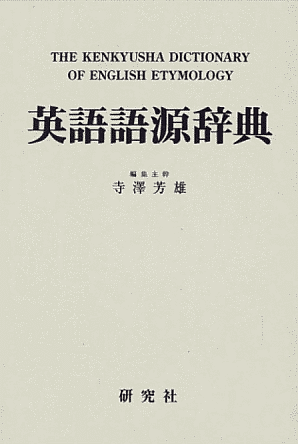
参考までに,本シリーズに関する hellog の過去記事へのリンクを以下に張っておきます.第3回講座も,多くの皆さんのご参加をお待ちしております.
・ 「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1])
・ 「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1])
・ 「#5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内」 ([2024-05-04-1])
(以下,後記:2024/05/30(Thu))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2024-05-27 Mon
■ #5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書かせていただいています.先日『ふらんす』6月号が刊行されました.今回で第3回となる記事のタイトルは「英語に借用された最初期の仏単語」です.以下の小見出しのもと,2頁ほどの読み物となっています.
・ フランス語との腐れ縁とその馴れ初め
・ 最初の仏借用語は古英語末期から
・ ノルマン征服後の2世紀は意外と地味
・ フランス語に置き換えられた法律用語
英語語彙にフランス語からの借用語が多く含まれていることはよく知られていますが,そもそも英仏語の言語接触 (contact) にはどのような背景があったのでしょうか.今回の記事では,両言語の出会いと,言語接触の最初期の状況を記述しました.最初期にはフランス語からの影響は意外と限定的だったことなどが,主たる話題となっています.
フランス語と英語史を掛け合わせた話題は豊富にあり,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも多く取り上げてきました.参考までに,関連する配信回をいくつか挙げておきます.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」
・ 「#1087. 英語の料理用語はフランス語とともにあり」
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第3回 英語に借用された最初期の仏単語」『ふらんす』2024年6月号,白水社,2024年5月23日.52--53頁.
2024-05-22 Wed
■ #5504. 接尾辞 -ive を OED で読む [etymology][suffix][french][oed][loan_word][oed][adjective][word_formation][noun][conversion][productivity]
「#2032. 形容詞語尾 -ive」 ([2014-11-19-1]) で取り上げた形容詞(およびさらに派生的に名詞)を作る接尾辞 (suffix) に再び注目したい.OED の -ive (SUFFIX) の "Meaning & use" をじっくり読んでみよう.
Forming adjectives (and nouns). Formerly also -if, -ife; < French -if, feminine -ive (= Italian, Spanish -ivo):--- Latin īv-us, a suffix added to the participial stem of verbs, as in act-īvus active, pass-īvus passive, nātīv-us of inborn kind; sometimes to the present stem, as cad-īvus falling, and to nouns as tempest-īvus seasonable. Few of these words came down in Old French, e.g. naïf, naïve:--- Latin nātīv-um; but the suffix is largely used in the modern Romanic languages, and in English, to adapt Latin words in -īvus, or form words on Latin analogies, with the sense 'having a tendency to, having the nature, character, or quality of, given to (some action)'. The meaning differs from that of participial adjectives in -ing, -ant, -ent, in implying a permanent or habitual quality or tendency: cf. acting adj., active adj., attracting adj., attractive adj., coherent adj., cohesive adj., consequent adj., consecutive adj. From their derivation, the great majority of these end in -sive and -tive, and of these about one half in -ative suffix, which tends consequently to become a living suffix, as in talk-ative, etc. A few are formed immediately on the verb stem, esp. where this ends in s (c) or t, thus easily passing muster among those formed on the participial stem; such are amusive, coercive, conducive, crescive, forcive, piercive, adaptive, adoptive, denotive, humective; a few are from nouns, as massive. In costive, the -ive is not a suffix.
Already in Latin many of these adjectives were used substantively; this precedent is freely followed in the modern languages and in English: e.g. adjective, captive, derivative, expletive, explosive, fugitive, indicative, incentive, invective, locomotive, missive, native, nominative, prerogative, sedative, subjunctive.
In some words the final consonant of Old French -if, from -īvus, was lost in Middle English, leaving in modern English -y suffix1: e.g. hasty, jolly, tardy.
Adverbs from adjectives in -ive are formed in -ively; abstract nouns in -iveness and -ivity suffix.
OED の解説を熟読しての発見としては:
(1) -ive が接続する基体は,ラテン語動詞の分詞幹であることが多いが,他の語幹や他の品詞もあり得る.
(2) ラテン語で作られた -ive 語で古フランス語に受け継がれたものは少ない.ロマンス諸語や英語における -ive 語の多くは,かつての -ivus ラテン単語群をモデルとした造語である可能性が高い.
(3) 分詞由来の形容詞接辞とは異なり,-ive は恒常的・習慣的な意味を表わす.
(4) -sive, -tive の形態となることが圧倒的に多く,後者に基づく -ative はそれ自体が接辞として生産性を獲得している.
(5) -ive は本来は形容詞接辞だが,すでにラテン語でも名詞への品詞転換の事例が多くあった.
(6) -ive 接尾辞末の子音が脱落し,本来語由来の形容詞接尾辞 -y と合流する単語例もあった.
上記の解説の後,-ive の複合語や派生語が951種類挙げられている.私の数えでこの数字なのだが,OED も網羅的に挙げているわけではないので氷山の一角とみるべきだろう.-ive 接尾辞研究をスタートするためには,まずは申し分ない情報量ではないか.
2024-05-04 Sat
■ #5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][loan_word][borrowing][word_formation][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
第1回「語源辞典でたどる英語史」は,4月27日(土)の 17:30--19:00 に開講され,おかげさまで盛況のうちに終了しました.こちらの回については,本ブログでも「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1]) および「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1]) で事前・事後に取り上げました.
第2回「英語語彙の歴史を概観する」は2週間後の5月18日(土)の 17:30--1900 に開講される予定です.対面・オンラインによるハイブリッド開講で,「見逃し配信」サービスもご利用可能です.第1回を逃した方も問題なくご参加いただけます.ご関心のある方は,ぜひこちらよりお申し込みください.

第2回は,シリーズ全体のイントロとして,1500年以上にわたる英語語彙史を俯瞰してみます.今後のシリーズ展開に向けて,英語の語彙の変遷について大きな見通しを得ることが目標です.英語語彙史を概観していく過程で,英語史の各時代からいくつかのキーワードをピックアップして『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする各種の英語語源辞典を参照します.同辞典をお持ちの方は,ぜひお手元にご用意しつつ,講座にご参加ください.どんな単語が取り上げられるかを予想しながら講座に臨んでいただければ.
(以下,後記:2024/05/14(Tue))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow