2025-01-08 Wed
■ #5735. 19世紀,英語がフランス語に及ぼした影響 [french][loan_word][purism][history_of_french]
18世紀のフランス語における英語の影響については,「#1026. 18世紀,英語からフランス語へ入った借用語」 ([2012-02-17-1]) でみた.そこでも参照したホームズ・シュッツ (167--68)が,19世紀の英語の言語的影響について1節を割いている.
94. 英語の影響
19世紀を通じて英語はフランスで,大きな影響を商業,政治,ジャーナリズムと特にスポーツに与えた.新しく加えられた語の中のいくつかは実際は昔,フランス語であった語の逆輸入で,外国で使われているうちに新しい性格を身につけたフランス語であった.中世フランス語の bougette [小さな革袋]はイギリスに渡って budget [予算]となり,故国に戻って来た.中世フランス語の desport, disport も同様で,英語で sport となって戻ってきた.entrevue > interview, étiquette > ticket.だが多くの語は,事実は大部分だが,採用されるまではフランスの土を踏んだことのない語である.フランスのある人びとは新しい英語マニアを毛嫌いした.ミュッセ Alfred de Musset (1810--1857) は自作の戯曲 Il ne faut jurer de rien の中の Van Buck という登場人物の口を借りて珍な発音の単語について痛烈な皮肉を十分に言っている.すぐれた批評家で作家でもあったレミ・ド・グールモン Rémy de Gourmont (1958--1915) は自分の母国語の精髄に対して脅威となると信じたこの英語の侵入について自著 Esthétique de la langue française の多くのページをさいている.彼によれば,単語を借用すべきというのは正しく,ガストン・パリス Gaston Paris (1839--1903) を先頭にする言語学研究の歴史をみてもそれは解るという.彼はガストン・パリスを師とすることに誇りを感じている.しかし,英語はフランス語が単語を借りる自然の泉ではないという.英語はしばしば耳に不快である.話す時に多くの外国語的言い廻しを使うのは当世の écoliet limousin 〔「パンタグリュエル」中の人物〔中略〕〕である.時には英語からの借用語は滑稽である.たとえば Harry Cower という名のバラは,まるで haricot vert [さや隠元]と書いてあるような発音になるではないか〔原註:この例は R. de Gourmont のような趣味豊かな人でも反感を持つとこのような極端なことを言うに至るというよい例である〕.この批評家も英語の侵入をとめることは出来なかった.
引用の最後のほうの原注部分が興味深い.言葉遣いに関する流行やそのアンチというものは常に存在し,その世代の内部にあっては,完全に客観的な批評家になることが難しいことを示している.
逆にいえば,時代を代表する批評家ですら当時の英語の影響力に待ったをかけることができなかった,ということかもしれない.
・ U. T. ホームズ,A. H. シュッツ 著,松原 秀一 訳 『フランス語の歴史』 大修館,1974年.
2024-11-28 Thu
■ #5694. ゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説について --- 池上俊一(著)『森と山と川でたどるドイツ史』より [purism][germanic][language_myth][linguistic_ideology]
3日前の記事「#5691. 池上俊一(著)『森と山と川でたどるドイツ史』(岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年)の目次」 ([2024-11-25-1]) で紹介した書籍より,ゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説について,著者の解説を引用したい.本書の最後の第7章の「政治と結びつく危険性」と題する1節 (206--07) より.
ドイツ人は二〇〇〇年近くにわたって,具体的な自然を活用して生活に役立てるだけでなく,より深い精神的・身体的な交流をもってきました.それが,彼らを政治的不安定・未確定の宙吊り状態の不安から救い,安心感,誇りと名誉の感覚さえ与えてきたのです.
パリやロンドンのような中心もなければ拠るべきギリシャ・ローマの伝統やキリスト教の伝統もない,しかもおびただしい領邦に分断されたドイツ人が,自己の定着地として認められるのは,曖昧だが根源的な自然や風景であって,生命とエロスが躍動しているーー個体としての人間とその魂がごく一部を構成するーー有機体世界=自然世界でした.
ですから一九世紀になって,ドイツにナショナリズムがわきおこってきたとき,根源とか自然とか,家郷とか祖国とか,血縁とか地縁などとの,情感あふれる結びつきに深く訴えながらのプロパガンダがくり広げられました.まさにウェットなナショナリズムなのですが,その大元には,ドイツ人にとっては「自然」こそが「家郷」であり,そこから引き離されてはドイツ人のドイツ人たる存在理由がなくなる,という思いがあったのです.
この独特な自然観を深く考察した当時の思想家たちによると,その「自然」には「言語」との密接な連関がありました.そして「ドイツ人の祖先はーー他のゲルマン民族とは異なりーー原民族の居住地にずっと止まり,かつもとの言語をそのまま維持した」「だからドイツ民族のみが根元とつながっており,そこに真に固有文化が育つのだ」と主張されました.
ここでは「言語」こそがひとつの「民族」の基礎をなすものであり,それがあたかも,植物や動物であるかのように分化し,成長していくととらえられています.「ドイツ人は言語も自然の根源性につながっているのに,他の諸民族は余所の言語を受け容れたり,故地から別の地域に移動して堕落し,文化も停滞してしまった」とされるのです.
このような考えに立てば「ドイツ語が話されているすべての地域がドイツとして統一されるべきだ」ということになり,このドイツ民族中心主義が,純血主義や世界主義と結びついていくとどんな恐ろしい結果がおきるかは,ナチ・ドイツが赤裸々に示したとおりです.
ドイツ語が「もとの言語をそのまま維持した」と考えられた際に,比較対照されたゲルマン諸語の筆頭はおそらく英語と考えてよいだろう.歴史的にみても,英語ほど純粋でないゲルマン語はないからだ.あまつさえ,英語は世界語の地位を得つつある著名な言語でもある.もちろん英語(の歴史)そのものに罪はないが,英語がゲルマン民族・ドイツ語純粋主義の言説のために引き合いに出されたということは十分にありそうだ
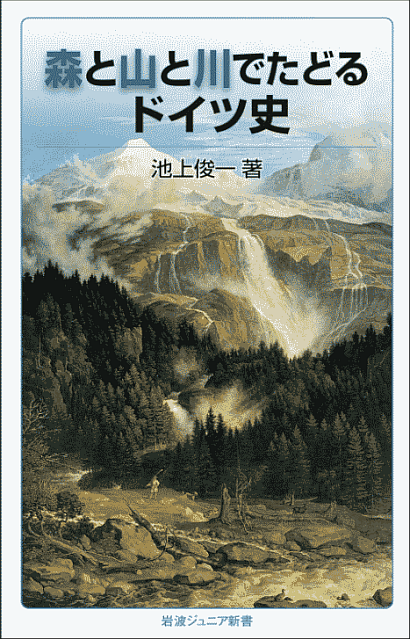
・ 池上 俊一 『森と山と川でたどるドイツ史』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2015年.
2023-01-18 Wed
■ #5014. When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? の諺のヴァリエーション [proverb][spenser][conversion][purism]
2日間の記事 ([2023-01-16-1], [2023-01-17-1]) で標題の諺について考えてきた.今回は Speake の諺辞典と OED より,歴史的なヴァリエーションを拾い出してみよう.
・ c 1340 R. Rolle in G. G. perry Religious Pieces (EETS) 88 When Adam dalfe [dug] and Eue spane ... Whare was than the pride of man?
・ 1381 in Brown & Robbins Index Middle English Verse (1943) 628 Whan adam delffid and eve span, Who was than a gentilman?
・ a1450 in C. Brown Relig. Lyrics 14th Cent. (1924) 96 When adam delf & eue span, spir, if þou wil spede, Whare was þan þe pride of man þat now merres his mede.
・ a1450 T. Walsingham Historia Anglicana (1864) II. 32 Whan Adam dalf, and Eve span, Wo was thanne a gentilman?
・ c1525 J. Rastell Of Gentylnes & Nobylyte sig. Aviv For when adam dolf and eue span who was then a gentylman.
・ 1562 J. Pilkington Aggeus & Abadias I. ii. When Adam dalve, and Eve span, Who was than a gentleman? Up start the carle, and gathered good, And thereof came the gentle blood.
・ 1777 T. Campbell Philos. Surv. S. Ireland xxxii. 308 England..had its Levellers, who, aggrieved by the monopoly of farms, rebelliously asked, When Adam delved, and Eve span, Where was then your Gentleman?
・ 1979 C. E. Schorske Fin-de Siécle Vienna vi. When Adam delved and Eve span Who was then the gentleman? The question had ironic relevance for the arrivé.
・ 2013 New Statesman May (online) An oral peasant culture, such as still survives in the Balkan countryside, is a fertile context for the transmission of history and ideas through ballad and song. This is not so different from 'When Adam Delved and Eve Span', which we've inherited from our 14th-century Peasants' Revolt.
delve の過去形としては,後期中英語の段階から従来の強変化形に加えて新しい弱変化形も現われていたことが分かる.一方,今回の証拠の範囲内では,過去形 span は不変であり,現代標準的な spun に置き換えられた例はない.また,疑問詞として who の代わりに where が用いられているもの,a gentleman や your gentleman のように the 以外が用いられているものもあった.gentleman の代わりの pride of man というのもおもしろい.
最後に,古風あるいはほとんど使われない名詞 delve について一言触れておきたい.これは古英語 gedelf (> PDE delf) に遡る一種の異形とも解釈できるかもしれないが,初出が1590年の Spenser Faerie Queene であることを考えると,Spenser 流の懐古的・擬古的な言葉遣いが反映された,動詞 delve からの品詞転換 (conversion) の事例とととらえることもできそうだ(cf. 「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1])).見方次第だが,死語の復活に類するものといえる.
・ Speake, Jennifer, ed. The Oxford Dictionary of Proverbs. 6th ed. Oxford: OUP, 2015.
2021-06-28 Mon
■ #4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか? [historiography][dutch][flemish][low_german][contact][loan_word][borrowing][purism][register][oed]
昨日の記事「#4444. オランダ借用語の絶頂期は15世紀」 ([2021-06-27-1]) でも触れたように,英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきたきらいがある (cf. 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])).これは英語史記述に関する小さからぬ問題と考えているが,なぜそうだったのだろうか.
Hendriks (1660) によれば,過小評価されてきた理由の1つとして,オランダ語を代表とする低地諸語がいずれも英語と近縁言語であり,個々の単語の語源確定が困難である点を指摘している.積極的にオランダ語由来であると判定できない限り,英語本来語であるという保守的な判断が優先されるのも無理からぬことだ.英語史はまずもって英語の存在を前提とする学問である以上,この点において強気の議論を展開することは難しい.明らかに英語とは異質の語源であると判明しやすいフランス語(そして,ある程度そうである古ノルド語)と比べれば,この点は確かに理解できる.
[C]ontributions from the Scandinavian and French languages to the lexicon of English, for example, are discussed in terms of certainty, whereas contributions from the closely related varieties of "Low Dutch" or "Low German" are couched in terms of "probably" or "possibly" or are simply not discussed.
しかし,それ以上に Hendriks が強調しているのは,従来の英語史の標準的参考書の背景に横たわる "purist language ideologies" (1659) である.Hendriks はさほど過激な物腰で論じていてるわけではないのだが,効果としては伝統的な英語史記述に対する強烈で辛辣な批判となっているといってよい.非常に注目すべき論考だと思う.
Hendriks は議論を2点に絞っている.1つめは,OED の文学テキスト偏重への批判である.OED は伝統的に,中英語における複数言語の混交した "macaronic" なテキストをソースとして除外してきた.実際には,このような実用的で現実的なテキストこそが,まさにオランダ語などからの新語導入の契機を提供していたかもしれないという視点が,OED には認められなかったということである(ただし,目下編纂中の第3版においてはこの点で改善が見られるということは Hendriks (1669) 自身も言及している).
もう1つは上記とも関連するが,OED は現代の標準英語に連なる英語変種にしか焦点を当ててこなかったという指摘だ.オランダ語からの借用語は,むしろ標準英語から逸脱したレジスター,例えば商業分野や通商分野の "macaronic" なレジスターでこそ活躍していたと想定されるが,OED なり英語史の標準的参考書では,そのような非標準的なレジスターはまともに扱われてこなかった.Hendriks (1662) 曰く,
Non-literary sources such as macaronic business writings, however, may be more likely to reflect the vernacular of London than the more pure literary texts selected to compile the atlas. Given the literary emphasis in the OED and the LALME, the range of topics which appear in these sources may be considerably restricted. The consequence of this is that entire semantic fields --- such as those pertaining to industrial or commercial relations, that is, fields where the significant contribution of Low Dutch to the English lexicon would be observed --- remain undocumented.
さらに,近代英語期以降に限れば,OED は "Standard English" 以外のソースを軽視してきたという事実も指摘せざるを得ない.
要するに,オランダ借用語が存在感を示してきたはずのレジスターが,OED を筆頭とする標準的レファレンスのソースには含まれてこなかったということなのだ.これは,英語史の historiography における本質的な問題と言わざるを得ない.
・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.
2020-12-25 Fri
■ #4260. 言葉使いの正しさとは? --- ことばの正誤について [purism][register][dialect][language_change][prescriptivism]
言葉使いに関して「正しい」「正しくない」と評価することは日常茶飯である.ら抜き言葉は正しくない.雰囲気の発音は「ふいんき」ではなく「ふんいき」が正しい.こんにち「わ」ではなく,こんにち「は」の書き方が正しい,等々.一般に言葉使いには規範的に正しい答えがあると信じられており,それに照らして正誤を判断するわけだ.
しかし,言語学的にいえば --- 記述主義的にいえば --- 言葉使いに「正誤」の問題は存在しない.「正しくない」とおぼしきケースがあったとしても,それは「正しくない」というよりは,むしろ「通じない」や「ふさわしくない」に近いことが多い.
Hughes et al. (16) は言葉使いの "correctness" について,3種類を区別している.
The first type is elements which are new to the language. Resistance to these by many speakers seems inevitable, but almost as inevitable, as long as these elements prove useful, is their eventual acceptance into the language. The learner needs to recognize these and understand them. It is interesting to note that resistance seems weakest to change in pronunciation. There are linguistic reasons for this but, in the case of the RP accent, the fact that innovation is introduced by the social elite must play a part.
The second type is features of informal speech. This, we have argued, is a matter of style, not correctness. It is like wearing clothes. Most people reading this book will see nothing wrong in wearing a bikini, but such an outfit would seem a little out of place in an office (no more out of place, however, than a business suit would be for lying on the beach). In the same way, there are words one would not normally use when making a speech at a conference which would be perfectly acceptable in bed, and vice versa.
The third type is features of regional speech. We have said little about correctness in relation to these, because we think that once they are recognized for what they are, and not thought debased or deviant forms of the prestige dialect or accent, the irrelevance of the notion of correctness will be obvious.
第1のものは,言語変化によってもたらされた新表現の類いである.純粋主義者を含めた言語について保守的な陣営から,しばしば「正しくない」とレッテルを貼られる語法などである.多くは時間とともに言語共同体のなかで広く受け入れられ,「正しい」語法へと格上げされていく.
第2のものは,語法そのものの正誤の問題というよりは,用いる場面を間違えてしまうという,register の観点からの「ふさわしさ」の問題といえば分かりやすいだろうか.ビキニを着ることそれ自体は問題ないが,会社で着るのは問題だ,という比喩がとても分かりやすい.
第3のものは,地域方言に関する誤解である.標準語使用が予期される文脈で地域方言の語法が用いられるとき誤解が生じることがあるが,後に単に地域方言の語法だったと分かり,誤解が解けさえすれば,言葉使いの正誤の問題とはみなさなくなるだろう.
日常生活である言葉使いが「正しくない」と思ったとき,それが記述主義的な立場からどのように解釈できるか,冷静に考えてみるとおもしろい.
・ Hughes, Arthur, Peter Trudgill, and Dominic Watt. English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles. 4th ed. London: Hodder Education, 2005.
2020-09-10 Thu
■ #4154. 借用語要素どうしによる混種語 --- 日本語の例 [japanese][hybrid][shortening][borrowing][loan_word][etymology][word_formation][contact][purism][covid]
先日の記事「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) を受けて,日本語の事例を挙げたい.和語要素を含まない,漢語と外来語からなる混種語を考えてみよう.「オンライン授業」「コロナ禍」「電子レンジ」「テレビ電話」「牛カルビ」「豚カツ」などが思い浮かぶ.ローマ字を用いた「W杯」「IT革命」「PC講習」なども挙げられる.
『新版日本語教育事典』に興味深い指摘があった.
最近では,「どた(んば)キャン(セル)」「デパ(ート)地下(売り場)めぐり」のように,長くなりがちな混種語では,略語が非常に盛んである.略語の側面から多様な混種語の実態を捉えておくことは,日本語教育にとっても重要な課題である. (262)
なるほど混種語は基本的に複合語であるから,語形が長くなりがちである.ということは,略語化も生じやすい理屈だ.これは気づかなかったポイントである.英語でも多かれ少なかれ当てはまるはずだ.実際,英語における借用語要素どうしによる混種語の代表例である television も4音節と短くないから TV と略されるのだと考えることができる.
日本語では,借用語要素どうしによる混種語に限らず,一般に混種語への風当たりはさほど強くないように思われる.『新版日本語教育事典』でも,どちらかというと好意的に扱われている.
混種語の存在は,日本語がその固有要素である和語を基盤にして,外来要素である漢語,外来語を積極的に取り込みながら,さらにそれらを組み合わせることによって造語を行ない,語彙を豊富にしてきた経緯を物語っている. (262)
英語では「#4149. 不純視される現代の混種語」 ([2020-09-05-1]) で触れたように,ときに混種語に対する否定的な態度が見受けられるが,日本語ではその傾向は比較的弱いといえそうだ.
・ 『新版日本語教育事典』 日本語教育学会 編,大修館書店,2005年.
2020-09-05 Sat
■ #4149. 不純視される現代の混種語 [hybrid][etymology][word_formation][combining_form][contact][waseieigo][borrowing][loan_word][waseieigo][purism][complaint_tradition]
「#4145. 借用語要素どうしによる混種語」 ([2020-09-01-1]) で,混種語 (hybrid) の1タイプについてみた.このタイプに限らず混種語は一般に語形成が文字通り混種なため,「不純」な語であるとのレッテルを貼られやすい.とはいっても,フランス語・ラテン語要素と英語要素が結合した古くから存在するタイプ (ex. bemuse, besiege, genuineness, nobleness, readable, breakage, fishery, disbelieve) は十分に英語語彙に同化しているため,非難を受けにくい.
不純視されやすいのは,19,20世紀に形成された現代的な混種語である.たとえば amoral, automation, bi-weekly, bureaucracy, coastal, coloration, dandiacal, flotation, funniment, gullible, impedance, pacifist, speedometer などが,言語純粋主義者によって槍玉に挙げられることがある.この種の語形成はとりわけ20世紀に拡大し,genocide, hydrofoil, hypermarket, megastar, microwave, photo-journalism, Rototiller, Strip-a-gram, volcanology など枚挙にいとまがない (McArthur 490) .
Fowler の hybrid formations の項 (369) では,槍玉に挙げられることの多い混種語がいくつか列挙されているが,その後に続く議論の調子ははすこぶる寛容であり,なかなか読ませる評論となっている.
If such words had been submitted for approval to an absolute monarch of etymology, some perhaps would not have been admitted to the language. But our language is governed not by an absolute monarch, nor by an academy, far less by a European Court of Human Rights, but by a stern reception committee, the users of the language themselves. Homogeneity of language origin comes low in their ranking of priorities; euphony, analogy, a sense of appropriateness, an instinctive belief that a word will settle in if there is a need for it and will disappear if there is not---these are the factors that operate when hybrids (like any other new words) are brought into the language. If the coupling of mixed-language elements seems too gross, some standard speakers write (now fax) severe letters to the newspapers. Attitudes are struck. This is all as it should be in a democratic country. But amoral, bureaucracy, and the other mixed-blood formations persist, and the language has suffered only invisible dents.
なお,混種語は,借用要素を「節操もなく」組み合わせるという点では「和製英語」 (waseieigo) を始めとする「○製△語」に近いと考えられる.不純視される語形成の代表格である点でも,両者は似ている.そして,比較的長い言語接触の歴史をもつ言語においては,極めて自然で普通な語形成である点でも,やはり両者は似ていると思う.最後の点については「#3858. 「和製○語」も「英製△語」も言語として普通の現象」 ([2019-11-19-1]) を参照.
・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford University Press, 1992.
・ Burchfield, Robert, ed. Fowler's Modern English Usage. Rev. 3rd ed. Oxford: OUP, 1998.
2018-08-13 Mon
■ #3395. 20世紀初頭に設立された英語アカデミーもどき [academy][purism]
イギリスでは,1712年に Jonathan Swift (1667--1745) の提案した Academy 創設の試みが頓挫したのち,公的に言語を統制しようとする動きは目立たなくなった.しかし,18,19,20世紀,そして現在に至るまで,統制とは言わずとも何らかの意味で言語を管理しようとする欲求が完全に消えたわけではない.言語について保守的・純粋主義的な人々は常に一定数存在したし,小規模あるいは私的なレベルで統制のために声を上げることはあった.その1つの例として,1913年に設立された Society for Pure English (S.P.E) を挙げよう.
S.P.E は1913年に設立されたが,実際に活動を始めたのは第1次世界大戦の休戦後のことである.当初の委員は,錚々たるメンバーだった.リーダー役を演じた桂冠詩人 Robert Bridges,著名な文献学者 Henry Bradley,オックスフォード大学英文学教授 Sir Walter Raleigh,文学者 Logan Pearsall Smith である.彼らの目的は,人々の言語(使用)に介入することではなく,あくまで "to agree upon a modest and practical scheme for informing popular taste on sound principles, for guiding educational authorities, and for introducing into practice certain slight modifications and advantageous changes" (qtd. in Baugh and Cable, p. 328) ということだった.人々の言語使用をむしろ尊重しているということを強調し,その上に立って若干の整理を行ないたい,ということだった.
しかし,それでもそこにアカデミーぽい匂い,言語統制の風味をかぎ取ったものもいた.例えば,Robert Graves という著者が,1926年に Impenetrability, or The Proper Habit of English において,次のように S.P.E を批判している.彼にとっては,Society for Pure English という名前からして胡散臭く思われたろう.
The 'Society for Pure English,' recently formed by the Poet Laureate, is getting a great deal of support at this moment, and is the literary equivalent of political Fascism. But at no period have the cultured classes been able to force the habit of tidiness on the nation as a whole. . . . The imaginative genius of the uneducated and half-educated masses will not be denied expression. (qtd. in Baugh and Cable, p. 328)
どの時代にも,統制に傾く派閥と自由を訴える派閥がある.アカデミー(もどき)設立の議論は,決して1712年をもって永久に幕を閉じたわけではない.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2018-05-28 Mon
■ #3318. 言語変化の最中にある新旧変異形を巡って [language_change][variation][subjunctive][purism][register][language_change]
伝統文法では be 動詞の仮定法過去形として,1人称単数および3人称単数で was ならぬ were が用いられる.If I were you . . . や as it were の如くである.しかし,このような決り文句や形式的な文体での使用を離れれば,くだけた言い方では直説法に引っ張られて was も用いられるようになってきていると言われる(例えば,I wouldn't do that, if I was you. や I wish I was dead! など).
伝統的な価値観の論者であれば,このような was の用法を「誤用」と感じ,その使用者を「堕落した」話者とみなすかもしれない.一方,言語変化を進歩とみる論者は,was の使用の増加によって,奇妙な振る舞いをする仮定法(過去形)が失われていくことを喜ぶかもしれない.ほかには,「万物は流転する」「行く河の流れは絶えずして」と達観して言語変化を眺める人もあるだろう.一般論として,言語変化の最中にある(とおぼしき)新旧変異形は,互いに異なる含蓄的意味 (connotation) やニュアンスを獲得し,様々な社会的・文体的な価値を帯びることが多い.
この一般論を,もう少し丁寧に説明しよう.A → B という言語変化が生じている最中には,当然ながら A と B が共に用いられる期間がある.今回の場合であれば,仮定法過去の If I were . . . (= A) と If I was . . . (= B) の両方が用いられる期間がある.この共用期間にはそれなりの長さがあり,初期,中期,末期などの局面が区別されるが,局面に応じて A と B のあいだには社会的・文体的価値や使用域において各種の差異が生じることが多い.ある局面では,A には正統の手堅さが,B には新参物としての軽佻浮薄な響きが感じられるかもしれない.別の局面では,A は教養を,B は無教養を標示するかもしれない.また別の局面では,A は旧時代の雰囲気をまとった古色蒼然たるおもむきを,B は新時代を予見させる若々しさを喚起させるかもしれない.しかし,最終的に A が消え,B のみが可能となったとき,それまでの各局面での両者のライバル関係は,(思い出せば懐かしい?)過去のドラマとなっており,すでに世代交代は完了しているのである.
If I were/was . . . の例にかぎらず,言語変化とはそのようなものだろう.しかし,当該の変化のさなかで共時的に生きている話者にとっては,新旧両形の対立は現在進行中のリアルなドラマなのであり,そこに保守,革新,その他諸々の立場が錯綜するのもまた常なのではないだろうか.
2017-09-15 Fri
■ #3063. Sir John Cheke の英語贔屓 [purism][bible][compounding][wycliffe][inkhorn_term]
Sir John Cheke (1514--57) はケンブリッジ大学の欽定ギリシア語講座の初代教授だった.当時は聖書の英訳が様々に試みられた時代であり,Cheke も1550年頃に「マタイ伝」および「マルコ伝」の最初の一部を英訳した.その際,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) で見たとおり,Cheke は言語的純粋主義 (purism) の立場を取り,訳語にむりやり感のある本来語(しばしば複合語)を採用した.Cheke 訳は,The Authorised Version (1611) に比べて純粋主義的としばしば言われる Tyndale 訳 (1525) よりもさらに純粋主義的であり,遡って14世紀後半の Wycliffe 訳と比較してすら古風な趣がある.以下に,「マタイ伝」よりいくつかの訳語について比較しよう(渡部,p. 239).
| Cheke | Wycliffe (1380) | Tyndale (1525) | Authorized Version (1611) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (バビロンへ)移す | outpeopling | transmygracioun | captivate | carrying away | chap. i. 17 |
| 予言者 | wiseards | astromyens | wyse men | wise men | chap. ii. 16 |
| てんかん | mooned | lunatik | lunatyke | lunaticke | chap. iv. 24 |
| みつぎ取り | tollers | pupplicans | publicans | publicans | chap. v. 46 |
| 百夫長 | hundreder | centurien | centurion | centurion | chap. viii. 5 |
| 使徒 | frosent | apostlis | apostles | apostles | chap. x. 2 |
| たとえ話 | biwordes | parablis | similitudes | parables | chap. xiii. 3 |
| 改宗者 | freschman | prosilite | 動詞構文 | proselyte | chap. xxiii. 15 |
| 十字架にかけられた | crossed | crucified | crucified | crucified | chap. xxvii. 22 |
Cheke がひときわ目立って本来語(しばしば複合語)を用いているのがわかるだろう.複合語のむりやり感は,古英語さながらである.
ラテン語やギリシア語からの小難しい借用語,すなわちインク壺語 (inkhorn_term) の全盛の時代において,これらの古典語を熟知した人文学者 Cheke が,母国語たる英語を贔屓したというのがおもしろい.彼が Henry VIII を継ぐ Edward VI をプロテスタント王として育てたほどのプロテスタントだったことも,この英語贔屓と関わっているだろう.Cheke は人文主義と宗教改革が同時に走っていた16世紀イングランドの両側面を1人で体現したような人物だったのである.渡部 (240) 曰く,「Cheke の例はわが国の明治の頃に留学して西洋の学問の先駆者となりながら,同時に国粋主義になった人と比較することもできよう」.
ただし,Cheke の語法に関しては別の評価もありうる.「#2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか?」 ([2016-02-09-1]) も参照されたい.Cheke については,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) と「#1709. 主要英訳聖書年表」 ([2013-12-31-1]) でも触れている.
・ 渡部 昇一 『英語の歴史』 大修館,1983年.
2017-07-09 Sun
■ #2995. Augustan Age の語彙的保守性 [lexicology][emode][inkhorn_term][purism][loan_word][latin][greek]
17世紀後半から18世紀にかけて語彙の増加が比較的低迷した時期がある.この事実は「#203. 1500--1900年における英語語彙の増加」 ([2009-11-16-1]),「#1226. 近代英語期における語彙増加の年代別分布」 ([2012-09-04-1]) のグラフより,一目瞭然だろう.英国史では,一般に1700年に前後する時代は保守的で渋好みの新古典主義時代(Augustan Age) と称されており,その傾向が言語上に新語彙導入の低迷というかたちで反映していると解釈することができる(関連して,「#2650. 17世紀末の質素好みから18世紀半ばの華美好みへ」 ([2016-07-29-1]),「#2782. 18世紀のフランス借用語への「反感」」 ([2016-12-08-1]) を参照).
この時代の語彙的保守性には歴史的背景がある.1つは,先立つ時代,特に16世紀後半から17世紀前半に,ラテン語やギリシア語といった古典語から大量の語彙が流入したという事実がある.「インク壺用語」 (inkhorn_term) と揶揄されるほどの,鼻につくような外国語の洪水に特徴づけられた時代である.このような大量借用は,確かに部分的には必要だった.科学,宗教,医学,哲学などの媒介言語がラテン語から英語へと急激に切り替わる時代にあって,英語は多くの語彙を確かに必要とした.しかし,短期集中で語彙を借用した結果,早々と英語の「語彙の必要」は満たされ,続く時代にはそれ以上借用するものがなくなってきた.Augustan Age で相対的に語彙借用が減ったのは,先立つ時代の「借用しすぎ」によるところも大きかったと思われる.語彙史も,ピークばかりでは疲れてしまうということか.
もう1つの歴史的背景としては,Augustan Age は,前時代の「借用しすぎ」を差し引いても,やはり保守的な言語観に支配されていた時代だったという事実がある.例えば,Jonathan Swift (1667--1745) や Joseph Addison (1672--1719) は当時を代表する保守派の論客であり,英語の堕落を嘆き,その改善・洗練・固定化を目指すために活発な執筆活動を行なっていた.「#1947. Swift の clipping 批判」([2014-08-26-1]) や「#1948. Addison の clipping 批判」 ([2014-08-27-1]),「#2741. ascertaining, refining, fixing」 ([2016-10-28-1]) に見られるように,時代の雰囲気は,華美を避け,質実剛健を求める保守主義だったのである.
Augustan Age の全体的な言語的傾向としては上記の通りだが,個々の年でいえば,例外的に新語彙導入の目立つ年もあった.例えば,1740年代から50年代にかけては,全体として語彙増加が最も低調な時代ではあるが,1753年には Chambers' Cyclopaedia が出版されており,そこに多くの科学用語が含まれていたために,例外的に語彙の生産力が高まった年として記録されている (Beal 21) .具体例を挙げれば,ラテン語およびギリシア語から adarticulation, aeronautics, azalea, ballistics, hydrangea, primula, sphagnum, trifoliate; anthropomorphism, eczema, mnemonic, urology 等が,この年に記録されている.
・ Beal, Joan C. English in Modern Times: 1700--1945. Arnold: OUP, 2004.
2017-07-03 Mon
■ #2989. 英語が一枚岩ではないのは過去も現在も同じ [variety][world_englishes][model_of_englishes][purism][standardisation][hel_education]
英語に作用する求心力と遠心力の問題(cf. 「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1]))を議論する際には,英語史の知識がおおいに役立つ.英語の歴史において,英語は常に複数形の Englishes だったのであり,単数形 English の発想が生まれたのは,近代以降に標準化 (standardisation) という社会言語学的なプロセスが生じてから後のことである.そして,その近代以降ですら,実際には諸変種は存在し続けたし,むしろ英語が世界中に拡散するにつれて変種が著しく増加してきた.その意味において,English とはある種の虚構であり,英語の実態は過去も現在も Englishes だったのである.
では,21世紀の英語,未来の英語についてはどうだろうか.求心力と遠心力がともに働いていくとおぼしき21世紀において,私たちは English を語るべきなのか,Englishes を語るべきなのか.この問題を議論するにあたって,Gooden (230--31) の文章を引こう.
After undergoing many changes at the hands of the Angles and Saxons, the Norman French, and a host of other important but lesser influences, English itself has now spread to become the world's first super-language. While this is a process that may be gratifying to native speakers in Britain, North America, Australia and elsewhere, it is also one that raises certain anxieties. The language is no longer 'ours' but everybody's. The centre of gravity has shifted. Until well into the 19th century it was firmly in Britain. Then, as foreseen by the second US president John Adams ('English is destined to be in the next and succeeding centuries [ . . . ] the language of the world'), the centre shifted to America. Now there is no centre, or at least not one that is readily acknowledged as such.
English is emerging in pidgin forms such as Singlish which may be scarcely recognizable to non-users. Even the abbreviated, technical and idiosyncratic forms of the language employed in, say, air-traffic control or texting may be perceived as a threat to some idea of linguistic purity.
If these new forms of non-standard English are a threat, then they are merely the latest in a centuries-long line of threats to linguistic integrity. What were the feelings of the successive inhabitants of the British Isles as armies, marauders and settlers arrived in the thousand years that followed the first landing by Julius Caesar? History does not often record them, although we know that, say, the Anglo-Saxons were deeply troubled by the Viking incursions which began in the north towards the end of the eighth century. Among their responses would surely have been a fear of 'foreign' tongues, and a later resistance to having to learn the vocabulary and constructions of outsiders. Yet many new words and structures were absorbed, just as the outsiders, whether Viking or Norman French, assimilated much of the language already used by the occupants of the country they had overrun or settled.
With hindsight we can see what those who lived through each upheaval could not see, that each fresh wave of arrivals has helped to develop the English language as it is today. Similarly, the language will develop in the future in ways that cannot be foreseen, let alone controlled. It will change both internally, as it were, among native speakers, and externally at the hands of the millions in Asia and elsewhere who are already adopting it for their own use.
ここでは言語的純粋性 (linguistic purity; purism) についても触れられているが,いったい正統な英語というものは,単数形で表現される English というものは,存在するのだろうか.存在するとすれば,具体的に何を指すのだろうか.あるいは,存在しないとすれば,「英語」とは諸変種の集合体につけられた抽象的な名前にすぎず,意味上は Englishes に相当する集合名詞に等しいのだろうか.
これは英語の現在と未来を論じるにあたって,実にエキサイティングな論題である.「#2986. 世界における英語使用のジレンマ」 ([2017-06-30-1]) の問題と合わせて,ディスカッション用に.
・ Gooden, Philip. The Story of English: How the English Language Conquered the World. London: Quercus, 2009.
2017-01-31 Tue
■ #2836. カタカナ語の氾濫問題を solidarity の観点から視る [sociolinguistics][japanese][katakana][loan_word][purism][solidarity][inkhorn_term]
「カタカナ語」と称される外来語の氾濫は,しばしば日本語の問題として話題となる.本ブログでも,「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1]) などで問題にしてきた.
#1617の記事で触れたように,とりわけ「高齢者の介護や福祉に関する広報紙の記事は,読み手であるお年寄りに配慮した表現を用いることが,本来何よりも大切にされなければならないはず」にもかかわらず,外来語が多用されている現実が問題とされることが多い.「お年寄りに配慮した表現」とは,理解しやすい漢語や和語での言い換え表現であるとか,あるいは少なくとも括弧で説明を付すなどの気遣いのことと把握していたが,社会言語学的な観点,特に solidarity (連帯)の観点から視ると,もう少し根の深い問題がありそうだということが分かる.井上 (190) は,「連帯」の裏返しとしての「排除」について次のように述べている.
日本のお役所ことばにカタカナ語を乱用するのはそれがわからない高齢者などを排除することになる.カタカナ語が問題なのは,意味がわからないことだけではない.連帯と排除の構造を社会に作り出してしまうことこそより問題である.
つまり,多くのお年寄りがカタカナ語の意味を理解できないという言語コミュニケーション上の問題以上に,お年寄りが,その意味を理解する若年集団と社会的に「連帯」できないという問題,もっと言えば「排除」されてしまうという問題があるという
この社会言語学的な説明は,ただお年寄りとカタカナ語の問題に限らず,ある言語に借用語が氾濫したときにしばしば生じるアンチ借用語の言語的純粋主義 (purism) を論じるにあたって,一般的に有効なのではないかと思われる.例えば,初期近代英語の「インク壺語論争」(inkhorn_term) においても,ラテン借用語の氾濫は,一般庶民の理解を超えるという点で言語コミュニケーション上の問題と捉えることもできるが,それ以上に,ラテン語を操れる知識層と操れない一般庶民たちの間の断絶という社会的な含意をもった問題と捉えるほうが妥当かもしれない.
・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.
2017-01-08 Sun
■ #2813. Bokenham の純粋主義 [purism][french][latin][lme][reestablishment_of_english]
「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]) で触れたように,Polychronicon を15世紀に英訳した Osbern Bokenham (1393?--1447?) という人物がいる.ノルマン征服以来,英語がフランス語やその他の言語と混合して崩れた言語になってしまったこと,英語話者がろくでもない英語を使うようになってしまったことを嘆いた純粋主義 (purism) の徒である.Bokenham の批判の直接の対象は,フランス語やラテン語にかぶれたイングランド社会の風潮であり,結果として人々がどの言語を用いるにせよ野蛮な言葉遣いしかできなくなっている現状だった.Bokenham のぼやきを,Gramley (110) からの引用で示そう.
And þis corrupcioun of Englysshe men yn þer modre-tounge, begunne as I seyde with famylyar commixtion of Danys firste and of Normannys aftir, toke grete augmentacioun and encrees aftir þe commyng of William conquerour by two thyngis. The firste was: by decre and ordynaunce of þe seide William conqueror children in gramer-scolis ageyns þe consuetude and þe custom of all oþer nacyons, here owne modre-tonge lafte and forsakyn, lernyd here Donet on Frenssh and to construyn yn Frenssh and to maken here Latyns on þe same wyse. The secounde cause was þat by the same decre lordis sonys and all nobyll and worthy mennys children were fyrste set to lyrnyn and speken Frensshe, or þan þey cowde spekyn Ynglyssh and þat all wrytyngis and endentyngis and all maner plees and contravercyes in courtis of þe lawe, and all maner reknyngnis and countis yn howsoolde schulle be doon yn the same. And þis seeyinge, þe rurales, þat þey myghte semyn þe more worschipfull and honorable and þe redliere comyn to þe famyliarite of þe worthy and þe grete, leftyn hure modre tounge and labouryd to kunne spekyn Frenssh: and thus by processe of tyme barbariȝid thei in bothyn and spokyn neythyr good Frenssh nor good Englyssh.
実際には15世紀にはイングランド人のフランス語やラテン語の能力はぐんと落ちていたはずであり,どの階層の人々も日常的に英語を用いる時代になって久しかったのだから,これらの外国語を母語たる英語に対する本格的な脅威として見ていたわけではないだろう(関連して「#2612. 14世紀にフランス語ではなく英語で書こうとしたわけ」 ([2016-06-21-1]),「#2622. 15世紀にイングランド人がフランス語を学んだ理由」 ([2016-07-01-1]) を参照).だが,これらの言語からの借用語などの「遺産」は英語において累々と積み重ねられており,それが Bokenham の言語的純粋主義を刺激していたものと思われる.むしろ英語の復権が事実上達成された後の時代における不満,あるいはいまだフランス語やラテン語にかぶれている貴族階級を中心とするイングランド人への非難,というように聞こえる.
・ Gramley, Stephan. The History of English: An Introduction. Abingdon: Routledge, 2012.
2016-12-08 Thu
■ #2782. 18世紀のフランス借用語への「反感」 [french][loan_word][purism][dryden]
18世紀は,ヨーロッパにおけるフランス語の威信が高まった時代である.イギリスにおいてもこの傾向は確かにみられ,実際に,18世紀には少なからぬフランス借用語が英語に流れ込んでいる(「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]),「#1792. 18--20世紀のフランス借用語」 ([2014-03-24-1]) を参照),
中英語期の大量借用とは比べるべくもないが,英語史においてフランス語が再び威信を取り戻した1つの時代ではあった.しかし,この世紀は比較的保守的で渋好みの新古典主義時代(Augustan Period) にも相当しており,とりわけその前半期には外来語への「反感」を示す声も一部から漏れていたというのも事実である.一般に,外来のものが大好きという向きが多い時代には,一方で大嫌いという向きも必ず現われるものである.語彙の借用を推進する人々がいれば,語彙の純粋さ (purism) を保とうと運動する保守的な論客も現われるというのが,古今東西の通例である.以下,この時代の状況を,Baugh and Cable (281--82) に引用されている当時の原文により伝えたい.
18世紀に外来語(主としてフランス借用語)の流入に苦言を呈した文人として,例えば Daniel Defoe (1660--1731) がいる.1708年10月10日付の Review では,"I cannot but think that the using and introducing foreign terms of art or foreign words into speech while our language labours under no penury or scarcity of words is an intolerable grievance." と述べている.
それよりも少し前の1672年のことだが,John Dryden (1631--1700) も Dramatic Poetry of the Last Age のなかで英語におけるフランス語の乱用を非難している.
I cannot approve of their way of refining, who corrupt our English idiom by mixing it too much with French: that is a sophistication of language, not an improvement of it; a turning English into French, rather than a refining of English by French. We meet daily with those fops who value themselves on their travelling, and pretend they cannot express their meaning in English, because they would put off on us some French phrase of the last edition; without considering that, for aught they know, we have a better of our own. But these are not the men who are to refine us; their talent is to prescribe fashions, not words.
Addison (1672--1719) も,1711年に Spectator (no. 165) で次のように述べている.
I have often wished, that as in our constitution there are several persons whose business is to watch over our laws, our liberties, and commerce, certain men might be set apart as superintendents of our language, to hinder any words of a foreign coin, from passing among us; and in particular to prohibit any French phrases from becoming current in this kingdom, when those of our own stamp are altogether as valuable.
語彙の純粋さを巡る問題の常として,借用語使用を批判する論客が人々の言語使用に影響を与えることは,ほとんどない.18世紀の場合も例外ではなく,彼らは苦言こそ呈したが,ほぼ効き目はなかったのである.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2016-11-17 Thu
■ #2761. 「言語的保守主義」再考 [language_myth][purism][linguistic_ideology]
「#2751. T. S. Eliot による英語の詩の特性と豊かさ」 ([2016-11-07-1]) で引用した宇野によると,保守主義の源流はアイルランド生まれの英国ホイッグ党の政治家 Edmund Burke (1729--97) に遡る.「保守主義」という用語を Burke の用いた意味で用いるならば,以下のことを踏まえる必要があるという(宇野,p. 13).
(1) 保守すべきは具体的な制度や慣習であり,
(2) そのような制度や慣習は歴史のなかで培われたものであることを忘れてはならず,
(3) 大切なのは自由を維持することであり,
(4) 民主化を前提にしつつ,秩序ある漸進的改革が目指される
Burke は政治における「保守主義」のことを語っているわけだが,これを言語における「保守主義」に応用するならば,どのようなことになるだろうか.というのは,「#1318. 言語において保守的とは何か?」 ([2012-12-05-1]),「#1304. アメリカ英語の「保守性」」 ([2012-11-21-1]) で論じたように,言語における保守性という概念は,様々な問題を含んでいるからだ.
もっとも,政治上の用語を言語の話題にそのまま当てはめようとしても無理が生じるだろうとは予想できる.(1) の「制度や慣習」というのは,言語でいえば文法,発音,語法などの具体的な言語項目といってよさそうであり,(2) の「歴史の中で培われた」という表現もそのまま言語に当てはめることができる.しかし,(3) 「自由を維持する」とは,言語において何に相当するのだろうか.言語使用者による個々の表現選択の自由のことだろうか,あるいは絶対的な規範主義の忌避というようなことを意味するのだろうか.(4) の「民主化」も,言語に当てはめると,その意味が分からなくなる.これについては,別途「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]),「#2359. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (3)」 ([2015-10-12-1]) で考えてきた通りである.(4) の「秩序」や「改革」も,言語の場合には何に相当するのか判然としない.
おそらく「言語的保守主義」とは「政治的保守主義の言語的側面」と理解しておくのがよいのだろう.つまり,言語体系そのものに関する話題ではなく,言語についての政治的信条に関する話題なのだろう.その意味で,「言語的保守主義」とは,もう1つの言語イデオロギー (linguistic_ideology) にすぎないのかもしれない (see 「#2163. 言語イデオロギー」 ([2015-03-30-1])) .
・ 宇野 重規 『保守主義とは何か 反フランス革命から現代日本まで』 中央公論新社〈中公新書〉,2016年.
2016-08-12 Fri
■ #2664. 「オープン借用」と「むっつり借用」 (2) [borrowing][loan_word][semantic_borrowing][loan_translation][contact][purism]
昨日の記事 ([2016-08-11-1]) で導入した「オープン借用」と「むっつり借用」の対立は,Haugen の用語である importation と substitution の対立に換言される.「#901. 借用の分類」 ([2011-10-15-1]) でみたように,importation とは借用元の形式をおよそそのまま自言語に取り込むことであり,substitution とは借用元の形式に対応する自言語の形式を代用することである.しかし,借用 (borrowing) と呼ばれるからには,必ず相手言語の記号の意味は得ている.その点では,オープン借用もむっつり借用も異なるところがない.
さて,この2種類の借用方法の対立を念頭に,語彙借用の比較的多いといわれる英語や日本語などの言語と,比較的少ないといわれるアイスランド語やチェコ語などの言語の差について考えてみよう.これらの言語の語彙を比較すると,なるほど,例えば英語には形態的に他言語に由来するものが多く,アイスランド語にはそのようなものが少ないことは確かである.オープン借用の多寡という点に限れば,英語は借用が多く,アイスランド語は借用が少ないという結論になる.しかし,むっつり借用を調査するとどうだろうか.もしかすると,アイスランド語は案外多く(むっつり)借用している可能性があるのではないか.むっつり借用は,表面上,借用であることが分かりにくいという特徴があるため,詳しく語源調査してみないとはっきりしたことが言えないが,その可能性は十分にある.「#903. 借用の多い言語と少ない言語」 ([2011-10-17-1]) で触れたように,「例えば借用の多いと言われる英語と少ないと言われるアイスランド語の差は,実のところ,借用の多寡そのものの差ではなく,2つの借用の方法 (importation and substitution) の比率の差である可能性があることにな」り,「両方法による借用を加え合わせたものをその言語の借用の量と考えるのであれば,一般に言われているほど諸言語間に著しい借用の多寡はないのかもしれない」とも言えるかもしれない.ひょっとすると,あらゆる言語が,スケベの種類こそ異なれ,結局のところ結構スケベ(借用好き)なのではないか.言語間にスケベ(借用好き)の程度の差がまったくないとまでは言わないが.
さらに,2種類の借用方法という観点から,他言語からの借用を嫌う言語的純粋主義 (purism) について考えてみたい.英語史にも日本語史にも,純粋主義者が他言語からの語彙借用を声高に批判する時代があった.「古き良き英語を守れ」「美しい本来の日本語を復活させよ」などと叫びながら,洪水にように迫り来る外来語に抵抗することが,歴史のなかで1度となく繰り返された.しかし,そのような純粋主義者が抵抗していたのはオープン借用に対してであり,実は彼ら自身が往々にしてむっつり借用を実践していた.現代日本語の状況で喩えれば,純粋主義の立場から「ワーキンググループ」と言わずに「作業部会」と言うべしという人がいたとすると,その人は英語の working group という記号の signifiant の借り入れにこそ抵抗しているものの,signifié については無批判に受け入れていることになる.同じスケベなら目に見えるスケベがよいという意見もあれば,同じスケベでも節度を保った目立たない立居振舞が肝要であるという意見もあろう.言語上の借用とスケベとはつくづく似ていると思う.
純粋主義と語彙借用については,「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]),「#1545. "lexical cleansing"」 ([2013-07-20-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1])),「#2068. 言語への忠誠」 ([2014-12-25-1]),「#2069. 言語への忠誠,言語交替,借用方法」 ([2014-12-26-1]),「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]),「#2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか?」 ([2016-02-09-1]) などを参照.
・ Haugen, Einar. "The Analysis of Linguistic Borrowing." Language 26 (1950): 210--31.
2016-02-09 Tue
■ #2479. 初期近代英語の語彙借用に対する反動としての言語純粋主義はどこまで本気だったか? [purism][lexicology][borrowing][emode][renaissance][inkhorn_term][cheke][aureate_diction]
「#1408. インク壺語論争」 ([2013-03-05-1]) ,「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) などの記事で,初期近代英語の大量語彙借用の反動としての言語純粋主義 (purism) に触れた.確かに純粋主義者として Sir John Cheke (1514--57), Roger Ascham (1515?--68), Sir Thomas Chaloner, Thomas Wilson (1528?--81) などの個性の名前が挙がるが,Görlach (163--64) は,英国ルネサンスにおける反動的純粋主義については過大評価されてきたという見解を示している.彼らとて必要な語彙は借用せざるを得ず,実際に借用したのであり,あくまでラテン語やギリシア語の語彙の無駄な借用や濫用を戒めたのである,と.少々長いが,おもしろい議論なので,そのまま引用しよう.
Purism, understood as resistance to foreign words and as awareness of the possibilities of the vernacular, presupposes a certain level of standardization of, and confidence in, the native tongue. It is no surprise that puristic tendencies are unrecorded before the end of the Middle Ages --- wherever native expressions were coined to replace foreign terms, they served a different purpose to help the uneducated understand better, especially sermons and biblical paraphrase. Tyndale's striving for the proper English expression was still motivated by the desire to enable the ploughboy to understand more of the Bible than the learned bishops.
A puristic reaction was, then, provoked by fashionable eloquence, as is evident from aspects of fifteenth-century aureate diction and sixteenth-century inkhornism . . . . The humanists had rediscovered a classical form of Latin instituted by Roman writers who fought against Greek technical terms as well as fashionable Hellenization, but who could not do without terminologies for the disciplines dominated by Greek traditions. Ascham, Wilson and Cheke (all counted among the 'purists' in a loose application of the term) behaved exactly as Cicero had done: they wrote in the vernacular (no obvious choice around 1530--50), avoided fashionable loanwords and fanciful, rare expressions, but did not object to the borrowing of necessary terms.
Cheke was as inconsistent a 'purist' as he was a reformer of EModE spelling . . . . On the one hand, he went further than most of his contemporaries in his efforts to preserve the English language "vnmixt and vnmangeled" . . ., but on the other hand he also borrowed beyond what was necessary and what his own tenets seemed to allow. (The problem of untranslatable terms, as in his renderings of biblical antiquities, was solved by marginal explanations.) The practice (and historical ineffectiveness) of other 'purists', too, who attempted translations of Latin terminologies --- Golding for medicine, Lever for philosophy and Puttenham for rhetoric . . . --- demonstrates that there was no such rigorous puristic movement in sixteenth-century England as there was in many other countries during the eighteenth and nineteenth centuries. The purists' position and their influence on EModE has often been exaggerated; it is more to the point to speak of "different degrees of Latinity" . . . .
Görlach の見解は,通説とは異なる独自の指摘であり,斬新だ.中英語期のフランス借用語批判や,日本語における明治期のチンプン漢語及び戦後のカタカナ語の流入との関係で指摘される言語純粋主義も,この視点から見直してみるのもおもしろいだろう (see 「#2147. 中英語期のフランス借用語批判」 ([2015-03-14-1]),「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]),「#1999. Chuo Online の記事「カタカナ語の氾濫問題を立体的に視る」」 ([2014-10-17-1])).
・ Görlach, Manfred. Introduction to Early Modern English. Cambridge: CUP, 1991.
2015-10-12 Mon
■ #2359. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (3) [history][loan_word][lexicology][borrowing][linguistic_imperialism][language_myth][purism]
標題と関連して,「#134. 英語が民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2009-09-08-1]),「#1366. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由」 ([2013-01-22-1]),「#1845. 英語が非民主的な言語と呼ばれる理由 (2)」 ([2014-05-16-1]) で様々な見解を紹介してきた.今回は,主として英語が歴史的に他言語から多くの語彙を借用してきた事実に照らして,英語の民主性・非民主性について考えてみたい.
英語が多くの言語からおびただしい語彙を借用してきたことは,言語的純粋主義 (purism) の立場からの批判が皆無ではないにせよ,普通は好意的に語られる.英語の語彙借用好きは,ほとんどすべての英語史記述でも強調される特徴であり,これを指して "cosmopolitan vocabulary" などと持ち上げられることが多い.続けて,英語,そして英語国民は,柔軟にして鷹揚,外に対して開かれており,多様性を重んじる伝統を有すると解釈されることが多い.歴史的に英語国では言語を統制するアカデミーが設立されにくかったこともこの肯定的な議論に一役買っているだろう.また,もう1つの国際語であるフランス語が上記の点で英語と反対の特徴を示すことからも,相対的に英語の「民主性」が浮き彫りになる.
しかし,英語の民主性に関する肯定的なイメージはそれ自体が作られたイメージであり,語彙借用のある側面を反映していないという.Bailey (91) によれば,植民地帝国主義時代の英国人は,その人種的優越感ゆえに,諸言語からの語彙をやみくもに受け入れたわけではなく,むしろすでに他のヨーロッパ人が受け入れていた語彙についてのみ自らの言語へ受け入れることを許したという.これが事実だとすれば,英語(国民)はむしろ非民主的であると言えるかもしれない.
Far from its conventional image as a language congenial to borrowing from remote languages, English displays a tendency to accept exotic loanwords mainly when they have first been adopted by other European languages or when presented with marginal social practices or trivial objects. Anglophones who have ventured abroad have done so confident of the superiority of their culture and persuaded of their capacity for adaptation, usually without accepting the obligations of adapting. Extensive linguistic borrowing and language mixing arise only when there is some degree of equality between or among languages (and their speakers) in a multilingual setting. For the English abroad, this sense of equality was rare. Whether it is a language more "friendly to change than other languages" has hardly been questioned; those who embrace the language are convinced that English is a capacious, cosmopolitan language superior to all others.
Bailey によれば,「開かれた民主的な英語」のイメージは,それ自体が植民地主義の産物であり,植民地主義時代の語彙借用の事実に反するということになる.
ただし,Bailey の植民地主義と語彙借用の議論は,主として近代以降の歴史に関する議論であり,英語が同じくらい頻繁に語彙借用を行ってきたそれ以前の時代の議論には直接触れていないことに注意すべきだろう.中英語以前は,英語はラテン語やフランス語から多くの語彙を借り入れなければならない,社会的に下位の言語だったのであり,民主的も非民主的も論ずるまでもない言語だったのだから.
・ Bailey, R. Images of English. Ann Arbor: U of Michigan P, 1991.
2015-03-14 Sat
■ #2147. 中英語期のフランス借用語批判 [purism][loan_word][french][inkhorn_term][me][lexicology]
16世紀には,ラテン借用語をはじめとしてロマンス諸語などからの借用語がおびただしく英語へ流入した(「#1410. インク壺語批判と本来語回帰」 ([2013-03-07-1]) や「#1411. 初期近代英語に入った "oversea language"」 ([2013-03-08-1]) を参照).日本語でも明治以降,大量の漢語が作られ,昭和以降は無数のカタカナ語が流入した(「#1617. 日本語における外来語の氾濫」 ([2013-09-30-1]) 及び「#1630. インク壺語,カタカナ語,チンプン漢語」 ([2013-10-13-1]) を参照).これらの時代の各々において,純粋主義 (purism) の立場からの借用語批判が聞かれた.借用語をむやみやたらに使用するのは控えて,本来語をもっと多く使うべし,という議論である.
英語史においてあまり聞かないのは,中英語期に怒濤のように押し寄せたフランス借用語に対する批判である.「#117. フランス借用語の年代別分布」 ([2009-08-22-1]) で見たとおり,英語はノルマン・コンクェスト後の数世紀間で,歴史上初めて数千語という規模での大量語彙借用を経験してきたが,そのフランス借用語への批判はなかったのだろうか.
確かにルネサンス期のインク壺語批判ほどは目立たないが,中英語におけるフランス借用語批判がまったくなかったわけではない.Ranulph Higden (c. 1280--1364) によるラテン語の Polychronicon を1387年に英訳した John of Trevisa (1326--1402) は,ある一節で,古ノルド語とともにフランス語からの借用語の無分別な使用について苦情を呈している.Crystal (186) からの引用を再現しよう.
by commyxstion and mellyng, furst wiþ Danes and afterward wiþ Normans, in menye þe contray longage ys apeyred, and som vseþ strange wlaffyng, chyteryng, harryng, and garryng grisbittyng.
同様に,Richard Rolle of Hampole (1290?--1349.) による Psalter (a1350) でも,"seke no strange Inglis" (見知らぬ英語は使わない)とフランス借用語に対して暗に不快感を示しているし,15世紀に Polychronicon を英訳した Osbern Bokenham (1393?--1447?) も,フランス語が英語を野蛮にしたと非難している (Crystal 186) .しかし,彼らとて,自らの著書のなかで,洗練されたフランス借用語を用いていたことはいうまでもない.
このように中英語期のフランス借用語への純粋主義的な非難はいくつか確認されるが,後世の激しいインク壺語批判に比べれば単発的であり,特に大きな潮流を形成しなかったようだ.英語自体がまだ一国の言語としておぼつかない地位にあって,英語の本来語への思慕や借用語の嫌悪という純粋主義的な態度が世の注目を浴びるには,まだ時代が早かったものと思われる.それでも,この中英語期の早熟な純粋主義的批判は,後世の苛烈な批判の前段階として,確かに英語史上に位置づけられるものではあるだろう.
・ Crystal, David. The Stories of English. London: Penguin, 2005.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow