2024-12-21 Sat
■ #5717. 高橋真理子先生との2回の heldio 対談 --- 『World Englishes 入門』の第8章「ヨーロッパと中東の英語」 [voicy][heldio][notice][world_englishes][we_nyumon][european_english][review][lingua_franca]
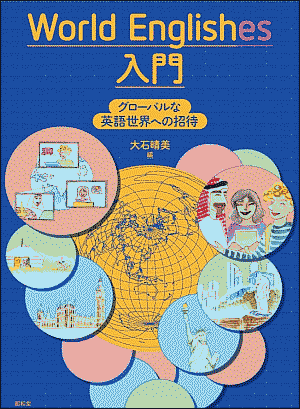
先日,高橋真理子先生(関西学院大学)と Voicy heldio で2度にわたり対談させていただきました.昨年昭和堂より出版されている『World Englishes 入門』より,高橋先生の執筆された第8章「ヨーロッパと中東の英語」について,著者じきじきにお話をうかがうという回でした.
・ 「#1294. 著者と語る『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年) --- 高橋真理子先生とのヨーロッパと中東の英語をめぐる対談」(2024年12月14日配信)
・ 「#1300. 高橋真理子先生とのアフタートーク --- 『World Englishes 入門』(昭和堂,2023年)の第8章「ヨーロッパと中東の英語」をめぐって」(2024年12月20日配信)
今回は,知っているようで意外と知らないヨーロッパと中東の英語事情について,本書第8章の記述を土台にしつつ,高橋先生にご解説いただきました.この広い地域には多様な言語,文化,民族が分布しています.そのなかで英語がいかにリンガフランカ (lingua_franca) として機能しているのか,社会的にどのように位置づけられているのか,いかなる英語変種が用いられているのか.様々な疑問が生じます.さらに,なぜヨーロッパと中東が,同じ章で扱われているのでしょうか.アフタートークを含め,今回の対談では,このような質問にお答えいただきました.
ぜひ,これまでの『World Englishes 入門』関連の hellog 記事や heldio 対談回へ,we_nyumon を通じてアクセスしていただければと思います.
最後に,アフタートークでも触れましたが,高橋先生の最近のご単著にもご注目ください.『アジア英語における口語表現の比較』(ナカニシヤ出版,2023年)です.高橋先生,このたびは対談のお時間を割いていただきまして,ありがとうございました!
・ 大石 晴美(編) 『World Englishes 入門』 昭和堂,2023年.
・ 高橋 真理子 『アジア英語における口語表現の比較』 ナカニシヤ出版,2023年.
2024-10-29 Tue
■ #5664. 初期近代のジェスチャーへの関心の高まり [gesture][emode][gesture][paralinguistics][history_of_linguistics][latin][lingua_franca][vernacular]
西洋の初期近代では普遍言語や普遍文字への関心が高まったが,同様の趣旨としてジェスチャー (gesture) へも関心が寄せられるようになった.Kendon (73) によれば,その背景は以下の通り.
The expansion of contacts between Europeans and peoples of other lands, especially in the New World, led to an enhanced awareness of the diversity of spoken languages, and because explorers and missionaries had reported successful communication by gesture, the idea rose that gesture could form the basis of a universal language. The idea of a universal language that could overcome the divisions between peoples brought about by differences in spoken languages was longstanding. However, interest in it became widespread, especially in the sixteenth and seventeenth centuries, in part because, as Latin began to be replaced with vernaculars, the need for a new lingua franca was felt. There were philosophical and political reasons as well, and there developed the idea that a language should be created whose meanings were fixed, which could be written or expressed in forms that would be comprehensible, regardless of a person's spoken language. The idea that humans share a 'universal language of the hands,' mentioned by Quintilian, was taken up afresh by Bonifaccio. In his L'arte dei cenni ('The art of signs') of 1616 (perhaps the first book ever published to be devoted entirely to bodily expression) . . . , he hoped that his promotion of the 'mute eloquence' of bodily signs would contribute to the restoration of the natural language of the body, given to all mankind by God, and so overcome the divisions created by the artificialities of spoken languages.
西洋の初期近代におけるジェスチャーへの関心は,新世界での見知らぬ諸言語との接触,リンガフランカとしてのラテン語の衰退,哲学的・政治的な観点からの普遍言語への関心,「自然な肉体言語」の再評価などに裏付けられていたという解説だ.関連して「#5128. 17世紀の普遍文字への関心はラテン語の威信の衰退が一因」 ([2023-05-12-1]) の議論も思い出される.
・ Kendon, Adam. "History of the Study of Gesture." Chapter 3 of The Oxford Handbook of the History of Linguistics. Ed. Keith Allan. Oxford: OUP, 2013. 71--89.
2024-05-23 Thu
■ #5505. 古代ギリシアの方言観 [greek][dialect][dialectology][hellenic][koine][lingua_franca]
よく知られているように,古代ギリシア人はギリシア語以外の言語・民族については「バルバロイ」と蔑視する姿勢を示したが,ギリシア語諸方言についてはどのように見ていたのだろうか.Robins (15) に,古代ギリシアの他言語に対する態度やギリシア語内部の諸方言への眼差しを解説している箇所がある.特に後者を扱っている箇所を引用しよう.
. . . . the Greek designation of alien speakers as bárbaroi (βάρβαροι, whence our word barbarian), i.e. people who speak a language other than Greek, is probably indicative of their attitude.
Quite different was the Greek awareness of their own dialectal divisions. The Greek language in Antiquity was more markedly divided into fairly sharply differentiated dialects than many other languages were. This was due both to the settlement of the Greek-speaking areas by successive waves of invaders, and to the separation into relatively small and independent communities that the mountainous configuration of much of the Greek mainland and the scattered islands of the adjoining seas forced on them. But that these dialects were dialects of a single language and that the possession of this language united the Greeks as a whole people, despite the almost incessant wars waged between the different 'city states' of the Greek world, is attested by at least one historian: Herodotus, in his account of the major achievement of a temporarily united Greece against the invading Persians at the beginning of the fifth century B.C., puts into the mouths of the Greek delegates a statement that among the bonds of unity among the Greeks in resisting the barbarians was 'the whole Greek community, being of one blood and one tongue'.
引用最後のヘロドトス (8.114.2) への言及が興味深い.おそらく古代ギリシア人たちは明確に分かれていたギリシア語諸方言の存在を互いに認識していた.そして,それらを異なる方言とこそ捉えてはいたが,異なる言語とは捉えていなかった.諸方言からなるギリシア語は,ギリシア民族を(ペルシアに対抗して)まとめ上げる役割を果たしていたということだ.
考えてみれば,ギリシア語は dialect という単語を生み出した母体であり,諸方言間を平準化した共通語 (koine) を誇った言語でもあった.関連して,以下の記事も参照されたい.
・ 「#1454. ギリシャ語派(印欧語族)」 ([2013-04-20-1])
・ 「#2752. dialect という用語について」 ([2016-11-08-1])
・ 「#1671. dialect contact, dialect mixture, dialect levelling, koineization」 ([2013-11-23-1])
・ 「#1391. lingua franca (4)」 ([2013-02-16-1])
・ Robins, R. H. A Short History of Linguistics. 4th ed. Longman: London and New York, 1997.
2023-03-05 Sun
■ #5060. 講座「英語の歴史と世界英語」のシリーズが終了ました [asacul][world_englishes][elf][lingua_franca][link][voicy][heldio]
昨日3月4日,朝日カルチャーセンター新宿教室にて,シリーズ講座「英語の歴史と世界英語」の最終回となる「21世紀の英語のゆくえ」を対面・オンラインでお話ししました.これにて,昨年6月に始まった全4回にわたるシリーズが終了となりました.毎回質問を寄せ議論を盛り上げてくださったご出席の方々には,感謝申し上げます.ありがとうございました.
改めてシリーズ全体の趣旨を振り返ります.以下を掲げていました.
英語は現代世界において最も有力な言語です.しかし,英語の世界的拡大の結果,通常私たちが学んでいる「標準英語」以外にも様々な英語が発達しており,近年はその総体を「世界(諸)英語」 "World Englishes" と呼ぶことが増えてきました.
この全4回のシリーズでは,世界英語とは何か,英語はいかにしてここまで拡大したのか,英語の方言の起源はどこにあるのか,そして今後の英語はどうなっていくのかといった問題に英語の歴史という視点から迫ります.
目下,世界は急速に変化しています.このような現代世界において人と人をつなぐリンガ・フランカである英語と,私たちは今後どのように付き合っていけばよいのか.英語史の観点から世界英語に迫った今回のシリーズ講座は,この問題を考える糧となったはずです.
世界英語 (world_englishes) については,本ブログや Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも関連する話題を多くお届けてしてきました.以下では,とりわけ講座と併走しつつ提供してきた記事・放送回を列挙します.復習などに役立てていただければ幸いです.
なお,来年度は同じ朝日カルチャーセンター新宿教室にて新シリーズ「文字と綴字の英語史」を開始します.こちらについての詳細は近日中に改めてご案内致します.どうぞお楽しみに.
[ 第1回 世界英語入門 (2022年6月11日)]
・ hellog 「#4775. 講座「英語の歴史と世界英語 --- 世界英語入門」のシリーズが始まります」 ([2022-05-24-1])
・ heldio 「#356. 世界英語入門 --- 朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが始まります」
・ heldio 「#378. 朝カルで「世界英語入門」を開講しました!」
[ 第2回 いかにして英語は拡大したのか (2022年8月6日)]
・ hellog 「#4813. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」のご案内」 ([2022-07-01-1])
・ heldio 「#393. 朝カル講座の第2回「英語の歴史と世界英語 --- いかにして英語は拡大したのか」」
[ 第3回 英米の英語方言 (2022年10月1日)]
・ hellog 「#4875. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」のご案内」 ([2022-09-01-1])
・ heldio 「#454. 朝カル講座の第3回「英語の歴史と世界英語 --- 英米の英語方言」」
[ 第4回 21世紀の英語のゆくえ (2022年3月4日)]
・ hellog 「#4954. 朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」のご案内」 ([2022-11-19-1])
・ hellog 「#5048. heldio で朝カル講座の第4回(最終回)「英語の歴史と世界英語 --- 21世紀の英語のゆくえ」の予告編をお届けしています」 ([2023-02-21-1])
・ heldio 「#630. 世界英語の ENL, ESL, EFL モデルはもう古い? --- 3月4日,朝カル新宿教室で「英語の歴史と世界英語」のシリーズが完結します」
2022-06-23 Thu
■ #4805. "World Englishes" と "ELF" の共存を目指して [world_englishes][elf][lingua_franca][sociolinguistics]
現代世界の英語事情を巡る論文集 English in the World を読み進めているが,関連する様々な議論への入り口となる論考の結論において Seidlhofer (48) が "World Englishes" と "ELF" の相互関係について,対立ではなく共存であるべきだと主張している.
Conclusion: Live and let live
This volume is intended as a contribution to an exchange of views and a constructive debate between proponents of World Englishes, or nativized varieties of English, and proponents of EIL, or ELF. It seems to me that each group (although the 'groups' themselves are of course abstractions and constructions) can benefit from learning more about what is happening in the field of 'English in the World' as a whole, and again, I am hopeful that this collection will make this possible. There are certainly important differences between World Englishes and EIL --- simply by virtue of the very different sociohistorical and sociocultural settings in which these Englishes have arisen and are being used. But acknowledging and understanding these differences does not have to entail the setting up of what are actually false dichotomies, such as WE vs EIL, pluricentric vs monolithic, tolerance of diversity vs prescribed rules. It is perfectly clear that the functions of language are manifold in all societies, and that any language serves the purposes of identification and communication. Identification with a primary culture on the one hand and communication across cultures on the other are equally worthwhile endeavours, and there is no reason why they should not happily coexist and enrich each other.
1つは英語を諸英語へと分裂させていく遠心力としての "identification" 作用.もう1つは英語をまとめあげていく求心力としての "communication" 作用.ここで Seidlhofer は,英語という言語に認められる2つの相反する作用を指摘し,そのバランスを取ることの重要性を主張している.これは私自身が抱いている英語観や言語観とも一致する.関連して以下の記事を参照.
・ 「#1360. 21世紀,多様性の許容は英語をバラバラにするか?」 ([2013-01-16-1])
・ 「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1])
・ 「#2073. 現代の言語変種に作用する求心力と遠心力」 ([2014-12-30-1])
・ 「#2922. 他の社会的差別のすりかえとしての言語差別」 ([2017-04-27-1])
・ 「#2989. 英語が一枚岩ではないのは過去も現在も同じ」 ([2017-07-03-1])
・ 「#3671. オーストラリア50ドル札に responsibility のスペリングミス (1)」 ([2019-05-16-1])
・ 「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1])
・ Seidlhofer, Barbara. "English as a Lingua Franca in the Expanding Circle: What It Isn't." English in the World: Global Rules, Global Roles. Ed. Rani Rubdy and Mario Saraceni. London: Continuum, 2006. 40--50.
2022-06-18 Sat
■ #4800. Lingua Franca Core への批判 [world_englishes][lingua_franca][elf][lfc][elt][standardisation][language_planning]
昨日の記事「#4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core"」 ([2022-06-17-1]) で Lingua Franca Core (LFC) を導入した.LFC が提示された背景には,世界英語 (world_englishes) の時代にあって,世界の英語学習者,とりわけ EFL の学習者は,伝統的な英米標準変種やその他の世界各地で標準的とみなされている変種を習得するのではなく,ELF (= English as a Lingua Franca) や EIL (= English as an International Language) と称される変種を学習のターゲットとするのがよいのではないかという英語教育観が見え隠れする.世界の英語話者人口のおそらく半分以上は EFL 話者であり,その点では LFC を尊重する姿勢は EFL 学習者にとって「民主的」に見えるかもしれない.
しかし,LFC に対して批判的な意見もある.LFC も,伝統的な英米標準変種と同様に,単なる標準であるにとどまらず,規範となっていく恐れはないかと.規範の首を古いものから新しいものへとすげ替えるだけ,ということにならないだろうか.本当に民主的であろうとするならば,そもそも言語学者や教育者が人為的に「コア」として提示するということは矛盾をはらんだ営みではないか,等々.
Tomlinson (146) は,LFC のようなものを制定し「世界標準英語」の方向づけを行なおうとする行為は "arrogant" であると警鐘を鳴らしている.
But, are we not being rather arrogant in assuming that it is we as applied linguists, language planners, curriculum designers, teachers and materials developers who will determine the characteristics of a World Standard English? Is it not the users of English as a global language who will determine these characteristics as a result of negotiating interaction with each other? We can facilitate the process by making sure that our curricula, our methodology and our examinations do not impose unnecessary and unrealistic standards of correctness on our international learners, and by providing input and guiding output relevant to their needs and wants. But ultimately it is they and not us who will decide. To think otherwise is to be guilty of neo-colonist conceit and to ignore all that we know about how languages develop over time.
標準か規範かを巡るややこしい問題である.関連して「#1246. 英語の標準化と規範主義の関係」 ([2012-09-24-1]) を参照.
・ Tomlinson, Brian. "A Multi-dimensional Approach to Teaching English for the World" English in the World: Global Rules, Global Roles. Ed. Rani Rubdy and Mario Saraceni. London: Continuum, 2006. 130--50.
2022-06-17 Fri
■ #4799. Jenkins による "The Lingua Franca Core" [world_englishes][lingua_franca][elf][lfc][epenthesis]
昨日の記事「#4798. ENL での言語変化は「革新」で,ESL/EFL では「間違い」?」 ([2022-06-16-1]) で引用した Jenkins (37) は,ELF (= English as a Lingua Franca) の核となる言語特徴(発音)を一覧している.これは,調査の結果,様々な英語母語変種に認められた特徴であり,相互理解のための ELF 使用においてきわめて重要な項目ということになる.
The Lingua Franca Core (LFC)
1. Consonant sounds except for substitutions of 'th' and of dark /l/
2. Aspiration after world-initial /p/, /t/ and /k/
3. Avoidance of consonant deletion (as opposed to epenthesis) in consonant clusters.
4. Vowel length distinctions
5. Nuclear (Tonic) stress production and placement within word groups (tone units)
一方,次の特徴は EFL において核とはならないものである (Jenkins 37) .
Non-core features:
1. Certain consonants (see Lingua Franca Core no. 1)
2. Vowel quality
3. Weak forms
4. Features of connected speech such as elision and assimilation
5. Word stress
6. Pitch movement on the nuclear syllable (tone)
7. Stress-timed rhythm
日本語母語話者に典型的にみられる英語発音の例を上記の「コア」に当てはめてみると,read と lead はともに「リード」と発音してしまいがちだが,語頭の /r/ と /l/ の区別は Core no. 1 に含まれるので,コア特徴としてぜひとも発音し分ける必要がある,ということになる.一方,語末に母音が挿入 (epenthesis) されて /ri:d/ ではなく /ri:do/ と発音されたとしても,コア特徴には含まれないため,許容され得る (cf. Core no. 3) .
・ Jenkins, Jennifer. "Global Intelligibility and Local Diversity: Possibility or Paradox?" English in the World: Global Rules, Global Roles. Ed. Rani Rubdy and Mario Saraceni. London: Continuum, 2006. 32--39.
2022-06-13 Mon
■ #4795. 標準英語,世界英語,ELF の三すくみモデル [standardisation][world_englishes][elf][lingua_franca][elt][model_of_englishes]
昨日の記事「#4794. 英語の標準化 vs 英語の世界諸変種化」 ([2022-06-12-1]) で取り上げたように Standard English か World Englishes かという対立の根は深い.とりわけ英語教育においては教育・学習のターゲットを何にするかという問題に直結するため,避けては通れない議論である.Rubdy and Saraceni は,この2つの対立に EIL/EFL という第3の要素を投入した三すくみモデルを考え,序章にて次のように指摘している (6) .
Towards simplifications: the teaching and learning of English
While an exhaustive description of the use of English is a futile pursuit, with regard to the teaching and learning of English in the classroom such complexities have necessarily to be reduced to manageable models. The language of the classroom tends to be rather static and disregardful of variation in style and register and, more conspicuously, of regional variation. One of the main issues in the pedagogy of English is indeed the choice of an appropriate model for the teaching of English as a foreign or second language. Here 'model' refers to regional variation, which is the main focus in the whole volume. In this sense, the choice is seen as lying between three principal 'rival' systems: Standard English (usually Standard British or Standard American English), World Englishes, and EIL/ELF (English as an International Language/English as a Lingua Franca).
ここでライバルとなるモデルとして言及されている Standard English, World Englishes, ELF は,それぞれ緩く ENL, ESL, EFL 志向の英語観に対応していると考えられる(cf. 「#173. ENL, ESL, EFL の話者人口」 ([2009-10-17-1])).
Standard English を中心に据える英語教育は,ENL 話者(とりわけ英米英語の話者)にとって概ね有利だろう.歴史的に威信が付されてきた変種でもあり「ブランド力」は抜群である,しかし,英語話者全体のなかで,これを母語・母方言とする話者は少数派であることに注意したい.
World Englishes は,主に世界各地の非英語母語話者,とりわけ ESL 話者が日常的に用いている変種を含めた英語変種の総体である.ESL 話者は英語話者人口に占める割合が大きく,今後の世界における英語使用のあり方にも重要な影響を及ぼすだろうと予想されている.昨今「World Englishes 現象」が注目されている理由も,ここにある.
ELF は,非英語母語話者,とりわけ EFL 話者の立場に配慮した英語観である.英語は国際コミュニケーションのための道具であるという,実用的,機能的な側面を重視した英語の捉え方だ.ビジネス等の領域で,非英語母語話者どうしが英語を用いてコミュニケーションを取る状況を念頭に置いている.理想的には,世界のどの地域とも直接的に結びついておらず,既存の個々の変種がもつ独自の言語項目からも免れているという中立的な変種である.EFL 話者は英語話者全体のなかに占める割合が最も大きく,この層に訴えかける変種として ELF が注目されているというわけだ.しかし,ELF は理念先行というきらいがあり,その実態は何なのか,人為的に策定すべきものなのかどうか等の問題がある.
日本の英語教育は,伝統的には明らかに Standard English 偏重だった.近年,様々な英語を許容するという World Englishes 的な見方も現われてきたとはいえ,目立っているとは言いがたい.一方,英語教育の目的としては ELF に肩入れするようになってきているとは言えるだろう.
今回の「三すくみ」モデルは,3つの英語観のいずれを採用するのかという三者択一の問題ではないように思われる.むしろ,3種類を各々どれくらいの割合でブレンドするかという問題なのではないか.
・ Rubdy, Rani and Mario Saraceni, eds. English in the World: Global Rules, Global Roles. London: Continuum, 2006.
2021-11-04 Thu
■ #4574. ELF の2つの特徴 --- 歴史上の他のリンガ・フランカと比較して [elf][lingua_franca][history][latin]
英語は現代世界で最も有力なリンガ・フランカ (lingua_franca) であり,ELF (= English as a Lingua Franca; cf. elf) と呼ばれている.人類史上,その時代その時代で「世界」として捉えられていた領域において,異なる言語を母語話者とする人々の間で共通語として用いられてきた有力なリンガ・フランカが存在してきた.例えば,サンスクリット語,ギリシア語,ラテン語,アラビア語,ポルトガル語,フランス語,中国語などはいずれも各自の世界のなかでリンガ・フランカとして機能してきた歴史をもつ.
21世紀の現代世界において(これは正真正銘の地球規模の「世界」である)においては,英語がリンガ・フランカの役割を担っているわけだが,歴代のリンガ・フランカと比べて異なる点はあるのだろうか.ELF の際だった特徴は何なのだろうか.Jenkins (549) は,(1) 規模の大きさと,(2) 大多数の英語話者が外国語としての英語の話者,換言すれば Kachru のいう "expanding circle" に属する人々であるという2点を挙げている (cf. 「#217. 英語話者の同心円モデル」 ([2009-11-30-1])) .
ENGLISH as a Lingua Franca (henceforth ELF) has much in common with other lingua francas (contact language used by people who do not share a first language) that have existed over many centuries. Languages such as Sanskrit, Greek, Latin, Arabic and Portuguese among others have all, at various times, served lingua franca functions, while English itself has been a lingua franca since the late 16th century, when the countries of the outer circle . . . were first colonised by the British. ELF differs from all the previous lingua francas, however, in terms of its scale. Because English has become so closely bound up with the phenomenon of globalization . . . , it is spoken by larger numbers of people across a far wider range of countries than is true of any other lingua franca past or present, including earlier manifestations of English. And the majority of these people, perhaps as many as two billion . . . , come from the countries of the expanding circle . . . . These are countries, particularly in mainland Europe, East Asia, and, to a lesser extent, Latin America, where English is neither a mother tongue nor a postcolonial language. So although ELF is used as a contact language both across and within all three of Kachru's circles, inner, outer, and expanding, it is above all an expanding circle phenomenon . . . .
考えてみれば2つとも自明の特徴のように思われるが,自明な点こそ忘れずに押さえておく必要がある.ELF の歴史上の意義は,史上最多の人口が関わっているということ,そして何よりも "expanding circle phenomenon" であるということだ.
リンガ・フランカという用語それ自体については,「#1086. lingua franca (1)」 ([2012-04-17-1]),「#1087. lingua franca (2)」 ([2012-04-18-1]),「#1088. lingua franca (3)」 ([2012-04-19-1]) を参照.
また,リンガ・フランカとして英語としばしば比較されるラテン語については,「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]),「#4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか?」 ([2021-08-27-1]) を参照.
・ Jenkins, Jennifer. "English as a Lingua Franca in the Expanding Circle." Chapter 27 of The Oxford Handbook of World Englishes. Ed. by Markku Filppula, Juhani Klemola, and Devyani Sharma. New York: OUP, 2017. 549--66.
2021-08-27 Fri
■ #4505. 「世界語」としてのラテン語と英語とで,何が同じで何が異なるか? [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes][diglossia]
昨日の記事「#4504. ラテン語の来し方と英語の行く末」 ([2021-08-26-1]) に引き続き,「世界語」としての両者がたどってきた歴史を比べることにより英語の未来を占うことができるだろうか,という問題について.
ラテン語と英語をめぐる歴史社会言語学的な状況について,共通点と相違点を思いつくままにブレストしてみた.
[ 共通点 ]
・ 話し言葉としては様々な(しばしば互いに通じない)言語変種へ分裂したが,書き言葉としては1つの標準的変種におよそ収束している
・ 潜在的に非標準変種も norm-producing の役割を果たし得る(近代国家においてロマンス諸語は各々規範をもつに至ったし,同じく各国家の「○○英語」が規範的となりつつある状況がある)
・ ラテン語は多言語のひしめくヨーロッパにあってリンガ・フランカとして機能した.英語も他言語のひしめく世界にあってリンガ・フランカとして機能している.
[ 相違点 ]
・ ラテン語は死語であり変化し得ないが,英語は現役の言語であり変化し続ける
・ ラテン語の規範は不変的・固定的だが,英語の規範は可変的・流動的
・ ラテン語は書き言葉と話し言葉の隔たりが大きく,前者を日常的に用いる人はいない(ダイグロシア的).しかし,英語については,標準英語話者に関する限りではあるが,書き言葉と話し言葉の隔たりは比較的小さく,前者に近い変種を日常的に用いる人もいる(非ダイグロシア的)
・ ラテン語は地理的にヨーロッパのみに閉じていたが,英語は世界を覆っている
・ ラテン語には中世以降母語話者がいなかったが,英語には母語話者がいる
・ ラテン語は学術・宗教を中心とした限られた(文化的程度の高い)分野において主として書き言葉として用いられたが,英語は分野においても媒体においても広く用いられる
・ ラテン語の規範を定めたのは使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々.英語の規範を定めたのも,18世紀を参照する限り,使用者人口の一部である社会的に高い階層の人々であり,その点では似ているといえるが,21世紀の英語の規範を作っている主体はおそらくかつてと異なるのではないか.一般の英語使用者が集団的に規範制定に関与しているのでは?
時代も状況も異なるので,当然のことながら相違点はもっと挙げることができる.例えば,関わってくる話者人口などを比較すれば,2桁も3桁も異なるだろう.一方,共通項をくくり出すには高度に抽象的な思考が必要で,そう簡単にはアイディアが浮かばない.皆さん,いかがでしょうか.
英語の未来を考える上で,英語史はさほど役に立たないと思っています.しかし,人間の言語の未来を考える上で,英語史は役に立つだろうと思って日々英語史の研究を続けています.
2021-08-26 Thu
■ #4504. ラテン語の来し方と英語の行く末 [future_of_english][latin][lingua_franca][history][world_englishes]
かつてヨーロッパではリンガ・フランカ (lingua_franca) としてラテン語が長らく栄華を誇ったが,やがて各地で様々なロマンス諸語へ分裂していき,近代期中に衰退するに至った.この歴史上の事実は,英語の未来を考える上で必ず参照されるポイントである.英語は現代世界でリンガ・フランカの役割を担うに至ったが,一方で諸英語変種 (World Englishes) へと分裂しているのも事実もあり,将来求心力を維持できるのだろうか,と議論される.ある論者はラテン語と同じ足跡をたどることは間違いないという予想を立て,別の論者はラテン語と英語では歴史的状況が異なり単純には比較できないとみる.
両言語の比較に基づいた議論をする場合,当然ながら,歴史的事実を正確につかんでおくことが重要である.しかし,とりわけラテン語に関して,大きな誤解が広まっているのではないか.ラテン語がロマンス諸語へ分裂したと表現する場合,前提とされているのは,ラテン語がそれ以前には一枚岩だったということである.ところが,話し言葉に関する限り,ラテン語はロマンス諸語へ分裂する以前から各地で地方方言が用いられていたのであり,ある意味では「ロマンス諸語への分裂」は常に起こっていたことになる.ラテン語が一枚岩であるというのは,あくまで書き言葉に関する言説なのである.McArthur (9--10) は,"The Latin fallacy" という1節でこの誤解に対して注意を促している.
Between a thousand and two thousand years ago the language of the Romans was certainly central in the development of the entities we now call 'the Romance languages'. In some important sense, Latin drifted among the Lusitani into 'Portuguese', among the Dacians into 'Romanian', among the Gauls and Franks into 'French', and so on. It is certainly seductive, therefore, to wonder whether American English might become simply 'American', and be, as Burchfield has suggested, an entirely distinct language in a century's time from British English.
There is only one problem. The language used as a communicative bond among the citizens of the Roman Empire was not the Latin recorded in the scrolls and codices of the time. The masses used 'popular' (or 'vulgar') Latin, and were apparently extremely diverse in their use of it, intermingled with a wide range of other vernaculars. The Romance languages derive, not from the gracious tongue of such literati as Cicero and Virgil, but from the multifarious usages of a population most of whom were illiterati.
'Classical' Latin had quite a different history from the people's Latin. It did not break up at all, but as a language standardized by manuscript evolved in a fairly stately fashion into the ecclesiastical and technical medium of the Middle Ages, sometimes known as 'Neo-Latin'. As Walter Ong has pointed out in Orality and Literacy (1982), this 'Learned Latin' survived as a monolith through sheer necessity, because Europe was 'a morass of hundreds of languages and dialects, most of them never written to this day'. Learned Latin derived its power and authority from not being an ordinary language. 'Devoid of baby talk' and 'a first language to none of its users', it was 'pronounced across Europe in often mutually unintelligible ways but always written the same way' (my italics).
The Latin analogy as a basis for predicting one possible future for English is not therefore very useful, if the assumption is that once upon a time Latin was a mighty monolith that cracked because people did not take proper care of it. That is fallacious. Interestingly enough, however, a Latin analogy might serve us quite well if we develop the idea of a people's Latin that was never at any time particularly homogeneous, together with a text-bound learned Latin that became and remained something of a monolith because European society needed it that way.
引用の最後にもある通り,この「ラテン語に関する誤謬」に陥らないように注意した上で,改めてラテン語の来し方と英語の行く末を比較してみるとき,両言語を取り巻く歴史社会言語学的状況にはやはり共通点があるように思われる.英語の未来を予想しようとする際の不確定要素の1つは,世界がリンガ・フランカとしての英語をどれくらい求めているかである.その欲求が強く存在している限り,少なくとも書き言葉においては,ラテン語がそうだったように,共通語的な役割を維持していくのではないか.
・ McArthur, Tom. "The English Languages?" English Today 11 (1987): 9--11.
2021-07-19 Mon
■ #4466. World Englishes への6つのアプローチ [world_englishes][variety][sociolinguistics][lingua_franca][contact][linguistic_ideology][linguistic_imperialism]
現代世界に展開する様々な英語変種,いわゆる "World Englishes" の研究は,この40年ほどの間,主に社会言語学の立場から注目されてきた.世紀をまたぐこの数十年間,リングア・フランカとしての英語は存在感を著しく増し,世界を席巻する社会現象というべきものになった.英語研究においても明らかにその衝撃が感じられ,例えば World Englishes に関する学術雑誌が続々と発刊されてきた.English World Wide (1979),English Today (1984) ,World Englishes (1985) などである.
World Englishes は(応用)言語学の様々な角度から迫ることができる.英語史も様々な角度の1つであり,本ブログでも種々に取り上げてきた次第である.Mesthrie and Bhatt の序説 (1) によると,World Englishes へのアプローチとして6点が挙げられている.
・ as a topic in Historical Linguistics, highlighting the history of one language within the Germanic family and its continual fission into regional and social dialects;
・ as a macro-sociolinguistic topic 'language spread' detailing the ways in which English and other languages associated with colonisation have changed the linguistic ecology of the world;
・ as a topic in the filed of Language Contact, examining the structural similarities and differences amongst the new varieties of English that are stabilising or have stabilised;
・ as a topic in political and ideological studies --- 'linguistic imperialism' --- that focuses on how relations of dominance are entrenched by, and in, language and how such dominance often comes to be viewed as part of the natural order;
・ as a topic in Applied Linguistics concerned with the role of English in modernisation, government and --- above all --- education; and
・ as a topic in cultural and literary studies concerned with the impact of English upon different cultures and literatures, and the constructions of new identities via bilingualism.
このような概説は,実に視野を広げてくれる.私など World Englishes を主として英語史の立場から見るにすぎなかったが,とたんに多次元の話題に見えてくるようになった.各分野の概説書の第1ページというものは,しばしば啓発的である.
・ Mesthrie, Rajend and Rakesh M. Bhatt. World Englishes: The Study of New Linguistic Varieties. Cambridge: CUP, 2008.
2021-02-01 Mon
■ #4298. ヨーロッパの有力な共通語とならなかったスペイン語 [spanish][lingua_franca][history][hispanification][prestige][language_planning][sociolinguistics]
現代世界において,スペイン語の話者人口は著しく増加している.母語話者数でいえば,この10年ほどの間に英語を追い抜き,中国語に継ぐ世界第2位の地位を誇るに至った超大言語である(cf. 「#3009. 母語話者数による世界トップ25言語(2017年版)」 ([2017-07-23-1])).ただし,スペイン語のこの勢いは,スペイン本国というよりは南米諸国の勢いに大きく依存している.また,アメリカ合衆国内部での伸張が著しいことも注目に値する(cf. 「#256. 米国の Hispanification」 ([2010-01-08-1])).
現代世界におけるスペイン語の伸張はこのように明らかだが,お膝元のヨーロッパにおいてはどうだろうか.スペイン語はヨーロッパでももちろん大言語の1つとは言い得るが,域内の近代史のなかでリンガ・フランカとして影響力を示したことはなかった.少なくとも英語,フランス語,ドイツ語に比べれば,その影響力は常に小さいものだったし,現在もそうである.なぜスペイン語はヨーロッパの有力な共通語とならなかったのだろうか.
この問いに関して,アジェージュに記述がある.ラテン語から派生し,カスティーリャ語として国家語の地位に就き,新大陸へも拡張したスペイン語の歴史を振り返った後で,次のように述べている (27--28) .
スペイン語はこれほど波瀾万丈の歴史を経てきたのだから,それを糧にして,ヨーロッパの共通語として名乗りをあげてもよさそうなものではないだろうか.ところが実際にはそううまくはいかなかった.というのも,スペイン語は,その歴史を通じて,ヨーロッパの超国民的なコミュニケーション言語として使われたことがまったくないからである.たとえば,スペイン語と同じくらいの話者数をもつ言語にポーランド語やウクライナ語があり,約三〇〇〇から三五〇〇万のひとびとに話されているが,スペイン語はこれらの言語と比べても地域的なひろがりをもっていない.スペイン王国がつぎつぎと国外の王国を併合したおかげで,スペイン語を母語とする君主たちが,スペインよりも広大な領土をもつ帝国を支配することとなったことはたしかである.けれども,どの土地でもスペイン語は優越した地位を占めなかった.ポルトガルでも,イベリア半島の外でもそうであった.たとえば,十七世紀,十八世紀のスペイン領ネーデルラント,さらにミラノやナポリがそうであった.もし歴史の女神がスペインを大西洋のはるかかなたの大陸に向かわせることがなかったならば,そして十九世紀半ばまでに,スペイン独特の政治,経済,社会,宗教のあり方が,他の西欧諸国に見られるのとは異質の文明をスペインに作りあげてこなかったならば,スペイン語はヨーロッパの共通語のひとつになってもなんらおかしくはなかったはずだ.とはいえ,いまやアメリカ合衆国では,東はプエルトリコ系から西はメキシコ系にいたるまで,カスティーリャ語のさまざまなアメリカ的変種の占める地位がますます増大している状況を見ると,スペイン語の未来は約束されているように思えるかもしれない.こうした動向を応援するひとのなかには,スペイン語がアメリカ大陸にいまよりさらにひろい領土を獲得した後に,凱旋将軍としてヨーロッパにもどってくる日が来るのを心待ちにしているひとさえいるだろう.しかしいずれにせよ,いまのところスペイン語は,ヨーロッパ大陸を結びつける言語のモデルとしては役不足である.
この記述は,先の「なぜ」の問いに答えているわけではない.「歴史の女神」を引き合いにしているにすぎないからだ.この問題は,とりわけ英語やフランス語の歴史と比較していけば解決するにちがいない.言語の帯びる威信 (prestige) や言語計画 (language_planning) という観点からの比較もおもしろそうだ.
・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.
2019-11-23 Sat
■ #3862. 「アレクサンドロスの大征服」の意義の再評価 [history][writing][greek][koine][lingua_franca]
昨日の記事「#3861. 「モンゴルの大征服」と「アラブの大征服」の文字史上の意義の違い」 ([2019-11-22-1]) に引き続き,文字史の観点から世界史を描いた鈴木 (73--75) より,今回は「アレクサンドロスの大征服」の意義について触れられている箇所を引用する.
アレクサンドロスの遠征はしばしば「空前の大遠征」といわれ,その帝国も「空前の世界帝国」といわれる.
確かにマケドニア,ギリシア側からみれば「空前の世界帝国」かもしれないが,ペルシア側からみれば,アケメネス朝ペルシア帝国の版図にわずかにマケドニアとギリシアが加わったに過ぎない.この「大征服」の眼目は,まさに「小が大を呑んだ」ことになるのである
....
〔中略〕
....
さて,アレクサンドロスの東征の「成果」についても,この大遠征がヘレニズムの文明を生み出し,征服地でギリシア文明が普及し,その影響はさらに遥か東方まで及んだとされている.
確かにアレクサンドロスの帝国内では,いくつものアレクサンドリアをはじめ,多くのギリシア風都市が建設され,ギリシア的要素をもつ文化が生まれ,少なくとも一時期はギリシア語も痕跡を残した.また東西が融合した文化が生まれ,とりわけ西方で一時代をなしたのも事実である.
ここで我々の「文化」と「文明」の概念に照らしてみれば,「文化」のうえでは東方に確かに刻印を残した.しかしその影響が持続し,定着したとはいいがたいのではないか.
「文明」についてみれば,後代のギリシア・ローマ世界の人間の目,また「ヘレニズム」の概念を創案した一九世紀西欧人の目をもってすると,ギリシアの「文明」が東方に大きな影響を与え,大きな発展に役立ったとみえたかもしれない.
だがそれは,ギリシアの「文明」が東方の「文明」に対し遥かに高いものであるとの固定観念によるところが大であったように思える.実際には,希臘文明の「東漸」もさることながら,東方文明の「西漸」こそ,問題とされるべきではなかろうか.
「アレクサンドロスの大征服」により東方でも一時的にギリシア語のコイネーがリンガ・フランカとして機能したことは事実だが,その後代への影響がどれだけ持続したかという観点からみると,その意義は言われているほど著しいものではない,という評価である.
昨日の記事で取り上げた2つの征服と合わせて考えると,文字・言語史上の意義という点に関しては,「アラブの大征服」>「アレクサンドロスの大征服」>「モンゴルの大征服」ということになろうか.
・ 鈴木 董 『文字と組織の世界史 新しい「比較文明史」のスケッチ』 山川出版社,2018年.
2019-11-12 Tue
■ #3851. 帝国主義,動物園,辞書 [history][linguistic_imperialism][lingua_franca][lexicography]
出口治明の『「全世界史」講義 I 古代・中世編』を読んでいて,「#3603. 帝国主義,水族館,辞書」 ([2019-03-09-1]),「#3767. 日本の帝国主義,アイヌ,拓殖博覧会」 ([2019-08-20-1]) で取り上げた話題と同趣旨の言及をみつけた.帝国というものは,世界中の生き物の収集に凝るのと同様に,(過去の)言葉の収集にも凝るものだという内容だ.
世界最古のシュメールの都市国家群を滅ぼして,メソポタミア地方全域からアナトリア半島西部まで遠征したのが,アッカド王サルゴンでした.メソポタミアで初の統一国家,アッカド帝国が出現したのです.BC二三三四年のことでした.
アッカドは史上初の帝国となりました.なお本書では,複数の異なる言語を話す民族を統合した政権を,慣用に従って帝国と呼びます.アッカドとシュメールは南北に隣同士ですが,言語も民族も異なっていました.
帝国にとって何が必要かといえば,共通語です.これがないと国の統一ができません.ここでリンガ・フランカ(共通語)という概念が出てきます.こうしてアッカド語が,人類最初の共通語になりました.
さて,サルゴンは,当時の最先進地域を統一しただけに,多くのエピソードを残しています.粘土板の記述によると,サルゴンは世界で初めて動物園をつくり,そこにはインダス川の水牛もいたそうです.なぜ動物園をつくったのかについては,次のように考えられています.
言語が異なる民族を征服して,統一帝国をつくったということは,すべての人間を支配したことを意味します.すべての人間を支配すると,次はすべての生き物を支配しようと思い立ち,動物園をつくる.さらに進むと過去もすべて支配したいと思い,文物の収集へと至ります.アッシリア王は大図書館をつくり,中国・清の康煕帝は『康煕字典』という空前の大漢字辞書をつくる.ナポレオンのルーブルや大英帝国の大英博物館も,すべて同様の意志から生まれています.サルゴンは,まさにその先鞭をつけたのです.(32)
収集は支配の証ということか.すると,収集癖は支配マニアということになる.その考え方によると,ある言語の単語を収集し,整理し,提示することを目的とする辞書学 (lexicography) は,言語(とそれを用いる人々)を支配する方法を追究する分野ということになる!?
・ 出口 治明 『「全世界史」講義 I 古代・中世編』 新潮社,2016年.
2019-10-06 Sun
■ #3814. アフリカの様々な超民族語 [africa][lingua_franca][terminology][world_languages][map][bilingualism]
異なる民族間で用いられるリンガ・フランカ (lingua_franca) のことを「超民族語」 (langue véhiculaire) と称することがある.ある民族に固有の言語である点を強調する「群生言語」 (langue grégaire) に対して,「地理的に隣接してはいても同じ言語を話していない,そういう言語共同体間の相互伝達のために利用されている言語」である点を強調した用語である(カルヴェ,p. 33).他の呼称としては,「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]) で用いたように「族際語」という用語もある.
超民族語に関わる話題は,lingua_franca の各記事や,とりわけ「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#1789. インドネシアの公用語=超民族語」 ([2014-03-21-1]) で取り上げてきた.超民族語が非常に多く分布し,今後,社会的な役割が増してくると見込まれるのは,アフリカである.それぞれ通用する地域や人口は様々だが,アラビア語,ウォロフ語,バンバラ語,ソンガイ語,ハウサ語,ジュラ語,アカン語,ヨルバ語,フルフルデ語,サンゴ語,マバ語,リンガラ語,トゥバ語,ルバ語,ンブンドゥ語,ロジ語,アムハラ語,オロモ語,ソマリー語,サンデ語,ガンダ語,スワヒリ語,ニャンジャ語,ショナ語,ツワナ語,ファナガロ語など多数あげることができる(宮本・松田,p. 700) . *
宮本・松田 (706--07) は,アフリカの言語事情の未来は,これらの超民族語にかかっていると主張している.アフリカが複雑な言語問題に自発的に対処していくためには,旧宗主国の西欧諸言語ではなく,植民地時代以前から独自に発展していた超民族語に立脚するのが妥当だろうと.これはアフリカのみならず世界の多様化する言語問題に対する1つの提案となっているようにも思われる.
グローバル化の覇権言語の攻勢下にあっても,「超民族語」を含めて,アフリカの民族諸言語は,新しい次元へと常に昇華していくであろう.同時に,いわゆる「ナイジェリアン・ピジン」(ナイジェリア英語のこと.すでに,クレオール化している)を典型例として,英語やフランス語も,特に話し言葉のレベルで,アフリカの土壌に根付いていくことだろう.これらの言語が運ぶ新旧・内外の文化伝統は,アフリカ人の多言語生活のなかで相補の関係を結び,やがて融和していくに違いない.
だが,異質な文化伝統を無条件に融和させることが最終目的ではない.むしろ,両者の間に生起する摩擦に注目し,不整合な部分を強調しておくことが大切であろう.現代のアフリカは,さまざまな文化の綜合をはかる巨大な実験場となっている.この文化的綜合の事業のなかへ,すべての民族諸言語と民族文化が吸収されるような方策が立てられるべきであろう.この事業で最も大切なことは,だれがそのイニチアチブを握るかという問題である.アフリカ人がこの事業のイニシアチブを握るのであれば,この種の文化的綜合は,決してアフリカの尊厳を損なうものとはならないであろう.その意味でも,民族諸言語,わけても「超民族語」が引き受ける役割は大きい.
アフリカの諸言語は,有史以来,この大陸に住んできた数えきれない諸民族の貴重な文化遺産であり,今を生きている人々にとっては,日々の生活,実存そのものなのだ.それらを封印するのではなく,その壮大な言語宇宙を開くことは,アフリカの文化的再生の必須要件と言うべきであろう.
・ ルイ=ジャン・カルヴェ 著,林 正寛 訳 『超民族語』 白水社〈文庫クセジュ〉,1996年.
・ 宮本 正興・松田 素二(編) 『新書アフリカ史 改訂版』 講談社〈講談社現代新書〉,2018年.
2018-11-15 Thu
■ #3489. 人的・知的リソースの「横領」の結果としての英語の世界語化 [war][elf][lingua_franca][history]
近藤 (279--80) は,英語が知的なグローバル言語に成長した現代的な背景として,第二次世界大戦の結果,人的・知的リソースが英語圏へ流入したことがあるとしている.
人材と科学技術について,アメリカ・イギリス(とソ連)は旧ドイツ・オーストリア(中欧)の資産をむさぼり領有した.S・ヒューズ『大変貌――社会思想の大移動』が描くとおり,中欧から英語圏への知識人の脱出・移動によって一九三〇――四〇年代のイギリス・アメリカが獲得したものは大きい.スケールにおいて一六八五年以後のフランスから逃げたユグノ,オランダからイギリスに軟着陸した人材に数倍する.
イギリスに渡来した人文社会系の学者だけをみても,I・バーリン,S・フロイト,F・ハイエク,ポラニー兄弟,K・ポパー,L・ウィトゲンシュタイン.歴史家に限ると(ネイミア)は早々と一九〇八年に来英),G・エルトン,M・フィンリ,E・ボブズボーム,N・ペヴズナ,M・ポスタン,A・ヴァールブルク…….二〇世紀の学問の革新者は,ほとんど追われて,あるいは自主的に渡来した人びとである.英語が真に知的なグローバル言語になったのは,このときからであろう.
著者 (303) は,イギリス史を貫くのキーワードの1つとして「横領」を挙げているが,まさにイギリスやアメリカは外部からの知的横領によって,英語(文化)を磨き上げてきたといえるだろう.
引用中に触れられているユグノの渡英に関して,その英語史上の意義について「#594. 近代英語以降のフランス借用語の特徴」 ([2010-12-12-1]),「#678. 汎ヨーロッパ的な18世紀のフランス借用語」 ([2011-03-06-1]) などで触れているので,そちらも参照されたい.近代初期のオランダからの移民による言語的影響については「#3436. 英語と低地諸語との接触の歴史」 ([2018-09-23-1]) の (4) を参照.
・ 近藤 和彦 『イギリス史10講』 岩波書店〈岩波新書〉,2013年.
2018-10-27 Sat
■ #3470. 言語戦争の勝敗は何にかかっているか? [japanese][world_languages][lingua_franca][elf][demography][sociolinguistics]
徳川 (245--46) は,日本語史における東西方言(江戸方言と上方方言)の優位をめぐる争いを「言語戦争」の例としながら,一般に言語戦争の勝敗が何によって左右されるのか,されないのかについて論じている.
まず第一に,言語戦争の勝敗は,単純な言語の使用人口などによってきまるものではない,ということである.ひとにぎりの権力者の言語が,多数の庶民の上に君臨するといった場合がある.
また,言語戦争の帰趨は,一般的に,なにも言語それ自体の構造によってきまるものでもない.
たとえば,母音の数が多いから戦に負けるとか,名詞に性と数の別があるから勝つ,といったものではない.ただし,その言語が,言語機能に関して,新しい社会に適応できる性質を具備しているかどうか,といった問題はある.現代にひきつけていえば,複雑な社会機構に対応できるかといった,たとえば表現文体の種類の問題や,原子物理学がその言語で処理できるか,といった内容の問題などがある.さらに,言語コミュニケーションが,他のコミュニケーションチャンネルと,どれほど切り離されているか,といった問題などもあるかもしれない.このことは,おそらく,書きことばの文体の確立と,不離の関係にある.
さきに単なる使用人口の差は言語戦争の勝敗の鍵にならないとしたが,もし多数者の使用言語が,その社会の複雑さと対応して,すでに述べた言語機能を高め,今後さらに多くの人びとをのみ込んでいく包容力といったものを備えているということと結びつくようになれば,それは,ある程度利いてくる条件と言えるであろう.これに対して,土俗的な小言語は,こうした言語機能の面で,将来性について劣る場合が多そうに思われる.また,言語の使用人口の多さが,その言語社会の経済的・政治的・文化的な優位に結びついて,言語の威信といったものの背景になることはありうる.“東西のことば争い”の歴史を考えるにあたっても,こうしたことへの配慮が必要となってくる.
ここで徳川は慎重な議論を展開している.話者人口や言語構造そのものが直接に言語戦争の勝利に貢献するということはないが,それらが当該言語の社会的な機能を高める方向に作用したり,利用されたりすれば,その限りにおいて間接的に貢献することはありうるという見方である.結局のところ,社会的な要素が介在して初めて勝敗への貢献について論じられるということなので,話者人口や言語構造の「直接的な」貢献度はほぼゼロと考えてよいのだろう.英語の世界的拡大や「世界語化」を考える上で,とても重要な論点である.
英語の世界語化の原因を巡っては,関連する話題として「#1072. 英語は言語として特にすぐれているわけではない」 ([2012-04-03-1]),「#1082. なぜ英語は世界語となったか (1)」 ([2012-04-13-1]),「#1083. なぜ英語は世界語となったか (2)」 ([2012-04-14-1]),「#1607. 英語教育の政治的側面」 ([2013-09-20-1]),「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#2487. ある言語の重要性とは,その社会的な力のことである」 ([2016-02-17-1]),「#2673. 「現代世界における英語の重要性は世界中の人々にとっての有用性にこそある」」 ([2016-08-21-1]),「#2935. 「軍事・経済・宗教―――言語が普及する三つの要素」」 ([2017-05-10-1]) を参照.
・ 徳川 宗賢 「東西のことば争い」 阪倉 篤義(編)『日本語の歴史』 大修館書店,1977年.243--86頁.
2018-08-23 Thu
■ #3405. esoterogeny と exoterogeny [sociolinguistics][contact][lingua_franca][sociolinguistics][simplification][terminology][accommodation_theory][suppletion]
「#1585. 閉鎖的な共同体の言語は複雑性を増すか」 ([2013-08-29-1]) で "esoterogeny" という概念に触れた.ある言語共同体が,他の共同体に対して排他的な態度をとるようになると,その言語をも内にこもった複雑なものへと,すなわち "esoteric" なものへと変化させるという仮説だ.裏を返せば,他の共同体に対して親密な態度をとるようになれば,言語も開かれた単純なものへと,すなわち "exoteric" なものへと変化するとも想定されるかもしれない.この仮説の真偽については未解決というべきだが,刺激的な考え方ではある.Campbell and Mixco の用語集より,両術語の解説を引用する.
esoterogeny 'A sociolinguistic development in which speakers of a language add linguistic innovations that increase the complexity of their language in order to highlight their distinctiveness from neighboring groups' . . . ; 'esoterogeny arises through a group's desire for exclusiveness' . . . . Through purposeful changes, a particular community language becomes the 'in-group' code which serves to exclude outsiders . . . . A difficulty with this interpretation is that it is not clear how the hypothesized motive for these changes --- conscious (sometimes subconscious) exclusion of outsiders . . . --- could be tested or how changes motivated for this purpose might be distinguished from changes that just happen, with no such motive. The opposite of esoterogeny is exoterogeny. (55)
exoterogeny 'Reduces phonological and morphological irregularity or complexity, and makes the language more regular, more understandable and more learnable' . . . . 'If a community has extensive ties with other communities and their . . . language is also spoken as a contact language by members of those communities, then they will probably value their language for its use across community boundaries . . . it will be an "exoteric" lect [variety]' . . . . Use by a wider range of speakers makes an exoteric lect subject to considerable variability, so that innovations leading to greater simplicity will be preferred.
The claim that the use across communities will lead to simplification of such languages does not appear to hold in numerous known cases (for example, Arabic, Cuzco Qechua, Georgian, Mongolian, Pama-Nyungan, Shoshone etc.). The opposite of exoterogeny is esoterogeny. (59--60)
exoterogeny と esoterogeny という2つの対立する概念は,カルヴェのいう「#1521. 媒介言語と群生言語」 ([2013-06-26-1]) の対立とも響き合う.平たくいえば,「開かれた」言語(社会)と「閉ざされた」言語(社会)の対立といっていいが,これが言語の単純化・複雑化とどう結びつくのかは,慎重な議論を要するところだ.「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1]) では,私はこの補充法の問題について esoterogeny の考え方を持ち出して説明したことになるし,「#1247. 標準英語は言語類型論的にありそうにない変種である」 ([2012-09-25-1]) で紹介した Hope の議論も,標準英語の偏屈な文法を esoterogeny によって説明したもののように思われる.だが,これも1の仮説の段階にとどまるということは意識しておかなければならない.
そもそも言語の「単純化」 (simplification) とは何を指すのかについて,諸家の間で議論があることを指摘しておこう (cf. 「#928. 屈折の neutralization と simplification」 ([2011-11-11-1]),「#1839. 言語の単純化とは何か」 ([2014-05-10-1]),「#3228. Joseph の言語変化に関する洞察,5点」 ([2018-06-07-1])) .また,どのような場合に単純化が生じるかについても,言語接触 (contact) との関係で様々な考察がある (cf. 「#1788. 超民族語の出現と拡大に関与する状況と要因」 ([2014-03-20-1]),「#3151. 言語接触により言語が単純化する機会は先史時代にはあまりなかった」 ([2017-12-12-1])) .
・ Campbell, Lyle and Mauricio J. Mixco, eds. A Glossary of Historical Linguistics. Salt Lake City: U of Utah P, 2007.
2017-07-26 Wed
■ #3012. 英語はリンガ・フランカではなくスクリーニング言語? [lingua_franca][linguistic_imperialism][elf][native_speaker_problem]
連日取り上げているが,『中央公論』8月号の特集「英語1強時代,日本語は生き残るか」より話題を追加.三上喜尊による「日本語は普遍語になりうるか データが示す世界の中の日本語」という記事で,世界における日本(語)のプレゼンスを高めるために,多言語による情報受発信を推進すべきだという提案がなされている.
「英語の世紀」に危機感を覚える者は,英語以外の言語による情報発信にもっと真剣に取り組まなければならないし,英語以外の言語によって発信される情報に対してもっと敏感にならなければならない.世界中の多くの言語の話者に対して,彼らの言葉で語りかけることは,日本に対する共感を呼び覚ます効果が大きい.また,彼らの言語で発せられる情報には,英語あるいは英語話者によるスクリーニングを経ていない重みがある.(57)
最後にある「英語あるいは英語話者によるスクリーニング」という見方が非常に意味深長である.リンガ・フランカ (lingua_franca) としての英語 (elf) を論じる場合には,当然ながら英語が諸言語(話者)の「橋渡し」の役を果たしているということが前提とされている.ポジティヴな英語観だ.
しかし,「スクリーニング」という見方は,ネガティヴな英語観を表わす.英語という第三者を経由することで,本来の意図や意味が遮られたり歪められてしまうという含意がある.さらに,権力による検閲という言語帝国主義な含みすら感じられる (cf. native_speaker_problem) .このように英語を見る視点からは,"English as a Language of Censorship" (= ELC) などの呼称が提案されるようになるかもしれない.これは英語を意地悪くとらえているというわけではなく,英語に限らず普遍語の地位にある言語であれば,必ずリンガ・フランカとしての側面と ELC 的な側面を合わせもつものだろうと指摘しているにすぎない.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow