2023-12-10 Sun
■ #5340. 「ゲルマン征服」をめぐって Taku さんと対談精読実況生中継しました --- heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズ [voicy][heldio][hel_education][link][notice][bchel][anglo-saxon][oe][jute][history][germanic]
一昨日12月8日(金)の夜に,帝京科学大学の金田拓さんとともに,Baugh and Cable の英語史書の「対談精読実況生中継」を Voicy heldio/helwa で配信しました.前半と後半を合わせて2時間弱の濃密なおしゃべり読書会となりました.ライヴでお聴きいただいた多くのリスナーの方々に感謝いたします.ありがとうございました.
精読対象となったのはの同書の第32節 The Germanic Conquest (ゲルマン征服)です.伝統的に英語史の開始とされる449年とその前後の出来事にフォーカスしました.対談相手を務めていただいた Taku さんとともに,著者の英文に唸りつつ,内容についてもなるべく深く掘り下げて議論しました.当該の英文テキストは,先日の予告記事「#5335. 「ゲルマン征服」 --- Baugh and Cable の英語史より」([2023-12-05-1])に掲載しています.
(1) 「#922. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(前半)」
(2) 「【英語史の輪 #65】英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (32) The Germanic Conquest --- Taku さんとの実況中継(後半)」(12月分のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) に含まれる有料配信です)
今回の対談精読実況生中継をお聴きになって,このオンライン精読シリーズに関心を持った方は,ぜひ本書を入手し,シリーズ初回からゆっくりと追いかけていただければと思います.間違いなく良書です.配信のバックナンバーは「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご確認ください.今後も週1,2回のペースでシリーズを継続していきます!
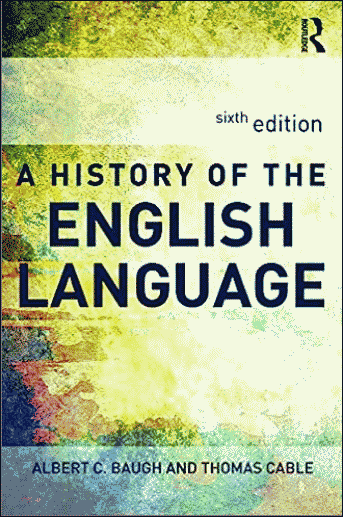
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2023-08-20 Sun
■ #5228. 古英語の人名の愛称には2重子音が目立つ [oe][anglo-saxon][onomastics][name_project][personal_name][consonant][phonetics][shortening][hypocorism][germanic][sound_symbolism]
古英語の人名の愛称 (hypocorism) の特徴は何か,という好奇心をくするぐる問いに対して,Clark (459--60) が先行研究を参考にしつつ,おもしろいヒントを与えてくれている.主に音形に関する指摘だが,重子音 (geminate) が目立つのだという.
Clearly documented hypocoristics often show modified consonant-patterns . . . . Thus, the familiar form Saba (variant: Sæba) by which the sons of the early-seventh-century King Sǣbeorht (Saberctus) of Essex called their father showed the first element of the full name extended by the initial consonant of the second, in a way perhaps implying that medial consonants following a stressed syllable may have been ambisyllabic . . . . In the Germanic languages generally, a consonant-cluster formed at the element-junction of a compound name was often simplified in the hypocoristic form to a geminate, Old English examples including the masc. Totta < Torhthelm, the fem. Cille < Cēolswīð, and also the masc. Beoffa apparently derived from Beornfrið . . . .
重子音化や子音群の単純化といえば,日本語の「さっちゃん」「よっちゃん」「もっくん」「まっさん」等々を想起させる.日本語の音韻論では重子音(促音)そのものの生起が比較的限定されているといってよいが,名前やその愛称などにはとりわけ多く用いられているような印象がある.音象徴 (sound_symbolism) の観点から,何らかの普遍的な説明は可能なのだろうか.
・ Clark, Cecily. "Onomastics." The Cambridge History of the English Language. Vol. 1. Ed. Richard M. Hogg. Cambridge: CUP, 1992. 452--89.
2023-08-10 Thu
■ #5218. スコットランド地名の強勢位置は数世紀を経ても変わらない? [onomastics][toponymy][stress][namae_project][germanic][celtic][scottish_gaelic][pictish][scots_english]
「#5212. 地名学者はなぜフィールドワークをするのか?」 ([2023-08-04-1]) で言及した Taylor の論文の後半で,スコットランド地名の強勢位置に関する驚くべき見解に出くわした (82--83) .語源を提供した言語が話されなくなって数世紀の時間を経たとしても,地名の強勢位置は保たれる傾向があるということだ.規則ではなく傾向ということのようだが,逆にいえば強勢位置の確認によって語源提供言語がある程度の確率で特定できるということにもつながる.
It is very important to record how a place-name is pronounced, since this can yield vital clues for its correct analysis. For example it is a general, though by no means universal, rule that place-names which are stressed on the first element are in languages of Germanic origin, such as Scots or Norse, while place-names which are stressed on the second or third element are of Celtic origin, such as Pictish or Gaelic. It would be more accurate to say that in both language groups it is the specific element which bears the stress, but that in Scots and Norse names the specific usually comes first, the generic second, while in names of Celtic origin it is usually the other way round. It is a remarkable fact that the original stress pattern of a name tends to survive, even when the original language of coining has not been spoken locally for many hundreds of years.
これはおもしろい.いろいろな疑問が頭に湧き上がってくる.
・ 通言語的に specific/generic の区別と統語位置や強勢位置は相関関係にあるものなのか
・ 地名と一般語とでは,歴史的な強勢位置の保持されやすさに差があるのかないのか
・ 同じ地名でも現地話者と外部話者との間で強勢位置や発音が異なることがあるが,これは通常語の地域方言による差違の問題と同一ととらえてよいのか
・ Taylor, Simon. "Methodologies in Place-name Research." Chapter 5 of The Oxford Handbook of Names and Naming. Ed. Carole Hough. Oxford: OUP, 2016. 69--86.
2023-07-19 Wed
■ #5196. 「ゆる言語学ラジオ」出演第4回 --- 『英単語ターゲット』より英単語語源を語る回 [yurugengogakuradio][notice][youtube][etymology][indo-european][germanic][latin][french][greek]
「ゆる言語学ラジオ」からこちらの「hellog~英語史ブログ」に飛んでこられた皆さん,ぜひ
(1) 本ブログのアクセス・ランキングのトップ500記事,および
(2) note 記事,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の人気放送回50選
(3) note 記事,「ゆる言井堀コラボ ー 「ゆる言語学ラジオ」×「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」×「Voicy 英語の語源が身につくラジオ (heldio)」」
(4) 「ゆる言語学ラジオ」に関係するこちらの記事群
をご覧ください.
昨日7月18日(火)に,YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回がアップされました.これまで3回ゲストとして出演させていただきまして,今回は第4回目となります.「英単語帳の語源を全部知るために,研究者を呼びました【ターゲット1900 with 堀田先生】#247」です.どうぞご覧ください.
最後のほうでも力説しているように,「英語史」は決して狭い学問領域ではなく,英語を学ぶ皆が英語に抱く疑問のほとんどについて,何か言うべきことをもっている頼もしい存在です.ぜひこの機会に英語史の存在を(再)認識していただければ.
過去の3回の出演回も合わせてご視聴ください.
・ 第1弾 「#227. 歴史言語学者が語源について語ったら,喜怒哀楽が爆発した【喜怒哀楽単語1】」(5月6日)
・ 第2弾 「#228. 「英語史の専門家が through の綴りを数えたら515通りあった話【喜怒哀楽単語2】」(5月9日)
・ 第3弾:「#234. 英語史の専門家と辞書を読んだらすべての疑問が一瞬で解決した」(5月30日)
2023-06-01 Thu
■ #5148. ゲルマン祖語の強変化動詞の命令法の屈折 [germanic][imperative][inflection][paradigm][verb][person][number][subjunctive][mood][reconstruction][comparative_linguistics]
現代英語の動詞の命令法の形態は,原形に一致する.一方,古英語に遡ると,命令法では原形(不定詞)とは異なる形態を取り,さらに2人称単数と複数とで原則として異なる屈折語尾を取った.
しかし,さらに歴史を巻き戻してゲルマン祖語にまで遡ると,再建形ではあるにせよ,数・人称に応じて,より多くの異なる屈折語尾を取っていたとされる.以下に,ゲルマン祖語の大多数の強変化動詞について再建されている屈折語尾を示す (Ringe 237) .
| indicative | subjunctive | imperative | ||
| active | infinitive -a-ną | |||
| sg. | 1 -ō | -a-ų | --- | participle -a-nd- |
| 2 -i-zi | -ai-z | ø | ||
| 3 -i-di | -ai-ø | -a-dau | ||
| du. | 1 -ōz(?) | -ai-w | --- | |
| 2 -a-diz(?) | -a-diz(?) | -a-diz(?) | ||
| pl. | 1 -a-maz | -ai-m | --- | |
| 2 -i-d | -ai-d | -i-d | ||
| 3 a-ndi | -ai-n | -a-ndau |
とりわけ imperative (命令法)の列に注目していただきたい.単数・両数・複数の3つの数カテゴリーについて,2・3人称に具体的な屈折語尾がみえる.数・人称に応じて異なる屈折が行なわれていたことが理論的に再建されているのだ.
英語史も含め,その後のゲルマン語史は,命令法の形態の区別が徐々に弱まり,失われていく歴史といってよい.英語史内部での命令法の形態や,それと関連する話題については,以下の記事を参照.
・ 「#2289. 命令文に主語が現われない件」 ([2015-08-03-1])
・ 「#2475. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか」 ([2016-02-05-1])
・ 「#2476. 英語史において動詞の命令法と接続法が形態的・機能的に融合した件」 ([2016-02-06-1])
・ 「#2480. 命令にはなぜ動詞の原形が用いられるのか (2)」 ([2016-02-10-1])
・ 「#2881. 中英語期の複数2人称命令形語尾の消失」 ([2017-03-17-1])
・ 「#3620. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (1)」 ([2019-03-26-1])
・ 「#3621. 「命令法」を認めず「原形の命令用法」とすればよい? (2)」 ([2019-03-27-1])
・ 「#4935. 接続法と命令法の近似」 ([2022-10-31-1])
・ Ringe, Don. From Proto-Indo-European to Proto-Germanic. Oxford: Clarendon, 2006.
[ 固定リンク | 印刷用ページ ]
2023-01-08 Sun
■ #5004. 聖書で英語とフリジア語を比較 --- まさにゃんの note 記事の紹介 [notice][frisian][bible][link][masanyan][khelf][contrastive_linguistics][comparative_linguistics][contrastive_language_history][germanic][voicy][heldio]
昨日の記事「#5003. 聖書で英語史 --- 寺澤盾先生の著書と講座のご案内」 ([2023-01-07-1]) で,聖書が英語の通時的な比較に適したテキストであることを述べました.内容が原則として古今東西同一だからです.ということは,聖書は通言語的な比較にも適しているということになります.ギリシア語,ラテン語,英語,フランス語,ドイツ語,中国語,日本語などの間で手軽に言語比較できてしまいます.つまり,聖書は対照言語学 (contrastive_linguistics),比較言語学 (comparative_linguistics),そして対照言語史 (contrastive_language_history) の観点からも有用なテキストとなります.
年末に,khelf(慶應英語史フォーラム)の会長のまさにゃんが,自身の note にて「ゼロから始めるフリジア語(シリーズ企画)」を開始しました.フリジア語は年末から始めたにわか趣味とのことです(笑).1日目,2日目,3日目,4日目と,4日分の記事が掲載されています.「創世記」より英語訳 In the beginning God created the heaven and the earth. とフリジア語訳 Yn it begjin hat God de himel en de ierde skepen. を主に比べながら,軽妙な口調でフリジア語超入門を展開しています.
フリジア語 (Frisian) は,比較言語学的に英語と最も近親の言語とされています.この言語について hellog でも以下の記事で触れてきましたので,ぜひご覧ください.
・ 「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1])
・ 「#2950. 西ゲルマン語(から最初期古英語にかけての)時代の音変化」 ([2017-05-25-1])
・ 「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1])
・ 「#3435. 英語史において低地諸語からの影響は過小評価されてきた」 ([2018-09-22-1])
・ 「#4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」」 ([2022-02-08-1])
Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも「#40. 英語に最も近い言語は「フリジア語」」にて解説しています.ぜひお聴きください.
2022-12-15 Thu
■ #4980. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第22回「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][indo-european][comparative_linguistics][reconstruction][germanic][italic][french][latin][german][dutch][spanish][italian][heldio]
『中高生の基礎英語 in English』の1月号が発売されました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第22回として「なぜヨーロッパの人は英語が上手なの?」に答えています.

この素朴な疑問は,大雑把でナイーヴな問いに響くかもしれません.ヨーロッパ人がみな英語が上手なわけではありませんし,アジアやアフリカを含めた世界の各地に英語が上手な人はたくさんいます.このことは承知の上で,今回の記事をなるべく多くの中高生に届けたいという思いから,あえてこのような表題を掲げた次第です.
中高生に英語学習の早い段階でぜひとも知ってもらいたい重要なことがあります.それは,英語とヨーロッパの主要言語との関係です.将来大学などに進学して英語以外の言語を学ぶことになったとき,あるいは独学で他言語に挑んでみようと思い立ったとき,もしヨーロッパの諸言語を念頭においているのであれば,ぜひ英語,ドイツ語,オランダ語,フランス語,スペイン語,イタリア語などの相互関係について言語学・言語史的な観点から理解しておいてください.学習言語を選択する上で,とても大事な知識だからです.
大学教員である私は日常的に大学生と付き合っていますが,彼らのなかには,英語史の授業などで英語とヨーロッパの諸言語との関係を初めて知ると,第2外国語として○○語ではなくフランス語/ドイツ語を選択しておけばよかった,などと口にする学生がいます.もう1年か2年早く諸言語間の関係を知っていたら△△語を選んでいたのに,と後悔しているようなのです.
中高生の皆さんは,いずれ英語以外の言語を学ぶ可能性があるのであれば,英語と他の言語との関係について知っていたほうが得です.主体的に学習言語を選択できることになるからです.最終的にどの言語を選ぶにせよ,事前に多くの情報をもっておくに越したことはありません.
英語やヨーロッパの主要言語は,いずれもインドヨーロッパ語族と呼ばれる言語家族の一員です.おおまかにいえば言語が互いに似ているのです.しかし,英語と比較してどの点でどのくらい似ているのか,あるいは似ていないのかは,言語ごとに異なります.
ドイツ語とオランダ語は,英語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもゲルマン語派という派閥に属しており,文法や発音において互いに似ているところがあります.しかし,実際にドイツ語やオランダ語に触れてみると,英語と同じ派閥に属しているわりには,それほど似ていないという印象を受けるかもしれません.似ているけれども似ていない,似ていないけれども似ている,といった妙な距離感です.
一方,フランス語,スペイン語,イタリア語などは,長らくヨーロッパの共通語だったラテン語とともにインドヨーロッパ語族のなかでもイタリック語派という派閥に属しています.英語とは大きく異なる派閥なのですが,英語は歴史を通じてフランス語やラテン語から多くの単語を借りてきた経緯があるため,語彙に関しては実は共通しているものが非常に多いのです.したがって,これらの言語を学んでみると,表面的には英語とよく似ているという印象を受けます.
英語は,ゲルマン語派にルーツをもつけれどもイタリック語派の影響を大きく受けながら発展してきた言語なのです.単純化していえば,英語はヨーロッパのいくつかの言語を混ぜ合わせたような混合言語といってよいでしょう.皆さんが英語の次に学ぶ言語を選択する際には,ぜひこのことを参考にしてみてください.
今回の話題と関連する Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の放送回としては「#486. 英語と他の主要なヨーロッパ言語との関係 ー 仏西伊葡独語」がお勧めです.ぜひお聴きください.
2022-11-24 Thu
■ #4959. bright の音位転換 [metathesis][personal_name][indo-european][germanic][etymology]
今朝の朝日新聞「天声人語」で音位転換 (metathesis) が話題とされていた.日本語からの例がいくつか挙げられていたので挙げてみよう.
・ サンザカ(山茶花)→サザンカ
・ アラタシ→アタラシ
・ しだらがない→だらしがない
・ シタツヅミ(舌鼓)→シタヅツミ
芥川龍之介が友人の「フトロコ」「コシャマクレル」という音位転換した発音にいらついたという逸話にも触れられていた.
英語も音位転換の例には事欠かない.「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1]) や「#2809. 英語の音位転換は直接隣り合う2音に限られる」 ([2017-01-04-1]) を含む metathesis の多くの記事で事例を紹介してきたが,全体として /r/ と母音の転換例が比較的多いのが特徴的である.
今回はこれまで /r/ と母音の関わる音位転換の例として取り上げてこなかったけれども,頻度の高い重要な語として bright (明るい)を紹介しよう.印欧語根 *bherəg- "to shine; bright, white" に遡り,ゲルマン祖語では *berχtaz の形が再建されている.古英語では beorht の形で,ここまでは一貫して「母音 + /r/」の順序であることがわかる.しかし,すでに古英語でも音位転換を経た breoht などの形も文証され,中英語期以降は「/r/ + 母音」型が一般化していく.
音位転換を経ていないオリジナルの「母音 + /r/」は,いくつかの人名に化石的に残っている.Albert (nobly bright), Bertha (the bright one), Bertrand (bright raven), Herbert (army-bright) など.
2022-09-17 Sat
■ #4891. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第19回「なぜ単語ごとにアクセントの位置が決まっているの?」 [notice][sobokunagimon][rensai][stress][prosody][french][latin][germanic][gsr][rsr][contact][borrowing][lexicology][hellog_entry_set]
『中高生の基礎英語 in English』の10月号が発売となりました.連載「歴史で謎解き 英語のソボクな疑問」の第19回は「なぜ単語ごとにアクセントの位置が決まっているの?」です.

英単語のアクセント問題は厄介です.単語ごとにアクセント位置が決まっていますが,そこには100%の規則がないからです.完全な規則がないというだけで,ある程度予測できるというのも事実なのですが,やはり一筋縄ではいきません.
例えば,以前,学生より「nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」という興味深い疑問を受けたことがあります.これを受けて hellog で「#3652. nature と mature は1文字違いですが,なんで発音がこんなに異なるのですか?」 ([2019-04-27-1]) の記事を書いていますが,この事例はとてもおもしろいので今回の連載記事のなかでも取り上げた次第です.
英単語の厄介なアクセント問題の起源はノルマン征服です.それ以前の古英語では,アクセントの位置は原則として第1音節に固定で,明確な規則がありました.しかし,ノルマン征服に始まる中英語期,そして続く近代英語期にかけて,フランス語やラテン語から大量の単語が借用されてきました.これらの借用語は,原語の特徴が引き継がれて,必ずしも第1音節にアクセントをもたないものが多かったため,これにより英語のアクセント体系は混乱に陥ることになりました.
連載記事では,この辺りの事情を易しくかみ砕いて解説しました.ぜひ10月号テキストを手に取っていただければと思います.
英語のアクセント位置についての話題は,hellog よりこちらの記事セットおよび stress の各記事をお読みください.
2022-07-30 Sat
■ #4842. 英語は歴史の始まりからすでに混種言語だった? [variety][dialect][germanic][oe][jute][history][oe_dialect][anglo-saxon][dialect_contact][dialect_mixture]
1860年代に出版された Marsh による英語史講義録をパラパラめくっている.Marsh によれば,アングロサクソン語,すなわち古英語は,大陸からブリテン島に持ち込まれた諸方言の混合体であり,その意味においてブリテン島に "aboriginal" な言語とは言えないものの "indigenous" な言語ではあると述べている.言語としては混合体ならではの "diversity" を示し,"obscure", "confused", "imperfect", "anomalous", "irregular" であるという.以下,関連する箇所を引用する.
§15. It has been already shown that the Anglo-Saxon conquerors consisted of several tribes. The border land of the Scandinavian and Teutonic races, whence the Anglo-Saxon invaders emigrated, has always been remarkable for the number of its local dialects. The Friesian, which bears a closer resemblance than any other linguistic group to the English, differs so much in different localities, that the dialects of Friesian parishes, separated only by a narrow arm of the sea, are often quite unintelligible to the inhabitants of each other. Moreover, the Anglo-Saxon language itself supplies internal evidence that there was a great commingling of nations in the invaders of our island. This language, in its obscure etymology, its confused and imperfect inflexions, and its anomalous and irregular syntax, appears to me to furnish abundant proof of a diversity, not of a unity, of origin. It has not what is considered the distinctive character of a modern, so much as of a mixed and ill-assimilated speech, and its relations to the various ingredients of which it is composed are just those of the present English to its own heterogeneous sources. It borrowed roots, and dropped endings, appropriated syntactical combinations without the inflexions which made them logical, and had not yet acquired a consistent and harmonious structure when the Norman conquest arrested its development, and imposed upon it, or, perhaps we should say, gave a new stimulus to, the tendencies which have resulted in the formation of modern English. There is no proof that Anglo-Saxon was ever spoken anywhere but on the soil of Great Britain; for the 'Heliand,' and other remains of old Saxon, are not Anglo-Saxon, and I think it must be regarded, not as a language which the colonists, or any of them, brought with them from the Continent, but as a new speech resulting from the fusion of many separate elements. It is, therefore, indigenous, if not aboriginal, and as exclusively local and national in its character as English itself.
古英語の生成に関する Marsh のこの洞察は優れていると思う.しかし,評価するにあたり,この講義録がイギリス帝国の絶頂期に出版されたという時代背景は念頭に置いておくべきだろう.引用の最後にある "exclusively local and national in its character as English itself" も,その文脈で解釈する必要があるように思われる.
古英語の生成については「#389. Angles, Saxons, and Jutes の故地と移住先」 ([2010-05-21-1]),「#2868. いかにして古英語諸方言が生まれたか」 ([2017-03-04-1]),「#4439. 古英語は混合方言として始まった?」 ([2021-06-22-1]) の記事も参照.
・ Marsh, George Perkins. Lectures on the English Language: Edited with Additional Lectures and Notes. Ed. William Smith. 4th ed. London: John Murray, 1866. Rpt. HardPress, 2012.
2022-06-25 Sat
■ #4807. -ed により過去形を作る規則動詞の出現は革命的だった! [youtube][notice][sobokunagimon][germanic][indo-european][verb][inflection]
3日前の6月22日(水)に,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 の第34弾が公開されました.「昔の英語は不規則動詞だらけ!」です.
-ed をつければ過去形になる,というのは単純で分かりやすいですね.大多数の動詞に適用される規則なので,このような動詞を「規則動詞」と呼んでいます.一方,日常的で高頻度の一握りの動詞はこの規則に沿わず,「不規則動詞」と呼ばれています.sing -- sang -- sung や come -- came -- come のような,暗記しなければならないアレですね.語幹母音を変化させるのが特徴です.
上記の YouTube で話したことは,歴史的には不規則動詞のほうが先に存在しており,規則動詞は歴史のかなり遅い段階に初めて現われた新参者である,ということです.規則動詞は新参者として現われた当初は,例外的なものとして白眼視されていた可能性が高いのです.しかし,その合理性が受け入れられたのでしょうか,瞬く間に多くの動詞を飲み込んでいき,古英語期が始まるまでにはすっかり「規則的」たる地位を確立していました.逆に,オリジナルの語幹母音を変化させるタイプは,当時すでに「不規則的」な雰囲気を醸すに至っていたというわけです.
このような動詞を巡る大変化は,ゲルマン語派に特有のものでした.つまり,この変化は英語,ドイツ語,アイスランド語などには生じましたが,フランス語,ロシア語,ギリシア語などには生じていないのです.すなわち,ゲルマン語派にのみ生じた印欧語形態論の大革命というべき事件でした.
YouTube により関心をもった方は,専門的な話しにはなりますが,この重大事件について,ぜひ次の記事を通じて深く学んでみてください.英語史のおもしろさにハマること間違いなしです.
・ 「#3345. 弱変化動詞の導入は類型論上の革命である」 ([2018-06-24-1])
・ 「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1])
・ 「#3135. -ed の起源」 ([2017-11-26-1])
・ 「#3339. 現代英語の基本的な不規則動詞一覧」 ([2018-06-18-1])
・ 「#764. 現代英語動詞活用の3つの分類法」 ([2011-05-31-1])
・ 「#178. 動詞の規則活用化の略歴」 ([2009-10-22-1])
・ 「#3385. 中英語に弱強移行した動詞」 ([2018-08-03-1])
・ 「#3670.『英語教育』の連載第3回「なぜ不規則な動詞活用があるのか」」 ([2019-05-15-1]) と,そこに示されている記事群
2022-05-21 Sat
■ #4772. Gotland と Gutnish [germanic][gutnish][map]
5月18日,ロシアのウクライナ侵攻を受けて,スウェーデンとフィンランドが NATO への加盟を同時に申請した.本日の読売新聞朝刊7面に「対露最前線の島 強化急ぐ」と題する記事が掲載されていた.その島とは,バルト海に浮かぶスウェーデン領ゴットランド (Gotland) のことである. *

ゴットランドはスウェーデンの首都ストックホルムから約190キロの距離にある.一方,島からロシアの飛び地であるカリーニングラードまでの距離は約300キロである.古来ロシアと西欧をつなぐバルト海の要衝だったが,現在も地政学的な重要性は変わっていない.
ゴットランドの歴史は古い.島は紀元900年頃からスウェーデンの一部を構成していたが,住民は独自の言語と文化を守り続けてきた.島では現在に至るまでゴットランド語 (Gutnish, Gutnic) が用いられている.スウェーデン語の1方言とみなされることが多いが,スウェーデン語やデンマーク語とともに,北ゲルマン語群 (North Germanic) の東ノルド語 (East Norse) の独立したメンバーとみなすこともできる.(ゴットランド語の位置づけについては「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]),「#2239. 古ゲルマン諸語の分類」 ([2015-06-14-1]) を参照されたい.現代ゲルマン諸語の言語地図はこちらから.)
12世紀までに,ゴットランドの商人たちはロシアのノヴゴロドに貿易拠点を構えて,バルト海の貿易ルートを掌握していた.島の随一の町 Visby にはドイツ商人が住むようになり,ハンザ同盟に組み込まれるに至って14世紀半ばまでおおいに繁栄した.
しかし,1361年にデンマークのヴァルデマール4世が島を征服すると,バルト海の貿易ルートが変わり,ゴットランドは衰退していった.その後1645年にスウェーデンに譲渡されると,状況は好転していった.19世紀末にかけては,戦略的要衝として島が要塞化された.
そして,21世紀の現在.島の住民は6万人ほどにすぎないが,今回の国際的緊張のなか,北欧における最前線の1つとなっている.
2022-05-09 Mon
■ #4760. 過去分詞と現在分詞の由来は大きく異なる [infinitive][germanic][morphology][inflection][verb][oe][germanic][indo-european][etymology][suffix]
「#4349. なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」 ([2021-03-24-1]) という素朴な疑問と関連して,そもそも両者の由来が大きく異なる点について,Lass の解説を引用しよう.まず過去分詞について,とりわけ強変化動詞の由来に焦点を当てる (Lass 161) .
. . . its [= past participle] descent is not always very neat. To begin with, it is historically not really 'part of' the verb paradigm: it is originally an independent thematic adjective (IE o-stem, Gmc a-stem) formed off the verbal root. The basic development would be:
IE PGmc *ROOT - o - nó- > *ROOT - α -nα-
強変化動詞に関する限り,過去分詞は動詞語根から派生したにはちがいないが,もともと動詞パラダイムに組み込まれていなかったということだ.形態的には,動詞からの独立性が強く,しかも動詞の強弱の違いにも依存した.
一方,現在分詞には,歴史的に動詞の強弱の違いに依存しないという事情があった (Lass 163) .これについてはすでに「#4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達」 ([2021-03-20-1]) で引用したとおりである.
「なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」という疑問に向き合うに当たって,そもそも過去分詞と現在分詞の由来が大きく異なっていた点が重要となるだろう.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2022-05-09 Mon
■ #4760. 過去分詞と現在分詞の由来は大きく異なる [infinitive][germanic][morphology][inflection][verb][oe][germanic][indo-european][etymology][suffix]
「#4349. なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」 ([2021-03-24-1]) という素朴な疑問と関連して,そもそも両者の由来が大きく異なる点について,Lass の解説を引用しよう.まず過去分詞について,とりわけ強変化動詞の由来に焦点を当てる (Lass 161) .
. . . its [= past participle] descent is not always very neat. To begin with, it is historically not really 'part of' the verb paradigm: it is originally an independent thematic adjective (IE o-stem, Gmc a-stem) formed off the verbal root. The basic development would be:
IE PGmc *ROOT - o - nó- > *ROOT - α -nα-
強変化動詞に関する限り,過去分詞は動詞語根から派生したにはちがいないが,もともと動詞パラダイムに組み込まれていなかったということだ.形態的には,動詞からの独立性が強く,しかも動詞の強弱の違いにも依存した.
一方,現在分詞には,歴史的に動詞の強弱の違いに依存しないという事情があった (Lass 163) .これについてはすでに「#4345. 古英語期までの現在分詞語尾の発達」 ([2021-03-20-1]) で引用したとおりである.
「なぜ過去分詞には不規則なものが多いのに現在分詞は -ing で規則的なのか?」という疑問に向き合うに当たって,そもそも過去分詞と現在分詞の由来が大きく異なっていた点が重要となるだろう.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
2022-05-08 Sun
■ #4759. to 不定詞の起源,再訪 [infinitive][gerund][germanic][morphology][inflection][verb]
to 不定詞の起源について,「#2502. なぜ不定詞には to 不定詞と原形不定詞の2種類があるのか?」 ([2016-03-03-1]) では次のように述べた.
「to 不定詞」のほうは,古英語の前置詞 to に,上述の本来の不定詞を与格に屈折させた -anne という語尾をもつ形態(不定詞は一種の名詞といってもよいものなので,名詞さながらに屈折した)を後続させたもの
これは,英語史の教科書などでよく見かける一般的な記述を要約し,提示したものである.ところが,これは必ずしも正確な説明ではないようだ.Los (144) に異なる解釈が提示されており,そちらのほうが比較言語学的に説得力がある.
The etymology of the to-infinitive is often given as a bare infinitive in the complement of a preposition to, but this leaves the gemination ('doubling') of the -n- in the to-infinitive unexplained. The gemination points to the presence of an earlier -j-, probably part of a nominalising suffix. This parallells (sic) the origin of the gerund . . . , and indicates that the to-infinitive is not built on the bare infinitive, which was a much earlier formation, but on a verbal stem, like any other nominalisation:
(57) to (preposition) + ber- (verbal stem) + -anja (derivational suffix) + -i (dative sg) → Common Germanic *to beranjōi, Old English: to berenne, Middle English: to beren/bere, PDE: to bear.
確かに古英語の原形不定詞 beran を普通の名詞と見立てて与格に屈折させても *berane にこそなれ berenne にはならない.母音も異なるし,子音の重ね (gemination) も考慮にいれなければならないことに,改めて気づいた.
・ Los, Bettelou. A Historical Syntax of English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2015.
2022-03-08 Tue
■ #4698. 池上俊一(著)『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』より「ゲルマンの習俗」について [review][history][germanic]
西洋中世史家の池上俊一氏による『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』(岩波ジュニア新書)を読んでいる.専門家がかみ砕いて書いたジュニア向け本は良いものが多いが,本書もヨーロッパの本質を分かりやすくえぐっている.
著者は「文化としてのヨーロッパ」という捉え方をしており,10世紀末から12世紀前半にかけて成立したそのヨーロッパの構成要素は「ギリシャ・ローマの知」「キリスト教の霊性」「ゲルマンの習俗」「ケルトの夢想」の4点であると主張する (212--13) .
英語史との関わりでは,とりわけ「ゲルマンの習俗」の立ち位置に興味がわいてくる.文化としてのヨーロッパのなかで果たしてきた「ゲルマン」の役割は何か.これについて,池上 (40--42) より引用したい.
ここで,習俗や技芸について,ゲルマン人が何を「ヨーロッパ」に伝えたのかについても考えてみましょう.ヨーロッパの人々の大半がキリスト教に改宗するようになるのは,四世紀以来の布教家の努力の賜物でした.しかしそれで住民たちのそれまでの信仰のあり方や心性が一変したわけではありません.異教的習俗・信仰と,それを否認する教会当局との長い長い争い,つばぜり合いが,その後もずっと続くのです.
ゲルマン人たちは,自然を崇拝し,多神教を信じていました.彼らは,キリスト教に改宗してからも,じつは旧来の信心を守っており,いわば表面のメッキがかわっただけだったのです.聖人崇敬や聖遺物崇敬は,異教時代の大樹や巨石・泉信仰,それら自然物に宿る神々への帰依を,聖母マリアや他の聖人たちへの崇敬に置きかえたものでしたし,現にそうした樹木や巨石,泉などを破壊・除去した跡地に,教会が建てられたのです.また,キリスト教会暦,聖人暦などの暦も,異教の祭儀の時を置きかえたものでした.たとえばキリスト生誕を祝うクリスマスは,実はローマの「不敗の太陽」の祭儀の日の置きかえでした.
キリスト教会が,ゲルマン人の習俗でなにより問題視したのは,福音(キリストの教え)に背馳する迷信行為でした.それは後に「贖罪規定書」というジャンルの作品にまとめて規定されることになりますが,自然物への願かけ・呪い・占いや,神の全能を損なうような行為が非難され罰せられました.
しかしこれは,消えることのないマグマのように近代初頭まで地下にわだかまり,ときにおどろくような形で噴出します.〔中略〕「異端」や「魔女」はその典型ですが,多くは民俗伝統として,ふるまいや民話・迷信となって農村社会に残っていきます.
ほかに,直接キリスト教に背馳するものではない,ゲルマン由来の要素もありました.家族・氏族・部族のしくみや習俗は,とくに貴族社会・騎士社会のベースになっていった点で重要です.ゲルマン人たちの紛争解決法としての復讐行為や,ジッペの間での戦い・フェーデ(後述,一族の義務たる血讐)は,中世の半ば以降にも残りましたし,その背景にあるジッペの名誉観念も中世の貴族・騎士たちに伝わりました.王・首長の統率下に一般自由人男子が入り,さまざまな贈与を受け保護されるかわりに,主君に忠誠を誓い彼のために戦うという「従士制」は,中世の封建的主従関係の柱として使われます.
ようするに「ギリシャ・ローマの理知」とならんで「ゲルマンの習俗」も,その後,中世におけるヨーロッパの形成因となっていったわけです.
工芸品をはじめとする技術や耕作・冶金・乗馬・武器のあつかいなどの実践的な知識も彼らはもたらしました.そしてそれら以上に,「言語」が重要な寄与でした.ローマの共通語ラテン語にゲルマン諸語が混ざって,ヨーロッパの各国語ができあがっていくのですから.
引用の最後の部分に言語の話題が出てくる.もちろん英語も「ヨーロッパの各国語」の1つであり,まさに中英語期以降,ゲルマン語的要素とラテン語的要素の混交が激しく起こっていくことになったのである.
・ 池上 俊一 『ヨーロッパ史入門 原形から近代への胎動』 岩波書店〈岩波ジュニア新書〉,2021年.
2022-02-08 Tue
■ #4670. アジェージュによる「フリジア語の再征服」 [frisian][ethnic_group][germanic][sociolinguistics][language_death][academy]
印欧語比較言語学では,英語と最も近親の言語は何かといえばフリジア語 (Frisian) ということになっている.本ブログでは英語史の周辺の話題も様々に扱ってきたが,フリジア語については「#787. Frisian」 ([2011-06-23-1]) や「#3169. 古英語期,オランダ内外におけるフリジア人の活躍」 ([2017-12-30-1]) で取り上げた程度で,あまり注目してこなかった.
そこで近現代のフリジア語の状況について話題を提供すべく,アジェージュより「フリジア語の再征服」と題する魅力的な1節を引用したい (262--63) .「民族が言語を生み出す」1例としてフリジア語が取り上げられている箇所だ.
ある言語がより勢力の強い言語の圧力によって消滅の危機にさらされても,民族的マイノリティがアイデンティティを要求することで,その言語の地位の向上につながることがある.フリジア語の場合がそれである.フリジア語は,英語と同じく西ゲルマン語群の海洋語群〔アングロ・フリジア語群〕に属し,英語と多くの共通点を持っている.この言語は非常に古い歴史をもっており,紀元一世紀ごろから古代ローマと関係をもっていたヨーロッパの民族の言語である.かつてフリジア語の話者は,彼らの海との戦いを示す治水と干拓の営みをさして,誇り高くこういっていた.《Deus mare, Friso litora fecit》「神が海をつくり,フリジア人が海岸をつくった」と.ところが,フリジア語を話すひとびとは,オランダ(フリースラント州とフローニンゲン州に三五万人)とドイツ(デンマークと国境を接するシュレスヴィヒ=ホルシュタイン州,ニーダーザクセン州のうちエムス川とヴィルヘルムスハーフェンの間にある地域,さらに北部沿岸をとりまく諸島で話されている大陸部諸方言とはかなり異なる方言も入れて数万人)のあいだに分散してしまい,そのなかでフリジア語は二十世紀初めには衰退していた.
衰退の動きは十七世紀半ばからすでに始まっていた.そのころオランダでは,フリジア語は農村でしか話されていなかったし,オランダ語が行政や法律文書においてフリジア語にとって代わりはじめた.けれども,近代になって,領域をもつ行政体としてオランダ・フリースラントが存在したことは,アイデンティティの覚醒を促した.作家たちは,方言横断的な規範に留意しつつ,この言語にまとまった統一正書法をあたえようとした.こんにち,オランダにはフリジア・アカデミーがあり,新造語を管理している.フリジア語は教育や法律の領域にはまだほとんど導入されていないけれども,一九三七年以降小学校で選択科目として導入され,一九五四年から裁判で随時使用できるようになったことを見ると,その後退を食い止めた自覚的な行動のおかげで,フリジア語はオランダ語の非常に強い圧力に以前よりもよくもちこたえているといえる〔後略〕.
「フリジア・アカデミー」なる組織があることは知らなかったので驚いた.オランダ語,英語,ドイツ語,北欧諸語という,地理的にも歴史的にも社会的にも強大な諸言語の狭間にあって,たくましく生き延びているというのは奇跡のようにも思える.
・ グロード・アジェージュ(著),糟谷 啓介・佐野 直子(訳) 『共通語の世界史 --- ヨーロッパ諸語をめぐる地政学』 白水社,2018年.
2021-07-11 Sun
■ #4458. 固定的な強勢アクセント --- ゲルマン語の最大の特徴 [stress][germanic][indo-european]
英語は,印欧語族 (indo-european) のなかの1派閥であるゲルマン語派 (germanic) に属する.ドイツ語,オランダ語,アイスランド語,フリジア語などと同派閥の言語である.この派閥の言語には,他の派閥には必ずしも観察されない共通の特徴がある.概論は「#182. ゲルマン語派の特徴」 ([2009-10-26-1]) に述べたとおりだが,その中でもとりわけ重要なのは,ゲルマン語においては,語に固定的な強勢アクセントが落ちるという事実である.
では,「固定的な強勢アクセント」とは何か,まず強勢アクセント (stress accent) について考えてみよう.強勢アクセントとは,ある音節に注目したときに,それが強く発音されるか弱く発音されるかというエネルギーの強弱の観点からみたアクセントのことである.言語には,もう1つ別に高低アクセント (pitch accent) というものがある.日本語が高低アクセントの言語なので,強勢アクセントとの違いは理解しやすいと思われるが,要するに強さそのものよりも発音の高低(ピッチ)によって区別されるアクセントである.ピアノの演奏にたとえれば,同一のドの鍵盤をたたく力強さの強弱(フォルテかピアノか)によって変わるのが強勢アクセントであり,同じドといっても1オクターブ低いドと高いドとで交代するのが高低アクセントといったらよいだろうか.より詳しくは「#2627. アクセントの分類」 ([2016-07-06-1]) を参照されたい.
次に,固定的なアクセントというのは,いかなる文脈においても,語の強勢は原則としてその語の決まった場所に落ちるということだ.例えば,visit, visits, visited, visiting などは,異なる屈折語尾がついているけれど,アクセントは変わりなく第1音節に落ちている.
英語を学んでいると「語に固定的な強勢アクセントが落ちる」は当たり前のように思われるのだが,これは実は英語というよりもゲルマン語全体に共通する一大特徴なのである.そして,この音韻的な特徴は,歴史的にもゲルマン語の音韻論のみならず形態論や統語論にも甚大な影響を与えてきた.ゲルマン語的な特徴の多くが,実はこのアクセントに関する特徴の派生物といってもよいくらいなのである.
これは,英語史研究者がつとに強調してきたことである.最近パラパラとめくっていた英語音韻論の古典書 Prins (33) にも,この趣旨の記述があったので紹介しておこう.
One of the chief characteristics of the Germanic languages was and still is their strong dynamic accent. Indo-European was characterised by a musical accent which was not fixed, and though in later time this was often replaced by a dynamic accent which was combined with the musical accent, this accent was still free at the time when the Germanic group of dialects began to differentiate from the other Indo-European dialects. The strong dynamic accent of Germanic was, however, fixed and generally fell on the stem or first syllable. This had important results for the vowels in the weaker-stressed syllables . . . .
Prins の "dynamic accent" と "musical accent" という用語は,各々上記の「強勢アクセント」と「高低アクセント」と読み替えて差し支えない.英語 --- そしてゲルマン諸語 --- の歴史は,およそこの「固定的な強勢アクセント」に運命づけられていたといってもよい.それほど重要な特徴である.
・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.
2021-06-30 Wed
■ #4447. 英語史であまり目立たないドイツ語 [german][germanic][borrowing][loan_word]
英語史において高地ドイツ語 (german) が登場する機会は非常に少ない.これは,ある意味では驚くべきことかもしれない.英語もドイツ語も同じゲルマン語派に属する姉妹言語だし,地理的にもイギリスとドイツはさほど隔たっているわけでもないのだから,もっと歴史的な交流があったとしもおかしくないのではないか,という疑問は理解できる.
しかし,英語史においてドイツ語との接触が話題となってくるのは,せいぜい近代に入ってからのことである.英語とドイツ語の間には,確かにゲルマン語派の仲間としての「系統関係」こそあれ,「影響関係」は薄かったといってよい.(系統と影響の区別および German と Germanic の区別の重要性については「#369. 言語における系統と影響」 ([2010-05-01-1]),「#4380. 英語のルーツはラテン語でもドイツ語でもない」 ([2021-04-24-1]),「#4411. German と Germanic の違い --- ややこしすぎる言語名の問題」 ([2021-05-25-1]) を参照.)
上記の事情で,本ブログでもドイツ語の存在感は薄く,「#2164. 英語史であまり目立たないドイツ語からの借用」 ([2015-03-31-1]),「#2621. ドイツ語の英語への本格的貢献は19世紀から」 ([2016-06-30-1]),「#150. アメリカ英語へのドイツ語の貢献」 ([2009-09-24-1]) などで取り上げてきた程度である.
連日引用している Hendriks の論文のタイトルは "English in Contact: German and Dutch" であり,German が Dutch よりも先に立っているわけだが,High German の扱いは,1/3ページにも満たない1段落のみ,以下にすべてを引用してしまえる程度の分量である.(ただし,Hendriks (1660) も本論の最初に明言している通り,焦点は11世紀から17世紀までの言語接触であり,18世紀以降の近現代史は考慮から外していることに注意が必要である.)
4.3 Influence from High German
The 16th century is frequently noted as the starting point for lexical influence from High German (Serjeantson 1961: 179; Viereck 1993: 70; Nielsen 2005: 182). During this period, German miners were brought to England to develop the mineral resources industry; it has been suggested (Luu 2005: 31) that the necessary contacts required to recruit southern German miners were established in the late 15th/early 16th century in the commercial center of Antwerp. Some of the words having entered the language as a result of this connection are zinc, cobalt, shale, and quartz. Regarding German influence on English dialects, Wakelin (1977: 23) states: "There has been contact with Germany since the Middle Ages, but from the dialectal point of view it is not until the seventeenth century that there is much to note". Again, this is a reference to mineralogy. A detailed, OED-based study of High German lexical influence on English is Carr (1934). Briefly noting loans prior to 1600, the study focuses primarily on cultural loans in English from the 17th-19th centuries. The words identified are frequently technical scientific terms or are from other domains of influence such as religion, the military, philosophy and music.
16世紀にドイツの鉱夫が鉱山技術を伝えるべくイングランドにやってきたということ,またそのための商業上の拠点がアントワープにできていたということは初めて知った.
だが,いずれにせよ英語史においては,近代,実質的には後期近代を待たなければ,ドイツ語はまともに現われてこないといってよさそうだ.
・ Hendriks, Jennifer. "English in Contact: German and Dutch." Chapter 105 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1659--70.
2021-06-12 Sat
■ #4429. 序数詞 third の d と fourth の th の関係 [indo-european][germanic][numeral][grimms_law][verners_law][suffix][metathesis]
6月2日より,音声配信プラットフォーム Voicy にて「英語の語源が身につくラジオ」と題するチャンネルをオープンしています.日々10分弱の英語史の話題を配信していますが,昨日は「third は three + the の変形なので準規則的」という話題を取り上げました(cf. 「#92. third の音位転換はいつ起こったか」 ([2009-07-28-1]),「#93. third の音位転換はいつ起こったか (2)」 ([2009-07-29-1]),「#60. 音位転換 ( metathesis )」 ([2009-06-27-1])).この話題について専門的な補足を加えたいと思います.
third の末尾の -d は fourth など4以上の序数詞の末尾に現われる -th と起源的に同一物であり,それが変形したものであるという趣旨で話しました.大雑把にいえば上記の通りに理解しておいてよいのですが,厳密に議論すればそれなりに込み入った事情があります.
印欧語族の序数詞の語尾にはいくつかの種類があり,英語の -th に連なる語尾が唯一のものではありませんでした.3の序数詞についていえば,再建された形態としては,-th に連なる語尾を含む *tri-to- もあれば,別に *triy-o という形態もありましたし,さらにこれらの複雑な混成形と考えられる *t(e)r(e)tiyo- もありました.この最後のものが,現代英語の third (< OE þridda) を出力することになります.したがって,third の d は -th の起源である *-to- と直系の関係にはなく,あくまで「混成」を経由しての間接的な関係というのが正確なところです.典拠として,Mallory and Adams (311) を引用しておきます.
The number 'three', *tréyes (neuter: triha), is also marked by different forms for the different genders and was declined as an -i-stem plural (e.g. OIr trī, Lat trēs, NE three, Lith trỹs, OCS trije [m.], tri [f./nt.], Alb tre [m.], tri [f.], Grk treîs, Arm erek ̔, Hit tēri-, Av θrayō [m./f.], θri [nt.], Skr tráyas [m./f.], trī [nt.], Toch B trai [m.], tarya ([f.]). In some languages we have reflections of a very unusual feminine form, *t(r)is(o)res, i.e. OIr teōir, Av tišrō, Skt tisrás. The underlying derivation of *tréyes is generally sought in either *ter 'further', i.e. the number beyond 'two', or from a *ter- 'middle, top, protruding', i.e. the middle finger, assuming one counted on one's fingers in Proto-Indo-European. Again, the probability that either suggestion is correct is very low. The ordinal number is indicated by a variety of forms similar to *triy-o (e.g. Arm eri 'third', Hit teriyan 'third', tariyanalli- '賊 third officer'), or *tri-to- (e.g. Alb tretê, Grk trítos, Skt tritá-, Toch B trite), or finally *t(e)r(e)tiyo- (e.g. NWels tryddyd, Lat teritius, NE third, Lith trẽčias, Rus trétij, Av θritiya-, Skt tr̥tíya-) which is presumably a conflation of sorts, in various ways, of the previous two while *tris supplies the multiplicative (e.g. Lat ter, Grk trís, Av θriš, Skt tríṣ; despite its apparent phonetic similarity, NE thrice is of a different origin.
上記の通り,現代英語 third そして古英語 tridda の祖形は *t(e)r(e)tiyo- にあったと想定され,問題の語尾の子音は t だったことになります.この子音は順当に発達すればグリムの法則 (grimms_law) により θ に発達していたはずと想定されますが,強勢が後続していたために同発達がブロックされ,ヴェルネルの法則 (verners_law) に従って有声化して ð となり,これが後に脱摩擦音化して d となりました.この一連の流れは,古英語 fæder (> PDE father) に d が確認されるのとまったく同じ流れです(cf. 「#480. father とヴェルネルの法則」 ([2010-08-20-1])).この点については Lass (214) より引用しておきましょう.
3rd. Go þridja, OE þridda, OIc þriþe. This is not entirely suppletive, as it still obviously contains the root for '3'. But the formation is different from that of the other ordinals, involving a suffix */-tjo:-/ (cf. L ter-ti-us). The E, WGmc forms must go back to a variant with an accented suffix, hence the voiced dental from Verner's Law. ModE third is metathesized from þridda (cf. bird < OE bridd, dirt < Osc drit).
なお,印欧祖語レベルでは,英語の -th 語尾に連なる */-to-/ は4,5,6の序数詞のみに当てはまり,ゲルマン語において7以上の序数詞にも付されるようになったのは,後の類推 (analogy) によるものです (Lass 215) .現代英語では4以上の序数詞は -th できれいに揃っているように見えますが,もともとはそうではなかったことになります.
・ Mallory, J. P. and D. Q. Adams. The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford: OUP, 2006.
・ Lass, Roger. Old English: A Historical Linguistic Companion. Cambridge: CUP, 1994.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow