2024-11-20 Wed
■ #5686. B&C の第60節 "Latin Influence of the Second Period" の第1段落を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][christianity][link][voicy][heldio][anglo-saxon][st_augustine][history][bede][link]
今朝配信された Voicy heldio にて「#1270. 英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む (60-1) Latin Influence of the Second Period --- 対談精読実況中継」をお届けしています.英語史の古典的名著を読むシリーズはゆっくりと続いており,第60節まで進んできました.全部で264節ある本なので,まだまだ序盤戦ではあります.バックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) よりご覧いただけます.
ニッチなシリーズなので通常は Voicy heldio の有料配信としてお届けしているのですが,たまに一緒に精読してくださる方をお招きして「対談精読実況中継」をフリーでお届けしています.今回の精読会は,金田拓さん(帝京科学大学)に仕切っていただきまして,helwa リスナーを中心に7名の方々が対面で参加されました(lacolaco さん,ykagata さん,藤原郁弥さん,ぷりっつさん,Lilimi さん,小河舜さん).たいへん熱い読書会となりました.(なお,今回の精読会とほぼ同じメンバーで『英語語源辞典』の読書会もたまに開催しています.heldio より「#1266. chair と sit --- 『英語語源辞典』精読会 with lacolaco さんたち」をお聴きください.)
今回の精読箇所は第60節 "Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain" です.古英語期におけるラテン語の影響について,イングランドのキリスト教化との関連で論じられています.3段落からなる節ですが,今回は1時間ほどかけて最初の1段落のみを超精読して終わりました(本シリーズの精度と速度のほどがわかるかと思います).以下に当該テキスト (Baugh and Cable, pp. 78--79) を掲載します.
60. Latin Influence of the Second Period: The Christianizing of Britain The greatest influence of Latin upon Old English was occasioned by the conversion of Britain to Roman Christianity beginning in 597. The religion was far from new in the island, because Irish monks had been preaching the gospel in the north since the founding of the monastery of Iona by Columba in 563. However, 597 marks the beginning of a systematic attempt on the part of Rome to convert the inhabitants and make England a Christian country. According to the well-known story reported by Bede as a tradition current in his day, the mission of St. Augustine was inspired by an experience of the man who later became Pope Gregory the Great. Walking one morning in the marketplace at Rome, he came upon some fair-haired boys about to be sold as slaves and was told that they were from the island of Britain and were pagans. "Alas! what pity," said he, "that the author of darkness is possessed of men of such fair countenances, and that being remarkable for such a graceful exterior, their minds should be void of inward grace?" He therefore again asked, what was the name of that nation and was answered, that they were called Angles. "Right," said he, "for they have an angelic face, and it is fitting that such should be co-heirs with the angels in heaven. What is the name," proceeded he, "of the province from which they are brought?" It was replied that the natives of that province were called Deiri. "Truly are they de ira," said he, "plucked from wrath, and called to the mercy of Christ. How is the king of that province called?" They told him his name was Ælla; and he, alluding to the name, said "Alleluia, the praise of God the Creator, must be sung in those parts." The same tradition records that Gregory wished himself to undertake the mission to Britain but could not be spared. Some years later, however, when he had become pope, he had not forgotten his former intention and looked about for someone whom he could send at the head of a missionary band. Augustine, the person of his choice, was a man well known to him. The two had lived together in the same monastery, and Gregory knew him to be modest and devout and thought him well suited to the task assigned him. With a little company of about forty monks Augustine set out for what seemed then like the end of the earth.
本節と関連の深い hellog 記事や heldio コンテンツを数多く公開してきたので,以下にリンクを張っておきます.
[ hellog 記事 ]
・ 「#2902. Pope Gregory のキリスト教布教にかける想いとダジャレ」 ([2017-04-07-1])
・ 「#5526. Pope Gregory のダジャレの現場を写本でみる」 ([2024-06-13-1])
・ 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1])
・ 「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1])
・ 「#5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-04-24-1])
・ 「#5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-05-15-1])
・ 「#5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん」 ([2024-06-01-1])
・ 「#5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん」 ([2024-06-14-1])
[ heldio コンテンツ ]
・ 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
・ 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
・ 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」
・ 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」
・ 「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」
今後もこの精読シリーズは続いていきます.ぜひ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013. を入手して,お付き合いいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2024-11-17 Sun
■ #5683. 英語本来語かオランダ借用語かの判定が難しい理由 [dutch][low_german][flemish][contact][lexicology][borrowing][loan_word][germanic][old_norse][evidence]
昨日の記事「#5682. Low Dutch という略称」 ([2024-11-16-1]) で,オランダ語やそれと関連する言語変種からの語彙借用の話題に触れた.過去の記事でも,同じ関心から「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) などで議論してきた.
英語とオランダ語はともに西ゲルマン語派の低地ドイツ語群に属しており,単語もよく似ている.したがって,ある英単語が歴史的に英語本来語なのかオランダ借用語なのかを確信をもって判定するのは,しばしば困難である.この困難の背景について,Durkin (356) がもう少し丁寧に解説しているので,引用したい.
Normally such certainty is only available in cases where the absence of an English sound change or the presence of a Dutch or Low German one demonstrates borrowing: the situation is similar to that explored with reference to early Scandinavian borrowings . . . , with the added complication that there are fewer sound changes distinguishing English from Dutch and Low German. The same problem even affects some words first attested much later than the Middle English period, especially those found in regional varieties for which earlier evidence is in very short supply.
英語本来語かオランダ借用語か否かの判定において,音変化の有無の対比といった言語内的な証拠に訴えかけられるチャンスが低いという点が悩ましい.この点で古ノルド借用語の判定にかかわる困難とも比較されるが,古ノルド語の場合には,北ゲルマン語派に属する言語なので,もう少し言語内的な差異に頼ることができるのだろう.
また,現存する歴史的証拠が乏しい地域変種における語彙となると,さらに判定が困難になるというのもうなずける.個々の単語について,言語内的な証拠だけでなく言語外的な証拠をも収集し,厳密に考慮していかなければならない所以である.
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.
2024-11-16 Sat
■ #5682. Low Dutch という略称 [dutch][low_german][flemish][contact][lexicology][borrowing][loan_word][terminology][germanic][variety]
「#2646. オランダ借用語に関する統計」 ([2016-07-25-1]) で,英語史におけるオランダ借用語をめぐって Durkin を参照した.そこで Dutch でも Low German でもなく,中間的な Low Dutch という用語が使われていた.これが何を指すのかといえば,Durkin 自身が丁寧に解説してくれていた.その1節 (354) を読んでみよう.
Loanwords into English from Dutch (including Flemish) and Low German are normally considered together, because it is so difficult to tell them apart. This is partly because word forms in both languages were, and to some extent still are, so similar, and partly because the social and cultural circumstances of borrowing into English are also often hard to tell apart. 'Low Dutch' is sometimes used as a collective cover term for borrowings from either or both languages into English, although it is important to note that Low Dutch is not itself a language name, but simply a terminological shorthand for referring to a complex situation.
Dutch と Low German は各々区別される言語変種ではあるが,単語の形態が互いによく似ており,借用元同定の文脈においては,実際上区別がつかないことも多いために,便宜上2変種を合わせた用語として Low Dutch を設定しておく,ということだ.ある意味で Low Dutch はフィクションということになる.フランス借用語かラテン借用語か判別がつきにくいときに,便宜上「フランス・ラテン系借用語」などと一括して呼ぶのに似ている.
しかし,こうした用語のフィクション性それ自体も程度の問題ともいえるかもしれない.というのは,上記の Dutch にしても Low German にしても,「区別される言語変種」と一応のところ述べはしたが,やはり何らかの程度においてフィクションでもあるからだ.この点については「#415. All linguistic varieties are fictions」 ([2010-06-16-1]) を参照.
便利に使えるのであれば Low Dutch というタームは悪くない.
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.
2024-09-18 Wed
■ #5623. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継しました [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]
一昨日の Voicy heldio にて「#1205. Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継 --- 「英語史ライヴ2024」より」をアーカイヴ配信しました.これは「#5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します」 ([2024-09-02-1]) で予告したとおり,9月8日(日)に開催された「英語史ライヴ2024」の早朝枠にて生配信された番組がもとになっています.
金田拓さん(帝京科学大学)がメインMCを務め,小河舜さん(上智大学)と私が加わる形での対談精読実況生中継でした.ヘルメイト(helwa リスナー)や khelf メンバーも数名がギャラリーとして収録現場に居合わせ,生配信でお聴きになったリスナーものべ81名に達しました.たいへんな盛況ぶりです.皆さん,日曜日の朝から盛り上げてくださり,ありがとうございました.
今回取り上げたセクションは,実はテクニカルです.古英語期のラテン借用語について,それぞれの単語が同時期内でもいつ借りられたのか,いわば借用の年代測定に関する方法論が話題となっています.取り上げられているラテン借用語の例はすこぶる具体的ではありますが,音変化の性質や比較言語学の手法に光を当てる専門的な内容となっています.
しかし,今回の対談精読会にそってに丁寧に英文を読み解いていえば,必ず理解できますし,歴史言語学研究のエキサイティングな側面を体験することもできるでしょう.本編48分ほどの長尺ですが,ぜひお時間のあるときにゆっくりお聴きください.
Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.

・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2024-09-02 Mon
■ #5607. 「英語史ライヴ2024」で B&C の第57節 "Chronological Criteria" を対談精読実況生中継します [bchel][latin][borrowing][methodology][sound_change][palatalisation][loan_word][oe][chronology][lexicology][phonetics][hellive2024]

Baugh and Cable による英語史の古典的名著を Voicy heldio にて1節ずつ精読していくシリーズをゆっくりと進めています.昨年7月に開始した有料シリーズですが,たまの対談精読回などでは通常の heldio にて無料公開しています.
9月8日(日)に12時間 heldio 生配信の企画「英語史ライヴ2024」が開催されますが,当日の早朝 8:00-- 8:55 の55分枠で「Baugh and Cable 第57節を対談精読実況生中継」を無料公開する予定です.金田拓さん(帝京科学大学)と小河舜さん(上智大学)をお招きし,日曜日の朝から3人で賑やかな精読回を繰り広げていきます.
テキストをお持ちでない方のために,当日精読することになっている第57節 "Chronological Criteria" (pp. 73--75) の英文を以下に掲載しておきます.古英語期のラテン借用語の年代測定に関するエキサイティングな箇所です.じっくりと予習しておいていただけますと,対談精読実況生中継を楽しく聴くことができると思います.
57. Chronological Criteria. In order to form an accurate idea of the share that each of these three periods had in extending the resources of the English vocabulary, it is first necessary to determine as closely as possible the date at which each of the borrowed words entered the language. This is naturally somewhat difficult to do, and in the case of some words it is impossible. But in a large number of cases it is possible to assign a word to a given period with a high degree of probability and often with certainty. It will be instructive to pause for a moment to inquire how this is done.
The evidence that can be employed is of various kinds and naturally of varying value. Most obvious is the appearance of the word in literature. If a given word occurs with fair frequency in texts such as Beowulf, or the poems of Cynewulf, such occurrence indicates that the word has had time to pass into current use and that it came into English not later than the early part of the period of Christian influence. But it does not tell us how much earlier it was known in the language, because the earliest written records in English do not go back beyond the year 700. Moreover, the late appearance of a word in literature is no proof of late adoption. The word may not be the kind of word that would naturally occur very often in literary texts, and so much of Old English literature has been lost that it would be very unsafe to argue about the existence of a word on the basis of existing remains. Some words that are not found recorded before the tenth century (e.g., pīpe 'pipe', cīese 'cheese') can be assigned confidently on other grounds to the period of continental borrowing.
The character of the word sometimes gives some clue to its date. Some words are obviously learned and point to a time when the church had become well established in the island. On the other hand, the early occurrence of a word in several of the Germanic dialects points to the general circulation of the word in the Germanic territory and its probable adoption by the ancestors of the English on the continent. Testimony of this kind must of course be used with discrimination. A number of words found in Old English and in Old High German, for example, can hardly have been borrowed by either language before the Anglo-Saxons migrated to England but are due to later independent adoption under conditions more or less parallel, brought about by the introduction of Christianity into the two areas. But it can hardly be doubted that a word like copper, which is rare in Old English, was nevertheless borrowed on the continent when we find it in no fewer than six Germanic languages.
The most conclusive evidence of the date at which a word was borrowed, however, is to be found in the phonetic form of the word. The changes that take place in the sounds of a language can often be dated with some definiteness, and the presence or absence of these changes in a borrowed word constitutes an important test of age. A full account of these changes would carry us far beyond the scope of this book, but one or two examples may serve to illustrate the principle. Thus there occurred in Old English, as in most of the Germanic languages, a change known as i-umlaut. (Umlaut is a German word meaning 'alteration of sound', which in English is sometimes called mutation.) This change affected certain accented vowels and diphthongs (æ, ā, ō, ū, ēa, ēo , and īo) when they were followed in the next syllable by an ī or j. Under such circumstances, æ and a became e, and ō became ē, ā became ǣ, and ū became ȳ. The diphthongs ēa, ēo, īo became īe, later ī, ȳ. Thus *baŋkiz > benc (bench), *mūsiz > mȳs, plural of mūs (mouse), and so forth. The change occurred in English in the course of the seventh century, and when we find it taking place ina word borrowed from Latin, it indicates that the Latin word had been taken into English by that time. Thus Latin monēta (which became *munit in Prehistoric OE) > mynet (a coin, Mod. E. mint) and is an early borrowing. Another change (even earlier) that helps us to date a borrowed word is that known as palatal diphthongization. By this sound change ǣ or ē in early Old English was changed to a diphthong (ēa and īe, respectively) when preceded by certain palatal consonants (ċ, ġ, sc). OE cīese (L. cāseus, chesse) mentioned earlier, shows both i-umlaut and palatal diphthongization (cāseus > *ċǣsi > *ċēasi > *ċīese). In many words, evidence for date is furnished by the sound changes of Vulgar Latin. Thus, for example, an intervocalic p (and p in the combination pr) in the Late Latin of northern Gaul (seventh century) was modified to a sound approximating a v, and the fact that L. cuprum, coprum (copper) appears in OE as copor with the p unchanged indicates a period of borrowing prior to this change (cf. F. cuivre). Again Latin ī changed to e before A.D. 400 so that words like OE biscop (L. episcopus), disc (L. discus), sigel 'brooch' (L. sigillum), and the like, which do not show this change, were borrowed by the English on the continent. But enough has been said to indicate the method and to show that the distribution of the Latin words in Old English among the various periods at which borrowing took place rests not upon guesses, however shrewd, but upon definite facts and upon fairly reliable phonetic inferences.
Baugh and Cable の精読シリーズのバックナンバー一覧は「#5291. heldio の「英語史の古典的名著 Baugh and Cable を読む」シリーズが順調に進んでいます」 ([2023-10-22-1]) に掲載しています.ぜひこの機会にテキストを入手して,第1節からお聴きいただければ.
・ Baugh, Albert C. and Thomas Cable. A History of the English Language. 6th ed. London: Routledge, 2013.
2024-07-28 Sun
■ #5571. 朝カル講座「現代の英語に残る古英語の痕跡」のまとめ [asacul][notice][lexicology][vocabulary][oe][kenning][beowulf][compounding][derivation][word_formation][celtic][contact][borrowing][etymology][kdee]
先日の記事「#5560. 7月27日(土)の朝カル新シリーズ講座第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」のご案内」 ([2024-07-17-1]) でお知らせした通り,昨日朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」の第4回「現代の英語に残る古英語の痕跡」を開講しました.今回も教室およびオンラインにて多くの方々にご参加いただき,ありがとうございました.
古英語と現代英語の語彙を比べつつ,とりわけ古英語のゲルマン的特徴に注目した回となっています.古英語期の歴史的背景をさらった後,古英語には借用語は比較的少なく,むしろ自前の要素を組み合わせた派生語や複合語が豊かであることを強調しました.とりわけ複合 (compounding) からは kenning (隠喩的複合語)と呼ばれる詩情豊かな表現が多く生じました.ケルト語との言語接触に触れた後,「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」で注目された Beowulf からの1文を取り上げ,古英語単語の語源を1つひとつ『英語語源辞典』で確認していきました.
以下,インフォグラフィックで講座の内容を要約しておきます.
2024-07-23 Tue
■ #5566. 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第5弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][borrowing][norman_french][doublet][hybrid][lexicology]
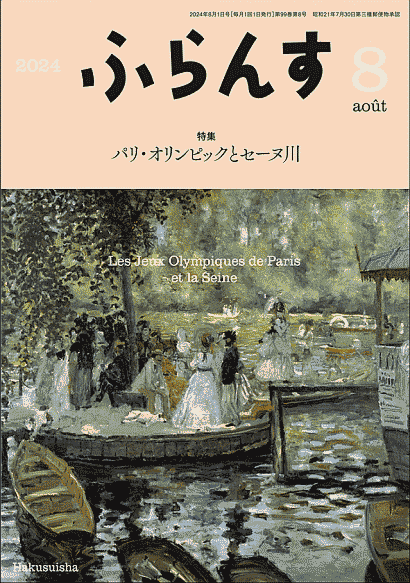
*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.本日『ふらんす』8月号が刊行されました.連載としては第5回となります.
今回は前回の「フランス借用語の大流入」に引き続いての話題です.大流入の結果,英語語彙にどのような衝撃がもたらされたのか,に迫ります.以下の4つの小見出しのもとにエッセイを書いています.
1. 単語借用と語彙体系の変化
中英語期にフランス語からの大量の単語借用があり,英語の語彙体系に大きな影響を与えました.これにより,英語の語彙のあり方が大きく変化しました.
2. 死語となった本来の英単語
フランス語からの借用語により,既存の英単語が置き換えられ死語となるケースが多くありました.例えば「おじ」を意味する ēam が uncle に,「嫉妬」を意味する anda が envy に置き換えられるなどしました.
3. ノルマン・フランス語と中央フランス語
初期の借用語はノルマン方言から,後期はパリの中央フランス語から入りました.これにより,同じ語源を持つ単語が異なる形で英語に入り,2重語 (doublet) として共存するようになりました.
4. 英仏ハイブリッド語
フランス語の語形成に慣れた英語は,フランス語由来の接辞を英語本来の単語に付けて新しい単語を作り出しました.これらは英仏要素を含むハイブリッド語として英語に定着しました.
過去4回の連載記事も hellog で紹介してきましたので,以下よりお読みください.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 「#5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾」 ([2024-06-25-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第5回 中英語期のフランス借用語が英語語彙に与えた衝撃」『ふらんす』2024年8月号,白水社,2024年7月23日.52--53頁.
2024-07-21 Sun
■ #5564. 古英語のラテン語からの借用語はせいぜい数百語 [oe][loan_word][borrowing][latin][old_norse][celtic][latin][germanic][lexicology][link]
古英語の語彙は相当程度にピュアなゲルマン系の語彙といってよく,借用語は限られている.しかも,その限られた借用語の大部分がラテン語 (latin) からのものである.ほかには古ノルド語 (old_norse),ケルト語 (celtic),ゲルマン諸語 (germanic), フランス語 (french) からの借用語もないではないが,あくまで影は薄い.
これらの言語から古英語への借用語は,むしろ例外的だからこそ気になるのだろう.数が少ないので,古英語を読んでいるときに出くわすとやけに目立つのである.英語史研究でもかえってよく注目されている.Hogg は,古英語期の語彙と語彙借用について次のように評している.
. . . there are words of non-native origin in Old English, the vast majority of which are from Latin. It has been estimated only about 3 per cent of Old English vocabulary is taken from non-native sources and it is clear that the strong preference in Old English was to use its native resources in order to create new vocabulary. In this respect, therefore, and as elsewhere, Old English is typically Germanic. (102--03)
. . . there was in Old English only a very limited use of words taken from other language, i.e. borrowed or loan words, and those words were primarily from Latin. Apart from Latin, Old English borrowed words from the Scandinavian languages after the Viking invasions, from the celtic languages mostly at a very early date, and there was also a scattering of forms from the other Germanic languages. At the very end of the period we begin to see the first loan words from Norman French. (109)
古英語期の各言語からの語彙借用については,以下の記事を参照.
・ 「#32. 古英語期に借用されたラテン語」 ([2009-05-30-1])
・ 「#1437. 古英語期以前に借用されたラテン語の例」 ([2013-04-03-1])
・ 「#1619. なぜ deus が借用されず God が保たれたのか」 ([2013-10-02-1])
・ 「#1945. 古英語期以前のラテン語借用の時代別分類」 ([2014-08-24-1])
・ 「#2578. ケルト語を通じて英語へ借用された一握りのラテン単語」 ([2016-05-18-1])
・ 「#3787. 650年辺りを境とする,その前後のラテン借用語の特質」 ([2019-09-09-1])
・ 「#3788. 古英語期以前のラテン借用語の意外な日常性」 ([2019-09-10-1])
・ 「#3789. 古英語語彙におけるラテン借用語比率は1.75%」 ([2019-09-11-1])
・ 「#3790. 650年以前のラテン借用語の一覧」 ([2019-09-12-1])
・ 「#3829. 650年以後のラテン借用語の一覧」 ([2019-10-21-1])
・ 「#3830. 古英語のラテン借用語は現代まで地続きか否か」 ([2019-10-22-1])
・ 「#1216. 古英語期のケルト借用語」 ([2012-08-25-1])
・ 「#3821. Old Saxon からの借用語」 ([2019-10-13-1])
・ 「#302. 古英語のフランス借用語」 ([2010-02-23-1])
・ Hogg, Richard. An Introduction to Old English. Edinburgh: Edinburgh UP, 2002.
2024-06-25 Tue
■ #5538. フランス借用語の大流入 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第4弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][reestablishment_of_english]
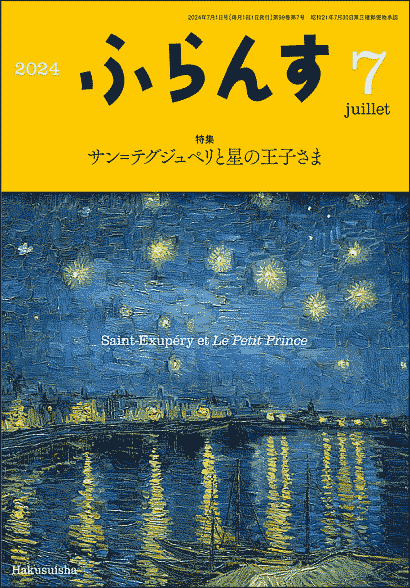
*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書いています.昨日『ふらんす』7月号が刊行されました.今回は連載第4回となります.タイトルは「フランス借用語の大流入」です.以下の小見出しのもとに,2頁ほどの英語史エッセイを執筆しています.
・ フランス借用語の爆発期
・ 多分野にわたるフランス借用語
・ なぜ英語復権期にフランス借用語が多くもたらされたのか?
前回までの連載記事では,英語にフランス借用語は多いけれども,実はフランス語彙の流入は初期中英語期まではさほど著しくなかった,というところまで述べました.今回はいよいよ1250年以降の大流入について導入しています.
フランス語彙が数千語という規模で一気に入ってきた,その量にまず驚きますが,それ以上に興味深いのはカバーしている語彙分野の広さです.ノルマン征服以降,イングランドの社会や文化の多くの部分がフランス(語)の影響下に入りましたが,とりわけ政治・行政,教会,法律,軍事,流行,食物,社会生活,芸術,学問,医学の分野ではフランス語の存在感は圧倒的でした.連載記事では,そのような借用語彙のサンプルを挙げています.
ここで1つ大きな謎は,なぜノルマン征服から200年も経った後に,フランス語彙の大流入が生じたのか,です.普通に考えると,ちょっと遅すぎるように感じませんか.遅くてもせいぜい数十年,もっと我慢したとしても100年くらいが良いところではないか,と思われます.ところが,フランス語彙の流入が軌道に乗り調子が出てくるまでに,ノルマン征服後,200年もの長い時間が経過してしまっているのです.これはどのように考えればよいのでしょうか.今回の記事では,この謎に一つの答えを与えています.
連載は年度末まで続く予定ですが,これまでの3回分を購読された読者の方は,すでに仏英語の関係についておおいに関心を抱くようになったのではないでしょうか.
過去3回の連載記事についても hellog で取り上げてきましたので,以下よりお読みいただければ.関連するリンクも,そちらにたくさん張っています.
・ 「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1])
・ 「#5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾」 ([2024-04-25-1])
・ 「#5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾」 ([2024-05-27-1])
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第4回 フランス借用語の大流入」『ふらんす』2024年7月号,白水社,2024年6月24日.52--53頁.
2024-05-27 Mon
■ #5509. 英語に借用された最初期の仏単語 --- 月刊『ふらんす』の連載記事第3弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]
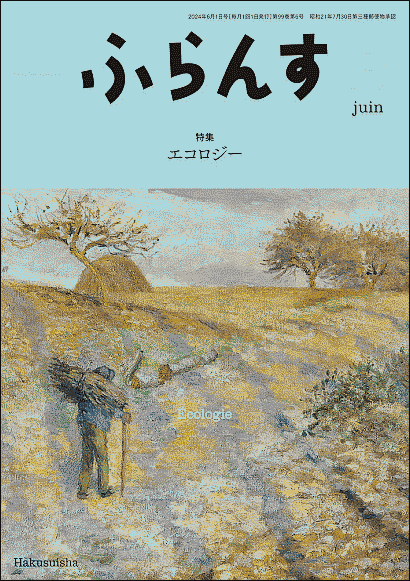
*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』にて連載記事「英語史で眺めるフランス語」を書かせていただいています.先日『ふらんす』6月号が刊行されました.今回で第3回となる記事のタイトルは「英語に借用された最初期の仏単語」です.以下の小見出しのもと,2頁ほどの読み物となっています.
・ フランス語との腐れ縁とその馴れ初め
・ 最初の仏借用語は古英語末期から
・ ノルマン征服後の2世紀は意外と地味
・ フランス語に置き換えられた法律用語
英語語彙にフランス語からの借用語が多く含まれていることはよく知られていますが,そもそも英仏語の言語接触 (contact) にはどのような背景があったのでしょうか.今回の記事では,両言語の出会いと,言語接触の最初期の状況を記述しました.最初期にはフランス語からの影響は意外と限定的だったことなどが,主たる話題となっています.
フランス語と英語史を掛け合わせた話題は豊富にあり,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも多く取り上げてきました.参考までに,関連する配信回をいくつか挙げておきます.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
・ 「#370. 英語語彙のなかのフランス借用語の割合は? --- リスナーさんからの質問」
・ 「#1087. 英語の料理用語はフランス語とともにあり」
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第3回 英語に借用された最初期の仏単語」『ふらんす』2024年6月号,白水社,2024年5月23日.52--53頁.
2024-05-04 Sat
■ #5486. 5月18日(土)の朝カル新シリーズ講座第2回「英語語彙の歴史を概観する」のご案内 [asacul][notice][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link][lexicology][vocabulary][loan_word][borrowing][word_formation][voicy][heldio]
新年度より,朝日カルチャーセンター新宿教室にてシリーズ講座「語源辞典でたどる英語史」を月に一度のペースで開講しています.
第1回「語源辞典でたどる英語史」は,4月27日(土)の 17:30--19:00 に開講され,おかげさまで盛況のうちに終了しました.こちらの回については,本ブログでも「#5453. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」が4月27日より始まります」 ([2024-04-01-1]) および「#5481. 朝カル講座の新シリーズ「語源辞典でたどる英語史」の第1回が終了しました」 ([2024-04-29-1]) で事前・事後に取り上げました.
第2回「英語語彙の歴史を概観する」は2週間後の5月18日(土)の 17:30--1900 に開講される予定です.対面・オンラインによるハイブリッド開講で,「見逃し配信」サービスもご利用可能です.第1回を逃した方も問題なくご参加いただけます.ご関心のある方は,ぜひこちらよりお申し込みください.

第2回は,シリーズ全体のイントロとして,1500年以上にわたる英語語彙史を俯瞰してみます.今後のシリーズ展開に向けて,英語の語彙の変遷について大きな見通しを得ることが目標です.英語語彙史を概観していく過程で,英語史の各時代からいくつかのキーワードをピックアップして『英語語源辞典』(研究社,1997年)をはじめとする各種の英語語源辞典を参照します.同辞典をお持ちの方は,ぜひお手元にご用意しつつ,講座にご参加ください.どんな単語が取り上げられるかを予想しながら講座に臨んでいただければ.
(以下,後記:2024/05/14(Tue))
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2024-04-25 Thu
■ #5477. なぜ仏英語には似ている単語があるの? --- 月刊『ふらんす』の連載記事第2弾 [hakusuisha][french][loan_word][notice][rensai][furansu_rensai][norman_conquest][borrowing][voicy][heldio]

*
今年度,白水社の月刊誌『ふらんす』に「英語史で眺めるフランス語」というシリーズタイトルで連載記事を寄稿しています.一昨日『ふらんす』5月号が刊行されました.シリーズ第2回の記事は「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」です.今回の記事は以下の小見出しで構成しています.
・ 単語が似ているのにはワケがある
・ 借用の方向に基づく3つのパターン
・ 言語学的な観点に基づく3つのパターン
・ 似ている単語を見つけたときには要注意
仏英語には似ている単語が多く見られます.背景には1066年のノルマン征服とその後の歴史があります.しかし,理由はこれに尽きません.歴史的および言語学的に検討すると,両言語に類似単語が存在する背景には6つのパターンがあるのでス.今回の記事では,具体例を交えつつ,この点を解説しています.
新年度に新しい外国語としてフランス語を学び始めている方も多いかと思います.そのなかには,すでに英語について知識のある方も少なくないはずです.英語とフランス語の学習は,連動させるのが吉です.その上で英語史の知見も連動させると,学び全体に何倍もの相乗効果が生み出されることを強調したいと思います.この観点から,以下の Voicy 配信回もお聴きいただければ.
・ 「#26. 英語語彙の1/3はフランス語!」
・ 「#329. フランス語を学び始めるならば,ぜひ英語史概説も合わせて!」
・ 「#327. 新年度にフランス語を学び始めている皆さんへ,英語史を合わせて学ぶと絶対に学びがおもしろくなると約束します!」
シリーズの初回記事については,hellog 記事「#5449. 月刊『ふらんす』で英語史連載が始まりました」 ([2024-03-28-1]) で取り上げていますので,そちらもご覧ください.
(以下,後記:2024/05/08(Wed))
5月8日に heldio で「#1073. 『ふらんす』5月号で「なぜ仏英語には似ている単語があるの?」を書いています」を配信しました.
・ 堀田 隆一 「英語史で眺めるフランス語 第2回 なぜ仏英語には似ている単語があるの?」『ふらんす』2024年5月号,白水社,2024年4月23日.62--63頁.
2024-03-12 Tue
■ #5433. フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce へ [etymological_respelling][french][latin][loan_word][waseieigo][borrowing][analogy]
seduce (誘惑する)の語源はラテン語の動詞 sēdūcere に遡る.接頭辞 sē- は "away; without" ほどを意味し,基体の dūcere は "to lead" の意味である.合わせて「外へ導く」となり,「悪の道に導く;罪に導く;そそのかす;誘惑する」などの語義を発達させた.
現代英語では「(性的に)誘惑する」の語義が基本だが,15世紀に初めて英語に入ってきたときには「自らの義務を放棄するように説得する」という道徳的な語義が基本だった.OED によると,初出は Caxton からの次の文である.
1477 Zethephius seduysed [French seduisoit] the peple ayenst him by tyrannye al euydente. (W. Caxton, translation of R. Le Fèvre, History of Jason (1913) 104)
この初出での語形は seduysed となっており,当時のフランス語の seduisoit に引きつけられた綴字となっている.
しかし,以下に挙げるもう1つの最初期の例文では,同じ Caxton からではあるが,語形は seduce となっている.
a1492 He [sc. the deuyll] procureth to a persone that he haue all the eases of his bodye, and may not begyle and seduce [Fr. seduire] hym by delectacyons and worldly pleasaunces. (W. Caxton, translation of Vitas Patrum (1495) ii. f. cclv/1
これ以降の例文ではすべて現代的な seduce が用いられている.つまり最初例のみフランス語形を取り,それ以後はすべてラテン語形をとっていることになる.
英語に借用されてきたのが,中英語期の最末期,あるいは初期近代英語期への入り口に当たる時期であることを考えると,英単語としての seduce の綴字は,ラテン語形を参照した語源的綴字 (etymological_respelling) の1例と見ることもできるかもしれない.当初はフランス語形を模していたものが,後からモデルをラテン語形に乗り換えた,という見方だ.あるいは,すでに英語に借用されていた adduce, conduce, deduce, educe, introduce, produce, reduce, subduce などの -duce 語からの類推作用が働いたのかもしれない.その場合には,英語内部で作り出された英製羅語の1例とみなせないこともない.
フランス語風 seduyse からラテン語風 seduce への乗り換えはあくまで小さな変化にすぎないが,英語史的には深掘りすべき側面が多々ある.
2023-09-21 Thu
■ #5260. 喜びに満ちた delicious の同根類義語 [eebo][synonym][me][cognate][lexicology][borrowing][loan_word][latin][french][oed][thesaurus][htoed][voicy][heldio]
今週の月・火と連続して,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」(毎朝6時に配信)にて delicious とその類義語の話題を配信しました.
・ 「#840. delicious, delectable, delightful」
・ 「#841. deleicious の歴史的類義語がたいへんなことになっていた」
かつて「#283. delectable と delight」 ([2010-02-04-1]) と題する記事を書いたことがあり,これとも密接に関わる話題です.ラテン語動詞 dēlectāre (誘惑する,魅了する,喜ばせる)に基づく形容詞が様々に派生し,いろいろな形態が中英語期にフランス語を経由して借用されました(ほかに,それらを横目に英語側で形成された同根の形容詞もありました).いずれの形容詞も「喜びを与える,喜ばせる,愉快な,楽しい;おいしい,美味の,芳しい」などのポジティヴな意味を表わし,緩く類義語といってよい単語群を構成していました.
しかし,さすがに同根の類義語がたくさんあっても競合するだけで,個々の存在意義が薄くなります.なかには廃語になるもの,ほとんど用いられないものも出てくるのが道理です.
Historical Thesaurus of the Oxford English Dictionary (= HTOED) で調べてみたところ,歴史的には13の「delicious 語」が浮上してきました.いずれも語源的に dēlectāre に遡りうる同根類義語です.以下に一覧します.
・ †delite (c1225--1500): Very pleasant or enjoyable; delightful.
・ delightable (c1300--): Very pleasing or appealing; delightful.
・ delicate (a1382--1911): That causes pleasure or delight; very pleasing to the senses, luxurious; pleasurable, esp. in a way which promotes calm or relaxation. Obsolete.
・ delightful (a1400--): Giving or providing delight; very pleasant, charming.
・ delicious (c1400?-): Very pleasant or enjoyable; very agreeable; delightful; wonderful.
・ delectable (c1415--): Delightful; extremely pleasant or appealing, (in later use) esp. to the senses; very attractive. Of food, drink, etc.: delicious, very appetizing.
・ delighting (?a1425--): That gives or causes delight; very pleasing, delightful.
・ †delitous (a1425): Very pleasant or enjoyable; delightful.
・ delightsome (c1484--): Giving or providing delight; = delightful, adj. 1.
・ †delectary (?c1500): Very pleasant; delightful.
・ delighted (1595--1677): That is a cause or source of delight; delightful. Obsolete.
・ dilly (1909--): Delightful; delicious.
・ delish (1915--): Extremely pleasing to the senses; (chiefly) very tasty or appetizing. Sometimes of a person: very attractive. Cf. delicious, adj. A.1.
廃語になった語もあるのは確かですが,意外と多くが(おおよそ低頻度語であるとはいえ)現役で生き残っているのが,むしろ驚きです.「喜びを与える,愉快な;おいしい」という基本義で普通に用いられるものは,実際的にいえば delicious, delectable, delightful くらいのものでしょう.
このような語彙の無駄遣い,あるいは類義語の余剰といった問題は,英語では決して稀ではありません.関連して,「#3157. 華麗なる splendid の同根類義語」 ([2017-12-18-1]),「#4969. splendid の同根類義語のタイムライン」 ([2022-12-04-1]),「#4974. †splendidious, †splendidous, †splendious の惨めな頻度 --- EEBO corpus より」 ([2022-12-09-1]) もご覧ください.
2023-05-28 Sun
■ #5144. 英語史における内的所有構造の発展と「ケルト語仮説」 [celtic_hypothesis][celtic][borrowing][substratum_theory][syntax][construction][linguistic_area][welsh][cornish]
「#5139. 英語史において「ケルト語仮説」が取り沙汰されてきた言語項」 ([2023-05-23-1]) で紹介した項目の1つに "Lack of external possessor construction" がある.現代英語には「外的所有構造」が欠けており,原則として「内的所有構造」 (internal possessor construction) のみがあるとされる.そして,後者の特徴はケルト諸語との言語接触によって誘引されたものではないかという仮説が唱えられている.
内的所有構造とは my head のように,属格(所有格)により直接名詞を修飾して所有関係を示す構造のことである.一方,外的所有構造とは,*the head to me のような表現にみられるように,典型的には与格により間接的に名詞を修飾し,名詞句の外側から所有関係を示す構造のことである.
現代英語では内的所有構造が原則だが,古英語ではむしろ外的所有構造がみられた.例えば,Hickey (499) は古英詩 Poem of Judith より以下の例を挙げている.
þæt him þæt heafod wand forð on ða flore
lit.: that him-DATIVE that head ...
'that his head rolled forth on the floor'
古英語に限らず大多数のヨーロッパの諸言語では,外的所有構造が好まれてきた.バスク語,ハンガリー語,マルタ語などの非印欧諸語でも外的所有構造が用いられていることから,汎ヨーロッパ的な言語特徴とみなすことができる.
その稀な例外が,現代英語であり,ウェールズ語であり,コーンウォール語だという.これらのイギリス諸島に分布する(した)少数の言語では,内的所有構造が好まれる.他に内的所有構造が現われるのは,遠く離れたヨーロッパの東の外縁であり,トルコ語やレズギン語(カフカス諸語の1つ)にみられるが,これとイギリス諸島の諸言語が関係しているとは考えにくい.つまり,英語,ウェールズ語,コーンウォール語は内的所有構造を示す言語として地理的に孤立しているのである.
さて,英語史においては上記で示したとおり,古英語では外的所有構造を用いていたが,後に内的所有構造へと鞍替えした経緯がある.ここにウェールズ語やコーンウォール語などケルト諸語にみられた内的所有構造が,英語の所有構造に影響を及ぼした可能性が浮上する.
Hickey (500) は,この仮説の解説を次のように締めくくっている.
This transfer did not affect the existence of a possessor construction, but it changed the exponence of the category, a frequent effect of language contact, especially in language shift situations.
「#5134. 言語項移動の主な種類を図示」 ([2023-05-18-1]) の類型論でいえば,この場合の "transfer" は "Rearrangement" に該当するのだろうか.興味深い仮説ではある.
・ Hickey, Raymond. "Early English and the Celtic Hypothesis." Chapter 38 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 497--507.
2023-05-23 Tue
■ #5139. 英語史において「ケルト語仮説」が取り沙汰されてきた言語項 [celtic_hypothesis][contact][borrowing][substratum_theory][syntax][be][progressive][do-periphrasis][nptr][th][vowel][voicy][heldio]
英語史における「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) について,これまでいくつかの記事で取り上げてきた.
・ 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1])
・ 「#1254. 中英語の話し言葉の言語変化は書き言葉の伝統に掻き消されているか?」 ([2012-10-02-1])
・ 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])
・ 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1])
・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])
・ 「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1])
・ 「#3969. ラテン語,古ノルド語,ケルト語,フランス語が英語に及ぼした影響を比較する」 ([2020-03-09-1])
・ 「#4528. イギリス諸島の周辺地域に残る3つの発音」 ([2021-09-19-1])
・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])
・ 「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1])
近年の「ケルト語仮説」では,(主に語彙以外の)特定の言語項がケルト諸語から英語へ移動した可能性について検討が進められてきた.Hickey (505) によりケルト語の影響が取り沙汰されてきた言語項を一覧してみよう.ただし,各項目について,注目されている地域・変種や文献に現われるタイミングなどはバラバラであること,また言語接触によらず言語内的な要因のみで説明もし得るものがあることなど,一覧の読み方には注意が必要である.
Table 3. Possible transfer features from Celtic (Brythonic) to English
1. Lack of external possessor construction Morphosyntactic 2 Twofold paradigm of to be 3. Progressive verb forms 4. Periphrastic do 5. Northern subject rule 6. Retention of dental fricatives Phonological 7. Unrounding of front vowels
1 は,英語で My head is sore. のように体の部位などに関して所有格で表現し,The head is sore. のように冠詞を用いない用法を指す.
2 は,古英語(主にウェストサクソン方言)において be 動詞が,母音あるいは s- で始まる系列と,b- で始まる系列の2種類の系列が併存していた状況を指す.
3 は,「#5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」」 ([2023-05-13-1]) を参照.
4 は,「#486. 迂言的 do の発達」 ([2010-08-26-1]),「#3755. 「ケルト語仮説」の問題点と解決案」 ([2019-08-08-1]) を参照.
5 は,「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]) を参照.
6 は,th = [θ] という比較的稀な子音が現代まで残っている事実を指す.
7 は,古英語に円唇前舌母音 [y, ø] があったことを指す.
今回の Hickey の一覧と類似するリストについては「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) も参照.
関連して,Voicy heldio より「#715. ケルト語仮説」もどうぞ.
・ Hickey, Raymond. "Early English and the Celtic Hypothesis." Chapter 38 of The Oxford Handbook of the History of English. Ed. Terttu Nevalainen and Elizabeth Closs Traugott. New York: OUP, 2012. 497--507.
2023-05-18 Thu
■ #5134. 言語項移動の主な種類を図示 [contact][borrowing][grammaticalisation][terminology][typology]
昨日の記事「#5133. 言語項移動の類型論」 ([2023-05-17-1]) の続編.Heine and Kuteva (87) が,言語項移動 (linguistic transfer) の主な種類を次のように分類している(ここでは提示の仕方を少々改変している).
Contact-induced transfer ─┬─ Borrowing │ └─ Replication ─┬─ Lexical replication │ └─ Grammatical replication ─┬─ Contact-induced grammaticalization │ └─ Restructuring ─┬─ Loss │ └─ Rearrangement
Heine and Kuteva によれば,これらの用語やその背後にある洞察は,Weinreich に負っている (86) .replication とは "kinds of transfer that do not involve phonetic substance of any kind" のことであり,伝統的に "structural borrowing" や "(grammatical) calquing" と呼ばれてきたものに相当する.この replication には,一方で語彙に関するものがあり,他方で文法的意味・構造に関するものがある.後者の replication は,本質的には文法化 (grammaticalisation) に沿ったものとなるが,そうでない少数の例のために restructuring という用語を充てておく(そしてさらに細分化する).上の図は,このような言語項移動に関する見方を整理したものである.
言語接触 (contact) に関する類型論 (typology) は様々なものが提案されてきたが,この Heine and Kuteva の分類もたいへん示唆的である.その他,以下の記事などを参照されたい.
・ 「#1779. 言語接触の程度と種類を予測する指標」 ([2014-03-11-1])
・ 「#1780. 言語接触と借用の尺度」 ([2014-03-12-1])
・ 「#1781. 言語接触の類型論」 ([2014-03-13-1])
・ 「#1985. 借用と接触による干渉の狭間」 ([2014-10-03-1])
・ 「#2008. 言語接触研究の略史」 ([2014-10-26-1])
・ 「#2009. 言語学における接触,干渉,2言語使用,借用」 ([2014-10-27-1])
・ 「#2079. fusion と mixture」 ([2015-01-05-1])
・ 「#4410. 言語接触の結果に関する大きな見取り図」 ([2021-05-24-1])
・ Heine, Bernd and Tania Kuteva. "Contact and Grammaticalization." Chapter 4 of The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 86--107.
・ Weinreich, Uriel. Languages in Contact: Findings and Problems. New York: Publications of the Linguistic Circle of New York, 1953. The Hague: Mouton, 1968.
2023-05-17 Wed
■ #5133. 言語項移動の類型論 [contact][borrowing][grammaticalisation][semiotics][semantic_borrowing][syntax][word_order][terminology][typology]
言語Aから言語Bへある言語項が移動することを "linguistic transfer" (言語項移動)と呼んでおこう.言語接触 (contact) において非常に頻繁に起こる現象であり,その典型的な現われの1つが語の借用 (borrowing) である.しかし,それだけではない.語の意味だけが移動する意味借用 (semantic_borrowing) もあれば,統語的な単位や関係が移動する例もある.音素(体系)の移動や語用論的項目の移動もあるかもしれない.一言で "linguistic transfer" といっても,いろいろな種類があり得るのだ.
Heine and Kuteva (87) は,5種類の言語項移動を認めている.
a. form, that is, sounds or combinations of sounds,
b. meanings (including grammatical meanings) or combinations of meanings,
c. form-meaning units,
d. syntactic relations, that is, the order of meaningful elements,
e. any combination of (a) through (d).
音形の移動を伴う a と c は,平たくいえば「借用」 (borrowing) である.一方,b と d は音形の移動を伴わない移動であり,先行研究にならって「複製」 (replication) と呼んでおこう.大雑把にいえば,借用はより具体的な項目の移動で,複製はより抽象的な項目の移動である.ちなみに e はすべてのごった煮である.この言語項移動の類型論は,意外とわかりやすいと思っている.
・ Heine, Bernd and Tania Kuteva. "Contact and Grammaticalization." Chapter 4 of The Handbook of Language Contact. Ed. Raymond Hickey. 2010. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2013. 86--107.
2023-05-13 Sat
■ #5129. 進行形に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][progressive][verb][irish_english][aspect]
「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1]) で参照した Filppula and Klemola の論文を再読している.同論文では,英語における be + -ing の「進行形」 (progressive form) の発達(その時期は中英語期とされる)も基層のケルト語の影響によるものではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が唱えられている.
まず興味深い事実として,現代のケルト圏で行なわれている英語諸変種では,標準英語よりも広範に進行形が用いられるという.具体的には Irish English, Welsh English, Hebridean English, Manx English において,標準的には進行形を取りにくいとされる状態動詞がしばしば進行形で用いられること,動作動詞を進行形にすることにより習慣相が示されること,would や used (to) に進行形が後続し,習慣的行動が表わされること,do や will に進行形が後続する用法がみられることが報告されている.Filppula and Klemola (212--14) より,それぞれの例文を示そう.
・ There was a lot about fairies long ago [...] but I'm thinkin' that most of 'em are vanished.
・ I remember my granfather and old people that lived down the road here, they be all walking over to the chapel of a Sunday afternoon and they be going again at night.
・ But they, I heard my father and uncle saying they used be dancing there long ago, like, you know.
・ Yeah, that's, that's the camp. Military camp they call it [...] They do be shooting there couple of times a week or so.
これらは現代のケルト変種の英語に見られる進行形の多用という現象を示すものであり,事実として受け入れられる.しかし,ケルト語仮説の要点は,中英語における進行形の発達そのものが基層のケルト語の影響によるものだということだ.前者と後者は注目している時代も側面も異なっていることに注意したい.それでも,Filppula and Klemola (218--19) は,次の5つの論点を挙げながら,ケルト語仮説を支持する(引用中の PF は "progressive forms" を指す).
(i) Of all the suggested parallels to the English PF, the Celtic (Brythonic) ones are clearly the closest, and hence, the most plausible ones, whether one think of the OE periphrastic constructions or those established in the ME and modern periods, involving the -ing form of verbs. This fact has not been given due weight in some of the earlier work on this subject.
(ii) The chronological precedence of the Celtic constructions is beyond any reasonable doubt, which also enhances the probability of contact influence from Celtic on English.
(iii) The socio-historical circumstances of the Celtic-English interface cannot have constituted an obstacle to Celtic substratum influences in the area of grammar, as has traditionally been argued especially on the basis of the research (and some of the earlier, too) has shown that the language shift situation in the centuries following the settlement of the Germanic tribes in Britain was most conductive to such influences. Again, this aspect has been ignored or not properly understood in some of the research which has tried to play down the role of Celtic influence in the history of English.
(iv) The Celtic-English contacts in the modern period have resulted in a similar tendency for some regional varieties of English to make extensive use of the PF, which lends indirect support to the Celtic hypothesis with regard to early English.
(v) Continuous tenses tend to be used more in bilingual or formerly Celtic-speaking areas than in other parts of the country . . . .
ケルト語仮説はここ数十年の間に提起され論争の的となってきた.いまだ少数派の仮説にとどまるといってよいが,伝統的な英語史記述に一石を投じ,言語接触の重要性に注目させてくれた点では,学界に貢献していると評価できる.
・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.
2023-02-28 Tue
■ #5055. 英語史における言語接触 --- 厳選8点(+3点) [contact][loan_word][borrowing][latin][celtic][old_norse][french][dutch][greek][japanese][link]
英語が歴史を通じて多くの言語と接触 (contact) してきたことは,英語史の基本的な知識である.各接触の痕跡は,歴史の途中で消えてしまったものもあるが,現在まで残っているものも多い.痕跡のなかで注目されやすいのは借用語彙だが,文法,発音,書記など語彙以外の部門でも言語接触のインパクトがあり得ることは念頭に置いておきたい.
英語の言語接触の歴史を短く要約するのは至難の業だが,Schneider (334) による厳選8点(時代順に並べられている)が参考になる.
・ continental contacts with Latin, even before the settlement of the British Isles (i.e., roughly between the second and fourth centuries AD);
・ contact with Celts who were the resident population when the Germanic tribes crossed the channel (in the fifth century and thereafter);
・ the impact of Latin through Christianization (beginning in the late sixth and seventh centuries);
・ contact with Scandinavian raiders and later settlers (between the seventh and tenth centuries);
・ the strong exposure to French as the language of political power after 1066;
・ the massive exposure to written Latin during the Renaissance;
・ influences from other European languages beginning in the Early Modern English period; and
・ the impact of colonial contacts and borrowings.
よく選ばれている8点だと思うが,私としてはここに3点ほど付け加えたい.1つは,伝統的な英語史では大きく取り上げられないものの,中英語期以降に長期にわたって継続したオランダ語との接触である.これについては「#4445. なぜ英語史において低地諸語からの影響が過小評価されてきたのか?」 ([2021-06-28-1]) やその関連記事を参照されたい.
2つ目は,上記ではルネサンス期の言語接触としてラテン語(書き言葉)のみが挙げられているが,古典ギリシア語(書き言葉)も考慮したい.ラテン語ほど目立たないのは事実だが,ルネサンス期以降,ギリシア語の英語へのインパクトは大きい.「#516. 直接のギリシア語借用は15世紀から」 ([2010-09-25-1]) および「#4449. ギリシア語の英語語形成へのインパクト」 ([2021-07-02-1]) を参照.
最後に日本語母語話者としてのひいき目であることを認めつつも,主に19世紀後半以降,英語が日本語と意外と濃厚に接触してきた事実を考慮に入れたい.これについては「#126. 7言語による英語への影響の比較」 ([2009-08-31-1]),「#2165. 20世紀後半の借用語ソース」 ([2015-04-01-1]),「#3872. 英語に借用された主な日本語の借用年代」 ([2019-12-03-1]),「#4140. 英語に借用された日本語の「いつ」と「どのくらい」」 ([2020-08-27-1]) を参照.
Schneider の8点に,この3点を加え,私家版の厳選11点の完成!
・ Schneider, Edgar W. "Perspectives on Language Contact." Chapter 13 of English Historical Linguistics: Approaches and Perspectives. Ed. Laurel J. Brinton. Cambridge: CUP, 332--59.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow