2024-03-09 Sat
■ #5430. 行為者接尾辞 -er は本来は動詞ではなく名詞の基体についた [analogy][reanalysis][agentive_suffix][suffix][morphology][word_formation][dutch][german]
-er は典型的な行為者接尾辞 (agentive_suffix) の1つである.一般に動詞の基体に付加することで,対応する行為者の名詞を作る接尾辞としてとらえられている.
しかし,この接尾辞は,本来は名詞の基体について「~に関係する人」ほどを意味する行為者名詞を作るものだった.例えば fisher (漁師)は,動詞 fish に -er がついたものと思われるかもしれないが,語源的には名詞 fish に -er がついたものなのである.
『英語語源辞典』の -er1 によると,もともとは名詞にのみ付加された接尾辞が,まず弱変化動詞にもつくようになり,さらに強変化動詞にもつくようになったという.なぜ接尾辞の適用範囲が動詞にも拡がったかといえば,まさに上に挙げた fish のような名詞と動詞を兼ねた基体が橋渡しとなり,再分析 (reanalysis) を促したのだろうと考えられる.
Fertig (35) が,この種の再分析の例として,まさに -er を取り上げている.
An even more striking example is the English/German/Dutch agentive suffix -er (< proto-Germanic *-ārjo-z). Originally, this suffix could only be attached to nouns to produce new nouns with the meaning 'person having something to do with X' (where X is the meaning of the base noun). This use can still be seen in Modern English words such as hatter and is highly productive with place names, e.g. English New Yorker; Dutch Amsterdammer; German Pariser, etc. In the older languages, we see this original use clearly in examples such as Gothic bôkareis/Old English bócere 'scribe', derived from the noun corresponding to Modern English book. As this example suggests, the construction was used especially to designate professions and occupations, and there was very often also a related denominal verb. In Gothic, for example, we find the basic noun dôm- 'judgment', the derived verb dômjan 'to judge' and the noun dômareis 'judge (i.e. person who judges)'. Nouns like dômareis were then reanalyzed as being derived from the verbs rather than directly from the basic nouns.
この接尾辞については,hellog でも多く取り上げてきた.以下の記事などを参照.
・ 「#1748. -er or -or」 ([2014-02-08-1])
・ 「#3791. 行為者接尾辞 -er, -ster はラテン語に由来する?」 ([2019-09-13-1])
・ 「#5392. 中英語の姓と職業名」 ([2024-01-31-1])
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-02-29 Thu
■ #5421. 最上級の -est は比較級の -er にもう1要素付け加わっただけ [superlative][comparison][adjective][suffix][reconstruction][indo-european][analogy]
へぇ,そうだったのか,という話題.
Fertig (34) によると,標題の通り,形容詞・副詞の最上級を標示する接尾辞 -est は,比較級の -er を基にした発展版ということらしい.
The superlative suffix -est, for example, is historically a combination of the ancestor of the -er comparative suffix (*-ôz-/*-iz- in proto-Germanic) followed by an originally separate *-to-.
もともとは *-ôz-/*-iz- と *-to- は別々の役割を果たす別々の接尾辞だったが,これが合わさる機会も多かったので,合わさった結果の形が1つの新しい接尾辞として理解されるようになったということだ.
これはちょうど現代英語で -ist と -ic が別々の接尾辞とみなされているが,合わさった -istic も1つの独立した接尾辞ととらえられ得る状況に比べられる.例えば cannibalistic において,切り出すべき接尾辞は -ist と -ic の2つと分析するよりも,-istic の1つと分析するほうが実際的だろう.というのは,*cannibalist という単語はないからだ.
これを教訓とすれば,比較級の -er は -ist に,最上級の -est は -istic に相当するということになろう.分かりやすいような分かりにくいような.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-02-21 Wed
■ #5413. ゲルマン祖語と古英語の1人称単数代名詞 [comparative_linguistics][personal_pronoun][pronoun][person][germanic][reconstruction][paradigm][oe][indo-european][rhotacism][analogy][sound_change]
Hogg and Fulk (202--203) を参照して,ゲルマン祖語 (Proto-Germanic) と古英語 (Old English) の1人称単数代名詞の格屈折を並べて示す.
| PGmc | OE | |
|---|---|---|
| Nom. | *ik | iċ |
| Acc. | *mek | mē |
| Gen. | *mīnō | mīn |
| Dat. | *miz | mē |
表の左側の PGmc の各屈折が,いかにして右側の OE の形態へ変化したか.ここにはきわめて複雑な類推 (analogy や音変化 (sound_change) やその他の過程が働いているという.Hogg and Fulk (203) の解説をそのまま引用しよう.
nom.sg.: *ik must have been the unstressed form, with analogical introduction of its vowel into the stressed form, with only ON ek showing retention of the original stressed vowel amongst the Gmc languages (cf. Lat egō/ǒ).
acc.sg.: *mek is the stressed form; all the other Gmc languages show generalization of unstressed *mik. The root is *me-, with the addition of *-k borrowed from the nom. The form mē could be due to loss of *-k when *mek was extended to unstressed positions, with lengthening of the final vowel when it was re-stressed . . . . More likely it represents replacement of the acc. by the dat. . . . as happened widely in Gmc and IE . . . .
gen.sg.: To the root *me- was added the adj. suffix *-īn- (cf. stǣnen 'made of stone' < *stain-īn-a-z . . .), presumably producing *mein- > *mīn- . . . . To this was added an adj. ending, perhaps nom.acc.pl. neut. *-ō, as assumed here.
dat.sg.: Unstressed *miz developed in the same way as *hiz . . . .
最後のところの PGmc *miz が,いかにして OE mē になったのかについて,Hogg and Fulk (198) を参照して補足しておこう.これはちょうど3人称男性単数主格の PGmc *hiz が OE *hē へ発達したのと平行的な発達だという.*hiz の z による下げの効果で *hez となり,次に語末子音が rhotacism を経て *her となった後に消失して *he となり,最後に強形として長母音化した hē に至ったとされる.
人称代名詞は高頻度の機能語として強形と弱形の交替が激しいともいわれるし,次々に新しい強形と弱形が生まれ続けるともされる.上記の解説を事情を概観するだけでも,比較言語学の難しさが分かる.関連して,以下の記事も参照.
・ 「#1198. ic → I」 ([2012-08-07-1])
・ 「#2076. us の発音の歴史」 ([2015-01-02-1])
・ 「#2077. you の発音の歴史」 ([2015-01-03-1])
・ 「#3713. 機能語の強音と弱音」 ([2019-06-27-1])
・ 「#3776. 機能語の強音と弱音 (2)」 ([2019-08-29-1])
・ Hogg, Richard M. and R. D. Fulk. A Grammar of Old English. Vol. 2. Morphology. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2024-01-25 Thu
■ #5386. 英語史上きわめて破格な3単過の -s [3ps][impersonal_verb][verb][inflection][agreement][analogy][shakespeare][link][methinks]
昨日の記事「#5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介」 ([2024-01-24-1]) の後半で少し触れましたが,近代英語期の半ばに methoughts なる珍妙な形態が現われることがあります.直説法・3人称・単数・過去,つまり「3単過の -s」という破格の語形です.生起頻度は詳しく調べていませんが,OED によると,Shakespeare からの例を初出として17世紀から18世紀半ばにかけて用例が文証されるようです.英語史上きわめて破格であり,希少価値の高い形態といえます(英語史研究者は興奮します).
OED の methinks, v. の異形態欄にて γ 系列の形態として掲げられている5つの例文を引用します.
a1616 Me thoughts that I had broken from the Tower. (W. Shakespeare, Richard III (1623) i. iv. 9)
1620 The draught of a Landskip on a piece of paper, me thoughts masterly done. (H. Wotton, Letter in Reliquiæ Wottonianæ (1651) 413)
1673 I had..coyned several new English Words, which were onely such French Words as methoughts had a fine Tone wieh them. (F. Kirkman, Unlucky Citizen 181)
1711 Methoughts I was transported into a Country that was filled with Prodigies. (J. Addison, Spectator No. 63. ¶3)
1751 The inward Satisfaction which I felt, had spread in my Eyes I know not what of melting and passionate, which methoughts I had never before observed. (translation of Female Foundling vol. I. 30)
methoughts の生起頻度を詳しく調べていく必要がありますが,いくつかの例が文証されている以上,単なるエラーで済ませるわけにはいきません.この形態の背景にあるのは,間違いなく3単現の形態で頻度の高い methinks でしょう.methinks からの類推 (analogy) により,過去形にも -s 語尾が付されたと考えられます.逆にいえば,このように類推した話者は,現在形 methinks の -s を3単現の -s として認識していなかったかとも想像されます.他の動詞でも3単過の -s の事例があり得るのか否か,疑問が次から次へと湧き出てきます.
実はこの methoughts という珍妙な過去形の存在について最初に教えていただいたのは,同僚のシェイクスピア研究者である井出新先生(慶應義塾大学文学部英米文学専攻)でした.その経緯は,先日の YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」にて簡単にお話ししました.「#195. 井出新さん『シェイクスピア,それが問題だ! --- シェイクスピアを楽しみ尽くすための百問百答』(大修館書店)のご紹介」をご覧ください.
関連して,井出先生とご近著について,以下の hellog および heldio でもご紹介していますので,ぜひご訪問ください.
・ hellog 「#5357. 井出新先生との対談 --- 新著『シェイクスピア それが問題だ!』(大修館,2023年)をめぐって」 ([2023-12-27-1])
・ heldio 「#934. 『シェイクスピア,それが問題だ!』(大修館,2023年) --- 著者の井出新先生との対談」
英語史にはおもしろい問題がゴロゴロ転がっています.
・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.
2024-01-24 Wed
■ #5385. methinks にまつわる妙な語形をいくつか紹介 [3ps][impersonal_verb][verb][syntax][inflection][hc][agreement][analogy][shakespeare][methinks]
非人称動詞 (impersonal_verb) の methinks については「#4308. 現代に残る非人称動詞 methinks」 ([2021-02-11-1]),「#204. 非人称構文」 ([2009-11-17-1]) などで触れてきた.非人称構文 (impersonal construction) では人称主語が現われないが,文法上その文で用いられている非人称動詞はあたかも3人称単数主語の存在を前提としているかのような屈折語尾をとる.つまり,大多数の用例にみられるように,直説法単数であれば,-s (古くは -eth) をとるということになる.
ところが,用例を眺めていると,-s などの子音語尾を取らないものが散見される.Wischer (362) が,Helsinki Corpus から拾った中英語の興味深い例文をいくつか示しているので,それを少々改変して提示しよう.
(10) þe þincheð þat he ne mihte his sinne forlete.
'It seems to you that he might not relinquish his sin.'
(MX/1 Ir Hom Trin 12, 73)
(11) Thy wombe is waxen grete, thynke me.
'Your womb has grown big. You seem to be pregnant.'
(M4 XX Myst York 119)
(12) My lord me thynketh / my lady here hath saide to you trouthe and gyuen yow good counseyl [...]
(M4 Ni Fict Reynard 54)
(13) I se on the firmament, Me thynk, the seven starnes.
(M4 XX Myst Town 25)
子音語尾を伴っている普通の例が (10) と (12),伴っていない例外的なものが (11) と (13) である.(11) では論理上の主語に相当する与格代名詞 me が後置されており,それと語尾の欠如が関係しているかとも疑われたが,(13) では Me が前置されているので,そういうことでもなさそうだ.OED の methinks, v. からも子音語尾を伴わない用例が少なからず確認され,単純なエラーではないらしい.
では語尾欠如にはどのような背景があるのだろうか.1つには,人称構文の I think (当然ながら文法的 -s 語尾などはつかない)との間で混同が起こった可能性がある.もう1つヒントとなるのは,当該の動詞が,この動詞を含む節の外部にある名詞句に一致していると解釈できる例が現われることだ.OED で引用されている次の例文では,methink'st thou art . . . . というきわめて興味深い事例が確認される.
a1616 Meethink'st thou art a generall offence, and euery man shold beate thee. (W. Shakespeare, All's Well that ends Well (1623) ii. iii. 251)
さらに,動詞の過去形は3単「現」語尾をとるはずがないので,この動詞の形態は事実上 methought に限定されそうだが,実際には現在形からの類推 (analogy) に基づく形態とおぼしき methoughts も,OED によるとやはり Shakespeare などに現われている.
どうも methinks は,動詞としてはきわめて周辺的なところに位置づけられる変わり者のようだ.中途半端な語彙化というべきか,むしろ行き過ぎた語彙化というべきか,分類するのも難しい.
・ Wischer, Ilse. "Grammaticalization versus Lexicalization: 'Methinks' there is some confusion." Pathways of Change: Grammaticalization in English. Ed. Olga Fischer, Anette Rosenbach, and Dieter Stein. Amsterdam: John Benjamins, 2000. 355--70.
2024-01-19 Fri
■ #5380. 類推は言語が変化しないことをも説明できる [analogy][language_change][plural][voicy][heldio]
Fertig (76) は "Analogical non-change" と題する節のなかで,英語の規則的な複数形を作る -s を題材にして,類推作用 (analogy) の役割について独特な視点から論じている.
. . . stasis over time can be just as interesting a historical phenomenon as change (Janda and Joseph 2003: 83, 86). Although accounts of analogy rarely call attention to the fact, there are a number of examples in the literature where the mechanisms of morphological change are invoked to account for an absence of overt change, i.e. for the survival of an element, construction or distinction. Saussure (1995 [1916]: 236--7) reminds us that analogy2 is just as much responsible for the lack of change in the inflection of most forms that have always belonged to dominant, regular classes as it is for change in other, primarily irregular items. English speakers, for example, form the plural of dozens of nouns such as stone, eel, oath, comb, stool, etc. essentially the same way they were formed in Old English, not because each of these plurals has been transmitted perfectly across all the generations, but rather primarily because analogy2 yields exactly the same results as if the forms had been transmitted perfectly. These nouns all belong to the dominant class that formed their plurals with -as in Old English so even if English speakers never memorize any of them and always rely on analogy2 to recreate them, they continue to come up with the same forms that were used in the past.
Fertig は,言語の変化のみならず言語の無変化の背景にも関心を寄せる論者である.「#4228. 歴史言語学は「なぜ変化したか」だけでなく「なぜ変化しなかったか」をも問う」 ([2020-11-23-1]) でも,Fertig からの重要な指摘を引用している.言語の無変化にも意義があるという議論については「#2115. 言語維持と言語変化への抵抗」 ([2015-02-10-1]),「#2208. 英語の動詞に未来形の屈折がないのはなぜか?」 ([2015-05-14-1]),「#2220. 中英語の中部・北部方言で語頭摩擦音有声化が起こらなかった理由」 ([2015-05-26-1]),「#2574. 「常に変異があり,常に変化が起こっている」」 ([2016-05-14-1]) も参照されたい.
今年の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の主題は言語変化 (language) だが,同様に言語無変化も取り上げていきたい.新年の2回の配信回もぜひお聴きください.
・ 「#945. なぜ言語は変化するのか?」 (2024/01/01)
・ 「#947. なぜ言語は変化しないのか?」 (2024/01/03)
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-01-18 Thu
■ #5379. blend は形態理論や韻律理論にとっても有意義な現象である [blend][morphology][frequency][word_formation][prosody][analogy]
近年,英語語彙に blend (混成語)が激増している事実については,すでに hellog でも繰り返し取り上げてきた.
・ 「#631. blending の拡大」 ([2011-01-18-1])
・ 「#876. 現代英語におけるかばん語の生産性は本当に高いか?」 ([2011-09-20-1])
・ 「#4369. Brexit --- 現代の病理と遊びの語形成」 ([2021-04-13-1])
一見すると blend は人目を引く言葉遊びにすぎず,形態論上あくまで周辺的な現象にとどまると思われるかもしれない.しかし,近年の英語語形成におけるその生産性の高さは,従来の見方を変えつつある.例えば,Fertig (70) は,混成という語形成が理論的な意義をもつことを次のように力説している.
Blends are often treated as a marginal phenomenon (Haspelmath and Sims 2010:40). Aronoff discusses them under the heading 'oddities' and considers them 'words which have no recognizable internal structure or constituents'; they are 'opaque, and hence uncommon' (1976: 20). Recent developments suggest that Aronoff may have had the relationship between opacity and frequency backwards here. Blends may have been rather opaque in 1976 precisely because they were still relatively uncommon. Today, at least in English, blends (of certain types) can hardly be called uncommon, and we generally seem to have little trouble parsing and processing them. As we will see in §7.3.8, this issue of the relationship between the frequency of a morphological pattern and its transparency/opacity has implications for some fundamental theoretical issues of great relevance to morphological change.
To the extent that some types of blending have become productive and predictable morphological operations in present-day English, it is no longer accurate to classify them as non-proportional. They amount to a kind of compounding with the two elements overlapping in accordance with well defined constraints. Within Paul's proportional theory, they could thus be handled by an extension of the (syntagmatic) proportional equations that he proposes for syntax (see §6.2 below). Blending as a type of word formation would fit even more easily into certain other theories of morphology. Insights and analytical tools from Prosodic Morphology (McCarthy and Prince 1995) have made it clear that (most) blends absolutely do have 'recognizable internal structure'. They are a type of non-concatenative morphology. Instead of combining two words into a linear string as in compounding, blends superimpose one word onto the prosodic structure of another (Piñeros 1998, 2004).
従来,混成語は形態論的には内部構造が不透明とみなされてきた.しかし,それは混成による語形成の生産性がまだ低かったために十分に解明されておらず,「不透明」とのレッテルを貼られてきただけなのではないか.混成語が横溢している現在,使用者もすっかり慣れ,むしろ透明性が高くなってきたといえるのではないか.そして,遅ればせながら,形態理論や音韻理論による解明のメスが入り始めたのではないか,とそのような議論である.
韻律形態論 (Prosodic Morphology) という分野が提唱されているようであり,さらに「#3722. 混成語は右側主要部の音節数と一致する」 ([2019-07-06-1]) でみた通り,混成語に特徴的な韻律上の制限も確かにあるようだ.今後の混成語言語学の展開に期待したい.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-01-17 Wed
■ #5378. 歴史的に正しい民間語源? [folk_etymology][spelling_pronunciation][etymological_respelling][analogy][hypercorrection]
一般に「民間語源」 (folk_etymology) は勘違いの語源解釈とみなされている.歴史的に真実の語源(しばしば「学者語源」といわれる)とは異なる誤った語源説として言及されることが多い.
しかし,古今東西,言語には民間語源の事例は多く,むしろ言語変化の重要な原動力の1つであると積極的に評価することもできる.このポジティヴな見方については「#2174. 民間語源と意味変化」 ([2015-04-10-1]) や「#5180. 「学者語源」と「民間語源」あらため「探究語源」と「解釈語源」 --- プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) の最新回より」 ([2023-07-03-1]) などで取り上げてきた.
Fertig による類推 (analogy) に関する本を読んでいて,民間語源が関与した結果,歴史的に正しい形に戻る事案,つまり「歴史的に正しい民間語源」の例があることを知った.関連する箇所を引用する.
The fact that we say churchyard rather than *churchard, which would show the normal phonetic reduction of the second, more weakly stressed element of the compound (as in orchard), and the widespread pronunciation of forehead as /fɔrhɛd/ rather than reduced /fɔrɪd/ can be ascribed to speakers analyzing these compounds just as they do in cases of folk etymology, the only difference being that here their analysis is historically accurate.
いったんこの民間語源の捉え方を知ってしまうと,コトバの見え方がガラッと変わる.forehead に代表される綴字発音 (spelling_pronunciation) には「歴史的に正しい民間語源」の例が多そうだが,すると昨今 often を [ˈɔ:fn] ではなく [ˈɔ:ftən] と発音したり,assume を[əˈʃu:m] ではなく [əˈsju:m] と発音するようになってきているのも,正しい民間語源の例だったのか,と気づくに至る.
さらに考えを進めていくと,もともとラテン語由来の単語だ(ろう)からという知識に基づき,doute に <b> を挿入して doubt などと綴りだした語源的綴字 (etymological_respelling) の現象も,結果的には歴史的に正しい語源形に近づいていったという点で「歴史的に正しい民間語源」の仲間とも言えそうだ.ただし,ここには意図性の有無という基準も関わってきそうであり,どのような点で仲間といえるのかは問題となるかもしれない.
Fertig は "hypercorrective folk etymology" 「修正しすぎの民間語源」 (60--61) と表現しているが,この現象,いなこの見方は新鮮で興味深い.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2024-01-13 Sat
■ #5374. 類推および関連する過程を例示する英文 --- Fertig の冒頭より [analogy][backformation][folk_etymology][morphology][language_change][voicy][heldio]
一昨日の heldio で「#955. 妙な英文で味わうアナロジー(および関連する過程)」を配信した.本ブログでも同じ話題をカバーしておきたい.
「#4229. Fertig による analogy の定義」 ([2020-11-24-1]) や「#5336. Fertig による analogy の本格的研究書の目次」 ([2023-12-06-1]) で紹介した Fertig の analogy に関する研究書の冒頭は,次のような英文の例示で飾られる.
A book about analogy and morphological change? That is so not what I was expecting. I never imaginated there'd ever be such a book. I guess I had another thing coming. Who'd of thunk it?
この英文には類推 (analogy) およびそれと関連する言語革新の過程を示す事例が4つ(あるいは5つ)含まれている.すべてが類推の事例,あるいは類推に似ている事例である.それぞれを解説する1節も引用しておきたい.
The short paragraph above contains at least four recognizable examples of some of the different kinds of innovations that we will be exploring in this book. That is so not . . . is an example of analogical change in syntax. Until recently, the intensifier so could only be used directly before an adjective or adverb. Now some speakers regularly use it in other syntactic contexts, such as before the negative particle not. This change can be attributed to the analogy of other intensifiers such as really . . . . The next sentence contains the verb imaginate, which sounds very odd to many English speakers today but has been around since 1541. It means the same thing as the much more common and older verb imagine and may have been created by backformation from the noun imagination, on the analogical model of pairs like speculation--speculate, dedication--dedicate, etc. The fourth sentence contains an altered version of the familiar expression to have another think coming, meaning 'to be seriously mistaken about something'. For at least a century, English speakers/learners have sometimes mistaken the word think in this expression for thing. This kind of change is called folk etymology. It occurs when speakers identify one element in an expression with a different, often historically unrelated element. The word of (for 've) in the final sentence of the paragraph could also be considered folk etymology. Finally, thunk is obviously an innovative past-participle form corresponding to standard thought. It is based on analogical models such as sink--sank--sunk or stick--stuck.
ここから太字表記のものも含めいくつかキーワードと拾うと,innovations, analogical change, backformation, analogical model, folk_etymology などが挙がってくる.Fertig の本では,これらの用語や概念が丁寧に議論されていく.言語における類推(作用)の研究の必読書である.
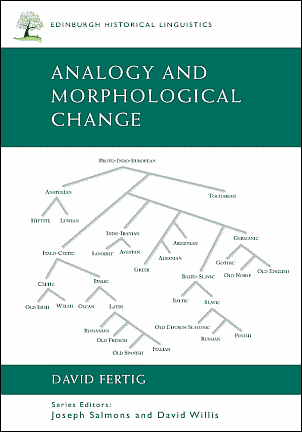
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2023-12-06 Wed
■ #5336. Fertig による analogy の本格的研究書の目次 [analogy][toc][terminology][voicy][heldio]
言語変化の説明原理の1つ analogy (類推作用)については,本ブログでも多くの記事を書いてきた.言語学史上,analogy は軽視されてきたきらいがある.規則的とされる音変化に対し,その規則から外れる例外事項は analogy という「ゴミ箱」に投げ捨てられてきた経緯がある.ここには,analogy が言語変化の説明原理としてある意味で強力すぎるという点も関係しているのかもしれない.analogy のこのような日陰者ぶりについては,hellog 「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1]) や Voicy heldio 「#911. アナロジーは言語変化のゴミ箱!?」も参照されたい.
このような言語学史上の事情により,言語変化における analogy に真正面から切り込んだ研究書は多くない.そのなかでも本格派といえるのが,本ブログでも何度か参照してきた David Fertig による Analogy and Morphological Change (Edinburgh UP, 2013) である.本格派であることは,以下に掲げる目次の細かさからも伝わるのではないか.analogy でここまで語れるとは!
1 Fundamental Concepts and Issues
1.1 Introduction
1.2 Essential Historical Background: Hermann Paul and the Neogrammarian Period
1.3 Preliminary (Narrow) Definitions
1.4 Conceptual and Terminological Fundamentals
1.4.1 The term 'analogy'
1.4.2 Analogy vs. analogical innovation/change
1.4.3 Speaker-oriented approaches
1.4.4 Change vs. diachronic correspondence
1.4.5 Innovation vs. change
1.4.6 Defining historical linguistics
1.5 Clarifying the Definition of Analogical Innovation/Change
1.5.1 Narrow vs. broad definitions of analogical innovation
1.5.2 Toward a more adequate definition of analogical innovation/change
1.5.3 Some other definitions
1.6 Analogical Change as Opposed to What?
1.6.1 Analogy vs. reanalysis
1.6.2 Analogy2 and sound change
1.6.3 2 and language contact
1.6.4 Changes attributable to extra-grammatical factors
1.6.5 What about grammaticalization?
1.7 Proportions and Proportional Equations
1.8 Why Study Analogy and Morphological Change?
2 Basic Mechanisms of Morphological Change
2.1 Introduction
2.2 Defining (Re)analysis
2.3 Associative Interference
2.4 (Re)analysis, Analogy2 and Grammatical Change
2.4.1 history, synchrony, diachrony, panchrony
2.4.2 'Language change is grammar change'?
2.4.3 The role of transmission/acquisition in grammatical innovation
2.4.4 The relationship of analogical innovation to grammatical change in static and dynamic models of mental grammar
2.5 Types of Morphological Reanalysis
2.5.1 D-reanalysis
2.5.2 C-reanalysis
2.5.3 B-reanalysis
2.5.4 A-reanalysis
2.5.5 Summary of A-, B-, C- and D-reanalysis
2.5.6 Exaptation
2.6 Chapter Summary
3 Types of Analogical Change, Part 1: Introduction and Proportional Change
3.1 Introduction
3.2 Outcome-Based vs. Motivation-Based Classifications
3.3 Terminology and Terminological Confusion
3.4 Proportional vs. Non-Proportional Analogy
3.5 Morphological vs. Morphophonological Change
3.6 A Critical Overview of Traditional Subtypes of Proportional Change
3.6.1 Four-part analogy
3.6.2 Extension
3.6.3 Backformation
3.6.4 Regularization and irregularization
3.6.5 Item-by-item vs. across-the-board change
4 Types of Analogical Change, Part 2: Non-Proportional Change
4.1 Introduction
4.2 Folk Etymology
4.3 Confusion of Similar-Sounding Words
4.4 Contamination and Blends
4.4.1 Contamination
4.4.2 Double marking of grammatical categories
4.4.3 Blends and related phenomena
5 Types of Analogical Change, Part 3: Problems and Puzzles
5.1 A Problem Child for Classification Schemes: Paradigm Leveling
5.2 Analogical Non-Change
5.3 Phantom Analogy
5.3.1 'Regularization is much more common than irregularization': a case study in circular reasoning
5.4 Summary of Types of Analogical Change (Chapters 3--5)
6 Analogical Change beyond Morphology
6.1 Introduction
6.2 Syntactic Change
6.3 Lexical (Semantic) Change
6.4 Morphophonological Change
6.5 Phonological Change
6.6 Regular Sound Change as Analogy
6.7 The Interaction of Analogy2 and Sound Change
6.7.1 Sturtevant's so-called paradox
6.7.2 'Therapy, not Prophylaxis'
6.8 Chapter Summary
7 Constraints on Analogical Innovation and Change
7.1 Introduction
7.2 Predictability and Directionality
7.3 Constraints on the Interparadigmatic Direction of Change
7.3.1 Analogical change as 'optimization'
7.3.2 Formal simplification/optimization of the grammar
7.3.3 Preference theories
7.3.4 System-independent constraints
7.3.5 System-dependent constraints
7.3.6 Analogical extension of patterns with initially low type frequency
7.3.7 System-dependent naturalness vs. formal simplicity/optimality
7.3.8 Universal preferences and 'evolutionary' grammatical theory
7.4 Constraints on the Intraparadigmatic Direction of Change
7.5 Token Frequency
7.6 Teleology
7.7 Chapter Summary
8 Morphological Change and Morphological Theory
8.1 Introduction
8.2 Grammatical Theory and Acquisition
8.3 The Nature and Significance of Linguistic Universals
8.4 Static vs. Dynamic conceptions of Grammar
8.5 Exemplar-Based vs. Rule-Based Models
8.6 Analogy vs. Rules
8.6.1 Dual-mechanism models
8.7 Rules vs. Constraints
8.8 Syntagmatic/Compositional vs. Paradigmatic/Configurational Approaches to Morphology
8.8.1 Asymmetric vs. symmetric paradigmatic models
8.8.2 Paul's proportional model
8.9 Chapter Summary
References
Index
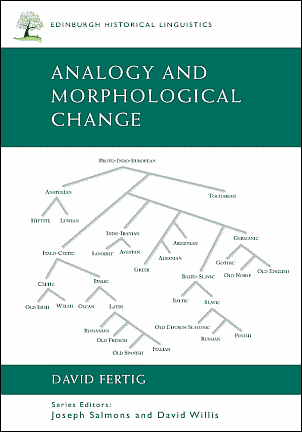
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2023-11-12 Sun
■ #5312. 「ゆる言語学ラジオ」最新回は「不規則動詞はなぜ存在するのか?」 [yurugengogakuradio][verb][inflection][conjugation][sobokunagimon][frequency][voicy][heldio][youtube][link][notice][numeral][suppletion][analogy]
昨日,人気 YouTube/Podcast チャンネル「ゆる言語学ラジオ」の最新回が配信されました.今回は英語史ともおおいに関係する「不規則動詞はなぜ存在するのか?【カタルシス英文法_不規則動詞】#280」です.
ゆる言語学ラジオの水野太貴さんには,拙著,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio),および YouTube チャンネル「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」のいくつかの関連コンテンツに言及していただきました.抜群の発信力をもつゆる言語学ラジオさんに,この英語史上の第一級の話題を取り上げていただき,とても嬉しいです.このトピックの魅力が広く伝わりますように.
概要欄に掲載していただいたコンテンツ等へのリンクを,こちらにも再掲しておきます.
・ 拙著 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』(研究社,2016年)
・ 拙著 『英語史で解きほぐす英語の誤解 --- 納得して英語を学ぶために』(中央大学出版部,2011年)
・ heldio 「#58. なぜ高頻度語には不規則なことが多いのですか?」
・ YouTube 「新説! go の過去形が went な理由」 (cf. 「#4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である」 ([2022-05-23-1]))
・ YouTube 「英語の不規則活用動詞のひきこもごも --- ヴァイキングも登場!」 (cf. hellog 「#4810. sing の過去形は sang でもあり sung でもある!」 ([2022-06-28-1]))
・ YouTube 「昔の英語は不規則動詞だらけ!」 (cf. 「#4807. -ed により過去形を作る規則動詞の出現は革命的だった!」 ([2022-06-25-1]))
・ heldio 「#9. first の -st は最上級だった!」
・ heldio 「#10. third は three + th の変形なので準規則的」
・ heldio 「#11. なぜか second 「2番目の」は借用語!」
「不規則動詞はなぜ存在するのか?」という英語に関する素朴な疑問から説き起こし,補充法 (suppletion) の話題(「ヴィヴァ・サンバ!」)を導入した後に,不規則形の社会言語学的意義を経由しつつ,全体として言語における「規則」あるいは「不規則」とは何なのかという大きな議論を提示していただきました.水野さん,堀元さん,ありがとうございました! 「#5130. 「ゆる言語学ラジオ」周りの話題とリンク集」 ([2023-05-14-1]) もぜひご参照ください.
2023-06-07 Wed
■ #5154. なぜ height はこの綴字でこの発音なの? [spelling_pronunciation_gap][sobokunagimon][gvs][analogy][vowel][consonant][spelling][pronunciation]
形容詞 high と名詞 height は,それぞれ /haɪ/, /haɪt/ と発音されます.綴字と発音の関係について,前者は規則通りと考えられますが,後者は例外的です.これはなぜでしょうか.
まず high の綴字と発音の発達を振り返ってみましょう.古英語 hēah は中英語にかけて hēh > hēih > heih/hīh と発達しました.最後の段階で異形が2つ現われますが,後者の hīh が大母音推移を経て現代英語の high /haɪ/ に至ります.前者の heih は中英語ではむしろ有力でしたが,後に high に首席を明け渡しました.
ちなみに,古英語 nēah "near" もまったく同じ発達を遂げています.中英語にかけて nēh > nēih > neih/nīh と変化しました.最終段階の異形のうち前者は neighbour の第1要素に現われており,後者は nigh に連なります.
さて,名詞 height の古英語の形態は hēhþu でした.これは形容詞 hēah と歩調を揃えて中英語にかけて語形を発達させていき,hēhþ > hēihþ > heiht に帰着しました.ただし,形容詞と異なり,最後の段階に予想される異形 *hīht はありませんでした.名詞接尾辞に含まれる þ が後続する環境では,形容詞には生じた音変化が抑止されたからです.
こうして,名詞の綴字については,その後に綴字の若干の変化を経つつも height に落ち着きました.ところが,発音のほうは形容詞に引きつけられるようにして /haɪt/ で定着しました.こうして発音と綴字の複雑な発達過程と類推作用の結果, height ≡ /haɪt/ というちぐはぐな関係になってしまったのです.
以上,Prins (97) を参照して執筆しました.関連して,heldio より「#595. heah/hih/high --- 「ゆる言語学ラジオ」から飛び出した通時的パラダイム」をご参照ください.
・ Prins, A. A. A History of English Phonemes. 2nd ed. Leiden: Leiden UP, 1974.
2022-11-05 Sat
■ #4940. 再分析により -ess から -ness へ [reanalysis][metanalysis][analogy][suffix][morpheme]
形態論的な再分析 (reanalysis) にはいくつかの種類があるが,今回は Fertig (32) を引用しつつ,名詞化接尾辞 -ness が実は -ess に由来するという事例を紹介する.
This [type of reanalysis] occurs frequently when the reanalysis affects the location of a boundary between stem and affix. A well-known example involves the Germanic suffix that became English -ness. The corresponding suffix in proto-Germanic was -assu. This suffix was frequently attached to stems ending in -n, and this n was subsequently reanalyzed as belonging to the suffix rather than the stem. In Old English, we find examples based on past participles, such as forgifeness 'forgiveness', which could still be analyzed as forgifen + ess, but also many instances based on adjectives, such as gōdness 'goodness' or beorhtness 'brightness', which provide unambiguous evidence of the reanalysis and the new productive rule of -ness suffixation . . . . Similar reanalyses give us the common Germanic suffix -ling --- as in English darling, sapling, nestling, etc. --- from attachment of -ing (OED -ing, suffix3 'one belonging to') to stems ending in l, as well as the German suffixes -ner and -ler, attributable to words where -er was attached to stems ending in -n or -l and then extended to give us new words such as Rentner 'pensioner' < Rente 'pension' and Sportler 'sportsman'.
『英語語源辞典』よりもう少し補っておこう.接尾辞 -ness は強変化過去分詞の語尾に現われる n が,ゲルマン祖語の弱変化動詞の接辞 *-atjan に由来する *-assus (後の古英語の -ess)に接続したものである.つまり n は本来は基体の一部だったのだが,それが接尾辞 -ess と一体化して,-ness なる新たな接尾辞ができたというわけだ.
オランダ語 -nis,ドイツ語 -nis,ゴート語 -inassus のような平行的な例がゲルマン諸語に確認されることから,この再分析の過程はゲルマン祖語の段階で起こっていたと考えられる.ゲルマン諸語間の母音の差異については不詳である.英語内部でみても初期中英語では -nes(se) と -nis(se) が併存していたが,後期中英語以降は前者が優勢となった.
身近な -ness という接尾辞1つをとっても,興味深い歴史が隠れているものだ.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
・ 寺澤 芳雄(編) 『英語語源辞典』 研究社,1997年.
2022-02-18 Fri
■ #4680. Bybee による言語変化の「なぜ」 [language_change][causation][how_and_why][multiple_causation][cognitive_linguistics][usage-based_model][context][analogy]
言語変化論の第一人者である Bybee (9) が,標題の問題について大きな答えを与えている.
A very general answer is that the words and constructions of our language change as they cycle through our minds and bodies and are passed through usage from one speaker to another.
言語変化の「なぜ」というより「どのように」への答えに近いのではないかと考えられるが,いずれにせよこの1文だけで Bybee の言語変化観の枠組みをつかむことができる.一言でいえば,認知基盤および使用基盤の言語変化観である.
続けて Bybee は,言語変化には3つの傾向が見いだされると主張する.引用により,その3点の骨子を示す.
Because language is an activity that involves both cognitive access (recalling words and constructions from memory) and the motor routines of production (articulation), and because we use the same words and constructions many times over the course of a day, week, or year, these words and constructions are subject to the kinds of processes that repeated actions undergo. (9)
Another pervasive process in the human approach to the world is the formation of patterns from our experience and application of these patterns to new experiences or ideas. (10)
The other major factor in language change is the way words or patterns of language are used in context. Very often the meaning supplied by frequently occurring contexts can lead to change. Words and constructions that are used in certain contexts become associated with those contexts. (10)
1つめは認知・運動基盤,2つめは広い意味での類推作用 (analogy),3つめは使用基盤 (usage-based_model) と言い換えてもよいだろう.
・ Bybee, Joan. Language Change. Cambridge: CUP, 2015.
2022-01-20 Thu
■ #4651. なぜ fire から派生した形容詞 fiery はこの綴字なのですか? [sobokunagimon][spelling][pronunciation][adjective][gvs][vowel][syllable][analogy][suffix]
この素朴な疑問は私も長らくナゾだったのですが,最近ゼミの学生に指摘してもらう機会があり,改めて考え出した次第です.fire に派生接尾辞 -y を付すのであれば,そのまま *firy でよさそうなものですが,なぜ fiery となるのでしょうか.expire → expiry, mire → miry, spire → spiry, wire → wiry などの例はあるのですが,fire → fiery のタイプは他に例がないようなので,ますます不思議です.
暫定的な答え,あるいはヒントとしては,近代英語期に fire が1音節ではなく2音節で,fiery が2音節ではなく3音節で発音されたことが関係するのではないかと睨んでいます.
教科書的にいえば,中英語の [fiːr], [ˈfiː ri] は大母音推移 (gvs) を経て各々 [fəɪr], [ˈfəɪ ri] へ変化しました.長母音が2重母音に変化しただけで,音変化の前後でそれぞれ音節数に変化はありませんでした.
しかし,語幹末の r の影響で,その直前に渡り音として曖昧母音 [ə] が挿入され,それが独立した音節の核となるような発音が,初期近代英語期には変異形として存在したようなのです.要するに fi-er, fi-e-ry のようなプラス1音節の異形態があったということです.似たような音構成をもつ語について,その旨の報告が同時代からあります.Jespersen (§11.11)の記述を見てみましょう.
The glide before /r/ was even before that time [= 1588 or †1639] felt as a distinct vowel-sound [ə], especially after the new diphthongs that took the place of /iˑ, uˑ/. This is shown by the spelling in some cases after ow: shower < OE scūr bower < OE būr . cower < Scn kūra . lower by the side of lour < Scn lūra 'look gloomy'. tower < F tour; cf. on flower and flour 3.49. Thus also after i in brier, briar, frier, friar, ME brere, frere; fiery, fierie, fyeri (from the 16th c.) for earlier fyry, firy. The glide-vowel [ə] is also indicated by Hart's phonetic spellings 1569: [feiër/ fire (as /heiër/) higher) . /meier/ mire /oˑer/ oar . [piuër] pure . /diër/ dear . [hier/ here (hie r, which also occurs, many be a misprint).
要するに,fire の形容詞形に関する限り,もともとは発音上2音節であり,綴字上も2音節にみえる由緒正しい firy もあったけれども,初期近代英語期辺りには発音上渡り音が挿入されて3音節となり,綴字上もその3音節発音を反映した fiery が併用されたということのようです.そして,もとの名詞でも同じことが起こっていたと.
ところが,現代英語の観点から振り返ってみると,名詞では渡り音を反映していないかのような fire の綴字が標準として採用され,形容詞では渡り音を反映したかのような fiery の綴字が標準として採用されてしまったように見えます.どうやら,英語史では典型的な(というよりも,お得意の)「ちぐはぐ」が,ここでも起こってしまったということではないでしょうか.
あるいは,意味上の「激しさ」つながりで連想される形容詞 fierce との綴字上の類推 (analogy) もあったかもしれないと疑っています.いかがでしょうか.
上の引用でも触れられていますが,flower と flour が,同語源かつ同じ発音でありながらも,異なる綴字に分化した事情と,今回の話題は近いように思われます.「#183. flower と flour」 ([2009-10-27-1]),「#2440. flower と flour (2)」 ([2016-01-01-1]),および 「flower (花)と flour (小麦粉)は同語源!」 (heldio) も参照ください.
・ Jespersen, Otto. A Modern English Grammar on Historical Principles. Part 1. Sounds and Spellings. London: Allen and Unwin, 1909.
2021-09-06 Mon
■ #4515. <gn> の発音 [phonetics][consonant][spelling][phoneme][nasal][etymological_respelling][analogy][silent_letter]
英語の綴字 <gn> について,語頭に現われるケースについては <kn> との関係から「#3675. kn から k が脱落する音変化の過程」 ([2019-05-20-1]) の記事で簡単に触れた.16--17世紀に [gn] > [n] の過程が生じたということだった.では,語頭ではなく語中や語末に <gn> の綴字をもつ,主にフランス語・ラテン語由来の語について,綴字と発音の関係に関していかなる対応があるだろうか.Carney (247, 325) を参照してみよう.
まず <gn(e)> が語末にくる例を挙げてみよう.arraign, assign, benign, campaign, champagne, cologne, deign, design, ensign, impugn, malign, reign, resign, sign などが挙がってくる.これらの語においては <g> は黙字として機能しており,結果として <gn(e)> ≡ /n/ の関係となっている.ちなみに foreign と sovereign は非歴史的な綴字で,勘違いを含んだ語源的綴字 (etymological_respelling) あるいは類推 (analogy) の産物とされる.
ただし,上記の単語群の派生語においては <g> と <n> の間に音節境界が生じ,発音上 /g/ と/n/ が別々に発音されることが多い.assignation, benignant, designate, malignant, regnant, resignation, signature, significant, signify の通り.
上記の単語群のソースとなる言語はたいていフランス語である.フランス語では <gn> は硬口蓋鼻音 [ɲ] に対応するが,英語では [ɲ] は独立した音素ではないため,英語に取り込まれる際には,近似する歯茎鼻音 [n] で代用された.[ɲ] に近い音として英語には [nj] もあり得るのだが,音素配列的に語末には現われ得ない規則なので,結果的に [n] に終着したことになる.なお,語末でなければ /nj/ で取り込まれたケースもある.例えば,cognac, lorgnette, mignonette, vignette などである.イタリア語からの Bologna, Campagna も同様.poignant については,/nj/ のほか /n/ の発音もある.
綴字について妙なことが起こったのは,フランス語 ligne に由来する line である.本来であればフランス語 signe が英語に取り込まれて <sign> ≡ /saɪn/ として定着したように,ligne も英語では <lign> ≡ /laɪn/ ほどで定着していたはずと想像される.だが,後者については英語的な綴字規則に則って <line> と綴り替えられて現在に至る.これに接頭辞をつけた動詞形にあっては <align> が普通の綴字(ただし aline もないではない)であるし,別に sign/assign というペアも見られるだけに,<line> はなんとも妙である.
line/align という語幹を共有する語の綴字上のチグハグは,ほかにも deign/disdain や feign/feint に見られる (Upward and Davidson 140) .
・ Carney, Edward. A Survey of English Spelling. Abingdon: Routledge, 1994.
・ Upward, Christopher and George Davidson. The History of English Spelling. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2011.
2021-02-13 Sat
■ #4310. shall's (= shall us = shall we) は初期近代英語期でそこそこ使われていた [eebo][personal_pronoun][speech_act][analogy]
昨日の記事「#4309. shall we の代わりとしての shall's (= shall us)」 ([2021-02-12-1]) で取り上げたように,shall we の代用としての shall's は Shakespeare などにもみられる.関心をもって,初期近代英語の巨大コーパス EEBO corpus により "shall 's" と "shal 's" で検索してみると,135例もヒットした.すべてのコンコーダンスラインを精査したわけではないが,多少のゴミは混じっているものの,大部分は目下問題にしている shall we の代用としての用例とみてよさそうだ.いくつか例を挙げよう(最初の4例は Shakespeare より).
・ if he couetously reserue it, how shall 's get it?
・ where shall 's lay him?
・ shall 's haue a play of this?
・ shal 's to the Capitoll?
・ shall 's daunce?
・ shall 's to th' Taverne?
・ come, shal 's shake hands, sirs?
・ what shall 's do this evening?
・ shall 's to dinner now?
・ come, come, shall 's go drink?
そもそもこの表現は統語的には疑問文であり,発話行為としては勧誘であり,口語的な色彩も強い.おそらく,当時,そのような響きをもったフレーズとして固定化していたものと思われる.機能的にいえば let's に近いと言えるが,この let's 自身も let us をつづめたものである.後者では us が正規の目的格形として用いられており,shall us の破格的な目的格形 us の使用とは一線を画していることは疑いようもないが,もしかすると両者の間に機能的類似に基づく類推 (analogy) が作用していたのかもしれない (cf. 「#1981. 間主観化」 ([2014-09-29-1])) .
なお,省略されていない "shall us" でも検索してみた.こちらでは88例がヒットしたが,us が正規の目的格として用いられている例も多く混じっており,省略版 shall's と比べれば shall we の代用表現としての用例は稀のようだ.
2020-11-25 Wed
■ #4230. なぜ father, mother, brother では -th- があるのに sister にはないのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][phonetics][consonant][sound_change][grimms_law][verners_law][analogy][etymology][relationship_noun][fricativisation]
標題の親族名称 (relationship_noun) は,英語を学び始めて最初に学ぶ単語の代表格です.いったん暗記して習得してしまうと「そういうものだ」という捉え方になり,疑うことすらしません.しかし,英語を学び始めたばかりの生徒の視点は異なります.標記のようなドキッとする質問が寄せられるのです.father, mother, brother, sister という親族名詞の基本4単語を眺めると,問題の子音について確かに sister だけが浮いていますね.これはどういうわけでしょうか.音声の解説をお聴きください.
千年前の古英語期,上記の4単語は fæder, mōdor, brōþor, sweostor という形態でした(<þ> は <th> に相当する古英語の文字です).つまり,<th> に相当するものをもっていたのは,実は brother だけだったのです.第5の親族名称である daughter (OE dohtor) も合わせて考慮すると,2単語で d が用いられ,さらに別の2単語で t が用いられ,そして1単語でのみ th が用いられたということになります.つまり,当時は brōþor の þ (= th) こそが浮いていた,ということすら可能なのです.これは,現代人からみると驚くべき事実ですね.
ここで疑問となるのは,なぜ古英語で d をもっていた fæder と mōdor が,現代までに当該の子音を th に変化させたかということです.これは中英語後期以降の音変化なのですが,母音に挟まれた d はいくつかの単語で摩擦音化 (fricativisation) を経ました.類例として furder > further, gader > gather, hider > hither, togeder > together, weder > weather, wheder > whether, whider > whither を挙げておきましょう.
議論をまとめます.現代英語の観点からみると確かに sister が浮いているようにみえます.しかし,親族名称の形態の歴史をひもといていくと,実は brother こそが浮いていたと結論づけることができるのです.英語史ではしばしば出くわす「逆転の発想」の好例です.
上の音声解説と比べるとぐんと専門的になりますが,音変化の詳細に関心のある方は,ぜひ##698,699,480,481,703の記事セットの議論もお読みください.
2020-11-24 Tue
■ #4229. Fertig による analogy の定義 [analogy][history_of_linguistics][terminology][review][morphology]
言語学史上,類推作用 (analogy) については多くが論じられてきた.「音韻法則に例外なし」を謳い上げた19世紀の比較言語学者たちは analogy を言語変化の例外を集めたゴミ箱として扱った一方で,英語史を含め個別言語の言語史記述においては,analogy を引き合いに出さなければ諸問題を考察することすら不可能なほどに,概念・用語としては広く浸透した(cf. 「#555. 2種類の analogy」 ([2010-11-03-1]),「#1154. 言語変化のゴミ箱としての analogy」 ([2012-06-24-1])).analogy を巡る様々な立場の存在は,それが日常用語でもあり学術用語でもあるという点に関わっているように思われる.学術用語としても,言語学のみならず心理学や認知科学などで各々の定義が与えられており,比較するだけで頭が痛くなってくる.
ここ数日の記事で引用している Fertig (12) は,言語学における analogy という厄介な代物を本格的に再考し,改めて導入しようとしている.読みながら多くのインスピレーションを受けているが,とりわけ重要なのは Fertig なりの analogy の定義である.これが本書の序盤 (12) に提示されるので,こちらに引用しておきたい.
(3a) analogy1 [general sense] is the cognitive capacity to reason about relationships among elements in one domain based on knowledge or beliefs about another domain. Specifically, this includes the ability to make predictions/guesses about unknown properties of elements in one domain based on knowledge of one or more other elements in that domain and perceived parallels between those elements and sets of known elements in another domain.
(3b) analogy2 [specific sense] is the capacity of speakers to produce meaningful linguistic forms that they may have never before encountered, based on patterns they discern across other forms belonging to the same linguistic system.
(3c) an analogical formation is a form (word, phrase, clause, sentence, etc.) produced by a speaker on the basis of analogy2.
(3d) associative interference is an analogical formation and/or a product of associative interference that deviates from current norms of usage.
(3f) an analogical change is a difference over time in prevailing usage within (a significant portion of) a speech community that corresponds to an analogical innovation or a set of related innovations.
定義というのは,それだけ読んでもなぜそのようになっているのか,なぜそこまで精妙な言い回しをするのか分からないことも多いが,それはこの analogy についても当てはまる.Fertig の新機軸の1つは,従来の analogy 観に (3d) の項目を付け加えたことである.伝統的な「比例式」を用いた analogy の定義には当てはまらないが,別の観点からは analogy とみなせる事例を加えるために,新たに検討されたのが (3d) だった.
もちろん Fertig の定義とて1つの定義,1つの学説にすぎず,精査していく必要があるだろう.
・ Fertig, David. Analogy and Morphological Change. Edinburgh: Edinburgh UP, 2013.
2020-10-14 Wed
■ #4188. なぜ sheep の複数形は sheep なのですか? --- hellog ラジオ版 [hellog-radio][sobokunagimon][hel_education][number][plural][oe][sound_change][analogy][high_vowel_deletion][analogy]
sheep, deer のような普通名詞の複数形は,どういうわけか無変化で sheep, deer のままです.英語には,このような「単複同形」と呼ばれる名詞が少ないながらもいくつか存在しますが,いったいどのような背景があるのでしょうか.ラジオの解説をお聴きください.
英語の歴史においては,もともとは sheep にせよ deer にせよ,単数形と複数形は形態的に区別されていました.古英語より前の時代には,単数形 scēap に対して *scēapu,同様に単数形 dēor に対して *dēoru のように,語尾によって単複が区別されていたのです.しかし,古英語期までに,専門的には「高母音削除」(high_vowel_deletion) と呼ばれる音変化が生じて語尾の -u が消失し,単複同形となってしまっていたのです.
さて,このタイプの単語に,動物や単位を表わす名詞が少なからず含まれていたことが,続く中英語期の展開においてポイントとなってきます.主として狩猟対象となる動物(群れ)や数の単位を表わす名詞は,単数よりも複数で用いられることが多いのは自然に理解できるでしょう.これらの名詞は,複数形で使われるのがデフォルトなのです.すると,あえて -s などをつけて複数形であることを明示する必要もなく,そのまま裸の形で実質的に複数を表わすという慣習が拡がりました.もともと古英語期には複数形に -s 語尾をとっていた fish ですら,この慣習に巻き込まれて単複同形となりました.結果として,狭い意味領域ではありますが,動物の群れや数の単位を表わすいくつかの名詞が,英語では特殊な「単複同形」を取ることになったのです.具体的には,sheep, deer, fish, carp や hundred, thousand, million, billion などの名詞です.
sheep や deer は,このような傾向のモデルとなった,古英語から続く老舗の名詞なのです.しかし,改めて強調しておきますが,sheep や deer とて,古英語より前の時代には,きちんと形態的に異なる複数形を示していたということです.音変化とその後の語彙・意味的な類推作用 (analogy) の結果,現代のような単複同形になっているのだということを銘記しておきたいと思います.
この問題と関連して,##12,1512,2232の記事セットを参照していただければと思います.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow