2025-06-28 Sat
■ #5906. 支柱語 (prop word) の「支柱」とは? [prop_word][pos][pronoun][personal_pronoun][syntax][terminology][existential_sentence][do-periphrasis][cleft_sentence]
My family is a large one. のような文における one のような語は支柱語 (prop_word) と呼ばれる.「支柱」という発想は,それがないと構文として立ちゆかない統語上の必須項ということだろうか.一方で,このような one は前述の可算名詞を指示こそすれ,それ自体の意味内容は空っぽといえるので,この点では「支柱」の比喩はあまり有効でないように思われる.
言語学用語としての prop とは何だろうか.Crystal の用語辞典で prop を引いてみた.
prop (adj.) A term used in some GRAMMATICAL descriptions to refer to a meaningless ELEMENT introduced into a structure to ensure its GRAMMATICALITY, e.g. the it in it's a lovely day. Such words are also referred to as EMPTY, because they lack any SEMANTICALLY independent MEANING. SUBSTITUTE WORDS, which refer back to a previously occurring element of structure, are also often called prop words, e.g. one or do in he's found one, he does, etc.
統語意味論的な観点からは,上記のように substitute word (代用語)と呼ぶのは分かりやすい.
ただし,意味のない形式上の it などをも指して "prop" と呼ぶとなれば,"empty", "expletive", "dummy" などの形容詞にも近しいだろう.実際 McArthur の用語辞典によれば,"prop" の項目を引くと "dummy" へ参照を促される.その第4項目を引用する(ただし,ここでは特に one は例として挙げられてない).
DUMMY [16c: from dumb and -y]. . . . (4) In grammar, an item that has little or no meaning but fills an obligatory position: prop it, which functions as subject with expressions of time (It's late), distance (It's a long way to Tipperary), and weather (It's raining); anticipatory it, which functions as subject (It's a pity that you're not here) or object (I find it hard to understand what's meant) when the subject or object of a clause is moved to a later position in the sentence, and is the subject in cleft sentences (It was Peter who had an accident); existential there, which functions as subject in an existential sentence (There's nobody at the door); the dummy auxiliary do, which is introduced, in the absence of any other auxiliary, to form questions (Do you know them?).
意味論的には空疎だが統語論上は必須とされる要素,これが prop の最大公約数的な性質といってよいだろうか.one の他の特殊用法については,以下の記事も参照.
・ 「#1815. 不定代名詞 one の用法はフランス語の影響か?」 ([2014-04-16-1])
・ 「#5170. 3人称単数代名詞の総称的用法」 ([2023-06-23-1])
・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008.
・ McArthur, Tom, ed. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: OUP, 1992.
2025-04-15 Tue
■ #5832. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? --- 語順の2つの原理から考える [word_order][oe][pde][japanese][linearity][syntax][information_structure][article][cleft_sentence][passive][voice][discourse]
1週間前の火曜日に heldio にて「#1413. なぜ古英語の語順規則は緩かったのか?(年度初めの生配信のアーカイヴ)」を生配信し,土曜日にそれをアーカイヴとして配信しました.語順 (word_order) という,言語において一般的な話題なので,関心をもたれたのでしょうか,おかげさまでこの回は平均よりも多く聴取されています.ありがとうございます.
英語史の分野で「語順」といえば,現代英語では語順規則が厳しいのに,古英語では語順が比較的緩かったという対比が話題になります.当然ながら「それはなぜ?」という素朴な疑問が湧いてくるのではないでしょうか.今回の話題は,この疑問に直接答えるものではなく斜めからのアプローチではありますが,語順とは何かという根本的な問題には真正面から取り組んでいると思います.
以下に文章で要旨を示しますが,ぜひ臨場感のあるオリジナルの音声配信にてお聴きいただければと思います.
1. そもそも「語順」とは何か? --- 言語の線状性 (linearity)
私たちは,外国語学習,特に英語学習を通じて,語順の重要性を学びます.現代英語は SVO が基本であり,これを崩すと意味が変わったり,非文法的になったりすると教わってきました.例えば I eat a banana. が標準的であり,*Eat I a banana. や *A banana I eat. は通常許容されません(強調などの特殊な文脈は除きます).
一方,日本語では「私はバナナを食べる」 (SOV) が自然ですが,「バナナを私は食べる」 (OSV) や「食べる,私はバナナを」 (VSO) なども,不自然さはあるにせよ,文法的に間違いとは言い切れません.
では,なぜ言語には語順というものが存在するのでしょうか.それは,言語が音声(あるいは文字)を時間軸に沿って直線的に並べることによって成立しているからです.これを言語の線状性と呼びます.私たちの発音器官(とりわけ声帯)は基本的に1つしかないので,複数の単語を同時に発することはできません.したがって,単語を順番に並べるしかないのです.これは言語における避けられない制約であり,物理学における重力に相当するものと捉えることができます.
While the dog is running in the yard, the cat is sleeping on the hot carpet. (犬が庭で走っている間,猫はホットカーペットの上で寝ている)という文は,本来同時に起こっている出来事を表わしていますが,言語の線状性の制約から,どちらかの節を先に言わざるを得ません.もし仮に人間が2つの声帯をもち,同時に2つの単語を発することができたなら,言語の構造は全く異なっていたことでしょう.
2. 語順規則の2つの原理
単語を順番に並べなければならないという,語順の存在理由は分かりました.しかし,問題は「どのように並べるか」という語順規則です.世界の言語を見渡すと,この語順規則の背後には,大きく分けて2つの異なる原理が存在するように思われます.
(1) 文法上の語順規則
・ 文(センテンス)内部の要素(主語,動詞,目的語など)の配置を固定する原理
・ 要素の文法的な機能(主語なのか目的語なのか)を語順によって示す傾向が強い
・ 典型例:現代英語 (SVO),中国語 (SVO) など
・ 文法的な関係性が語順によって明確になる反面,語順の自由度は低い
(2) 文脈上の語順規則
・ 文(センテンス)よりも広い文脈(談話)における情報の流れを重視する原理.
・ 多くの場合,主題・テーマ・旧情報を先に提示し,それに続く形で叙述・レーマ・新情報を配置する傾向がある
・ 典型例:日本語,古英語
・ 情報の流れが自然になる一方,文内部の語順は比較的自由で「緩い」と見なされやすい.
日本語の「昔々あるところに,おじいさんとおばあさんがいました.おじいさんは山へ芝刈りに・・・」という語り出しを考えてみましょう.最初の文では,舞台設定の後,新情報である「おじいさんとおばあさん」が「が」を伴って現れます.次の文では,既知となった「おじいさん」が「は」(主題)を伴って文頭に来て,新しい情報(山へ芝刈りに行ったこと)が続きます.このように,日本語は文脈上の情報の流れ(主題→叙述,テーマ→レーマ,旧情報→新情報)を語順や助詞によって表現することを好む言語なのです.
3. 古英語は日本語型だった?
さて,ここで古英語に注目してみましょう.なぜ古英語の語順規則は緩かったのか? 答えは,古英語が現代英語のような「文法上の語順規則」を第1原理とする言語ではなく,むしろ日本語に近い「文脈上の語順規則」を重視する言語だったからです.
古英語では,文脈に応じて,主題や旧情報と見なされる要素を文頭に置き,新情報を後に続けるという語順が好まれました.そのため,文の内部構造だけを見ると,SVO も SOV も VSO も可能であり,現代英語話者の視点から見ると,語順が固定されておらず緩い,と感じられるわけです.しかし,それは「規則がない」わけではなく,異なる種類の原理に基づいているものと理解すべきものなのです.
4. 語順原理の転換と英語史上の変化
英語の歴史は,この「文脈上の語順規則」を重視するタイプから「文法上の語順規則」を重視するタイプへと,言語の基本的な性格が大きく転換した歴史であると捉えることができます.この転換は,中英語期に顕著になり,近代英語期にかけて固定化していきます.この大きな原理の転換は,単に語順だけでなく,英語の他の様々な文法項目にも連鎖的な影響を及ぼしました.
・ 冠詞 (article) の発達:古英語にも冠詞の萌芽はありましたが,現代英語ほど体系的なカテゴリーではありませんでした.旧情報を示す定冠詞 the や,新情報を示す不定冠詞 a/an が発達してきたのは,まさに情報構造 (information_structure) を語順以外の方法で示す必要性が高まったことと関連していると考えられます.
・ 強調構文 (cleft_sentence) の発達:古英語では,強調したい要素を比較的自由に文頭に移動させることが可能でした.しかし,語順が固定化されると,そのような移動が制限されます.その代わりとして,It is ... that ... のような強調構文が発達し,特定の要素を際立たせる機能をもつようになりました.
・ 受動態 (passive) の多用:古英語にも受動態は存在しましたが,使用頻度は現代英語ほど高くありませんでした.語順が固定化される中で,本来目的語となる要素(新情報になりやすい要素)を主題として文頭に置きたい場合に,受動態が便利な装置として頻繁に用いられるようになってきたものと考えられます.例えば,目的語を文頭に置く OSV の語順が使いにくくなった代わりに,目的語を主語にして文頭に置く受動態が好まれるようになった,という見方です.
5. まとめ
古英語の語順が現代英語から見て「緩い」のは,語順規則がなかったからではなく,現代英語とは異なる「文脈上の語順規則」という原理をより重視していたためです.この原理は,くしくも日本語と共通する部分が多くあります.英語の歴史は,この基本原理が大きく転換したダイナミックな過程であり,その影響は英文法の様々な側面に及んでいるのです.
古英語を学ぶ際には,現代英語の固定的な語順観から一旦離れ,「情報の流れ」という視点をもつことが,かえって理解の助けになるかもしれません.日本語母語話者にとっては,むしろ馴染みやすい側面もあるといえるでしょう.語順という切り口から,英語の奥深い歴史を探求してみるのも,おもしろいのではないでしょうか.
2023-05-30 Tue
■ #5146. 強調構文の歴史に関するコンテンツを紹介 [hel_contents_50_2023][khelf][syntax][cleft_sentence][number][agreement][link]
khelf(慶應英語史フォーラム)が企画し展開してきた「英語史コンテンツ50」も,終盤戦に入りつつあります.休日を除く毎日,khelf メンバーが英語史コンテンツを1つずつウェブ公開していく企画です.
最近のコンテンツのなかでよく閲覧されているものを1つ紹介します.5月26日に公開された「#35. 「強調構文の英語史 ~ "It ARE John and Anne that are married."はアリ!? ~」です.
強調構文と呼ばれる統語構造は,英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) として言及されます.コンテンツではこの分裂文の歴史の一端が説明されていますが,とりわけ数の一致 (number agreement) をめぐる議論に焦点が当てられています.
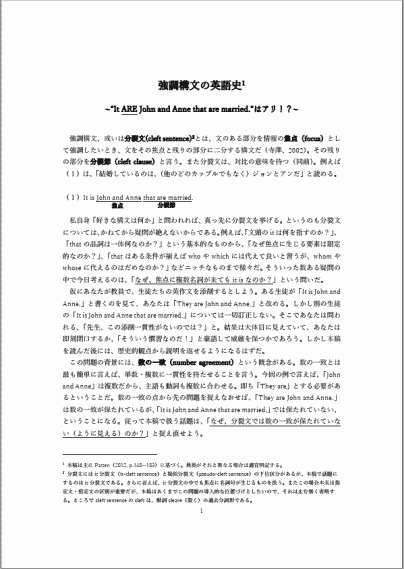
コンテンツの巻末には,関連するリソースへのリンクが張られています.分裂文に関する hellog 記事としては,以下を挙げておきます.
・ 「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1])
・ 「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1])
・ 「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1])
・ 「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1])
・ 「#4785. It is ... that ... の強調構文の古英語からの例」 ([2022-06-03-1])
2022-06-03 Fri
■ #4785. It is ... that ... の強調構文の古英語からの例 [syntax][cleft_sentence][personal_pronoun][oe]
学校文法で「強調構文」と呼ばれる統語構造は,英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と称されることが多い.分裂文の起源と発達については「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]),「#4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」」 ([2021-11-25-1]) などで取り上げてきた.
歴史的事実としては,使用例は古英語からみられる.ただし,古英語では,it はほとんど用いられず,省略されるか,あるいは þæt が用いられた.Visser (§63) より,いくつか例を示そう.
63---g. The type 'It is father who did it.'
This periphrastic construction is used to bring a part of a syntactical unit into prominence; it is especially employed when contrast has to be expressed: 'It is father (not mother) who did it'. In Old English hit is omitted (e.g. O. E. Gosp., John VI, 63, 'Gast is se þe geliffæst'; O. E. Homl. ii, 234, 'min fæder is þe me wuldrað') or its place is taken by þæt (e.g. Ælfred, Boeth. 34, II, 'is þæt for mycel gcynd þæt urum lichoman cymð eall his mægen of þam mete þe we þicgaþ'; Wulfstan, Polity (Jost) p. 127 則183, þæt is laðlic lif, þæt hi swa maciað; O. E. Chron. an. 1052, 'þæt wæs on þone monandæg ... þæt Godwine mid his scipum to suðgeweorce becom'). This pronoun þæt is still so used in: Orm 8465, 'þætt wass þe lond off Galileo þætt himm wass bedenn sekenn'.
中英語以降は it がよく使用されるようになったようだ.
名詞(句)ではなく時間や場所を表わす副詞(句)が強調される例も,上記にある通りすでに古英語からみられるが,それに対する Visser (§63) の解釈が注目に値する.そのような場合の is は意味的に happens に近いという.
When it was, it is has an adverbial adjunct of time or place as a complement, (as e.g. in 'It was on the first of May that I saw him first'), to be is not a copula, but the notional to be with the sense 'to happen', 'to take place' that also occurs in constructions of a different pattern, such as are found in e.g. C1350 Will. Palerne 1930, 'Manly on þe morwe þat mariage schuld bene; 1947 H. Eustis, The Horizontal Man (Penguin) 41, 'Keep your trap shut when you don't know what you're talking about, which is usually'; Pres. D. Eng.: 'The flower-show was last week' (OED).
分裂文の起源と発達は,英語統語史上の重要な課題である.
・ Visser, F. Th. An Historical Syntax of the English Language. 3 vols. Leiden: Brill, 1963--1973.
2021-11-25 Thu
■ #4595. 強調構文に関する「ケルト語仮説」 [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][cleft_sentence][irish_english]
「#2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ」 ([2016-01-03-1]),「#3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について」 ([2019-08-07-1]) で取り上げてきたように,「強調構文」として知られている構文の起源と発達については様々な見解がある(ちなみに英語学では「分裂文」 (cleft_sentence) と呼ぶことが多い).
比較的最近の新しい説によると,英語における強調構文の成長は,少なくとも部分的にはケルト語との言語接触に帰せられるのではないかという「ケルト語仮説」 (celtic_hypothesis) が提唱されている.伝統的には,ケルト語との接触による英語の言語変化は一般に微々たるものであり,あったとしても語彙借用程度にとどまるという見方が受け入れられてきた.しかし,近年勃興してきたケルト語仮説によれば,英語の統語論や音韻論などへの影響の可能性も指摘されるようになってきている.英語の強調構文の発達も,そのような事例の1候補として挙げられている.
先行研究によれば,古英語での強調構文の事例は少ないながらも見つかっている.例えば以下のような文である (Filppula and Klemola 1695 より引用).
þa cwædon þa geleafullan, 'Nis hit na Petrus þæt þær cnucað, ac is his ængel.' (Then the faithful said: It isn't Peter who is knocking there, but his angel.)
Filppula and Klemola (1695--96) の調査によれば,この構文の頻度は中英語期にかけて上がってきたという.そして,この発達の背景には,ケルト語における対応表現の存在があったのではないかとの仮説を提起している.論拠の1つは,アイルランド語を含むケルト諸語に,英語よりも古い時期から対応表現が存在していたという点だ.実はフランス語にも同様の強調構文が存在し,むしろフランス語からの影響と考えるほうが妥当ではないかという議論もあるが,ケルト諸語での使用のほうが古いということがケルト語仮説にとっての追い風となっている.
もう1つの論拠は,現代アイルランド英語 (irish_english) で,英語の強調構文よりも統語的自由度の高い強調構文が広く使われているという事実だ.例えば,次のような自由さで用いられる (Filppula and Klemola 1698 より引用).
・ It is looking for more land they are.
・ Tis joking you are, I suppose.
・ Tis well you looked.
このようなアイルランド英語における,統語的制限の少ない強調構文の使用は,そのような特徴をもつケルト語の基層の上に英語が乗っかっているためと解釈することができる.いわゆる「基層言語仮説」 (substratum_theory) に訴える説明だ.
今回の強調構文の事例だけではなく,一般にケルト語仮説に対しては異論も多い.しかし,古英語期(以前)から現代英語期に及ぶ長大な時間を舞台とする英語とケルト語の言語接触論は,確かにエキサイティングではある.
・ Filppula, Markku and Juhani Klemola. "English in Contact: Celtic and Celtic Englishes." Chapter 107 of English Historical Linguistics: An International Handbook. 2 vols. Ed. Alexander Bergs and Laurel J. Brinton. Berlin: Mouton de Gruyter, 2012. 1687--1703.
2019-08-07 Wed
■ #3754. ケルト語からの構造的借用,いわゆる「ケルト語仮説」について [celtic][borrowing][syntax][contact][substratum_theory][celtic_hypothesis][do-periphrasis][reflexive_pronoun][be][nptr][fricative_voicing][cleft_sentence]
この20数年ほどの間に,「ケルト語仮説」 ("the Celtic hypothesis") に関する研究が著しく増えてきた.英語は語彙以外の部門においても,従来考えられていた以上に,ブリテン諸島の基層言語であるケルト諸語から強い影響を受けてきたという仮説だ.1種の基層言語影響説といってよい(cf. 「#1342. 基層言語影響説への批判」 ([2012-12-29-1])).非常に論争の的になっている話題だが,具体的にどのような構造的な言語項がケルト語からの影響とみなされているのか,挙げてみよう.以下,Durkin (87--90) による言及を一覧にするが,Durkin 自身もケルト語仮説に対してはやんわりと懐疑的な態度を示していることを述べておこう.
・ 古英語における be 動詞の bēon 系列を未来時制,反復相,継続相を示すために用いる用法.ウェールズ語に類似の be 動詞が存在する.
・ -self 形の再帰代名詞の発達(cf. 「#1851. 再帰代名詞 oneself の由来についての諸説」 ([2014-05-22-1]))
・ be + -ing の進行形構造の発達
・ do を用いた迂言的構造 (do-periphrasis) の発達
・ 外的所有者構造から内的所有者構造への移行 (ex. he as a pimple on the nose → he has a pimple on his nose)
・ "Northern Subject Rule" の発達(cf. 「#689. Northern Personal Pronoun Rule と英文法におけるケルト語の影響」 ([2011-03-17-1]))
・ ゼロ関係詞あるいは接触節の頻度の増加
・ it を用いた分裂文 (cleft sentence) の発達 (ex. It was a bike that he bought (not a car).) .なお,フランス語の対応する分裂文もケルト語の影響とする議論があるという (Durkin 87) .
・ /f/ と /v/, /θ/ と /ð/ の音韻的対立の発達と保持(cf. 「#3386. 英語史上の主要な子音変化」 ([2018-08-04-1]) の2点目)
・ Durkin, Philip. Borrowed Words: A History of Loanwords in English. Oxford: OUP, 2014.
2016-01-03 Sun
■ #2442. 強調構文の発達 --- 統語的現象から語用的機能へ [syntax][agreement][pragmatics][construction_grammar][discourse_marker][relative_pronoun][expletive][cleft_sentence]
先日,掲示板にて "It is . . . that . . . ." の型をもつ分裂文 (cleft sentence),いわゆる強調構文の歴史について質問が寄せられた.これについて,以下のように粗々に回答した.
分裂文(いわゆる強調構文)の発展や,要素間の統語的一致の推移については,複雑な経緯と種々の説があり,一言では説明できません.相当するものは古英語からあり,主語には it のみならず that やゼロ形が用いられていました.現代英語における分裂文という現象を,共時的な観点にこだわらず,あえて通時的な観点から分析するのであれば,that は関係詞であり,it はその先行詞であると述べておきたいと思います.つまり,"It is father that did it." という例文でいえば,「それを為したところのもの,それは父です.」ということになります.人でありながら中性の it を用いるのも妙な感じはしますが,"Who is it?" の it などからも理解できると思います(古英語でも同じでした).ところが,後に "It is I that am wrong." にみられるように,that の先行詞は文頭の It ではなく直前の I であるかのような一致を示すに至りました.以上,取り急ぎ,かつ粗々の回答です.
この問題について,細江 (245--46) が次のように論じている.
注意を引くために用いられた It is... の次に来る関係代名詞が主格であるとき,その従文における動詞は It is I that am wrong. のようにこれに対する補語と人称数で一致する.たとえば,
It is you who make dress pretty, and not dress that makes you pretty.---Eliot
But it's backwaters that make the main stream. ---Galsworthy.
It is not I that bleed---Binyon.
これは今日どんな文法家でも,おそらく反対するものはないであろう.しかも that の先行詞は明らかに It である.それではなぜこの一致法が行なわれるかといえば,〔中略〕It は文法の形式上 that の先行詞ではあるけれども,一度言者の脳裏にはいってみれば,それは決して次に来る叙述中に含まれる動作もしくは状態などの主たり得る性質のものではない.すなわち,換言すれば It is I that am wrong. と言うとき,言者の脳裏にある事実は I am wrong. にほかならないからである.
細江は p. 246 の注で,フランス語の "Nous, nous n'avons pas dit cela." と "Ce n'est pas nous qui avons dit cela." の2つの強調の型においても,上記と同じことが言えるとしている.関連して,「#1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」」 ([2012-09-30-1]) を参照.
私の回答の最後に述べたことは,歴史の過程で統語的一致の様式が変化してきたということである.これを別の観点からみれば,元来,統語的な型として出発したものが,強調や対比という語用的・談話的な役割を担う手段として発達し,その結果として,統語的一致の様式も変化にさらされたのだ,と解釈できるかもしれない.細江の主張を,回答内の例文において繰り返せば,話者の頭の中には did it (それを為した)のは明らかに father (父)という観念があるし,wrong (間違っている)のは明らかに I という観念があるはずである.それゆえに,この観念に即した統語的一致が求められるようになったのだろう.そして,現代英語までに,この一致の様式をもつ統語的な型そのものが,語用的な機能を果たす構造として確立してきたのである.
・ 細江 逸記 『英文法汎論』3版 泰文堂,1926年.
2012-09-30 Sun
■ #1252. Bailey and Maroldt による「フランス語の影響があり得る言語項目」 [french][celtic][old_norse][contact][cleft_sentence][french_influence_on_grammar]
##1223,1249,1250,1251 の記事で,Bailey and Maroldt によって始められた中英語=クレオール語の仮説を巡る論争を見てきた.Bailey and Maroldt を批判する内容ばかりだったが,彼らの論文には示唆的な考察もあることを付け加えておきたい.
[2012-09-28-1]の記事「#1250. 中英語はクレオール語か? (3)」の (5) で取り上げた「英語とフランス語との間に平行関係が観察される言語項目」 (Bailey and Maroldt 51--52) を,「フランス語の影響があり得る言語項目」のリストとして捉えれば,英仏語言語接触の研究課題を提供してくれているという点で有用かもしれない.[2012-09-01-1]の記事「#1223. 中英語はクレオール語か?」で紹介したように,Görlach は,以下のほとんどの項目に異議を唱えるだろうが,一覧にしておくことはなにがしかの意味があるだろう.
A. Anglo-Saxon elements in French functions:
1) the -līce deadjectival adverb-formative;
2) the use of wh-interrogatives as relative pronouns; cf. French qu-interrogatives and relatives;
3) progressive formations and other tense/aspect/diathesis formations;
4) prepositions of the pattern exemplified by outside of, or Anglo-Saxon prepositions in French uses;
5) French-like uses of the pronoun cases;
6) the cleft-sentence formation;
7) case functions of the of-"genitive" and the to-"dative";
8) second-person informal/formal distinction in forms of address;
9) Middle English calques that got lost later; e.g. the which;
10) analytical comparison.
B. French-influenced developments, the first of which is essentially universal:
1) loss of inflections, especially case and gender distinctions;
2) word order, especially after negative elements; but not the order of adjectives.
C. French elements:
1) vocabulary --- quantitatively as well as qualitatively very considerable;
2) a huge part of English derivational morphology;
3) most phonomorphological rules;
4) certain sounds; e.g. initial [v dž] and the diphthong [ɔ].
また,これまであまり聞いたことのないケルト語あるいは古ノルド語からの影響の可能性として,次の言及も目に留まったので付け加えておく."The fact that clear [l] as well as non-aspirated [p t k] are widespread in the North could be due to either Keltic or Nordic influence" (25).
・ Bailey, Charles James N. and Karl Maroldt. "The French Lineage of English." Langues en contact --- Pidgins --- Creoles --- Languages in contact. Ed. Jürgen M. Meisel. Tübingen: Narr, 1977. 21--51.
2012-01-15 Sun
■ #993. flat adverb についてあれこれ [flat_adverb][adverb][adjective][swearword][intensifier][metanalysis][hendiadys][cleft_sentence]
年が明けて以来,flat_adverb についていくつか記事を書いてきた.調べているうちに諸々の話題が集まってきたので,雑記として書き残しておきたい.
(1) 「主にくだけた口語で用いられ,本来の副詞より端的で力強い表現」(小西,p. 507);「単純形副詞がよく用いられるのは,文が比較的短く,幾分感情的色彩がある場合で,口語体ではより力強い表現として好まれる傾向がある: It hurts bad. / Take it easy. / Go slow.」(荒木, p. 522)
(2) 米の口語・俗語で多用されることは既述だが,さらに例を挙げる(荒木,pp. 86, 91).ex. act brave, dance graceful, land safe, work regular, sit tight, mighty dangerous, reasonable busy, moderate good luck, everlasting cold, get ugly drunk, hustlingest busy; I see things different than I used to.; You are plain lucky.
(3) 歌曲の題名などで臨時的に用いられる.ex. "Love Me Tender", "Treat me nice".
(4) 副詞としての very の起源が示すとおり ([2012-01-12-1], [2012-01-13-1]) ,名詞を修飾する類義の形容詞の連続において,前の形容詞が後の形容詞を修飾する副詞として異分析される例がみられる (ex. an icy cold drink, a blazing hot fire) .さらに,名詞がなくとも独立して burning hot, soaking wet, dazzling white なども見られる(大塚,p. 589).
(5) 形容詞と副詞が同形のペアには5種類あり,以下の iii, iv 辺りが典型的に flat adverb と呼ばれるものだろう (Huddleston and Pullum 568) .
i daily, hourly, weekly, deadly, kindly, likely
ii downright, freelance, full-time, non-stop, off-hand, outright, overall, part-time, three-fold, wholesale, worldwide
iii bleeding, bloody, damn(ed), fucking
iv clean, clear, dear, deep, direct, fine, first, flat, free, full, high, last, light, loud, low, mighty, plain, right, scarce, sharp, slow, sure, tight, wrong
v alike, alone, early, extra, fast, hard, how(ever), late, long, next, okay, solo
(6) flat adverb と -ly adverb では,分裂文 (cleft sentence) で焦点化された場合の容認可能性が異なる.flat adverb は,動詞句と分断されることにより形態だけでは副詞とわかりにくくなるために,容認度が低くなるのではないか(荒木,p. 522).
*It was slow that he drove the car into the garage. vs It was slowly that he drove the car into the garage.
*It was loud that they argued. vs It was loudly that they argued.
ただし,flat adverb が等位接続されたり別の語で修飾されると,副詞であることが明確になり,容認されやすい.ex. It was loud and clear that he spoke.; It was extremely loud that they argued.
(7) A and B と形容詞を等位接続すると,A-ly B ほどの意となる二詞一意 (hendiadys) の例も,形容詞の副詞化という現象の一種としてとらえることができそうだ(大塚,pp. 531, 589).ex. nice and cool (= "nicely cool"), good and tired (="well tired"), rare and hungry (="quite hungry").
・ 小西 友七 編 『現代英語語法辞典』 三省堂,2006年.
・ 荒木 一雄,安井 稔 編 『現代英文法辞典』 三省堂,1992年.
・ Huddleston, Rodney and Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: CUP, 2002.
・ 石橋 幸太郎 編 『現代英語学辞典』 成美堂,1973年.
・ 大塚 高信,中島 文雄 監修 『新英語学辞典』 研究社,1987年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow