2025-10-12 Sun
■ #6012. 声の書評 --- 小河舜さんと khelf 疋田海夢さんが紹介する『英語固有名詞語源小辞典』 [khelf][hellive2025][review][voice_review][kenkyusha][heldio][voicy][onomastics][kdee][etymology][ogawashun]
Voicy heldio でお送りする khelf の「声の書評」シリーズ,第5弾はこれまでとは趣向を変え,対談形式でお届けします.上智大学の小河舜さんと khelf 大学院生の疋田海夢さんのお2人に,刈部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)の魅力を語っていただきました.本編で24分弱の音声配信となります.「#1596. 声の書評 by 小河舜さん&疋田海夢さん --- 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」をお聴きください.
本書は,人名や地名といった固有名詞の語源を探る「名前学」(onomastics) の世界への扉を開いてくれる一冊です.お2人の対談では,固有名詞が単なるレッテルではなく,その土地の地理や歴史,人々の暮らしといった豊かな物語を秘めていることが熱く語られます.
昨年度の慶應義塾大学の英語地名史の授業で教員・学生の関係にあったお2人の軽快な掛け合いは,聴いていて飽きることがありません.1つの名前から始まる探求が,いかに多方面へと思わぬ広がりを見せていくか.その知的な興奮が,対話を通じて生き生きと伝わってきます.まさにお2人の名前学と英語史にかける情熱の賜物でしょう.
この小辞典は,調べ物に便利なだけでなく,ページをめくるごとに新たな発見があり,歴史への想像力をかき立ててくれる読み物でもあります.お2人の楽しげな対談を聴けば,きっと英語固有名詞の世界に引き込まれるに違いありません.今回,専門分野のおもしろさを存分に伝えてくださった小河さん,疋田さんに改めて感謝します.
なお,本書については,私自身も heldio 「「#1564. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」」および 本ブログ「#5981. 苅部恒徳(編著)『英語固有名詞語源小辞典』(研究社,2011年)」 ([2025-09-11-1]) でも紹介していますので,合わせてご参照ください.
さらに,heldio/helwa コアリスナーの ari さんが,10月4日付で「#424【通読DEPN】英語固有名詞語源小辞典を読む(その1)」として,本書を通読するシリーズ企画を始められたことも付け加えておきます.いやはや,英語固有名詞が熱い!

・ 刈部 恒徳(編著) 『英語固有名詞語源小辞典』.研究社,2011年.
2025-07-14 Mon
■ #5922. 「主の祈りで味わう古英語の文体」 --- 小河舜さんによる力の入った Helvillian コンテンツ [helvillian][notice][heldio][oe][wulfstan][aelfric][stylistics][bible][ogawashun]
先日,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の「#1501. 「主の祈り」で味わう古英語の文体 --- Helvillian 7月号掲載,小河舜さんによる渾身の記事」でも語りましたが,これは改めて hellog 記事としても広く紹介しなければならないと思い,筆を執っています.hellog/heldio ではすっかりお馴染みで,先日刊行された『英語語源ハンドブック』でも校閲協力者として多大な貢献をしてくださった,上智大学の小河舜さんが,驚くべきコンテンツを公にしてくれました.
Helvillian は,heldio リスナーの有志によって制作・運営されているウェブマガジンで,先月末の6月28日に最新号となる7月号が公開されています(「#5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました」 ([2025-07-03-1]) を参照).その特集は「古英語を嗜もう」という,英語史ファンには実に魅力的なお題でした.この特集にあたり,編集部が古英語研究を専門とする小河さんに白羽の矢を立てたのは,しごく当然のことだったと想像します.そして,その期待に小河さんは120%で答えてくれました.寄稿された記事「主の祈りで味わう古英語の文体」は,まさしく専門家の手による圧巻のコンテンツです.
この記事は,聖書の中でも最も有名な祈祷文である Lord's Prayer 「主の祈り」を題材としています.しかし,単に古英語訳を紹介し,文法的な解説を施すといった入門的な内容にとどまるものではありません.古英語後期を代表する2人の偉大な散文作家,Ælfric と Wulfstan が残した「主の祈り」のヴァージョンを丹念に比較し,そこから両者の文体,ひいては思想や個性の違いまでをも鮮やかに炙り出すという,極めて専門的かつスリリングな論考となっています.これこそ英語史や英語文献学の研究のコンテンツです.
Ælfric と Wulfstan は,同時代に活躍しながらも,その文体は対照的でした.Ælfric は,明晰で整然とした,いわば「教育的」な文章を得意としていました.一方,小河さんが注目している Wulfstan は,頭韻 (alliteration) や同義語の反復を多用し,畳みかけるようなリズムで聴衆の感情に直接訴えかける,情熱的な説教で知られています.小河さんの記事の白眉は,この2人の文体の差異が,「主の祈り」というごく短い定型文の翻訳にさえ,いかに色濃く反映されているかを具体的に解き明かしている点にあります.特に Wulfstan のテキストにみられる畳語法や強調表現の分析は,小河さんの研究の真骨頂であり,読んでいて知的な興奮を禁じ得ません.
この記事のさらに驚くべき点を指摘したいと思います.専門性の高さにもかかわらず,徹頭徹尾 heldio リスナーを中心とする英語史の学習者を読者として強く意識し,非常に平易で分かりやすい言葉で書かれている点です.導入として日本語訳や近代英語訳から説き起こし,巧みな構成で読者を古英語の世界へと誘っています.途中,古英語LINEスタンプに言及するような遊び心も忘れていません.
上記の heldio 配信では「90分,いや180分の大学講義に匹敵する価値がある」と述べましたが,決して誇張ではありません.これほどの質の高いコンテンツが,誰でもアクセスできる形で公開されているというのは,望外の幸運といってよいです.(誰も信じてくれないかもしれませんが)信じられないことです.
Helvillian は私が直接関わっているウェブマガジンではありませんが,趣旨に賛同し,応援している雑誌です.その意味で,小河さんの Helvillian への今回のご寄稿を,本当に嬉しく思います.ありがとうございました!
2025-07-03 Thu
■ #5911. ウェブ月刊誌 Helvillian の7月号が公開されました [helwa][heldio][notice][helmate][helkatsu][helvillian][link][ogawashun][oe][hee]

月に1度のお祭りのお知らせです.先日6月28日,『月刊 Helvillian 〜ハロー!英語史』の2025年7月号(第9号)がウェブ公開されました.hellog 読者の方々にはもうお馴染みのことと思います.helwa のメンバー有志が毎月 note 上で制作している hel活 (helkatsu) の月刊ウェブマガジンです.創刊からあっという間に9号を数えることになりました.今回も質,量ともに充実のラインナップです.ゆっくりお読みいただき,じっくりお楽しみください.
今回の表紙を飾るのは,camin さんこと片山幹生さんがご提供くださったアイルランドの美しい写真です.静かなアイルランドの風景から,ヘルメイトの皆さんの熱い思いが伝わってきます.
今号の特集は「古英語を嗜む」です.古英語と聞くと,とっつきにくいと感じる方もいるかもしれません.現代英語とは異なる文字や文法をもつ言語ですから,それも当然です.しかし,今号の特集記事群を読めば,その奥深さと魅力が分かると思います.古英語の世界に足を踏み入れる良い機会になるはずです.
とりわけ注目していただきたいのは,heldio/helwa でもお馴染みの小河舜氏(上智大学)による特別寄稿です.「「主の祈り」で味わう古英語の文体」と題する書き下ろしの1編.古英語の専門家による古英語紹介ですので,たいへん貴重です.
また,「新企画 英語語源ハンドブック」も要注目です.『英語語源ハンドブック』の発売は6月18日のことでしたが,これに先だって,ヘルメイトの間では「ハンドブックにはあれこれの説明があるかもしれない,ないかもしれない」という予想遊びが繰り広げられていました.その遊びに関する記事をとりまとめたのが,この新企画のセクションです.
そのほか,今号には多彩な記事や寄稿文が満載です.ここですべてを紹介することはできませんが,寄稿者のお名前を列挙しておきましょう.ari さん,umisio さん,camin さん,川上さん,Grace さん,こじこじ先生,しーさん,ぷりっつさん,みさとさん,mozhi gengo さん,Taku さん(金田拓さん),lacolaco さん,り~みんさん,Lilimi さんです.
月刊 Helvillian は,helwa の活発なコミュニティ活動の賜物であり,「英語史をお茶の間に」届けるという目標を力強く推し進めてくれる存在です.helwa に参加している皆さんの活動の様子については,ぜひ Voicy プレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪 (helwa)」のメンバーになり,とくとお聴きいただければ.
Helvillian のバックナンバーはこちらのページにまとまっています.hellog の helvillian タグのついた各記事もお薦めです.
この夏は hel活も熱いです.hellog 読者の皆さんには,ぜひ最新号の Helvillian を広めていただければと思います.
Helvillian 7月号については,Voicy heldio でもご紹介しています.「#1494. Helvillian 7月号が公開! --- 古英語を嗜もう」もお聴きください.
2025-06-13 Fri
■ #5891. helwa で配信中 --- 英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん [senbonknock][sobokunagimon][voicy][helwa][hel_education][notice][ogawashun][helkatsu]
6月10日(火)の夜に Voicy のプレミアムリスナー限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) で生配信した「千本ノック」を,helwa アーカイヴとしても配信しました.今回の千本ノックは,6月18日(水)に発売予定の『英語語源ハンドブック』(研究社)の共著者・校閲協力者の4名が集まっての豪華版でした.千本ノックでお馴染みの小河舜氏(上智大学)に加え,千本ノックには初登場となる唐澤一友氏(立教大学)と福田一貴氏(駒澤大学)も参加されました.
84分ほどの長尺となりましたので,アーカイヴでは前編と後編に2分割しています.
・ 【英語史の輪 #301】英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん(前編)(約50分)
・ 【英語史の輪 #302】英語に関する素朴な疑問 千本ノック with 唐澤一友さん,福田一貴さん,小河舜さん(後編)(約34分)
英語史研究者4名での千本ノックは初めてでしたが,限定配信かつ深夜便ということで,もちろん学びもありましたが爆笑シーンも多々あり,新鮮な千本ノック回となりました.heldio の通常配信には流しにくいトンデモ回答も続出し,ある意味で聴きごたえのある内容となっています.
今回取り上げた素朴な疑問は,いつも通り,大学生から寄せてもらっていた疑問リストからランダムに選んだ9問です.普段の千本ノックよりもじっくりと議論できたように思います.
(1) なぜ英語は大文字で文が始まるの?
(2) どのような過程で英語はラテン語から変遷していったの?(←勘違いの質問です)
(3) 「What a/an +形容詞+名詞+主語+動詞」や「How +形容詞+主語+動詞」などの感嘆文の語順はどうなっているの?
(4) なぜ「カフェオレ」は(英語の coffee with milk ではなく)フランス語 café au lait なの?
(5) どうしてアルファベットは26文字なの? 日本語は平仮名だけで50音あるので,少なすぎるように感じます.
(6) 英語,スペイン語は English, Spanish などといいますが,日本語,中国語は *Japanish,*Chinish にならないのはなぜ?
(7) <th> は機能語の語頭で有声化したということですが,through ではなぜ無声のままなのですか?
(8) なぜ discuss には about が要らないのか?
(9) 月名が9月以降は -ber になるのはなぜ?
helwa は月額800円のサブスク配信ですが,初月は無料ですので,これを機にぜひお入りいただければ.
2025-05-24 Sat
■ #5871. 「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][notice][ogawashun][terasawashiho][khelf][helkatsu]
去る5月10日(土)の午前10時30分過ぎより,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」をライヴでお届けしました.いつもの千本ノック (senbonknock) は1時間ほどの長尺でお届けすることが多いのですが,今回はサクッと22分ほどのプチ回となりました.生配信でお聴きいただいたリスナーの皆さん,ありがとうございました.
前回の「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) のときと同様に,今回も小河舜さん(上智大学)とともにノックを受けました.小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設され,活発に情報発信されていますので,ぜひフォローしていただければ.
また,khelf(慶應英語史フォーラム)の寺澤志帆さんには,問題を選んで読み上げる係を務めてもらいました.寺澤さんも最近「『英語語源辞典』でたどる英語綴字史」シリーズという熱いhel活を始められているので,ぜひご訪問ください.
生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック生配信 with 小河舜さん」よりご覧ください.音声のみで聴きたいという方のために,後日 Voicy heldio でも配信すべく準備中ですので少々お待ちください.
今回取り上げた疑問は,いつものように慶應義塾大学文学部英米文学専攻の学生から寄せられたものです.今回はプチ回で,取り上げられたのは6問のみですが,おもしろいトークにはなっています.おおよその分秒とともに疑問を一覧します.
(1) 01:21 --- 「これ」は this,「あれ」は that なのに,「それ」は it になるのはなぜですか?
(2) 04:55 --- なぜ固有名詞(Tokyo や Japan など)の頭文字は大文字にしなければならないのですか?
(3) 08:57 --- なぜ -teen をもつ thirteen や fourteen とは異なり,eleven や twelve はこのような特別な形になるのですか? なぜ *twoteen や * threeteen ではないのですか?
(4) 12:52 --- 英語の方がおしゃれに感じるのは気のせいですか? 外国人もそう感じているのですか?
(5) 16:03 --- なぜ主節と従属節で時制を一致させる必要があるのですか?
(6) 19:15 --- なぜ相手の疑問文が肯定でも否定でも,答えが肯定なら Yes,否定なら No になるのですか?
今後も千本ノックのシリーズは続けていきます.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてください.
(以下,後記:2025/05/31(Sat))
今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1462. 英語に関する素朴な疑問 プチ千本ノック with 小河舜さん --- 皐月収録回@三田より」として配信しています.
2025-05-08 Thu
■ #5855. ギリシア語由来の否定の接頭辞 a(n)- と英語の不定冠詞 a(n) の平行性 [senbonknock][sobokunagimon][heldio][article][greek][prefix][consonant][ogawashun][khelf][negative][oe]
5月28日に,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,heldio にて小河舜さん(上智大学;X アカウント @scunogawa)とともに「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」をライヴでお届けしました.その様子をアーカイヴとしてすでに YouTube 版で公開していることは,先日の記事「#5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました」 ([2025-05-04-1]) でお伝えした通りですが,数日遅れで heldio のアーカイヴとしても配信しました.音声だけで十分という方,ながら聴きしたいという方は,「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご聴取ください.本編は65分ほどの長さです.
今回の千本ノックで取り上げた素朴な疑問は15件ありましたが,その5件目(本編の26分18秒辺りから)に注目します.質問の趣旨としては「不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の否定の接頭辞 an-/a- の現象と同じですか?」というものでした.質問者からのこの高度な指摘にむしろ勉強になった旨,小河さんとライヴでも触れた通りです.
調べてみると,確かに両者において,an- が歴史的には本来の形態素ですが,後ろに母音(あるいは h)で始まる要素が後続する場合には,音便により当該形態素より n が脱落し,a- という異形態が用いられています.きれいに平行的といえます.
Webster の辞書の第3版に所収の A Dictionary of Prefixes, Suffixes, and Combining Forms によると,ギリシア語由来の否定の接頭辞 a-, an- について次のように記述があります.
2a- or an- prefix [L & Gk; L a-, an-, fr. Gk --- more at UN-]: not: without <achromatic> <asexual> --- used chiefly with words of Gk or L origin; a- before consonants other than h and sometimes even before h, an- before vowels and usu. before h <ahistorical> <anesthesia> <anhydrous>
このなかで示唆されている通り,このギリシア語由来の否定の接頭辞は,英語本来の否定の接頭辞 un- とも同根である.ついでに同辞典より un- の項目も覗いておこう.
1un- prefix [ME, fr. OE; akin to OHG un- un-, ON ō, ū-, Goth un-, L in-, Gk a-, an-, Skt a-, an- un-, OE ne not]
古英語の否定辞 ne もこれらと同根であるから,つまるところ not, never, no などとも通じることになる.
寄せていただいた素朴な疑問からの展開でした.たいへん勉強になりました!
2025-05-04 Sun
■ #5851. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」のアーカイヴを YouTube で配信しました [senbonknock][sobokunagimon][voicy][heldio][youtube][hel_education][khelf][notice][ogawashun]
先日,5月28日(水)の午後1時30分過ぎより,khelf(慶應英語史フォーラム)の協賛のもと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて「千本ノックGW回 with 小河舜さん」の生配信をお届けしました.平日昼間の65分にわたるライヴでしたが,ご聴取くださった皆さん,ありがとうございました.
その生配信の様子は音声のみならず動画としても収録していたので,このたび YouTube 「heltube --- 英語史チャンネル」より公開しました.上記スクリーン,あるいは「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」よりご覧ください.(音声のみで十分という方は,後日 Voicy heldio のアーカイヴとしても配信する予定ですので,しばらくお待ちください.)
今回の千本ノックは,前回の「#5843. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- 年度初めの生配信」のアーカイヴを YouTube で配信しています」 ([2025-04-26-1]) とは異なり,私1人ではなく,小河舜さん(上智大学)にも久しぶりにご登場いただき,2人体制で千本ノックを受けるという形式をとりました.前回は孤独に大量の質問の矢面に立ちましたが,今回は強力な助っ人を得て,心強く千本ノックに臨むことができました.小河さん,ありがとうございました! 小河さんは,最近hel活のために X アカウント @scunogawa を開設されましたので,hellog 読者の皆さんは,ぜひフォローをお願い致します.
さて,今回の千本ノックの質問も,慶應義塾大学文学部英米文学専攻や通信教育課程で「英語史」を受講している学生の皆さんから事前に募ったものがほとんどです.鋭い質問や興味深い観点からの疑問が多く寄せられました.生配信では時間の制約もあり,取り上げられた質問は15件にとどまりますが,英語史の多様な側面が垣間見えたのではないでしょうか.
今回の15の疑問について,おおよその分秒とともに一覧します.
(1) 08:09 --- 肯定の平叙文で some + 名詞を含む文を疑問文や否定文にするとき,なぜ some が any にひっくり返るのか?
(2) 12:48 --- freedom と liberty は重なる部分が多いが,ニュアンスの違いもある.このように基本的に同義でも特定の解釈で慎重さが求められる語が生まれた理由は?
(3) 17:40 --- なぜ(文法書もなかったような)古い時代の英語で屈折に富んだ文法が使えたのか?
(4) 21:55 --- 数が 0 の場合,それを受ける可算名詞がなぜ複数形になるのか? (実際には単数形もあり得ます)
(5) 26:18 --- 不定冠詞 an/a の使い分け(an apple vs. a pen)の現象は,ギリシア語由来の接頭辞 an/a の現象と同じですか?
(6) 28:05 --- なぜ Monday など曜日の最初の文字は大文字なのか? なぜ固有名詞扱いなのか?
(7) 32:19 --- なぜ be 動詞は現在形では am, are, is の3種類なのに,過去形では was, were の2種類になるのか?
(8) 36:35 --- 英語が世界言語として広まったのは,他言語と似ていて習得しやすいからか?
(9) 39:39 --- なぜ英語では親指は finger ではなく thumb というのか?
(10) 43:19 --- なぜ関係代名詞で「前置詞 + that」の形はないのか? なぜ that は非制限用法で使えないのか?
(11) 46:47 --- 日本人の名字の長音(例:「大下」)のローマ字表記は,Ohshita, Ōshita, Oshita のどれが適切か?
(12) 50:02 --- なぜ昔の文章ほど難解に感じられるのか?
(13) 53:28 --- knight や knife の語頭の k は発音しないが,昔は発音されていたのか?
(14) 55:30 --- コンマ (,) の歴史的変遷は? 感嘆符 (!) や疑問符 (?) はどのようにして生まれたのか? なぜ文末にピリオド (.) を打つのか?
(15) 58:28 --- 倒置は強調したい要素を文頭に出す場合に起こるが,仮定法(例:Were it not for ...)では何を強調しているのか?
まだまだ未回答の疑問はたくさん残っていますので,別の機会に取り上げていきたいと考えています.過去の千本ノック企画については,本ブログの senbonknock 記事群よりアクセスしてみてください.引き続き,英語史の学びを楽しんでいきましょう!
(以下,後記:2025/05/08(Thu))
今回の千本ノック生配信は heldio でも「#1439. 英語に関する素朴な疑問 千本ノック --- GW回 with 小河舜さん」として配信しています.
2024-10-06 Sun
■ #5641. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 10 with 小河舜さん&まさにゃん at 「英語史ライヴ2024」 [voicy][heldio][hellive2024][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][helkatsu][instagram][khelf]
9月8日(日)に12時間の公開収録生配信として開催された「英語史ライヴ2024」(hellive2024) の目玉企画の1つとして,人気シリーズ「はじめての古英語」(hajimeteno_koeigo) の第10弾「#1219. 「はじめての古英語」第10弾 with 小河舜さん&まさにゃん --- 「英語史ライヴ2024」より」が実現しました.講師はいつものように,小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学),そして堀田隆一の3名です.
多くのギャラリーの方々を前にしての初めての公開収録となり,3名とも興奮のなかで34分ほどの古英語講座を展開しました.冒頭のコールを含め,これほど古英語で盛り上がる集団なり回なりは,かつて存在したでしょうか? おそらく歴史的なイベントになったのではないかと思います(笑).
今回の第10弾は,小河さん主導で古英詩の傑作 Beowulf の冒頭にほど近い ll. 24--25 の1文に注目しました(以下 Jack 版より).
lofdǣdum sceal in mǣgþa gehwǣre man geþēon.
忍足による日本語訳によれば「いかなる民にあっても,人は名誉ある/行いをもって栄えるものである」となります.古英語の文法や語彙の詳しい解説は,上記配信回をじっくりお聴きください.
実は上記の公開収録は Voicy heldio のほか,khelf(慶應英語史フォーラム)の公式 Instagram アカウント @khelf_keioでインスタ動画としても生配信・収録しております.ヴィジュアルも欲しいという方は,ぜひこちらよりご覧ください.会場の熱気が感じられると思います.
シリーズ過去回は hajimeteno_koeigo よりご訪問ください.
・ Jack, George, ed. Beowulf: A Student Edition. Oxford: Clarendon, 1994.
・ 忍足 欣四郎(訳) 『ベーオウルフ』 岩波書店,1990年.
2024-09-13 Fri
■ #5618. 早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん --- 「英語史ライヴ2024」より [hel_education][heldio][notice][sobokunagimon][senbonknock][hellive2024][helwa][ogawashun]
9月8日(日)に Voicy heldio を通じて12時間ライヴ配信としてお届けした「英語史ライヴ2024」では,早朝から夕方まで様々な英語史の番組が組まれていました.早朝一番 6:30 からの番組は,標題の通りの「早朝の素朴な疑問「千本ノック」 with 小河舜さん」でした.55分間にわたり,小河舜さん(上智大学)と私が,英語に関する素朴な疑問に対し,主に英語史の観点から回答し議論しました.
「千本ノック」は heldio の人気シリーズではありますが,今回は「英語史ライヴ2024」という一大イベントを盛り上げるための火付け役の位置づけでしたので,早朝ながらもハイテンションでお届けしました.プレミアムリスナー(=ヘルメイト)3名をギャラリーとしてお迎えし,ギャラリーや生配信リスナーからの投げ込み質問にも答えるという形で,勢いのある55分間となったと思います.早朝から,のべ77名のリスナーにライヴでお聴きいただきましたが,この数には本当に驚きました.ありがとうございます.
以下,今回の千本ノックで取り上げた8件の素朴な疑問を,おおよその分秒とともに一覧します.お時間のあるときにお聴きいただければ.
(1) 09:02 --- なぜ英語の歌詞は日本語の歌詞よりも聞き心地がよいのですか?
(2) 15:20 --- cow/beef,pig/pork のように,生きている場合と食肉の場合とで違う単語が使われますが,chicken はどちらにも同じ単語を使えるのはなですか?
(3) 20:01 --- AIでは実現不可能な言語の性質ってなんでしょうか?
(4) 25:17 --- 基本的に英語では修飾語句は後ろからかかるのに、どうして1語の形容詞は前からかかるのですか?
(5) 30:20 --- 「give 人 物」という語順は「give 物 to 人」と書き換えられるとされますが,何か違いはありますか?
(6) 36:30 --- 「5W1H」について,なぜ how だけ <h> で始まるのですか?
(7) 40:30 --- study と student で <u> の部分の発音の仕方が異なるのはなぜですか?
(8) 44:22 --- 日本語の読点や英語のコンマには,付け方の決まりはあるのですか?
参考までに過去3回分の「千本ノック」のへのリンクを張っておきます.それより前の回については,senbonknock の記事をご参照ください.
・ 「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」
・ 「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」
・ 「#1178. 千本ノック for 夏スク「英語史」」
2024-06-29 Sat
■ #5542. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 9 with 小河舜さん,まさにゃん,村岡宗一郎さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][beowulf][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][literature][preterite-present_verb][helkatsu]
先週の木曜日,6月20日(木)の夜に,堀田研究室に4名の英語史学徒が集結しました.そこで Voicy heldio にて「はじめての古英語」シリーズの第9弾を収録し,それを一昨日「#1124. 「はじめての古英語」第9弾 with 小河舜さん&まさにゃん&村岡宗一郎さん」としてお届けしました.生配信ではありませんでしたが,ライヴ感のある充実した内容となっているかと思います.ぜひお聴きいただければ.
今回の収録は,レギュラーメンバーの小河舜さん(上智大学),「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)に加え,村岡宗一郎さん(日本大学)をお呼びして収録しました.今回は古英語のある1文に集中しましたが,それだけで十分に堪能することができました.
上記のシリーズ回の翌日には「#1125. 「はじめての古英語」第9弾のアフタートーク」で,さらに4人が盛り上がる様子をお届けしています.個々のメンバーによる音読もあり,こちらも必聴です.
シリーズを重ねるにつれ,お聴きの皆さんの古英語への関心が高まってきているように感じます.さらにいえば,hel活 (helkatsu) 全般が活気づいてきています.リスナーの Grace さんによる A to Z の「英語史研究者紹介」というべき note,lacolaco さんによる「英語語源辞典通読ノート」,Lilimi さんによる古英語ファンアートを含む「Lilimiのオト」,り~みんさんによる X 上での古英語音読の試みなど,さまざまに盛り上がってきています
「はじめての古英語」シリーズ (hajimeteno_koeigo),これからも続けていければと思います.
2024-06-14 Fri
■ #5527. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 8 with 小河舜さん and まさにゃん and 五所万実さん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][goshosan][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
6月6日(木)の夜,Voicy heldio の生放送で「#1107. 「はじめての古英語」生放送(第8弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (5)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいた方々には,盛り上げていただきましてありがとうございました.
シリーズも第8弾となり安定感が出てきましたが,今回は普段の3人に加え,古英語を専攻していない五所万実さん(目白大学)に生徒役・聞き手役として出演していただきました.五所さんにリスナー代表として素朴な疑問を投げかけていただいたので,普段以上に学べる回となっています.結果として,これまでとは異なるおもしろさをお届けできたと思います.
今回も引き続き Bede 著『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節を読み進めました.古英語原文は hellog 「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますが,その第1段落の最後の "Þæt wīf" で始まる1文を超精読しました.語順,接続法(仮定法),関係代名詞などの統語的な観点からも,助動詞や動詞の意味変化の観点からも,英語史的に話題豊富な1文となっています.韻文から散文への文学史的な流れについても議論しています.
1時間弱にわたる文献学的な対談精読実況中継となっています.「古英語を楽しむ」という趣旨でお届けしていますので,ぜひリラックスして楽しみながらお聴きください.生放送に引き続き,4人で「#1108. 「はじめての古英語」第8弾のアフタートーク」も収録しました.恒例の3人の各々による古英語音読コーナーもあります.ぜひご聴取ください.
今後もシリーズを続けていきますが,今回で Bede のキリのよいところまで終えられたので,次回は別の古英語テキストに切り替えようと思っています.どうぞご期待ください.
2024-06-11 Tue
■ #5524. 「名前プロジェクト」のメンバー4名の発表ダイジェスト in heldio [onomastics][name_project][voicy][heldio][ogawashun][yadomisan][goshosan]
昨年の夏に立ち上げた「名前プロジェクト」 (name_project) の4名のメンバーが,9ヶ月ほどかけて「名前と英語史」に関する研究を各々進めてきました.その成果は学会シンポジウムにおける口頭発表という形で結実しましたが,それだけで終わらせるのはもったいないということで,Voicy heldio にて,それぞれのダイジェスト版を収録し,アーカイヴとして配信しました.
・ 「#1075. 「後期古英語期におけるヴァイキングの名称 --- 社会に呼応する名前とその役割」 --- 小河舜さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 小河舜さん(上智大学)
・ 「#1089. 「中英語の職業名 --- 英語名前史学の観点から」 --- 堀田隆一のシンポ発表ダイジェスト」 by 堀田隆一(慶應義塾大学)
・ 「#1102. 「初期近代英語におけるイエス・キリストの呼称 X に関する社会言語学的考察」 --- 矢冨弘さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 矢冨弘さん(熊本学園大学)
・ 「#1105. 「現代英語の商標にみる名前の価値とふるまい」 --- 五所万実さんのシンポ発表ダイジェスト」 by 五所万実さん(目白大学)
あくまでダイジェストですので特にハンドアウトなどの資料も添付していませんし,短時間の収録かつ声で伝えられることのみをお話ししています.むしろ発表の概要としては分かりやすくなっているかもしれません.
各配信回につきまして,Voicy のコメント欄を通じてご意見やご質問などいただけますと,ご本人からの回答があるかもしれません! ぜひお寄せいただければ幸いです.
2024-06-01 Sat
■ #5514. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 7 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
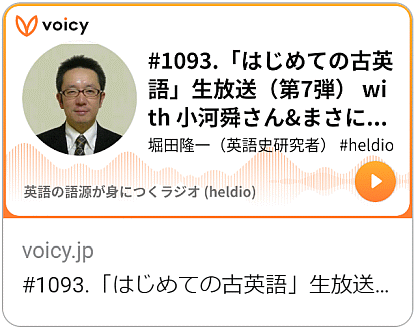
5月23日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.
今回もお相手は小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)です.毎回3人で元気に配信しています.
精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.
今回は,音読練習,統語的呼応と語順,仮定法を含む動詞屈折のおさらい,散文の発達に関する話題等で議論が盛り上がりました.収録後,3人のくだけた振り返り回として「#1094. 「はじめての古英語」第7弾のアフタートーク」も公開していますので,ぜひお聴きください.
これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.
(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」
(7) 「#1093.「はじめての古英語」生放送(第7弾) with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (4)」
次回もお楽しみに!
2024-05-15 Wed
■ #5497. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 6 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
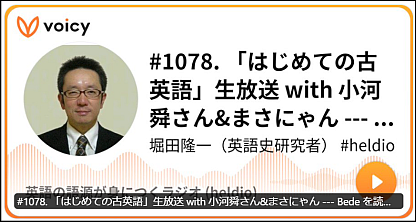
5月9日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」をお届けしました.ライヴでお聴きの方々には,投げ込みのコメントや質問をいただきましてありがとうございました.
精読対象テキストは,前回に引き続き,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳の1節です.原文は,hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載していますので,そちらをご覧になりながらお聴きください.
著者の Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.
今回は,古英語の動詞屈折の話題,とりわけ過去形や仮定法の話題に触れる機会が多くありました.また,定冠詞 the に相当する語の屈折についても議論しました.事後に出演者の1人「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)が,ご自身の note 上で復習となる記事「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#6 生放送3回目)」を公開されているので,そちらも合わせてご参照ください.
これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.
(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
(6) 「#1078. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (3)」
目下,次回 Part 7 に向けて3人とも鋭意準備中です.
2024-05-10 Fri
■ #5492. 「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」 --- 小河舜さんと東北本線普通列車より生放送でお届けしました [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock][ogawashun]
1週間前のことになりますが,5月3日午後,福島から仙台へ向かう東北本線普通列車の車中より,小河舜先生(上智大学)とともに,初の「道中千本ノック」を Voicy heldio の生放送でお届けしました.GW中にもかかわらず乗客の少ない車両の4人掛けの席より,陸奥の車窓風景を眺めながらの配信でした.各駅停車のアナウンスが入り込む等,普段の大学の研究室や教室で収録する千本ノックとは異なる風情と旅情があります.その様子は翌朝の heldio 通常配信回で「#1069. 千本ノック(生放送) with 小河舜さん --- 陸奥四人旅 その2」としてお届けしました.
先日,大学生より寄せてもらった素朴な疑問より,10件を取り上げています.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.お時間のあるときにお聴きいただければ.
(1) 02:25 --- 接頭辞には意味があると聞いたことがあります.例えば,ex- や in- などです.しかし experience など接頭辞の ex- に含意される「外に」という意味が含まれていなさそうな単語もあるのはなぜでしょうか?
(2) 07:25 --- デモで使う看板などはなぜ全て大文字で書くのか?
(3) 09:25 --- イギリス人はよく英語を誇りに思っているようですが,上流階級はフランス語由来の単語を好んで使うのはなぜですか?
(4) 11:50 --- is not, are not などは何故 ain't と省略されるのか?
(5) 15:21 --- 英語が SVO という語順をとるのはなぜ? なぜ日本語と違って結論が先にくるのか?
(6) 18:44 --- 語の省略に ' (アポストロフィ)が使われるのはなぜ?
(7) 22:16 --- A, B, C... を alphabet というのはなぜ?
(8) 23:22 --- 「パイレーツオブカリビアン」の原題は Pirates of THE Caribbean であるが,なぜ日本語版タイトルでは定冠詞が欠落するのか?
(9) 25:50 --- as の用法が多すぎるのはなぜか?
(10) 29:40 --- 英語語彙は豊富な借用が特徴の一つと聞きますが,助動詞にもラテン語・フランス語など他言語から借用されたものはありますか? また,助動詞のなかにも(本来語・仏・羅希の三層構造のような)formal --- informal の序列は認められますか?
前回の小河舜さんとの千本ノックもたいへん好評でした.そちらは「#5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています」 ([2024-04-23-1]) よりアクセスできますので,ぜひお聴きください.
2024-04-27 Sat
■ #5479. audience design の導入 with 3Ms [sociolinguistics][audience_design][accommodation_theory][variation][style][3ms][ogawashun][voicy][heldio][etymology][youtube]
Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」では,この木・金・土と連日 "3Ms" をお迎えして,賑やかに対談回(単なるおしゃべり?)をお届けしています.ちなみに "3Ms" とは,五所万実さん(目白大学),北澤茉奈さん(杉野服飾大学),尾崎萌子さん(慶應義塾大学大学院生;共立女子大学)のお三方のことです.実は小河舜さん(上智大学)も収録に部分的に同席しています.
とりわけ金・土の配信会は,聞き手ベースの言語学理論というべき Allan Bell による audience_design の導入回となっており,同理論に楽しく入っていくことができます.
(1) 「#1061. 聞き手ベースの言語学 --- 北澤茉奈さんとオーディエンス・デザインを導入します」(2024年4月26日配信)
(2) 「#1062. 21世紀のオーディエンスデザイン with 3Ms & 小河舜さん」(2024年4月27日配信)
同理論については,この hellog でも「#1934. audience design」 ([2014-08-13-1]) で紹介していますし,「いのほた言語学チャンネル」(旧「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」)でも北澤さんをお招きした回「#84. 新しい時代のオーディエンス・デザイン論・歴史言語学にも導入!---水曜言語学雑談飲み会」で導入しています.そちらもぜひご参照ください.
・ Bell, Allan. "Language Style as Audience Design." Language in Society 13 (1984): 145--204.
2024-04-24 Wed
■ #5476. 「ゼロから学ぶはじめての古英語」 Part 5 with 小河舜さん and まさにゃん [voicy][heldio][masanyan][ogawashun][oe][oe_text][bede][christianity][anglo-saxon][st_augustine][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][popular_passage][history][literature]
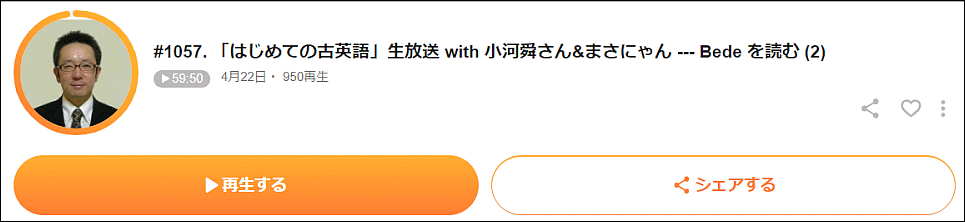
4月18日(木)の夜,Voicy heldio にて「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」をお届けしました.ライヴでお聴きいただいたリスナーの方々には,盛り上げていただき感謝いたします.
前回に引き続き,精読対象となったテキストは,Bede によりラテン語で著わされた『英国民教会史』 (Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum [= Ecclesiastical History of the English People]) の古英語訳からの1節です.3人で60分ほどかけてわずか1.5文しか進みませんでしたが,それだけ「超」精読・解説したということでお許しいただければと思います.同テキストは hellog の「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.
Bede については,heldio 「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」にて解説していますので,そちらもお聴きください.
復習のために,これまでの「はじめての古英語」シリーズ回を一覧しておきます.
(1) 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
(2) 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
(3) 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
(4) 「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」
(5) 「#1057. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む (2)」
今回の第5弾の収録の舞台裏については,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」としてお話ししていますので,ご関心のある方はぜひ helwa へお入りください.
最後に,本シリーズ出演者の小河舜さん(上智大学)と「まさにゃん」こと森田真登さん(武蔵野学院大学)については,以下の記事をご覧ください.
・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])
・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])
今後も応援のほどよろしくお願い致します! 本シリーズ第6弾もお楽しみに!
2024-04-23 Tue
■ #5475. 久しぶりの千本ノック収録を公開しています [notice][voicy][heldio][sobokunagimon][senbonknock][ogawashun]
4月18日(木)の午前11時より,事前に大学生より回収していた「英語に関する素朴な疑問」に英語史の観点から回答する「千本ノック」 (senbonknock) のイベントを開催しました.同イベントは Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」の公開収録生放送としてお届けしましたが,その音源はその翌日に heldio の通常配信として公開されており,アーカイヴとしても残っています.「#1054. 年度初めの「英語に関する素朴な疑問 千本ノック」生放送 with 小河舜さん」です.私のほか,もう一人の英語史研究者小河舜先生(上智大学)にも回答者としてお付き合いいただき,おおいに盛り上がりました.60分ほどの長尺ですが,内容は充実しています.お時間のあるときにお聴きください.
今回の千本ノックも,回答しがいのある素朴な疑問が多かったと思います.今回は17件の質問に回答しました.以下に本編(第2チャプター)の分秒を挙げておきます.
(1) 02:50 --- なぜ英語話者はめったに噛まないのか.
(2) 05:01 --- 筆記体がなぜ使われているのか.日本語において筆記体に値するくずし字なるものはすでに消失しているが,英語においては筆記体が残っている.成立の起源や使いやすさの違いがあるのか.
(3) 10:22 --- 外国の方が話す日本語や,日本人が話す韓国語などはたどたどしくても伝わりますが,非ネイティブが話す英語はネイティブの人々にどう捉えられているのでしょうか.
(4) 14:35 --- 疑問詞は how を除いてなぜ wh- で始まるのですか.(この疑問については hellog-radio 「#2. 疑問詞は「5W1H」といいますが,なぜ how だけ h で始まるのでしょうか?」もお聴きください.)
(5) 17:37 --- "hello" の L のようにアルファベットが2つ並ぶことがあるのはなぜか.
(6) 22:02 --- 英語は日本語よりも表現の幅や慣用表現が狭い/少ない気がするのですが本当のところはどうですか.洋楽をきいていると同じような言い回しが多い気がします.
(7) 25:26 --- どうして would や could などの過去形を使うと丁寧な意味になるのか.
(8) 29:15 --- 仮定法で現在の話でも過去形を使う理由.また,If I was ではなく If I wereである理由.
(9) 31:39 --- 英語学習ではアクセントに重点が置かれますが,いつ誰が今のアクセントを決めたのですか.
(10) 36:30 --- 「--ない?」という質問に対して答えが「ある」だった場合,なぜ Yes と答えるのか.
(11) 39:47 --- 翻訳アプリ技術の発達が目覚ましいので,外国語の勉強をあまりしなくても外国語をある程度運用できるようになってきています.今後の日本では外国語教育の時間を減らすべきでしょうか.
(12) 44:09 --- 「群れ」を表す英単語の種類が多いのはなぜか.(pack, flock, school, etc.)
(13) 46:30 --- 方角の in ですが,なぜ英語圏では方角を「空間」として捉えるのか.
(14) 48:52 --- 日本の英語訛りについて,GHQ をはじめアメリカ人に支配された過去があるにもかかわらず,なぜイギリス訛り(カタカナ英語?)に近い音なのか.
(15) 51:25 --- なぜ英語では疑問文でクエスチョンマークを使うのか.語順だけで疑問文だということがわかるのに.
(16) 55:45 --- 「風呂に入る」が「take a bath」となり bath が可算名詞であるのはなぜか.
(17) 57:45 --- なぜ時・条件を表す副詞節の中では未来のことを現在形で表すのか?
生放送後,小河先生とは振り返りの会を開き,そちらも heldio 収録しました.ぜひ「#1055. 「千本ノック with 小河舜さん」のアフタートーク」も聴いていただければ.
2024-04-07 Sun
■ #5459. 「はじめての古英語」シリーズのオマケとしての古英語音読投稿企画が続いています [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helkatsu]
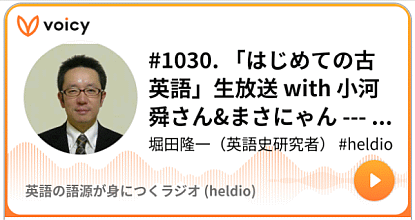
3月25日(月)に Voicy heldio の生放送としてお届けした「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」に対して,多くの反響をいただいています.本ブログでも「#5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」」 ([2024-03-29-1]) にて振り返った通りです.
上記配信回では「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) で公開した古英語テキストの一部を,小河舜先生(上智大学)および「まさにゃん」こと森田真登先生(武蔵野学院大学)と3人で精読・解説しました.
その後,復習用のオマケ・遊びとして,問題の古英語原文を音読・収録し,X(旧ツイッター)上に投稿する "The First Take" の企画を展開しました.3人による一発録り音読を投稿した後,熱心なお2人のリスナーさんにバトンを継いでいただきました.
(1) まさにゃんによる音読投稿
(2) 小河舜さんによる音読投稿
(3) 堀田隆一による音読投稿
(4) リスナーのり~みんさんによる音読投稿
(5) リスナーのりりみさんによる音読投稿
学びのための遊び企画として,ぜひ他の方々にもバトンを継いでいただければ幸いです.何度か音読を練習した上で,本番として動画録音し,その動画を X 上で投稿していただくだけです.その際に,上記の既存の投稿への引用ポストとしていただくか,あるいは #はじめての古英語 とハッシュタグを付けて投稿していただければ,皆さんがすぐに認識できます.
この古英語音読投稿企画は,今後の同シリーズでも継続していきたいと思っています.年度初めの「hel活」 (helkatsu) の一環として,一人でも多くの方に乗っていただければ.
2024-03-29 Fri
■ #5450. heldio の人気シリーズ復活 --- 「ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 4 with 小河舜さん and まさにゃん」 [voicy][heldio][ogawashun][masanyan][hajimeteno_koeigo][hel_education][notice][oe_text][helwa]
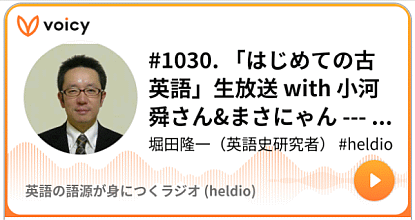
去る3月25日(月)13:30より予定通り Voicy heldio にて「「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん」をお届けしました.平日のお昼過ぎという時間帯ではありましたが,ライヴで参加し,盛り上げていただいたリスナーの皆さんに感謝いたします.生放送を収録したものを,翌朝の通常回にて「#1030. 「はじめての古英語」生放送 with 小河舜さん&まさにゃん --- Bede を読む」として配信しました.精読の対象となった古英語テキストは,「#5444. 古英語の原文を読む --- 597年,イングランドでキリスト教の布教が始まる」 ([2024-03-23-1]) に掲載しています.本編53分の長尺配信ですが,聴き応えのある回となっていますので,お時間のあるときにでもどうぞ.
「シリーズ復活」と述べましたが,過去に3回ほどお届けしてきました.いずれも昨年の8月から9月にかけての配信です.
・ 「#822. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 1 with 小河舜さん and まさにゃん」
・ 「#829. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 2 with 小河舜さん and まさにゃん」
・ 「#836. ゼロから学ぶはじめての古英語 --- Part 3 with 小河舜さん and まさにゃん」
今回も含め本シリーズに出演していただいている2人と,その heldio 出演歴については,以下の記事をご覧ください.
・ 「#5445. 小河舜さんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-24-1])
・ 「#5446. まさにゃんとのhel活(まとめ)」 ([2024-03-25-1])
今回の配信回の復習には,まさにゃんが自身の note のなかで公開している「ゼロから学ぶ はじめての古英語(#4 生放送)」もご覧ください.
ちなみに生放送の日の朝6時の heldio では「#1029. 尊師ベーダ --- The Venerable Bede」と題して,古英語テキストの究極のソースを表わしたアングロサクソンの大学者を紹介しています.
さらに生放送の日の夜には,プレミアム限定配信チャンネル「英語史の輪」 (helwa) のほうで「【英語史の輪 #111】「はじめての古英語」生放送の反省会&アフタートーク」もお届けしています.
最後に,昨日付でコアリスナーの umisio さんが,今回の配信回のまとめノートを作り,それをこちらのページにて公開されています.
本シリーズをさらに続けていけますよう,皆さん,応援をよろしくお願い致します!
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow