2026-02-06 Fri
■ #6129. language の <u> と /w/ [spelling][etymological_spelling][spelling_pronunciation][emode][orthography][mond]
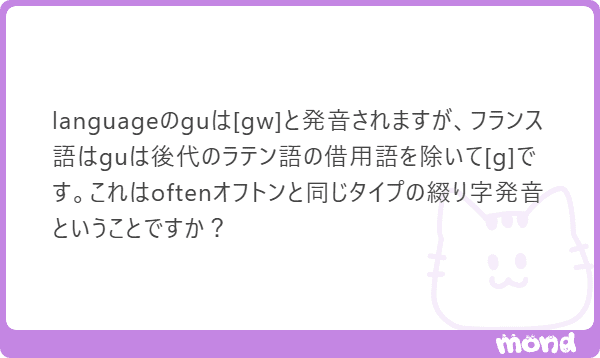
昨日の記事「#6128. 1月の mond で10件の問いに回答しました」 ([2026-02-05-1]) で触れた通り,先月の mond ではが綴字と発音の乖離 (spelling_pronunciation_gap) に関する話題が多く取り上げられた.そのなかに「language の gu は [gw] と発音されますが,フランス語は gu は後代のラテン語の借用語を除いて [g] です.これは often オフトンと同じタイプの綴り字発音ということですか?」という問いがあった.
この質問に対して1月27日に回答を投稿したのだが,回答準備のためにいくつか調べたことがあるので,ここに掲載しておきたい.まず MED の当該語の見出しを確認しておこう.
langāǧe (n.) Also langag, langaige, longage, language, languege, langwache, (errors) lanquage, langegage.
早くから異綴字として <u> や <w> を含むものもあったようだ.
次に OED の Notes の記述より.
Both in Anglo-Norman (where they are much more frequent than in continental French) and in English, spellings with insertion of u or w after g are due to the influence of classical Latin lingua, as is the standard pronunciation of the English word. In Middle English the word was usually pronounced without /w/ ; the 16th-cent. orthoepists Hart and Bullokar still record this pronunciation as the usual one, and it survives in Scots and Irish English, as shown e.g. by the spellings langidge, langige. See further E. J. Dobson Eng. Pronunc. 1500--1700 (ed. 2, 1968) vol. II. §421 note 7.
ここで言及されている Dobson (Vol. 2, §421, n. 7) に当たってみると,次のようにある.
Note 7: Language, being an adoption of OF langage, normally lacks [w] in ME; so Hart and Bullokar (normally). But it is early affected, in spelling and pronunciation, by Latin lingua (cf. the fourteenth-century spelling langwag recorded by OED); hence [gw] in Bullokar (as a rarer variant), Mulcaster, Gil (who actually gives u), Butler, Hodges, The English Schole-master, Strong, Young, Cooper, and Brown. Similarly banquet (OF banc + et) should have [k], as in Levins, Laneham, Hodges, Strong, and Young; but Coles gives the 'phonetic' spelling bang-quet (contrast blang-ket 'blanket'), which shows the beginning of the PresE spelling-pronunciation. Cooper says that the word is spelt either banquet or banket.
ここでは language の類例として banquet が挙げられている.mond の回答では banquet には触れなかったが,そちらの語も歴史的な振る舞いを調べてみると興味深そうだ.
・ Dobson, E. J. English Pronunciation 1500--1700. 2nd ed. 2 vols. Oxford: OUP, 1968.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow