2025-12-10 Wed
■ #6071. 「いのほた」で no に関する回が多く視聴されています [inohota][inoueippei][notice][youtube][negative][negation][etymology][article][sobokunagimon]
12月7日(日)の YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の話題は「#391. おなじ no でも元々ちがうことば --- no money の no と No, I don't. の no」でした.3週間ほど前の「#387. 英語にはなぜ冠詞があるの?日本語には冠詞がないが,英語の冠詞の役割と似ているのは日本語のあれ」が思いのほか人気回となった(1.45万回視聴)ので,冠詞 (article) の話題の続編というつもりで話しを始めたのですが,地続きのトピックとして no に言及したところ,井上さんがむしろそちらにスポットライトを当て,今回のタイトルとサムネになった次第です.結果として,今回も多くの方々に視聴していただき,良かったです.皆さん,ありがとうございます.
前回の冠詞回でも話したのですが,不定冠詞 a/an は,もともと数詞の one に由来しているので,その本質は存在標示にあるとみなせます.これに対して,否定語の no の本質は,まさに不在標示です.a/an と no は,ある意味で対極にあるものととらえられます.存在するのかしないのか,1か0か,という軸で,不定冠詞と no を眺めてみる視点です.
この観点から見ると,英文法で習う few と a few の意味の違いも理解できます.few は元来 many の対義語であり,「多くない」という否定的な意味合いが強い語です.しかし,これに存在標示の a をつけてみるとどうなるでしょうか.「ないわけではないが,多くはない」という few の否定に傾いた意味に,a が「少ないながらも存在はしている」という肯定的なニュアンスを付け加え,結果として「少しはある」へと意味が調整される,と解釈できるわけです.
さて,この a/an と no の対立構造も奥深いテーマなのですが,今回の動画で視聴者の皆さんが最も驚きをもって受け止めたのは,タイトルにもある通り,2つの no が別語源だった,という事実ではないでしょうか.現代英語では,形容詞として使われる no と,副詞として使われる no が,たまたま同じ綴字・発音になっていますが,実は歴史的なルーツは異なるものなのです.
普段何気なく使っている単語でも,そのルーツをたどると,驚くような歴史が隠されているものです.皆さんもこの不思議な no の歴史を,ぜひ YouTube の動画で確認してみてください.言語学的な知的好奇心を刺激されること請け合いです.また,冠詞や否定というテーマは,情報構造や会話分析にもつながる非常に大きな問題ですので,今後も多角的に掘り下げていきたいと考えています.
2025-07-25 Fri
■ #5933. 等位接続詞 but の「逆接」 [adversative][conjunction][semantics][pragmatics][presupposition][negative][negation][oximoron][but]
日本語の「しかし」然り,英語の but 然り,逆接の接続詞 ((adversative) conjunction) と呼ばれるが,そもそも逆接とは何だろうか.今回は英語の but を用いた表現に注目するが,例えば A but B とあるとき,A と B の関係が逆接であるとは,何を意味するのだろうか.
最も単純に考えれば,A と B が意味論的に反意の場合に,その関係は逆接といえるかもしれない.しかし,意味論的に厳密に反意の場合には,but を仲立ちとして組み合わされた表現は,逆接というよりは矛盾,あるいは撞着語法 (oxymoron) となってしまう.She is rich but poor. のような例だ.
したがって,多くの場合,but による逆接の表現は,意味論的に厳密な反意というよりも語用論的なズレというべきなのかもしれない.A を理解するために必要な前提 (presupposition) が B では通用しないとき,換言すれば A から期待されることが B で成立しないとき,語用論的な観点から,それを逆接関係とみなす傾向があるのではないか.
この辺りの問題をつらつらと考えていたが,埒が明かなそうなので,Quirk et al. (§13.32)に当たってみた.
The use of but 13.32
But expresses a contrast which could usually be alternatively expressed by and followed by yet. The contrast may be in the unexpectedness of what is said in the second conjoin in view of the content of the first conjoin:
John is poor, but he is happy. ['. . . and yet he is happy']
This sentence implies that his happiness is unexpected in view of his poverty. The unexpectedness depends on our presuppositions and our experience of the world. It would be reasonable to say:
John is rich, but he is happy.
if we considered wealth a source of misery.
The contrast expressed by but may also be a repudiation in positive terms of what has been said or implied by negation in the first conjoin (cf 13.42):
Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening. [1]
In such cases the force of but can be emphasized by the conjunct rather or on the contrary (cf 8.137):
I am not objecting to his morals, but rather to his manners. [2]
With this meaning, but normally does not link two clauses, but two smaller constituents; for example, the conjoins are two predicates in [1] and two prepositional phrases in [2]. The conjoins cannot be regarded as formed simply by ellipsis from two full clauses, since the not in the first clause conjoin is repudiated in the second. Thus the expansion of [2] into two full clauses must be as follows:
I am not objecting to his morals, but (rather) I am objecting to his manners.
この節を読み,not A but B の表現においてなぜ but が用いられるかの理屈が少し分かってきた.A は否定的で,B は肯定的であるという,極性が反対向きであることを逆接の接続時 but が表わしている,ということなのだろう.
・ Quirk, Randolph, Sidney Greenbaum, Geoffrey Leech, and Jan Svartvik. A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman, 1985.
2025-07-24 Thu
■ #5932. but の様々な用法をどう評価するか --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]
昨日の記事「#5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より」 ([2025-07-22-1]) でみた but の様々な用法間の関係について,Kruisinga は結論部となる1節で次のように述べている (II. 2, p. 433) .
1514. In dealing with the meanings of the conjunction as an attempt has been made to show most of its uses as a development of its comparative sense. No such attempt has been made in the case of but because its various meanings are not connected but isolated. The result of this isolation (indeed its cause as well) is that but is not so strong and live an element of present-day English, and several of its uses tend to be restricted to literary English, i.e. they are on the road that will ultimately lead to their disappearance. This may be said of the uses in 1509, 1 and 3; 1510, 2; the use of but what may be considered dialectal by some, although it is not corrected away by editors and writers.
but の多様な用法が as のそれと比較されているが,後者はある程度は統一的に説明できるものの,前者はそれが無理だと述べられている.それほど but の多義性は厄介である.歴史的な観点からも説明しがたい難物.
・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.
2025-07-23 Wed
■ #5931. but の様々な用法 --- Kruisinga より [but][polysemy][conjunction][preposition][adverb][negation][polarity][negative]
連日 but に注目している.この単語の様々な用法について.Kruisinga (II. 2, pp. 431--33) が5節にわたり紹介している.とりわけ関係代名詞的な用法や緩く副詞節を導く用法の扱いを取り上げている.
1509. But can be used in simple sentences, also as a coordinating conjunction, and as a subordinating conjunction to introduce a clause.
In simple sentences the conjunction but is not easily to be distinguished from adverbs; it may express:
(1) 'only', as in She is but a child.
(2) 'except', as in They are all wrong but he. See also 974f.
(3) 'than', after comparatives and similar words, as in There remains no more but to thank you for your courteous attention; It is nothing else but laziness.
1510. As a conjunction connecting sentences but may express a restriction of a preceding coordinate statement, as in You were right but you should not have said anything about it.
As a subordinating conjunction but may introduce:
(1) attributive clauses defining a noun in a negative sentence; the antecedent noun has the function of the subject of the clause.
- Not a paper reaches us from Russia but contains an account of some new educational enterprise. (Times Ed. S. 29/5, '19.)
- Few readers but will be astonished to find that the field should be so rich and wide. (Times Lit. 25/1, '18.)
- There are few thinking people but realize the great war as the death-agony of an old order, the birth-travail of a new. (Times Lit. 10/9, '15.)
- Colburn ... was too clever to need a magazine; not a living publisher but would have to yield to him in the gentle art of puffing. (ib. 20/4, '17.)
(2) adverb and object clauses. These two kinds are here grouped together because a distinction is necessarily arbitrary and meaningless. The leading clause is always negative just as in the preceding case.
- Justice was never done but someone complained.
- Who knows but he may hear of it?
1511. When the negative noun that may be said to be defined by a but-clause is not the subject of the subordinate clause, the attributive character of the clause is so little marked that it may be interpreted as an adverb clause (a). The same can be said of attributive clauses when the noun is referred to by a personal pronoun as a subject of the clause (b).
a. Scarcely a week passes but the association is consulted by private landowners or by public authorities.
b. There was never a Samson so strong but he met his Delilah. (Hobbes, Emotions I ch. 4.)
1512. The subordinating character of but is sometimes emphasized by adding that; see 1492. It occurs:
(1) in the sense of except that; compare 1509, 2.
- Each would have done the same by the other but that they lacked the courage.
(2) in a sense very similar to that of 1511.
- He is not such a fool but that he can see that.
- I do not think it possible but that some will agree with me.
1513. A less frequent group-conjunction is but what.
- Not a mood of his but what found a ready sympathiser in Margaret; not a wish of his that she did not strive to forecast, and to fulfil. (Gaskell, North and South ch. 41 p. 364)
- Not a soul in the auditorium or on the stage but what lived consummately during these minutes. (Bennett, Leonora ch. 6.)
- Therefore we seldom took a walk together but what we were stoned by boys in the street. (Davies, Super-Tramp ch. 21 p. 181.)
このような but の多様な用法を貫く原義や原理はあるのだろうか.いずれの用法にしても否定的な文脈で用いられているのが特徴的といえるが,この否定極性を別にすれば,共通する特徴を見出すのは容易ではない.
・ Kruisinga, E A Handbook of Present-Day English. 4 vols. Groningen, Noordhoff, 1909--11.
2025-07-22 Tue
■ #5930. 7月26日(土),朝カル講座の夏期クール第1回「but --- きわめつきの多義の接続詞」が開講されます [asacul][notice][conjunction][preposition][adverb][polysemy][semantics][pragmatics][syntax][negative][negation][hee][kdee][etymology][hel_education][helkatsu][link]
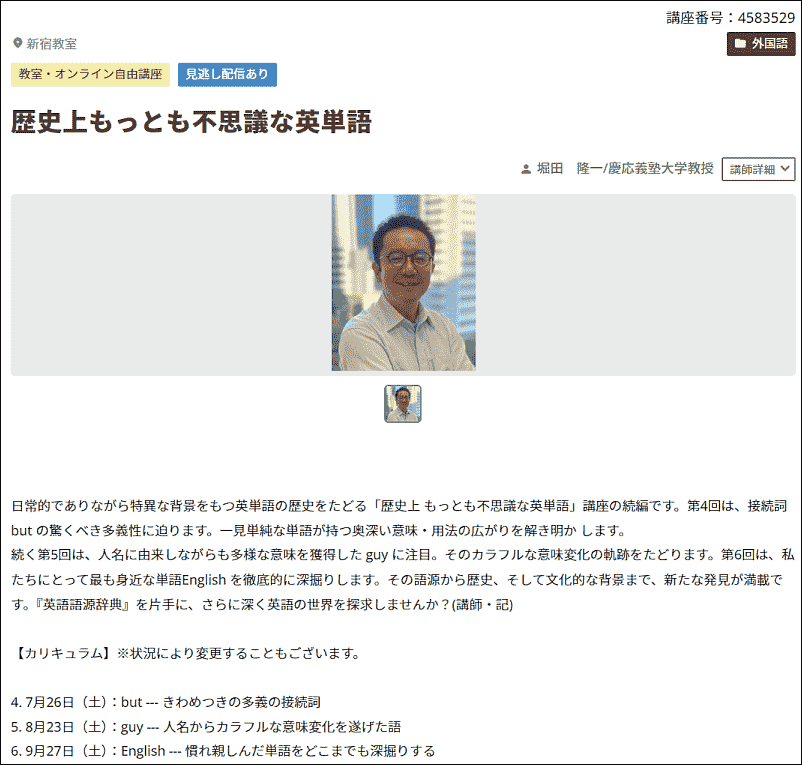
今年度朝日カルチャーセンター新宿教室にて,英語史のシリーズ講座を月に一度の頻度で開講しています.今年度のシリーズのタイトルは「歴史上もっとも不思議な英単語」です.毎回1つ豊かな歴史と含蓄をもつ単語を取り上げ,『英語語源辞典』(研究社)や新刊書『英語語源ハンドブック』(研究社)などの文献を参照しながら,英語史の魅力に迫ります.
今週末7月26日(土)の回は,夏期クールの初回となります.機能語 but に注目する予定です.BUT,しかし,but だけの講座で90分も持つのでしょうか? まったく心配いりません.but にまつわる話題は,90分では語りきれないほど豊かです.論点を挙げ始めるとキリがないほどです.
・ but の起源と発達
・ but の多義性および様々な用法(等位接続詞,従属接続詞,前置詞,副詞,名詞,動詞)
・ "only" を意味する but の副詞用法の発達をめぐる謎
・ but の語用論
・ but と否定極性
・ but にまつわる数々の誤用(に関する議論)
・ but を特徴づける逆接性とは何か
・ but と他の接続詞との比較
but 「しかし」という語とじっくり向き合う機会など,人生のなかでそうそうありません.このまれな機会に,ぜひ一緒に考えてみませんか?
受講形式は,新宿教室での対面受講に加え,オンライン受講も選択可能です.また,2週間限定の見逃し配信もご利用できます.ご都合のよい方法で参加いただければ幸いです.講座の詳細・お申込みは朝カルのこちらのページよりどうぞ.皆様のエントリーを心よりお待ちしています.
(以下,後記:2025/07/23(Wed))
本講座の予告については heldio にて「#1515. 7月26日の朝カル講座 --- 皆で but について考えてみませんか?」としてお話ししています.ぜひそちらもお聴きください.
・ 寺澤 芳雄(編集主幹) 『英語語源辞典』新装版 研究社,2024年.
・ 唐澤 一友・小塚 良孝・堀田 隆一(著),福田 一貴・小河 舜(校閲協力) 『英語語源ハンドブック』 研究社,2025年.
2024-11-07 Thu
■ #5673. 10月,Mond で5件の質問に回答しました [mond][sobokunagimon][hel_education][notice][link][helkatsu][numeral][grammaticalisation][number][category][dual][negation][perfect][subjunctive][heldio]
先月,知識共有サービス Mond にて5件の英語に関する質問に回答しました.新しいものから遡ってリンクを張り,回答の要約も付します.
(1) なぜ数量詞は遊離できるのに,冠詞や所有格は遊離できないの?
回答:理論的には数量詞句 (QP) と限定詞句 (DP) の違いによるものと説明できそうですが,一筋縄では行きません.歴史的にいえば,古英語から現代英語に至るまで,数量詞遊離は常に存在していましたが,時代とともに制限が厳しくなってきているという事実があります.詳しくは新刊書の田中 智之・縄田 裕幸・柳 朋宏(著)『生成文法と言語変化』(開拓社,2024年)をご参照ください.
(2) have got to の got とは何なのでしょうか?
回答:have got は本来「獲得したところだ」という現在完了の意味でしたが,16世紀末から「持っている」という単純な意味に転じました.文法化 (grammaticalisation) の過程を経て,口語で have の代用として定着しています.「#5657. 迂言的 have got の発達 (1)」 ([2024-10-22-1]),「#5658. 迂言的 have got の発達 (2)」 ([2024-10-23-1]) を参照.
(3) 英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか?
回答:「1」が他の数と比べて特に基本的で重要な数であるためと考えられます.古英語には双数形もありましたが,中英語以降は単数・複数の2区分となりました.世界の言語では最大5区分まで持つものもあります.「#5660. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より」 ([2024-10-25-1]) を参照.
(4) 完了形はなぜ動作の継続を表現できるのでしょうか?
回答:完了形の諸用法の共通点は「現在との関与」です.継続の意味は主に状態動詞で現われ,動作動詞では完了の意味が表出します.また「時間的不定性」も完了形の重要な特徴と考えられます.「#5651. 過去形に対する現在完了形の意味的特徴は「不定性」である」 ([2024-10-16-1]) を参照.
(5) subjunctive mood (仮定法・接続法)の現在完了について
回答:仮定法現在完了は理論上存在可能で実例も見られますが,比較的まれです.仮定法の体系は「現在・過去・過去完了」の3つ組みとして理解するのが妥当で,その中で完了相が必要な場合に現在完了形が使用される,と解釈するのはいかがでしょうか.
以上です.11月も Mond にて英語(史)に関する素朴な疑問を受け付けています.気になる問いをお寄せください.
2024-10-26 Sat
■ #5661. 否定とは何か? [negation][polarity][negative][terminology][syntax][double_negative][logic][assertion][semantics]
昨日の記事「#5670. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より」 ([2024-10-24-1]) で,否定 (negation) の話題を最後に出しました.言語において否定とは何か.これはきわめて大きな問題です.論理学や哲学からも迫ることができますが,ここでは言語学の観点に絞ります.
言語学の用語辞典に頼ることから始めましょう.まず Crystal (323--24) より引用します.
negation (n.) A process or construction in GRAMMATICAL and SEMANTIC analysis which typically expresses the contradiction of some or all of a sentence's meaning. In English grammar, it is expressed by the presence of the negative particle (neg, NEG) not or n't (the CONTRACTED negative); in LEXIS, there are several possible means, e.g. PREFIXES such as un-, non-, or words such as deny. Some LANGUAGES use more than one PARTICLE in a single CLAUSE to express negation (as in French ne . . . pas). The use of more than one negative form in the same clause (as in double negatives) is a characteristic of some English DIALECTS, e.g. I'm not unhappy (which is a STYLISTICALLY MARKED mode of assertion) and I've not done nothing (which is not acceptable in STANDARD English). . . .
A topic of particular interest has been the range of sentence STRUCTURE affected by the position of a negative particle, e.g. I think John isn't coming v. I don't think John is coming: such variations in the SCOPE of negation affect the logical structure as well as the semantic analysis of the sentence. The opposite 'pole' to negative is POSITIVE (or AFFIRMATIVE), and the system of contrasts made by a language in this area is often referred to as POLARITY. Negative polarity items are those words or phrases which can appear only in a negative environment in a sentence, e.g. any in I haven't got any books. (cf. *I've got any books).
次に Bussmann (323) を引用します.論理学における否定に対して言語学の否定を,次のように解説しています.
In contrast with logical negation, natural language negation functions not only as sentence negation, but also primarily as clausal or constituent negation: she did not pay (= negation of predication), No one paid anything (= negation of the subject NP), he paid nothing (= negation of the object NP). Here the scope (= semantic coverage) of negation is frequently polysemic or dependent on the placement of negation, on the sentence stress . . . as well as on the linguistic and/or extralinguistic context. Natural language negation may be realized in various ways: (a) lexically with adverbs and adverbial expressions (not, never, by no means), indefinite pronouns (nobody, nothing, none), coordinating conjunctions (neither . . . nor), sentence equivalents (no), or prepositions (without, besides); (b) morphologically with prefixes (in + exact, un + interested) or suffix (help + less); (c) intonationally with contrastive accent (in Jacob is not flying to New York tomorrow the negation can refer to Jacob, flying, New York, or tomorrow depending which elements are stressed); (d) idiomatically by expressions like For all I care, . . . . Formally, three types of negation are differentiated: (a) internal (= strong) negation, the basic type of natural language negation (e.g. The King of France is not bald); (b) external (= weak) negation, which corresponds to logical negation (e.g. It's not the case/it's not true that p); (c) contrastive (= local) negation, which can also be considered a pragmatic variant of strong negation to the degree that stress and the corresponding modifying clause are relevant to the scope of the negation (e.g. The King of France is not bald, but rather wears glasses. The linguistic description of negation has proven to be a difficult problem in all grammatical models owing to the complex interrelationship of syntactic, prosodic, semantic, and pragmatic aspects.
この2つの解説に基づいて,言語学における否定に関する論点・観点を箇条書き整理すると次のようになるでしょうか.
1. 否定の種類と範囲
・ 文否定 (sentence negation)
・ 節否定 (clausal negation)
・ 構成要素否定 (constituent negation)
2. 否定の実現様式
・ 語彙的 (lexically): 副詞,不定代名詞,接続詞,前置詞など
・ 形態的 (morphologically): 接頭辞,接尾辞
・ 音声的 (intonationally): 対照アクセント
・ 慣用的 (idiomatically): 特定の表現
3. 否定の形式的分類
・ 内的(強い)否定 (internal/strong negation)
・ 外的(弱い)否定 (external/weak negation)
・ 対照的(局所的)否定 (contrastive/local negation)
4. 否定の作用域 (scope)
・ 否定辞の位置による影響
・ 文強勢による影響
・ 言語的・非言語的文脈による影響
5. 2重否定 (double negative)
・ 方言や非標準英語での使用
・ 文体的に有標な肯定表現としての使用
6. 極性 (polarity)
・ 肯定 (positive/affirmative) vs. 否定 (negative)
・ 否定極性項目
7. 否定に関する統語的,韻律的,意味的,語用論的側面の複雑な相互関係
8. 自然言語の否定と論理学的否定の違い
この一覧は,否定の複雑さと多面性を示しています.案の定,抜き差しならない問題です.
・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.
・ Bussmann, Hadumod. Routledge Dictionary of Language and Linguistics. Trans. and ed. Gregory Trauth and Kerstin Kazzizi. London: Routledge, 1996.
2024-10-25 Fri
■ #5660. なぜ英語には単数形と複数形の区別があるの? --- Mond での質問と回答より [emode][number][category][plural][dual][negation][mond][sobokunagimon][ai][voicy][heldio]
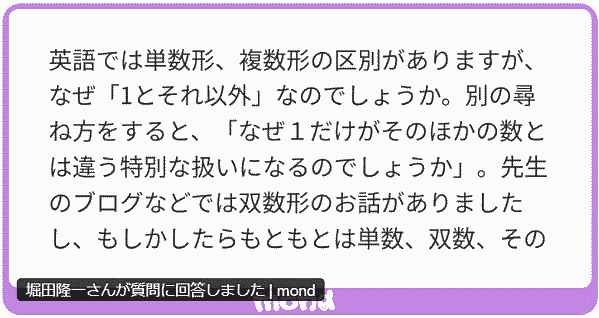
先日,知識共有サービス Mond に上記の素朴な疑問が寄せられました.質問の全文は以下の通りです.
英語では単数形,複数形の区別がありますが,なぜ「1とそれ以外」なのでしょうか.別の尋ね方をすると,「なぜ1だけがそのほかの数とは違う特別な扱いになるのでしょうか」.先生のブログなどでは双数形のお話がありましたし,もしかしたらもともとは単数,双数,そのほかの数(3や,「ちょっとたくさん」,「ものすごくたくさん」など?)によって区別されていたものが,言語の歴史の中で単純化されてきたということは考えられますが,それでも1の区別だけは純然と残っているのだとすると,とても不思議に感じます.
この本質的な質問に対して,私はこちらのようにに回答しました.私の X アカウント @chariderryu 上でも,この話題について少なからぬ反響がありましたので,本ブログでも改めてお知らせし,回答の要約と論点を箇条書きでまとめておきたいと思います.
1. 古今東西の言語における数のカテゴリー
・ 現代英語では単数形「1」と複数形「2以上」の2区分
・ 古英語では双数形も存在したが,中英語までに廃れた
・ 世界の言語では,最大5区分(単数形,双数形,3数形,少数形,複数形)まで確認されている
・ 日本語や中国語のように,明確な数の区分を持たない言語も存在する
・ 言語によってカテゴリー・メンバーの数は異なり,歴史的に変化する場合もある
2. なぜ「1」と「2以上」が特別なのか?
・ 「1」は他の数と比較して特殊で際立っている
・ 最も基本的,日常的,高頻度,かつ重要な数である
・ 英語コーパス (BNCweb) によれば,one の使用頻度が他の数詞より圧倒的に高い
・ 「1」を含意する表現が豊富 (ex. a(n), single, unique, only, alone)
・ 2つのカテゴリーのみを持つ言語では,通常「1」と「2以上」の区分になる
3. もっと特別なのは「0」と「1以上」かもしれない
・ 「0」と「1以上」の区別が,より根本的な可能性がある
・ 形容詞では no vs. one,副詞では not の有無(否定 vs. 肯定)に対応
・ 数詞の問題を超えて,命題の否定・肯定という意味論的・統語論的な根本問題に関わる
・ 人類言語に備わる「否定・肯定」の概念は,AI にとって難しいとされる
・ 「0」を含めた数のカテゴリーの考察が,言語の本質的な理解につながる可能性があるのではないか
数のカテゴリーの話題として始まりましたが,いつの間にか否定・肯定の議論にすり替わってしまいました.引き続き考察していきたいと思います.今回の Mond の質問,良問でした.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow