2025-07-31 Thu
■ #5939. 2025年度前期,英語史の授業を通じて何を学びましたか? [hel_education][sobokunagimon][voicy][heldio][khelf][inohota][inoueippei]
今年度の大学の前期も無事に終了.学期末に,英語史概説の講義について履修者から感想や意見を募った.多少の編集を加えつつ,匿名のままでコメントを紹介したい.
・ 言語の変化というものは,合理化・規則化されていったというだけの内面的な理由ではなく,その地域,その話者の文化・社会との関係性といった外面的な理由も探らなければ語ることはできないという,英語史の意議や深みを知ることができた
・ 「英語史」という学術領域がしっかりあるということに興味を持ってとった授業だったが,総じて学問としての面白さ,過去の歴史から現代を見つめ直す面白さを知れたと思う.その中で,初回の授業であった英語に対する純粋な疑問を受講生から集めて,それを解説する回は,学問に対する素直な姿勢と純粋な疑問から展開される学問の面白さを実感した.
・ 英語史の講義を通して,単なる英語の歴史を学んでいるのではなくて,「社会」のことも学べるという新たな視点を持つことができた.この新たな視点を持ってこれからの講義に臨みたいし,また新たな価値を創出したいと感じた.
・ 私は単語やつづりをおぼえるのがとても苦手で苦労している.しかし,その単語一つ一つに注目し,「これは,○○語由来かな」や「こういう経緯でこのつづりになったのかな」と考えを巡らせれば,英語学習もより楽しくなるのではないかと思った.歴史を学んだことで英語学習がよりおもしろくなると思う.
・ この学びにおいて,当初自分が現代英語の構成要素をかんちがいしていたように,今自分の回りにあるものに対しての認識のズレ,そしてそれを直そうとする中で新たな学びがあることが大切だと思いました.この授業をうけて,英語史だけでなく,自分の普段からの物の見方を変えてみようとまで思うことができました.
・ 言語というものが,それ単体としては成り立たず,社会と歴史と深く関わりがあることを証明するよい例であろう.言語を遡るという行為は人間の豊かな歴史的はぐくみを可視化させるものだと感じた.
・ 英語史や言語史もまた人が紡いできた歴史であるからこそ,画一的な物の見方や解釈を押しつけず,多面的に判断することを大切にしたいと思えたことが私にとって何よりの価値であった.
・ 私は最初「英語史」と聞いて身構えていた.しかし,英語を学習し始めたころから抱いてきた疑問について,英語史を学ぶなかで解決していくことができた.学べば学ぶほどおもしろくなるのが,この英語史だと感じた.高校で世界史を選択していた私にとって,英語史は大好きな英語と世界史のミックスであり,毎回目からうろこの内容であった.世界史で学んだ人名たちが,こんなにも英語に影響を及ぼしていることは衝撃だった.
そして,最後にきわめつけの名コメントを挙げよう.
・ グリムの法則は飲み会ネタで使える.現代英語学の井上先生が言語学のトピックは飲み会で使えると言っていたが,確かにその通りだと思った.
ということで,井上逸兵さんとお届けしている YouTube 「いのほた言語学チャンネル」を,ぜひよろしくお願いします(笑)
先日,今回の記事と同趣旨で Voicy heldio にて履修者のコメントを紹介した.本記事と合わせて,ぜひ「#1522. 「英語史」の講義を終えて --- 2025年度前期版」をお聴きいただければ.
2025-07-11 Fri
■ #5919. YouTube 「いのほたチャンネル」で350回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]
一昨日7月9日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,350回記念のライヴ配信をお届けしました.今回も多くの方々にライヴでご視聴いただきました.心より感謝申し上げます.アーカイヴ配信としても視聴できます.「いのほた言語学チャンネル350回記念ライブ!」より,ぜひご視聴ください(60分ほどの配信です).
チャンネル開始から3年半弱,我ながらよく続いてきたものだと感じ入っています.1年ほど前の記念配信を取り上げた「#5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました」 ([2024-07-19-1]) のことも思い出されます.毎回の配信回を積み上げていくと,このように長続きするものかと感慨ひとしおです.
今回のライヴ配信の直前のことでしたが,素晴らしいタイミングでチャンネル登録者数が15,000人を越えました.継続的に視聴していただいている皆さんに感謝申し上げます.
ライヴでは,主に最近の活動についてご報告しました.とりわけ,6月18日に刊行された『英語語源ハンドブック』(研究社)が発売2週間で重版,3週間で版元品切れとなった件につきましては,望外の喜びですし,ひとえに応援していただいている皆さんのおかげです.関連して,6月29日(日)に配信したいのほた回「#349. ついに出ました!『英語語源ハンドブック』 by 唐澤一友・小塚良孝・堀田隆一」は視聴回数が大きく伸びており,現時点で7,916回の視聴となっています.
ほかには,近い将来「いのほた本」の出版が予定されていること,これまでの2人の対話のなかから新たな企画の芽が育ちつつあることなどをお話ししました.
今後も50回,100回の節目ごとに,このようなライヴ配信を行ない,皆さんと交流していければと願っています.引き続き「いのほた言語学チャンネル」を温かく見守っていただけますと幸いです.言語学をお茶の間に!
2025-03-26 Wed
■ #5812. 516通り目の through を「いのほた言語学チャンネル」でも紹介しました [through][ormulum][spelling][voicy][heldio][helwa][youtube][yurugengogakuradio][inohota][link][notice][inoueippei]
3月23日(日)に YouTube 「いのほた言語学チャンネル」の最新回が公開されました.「#321. 中世の through の綴りは515通りと思っていたが」です.おかげさまでご好評いただいています(目下,視聴回数が5000に届きそうです).
through の探究に関するこれまでの経緯は,「#5738. 516番目の through を見つけました」 ([2025-01-11-1]) の記事に,過去の関連コンテンツへのリンク集を作っていますので,そちらからご覧ください.
through の異綴字をめぐる探究がながらく515通り停滞していたところ,久しぶりに新しい516通り目が見つかったということで,研究者の奇矯な生態(?)を眺めるかのようにおもしろがっていただいているのかと想像しますが,当人はいたって真面目です.関心のある方は多くはないかと思いますが,この発見の意義について heldio 有料配信「「516通りの through」の教訓とは?」で語っていますので,よろしければ.
2024-07-19 Fri
■ #5562. YouTube 「いのほたチャンネル」で250回記念としてライヴ配信を行ないました [youtube][inohota][notice][helkatsu][inoueippei][voicy][heldio]
一昨日7月17日(水)の19:00より,同僚の井上逸兵さんと運営している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」にて,250回記念のライヴ配信をお届けしました.100名を超える方々にライヴでご視聴いただきました.ありがとうございます.アーカイヴ配信としても視聴できますので,ぜひ「#250. 250回記念ライヴ」からどうぞ(80分ほどの配信です).
今回のライヴ配信は,半年前の200回記念「#5388. YouTube 「いのほたチャンネル」で200回記念として初めてのライヴ配信を行ないました」 ([2024-01-27-1]) に続く第2弾でした.今後も時折このようなライヴ配信をお届けしたいと思っています.
今回は雑談回ではありましたが,後半にかけて重要な呼びかけやお知らせがありました.
(1) この YouTube チャンネルの飲み会回「言語学バル」に,ゲスト出演していただける英語史界隈の方,ぜひお声がけください!
(2) 9月8日(日)に Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」として12時間生配信の「英語史ライヴ2024」を開催します.そのフィナーレには,井上逸兵さんも登場する予定です.こちらのイベントの最新情報は「#1145. 重大告知 --- khelf 主催「英語史ライヴ2024」の出演者と協賛社の発表」よりお聴きください!
引き続き「いのほた言語学チャンネル」をよろしくお願いいたします.
2024-06-05 Wed
■ #5518. 3年ぶりに再ブレイク --- 井上逸兵(著)『英語の思考法』(筑摩書房,2021年) [youtube][inohota][inoueippei][notice][voicy][heldio]
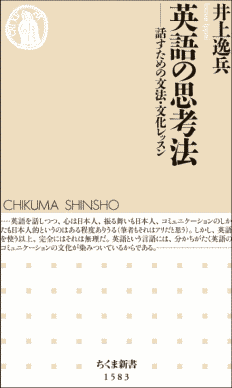
毎週水・日の午後6時に新作動画を配信している YouTube 「いのほた言語学チャンネル」でご一緒している井上逸兵さんの3年前の新書『英語の思考法』が再ブレイクしています.
あるインフルエンサーの方の言及が再ブレイクの直接のきっかけとのことですが,井上さんの分析によると,本質的な背景もあるのではないかとのことです.最新の YouTube 回で,この辺りをお話しいただいています.「#237. インフルエンサーさんのおかげだが,その背後にあるものは?」をご覧ください.
井上さんには,私の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」でも何度か対談させていただいています.『英語の思考法』を著者とともに語る贅沢な配信回もあります.ぜひお聴きいただければと思います.
・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)
・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)
・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)
・ 「#726. #726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」 (2023/05/28)
なお,もしかすると本日6月5日(水)の夕方に,井上逸兵さんと Voicy heldio で生放送をお届けするかもしれません(あるいは後日にアーカイヴ配信します).こちらからチャンネルをフォローしていただけますと通知が入るようになりますので,ぜひフォローをよろしくお願いいたします.
・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.
2023-05-27 Sat
■ #5143. Voicy heldio で「#726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」をアーカイヴとして公開 [notice][voicy][heldio][youtube][link][inoueippei]
一昨日5月25日(木)の午後1時より,同僚の井上逸兵さんと,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にて久しぶりの雑談生放送をお届けしました.30分強のカジュアルトークでしたが,YouTube の裏話,話し方のコツ,会話の「間」の問題,ポスト自動翻訳時代についてなど,楽しい話題が次々に展開しました.生放送でお聴きくださったリスナーの皆さん,事前に質問を寄せてくださった方々には感謝申し上げます.
今朝の Voicy heldio で,生放送を収録しておいたものをアーカイヴとして公開しました.「#726. 井上逸兵さんとの雑談生放送」をお聴きください.井上さんに再び出演・対談していただけるよう,皆様からのその趣旨のコメントもお待ちしています(Voicy のコメント欄よりどうぞ).
井上さんとは過去にも3回ほど Voicy heldio で対談し,配信しています.
・ 「#108. 『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」 (2021/09/17)
・ 「#144. 対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」 (2021/10/22)
・ 「#316. 井上逸兵先生との対談 YouTube を始めて1月半になりますが」 (2022/04/12)
今回の配信中でも触れていますが,井上さんとは昨年2月26日に「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設し,毎週水・日の午後6時に新作動画を公開してきました.順調に回を重ね,最新作は第130回となっています.こちらもチャンネル登録していただければ幸いです.Voicy heldio では,この YouTube チャンネル関連でも何度かお話ししています.
・ 「#272. 井上逸兵先生と YouTube を開始,そして二重否定の話し」 (2022/02/27)
・ 「#663. 私の幸せは井上逸兵先生との YouTube 収録です」 (2023/03/25)
本ブログの井上さん関連記事としては inoueippei をご覧ください.とりわけ「#4526. 井上逸兵(著)『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』」 ([2021-09-17-1]) では,最新のご著書を紹介しています.
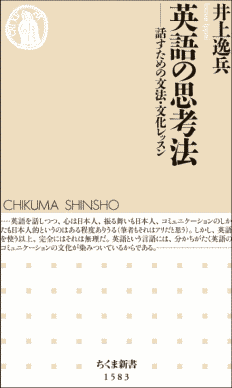
今回の配信の最後のほうで触れているように,井上さんは「NPO 法人地球ことば村」の理事長でもあります.また,井上さんのツイッター @ippeiinoue もおもしろいので,ぜひフォローを!
・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.
2022-08-18 Thu
■ #4861. YouTube 第50回記念 --- ダラダラおしゃべり飲み会,そしてまさにゃん登場 [youtube][notice][voicy][heldio][masanyan][khelf][inoueippei]
半年ほど前の2月26日に YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設し,毎週水・日曜日の午後6時に新作を配信してきました.本ブログの読者の皆さんの中にも,視聴していただいている方がいると思います.ここまで応援ありがとうございます(cf. 「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1])).
このたび記念すべき第50回に達しましたので,今回と次回は通常回とは異なり,2人でのダラダラおしゃべり飲み会をそのまま配信するということをやってみます.さほど英語学・言語学的な中身にはなっていない雑談回ですので,夏休みのひとときという趣旨でゆるリとご覧ください.「閲覧注意!ただ飲んでしゃべってます.50回記念雑談回<前編>」です.
最後に登場してくる「まさにゃん」は,日本初の古英語系 YouTube チャンネルである「まさにゃんチャンネル」を配信しています.とりわけ「毎日古英語」シリーズは,古英語初学者向けの導入シリーズとなっていますので,どうぞご覧ください.とりわけ昨日アップされた新作動画「毎日古英語 【中間テスト!】」は,まさにゃん渾身の(?)企画です.ぜひ受験してみてください(←私はすでに受験しました).遊び心がありながらも真面目なチャンネルです.
まさにゃんは khelf(慶應英語史フォーラム)の会長でもあり,本ブログおよび Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」にもたびたび登場しています.以下をご訪問ください.
・ hellog 「#4005. オンラインの「まさにゃんチャンネル」 --- 英語史の観点から英単語を学ぶ」 ([2020-04-14-1])
・ hellog 「#4566. heldio で古英語期と古英語を手短かに紹介しています(10分×2回)」 ([2021-10-27-1])
・ hellog 「#4740. 古英語入門のためのオンラインリソース」 ([2022-04-19-1])
・ heldio 「#149. 対談 「毎日古英語」のまさにゃんと,古英語ってどんな言語?」(2021年10月27日)
・ heldio 「#307. khelf 会長「まさにゃん」による『英語史新聞』の紹介」(2022年4月3日)
・ heldio 「#308. khelf 会長「まさにゃん」による「英語史コンテンツ50」の紹介」(2022年4月4日)
・ heldio 「#309. khelf 会長「まさにゃん」による「第一回古英語模試」」(2022年4月5日)
・ heldio 「#437. まさにゃんとの対談 ― メガフェップスとは何なの?」 (2022年8月11日)
今後も「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」では,英語学・言語学が身近に感じられてくるような話題をお届けしていきます.引き続きよろしくお願いいたします.
2022-06-11 Sat
■ #4793. 多くの方に視聴していただいています!井上・堀田の YouTube 第30弾「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた」 [word_order][syntax][youtube][notice][link][inoueippei]
6月8日(水)に,YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」 の第30弾が公開されました.「英語の語順は大昔は SOV だったのになぜ SVO に変わったかいろいろ考えてみた.祝!!30回!」です.過去数回と比べて多くの方に視聴していただいているようです.関心をもった方が多いと思われますので,今回はこの話題について情報を補足したいと思います.
基本語順で考えると,ゲルマン祖語では SOV,古英語では SOV + SVO,中英語以降は SVO というのが大雑把な流れです.基本語順の通時的変化の問題については,これまでも hellog その他で様々に扱ってきましたので,以下にリンクなどを張っておきます.上記 YouTube 動画と合わせてご参照ください.
[ 英語史における語順の変化・変異とその原因 ]
・ 「#3127. 印欧祖語から現代英語への基本語順の推移」 ([2017-11-18-1])
・ 「#132. 古英語から中英語への語順の発達過程」 ([2009-09-06-1])
・ 「#4597. 古英語の6つの異なる語順:SVO, SOV, OSV, OVS, VSO, VOS」 ([2021-11-27-1])
・ 「#4385. 英語が昔から SV の語順だったと思っていませんか?」 ([2021-04-29-1])
・ 「#2975. 屈折の衰退と語順の固定化の協力関係」 ([2017-06-19-1])
[ 基本語順の類型論 ]
・ 「#137. 世界の言語の基本語順」 ([2009-09-11-1])
・ 「#3124. 基本語順の類型論 (1)」 ([2017-11-15-1])
・ 「#3125. 基本語順の類型論 (2)」 ([2017-11-16-1])
・ 「#3128. 基本語順の類型論 (3)」 ([2017-11-19-1])
・ 「#3129. 基本語順の類型論 (4)」 ([2017-11-20-1])
・ 「#4316. 日本語型 SOV 言語は形態的格標示をもち,英語型 SVO 言語はもたない」 ([2021-02-19-1])
・ 「#3734. 島嶼ケルト語の VSO 語順の起源」 ([2019-07-18-1])
[ 過去の連載記事などの紹介 ]
・ 英語史連載企画(研究社)「現代英語を英語史の視点から考える」の第11回と第12回
- 「#3131. 連載第11回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(前編)」」 ([2017-11-22-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
- 「#3160. 連載第12回「なぜ英語はSVOの語順なのか?(後編)」」 ([2017-12-21-1]) (連載記事への直接ジャンプはこちら)
・ 知識共有サービス「Mond」での回答:「日本語ならSOV型,英語ならSVO型,アラビア語ならVSO型,など言語によって語順が異なりますが,これはどのような原因から生じる違いなのでしょうか?」
・ 「#3733.『英語教育』の連載第5回「なぜ英語は語順が厳格に決まっているのか」」 ([2019-07-17-1])
・ 「#4583. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第9回「なぜ英語の語順は SVO なの?」」 ([2021-11-13-1])
・ 「#4527. 英語の語順の歴史が概観できる論考を紹介」 ([2021-09-18-1])
2022-05-23 Mon
■ #4774. go/went は社会言語学的リトマス試験紙である [sociolinguistics][suppletion][verb][inflection][solidarity][inoueippei]
「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を始めて3ヶ月ほどが経ちました.英語・言語に関して大学の講義ぽいものではなく,あくまで研究者どうしの廊下での立ち話し的な,ゆるめのおしゃべりを目指して,毎週日曜日と水曜日の18:00に10分間前後の動画をアップロードしています.多くの方々にチャンネル登録をしていただいています.ありがとうございます.今後もよろしくお願いいたします.
昨日,第25弾が公開されました.「新説! go の過去形が went な理由」です.YouTube という場を借りまして,私のトンデモ仮説!?を開陳させていただきました(笑).反証可能な仮説ではなく,あくまで私論にとどまるものではありますが,長らく抱いている考え方です.
その私論を単純化していえば,go/went に限らず英語(ひいては言語一般)に観察される数々の不規則な言語項目は,それをマスターしていない個人は英語話者集団の仲間に入れてあげないよ,という社会言語学上のリトマス試験紙として機能しているのではないかということです.「go といえば goed ではなく went」という,仲間うちのみに共有されている合い言葉を,きちんと習得しているかどうかを確かめるリトマス試験紙なのではないかと.
もちろんそのようなリトマス試験紙が,取り立てて go/went のペアである必要はありません.ほかのどんなペアでも良かったはずです.ですが,英語においては,たまたま不規則性を歴史的に体現してきた go/went が,社会言語学的なリトマス試験紙として選ばれ,利用されている,ということなのだろうと考えています.
「なぜ go の過去形が went なのか」という素朴な疑問には,2つの側面があります.1つは,なぜよりによって went という形なのですか,という問いです.こちらへの回答は英語史が得意とするところです.「#43. なぜ go の過去形が went になるか」 ([2009-06-10-1]),「#4094. なぜ go の過去形は went になるのですか? --- hellog ラジオ版」 ([2020-07-12-1]),「#4403. 『中高生の基礎英語 in English』の連載第3回「なぜ go の過去形は went になるの?」」 ([2021-05-17-1]) をご覧ください.
一方,なぜいつまでたっても go の過去形として goed が採用されないのか,という問いに対しては,異なる回答ができるように思われます.上記の社会言語学的な観点からの回答です.これについて「#1482. なぜ go の過去形が went になるか (2)」 ([2013-05-18-1]) や,拙著『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』の p. 78 をご覧ください.
言葉にはあちこちに不規則性という罠がちりばめられているのです.
・ 堀田 隆一 『英語の「なぜ?」に答えるはじめての英語史』 研究社,2016年.
2022-03-04 Fri
■ #4694. 井上逸兵流「2つの英語学」説 [terminology][inoueippei]
先日の「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1]),「#4690. 深く考えたことのなかった「英語学とは何か?」」 ([2022-02-28-1]) でも話題となった英語学・言語学とは何かという問いについて,改めて考えてみたい.
先日の議論を振り返り対立的な図式に落とし込めば「英語学とは英米流の言語学である」(堀田説)と「英語という言語を対象とする言語学である」(井上説)の2種類の解釈があった.ただし,これはどちらが正しいかという問題というよりも,2つの見方があり得るということの確認なのだろうと思う.実際,井上自身も英語学概論書のなかで,2つの英語学があることについて議論している (1--2) .
大きく分けて,「英語学」は2つの分野を指している.この2つは重なっている部分もあるが,大きく離れて別の分野と言ってよい部分もある.
1つは「英語という言語の研究」という意味である.つまり,英語で言えば,the study of English language ということで,最近の世界の英語状況を考えると,the study of English languages と複数形にしてもよいかもしれない(本書のスタンスはそれだ).もともとはアングロ・サクソンの民族的文化的背景を持った一民族語としての英語の研究という意味合いが強い研究もある.〔中略〕英語という言語そのものを深く探究する学問である.その成り立ちを考えたとき,当然ながら,英語という言語の背景である歴史に目を向けることは理にかなったことである.その実,この分野の英語学は「英語史」という色彩を強く持つことになり,過去の英語の文献をひもとき,つぶさに分析することが重要な作業となる.この分野の英語学が,英語では philology と呼ばれるゆえんである.
もう1つの「英語学」の意味するところは,「英米系の言語学」という意味である.「英米系」というのは,つまり「英米で議論されてきた伝統をくんでいる」という意味である.かつての「国語学」,現在では「日本語学」にも伝統があり,「仏語学」「独語学」も同様に,それぞれに議論の伝統があり,扱われる事象にも違いがある.流派のようなものと考えてもそう間違ってはいない.それぞれの流派の言語学はそれぞれの特定の言語を対象に議論するので,「○○語をデータとして用いる言語学」と言ってもよいが,それだけではない.扱い方や議論の仕方にも違いがある.ここでは,それらを比較して論じることはしないが,まずは「英米で論じられてきた伝統にある言語学」と理解しておくとよいであろう.1つ目の英語学に対して,こちらの英語学は英語では linguistics と読んでいる.この意味においては,英語学は言語学とほぼ同義と考えてよい.
実際,「英語学」という分野名が意味するところは,使われる文脈が異なれば,それに応じて異なっているように思われる.ただし,両方の解釈を合わせて広く「英語学」と指示することは(少なくとも私にとっては)よくあることでもある.
・ 井上 逸兵 『グローバルコミュニケーションのための英語学概論』 慶應義塾大学出版会,2015年.
2022-02-28 Mon
■ #4690. 深く考えたことのなかった「英語学とは何か?」 [sobokunagimon][youtube][terminology][linguistics][philology][inoueippei]
昨日の記事「#4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました」 ([2022-02-27-1]) で,井上逸兵先生と共同で YouTube チャンネルを開設した旨をアナウンスしました.初回の「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!では,対談という形で「英語学」そのものに迫ってみました.
ところが,この質問は私にとってはそこそこ不意打ちの質問でして,ちょっと考えてしまいました.私の専門は「英語史」ですが広い意味で「英語学」の1分野ですし,これまでも「英語学」の講義を担当してきた経緯があります.その割には「英語学とは何か」を考えてきていなかったということに気づきました.もやもやとは答えをもっていましたが,自明すぎて本気で問うことをしてこなかったようです.
私の答えを端的にいえば「英語という言語を対象とする言語学である」ということでした.ここには私の専門の英語史や英語文献学も含まれます.英語のスキルを磨くための「規範」に基づく語学学習とは一線を画し,英語のありのままを「記述」するのが英語学であると.つまり,とりわけ英語という個別言語をターゲットに絞って研究する言語学が英語学であるという認識です.
一方,井上氏の認識は,端的にいって「英語学とは英米流の言語学である」ということでした.ターゲットというよりもアプローチを指す用語だというわけです.例えば,日本語を対象としていても英語学は成り立つという立場です.確かに,英語学のアプローチを用いながら実際のところは日本語を研究しているという事例は,日本の関連学会でも英文科の大学院でもしばしば見受けられることです.その観からいえば,井上流の「英語学」の解釈もうなずけます.
どうやら「英語学」の理解にもいろいろとありそうだということに,今更ながら気づきました.では,英語学辞典などでは「英語学」はどのように定義されているのだろうと何冊か引いてみると,なんと載っていないのです! 自明すぎて載せないという建前なのでしょうが,実は自明ではないというのが今回の私の発見です.
では英語学の教科書ではどうだろうかと,まず手元にあった『日英対照 英語学の基礎』を開いてみました.「まえがき」の p. ii に次のようにありました.
みなさんは,「英語学」と聞くと,これまで勉強している「英語」と何が違うのだろうと思うことでしょう.「英語学」というのは,英語という言葉がどのような仕組みになっているかを考える言語学の一領域です.つまり,英語の音や単語,文や会話などがどのような仕組みになっており,そこにどのような規則が潜んでいるかを明らかにしようとする研究分野です.
これは,だいたいのところ私が理解している「英語学」に近いと思います.ただ,英語史贔屓の私にとっては,これだけではちょっと物足りないという感じがしています.
英語学って何なのでしょうかね.捉え方は十人十色なのだろうと思います.この事実は意外とびっくりでした.皆さんの考えははいかがでしょうか?
なお,「英語史」も負けず劣らず難しいです.とりあえず「#225. 「英語史研究」とは?」 ([2009-12-08-1]) 辺りをご覧ください.
・ 三原 健一・高見 健一(編著),窪薗 晴夫・竝木 崇康・小野 尚久・杉本 孝司・吉村 あき子(著) 『日英対照 英語学の基礎』 くろしお出版,2013年.
2022-02-27 Sun
■ #4689. YouTube で「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました [youtube][notice][linguistics][philology][inoueippei]
昨日,標記の通り井上逸兵先生と共同で YouTube にて「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」を開設しました.
初回動画「英語学」ってなに?--むずかしい「英語」を「学」ぶわけではありません!!のなかでも触れていますが「英語学・言語学って何なの?」という辺りから始めて,それぞれの専門分野(井上氏は社会言語学・認知言語学・語用論,堀田は英語史)の観点から,英語や言語一般に関する様々な話題を,定期的にお届けしていきます.初回は自己紹介的な雰囲気ですが,今後はどんどん濃くなっていくと思います.ぜひ視聴してみてください.チャンネル登録もよろしくどうぞ.
共演者である井上逸兵氏を紹介したいと思います.慶應義塾大学文学部英米文学専攻の教授で,社会言語学,認知言語学,語用論などの分野を専門とされています(←同僚としても日々お世話になっています).NPO法人地球ことば村・世界言語博物館の理事長でもあります.2018--19年度には,NHK教育テレビ「おもてなしの基礎英語」の講師を務められました.著書も多数ありますが,とりわけ昨年話題となったのが『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』(筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年)です.詳しい業績その他の詳細は,井上逸兵のページをご覧ください.人気の Twitter はこちらです.
井上氏には,すでに私の Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」でも,2度ほど対談・出演していただいています.普段の私一人のしゃべりによる放送に比べて,ずっと多く聴かれているようです,さすがですね.
・ 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(2021年9月17日放送)
・ 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(2021年10月22日放送)
今回開設した YouTube チャンネルの趣旨は,2人の英語学研究者による肩のこらない緩いおしゃべり,といったところです.高校生から大学生にかけての視聴者を念頭に「英語学・言語学って何?」というところから始めますが,広く英語や言語一般に関心のある方々にも視聴してもらえるような内容を織り込んでいきたいと思っています.
同じお題でおしゃべりしても,異なる分野を専門とする2人が話せば,これだけ違う意見が出るのだなというところが見所かと思います.作り手もそれを楽しんでいるところがあります.
今後は本ブログ,Voicy の「英語の語源が身につくラジオ」と合わせて,「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」もよろしくお願いいたします.
2022-01-14 Fri
■ #4645. 『三田評論』1月号の「“新書”で英語を学ぶ」の記事 [review][inoueippei]
『三田評論』2022年1月号 (no. 1262) に「時の話題」の企画として「“新書”で英語を学ぶ」 (pp. 36--41) が掲載されています.2020年から2021年にかけて英語新書ブームを巻き起こした3名の著者による3本の記事です(オンライン版ではまだ閲覧できないようです).
・ 北村 一真(杏林大学外国語学部) 「英語の読解で拡がる世界」 (pp. 36--37)
・ 井上 逸兵(慶應義塾大学文学部) 「タテマエから知る英語のわかり方」 (pp. 38--39)
・ 今井 むつみ(慶應義塾大学環境情報学部) 「英語を自由に使うための“スキーマ”の習得」 (pp. 40--41)
ブームとなった新書は各々以下の通りです.
・ 北村 一真 『英語の読み方 ー ニュース,SNS から小説まで』 中央公論新社〈中公新書〉,2021年.
・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.
・ 今井 むつみ 『英語独習法』 岩波書店〈岩波新書〉,2020年.
これまでも日本人の英語学習熱は常に高かったといってよいですが,英語を学ぶための新書ブームがこのタイミングで来たというのはおもしろいことだと思っています.なぜなのでしょうか,たまたまなのでしょうか.この点について私も関心をもち,昨秋,井上先生とおしゃべりしました.Voicy の私のチャンネル「英語の語源が身につくラジオ」にて収録・配信しましたので,関心のある方はぜひどうぞ.
・ 「『英語の思考法』(ちくま新書)の著者,井上逸兵先生との対談」(9月17日放送)
・ 「対談 井上逸兵先生と「英語新書ブーム」を語る」(10月22日放送)
『三田評論』の記事のなかで,井上先生は「コロナで「おうち時間」が増え,コロナ前のインバウンド歓待のムードも遠い昔に思え,「英会話」よりもじっくり腰をすえて本を読むという人が広い世代で増えたのかもしれない」 (p. 38) と述べています.
英語の勉強と合わせて英語史の学習についても,じっくり腰をすえてみてはいかがでしょうか.
(後記 2022/03/03(Thu):上記の『三田評論』の記事がオンラインで自由に閲覧できるようになったようです.こちらからどうぞ.)
2021-09-17 Fri
■ #4526. 井上逸兵(著)『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 [review][politeness][japanese][face][pragmatics][sociolinguistics][t/v_distinction][heldio][inoueippei]
去る7月に,ちくま新書より井上逸兵(著)『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』が出版されました.著者は私の慶應義塾大学文学部英米文学専攻の同僚です(井上さん,ご献本いただきましてありがとうございます!).
著者の井上氏には本日,私が6月から放送している「英語の語源が身につくラジオ」(heldio) に特別ゲストとして出演していただいています(←同僚としての役得に甘えました).新書についてのおしゃべりです.10分×2本の収録となっていますので,2本目もお聞き逃しなく! しかも,2本目の最後は5秒ほど時間が足りなくてお尻が切れています(泣).
日本語(文化)には厄介なタテマエとホンネがありハッキリとものを言いにくいのに対して,英語(文化)ではそういうものがないのでハッキリ主張することが好ましい.これは,日本人の英語学習者の多くが感じていることではないでしょうか.しかし,井上氏が本書で軽妙なオヤジギャグと豊富な用例により次々と明らかにしていくのは,そうではないということです.英語(文化)にもタテマエとホンネはちゃんとある.ただし,日本語(文化)のそれとは違った形で存在している,ということです.
では,どう違っているのかといえば,英語(文化)の基盤には「独立」「つながり」「対等」への志向があるということです.「個人として対等な関係を保ちながらつながりを求める」のが英語流ということですね.個性や独立心が比較的弱く,上下関係のつながりを重視する伝統的な日本語(文化)の発想とは,確かに大きく異なります.
私が英語史の観点から抱いた関心は,英語的な「独立」「つながり」「対等」への志向は,いつ生まれたのだろうかということです.中世まではさほど強くなかったように思われるからです.おそらく近代に入ってからではないかと.社会的上下関係を内包する2人称代名詞の you/thou の区別が解消していくのも,近代期(17世紀以降)だった事実が思い出されます.
本書の中心テーマは日英語文化比較やポライトネスといったところだと思いますが,英語学研究者としての著者の真骨頂は,副題の「文法・文化レッスン」に現われているように思われます.文法という言語学的な堅い代物にも,その担い手の社会に特有の文化や思考回路が色濃く反映されているのだという点です.
一方,本書はすぐに使える英語の用例が豊富で,実用書的に読むこともできます.実際,私も英語を話したり書いたりするときに,早速いくつかの語法を活用しています.You lost me. とか Let me share with you . . . . とか.ですが,褒められたときに Can you tell my wife that? と返すのは,私には歯が浮いて言えなさそうです.
笑いながら読める英語本です.ぜひご一読ください.
・ 井上 逸兵 『英語の思考法 ー 話すための文法・文化レッスン』 筑摩書房〈ちくま新書〉,2021年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow