2025-02-13 Thu
■ #5771. 品詞とは何か? --- 分類基準の問題 [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]
「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1]) と「#5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解」 ([2025-02-07-1]) で品詞論を紹介してきた.今回は『新英語学辞典』の parts of speech の項を参照しながら,英語の伝統的な8品詞の分類基準について考えてみる.
英語の伝統的な8品詞は,意味,機能,形態の3つの分類基準がごちゃ混ぜになった分類であり,理論的には問題があるとされる.まず,名詞,形容詞,動詞,間投詞については,主に意味的な基準で分けられているといってよい.もちろん意味的な基準といっても微妙なケースはいくらでもある.英語で white は,日本語では「白」という名詞にも,「白い」という形容詞にも相当し,意味的には互いに限りなく近い.同様に,分詞は形容詞と動詞の合いの子といってよいが,合いの子からみればいずれにも意味的に近い.さらに,以上4品詞の分類については形態的な基準も少なからず関わっており,意味的な基準だけで語れるわけではない.間投詞は他と比べて意味的な自律性があるといえそうだが,これもまだ検討の余地があるかもしれない.
一方,代名詞,副詞,接続詞は機能的な基準による分類だ.ただし,言語において「機能的」とのラベルはカバーする範囲が非常に広い.かりに「統語的」と狭めておけば,それなりに説明できるかもしれないが,グレーゾーンは残る.副詞や接続詞は統語的に決定できそうだが,代名詞は統語論的機能と同時に語用論的機能も帯びており,「機能的」のカバー範囲をもっと広めに設定しておく必要があるようにも思われる.
最後に前置詞はどうだろうか.基本的には統語的な機能の観点からの分類といってよさそうだが,意味的な考慮が入っていないとはいえない.like や worth は後ろに「目的語」らしきものをとる点で統語的には前置詞的な振る舞いを示すが,比較的中身のある語彙的意味をもっている点では形容詞ぽい.
品詞間の境目が明確でないという問題自体は古くからあり,個々の論点が指摘されてきたが,それ以前に3つの分類基準が複雑にオーバーラップしているという本質的な課題を抱えているのである.
・ 大塚 高信,中島 文雄(監修) 『新英語学辞典』 研究社,1982年.
2025-02-07 Fri
■ #5765. 品詞とは何か? --- Bloomfield の見解 [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]
一昨日の記事「#5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか」 ([2025-02-05-1]) で,"parts of speech" (品詞),"word-class" (語類),"form-class" (形式類)といった近似する用語群について考えた.アメリカ構造主義の旗手 Bloomfield は,代表的著書 Language (§12.11) にて,この3つを区別して考えている.
The syntactic form-classes of phrases . . . can be derived from the syntactic form-classes of words: the form-classes of syntax are most easily described in terms of word-classes. Thus, in English, a substantive expression is either a word (such as John) which belongs to this form-class (a substantive), or else a phrase (such as poor John) whose center is a substantive; and an English finite verb expression is either a word (such as ran) which belongs to this form-class (a finite verb), or else a phrase (such as ran away) whose center is a finite verb. An English actor-action phrase (such as John ran or poor John ran away) does not share the form-class of any word, since its construction is exocentric, but the form-class of actor-action phrases is defined by their construction: they consist of a nominative expression and a finite verb expression (arranged in a certain way), and this, in the end, again reduces the matter to terms of word-classes.
The term parts of speech is traditionally applied to the most inclusive and fundamental word-classes of a language, and then, in accordance with the principle just stated, the syntactic form-classes are described in terms of the parts of speech that appear in them. However, it is impossible to set up a fully consistent scheme of parts of speech, because the word-classes overlap and cross each other.
form-class は語句の統語的な役割に対応する単位,word-class はその form-class の典型的な主要部を示す語の属する語彙的な区分,parts of speech はその word-class の伝統的で基本的な型,ということになるだろうか.
あえてすっきりまとめるのであれば,それぞれ統語的単位,語彙的単位,語彙・統語・形態的単位といってよい.「品詞」 (parts of speech) は実用的な便利さゆえに広く用いられているが,実際には複合的(で意外と複雑)な単位ということになる.
・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.
2025-02-05 Wed
■ #5763. 品詞とは何か? --- ただの「語類」と呼んではダメか [pos][terminology][linguistics][history_of_linguistics][category][structuralism]
昨日の記事 ([2025-02-04-1]) に続き,品詞 (parts of speech, or pos) という概念・用語をめぐる話題.今回は Crystal の言語学用語辞典を繰ってみた.
part of speech The TRADITIONAL term for a GRAMMATICAL CLASS of WORDS. The main 'parts of speech' recognized by most school grammars derive from the work of the ancient Greek and Roman grammarians, primarily the NOUN, PRONOUN, VERB, ADVERB, ADJECTIVE, PREPOSITION, CONJUNCTION and INTERJECTION, with ARTICLE, PARTICIPLE and others often added. Because of the inexplicitness with which these terms were traditionally defined (e.g. the use of unclear NOTIONAL criteria), and the restricted nature of their definitions (reflecting the characteristics of Latin or Greek), LINGUISTS tend to prefer such terms as WORD-class or FORM-class, where the grouping is based on FORMAL criteria of a more UNIVERSALLY applicable kind.
ギリシア語やラテン語の文法の遺産を引き継いだ歴史的で伝統的な文法範疇 (category) であることが強調されており,それが必ずしも明確な語彙の区分であるわけではないことにも触れられている.従来,品詞は概念的な語彙区分として理解されることが多かったが,実際にはそれも "unclear" (不明確)であるとすら述べられている.
加えて,Crystal は言語学ではむしろ "word-class" (語類)や "form-class" (形式類)と呼ぶ向きも多いと述べている.確かに「品詞」という用語を敢えて避けるケースはありそうだ.「品詞」できれいに割り切れない場合に,より一般的な概念・用語としての「語類」を持ち出すことはあると思う.
それでも,言語学においては,拠って立つ理論次第ではあるが,「品詞」はあまりに便利すぎて手放せないケースのほうが多いのではないか.方便としてここまで踏み固められた「品詞」を手放すのは惜しい.
・ Crystal, David, ed. A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 6th ed. Malden, MA: Blackwell, 2008. 295--96.
2023-06-04 Sun
■ #5151. 日本語反対語辞典の「まえがき」より [lexicology][semantics][antonymy][synonym][structuralism][thesaurus][dictionary]
「反対語」「対義語」「対照語」「対応語」などと称される antonym は,語彙意味論においても関心を集めてきた.私も反対語辞典の類いは好きでよく引くのだが,日本語で常用しているものとして『反対語対照語辞典 新装版』がある.
反対語といっても「反対」のあり方は様々で,語彙意味論でもまさにその点が問題となる.上記の辞典の「まえがき」 (i--ii) を読めば,その難しさとおもしろさが理解できるだろう.
単語は一つ一つがばらばらに存在しているのではなく,まとまりをもち,いわばネットワークをなしている.たとえば「父」という単語は,「お父さん」「おやじ」「パパ」などと言い換えることができる.これら四語は,同じものを指している.四語の間には敬意の有無やニュアンスの違いなどがあり,完全に同義であるとはいえないが,同義に近い関係ーー類義の関係ーーにあるということができる.一方,「父」の対として「母」という語がある.そして,「母」にも「お母さん」「おふくろ」「ママ」といったような類義の語が存在する.また,「父」と「母」の両者を包含する語として「親」があり,「親」の対として「子」という語がある.このように,単語は相互に関連して複雑な組織網を形成している.
反対語の定義はきわめて難しい.同義語・類義語には同じものを指すといった基準があるが,反対語の条件は単純ではない.反対語という場合,まず両者の間に共通する意味がなければならない.「母」が「父」の反対語になるのは,両者が<親>という共通の意味をもっているからである.しかし,共通する意味をもっているだけでは,もちろん反対語にはならない.「母」が「父」の反対語になるのは,男性ではなく女性であるということによる.つまり,男性か女性かという基準から見て反対の意味になるのである.反対語の条件は,
(1) 共通する意味をもっていること
(2) その上で,ある基準から見て,反対の意味をもっていること
の二点であるということになるだろう.
もう一つの例をあげよう.「大勝」の反対語には,「大敗」と「辛勝」とがあげられるが,前者は,(1) 大差で勝負がつくという共通点をもち,(2) 勝ち負けという基準から見て反対の意味をもっており,後者,つまり「辛勝」は,(1) 勝つという共通の意味をもち,(2) 勝ち方が大差か小差かという基準から見て反対の意味をもっている.ある語の反対語は,一つとは限らない.基準が変わると,いくつも存在することになる.
以上のように説明すると,反対語の判定は比較的容易なように見えるが,一語一語について具体的に考えていく段になると,反対の意味とは何かということが問題になってきて,判断に苦しむことが多い.
上記で例に挙げられている「大勝」に関する辞典内の図を参照しよう.構造主義的な,きれいなマトリックスとなる.
| <大差> | <小差> | ||
| <勝利> | 圧勝(大勝・快勝) | ←───→ | 辛勝 |
| ↑ | ↑ | ||
| │ | │ | ||
| ↓ | ↓ | ||
| <敗北> | 惨敗(大敗・完敗) | ←───→ | 惜敗 |
しかし,多くの場合,そこまできれいなマトリックスにはならない.反対関係はもっと複雑になることも多い.例えば「水」を中心とした語彙の関係図を示そう.
┌─┐ │油│ └─┘ ┌─┐ ↑ ┌─┐ │ │ │ │ │ │ │ ↓ │ │ │水│←──────→┌─┐ │ │ │ │ ┌─┐ │ │ │ │ │蒸│ │湯│←─→│水│←─→│氷│ │ │ └─┘ │ │ │ │ │気│ └─┘ │ │ │ │ ↑ │ │ │ │←────────┼───→│ │ └─┘ ↓ └─┘ ┌─┐ │火│ └─┘
反対語の意味論については,hellog および heldio より以下を参照.
・ hellog 「#1800. 様々な反対語」 ([2014-04-01-1])
・ hellog 「#1804. gradable antonym の意味論」 ([2014-04-05-1])
・ hellog 「#1968. 語の意味の成分分析」 ([2014-09-16-1])
・ hellog 「#4102. 反意と極性」 ([2020-07-20-1])
・ heldio 「#353. 反対語っていろいろあっておもしろい!」
・ heldio 「#354. long と short は対等な反対語ではない?」
・ 北原 保雄・東郷 吉男(編) 『反対語対照語辞典 新装版』 東京堂出版,2015年.
2023-02-09 Thu
■ #5036. 語用論の3つの柱 --- 『語用論の基礎を理解する 改訂版』より [pragmatics][review][youtube][history_of_linguistics][generative_grammar][structuralism]
昨年,開拓社より Gunter Senft (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳)『語用論の基礎を理解する 改訂版』が出版されました.
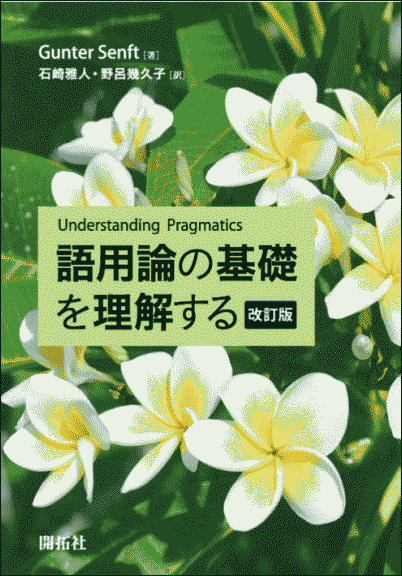
語用論 (pragmatics) の骨太の入門書です.本書は YouTube 「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」で2回ほど井上氏が話題として取り上げ,紹介しています.第85回「Gunter Senft著・石崎雅人・野呂幾久子訳『語用論の基礎を理解する・改訂版』(開拓社,2022年)のご紹介」と第93回「指示代名詞は意外に奥深いーダイクシスの豊かな世界・語用論の展開」です.そちらもご覧ください.
YouTube で井上氏が取り上げ,私も「ぜひ読んでみたい」という趣旨の発言をしたこともあって(と拝察していますが),訳者の石崎先生より本書をご献本いただいてしまいました(すみません,たいへん感謝しております).本書を読み始めていますが,序章の p. 5 に,本書には3つの議論の柱があるとして,重要事項が列挙されています.次の通りです.
1. 言語は社会的相互行為においてその話し手により用いられる.言語は何よりも社会的なつながりと説明責任の関係を創出する道具である.これらのつながりや関係を創出する手段は言語や文化によって様々である.
2. 発話はそれがなされる状況の文脈の一部であり,本質的に言語は語用論的な性格をもち,「意味は発話の語用論的機能に依拠する」 (Bauman 1992: 147) .
・ 言語話者は社会的相互行為において言語を使用するさい,慣習,規範,規則に従う.
・ 単語,句,文の意味は,一定の種類の状況的な文脈の中で伝えられる.
・ 話し手の言語使用は,これらの話者のコミュニケーション行動に内在し,そのコミュニケーション行動に資する特定の機能を実現する.
3. 語用論は言語および文化に特有の言語使用の形態を研究する分野横断的学問である.
このような語用論の特徴,そしてこの分野が1970年代以降に盛んになってきた背景には,アメリカ構造言語学と生成文法に対する反動があったろうとも述べられています (3--4) .語用論の名の下に,言語学がいよいよ生身の言語使用を本格的に扱う段階に入ってきたのだろうと私は理解しています.
・ Senft, Gunter (著),石崎 雅人・野呂 幾久子(訳) 『語用論の基礎を理解する 改訂版』 開拓社,2022年.
・ Senft, Gunter. Understanding Pragmatics. London and New York: Routledge, 2014.
2022-03-31 Thu
■ #4721. 構造主義言語学とは? [structuralism][history_of_linguistics][terminology][saussure][heldio]
1ヶ月ほど前に始めた「井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル」も,週2回のペースを守りつつ,昨日第10回を迎えることができました.視聴者の皆さん,ありがとうございます.
その昨日の第10回は,これまでに比べてかなり硬派といえば硬派な話題です.「ゲンゴガクシ」についてです.言語学史 (history_of_linguistics) は,言葉に関心のあるすべての人にとって実はかなりおもしろい分野なのですが,それを分かりやすく説明するのは簡単ではありません.
収録を通じて,言語学そのもの以上に言語学史に深い関心を抱くと互いに知った2人が,20世紀前半の学界の潮流を決定づけた構造主義言語学 (structural linguistics) について話しをしてみました.構造主義は歴史言語学を敵に回したか!?ー言語学理論のおもしろさ【井上逸兵・堀田隆一英語学言語学チャンネル # 10 】をご視聴ください.
構造主義言語学とは何か? 私にはとうてい端的に説明できる自信がないので,イヴィッチの言語学史の概説 (81--82) に頼りたいと思います.
構造主義言語学の時代は,ヨーロッパとアメリカで共に1930年の少し前に始まった.
他の学問分野においてもそうであるが,言語学における構造主義はまず第一に既知の事実に対する新しい見方を意味している.即ち,既知の事実が体系の中で機能している点に注目して検討を加える見方である.同時にこの構造主義的な見方は,言語の社会的な(つまりコミュニケーションの)機能の強調,歴史的現象と或一時点における一言語体系の諸特徴との明確な区別をも伴うものである.
この時代の先駆者はそれ以前に,ある者は早くも19世紀に,そこかしこに現れていた.しかしこれらの孤立した試みはその時代の人々の注意をひくことはなかった.真に人々の耳をそばだたせ,今日なお鳴り響いている最初の声を発したのはフェルディナン・ドゥ・ソシュール Ferdinand de Saussure であった.ドゥ・ソシュールが初めて言語学における新しい思想によってその時代の人々に強い影響を与えたことと,その直接の影響下になかった人々さえも彼の思想の根底にあるのと同一の理論的基盤から出発したことによって,ドゥ・ソシュールは今では構造主義言語学の創始者と見なされている.
構造主義言語学のイロハともいえるドゥ・ソシュールの基本的言語学説は,以下のようなものである.
言語は体系であり,体系として研究すべきである:個々の事実を単独に取り上げるのではなく,常に全体として見るべきである.且つ細かい事柄の一つ一つは体系の中での位置によって規定されるということを考慮に入れるべきである.
言語はまず第一に相互理解の目的を果たす社会的現象であり,そのようなものとして研究すべきである:音と意味との相互関係は,コミュニケーション過程において決定的な重要性を持つので,常にこれを念頭に置くべきである.
言語の発展と言語の実現されている[一時点の]状態とは,根本的に異る別の現象である.従って,方法論の点から見て,言語の現在の状態を解釈する時に歴史的な規準を持ち込むことは許されない.
他の学問分野と同様に,言語学においても構造主義は不変のもの invariants の探究,余情な redundant 現象と関与的な relevant 現象を分離しようとする努力,を含んでいる.
構造主義言語学の信奉者たちはすべて,客観的な分析基準(メンタリスティックな規準の入る余地をなくすようなもの)を見出そうと希求している.
イヴィッチの説明はさらに延々と続くのですが,この辺りで止めておきましょう.
YouTube 動画内でも述べた通り,私にとって構造主義言語学とは「マトリックス思考」です.今朝の Voicy 「英語の語源が身につくラジオ」 (heldio) でも「構造主義言語学とはマトリックス思考である」と題してしゃべっていますので,よろしければどうぞ.
・ ミルカ・イヴィッチ 著,早田 輝洋・井上 史雄 訳 『言語学の流れ』 みすず書房,1974年.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow