2025-04-11 Fri
■ #5828. heldio で『ヴォイニッチ写本』の著者対談シリーズがスタート [voicy][heldio][manuscript][voynich][cryptology][cryptography][notice][review]
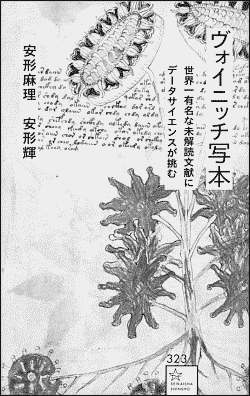
先日の記事「#5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年)」 ([2025-03-29-1]) と「#5816. ヴォイニッチ写本に関する有用なウェブサイト」 ([2025-03-30-1]) で,昨年末に出版された新書を紹介しました.
この度,Voicy 「英語の語源が身につくラジオ (heldio)」上で著者お二方との特別対談が実現しました(安形麻理先生,安形輝先生,収録のためにお時間を割いていただきありがとうございました!).対談は全3回のシリーズとしてお届けする予定ですが,昨日第1回を配信したのでご案内します.「#1411. 著者と語る『ヴォイニッチ写本』 (1) --- 安形麻理先生&安形輝先生との対談」と題して,20分ほどのトークとなっています.
3人でおしゃべりしながらの楽しい収録でしたが,録音していない時間帯にも,ヴォイニッチ写本をめぐる様々な議論や研究の裏話が尽きることなく続きました.役得以外の何ものでもありません.私はヴォイニッチ写本についてはさほど詳しく知らなかったのですが,今回の書籍の刊行,そして著者のお二人から直接お話を伺うことで,同写本の魅力に俄然引き込まれそうです.
対談シリーズの第2回,第3回は,今後数日の間隔を空けながら配信していく予定です.ぜひ星海社新書『ヴォイニッチ写本』をお手に取っていただくとともに,残りの対談の配信にもご注目ください.この対談を通して,『ヴォイニッチ写本』がより広く知られ,その魅力が多くの人に語られるようになることを願っています.
・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.
2025-03-29 Sat
■ #5815. 安形麻理・安形輝『ヴォイニッチ写本』(星海社,2024年) [review][toc][manuscript][voynich][cryptology][cryptography]
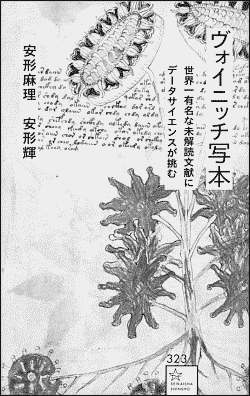
昨年末,「世界で最も謎に満ちた写本」といわれるヴォイニッチ写本 (The Voynich Manuscript) についての,待望の新書が出版された.200頁弱の薄めの新書のなかに,未解読のヴォイニッチ写本(研究)の魅力が濃厚に詰め込まれている.本書後半では,著者らによる最新の研究の成果が示されており,ヴォイニッチ手稿がでたらめな文字列ではなく,背後に何らかの言語が隠されている,つまり解読に値するテキストであることが主張される.巻末には,著者らと博物学者・荒俣宏氏との鼎談の様子も収められており,最後までワクワクしながら読み続けることができる.
以下,本書の目次を示そう.
第1章 謎めいたヴォイニッチ写本
1. ヴォイニッチ写本とは
外観
文字と挿絵
2. ヴォイニッチ写本の魅力
解読へのチャレンジ精神
真贋論争:中世の写本か20世紀の捏造か
ヴォイニッチ写本研究の楽しみ
3. ヴォイニッチ写本発見の経緯
発見者ヴォイニッチ
発見から現在まで
発見されるまでの所在
4. 中世ヨーロッパにおける写本の作り方
第2章 これまでのヴォイニッチ写本研究
1. 来歴を明らかにする
ジョン・ディー
ルドルフ2世
ヤコブズ・デ・テペネチ
ゲオルグ・バレシュ
マルクス・マルチ
アタナシウス・キルヒャー
2. 年代を測定する
3. 文字を分析する
4. 解読を試みる
5. 言語学的に分析する
6. 似た文書を再現する
7. テキストの解読可能性を判定する
第3章 データサイエンスと古い本
1. データサイエンス
データサイエンスとビッグデータ
データサイエンスを学ぶことができる大学
2. 本を研究する
書誌学とデジタル化
データに基づく著者推定
難読化文字や隠された文字の解読
暗号の解読
第4章 クラスタリングによる分析:解読の可能性そのものを判定する
1. 解読の可能性の判定
クラスタリング
2. 実験の手順
全体の流れ
テキストデータの類似度
トークン化
トークンに対する重み付け
ベージ同士の類似度算出
クラスタリング分析手法
ページ順に基づく分析法
クラスタリングの評価
3. 実験の結果
ページ同士の内容の類似度
挿絵によるセクション構造との比較
ページのクラスタリング結果
4. クラスタリング結果の評価と比較
比較対象
クラスタリングの評価と比較結果
ページ順の比較
第5章 ヴォイニッチ写本研究の意義と広がり
1. 分析手法を発展させる
2. シチズンサイエンス
3. ヴォイニッチ写本の影響の広がり
4. 謎に立ち向かいたい方のために:有用な情報源の紹介
第6章 ヴォイニッチ写本の可能性とこれからの研究
特別鼎談 荒俣宏 × 安形麻理 × 安形輝
最後の方に「シチズンサイエンス」への言及がありますが,多くの読者の皆さんも,ぜひヴォイニッチ写本解読に貢献してみてはいかがでしょうか?
・ 安形 麻理・安形 輝 『ヴォイニッチ写本』 星海社〈星海社新書〉,2024年.
2020-09-18 Fri
■ #4162. taboo --- 南太平洋発,人類史上最強のパスワード [taboo][cryptography][oed][etymology]
今回の話題は,先日終えたオンライン・ゼミ合宿 (「#4159. 2日間のオンライン・ゼミ合宿を決行しました」 ([2020-09-15-1])) の一環として私自身が参加したハードなイベントの成果物である."taboo" というお題を与えられ,それについて OED を用いて制限時間内に「何かおもしろいこと」を書かなければならないという即興デスマッチだった.後日,少々の手直しを加えたが,およそそのままの形で以下に掲載する.
見るなといわれれば見たくなる.触るなといわれれば触りたくなる.言うなといわれれば言いたくなる.古今東西,この誘惑に打ち勝った童話の主人公はいない.童話の主人公のみならず,人間は誰しも --- あなたも私も --- このマグネットの超強力な引力から逃れることはできない.タブーと称されるものは,人間社会のなかに負のパワーをまき散らしながらも,個々人にとって異常に魅力的な光彩を放っている.
トンガ語を含むポリネシアやメラネシアの諸言語で用いられていた tabu あるいは tapu という語に由来する.18世紀イングランドを代表する大航海者 James Cook (1728--79),通称 Captain Cook が1777年にトンガにてこの語に出会い,その航海日誌のなかで何度も使用した結果,taboo あるいは tabu として英語に持ち込まれることになった.この語は現地語では当地の文化・習慣について「(ある特定の場合にのみ許容されるが)一般に禁じられている」を意味する叙述形容詞として用いられていたが,Cook は当初より形容詞としてのほか,現在もっとも普通の用法である「タブー,禁忌」を意味する名詞として用いている.
taboo はもともと宗教や迷信に基づく各種の習慣に関する「禁忌」,典型的には「食べてはいけないもの」「触ってはいけないもの」などを指した.それが,20世紀前半に言葉(遣い)の領域に適用され,言語学の用語として「言ってはいけないもの」を指すように転じた.すると,私たちにもなじみ深い「タブー語,禁句,忌み詞」の語義は,比較的新しいものということになる.OED によると,「タブー語」としての初例は,taboo | tabu, adj. and n., 3b に挙げられている.名高いアメリカの言語学者 Bloomfield の教科書からである.
1933 L. Bloomfield Language xxii. 396 In America, knocked up is a tabu-form for 'rendered pregnant'; for this reason, the phrase is not used in the British sense 'tired, exhausted' . . . In such cases there is little real ambiguity, but some hearers react nevertheless to the powerful stimulus of the tabu-word.
今回の記事では,Bloomfield が使うこの意味での taboo,すなわち言語に関するタブー --- 言ってはいけない言葉 --- に注目する.
言語は,第1に互いの意図を伝え合うための道具である.私たち人間は,語彙を共有し,共通理解の下でそれを用いながらコミュニケーションを取り合っている.この「言語の第1の役割」を考えるとき,タブー語の存在は明らかに矛盾をはらんでいるように見える.「言ってはいけない言葉」はその社会のなかで不使用が前提とされており,コミュニケーションの目的に照らして,存在意義がないように思われるからだ.
しかし,タブーに関して厳然たる1つの事実が存在する.それは,古今東西の人間の言語で,タブー語をもたないものは存在しないということだ.とすると,タブー語には存在しなければならない理由があると考えざるを得ない.なぜ誰も使用しないはずの「言ってはいけない言葉」などが存在するのだろうか.
タブー語は,建前上,誰も使用しないはずなのだが,実際には皆が知っている.あの言葉を口にしてはいけないということを,社会の皆が知っている.建前上は耳にしたこともなく,学校でも習わないはずであり,知る機会がなさそうに思われる.しかし,不思議と皆が知っている.いや,もし誰も知らなかったら,そもそも語として存在しない(廃語になっている)だろうし,避けるべきものとして意識されることすらないはずだ.実は皆が知っているからこそ,意識的に避けることもできるという理屈なのだ.では,なぜ知る機会のないはずのものを,皆が知っているのだろうか.
上記の逆説に対する答えは「タブー語は実際にはむしろよく使用されている」である.タブー語は,規範として使用が避けられるべき表現にすぎず,現実には頻繁に使用されている.むしろ,タブー化される語は,日常的で身近なもの,つまり人間が生きていくなかで毎日毎日必ず付き合っていかなければならないものに関する語が多い.性,排泄,死,超自然的存在に関するものが多い.日本語では「ち○こ」「う○こ」「(お葬式で)死ぬ」「(霊)アレ」.英語では cock, shit, die, (oh my) God 等も(少なくとも特定の文脈では)遣いにくい.いずれも日常的で身近で,小学生男子が大好きな言葉群である.
性器を表わす英単語を例に取ろう.coney /ˈkʌni/ はもともと「アナウサギ」を表わしたが,後に俗語でタブー性の高い「女性器」に語義を転じた.すると,「アナウサギ」の意味で用いるのに抵抗を感じる話者が増え始め,「アナウサギ」には少しずらした /ˈkoʊni/ の発音を代わりに用いるようになったのである.かわいい「アナウサギ」は,タブー性の強い毒々しい「女性器」に,coney /ˈkʌni/ という発音を明け渡さざるを得なくなったのである.ちなみに,男性器版もある.もともと「雄鳥」を表わしていた cock が,米俗語において性的な語義を獲得するにおよんで,「雄鳥」の語義から追い出され,その語義は rooster という別の語によって担われるようになった.coney にせよ cock にせよ,後からやってきた毒々しいタブー性をもつ語義が,伝統的な形式をふてぶてしくも乗っ取ってしまうということが繰り返されている.
このように,タブー語はたいてい日常的で身近だから,誰しも関心をもっているというのが実態である.その上で,タブー語は何のために存在するのかという核心的な疑問に舞い戻ろう.私見によれば,タブー語は,その言語を用いている社会のすべての構成員が,それは言ってはならない言葉だと知っていることを確認しあう機会を提供しているのではないかということだ.言ってはダメだということを知っていれば,その人は私たちと同じグループに属していることが確認でき,そうでなければ外部の者だと認識できる.「負の合い言葉」と表現してもよい.通常の「正の合い言葉」は,互いに対応する文句を発することによって,直接的にその文句を知っていることを確認し,身内だと認識する.しかし,タブー語という「負の合い言葉」の使用においては,「知っているけれどもあえて言わない」というきわめて高度な内部ルールが関与しているのだ.子供の頃よりその言語社会のなかで生活していない限り,外部の者には簡単に習得できない暗黙知 --- それが社会におけるタブー語の役割なのではないか.タブー語は,コミュニケーションの道具であるという言語の第1の役割を逆手にとりつつ,社会の内と外を分けるための最強のパスワードとして機能しているのである.
21世紀の最先端の量子暗号ですら,「ち○こ」「う○こ」 coney, cock にはかなわない.どうだ,タブー語は凄いだろう!(←我ながらひどい終わり方,力尽きた)
・ Bloomfield, Leonard. Language. 1933. Chicago and London: U of Chicago P, 1984.
・ The Oxford English Dictionary Online. Oxford: OUP, 2020. Available online at http://www.oed.com/ . Accessed 8 September 2020.
Powered by WinChalow1.0rc4 based on chalow