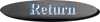 to My Profile
to My Profile
対流圏活動が下部成層圏のオゾン分布に及ぼす影響を調べるために人工衛星データを解析した。対流圏擾乱の強度をGMS(Geostationary Meteorological Satellite:「ひまわり」)による雲頂温度データを用いた。オゾンデータについては、EXOS−C(おおぞら)によるBUV(Back-scattered Ultra Violet:後方紫外散乱光)データと、NIMBUS− TOMS(Total Ozone Mapping Spectrometer)によるトータルオゾンデータを用いた。また、対流圏界面の高度がオゾン量に影響を与えていることがすでに指摘されているので、対流圏擾乱および成層圏オゾン分布と対流圏界面の関係を調べるためにISCCP(International Satellite Cloud Climatology Project)による圏界面高度気圧を用いて解析した。時期はTOMS、ISCCPについては1984年1月〜1987年12月、BUVについては1984年1月〜1986年12月である。範囲は、対流活動が最も活発である東南アジア域、東経70°〜140°、北緯30°〜南緯30°の領域である。
BUVデータについては時間的分解能がある時期についてTOMSのトータルオゾンデータとの関係を調べたところ赤道域において有意な関係が見られた。
GMS、TOMS、そしてISCCPデータを緯度10°刻みに月毎の平均値を求め、各月平均からの偏差を取り年変動を消去したデータを作成し時系列変化を調べた。GMSデータとTOMSデータの関係から、対流活動が活発になることで、トータルオゾン量が減少する傾向があるということを赤道域の±10°〜0°において確からしいことが分かった。
また、対流圏界面の上昇に伴いトータルオゾン量が減少する傾向が中緯度に近い緯度30°〜20°、-20°〜-30°の領域で明瞭に存在することが分かった。オゾンの生成域である赤道域では対流圏界面の高さとトータルオゾンの分布には明瞭な関係がなかった。
GMSデータとISCCPデータの関係には有意な相関関係は無く、対流圏界面高度が対流活動によって押し上げられるような現象は今回解析した範囲において見いだすことが出来なかった。
TOMSとGMSの日変化データを作成し、対流活動は低緯度域の夏期に最も強まり、ITCZに対応して1年周期で振動していることが見いだせた。トータルオゾン量は、低緯度域に分布の最小値を持つが、ITCZとは逆に振動をしていることを見いだした。前述の通り赤道域においては対流活動が活発になればトータルオゾンが減少する傾向があるが、分布の最小域は対流活動の最も強い場所には対応していない。また、 QBO(Quasi-Biennial Oscillation:準2年振動)による赤道域成層圏下層の西風と東風の入れ替わりの時期に、輸送によるオゾンが供給されないような場所では、トータルオゾン量が激減するような現象が見られた。
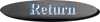 to My Profile
to My Profile