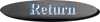 to My Profile
to My Profile
ネットワーク学習環境下におけるDTPの共同制作及びプレゼンテーションの実践を高校と大学で行なった。とくに共同制作の過程においてサーバーのデータファイル共有、グループ間の電子メールの相互送信(作品添付可)という場をデザインし、学習者間で伝達される情報がどのような性質を帯び、学習者にとってどういう意味を持つのかを主たる考察対象とした。
ネットワーク社会における学校の役割を考えるとき、外部からの情報へのアクセスがテクノロジーを介して容易かつ柔軟になる分、教師の「知識伝達」の割合が減り、逆に『かかわりの場』としての学校・教室内の学習者間のコミュニケーションをデザインする場面が増えるであろう。
近い将来、すべての学校へのインターネットの接続が予想されるが、学校外とのCMC(Computer Mediated Communication)の前提として、まず情報の港である自分達の教室や学校内のコラボレーションが不可欠であろう。『かかわりの場』における学習者相互の対面感覚を伴った情報交換が、自己の学習をモニタリングし新たな情報を生成していくのである。テクノロジーを柔軟な学習選択の手だてとしたオープン学習(Open Learning)時代の学校の存在意義も『かかわりの場』のデザイン構築に見い出されよう。
Harasimら(1995)は、ネットワーク上のCSCW(Computer Supported Cooperative Work)について、情報や考えを自分たちの言葉で系統だてて記述することや、それに対する仲間からのフィードバックや評価を受けることを通して、知識・思考能力・意味が社会的に構成されることを指摘している(1)。
このような社会的構成主義のアプローチから、おそらく現在大部分の学校において、特定の教科内で教師が主導する目的合理的授業にのみ使われがちな情報処理室を、教科の枠にとらわれず、ときには学習者のコラボレーションに開放するという柔軟な学習デザインが増えてもよい。
大島(1994)は情報を取り扱う授業のモデルとして、「情報伝達モデル」と「自己表現モデル」を提示し、特に後者の中核となる「コミュニケーション的行為」は日本の学校教育において、教育的な考慮の対象として、ほとんど取り上げられてこなかったことを指摘している。そして他者(クラスメート、教師、その他の人々)の存在を前提とした情報形成の過程(対象とのかかわりで最初に生まれてくる情報から、その情報に関する情報やその情報獲得に関する情報を付け加えていくこと)に着目し、コンピュータなどの新いメディアや伝統的メディアの組み合わせよってそれぞれの個性化と全体としての統合が促進される使い方の追求を提言する(2)。
本研究は、質的アプローチから、「自己表現モデル」の事例として、ネットワーク環境下でのCSCWにおいて学習者間で伝達される情報がどのような性質を帯び、また学習者にとってどういう意味を持つのかを主たる考察対象とした。併せて学習者の他者への「かかわり」を調査し、教科の枠にとらわれず、手軽に各学校の情報処理室のLANを学習者中心に開放したCSCWの学習形態の条件を検討した。
横浜国立大学教育学部の2年の学生20名
(1995年 10月〜11月/90分×3回)
慶應義塾高等学校の1年の生徒42名
(1996年 6月〜7月/90分×3回)
両者ともイーサネット型LANによるクライアント・サーバーシステムが構築されている。このシステムは低コスト化・情報の共有・負荷分散に有益な分散処理が実現でき、学習者中心の柔軟な情報アクセス・発信を可能にするメリットがあると判断し、選択した。
横浜国立大学:2人ないし3人1組でMacintosh のパソコンを、合計8台利用(内1台はサーバー兼用)。簡易DTP用ソフトとしてClaris Works。ネットワーク用グループウェアとしてパソコンに内蔵された「郵便とカタログ」機能の Apple Mail を利用した。
慶應義塾高等学校:2人1組でIBMのパソコンを24台利用(学習者用22台、教員用1台、サーバー用1台)。
簡易DTP用ソフトはMicrosoft Word。グループウェアとしてMicrosoft Exchangeを使用した。
図3 慶應高校生徒の作品例
4)考察に使用したデータ
1より。横浜国大・慶應高校とも学習者が最も興味をもったのは電子メールを介した情報であると観察された。これに対し、完成後のプレゼンテーションに関しては、全体的に消極的な印象を得た。
2と3より。3の電子メールの内容をカテゴリー分析すると抽出要素の46%はテーマ課題や紙面づくりとは無関係な私的な呼びかけと応答であり、残りがテーマ課題や紙面づくりに関するものであった。これに対し紙面及び紙面上の「編集後記欄」にはそのほとんどがテーマや紙面作りに関する記述であった。これは、授業枠内での課題遂行というフォーマルなコミュニケーション空間に、電子メールという使い方によってはフォーマルにもインフォーマルにもなるメディアが導入されたことで、学習者が送信対象に応じて使い分けたこと考察される。
4より。電子メールについては、「はっきりと言いにくいことが書きやすい」というカテゴリーが多く、57.3%が電子メール(ファイル添付含む)を肯定的にとらえていた。また、新聞の制作過程において最も考慮されていることは、阪神大震災というテーマに関する内容表現(直接的情報)よりも、他者へ情報が伝わりやすいように、レイアウト等の紙面構成表現(間接的情報)が多かった。
2)他者への「かかわり」の意識態度と学習過程に関する印象に関する考察
4より。他者へのかかわりへの意識態度に関する質問紙12項目に関してt検定を行ない、横浜国大・慶應高校間での有意差は、質問紙の1項目を除いて見られなかった(P<0.05)。データから、概して他者とのかかわりを意識している者が多かったと判断した。(図4-6,4-7)さらに、学習者間の情報の受容と発信との間に差が見受けられたことが指摘できよう。つまりグループ内で話し合って表現することや、電子メールでの私的な作品公開にさほど抵抗はなく、学習空間を共有する他グループの様子を気にしているが、フォーマルな場に情報発信して評価を受けることにはあまり積極的でないといえる。
5より。補足データとして、SD法(14項目)によるこの学習活動自体の印象評定について、主因子法による因子分析を行ない、2因子を抽出したので参考までに付しておきたい。第1因子は‘能動的な’‘おもしろい’‘新しい’など5項目に負荷が高く「新奇性」因子とした(α=.78)。一方、第2因子は‘明るい’‘開かれた’‘あたたかい’の3項目に負荷が高く、「コミュニケーション」因子とした(α=.72)
横浜国大・慶應高校とも、とくにコンピュータリテラシーを持つ学習者を対象にした訳ではない。学習者は短い時間にDTPを実践しグループウェアの概念を修得しメールのやりとりを行った。今回の実践において筆者らの考える状況設定を実現するために、被験者がコンピュータの操作法を修得する必要があり、筆者らはその学習に要する所要時間をかなり危惧していた。ともすればそういった学習が目的になってしまうからである。近い将来、学校でコンピュータを使うのが当然であるような状況下になれば、入学時のオリエンテーションでコンピュータリテラシーの修得がなされるようになるであろうが、今回の実践では操作法の修得も同時に行う必要があった。この問題に対し、結論から言えば想像以上に楽にクリアすることができた。最近の発達したGUI環境によってコンピュータが飛躍的に使いやすくなったのと、液晶プロジェクターで教卓機の画面を投影し、一斉に操作説明を行うことができたためであろう。また、SD法調査にもあるように、状況設定が生徒の好奇心を強く引き、コミュニケーションの楽しさが興味を持続させるのに寄与したともいえるだろう。
このような状況設定の中で、学習者らの関心を集めたのはメール機能である。特に同じメールをグループ全員に送ることのできる「一斉送信」の機能に興味を引かれたようである。制作途中の作品を一斉送信で全員に送り、方々から返ってくる返信を楽しんでいるようであった。また、そうやって送られてきた他者の作品は受信者の作品を刺激し、そこから発信されるリアクションはさらに元の発信者を刺激していた。有機的に駆けめぐる情報はプラスの方向に相乗効果を生んでいたように見受けられた。
また、コンピュータが1人1台の環境でありながら、あえて2〜3人1台とし、コンピュータをコミニュケーションツールとしての性格付けを明確にした。その結果、共同作業によって、一つの作品を完成させる必要が生じ、制作に責任を持って当たるようになった(図4-1,4-2)。操作に関してはコンピュータに熟達した方の生徒のみがキーボードを打つ様子が観察されたが、内容に関しては片方の意見のみで編集が進められることは少なかった。さらに、メールのやりとりが学習者の発想を膨らませ、作品をより高いものに導いたと観察された。
編集作業に関して、内容の深めより文字フォントやレイアウトなどの「目に見えやすい」技術的な興味が先行したことが観察された。これは、今回の学習者がコンピュータ自体に対してあまり慣れていないため、コンピュータに対する新奇性が強調されたためであろう。
授業中の観察からは、以上のように、ネットワーク環境下におけるCSCWによってコミニュケーションが促進され、学習者の意欲・態度を向上させたといえるであろう。
この実践により、ネットワーク環境下でCSCWを行なう場合、他者との「かかわり」が深まり、学習を活性化させることが示された。
また、電子メール(ファイル送信)に関しては、私的なコミュニケーションが存在することがわかった。インフォーマルなコミュニケーションは全体の発信量の約半分を占めた。このコミュニケーションは従来の形態の授業では存在し得なかっただろう。あるとすれば、それは授業が成立していないことを意味している。今回の実践ではインフォーマルなコミュニケーションが可能で、かつ授業も十分に成立している。このような状況が学習の場にどう作用していくかは今後の研究課題であるが、学生や生徒が非常に熱心に作業に打ち込んだ今回の実践の様子から、筆者らは授業を活性化することのできる要因になり得ると考える。しかし、またそれは学習の場を破壊する要因も同時に持っているのも事実である。インフォーマルなコミュニケーションをいかにして当面の学習に関する情報生成に結びつけるかが課題となってくるだろう。
本小論をまとめるにあたり、実践についてご協力頂き、多くの適切なアドバイスを与えてくださった、横浜国立大学教育学部の大島聡助教授に深く感謝いたします。
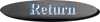 to My Profile
to My Profile