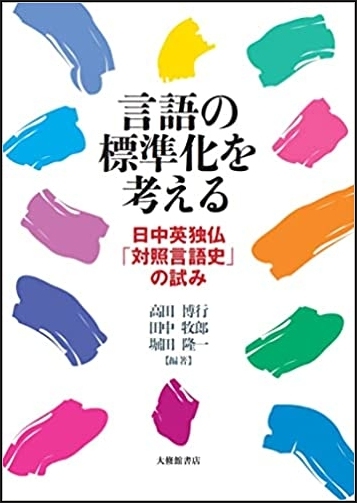
ちょうど2年前の5月に,上掲の 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館,2022年) が出版されました.言語の標準化 (standardisation) を主題としながら対照言語史 (contrastive_linguistics) という新アプローチを提唱した共著でした.著者間の議論を紙面に再現すべく特殊なレイアウトを施すなど,いろいろな意味で挑戦した本ですが,本作りにはその分多くの時間を要しました.
このたび同著について『社会言語科学』誌上で丁寧な書評をいただきました.清沢紫織氏(北海学園大学)による6ページにわたる解説と論評です.J-STAGE 経由でこちらのページよりアクセスできます.ぜひご一読いただければ.
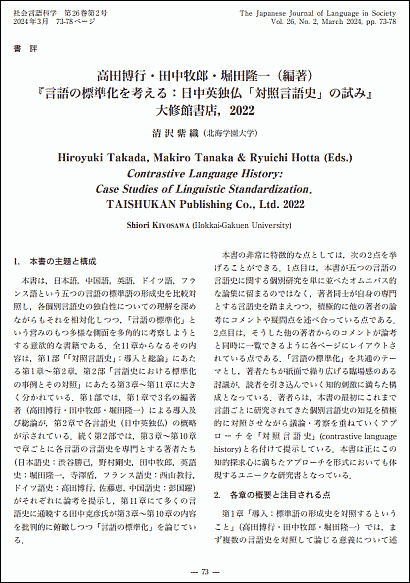
この書評は,(1) 本書の主題と構成,(2) 各章の概要と注目される点,(3) おわりにかえて,の3部立てで書かれています.本書の大きな特徴として,2点が指摘されています (73) .1つは「著者同士が自身の専門とする言語史を踏まえつつ,積極的に他の著者の論考にコメントや疑問点を述べ合っている点」,もう1つは「そうした他の著者からのコメントが論考と同時に一覧できるように各ページにレイアウトされている点」です.
導入的な第1章については「この章は著者らが丹念な議論・意見交換を通じて導き出してきた言語の標準化研究の視座を提供する内容ともなっており,これから個別言語の標準化を研究しようとする者や既に取り組んでいる者にとっては頼もしい道標となることだろう」との評で締めくくられてます (74) .
続く各章の概要と論評はいずれも示唆に富み,評者の視点を共有しながら,本書はこのようにも読めるのか,と多くの発見がありました.全体として,本書の狙いをすくい取り,丁寧な評を与えてもらったと感じています.
本書についての書評は,今回のもののほかにも以下の2点が出されています.それぞれ J-STAGE よりアクセスできるので,合わせてお読みいただければ.
・ 家入 葉子 「書評:高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著) 『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』(大修館書店2022年6月刊,viii+247pp.)」 『歴史言語学』第11号(日本歴史言語学会編),2022年.47--54頁. *
・ 片山 幹生 「書評:高田博行他編著 (2022) 『言語の標準化を考えるー日中英仏語「対照言語史」の試み』,東京:大修館書店,248 p.」 Revue japonaise de didactique du français 18.1--2 (2023): 134--37. *
『言語の標準化を考える』については,本ブログでも多く紹介してきました.gengo_no_hyojunka タグのついた記事群をご覧いただければと思います.
・ 高田 博行・田中 牧郎・堀田 隆一(編著)『言語の標準化を考える --- 日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館,2022年.
・ 清沢 紫織 「書評:高田博行・田中牧郎・堀田隆一(編著) 『言語の標準化を考える:日中英独仏「対照言語史」の試み』 大修館書店,2022」 『社会言語科学』第26巻第2号(社会言語科学会編),2024年.73--78頁. *