パーソナリティ心理学 #15 木島伸彦 nkijima@hc.cc.keio.ac.jp 慶應義塾大学
行動遺伝学
双生児を研究対象として、人の様々な特性や病気などの遺伝の影響を遺伝と環境の両側面から検討する学問。
例.遺伝率(遺伝による影響度)
知能は、遺伝率は約( )%
体重は、約( )%
身長は、約( )%
そして、パーソナリティ(気質)は、約( )%
1 双生児
一卵性双生児と、二卵性双生児の二種類がある。
一卵性双生児は、遺伝子情報が、( )%共通していると考える。
二卵性双生児は、遺伝子情報が、( )%共通していると考える。
注.一般のきょうだいでの、遺伝子情報の一致度は、( )%である。
前提条件.
一卵性双生児では、遺伝子の共有度は、( )%。 → 従って、相関係数は、r=1.0
二卵性双生児では、遺伝子の共有度は、( )%。 → 従って、相関係数は、r=0.5
一卵性・二卵生とも、共有環境の一致度は、( )%
A:相加的遺伝要因
D:非相加的遺伝要因
C:共有環境
E:非共有環境
( ):心理学的特性や病気などには、多数の(ポリ)、遺伝子(ジーン)が関与しているという仮説。
双生児1 双生児2 遺伝相関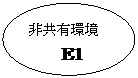
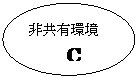
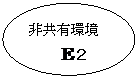
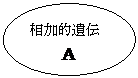
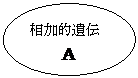
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


・( )の公式:A = 2(rmz-rdz)
遺伝率の算出には、上記の( )の公式が基になって算出される。
一卵性双生児の気質得点の相関係数が、0.50
二卵性双生児の気質得点の相関係数が、0.25 であったとする。
rmz = 0.50=A+C+
rdz = 0.25=0.5A+C
A+C+E=1
問題1:この3つの式から、気質得点の相加的遺伝要因の割合(A)を求めよ。
問題2:共有環境要因の割合(C)を求めよ。
問題3:非共有環境要因の割合(E)を求めよ。
2 遺伝か環境か、nature or nurture
多くの研究結果をまとめると、気質得点に関しては、以下のとおり。
遺伝要因の割合は、ほぼ( )%
共有環境の割合は、ほぼ( )%
非共有環境の割合は、ほぼ( )%
共有環境とは、双生児が同時に育つにあたって、同一の影響をうける環境要因。
非共有環境とは、双生児が同時に育っても、固有の影響をうける環境要因。
注.家族の中にあっても、共有環境と非共有環境がある。
この結果から、パーソナリティの形成にあたっては、非環境要因が極めて大きな働きをしていることがわかる。
→ 親の要因よりも、友達関係の方がはるかに大きな影響を受ける、と考えられる。
3 遺伝と環境の交互作用
遺伝と環境は、交互作用する。
例.( )(適性処遇交互作用)
子どもの能力を伸ばすには、個人個人にあった方法で行うことが必要であると考えられる。
また、子どもの遺伝要因の影響があったとしても、それで、全て決定される訳では決してない。
4 遺伝の年齢を超えた影響の仕方
遺伝の影響は、一生を通じて、それぞれの時期に固有の影響の与え方をする。
例1. 例1.
知能
年齢を経るごとに遺伝要因の割合が大きくなっていく。
例2. 例2.
アルツハイマー型痴呆
若いときには、全く影響がないが、歳をとってから影響が現れる。
5 パーソナリティを形成するものは?
遺伝の要因は、無視できないほど、大きい。
また、環境によって学習して形成されていく部分もある。
→では、環境と遺伝のみによってパーソナリティは決定されるのだろうか?
参考文献
こころはどのように遺伝するか 安藤寿康 講談社ブルーバックス