(ニュースの中の生物科学)



履修案内
履修案内とシラバス(平成19年度分):
生物学I/II
(ニュースの中の生物科学)



履修案内
毎日のように、生物学関連の話題がニュースの中に取り上げられています。一般社会人も、生物学的背景を持った社会問題にさらされているといえます。BSEと狂牛病の問題、鳥インフルエンザ問題、遺伝子鑑定、遺伝子組み替え食品などの遺伝子関連の話題、クローン、臓器移植、代理母、ガンやエイズなどの病因解析、さまざまな環境問題などなど、これらの話題は専門家のみならず、現代社会に生きる一般人にとって時代を読み解くキーワードとなってきました。この授業では、これらの生物学的背景を持った社会問題をトピックスとして各回一話完結型で取り上げます。生物科学の入門編ではありますが、体系的な概論ではなく、映像資料や教材も加えて、最後に問題点を自分で考えるように進めていきます。このため、予備知識が無くても理解できるように基礎用語から解説していきます。隔週に行われる実習は、できるだけ身近な生き物を対象とし生命現象を具体的に理解するように用意されています。実習の前にプリントを配付し、目的や手順を説明します。講義の始めに、年間授業予定を検討しますので皆さんからも興味のあるテーマを提案して下さい。この授業で日々のニュースの中の生物学関連の話題が理解され、自分で問題認識できるようになること、そして、これまでに余り生物に触れる機会がなかった人も、精緻でファジーな生命の不思議について楽しみながら理解されれば良いと思います。
5. 教科書
「生きているってどういうこと」種田保穂・秋山豊子共著 培風館(2006年刊行)
6. 参考書 授業時に適宜、紹介します。
シラバス
講義
① ガイダンス
② 生命の定義、生物と非生物の比較
③ BSE狂牛病とその病原体プリオン
④ 生殖工学と生命倫理 代理母・人工授精・クローン動物
⑤ 脳死と臓器移植 神経と脳の働き、脳死とは?
⑥ ヒト・ゲノム解読とその問題点 遺伝子の働きI
⑦ 遺伝子組み換え技術とその応用 遺伝子の働きII
実習
① 「花を観る」日吉キャンパスを歩きましょう。野草とタンポポの観察・調査
② ダンゴムシはどう歩く ダンゴムシの行動解析
③ ヒトとニワトリの血液細胞の観察 (赤血球・白血球・リンパ球)
④ 原形質流動の観察と流速測定 マイクロメーターを使って顕微鏡下で長さを計る
⑤ 染色体の観察 ソラマメの染色体と細胞分裂の過程
⑥ 酸性雨調査と環境汚染調査 日吉キャンパスの空気と雨は?
担当教員から履修者へのコメント
実習があるため適正規模で行います。今年度は春・秋学期とおしてI・IIとも履修する方を優先します。秋学期のダイダンスはないため、春学期にI・IIの履修申告をすることになります。履修希望者は初回(1・2時限は9時から、3・4時限は13時から)のガイダンスに出席して履修カードを受け取って下さい。定員になった段階で締め切ります。
成績評価方法
今年度入学生は、半期制ですので、半期ごとに、それ以外の通年科目として履修する方は学年末に評価を出します。実験の小レポート、講義の出席・即レポ、試験(専用用紙のみ持ち込み可)などを総合的に評価します。
10. 質問・相談
メールにて随時、あるいはメールにて予約の上、木曜日のお昼休みに受けます。
自然科学研究会 I (春学期)・II(秋学期)
「ヒトと生物環境との共存を考える」

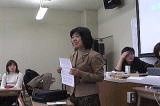
履修案内
少人数のメリットを生かしたセミナー形式を主にし、学生自身によってテーマ・問題点を提案し、授業日程や進行方法を決定し、発表・討議など進行も行います。自分で学習して積極的・主体的に学びたいという学生諸君に履修を勧めます。
現在社会は、ようやく経済的に明るさが見えてきたものの、大量消費とその後の経済的な低迷期の結果、私たちの生活環境にはさまざまな問題が生じています。他方、良い意味では、持続できる地球を目指して大量消費していた多くの製品でリサイクルをし、無駄を省いてシンプルな生活へと向かっているように思われます。スローライフの勧めや自然志向に見られるように、豊かな自然への回帰現象の中にあるように思われます。環境ホルモンやダイオキシンなど様々な環境汚染、野生動物の保護、バイオテクノロジーのもたらす恩恵と問題点、エイズなど感染症の防御とその人権問題、脳死や臓器移植、尊厳死の問題など、現代人の関心事となっています。ヒトと多様な生物との共存の道を考察するという視点から、これらの現代社会における自然科学を背景とした問題を考えてゆきます。自分自身が具体的に環境問題や自然科学の問題を考える第一歩となれば良いと考えています。今年は、校外活動、資料収集、観察、臨海実習などキャンパス外での活動も考えています。
教科書
特に指定はしません。
参考書
「生きているってどういうこと」種田保穂・秋山豊子 培風館 2006年刊行
授業の計画
学生の希望により、討論の上、授業の形式や班構成・各回のテーマなどを決めます。以下は昨年度のテーマです。参考にして下さい。
春学期: ヒトと地球環境に関する自然科学的背景を持つ問題
① 班分け、テーマ討議、発表日程決定、班で課題への取り組み方など相談・討議
② プレゼン用ソフトパワーポイントの練習
③ 環境問題の考え方、班での打ち合わせ
④ 森林破壊と野生動物減少
⑤ 原子力発電の是非
⑥ 生態系の汚染と維持
⑦ 大気汚染問題
⑧ 温暖化とチーム-6%
⑨ リサイクル(廃棄物問題)
⑩ 公害問題と保障 水俣病
⑪ アスベスト問題
⑫ 公害問題と保障 イタイイタイ病
担当教員から履修者へのコメント
小人数セミナーの形式のため、約20名までを適正規模といたします。履修にあたっては、I(春学期)・II(秋学期)共に履修されることが望ましいため、I,II共に履修する希望者を優先します。秋学期はガイダンスがないため、I・IIともに受講希望者は必ず春学期の初回のガイダンス(5限ですから16時30分から)に出席して下さい。その中から履修者を決定致します。自ら学び、討議や発表を通して主体的に授業に取り組みたい熱意ある学生の履修を望みます。
成績評価方法
半期制科目ですので、半期ごとに、評価を出します。講義の出席・即レポ、発表・授業内での貢献度・レポートなどを総合的に評価します。
質問・相談
毎回、授業後に受けます。
授業紹介・教材など:
「自然科学研究会」は約20名くらいのセミナー形式で、学生によるテーマ選択、
発表、討論などで学生が主体的に授業を構成しています。